2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2012年09月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
『現代の作家一〇一人(百目鬼恭三郎)』
『現代の作家一〇一人(百目鬼恭三郎)』阿川弘之から和田芳恵までの一〇一人を切り刻んで一歩も退かない。読み手にとっては痛快。誰の評かは伏せるが、【純文学か通俗小説かは、物語性が弱い強いで決まることではなくて、文章の力によって左右されるものなのだ。このことを、私たちは良く心得ておく必要があろう。】大岡昇平のところ、【人は年をとると、想像力を失う代わりに、事実に対する興味がつよくなって考証趣味に陥るといわれる。大岡の近年(*)の傾向も、ひとつにはたしかに年のせいであろう。】【私たちは考証家大岡に、新しい文学、たとえば露伴の『運命』のごときもの、を期待できそうな気がしてならないのだ。】佐多稲子のところ、【佐多稲子の処女作『キャラメル工場から』を読むと、小説の上手下手は天分次第だ、ということを痛感させられる。むろん、教養や修行によって段々小説が上手くなってゆく作家もいて、云々・・・一言でいうと、天性のうまさのほうがより直接に読者の心をとらえるものである。】これら101人の評を読みながら、手許の本を漁ったり、図書館で借りたりしました。佐多稲子の短編「水」は面白く読みました。また露伴の「運命」に手をつけたのですが難しすぎて・・・、辞書を片手に、というより辞書(漢和辞典)と首っ引きで解読というように読んでいます。いつまで掛かるか今はわかりません。そして、前書「この本の宣伝のための架空講演」・・・【これまで熱心な文学読者ではなかった私は、純文学と大衆文学の差はそれほどなかろう位に考えていたのであります。ところが、よく読んでみると、その差が予想以上に大きいことを知って驚いたのですね。通俗小説を純文学作品と同列にならべたのでは、悪口を書くほかなくなる(笑声)。で、通俗小説のほうは、できるだけそのとりえを推奨することに重点をおくことにしたのであります。にもかかわらず「けしからんことを書いた」と腹を立てて騒いだのは、甘くしたはずの通俗小説作家ばかりだった(笑声)。通俗作家のほうは、日ごろ雑誌の編集者からほめられてばかりいて、まともに批評されたことがない。だから、ちょっとでも自分の欠点を指摘されると、カッと頭に血がのぼるらしいのですね。ことに女流はそうらしい(笑声)。】云々・・・この後は痛烈【悪口をいわれて腹を立てるのは、人間性が健全な証拠である。実をいうと、私はそれまで、この人たちがあんな小説を平気で書いていられるのはどういう神経なのか、よくわからなかったのですね(笑声・拍手)。それがこれでよくわかって安心したような次第であります。】初めに紹介した「誰か」は日経新聞連載の小説が有名ですね。これを再び読むきっかけは、本の処分で整理をしていて見つかったもの。百目鬼恭三郎をまとめて読んだことがある。百目鬼恭三郎は「風」の名で週刊誌の文学批評を書いていた。ボクは「風」の書評を2冊読みその後これを読んだように思う。今回の方がより面白く読めたようだ。「ようだ」というのは、以前に読んだ時の記憶がないからだ。百目鬼恭三郎と一緒に見つけたのが山本夏彦の後期の評論である。それも処分を免れた。*昭和48年2月から50年3月にかけて、朝日新聞に連載された「作家Who’s Who」の単行本。だから、近年とは48年2月から50年3月のこと。【】内 引用。現代の作家一〇一人百目鬼恭三郎(どうめききょうざぶろう)発行/昭和50年10月20日10刷/昭和53年12月25日新潮社
2012.09.17
コメント(0)
-

『光線(村田喜代子)』
東日本大震災をはさんで書かれた8編の短編集。「光線(2011/10)」「海のサイレン(2011/12)」「原子海岸(2012/2)」「ばあば神(2012/4)」「関門(2011/2)」「夕暮れの菜の花の真ん中(2011/4)」「山の人生(2010/7)」「楽園(2010/11)」「楽園」について大学のゼミ、コミュニケーション学の実習で鍾乳洞の洞窟探検。その中に洞窟潜水というのがある。白蓮洞(これと同名の洞が東北にあるが、この話は山口県=秋芳洞が舞台)の地底湖を巡り語られる。その地底湖の第七新洞を発見した瀧山晋司とゼミ学生とのメールが興味深い。実は第七新洞を発見したとされる瀧山晋司を含むチームは、発見時あまりにも第七新洞が深く途中で引き返している。その翌年イギリスの調査隊が踏破して終点に到達したが、その成果を彼ら(=瀧山ら)に譲った。だが、瀧山はその翌年単独で第七新洞を潜り直し、イギリス隊の到達点を超えた奥に、さらに1キロメートルに及ぶ支洞、第七超新洞を発見するも、そこで瀧山は支洞に迷い込み約七時間さまよい帰還する。潜水開始が午前10時、帰還が午後8時45分。なんと8時間45分洞窟に居たことになる。帰還後瀧山は廃人同様になるが二年後奇跡的に復帰する。学生とのメールは復帰後のもの・・・、ボクが興味を持ったところを引用します。【瀧山晋司:闇は物量でも、奈落でもありません。闇は人間の精神の中にあり、洞窟の闇は簡単に光りを持ち込める軽い種類の闇と感じます。一枚田梨花(学生):確かに闇は光りを持ってくればすぐ払われますが、ライトが消えてしまって二度と点かないとしたら、それでも軽い闇と言えますか?瀧山:ともかく光源さえあれば暗くなるという意味で、洞窟の闇は軽いです。(言葉の限界を感じますが)p207~208】【瀧山晋司:造物主の存在に拮抗するものの一つとして科学があると思うのです。多くの場合、洞窟の存在の仕方は科学の推測するものと違う形で存在します。p210】ボクが面白いと思った(=興味を持った)のは、【光源さえあれば暗くなるという意味で、洞窟の闇は軽い】の所。光源があっても暗い所、それは地上には無いのだろう。宇宙の中にはそういう場所がある?このような話を読むと、今の電気不足が云々と言われているが、闇(=暗さ)なんかは高が知れていると思うのだ。次の引用は、科学(=理論・理屈・計算など)は自然を予測しきれないと言うことの、一つの証明。政府などの統計の予測も多くの場合外れる。人の動き(=変化)や自然の動き(=変化)は造物主の掌の上か?科学の予測は一つの見解であり自身の勘と経験も一つの見解ということ。どちらが重い訳ではないだろう。「楽園」の参考書『未踏の大洞窟へ(櫻井進嗣)』を見てみたい(読みたいではなく、パラパラと見てみたい)。『光線(村田喜代子)』文藝春秋/2012年7月15日第1刷発行
2012.09.08
コメント(0)
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
-

- ドラマ大好き
- 終幕のロンド 第3話を観た 基本路…
- (2025-11-25 21:33:12)
-
-
-

- 懐かしのTV番組
- ブラッシュアップライフ 第3話
- (2025-11-25 16:36:35)
-
-
-
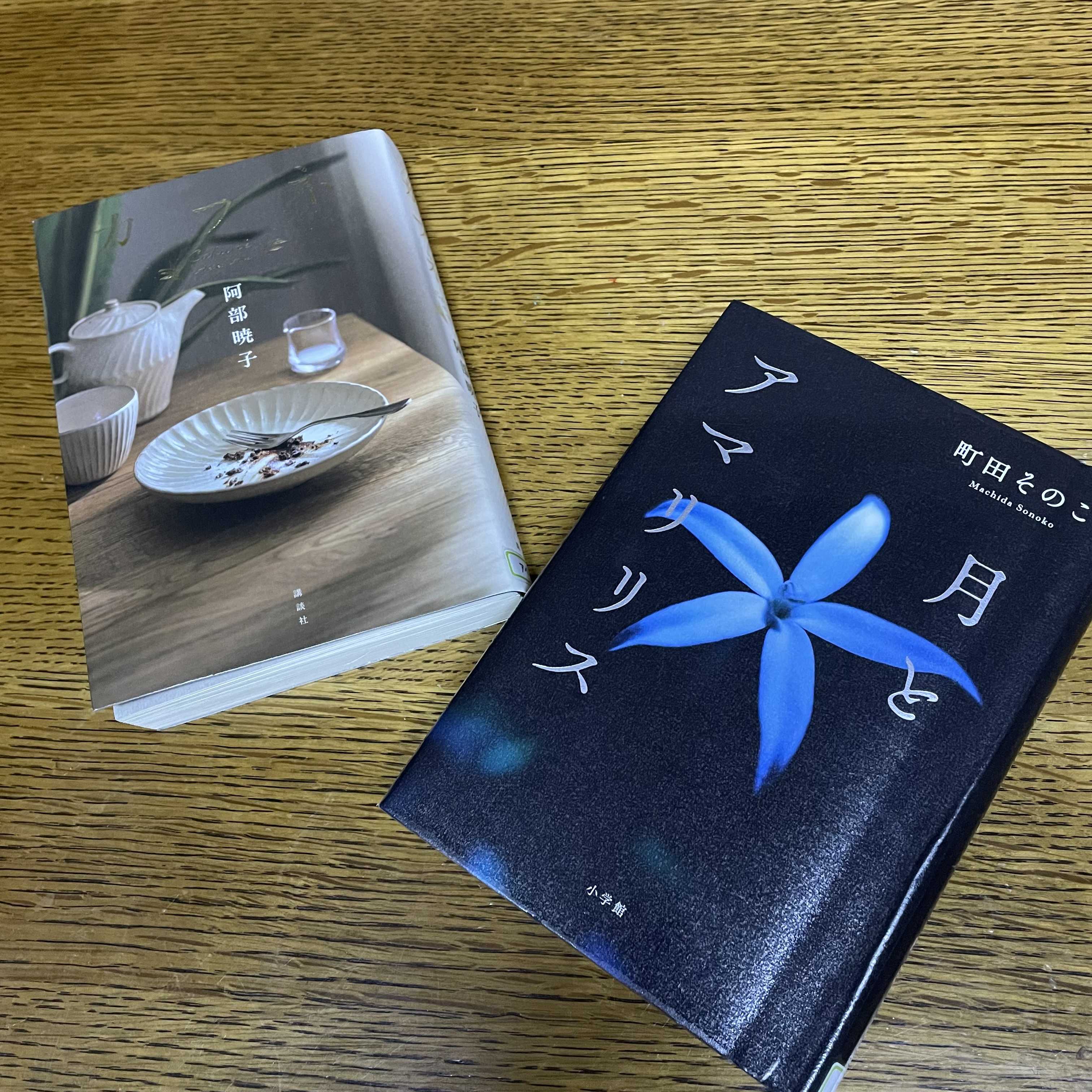
- SMAPが大好きな(興味が)ある人♪
- ハピバ☆ ・「カフネ」
- (2025-08-18 23:53:31)
-







