2017年08月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-

8月のおしゃれ手紙:読書三昧
■7月に引き続き■時代小説にどっぷりハマって次々読んでいった。■武士の家計簿■も面白かった。■あきない世傳金と銀■・・・。あきない世傳金と銀(3)は、一か月待って読んだ。妹も時代小説がマイブームだと言っていた。読んだ本は、忘れないように内容を残しておこうと思うのでたいへん。読みっぱなしはもったいない! 今読んでいるのは、「リーチ先生」。■バーナード・リーチ日本絵日記■を読んでたし、■小鹿田(おんた)■に旅行したこともあるのでよく分かった。■皇妃エリザベート:ハプスブルグの美神■ また、暑い中を中之島の橋を写真を撮りながら歩いた。胃の具合はよし。■8月見た映画■*ファウンダー /ハンバーガー帝国のヒミツ*海辺の生と死*麗しのサブリナ*フェリシーと夢のトウシューズ*ハイジ アルプスの物語■書き残したネタ■*俯瞰力(ふかんりょく):続・断捨離*フランス人は10着しか服を持たない:スタイル*省エネライフ*あきない世傳金と銀(3):高田郁*ひとりで暮らして気楽に老いる―夫のいない自由な生き方*白樺の籠*水田と景観*中之島の橋*古墳のトリビア2*中ノ島界隈*花かご*「リーチ先生」*本「人はこうして食べるを学ぶ」*ひふみん、よっちゃん、てんてー・・・。*てるみくらぶ。*いらっとする言葉。*葛井寺*江戸の人口と明治の人口と移民問題*湖水地方、*スコットランドのエコ。*スモーキング フリー*瀬田川洪水の原因と対策*電気の自由化・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.31
コメント(0)
-
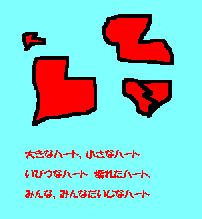
パターソン★一週間
■パターソン■♪音が出ます!毎日が、新しい。ニュージャージー州パターソン。街と同じ名前を持つバス運転手のパターソン(アダム・ドライバー)の1日は朝、隣に眠る妻ローラ(ゴルシフテ・ファラハニ)にキスをして始まる。いつものように仕事に向かい、決まったルートを走り、フロントガラス越しに通りを眺め、乗客の会話に耳を澄ます。乗務をこなすなか、心に浮かぶ詩を秘密のノートに書きとめていくパターソン。一方、ユニークな感性の持ち主であるローラは、料理やインテリアに日々趣向を凝らしている。帰宅後、パターソンは妻と夕食をとり、愛犬マーヴィンと夜の散歩、いつものバーへ立ち寄り、1杯だけ飲んで帰宅。そしてローラの隣で眠りにつく。そんな一見代わり映えのしない日常。だがパターソンにとってそれは美しさと愛しさに溢れた、かけがえのない日々なのであった……。『パターソン』は、ひっそりとした物語で、主人公たちにドラマチックな緊張らしき出来事は一切ない。物語の構造はシンプルであり、彼らの人生における7日間を追うだけだ。『パターソン』はディテールやバリエーション、日々のやりとりに内在する詩を賛美し、ダークでやたらとドラマチックな映画、あるいはアクション志向の作品に対する一種の解毒剤となることを意図している。本作品は、ただ過ぎ去っていくのを眺める映画である。例えば、忘れ去られた小さな街で機械式ゴンドラのように移動する公共バスの車窓から見える景色のように。── ジム・ジャームッシュ(監督)「うちには、マッチが沢山ある。」というマッチの詩が映画の中に出てくる。途中に何回も何回も・・・。■って、うちにもマッチ■あるわ!!今年の冬が終わった時、こんだけ使ったわ!!と、ツッコミながら見てしまう。(ノД‘)この作品の詩に共感することが出来なかったし、インテリアに凝っているという妻のセンスにも共感できなかった。ただ、妻、ローラの美貌には、みとれた。主人公の何が起きても動じない性格、大切なものを壊されても、怒らない性格も羨ましい。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.30
コメント(0)
-

ハイジ アルプスの物語★実写
■ハイジ アルプスの物語■また会えたね、ハイジ。ハイジ(アヌーク・シュテフェン)は、アルプスの山の大自然に囲まれ、ガンコだけれど優しい祖父(ブルーノ・ガンツ)と楽しく暮らしていた。ところがある日、フランクフルトの都会で暮らす大富豪のお嬢様クララ(イザベル・オットマン)の話し相手として連れて行かれる。クララは足が悪く、車いす生活を送っていた。明るく素直なハイジのお陰で元気を取り戻したクララとハイジは固い友情で結ばれるが、ハイジは日に日に祖父の待つアルプスの山が恋しくなる……。ヨハンナ・スピリの児童文学「アルプスの少女ハイジ」を映画化。出演は、「ヒトラー 最期の12日間」のブルーノ・ガンツ、500人の候補の中から選ばれたアヌーク・シュテフェン。監督は、「リトル・ゴースト オバケの時計とフクロウ城の秘密」のアラン・グスポーナー。 「また会えたね、ハイジ。」というコピーは、原作「ハイジ」が何回も映画化されているから。■ハイジ■ それほど、みんな、ハイジが大好きなのだ。無邪気で元気で、優しいハイジは気難しいお爺さんでさえも、打ち解けさせる魅力を持っている。■秘密の花園■のディッコンも元気で明るく無邪気で親切だ。ディコンの魅力で気難しいメアリーもコリンも明るく元気になる。気難しい老きょうだいの所に来た■赤毛のアン■もそうだ。私たちは、このように無邪気な子どもらしい子どもが大好きなのだろう。映画中のアルプスの景色も素晴らしかった。映画の中でハイジが汽車に乗ってフランクフルトに行くというシーンがあったので、物語はいつだろうと調べたら「ハイジ」の出版は1880年だった。■ハイジ豆知識■■小公子■は1886年■赤毛のアン■は、1908年■秘密の花園■は1911年の作品だ。19世紀の終わりから20世紀の初めに、ガンコな大人、美しい自然、そしてかわいい子ども・・・という■幸せを運ぶ子どもたち■が流行したという。アニメが有名だけど、実写もいい。ハイジ役の女の子は、ピッタリの子だった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村
2017.08.29
コメント(0)
-

あきない世傳(せいでん)金と銀2:高田郁
■あきない世傳(せいでん)金と銀2■■あきない世傳金と銀<1>■学者の娘として生まれ、今は大坂天満の呉服商「五鈴屋」に女衆として奉公する主人公・幸。十四歳の幸に、店主徳兵衛の後添いに、との話が持ち上がった。店主は放蕩三昧で、五鈴屋は危機に瀕している。番頭の治兵衛は幸に逃げ道を教える一方で、「幸は運命に翻弄される弱い女子とは違う。どないな運命でも切り拓いて勝ち進んでいく女子だす」と伝える。果たして、「鍋の底を磨き続ける女衆」として生きるのか、それとも「五鈴屋のご寮さん」となるのか。あきない戦国時代とも呼べる厳しい時代に、幸はどのような道を選ぶのか。話題沸騰のシリーズ第二弾!★「あもや、と書かれた暖簾を示して、富久は言い、番頭の返事を待たずに店内に入る。」(▲あも)餅のことを大坂では「あも」と呼ぶ。」■あもも団子も■★「幸の脳裏に浮かんだのは、菊栄が花帰りの際に、紅屋からの土産と称して五鈴屋へ持ち込んだ、箱入りの鰹節だった。」私も結婚式の引き出物に鰹節をもらった事があるが、昔から縁起物をして使われていたのだ。★天神橋■を渡り、 ■今橋■を左手に見て、そのまま東横堀川に沿って南へ下る。少し行くと■高麗橋。■西詰に高札場と橋番の小屋があり、その脇から川面に続く階段があった。というのがあったが、私が行ったことがある所ばかり!★結婚すると女は帯を前で結ぶ。これを■「前帯」■という。江戸その他、地方に依ってはその用い方は少なく、京阪地方には広く用いられたもので、その風は大正初年にも及んでいる。★花帰り新婦が初めて里帰りすること。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.28
コメント(0)
-

昔語り:ラジオ体操と縁台と。
今から60年ほど前の岡山県の田舎の夏休み。 ■朝顔の思い出■■合歓の木(ねむのき)の下の水遊び■ ■カワニナひろい■幼い日の夏休みの■思い出は、ボロボロ■とこぼれてくる。ラジオ体操もその一つだ。眠い目をこすりながら、ラジオ体操に行った。ラジオ体操の会場は、Kさんの家の庭だった。Kさんは、父より10歳ほど年上で当時50半ばだったのではないかと思う。会場となった家の庭には、タタミ一畳ほどもある縁台が家の影になる場所に置いてあった。子どもたちは、持ってきたラジオ体操のカードを、その縁台の上に置く。すると、Kさんがハンコを押してくれた。私の家には、この大きな縁台がなかったので、羨ましくて仕方がなかった。 この縁台があれば、夕涼みの時、花火をすることが出来る。 ここで、スイカだって食べられる。Kさんは、ラジオ体操の後、この縁台で将棋をすることがあった。タタミ一畳の大きさの縁台が、何でもできる魔法の場所のように思われた。■縁台の写真■大阪で暮らし始めた40年ほど前、この大きさの縁台を何度も見たが最近は見なくなった。クーラーの出現で夕涼みという言葉とともに縁台も消えたのだろうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.26
コメント(0)
-

折々のうた:蝉と蛍
恋に焦がれて泣く蝉よりも 鳴かぬ蛍が身を焦がす*「山家鳥虫歌(さんかちょうちゅうか)」*(山城国の民謡)近世諸国民謡集「山家鳥虫歌」の校注者、浅野建二は、蝉と蛍は「恋情に焦がるる虫」として古(いにしえ)より対照されてえきたという。切なそうにみんみん泣くこともできず心を折り畳むばかりの片恋の心情は、やがて心を届けえぬ自分を憐れむほうへ向かいがちだが、その人への思いはそれでも断ちがたく、「思ひ」が「火」となり身を焦がす。「折々のうた」2016.9.15 この本の発売日は1980年03月。この歌は、新聞の切り抜きを転記したもの。切り抜きだと、整理しにくいのでブログに載せた。*ゆるやかに着てひとと逢ふ蛍の夜桂 信子*閑かさや 岩にしみ入る 蝉の声松尾 芭蕉*大蛍(おおぼたる)ゆらりゆらりと通りけり小林 一茶があった。今年は、蛍を見ないまま、夏が終わろうとしている。*「山家鳥虫歌(さんかちょうちゅうか)」*江戸中期の諸国の民謡集。68カ国、399首が収められている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.25
コメント(0)
-

「河内大塚山古墳」の中には昭和のはじめまで村があった。
■「河内大塚山古墳」被葬者不明陵墓の“孤絶”■(略)松原市と羽曳野市の、ちょうど市境にある河内大塚山古墳は、不思議なミササギである。深々とした木々におおわれた丘陵は、周辺一帯にある天皇陵とほとんど変わらない。変わらないというよりも、これまで見てきたミササギのなかでも、住宅などに囲まれた周囲の景観を無視し、「孤絶」しているような面持ちがただよってくる。(古墳へと続く)石垣の道は、羽曳野側と松原側の、前方後円墳の前方部に2カ所ある。こんな道がついたミササギは初めて見た。よく眺めると、道のさきの森のなかには、黒々とした道がつづいていた。現在は、宮内庁によって陵墓参考地として「立ち入り禁止」となっている。だが明治以降も、人々がこの石垣の道を通ってミササギのなかに住んでいた。案内板には、大正14年9月に陵墓参考地となり、昭和3年までに、数十戸の民家が濠外に「去った」と書かれていた。数十戸と言えば、100人ほどの、おそらく農民とその家族が住んでいた。「昭和3年」という時期を考えると、「去った」のではなく、「退去させられた」のであろう。古市や百舌鳥の両古墳群一帯にある天皇陵は、その大半が江戸末期から明治期の尊皇思想の高まりによって、たとえば蒲生君平らといった尊皇家の「ボランティア調査」などにもとづき指定された。蒲生の調査は、ハンパではなかった。大和や河内、京だけでなく、はるばる佐渡島の順徳天皇陵まで足をのばし、『山陵志』を書いた。現在も使われている「前方後円墳」の命名者でもある。だがこの古墳は、どうにも分からなかったらしい。明治以降も、被葬者不明とされた。もれたのに大正期になってナゼ、突然、陵墓参考地になったのか。 * * *理由は容易に推定できる。全長335メートル、墳丘の高さ20メートルという規模は、両古墳群のなかでも4番目、全国でも5番目の大きさである。これだけリッパなミササギに葬られているのは、きっとリッパな大王だったはずである。だれか分からないが、とりあえず陵墓参考地にしておこうと、当時の陵墓担当の官僚が考えたのであろう。参考地であったため、3年ほどまえには、学者らによる立ち入り調査も行われた。もちろん発掘などできなかったが、石室の天井石などが確認され、6世紀後半の古墳である可能性が強いとされた。規模から、築造されたのは5世紀代で、未完成だったという見方も示された。 5世紀代ならば、中国の史書にある「倭王武」に比定される雄略天皇の可能性もある。雄略陵は1キロほど東にある「高鷲」の項でも紹介したが、大塚山古墳のほうが雄略陵だとする説もある。こだわりたいのは、未完成の理由である。完成したが、のちに壊されたとも考えられる。 * * *雄略はすさまじい権力闘争のすえ、天皇位についた。兄や従兄弟など皇位継承権のある親族を次々と、焼き殺すなど残忍な方法で抹殺した。そのなかに、市辺押磐皇子(いちのへのおしはのみこ)もふくまれていた。近江に狩りに誘いだされ、雄略に弓矢で射殺された。その身は切りきざまれ、馬のかいば桶に入れて埋められた。すさまじい殺され方である。この皇子の2人の息子が、のちの顕宗(けんぞう)、仁賢(にんけん)両天皇である。当然、雄略に対するウラミもハンパではない。『古事記』によると、最初に天皇位についた弟の顕宗は、雄略の「御陵を毀(やぶ)らむと欲(おも)ほし」た。のちに仁賢となる兄がかわりに壊しに行ったが、すぐに帰ってきて、「その陵の土を少し掘りつ」と答えた。 徹底破壊をのぞんだ顕宗がただすと、いくら父のカタキとはいえ、兄は後の世のこともあると応じ、納得させた。破壊の規模は分からないが、「未完成」と思わせるていどには壊してしまったのではないだろうか。この古墳をさらに難解にさせているのは、戦国期に地元の豪族の城まで築かれ、そうとうな規模で墳丘部が壊され、改変されたからである。蒲生もミササギの中に入りこみ、農家からあがるカマドの煙や、歓声をあげて遊びまわる子供たちの姿を眺めたはずである。「う~む」と悩んだすえ、「分からん」とサジを投げたのであろう。--ぐるりと一周まわったが、もうネコはいなかった。おりからの寒さで凍りついた濠には、カモが泳いでいた。ときたま氷の上にあがり、悠然と歩いていた。もちろん、ギョッとはならなかった。(福嶋敏雄)2013.1.14 15:00更新私の家から遠くない所にある■「河内大塚山古墳」■は、昭和のはじめまで、集落があった。「○○さんのお母さんは、古墳の中の家で生まれた」などという話を地元の人から聞いたことがある。古墳が造られたのは■古市大溝■と同じくらいの時代なのだろうか。■古市大溝は■全長4kmにもおよぶ古代の運河だった。しかし、その用途は灌漑説、船運説などがあり、意見の一致をみていない。 掘削時期については、古市古墳群の南群の築造と古市大溝は密接に関わっていたとして、古墳時代中期の5世紀ごろに築かれたとする意見が一般的である。だが、この大溝を掘削するのに破壊された古墳があることが明らかになってきており、6世紀中葉以降に掘削されたとの意見もある。*以前から気になっていたこの古墳の記事をアップしておく。 この古墳は「大阪みどりの100選」にも選ばれている所で、写真を撮っていたらサギ?がいた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.24
コメント(0)
-

トリビア:金沢にお寺が多いわけ
7月10日(月)■金沢■に行ってガイドさんの案内で、まちを歩いた。「金沢は、お寺が多いんですよ。」と言いながらガイドさんは、案内してくれた。 先日、■武士の家計簿■を読んで、金沢にお寺が多いわけが分かった。★加賀藩は、百万石と大きな藩なので、それに見合った沢山の武士がいた。武士の家禄(給料)は、200年以上も前の先祖の働きに対してのものだった。世襲制ということは、「先祖のおかげ」ということで、武士は先祖を大事にした。下級武士の猪山家も「武士」という身分だから仏壇への花代、菩提寺への喜捨、仏様へのお供えとお金を使う。借金の返済にあてることを決断し、薬缶まで売る猪山家であっても寺に今の価値で年間18万円のお布施をする。金沢市内に寺院が多いのは、加賀百万石は、武士と領民が多い。多くの武士が先祖を祀り、寺に沢山の寄進をしたからだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.23
コメント(0)
-

あきない世傳(せいでん)金と銀:高田郁
■あきない世傳 金と銀■物がさっぱり売れない享保期に、摂津の津門村に学者の子として生を受けた幸(さち)。父から「商は詐なり」と教えられて育ったはずが、享保の大飢饉や家族との別離を経て、齢九つで大坂天満にある呉服商「五鈴屋」に奉公へ出されることになる。慣れない商家で「一生、鍋の底を磨いて過ごす」女衆でありながら、番頭・治兵衛に才を認められ、徐々に商いに心を惹かれていく。果たして、商いは詐なのか。あるいは、ひとが生涯を賭けて歩むべき道かー大ベストセラー「みをつくし料理帖」の著者が贈る、商道を見据える新シリーズ、ついに開幕! ■NHKのドラマで見て好きになり読んだ■「みおつくし料理帖」シリーズの次に読んだのが「あきない世伝(せいでん)金と銀」。「みおつくし・・・」と同様、家を無くした娘が奉公に出るという物語。幸(さち)の奉公先は天満の天満堀川近くにある。■今は無くなっている天満堀川■は、先日、見に行ったところだ。江戸時代の商人の暮らしがよく分かる。また、船場と天満の関係もよく分かる。★おはぎは12個、入れ物は一升枡。昔ながらの作法通りに用意した・・・。(猪子の日のしきたり)★商家の純白の漆喰壁、磨かれて艶やかな格子、風に翻る色鮮やかな長暖簾、それに灰色の瓦屋根。それぞれが秋の陽射しに映えて眩い。天満に足を踏み入れた時、幸は町並みの美しさに怯んだ。★この界隈(あたり=天満)の井戸水は金気が強く、飲み水に適さない。料理や飲み水に使うものは、毛馬あたりで汲まれた大川の水を水売りから買わねばならなかった。幸は「みず」と書かれた木の札を表口の格子戸に下げに行く。この札を見て、水売りが水を運んでくれるのだ。■みおつくし料理帖■は、食べたくなる料理が出てきたのに、「あきない世傳・・・」は貧しい食卓だ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.22
コメント(0)
-

武士の家計簿:「加賀藩御算用者」の幕末維新
■武士の家計簿■「加賀藩御算用者」の幕末維新「金沢藩士猪山家文書」という武家文書に、精巧な「家計簿」が例を見ない完全な姿で遺されていた。国史研究史上、初めての発見と言ってよい。タイム・カプセルの蓋を開けてみれば、金融破綻、地価下落、リストラ、教育問題…など、猪山家は現代の我々が直面する問題を全て経験ずみだった!活き活きと復元された武士の暮らしを通じて、江戸時代に対する通念が覆され、全く違った「日本の近代」が見えてくる。【目次】(「BOOK」データベースより)第1章 加賀百万石の算盤係/第2章 猪山家の経済状態/第3章 武士の子ども時代/第4章 葬儀、結婚、そして幕末の動乱へ/第5章 文明開化のなかの「士族」/第6章 猪山家の経済的選択■時代小説■がマイブーム。映画で見た■武士の家計簿■の原作を読んだ。幕末から明治時代にかけての直之と成之のやり繰りが時代の背景とともに描かれていて興味深い。小山市進(いちのしん)・・・やす之(やすゆき)・・・信之・・・直之・・・成之の5代に渡る猪山家の物語。「へぇ~!!へぇ~!!」の連続だったので、箇条書きにしてみる。★「加賀藩御算用者」は、世襲ではなく、試験で召し抱えられた。★東大の赤門は、藩主の婚礼に際して建てられた祝いの門で、その段取りをしたのが、三代目の信之だった。★武士の家禄(給料)は、200年以上も前の先祖の働きに対してのものだった。いくら頑張って働いても、現状の給料はよくならないという矛盾があった。★直之は家財道具を処分し、借金の返済にあてることを決断。家財道具なら何でも売る。古くても何でも売り買いできるのが■江戸のリサイクル社会。■直之は「薬缶」も売るが、72000円って高価!!★両替について。江戸時代の日本は金銀の二つの通貨圏があった。東日本は「金遣い」、西日本は「銀遣い」。領主から拝領するのは、金貨の小判だが金沢は銀遣い。日頃使うのは銭。金銀銭の三種類があるので、両替が必要だった。★明治4年7月14日、廃藩置県で「金沢藩」が消滅、翌8月「金沢県」となった。県政にあったのは、薩摩出身者だった。 主役は、「加賀藩御算用者」の5人だけれど、家族、親戚も出てくるので、大河ドラマにすれば面白いだろうと思う。■金沢にし茶屋街■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.20
コメント(0)
-
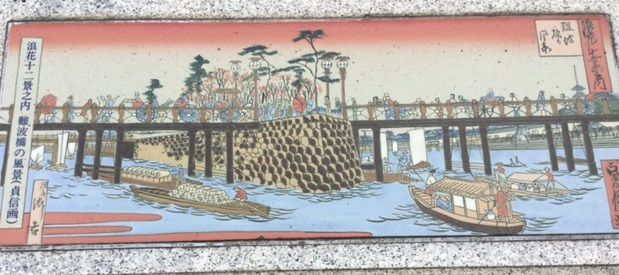
なにわ三橋
(略)杖を持った手で西側を指し■「あれが難波橋」■東側を指して■「あっちが天満橋や」■と教える。滔々と流れる大川、その広い川幅に合わせ、並んで架けられた三つの橋は、この地に暮らす者に誇りでもあった。「あれが天満の青物市や。見てみ、大根を仰山積んだ船が行くやろ?天満の大根、天王寺の鏑(かぶら)、難波の干瓢、吹田の慈姑(くわい)・・・大坂中の美味い食材が集まる場所なんやで。(略)」「この■天神橋■は今でこそ公儀橋やけんど、もとはあの天満宮が管理してはったんやで。せやから天神さんの橋で「天神橋」なんや」■「銀二貫」■より。『公儀橋』とは、江戸時代、江戸、大阪、京などで、公儀(江戸幕府)の経費で架設、架け替え、修復が行われた橋のことを言う。江戸では『御入用橋』と称し、まれに『公儀橋』と呼ばれ、大坂、京都では一般に『公儀橋』と呼ばれていた。西ひがし みな見にきたれ なには橋 すみずみかけて 四四の十六 蔭山 梅好難波橋からは、“西ひがし(西東)みな見(南)きたれ(北)”というように、東西南北の四方に四つずつ合計十六の橋が見渡せた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.19
コメント(0)
-

菜種晴れ:山本一力
■菜種晴れ■涙は見せない。江戸で花咲かすまで。安房勝山の菜種農家の末娘・二三は、五歳にして江戸深川の油問屋に養女として貰い受けられる。生家の母親譲りのてんぷらの腕、持ち前の気丈さで、江戸の町に馴染んでゆく。やがて、大店の跡取りとして逞しく成長した二三を、新たな苦難が見舞う。いくつもの悲しみを乗り越えた先に、二三が見たものとはー。涙の後に爽快な、人情時代小説。 今、■時代小説■がマイブーム。現在の千葉県・勝山から江戸深川の油問屋に養女になる二三(ふみ)の物語。二三(ふみ)の生れた家は、菜の花を作っているという設定。勝山が生産地で江戸が消費地という設定だが、調べたら■今も■菜の花作りが盛んなようだ。(▲琵琶湖のほとりの菜の花)菜の花畑は、南房総の花づくり発祥の地、南房総市和田町は冬でも暖かく12月から鮮やかな花畑が広がります。早春の風物詩となっています。また、当時の水運が分かって面白い。(▲パリ・サンマルタン運河を行く船)■千石船■千石船(せんごくぶね)は、船型に関わらず積石数(つみこくすう)を意味していたが、千石積みの弁才船が広く普及したため弁才船の俗称として千石船と呼ばれるようになった。千葉勝山から江戸■千葉・勝山の地図■勝山から千石(せんごく)船で江戸に行くのだが、途中、船橋に泊まるのだそうだ。勝山~船橋まで、5時間もかかる。ちなみに、江戸時代は三十石船で京都→大阪は片道約6時間(下り)。船橋から江戸までは、乗り合い船があったのだそうだ。(▲パリ・シテ島で見た看板)■屋形船■和船の一種で、主に船上で宴会や食事をして楽しむ、屋根と座敷が備えられた船のこと。油問屋、「勝山屋」が同業者と2泊3日で江島詣に行く時に使ったもの。主人の代わりに、二三(ふみ)が行った。(▲ロンドンの運河に浮かぶボート)■猪牙舟・猪牙船(ちょきぶね)■猪の牙のように、舳先が細長く尖った屋根なしの小さい舟。江戸市中の河川で使われたが、浅草山谷にあった吉原遊郭に通う遊客がよく使ったため山谷舟とも呼ばれた。長さが約30尺、幅4尺6寸と細長く、また船底をしぼってあるため左右に揺れやすい。そのため櫓でこぐ際の推進力が十分に発揮されて速度が速く、狭い河川でも動きやすかった。物語の中では、揺れの激しい舟の代名詞として使われていた。(▲クライストチャーチの公園にて)■八丁櫓(はちょうろ)■初鰹が神奈川宿近海で獲れた時、日本橋の魚河岸まで運ぶ船。名前の通り、櫓が八丁あり、客は5人までの快速船。(▲湖水地方の「スチーマー・ヨット・ゴンドラ」)■五大力船(ごだいりきぶね)■五大力船(ごだいりきせん、ごだいりきぶね)とは、江戸を中心に関東近辺の海運に用いられた海川両用の廻船の事。五大力の語源は五大力菩薩からという説が有力である。海上輸送が発達した江戸時代に主に活躍し、昭和初期まで用いられてきた。主に東京湾内の輸送に用いられ、武蔵・伊豆・相模・安房・上総・下総海辺で穀類や薪炭などの運送に用いられる他、人を乗せて旅客輸送も行っていた。江戸日本橋本船町の河岸と上総国木更津村間で貨客輸送を行っていた船は特に木更津船と呼ばれ、歌川広重の浮世絵にも描かれている。(▲のれんの町、岡山県・勝山)江戸末期のことなので、黒船まで出てくる。5歳から30過ぎまでの波乱に満ちた女の物語は、テレビや映画向きだと思った。(▲って、タライやないかいっ!!)写真と内容は、まったく関係ありません。m(_ _"m)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.17
コメント(0)
-

ニュージーランドのケーキ、「パブロバ」のトリビア
先日、■フェリシーと夢のトウシューズ■というバレエの映画を見たからというわけではないが、バレエにまつわる、ケーキの話を・・・。それは、パブロバ(パブロアともパブロワともいう)というケーキ。このケーキのことを知ったのは、去年の1月~2月に行ったニュージーランド(NZ)の■B&B■でのこと。NZの日本人向けの雑誌に載っていて、本物が見たいと思ったが見ることが出来なかった。今年の2月~3月■またNZ■に行くことが出来、スーパーで見つけた!!ニュージーランドのスーパーでは焼いた生地だけ売られていて、自分たちで生クリームやフルーツを盛って食べることもできます。ただし市販されているパブロバは砂糖の量がものすごく多くて、歯が溶けるかも!?と思うほど甘いものが多いです。パブロバはどちらかというと普段食べるデザートはなくて、お祝いの時や人がいっぱい集まったときに出されるケーキみたいな扱いをされることが多いみたいです。いわれてみれば語学学校の誕生日会ではパブロバが出てました。■パブロバの名前の由来■ところでパブロバってなんかちょっと変わった名前ですよね。 英語っぽくないし、だからと言ってマオリ語っぽくもない。ちなみにアルファベットで書くとPavlovaと書きます。パブロバの名前の由来はロシアのバレーダンサーAnna Pavlovaから来ています。彼女は世界で初めて世界ツアーをしたバレーダンサーであり、歴史上でもっとも素晴らしいバレーダンサーの一人と賞されているすごい人です。発祥の地はどっち?ニュージーランド?オーストラリア?パブロバの発祥の地がニュージーランドなのか、オーストラリアなのかはもう何十年にもわたって議論されています。でも、実はキチンと紐解いていくとその結果はすでに出ていました。意外とニュージーランド人もオーストラリア人もその真相を知らないのかもしれません。パブロバというお菓子が歴史に名前を見せるのは、奇しくもニュージーランドとオーストラリアで同じ年1926年です。ニュージーランドのパブロバが最初に登場するのはKeith Moneyが書いたAnna Pavlovaの伝記です。Anna Pavlovaが1926年に世界ツアーでウェリントンに訪れたとき、ホテルでパブロバを食べたと記されています。そしてオーストラリアのパブロバが登場するのも1926年。同じ年だった理由の1つは上で紹介したAnna Pavlovaが世界ツアー中の1926年に両国を訪れ、それぞれが彼女をモチーフにしてデザートを作ったからです。では、どちらがオリジナルなんでしょうか?実はどちらがオリジナルなのかを決める決定的なポイントは「どちらが早く作ったか」ではありません。 実はどちらが「今現在、一般的に食べられているパブロバを作ったのか」が重要な鍵を握っているんです。ウェリントンでAnna Pavlovaが食べたパブロバは、Anna Pavlovaが着ているバレエの衣装チュチュをモチーフにした卵白を焼いたデザートでした。メレンゲで形を作って生クリームが載っていたと彼女の伝記には書かれているそうです。ということで、パブロバはニュージーランド発祥ということで良いでしょうか。唯一決定に欠けるのはウェリントンで食べられたパブロバが本当にメレンゲで作られたデザートなのか、その作ったシェフの手記などが残っていないことです。でも、かなり核心に迫れたような気がしています。■日刊ニュージーランド■ ところで、このケーキの名前の由来にもなった有名なバレリーナ、アンナ・パブロバ。山岸涼子のバレエ漫画「アラベスク」の主人公、ノンナ・ペトロワの名前は、アンナ・パブロバからとったとか・・・。スーパーで「パブロバ」を何回も見つけたけれど、あまりの大きさに食べることを諦め、写真だけ撮った私。(ノД‘)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.16
コメント(0)
-

フェリシーと夢のトウシューズ★19世紀末パリ
■フェリシーと夢のトウシューズ■さぁ、夢へ跳ぼう。19世紀末のフランス。ブルターニュ地方の施設ではバレリーナを夢見る少女フェリシー(声:エル・ファニング)が軽やかに踊っていた。いつかはパリ・オペラ座の舞台に立つという大きな夢があるものの、施設で暮らす彼女にとってそれは遠い存在だった。ある日、同じ孤児院の親友であり、偉大な発明家を志すヴィクター(声:デイン・デハーン)に誘われたフェリシーは、エッフェル塔が建設中のパリを目指して施設を抜け出す。やっとの思いでパリに辿り着いたフェリシーだったが、突然ヴィクターとはぐれてしまい、右も左もわからず不安を抱えるフェリシーは、奇跡的に見つけたオペラ座で美しく踊るエトワールの姿を目にする。エル・ファニングがバレリーナを目指す少女の声を演じるアニメーション。施設で育った少女が持ち前の情熱で度重なる困難を克服し、夢を叶えようとする姿が描かれる。バレエシーンの振付をパリ・オペラ座バレエ団芸術監督であるオレリー・デュポンとジェレミー・ベランガールが担当するなど細部へのこだわりにも注目。 19世紀末のフランスという設定。もっと時代を詳しくと思って調べたら■あった!■1888年だ!写真を見ると、1888年、半分出来たエッフェル塔がうつっている。1888年と断定して、もう一つのカギ「自由の女神」を調べてみた。自由の女神像はアメリカ合衆国の独立100周年を記念して、独立運動を支援したフランス人の募金によって贈呈され、1886年に完成した。えっ!!1886年に完成してる!!映画の中では、製造中だったけど・・・。結局、映画の中の時代は、断定できなかったけど■自由の女神を作っている写真があった!!■1878年、パーツを作成するパリの工場風景。これを見に30万人が訪れたそうです。古き良き時代と言われた時代のパリが、映画の中で、そこここに見られる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.15
コメント(0)
-

麗しのサブリナ★サブリナパンツ
■麗しのサブリナ■実業家一家の兄と弟、一家のお抱え運転手の娘との恋のかけひき。富豪ララビー家のお抱え運転手の娘サブリナ(オードリー・ヘップバーン)は、邸の次男坊デイヴィッド(ウィリアム・ホールデン)に仄かな思いを寄せていた。しかし父は娘に叶わぬ恋を諦めさせようと、彼女をパリの料理学校へやる。それから2年、サブリナは一分のすきのないパリ・スタイルを身につけて帰ってきた。女好きのデイヴィッドは美しくなったサブリナにたちまち熱を上げ、自分と財閥タイスン家の令嬢エリザベス(マーサ・ハイヤー)との婚約披露パーティーにサブリナを招待し、婚約者をそっちのけにサブリナとばかり踊った。デイヴィッドの兄で謹厳な事業家ライナス(ハンフリー・ボガート)は、このままではまずいとデイヴィッドをシャンペン・グラスの上に座らせて怪我をさせ、彼が動けぬうちにサブリナを再びパリに送ろうと企てる。名匠ビリー・ワイルダー監督によるロマンティックコメディ。『ローマの休日』(1954)に引き続き、ヘプバーン演じる主人公のファッションが話題を呼び、サブリナ・パンツと呼ばれるスタイルが世界中で流行した。■「サブリナパンツ」の名を生み出す■この映画でのオードリー・ヘプバーンのファッションは話題となった。オードリーとデザイナーであるジバンシーの出会いは、この映画がきっかけだったと言われている。まだ二十代で若い二人はここで初めて出会い、その後のオードリーの出演作にもジバンシーの洋服が使われているのは有名である。この映画の衣装で、特に印象深いのは、黒の膝下丈のパンツであろう。女優にしてはかなり細身で、グラマラスなスタイルが好まれた時代ではあまりよく思われなかったオードリーのスタイル。しかしこの映画の衣装は彼女のスレンダーな体型を引き立てている。黒の膝下丈パンツは、たぶんグラマラスな体型では似合わず、オードリーのすらっとしたスタイルだからこそ魅力的に見える。まだ映画がモノクロだった頃なので、白い肌とのコントラストでかなりシャープに美しく映っている。オードリーがこの映画で着用したことにより、50年代「サブリナパンツ」と呼ばれて爆発的にヒットする。■主役3人が歳が違い過ぎる。■★オードリー・ヘップバーン(主役・サブリナ役)生年月日:1929年5月4日死没:1993年1月20日 (63歳)身長:170 cm1954年(製作年)・・・25歳★ハンフリー・ボガート(長男ライナス)生年月日:1899年12月25日(19世紀生まれ!!!)出身地:ニューヨーク死没:1957年1月14日 (57歳)1654年(製作年)・・・53歳★ウィリアム・ホールデン(次男デイヴィッド)生年月日:1918年4月17日死没:1981年11月12日 (63歳)身長:180.3 cm1654年(製作年)・・・36歳25歳のサブリナと53歳・長男の歳の違いは親子ほど。もちろん、サブリナは20歳~22歳と、ライナスももう少し若いという設定なのだろうが、もう少し、なんとかならなかったのかと思う。突っ込みどころも満載なのだが、オードリーの美しさを楽しみたい。■午前十時の映画祭8■☆ローマの休日 ★麗しのサブリナ ☆昼下りの情事 ★おしゃれ泥棒 と、A・ヘプバーンの映画が続く。■映画と写真展■◆写真展◆「オードリー・ヘプバーン」大阪開催~今よみがえる、永遠の妖精 映画編~会場大丸心斎橋店 北館14階イベントホール(大阪府)公演期間2017/09/20(水)~2017/10/02(月)開演時間開催日により異なります備考※小学生以下無料【会 期】2017/9/20(水)~10/2(月) ※会期中無休【入場時間】10:00~20:00(20:30閉場)※最終日は17:30まで(18:00閉場)【お問合せ】大丸心斎橋店 06-6271-1231(代表)【2会場共通前売券について】(9/19までの販売)※大丸京都店(ファッション編)・大丸心斎橋店(映画編)の本展入場券2枚セットです。◆映画◆「ティファニーで朝食を」無料上映。9月20日(水)~22日(金)各日、午前11時、午後3時、6時30分23日(土・祝)午後6時30分定員各回とも200人大丸心斎橋店:北館14階心斎橋劇場・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.14
コメント(2)
-

水晶橋:堂島川
水晶橋は、正確に言えば橋ではなかった。この橋は本来は昭和4年に完成した堂島川可動堰という、河川浄化を目的として建設されたゲートである。橋面の本体アーチと上部の小アーチの配置が絶妙で、重厚さの中に気品ある優雅さを感じさせた。可動堰にこれほど凝ったデザインが用いられているのは驚きだが、実は鉄筋コンクリート製のこの可動堰も、淀屋橋や大江橋と同じく、1921(大正10)年にスタートした「第一次大阪都市計画事業」の一環として建設されている。大正後期から昭和前期にかけての大阪市は、市域面積や人口、工業生産額で東京市を上回り、日本一の都市となった。その大阪を近代都市化するための市街地改造事業が、御堂筋の建設をも含む「第一次大阪都市計画事業」であった。この事業により、現在に至る「大阪の都市景観」の基礎が形成されたが、大阪の中心ゾーンである中之島周辺の橋梁(きょうりょう)に関しても、景観面から徹底的にデザイン性が吟味された。堂島川可動堰のゲートが外部から見えにくくなっていたのも、そして、ゲートの開閉操作室が、装飾的でモダンな照明灯の台座に擬せられていたのも、中之島ならではの景観や風情と調和させるための、意匠的な工夫だったのである。水晶橋という名の由来は今一つはっきりしないが、橋上にある照明灯が水面に映る様子が水晶のかがやきに似ているということから出た愛称であるとする説もあり、水都大阪が繁昌するようにという意味で水昌橋であるという説もあって決め難い。堂島川可動堰の造形的な美しさは、後に国の重要文化財となった淀屋橋や大江橋と比べても遜色なく、1929(昭和4)年の完成当時から、多くの画家に描かれてきた。堂島川可動堰は流速調整機能によって長年、水質改善に寄与する一方、人道橋としても利用されてきた。それが、法的な手続きを経て名実ともに橋となったのは、老朽化に伴う改装整備が行われた1982(昭和57)年のこと。この際に、アスファルト舗装だった橋面は、花崗(かこう)石と花崗擬石で敷き直され、橋上に植栽やベンチなどが設けられた。橋名の由来については、「水面に映る照明灯が水晶の輝きを思わせるので、以前から自然発生的にそう呼ばれていた」との説が有力だが、「水都大阪の『水』と、繁昌の『昌』の字を組み合わせた」等の説もあり、判然としない。2002(平成14)年に可動堰が撤去され、築後73年にしてようやく、純粋な意味での橋となった水晶橋は、いまも中之島の景観や散策になくてはならない橋として、独自の存在感を示している。電球色LEDでアーチ部分を強調するようにライトアップされた夜の水晶橋も、見惚(ほ)れるほどに美しい。水晶橋から上流、東を見ると、見えるこの構造物が気になる。これも水を浄化するための設備のひとつだろうか・・・。■住所〒530-0005 大阪市北区西天満2丁目~中之島1丁目 ■アクセス地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩5分 着工 - 1926年(大正15年)6月完成 - 1929年(昭和4年)3月改装 - 1982年(昭和57年)10月・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.13
コメント(0)
-

蓮花(れんか)の契り・出世花:高田郁
■蓮花(れんか)の契り・出世花:高田郁■下落合で弔いを専門とする墓寺、青泉寺。お縁は「三味聖」としてその湯潅場に立ち、死者の無念や心残りを取り除くように、優しい手で亡骸を洗い清める。そんな三昧聖の湯灌を望む者は多く、夢中で働くうちに、お縁は二十二歳になっていた。だが、文化三年から翌年にかけて、江戸の街は大きな不幸に見舞われ、それに伴い、お縁にまつわるひとびと、そしてお縁自身の運命の歯車が狂い始める。実母お香との真の和解はあるのか、そして正念との関係に新たな展開はあるのか。お縁にとっての真の幸せとは何か。生きることの意味を問う物語、堂々の完結。■出世花■ の続編。「夢の浮橋」の中で、永代橋崩落事件が題材になっているのがある。永代橋が架橋されたのは元禄11年(1698年)8月であり、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の50歳を祝したもの。橋脚は満潮時でも3m以上あり、当時としては最大規模の大橋であった。橋上からは「西に富士、北に筑波、南に箱根、東に安房上総」と称されるほど見晴らしの良い場所であったと記録(『武江図説』)に残る。元禄15年(1702年)12月の赤穂浪士の吉良上野介屋敷(所在地は現墨田区両国)への討ち入りでは、討ち入り後に上野介の首を掲げて永代橋を渡り、泉岳寺へ向ったという。■落橋事故■幕府財政が窮地に立った享保4年(1719年)に、幕府は永代橋の維持管理をあきらめ廃橋を決めるが、町民衆の嘆願により橋梁維持に伴う諸経費を町方が全て負担することを条件に存続を許された。通行料を取り、また橋詰にて市場を開くなどして維持に務めたが文化4年8月19日 (旧暦)(1807年9月20日)、深川富岡八幡宮の12年ぶりの祭礼日(深川祭)に詰め掛けた群衆の重みに耐え切れず、落橋事故を起こした。橋の中央部よりやや東側の部分で数間ほどが崩れ落ち、後ろから群衆が次々と押し寄せては転落し死傷者・行方不明者を合わせると実に1400人を超え、史上最悪の落橋事故と言われている。この事故について大田南畝が狂歌や「夢の憂橋」を著している。永代と かけたる橋は 落ちにけり きょうは祭礼 あすは葬礼 南町奉行組同心の渡辺小佐衛門が、刀を振るって群集を制止させたという逸話も残っている。上の史実も小説の中で知った。架けられてから100年以上たった橋は、老朽化が進んでいたのだろう。大事件だったのか事件を扱った多くの小説がある。 永代橋が落ち、1000人以上もの死者が出たという事件を読みながら、天神橋のことを思い出した。1832年(天保3年)の天神祭において、橋上からだんじりが大川へ転落して溺死者13名を出す事故があり、「天神橋長いな、落ちたらこわいな」と童歌に歌われた。この本のタイトルになっている「蓮花(れんか)の契り」。蓮花(れんか)は、仏の花という意味である。生きて契るよりも、より永遠という仏の道での契りという意味だ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.12
コメント(0)
-

日本人のおなまえっ!*ワラビーナ(童名)
先日テレビで■日本人のおなまえ■というのがあった。日本人の名前の由来などの番組だが、この回は沖縄編。その中で特に面白かったのが■「童名(ドーナ、ワラビナー)」。■沖縄には名字と下の名前以外に、さらに3つの名前があった!?今回、番組の徹底取材により、かつて琉球王国だったある島では「トゥク」や「マニュ」など、不思議な響きの名前で呼び合う風習があることを発見!南国の島暮らしに息づく“もうひとつの名前”の謎と魅力に迫る。さらに“一家の伝統が刻まれた”お名前や、“一族の結束を強める”お名前も登場。 沖縄の女性の名前には、「ウシ、カマ、ナベ、カマド、ツル、カメ、マツ、ウトといったものが比較的多く見られる」(寿岳1979:132-133) ツル、カメ、マツといった名前は、縁起のいいものとして本土にもその名を持つ人が存在するが、ウシ、カマ、ナベ、カマド、ウトは、いずれも本土ではなじみのない名前である。朝岡(1993)によると、沖縄ではカマドは「火の神」とされている。また、昔、沖縄では、カマとカマド、カマとナベがそれぞれ同じような意味合いを持っていたという。つまり、カマドが火の神であることから、それに類似するカマやナベも火の神と結びつき、宗教的にあがめられる存在になったのではないかと推測することができる。また、ウトに関しては、寿岳(1979)が、「祖先の霊に線香を上げて合掌することを「ウートートー」等ということがあり、そこから出たものとも考えられる」(寿岳)1979:133)と述べている。以上のことから、沖縄特有の女性の名前は、宗教的な意味合いを含むものが多いと考えられる。 ここで私は、あることに気が付いた。それは、「ナヴィの恋」という映画だ。「ナヴィ」というお婆さんの沖縄が舞台の映画を見たのは、もう20年近く前のこと。変わった名前と思っていた。そうか、このナヴィとは、鍋のことで、あのお婆さんのワラビーナ(童名)だったのか!!■日本人のおなまえっ!■は、前編と後編が再放送される!!★8月15日(火) 午前0時10分 人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ!【沖縄・前編】★8月22日(火) 午前0時10分 人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ!【沖縄・後編】名前で旅する沖縄!■八重山諸島に行った時のblog■■沖縄:は行とパ行■■八重山諸島のトリビア■■与那国の古代文字:カイダ文字■■「月刊やいま:古井戸の記憶■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.11
コメント(6)
-

海辺の生と死★島尾敏雄とミホ
■海辺の生と死■♪音が出ます!!ともに沿うて、行きたいと思っていた・・・。運命がそれを許さないなら、見届けてから散ろうと決意した。昭和二十年八月、旧暦文月のことであった。昭和19年(1944年)12月、奄美カゲロウ島。ある日、国民学校教員として働く大平トエ(満島ひかり)のもとに、島に新しく駐屯してきた海軍特攻艇部隊隊長・朔中尉(永山絢斗)が兵隊の教育用に本を借りたいとやって来る。島の子供たちに慕われ、軍歌よりも島唄を歌いたがる軍人らしくない朔にトエは惹かれ、やがてトエは朔と逢瀬を重ねるようになっていく。しかし、時の経過と共に敵襲は激化、沖縄は陥落し、広島に新型爆弾が落とされる。そして、ついに朔が出撃する日がやってきた。母の遺品の喪服を着て、短刀を胸に抱いたトエは家を飛び出し、いつもの浜辺へと無我夢中で駆けるのだった……。 「死の棘」の原作者である島尾敏雄とその妻・島尾ミホの出会いの物語を「アレノ」の越川道夫監督が、満島ひかり主演で映画化。太平洋戦争末期の奄美を舞台に、島に駐屯する海軍特攻艇部隊隊長・朔と国民学校教師・大平トエが、恋に落ち結ばれるまでを映し出す。共演は「闇金ウシジマくん ザ・ファイナル」の永山絢斗、「帝一の國」の井之脇海、「バンコクナイツ」の川瀬陽太、「かぞくのくに」の津嘉山正種。「死の棘」の作者、島尾敏雄の奥さんが作家だって知らなかった。「死の棘」と並んで置いてあった「海辺の生と死」が気になって買った。 私は、友人が「死の棘」のファンだったから名前だけは、何回も知っていたが島尾敏雄はおろか、島尾ミホも「海辺の生と死」も知らなかった。 そんなに有名じゃないのだろうと勝手に思っていたのだけれど映画館は満員で立ち見も出た。水曜で1100円ということもあるのだけれど、この映画、大阪では、■テアトル梅田■だけ。朔中尉役の永山絢斗(けんと)がいい。朝の連続小説「べっぴんさん」(2016年) では、「?」だったけど、NHK土曜時代ドラマ「みをつくし料理帖」の永田源斉 役で、時代劇が似合っていていいなと思い始めた。実兄は俳優の瑛太!!!って今知った!朔中尉に忠実な部下役の井之脇海(いのわき・かい)もいい。こちらは、朝の連続テレビ小説「ひよっこ」で、音楽好きな青年役で出ていた。映画の中で使われる、うちなーぐち(沖縄方言)や言い伝えも素晴らしい。原作はまだ読んでいないが楽しみだ。「死の棘」が大好きで何回も読んでいた■友人が生きていたら、どんな感想をいうだろう・・・。■ファンタジックなところもある、いい映画だったのだが、一つだけ気になることが・・・。それは、主人公トエの服装。素敵なブラウスとスカート、髪には、リボン、下着もレースが付いていた。当時、おしゃれは、いくら若い女性といえど、御法度。あの恰好だと「非国民」と言われそうだ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.10
コメント(0)
-

栴檀木橋(せんだんのきばし):土佐堀川
栴檀木橋(せんだんのきばし)は、大阪市の土佐堀川に架かる、北区中之島と中央区北浜を結ぶ橋。浪速の名橋50選選定橋。江戸時代、中之島には諸藩の蔵屋敷が建てられ、船場との連絡のために土佐掘川には多くの橋が架けられていた。栴檀木橋もそうした橋の一つであった。橋名の由来は『摂津名所図会』ではこの橋筋に栴檀ノ木の大木があったためとしているが、詳らかではない。明治になっても木橋のままであった栴檀木橋は明治18年の大洪水で流失した。再び架けられたのは大正3年のこととされる。これは明治37年に、大阪府立図書館が建てられ、明治末には大阪市庁舎の建設が決定されるなど、橋が再び必要となっていたためであろう。その後、昭和10年に架け替えられた橋は桁の高さが一定のシンプルな美しさを強調した設計であったが、当時の設計者はこれを理想としていたようである。昭和60年9月、新しい橋に架け替えられたが、旧橋のイメージを大切にしながら橋面などは府立図書館や中央公会堂など、背景にある歴史的建築物との調和を考えてデザインされた。また、センダンノキをモチーフにした欄間パネルが取付けられている。由来碑と大正時代の親柱は橋梁の橋詰に設置され、橋の歴史が一目でわかるようになっている。「この脇差はせんだん(栴檀)の木の橋から川へ、沈む来世は見えぬ沙汰」とは、天満で隣家の油屋の女房・お吉を殺し、金を奪った極悪人の与兵衛が、その凶器を土佐堀川に捨てるときに吐く台詞(近松門左衛門作・「女殺油地獄」の下之巻より)。(▲カフェから、正面に公会堂、左に栴檀の木橋を見る。)■【浪速の橋ものがたり】栴檀木橋■(栴檀の木橋より見た下流には、淀屋橋が見える。)(▲栴檀の木橋から船場を南に行く道を栴檀の木筋といい栴檀の木が植えてある。)■栴檀の木筋■「栴檀は双葉より芳(かんば)し」のことわざでよく知られるが、これはセンダンではなくビャクダン(白檀)を指す。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.09
コメント(2)
-

鉾流橋(ほこながしばし):堂島川
■鉾流橋(ほこながしばし)■堂島川に架かり、中之島北岸(大阪市中央公会堂や東洋陶磁美術館付近)と西天満(大阪高等裁判所付近)を繋ぐ橋。毎年7月24日の朝、橋のたもとで天神祭の「鉾流神事」(川に神鉾を流し、その年の神霊渡御地・お旅所を決定する行事)が行われることから、この名前がついたそうだ。初めて橋が架けられたのは、大正7年(1918)とされているが、現在の橋は昭和4年(1929)に完成。 高欄、照明灯、親柱など日本調にクラシックなデザインが採用されたのは、天神祭の鉾流神事が行われることを考慮したためと思われる。その後、戦争中の金属供出などによって、これらの高欄、照明灯は失われたが、昭和55年(1980)に中之島地区にマッチしたクラシックなデザインの高欄や照明灯、 レンガ敷きの歩道などが整備され、現在に至っている。7月24日の「鉾流神事」が行われている約40分間は、普段閑静なこの橋も、橋上からの見物人で埋め尽くされている。江戸時代の初めにはこの行事は、お旅所の常設化にともなって廃絶したといわれる。大阪町衆の切なる要望によって昭和5年(1930)に復活し、現在へ受け継がれている。 天満警察署の前に立つ鳥居のある場所が、神鉾を流す浜である。そこへかけられた橋の名が「鉾流橋」となった。(▲鳥居には「明治四十三年仲秋建立」とある。)ちなみに鉾流の神事は、明治維新の混乱で船渡御が中止されたのに伴って、長らく行われてこなかった。船渡御は明治15年に復活したが、鉾流の神事は中止されたままであり、復活したのは昭和5年(1930年)になってから。つまり鉾流橋が架けられたとき、鉾流の神事は行われていなかったのであり、昭和4年(1929年)の架け替えがきっかけになって復活したということになる。橋の上から中之島の方に、石段が見えた。この橋は大正7年(1918)に出来たというが荷揚げに使ったのだろうか?それとも、神事に使ったのか?石段のすぐそばには■大阪市立東洋陶磁美術館■がある。 ■鉾流橋(ほこながしばし)■住所〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目~中之島1丁目 アクセス地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩5分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.08
コメント(0)
-

出世花*高田郁
■出世花*高田郁■主人公の縁(艶、正縁)が9歳から16歳までの話。妻敵討ちを願う父矢萩源九郎に同行して各地を放浪していた艶は、空腹のために食べた野草に混じっていた毒草によって行き倒れる。二人は近くの青泉寺(せいせんじ)の僧侶たちによって発見されるが、看病の甲斐なく源九郎は亡くなってしまう。そして、回復した艶は縁という新たな名を与えられて、青泉寺で育てられ、やがて湯灌の手伝いをするようになる。そして、それが正真に認められ、正縁と名付けられる。他に「落合蛍」正縁が17歳のときの話。「偽り時雨」正縁が18歳のときの話。「見返り坂暮色」正縁が19歳のときの話。■みをつくし料理帖■の■銀二貫■■あきない世傳■と立て続けに高田郁氏の時代小説を読んでだ。今回読んだ「出世花」は、江戸期の湯灌をする職業、三昧聖(さんまいひじり)の物語。15歳から湯灌をする少女の話。他の小説と同じように幼くして親元を離れ生きていく話とはいえ、死者の体を洗う仕事は辛かっただろうと思う。「死」にかかわる仕事として「屍(しかばね)洗い」という差別を受ける縁。縁をもらい受けたいという商家もあったのに、なぜ続けるのか、私には分からない。江戸時代の湯灌をする人の様子が描かれていた。縁は、白麻の着物に縄の帯、縄の襷(たすき)といういでたち。縄の帯、襷は、捨てたのだろうか。また、湯灌に使った湯水も作法があってそれにのっとて処分されたという。他の小説を読んだときにも感じたが、多くの文献を読み参考にしたのだろうと思う。この小説は2007年に「第二回小説NON短編時代小説賞奨励賞」を受賞。選考委員の山本一力氏に「資料を読み過ぎても、それを小説に取り入れるのは100調べて95捨てよ」と言われたそうだ。改めて作家の世界ってスゴイなと思う。タイトルの「出世花」は、艶、縁、正縁と名が変わる主人公に「出世魚」のようだという仲間たち。それを受け、「正縁は魚ではない、さしずめ『出世花』というとことかな。」と正念の言葉。「仏教で言うところの『出世』とは世を捨てて仏道に入ることだ。正縁は名を変えるたびに御仏の御心に近づいていく。まことに見事な『出世花』だ。」というところから。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.07
コメント(0)
-

難波橋(ライオン橋):土佐堀川と堂島川
難波橋(なにわばし)は、大阪市の大川に架かる橋。浪速の名橋50選選定橋。大阪弁では「ナンニャバシ」と発音する。大阪市中央区北浜~北区西天満の堺筋にかかる、全長189.7m、幅21.8mの橋である。中之島を挟んで土佐堀川と堂島川の2つの川を渡る。橋の中央で下流側に中之島通を分岐させ、上流側に中之島公園へ降りる階段が設けられている。橋の南詰めおよび北詰めには、最上級の黒雲母花崗岩を素材にした獅子像(=ライオンの石像、天岡均一作)が左右両側にあるため、「ライオン橋」とも呼ばれている。このライオンは天王寺動物園の当時非常に珍しかったライオンがモデルと言われている。像は左側が口を開く阿形像、右側が口を閉じる吽形像となっており、狛犬(狛犬はライオンがモデルといわれる)の形式を採った獅子=ライオンであると言える。像は、当時の池上四郎大阪市長が天岡均一に依頼して作られた。中之島水上公園計画の一環として設計された事により、石橋風の外観、公園と一体となった階段、高欄の獅子像、親柱にはペディメントやメダリオンをあしらい、市章である「みおつくし」をアレンジした意匠が親柱や欄干に模られている。1975年には3年間に及ぶ補修工事により戦時中に金属供出で失われた欄干や橋上灯が復元され、近代大阪を彩った美しい外観を保っている。この日は7月24日で天神祭り。橋を提灯が彩っていた。■カフェ、北浜レトロビル■や■カフェ&ダイナーNORTHSHORE(ノースショア)・北浜■は、難波橋からすぐ。(▲難波橋(ライオン橋)から、「カフェ&ダイナーNORTHSHORE(ノースショア)・北浜」と「北浜レトロ」を見る。)▲橋の西側に立つと中之島の公会堂が見える。▲右から3番目が難波橋(ライオン橋)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.06
コメント(0)
-

太平橋と埋め立てられた天満堀川
■太平橋■天満堀川の最下流,堂島川に面する場所に架けられた橋。第一次都計事業ではCアーチが架けられた。中之島一帯はパリのシテ島を手本として一体感のある都市景観を創り出す。そのため堂島川に注ぐこの場所にもアーチ橋が採用されたらしい。昭和40年代の阪神高速建設・堀川埋め立てでは,最下流のこの橋だけ埋め立てずに残されたという。(西横堀川の金屋橋のような状態)。しかしそれも,昭和60年に行なわれた下水事業に伴う工事で撤去された。撤去年が遅いこともあり,親柱が4つとも残されている。加えて先々代の橋の親柱も一つ残されている。形式からして明治~大正時代のものであろうか。『橋梁年表』では1902年(明治35)に木橋が架けられた記録がある。 ■太平橋(たいへいばし)■ 天神橋の北詰を西に曲がると高速道路が横切っています。それを過ぎると、堂島川の岸側に空き地が有ります。空き地の中に石が2つ放置されていて「太平橋」・・・たいへいばしと書かれています。これは、橋の欄干の柱となります。この空き地部分が、大川から北へ延びていた天満堀川跡でここに太平橋が架かっていました。この場所は、乾物問屋の古い土蔵が建っていました。(▲天満堀川の少し下流にあるこの大阪天満宮の梅の印のある灯篭は乾物商が寄進したものだ。)この辺りを菅原町と言って、大阪天満宮の近く菅原道真に因む名前で、江戸時代より乾物問屋が多い所でした。川沿いで輸送に便利なのと、天満青物市場が近いのがその理由でした。この地域は戦災に遭わなかったので、古い家が残っており、船場と違って町並みが残っています。今は、高速道路や高層マンションが次々と建築され、この町並みもどのくらい見る事が出来るのかと思います。 天満堀川は、1598年に開削された古い堀川です。(1600年に関ヶ原の戦いですのでご理解出来ると思います) この堀川は、江戸時代で現在の扇町公園辺りで行き止まりでした。行き止まりの為、堀川は水の流れが無くゴミが溜まっていたと言われています。1838年、天満堀川は北端から北東へ大川に向けて新たに堀川が開削されました。(現在は、阪神高速守口線の下にあたります)1600年代、太平橋の位置には橋は架かっていますが、古地図では「新橋」となっています。そのひとつ北の橋が「樋上橋」です。天満堀川が、大川と分岐する地点(太平橋辺り)に水門(樋)があった為だと思われます。1600年代後半には「門樋橋」とあり、1700年代になって太平橋の名で呼ばれた様です。あの有名な近松門左衛門作の『心中天の網島』で小春と治兵衛の道行で出てくる「堀川の橋」は、この太平橋と考えられています。天満堀川は、昭和47年、1972年に埋め立てられましたが、太平橋はしばらくは残っていた様です。それも、昭和60年、1985年に撤去されました。天満堀川によって、現在の天神橋筋商店街や天満市場等、八百八橋の大阪は、その土地土地の形成やその橋の役割によって、作られていったと考えています。(▲太平橋のあるところから「ばらぞの橋」が見える。) 大川の都島橋下流側から南西へ分岐し、綿屋橋上流側から南流して堂島川に合流していた。南流区間では天満を東西に分ける境界でもあった。現在はほぼ全てが埋め立てられ、大部分が阪神高速12号守口線や扇町パイパスの用地に転用されている。もとは下流側から扇町公園付近まで(南流区間)の入堀だったが、大塩平八郎の乱で天満が壊滅的な被害を受けたため、窮民救済を兼ねて上流側が開削された。*入堀*とは**川沿いの蔵屋敷に直接船で多量の物産を搬入するため屋敷内には御船入という入堀を設けていた。**高速道路を目印に歩いていてみた。この道の横は、一段高くなっている。これは天満堀川の跡だと思うのだが、確認しようがない。▲天満から堂島川を見る方向にこの草地がある。道端で、ここだけ低くなっているのも怪しい。■中之島スタイル■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.05
コメント(0)
-

北浜レトロビルヂング
「北浜レトロビルヂング」は1912(明治45)年、株の仲買業を営む企業の社屋として建てられた。現存する煉瓦造りの建物としては、かなり古い部類に入るだろう。ファサードの淡い褐色のタイルは積まれた煉瓦の上に張られたものだ。シンメトリーの古典的な構成ながらも余り堅苦しさを感じさせないのは、そのコンパクトな規模もさることながら、世紀末ヨーロッパのデザイン潮流、より自由な表現を求めて生まれたアールヌーヴォーやセセッションの影響を受けているからだろう。戦後、建築資材を扱う商社の社屋を経て、1996(平成8)年に現オーナーである小山寿一さんが手に入れる。玄関先に「売却物件」と書かれ、不動産として売りに出ていたところを偶然見つけたそうだ。(▲一階から地下を見る。)一目ぼれして購入を決意したものの、長年使われていなかった内部は床が抜けそうなほど荒れ放題だった。しかし、所々に残るディティールはほれぼれする美しさで、小山さんは自ら重ねた(▲玄関のタイルもかわいい。)時代考証を元に、オリジナルを活かした再生を決意する。照明や建築金物、家具などは全てイギリスのアンティークを自ら買い付け、 ペンキの色は何度もテストを繰り返した。1997(平成9)年、本格的な英国紅茶とスイーツの店として「北浜レトロ」がオープン。本物にこだわった小山さんの店作りが瞬く間に人気を獲得した。2階の窓からは土佐堀川越しに中之島公園のバラ園を臨むことができ、水と緑と「近代建築」の大阪を満喫するには絶好のロケーションだ。■大大阪モダン建築■より。(▲1階から2階への階段には、順番を待つ客のために丸椅子があって、客が絶えない。)独特の雰囲気漂う、登録文化財の洋館1998年に国の登録文化財に指定された「北浜レトロビルヂング」(▲2階から1階を見る。)まるで絵本のような世界が広がる、紅茶と雑貨のショップ■北浜レトロ:ことりっぷ■トイレだって雰囲気たっぷり♪中之島から見た「北浜レトロ」。小ささが分かる。■北浜レトロビルヂング■■住所:〒541-0041 大阪市中央区北浜1-1-26北浜レトロビルヂング ■定休日:お盆休み、年末年始 ■アクセス:地下鉄堺筋線「北浜駅」より徒歩1分 ■中之島スタイル■・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.04
コメント(0)
-

ファウンダー/ハンバーガー帝国のヒミツ★マクドナルド
■ファウンダー /ハンバーガー帝国のヒミツ■怪物か。 英雄か。1954年、アメリカ。52歳のレイ・クロック(マイケル・キートン)は、シェイクミキサーのセールスマンとして中西部を回っていた。そんなある日、ドライブインレストランから8台ものオーダーが入る。どんな店なのか興味を抱き向かうと、そこにはマック(ジョン・キャロル・リンチ)とディック(ニック・オファーマン)の兄弟が経営するハンバーガー店“マクドナルド”があった。合理的な流れ作業の“スピード・サービス・システム”や、コスト削減・高品質という革新的なコンセプトに勝機を見出したレイは、壮大なフランチャイズビジネスを思いつき、兄弟を説得、契約を交わすのだった。フランチャイズ化は次々に成功していくが、利益を追求するレイと兄弟との関係は急速に悪化。やがてレイは、自分だけのハンバーガー帝国を創るため、兄弟との全面対決へと突き進んでいく……。 カリフォルニア州南部の小さなハンバーガーショップ、マクドナルドを世界最大のファーストフードチェーンへと成長させた男、レイ・クロックの実話を描く人間ドラマ。創業者であるマクドナルド兄弟とミキサーのセールスマンだったレイとの出会いから、両者の対立まで、成功の陰にあったダークな側面までも映し出す。レイをマイケル・キートンが演じる。厨房で働くスタッフ役の俳優たちは、振付師のキキ・エリーの指導を受けて「バーガー・バレエ」を作り出した。メトロノームを使って、きちんとした調理プロセスを進めながら俳優が同時に動けるのを助けた。スピーディー・システムを導入する前のマクドナルドでは伝統的に、マクドナルド兄弟がテニスコートに厨房の概略をチョークで書いて、スタッフに手順を練習させた。本作でもこのシーンが登場する。 あの有名な、マクド(関西ではマクドナルドをマクドという。)の物語。ハンバーガーを作った兄弟とマクドナルドをチェーン店に展開した男の物語。こんな裏話があったなんて知らなかったと感心した。 冒頭、ドライブインのレストランシーンがある。そこに集まる車のぽっこりとしたラインの可愛らしさ。今の車より絶対に可愛らしいのに、どうして形が変わったのだろう。現在のエンジンで形は50年代にして欲しいと運転できないのに強く思う。ところでマクドナルドという名前は、スコットランドに多い。調べてみたら、やはり、マクドナルド兄弟は、スコットランド系だった。マクドナルドという名前の故郷は、■スコットランドのスカイ島■だ。当初は、スコットランド系のマクドナルド兄弟が開いた店舗はハンバーガー店ではなかった。ハンバーガーもマクドナルド兄弟の発明品ではなく、それ以前から米国全土にあった料理だった。にもかかわらず、その後の世界展開により広く認知されるようになったことから、マクドナルドはしばしばハンバーガーの代名詞ともされる。 主力製品である「ビッグマック」を国際購買力平均価格の指標として用いるビッグマック指数が提唱されるほど、マクドナルドはよく知られている。その一方、ケンタッキーフライドチキンと伴に『アメリカニゼーションの代表』として、欧米・アジア圏で「マクドナルドの店舗が襲撃される」という事件も起こっている。そのマクドナルド兄弟の作ったシステムがすごかった。マクドナルド兄弟がテニスコートに厨房の概略をチョークで書いて、スタッフに手順を練習させるシーンは実際にあったそうだ。「ふたりは、今や世界中のファーストフード店の標準となる調理システムを編み出した偉大な革新者だった。」ゼロから生み出したマクドナルド兄弟とは反対に、成功のみを考える主人公のレイ。早く、安く、清潔に!!しかし、その背後に、使い捨てがあった。使い捨ては、半世紀以上前からやっていたのかと思うと恐ろしい。((((;゚Д゚)))))))「ファウンダー」とは創業者の意味。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.03
コメント(2)
-

銀二貫:江戸期の寒天商人
■テレビ:銀二貫■舞台は商人の町・大坂天満。仇討ちで父を目の前で亡くし、あわや自分も討たれるかというところを、偶然居合わせた寒天問屋・井川屋の主人・和助によって銀二貫と引き換えに救われた松吉。生きるために武士の身分を捨てて井川屋の丁稚となった松吉だが、商人の道を歩むことに心が揺れていた。大火で焼けた天満宮再建のためにかき集めた銀二貫で松吉を救った和助や、信心深いが故に松吉に辛くあたる番頭の善次郎から、商人としての厳しい修行と躾を受ける。そして、井川屋の暖簾をめぐる数々の事件を乗り越え、松吉は商人として成長していく。得意先の料理屋の娘・真帆との淡い恋あり、涙あり笑いありのなにわ商人の人情劇。★■べか車■「ベカ車」の名称が現われるのは、安永年間である。長さは2間ないし6、7尺で、幅は3尺余であり、大八車より狭かったが、これは大坂の道路の幅員が狭かったからである。前方で1、2本の綱を2、3人が引き、後方で1、2人が撞木を押し、これを「楫」といって進退を掌った。堅牢であったから、木石などの重量物を運搬するのに用いられた。安永3年(1774年)9月、ベカ車の橋上通過が令をもって禁止された。橋梁を破損させるというのが理由であった。ベカ車が普及したため、上荷船、茶船への影響は決して小さくなく、寛政3年(1991年)に彼らの請願によって制限令が発せられ、その後もしばしばきびしい取締が行なわれたが、その効はなく、広く用いられた。*本の中に「べか車」という言葉がよく使われていた。★■寒天■「井川屋」では寒天を京都・伏見で仕入れていた。その歴史は京都・伏見が発祥の地であり約400年と言われています。 1658年江戸時代初期、徳川4代目将軍家綱公の時代の冬の日、薩摩藩主の島津候が参勤交代の途中に山城の 国伏見の御駕籠町(現在の京都市伏見区)にある美濃屋太郎左衛門が営む旅館「美濃屋」に宿泊したことから 寒天の歴史は始まります。「銀二貫」では美濃志摩屋という名前で出てくる。★伏見の取引先が火事になり伏見の「美濃志摩屋」で働いていた職人が大坂の高槻で寒天を作ることになる。高槻の寒天づくりは、天明7~8年(1787~8)頃、市内の城山出身の宮田半平が、伏見から製法を学んで郷里に持ち帰ったことから始まったとされます。半平の功績をたたえて大正3年(1914)に建てられた石碑が、聞力寺(宮之川原元町)にあります。高槻の山間部で、寒天づくりがこれほどまでに盛んになったのには理由があります。その1つに、製造に適した冬の寒さがあげられます。2つめは、テングサを煮溶かすのに必要な薪や炭が豊富だったことです。3つめには、原料の入手や製品の出荷のために、淀川の河港・前島と原の間が「京坂越え」と呼ばれる山道で結ばれていたことで、淀川の水運が利用できたことです★夜船江戸時代に淀川の伏見と大坂の間を上下した三十国船には夜間の船があったという。★伊豆方面から仕入れることになった取引先は下田から紀伊半島をまわって大坂に入る廻船を使う。廻船(かいせん・回船)とは、港から港へ旅客や貨物を運んで回る船のこと。中世以後に発達し、江戸時代には菱垣廻船・樽廻船のほか、西廻り航路(北前船)・東廻り航路、さらに北国廻船・尾州廻船などの浦廻船が成立して船による輸送網が発達した。★牡蠣船が幾艘も、橋脚に繋がれて漂っている。安芸の国からの牡蠣船の到来は秋から冬にかけての上方の風物詩であった。「みをつくし料理帖」でも澪が幼い頃「天満一兆庵」の息子が幼い澪を連れて行くという思い出シーンがある。大坂の天満にある寒天商という設定。天満には乾物屋が多かったという。この灯篭も天満にあり、乾物商が寄進している。 このように江戸時代の暮らしや寒天に関することがいっぱい出てくる。本の終わりに参考文献リストとして専門書があった。「みをつくし料理帖」」シリーズや「あきない世傳」でも感じたが作者が読んだ沢山の専門書のエキスでこれらの本は書かれている。・・・・・・・・・・・・・・・・・・ にほんブログ村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.08.02
コメント(0)
-

ばらぞの橋:端と端を結ぶ橋
■ばらぞの橋■難波橋の下から東にはバラの花壇が設けられ、春や秋にはバラの花が咲き誇る。(▲オレンジ色の〇の所がばらぞの橋)また、南北方向に水路が流れ、西側にバラ園、東側に円形バラ園があり、ばらぞの橋が架かっている。なお、この水路はちょうど天満堀川(現在は埋立。 阪神高速12号守口線)の延長線上にあたる。天神橋より突き出た東端部は、大川を堂島川と土佐堀川に分けて尖っていることから「剣先」と呼ばれ、先端には安藤忠雄の構想による噴水が設置されている。 1766年(明和3年)、当時の中之島東端に■
2017.08.01
コメント(0)
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- プレッシャーに打ち勝つ方法
- (2025-11-19 07:37:30)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-19 16:55:20)
-
-
-

- 楽天市場
- SALE🍋噛んで食べる ビタミンC 私の…
- (2025-11-19 18:11:50)
-






