2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年09月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
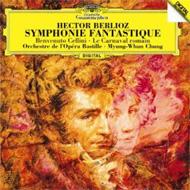
ベルリオーズ 「ローマの謝肉祭」序曲/ヒシバディゴ
今日の音楽~ベルリオーズ作曲 「ローマの謝肉祭」序曲ヘクトール・ベルリオーズ(1803-1869)の名前は中学生ごろだったか、トスカニーニの演奏したLP盤にこの「ローマの謝肉祭」が収録されていて、とても好きな旋律の一つだった記憶しています。今から約50年くらい前の話です。 その後さまざまなジャンルのクラシック音楽を聴くようになったのですが、オーケストラでの「序曲集」などもよく聴いていました。「フランス序曲集」などというレコードには大概この「ローマの謝肉祭」が入っていたように思います。曲の冒頭からいきなり情熱的な激しい音楽が鳴り響きます。 イタリアの民族舞踊音楽「サルタレロ」で音楽の幕を開けます。これがとても印象的な旋律でリズムなので、中学生であった私にはその旋律が心に焼きついたのでしょう。 「幻想交響曲」を初めて聴く前からベルリオーズの大好きな曲でした。ところでこの「ローマの謝肉祭」は、ベルリオーズのオペラ「ベンベヌート・チェッリーニ」の第2幕の前に演奏される序曲なですが、10分近くかかる長い曲でもあり曲そものがとても魅力的でもあるので、単独に演奏されコンサートのプログラムや録音などに採り上がられています。ところがそのオペラ「ベンベヌート・チェッリーニ」は現在ではほとんど全曲上演される機会はないそうです。 私もどんな筋の物語なのか知りませんし、オペラ全曲も聴いたことがありません。 「ローマの謝肉祭」序曲と「ベンベヌート・チェッリーニ」序曲だけを聴いています。 1893年の今日(9月10日)、ベリリオーズのオペラ「ベンベヌート・チェッリーニ」がフランスで初演されています。愛聴盤(1)チョン・ミュン・フン指揮バスティーユ歌劇場管弦楽団(UCCG ユニヴァーサル・ミュージック 1993年11月録音)私の持っている盤はベルリオーズの交響曲「イタリアのハルロド」とのカップリングですが、現在は「幻想交響曲」とカップリングされてリリースされています。(2)ジャン・フルネ指揮 オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団(DENON CREST1000 COCO70831 1996年9月録音)「フランス序曲集」というタイトルでフランスの作曲家ばかりのオペラ序曲集で1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「ヒシバ・ディゴ」
2009年09月10日
コメント(2)
-

ラヴェル「ツィガーヌ」/アメリカ・ディゴ
今日の音楽~ラヴェル作曲 「ツィガーヌ」モーリス・ラヴェル(1875-1937)も私の大好きな作曲家の一人です。 レヴェルが書いた作品を初めて聴いたのが中学2年生(1959年)の時でした。 曲はムソルグスキー原作の組曲「展覧会の絵」でした。ラヴェルが原曲のピアノ独奏曲を華麗な管弦楽版に編曲した有名な、あの「展覧会の絵」です。 演奏はトスカニーニ指揮NBC交響楽団。 小学校の恩師からLP盤を借りて聴かせてもらいました。 それがラヴェルとの出会いでした。以降「ボレロ」「ダフニスとクロエ」「逝ける王女のためのパヴァーヌ」「スペイン狂詩曲」「道化師の朝の踊り」「マ・メール・ロア」「ラ・ヴァルス」などをオーケストラ演奏で楽しみながら独奏楽器、特にピアノ曲「夜のガスパール」「水の戯れ」そしてピアノ協奏曲などで随分とラヴェルの音楽を楽しませてもらっています。ストラヴィンスキーはラベルを評して「スイス時計のような精密で精緻な音楽だ」と語っています。 まさに名言、ラヴェルの音楽を一言でしかも余すところなく述べている言葉だと思います。「オーケストラの魔術師」とも呼ばれたラヴェルの真骨頂は「ボレロ」でしょう。 約15分間を2つの旋律だけを駆使して楽器を次々と変えながら、聴く者を段々と興奮させながらやがてオーケストラの全合奏で終わる、この「ボレロ」は何回聴いても興奮して感動します。この曲を聴くと「オーケストラの魔術師」という言葉がぴったりだと感じます。そんなラヴェルがヴァィリオンにも優れた作品を書いています。 演奏会用狂詩曲として書かれた「ツィガーヌ」です。 この「ツィガーヌ」は「ジプシー」という意味で、ハンガリーの「チャルダッシュ」という民族音楽が使われており、10分足らずの小品ですがとても技巧的なヴァィリオン曲で、緩やかな「ラッサン」と急速なテンポの「フリスカ」の2つに分かれており、ラヴェルの天才とも言える閃きと、奔放とも言える情熱の塊のようなヴァイオリン曲の傑作です。 原曲はピアノ伴奏版ですがオーケストラ伴奏版もあります。初めのカデンツア部分がとても華麗で、ここで演奏者が乗ってしまうとあとは一気呵成に弾いていく感じで、聴いていても溜飲が下がる思いです。オーケストラ伴奏での演奏は更に華やかさが増して、音の世界が一層広がっていくようです。愛聴盤オーグスティン・デュメイ(ヴァイオリン)マリオ・ジョアン・ピリス(ピアノ)(グラモフォン 44580 1993年10月録音 輸入盤)庄司紗矢香(ヴァイオリン)イタマール・ゴラン(ピアノ)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG1100 2001年9月12-3日ライブ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「アメリカ・ディゴ」
2009年09月09日
コメント(2)
-

R.シュトラウス 「クラリネットとファゴットのための小協奏曲」
R.シュトラウス作曲 「クラリネットとファゴットための小協奏曲」リヒャルト・シュトラウス(1864-1949)は、私の大好きな作曲家の一人です。性格とか音楽家としての生き方が好きという意味ではなくて、彼の音楽を好んで聴いています。 代表的なのが交響詩として書かれた「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」「ドン・ファン」「ツラトゥストラはかく語りき」「英雄の生涯」、それに協奏曲としての「ドン・キ・ホーテ」など。 オペラでは「サロメ」「ばらの騎士」「ナクソス島のアリアドネ」などが挙げられます。そんな彼の作品の中でも非常に地味な小品があります。 「クラリネットとファゴットのための小協奏曲」がそれです。 R.シュトラウスは1949年に生涯を閉じており、この作品はその2年前に書かれていますので最晩年の作品の一つになるでしょう。R.シュトラウスの音楽は、濃厚なロマンティズムを漂わせながら時には豪華絢爛、時には19世紀末の滅びゆくロマンをオーケストラの響きの中に匂わせた風情で私を魅了しています。交響詩にもオペラにもこれらを濃厚に漂わせています。1947年に書かれたこの「小協奏曲」は、彼の最晩年の作品の一つでそこに描かれた音楽は、上に述べたような特徴はすべて消えてなくなっており、古典的な音楽への回帰ともいえるほどの調べが佇んでいます。 クラリネットの憧憬を表すかのような音色と対照的なファゴットの渋い響き、それに弦楽とハープのみという室内楽的なオーケストラの編成。 弦楽器もバロック時代を思わせる合奏協奏曲のような独奏群と総奏に分かれており、明晰なメロディ・ラインと古典的ともいえる音楽構成が、音楽そのものを簡素で明快な作品に仕上げています。もうここには19世紀末の滅びゆくロマンティズムに彩られたR.シュトラウス特有の音楽は、その片鱗もかけらさえも残していません。 3楽章形式で構成されていますが、切れ目なく演奏される約20分の作品です。1949年の今日(9月8日)R.シュトラウスは85歳の生涯を閉じています。 命日にちなんで今日はこの「クラリネットとファゴットのための小協奏曲」を聴いてみようと思っています。愛聴盤ヴェンツエル・フックス(クラリネット)リヒャルト・ガレール(ファゴット)ジェイムズ・デプリースト指揮 オーケストラ・アンサンブル金沢(ワーナー・クラシックス WPCS11922 2003年2月27日 金沢ライブ録音)カップリングはメンデルスゾーンの交響曲第3番「スコットランド」です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1841年 誕生 アントニン・ドヴォルザーク(作曲家)1949年 没 リヒャルト・シュトラウス(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「朝顔」
2009年09月08日
コメント(4)
-
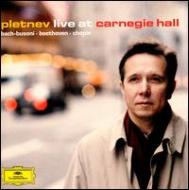
イスメライ/クレオメ
ミリ・バラキエフ作曲 「イスメライ~東洋風幻想曲」ミリ・バラキエフ(1837-1910)は旧ロシア帝国時代の作曲家で、「ロシア5人組」と呼ばれた作曲家の一人。 交響曲・協奏曲なども書いていますが、何といってもダントツに有名なのがこの「イスメライ」。8分~9分ほどの短いピアノ独奏曲ですが、バラキエフの最も有名でコンサートや録音などもよく採り上げられる作品です。「イスメライ」とはコーカサス地方の速いテンポの民族舞曲で、作曲家によくあるその地へ旅行に出かけてその土地の音楽に魅かれて作るという、その筋から出来たピアノ音楽です。急ー緩ー急の3部構成で書かれており演奏には、かなり高度な技術が要求される難易度の高い作品と言われており、第1部、第3部のコーダはまさに熱狂的な盛り上がりを見せており、舞踊のリズムや華麗な第3部、爆発的なコーダはすさまじいという比喩がぴったりのピアノ曲です。愛聴盤ミハイル・プレトニョフ(ピアノ)(Grammophon 471157 2000年11月1日 カーネギー・ホールライブ 輸入盤)プレトニョフのニューヨーク・カーネギー・ホールへのデビューリサイタルの録音。バッハのシャコンヌ、ベートーベンのピアノ・ソナタ第32番、ショパンの4つのスケルツオというプログラムの後にアンコールとしてこの「イスメライ」が演奏されており、コンサートの熱気が乗り移ったかのような凄まじい熱情をはらんだ演奏。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の花画像 クレオメ」
2009年09月07日
コメント(0)
-

キキョウソウ
「キキョウソウ」
2009年09月06日
コメント(2)
-
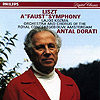
リスト 「ファウスト交響曲」
「今日の音楽」~リスト作曲 「ファウスト交響曲」1806年にゲーテが「ファウスト」第一部を発表、その後第二部を1831年に書きあげて依来、作曲家たちはこの文学を競い合うように音楽に表現しています。 ベルリオーズ(1803-1869)は劇的物語「ファウストの劫罰」を、シューマン(1810-1856)は「ファウストからの情景」を、グノー(1818-1893)はオペラ「ファウスト」を書いています。フランツ・リスト(1811-1886)もその一人でした。 彼がフランス・パリに滞在中にベルリオーズから薦められてゲーテの「ファウスト」を読んだのが最初とだそうで、それ以来ダンテの「神曲」と共に生涯の座右の書となったそうです。当然リストにも「ファウスト」を題材にした音楽を書こうという意欲が出てきますが、背中を押したのは恋愛中のカロリーネ・ゲットシュタイン侯爵夫人であったと言われています。1852年にベルリオーズから劇的物語「ファウストの劫罰」を献呈されたのが、この「ファウスト交響曲」を書く直接の契機になったと言われています。音楽は「ファウスト」を具体的に描写したものではなく、3楽章からなる「ファウストの3人の人物描写による」とあり、「ファウスト」「グレートヒェン」「メフィストフェレス~終末の合唱」から構成された、リスト自身が「ファウスト」を読んだこれらの人物への想い入れを音楽に表現しています。 リスト作曲の交響詩などに見られる音楽と同じように、どこかほの暗さがあって、しかも渋い音色とブラスが響き渡る華麗さが混じった、リストらしい色彩に染められた文学的情緒とでも言うのか、暗さと希望に錯綜する音楽に満ち溢れています。演奏時間が約70分の大作で、ベートーベンの「第九」とほぼ同じ演奏時間となります。この「ファウスト交響曲」が1857年の今日(9月5日)ドイツ・ワイマールで初演されており、大成功を収めたそうです。愛聴盤アンタル・ドラティ指揮 王立アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団・合唱団ラヨス・コズマ(テノール) (Philipsレーベル PHCP9330 1982年1月 アムステルダム ライブ録音 廃盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1791年 誕生 ジャコモ・マイヤベーヤ(作曲家)1857年 初演 リスト 「ファウスト交響曲」1883年 初演 ブラームス チェロ・ソナタ第1番1892年 誕生 ヨゼフ・シゲティ(ヴァイオリン奏者)1912年 誕生 ジョン・ケージ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2009年09月05日
コメント(0)
-

2本指のピアニスト
「左手2本指のピアニスト」世の中には常人が考え付かない凄いことをする人がいるものです。今年になって全盲のピアニスト辻井さんが、バン・クライバーン国際ピアノコンクールで優勝した感動がまだ残っているところへ、今度は18歳女子高校生のピアニスト、小林夏衣。 この人は、末端低形成症という病気のために先天的に左手の指が2本しかないそうです。その人が健常者が弾く同じピアノ音楽を奏でる。左手には親指と小指しかない。 だからまるでビデオの早送りかのような指の動きで演奏するらしい。 幼稚園のころから「ピアノを習いたい」と言い始めたので、お母さんは2年がかりで先生を探したらしい。その先生は、「この曲は難しいから飛ばそう」と弟子の彼女が左手にハンディ・キャップがあるからとは斟酌しないで教則本を教えたことに、彼女はとても感謝しているそうです。 彼女にとって左手2本指の演奏は当たり前だったからだと言う。 「最初5本あった指が2本になったら苦労があるかも知れないけれど、私の左手の指は初めから2本。 特に苦労を感じたことない。 普通の人と同じ」と言う。和音を弾く時は人さし指の付け根を使ったり、右手を補助的に使うが奏でられる音色は澄んでいるという。その彼女が昨夜(9月3日)大阪のザ・シンフォニーホールで、大植英次指揮の大阪フィルと共演で、モーツアルトのピアノ協奏曲第20番を弾いたそうだ。席は満席で立ち見席40席も完売という盛況。 演奏はどうだったのかな?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪堺市 大仙公園
2009年09月04日
コメント(6)
-

夕焼けエッセー
「出世払いで」「出世払いで」奴のいつものセリフである。街灯に集まる蛾のごとく夜な夜な徘徊する奴は、バイトでもらったお金も使い果たし、お母さんの生活費を「出世払いで」を合言葉にむしり取っていく。奴は長男次男の次に9年ぶりにわが家にやってきたお調子者である。家族だけではなく、ご近所さんにもかわいがられた。笑顔を武器に、実にうまく生きてきた。勉強もスポーツもそれなりにできた。第一志望の大学に入ってからだ、奴が変貌したのは。見るたび薄くなる眉。寝不足の目はいつも充血し、ヘアスタイルは奇妙である。これだけはと、きつく言ってきた。サラ金に手を出さない。突然赤ちゃんを連れてこない。変なものは飲まない。そんな奴が就活だけはえらく気合が入っていた。しかしながら時期が悪過ぎて苦戦が続いた。半ば諦めかけていたとき、内定をもらった。よほどうれしかったのか、メールを送ってきた。「泊まる」以外のメールは超ひさしぶりだ。あんな奴を採用してくれるとは、本当にありがたく申し訳ない。来年4月には東京に行く。「やっと楽になるわ」と嫌みのひとつも言ってやろう。会社のために精いっぱいがんばりなさい。それから貸したお金は全額返しなさい。それから、身体にはくれぐれも気をつけなさい。それから・・・・。大阪市 56歳主婦~2009年9月1日 産経新聞夕刊 「夕焼エッセー」より~大阪・堺市・大仙公園
2009年09月03日
コメント(2)
-

禁煙
「閑話休題」~ 禁煙昨年12月ークリスマス・イヴの前日に自宅で下血して救急車で運ばれて緊急入院をしました。大事に至らずに2週間ほどで退院出来たのですが、その折に行ったことの一つが禁煙でした。と言うよりも喫煙が難しい状態に置かれていたのです。まず第一に、救急車で搬送された時に自分が喫っていたタバコを自宅に置いたままで、喫いたければ新しい箱を買わねばならかった。 ご存知のように今やどの病院・医院でも全館禁煙となっており、病院の売店ではタバコさえ売っていない。 買いたければ外にある自販機、タバコ店、コンビニエンス・ストアーなどで買い求めなければ喫えない。当然家族に依頼しないと買えない。自分が外出など出来ない(昔はやったことがあるのですが)。 仕方なしにタバコなしの入院生活を2週間ほど続けているうちに、「喫いたい」という気分でなくなった。その気分が9月になっても同じ。 これに驚いています。 18歳から喫煙を始めて64歳まで本格的に禁煙をしたことがない。 ニューヨークなどへの長距離飛行便に搭乗して禁煙を強いられて、10数時間禁煙状態に置かれていても目的地に着くと灰皿を探していた私が、これほどすんなりと禁煙を9カ月近くも守っておれるのが不思議です。どんなに名演奏を聴かせてくれたコンサートでも、休憩時間15分の間に2本喫っていた私。酒場やコーヒー・ショップなどのテーブルに着くと、まずタバコだった私。そんな私が、禁煙をしていることが不思議でなりません。 今でも居酒屋で呑むことがあります。隣席の客が喫っていても苦にならない。そんな自分が不思議でならない。それでも、時々自宅やコーヒー・ショップで「タバコをどこに置いたかな?」とポケットを探る癖は抜けていません。まだ9ケ月。 まだまだ安心は出来ません。 友人で、1年と2カ月禁煙したのにまた喫っている人がいるからです。大阪・堺市・大仙公園
2009年09月02日
コメント(14)
-
プログの継続
長い間の休止期間でした。身の回りにいろいろと煩わしい問題が起こり、人生で最も信頼していた友人から裏切られて、一時は身の持って行き場がないほどに憔悴しておりましたが、時間が経つに連れて心も癒されてきました。 今ではもう一度ブログを立ち直らせようかなと考えています。休止期間中は専ら読書に時間を費やしていました。司馬遼太郎 「竜馬がゆく」(3巻) 「飛ぶが如く」 「峠」 「関ヶ原」 「梟の城」 「項羽と劉邦」 「人斬り以蔵」 「新撰組血風録」 「燃えよ剣」吉村 昭 「彰義隊」下母澤 寛 「勝海舟」池波正太郎 「真田太平記(全3巻)」 「人斬り半次郎」 「幕末新撰組」 「鬼平半科帳」 「その男」 「夜の戦士」 「剣客商売 黒白」松本清張 「逃亡」 「かげろう絵図」藤沢周平 「蝉しぐれ」澤田ふじ子 「流離の海ー平家物語」吉川英治 「三国志」船戸与一 「夢は荒れ地を」白川 道 「最も遠い銀河」今年の2月から上記のような作品を読みながら、時には戦国時代に、時には爛熟文化の江戸時代に遊ばせてもらっていました。 別に書評記事を書こうというつもりではなくて、依然と同じようにクラシック音楽にちなむ話題を紹介しながら、その音楽を聴いていただけたらと願っています。音楽に限らずに日常生活の話題かもしれません。映画の話題とか、料理の話題とか何とでも採り上げていこうと思っています。どうぞ従来に負けぬような応援をいただければ幸甚です。 どうか末長く見つめてあげてください。とも
2009年09月01日
コメント(31)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- UK~エイジア~ジョン・ウェットン
- Roxy Music - Out Of The Blue Midni…
- (2025-11-12 00:00:13)
-
-
-

- オーディオ機器について
- 試作スピーカー31.9(アルマイト処理…
- (2025-11-24 21:13:19)
-







