2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2008年01月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
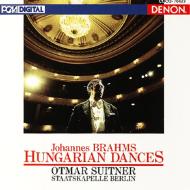
ブラームス ハンガリー舞曲集/CDの包装
「CDの包装」コンパクト・ディスク(CD)を購入して自宅に帰ると一刻も早く聴きたいと逸る気になる時があります。 CDプレーヤーの前で包装を解くのですが、ものすごくイライラするときがありあます。 簡単に解けない時があるからです。 どこからあのビニール包装を破ればいいのかわからないCDがあります。 ほとんど海外盤です。 破り易いように少し切ってあるのが日本盤。 CDの下方に横に切る線が見えています。日本盤なら少しだけ折り返しのように摘む部分があります。 これを引っ張ると大抵の包装は簡単に破れます。ところが海外盤の多くはCDケースを包むビニールをこれでもかとばかりに押さえつけて、その折り返しが付いていないから破れるまで時間がかかりイライラします。 爪で引っ掻くとケースに傷が付くし、「ええ~い!」と声を出して破こうとするときもあります。日本盤のきめ細かなサービスに感謝しながら海外盤に恨みを言ってるともさんです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲タイムの音楽」 ブラームス作曲 ハンガリー舞曲集一般的にヨハネス・ブラームス(1833-1897)の書いた音楽として最初に聴いた作品として挙げられるのがハンガリー舞曲第5番ではないでしょうか。 小学校の音楽教科書にも紹介されており、教室で聴かされる機会の多い曲の一つです。 私もこの第5番を初めて聴いたのが小学校5年生だったか6年生の時だと記憶しています。 実に親しみやすい音楽で一度聴けば忘れられないほどの名旋律です。 ところで、ハンガリーは日本と同じ「ウラルアルタイ語族」に属する民族で、東洋的な情緒を多分に残しているヨーロッパでは珍しい国です。 彼らの祖先は9世紀頃にアジアから移ってきた騎馬民族を起源としているからでしょう。 ヨーロッパでも「小さな東洋」と呼ばれることもあるほどです。 人名の呼び方も東洋的で、日本人と同じように姓・名の順番になっています。 例えばハンガリー出身の「ベラ・バルトーク」は西洋の呼び方で、バルトークが姓、ベラが名前です。 これがハンガリーでは「バルトーク・ベラ」となります。ブラームスは20歳の頃にハンガリー出身のヴァイオリニスト・レーメニーのピアノ伴奏者として演奏旅行に出かけた時期がありました。 この時の演奏旅行がブラームスに多大な刺激と影響を与えています。 当時一流だったフランツ・リストに会ったり、名ヴァイオリニストで親友となったヨアヒムとの邂逅、そしてヨアヒムの紹介でシューマンに出会って彼の支援を受けることとなり、シューマンの死後未亡人となったクララ・シューマンへの実らない「恋」などが生まれていくきっかけにもなった演奏旅行でした。その楽旅でブラームスはレーメニーからハンガリー音楽を教えてもらうことになったのです。 北ドイツのハンブルグ生まれのブラームスにとって南の地方はとても温かい陽光の地で、ハンガリーとて同じように彼にはまばゆいばかりの国ではなかったかと想像されます。そしてジプシーと東洋情緒が溢れるハンガリー音楽に魅せられたのでしょう。レーメニーとの演奏旅行と決別してから、ブラームスは教えられたハンガリー音楽をピアノ連弾曲集として書いたのが、この「ハンガリー舞曲集」でした。 当時のヨーロッパではピアノ連弾は「ハウスムジーク(家庭音楽)」として一家団欒の一つとして定着しており、最初の10曲が出版されると大人気となったそうです。 レーメニーと別れてから16年後のことでした。 以後ブラームスは最初の10曲に追加して全21曲を完成しています。ところが思わぬ横槍が入りました。 レーメニーなどのハンガリー系の音楽家たちからクレームがつけられたのです。 つまりハンガリーの古来から伝わる音楽なのに、ブラームス自身の創作のようにして楽譜出版するのはけしからぬ、という苦情でした。 この騒ぎが大きくなってとうとう裁判沙汰になってしまうのですが、楽譜には「ブラームス作」ではなくて「ブラームス編」と書かれているのが決め手となってブラームスが勝訴しました。ハンガリーの民俗音楽の東洋情緒の中にインドを起源とした「ジプシー」が混ざり合っていきます。 そのジプシー音楽が色濃く刻まれているのがこの「ハンガリー舞曲集」です。この曲に人気があるのは多分に東洋的な親しみやすい旋律が日本人の心を掴むのかも知れません。 代表的なのが「チャールダッシュ」で遅いテンポでゆったりとした「ラッサン」と、後半の情熱的な「フリシュカ」からなる音楽です。ブラームスの作曲した音楽の中でも、この「ハンガリー舞曲集」は異彩を放っています。 おそらく彼のどの作品ジャンルにも属さない曲でしょう。 愛らしい思わず微笑みたくなるような可愛い表情をした曲や、哀愁きわまりない悲しげな音楽、快活で明るく行進曲風の音楽など多彩に語られています。 全21曲を聴いていますと時間の経つのも忘れてしまいそうです。その後ピアノ独奏や管弦楽用に編曲されたのですが、現在では管弦楽演奏がとてもポピュラーになっているようです。愛聴盤 (1) オットマール・スイトナー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団(DENON CREST1000 COCO70423 1989年録音)21曲全曲を収録しており、今では1000円盤です。(2)ラヴェック姉妹(ピアノ連弾) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7038 1981年録音)ピアノ連弾用原曲でこれも21曲を収録しています。「フィリップス・スーパーベスト100」の中の1枚で1000円盤として再発売されています。聴き比べてみると面白いのですが、私は音楽空間が広がるオーケストラ版を好んで聴いています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」 1797年 誕生 フランツ・シューベルト(作曲家)
2008年01月31日
コメント(2)
-

モーツアルト フルートとハープのための協奏曲
「珈琲ブレイクの一曲」 モーツアルト作曲 フルートとハープのための協奏曲W.A.モーツアルト(1756-1791)は子供時代から父親と一緒にピアノ演奏会のためにヨーロッパを旅しています。 1777年9月もザルツブルグを離れて10月にマンハイムへ訪れています。この旅の目的は職探しでした。 職を得ることはできなかったのですが、ここマンハイムではフルートの曲を書いています。 フルート協奏曲第1番と第2番、それに第1番~第3番のフルート四重奏曲です。そして良く1778年3月にフランス・パリに行き、そこでこの「フルートとハープのための協奏曲ハ長調」を書き上げています。 パリで知り合ったフルートの名手ギーヌ公爵とハープを弾く公爵の娘のために書いています。 アマチュア演奏を考慮に入れてハ長調という調性は、この二つの楽器にとって最も演奏しやすい調性という理由で書かれたのであろうと言われています。 巨匠的な技巧を避けて、平明にして華やかさを残しており、メロディアスなフルートとアルペジオを主体とするハープが、まるで寄り添うかのように独奏部分を書かれています。音楽はロココ調・趣味のまるで輝くばかりの明るさにあふれており、優雅さと心地良さは例えの言葉もないほどで、祝宴向きの一曲です。愛聴盤 (1)ジャン=ピエール・ランパル(フルート) リリー・ラスキーヌ(ハープ) ジャン=フウランソワ・パイヤール指揮 パイヤール室内楽団(エラート原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21050 1960年録音)LP時代からも数え切れないほどの再発売を繰り返してきたディスク。 現在は1000円盤として再発売されています。 モーツアルト クラリネット協奏曲とのカップリング。(2)カールハインツ・ツエラー(フルート) ニカノール・サバレタ(ハープ) エルンスト・メルツェンドルファー指揮 ベルリンフィルハーモニー(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCG3088 1962年録音)これも再発売を繰り返している名演盤 ライネッケのハープ協奏曲とのカップリング。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1963年 没 フランシス・プーランク(作曲家)
2008年01月30日
コメント(0)
-

クライスラー名曲集/美帆さんへ!/橋下知事に期待
「緊急告知 美帆さんへ!」1月30日(明日)の件で大至急伝えたいことがあります。 この記事を読んだら大至急電話連絡してください。 事は一刻を争います。 お願いします。 とも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「橋下大阪府知事への期待」予想通りと言えば予想通り、やはり浪速府民は有名人・タレント候補を好きな土地柄を反映したと乱暴に切り捨て出来るほどの地すべり的勝利。 183万票の重みは大きい。 それは他人が言うまでもなく本人が一番自覚しているはずです。NHK大阪がこの府知事選挙の戦いを分析したところによると、橋下氏は有名人・タレントや自公議員の応援演説を断り、ひたすら独りで戦ってきたそうです。 選挙カーの自民党の名前も白い物で覆って出来る限り政党色を出さずに闘った。 そして訴えたのも「庶民の暮らしの向上」を第1義にしていたそうです。一方の熊谷氏(民主党推薦)の陣営では中小企業の景気回復、経済の復活・活性化を訴え、民主党の大御所を招き入れての選挙戦。 国会決議を欠席してまで応援に来阪した小沢代表でしたが、その苦労も結ばなかったという、今後の民主党の動き、府民の民主党への信頼度を図る一つのバロメーターが示されました。それに有名人・タレントなどの応援頼みもあって、どこか明確な選挙路線を見出さないままの選挙戦であったと報じています。 そこに大きな敗因があったと分析していました。橋下氏の知名度は抜群でした。 今や弁護士としてよりもTVタレントとして有名です。 歯に衣を着せぬ言葉。 人を引き付ける弁舌の巧さ、爽やかさ。 大阪府民が橋下氏を知事として選んだ理由は「もうええ加減府政をあんばいしてやあ~」なのでしょう。 橋下氏を選んだ府民の願いが聞こえるようです。 この声を新知事は背中に受けて走り出します。 これから38歳の若手府知事に府政を委ねます。 第一にやるべきことは府財政の緊縮化、これは本人も第1の問題だと明言しています。 府債発行もしない。 この府債は予算の歳入の7%にあたります。 それを発行しないとなるとどこからその財源を得るのか?それに実情に合った予算を組むと明言しています。 府債発行せず、実情にあった予算の編成。橋下知事は初っ端から大きな問題点を抱えて出港します。当分は温かい目で見守ってやりたいですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲タイムに一曲」 クライスラー名曲集ヴァイオリンの名曲は数々ありますが最も有名なのはフリッツ・クライスラー(1975-1960)の小品ではないでしょうか? 私がクラシック音楽を好きになった小学校6年生~中学校1年生の頃のヴァイオリン・リサイタルやLP録音での小品集には必ずと言っていいほど、このクライスラーが作曲したヴァイオリン曲が含まれていました。 私にとってクラシック音楽を聴き始めて一番長い付き合いをしているのがこのクライスラーのヴァイオリン曲だと思います。その当時はクラシック音楽は演奏時間が長いという思いがあって、クライスラーのヴァイオリン曲は実に親しみやすい美しい旋律に彩られている音楽で、何よりも演奏時間が短いのが好きでした。 今のように1曲で1時間近い曲を聴くだけの忍耐力がなかったものですから。「愛のよろこび」「愛の悲しみ」「美しきロスマリン」の「ウイーン古典舞曲3部作」と呼ばれているワルツ音楽にうっとりとしていた時代でした。 単刀直入に美しい音楽がスピーカーから流れてくるのをビクターのトレードマークでありませんが、耳を欹てて聴く白い犬と同じような恰好でハイフェッツの弾くLP盤を、隣の家で聴かせてもらっていた時代です。今聴き直してもどの曲もやはり素晴らしく美しい音楽です。 ヴァイオリンを知り尽くした人が書いた音楽。 どこを切り取っても美しさにあふれています。珈琲ブレイクに格好の音楽でしょう。 寒さが続く大阪です。 寒い冬の午後の珈琲ブレイクのひと時、クライスラーの命日に(87歳の生涯を1962年の今日ニューヨークで閉じています)久しぶりに彼のヴァイオリン小品の数々を聴いてみようと思っています。愛聴盤 ローラ・ボベスコ(ヴァイオリン) ウイルヘルム・ヘルヴェッツ(ピアノ) (Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7059 1985年録音)ボベスコがエレガントな表情付けて弾いている「クライスラー名曲集」で、「愛のよろこび」「愛の悲しみ」「美しきロスマリン」「中国の太鼓」「ウイーン奇想曲」など全20曲が収められたディスク。 数えきれないほど再発売を繰り返していて、現在は「フィリップス・スーパーベスト100」の中の1枚で1000円です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1862年 誕生 フレデリック・ディーリアス(作曲家)1905年 初演 マーラー 歌曲集「亡き児をしのぶ歌」1962年 没 フリック・クライスラー(ヴァイオリニスト・作曲家)
2008年01月29日
コメント(8)
-

ブラームス「6つのピアノの小品」/美帆さんへ
「緊急告知 美帆さんへ」30日の件で緊急告知したいことがあります。 このブログを読んだらすぐに大至急お電話を下さい。 必ずですよ。 事は一刻を争います。 とも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲タイムに一曲」 ブラームス作曲 「6つのピアノの小品」ヨハネス・ブラームス(1833-1897)は、以前の日記にも書きましたが、作曲の筆を止めようとした時期(1890年頃)がありましたが、クラリネット奏者ミュールフェルトとの出会いにより再び創作意欲をかき立てられてクラリネット三重奏曲やクラリネット五重奏曲、それにクラリネット・ソナタなどを書き始めています。その後創作意欲は衰えることなくピアノの小品を書き残しています。 作品116~119までのピアノ作品集「3つの間奏曲」「6つのピアノの小品」「4つのピアノの小品」などがそれにあたります。中でも私の好きなのが「6つのピアノの小品 作品118」です。 ブラームスの晩年のピアノ作品は季節で例えると秋のような音楽とよく言われています。 これは何もこうしたピアノ小品集だけでなく、他の曲にも例えられています。 「残照の音楽」とか「たそがれの音楽」とか「人生の秋」とか言った表現で晩年の音楽を例えています。こうしたピアノ小品にでもそれがあてはまるかのように、音楽はとても地味ですが深い内容をたたえたかのような佇まいをみせています。この「6つのピアノ小品 作品118」は、ブラームス最後のピアノ作品である「4つのピアノ小品 作品119」の一つ手前にあたる作品で、4つの間奏曲とロマンス、バラードの2曲から成る曲集です。 2分から8分近くまでの小品で演奏時間は全曲で30分ほどの作品です。情熱的な曲や清澄な美しさの曲、力強い旋律、柔和な歌に溢れた美しい曲、幻想風な曲と色彩豊かな小品集です。冬の午後の珈琲を味わいながら約30分間ブラームス晩年の心境に浮き沈みしたいなと思います。愛聴盤 (1) ペーター・レーゼル(ピアノ)(シャルプラッテン原盤 徳間音工 TKKC70665 1973年録音 廃盤)5枚のCDにブラームス全てのピアノ作品を録音した5枚目のCDで、現在は廃盤となっています。 いずれキング・インターナショナルから復刻されると思います。(2) ヴァレリー・アフェナシエフ(ピアノ) (DENON CREST1000 COCO70444 1992年録音)CREST1000シリーズの1枚で遅めのテンポでじっくりと弾くアフェナシエフの名演。 1000円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1887年 誕生 アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアニスト)1892年 初演 フォーレ 「レクイエム」1935年 没 イッポリトフ=イワーノフ(作曲家)1947年 没 レイナルド・アーン(作曲家)
2008年01月28日
コメント(0)
-

トリスタンとイゾルデ~前奏曲と愛の死/白鵬優勝!
「緊急告知 美帆さんへ」30日の件で緊急告知したいことがあります。 このブログを読んだらすぐに大至急お電話を下さい。 必ずですよ。 事は一刻を争います。 とも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「大相撲初場所 白鵬優勝!」本当に朝青龍と白鵬の横綱同士のマッチレースになった初場所。 今日の結びの一番で両者意地をかけての一戦。 最近にない盛り上がりです。 これで相撲人気が戻ればいいのですが。日に日にテンションを上げて来た朝青龍。 一人横綱を張ってきて朝青龍が戻れば後塵の灰をかぶる訳にはいかない白鵬。 俺が東の正横綱だとアッピールしたい朝青龍。 意地のぶつかり合いとなる今日の大一番。 今場所は朝青龍が負けることを願う相撲ファンが9割という数字が新聞に報道されていました。 真実なら明日こそがそのクライマックス。 朝青龍のファンはそれ見たことかと溜飲を下げたい気分。 5年ぶりの横綱同士の千秋楽の優勝をかけた大一番。 楽しみですね。大阪では明日は府知事選挙投票日。 午前中に済ませます。 午後は大阪女子国際マラソンの応援。 昼寝。 大相撲観戦。 夜は9時から久しぶりに渥美清の映画「寅さん」。 今日は忙しい一日になります。実に力が入った大一番でした。 両横綱ともに気合いは五分。 立ち会いも五分。 相撲展開も五分。 白鵬の勝ったのは? これは体の大きさの違いではないでしょうか。 あれだけがっぷりと胸を合わせ、お互いにまわしを引きつけおれば体の大きい方が有利。 これからも何度もこの両横綱の対戦はありますが、この体の大きさの違いが勝負の分かれ目になるのでは。朝青龍はこれからの対戦では頭を少し低くして白鵬に食い下がる形にすれば、勝利が見えてくるのではないでしょうか? それにしても両横綱の気迫の凄さ! 大関連の星取りが8勝7敗では言うべき言葉もありませんが、彼らはどう見たでしょうか? 気迫の凄さ、勝負の速さ。 学ぶべき点は多くあります。来場所すぐにとは言いませんが、せめて大関陣揃って11勝4敗くらいにとどめれば相撲人気も復活するかも。初場所は朝青龍に開けて、朝青龍に暮れた場所となりましたが、今度は追う番。 春場所も多いに盛り上げて欲しいですね。 そして大関陣の奮起を期待したいですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」~前奏曲と愛の死「ワグネリアン」という言葉があります。 ワーグナー音楽に魅せられたワーグナー好きの人を指して呼ぶ言葉です。 よほど好きなんでしょうね、こういう言葉があるというのは。 よくワーグナーの音楽は「麻薬」だと言われます。 その音楽の持つ魅力ー濃厚な音楽空間、そして甘く美しい、まるで海の波のようにいつまでも押し寄せる「無限旋律」の心地良さ、こうした魔力にも似た音楽に取り付かれた人たちを「ワグネリアン」と呼ぶのでしょう。ワーグナーの音楽の中でもそういう魅力に富んだ作品の一つが楽劇「トリスタンとイゾルデ」でしょう。 一度この作品の魅力の虜になるとまるで麻薬患者のように汲めども汲みつくせない魅力から離れることが出来ません。 それを「麻薬」と呼んでいるのだと思います。19世紀半ば(1859年)に作曲されたこの「トリスタンとイゾルデ」は、ドイツ中世の「トリスタン伝説」(実際には叙事詩「トリスタンとイゾルデ」を題材にしています)の中の「愛」のみを取り出してワーグナー自身が台本を書いています。時代は中世、アイルランドの王女イゾルデは、かつての婚約者をコンウォール(イングランド)の騎士トリスタンに殺されます。 そのトリスタンの傷を癒してあげたのがイゾルデでした。 少なからずイゾルデはトリスタンに好意を持ってしまいます。 しかし、その後イゾルデはコンウォールの国王・マルケの花嫁として嫁ぐことが決まり迎えの船に乗ります。国王の花嫁としてイゾルデを迎えに来たのがマルケ王の甥トリスタンでした。船が目的地に着く直前、イゾルデの侍女フランゲーネが二人に飲ませる毒薬と「愛の薬」を間違えてしまい、二人は「愛の薬」を飲んだために熱烈な恋仲になってしまいます。婚礼後にイゾルデが自分の甥と相思相愛になっていることを知ったマルケ王は激怒し、従臣にトリスタンを殺すよう命じます。紆余曲折の後、マルケ王も2人の仲を許すことにしたのですが…時すでに遅く、瀕死の状態のトリスタンはイゾルデの腕の中でやがて息絶え、イゾルデもトリスタンを抱擁しつつ死んでいく、というあらすじです。この「前奏曲と愛の死」は楽劇の冒頭、第1幕への前奏曲と最後の場面イゾルデの「愛の死」をつなぎ合わせた音楽で、およそこんな乱暴な音楽は他にはないでしょう。 オペラの序曲と幕切れの音楽をつなぎ合わせているのですから。ところがそれがちっとも不都合な、具合の悪い音楽ではないのです。 前奏曲の部分で予言したかのように「愛の高まり」が、後半の「愛の死」に受け継がれて見事に融合しているのです。 この曲を聴いただけでも楽劇の雰囲気が如実に理解できます。 愛の喜び、官能の高まり、許されぬ禁断の愛が情感豊かに「無限旋律」によって歌い上げられています。「ライトモティーフ」(人物や背景などに決まった音楽を与える方法)や終止音を使わずに永遠に続くかと思えるような「無限旋律」の魅力が込められた感動の音楽です。 バス・クラリネットで開始される「愛の死」。 演奏会やセッション録音では歌手なしでオーケストラのみで演奏されます。 「愛と官能」の押し寄せる音楽ですから「珈琲ブレイク」には向かないかも知れませんが、昨日の「ニュールンベルグの名歌手~第1幕への前奏曲」で刺激されて今日もワーグナー音楽となりました。愛聴盤(1) ウイルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウイーンフィルハーモニー キルステン・フラグスタート(ソプラノ) (EMI原盤 東芝EMI TOCE55710 1952年録音)フルトヴェングラー特有のテンポの動かし方で奥深い音楽空間が広がり、フラグスタートの感情表現が見事な歌唱です。 全曲盤からの抜粋で「ワーグナー管弦楽曲集」として収録されています。 1500円盤(2) オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE13348 1960年録音)遅めのテンポでじっくりと愛の情感を歌いあげたクレンペラーの名演。 こちらはオーケストラ演奏です。 1300円盤(3) ハンス・クナッパーツブッシュ指揮 ウイーンフィルハーモニー ビルギット・ニルソン(ソプラノ)(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7046 1959年録音)これもクナッパーツブッシュ特有の遅いテンポで深い深い情念を呼び起こした稀有な演奏の一つ。 ビルギット・ニルソンのイゾルデが圧巻です。1000円盤(4) カラヤン指揮 ウイーンフィルハーモニー ジェシー・ノーマン(S)(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG20031 1987年ライブ)1987年ザルツブルグ音楽祭でのライブ録音。 1984年セッション録音でベルリンフィルを振った新録音とほぼ同じプログラムをウイーンフィルで振っています。 驚くべきことはこの「トリスタンとイゾルデ」。 84年でも驚いたのですが、74歳でこれほどの官能をあぶり出していることでしたが、亡くなる2年前にもめくるめく官能の嵐をカラヤン流の美麗な塗りたくりで演奏していることです。 上記3人にはないカラヤン特有の美学を貫いた官能の極致が匂っており、舞台ではおそらく歌うことのない黒人歌手ジェシー・ノーマンの絶唱が聴ける演奏です。以上4点はもう現代指揮者に求められない非凡な説得力で迫ってくる演奏として紹介しておきます。 現代指揮者ではバレンボイム、ティーレマンやパッパーノのようなすばらしい指揮者がいます。 でも私はまだ手放しでこれらの現代の指揮者にのめり込めません。 やはり古い人間なんですね。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1756年 生誕 W.A.モーツアルト1823年 生誕 エドアール・ラロ(作曲家)1901年 没 ジュゼッペ・ヴェルディ(オペラ作曲家)1908年 初演 ラフマニノフ 交響曲第2番1958年 没 エーリッヒ・クライバー(指揮者 カルロスの父)
2008年01月27日
コメント(6)
-

ニュールンベルグの名歌手 前奏/大阪府出身 豪栄道
「大阪出身 豪栄道」この人が将来を嘱望されている若手力士なんですが、もっと前に出て行く相撲を取ってほしいですね。 立ち合いからが~んと当たるのいいのですが、悪い癖ですぐに引いてしまう。 昨日の相撲も当たるとはたいていました。 相撲の基本は前に出ること。 出て行って泳がされてもいいから前へ前へと進んで欲しい。 今の相撲なら前頭上位と下位のエレベーター力士に収まってしまいます。 あの引き技何とかならないのかなあ。 久し振りの浪速の関取、期待しているから頼むから引き技はやめてよ。 あれをやっている限り未来はないよ、豪栄道!頑張ってくれ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 ワーグナー 「ニュールンベルグの名歌手」前奏曲ワーグナーの音楽は気軽に聴こうと思っても重たい気分の曲が多いのですが、今日採り上げた楽劇「ニュールンベルグの名歌手」はワーグナーの作品の中でも世俗的で少し喜劇調の明るいオペラです。 全曲演奏に3時間半ほどかかりますから、とても「珈琲ブレイク」に気軽と言う訳にはいかないので、今日はその中から演奏会プログラムでもよく採り上げられる「第1幕への前奏曲」を選びました。ワーグナーの作品は交響曲や歌曲もありますが、まづオペラや楽劇の作品を書いた作曲家ということになるでしょう。 オペラ「リエンツェ」、「タンホイザー」、「さまよえるオランダ人」、そして「ローエングリン」までをオペラ或いは歌劇と呼ばれていますが、「ローエングリン」を最後にワーグナーは歌劇という呼び方から「楽劇」へと変わり、音楽も「無限旋律」と呼ばれる切れ目のない、繰り返し奏されるまるで海の波のような動きの巨大な音楽空間とドラマを重視したオペラへと変貌を遂げていきます。 そして楽劇「ニュールンベルグの名歌手」、楽劇「トリスタンとイゾルデ」や4部作の楽劇「二ーべルングの指輪」や舞台神聖劇「パルジファル」がそれです。この楽劇「ニュールンベルグの名歌手」は、ドイツの中世期ごろに盛んだった市井の「マイスタージンガー(名歌手あるいは親方歌手)の生活を描いた作品で、鍛冶屋のボーグナーが歌手コンクールの優勝者に娘エヴァを嫁に与えると広言します。それを聞いて騎士ワルターはエヴァと恋仲だったので出場を申し込みます。 ところが町の書記役のベックメッサーは予選でワルターに悪い点数を付けて振り落として、自分がエヴァと結婚しようと企んでいます。靴屋のハンス・ザックは親方気質で義侠心が強い男で、自分もエヴァを愛しているのですがワルターの歌の才能に惚れて恋を捨てて、ワルターを応援してコンクールで優勝させるという筋書きのドラマです。「第1幕への前奏曲」は演奏時間が9分から10分くらいですが、楽劇で使われる主要動機をほとんど使われています。 音楽は明るく、健康的な気分で進みます。 「名歌手の動機」が冒頭から堂々と始められ、ヴァイオリンの「愛の動機」へと移り、やがて「名歌手の行進」の動機が金管楽器によってファンファーレ風に堂々と表れます。 ここはまるで「巨人の歩み」のようで、この前奏曲中でも最も有名な旋律です。 「情熱の動機」なども表れますが最後に「名歌手の行進」が戻ってきて、晴れやかに健康的な気分で堂々と曲を閉じています。日本の新年コンサートなどでもよく採り上げられるのは、この曲の持つ明るさ、晴れやかさから選ばれているのだと思います。 管弦楽の素晴らしさの醍醐味を味わうのに格好の音楽です。愛聴盤(1) ウイルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウイーンフィルハーモニー(EMI原盤 東芝EMI TOCE55710 1949年録音)テンポ設定や間合いなどこの指揮者の個性豊かな解釈がワーグナー音楽の空間に知らず知らず引きこまれる稀有な演奏です。「タンホイザー」序曲、「さまよえるオランダ人」序曲、「ローエングリン」第1幕への前奏曲、「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死、「ワルキューレの騎行」などが収録されています。 1500円盤(2) オットー・クレンペラー指揮 フィルハーモニア管弦楽団 (EMI原盤 東芝EMI TOCE13349 1960年録音いかにもドイツ的な重厚で、クレンペラー特有のテンポの遅さでまるで巨人の足音のような力強い響きで迫る演奏。 1300円盤(3) ハインツ・レーグナー指揮 ベルリン放送管弦楽団(シャルプラッテン原盤 キング・インターナショナル KICC9473 1977年録音)かつて徳間音工からリリースされてたディスクで、キングからリマスターされて再発売されています。 「ジクフリート牧歌」、「ラインの黄金」「トリスタンとイゾルデ」第1幕への前奏曲が収録されています。フルトヴェングラーのような魔性のような個性でもなく、クレンペラーのような重厚さもありませんが、気宇壮大なワーグナーの音楽空間が果てしなく広がるような演奏で、特にコーダに入る前の瞬間技は何度聴いても堂々としており、私が数多いこの曲の演奏の中でも最も気に入った演奏です。 1800円盤です。 現在の徳間音工盤でも充分聴ける録音ですがハイパー仕様でリマスタリングされた音はきっと改善されていい音になっていると思います。旧東ドイツの指揮者で録音もそれほど数多くは残されていません。 奥さんに先立たれて失意が原因で引退したと聞いていますが、引退するには早過ぎる人でとても惜しい気がします。(4) アルトゥーロ・トスカニーニ指揮 NBC交響楽団(RCA原盤 M&Rレーベル CD-3008 1954年4月4日ライブ録音)トスカニーニにステレオ録音が残っていました。 LP時代に時折ありました電気的に処理を施した疑似ステレオではなくて、正真正銘のステレオ録音です。 勿論現代の技術とは比較にもなりませんが、従来のトスカニーニのモノラル録音とは一線を画す録音で聴ける「ワーグナー管弦楽作品集」。 トスカニーニ最後の演奏会の実況録音です。「ニュールンベルグの名歌手」「ローエングリン」第1幕への前奏曲や「ジーグフリート」森のささやき、「神々の黄昏」からジーグフリートのラインへの旅、「タンホイザー」序曲とバッカナールが収録されています。トスカニーニ節炸裂の速いテンポの推進力の強い演奏で、上記3人の指揮者とは全く違う解釈で小気味良くワーグナーの音楽空間を描いており、この指揮者特有のカンタービレの美しさは例えようもないほどで、現代指揮者からは求めることの出来ない名演集です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1882年 初演 ボロディン 弦楽四重奏曲第2番1911年 初演 R.シュトラウス オペラ「ばらの騎士」1947年 誕生 ジャクリーヌ・デュプレ(チェロ奏者)
2008年01月26日
コメント(2)
-

交響的絵画/クイズ雑学王
「クイズ雑学王」TBS系列で放映されています「クイズ雑学王」(毎週水曜日午後8時から9時まで)を初めて観たのですが、生活の中にある出来事や現象を問題に出してゲストの芸能人が答える番組ですごく勉強になりました。 例えば23日に放映ではこんな問題が出ていました。1. 消しゴム鉛筆で書いた文字や絵を消す「消しゴム」は1770年にイギリスで使われたのが始まりだそうです。 それ以前は食パンの耳などを使って消していたそうです。2. バター古代ローマでは馬の脂を取り出してバターとして使っていたのですが、それは食用ではなくて「塗り薬」として使用していたそうです。 食用として使われたのは7世紀のポルトガルが最初だそうです。3. 未明天気予報で「未明には・・・・」とか「未明から・・・」とかの言葉が使われていますが、この未明という時間帯は「午前0時~午前3時」を指すと気象庁では決めているそうです。 しかしこの定義は一方的に気象庁が決めたのではなくて、一般から公募して一番多かったのがこの時間帯の定義だったので、これに決めたそうです。 なかなか博学になれる番組です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 ラフマニノフ 2台のピアノのための組曲第1番 「交響的絵画」今日もピアノ曲の話題。 旧ソ連を代表するセルゲイ・ラフマニノフ(1871-1943)のピアノ曲「2台のピアノのための組曲第1番 交響的絵画」という作品を聴いてみたいと昨夜から思っていました。 ラフマニノフは誰もが知るピアノの名手。 大きな手が鍵盤上を動き回り見事なピアノ演奏を繰り広げたそうです。 20世紀の偉大なコンサート・ピアニストの一人であると同時に、稀代のメロディ・メーカーで作曲家としての方が有名な人。「ピアノ協奏曲第2番」や「第3番」、「交響曲第2番」、ピアノ曲「音の絵」や「前奏曲」など名作が目白押しの作曲家。 その彼が書いた作品の中にピアノ・デュオ用として書かれたのが「2台のピアノのための組曲」です。 組曲として2つの作品(第1番と第2番)を書き残しています。今日の話題曲第1番は彼が神経衰弱に陥る前に書かれた作品(初演は1893年11月30日)で、絵画を題材に幻想風に描かれた作品です。 4つの楽章から構成されており、「舟歌」 「夜ー愛」 「涙」 「復活祭」と副題が付けられており、それぞれに詩人が書いた「詩」が添えられています その詩からインスピレーションが湧いて幻想風に書いたのでしょうか?情感豊かな「舟歌」、 愛の情熱が高揚するような「夜ー愛」、 嘆きの悲歌の「涙」、 荘厳な風情の「復活祭」と自由に幻想を巡らして書かれています。 全曲で22-23の演奏時間です。今日はこの曲で珈琲を味わいたいと思います。愛聴盤 マルタ・アルゲリッチ、 アレクサンドル・ラビノヴィッチ (Teldec原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21139 1991年録音)Best 50 Moreシリーズの1枚で1000円という廉価で再発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1819年 初演 ロッシーニ オペラ「シンデレラ」1886年 誕生 ウイルヘルム・フルトヴェングラー(指揮者)1909年 初演 R.シュトラウス オペラ「エレクトラ」1913年 誕生 ヴィトルド・ルトスワフスキ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 節分草
2008年01月25日
コメント(6)
-
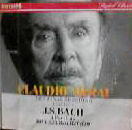
J.S.バッハ パルティータ第1番/大相撲初場所
「大相撲初場所」昨日の時点で先頭を走るのは朝青龍と白鵬の1敗力士だけ。 いつもの展開ですがあまりにも大関力士が弱すぎます。 今日で11日目。 それまで大関が土俵を割ったり、転がされたりとあまりにも弱すぎます。 もっと奮起していもらいたいと思います。 カド番となっても8勝すれば大関に戻れるというアドヴァンテージがいけないと思います。 10勝はしないと大関に復帰できないというルールに変えてはどうでしょうか? それが強くなる因とは思いませんが、気持ちだけも違うでしょう。そりゃあ怪我をして本調子でない大関もいますが、あれは何日目だったか大関全員が同じ日に負けたことがありました。 みっともないですね。 それに琴光喜が最近大関に昇進したと言っても変わりばえしない顔ばかりです。 もっと若手が上位を占めて大関を狙う力量をつけて欲しいですね。その意味でも希勢里、豊ノ島、普天王などがいい加減上位の定位置に収まって大関捕りを狙って欲しいものです。それともう一つ、もういい加減にモンゴル出身力士でなくて日本人力士に優勝を狙って欲しいものです。これからは朝青龍と白鵬のマッチレース的な展開になるのでしょうが、日本人力士の意地も観たいものです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに一曲」 J.S.バッハ作曲 パルティータ第1番変ロ長調久しぶりに大バッハの曲を聴こうと思います。 珈琲ブレイクに聴くのですから「受難曲」やオラトリオ、ミサ曲を避けて今日はピアノ曲で「パルティータ第1番」を聴こうと思います。「パルティータ」は17世紀ごろから発展したジャンルで「変奏曲」という意味合いのものだったそうですが、うがて「組曲」という意味に変化していったそうです。 「アルマンド」や「サラバンド」のような舞曲を連ねた組曲のようなものが、この大バッハが書き残した「パルティータ」で、全部で6曲書かれており最初は「クラヴィーア練習曲集」という名前が付けられていたそうです。1.「前奏曲」2.「アルマンド」3.「クーラント」4.「サラバンド」5.「メヌエット」6.「ジーグ」の6曲から構成されています。大バッハのピアノ曲を聴くといつも背筋が伸びるような感じがします。 この人の作品には「神」が宿っているのでしょうか? 流れてくる音楽からはいつも「神」の存在が聴こえてきます。 「受難曲」や「ミサ曲」などを聴いているからでしょうか? それとも教会のオルガニストでもあり「教会音楽」を書いていたからでしょうか? 定かな理由はわかりませんが、彼の音楽にはいつも「神」が宿っているように聴こえてきます。「前奏曲」が流れ始めると部屋に清風が爽やかに吹き渡るかのような晴朗さをいつも覚えます。 穏やかなピアノの音が静かに、清らかに、しかし確実な音で心を和ませてくれます。後の舞曲も同じです。 符点のついた舞曲のリズムで、しかし音楽は静かに浮き沈みしながら心の平安と和みをもたらさせてくれます。演奏時間約20分あまりの組曲ですが、心の安らぎを求めたいなあ、と思います。愛聴盤 クラウディオ・アラウ(ピアノ)(Philipsレーベル PHCP1305~6 1991年3月録音 廃盤?)「アラウ・ファイナルセッション」という録音で88歳での演奏。 この録音が最後となってしまった「白鳥の歌」。 これほどに枯れた味、心が和む、平安になれる演奏はおそらく稀有ではないでしょうか? ただひたすらにピアノに向かって音を紡ぎ出しているかのような、ただあるのはピアノの音だけという感じの老齢ピアニストの枯れた音色が部屋を満たしてくれます。 ピリスやシフの演奏も素晴らしいのですが、余命いくばくもない(この録音の3ヶ月後にアラウは亡くなっています)ピアニストがまるで遺言のように澄んだピアノの音色を聴かせてくれています。アラウの演奏はベートーベンを例にするといかにも無骨な感じの音色で「田舎者」と言った感じのするピアニストでしたが、このバッハでは欲も得も捨てたという感じで純粋無垢にピアノの音だけが伝わってきます。 それがバッハの曲なので余計に胸が熱くなります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1835年 初演 ベッリーニ オペラ「清教徒」1960年 没 エドウイン・フィッシャー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 寒咲き花菜
2008年01月24日
コメント(6)
-
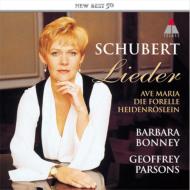
シューベルト 「アヴェ・マリア」/梅
「珈琲タイムに一曲」 シューベルト作曲 アヴェ・マリアこの歌曲は「エレンの歌III アヴェ・マリア」が正式名称で、イギリスの作家ウォルター・スコットの「湖の美人」の中に書かれている詩にシューベルトが歌をつけています。 逆臣の汚名を負った父ダグラスと娘エレンが、スコットランドの高地に逃げて洞窟のなかに住みます。 追手からの危機に瀕して歌うのがこの詩(曲)です。 およそ「神」を題材にした曲で、これほどに澄んだ美しい旋律があろうかと思えるほどの音楽が演奏時間6分あまりの間に展開する天国的ともいえる美しいメロディです。アヴェ・マリア! やさしい聖処女さま!この乙女の願いをおききとどけください。この険しくそびえ立つ岩山の上で神に捧げます、わたしの願いが御許にとどきますよう。願いをかなえていただければ、この世にどんなに辛くとも、朝まで安らかな気持ちで眠ることができるのです。ああ聖処女さま、この乙女の嘆きに目をおとめください。ああ聖処女さま、祈る子の願いをおききとどけください!アヴェ・マリア!アヴェ・マリア! 清浄無垢の御方!わたしたちが岩穴のなかで眠らねばなるぬとしても、マリアさまの御加護があれば、かたい岩もやわらかいしとねとも思えましょう。マリアさまがほほえめば、それはバラの香りとなって、このカビの匂う湿った岩穴も匂い立ちましょう。ああ、聖処女さま、この子の願いをおききとどけください、ああ、処女であられる御方に乙女がお願いしているのです!アヴェ・マリア!アヴェ・マリア! 清浄な乙女であられる御方!地の上にも、空中にもはびこって魔物たちをマリアさまの眼差しで追い払い、魔物たちがこの岩穴に住みつかぬようにしてください。聖処女さまのやさしい聖い御加護があれば、父とわたしは定められた運命に従順に従いましょう。この乙女にやさしく身をかがめてくださいませ、父のために切なる祈りを捧げるこの子のために!アヴェ・マリア!私はアメリカ出身のバーバラ・ボニーの「シューベルト歌曲集」というCDでこの曲を聴いています。 有名な「野ばら」、「ます」、「水の上で歌う」、「夕映えの中で」や「糸を紡ぐグレートヒェン」など17曲の歌曲が収録されています。 その第1曲に「アヴェ・マリア」が置かれています。このCDを買ってすぐにプレーヤーに置いて聴いたのですが、気軽にタバコでも吸おうと火を付けていました。 火が付いてすぐに消しました。 最初の言葉「アヴェ・マリア!」と歌うボニーの歌声がまるで天上から聴こえてくるような感じでした。 澄んだ高音の美しさ、乙女の純な願い! アメリンクやノイマンなどの色々な歌手で聴いてきたシューベルトおなじみの歌曲。 しかし、これほど願いを込めてマリアに祈る乙女の声を聴いたことがありません。私はドイツ語を解することはできません。 それでも詩の意味は邦訳で知っています。 しかしボニーの声は何かを超越したものを感じさせます。 次の曲に進むことができず、もう一度初めから、背筋を伸ばして聴き惚れていました。神さまはシューベルトという稀代のメロディメーカーをこの世に遣わしてくれました。 そして神さまはその曲を歌うべくバーバラ・ボニーを遣わし給うたのです。 これは「芸術の世界遺産」と呼んでもいいほどの絶唱です。 1956年生まれですからボニー38歳の録音です。 おそらくボニー自身も二度とこれほどの歌唱が出来るとは思えないほどの実に見事な演奏です。 この1曲だけ収録されていても私はこのCDを買ったでしょう。 2800円だったのが今は嬉しいことに1000円盤としてワーナー・ミュージックから再発売されています。 (Teldec原盤 ワーナー・ミュージック WPCS21241 1994年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1933年 初演 バルトーク ピアノ協奏曲第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 梅
2008年01月23日
コメント(4)
-
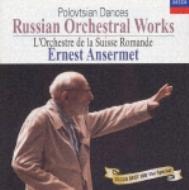
中央アジアの草原にて/「駅」
「森村誠一著 「駅」」「駅」は昔から小説や映画の舞台になっていました。 私の観た映画では「終着駅」(ジェニファー・ジョーンズ、モンゴメリー・クリフト主演)、「逢いびき」(シリア・ジョンソン、トレバー・ハワード主演)、「ひまわり」(ソフィア・ローレン、マルチェロ・マストロヤンニ主演)などが強烈に印象に残っています。「駅」そのものは映画での背景としか映りませんが、そこに繰り広げられる人間ドラマを毎日24時間見つ続けている語らぬ生き証人として描かれています。「駅」には出会いがあり、「別離」もあります。 また新婚旅行のような晴れがましい姿も見ています。 栄転や左遷で去っていく人も見届けています。 偶然の出会いもあります。 それまでに唯の一度も会ったことのない者同士が終着駅まで座席を共にして一期一会の機会を得ることもあります。 映画やドラマ、小説の背景として恰好の舞台にも成り得る場所です。「駅」には東京駅・大阪駅・新宿・渋谷駅など大都会の駅もあれば、日に何人乗り降りするか限られた駅もあれば、時間とか季節限定でしか開かない駅もあります。 それでも大なり小なり「駅」としての舞台装置は同じです。この森村誠一が書いた小説「駅」は新宿駅から始まります。 この駅で出会った、または到着する列車内で知り合った人たちが殺人事件に巻き込まれていく。 これから読まれる人のことを考慮してあらすじ・結末は省きますが、ホームレスとなった中年の浮浪者殺しから端を発して連続殺人事件に発展するのですが、この小説の主人公である新宿西署捜査一課刑事・牛尾正直の息子も殺され、それが連続殺人と関連する話なんですが、犯人を追いつめる謎解きも面白いのですが、この小説に込められた作者の深い人間愛がどの事件にもにじみ出ていて胸が熱くなります。とりわけ息子の遺体を確認するために現地の刑事と同行する牛尾夫妻。失った息子の死という残酷な確認をするための車の中の描写。突然ポタポタとなにかがしたたり落ちるような音がした。澄江の頬が濡れていた。目尻からあふれ出た母親の涙が頬を伝い、顎先から車のフロアにしたたり落ちる涙だった。 牛尾も宮沢も声を失っていた私の息子が20歳を目前にして突然亡くなり、韓国でその悲報を聞いた自分の思いと重なり思わず涙した場面でした。殺されたという事実がわかっていながらも毎日新宿駅中央本線の到着ホームにただずむ牛尾の妻澄江を描いていて、彼女の心が透けて見えるようです。一推理小説にとどまらずに深い人間への愛を塗り込めた絶品のサスペンス・ドラマでした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲タイムに一曲」 ボロディン作曲 交響詩「中央アジアの草原にて」アレクサンドル・ボロディン(1833-1887)が書き残した作品には交響曲第2番もあれば弦楽四重奏曲第2番もあり、オペラ「イーゴリ公」もありますが、今日はボロディンの代名詞のような作品、交響詩「中央アジアの草原にて」を採り上げました。ボロディンは作曲家であると同時に、ペテルブルグ医科大学の化学教授という地位にもあって、数多くの研究成果を発表しているそうです。 大学教授も本業であったので、自身を「日曜大工」ならぬ「日曜作曲家」と呼んでいたほどです。「中央アジアの草原にて」は当時のアレクサンドル2世の即位25周年祝賀行事の一つで、パントマイムのような無言劇に付ける音楽がボロディンに依頼されました。 ところがこの企画が実現できずに終わったために、彼は演奏会用管弦楽曲として完成させたのです。ボロディンは楽譜に音楽の説明を書いています。 「果てしない中央アジアの静かな中を、歌が聞こえてくる。馬やラクダを連ねた隊商がロシアの兵士に守られて遠くからやってきて、やがて草原の中に溶け込んでゆく」。音楽はまさにこの記載された言葉通りに展開していきます。 「歌」はクラリネットで表現されており、旋律は東洋的な響きと色彩を帯びており、一幅の絵画のようなのどかさがあって「交響的」「音樂的」絵画と呼べる、まさに「音の風景画家」と言える音楽です。演奏時間8分弱の短い小品です。愛聴盤 エルネスト・アンセルメ指揮 スイス・ロマンド管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7043 1954-1964年録音)「ロシア音楽コンサート」というアルバムに収録されています。 ロシア音楽ばかりで、大地のぬくもりを感じさせて哀愁の雰囲気もあります。 熱いロシア紅茶などを味わいながらもいいのではないでしょうか?数学者から指揮者に転向したアンセルメ。 スイス・ロマンド管弦楽団を創設して亡くなるまで常任指揮者を務め、フランス音楽、ロシア音楽を得意としており、繊細な響きでしっとりとした色彩を帯びた音楽を表現した、現代ではもう稀有な音楽家の一人です。 録音はもう古くなっていまあすが、最も得意としたロシアの作曲家が書いたオーケストラ音楽ばかりを1枚に収録した名盤の復刻です。収録曲ボロディン:歌劇「イーゴリ公」~〈だったん人の娘たちの踊り、だったん人の踊り〉ボロディン:交響詩「中央アジアの草原にて」リムスキー=コルサコフ:序曲「ロシアの復活祭」リムスキー=コルサコフ:歌劇「皇帝サルタンの物語」~〈熊蜂の飛行〉グリンカ:歌劇「ルスランとリュドミラ」序曲リャードフ:「ババ・ヤガー」 作品56リャードフ:「キキモラ」 作品63グラズノフ:交響詩「ステンカ・ラージン」 作品13・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1857年 初演 リスト ピアノ・ソナタロ短調1859年 初演 ブラームス ピアノ協奏曲第1番1926年 誕生 オーレル・ニコレ(フルート奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の風景」 奈良・長谷寺
2008年01月22日
コメント(0)
-
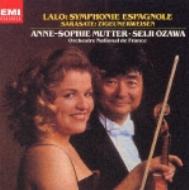
ラロ スペイン交響曲/初雪
「初雪だ!」今朝目が覚めて起きるとあまりの寒さに身ぶるいをしていました。 空気を入れ替えようと窓を開けてみるとなんと雪が薄らと積もっているではありませんか。 近所の風景がわずかな積雪でも一変しています。 雪が降ると寒いのですが、童謡の犬みたいに心が躍りました。 大阪で雪が降るなんて珍しくなってしまい、ほんとに嬉しくなりました。 子供のころは冬になるとよく雪が降り何センチも積る日があって「冬日」が多くあったのですが、今や大阪では「冬日」は死語になっています。まるで子供に帰ったように心が躍ります。 大雪に悩まされる地域の人には悪いのですが、雪ってほんとに心が和むものなんですね。あいにく雪が小雨となっているために写真撮影はやめました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲タイムに一曲」 ラロ作曲 スペイン交響曲エドアゥール・ラロ(1823-1892)は弦楽器が好きであったのか、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロなどを演奏していた作曲家だそうです。 この「スペイン交響曲」は名前こそ交響曲と名付けられていますが、実際は全5楽章からなるヴァイオリン協奏曲です。 いかにもヴァイオリンを知り尽くしたラロらしく華麗な協奏曲となっており、この曲を当時の優れたヴァイオリン奏者で作曲家でもあったサラサーテ(1844-1908)に捧げられています。ラロはフランス人ですが、祖父の代までは純粋なスペイン人だったそうで、ラロにもスペインの血が脈々と流れていたのでしょう。 しかし、彼の名前が作曲家として認められるようになったのはこの曲を発表してからです。 42歳まで独身で生活に追われていた彼がアルト歌手と結婚して、その彼女から熱心に作曲を勧められてから本格的に活動を始めたそうです。 この曲はヴァイオリン協奏曲としては2番目の曲になり、名前もヴァイオリン協奏曲として残っている曲があります。 その協奏曲や以前にもこのページで紹介しました「チェロ協奏曲」やオペラ「イスの王様」などを書いています。ラロの名前は名実共にこの「スペイン交響曲」によって音楽史上に確立されていますが、時にラロが52歳という晩年でしたから、フランスのセザール・フランクやオーストリアのアントン・ブルックナーと同じく「大器晩成型」だったのでしょう。曲は濃厚なスペイン的情緒に溢れており、 曲の冒頭の独奏ヴァイオリンの華麗な、むせ返るような情熱的なメロディを聴いた瞬間から聴き手はスペインへと誘われたような気分になります。 血が騒ぐ闘牛場の熱気、フラメンコダンスのむせ返る官能的な情緒、熱くかき鳴らされるスペインギターの音色、地酒のワインとパエリャの香りが一度に部屋中に沸き立つかのような曲の始まりです。 そしてその気分が終楽章まで持続しています。尚、この1800年代後半はヨーロッパでは「旅」が頻繁に行われるようになったせいでしょうか、「エキゾチック(異国情緒)」ということに作曲家が魅かれており、チャイコフスキーの「イタリア奇想曲」、R.コルサコフの「スペイン奇想曲」やフランスのシャブリエの「スペイン狂詩曲」などにも窺えます。ラロ自身もこの曲同様に他のヴァイオリン協奏曲にサブタイトルを付けています。 彼は全部で4曲の協奏曲を書いており、2番にあたるのが「スペイン」、3番が「ノルウエー幻想曲」、4番が「ロシア協奏曲」と言う風にラロも流行のエキゾチック・ムードに乗って書いたのでしょう。しかし、この曲については、ラロに流れる「スペインの血」がこうした音楽を書かせたのかとも思います。長い間この曲を聴いていないので、今日はスペイン情緒にひたりながら聴いてみたいと思っています。愛聴盤 (1)アンネ=ゾフィー・ムター(Vn) 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE13284 1984年録音) カラヤンに認められたのが76年、ムター13歳。 その翌年14歳でカラヤンと共演して一気にヴァイオリン界の妖精として、カラヤンと立て続けに演奏会・録音をこなしてきて、7年後の1984年に小澤征爾と組んでようやくカラヤンから離れた時の録音で、これが21歳の演奏かと思うほどに、もう完全に自己主張を堂々とやってのけている記念碑的演奏・録音です。 奔放で溌剌として、情熱的に弾きまくり、劇的緊張感も兼ね備えながら、色彩豊かな歌心たっぷりに聴かせてくれます。ただこの演奏がベストという意味ではなく、他にもグリュミオーやキョン・チョン・ファ、デュメイ、オイスオラフ、サラ・チャンなどの優れた演奏などが録音されています。 オリジナルの国内盤は88年にリリースされていますが、私が初めて購入した記念すべきCDの第1枚目にあたる盤でもあり(型番CC-30-9071)、現在の3,000枚のライブラリーの出発点になったという意味でここに紹介させていただきました。現在はリマスターされて1300円と値下げされて発売されています。(2) イザ・ヘンデル(Vn) カレル・アンチェル指揮 チェコフィルハーモニー(スプラフォン原盤 DENON COCQ83817 1964年録音)1924年生まれですから今年84歳の現役女性ヴァイオリニスト。2004年の来日コンサートでブラームスの協奏曲で話題になった人。 高温の魅力がたまらない演奏で、このスペイン交響曲録音時は40歳という脂の乗り切ったころで、技巧的には現代の若手にかないませんが、オーラのような物を発して高音の魅力をまき散らしている魅力ある演奏であり、現代では求め得ないスタイルの演奏ということから紹介しておきます。 1260円盤として再発売されています。(3)ミッシャ・エルマン(Vn) ウラジミール・ゴルシュマン指揮 ウイーン国立歌劇場管弦楽団(ヴァンガード原盤 DENON COCQ83834 1960年録音)これも往年のエルマン節が味わえるミッシャ・エルマンの美しいヴァイオリンの響きと率直な表現スタイルが魅力のヴァイオリン。 独特の艶やかな表現が魅力。 現代の演奏家からは味わえない昔のスタイルです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1903年 初演 ショスタコービチ 交響曲第3番「メーデー」1941年 誕生 プラシド・ドミンゴ(テノール)1948年 没 エルマン・ヴォルフ=フェラーリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 椿
2008年01月21日
コメント(6)
-
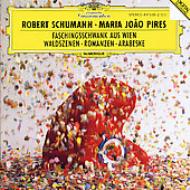
シューマン 「森の情景」/寒咲き花菜
「珈琲ブレイクに一曲」 シューマン作曲 「森の情景」19世紀前半は、ピアノに関しては革命のような時代でなかったかと思います。 ピアノが楽器としての機能が完成に近い形になって、ベートーヴェンや多くのピアノの名手たちが現れた時代でもあり、それによってピアノ曲が数多く生み出されていく土壌にもなったようです。 チェンバロにかわってピアノが家庭内でも弾かれるようになり、家庭的な音楽が楽しまれるようになったことから、サロン風や家庭風の作品も書かれるようになりました。 シューベルトやメンデルスゾーンなどが書いたピアノ小品も当時のそうした傾向を反映したものといえますし、ロベルト・シューマン(1810-1856)によるピアノ曲にも同じことがいえると思いますが、彼の場合はシューベルトやメンデルスゾーンの作品とは少し趣が違うとkろもあります。シューマンは本屋の息子として生まれ文学に親しむ土壌が出来ていたのか、若い時代から文学に尋常でない興味を抱いていたと言われていますが、最初はピアニストになるつもりでスタートしたのですが無理な練習で指を痛めてしまい、その時点で作曲家に転向するせざるを得なかったと言われています。 20歳前後のことです。若い時代から文学に親しみ文学青年であったシューマンは、そのピアノ作品にも文学的な雰囲気が色濃く影を落としていて、標題のある小品または小品連曲という形の曲集を書いています。「謝肉祭」や「子供の情景」など、広く知られている有名な作品をはじめどれにも文学的な標題がつけられていますが、そうした標題は聴く人がわかりやすいようにと作曲した後でつけられたということです。シューマンのピアノ作品は標題のついた小曲を組曲形式としてまとめたところに特徴があり、夢幻的な世界が繰り広げられています。声部が絡み合うようにして書かれている彼のピアノ曲は、ベートーヴェンのロマン的な後期のピアノ曲とは違っていて、そこには既に完全なロマン主義の表れを見ることができます。「森の情景」もその一つで、ヨーロッパの人たちが「森」に対して抱いていた「畏怖」や「怖れ」、あるいは「幻想的な夢想」を表現しています。 「森」には精霊が住んでいるとか、悪魔が人の入ってくるのを待ち構えて手を伸ばしてくるといった「怖れ」や、霊の住むところだから犯しがたい神聖な場所であるとか、色々な形で「森」と対局するようなところがあったようです。シューマンは文学に鋭い感覚を示した作曲家でもありました。ゲーテ、シェークスピア、バイロンを読み、性格も文学的で、感受性の鋭い若者であったようです。 感受性が鋭いというよりも一種の精神病的なところを家族から受け継いでいたのかも知れません。 というのは、彼の父は晩年に精神に異常をきたし、姉も同じく精神異常から自殺をしており、後にシューマンも自殺を計って、精神病の治療を受けることになることから、家族のそうした精神の異常な感覚のDNAを受け継いでいたのかも知れません。だからシューマンの魅力は研ぎ澄まされた感性・感覚とも言える、文学的な・詩的な世界にあるのではないでしょうか。この「森の情景」にしても人が散歩を楽しむ世界ではなくて、幻想的な夢想の果てに行きついたシューマン独自の世界が開かれているように感じます。 彼が「森」から受けた印象を感受性鋭く描いた文学的な世界であり、詩的な空間のように感じられます。曲は連作組曲のように書かれていて、「森の入口」 「待ち伏せる狩人」 「淋しき花々」 「呪われた場所」 「こころよい風景」 「旅籠屋」 「予言の鳥」 「狩の歌」 「別離」の9曲の小品から構成されており、全曲演奏に約30分かかる音楽です。この曲を聴きながらシューマンの書こうとした「森」を思い浮かべるのではなくて、私がうっそうとした森に入って出会う情景を夢想しながらいつも聴いています。 シューマンが与えてくれた「夢想の世界」を浮遊することも楽しいものです。愛聴盤 (1)マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ) (グラモフォンレーベル 437538 1994年録音 海外盤)ピリスの透明なピアノタッチが森の情景を澄んだ風景のように照らし出した名演としてお薦めできる盤です。(2)ヴァレリー・アファナシエフ(ピアノ)(DENON CREST1000シリーズ COCO70692 1992年録音)2004年に1000円盤として再発売されたディスク。 アファナシエフ特有の遅いテンポで詩的な世界を幽玄的に描いた名演。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー1855年 誕生 エルネスト・ショーソン(作曲家)1891年 誕生 ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 寒咲き花菜
2008年01月19日
コメント(2)
-
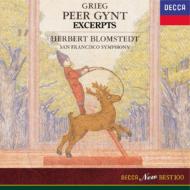
ペール・ギュント/恩師逝く/はこべ
「恩師逝く」自宅から徒歩3分のところに住んでいる小学校の恩師が昨日の朝に亡くなりました。 死因は肺炎です。 10年ほど前に道で倒れて足を骨折して歩行も一人でままならなくなってからは、気持ちも萎えてしまったのか介護に頼る日々となり、そのうちに脳内にも不具合が出来て話すことも不自由で入退院を繰り返していました。昨年4月に私が脳梗塞で入院した時も、先生は同じ病院で入院されていましたが、不自由な体ですがまだ元気にされておられ、先週も介護の車が自宅前に停まっていたので安心をしていたのですが、大阪のここのところの寒さで肺炎を起こしてそのまま亡くなられたようです。学校のみならず家が近いものですから夜も勉強を教えてもらい、5年~6年にかけては習字を習っていました。 私が書くことに興味を持ち、好きになった理由は先生から習字を教わったことにあります。小学生の頃から大きくなれば自分も習字の先生になりたいと淡い夢を持っていましたが、それも先生の立派な字を観ていたからだと思います。享年85歳でした。ご冥福をお祈り申し上げます。合掌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクの一曲」 グリーク作曲 「ペール・ギュント」北欧のノルウェーは、国土の1/3が北極圏に入っている国で、土地の大部分が山地です。 私がオスロを訪れたのがいつも冬のために、この海岸線のクルージングが出来なかったので、実際には見ていないのですが、ここの海岸線は「フィヨルド」と呼ばれる入り組んだ地形で、まるで切り刻まれたような形をしています。 そういう地形が国民性を育てていったのでしょうか、こういう地形によって海への航海術に優れていたのでしょう、「ヴァイキング」と呼ばれるヨーロッパの海岸線を巡って、強奪、略奪を繰り返す「海賊」の発祥地でもありました。現地の人に聞いた話ですが、コロンブスのアメリカ新大陸以前にこのヴァイキングがすでに新大陸に足を降ろしていたそうです。 富と冒険を求めて航海可能なところには勇敢に乗り出して行ったのでしょう。こういうノルウェーには有名な文豪イプセンがいます。 この人は「人形の家」や「野鴨」などの現代でも上演されています戯曲で有名な人です。 特に「人形の家」は、ヒロインのノラが夫に向かって叫ぶ言葉ー何よりも第一に、私は一人の人間です。 あなたと同じように」-は女性解放の高らかな宣言として有名です。 こういう社会問題とまったくかけ離れた戯曲も、イプセンは書いています。 ノルウェーに伝えられる「ペール・ギュント伝説」を戯曲にして冒険好きな国民性を描いてみせたのです。この戯曲の舞台上演に際して、イプセンは劇的効果を高めるために付随音楽を使いたいと願って、自国の作曲家グリーグ(1843-1907)にその音楽の作曲を依頼しました。 それが今日、優れたオーケストラ作品として親しまれています劇付随音楽「ペール・ギュント」です。主人公は冒険好きなペール・ギュントで、婚約者の女性ソルベイクがいるにもかかわらず、村を飛び出して結婚式最中の花嫁を奪ったり、魔王の娘をたぶらかして殺されそうになったりした挙句に、アメリカ新大陸に渡って巨万の富を手に入れて祖国に帰る航海中に嵐に遭い、一命を取り留めたものの無一文となって村に帰ってくると、白髪となったあのソルベイグが彼の帰りを待っていてくれたのです。 「私を救ってくれたのは君だ」と泣き崩れるペール・ギュントは彼女の膝を枕に、静かに安からに死を迎えるのでした。初演後、グリーグは全23曲から4曲ずつを選び、演奏会用組曲としました。 それが第1組曲、第2組曲です。愛聴盤 (1)ブロムシュテット指揮 サンフランシスコ交響楽団(Decca原盤 ユニヴァーサル・クラシック UCCD5039 1988年録音)20曲を選び、物語順に演奏され、台詞も入っておりほぼ舞台上演に近い形の演奏・録音です。ブロムシュテットらしい実直な丁寧な演奏で、各曲の隅々まで緻密に光を照らすようなほのぼのとした名演を聴くことができる盤です。 発売当時は3000円でしたが、6割ほど安くなって1800円として再発売されています。(2) サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団(EMI原盤 東芝EMI TOCE59146 1969年録音)バルビローリ最晩年の録音で、温かみのあるメロー・サウンドで魅了する「バルビローリ節」全開で、全部で14曲の付随音楽が収録されています。 1500円盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1787年 初演 モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」1854年 初演 ヴェルディ オペラ「トロヴァトーレ」1884年 初演 マスネ オペラ「マノン」1909年 誕生 ハンス・ホッター(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ハコベ
2008年01月19日
コメント(4)
-

ビゼー 交響曲ハ長調/ナズナ
「珈琲ブレイクに1曲」 ビゼー作曲 交響曲 ハ長調ビゼーと言えば歌劇「カルメン」があまりにも有名で今でも世界のオペラ劇場で上演されている彼の代名詞のようなオペラですが、今日は彼が17歳のころに書かれたと言われている「交響曲ハ長調」を取り上げました。ビゼーの交響曲ハ長調は、ビゼーがまだパリ音楽院時代の17歳のとき(1855年)に書かれたもので、彼にとっては、習作的な作品と言われています。しかし、親密で歌うような独創的なな旋律に支えられたチャーミングこの上ない作品で、若くして去った天才のみぞ書き得た逸品だと思います。 この作品は17才の習作とは信じがたいものですが、反面、いかにも若者が書いたさわやかさと活気にに満ちています。モーツァルトの妻コンスタンツェは悪妻として有名ですが、ビゼーの妻はもっとひどいでしょう。少なくとも、コンスタンツェは夫モーツァルトの作品を大切に保管しました。おかげで、彼の作品はほとんど失われずにすみ、私達は、600曲を超える彼の素晴らしい作品を現在、聴くことが出来るのです。 ところが、ビゼーの妻は夫の才能を全く信用しなかったのみならず、ビゼーがその不幸な人生を37歳の若さで終えると、彼女はさっさと別の男と再婚をしてしまい、彼の作品はほったらかしにされてしまったのです。このため、ビゼーの多くの作品が失われてしまいましたが、1933年、ビゼーの研究家D.C.パーカーが、パリ音楽院の図書館でこの交響曲ハ長調は原稿を発見し、日の目をみることになったそうです。そして、1935年にオーストリアの大指揮者ワインガルトナーによって80年の眠りからさめて初演され、その翌年に故国フランスでシャルル・ミュンシュによってフランス初演が行なわれています。若々しく、竹を割ったような率直な美しさで、全編を覆う南フランス風のラテン的な情緒いっぱいの曲で、ドイツやオーストリアの作風とは格別に違った明るい作風に溢れた名品です。愛聴盤 小澤征爾指揮 フランス国立管弦楽団1982年の若き小澤が熱狂的にパリに迎えられ、フランス国立管と息の合った演奏で彼の情熱が迸る素晴らしい演奏です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1835年 誕生 セザール・キュイ(作曲家)1841年 誕生 アレクシス=エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1874年 初演 ラロ ヴァイオリン協奏曲第1番1943年 初演 プロコフィエフ ピアノソナタ 第7番1946年 誕生 カティア・リッチャレッリ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 ナズナ(ペンペン草)
2008年01月18日
コメント(2)
-
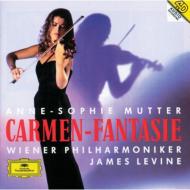
サラサーテ 「ツィゴイネルワイゼン」/小沢代表の釈明
「小沢代表の釈明」昨日民主党小沢代表が記者会見の席上で、自らが衆院の新テロ特別措置法案採決時に欠席したことについて釈明を行っています。その前日鳩山幹事長が民放のテレビ番組でこの問題について「国民の生活に重大な影響を与える法案採決に代表が欠席したことは、国民の不信を招くことになりここに謝罪致します」旨の発言をしたばかりでした。てっきり小沢代表から同じような趣旨のコメントが出ると思っていると、「この法案が国民の生活に重大な影響を与えるものなんですか? そうではないと思います。 党代表としてスケジュールに優先をつけて動くのが当然です。 可決されるのが決まっている採決に出ても仕方ないでしょう。(採決にあたっての会議を)欠席したことについて不適切と言われることが理解できません」と釈明していました。参院審議・可決前にはテレビに、街頭にあれほどアジテーションを繰り返してきた小沢代表の言葉と思えないコメントに唖然としました。 大阪府知事選挙応援に出かけるのに飛行機の出発時間に間に合わないということで欠席したのですが、もう少し他の釈明の言葉があってもいいのではないかと失望しました。国民からの信頼、民主党幹部の意見のズレを露呈させてみっともないというのが私の印象でした。 可決されるに決まっている法案だから出席しなくてもいいんだ、という考えは乱暴過ぎると思います。 これで次の衆院総選挙で政権奪取出来ると思っていれば甘いですね。 この人はやっぱり「壊し屋」で終わってしまう人なんでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに1曲」 サラサーテ作曲 「ツィゴイネルワイゼン」サラサーテと言えば「ツィゴイネルワイゼン」。 彼は自分のヴァイオリンの技巧を示すために、「アンダルシアのロマンス」「カルメン幻想曲」や「マラゲーニャ」などの技巧曲を書いていて、この「ツィゴイネルワイゼン」もそのうちの1曲です。 曲名はドイツ語の「ツィゴイナー」から由来しており、これは「ジプシー」を意味しています。ジプシーと言えば、スペインやハンガリーを思い起こす人が多いと思います。私もそのうちの一人でした。 学生時代に読みました中央公論社の「世界の歴史」を読むまでに、ジプシーの起源はスペインか、ハンガリーだと思っていました。この曲の解説(当時のLP盤)にもハンガリーの民族音楽としか書かれていなかったからです。ジプシーの起源は、インドの北西部にあるパンジャブ地方に住んでいたアーリア系民族が起源とされています。 彼らの一部はパンジャブ地方から、シルクロードの中継地であったタール砂漠に移住していったのです。10世紀頃、タール砂漠(ラジャスターン地方)から、西へ西へと移動し始めた民族は、ロマと呼ばれていたそうです。 このロマがジプシーにあたる言葉です。彼らは居住地を定めず、特定の宗教を持たず、特定の伝承も文字も持たない民族で、独特の民俗・慣習(ヒンドゥのカースト制度に由来すると言われる職業階級、同族同士の内婚など)は厳格に守られているそうです。職業は、行商や馬具・金属の加工、修理業(自動車の修理、解体業)、馬の売買(今は中古車売買)に従事する人たちが多くいます。しかし、芸能に関わり、占星術、遊芸や舞踊などを職業とするロマが有名です。俳優の故ユル・ブリンナーは、ロマ出身です。彼らはイラン、トルコなどで定住したのち、14世紀末~15世紀初頃にバルカン半島にまで到達して、ブルガリアやマケドニア周辺から欧州各地、ロシアや北アフリカなどに分布していきました。曲はハンガリーのジプシー音楽や民謡を素材にしています。 大きく分けて前半の「ハッサン」と後半部の「フリスカ」で構成される「チャルダッシュ」というハンガリーの舞曲形式をとっています。前半の「ハッサン」は2部構成で、緩やかな哀愁に満ちた憂いいっぱいの旋律で彩られた第1部、弱音器を付けて甘く、美しく奏でられる旋律の第2部で、ヴァイオリンのむせび泣くような音色に胸をしめつけられるような魅力がありあます。後半は速いテンポの「フリスカ」で、ヴァイオリンの目の覚めるような技巧が華麗に繰り広げられています。 今日の珈琲タイムには情熱的な音楽「ツィゴイネルワイゼン」を聴いてみようと思っています。愛聴盤 アンネ・ゾフィ=ムター(Vn) ジェームス・レヴァイン指揮 ウイーンフィル(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・クラシック 437554 1992年録音)むせ返るような情熱的で、スペインの香り高い演奏が繰り広げられています。 カップリングの「カルメン幻想曲」と共にムターの至芸が楽しめるディスクです。
2008年01月16日
コメント(6)
-
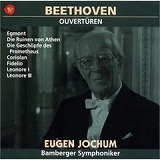
ベートーベン 「エグモント」序曲/花粉の飛散3倍に
「花粉の飛散3倍に」新聞報道に依ると今年の春の花粉の飛散は去年に比べて1.5~3倍に増えるそうです。 特に東北・関東方面にその増量が顕著であると予想されているそうです。 これも地球温暖化の影響だそうです。 しかも時期については例年より早まって1月下旬から始まるところもあるそうです。 私はまだ花粉症にかかったことはないので、この病気の辛さ・怖さを知りませんが患者さんには私の友人も含まれていて、たいそう辛い病気だそうです。 鼻は赤く腫れあがり、特に女性の場合は顔ですから表にも出られない、とこぼしています。花粉症の方はいっそうの注意が必要です。 春を待たずに花粉が早期に散ってくる公算が強いようですからくれぐれもご注意ください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに1曲」 ベートーベン作曲 「エグモント」序曲久しぶりにベートーベンの話題です。 この人の音楽は初期から晩年に至るまで常に安定した腰のどっしりとした落ち着くのある音楽であるのがとても好きな理由の一つです。特に後期ドイツロマン派の一人マーラーの音楽などを聴いたあとに、ベートーベンの曲を聴くといつも落ち着きが戻ってきます。 その安定感ある音楽は抜群の魅力をたたえています。またベートーベンは平和を願い正義感の強い人でもありました。 生涯を通じてその姿勢は変わっていません。 自由と平等を愛した音楽家でした。 有名な交響曲第3番「英雄」などはその典型的な例です。 またオペラ「フィデリオ」にもその思想が如実に表れています。またベートーベンはこよなく詩人ゲーテの作品を愛していたようです。 ゲーテの中に自分が目指す人生の哲学を見出していたのでしょう。ゲーテは戯曲「エグモント」を書き、1810年ウィーン宮廷歌劇場で初演されたゲーテの戯曲「エグモント」のために劇付随音楽をベートーベンは委嘱されました。 喜んで彼は承諾して10曲の劇付随音楽が作曲されています。その中の序曲はこの劇付随音楽のうちにとどまらず、あらゆる序曲というジャンルの中でも最も優れた音楽の一つではないでしょうか。 演奏会でもよく演奏される曲です。戯曲「エグモント」は実在した軍人・政治家であるラモラル・エグモントというオランダの英雄をモデルに描かかれており、物語は16世紀にスペインの圧制に苦しむオランダの民衆を救おうとエグモント伯爵が独立運動を指導し立ち上がりますが、捕らえられて死刑を宣告されてしまいます。おなじく捉えられた愛人のクレートヒェンが獄中で自殺します。そのクレートヒェンが自由の女神として彼の前に現れ勇気と正義を祝福します。すると伯爵は自分の死は無駄ではないと目覚めて敢然と死につくという悲劇的な英雄の生涯を表現した物語で、いかにもベートーベンが好みそうな戯曲です。この序曲はオーケストラの全奏とそれに続く弦楽器群による力強くゆったりとした序奏により始まりますが、オーボエとそれに続く管楽器による暗い主題が現れ、のちの悲劇を予感させます。テンポが早くなるとバイオリンとチェロに始まる弧を描くような動きが楽器と形を変化させながら繰り返し提示されるとともに、序奏の名残も現れて悲劇的な英雄であるエグモントが表現されます。最後はピアニシモで静かになった後、フォルテシモまで盛り上がり自殺するクレートヒェンと処刑されるエグモント伯爵の愛と正義を称える勝利の音楽として終わります。ベートーベンの音楽は「自由」を信じて力強く、聴く者に希望を与える「愛」と「正義」をたたえた壮烈な音楽詩として圧倒されてしまいます。今日の珈琲ブレイクに聴いてみようと思っています。愛聴盤 (1)「ベートーベン序曲集」 オイゲン・ヨッフム指揮 バンベルグ交響楽団 (RCA原盤 BMGジャパン BVCC5029 1985年録音) 1.「エグモント」op.84序曲 2. 「アテネの廃墟」op.113序曲 3. 「プロメテウスの創造物」op.43序曲 4. 序曲「コリオラン」op.62 5. 「フィデリオ」序曲op.72b 6. 「レオノーレ」序曲第1番op.138 7. 「レオノーレ」序曲第3番op.72a が収録されています。 演奏は純ドイツ風に重厚な味わいのある響きで、収録曲もベートーベンの代表的な序曲ばかりで納得のいく普遍的な演奏としてお薦めです。 1500円盤です。(2)劇付随音楽「エグモント」 ジョージ・セル指揮 ウイーンフィル(DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7036 1969年録音)劇音楽「エグモント」全曲が収録されています。 ドイツ語のナレーターが入って劇の進行を語っています。 グレートヒェンには懐かしいソプラノのピラール・ローレンガーが歌っています。 セル最晩年の録音でウイーンフィルハーモニーというのも嬉しいディスクです。 ヨッフムの演奏は純ドイツ風の堅牢な響きで素晴らしいのですが、セルの演奏は情熱的にウイーンフィルをあおりながら燃焼度の高いものとして訴えかけてきます。 これで1000円盤とはお買い得です。
2008年01月16日
コメント(4)
-
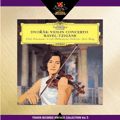
ドヴォルザーク ヴァイオリン協奏曲
「珈琲ブレイクの1曲」 ドヴォルザーク作曲 ヴァイオリン協奏曲 イ短調アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904)という作曲家の頭はどういう構造をしているのだろう、と思うことがあります。 チェコのスメタナ(1824-1884)亡き後、チェコ国民楽派の第一人者として揺ぎない地位を確立して、交響曲、室内楽、管弦楽曲などに優れた作品を数多く残していますが、彼の音楽に共通しているのは「スラブ的哀愁」に彩られた美しい旋律であると言えるでしょう。ドヴォルザークの音楽はとどめもないくらいに、美しい旋律が次々と現れては消え、消えては新たな魅力的な旋律が現れて消える、「方丈記」ではないですが、まるで河のように美しい音楽が滔々と流れています。9曲の交響曲、「スラブ舞曲」や交響詩、チェロ協奏曲やピアノ協奏曲、弦楽四重奏曲「アメリカ」、ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」、五重奏曲などの室内楽作品、どれをとっても美しい旋律に満ち溢れており、しかもそれぞれがとても親しみやすい音楽であることが特徴で、スラブ的哀愁を伴った哀感に溢れています。 まるで「メロディメーカー」と呼んでもいいほど美しい旋律に彩られた音楽ばかりです。そのドヴォルザークが書き残した、ただ一曲のヴァイオリン協奏曲も心や胸を打つ素晴らしく、美しい旋律に溢れた音楽で、有名なチェロ協奏曲やピアノ協奏曲に押され気味ですが、実に親しみやすく、美しさでは一級品の音楽です。第1楽章からドヴォルザーク節が全開で、スラブ的旋律が美しい独奏ヴァイオリンで奏でられており、スラブの情感がたっぷりの楽想です。第2楽章はまるでヴァイオリンとオーケストラが奏でるスラブのエレジーといった趣きのある、美しい音楽で楽章が満たされつくしています。第3楽章はスラブ舞曲のようで実に楽しい音楽で、チェコの農村地帯を色彩豊かに彩ったかのような曲想です。ドヴォルザークの音楽を聴いたことのある人がこの曲の名前を伏せて聴かされても、すぐにドヴォルザークの作品とわかるくらいに「ドヴォルザーク的」美しさと情感を曲のあちらこちらに聴ける音楽で、私は秋の夜長や冬の午後に取り出してはよく聴いています。その大好きな曲を今日はエディット・パイネマン(1937~)が1965年にプラハで録音した演奏で聴いてみようと思っています。今の若いクラシック音楽ファンには馴染みがないかも知れません。 美しい美貌と容姿に恵まれた上品な美音で60年代~70年代に根強いファンを持っていた女性ヴァイオリニストですが、クラシック音楽が家庭に普及した時代にも関わらず極端に録音枚数の少ないことが、やがてその名前も忘れ去られてしまった人でした。私の学生時代に(今から40年以上前になりますが)、FM放送から流れて来るこのヴァイオリン協奏曲にうっとりとしていました。 それが突如単売でタワー・レコードのVintage Collectonシリーズとしてリリースされたのです。この演奏をLP盤で買い求めるファンもいて、プレミアがつくほどの「幻の名盤」と呼ばれていた演奏が1000円で買い求めることが出来るようになり、早速私も購入しました。まるで初恋の想いを秘めた人との再会のようでした。 実に上品な美音で決して巨匠風にならず、しっとりとしていながら、曲の隅々まで照らすような緻密な音楽作りがとても魅力のあるヴァイオリンを聴かせてくれています。 共演はペーター・マーク指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団です。(グラモフォン原盤 タワーレコード PROA-164 1965年録音)
2008年01月15日
コメント(6)
-

チャイコフスキー「アンダンテ・カンタービレ」/大相撲初場所
「大相撲初場所始まる~朝青竜は」昨日から東京・両国国技館で大相撲初場所が始まりました。 話題は何と言っても横綱朝青龍の復帰です。 怪我・病気で休んでいたのではなくて、協会から2場所出場停止と謹慎を命じられての復帰場所。切符の売れ行きは完売で「満員御礼」の垂れ幕が下がっていました。やはり館内がぎっしりと満員になると観ている方だって熱気が伝わってくるようです。 TV観戦ですら感じるのですから相撲を取る力士にも力が入るだろうと思います。 無様な取り組みを出来ません。 これも朝青龍の復帰が話題になっているからでしょうか。テレビで観る限り朝青龍は元気いっぱい。体の張りもいいようです。 琴奨菊をいとも簡単に裏返していました。やはり強いですね。相撲にスピードがあります。 結びの白鵬も気迫あふれる横綱相撲でした。 まだ初日なのに何かすでに終盤を迎えたかのような緊迫感というか緊張感あふれる結び2番でした。 NHK解説者の北富士さんの朝青龍戦が終わった後のコメントが面白かったですね。 「いやあ、朝青龍の相撲よりも終わったあとの観客の反応が面白かったです。 拍手する人半分、しない人半分。 この反応は興味ありますね。 相撲より面白い!」嫌われる朝青龍の人気というか今の相撲ファンの心境を言い得て妙なるコメントでした。横綱だから勝って当たり前、どんな勝ち方をしてそのあとのマナーがどのように変わったのか、日本中の相撲ファンが観ています。 その熱い視線をバネにして力強い横綱復活を果たして白鵬と互角の優勝争いをして欲しいものです。私は特定の気に入りの力士はいませんが大相撲大好き人間です。 残念なのは日本人横綱が誕生しないことです。 朝青龍、白鵬の取り組みを観ていますと日本人力士とは違うパワーとスピードが段違いに勝っています。 ここ数年目立つのが「はたき」と「引き技」が多いのです。もっと押すとかまわしを取って寄ったり、投げるとかの技を見せてもらいたいものです。今のところ日本人の横綱候補はいないし、せめて今の二人の横綱が張り合って場所を盛り上げてもらいたいものです。 そして横綱としての品格を示してもらいたい、「ヒール」ではなく真の「ヒーロー」として尊敬される横綱を張って欲しいと願っています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに」 チャイコフスキー作曲 「アンダンテ・カンタービレ」チャイコフスキーの代表的名作。 弦楽四重奏曲第1番の「第2楽章」が原曲で、旋律の美しさは彼の作品中でも筆頭に挙げられる曲です。 ロシアの土俗的な地方の音楽を主題にしており、それをチャイコフスキーは藝術の香り高い音楽に浄化させたような、8分あまりの情緒あふれる名曲です。 弦楽合奏やチェロの独奏曲用にも編曲されて単独で演奏される機会が多い曲です。愛聴盤 ミッシャ・マイスキー(チェロ) オルフェウス室内管弦楽団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG10001 96年録音)チャイコフスキーの作品ばかりを収録したマイスキーの深い音色の至芸を味わうディスクです。 録音もデジタルらしい音ですが超優秀録音です。1 ロココ風の主題による変奏曲 2 青春は遠くすぎ去り*レンスキーのアリア 3 夜想曲 4 アンダンテ・カンタービレ*弦楽四重奏曲第1番ニ長調 5 フィレンツェの想い出*弦楽六重奏曲ニ短調
2008年01月14日
コメント(4)
-

譲り合い/メトネルのピアノ音楽
「譲り合う気持ち」昨日(1月12日)の産経新聞夕刊(関西版)2面の隅っこに面白いコラムが掲載されていました。 電車内での乗客の座席の占め方について書いていましたが、筆者はかねがね最近の乗客マナーを苦々しく思っていたそうです。私も電車に乗るたびにマナーの悪さを感じている一人なので思わずこのコラムを精読していました。 JRなら長椅子の場合は7人掛けを呼び掛けています。 確かにあの座席は7人なら十分座れるスペースです。 冬などの厚手のコートやオーバーを着ていても、乗客一人、一人が気をつければ7人は座れます。ところが乗客の中には大きく足を広げている人や、バッグなどを膝に置かずに座席に置いたりして7人が座れずにいる光景を何度も見ています。 そんな時は「あ、その人、もう少し足を普通にすれば座れるのに」とか「あのおばさん、バッグを膝に置いて上げれば前に立っている人が座れるのに」とか、隣の乗客と少し間隔を置いて座っている人を見れば「もう少し詰めてあげれば一人座れるのに」とか思うことがよくあります。私は電車に乗るとまづサッと座席を見渡します。 そしてカバンを座席に置いていたり、間隔を詰めていない人がいたり、足を広げている人を見れば、「すみません、もう少し詰めていただきませんか?」と断って座るのですが、中には私が座ると隣の人がわざと手の肘で私の脇腹をつつく人がいます。明らかに座られて迷惑だという意思表示なんでしょう。 そんな時にわざと大きな声でその人に訊きます。「どうかしましたか?」と。自宅を一歩出るとそこは公共の世界ですから、自我をすてなければならないことが多いにあります。 そこで生まれるのが「譲り合い」の気持ちです。 ところがこの産経のコラムでは「譲る」というのは所有権のある者から他の者への譲渡というのが本来の意味であって、この電車内での「譲り合い」の本来の意味ではないと書いています。この電車内の「譲る」は「膝送り」とか「膝繰り」が適しているのではないかと書いています。確かにそうですね。 少しでも膝を縮めていけば一人座れる余裕ができます。だがこの筆者の言いたいことは他にありました。江戸風情の言葉に「傘傾げ(かさかたげ)」という言葉があって、雨の日にすれ違う人たちはお互いの傘が通行の邪魔にならぬよう、また雨がかからぬようにお互いに傘をすこし傾けて相手の傘があたらぬようにしたことを言う言葉だそうです。「譲り合ってお座りください」というJRの標語は「席を譲り合う」ことではなくて互いに「気持ちを譲り合う」、つまり「気持ちを寄せ合う」ことなんだと締めていました。この精神は現代の日本の、いや人が生きていく限り大切なことだと痛感しました。「半ばは己の幸せを、半ば他人の幸せを」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「珈琲ブレイクに」 メトネルのピアノ音楽冬の寒い午後に熱い珈琲を味わいながら聴く音楽はいいものです。 私が音楽を聴くときには珈琲は欠かせません。 以前は豆を買ってきて自分で豆を曳いてサイフォンで作っていましたが、最近は専らネスカフェのゴールドブレンドというインスタント・コーヒーで飲んでいます。今日のように冬らしい寒い日に珈琲を味わいながら聴く音楽としてロシアの作曲家ニコライ・メトネル(1880-1951)のロシア色濃厚なピアノ小品集を聴くのもいいものです。 「ロシアのショパン」とも呼ばれ、古典的なたたづまいの中にドイツ後期ロマン主義を垣間見せながら、ロシアの香りをふりまいている魅力あふれるピアノ曲を残しています。今日のCDには1)おとぎ話変ロ短調op.20-12)4つのおとぎ話op.263)おとぎ話ホ短調op.34-24)おとぎ話ホ短調op.14-2「騎士の行進」5)おとぎ話ソナタ ハ短調op.25-16)ダンツァ・グラツィオーザ(優美な舞曲)イ長調op.38-27)ダンツァ・フェスティヴァ(祝祭の舞曲)ニ長調op.38-38)カンツォーナ・セレナータ(夕べの歌)ヘ短調op.38-69)プリマヴェイラ(春)変ロ長調op.39-3 が収録されており、ラフマニノフやチャイコフスキーなどと同じようにロシアの情緒を味わえる素晴らしい音楽ばかりです。愛聴盤 イリーナ・メジューエワ(ピアノ)(DENON CREST1000 COCO70756 年録音)買い求めやすい1000円盤でDENONのCREST1000シリーズの1枚です。
2008年01月13日
コメント(10)
-
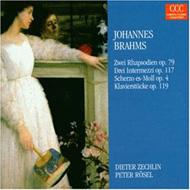
ブラームス 3つの間奏曲
「足し算、引き算の思考」作家曽野綾子氏がいつも機会のあるごとに述べておられるのが「足し算、引き算の思考」です。健康で、すべてが十分に与えられて当然と思っている人は、少しでもそこに欠落した部分ができるともう許せず耐えられなくなる。 これが氏に言わせると「引き算型」の思考だと。食糧、寝る場所、水道、清潔なトイレ、安全かつ正確な輸送機関、仕事があること、困った時に相談できる場所、無料で本が読めて借りることのできる図書館、健康保険、お金が無くても病気なら運んでくれる救急車、そんな結構な社会に住んでおられる自分は幸せだと思う、これが「足し算型」思考だと。こんな恵まれた国・社会に住んでいて幸せと考えることがまづ第一だと氏は述べている。 そう感じたら「感謝」が生まれるはず。 自分を生んでくれた親に感謝する。 その気持ちが湧いてくるはずだと。氏が述べている通りだと思います。 個々の人間にストレス、悩みなどがあるのは当たり前。その当たり前の悩みの解決を考える前に、上述の「足し算型思考」を思い出してみようと思います。 きっと先が見えてくるかも。「CD棚から1枚」 ブラームス作曲 3つの間奏曲 作品117今日は久しぶりにピアノ曲を聴こうと採り出したのがブラームスの後期ピアノ作品集。昨年のブログ記事「室内楽の楽しみ」シリーズで採り上げたブラームスの「クラリネット五重奏曲」の中でも触れましたが、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)は57歳の頃に友人あてに書いた手紙に「私は自分の生涯は勤めたから、このあとは平穏に楽しもうと思う、もうこれ以上作曲はしないよ」と書いています(門馬直美著 「ブラームス」)。しかし彼はそのあとクラリネット奏者ミュールフェルトとの邂逅によって、クラリネット三重奏曲、五重奏曲、クラリネット・ソナタという珠玉の名曲を書いています。 そして創作意欲を取り戻したブラームスは20曲のピアノ独奏曲(作品116~119)を書いています。明らかに青年期、壮年期のピアノ作品の情緒と異なる音楽が生まれています。 何よりもまづ音楽が瞑想的で、しみじみとした滋味あふれる深い味わいがあり、詩的で、しかも内面に潜む情熱を感じさせる音楽です。ブラームスの晩年に書かれた音楽を「たそがれの秋」「人生の秋」「残照の音楽」とかの言葉で語られていますが、ピアノ音楽でも同じことが言えるようです。曲は短い作品ばかりですが(長くてせいぜい7~8分)、その1曲、1曲に描かれた音楽はまさに「秋」から「晩秋」の風景で、深い思考を思わせる音楽ばかりです。この「3つの間奏曲 作品117」は激しさのない、ゆったりとした優しさにあふれた作品で、子守唄のような第1曲、即興風でアルペジオを主体とした第2曲、暗さのあるモノローグのような第3曲から構成された20分ほどの作品です。冬の夜に聴くのにふさわしいピアノ作品です。愛聴盤 ペーター・レーゼル(ピアノ)(シャルプラッテン原盤 CORONAレーベル CCC0002002 1972年録音)私が聴いているのは徳間音工から発売されたCDですが、紹介盤は同じ音源です。晩年の4つのピアノ作品集がカップリングされています。
2008年01月12日
コメント(2)
-

ハチャトリアン ピアノ協奏曲
『CD棚から1枚』 ハチャトリアン作曲 ピアノ協奏曲 変ニ長調今日もCD棚を見ながら最近聴いていない曲を探していると、目にとまった1枚がありました。 ハチャトリアンです。 随分と長い間この人の音楽を聴いていません。 この人の作品を聴くときはいつもバレエ音楽なので、今日は協奏曲を採り上げてみました。 昨年の終わりごろから室内楽ばかり採り上げていましたので、久しぶりの協奏曲の話題です。ソ連時代にとても個性的な音楽作品を書いたアラム・ハチャトリアン(1903-1978)は、クラシック音楽が好きな方なら誰も知っているバレエ音楽「ガイーヌ」「スパルタカス」などを書いた人です。 「ガイーヌ」の中の「剣の舞」「レスギンカ舞曲」などは演奏会のアンコールピースなどでしばしば演奏されている超有名曲です。ハチャトリアンの作品はどれも超個性的で、同じソ連の作曲家と比べてもロシアの大地が浮かんでくるような「憂愁の音楽」ではなくて、どこか東洋的な情緒がただようユニークな作風の音楽を書いています。 原始的、野性的な一種独特の味わいのある、魅力的な音楽が多い人でした。ハチャトリアンは1903年にアルメリアに生れ、1978年に亡くなっています。 プロコフィエフ、ショスタコービチと共にロシアの3大作曲家とも呼ばれています。上述の2曲のバレエ音楽の他に、3曲の交響曲、ヴァイオリン協奏曲やピアノ協奏曲が書き残されており、またソ連時代の作曲家の常で映画音楽なども数多く書いている人です。 これらの曲はハチャトリアンの故郷グルジアの味わいのある民族舞曲や民謡などが使われていて、リズミックで野性的で爆発するような生命力を持った音楽が特徴です。彼の生み出す音楽はアルメリアという特殊な国(西欧と東欧の交錯する文化地域)に生れていることから産み出されているのでしょうか、東洋的な情緒が色濃く音楽に彩られています。1936年に書かれた唯一のピアノ協奏曲は、3楽章の伝統的構成に基づいて書かれており、全曲に溢れる東洋的な美しい旋律は、非常に魅力的な響きを醸し出しています。 比較的平明な旋律で彩られており、郷愁を誘うような彼の東洋的な資質を余すところなく表現したピアノ協奏曲の佳品です。この曲はハチャトリアンを国際的に有名な作曲家として認められるようになった作品と言われています。愛聴盤 オクサナ・ヤブロンスカヤ(p)/ドミトリ・ヤブロンスキー指揮/モスクワ交響楽団(Naxosレーベル 8.550779 1996年録音)
2008年01月11日
コメント(0)
-
源氏物語(瀬戸内寂光訳)
「源氏物語を読み始める」昨日大阪市立中央図書館で「源氏物語」(瀬戸内寂光訳 講談社刊)の巻1と巻2を借りてきました。「桐壺」~「花散里」までの11帖です。 54帖の長編(全10巻)を完読するのは大変なことだと40年前の谷崎潤一郎新訳で承知しています。第1帖「桐壺」の冒頭の有名な書き出し「いつの御代のことでしたか、女御や更衣が賑々しくお仕えしておりました帝の後宮に、それほど高貴な家柄のご出身ではないのに、帝に誰よりも愛されて、はなばなしく優遇されていらっしゃる更衣がありました・・・・」を読み始めますと、瀬戸内氏の見事な現代語訳に惹きこまれて「平安時代」へとタイプスリップしております。全10巻を巻/月で読めば10月末には終わるかなと安易に考えています。図書館で読み易い文庫本を探したのですが全巻借り出し中でした。 ここの図書館は書籍は8冊までが貸出限度ですから、複数の人が借りているのでしょう。 それを待つのは大変なので相談カウンターで瀬戸内訳が他にないか検索してもらうと単行本で全10冊が借り出されていないので、第1巻と第2巻を借りることにしたのです。借り出し可能期間が2週間ですから2巻でも2週間で読むことにチャレンジしてみようと思ったからです。読み終えることができなければ借り出し期間を延長すればいいかな?さあ、今日から「平安時代」に入り込み、またすぐに「明治時代」(「日本の近代化 第2巻)に移り入る生活になるぞ。 何だか楽しくなってくるような感がします。
2008年01月10日
コメント(2)
-
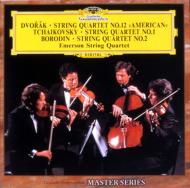
ボロディン/弦楽四重奏曲第2番/危険運転致死罪 適用せず
「危険運転致死罪 適用せず」福岡市で18年8月に後から車で追突され海に転落して亡くなった3児死亡事故の判決公判が昨日福岡地裁で下されました。 この加害者は缶ビール1本、焼酎水割り9杯という飲酒のあと運転してこの事故を起こしており、本人も飲酒運転が問われるので事故後水を大量に呑んでアルコールを少しでも減量させようとしたと当時報道されていました。しかし福岡地裁の判決は「危険運転致死罪」(飲酒運転による死亡事故を起こした場合にも科される罪)でなく「業務上過失致死罪」を適用して「わき見運転」による事故と断定していました。「危険運転致死罪」を適用するには「衝突回避措置を講じており、相応の判断能力を失っていなかった」ので「正常な運転が困難だったとは認められない」として「過失致死罪」で懲役7年6か月の判決を言い渡しています。飲酒運転が危険で酒を飲めば運転しないが今では社会の常識となっているのですが、「法律の壁」は厚いのですね。 上記のアルコール量を飲酒して人が3人まで亡くなっていても、「正常な運転が困難だったとは認められない」という裁判所判断に釈然としないものを感じます。この二つの法律による量刑の差が大き過ぎるからです。 「危険運転」は最高が懲役25年、「過失致死」が最高刑で7年6か月です。飲酒運転根絶が叫ばれている中、飲酒して運転した死亡事故が、脇見運転という単純な過失と同じように評価されていることに、私はとてもこの判決に???視したいし、違和感が残ります。 これは3人の子供をこの事故で失った両親への心情的な想いではなくて、法律の適用にはまだまだ議論すべき余地が残っているのではないかと感じます。皆さんはどう思われますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「CD棚から1枚」 ボロディン作曲 弦楽四重奏曲第2番アレクサンドル・ボロディン(1833-1887)はサンクトペテルブルクで、グルジア皇室の皇太子ルカ・ゲデヴァニシヴィリの非嫡出子として生まれています。 実子としての扱いはなかったのですがピアノの稽古を含めて高等教育を受けて化学を専攻している、作曲家としては毛色の変わった人でした。 正式な作曲法は30歳になってバラキレフから学ぶという変わり種の作曲家です。ボロディンは多作ではなく、現在も演奏される作品は交響曲第2番、オペラ「イーゴリ公」、そのオペラの中の「ダッタン人の踊り」、交響詩「中央アジアの草原にて」、それに弦楽四重奏曲第2番が主な作品です。化学を専攻しており生涯その道を歩んだ人でもあり、「ボロディン反応」という名前で化学史に名を残しているそうです。 作曲はその化学の研究の余暇にしていたと思われるほどで、自らを「日曜作曲家」と呼んでいたそうです。ボロディンの音楽は力強く叙事詩的情緒が色濃く、また豊かな和声が特色です。名高い「ロシア五人組」の一人で、ロシア的な音楽を濃厚に彩っており情熱的な音楽表現やその和声法は、ドビュッシーやラヴェルといったフランスの作曲家にも影響を与えたと言われています。ボロディンは動脈瘤の突然の破裂によって1887年2月27日に急死しています。そのボロディンの傑作の一つで、室内楽の音楽史における全作品の中でも最も人気のある曲の一つに「弦楽四重奏曲第2番」があります。この曲は、1881年8月に作曲されており、和声や調性の変化によって微妙な彩りの移り変わりを情緒豊かに歌い上げて、ロシア的・スラブ的な抒情に溢れた音楽でありながら、西欧の古典的な様式にそって書かれており、その融合というか統一感が素晴らしく生きている曲の一つです。各楽章の主旋律が非常に明確で、スラブ的な哀愁と濃厚なロシアのロマンティシズムが豊かに流れる美しい作品で、特に、第3楽章は「ノットゥルノ(夜想曲) アンダンテ」と記され、哀愁感のあるロシア的な美しいメロディがチェロで歌われており、この楽章が色々な楽器や編成の音楽用として編曲もされているほどに、美しい、有名な旋律です。憂愁と哀感、幻想と色彩豊かなロシア的な素晴らしい室内楽作品で、1882年の1月26日ロシアのペテルブルグ帝室ロシア音楽協会の演奏会で、同協会の弦楽四重奏楽団によって初演されています。愛聴盤 エマーソン弦楽四重奏団(グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG3579 1984年録音)収録は他にチャイコフスキーの弦楽四重奏曲第1番、ドヴォルザークの「アメリカ」という好カップリングが魅力です(私が聴いていますのはドヴォルザークが収録されていない、初出当時の盤です)。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1887年 初演 フランク 交響曲ニ短調1904年 初演 ドビッシー 「版画」
2008年01月09日
コメント(4)
-
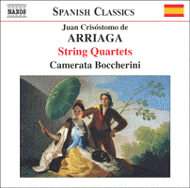
スペインのモーツアルト/電車内から本が消えた/水仙
これはもうだいぶ以前から感じていたことですが、どの路線の電車に乗っても(関西地域内)乗客が本を開いて読んでいる光景がまるで消えてしまったようです。 「電車内から消えた本」とでも揶揄したくなるような情景です。 たまに本を読んでいる人は中年~高年の人で、若い人が読書をしている姿はほとんど見かけなくなりました。本を読む姿から携帯電話を手にしてせっせと指を動かす姿に変わっています。 通勤時間帯の身動きできないほど混んでいるときは別ですが、少し時間帯をずらして立っている人が比較的少ない時間では、座っている人も立っている人も一生懸命に携帯電話上で指を走らせています。私からすれば異常な光景です。 女性も男性も一心不乱に指を動かしています。 BOSS缶コーヒーのテレビに流れるコマーシャル風に言えば「この星の人間は携帯電話に対して異常な執着心を持っているようだ」となるのでしょうか?当の本人たちはこの光景を異常と思わずに、そういう風に異常と観ている私を「変な人!」と思うのでしょうか?30年ほど前の通勤時間帯の電車内では多くの乗客たちが本を広げて読んでいたのですが、それはもう「帰り来ぬ古き良き時代」となってしまったのでしょうか?携帯電話の普及と情報の発達が何かを歪めているような感じがしてならない昨今の電車内風景です。「CD棚から1枚」 アリアーガ作曲 弦楽四重奏曲第1番ニ短調今日もCD棚から1枚を選んで聴こうと思います。 最近はオペラや交響曲・管弦楽曲・長大な協奏曲には目が行かず、もっぱら室内楽作品・器楽曲を選ぶ方が多いようです。 どうしてなのか自分でも説明がつかないのですが、室内樂作品はしっとりとした趣きがあって聴いていても心が落ち着くのでしょう。 オペラや交響曲を聴くときのように大きな心の高揚がなくて、流れくる音楽に心を沈めて聴けるからでしょうか?そんなことを想念しながら取り出してきたのがアリアーガが書いた「弦楽四重奏曲集」というNaxosからリリースされている1枚です。スペインの作曲家ホアン・クリソストモ・アリアーガ(1806-1826)は奇妙にもあのモーツアルト(1756-1791)と接点のある作曲家です。 何が接点かと言いますと一つは誕生日が同じなんです。 モーツアルトは1756年1月27日に生まれており、そのちょうど50年後の1806年の同じ日に生まれたのがアリアーガです。もう一つの接点は「若死に」です。 モーツアルトは35歳で生涯を閉じています。 アリアーガは20歳(正式には20歳にあと10日という19歳)で亡くなっています。これだけではただの数字合わせですが、このアリアーガが書き残した3曲の弦楽四重奏曲がこの数字合わせ以上に接点を感じさせてくれます。 アリアーガのこれらの曲はまるでモーツアルトかと想うほどに古典的な佇まいと、情緒は少しばかり違いますが典雅な趣きのある音楽です。 まるでモーツアルトの模倣かとも思える音楽です。特に、第1番ニ短調はまるでモーツアルトの弦楽五重奏曲ト短調のような、哀愁と晴朗・清澄さに溢れた名品です。この曲がアリアーガ16歳の時に作曲されたと知って驚きです。まるで人生の苦渋を嘗めてきた「人生の秋」を知った人が語っているかのような、落ち着いた情緒・佇まいなんです。ひょっとしてこのアリアーガはモーツアルトの「甦り」ではないか、モーツアルトがキリストならず「復活」してアリアーガとなったのではないかと、あらぬ妄想を引き起こすほどの音楽です。 アリアーガのこのニ短調の曲には、そういう妄想を起こすほどに、色濃く「人生の黄昏」「人生の秋」のような情緒・趣きが刻み込まれています。 わずか16歳で。そのアリアーガは「スペインのモーツアルト」と呼ばれているそうです。2年前に買ったこのCDを年に一度取り出して聴いています。↓ (Naxosレーベル 8.557628 2003年6月録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 シューマン ピアノ五重奏曲1927年 初演 ベルク 抒情組曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 水仙水仙があちこちで咲いてきました。 冬に花がない時期に椿や茶々花共に貴重な花ですね。
2008年01月08日
コメント(8)
-
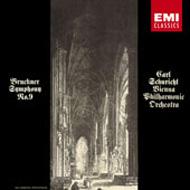
カール・シューリヒト/椿(詫び助)
「今日のクラシック音楽」 名指揮者 カール・シューリヒトカール・シューリヒト(1880年7月3日 - 1967年1月7日)は、ドイツ生まれの指揮者。 私が初めてこの人の演奏を聴いたのは高校2年生の時でした。 LP盤でした。 パリ音楽院管弦楽団を振ってベートーベン交響曲全集が東芝から発売されました。 7枚組モノラル録音で7千円。 父親から買ってもらった盤でした。 その時は何にも考えずにただ「買って」のおねだりでしたが、当時の7千円は国家公務員の父には相当な負担だった後になって申し訳ない気持ちでいっぱいでした。この全集を聴くことで私はベートーベンの9曲の交響曲の全容を知ることができたのです。それから1年後だったかウイーンフィルを振ったブルックナーの交響曲第9番の新録音が発売されました。 雑誌「レコード藝術」で故村田武雄氏がこのレコードの批評を書いておられて、演奏云々よりもこの曲の紹介にとても興味を持ったので、小遣いをためて買いました。 これが私のブルックナー体験の原点です。まだ高校生ですから指揮者の良い、悪いはわかりません。 ベートーベンの交響曲も生演奏やLPで他の指揮者の演奏を聴いて、シューリヒトの素晴らしさを感じたのです。 例えば大学生時代に聴いたカラヤンのベートーベン。 確かに美麗な演奏なんですが、あれが「カラヤン美学」なんでしょうか、カラヤン流にこてこてに塗りたくった表情は我慢がならず、以来この人の演奏は作曲家を選ぶようになりました。 シューリヒトの枯淡の味とは別次元でした。また純ドイツ風スタイルを頑なに守ったフランツ・コンビチュニーや朝比奈 隆の演奏と比べると、その違いは際立っています。 前者は遅めのテンポを守り、腰をどっしりと落として音楽を推進させたタイプの指揮者で、特に朝比奈のベートーベンやブラームスを聴くとこの人はドイツ人かと思えるほどの濃密なドイツ風スタイルで演奏を聴かせています。しかしシューリヒトはそういうスタイルとは次元の違う表現でベートーベン、ブラームス、ブルックナーを聴かせてくれます。 それはまるで竹を割ったような率直さと直截的なアプローチという、前者二人の指揮者とは異なるアプローチをかけています。その演奏スタイルは、基本的にテンポが速く、リズムは鋭くて冴えており、響きには生命力が感じられ、また音色は透き通るほどの透明度の高いものでした。 演奏スタイルは他のどの指揮者よりも個性的で、ある時はザッハリヒに厳しく響かせ、直截的に曲に対するアプローチをかけたり、またある時はテンポを動かしながらロマンティックな表情づけをして歌わせるなどをする指揮者でした。 そこに表現された音楽には滋味あふれる豊かな生命力が生まれて聴く者を納得させるのです。音楽全体を確信と明晰さで貫き通した指揮者で、上述のベートーベンやブルックナーの交響曲演奏に特にそれが顕著でした。シューリヒトはバッハからマーラー、ドビュッシー、ストラヴィンスキー、ディーリアスまでレパートリーが広いのですが、私が聴いたのはモーツァルトやブルックナー、ベートーヴェン、ブラームス、それにシューベルトに限られていました。1967年の今日(1月7日)、スイスで86歳の生涯を閉じています。命日にちなんで今日は彼がウイーンフィルを振ったブルックナーの交響曲第9番を聴いてみようと思っています。愛聴盤 カール・シューリヒト指揮 ウイーンフィルハーモニーブルックナー 交響曲第9番(EMI原盤 東芝EMI TOCE14023 1961年録音)何度も再発売を繰り返している盤です。 上記番号が最新のディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1857年 初演 リスト ピアノ協奏曲第2番1895年 生誕 クララ・ハスキル(ピアニスト)1912年 生誕 ギュンター・ヴァント(指揮者)1922年 生誕 ピエール・ランパル(不世出のフルート奏者)1967年 逝去 カール・シューリヒト(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 椿 詫助これも過去に掲載した椿の画像です。 椿と言えばこれ。 詫助です。
2008年01月07日
コメント(2)
-

アルウイン ハープ協奏曲/「日本の近代化」
『CD棚の1枚』 アルウィン作曲 ハープと弦楽のための協奏曲今、私の手元に中央公論社から発売された「日本の近代化」という江戸幕末のペルーの黒船来航から現代日本までの歴史を書いた本があります。 第1巻の「維新と開国」は昨年末までにようやく読み終えて、第2巻「明治国家の建設」を読み始めたところです。 全部で16巻(1冊あたり400ページ平均の書物)です。 これは通史的な読み物でなくて大学教授の書く論文調の読み物なので、なかなか次のページに進まない代物です。この全16巻(正確にはあと15巻)を今年12月まで読み通してみようと思っています。 月に1冊半の計算になります。 歴史を読み解くことで私たちのこれからの生き方の指針となればと思っています。歴史に関しては通史を高校の検定教科書を読み直そうと思って1冊買って読み始めました。 「日本史」です。 幕末以前の歴史は教科書で基礎知識を洗い直そうと思っています。あ、そうそう今年は「源氏物語1000年紀」にあたるそうです。 大学2年生の時に父が買って読んでいた谷崎潤一郎の現代語訳で全巻呼んだことがあるのですが、もう40年以上前のことです。 大学内の英語弁論大会でこの「源氏物語」を題材にして英語でスピーチした思い出深い小説です。 記念となる年に読み直してみたいと思っています。 図書館で瀬戸内寂光の現代語訳を借りて読んでみようと思っています。 こんなにできるかどうか不安ですね。 でも挑戦してみます。その他小説も読みたいし今年は読書に追われる年になりそうです。今日も珈琲ブレイクに何か聴きたいとCD棚を探していると快晴の冬の午後に聴くのに格好の1曲を見つけました。 アルウインが書いた「ハープ協奏曲」です。 この曲は2年ほど前にもこのブログで紹介した記事を加筆・修正してここに掲載しておきます。私はかねがねイギリスの作曲家ウイリアム・アルウィン(1905-1985)に興味を持ちながら彼の書いた曲をまったく聴いていませんでした。 それがNaxosのライブラリーに彼の作品が録音されているの知り、2005年の12月にそのCDを買って初めて彼の曲を聴きました。このCDには交響曲第2番、第5番とハープ協奏曲が収録されていますが、買った目的はハープ協奏曲を聴くためでした。アルウィンは、5曲の交響曲や、ピアノ協奏曲、オペラなどの他に200以上の映画音楽を含む作品を残しているそうです。アルウィンは自分からメッセージを発して、頭で聴いてもらう音楽よりも心に訴えかける音楽を重視して書いており、ロマンティストであることを公言していたそうです。音楽を聴くと確かに彼のメッセージが伝わってきます。このハープ協奏曲は弦楽合奏とのための曲で、管楽器を含む管弦楽との協奏に比べて、弦楽だけなのでしっとりと響きが実に美しく、ハープの繊細な響きが十全に伝わってきて、「ロマンティスト」アルウィンが紡ぎ出す旋律はとてもロマン情緒豊かで、楽想が弦楽合奏によるために全体にしっとりとしており、ハープがそれに美しく乗って、心を癒してくれるような27分間でした。このCDですスザンヌ・ウイルソン(HP) デーヴィッド・ロイド=ジョーンズ指揮 ロンドン・リヴァプールフィルハーモニー↓(Naxos レーベル 8.557647 2005年1月ロンドン録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1838年 誕生 マックス・ブルッフ(作曲家)1872年 誕生 アレクサンドル・スクリャービン(作曲家)1888年 初演 ドヴォルザーク ピアノ五重奏曲1924年 初演 プーランク バレエ音楽「雌鹿」1924年 初演 イベール 交響組曲「寄港地」
2008年01月06日
コメント(6)
-

川柳のおもしろさ/カルッリ ギター協奏曲/椿
「川柳のおもしろさ」最近どの新聞、どの週刊誌にも川柳というコラムがあり、男女を問わず投稿の数が増えていて選者は優秀作品の選考に追われているそうです。川柳のおもしろさは、まず作者の時代に起こっていることを即座に、時機よく歌われることでしょう。 発表するタイミングを失ってはいけません。 勿論、作者の家庭、学校、職場などを皮肉ったもの「
2008年01月05日
コメント(12)
-
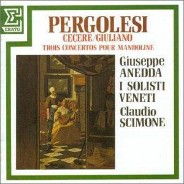
ペルゴレージ マンドリン協奏曲/石油枯渇
『今日のクラシック音楽』 ペルゴレージ作曲 マンドリン協奏曲 変ロ長調今日のテレビ・ニュースを観ていて驚いたことがあります。 全世界の石油埋蔵量が68年後には枯渇を始めるという話題です。 5年前のデータよりも11年早くなったことも報じられていました。 そんなことを私はちっとも覚えていません。 そんなニュースが5年前にも報じられていたことを覚えておらず、今日観たニュースで驚いています。そんな未来には私は当然生きてはいないのですが、孫たちの世代が心配です。 枯渇するのが5年間で11年も早まったのは当然使用量の増加です。 中国やインドでの経済発展による増加などが挙げられていました。この石油エネルギーに変わる材質変更・燃料の代替物の開発がこれから拍車をかけるように迫られてくるでしょう。1970年にも「オイル・ショック」があり、ドル価値絶対の神話が崩壊してドルが全世界で暴落しました。 日本も円からドルへの交換相場が固定相場から変動相場に移行して、輸出などでは逆鞘で儲けましたが、原材料を輸入に頼る国家の根幹を揺るがす大きな出来事でした。日常生活ではティッシュ・ペーパーが店頭から無くなるという社会現象が起こり、主婦たちはペーパーの確保に躍起になったことがあります。 あれから40年。 大きく社会・経済・国際現象が変わりました。 しかしどう変わっても石油は無尽蔵に埋蔵していることはないようです。そんなニュースを夕食時に観て驚いていました。昨日の夜は何故かテレビ番組を観る気がしなくて、久しぶりに音楽カレンダーを観ていると今日はペルゴレージの誕生日。 おそらく1年に1度聴くかという作曲家です。 「スターバトマーテル」は演奏時間が長いので、マンドリン協奏曲を取り出して聴いていました。ジョバンニ・ペルゴレージ(1710-1736)はモーツアルトにも較べられるほどの有り余る音楽の才能を持ちながら、わずか26歳という若さでこの世を去った作曲家でした。 26年という短い人生で、作曲活動を行なったのは5年間だけだったと言われています。劇音楽や宗教音楽、室内楽に多くの曲を書残しているそうです。 歌劇「奥様女中」や宗教曲「スターバト・マーテル」などは今尚演奏されている傑作です。ところが、その死後に彼の人気は急騰して、色々な偽物作品まで彼の作として出版されたために、後世では彼の音楽の年譜も作成することが難しくなり、謎の多い作曲家となってしまいました。実際には、この「マンドリン協奏曲 変ロ長調」も確かに彼の作品であるという確証がないそうで、楽想からそうだろうという憶測が定説となり、今では彼の曲となっているそうです。3つの楽章からなる伝統的な協奏曲スタイルで、マンドリンの魅力がふんだんに味わえる音楽です。 明るく、典雅な第1楽章、シチリアーナと呼ばれる情緒いっぱいの第2楽章、マンドリンの独奏がきらびやかな第3楽章の、20分ほどの音楽です。この盤が発売されたのがオイルショック時代でした。 LP盤を買って長年聴いていた好きな曲の一つでした。1710年の今日(1月4日)、このペルコレージ(1710-1736)が生まれています。 彼の誕生日にちなんで聴いていました。愛聴盤 ジュゼッペ・アネッダ(マンドリン) クラウディア・シモーネ指揮 イ・ソリスティ・ヴェネティ(エラート原盤 BMGビクター B15D-39204 1971年録音 廃盤)カップリングはC.チェチェレーレ(18世紀)とG.ジュリアーノ(18世紀)のマンドリン協奏曲です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1710年 誕生 ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ(作曲家)1881年 初演 ブラームス 「大学祝典」序曲
2008年01月04日
コメント(8)
-
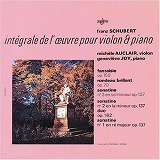
ミッシェル・オークレール/素心蝋梅
「今日のクラシック音楽」 ヴァイオリニスト ミッシェル・オークレール昨年12月30日の日記に書きましたが、今年はこのブログも少し趣向を変えて内容をクラシック音楽に拘らずに書いていこうと思っていました。 しかし年頭からそのクラシック音楽ネタとなりました。今朝から3,000枚ほどあります自分のライブラリーから取り出して聴いてみたCD1枚があります。 フランスの女流ヴァイオリニスト、ミッシェル・オークレール。 名前をご存じない方がほとんどだと思います。 1924年6月16日生まれ、2005年6月10日に亡くなった演奏家です。しかし彼女の演奏記録は限られています。 メンデルスゾーンやチャイコフスキー、ブラームスの協奏曲数枚とクライスラーの小品、それに今日の話題盤シューベルトが残されているだけです。60年代に結婚を機会に引退をしたからです。 だから若い人たちには無名とも言えるヴァイオリン奏者でしょう。 彼女がなぜ若くして引退したのかはわかりません。少なくとも私がその理由を知りません。 引退後は桐朋学園で教鞭を執っていたこともあるそうです。彼女のヴァイオリンの音色はローラ・ボベスコと同じように一言で表現すれば「エレガント」という言葉で語ることができる奏者です。 あるいは「濡れそぼつ」という表現もできるヴァイオリンでした。気品があり、しっとりとした表情づけがとても魅力のある音色でした。 今は私もシューベルトの紹介盤「ヴァイオリンとピアノのための作品集」1枚のみを所有するだけですが、LP時代には協奏曲(メンデルスゾーンとチャイコフスキー)を聴いていました。 確かフォンタナ盤だったと思います。その彼女のCD盤が1997年にエラートから再発売されていたのを聴いています(シューベルトの作品)。 長い間チョン・キョン・ファや五嶋みどり、ムター、それに往年のオイストラフやグリュミオー、シェリング、ミルスティン、最近の諏訪内晶子などの演奏ばかり聴いていて、すっかりオークレールの美音を忘れていたのですが、今朝ライブラリーで見つけて懐かしく思い久しぶりに聴いていました。技術的にはもっと巧い若手のヴァイオリニストはいくらでもいると思います。しかし、技術では彼らより劣っていても、この情感あふれる美音は生半可なものではありません。 このシューベルトの音楽から聴こえてくるヴァイオリンは、曲の美しさを際立たせており、しかも高貴あふれる上品さで迫ってきます。 シューベルトのこんこんと湧き出る美しい旋律を優雅に弾きこなすオークレールのヴァイオリンは、聴く者を純粋に音楽の中に沈めてしまう不思議な魅力に溢れたヴァイオリン奏者です。紹介のCDは2003年8月に「エラート・アニヴァーサリー50」の1枚として再発売されたのを今月31日に再プレスされて発売されます。 ヴァイオリン好きのお方で未聴の人にはぜひ薦めたい1枚です。 録音は40年以上前の1962年ですから現在のような優秀録音ではありませんが、そこは「音のエラート」です。きっといいリマスターでよみがえっていると確信しています。(エラート原盤 ワーナーミュージック WPCS20284 1962年録音)この商品番号は今月再発売される番号です。収録曲は(1)幻想曲ハ長調(2)華麗なるロンド ロ短調(3)ソナチネ第1番~第3番(4)ヴァイオリン・ソナタ(デュオ)以上すべてシューベルトの作品で2枚組です。 価格は2枚組で3000円でお釣りがきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の音楽カレンダー」1843年 初演 ドニゼッティ オペラ「ドン・パスクヮーレ」1890年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「今日の一花」 素心蝋梅(ソシンロウバイ)もう町内のおうちの庭で咲き始めています。 この花は香りがとてもよくて咲いている近くでは妖しい匂いをまき散らせています。 昨日は久しぶりの青空で黄色と青がとてもいいコントラストでした。蝋梅科 ロウバイ属 中国原産で日本には17世紀頃に渡来したそうです 開花時期 12月末~3月中旬。お正月頃から咲き出す花で冬の花の少ない時期だけに貴重な花です。 蝋細工のようで梅に似ていることからこの名前が付けられています素心の意味は外側だけでなく内側も黄色であることから命名されています。ただの「蝋梅」であれば内側が赤っぽくなっています。
2008年01月03日
コメント(4)
-
祝 新年!
明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては良いお年をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年もどうぞかわりませぬご愛顧をよろしくお願い申し上げます。昨年暮れから元旦にかけて少しお酒が過ぎたようです。 29日から元旦まで日本酒を1升半ほど呑んでしまいました。 大晦日のお寺行事(除夜の鐘つきー檀家の人たちが新年への願いを込めて打ちにきます)で茶碗酒5杯呑んで午前2時頃に帰宅、昨日の朝10時からの元旦会(がんたんえ)でも檀家の皆さんと新年を祝って食事会をお寺でやったのですが、そこでも銚子5本呑んでいい新年を迎えていました。 これも体調が完全に回復したおかげと思います。 それまではアルコールを飲みたいという気分にならななかったのです。帰宅したのが午後2時。 風呂に入って身体ともすっきりさせて7時まで寝正月を楽しむ元旦でした。元旦には「聴き始め(ききぞめ)」の曲があります。 モーツアルトのヴァイオリン協奏曲第3番。 掛け値なしに明るく、伸びやかで晴れがましい旋律が新年を祝う曲としてぴったりで、学生時代から元旦に聴く曲として選んでおります。元旦の夜も(ほんとは朝がいいのですが)この曲を聴いて新年を祝っていました。ほとんどBGMに近い聴き方なんですが、この曲がぴったりと新年を祝ってくれるような気がします。昨年も相変わらず殺人事件が新聞紙上やテレビのニュースなどでにぎわいました。ほぼ毎日のように殺人事件が報じられていたような気がするほど多かったです。 それも身内が絡んだ事件が多く、夫婦の絆、親子の愛が壊れてしまった象徴のような事件が多かったですね。今年はそんな事件が少しでも減るように願っています。高齢化が進んでいます。 突然の発病への救急の処置が行き届いていても、病院の手不足で落とさなくてもいい命が消えています。 この医療現場の改善も今年はなんとか道筋をつけて欲しいものです。今年は北京オリンピックが開かれます。 また感動の時間を与えて欲しいものです。それと555兆円にも膨れ上がった日本の借金。 次世代へ少しでもこの借金を減らしてあげたいものです。 政治家の奮闘をお願いしたいものです。そんなことをぼんやりと考えながらモーツアルトの曲を聴いていました。 今年の年末には1年を振り返る言葉として「喜」か「幸」という漢字が選ばれることを祈って。
2008年01月02日
コメント(14)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪菅原咲月(MC)『週刊乃木坂…
- (2025-11-25 04:48:40)
-
-
-

- プログレッシヴ・ロック
- Steve Hackett - The Lamb Highlight…
- (2025-11-22 00:00:10)
-
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-







