2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
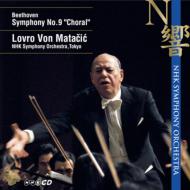
マタチッチの「第9」
『今日のクラシック音楽』 マタチッチ指揮のベートーベン「第9」未聴CDを聴くー第10弾これも昨年11月にキング・レコードからNHK音源としてリリースされたN響との1973年のライブ録音で、放送でも聴いたり観たりしました気に入りの演奏です。 曲はベートーベンの交響曲第9番「合唱付き」。マタチッチ特有の骨太の骨格で刻み込まれた会心の演奏が聴ける「第9」です。第1楽章からドラマティックな表現で、ここでのN響の弦楽器はとても分厚く響いており、そこへブラスの鳴動が「威風堂々」とした雄渾極まりない表現で「壮麗」とも言える音楽の進行に聴く者が圧倒されるような展開をみせています。第2楽章は少し早めのテンポで進められているのに、音の透明度が見事でこの演奏当時のN響のいい面が100%表された音楽が展開しています(いい指揮者では素晴らしい演奏を行う)。 早めのテンポがこの楽章をぐいぐいと推進力にあふれた素晴らしい音楽であることを証明するかのように堅牢強固な響きが魅力の演奏です。第3楽章ではブルックナーの第7番シンフォニーの「アダージョ」のように、実に丁寧にしかも起伏の大きい表現が魅力の楽章としています。 テンポは速めですが美しく琢磨された響きが崇高な気分を十全に伝えています。終楽章ではこれまで抑えてきたエネルギーを爆発させるかのように、壮麗に満ちた火山のマグマのエネルギーの爆発のような、力強い音楽を聴かせています。 国立音楽大の合唱も壮麗な響きで盛り立てており、当時の一流日本人独唱家による「歌」も満足できる歌唱を聴かせています。 コーダの迫力はただただ「凄い!」としか言いようのないマタチッチの堅牢・強固・骨太の表現の極みのようです。機会あるごとに書いていますが、70年代にはこういう指揮者・演奏家がごろごろといたのですが、今は昔日の感と言えるのは寂しいことだと思います。(NHK音源 NHK CD キングレコード販売 KICC3066 1973年12月19日ライブ)ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 NHK交響楽団中沢桂(S) 春日成子(A) 丹羽勝海(T) 岡村喬生(Br)国立音楽大学合唱団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1797年 誕生 フランツ・シューベルト(作曲家)
2007年01月31日
コメント(6)
-

村治佳織 「ライア&ソネット」
『今日のクラシック音楽』 村治佳織の新録音盤「ライア&ソネット」未聴CDを聴くー第9弾 村治佳織という女性ギター奏者は新録音盤がリリースされるたびに話題となる若手演奏家のようです。 イギリス・デッカ レーベルに移籍しての第3作CDが「ライア&ソネット」というタイトルがつけられています。買ってからしばらく未聴のままになっていたのですが、先日ようやくCDプレーヤーに載せてみました。 タイトルの「ライア&ソネット」の意味もわからずに聴き始めると、冒頭の曲から美しい合唱アンサンブルが聴こえてきました。慌ててCD解説書を読むと独奏ギターと合唱のコラボレーションとなったアルバムの旨書かれていました。 こういうスタイルの演奏はとても珍しく、初めて耳にするコラボレーションでした。 タイトルの「ライア&ソネット」とは古代の「ライア」という弦を爪弾いて楽器に抒情を託する行為の象徴的な意味で、「ソネット」は詩の意味。これでタイトルが何を表そうとしているのかわかります。 村治佳織が独奏ギターを受け持って合唱が「詩」を歌う、何とも優雅で高貴な情緒を醸し出すコラボレーションなのでしょう。幾つかはギター独奏もありますが、ほとんどがギターと合唱の共演で音楽史のジャンルに入る曲から現代民族音楽に至る曲まで網羅されており、まさに「癒しの音楽」そのものと言えるディスクで、ギター演奏の新しい発展の可能性を問いかけた注目の演奏と言えるでしょう。一聴以来、時々このディスクを取り出しては数曲を選んでは聴いています。 特に夜の帳が降りた後に聴く情緒は言葉にし得ない至福の時空を生み出してくれています。ヒーリング系クラシック音楽ディスクとは明らかに一線を画した、芸術性豊かさで聴き手を癒してくれるのは、村治佳織の類まれな弦さばきとザ・シクスティーンという16名(現在は18名だそうです)の素晴らしいアンサンブルによる名技性を兼ね備えた集団による演奏の賜物なのでしょう。様々な世代に聴かれるべく第1級の「癒しの音楽」が刻まれています。 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD1176 2006年7月ロンドン録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1963年 没 フランシス・プーランク(作曲家)
2007年01月30日
コメント(6)
-
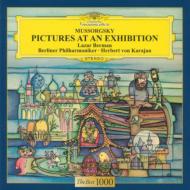
カラヤンの「展覧会の絵」
『今日のクラシック音楽』 カラヤンの「展覧会の絵」未聴CDを聴くー第8弾ロシアの作曲家モデスト・ムソルグスキー(1839-1881)が書き残した作品の中で、最も有名な曲が組曲「展覧会の絵」と交響詩「禿山の一夜」でしょうか。クラシック音楽に魅かれた頃はほとんどオーケストラ曲、それも豪華・華麗な曲が好きだったと覚えています。 特にブラスが咆哮して弦楽器の上に乗って鳴るような音楽に魅かれていたようです。ムソルグスキーの「展覧会の絵」は長い間オーケストラ版で楽しんでいました。 トスカーニ指揮のNBC交響楽団の演奏する小学校の恩師から借りたLP盤で、この曲を初めて聴いたのが中学3年生でした。 以来私の最も好きな管弦楽曲の一つになっています。LP時代にはトスカーニは勿論、ストコフスキーやフリッツ・ライナー、カルロ・マリア・ジュリーニのディスクで随分と楽しみ、CD時代になってもデュトワ、フェドセーエフやゲルギエフ、チェリビダッケなどの録音盤で楽しんでいます。この曲はロシアの画家ハルトマンが亡くなったのを悼んで、友人ムソルグスキーがハルトマンの絵を展覧会場で観て歩いているさまを描いた音楽で、絵から絵に移動する空間を「プロムナード」と称して歩いているさまを描写すという秀逸のアイデァで音楽を盛り上げています。ムソルグスキーの原曲は独奏ピアノにるものですが、フランスの作曲家モーリス・ラヴェル(1875-1937)の管弦楽への編曲によって、原曲とはまったく異なる華麗・豪華・多彩・表情豊かな音楽に生まれ変わり、あたかもラヴェルが作曲したかのような曲に変貌しています。弦楽器の重々しい音色、木管楽器による寂しさ、哀愁のようなものや、金管楽器や打楽器の多彩な彩りの表情がピアノスコアから解き放たれて自由に闊歩しているかの如き音楽に生まれ変わらせた、まさに「オーケストラの魔術師」と呼ばれたラヴェルらしい華麗なオーケストレーションが聴き物の音楽です。演奏会やLP・CD・放送などで随分とオーケストラ版を聴いていましたが、昨年11月にユニヴァーサル・ミュージックから再発売された1000円盤シリーズの中に、1965年に録音されたヘルベルト・フォン・カラヤン指揮のベルリンフィルの演奏盤がありました。これまでLPやCDで幾度と無く再発売されてきた演奏なのですが、この「展覧会の絵」をカラヤン指揮での演奏を唯の一度も聴いていなかったのを思い出して、1000円ならいいか、と自分を納得させて購入して聴いてみました。録音は40年以上も前のものですが、音質としては可も無く不可もない音でした。それよりも驚いたのはテンポが他の指揮者よりも少し遅く、楽譜に書かれた音を抉り出すように表現されており、曲の彩りがカラヤン独特の美麗として磨かれたベルリンフィルの艶のある表情豊かな音楽が部屋を満たしてくれたことです。冒頭の「プロムナード」からしてテンポが遅めで重厚に描かれており、これから語られる「絵」に対する興味を涌かせてくれるような表現にまず魅かれます。「古城」の侘しさ・寂しさも十全に語られてるし、「ビドロ」における圧倒的な盛り上がりも悲痛な叫びとなって迫ってきます。速いテンポの曲(「殻をつけた雛の踊り」や「ルモージュの市場」など)でも、軽快に表情豊かに描きだしており、クライマックスの「キエフの大門」では圧倒的な迫力で迫ってきます。一言で例えるならロシアの香りを匂い立たせる演奏ではなく、「カラヤン美学」の華麗さ・美麗でいっぱいの演奏です。 これは良くも悪しきもカラヤンの美点・欠点の表裏一体となった「カラヤンの展覧会の絵」と言える演奏だと思います。(ドイツ・グラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCG5051 1965年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1862年 誕生 フレデリック・ディーリアス(作曲家)1905年 初演 マーラー 歌曲集「亡き児をしのぶ歌」1962年 没 フリック・クライスラー(ヴァイオリニスト・作曲家)
2007年01月29日
コメント(0)
-

フルート・レヴォルーション
『今日のクラシック音楽』 フルート・レヴォルーション昨年11月にリリースされました少し変わったフルート演奏のCDを今日は紹介したいと思います。1. ヴィヴァルディ「四季」から春2. マスネーの習作3. ケテルビーの「スケルツオ」4. フランクの小品5. ショパン「ロッシーニの主題による変奏曲」6. チャイコフスキー 「フルート小協奏曲」7. 深井史郎「小間奏曲」8. キュイ「スケルツェット」9. ラスカ「奈良」10. 冬木 透「魔笛の主題による変奏曲」11. 冬木 透「帰ってきたワンダバ」12. 武満 徹「Mi-Yo-Ta」13. ツィピン「コンツェルタント第1番」このCDを買った理由はショパンとチャイコフスキーの曲に惹かれたことと、多彩なプログラミングでした。「春」はあの有名なヴァイオリン協奏曲「四季」の第1楽章「春」のフルートへの編曲で、編曲者は日本の童謡「むすんで ひらいて」の原作者であり、フランスの啓蒙思想家ジャン=ジャック・ルソーです。 フルートが奏でる「春」は、ヴァイオリンと違った彩りを聴かせてくれます。 ただ原曲のヴァイオリンと違ってイタリア的な眩いような「春」の情景と趣が違いますが、小鳥のさえずりのような音色が魅力的です。ショパン作曲のロッシーニの主題と変装は、オペラ「シンデレラ」のアリア「もう悲しくはありません」をモチーフにしており、「ピアノの詩人」による14歳の時の作品で、彼の作品群の中でユニークな存在です。 音楽もいかにも正攻法で書かれた曲という感じです。 ロッシーニの美しい旋律をフルートに歌わせるというアイデァの生きた小粋な作品でした。このCDの目玉であるチャイコフスキー。 世界初の録音だそうです。 この曲はチャイコフスキー自筆のスコアは数小節残さされているのを、ブラジル出身のフルート奏者ジェイムズ・ストロースが様々な文献を調べあげて完成したそうです。こうきょうきょく第6番「悲愴」を書き終えた後に、チャイコフスキーは「フルート小協奏曲」を書きあげようと試みて、未完のまま生涯を終えてしまったそうです。音楽はいかにもチャイコ節らしいところもありますが(オペラ「オルレアンの少女や「悲愴」の旋律が現れます)、タファネルの作品なども流用されていて、チャイコフスキー独自の遺稿だけに基づく編曲ではないようです。音楽はチャイコフスキー的なバレエ音楽に想いをはせるような作品で、興味あるフルート作品です。演奏はこのCDがデビューとなる日本の若手美貌の女性フルート奏者難波 薫と指揮者沼尻竜典のピアノです。デビューCDとなればフルートの有名曲などを収録するのが普通ですが、ここに収められた曲はまさに異色の作品ばかりで、その意味からも「フルート・レヴォルーション」なんでしょう。(たまゆら原盤 キング・インターナショナル KKCC3015 2006年2-8月録音)
2007年01月28日
コメント(2)
-
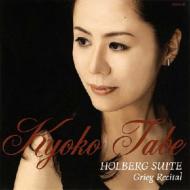
田部京子の「グリーグ・リサイタル」
『今日のクラシック音楽』 田部京子の「グリーグ・リサイタル」未聴CDを聴く - 第7弾田部京子が新録音盤を昨年の11月にリリースしています。 作品はすべてエドヴァルド・グリーグ(1843-1907)の作品です。グリーグの代名詞のような曲ー「ペール・ギュント」から4曲、「ホルベアの時代から」という管弦楽曲をグリーグ自身のピアノへの編曲にもとずく演奏と、これもグリーグの代表作「抒情小曲集」から7曲というラインナップです。私は田部京子のピアノに出会ったのはDENONからリリースされたメンデルスゾーンの「無言歌」集の1枚でした。 もう12~3年前のことです。 とても清潔感のある濁りのないピアノに魅かれました。 以後彼女のリリースしたシューベルトの最後のソナタや「アンコール小品集」「ロマンス」などを買っては楽しんでいます。彼女のすべての録音盤を買ってはいませんが、久しぶりに新録音を買ったのがこの「グリーグ・リサイタル」です。「ペール・ギュント」「ホルベアの時代から」両曲はオーケストラで聴く感じとは全く違う感じです。 オリジナルは音の広がりや色彩豊かな情緒いっぱいなのですが、ピアノだけで聴くこれら2曲の清澄な響きに新たに曲の魅力の新発見をしたような感じです。田部京子のピアノは、粒立ちの良い、透明感あふれる音色でグリーグ特有の叙情性を引き立てています。 ソノリティが清潔なほどに整えられており、それが叙情性をこの上なく醸し出しています。 ノルウエーの澄み切った透明感あふれる空気を透き通ったようなピアノの音色で部屋いっぱいに運んでくれます。「ペール・ギュント」の「朝」は、オリジナルでは少し朝靄の感じで素晴らしいのですが、彼女のピアノは「冷たい朝」「北欧の澄んだ朝」の情景を清潔感(清らかさ)に満ちています。「オーゼの死」は原曲が悲痛な色合いに満ちているのですが、彼女のピアノの濁りのない音でいっそうの悲しさを表現しています。「ホルベアの時代から」も同じで、叙情性を見事な技巧で表現しており、グリーグの美しい旋律を浮き彫りにしています。「抒情小曲集」はリリックに歌い込まれた響きが一種緊張を伴う、澄んだ音色で醸し出されており、ここにも濁りのない清潔なピアノが部屋を「幸せ空間」へと変えてくれる演奏です。またいいディスクに出会えた喜びに浸っています。このCDです。 田部京子 「グリーグ・リサイタル」 (DENONレーベル COGQ20 2006年8月録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1756年 誕生 W.A.モーツアルト(作曲家)1823年 誕生 ラロ(作曲家)1901年 没 ジュゼッペ・ヴェルディ(作曲家)1908年 初演 ラフマニノフ 交響曲第2番
2007年01月27日
コメント(4)
-
ありがとうございました
私のPCダメージにつきまして多くの方々からアドヴァイスをいただきましたことにお礼を申し上げます。 ありがとうございました。 昨日の日記に書きましたように仕事と神社の会計帳簿を引き続き作成する必要のあることから、今朝PCをジョーシンに修理のための見積もり(金額と期間)をして貰うために渡してきました。 その結果で次のステップに進みたいと思っています。 皆様のお心遣いに感謝の気持ちでいっぱいです。 ひとまづ、この問題は時間を置くことに致します。 楽天の管理画面も修正されて、使い勝手が少しは改善されたようです。 ネット・カフェのPCを使って明日から音楽日記を再開致しますので、これまで同様にご支援を賜れば幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
2007年01月26日
コメント(4)
-
PCの修理
昨日は友人から電話で色々とアドヴァイスを受けました。 PCショップにも訊きました。 それからメーカーに電話で訊いてみたのですが、100%近くの確立で修理でしょうと言われました。ハードディスクのダメージと推測されています。 修理することはいいのですが、問題は期間です。 1ヶ月以上かかるようでしたら、仕事に差し支えて、仕事をもらえなくなります。それに神社会計を担当していますから、3月中旬には決算報告書を作り上げておかねばならないですが、その基礎データーがすべてPCに入っています。最悪は新しいPCを買わねばと腹をくくってはいますが。
2007年01月25日
コメント(6)
-
PCが完全にダウン!
昨夜、PCを立ち上げて仕事をしている最中に突然画面が消えて、英文でPCダメージを防ぐためにシャットダウンしますと表示があって再起動されたのですが、PCメーカーロゴ表示画面のまま動かなくなり、1時間そのまま様子を見ていたのですが変わる様子もなく、PCからの音もしなくなりました。 電源を切るにも切れず、強制終了もできず、もちろんリカヴァリーするためにF8を押しても反応なしで、仕方なしにケーブルを引き抜いて終了させました。 以後2度試みましたが結果は同じでした。1月ほど前から動きが重く、一度買った時点に戻さなければと思っていたのですが、とうとうこんな事態になりました。とりあえずこの記事はネット・カフェで書いています。昨日は夜までルンルン気分で、楽天への腹立たしさも落ち着いてきた矢先の出来事でした。困るのは仕事ができないのと、保存していなかった資料が消えてしまうことです。 メーカー店に持ち込んでハードディスクに残っているデーターの保存を以来できるかも知れませんが、仕事のデーターについては時間的に間に合わずに困っています。今年は何かと「出入り」の激しい年になっています。昨日の記事でコメントをいただいた方々への返信は遅くなりますがしばらくお待ちください。 まず仕事最優先にしたいと思っていますので、ご了解下さい。
2007年01月24日
コメント(12)
-
財布が戻ってくる!
今朝9時半ごろに奈良県・桜井警察署から財布が届けられていると電話で知らせがありました。 財布の中に私の名刺1枚を入れてあったので電話をくれたようです。 届主が取得物へのお礼を貰う権利を放棄したのか、署まで取りに来るか着払い郵送で送るかの方法がありますという話でした。 この2~3日は済ませなければいけない仕事に追われているので、桜井市まで出かけるのは少しきついので、送ってもらうことにしました。届けていただいた方にお礼を申し上げたいのでお名前と電話番号を教えて欲しいと言ったのですが、個人情報流出防止のために教えていただけませんでした。Xさんに感謝の言葉もありません。 ありがとうございました。 ありがとうございました。 このご恩は決して忘れません。 人の心の温かさを身にしみてわかりました。
2007年01月23日
コメント(28)
-

奈良県・長谷寺
今日はいつも呑みに行く居酒屋夫婦と一緒に奈良県桜井市にある長谷寺へ行ってきました。このお寺は西国三十三所観音霊場の八番札所で、真言宗豊山派総本山で686年に始まり、727年に十一面観音菩薩が祀れている由緒あるお寺です。登楼撮影日 2007年1月22日「花の寺」としても有名で、桜・牡丹・紫陽花・寒牡丹などは見事な花を咲かせて訪れる人たちを癒してくれるお寺です。 本堂は国宝(1650年建立)に指定されています。大阪・和泉市から車で1時間余りで行けるようになり、大変便利になっています。今日のお目当ては見頃の寒牡丹の撮影でしたが、肝心の撮影は思うようにいかず満足できる画像がなくて実に残念でした。更に1万2~3000円入っていた財布を落としてしまい、最悪の日となりました。 銀行キャッシュ・カード、それにタワーレコードのポイントカード(20,000円相当のポイントがたまっています)、30年間使い慣れた財布そのものが惜しくてなりません。このブログを始めてからほぼ毎日クラシック音楽記事を書いていましたが、そのことだけでもとても緊張する日々を送ることができました。 今日はどんな記念日なのかメモを見ながら、その日にまつわる曲について、独断と偏見ですが書くことにある種の緊張があって、充実した毎日を送ってこれました。ところが今回の管理画面のリニューアルについては、詳しい楽天の意図説明がほとんどないままに、突然としか言い様のない改悪された画面を見て驚き、これまで続けて来れた「緊張感」がぷっつりと途切れてしまったような感じでいます。書きたい音楽・曲・演奏などまだまだありますが現在はとても書く気が起こりません。 もうしばらくお待ち下さい。 私もまだ楽天のこれからの出方を静観しています。 その出方次第で楽天を撤退するかもしれません。 楽天の意図がリンクスを増やすことだけにある今回のリニューアルであるならば、リンクを貼っていただいている方々には申し訳ありませんが、もっと使い勝手のいい場所を探してみたいと思います。
2007年01月22日
コメント(10)
-
管理画面の最悪リニューアルを元に戻して!
あちらこちらのブログで今回の管理画面のリニューアルに不満・抗議が続出しています。 楽天さん、これを真摯に受け止めてください。 ほんとに使いづらい管理画面なんですから。私のページをリンクしていただいている方が75名おられます。 その方々が新しい記事を書いても見落とす可能性大なんです。 全てをチェックしないといけません。それにコメントを書いていただいても、以前ならどなたが書かれたかをすぐにわかるようになっていましたが、このリニューアルではとてもわかりづらいです。楽天から撤退しようかと真剣に考えています。 どなたもリンクを貼っておられなければ、即撤退していると思います。 どうにか踏み止まっているのは75名もおられるからなんです。 私の独断と偏見のクラシック音楽と四季の花画像の更新を楽しみにしておられる方々のことを考えると、簡単に撤退はできません。お願いすることは、ただ一つです。 元の管理画面に戻して下さい。 そうしてリニューアルのことをじっくりと検討して下さい。 あまりにも性急過ぎてはいませんか?それとも無料ブログだから問答無用なんでしょうか?メンタル面で、更新の意欲を失くしています。
2007年01月21日
コメント(19)
-

素心蝋梅(ソシンロウバイ)
ともの『今日の一花』 素心蝋梅冬の代表花の一つです。 今を盛りと咲いています。撮影地 大阪府和泉市 2007年01月15日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1855年 誕生 エルネスト・ショーソン(作曲家)1891年 誕生 ミッシャ・エルマン(ヴァイオリン奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『音楽記事』は休載します。
2007年01月20日
コメント(4)
-
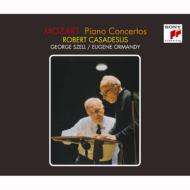
カサドジュのピアノ/はこべ
『今日のクラシック音楽』 モーツアルトのピアノ協奏曲選集未聴CDを聴くー 第6弾ロベール・カサドジュ(1889-1972)はフランス生れのピアニストで、私が最初にレコードで聴いたピアニストでした。 自分で買った2枚目のLPがカサドジュの独奏ピアノ、ミトロプーロス指揮 ニューヨークフィルとのベートーベンのピアノ協奏曲第5番「皇帝」でした。 1958年のことでした。 25cmのモノラル録音で繰り返し聴いたために、すぐに盤が擦り切れてしまいました。 それでも長年聴いていた「皇帝」のバイブルのような演奏でした。以来カサドジュは私にとって忘れられないピアニストになっています。 時が流れて10年後にカサドジュは来日公演を行いました。 1968年の4月のことで東京厚生年金会館でのコンサートでした。イシュトヴァン・ケルテス指揮、日本フィルハーモニー交響楽団との共演でした。 その時のプログラムはバルトークの「ハーリ・ヤーノシュ」、ドヴォルザークの「新世界より」、そしてあのピアノ協奏曲第5番「皇帝」でした。「皇帝」冒頭の華々しいピアノのカデンツァが会場を流れた時には、不覚にも涙が頬を伝いました。 あのLPでさんざん聴き込んだ清澄な音色と全く変わりのない同じ音に、懐かしさと感動に包まれていました。それから4年後に彼は他界しました。 レコード会社が追悼として彼の録音盤LPが多数再発売された中に、モーツアルトのピアノ協奏曲が2枚組みでりりースされていたのを購入して、彼のピアノ演奏をしのんでいました。 しかし、そのLPはもう知人の収集家に譲ってしまいました。 LPプレーヤー修理不能となりCDにかえましたから、それ以来カサドジュをしのぶ演奏はCDに復刻された「皇帝」とフランチェスカッティ(Vn)との共演の「クロイツェル」「春」のみでした。 ヴァイオリン・ソナタには大いに不満が残り、聴いていただく方がいればと思い放出しました。そこへ昨年ソニーからそのモーツアルトの録音盤が3枚組の廉価で再発売されたので購入しました。1枚目冒頭の曲が第21番ハ長調で、スピーカーから流れ来るカサドジュの懐かしい音色に、40年の歳月が一気にタイム・スリップしたような錯覚を覚えました。収録されているのはカサドジュが米コロンビアに残したモーツアルトの協奏曲を全て網羅しています。1. 第21番ハ長調 K.4672. 第22番変ホ長調 K.4823. 第23番イ長調 K.4884. 第24番ハ短調 K.4915. 第26番ニ長調 K.5376. 第27番変ロ長調 K.5957. 2台のピアノのための協奏曲変ホ長調 K.365カサドジュのピアノの音色は、ごく自然に聴く者の心に入り込んでくるもので、技巧的なものを感じさせない清々しさがあり、透明な響きがとても心地よいのです。 しかし、強烈な個性に彩られた、例えばアルゲリッチのような激しさがあるわけもない、さり気ない表情で、洗練された美しさに自然体の演奏スタイルが感じられます。技巧的には今の若いピアニストの方がはるかに巧いピアニストがいますが、これほど「演奏」というものを感じさせない自然体の音色を紡ぎ出すピアニストは稀かもしれません。 カサドジュの音色を聴いていると息遣いというか、彼の心のうちが見えてくる、まるで純粋無垢にモーツアルトの音楽を奏でているように聴こえてきます。 聴き終わった時に「ありがとう」と言いたくなるような稀有なピアノの響きです。 自分の部屋にこういう響きが流れることに、無上の喜びと至福の時空を過ごせる嬉しさがこみ上げてくる素晴らしいカサドジュのピアノに感謝!このCDです。↓(SONY原盤 ソニーレコード SICC482-4 1959-1962年録音)3枚組で2940円という廉価盤です。ロベール・カサドジュ(ピアノ)ジョージ・セル指揮 コロンビア交響楽団ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1787年 初演 モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」1854年 初演 ヴェルディ オペラ「トロヴァトーレ」1884年 初演 マスネ オペラ「マノン」1909年 没 ハンス・ホッター(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の一花』 はこべ「はこべ」も早春から咲く野草花だと思っていましたが、もう近所の庭で咲いていました。 撮影地 大阪府和泉市 2007年01月18日
2007年01月19日
コメント(2)
-

ジャニーヌ・ヤンセンのヴァイオリン/ナズナ
『今日のクラシック音楽』 ジャニーヌ・ヤンセンのヴァイオリンに魅せられて未聴CDを聴くー第5弾昨日は未聴CDを聴いての感想記事は休みましたが、また今日から紹介の記事に戻ります。 第5弾はヤンセンの弾くヴァイオリン協奏曲2曲です。 ジャニーヌ・ヤンセンは1978年にオランダで生まれた、今年29歳になる女性ヴァイオリニストですが、今回私は初めて彼女の演奏をCDで聴きました。 昨年12月6日にリリースされた2枚目のCDで、メンデルスゾーンとブルッフの協奏曲(第1番)が収録されています。メンデルスゾーンから聴きましたが、冒頭の有名な美しい旋律から魅せられました。 まるでヴァイオリンに魂が込められているかのように、すすり泣くかのように旋律が歌われています。 彼女のヴァイオリンは、まるで血の通った人間の心の叫びのように聴く者の心の琴線に触れてきます。カデンツァでの「歌」はヤンセンの心の内を透けて見せてくれるような、温かさとぬくもりと情熱を感じさせます。 第2楽章の「アンダンテ」でもたっぷりとした間合いで、抒情的に歌いこまれており、こちらの心がヴァイオリンにぴったりと寄り添って行くのを感じるほどです。終楽章での速いパッセージでも形振りかまわずという演奏ではなくて、ハッとさせられるような間合いを取りながら、ヴィヴィッドさを失わずに高揚していく様も圧巻です。ブルッフでも同じことが言えます。 思い切りロマンティックに旋律を歌わせており、この聴きなれた協奏曲が初めて聴く様な錯覚をおこさせるほどの、ヴァイオリン独特のたっぷりとした旋律の美しさを伝えてきます。私がよく使う表現ですが、ヤンセンの演奏のどこを切っても真っ赤な血が流れてくるような、決して技巧だけの無機的な「歌」ではなくて、彼女の心の鏡を照らすような有機的な音色がいっぱい詰まった素晴らしい演奏です。しかもこの演奏が全て演奏会でのライブ録音であることに驚いています。ジャニーヌ・ヤンセンが2004年に来日して大阪でも演奏会を開いたそうですが、まったく知らなくてえらい損をした気分になっています。 今度大阪に来る時は何としてでも聴きに行かねばと思っています。彼女と数多くの共演をしたヴラディーミル・アシュケナージはこう語っています。「私がこの2、30年の間に出会った中で、彼女は最も素晴らしく調和の取れた才能を持っていると思います。私の意見では、この若い女性は全てを持っています‐楽器に完璧に精通し、暖かさ、理解力、もったいぶらない態度、無類のコミュニケーション力。彼女との共演でチャイコフスキーのバイオリン・コンチェルトを指揮できて、私がどんなに楽しかったかを的確に表現できる言葉が見つかりません。」このCDです。↓ジャニーヌ・ヤンセン(Vn)リッカルド・シャイー指揮 ライプチッヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7178 2006年9月ライブ録音)収録曲1. メンデルスゾーン ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品632. ブルッフ 「ヴィオラと管弦楽のためのロマンチェ」3. ブルッフ ヴァイオリン協奏曲第1番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1835年 誕生 セザール・キュイ(作曲家)1841年 誕生 アレクシス=エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1874年 初演 ラロ ヴァイオリン協奏曲第1番1943年 初演 プロコフィエフ ピアノソナタ 第7番1946年 誕生 カティア・リッチャレッリ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ナズナナズナは春に咲く野草花と思い込んでいましたが、もう咲いていました。 調べてみると1月から咲く花なんですね。 撮影地 大阪府和泉市 2000年01月17日 油菜科 ナズナ属開花時期 1月中旬~5月中旬別名 ペンペン草
2007年01月18日
コメント(0)
-
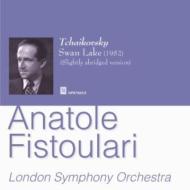
初めて買ったLP盤/シンピジウム
『
2007年01月17日
コメント(8)
-

ハープの巨匠 サバレタ/寒咲き花菜
『今日のクラシック音楽』 サバレタ・プレイズ・バッハスペイン生まれのハープ奏者ニカノール・サバレタ(1907-1993)は、女性奏者の多いハープ演奏家の中でも男性奏者として異色の存在であったし、2度にわたる来日経験もあって日本でも人気のあったハープの第一人者でした。 今日の紹介CDはLP時代に聴きこんだ懐かしい演奏で、何年も会えなかった恋人に逢えたような喜びを感じています。 と言えば格好いいのですが、記憶からはほとんど消えていました。 スケールの大きなシンフォニックな音楽、ドラマティックなオペラ、渋い室内楽、華麗な器楽曲作品、敬虔な宗教音楽などを主に聴いてきて、ハープ音楽をあまり聴いていなかったことが一番大きな理由かもしれません。久しぶりに聴きましたサバレタの演奏に酔ってしまいました。 とても気品のある高貴な情緒で、音色は清澄で、実に透き通った音で楽しめます。 まるでスコアが透けて見えるかと思えるような透明な響きが、サバレタの大きな特徴でしょう。私が聴いていたのは、サバレタ自身の編曲によるこの大バッハの曲や、ヘンデルなどのハープ協奏曲という限られた作品でしたが、彼自身はバロック音楽から現代音楽までの幅広いレパートリーを演奏しており、ヒナステラ、ミヨー、ホヴァネス、ヴィラ=ロボスなどから献呈された作品も数多いのだそうです。更にサバレタの偉大さは編曲にもあります。 独奏フルートなど他の楽器のために書かれた音楽をハープ用に編曲するなど、ハープの演奏の可能性を広めたことでも大きな功績として評価を高めています。 このディスクに収録されている大バッハの作品もサバレタの編曲ですが、まるでバッハがハープのために書いたような音楽に仕上げており、しかも清澄で、透明感に溢れた演奏はバッハの原曲の素晴らしさを改めて感じさせる響きとなっています。 特に「パルティータ第2番」(原曲は無伴奏ヴァイオリン用)ではほぼ原曲通りに演奏しており、ハープの独特の分散和音やオクターヴ奏法によって、有名な「シャコンヌ」などもハープの魅力を見事に伝えています。まさに20世紀のハープの巨匠です。これもタワーレコードがヴィンテージ・コレクションとして昨年12月に、1000円の廉価盤としてリリースした注目の名演奏です。このCDです。↓ (グラモフォン原盤 タワーレコード・ヴィンテージ・コレクション 1972年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1891年 没 レオ・ドリーブ(作曲家)1928年 誕生 ピラール・ローレンガー(ソプラノ)1929年 誕生 マリリン・ホーン(ソプラノ)1957年 没 アルトゥーロ・トスカニーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒咲き花菜 撮影地 大阪市立長居植物園 2007年01月10日
2007年01月16日
コメント(8)
-

アニア・タウアーのチェロ/アンスリウム
『今日のクラシック音楽』 アニア・タウアーのチェロアリア・タウアー(1945-1973)というドイツ生れのチェロ奏者をご存知の方は、よほどクラシック音楽に詳しい方だと思います。 私はクラシック音楽を聴き初めて今年で52年目になりますが、このチェリストのことは忘却の彼方に消えていました。 それもそのはず、彼女の演奏をFMで聴いたのが1回きりで、どんな演奏だったのかも覚えていません。1973年のある日、ドヴォルザークのチェロ協奏曲がFM放送で流れていました。 その頃のこの曲はシュタルケル、フルニエ、デュ・プレの3枚のLPで楽しんでいて、この放送で流れた時はさほど心に留めなかったのですが、解説だけは覚えていました。 美貌の若手女流チェロ奏者がドイツ・グラモフォンにわずか2枚のLPを残して、28歳という若さで自ら命を絶ったという説明でした。 この「28歳の若さで自ら命を絶った」ことだけが記憶に残っていました。 アニア・タウアーという名前は全く覚えていないし、演奏もどんなものだったかは、まるっきり記憶にはありません。ドイツ・グラモフォンに眠っていたテープを掘り起こしたのが「Tower Record」でした。 Towerはレーベル各社に眠る名盤と呼ばれている録音を復刻させて、「ヴィンテージ・コレクション」というシリーズで1000円という廉価でリリースしており、これまでにも様々な素晴らしい演奏を復刻しているのですが、このアニア・タウアーもそのうちの1枚で、昨年12月初旬にリリースされています。ドヴォルザークの協奏曲におけるタウアーのチェロは、女性とは思えぬほどに力強く弾かれています。 こう書くとデュ・プレを思い出しますが、デュ・プレのような激しい情熱ほどではないのですが、音色はとても艶っぽく、妖艶とまで言えそうな演奏が繰り広げています。とても艶やかな音色が第1楽章の独奏が入る部分から聴かれて、尋常でないチェロ奏者であることは最初のフレーズでわかります。 第2楽章の郷愁を誘うような旋律をとても丁寧に弾きながら、大地に根ざしたボヘミアの風土を部屋に運んでくるような美しさがあります。第3楽章でも同じで力強さに溢れて、しかも艶やかさを失わない音色に魅せられます。 1973年に聴いた時の印象の違いは、私の34年間の音楽を聴く経験の違いでしょうか? こんな素晴らしい演奏に心を奪われなかった未熟さかもしれません。いいディスクに廉価で出会えた喜びがこみ上げてきます。 こんな素晴らしい演奏をお蔵入りさせているグラモフォンは怠慢だと思いたくなります。 いつまでもベームやアルゲリッチなどの古い録音ばかりを、繰り返し再発売することもないと思うのですが。このCDです。 ↓アニヤ・タウアー(チェロ) ズデニック・マーツァル指揮 チェコフィルハーモニー (グラモフォン原盤 タワーレコード・ヴィンテージ PROA-62 1968年3月録音)収録曲1.ドヴォルザーク:チェロ協奏曲2.レーガー:無伴奏チェロ組曲第3番3.フランセ:チェロとピアノのための幻想曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1923年 初演 ピエルネ バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」1926年 没 エンリコ・トセリ(作曲家)1941年 初演 メシアン 「世の終わりのための四重奏曲」2006年 没 ヴィクトリア・デ・ロスアンヘルス(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 アンスリウムこれも長居植物園での撮影です。 撮影地 大阪市立長居植物園 2007年01月10日
2007年01月15日
コメント(0)
-
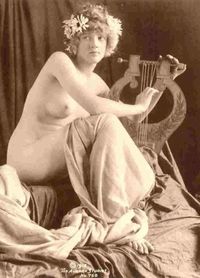
ヴィヴァルディ 「ラ・チェートラ」/胡蝶蘭
『今日のクラシック音楽』 ヴィヴァルディ作曲 協奏曲集「ラ・チェートラ」昨年12月20日にDENON CREST1000シリーズから、イタリア合奏団が演奏するヴィヴァルディ(1678-1714)が書いた独奏ヴァイオリンとの弦楽合奏による「協奏曲集 ラ・チェートラ 作品9」が廉価盤として再発売されました。 全12曲からなるヴァイオリン協奏曲集で1991年4月の録音盤。ヴィヴァルディと言えばクラシック音楽を大好きといかなくても、ヴァイオリン協奏曲「四季」(「和声と創意への試み」の中の一曲)は彼の代名詞となっているほどに超有名曲ですが、その「四季」と同じ様なスタイルで書かれているヴァイオリン協奏曲集です。ヴィヴァルディはイタリア・ヴェネツィアの慈善院女子音楽院で音楽の教鞭をとっていたことは有名な話ですが、この「ラ・チェートラ」はこの女子音楽院オーケストラのために書かれたと言われています。全12曲は急ー緩ー急のイタリア風スタイルで書かれていて、どの曲を聴いても部屋には「幸せな気分」を満たしてくれる音楽ばかりです。 速いテンポの楽章でも激しさはあまりなくて、愉悦に満ちた音楽となっています。ヴィヴァルディの「四季」や「調和の霊感」などに較べると音楽は小粒で、それがかえってイタリアの陽光を味わえる音楽かもしれません。「ラ・チェトーラ」という副題は楽器の「リラ(ライアー)」からとられているそうですが、「リラ」とは現在のハープのような楽器なのですが、「リラ」の起源は古く5000年前と言われており、様々な形に発展しており、「手回しヴァイオリン」と呼ばれる種類もあるそうです。 もしかしたらそういうところからヴィヴァルディが命名したのかも知れません。↓(女性が左手に持っているのが古代ギリシャで使われていたであろうという「リラ」です。 1913年の撮影画像だそうです)この音楽の響きと何ら関係なく何故この副題が付けられたのか、首をかしげたくなるようなタイトルで、この副題に気を取られずに聴けばいいと思います。このCDです。 イタリア合奏団↓ (DENON CREST1000 COCO70834-5 1991年4月録音)全12曲が2枚組CDに収録されており、価格は1,500円とお買い徳盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1900年 初演 プッチーニ オペラ「トスカ」1932年 初演 ラヴェル ピアノ協奏曲1949年 没 ホアキン・トゥリーナ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭今日も昨日と同じ胡蝶蘭ですが、色違いです。 撮影地 大阪市立長居植物園 2007年01月10日
2007年01月14日
コメント(4)
-

トスカニーニのステレオ録音/胡蝶蘭
『今日のクラシック音楽』 トスカニーニの最後の演奏会今日から昨年の10月から購入しました45組のCD・DVD、それに8月に紹介しました11組のディスクについて書いて行こうと思っています。 従来書いていましたその日に因む曲(初演など)や作曲家・演奏家の誕生や死亡日にちなむ記事は当分の間は休みます。その第1弾として「トスカニーニ・ファイナルコンサート」を採り上げました。アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957)は、私がクラシック音楽を聴き始めた頃には他界していましたが、フルトヴェングラー、ブルーノ・ワルターなどと共に絶大な人気のある指揮者でした。彼の演奏はドイツの比較的ゆったりとした、少しテンポの遅い重厚な伝統表現と異なっており、フルトヴェングラーに代表されるロマン的な表現を特徴とする演奏とは対極にあるスタイルでした。楽譜に忠実で、感情をあまり移し込まずに透明な響きで音楽を表現するタイプの指揮者でした。あるいは作品全体のバランスを重視した客観的な演奏が特徴でした。 その顕著な例がベートーベンやブラームスの全ての交響曲演奏、娘婿のホロヴィッツと共演したチャイコフスキーのピアノ協奏曲に刻印されており、まるでスコアが透けて見えるほどの透明な響きで表現されています。有名なエピソードがあります。 トスカニーニがアメリカでカリスマ的な存在で君臨していた頃に、50年の永きにわたってアムステルダム・コンセルトへボーの常任指揮者であったウイエルヘルム・メンゲルベルグがいました。 メンゲルベルグは実にロマン的表現の最たる指揮者で、バッハの「マタイ受難曲」などは「メンゲルベルグのマタイ」と言いたくなるほどの超個性的なロマンにあふれた演奏が残されている指揮者です。そのメンゲルベルグがベートーベンの直弟子から聞いた話として、ベートーベンの交響曲演奏の方法を滔々と語ったところ、トスカニーニはたった一言でこの話を締めくくりました。 「そんなことはスコアに書いてありますよ」と。しかし、トスカニーニの演奏は決して楽譜に忠実・機会的演奏ではありません。 歌謡的な表現のイタリア人演奏家らしいカンタービレの美しさを強調して、豊麗・豊穣な表現を得意としており、クライマックスの高揚感などは、トスカニーニ独特な主観・主張を明確に表す指揮者でした。しかもそこにトスカニーニの激しい情熱が吹き込まれています。 それはもう火を噴くかのような激しさで、リズムは深く突き刺すかのような表現なので、人間の持つ弱みなどを感じさせない強さがあります。 彼のベートーベン演奏に魅かれるのはその「火を噴く」かのような激しい熱さなんです。 それがトスカニーニの芸術を更に高めている理由だと思います。こうしたトスカニーニの特徴・美点が顕著に表われているのがオペラ演奏です。 特にヴェルディの「オテロ」「アイーダ」「椿姫」「仮面舞踏会」「ファルスッタフ」などに如実に表われています。 これらオペラについては後日改めて書くことにします。1954年4月4日にニューヨークのカーネギー・ホールでNBC交響楽団の定期演奏会が行われています。 これが彼の最後の演奏会となりました。 トスカニーニ87歳でした。この演奏会の模様がステレオ録音として遺されています。 プログラムは全てワーグナーのオペラ作品からでした。1)「ローエングリン」第1幕への前奏曲2)「ジーグフリード」森の囁き3)「神々のたそがれ」夜明けとジーグフリードのラインへの旅4)「タンホイザー」序曲とバッカナールの音楽5)「ニュールンベルグの名歌手」第1幕への前奏曲当然ステレオ録音黎明期の頃の音質ですから、貧弱ではありますが従来のモノラル録音で遺されているトスカニーニの音質とは違って、音場は広く、弦等も深い音として刻み込まれています。演奏は上に書いたトスカニーニの表現の特徴がすべて描き出された、87歳とは思えない激しく・熱い情熱に満ちたトスカニーニ芸術を味わえる最良のディスクだと推奨できます。このCDです。(Music & Artsレーベル CD-3008 1954年ライブ録音 USA輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1864年 没 スティーヴン・フォスター(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭撮影地 大阪市立長居植物園 2007年01月10日
2007年01月13日
コメント(4)
-
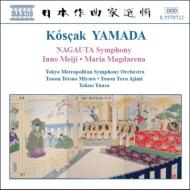
未聴のCD & DVDを前にして・・・・/水仙
『今日のクラシック音楽』 未聴のCDとDVDを前にしていつの間にたまってしまったのか私の前にまだ聴いていないCDとDVDが45組あります。 その中にはカイルベルトが指揮した1955年のバイロイト音楽祭のステレオ・ライブ録音の、ワーグナーの「ニーベルングの指環」4部作やフリードリッヒ・グルダのベートーベン・ピアノソナタ全曲及び協奏曲全曲という12枚組CDがあります。 ジャンル別ではオペラ・声楽が25組もあるのが大変です。 オペラは何しろ長時間かかる曲ですから全部聴き通すだけも相当の日数がかかります。 それでもまだ予約発注しているオペラCDが今月末に届きます。今年はその日の記念日に関係する曲や作曲家・演奏家の記事は後回しにして、これらの未聴ディスクを毎日紹介していこうと思っています。 となるとよほど集中して聴かないと記事は書けませんから、自分にとっても1枚、1枚を丁寧に聴く機会にもなります。2006年8月4日の日記に書きました11組どころではありません。 8月4日に書きましたディスクも含めて紹介するつもりです。昨年この日記で音楽の聴き方が昔と較べて変わってしまったと嘆きましたが、この45組+11組の紹介記事を書くことで、もう一度聴き方を昔のように集中して聴けたら、と思っています。明日の日記からその紹介記事を書くことにします。 下記はそれらディスクの例です。山田耕作 「長唄交響曲」他ローザンド 「ロマンティック協奏曲集」ウィスペルウェイ ベートーベン・チェロソナタ全集ジャニーヌ・ヤンセンのメンデルスゾーン/ブルッフ Vn協奏曲ショスタコービチ オペラ「ムチェンスク郡のマクベス夫人」(DVD)これらはほんの一例ですが、順不同で紹介していきます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1876年 誕生 ヴォルフ=フェラーリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 水仙1月10日に長居植物園で撮影した水仙です。 撮影地 大阪市立長居植物園 2007年1月10日
2007年01月12日
コメント(10)
-
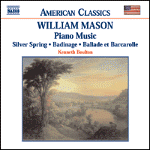
メイソン 「銀の泉」/山茶花(さざんか)
『今日のクラシック音楽』 メイソン作曲 「銀の泉」作品6ウイリアム・メイソン(1829-1908)はアメリカの作曲家で、シューベルト(1797-1828)の亡くなった翌年に生まれ、マーラーやドヴォルザークの時代に生きた、アメリカのクラシック音楽の黎明期の人という位置づけのできる作曲家です。解説書によればフランツ・リストにもピアノの修行を受けたこともあって、メイソンのピアノ音楽は華麗な彩りのある、どこか19世紀のサロン風の音楽とピアノ響きです。メイソンは一体何曲の音楽を書き残しているのか知りませんが、この「銀の泉」は作品番号6ですから初期の作品となるのでしょうか?6分足らずの短い曲ですが、リスト風のパッセージが顕れたりする実に美しいピアノの旋律・音楽を楽しめる曲です。 ゆったりとした「たゆたさ」のある主旋律に、華麗に舞うアルペジオとのバランスが絶妙で、聴く者の心を癒してくれる、まさに「サロン風音楽」の極上の響きを味わうことの出来るピアノ音楽の佳品です。その他「詩的な夢」作品24も同じような音楽で、ゆったりと奏でられるピアノは「銀の泉」と共に、冬の寒い午後にブレンドされた珈琲と共に味合われたらいかがでしょうか?このCDです。 「メイソン ピアノ音楽集」 ケネス・ボールトン(ピアノ)↓(Naxosレーベル 8.559142 2001年録音 輸入盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1801年 没 ドメニコ・チマローザ(作曲家)1865年 誕生 クリスティアン・シンディング(作曲家)1940年 初演 プロコフィエフ バレエ音楽「ロメオとジュリエット」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 山茶花(さざんか)昨日(1月10日)大阪市内の長居植物園に出かけて冬の花を探して撮影をおこなってきましたが、やはりこの時期は花が少ないですね。 山茶花・椿・水仙くらいのものでした。 椿はまだ開花が始まって間もなく、ほとんどが蕾でした。 山茶花は見頃でしたが、肝心の撮影で大失敗でした。撮った写真のほとんがピントが甘くここに掲載できる画像ではないのが残念でした。 比較的ましなものを掲載しておきます。撮影地 大阪市立長居植物園 2007年01月10日
2007年01月11日
コメント(2)
-
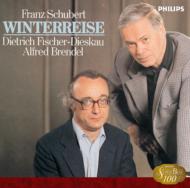
シューベルト 歌曲集「冬の旅」/寒あやめ
『今日のクラシック音楽』 シューベルト作曲 歌曲集「冬の旅」1828年1月10日、フランツ・シューベルト(1797-1828)が作曲しました歌曲集「冬の旅」前半の12曲が、ウイーンの楽友協会ホールで初演されています。 シューベルトは、31歳という短い生涯で9曲の交響曲、14曲の弦楽四重奏曲、2曲のピアノ三重奏曲、21曲のピアノソナタや多くのミサ曲、合唱曲やオペラなどを書残していますが、彼の名が音楽史上で語られるときに必ず言われるのは「歌曲王」という言葉です。 600曲を超える歌曲を書いたと言われているほど、数多くの歌曲を作曲しています。声楽でも、オペラは登場人物の数だけの歌手、合唱団、オーケストラ、指揮者、演出家、舞台美術・小道具・衣装などを揃えて公演を行なう大プロジェクトとなるのが普通です(コンサート形式は別として)。 そして、これらの大人数によって物語が進められていきます。それに較べると歌曲の世界は、オーケストラ伴奏のある音楽は別として、コンサート・ホールででもピアノ1台と伴奏者(譜面めくりの人1名)と歌手1人という簡素な仕立ての世界で、1曲によって物語が終ってしまうという音楽空間です。 そして深い精神性とそれを心象的に表す光景、風景の世界で人間の幸せ、楽しさ、悲しみ、辛さ、苦しみ、嘆き、喜びなどがわずか数分間という短い曲の中で表現されています。 それは、ドイツの詩人ゲーテやハイネ、ミューラーといった詩人の作った「詩」に歌と伴奏音楽を付けている世界だからです。 「詩」そのものを音楽で表現している世界だからです。そうした歌曲を「連作歌曲」としてシューベルトは、まづ最初に歌曲集「美しい水車小屋の娘」を作曲して、恋に破れた若い男の心理を見事に歌い上げました。今日採り上げました「冬の旅」もミューラーの詩による歌曲集として24曲から構成されていますが、前後の物語性は前作の「水車小屋の娘」のようにはなくて、詩そのものが単独に書かれているのですが、共通していることは失恋した一人の若い男があてのない旅に出て、その旅で経験する色々な出来事や心情を歌っている音楽です。 歌曲集全体としては、暗い、孤独と絶望感に包まれたような音楽ですが、シューベルト独特の抒情と旋律が聴く者の心を打つ歌曲集です。 「おやすみ」「春の夢」「菩提樹」などの、リサイタルで単独で採り上げられる有名曲の含まれた前半12曲が初演された日です。この初演は、亡きベートーベンの棺に泣きながら付き添ってから、まだ1年と経たない日で(ベートーベンの命日は1827年3月29日)、この「冬の旅」初演から約11月後の1828年11月19日にシューベルトは、その短い、不遇な人生を閉じたのです。 この「冬の旅」最後の24曲目の「辻音楽師」は、寒風の中で村のはずれに立って、震えながらオルゴールを手で回しながら歌う老辻音楽師が描かれています。村のはずれに一人の筒琴弾きが立っていて、凍える指でいつまでも筒琴をかき鳴らす。氷の上を、裸足であちこちと歩き回りながら。しかし彼の小さな盆にはいつまでも銭が入らない。誰一人耳をかたむけず誰一人目をとめる者もなく。ただ犬だけがその老人のまわりで吠えたてる。すべてをなすがままに勝手にさせながら、老人は筒琴を奏でその音はいつまでも絶えずに続く。ふしぎな老人よ、お前と一緒に従いて行ってよいだろうか?私の歌にお前の筒琴のしらべを合わせてくれまいか? (訳 高崎保男)この「辻音楽師」に、貧困と不遇な人生を若くして閉じたシューベルトにダブらせてしまうのは、私だけでしょうか?愛聴盤 ディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウ(バリトン) アルフレード・ブレンデル(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCP7069 1985年録音 )この盤は現在では1000円の廉価盤として再発売されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1828年 初演 シューベルト 歌曲集「冬の旅」前半12曲1886年 初演 ブルックナー 「テ・デウム」1935年 生誕 シェリル・ミルンズ(バリトン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 寒あやめこれも旧画像です。撮影地 奈良県・石光寺 2005年1月19日
2007年01月10日
コメント(14)
-
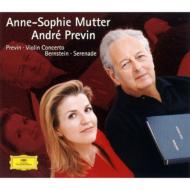
プレヴィン ヴァイオリン協奏曲/胡蝶蘭
『今日のクラシック音楽』 プレヴィン作曲 ヴァイオリン協奏曲アンドレ・プレヴィン(1930~)とレナード・バーンンスタイン(1918-1990)の二人は、共通点のたくさんある音楽家です。 どちらも20世紀の名指揮者、作曲家、ピアニストでもあり、オーケストラや室内楽でもその技量を発揮しており、アメリカではジャズの分野、映画音楽、そしてブロードウェイの舞台音楽と、非常に似た道程を歩き、優れた才能を発揮している音楽家です。そのプレヴィンが自作のヴァイオリン協奏曲とレナード・バーンスタイン作の「セレナード」(実質はヴァイオリン協奏曲)を愛妻のアンネ=ゾフィー・ムターと共演でCDをリリースしています。今日はその中からプレヴィン自作のヴァイオリン協奏曲を採り上げました。1999年の11月にドイツ旅行中に列車の乗り継ぎの際に、ニューヨーク在の友人に電話をかけたことが、このヴァイオリン協奏曲誕生のきっかけになったそうです。プレヴィンはボストン交響楽団から新作の委嘱を受けていたのですが、新作に悩んでいた頃で、その友人から「ドイツの列車に関係ある音楽を書いたらどうだい?」と電話で言われたそうです。プレヴィンは、この半分冗談のような友人のアドヴァイスで、子供の頃に親しんだドイツ民謡を取り入れた音楽を書くことを想い立ったそうです(彼はドイツの生まれです)。 もともとオーケストラ作品を書く予定だったのですが、ドイツの歌を口ずさんでいるうちに、ムターのヴァイオリンによる協奏曲を書こうと決めたそうです。そうしてこのヴァイオリン協奏曲は2001年10月に完成して、2002年3月14日にプレヴィン指揮ボストン交響楽団、独奏ヴィオリンがムターという共演で初演されたそうです。もともとムターのヴァイオリン独奏を念頭に置いて書かれている(プレヴィンはこの曲に”アンネ=ゾフィー”と副題を付けています)ためか、第1楽章冒頭からむせ返るような、下世話な比喩で言いますと、適度に熟れた女性の色香が纏わりつくような、どこか艶っぽく、官能的とさえ形容できそうなムターの美音で始まります。音楽はコルンゴルドの映画音楽のような、甘く、ロマンティックな薫りが全編に流れており、ムターがまるで情愛こめて弾いているかのように、美しく滴り落ちるような音色で聴かせてくれます。 3楽章構成で、第2楽章は始めから終わりまで瞑想的なムードに終始しており、ここでもプレヴィンの美しい旋律的な音楽とムターの奏でるヴァイオリンの美音を楽しめます。終楽章になってドイツの子供の歌が現れます。 「主題と変奏」と書かれており「夜汽車」という歌が取り入れられています(文部省唱歌として日本でも歌われていました)。 ここでもムターは音の一つ、一つを慈しむかのように奏でており、幻想的な情緒を醸し出しながら静かに曲を閉じていきます。20世紀のクラシック音楽としては、甘くロマンティックな映画音楽のような曲ですが、聴いていてとても居心地の良さを感じる、プレヴィンの新作音楽です。このCDです アンネ=ゾフィー・ムター(Vn)アンドレ・プレヴィン指揮 ボストン交響楽団↓ (ドイツ・グラモフォン 474500 2002年10月 ボストン録音 輸入盤)この曲の作曲・初演の経緯はCDの英文解説より要旨をまとめて書きました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1887年 初演 フランク 交響曲ニ短調1904年 初演 ドビッシー 「版画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 胡蝶蘭これも1年前の画像です。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年1月19日
2007年01月09日
コメント(2)
-
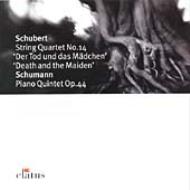
シューマン ピアノ五重奏曲/素心蝋梅
『今日のクラシック音楽』 シューマン作曲 ピアノ五重奏曲ロベルト・シューマン(1810-1856)は何故かある特定の音楽ジャンルの作品を一定期間に集中して書くという癖のようなものがあったようです。 苦難の末にクララ・シューマンと結婚した1840年には多くの歌曲を書いていて「歌の年」と呼ばれており、結婚前にはピアノ曲を集中して書いていて「ピアノの年」と呼ばれています。彼の室内楽作品もその例にもれず、ピアノ四重奏曲や弦楽四重奏曲などが1842年に集中して書かれており、「室内楽の年」と呼ばれています。その「室内楽の年」に書かれた作品にピアノ五重奏曲変ホ長調 作品44があります。 この曲は弦楽四重奏と独奏ピアノの組み合わせで演奏されますが、音楽史上でもこの組み合わせの成功例の最初の曲と言われています。ピアノが主導するかの如きに音楽が展開するのですが、弦楽器とのバランスが見事に保たれており、しかも旋律はロマンの影を色濃く落としていて、ピアノの美しい旋律が弦楽器と溶けあう様は実に見事な明暗を描き出している傑作です。4楽章構成で書かれており、どの楽章もロマンの香りがいっぱいに匂い立つ情緒に包まれています。 特に、第2楽章の引きずるような葬送行進曲風の音楽を好んで聴いています。 後に書かれたブラームスのピアノ五重奏曲共にロマン派室内楽作品を代表する名作だと思います。冬の寒い日に、熱い珈琲を味わいながら聴くのにぴったりの音楽です。1843年の今日(1月8日)、このピアノ五重奏曲が初演されています。愛聴盤 S.リヒテル(P) ボロディン弦楽四重奏団 (Eratusレーベル 0927.49002 1994年録音 海外盤)アルゲリッチと仲間たち (EMIレーベル 724355.7308 1994年オランダ・ライブ録音 海外盤)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 シューマン ピアノ五重奏曲1927年 初演 ベルク 「抒情組曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 素心蝋梅(ソシンロウバイ)これも昨年撮影の旧画像です。 撮影地 大阪府和泉市 2006年1月9日
2007年01月08日
コメント(4)
-
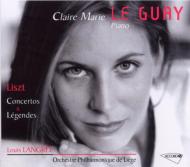
リスト ピアノ協奏曲第2番/椿(侘助)
『今日のクラシック音楽』 リスト作曲 ピアノ協奏曲第2番ピアノ協奏曲はよほど作曲が難しいのでしょうか、W.A.モーツアルト(1756-1791)が27曲書いた以外に、ピアノの名人で有名作曲家はそれほど数多く書き残していません。 モーツアルトは有り余る才能によって書き綴ったのか、お金のために書いたのかわかりませんが、とにかくモーツアルト以外には同じ作曲家によって数多く書かれていないのは不思議なことです。ベートーベン(1770-1827)も「傑作の森」と呼ばれている中期に第5番を書いた以降は作曲していませんし、あの「ピアノの詩人」とまで呼ばれるショパン(1810-1849)でさえも協奏曲は2曲書き残したのみです。 そのショパンと同じようにピアノの名人と言われるフランツ・リスト(1811-1886)も、あれほどのピアノ曲を書いていますが、協奏曲はショパンと同じように書き残したは2曲だけです。そのリストが書いた第2番はとても画期的な作品として音楽史上に燦然と輝く曲として現代でも演奏会のプログラムや録音などに採り上げられています。この第2番は、第1番と同様にリストがワイマールの宮廷指揮者を務めていた1849年頃の作品ですが、この頃はリストは比較的落ち着いて作曲活動を行っていた時代と言われています。協奏曲スタイルとしては伝統的な3楽章形式ではなくて、切れ目なく演奏される単一楽章形式となっていますが、音楽は6つの部分から構成されています。聴いてみて誰もが感じるのはピアノ付き交響詩とでも呼べるような内容の音楽が大きな特色となっています。 第1番が華麗に、輝かしい音色で書かれているの対して、この第2番はとても詩的な気分にあふれたロマンティックな情緒が濃厚で、幻想的な彩りに満ちている音楽となっています。しかも20分ほどの演奏時間の第1番と較べて規模もスケールも大きく変貌しており、演奏時間も第1番の2倍ほどかかる曲となっています。ロマン情緒に溢れた詩的なピアノの音色がとても美しく、聴く者の心を捉えて離さないロマン派ピアノ協奏曲の名作の一つです。そのピアノ協奏曲第2番が1857年の今日(1月7日)、リストの指揮、弟子のプロンザルトの独奏ピアノで初演されています。愛聴盤クレール=マリ・ルゲ(ピアノ) ルイ・ラングレー指揮 リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団 (ACCORD CLASSICS 427728 2002年7月録音 海外盤)透明でクリスタルな響きのピアノがとても美しい若い逸材の演奏に魅かれています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1842年 初演 ロッシーニ 「スターバト・マーテル」1857年 初演 リスト ピアノ協奏曲第2番1859年 誕生 クララ・ハスキル(ピアニスト)1899年 誕生 フランシス・プーランク(作曲家)1922年 誕生 ジャン=ピエール・ランパル(フルート奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿・侘助冬の花が少ないので今日も旧画像です。 1月8日(祝)には風が止んでおれば長居植物園に撮影に出かけようと思ってます。撮影地 大阪市立長居植物園 2006年1月
2007年01月07日
コメント(8)
-
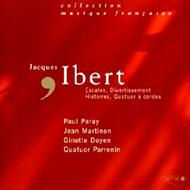
イベール 交響組曲「寄港地」/椿(白西王母)
『今日のクラシック音楽』 イベール作曲 交響組曲「寄港地」 ローマ大賞という、芸術を専攻する学生に対して(対象は30歳以下)フランス国家が授与した奨学金付留学制度で、1663年、ルイ14世によって創設され、1968年廃止されるまで継続した賞がありました。創設当初は建築、絵画、彫刻、版画の各賞が設けられ、王立アカデミーの審査により優秀者が選出されたのですが、1803年に改革されて音楽賞が追加されています。 受賞者はローマにあるフランス・アカデミーへの留学が許されるという特典がありました。1803年の改革によって芸術アカデミー会員による審査に変わってからは、疑惑・批判が生じたそうです。 その最初がベルリオーズ(1803-1869)でした。 彼が落選した時の音楽部門審査員は40名の審査員中わずか5名だったそうです。モーリス・ラヴェル(1875-1937)も5回も応募しましたが、一度も受賞していません。そんな「ローマ大賞」を、31歳でパリ音楽院に入学した晩生の作曲家ジャック・フランソワ・イベール(1880-1962)が入学後8年にして1919年にこの「ローマ大賞」を受賞しています。 ラヴェルと較べるといかにも皮肉な結果です。 ラヴェルに較べると現在演奏・録音の機会のある彼の作品と言えば、今日の話題曲である組曲「寄港地」と「フルート協奏曲」くらいでしょうか。作曲家として晩生であり、第一次世界大戦への従軍という期間もありながら、作曲をやめずにこの曲を書いたのです。 海軍時代に地中海を巡る体験から書かれた3曲で構成された組曲です。第1曲「ローマ~パレルモ」第2曲「チェニス~ネフタ」第3曲「ヴァレンシア」の3曲で、とても明るい気分に溢れた音楽です。全編が色彩豊かな彩りで地中海地域を、華麗なオーケストレーションで描いています。 第1曲「ローマ~パレルモ」におけるフルートやトランペット、第2曲「チェニす~ネフタ」におけるオーボエなどの管楽器がとても美しく響いており、「管楽器のフランス」の面目躍如たる作品です。1924年の今日(1月6日)、この「寄港地」がポール・パレー指揮 ラムルー管弦楽楽団によって初演されています。愛聴盤 ポール・パレー指揮 デトロイト交響楽団 (マーキュリー原盤 ACCORD Classics 1960年録音 海外盤)マーキュリーからリリースされていたPHCP20396と同じ音源です。 カラフルな面を抑えたしっとりとした演奏です。佐渡 裕指揮 ラムルー管弦楽団 (Naxosレーベル 8.554222 1996年4月録音)この曲の持つ色彩豊かな情緒を引き出した秀演です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1838年 誕生 マックス・ブルッフ(作曲家)1872年 誕生 アレクサンドル・スクリャービン(作曲家)1888年 初演 ドヴォルザーク ピアノ五重奏曲1924年 初演 プーランク バレエ音楽「雌鹿」1924年 初演 イベール 交響組曲「寄港地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(白西王母)これも昨年撮影した画像です。 近所の貸し畑の畦に1本だけ咲いている椿で、今年も撮影に行ったのですがいつも傷みがひどくて写真にならないので、旧画像を掲載しておきます。撮影地 大阪府和泉市 2006年1月18日
2007年01月06日
コメント(12)
-

みかんの高糖度/花月(金のなる木)
昨日(1月4日)の産経新聞の記事(大阪版)に大阪・千早赤阪村の農家が高糖度のみかんの栽培に成功したことが報じられていました。 みかんが甘いと評される程度は「糖度値」で表示されています。先日うちも歳暮で一箱のみかんをただきましたが、これがとても甘いのです。 私は極端に酸っぱいみかんは敬遠しますが、甘さだけのみかんも好きではありません。 この記事によると甘いといわれるみかんの最高糖度は11~12くらいの値そうです。私が口にしたみかんの糖度は11~12くらいだと思います。 それでも、もう口にするのさえ嫌なくらいに甘いみかんでした。 甘さばかり酸っぱさがないみかんでした。今日の記事の高糖度は何と20だそうです。 これだけの高い糖度を得るには、水を吸収し過ぎない工夫が必要だそうですが、それでも過去には16.3だったそうです。 この高い糖度をギネスブックに申請して「糖度世界一」の認定をもらうもくろみで、それを大阪のみかんは甘いをアッピールするそうです。そんな甘いみかんはごめんだと記事を読みながら思っていました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1920年 誕生 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェロ(ピアニスト)1931年 誕生 アルフレード・ブレンデル(ピアニスト)1974年 没 レフ・オボーリン(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 (花月)金のなる木町内のおうちの庭でもう「金のなる木」が花をつけていました。 撮影地 大阪府和泉市 2007年01月04日 弁慶草(べんけいそう)科 クラッスラ属 南アフリカ原産 開花時期は12月中旬から4月中旬 12月から咲くとは聞いていますが、近所やうちの庭で開花する時期が毎年3月頃なので、早い開花だなと思って撮らせてもらいました。
2007年01月05日
コメント(12)
-
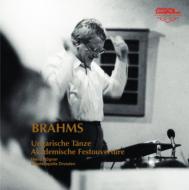
ブラームス 笑う序曲/椿(小春)
『今日のクラシック音楽』 ブラームス作曲 「大学祝典序曲」高校生の頃に毎晩ラジオから流れる大学入試向け番組がありました。 旺文社提供の受験番組でした。 その番組のテーマ音楽がヨハネス・ブラームス(1833-1897)が書いた「大学祝典序曲」でした。 さあ、しっかり勉強して志望する大学へ入りましょうという番組提供者からの受験生へのメッセージだったのでしょう。ブラームスは序曲を2曲書いています。 どちらも47歳になる1880年に書かれており、この2つが全く性格の異なる音楽として書かれています。 ブラームス自身が「笑う序曲」と呼んだ「大学祝典序曲」、もう一つは「泣く序曲」と呼んだ「悲劇的序曲」です。「大学祝典序曲」の作曲は、ブラームスにドイツ・プレスラウ大学から名誉哲学博士号を授けられた返礼として書かれた作品です。 この曲はブラームスにしては珍しい、彼が「笑う序曲」と呼んだ意味がわかるほど陽気な気分に溢れた、明るい屈託のない音楽です。曲はブラームス自身が学生時代に歌った、また現在でも歌われている学生歌から選んで序曲の基幹として使っています。 それらがこの曲の気分を陽気に、明るくしているのでしょう。 オペレッタのような楽しい音楽に仕上げられています。1881年の今日(1月4日)、この「大学祝典序曲」がウイーンのコンチェルトハウスで初演されています。愛聴盤 ハインツ・レーグナー指揮 シュターツカペレ・ドレスデン(ドイツ・シャルプラッテン原盤 キング・インターナショナル KICC9415 1973年録音)この盤を聴いてはいませんが、廃盤となっています徳間音楽工業がリリースしていました旧盤を聴いています。 音源は同じです。 このディスクはブラームスのハンガリー舞曲全集とのカップリングです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1710年 誕生 ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ1881年 初演 ブラームス 「大学祝典」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿(小春)これも古い蔵出し画像です。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月12日
2007年01月04日
コメント(4)
-
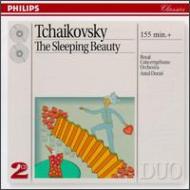
チャイコフスキー 「眠りの森の美女」/勧進帳/椿
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 バレエ音楽「眠りの森の美女」チャイコフスキーは、その生涯で交響曲を6曲、協奏曲ではピアノやヴァイオリンなど、それに室内楽作品、管弦楽曲、オペラ、歌曲など数多くの作品を書残していますが、バレエ音楽でも素晴らしい作品を書いています。 所謂「3大バレエ音楽」と呼ばれているもので「白鳥の湖」「くるみ割り人形」そして今日、話題の「眠りの森の美女」の3つです。1960年頃だったと記憶していますが、ウォルト・ディズニーが製作したアニメ「眠りの森の美女」が日本で上映されました。 ディズニー独特の、前作「白雪姫」同様の人物の表情豊かな楽しいアニメでした。 音楽は勿論このバレエ音楽でした。 チャイコフスキーの流麗な音楽が全編に流れる素晴らしいアニメ映画でした。 私の記憶ではこの曲を聴いた最初の機会がこの映画でした。 物語はフランスの童話作家ペローが書いた有名な物語で、17世紀ごろの話で、国王に女児が生まれてオーロラ姫と名付けられ盛大な宴会が開かれますが、邪悪な妖精カラボスが招待されなかったのを恨みに思い、オーロラ姫に呪いをかけますが、「リラの精」が現れて「姫は100年間眠るだけ」だと言って皆を安心させます。 そして国王や家来にも眠りにつかせる魔法をかけます。邪悪な妖精カラボスの呪い通りに16歳になった姫が紡錘で指を指して眠りにつきますが、「リラの精」が100年後に狩りに来ていたデジレ王子を誘って城に入らせて、姫を眠りから目覚めさせるという話です。全曲で3時間ほどかかる大曲で、他の2曲「白鳥の湖」「くるみ割り人形」などに較べると、規模が大きく、シンフォニックな響きで、華麗・流麗な音楽が全編に流れています。「序奏とリラの精」「バラのアダージョ」「パノラマ」「ワルツ」など聴きどころの音楽がいっぱいの、チャイコフスキー独特の美しい旋律にあふれたバレエ音楽です。1890年の今日(1月3日)、このバレエ音楽「眠りの森の美女」が旧ロシアのペテルブルグ・マリンスキー劇場で初演されています。愛聴盤 アンタル・ドラテイ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団(Philipsレーベル 466166 1979-81年録音 輸入盤)このCDは2枚組みの全曲盤で、華麗で流麗なコンセルトへボウ管弦楽団の演奏がこのバレエ音楽の魅力をいっぱいに引き出して聴かせてくれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 ドニゼッティ オペラ「ドン・パスクヮーレ」1890年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『歌舞伎十八番の内 勧進帳』昨夜はNHK教育TVで東京と大阪の歌舞伎を生中継で「新春大歌舞伎」を放映していました。 この放送の目玉は何と言っても現在大阪松竹座で興行されている、歌舞伎十八番「勧進帳」でした。武蔵坊弁慶 市川団十郎源 義経 坂田藤十郎富樫 市川海老三歌舞伎の歴史の中でも藤十郎と団十郎が同じ舞台に立ったという記録がなくて、初めての顔合わせという魅力的なキャストの正月興行。 昨年から何かと話題になった舞台です。 いい席はほとんど売り切れの状態で、何とかNHKで放映してくれないかと願っていると正月2日のお年玉でした。かすかな記憶ですが、多分4歳~5歳くらいだったと思います。 歌舞伎好きの祖母に連れられてよく歌舞伎座へ行きました。 家に帰ってからは歌舞伎の真似をしていたそうです。 自分の記憶にあるのは片足あげてトントンと歩いて「勧進帳」弁慶の真似をしていたことを覚えています。さすがに団十郎の弁慶。 荒事の中で見せる「見得」を切る姿は圧巻。 団十郎の息子、海老三の富樫の「見得」と共に見せてくれました。そこへ関西歌舞伎得意の「柔」、藤十郎の義経。 「荒事」と「柔」の見事な組み合わせにTVの前でうっとりと見とれていました。最後は花道を下がる弁慶の「六法」。 さすが団十郎。 客席の呼吸を見ながらの最後の「見得」。 「成田屋!」と声をかけたくなる瞬間です。観終わったあと、やっぱり松竹座で観たいと思いました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿これも古い写真からの蔵出し画像です。撮影地 大阪市長居植物園 2005年3月
2007年01月03日
コメント(2)
-

サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番
『今日のクラシック音楽』 サン=サーンス作曲 ヴァイオリン協奏曲第3番サン=サーンスは、フランクやフォーレなどと近代フランス音楽を確立した作曲家で、交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽、それにオペラも手がけた多才な人でした。 ピアノの演奏家としても活躍したらしくて協奏曲のうち半分の5曲がピアノ協奏曲が書かれています。またヴァイオリンでも優れた作品を残しています。 「ハバネラ」「序奏とロンド・カプリチオーソ」などがそうです。 これらの2曲のヴァイオリンのための作品と並んで「ヴァイオリン協奏曲第3番」がつとに有名です。 サン=サーンスは3曲のヴァイオリン協奏曲を書いていますが、あとの2曲はほとんど演奏されないでこの第3番のみが取り上げられています。旋律がとても美しく、全体の構成もすぐれており、第1楽章の開始からフランス風で、まるで春の午後の美しさを感じさせるような音楽です。 第2楽章は舟歌風の抒情が漂う詩的な、田園情緒のような色彩の美しい楽章です。 私はこの曲では第1楽章の開始部分と第2楽章のヴァイオリンのフラジョネットがクラリネットと音を重ねていく部分にいつも魅かれています。1880年の今日(1月2日)、この協奏曲は名手サラサーテを得てパリで初演されています。初演日にちなんで今日はこの曲を聴こうと思っています。愛聴盤 チョン・キョン=ファ(Vn) ローレンス・ファスター指揮 ロンドン交響楽団 (DECCA原盤 ユニヴァーサル・ミュージック UCCD7031 1975年ロンドン録音)チョン・キョン=ファ若き日の録音ですが、流麗に紡ぎ出される美音としっかりとした構成、しっとりとした第2楽章のため息がこぼれるようなフラジョレット、LP以来の長年の愛聴盤です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 ワーグナー オペラ「さまよえるオランダ人」1881年 初演 サン=サーンス ヴァイオリン協奏曲第3番
2007年01月02日
コメント(4)
-
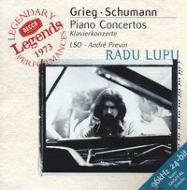
シューマン ピアノ協奏曲
『今日のクラシック音楽』 ロベルト・シューマン作曲 ピアノ協奏曲 イ短調 作品54謹賀新年新年明けましておめでとうございます。新年を迎えまして、昨年は多くの皆様方にご訪問いただきましたことをここに改めてお礼申し上げます。今年はたくさんの方々の「癒しの場」となれますように願いながら、「毎日日記の更新を続けること」を目標に、好きなクラシック音楽について、できる限り毎日書き綴けていけるように頑張っていく所存です。 四季折々の花の写真も出来る限るアップしてまいります。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。(追記)昨年の大晦日には多くの方々にコメントをいただいておりましたが、お寺と神社の大晦日行事で忙しくしておりましたので、いただきましたコメントの一つ、一つを読ませていただく充分な時間もなく、昨夜は行事終了で帰宅しましたのが午前3時となってしまいました。大晦日のお忙しい時間にもかかわらず、多数のかたにコメントをいただきましたことを、ここに改めてお礼を申し上げます。 ありがとうございました年末の風邪ひきが治ったとは言え大晦日は朝から元旦の午前3時までの奉仕活動と今朝のお寺での年々の勤行がこたえたのか、帰宅後は夕方4時半まで寝ていました。遅くなりましたが、これから大晦日にいただきましたコメントに返信させていただきます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シューマンは、ピアノ音楽をこよなく愛した人で、数多くのロマンの香り豊かなピアノ音楽を 書残しています。 ピアノ協奏曲はこの「イ短調」1曲だけが今日では演奏されています。 若い頃には習作として作曲を手がけていたそうですが、この「イ短調」は1841年に「ピアノと管弦楽のための幻想曲」として、1楽章構成で書かれていたのですが後年になって協奏曲の形式として2楽章、3楽章として書き綴って完成されたそうです。曲は華麗なピアノ・カデンツアで始まるヴィルトーゾ的な(巨匠風)序奏から始まり、ロマン溢れる美しい旋律で散りばめられており、ショパンの曲と共に「ロマン派」を代表する美しいピアノ協奏曲です。1846年今日(1月1日)、このピアノ協奏曲イ短調がドイツ・ライプチッヒのゲバントハウスで、愛妻クララ・シューマンのピアノ、メンデルスゾーンの指揮 ライプチッヒ・ゲンヴァントハウス管弦楽団によって初演されています。愛聴盤 ラド・ルプー(ピアノ) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA レーベル 466383 1973年録音 旧LONDON レーベル F28L-28012)「千人に一人のリリシスト」というとてつもない例えで賞賛されたラド・ルプーが遺した録音の1枚で、彼の感性を物語るしなやかな、豊かな美音が聴けるアナログ録音時代の遺産だと思います。 録音も非常に優秀で、見事にルプーのリリシズムの溢れるピアノの美しい音を表現しています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1846年 初演 シューマン ピアノ協奏曲1879年 初演 ブラームス ヴァイオリン協奏曲1894年 初演 ドボルザーク 弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」
2007年01月01日
コメント(12)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪菅原咲月(MC)『週刊乃木坂…
- (2025-11-25 04:48:40)
-







