2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
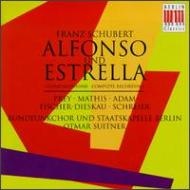
シューベルト オペラ「アルフォンソとエストレッサ」 / ギックリ腰の後遺症
『今日のクラシック音楽』 シューベルト作曲 オペラ「アルフォンソとエストレッサ」今日はフランツ・シューベルト(1797-1828)の誕生日です。 彼の亡くなった日の日記には有名な交響曲第8番「未完成」を紹介しましたので、今日は珍しい彼の書いたオペラ「アルフォンソとエストレッサ」について紹介します。シューベルトは交響曲やピアノ・ソナタ、弦楽四重奏曲などの室内楽、それに歌曲、合唱曲、ミサ曲などを残していますが、オペラ作曲家としての願望が強かったのか少なからず書いていたようです。 この「アルフォンソとエストレッサ」はその中でも有名なオペラで、時折ヨーロッパでは今でも上演されているようです。音楽は「歌曲王」と呼ばれているだけにアリアにシューベルトらしい美しい叙情があり、劇音楽「ロザムンデ」のように管弦楽も本格的なグランド・オペラを目指そうとしていたのか大掛かりな編成になっていて、3幕の長いオペラを聴き通すことが出来ますが(CDで3枚組)、物語が図式的で人物描写が個性的なところが付加されずに、ただ単なる「善」と「悪」の対比や、親同士が敵の息子と娘が恋人というありふれた類型になっていて、そこへ脚本が荒唐無稽で粗っぽく書かれているので、ご都合主義の典型のような物語となってしまっているのが欠点です。勿論、ヴェルディの「トロヴァトーレ」やプッチーニの「トゥーランドット」なども物語は荒唐無稽なんですが、音楽をそれをかばって余りあるオペラで、まさに声の饗宴とでも形容できるほどの出来栄えになっているオペラもあります。ところがこのオペラの音楽、とりわけアリアはイタリア・オペラのような訳にはいかず、美しい歌曲を聴くような趣きにとどまっていますので、その点が随分と物足りなさを感じます。それでも私がこのオペラを時折聴いていますのは、多分に中途半端な感じに終わるオペラにもかかわらず、それなりにシューベルトの「歌」を楽しめるオペラだからです。シューベルトのオペラとはどんな音楽かということに興味のある方にはお薦めの一曲です。愛聴盤 オットマール・スイトナー指揮 ベルリン国立歌劇場管弦楽団・合唱団(シャルプラッテン原盤 ベルリンクラシックス BC21562 1978年録音) 出演歌手の豪華さには驚きます。 ヘルマン・プライ(Br) エディット・マティス(S) テオ・アダム(B) フィッシャー=ディスカウ(Br) ペーター・スラオヤー(T)というこの録音当時(1977年)のドイツを代表するオペラ歌手の競演となっていて、このオペラの弱点を補うに十分なキャストです。『今日の音楽カレンダー』1879年 生誕 フランツ・シューベルト(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『ギックリ腰の後遺症』ギックリ腰の後遺症に苦しめられています。 ギックリそのものは治ったのですが、痛い期間中に腰をかばって無理な姿勢で座ったり、寝たりしていましたから、血流が悪くなって腰の周りやお尻の筋肉に絶えず痛みを感じる毎日でしたが、昨日からとうとう右足に肉離れのような症状が現れてきました。起き上がりや立ち上がりにはそれほど痛みがないのですが、立ってから右足を踏み出すのに大変な痛みが腿の後ろに走り、立ってから屈むときにも痛みがあります。 今朝、もう一度整形外科で診てもらいます。それにしても今年の初め(1月4日)からずーと痛みに悩まされています。 これは一体何なんだろうと思うこともあります。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月31日
コメント(10)
-
寒アヤメ(奈良・石光寺)
『寒アヤメ』昨日(29日)奈良県當麻町にある石光寺に行ってきました。 今が見ごろの「寒アヤメ」の撮影のためでした。近鉄南大阪線阿倍野から準急で35分。 二上神社口駅で下車、徒歩15分のところにあります。 駅員に道を尋ねると丁寧に書かれたプリント地図をくれました。 お寺までの道にはまるで小春日和のような、暖かい陽射しが降り注いでいて、右手に見えるニ上山まで農家と畑が続く田園情緒いっぱいの奈良県北葛城郡當麻町の一角に「石光寺」の門が見えてきました。寺の門を見上げますと二上山(ふたかみやま)雄岳と雌岳がすぐ目の前にありました。 大阪平野から見ている姿とはえらい違いだなと思いながら門をくぐる。 天智天皇の時代(630年頃)、不思議な光を放つ大石があり、その場所を掘ると弥勒三尊の石像が出てきたので「石光寺」と名付け、その名を、天智天皇に賜ったそうです。 平成3年に境内で発掘された石の弥勒菩薩像は、白鳳期の作。その顔と胴、足の一部が弥勒堂に安置されています。 そのまろやかな表情の顔は、笑っているようです。 逆三角形の堂々とした体形は、おおらかでもあり、力強く、石の丸彫りの像としては、日本最古の仏像だそうです。 石光寺は、中将姫伝説の寺です。 奈良時代、浮き世をはかなんだ中将姫が、観音菩薩の導きで、蓮の茎から糸を作り、それを染めて曼荼羅を織り上げたそうです。 境内には、糸を染めた「染の井」と、染めた糸を掛けて干したという「糸掛け桜」があります。 寺は別名「染寺」といい、この辺り一帯を「染野(しめ)」というそうです。 ひなびた山懐で、冬の境内には、寒牡丹がひそやかに咲いている、のが見ごろのことで3000株の牡丹が迎えてくれるのですが、昨日はもう見ごろが終わっていました。それでも寒牡丹に沿うように「寒アヤメ」がひっそりと咲いていました。 明るい冬の柔らかい陽射しがいっぱいの境内で、「もっと見てよ」と言わんばかりに咲き競っていました。 寺は今でも伝説の中に静かに息づいているような趣の中に佇んでいました。
2005年01月30日
コメント(16)
-
フリッツ・クライスラー
『今日のクラシック音楽』 フリッツ・クライスラーの音楽今日はヴァイオリニストで作曲家のフリッツ・クライスラーの命日です。 1962年1月29日に86歳の生涯を閉じています。彼はオーストリアが生んだ今世紀最高と言われているヴァイオリン奏者であり、またヴァイオリン曲の作曲家でした。子供のころクラシック音楽に興味を持って聴き始めた頃の大好きな音楽でした。 電蓄といわれた大きな蓄音機の前にちょこんと座り、まるでビクターレコードのトレードマークの犬のように、スピーカーから流れてくるクライスラーの「愛の喜び」「愛の悲しみ」「美しきロスマリン」などを毎日、毎日聴いていました。 これらの音楽が流れ出すと、まるで部屋にさわやかな風が吹き渡るかのような、清々しい気分になり、ヴァイオリンの奏でる美しい音色に、どうしてこんな曲を作れるのだろう、この人の頭の中はどうなっているんだろうとかを思い巡らすこともしばしばでした。中学1年生(1958年)の頃、大阪松竹座で「クリスマスコンサート」があり、朝比奈 隆と関西交響楽団(大阪フィルの前身)やヴァイオリンの辻 久子、大阪音楽大学コーラス部、五十嵐喜芳(テノール)や栗林義信(バリトン)、 それに私と同い年の映画の子役だった鰐淵晴子のヴァイオリンなどを聴いた音楽会でしたが、その時の辻久子のクライスラー作品の演奏に大感激していたのを忘れられません。 生演奏のヴァイオリンの美しい音色にうっとりとしている少年でした。 ところがそのコンサートが終わってから電車で帰宅するときに、座りたいために始発駅から普通電車に乗ったのですが、これが間違いのもとで今でも50分かかる距離なのに、当時はもっと時間がかかっていたと思います。 その電車の中で居眠りをして乗り越してしまい、また電車で引き返したのですが最寄駅の2つ手前までの電車で、それが最終でした。 仕方なしにその駅から歩いて帰宅しました。 冬の寒風の中、暗い夜道を歩くのはとても怖い体験だったのですが、クライスラーの曲を聴くたびにこのことが思い出されます。愛聴盤 クライスラー作品集 ローラ・ボベスコ(Vn) ウイルヘルム・ヘルヴィック(P)(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシック PHCP6020 1985年11月録音)『今日の音楽カレンダー』1862年 生誕 フレデリック・ディーリアス(作曲家)1905年 初演 マーラー 「亡き児をしのぶ歌」1962年 逝去 フリッツ・クライスラー(ヴァイオリニスト、作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月29日
コメント(10)
-
イッポリトフ=イワノフ 「コーカサスの風景」 / いい加減にしろよ、井川、上原!
『今日のクラシック音楽』 イッポリトフ=イワノフ作曲「コーカサスの風景」1935年1月28日、ロシアの作曲家イッポリトフ=イワノフ(1859-1935)が亡くなっています。正式な名前はミハイル・ミハイロヴィチ・イッポトリフ=イワノフ。 この人の名前が出るとすぐに思い浮かぶ音楽が組曲「コーカサスの風景」です。私はまだ「コーカサス」地方に行ったことはありませんが、写真で見ると美しい山々に囲まれた、自然がいっぱいの地方で、この音楽が流れてくるような気分になります。コーカサスは、「カフカス」と表記されています黒海とカスピ海に挟まれた地方のことで、ソ連崩壊後はアセルパイジャン、アルメニア、グルジアなどに分離されている地域で、民族紛争の絶えない地域です。 昔から長寿地帯と知られているところです。組曲は、「渓谷にて」 「村で」 「イスラム寺院にて」 「酋長の行進」 の4曲で、いずれもコーカサスの風を運んで来るような東洋風のエキゾチックな旋律いっぱいの音楽です。 4曲目の「酋長の行進」は特に有名で単独でコンサートのプログラムや録音に選ばれています。 軽快な異国情緒豊かな旋律が、だんだんと盛り上がっていく楽しい音楽です。 一度聴くと忘れられない親しみのある曲です。愛聴盤 デイビッド・ジンマン指揮 ボルティモア交響楽団 (TELARC レーベル CD-80378 1989-1994年録音 輸入盤)「ロシアン・スケッチ」というタイトルのCDで他にグリンカの序曲、チャイコフスキーの幻想的序曲やR.コルサコフの曲などを収録したロシア色満載の素晴らしい、テラーク特有の超優秀録音盤です。『今日の音楽カレンダー』1887年 生誕 アルトゥール・ルビンシュタイン(ピアニスト)1915年 初演 フォーレ 「レクィエム」1935年 逝去 イッポロトフ=イワノフ(作曲家)1947年 逝去 レイナルド・アーン(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『いい加減にしろよ、井川、上原!』最近プロ野球記事を見る、読むたびに非常に気分が悪くなる報道があります。 それは阪神タイガースの井川、読売ジャイアンツの上原のメジャー入り希望です。まだFA権のない二人ですから当然ポスティング(入札制度)でのメジャー移行となるのですが、両球団共その意思がないことを明言しています。 それでも二人はまだそれを要望しており契約更改に応じません。プロ野球改革については賛成します。 いい改革で運営すべきであると思います。 しかし、この二人は「わがまま」以外にありません。 「日本プロ野球機構」に就職した二人です。 そして阪神部、読売部に希望または指名で配属されて働いているのです。 その配属時に「統一契約書」にサインしているわけです。 このときに移籍についてFA権を認められています。 それ以外の本人希望による移籍は認められていません。この二人に希望を聞き入れるとプロ野球の球団と選手の秩序は乱れてしまいます。 球団に、プロ野球に貢献したイチローだから、オリックスはビジネスとしてポスティングでメジャーリーグに送り出しました。もっと国内でやることがあるでしょう、井川、上原両君! ごり押しはダメです。 そして、井川君、代理人交渉をやめなさい。 それほど行きたいなら、代理人交渉をやめて自分が出席して球団に訴えなさい。 もっと実績を積んでから訴えなさい、両選手!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月28日
コメント(10)
-
ラフマニノフ 交響曲第2番 / 「クラシック・イン」(小学館発行)
『今日のクラシック音楽』 セルゲイ・ラフマニノフ作曲 交響曲第2番ホ短調 作品271908年1月27日、セルゲイ・ラフマニノフ(1873-1943)が作曲しました交響曲第2番が旧ロシアのペテルブルグで初演されています。この曲の作曲の前に、ピアノ協奏曲第2番で大成功を収めたあとの交響曲で、全体に濃い、ロシア的なリリシズムに彩られています。 暗く、切ない、ロマン的な、まるで映画音楽のような美しい旋律が、全楽章を覆っている音楽です。特に、第3楽章の「アダージョ」は有名で、メランコリーに、甘く、濃厚なロシア的なロマンの香りが匂い立つような音楽で全編包まれた楽章です。映画広告風な言葉ですと「ハンカチをご用意下さい」楽章で、失恋した人、誰かを亡くした人、ブルーな気分の人、落ち込んでいる人は聴かない方がいいかも知れません。 それほどに聴く人の心に、甘美な寂寥感が入り込んでくるアダージョです。 ハンカチがやはり必要です。逆に愛する人と聴くときは、優しく懐に包まれて聴きたくなるような気分にさせる音楽です。愛聴盤 クルト・ザンテルリング指揮 フィルハーモニア管弦楽団(テルデック原盤 ワーナー・クラシックス WPCC-3121 1989年4月録音)『今日の音楽カレンダー』1756年 生誕 W.A.モーツアルト1823年 生誕 エドアール・ラロ(作曲家)1901年 逝去 ジュゼッペ・ヴェルディ(オペラ作曲家)1908年 初演 ラフマニノフ 交響曲第2番1958年 逝去 エーリッヒ・クライバー(指揮者 カルロスの父)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『クラシック・イン(小学館発行)』今日、本屋で小学館発行の「クラシック・イン」というCD1枚付きの雑誌が目にとまりました。 昨日が発売日のようで創刊号です。 隔週火曜日、毎月2回の発行予定で全50巻。バロック音楽からショスタコービチまでの音楽を網羅しています。 選曲は実に妥当で、これだけは聴いておきたいという曲、音楽がバロック音楽、管弦楽曲、協奏曲、交響曲、室内楽、器楽曲、歌曲、オペラ・アリア集といったラインナップです。雑誌はその刊の音楽、作曲家、演奏家について書かれており、これが簡潔ですが懇切・丁寧に書かれています。 例えば創刊号のモーツアルトについては、「モーツアルト~安らぎの芸術」「名曲のからくり~渡辺晋一郎」「作曲家ガイド」「楽曲解説」「演奏家について」「同曲の他のCDガイド」「行ってみたい音楽名所」「クラシックの基礎知識」それにコンサート情報があって応募すれば5組招待されるという豪華さ。 美麗グラビア紙に大判のカラー写真入り。音源は東芝EMI。 創刊号はモーツアルトのP協20番と26番に「トルコ行進曲」でダニエル・バレンボイムのピアノと指揮。 第2巻はヴィヴァルディの「四季」でキョン・チョン・ファの演奏。 第3回はピアノ名曲集でフジコ・へミングのピアノ。 以下続刊ではラトル指揮/ウイーンフィルのベートーベンの「英雄」。 チャイコフスキーのVn協奏曲が諏訪内晶子、ワーグナーやマーラーがテンシュテット/ベルリンフィル、シューベルトの「未完成」「グレイト」がカラヤン、グリーグ/シューマンのP協がリヒテル/マタチッチといった名演奏の録音がずらり。これで価格が980円なんです(創刊号のみ特価490円)。 今からCDを買い集める人には素晴らしいコレクションとなると思います。 書店に置いてある現品で記事の内容、続刊内容など立ち読みで見られますから、確認して購入できます。私も買いそびれているCDがこの中にありますので、そのお目当てが発売された時に買おうと思っています(マリス・ヤンソンス指揮オスローフィルの「展覧会の絵」)。お薦めのCD付雑誌です。 ネット検索はここからどうぞクラシックイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月27日
コメント(16)
-

ジャクリーヌ・デュ・プレ / 私の探しもの(追記)
『今日のクラシック音楽』 ジャクリーヌ・デュ・プレ1945年1月26日、不世出の女流チェロ奏者のジャクリーヌ・デュ・プレ(1945-1987)が生まれています。デュ・プレは、イギリスが生んだチェロ奏者の最高の一人です。 幼少の頃からチェロを習いはじめ、その音楽的才能はすぐさま開花して、カザルス、トルトゥリエ、ロストロポーヴィッチなどの今世紀最高のチェリストたちに師事することによって、その才能はますます磨き上げられていきました。彼女は演奏家としてのデビューは16歳でした。 そのときのロンドンの聴衆は、天才少女の演奏を熱狂的な拍手で迎えられたそうです。私はデュ・プレの演奏したCDを数枚持っていますが、古典音楽からエルガーまで幅広い音楽を、ほとばしるような熱気と情熱で演奏しているのが伝わってきます。 演奏家は音楽に没頭して、作品と一体になってこそ聴く人を感動させてくれます。彼女はまるで我を忘れて音楽に没入して、音楽そのものが彼女に乗り移ったかのような気迫と熱気を感じさせる演奏家でした。華々しいデビュー後の22歳の時には、ピアニストで現在は指揮者でもあるダニエル・バレンボイムと結婚しました。 幸せの絶頂にいた頃だったと思います。 輝くばかりの未来が開けているような時期だったと想像されます。 しかし1971年に突然の不幸がデュ・プレを襲います。 多発性脳脊髄硬化症という不治の難病によって、彼女は引退を余儀なくされてしまったのです。 わずか10年間の演奏活動でした。 バレンボイムや、チェリビダッケ、バルビローリ、ボールトなどの指揮者との協奏曲録音や、バレンボイム、ズーカーマンとのピアノ三重奏曲、はたまたルービンシュタイン、パールマンとの室内楽トリオの演奏など、まさにばら色の演奏活動であったことは容易に想像されますが、わずか10年でその舞台から降りることを余儀なくされました。ほとんど寝たきりの日々を送るデュ・プレ。 けれど彼女の音楽への情熱は冷めることはなく、後進の音楽家の教育活動に専念するようになったのですが、1987年、20世紀の財産ともいえる素晴らしい演奏を残し、42年の生涯を閉じたのでした。愛聴盤 (1) ブラームス チェロ・ソナタ 全2曲 (東芝EMI TOCE-11574/5 1967年-1971年録音)(2) ベートーベン チェロ・ソナタ 全5曲 (EMI原盤 東芝EMI TOCE13587 1968年ライブ録音)(3) 協奏曲集(EMIレーベル 5673412 1965-70年録音 海外盤)ハイドン、ボッケリーニ、シューマン、サン=サーンス、ドヴォルザーク、エルガー、ディーリアス、R.シュトラウスなどの協奏曲を5枚に収めた2400円という廉価盤です。『今日の音楽カレンダー』1790年 初演 モーツアルト オペラ「コジ・ファン・トゥッテ」1882年 初演 ボロディン 弦楽四重奏曲第2番1911年 初演 R.シュトラウス オペラ「ばらの騎士」1945年 生誕 ジャクリーヌ・デュ・プレ(チェロ奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・『私の探しもの』阪神大震災から10年の1月17日、すごい揺れを思い出した。 あの瞬間、夫が私の上に覆いかぶさり、私も自分の枕を夫の頭に乗せてお互いを守り合った。 身じろきできない程、体が硬直していた。 その後も余震が続き、不安な数日を過ごした。未曾有の体験をすると少しの揺れにも過敏になり、神経が休まらなかった。 ある日、夫が「いつも一緒にいるとは限らない。 何かあった時には、小学校の校庭で落ち合おう。 絶対やで。 ちゃんと探すから」と言ってくれた。私はとてもうれしかった。 ここまで気遣ってくれる人は、世界中探してもいないだろうとさえ思えた。それなのに3年前の七夕の日に逝ってしまった。 もうどんなことがあっても私を守ってくれる人はこの世にいない。 そう思うと恐ろしくなるくらい、寂しさがこみ上げてくる。 小学校の校庭で待っていたら、来てくれるかなあ・・・・。そんなはずないよね。 でも何かに守られているような感じがするのは気のせいでしょうか。ある本に書いてありました。 肉体は消えても、魂は家の中であなたを見守ってくれていますよ、と。 私は信じて疑わず、今日まで生きてこられました。 いつか宇宙のどこかの星で落ち合えればいいなあ。そのときは、私がちゃんと探すから。 50歳女性(芦屋市) 毎日新聞2005年1月25日朝刊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月26日
コメント(10)
-
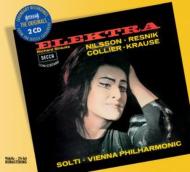
R.シュトラウス オペラ「エレクトラ」 / クルド人の強制送還
1909年1月25日、ルヒャルト・シュトラウスが作曲しましたオペラ「エレクトラ」がドイツ・ドレスデンの宮廷歌劇場で初演されています。R.シュトラウスは、映画「2001年宇宙の旅」に使われています交響詩「トュラトゥウストラはかく語りき」などや、「ドン・キホーテ」「英雄の生涯」などの優れた管弦楽作品と共に、オペラにも多くの名作を書いています。 「バラの騎士」「ナクソス島のアリアドネ」「影のない女」「アラベラ」「サロメ」「カプリッチョ」など素晴らしいオペラが残されています。それらの中の「エレクトラ」は、前作「サロメ」に続く肉親同士が血で血を洗う物語で、ギリシャ悲劇を基にしたオペラです。 どす黒い内容のドラマに加えてすごい衝撃音と、大音響の音楽という画期的なオペラとなっています。物語の舞台は、古代ギリシャ神話時代のミケナイで、その宮廷の物語です。 王アガメムノンはトロイ戦争に出陣して帰還すると、王妃クリテムネストラが愛人エギストと共謀して王アガメムノンを殺害します。 王の娘エレクトラは弟オレストの助けで、二人に復讐することを誓いますが、 弟は逃亡します。 妹クリソテミスは復讐を思い留まるようエレクトラを説きます。その後一人の青年が弟オレストの死を報告に来ます。 絶望するエレクトラ姉妹。 エレクトラは一人で復讐することを決心しますが、実はその青年が弟オレストで、 王妃と愛人エギストに復讐を果たします。 狂喜乱舞するエレクトラはやがて倒れて息絶えます。 妹クリステミスは驚いて、宮殿の扉を叩いて弟オレストを呼びますが応答はありません。 -幕ー愛聴盤 ビルギット・ニルソン、ゲオルグ・ショルティ指揮 ウイーンフィルハーモニー(DECCA 4758231 1966/67録音 海外盤)DECCAのオペラ黄金時代の遺産。 名プロデューサー、ジョン・カルーショーが手がけたこの頃のオペラは凄かった。 カラヤン/ウイーンフィル/デル・モナコ/テバルディの「オテロ」、ショルティ/ウイーンフィルのワーグナー「二ールンベルグの指輪」4部作などを遺しており、この演奏・録音時には、ビルギット・ニルソンの絶頂期で、音響でも現代に通じる優秀録音でオペラの真髄を味わえる1枚です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1819年 初演 ロッシーニ オペラ「シンデレラ」1886年 生誕 ウイルヘルム・フルトヴェングラー(指揮者)1909年 初演 R.シュトラウス オペラ「エレクトラ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『クルド人の強制送還』なんともやり切れないニュースが続く昨今の世相に、もう一つ暗澹としたニュースがクルド人への国外追放です。 国連が難民として認定しているクルド人家族を日本での不法滞在と難民としての認定をしない日本政府が、入管に出頭した父と息子がそのまま強制送還処置を取ってしまいました。法の前には「情」が通らないことはわかりますが、もう少し対応のやり方があってもいいのではないかと思います。 あの親子が強制送還されてトルコでどういう扱いを受けるかは想像に難くありません。 トルク国内でのクルド人への迫害は長い年月にわたって行われていることは、もう有名な話です。 批判をして暮らしていた家族が、迫害を恐れて日本に来て国連から難民として認定されていました。強制措置を取る前に、国連高等弁務官東京事務所に相談するだけの度量を持ち合わせない日本が、国連への常任理事国入りをアッピールしても相手にされないのではないかと思います。被災地への高額支援も大事ですが、こういうヒューマンな問題でも日本政府はもっと擦り寄る姿勢を持って対処して欲しいと思います。 真の支援、義捐を考えるべきだと思います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月25日
コメント(8)
-
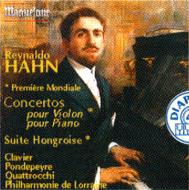
レイナルド・アーン 「ピアノ協奏曲」
『今日のクラシック音楽』 レイナルド・アーン 「ピアノ協奏曲」今日は音楽カレンダーから離れて別の話題を採り上げます。レイナルド・アーン(1875-1947)が作曲しました「ピアノ協奏曲」。 アーンはフランスで活動した作曲家ですが、南米ベネズエラに生まれています。「失われし時を求めて」のプルーストとは友だちの仲だったといわれています。フランス歌曲に興味のある方にはよく知られた作曲家で、歌曲はたくさん書いているとぐらいの知識にとどまっていましたが、ある人のプログを読んで、この人のピアノ曲を聴きたくなって探した結果、このピアノ協奏曲とヴァイオリン協奏曲のカップリングされたCDを見つけました。ピアノソロからゆったりと始まりますこの曲は、色彩豊かな音楽世界に導いてくれます。 それはまるで遠い昔を思い出しているような叙情ある趣です。 ブラスの響きが明るく、オーケストレーションはイギリスの作曲家ディーリアスのように心地良く響いてきます。 そのオーケストラと絡むピアノは非常に流麗で、洗練されたおしゃれムードの音楽で、まるで映画音楽を聴いているかのように楽しめる協奏曲です。アーンは、ピアノ・ソロ曲も数多く書いているようですのでこちらの方も聴いてみたいと思っています。(Maguclone レーベル MAG 111106 フランス輸入盤)『今日の音楽カレンダー』1960年 逝去 エドウイン・フィッシャー(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 ハナナ(菜の花)
2005年01月24日
コメント(12)
-
アルフレッド・ハウゼ / 神社会計引き継ぐ
『今日のクラシック音楽』「コンチネンタルタンゴの王様」と呼ばれ、日本でもタンゴブームの立役者として親しまれていました指揮者のアルフレッド・ハウゼさんが1月14日、長い闘病の末にドイツ・ハンブルクで84歳で死去したと、新聞で訃報を報じています。 ドイツ・ミュンスター地方生まれ。6歳でバイオリンを始め、39年にベルリンに出て楽団の奏者となり。48年に自身のタンゴオーケストラを結成。数十人の奏者による重厚な編成と、コンチネンタルタンゴに新たな感覚を採り入れたフレッシュな編曲で、欧米から日本までファン層を広げて、戦後のタンゴ音楽を普及させ、日本にも何度も来日して公演を行なっていました。タンゴは南米アルゼンチンが発祥と言われており、その本場のタンゴを「アルゼンチン・タンゴ」と呼び、土臭い香りのエキゾチックな音楽に、華麗さと豪華さ、スマートな編曲でヨーロッパで戦前から普及していたそうです。 それを「コンチネンタル・タンゴ」と呼び、ムード溢れる音楽が世界に広まっていたそうです。 名曲「碧空」「ジェラシー」などは、戦前に生まれていた曲だったのですが、このアルフレッド・ハウゼの絶妙のアレンジで、よみがえりました。ハウゼの演奏は学生時代から大好きで、行きつけの珈琲ショップでは毎日この楽団のLPをかけて聴かせてくれたことを思い出します。現代では「セミ・クラシック」CDの中にも選ばれるほど、タンゴ演奏の古典のようになっています。今日はハウゼの死を悼み、ヨーロッパ・タンゴの香りの中で過ごしたいと思います。なお、「コンチネンタル・タンゴ」と呼んでいるのは、日本だけらしいです。 うまく命名したものだと思います。愛聴盤 アルフレッド・ハウゼのすべて(ユニヴァーサル・インターナショナル UYCY8012)名曲「碧空」「ジェラシー」など20曲収録されたベスト・オブ・ハウゼです。『今日の音楽カレンダー』1933年 初演 バルトーク ピアノ協奏曲第2番・・・・・・・・・・・・・・・・・『神社会計引き継ぐ』今朝8時から定例の神社境内と外回りの清掃を行なってきました。 ヴォランティア(婦人会)と一緒になって、冷たい冬の朝の清掃は寒くて厳しいけれど、終わってみると清々しい気分になれます。 やはり落ち葉のない境内は威厳を取り戻して神々しく感じます。 この瞬間が好きでいつも欠かさずに参加しています。清掃後に、昨年までの会計から書類、通帳、印鑑を引き継ぎました。 神社役員の任期は4年で、2年ごとに半数の役員が交代します。 私はこれから2年、会計役員として神社の資金運営をまかされて身が引き締まる思いです。 運営する金額が半端な額ではないのと、村の皆さんからの寄進で運用するものですから、扱いに責任を感じます。でも、これから2年間プレッシャーの中で過ごすのもいいことかな、とも思っています。 今夜は新人役員の歓迎と辞めていく旧役員の慰労を兼ねた親睦夕食会を行います。 これが会計としての初仕事。今年も神社のために頑張るぞ!・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月23日
コメント(13)
-
ブラームス ピアノ協奏曲第1番 / 警官の告発
『今日のクラシック音楽』 ヨハネス・ブラームス作曲 ピアノ協奏曲第1番 二短調1859年1月22日、ヨハネス・ブラームス(1833-1897)が作曲しました「ピアノ協奏曲第1番 ニ短調」がブラームス自身のピアノで初演されています。 ブラームス26歳の時でした。このピアノ協奏曲は全体に交響楽的な響きにあふれた音楽で、ピアノとオーケストラのための交響曲といった雰囲気のある曲です。 第1楽章の出だしなどは重厚なハーモニーのオーケストラに呼応するかのように、鋼のような響きのピアノが奏い始めるところなどは、まるで重厚・長大型シンフォニーの始まりのようです。長大と言えば、この曲は約50分かかる長い曲です。 ブラームスのどの協奏曲についても指摘されることですが、前述のように曲はきわめて交響楽的に書かれています。 それまでのピアノ協奏曲のスタイルとは曲の長さ、オーケストレーションなどに、明らかに違いのあるブラームス特有の渋みと重厚な響きが特徴の協奏曲です。 もともと「2台のピアノのためのソナタ」として書かれたのを交響曲に仕上げる予定であったそうです。 ピアノソナタをシンフォニーに仕上げる難しさから、ピアノ協奏曲として仕上げた経緯を知りますとこの響きも納得できます。それでも後に書かれました第2番のピアノ協奏曲に比べますと、若々しい、清冽な気分に溢れた音楽であることに特色があります。 やはり青年ブラームスの若さが楽想に漂っているのでしょう。ところが、この曲の初演は失敗に終わったそうです。 失敗というよりも聴衆にとって難解な曲であったようです。 その理由はピアノがオーケストラの一部としての楽器のように書かれていること(交響曲にピアノ独奏部が大展開しているような印象)への、聴衆の困惑があったようです。 愛聴盤 伊藤 恵(P) 朝比奈 隆指揮 新日本フィルハーモニー交響楽団(FONTECレーベル FODC3136 1990年5月録音)ギレリス/ヨッフム指揮、ルービンシュタイン/メータ指揮、ブレンデル/アバド指揮、ツィンマーマン/バーンスタイン指揮他の演奏も聴いていますが、これほど純ドイツ風を感じさせる演奏はありません。 朝比奈 隆の真骨頂のような演奏に伊藤 恵ピアノのが触発されたかのように見事に活き活きとした音色を聴かせてくれています。『今日の音楽カレンダー』1857年 初演 リスト 「ピアノソナタ ロ短調」1859年 初演 ブラームス ピアノ協奏曲第1番1926年 生誕 オーレル・ニコレ(フルート奏者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『警官の告発』愛媛県警の捜査費が不正に支出されていた問題にからみ、同県警鉄道警察隊の仙波敏郎巡査部長(55)が20日、松山市内で会見し、73~95年の23年間、上司から偽造領収書を作るよう要求されたと証言しました。会見に同席したオンブズえひめ(代表・草薙順一弁護士)のメンバーによると、一連の警察不正経理問題で、現職警察官が会見して、内部告発したのは全国初のケース。 仙波さんによると、73年に配属された県警三島署では、当時の会計課長から「3000円」「5000円」と金額だけが書き込まれた領収書3枚と、3人の住所と名前が記されたメモを手渡され、「住所と名前を書き写せ」と、偽造領収書作りを求められ、仙波さんが「何のためですか」と聞くと、「組織のためだ」と言われ、拒否したという。仙波さんは「監査が入った際、筆跡で偽造領収書作りがばれないよう警官1人につき、3人までが“ルール”だったようだ。住所、名前は電話帳から抽出していた」と証言しています。仙波さんは95年まで県内11署の地域課で勤務。各署で毎年約2回ずつ、同様の偽造領収書作りを求められ、すべて断ったという。また、「偽造領収書でつくった裏金は、幹部らの飲食代などに使われたようだ」と話している。仙波さんは「県議会などで説明を求められれば、再度、証言したい」としている。証言しようと思った動機については、「正義感から。特別監査で何かが明らかになるかと期待したが、だめと思った。県警幹部から『お前が会見したら県警は1年間は立ち上がれなくなる』と言われたが、問題にフタをしたら一生後悔すると思った」と話していました。この警察の裏金作りはとどまるところを知らない。 いつまで続くのか? これでは泥棒ではないか? 国民の税金を横領しているのと同じです。 警察こそ高潔な思想で任務を遂行する公務員でなければならないのに、お金を搾取して、それも長期にわたり罪悪感なしに続けていることに唖然として声を失うほどの怒りを覚えます。きちんと調査して刑事事件として告訴すべき問題なのに、こういう不祥事のあった警察では、それもなくごまかしの対応で済ませてきています。もういい加減にしろと怒鳴りたくなる、犯罪を取り締まる権限を与えられた警察の、警察による税金泥棒という犯罪の話です。・・・・・・・・・・・・・
2005年01月22日
コメント(14)
-
プラシッド・ドミンゴ / 胃カメラで検査 / 花の説明に誤記訂正あり
『今日のクラシック音楽』 プラッシド・ドミンゴ(テノール)1941年1月21日、スペイン・マドリッドでテノール歌手プラシッド・ドミンゴが生まれています。今や、50に及ぶ役柄をこなしている現代最高のテノール歌手。 世界中のオペラハウスを席捲する不世出のテノール歌手。 彼を形容讃える言葉はとどまるところがありません。 リサイタル、テレビ出演、そして今はオペラ指揮者としても順調な活動を続けています。 オペラ歌手としての役柄も、リリコからドラマティコまでこなし、ドミンゴにとっては「境界線」がないような見事な歌唱を演奏・録音ごとに刻み込んできました。 音楽的には「知性」がみなぎり、女性をうっとりさせる恵まれた美男と容姿。 しかも「オテロ」などに顕著なステージ上でのカリスマ性もあり、およそオペラ歌手に要求される全てのものを兼ね備えています。 イタリアやフランスオペラのみならず、ワーグナーのオペラ「ローエングリン」での「白鳥の騎士」の名演は彼の才能を如実に示した例でしょう。 イタリアオペラでの生舞台よりも、私はこの『白鳥の騎士』の舞台を是非見たいと願い続けてきましたが、とうとうその機会もなくなったようです。今日は残された彼の録音・映像の中から、オペラ映画「カルメン」を採り上げました。 ドン・ホセ : プラシッド・ドミンゴカルメン : ジュリア・ミゲネス・ジョンソンエスカミリオ: ルッジェッロ・ライモンディミカエラ : フェイス・エシャムロリン・マゼール指揮 フランス国立管弦楽団・国立放送合唱団・児童合唱団フランチェスコ・ロジー監督映画 1982年制作これはただスタジオなどで映像化された従来のオペラ映画ではありません。 スペイン・アンダルシア地方での大ロケーションによって撮影された、汗が飛び散る、血が流れる、灼熱の太陽とカラカラに乾いた大地、タバコ工場の劣悪な労働条件から開放されて家路につく女工の群れ、群れ。小川の泉に立って歌われるカルメンの妖艶な「ハバネラ」、カルメンを引っ立てる乗馬姿の警官と、縄で引かれていくカルメンの背景は180度レンガ造りのアンダルシアの民家。ホセを誘惑しながら、太股を大胆に露出、乳房がはみ出しそうになる官能的、セクシーなカルメンを演じるミゲネス=ジョンソンの体当たり演技と歌唱のすごさ。 そんなカルメンに溺れていくホセ役のドミンゴ。 全てロケによる撮影。 エスカミリオの「闘牛士の歌」のジプシーキャンプ、酒場での「ジプシーの歌」のスペインの血潮のたぎり。オペラが、劇場からスペインの大地に飛び出して、前奏曲もアリアも忘れて見惚れてしまい、聴き惚れてしまう映画です。この映画はVHSとして15年前にリリースされて以来、カタログから姿を消してしまいました。 DVDへの復刻が待たれる、ドミンゴ、ジョンソン、マゼール、そしてフランチェスコ・ロジー監督が残してくれた異色のオペラ映画「カルメン」です。ドミンゴにちなむ日は、真っ先に観たい映画です。『今日の音楽カレンダー』1930年 初演 ショスタコービチ 交響曲第3番「メーデー」1941年 生誕 プラッシド・ドミンゴ(テノール)1948年 逝去 ヴォルフ=フェラーリ(作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『胃カメラで検査』今朝、市立病院で胃カメラで胃の検査を受けました。 昨年12月頃から時間を問わず、時々胃にチクチクした痛みを覚えていましたので診察を受けたところ、胃カメラによる検査を受けることになっていましたが、検査日には風邪をひいていたり、ギックリ腰だったりして延期となっていたのが、今日やっと受けられるようになりました。この検査は二度目なんですが、管を口から胃に入れて胃の中をカメラで透視して異常個所を調べるのですが、これは何度やっても嫌なものです。 口から入れるとどうしても気分が悪くなり、胃から何かが出てくるような感じにどうしても馴染めません。 検査では異常が認められなかったとの医師の検査後の所見でしたが、来週25日に正確な検査結果を聞きにいきます。ひとまづ安心しました。・・・・・・・・・・・・
2005年01月21日
コメント(10)
-
ミッシャ・エルマンのヴァイオリン / 今日は「大寒」
『今日のクラシック音楽』 ミッシャ・エルマンのヴァイオリン1891年1月20日、旧ロシア生まれの偉大なヴァイオリニストのミッシャ・エルマン(1891-1967)が生まれています。私が15-16歳の頃(1958-1961年頃)に最も聴きたかったヴァイオリニストの一人でした。 しかし、その頃はエルマンの晩年期で来日公演がなくて、もっぱらLP盤でその音色を楽しんでいました。13歳でドイツ・ベルリンでチャイコフスキーの協奏曲で衝撃的なデビューを果たし、14歳で英国王室に招かれてカルーソー(テノール)らと共に演奏をした神童でした。当時は並外れた技巧と、情熱的な演奏で話題を呼び、加えて甘い、美しい響きで人々を魅了した演奏家と言われています。 甘く、柔らかい味があって、これを「エルマン・トーン」ともてはやされていました。懐かしいLP盤を処理したあとに、長い間彼の演奏を耳にすることもなくなっていましたが、昨年アメリカのヴァンガード社に録音されていた1960年制作の演奏がCDに復刻されて廉価盤でリリースされたので、懐かしさでいっぱいで購入して聴いてみました。彼の演奏スタイルはとにかく癖のある弾き方で、「エルマン・トーン」と呼ばれた甘い音色は、現代の優れた演奏家の音色を聴き込んでいますと、それほどのものでないと感じなくなっているのは、時代の変遷なのか私が多くのヴァイオリニストの演奏を聴いてきました結果なのでしょうか。 現代では時代遅れを感じさせる大げさな表現ですが、こういうスタイルのヴァイオリン演奏家はもう二度と出ないと思います。懐古趣味の演奏を聴くような思いで聴いていました。この1枚 ミッシャ・エルマン(Vn) ゴルシュマン指揮 ウイーン国立歌劇場管弦楽団(ヴァンガード・クラシックス COCQ 83834 1960年録音)「ヴァンガード名盤選」の中の1枚で、メンデルスゾーンの協奏曲とラロのスペイン交響曲が収録された日本コロンビアからのリリースです。『今日の音楽カレンダー』 1855年 生誕 エルネスト・ショーソン(作曲家)1891年 生誕 ミッシャ・エルマン(ヴァイオリニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日は大寒』今日1月20日は24節季のうちの「大寒」です。 「寒中」の真ん中で、一年で最も寒い時期とされています。天文学的には、天球上の黄経300度の点を太陽が通過する時です。 24節季とは、節分を基準に太陽の行動上の位置によって決められた季節区分で、1年を24等分して約15日ごとに分けた季節で、冬至から約15日ごとに節気(せっき)と中気(ちゅうき)が交互にあります。 各節季の日付は年によってずれます。大寒には行事が多くあります。「大寒みそぎ」(防府氏)などはTVで見ているだけで身震いします。 1年間風邪をひかないと言い伝えがあるそうですが、あのみそぎで風邪をひかないのかなと心配になります。「大寒仕込み」という味噌仕込みや日本酒の仕込みも行われています。 寒さが厳しい頃は、空気中に雑菌が少ないので味噌を仕込むのに最適だという昔の賢人の知恵だそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月20日
コメント(10)
-
モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」 / 文部科学省に有能大臣を!
『今日のクラシック音楽』 W.A.モーツアルト作曲 交響曲第38番「プラハ」1787年1月19日、モーツアルトが作曲しました交響曲第38番ニ長調 K.504が、チェコのプラハで初演されました。モーツアルトは、オペラ「フィガロの結婚」でウイーン初演で成功をおさめていましたが、チョコのプラハでも上演されて大人気となり、プラハの音楽愛好家たちからプラハ訪問の招待を受けました。そのときに、書いていた交響曲をもって訪問して、モーツアルト自身の指揮でプラハで初演されたそうです。 この曲の「プラハ」という副題は、標題的な意味はまったくなくて、ただプラハで初演されてということから命名されているだけです。 36番の「リンツ」と同じ理由です。交響曲は、普通4楽章構成となっていますが、この「プラハ」は3楽章構成で、「メヌエット」楽章がありません。 そのためか、ドイツでは「メヌエットなし」と呼ばれているそうです。この曲を聴いていますと、彼の書いたオペラ「ドン・ジョバンニ」と似た雰囲気があります。 そう感じるのは、第1楽章の序奏部が、劇的な緊張感が与えるところから来るものかも知れません。 メヌエット楽章なしでも違和感を感じさせないところに、モーツアルトの才能の一端を聴く思いのする交響曲です。愛聴盤 ラファエル・クーベリック指揮 バイエルン放送交響楽団(SONYクラシックス SRCR2002 1980年10月録音)『今日の音楽カレンダー』1787年 初演 モーツアルト 交響曲第38番「プラハ」1854年 初演 ベルディ オペラ「トロヴァトーレ」1883年 生誕 ヘルマン・アーベントロート(指揮者)1884年 初演 マスネ オペラ「マノン」1909年 生誕 ハンス・ホッター(バリトン歌手)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『文部科学省に有能大臣を!』文部科学省の学校教育方針の転換に疑問を抱かざるを得ない発言が中山文部科学省大臣から飛び出しています。99年に有馬大臣が「教育内容の厳選」をうたい文句に「ゆとりのある教育ー2002年から総合学習を取り入れる」方針を発表して、新しい教育へのスタートを切りましたが早くもその2002年に遠山大臣が方針転換となる「学力低下」問題を指摘して物議をかもし出し、今度は中山大臣が「週5日制による抱く力低下は当然。 ゆとりある総合学習への費用削減して学力重視」を発言しています。99年の有馬大臣の「ゆとりある」教育の根本方針は、「学ぶ」ことから「考える力」への転換だったはず。 それがスタートする02年には早や、「学力重視」を見直されてきました。 そして中山大臣の発言。子供の学校教育方針で、子供を政策の道具に使うなと言いたくなるほどの「朝礼暮改」的な文部科学省の考え方の変換に疑問を抱かざるを得ません。もっと有能な、国民が納得できる大臣をポストに付けてください、小泉さん。 行政改革実行に賛成する議員への「お手盛り人事」のような議員の大臣配置はやめて欲しい、と言いたくなります。日本の将来を担う子供たちへの学校教育をもっと真剣に考えてやって下さい。 これでは現場の学校、教師が困るでしょう。 もっとしっかりした議員を大臣にしてくださいね、小泉さん!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月19日
コメント(16)
-
シャブリエ 狂詩曲「スペイン」 / 今、ここで
『今日のクラシック音楽』 エマニュエル・シャブリエ作曲 狂詩曲「スペイン」1841年1月18日、フランスの作曲家エマニュエル・シャブリエ(1841-1894)が生まれた日です。シャブリエの、作曲家として名を残している曲に狂詩曲「スペイン」があります。 彼はスペイン人ではなくフランス人ですが、降り注ぐかのような陽射しの太陽、底抜けに明るい国民性、賑やかな舞曲など、フランスの洒落た音楽とは違う情熱的な激しさを伴っているのがスペイン音楽の特徴です。多くの作曲家が異国に旅行して、その風土、文化、歴史、美術、文学・詩などに触れてその国にちなんだ、素晴らしい音楽を残しています。 チャイコフスキーやR.コルサコフの「イタリア奇想曲」、 メンデルスゾーンの「イタリア」交響曲、「スコットランド」交響曲、 ラヴェルの「スペイン狂詩曲」など数多くの音楽が書かれています。この狂詩曲「スペイン」も、シャブリエが1882年にスペインを旅行してその風景、音楽、ダンスなどに感動して書かれたそうです。弦楽器が歯切れ良くピツィカートを刻んでで始まるこの曲は、スペインの舞曲の一種「ホタ」や「マラゲーニヤ」などのスペイン独特のリズム、旋律を取り入れ、フランス人シャブリエの洒落た軽妙さをまじえた、スペイン舞曲の豊かな色彩感とスペイン風土の味わいを持った曲に仕上がっています。今日、演奏会などで採り上げられるシャブリエの曲は、この狂詩曲「スペイン」と「楽しい行進曲」ですが、今日紹介しますCDには彼の他のオーケストラ楽曲が収録されており、シャブリエの音楽を知り、聴く上にとても貴重なCDです。愛聴盤 ジョン・エリオット・ガーディナー指揮 ウイーン・フィルハーモニー (グラモフォン ユニヴァーサル・クラシック POCL1949 95年録音)収録されています曲は、1 「田園組曲」 2 「ハバネラ」 3 狂詩曲「スペイン」 4 「ラルゲット(ホルンとオーケストラのための)」 5 序曲「グベンドリーヌ」 6 「ポーランドの祭り」の6曲です。『今日の音楽カレンダー』1841年 生誕 アレクシス=エマニュエル・シャブリエ(作曲家)1943年 初演 プロコフィエフ ピアノソナタ第7番1946年 生誕 カティア・リッチャレッリ(ソプラノ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今、ここで
2005年01月18日
コメント(6)
-
アルビノーニのアダージョ / 必要なもの
『今日のクラシック音楽』 トマゾ・アルビノーニ作曲 「弦とオルガンのためのアダージョ」1751年1月17日、イタリアの作曲家トマゾ・アルビノーニ(1671-1751)が亡くなった日です。アルビノーニは「イタリア・バロック音楽」時代に、協奏曲集「四季」など数多くの名品を書残していますヴィヴァルディと同じ頃に、合奏協奏曲集などを残した人で、今もこれらの曲が演奏会のプログラムを飾り、レコード・CDなどに録音されています。朗々と響き、鳴る弦楽の音色と豊かな歌にあふれたイタリア・バロック音楽は、今も人の心を癒し続けています。 その中でもアルビノーニの「アダージョ」はその筆頭に位置する曲で、CDなどで「バロック名曲集」などに必ず収録されています定番曲で、「弦とオルガンのためのアダージョ」というのが正式な名前です。この曲は、アルビノーニ自身が書いた曲ではなくて、現代イタリアの音楽研究家レーモ・ジャゾットが、アルビノーニが書残していました数小節のスケッチを元に加筆して完成した曲だそうです。 しかし、この曲は暗く、荘厳で悲しみの情感に溢れた曲想なのですが、一度聴けば忘れられない美しい旋律で、イタリア・バロック音楽の名品の一つです。今日は阪神淡路大震災から10年を迎えた日です。 この震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りしながら、この曲を聴こうと思います。愛聴盤 イタリア合奏団(DENON レーベル COCO70721 1988年録音)昨年12月に「クレスト1000」シリーズとして再発売された「バロック名曲集」というタイトルで、私の聴いています盤と同じ音源で、価格は1,000円と値下げされたお買い得盤です。『今日の音楽カレンダー』1751年 逝去 トマゾ・アルビノーニ(作曲家)1880年 初演 フランク ピアノ五重奏曲1886年 逝去 アミルカーレ・ポンキェッリ(オペラ作曲家)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『必要なもの』風邪のとき必要なものは病院でもなく風邪薬でもないおでこにさわるやさしいあなたの手ですおかあさん東京都20歳女性 -産経新聞2005年1月16日朝刊 「朝の詩」-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月17日
コメント(9)
-

アルトゥーロ・トスカニーニ
『今日のクラシック音楽』 アルトゥーロ・トスカニーニを偲ぶ1957年の今日(1月16日)20世紀の偉大な指揮者アルトゥーロ・トスカニーニ(1867-1957)が90歳の生涯を閉じた日です。1958年、私が確か中学生だった時に、クラシック音楽に魅せられて聴く音楽、曲がすべて新鮮でこの世にこんな素晴らしい、美しい音楽が、心を揺さぶって離さない音楽があるものかと聴くたびに感動していた頃、レコードショップのチラシに「ベートーベン交響曲第7番 トスカニーニ永遠の名盤 復刻なる!」がありました。 その頃に聴いていた交響曲は、「新世界より」と「運命」だけだった(実演で悲愴交響曲を聴いてさっぱり理解できず、友人宅で聴かせてもらっていました)私には7番というベートーベンの交響曲が大変新鮮に映ったのでした。 同級生でピアノを弾く男子生徒にその話をすると「トスカニーニのベートーベンは凄いよ。 情熱の迸りみたいなものを感じるよ。 フルトヴェングラーとは違う大きな魅力がある指揮者だよ」と言われて、演奏ってそんなものなのか、指揮者で音楽が変わるのかと思ったものでした。そして小遣いを貯めて、このCamdenレーベルから発売された1000円盤LPを買って聴きました。 それがトスカニーニ初体験でした。 でも初めて聴く曲ですから、何のバイアスもなく聴いていますから他の演奏と較べることもなく、ただ曲の素晴らしさに酔っている毎日でした。 その後、カラヤンやフルトヴェングラー、ワルターなどの演奏を友人の家で聴かせてもらい歴然とした演奏の違いを知りました。話が長くなりますので、トスカニーニとの出会いはこれくらいに留めておきます。その後色々な交響曲、管弦楽演奏に触れるに従って、トスカニーニの演奏に表現されています、炎の塊のような情熱と鋼鉄のような精神の強さを感じてきました。炎のように燃え上がらせる情熱、一糸乱れぬ緊張感を伴った鋼のようなアンサンブルで音楽を表現していくさまに、いつも息を呑む思いでステレオ装置の前で緊張しながら聴いていました。トスカニーニの演奏は、隙もないほどに磨き抜かれた、精緻な美しさを持っていて、決して音楽に溺れることがないような演奏に聴こえます。 テンポが他のドイツ・オーストリア系の所謂「ドイツ音楽の伝統」のような、テンポをゆったりと取りながら、重厚な音楽を作る指揮者たちとは一線を画す演奏でした。 疾走するようなテンポの中に炎のように滾った情熱が織り込まれていて、聴いていますと精神が高揚し、血がたぎるような想いで聴いていました。 そうしたトスカニーニのスタイルは、晩年まで衰えることのない輝きを放っていましたから凄いという言葉以外に見つかりません。彼のデビューも尋常でなかった話が有名です。 1886年オペラ公演の折に指揮者が演奏できなくなってしまい、この時、オーケストラの首席チェリストであったトスカニーニが、当日の演目「アイーダ」を全て暗譜していたことから、楽団員の要請により、ぶっつけ本番で、しかも暗譜で指揮を行い、見事に大成功を収めて指揮者として華々しいデビューを飾りました。 彼は、驚異的な記憶力と、極度の近眼のためにほとんど全ての曲を暗譜で演奏したといわれています。トスカニーニの創り出す音楽は、フルトヴェングラーの19世紀のロマン濃厚な薫りの指揮に対して、造形を何よりも重視して、「カンタービレ」の美しさを具現しており、その後の20世紀のカラヤンやアバド、ショルティ、ムーティ、といった指揮者たちに大きな影響を与えていると思います。幸いにも、彼の演奏した録音がすでに古いものに関らず、フルトヴェングラーのそれと同じように現代テクノロジーの進化によって、聴きやすい音質で蘇っています。レスピーギの「ローマ3部作」(交響詩「ローマの松」「ローマの噴水」「ローマの祭」)などは、彼の演奏特質を伝える「永遠の名盤」として残されています。 きらびやかさと音の洪水のような演奏です。 この演奏がトスカニーニを語るに充分なほど、明快で情熱の迸りが曲の隅々まで感じられ、カンタービレの美しさの極致のような演奏です。 (RCA原盤 BMGジャパン BVCC9935 49/51/53年録音)トスカニーニの娘が、ウラジミール・ホロヴィッツと結婚していますが、花婿と共演していますチャイコフスキーのピアノ協奏曲も、若きホロヴィッツとの火花が散るような情熱の滾りは、まるで楽譜が透けて見えるような明解さと共に、永遠に語られるべく不滅の演奏として愛聴しています。(RCA レーベル 60321-2RG 1941年5月録音 USA輸入盤) そのトスカニーニの膨大なディスコグラフィーの総集編として東芝EMIからリリースされましたのが、「トスカニーニ TVコンサート」なる5枚組のDVD映像です。 トスカニーニの生きた指揮姿と熱い演奏を繰り広げるNBC交響楽団のコンサートの模様を堪能できます。 1948年から1952年までの最晩年の貴重な指揮姿を収録した、NBC制作によるTVコンサートの復刻DVDです。(東芝EMI TOBW-3531~35 48/49/51/52年録画) 収録されている演奏は圧倒的な名演奏ばかりです。 エネルギーが炎と化したかのような音の塊のベートーヴェンの「第9」。 そしてブラームスの第1番の交響曲。 スケールの巨大さに包まれたワーグナーの「タンホイザー序曲」。 燃え尽くすかのような情熱とカンタービレの美しさとスリリングな「スイス軍の行進」が聴ける、ロッシーニの《ウィリアム・テル》序曲。そしてこのDVDの白眉は、1949年3月26日と4月2日に分けて演奏された演奏会形式によるヴェルディの《アイーダ》全曲です。 これほど凄絶な迫力と精緻と繊細な歌に満ちた《アイーダ》がないと断言できるほどで、 時間の経つのも忘れてしまうくらいに映像と演奏にひきつけられます。 もうこういう「アイーダ」の演奏をする指揮者がいなくなったのかという郷愁と、偉大な再現芸術家の演奏記録に酔えるオペラです。曲目1 ワーグナーの音楽 歌劇「ローエングリン」第1、第3幕への前奏曲 歌劇「タンホイザー」序曲とバッカナール 楽劇「ワルキューレ」ワルキューレの騎行 楽劇「ジークフリート」夜明けとラインへの旅 楽劇「ジークフリート」ジークフリートの死と葬送行進曲 楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死2 ブラームス 交響曲第1番 ハ短調 Vnとチェロのための二重協奏曲 ハンガリー舞曲第1番 ワルツ集「愛の歌」3 モーツアルト 交響曲第40番 ト短調4 ドヴォルザーク 交響的変奏曲5 フランク 交響詩「贖罪」6 ドビッシー 「夜想曲」7 シベリウス 交響詩「伝説(エン・サガ)」8 ロッシーニ 歌劇「ウイリアム・テル」序曲9 レスピーギ 交響詩「ローマの松」10 ベートーベン 交響曲第5番「運命」 交響曲第9番「合唱付き」11 ヴェルディ 歌劇「アイーダ」全曲 数多くのエピソードの残るトスカニーニですが、彼はオーケストラ団員をしごくタイプの「専制君主」のような指揮者だったそうです。 オーケストラを徹底的にしごき、その結果あの鋼のような完璧なアンサンブルが生まれてきたのでしょう。 この専制的な態度は、オペラの歌手にも容赦はなく、あるとき有名な女性歌手が彼にこう反論したそうです。 「マエストロ、私はスターですよ!」。 トスカニーニは平然と答えたそうです。 「マダム、スターは空にあるものです」。今日は、長い、独断と偏見の私のトスカニーニへの想いの記事にお付き合いをいただきまして、ありがとうございました。『今日の音楽カレンダー』1891年 逝去 レオ・ドリーブ(バレエ音楽「コッペリア」の作曲家)1928年 生誕 ピラール・ローレンガー(ソプラノ)1929年 生誕 マリリン・ホーン(ソプラノ)1938年 初演 バルトーク 「2台のピアノと打楽器のための協奏曲」1957年 逝去 アルトゥーロ・トスカニーニ(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月16日
コメント(8)
-

ピエルネ バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」
『今日のクラシック音楽』 ガブリエル・ピエルネ作曲 バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」1923年1月15日、フランスの作曲家ガブリエル・ピエルネ(1863-1937)が書きました、バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」がパリ・オペラ座で初演されています。この作品は、ニ幕三場のバレエのために書かれたもので、森の中の牧羊神学校から抜け出したステラティックスが、ヴェルサイユ宮殿に招かれて行く舞姫シダリーズに魅せられて彼女と踊る幻想的な物語です。 全曲で約50分の演奏時間です。この初演のあとピエルネは全曲から抜粋した音楽を、演奏会用に第1組曲、第2組曲に編集しています。 第1組曲に入っています「小牧神の入場」はこの音楽の中でも有名で、単独でもよく演奏される曲です。小牧神たちが勉強を習う森の学校に、牧神たちに引率されていく様子を描いており、行進が去っていく様子がうまく書かれている曲です。 愛聴盤 デヴィッド・シャローン指揮 ルクセンブルグ・フィルハーモニー (TIMPANI レーベル 1C1059 2000年5月録音 フランス輸入盤 全曲盤)学生時代に誰の演奏かは忘れましたがLP盤で聴いていた曲です。『今日の音楽カレンダー』1923年 初演 ピエルネ バレエ音楽「シダリーズと牧羊神」1926年 逝去 エンリコ・トセリ(イタリアの作曲家)1941年 初演 メシアン「世の終わりのための四重奏曲」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『思い出の風景』 京都嵯峨野 竹林散策路 撮影地 京都嵯峨野 天竜寺裏 竹林 2003年11月色々な思い出を秘めた1枚です。
2005年01月15日
コメント(16)
-

ラヴェル 「ピアノ協奏曲 ト長調」 / 運勢
『今日のクラシック音楽』 モーリス・ラヴェル作曲 ピアノ協奏曲ト長調1932年1月14日、モーリス・ラヴェル(1875-1937)が作曲しました「ピアノ協奏曲 ト長調」が、パリで作曲者自身の指揮、マルグリット・ロンのピアノによって初演されています。ラヴェルは、晩年になって2曲のピアノ協奏曲を書いています。 一つは第一次世界大戦で右手を失ったピアニストの依頼を受けて書かれました、「左手のための協奏曲」、もう一曲は今日採り上げました「ピアノ協奏曲 ト長調」です。ラヴェル56歳の時に書かれたこの協奏曲は、ラヴェル独特の精緻な曲想と、色彩豊かな音色で書かれており、曲の開始冒頭ではムチの強打で始まるという意表をつく斬新さも盛り込まれており、またフィナーレの第3楽章はアメリカを訪れた際に聴いたジャズ音楽の手法も取り入れており、しかも日本の作曲家伊福部 昭の不朽の名作、「ゴジラ」のテーマにそっくりなところもあり、ピアノとオーケストラが渾然一体となった近代ピアノ音楽史上に燦然と輝く、素晴らしいピアノ協奏曲です。余談ですが、この曲の初演のピアニスト、マルグリット・ロンは1966年に91歳で亡くなっていますが、 彼女はフォーレ、ドビッシー、ラヴェルなどと親交を深めたピアニストだそうで、現在フランスで行なわれています「ロン=ティボー国際コンクール」としても名前を残しています(ティボーは同じくフランスの偉大なヴァイオリニストです)。愛聴盤 エレーヌ・グリモー(P) へスス・ロペス=コボス指揮 ロイヤル・フィルハーモニック管弦楽団(DENON原盤 Briliant Clasics BRL92437 1992年録音 海外盤)このディスクは5枚組でグリモーがメジャーレーベルに録音したラフマニノフやショパン、などのピアノ作品をBriliantがライセンス契約でリリースした廉価盤で2500円以下の廉価での発売で、グレモーの魅力いっぱいのディスクです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』 1900年 初演 プッチーニ オペラ「トスカ」1932年 初演 ラヴェル 「ピアノ協奏曲 ト長調」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『運勢』たまたま私のページをリンクしていただいている方が同じ日に同じような話題の日記を掲載されていました。 「おみくじ」と「占い」です。今年の私の運勢は高島易によれば、ばら色の1年なんですが、細木数子さんの六占星術では向こう3年は「大殺界」だそうです。 こういう占いとか運勢を信じる、信じないは個人差があり、信じる人は出た占い結果や運勢に悩んだり、喜んだりすると思われますし、信じない人は無視するのでしょうね。私はこうした「占い」「運勢」を自分自身への「戒め」だと理解していくことに決めています。 困難こと、辛いこと、悲しいことがあれば、その先に幸せや楽しみがきっと来るんだと思い、うまくことが運んでいるときは「ちょっと待てよ」と戒めように心がけるようにしています。そうすれば「占い」「運勢」の呪縛から解放されると思えるからです。皆さんはどうでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月14日
コメント(18)
-

フォスター 「夢見る人」 / 花粉症
『今日のクラシック音楽 』 スティーヴン・フォスター作曲「夢見る人」1864年1月13日、アメリカの作曲家スティーヴン・フォスター(1826-1864)がわずか38歳の若さで亡くなった日です。フォスターはアメリカ・ピッツバーグに生まれ、本格的な音楽教育を受けずに独学で音楽を勉強した人で、遺されている曲は「歌曲」で、後に「アメリカの歌曲王」と呼ばれるほど数多くの歌を書残しています。 その数は約160曲といわれています。彼の曲は誰もが口ずさむことのできる親しみにあふれており、しかもアメリカ風土の薫と匂いのいっぱい詰まった美しい旋律が今でも人の心を捉えて離しません。 子供の頃から連れられて見た、黒人たちの集う教会などで耳にした旋律などを自由に使って、その頃の生活風景、人物などを歌にして残しています。「草競馬」「オールド・ブラック・ジョー」「故郷の人々」などの名曲にそういうものが如実に表れています。 また「夢見る人」や愛妻に捧げた「金髪のジェニー」なども美しいメロディーがいっぱいの曲で, 今も世界中で歌われ続けている「愛唱歌」です。愛聴盤 ロジェー・ワグナー合唱団 (東芝EMI TOCE59720 1960年代録音)「なつかしきケンタッキーのわが家」「おお、スザンナ」「故郷の人々 (スワニー河)」「草競馬」「夢見る人 (ビューティフル・ドリーマー)」「金髪のジェニー」や黒人霊歌が収録されています。 これも16歳の頃からLP盤で聴いてきた演奏・録音です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『花粉症』目が痒い、鼻が痒くてムズムズ。 嫌な花粉症が暴れる季節が近づきました。 私はこの花粉症にかかったことがないので、どれだけ辛いものかを実感していないのですが、友人で花粉症を持っている人を見ているとほんとに辛そうです。昨年の記録的は夏の猛暑が、今年の春の花粉飛散量は過去最大級という予想もされていると、その友人が憂鬱そうに語っていました。 今春の近畿でのスギ・ヒノキの花粉飛散は、昨年の20-30倍、例年の2-3倍で過去最大の平成7年に迫る量だと友人が語っています。花粉症の人は、今からもう薬局に出かけて対策を講じており、関連商品を売る店は強気の販売姿勢だそうです。 花粉カット機能マスクや、ゴーグル(眼鏡)などがそれらしいです。早くこの症状を断ち切る画期的な医療が待ち望まれます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ともの『今日の一花』 椿 「初化粧」 撮影地 大阪市「慶澤園」2004年12月椿(つばき)科 ツバキ(カメリア)属 開花時期は、12月~4月末頃 日本特産で学名はCamellia(カメリア)で、17世紀のチェコスロバキアの宣教師「Kamell カメル」さんが18世紀に東洋からヨーロッパにもたらしたことで広まったそうで、このカメルさんの名にちなんで「カメリア」となったそうです。 英語でも「カメリア」と呼ばれています。 藪椿という種類がありますが、園芸種では1万を超す種類があるそうです。現在は「椿」の字で知られていますが、この「椿」の字は日本で作られた字(春に花咲く)で中国では「椿」は、「ちゃんちん」という木のことを指しており、漢名では日本「椿」は「山茶花」と書くそうです。 日本では「山茶花」は”さざんか”で、昔からの取り違えをしています。
2005年01月13日
コメント(14)
-
ヴォルフ=フェラーリ 「聖母の宝石」間奏曲 / あの日、見えたもの
『今日のクラシック音楽』 ヴォルフ=フェラーリ作曲 「聖母の宝石」間奏曲1876年1月12日、イタリアの作曲家エルマン・ヴォルフ=フェラーリ(1876-1948)が生まれた日です。ヴォルフ=フェラーリは、オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」で有名なマスカーニと同時代の作曲家で、オペラ「聖母の宝石」が有名ですが、今でも演奏されるのはそのオペラの「間奏曲」くらいで、私も一度もこのオペラの全曲を聴いたことがなく、おそらくレコード・CDに全曲録音されたことがないかも知れません。 このオペラは「間奏曲」で有名なのですが、物語はよくわかりません。 オペラ関係の書籍などで調べるとわかると思いますが、今日はこの間奏曲のみの話題にしておきます。 「間奏曲」は2曲ありますが、有名なのは第1幕と第2幕の間で演奏される第1番の方です。この第1番の間奏曲は、コンサートやオーケストラ作品集、オペラ間奏曲集などのレコード・CDの定番のような曲になっています。 フルートの清らかで澄んだ感じの序奏で始まり、弦楽器によって奏される、甘い感傷的な旋律は一度聴いたら忘れられないほど美しさに溢れた名品です。愛聴盤 ネロ・サンティ指揮 パリ音楽院管弦楽団16歳の頃にLP盤を買って盤が擦り切れるほど聴きました懐かしい演奏・録音です。 フェラーリの管弦楽曲が収録されていて、「聖母の宝石」はオペラの音楽をまとめた組曲となっています。 ファラーリ音楽を知る上で現在も、求め得る1枚だけのCDです。1.歌劇「スザンナの秘密」~序曲2.歌劇「町の広場」~間奏曲3.歌劇「町の広場」~リトルネッロ4.歌劇「愚かな女」~序曲5.歌劇「四人の気むずかし屋」~前奏曲6.歌劇「四人の気むずかし屋」~間奏曲7.組曲「マドンナの宝石」(同名の歌劇から)が収録されています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『あの日、見えたもの』震度7の揺れが我が家を押し潰した日の朝、いろんなものを見た。息子と小さい頃から一緒に遊んできた小四の女の子が亡くなった。 一人娘だった。前々日、通園バスを降りて「おばちゃん、またね」と手を振ってくれた友だちの園児も亡くなった。 お母さんがお産のために病院へ行かれた留守中の出来事だった。 お寺の前の電話に行列していた時、毛布にくるんだ我が子を運んでくるお父さんを見た。 「子供が死んだんだけど、どこに連れて行ったらいいんですか」と女の人に道で聞いていた。人の死があたり前のように誰もの感覚が麻痺していた頃、他のたくさんのことも見た。 壊れた家々から荷物を出していた大勢の若者たち。 道路に座り込んでやっと休憩をとっていた自衛隊の人たち。水も電気もない自宅に多くの人を泊めてくれた友人。 半分壊れた自宅で食事を振舞ってくれた近所の顔見知りのおじさん。 廃墟の中、真っ先に園児の安否確認に走りまわって先生たち。北海道警のパトカーを街で見かけた時は、思わず頭が下がった。やっぱり人間はすばらしい。 どんな時でもたくましい生き物なのです。産経新聞2005年1月11日付け夕刊 「あの日、見えたもの」~震災エッセイ 大阪市 48歳主婦 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月12日
コメント(10)
-
シンディング ピアノ曲「春のさざめき」(誤記訂正) / 悲惨なニュースの中の朗報!
『今日のクラシック音楽』 クリスティアン・シンディング作曲 ピアノ曲「春のさざめき」1856年1月11日、ノルウエーの作曲家クリスティアン・シンディング(1856-1941)が生まれた日です。彼の名前は、ピアノ曲「春のざめき」でピアノを弾く人に良く知られています。 彼は歌曲や管弦楽曲、交響曲も書いており、昨今ではその4曲の交響曲が『隠れ交響曲』として人気の曲となっているようです。今日は彼の誕生日にちなんで、一番有名なピアノ曲「春のさざめき」を採り上げることにします。ノルウエーでは先輩であるグリーグのすぐ後の世代ですが, グリーグ同様に彼はノルウェー政府からの奨学金によって、ドイツに留学しています。 先輩のグリーグがドイツ音楽に影響を受けても、ノルウェー国民主義的作風の曲を書いたのに較べて、シンディングは生涯をかなり長期間ドイツで過して、ドイツ・ロマン主義の影響を多分に受けて、その作風に反映しています。4つの交響曲などは、マーラーより後の世代なのに随分と保守的な、ドイツ後期ロマン派の薫のする音楽を書いています。第2番の交響曲などは、作曲された7年後の1913年にはストラビンスキーのバレエ音楽「春の祭典」がロシア・バレエ団との初演が行なわれて、当時としては破天荒な音楽のために未曾有の混乱を引き起こしていた時代であることと比べますと、随分と伝統的な、保守的な音楽を書いていたものだと感じます。 (アリ・ライシネン指揮 ノルウェー放送管弦楽団 FINLANDIA レーベル 3984-27889-2)「春のさざめき」は、まるでそよ風の囁きを語るかのように、分散和音にのって表れる美しい旋律のピアノ曲です。 一般的には、シンディングの名前を残している曲と言っても過言でないピアノの定番のような曲です。愛聴盤 ペーテル・ナジ(ピアノ) 「ロマンティック ピアノ名曲集」 第4巻ラフマニノフの「ヴォカリーズ」や「乙女の祈り」、ドビッシーの「月の光」など有名ピアノ曲が収録された廉価盤CDで、仕事の合間のちょっとした休憩時間などに耳を傾けています。『今日の音楽カレンダー』1856年 生誕 クリスティアン・シンディング(作曲家)1940年 初演 プロコフィエフ バレエ音楽「ロミオとジュリエット」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『悲惨なニュースの中の朗報!』インド洋大津波が多くの人々をのみ込んだ日、産声を上げた女の子がいる。スリランカ北東部のトリンコマリー県。ノナシダヤさん(35)は先月26日、海岸に近い入院先の病院から約200メートル流されたものの助けられ、産湯もないまま出産した。奇跡的に授かったその子を両親は「TSUNAMI」(ツナミ)と名付けた。母親の入院先は全壊し、他の妊婦ら約30人が死亡。両親は「特別に授かった命だと感じる。みんなに、この地で起きた悲しい出来事を忘れてほしくない」と話している。英語教師のファリードさん(40)、ノナシダヤさん(35)夫妻に生まれた第4子で、初めての女の子。母親は海岸線から約120メートルの病院に入院しており、26日午前9時ごろ、陣痛を和らげようと病棟の外を歩いていた。そこへ、いきなり大津波が襲った。建物や樹木など、どこにもつかまることが出来ず、約200メートル流されながら「このまま死ぬ」と観念したという。津波が引いた路上に倒れていたところを若い男性に助けられ、近くの学校へ運ばれた。そのわずか5分後に出産。偶然いた看護師が手伝ったが産湯もなく、へその緒を切っただけだった。大きな産声を上げた女児に、母親は「動転して、キスすらしてあげられなかった」と振り返る。一方、病院から約400メートル離れた自宅も腰の高さまで浸水した。父親は、自宅周辺で5歳と2歳のおいを含む15人の遺体を収容した。「病院は全滅」という話を聞き、「妻も死んだに違いない」と思ったが、同日午後6時ごろ、思いがけず妻の生存を聞いた。出産の事実を知って二重に驚いたという。今は、家族6人で父親の実母宅に避難中。ツナミちゃんは当初、母乳を吐き出し、「海水のせいか」と心配させたが、健康に育っている。母親の腕の中でよく眠り、目を開けた時は母親をじっと見つめる。栄養不足など心配は尽きないが、「この子が生まれたこと以上の幸せがあるでしょうか」。母親はツナミちゃんをギュッと抱きしめた。ー毎日新聞記事からー 2005年1月10日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月11日
コメント(10)
-
シューベルト 歌曲集「冬の旅」 / PCが復旧しました
『今日のクラシック音楽』 フランツ・シューベルト作曲 歌曲集「冬の旅」1828年1月10日、フランツ・シューベルト(1797-1828)が作曲しました歌曲集「冬の旅」前半の12曲が、ウイーンの楽友協会ホールで初演されています。 シューベルトは、31歳という短い生涯で9曲の交響曲、14曲の弦楽四重奏曲、2曲のピアノ三重奏曲、21曲のピアノソナタや多くのミサ曲、合唱曲やオペラなどを書残していますが、彼の名が音楽史上で語られるときに必ず言われるのは「歌曲王」という言葉です。 600曲を超える歌曲を書いたと言われているほど、数多くの歌曲を作曲しています。声楽でも、オペラは登場人物の数だけの歌手、合唱団、オーケストラ、指揮者、演出家、舞台美術・小道具・衣装などを揃えて公演を行なう大プロジェクトとなるのが普通です(コンサート形式は別として)。 そして、これらの大人数によって物語が進められていきます。それに較べると歌曲の世界は、オーケストラ伴奏のある音楽は別として、コンサート・ホールででもピアノ1台と伴奏者(譜面めくりの人1名)と歌手1人という簡素な仕立ての世界で、1曲によって物語が終ってしまうという音楽空間です。 そして深い精神性とそれを心象的に表す光景、風景の世界で人間の幸せ、楽しさ、悲しみ、辛さ、苦しみ、嘆き、喜びなどがわずか数分間という短い曲の中で表現されています。 それは、ドイツの詩人ゲーテやハイネ、ミューラーといった詩人の作った「詩」に歌と伴奏音楽を付けている世界だからです。 「詩」そのものを音楽で表現している世界だからです。そうした歌曲を「連作歌曲」としてシューベルトは、まづ最初に歌曲集「美しい水車小屋の娘」を作曲して、恋に破れた若い男の心理を見事に歌い上げました。今日採り上げました「冬の旅」もミューラーの詩による歌曲集として24曲から構成されていますが、前後の物語性は前作の「水車小屋の娘」のようにはなくて、詩そのものが単独に書かれているのですが、共通していることは失恋した一人の若い男があてのない旅に出て、その旅で経験する色々な出来事や心情を歌っている音楽です。 歌曲集全体としては、暗い、孤独と絶望感に包まれたような音楽ですが、シューベルト独特の抒情と旋律が聴く者の心を打つ歌曲集です。 「おやすみ」「春の夢」「菩提樹」などの、リサイタルで単独で採り上げられる有名曲の含まれた前半12曲が初演された日です。この初演は、亡きベートーベンの棺に泣きながら付き添ってから、まだ1年と経たない日で(ベートーベンの命日は1827年3月29日)、この「冬の旅」初演から約11月後の1828年11月19日にシューベルトは、その短い、不遇な人生を閉じたのです。 この「冬の旅」最後の24曲目の「辻音楽師」は、寒風の中で村のはずれに立って、震えながらオルゴールを手で回しながら歌う老辻音楽師が描かれています。村のはずれに一人の筒琴弾きが立っていて、凍える指でいつまでも筒琴をかき鳴らす。氷の上を、裸足であちこちと歩き回りながら。しかし彼の小さな盆にはいつまでも銭が入らない。誰一人耳をかたむけず誰一人目をとめる者もなく。ただ犬だけがその老人のまわりで吠えたてる。すべてをなすがままに勝手にさせながら、老人は筒琴を奏でその音はいつまでも絶えずに続く。ふしぎな老人よ、お前と一緒に従いて行ってよいだろうか?私の歌にお前の筒琴のしらべを合わせてくれまいか? (訳 高崎保男)この「辻音楽師」に、貧困と不遇な人生を若くして閉じたシューベルトにダブらせてしまうのは、私だけでしょうか?愛聴盤 ディートリッヒ・フィッシャー=ディスカウ(バリトン) アルフレード・ブレンデル(P)(Philips レーベル 464739 1985年録音 ヨーロッパ輸入盤)『今日の音楽カレンダー』1828年 初演 シューベルト 歌曲集「冬の旅」前半12曲1886年 初演 ブルックナー 「テ・デウム」1935年 生誕 シェリル・ミルンズ(バリトン)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『PCが復旧しました』昨日の午後、PCショップ「ジョーシン」のサービス員が叔父宅に出張に来て、PCを診断してから初期化を行い、インターネット接続(無線LAN)を行い、全てPCを購入時に戻す設定が終わり、ウイルス・バスターもインストールして帰りました。 叔父がもう難聴になっているので、私に立ち会って欲しいとの要請があったので、2時間半付き合って叔父の口になってサービス員に説明などを行なってきました。全ての設定が終ると叔父は嬉しそうに、満足そうにしていました。 素人の私や親戚の者に頼むよりも専門家に設定してもらい、「これで明日からまたパソコン生活に戻れる」という安堵感が表情に表れていました。今日からまた私のこのページを訪問してくれるでしょう。めでたし、めでたし。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月10日
コメント(18)
-
フランク 交響曲ニ短調 / 妹に感謝!
『今日のクラシック音楽』 セザール・フランク作曲 交響曲 二短調1887年1月9日、「近代フランス音楽の父」と呼ばれているセザール・フランク(1822-1890)が作曲しました「交響曲ニ短調」が初演されています。フランクはベルギーで生まれた人で、ベルギーはフランス・オランダ・ドイツなどの近隣諸国の文化などから、多分に影響され反映してきた国で、言葉も自国語の他にフランス語、オランダ語、ドイツ語の通用するヨーロッパ(EU)特有の特質を持つ国の一つです。フランクはパリの「パリ音楽院」で音楽の勉強を積み、後に「サン・クロティルド教会」のオルガン奏者として迎えられるほどのオルガン弾きの名手となり、彼も生涯オルガンを愛した音楽家でした。 彼の作品にはオルガン曲が多数あり、バッハのオルガン音楽と並び賞されるほどの名曲が遺されています。 ブルックナーの音楽人生にも例えられる「大器晩成型」の典型で、世に有名となったのは50歳を過ぎてからでした。彼の音楽はフランス流の明快さとドイツ音楽の渋い、重厚さを兼備えている作品があり、ベルギーという国の伝統性がここにも表れているのでしょう。 この「交響曲ニ短調」は、フランクが書きました唯一のシンフォニーで、彼のフランスとドイツの融合した音楽の特質が明確に刻まれている曲です。彼はこの曲で音楽史上に画期的ともいえる「循環形式」を用いています。 この形式は初めに出てくる主題が全曲を通じて表れて、有機的に、まるで単一楽章のように音楽を構成しているのが特色です。 のちにフランスの交響音楽に大きな影響を与えています。音楽はフランス風の軽快さ、明快さとオルガンを愛したフランクらしい重厚な響きに溢れています。愛聴盤 シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団(RCAビクター原盤 JMCXR0018 1957年11月 ボストン録音)1957年というステレオ録音の最初期の演奏ですが、ビクターが開発しましたXrcdという独自のリマスター方式によって、最新の優秀録音と変わらぬ、見事な美しい音質となって蘇っています。もう1枚の愛聴盤 ジャン・マルティノン指揮 フランス国立管弦楽団 (エラート原盤 ワーナーミュージックジャパン WPCS22105)LP時代から好きな演奏で現在はワーナーミュージックからこの型番でリリースされています。『今日の音楽カレンダー』1887年 初演 フランク 交響曲 ニ短調1904年 初演 ドビッシー 「版画」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『妹に感謝!』昨日は体がだるくて起き上がるのが億劫な朝を迎えました。 痛み止め薬を服用する前に、朝食を摂らないと胃に悪いからと思っても布団から出るのが億劫。 昨夜飲んだ薬がもう切れてきているから早く飲まないと、と思っても体がだるくそのままずるずる9時まで。 そこへ妹からの電話。 「兄さん、どう?」と尋ねてくれる。 「痛みは少しましになったけど、体がだるいわ。 痛み止めの薬のせいかな?」とか何とか問答して電話を切ると、母が部屋に入って来て「風邪をひいて7度5分の熱がある」と言う。 これは大変と起き上がって朝食を準備してあげて、私も済ませたがやはりだるい。 とにかく横になっていようと午前中は楽な姿勢でいるとしゃんとしてきた。昼食も済ませてから、妹が来てくれた。 夕食にと水菜と豚肉を煮てくれて、マカロニ・サラダ、オクラの胡麻和えを作り、「おでん」の仕込みまでして帰って行った。今夜はそのおでんを温めるだけ。妹に感謝でした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月09日
コメント(12)
-
アルバン・ベルク 「抒情組曲」 / まだやるの?
『今日のクラシック音楽』 アルバン・ベルク作曲 「抒情組曲」1927年1月8日、オーストリアの作曲家アルバン・ベルク(1885-1935)が作曲しました弦楽四重奏のための「抒情組曲」が初演されています。ベルクは、オペラ「ルル」「ヴォツェック」やヴァイオリン協奏曲、室内協奏曲などを書残しています。 その彼の代表作の一つに「抒情組曲」があります。 この曲は1926年に弦楽四重奏のために書かれており、ピアノ・ソナタや「ヴォツェック」などで調性のない「無調音楽」を作曲した後に、12音技法という新しい音楽技法で作曲されています。 曲は6つの楽章から構成され、テンポの速い楽章と遅い楽章が交互に並べられており、曲想は速い曲は段々早く、遅い曲はもっと遅くなるように書かれています。 第4楽章は彼の師匠シェーンベルクの「抒情交響曲」の第3楽章の旋律が使われています。 ベルクの音楽は現代的な響きに満ちてはいるものの、後期ロマン派の色彩が色濃く残されている音楽で、この「抒情組曲」もそうした色彩があり、叙情的に書かれている曲です。 愛聴盤 ジュリアード弦楽四重奏団(RCA原盤 BMGジャパン BVCC37328 1959年録音)また弦楽合奏版として3楽章構成で編曲された版もあります。『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 シューマン ピアノ五重奏曲1927年 初演 アルバン・ベルク 「抒情組曲」1986年 逝去 ピエール・フルニエ (チェロ奏者 チェロのプリンスと呼ばれたフランスの不世出のチェリスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『まだやるの?』昨年の9月30日の日記に掲載しました「90歳でパソコンを』の叔父のPCが不具合状態になっています。 昨年12月の半ばから調子がおかしくて、親戚の人に一度初期化してもらったのですが、使い勝手が悪くなってしまいました。 叔父は購入時の状態に戻してくれたと思っていたのですが、エクセルとワードのアイコンがデスクトップに表示されず、プログラムを見ても入っていません。 バックアップしてあるCDを挿入すればそれでいいでしょうということらしいのですが。 それに無線LANの接続がどうもおかしい。接続先の表示がおかしいのとパスワード無効の表示が出ます。 叔父は耳が遠くなっているので、PCショップの出張サービスと話をしても聞こえないために、私に話をして欲しいと依頼されました。 PCを購入時の状態に戻して、LANの接続、ウイルス・ソフトの再インストールの作業をジョーシンのサービスマンにやってもらって34,600円かかります。 私が自宅でやってあげると(ノートPCです)言いましたが、プロにきちっとした仕事をしてもらいたいからでしょう、この金額を払ってやってもらうそうです。叔父さんのまだまだやるぞという意気込みが伝わってきます。 自分史もまだ完成半ば。 先月姉になる叔母が亡くなり、寂しい思いでいるのをPCで紛らわそうとしているのか、まだヤル気満々です。我々、若い者は負けていられません。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月08日
コメント(10)
-
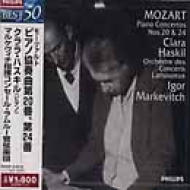
クララ・ハスキルのピアノ / その後のギックリ腰(追記あり)
『今日のクラシック音楽』 クララ・ハスキルのピアノ 「最後の録音」 モーツアルト ピアノ協奏曲第20番ニ短調K.4661895年1月7日、ルーマニア出身の孤高の女流ピアニストのクララ・ハスキル(1895-1960)が誕生した日です。今日はこのハスキルのピアノを、モーツアルトのピアノ協奏曲 第20番 ニ短調 K.466で偲んでみたいと思います。ハスキルは、私が高校生の頃(1962年)から聴き親しんできたピアニストの一人で、深い慰めと、喜びを与えてくれた演奏家でした。彼女が紡ぎ出すピアノ音楽は、悲しさと喜び、暗さと明るさ、重厚さと軽やかさ、といった相対するものが美しく融合しており、それが聴く者の心の琴線に触れてくる稀有なピアニストでした。彼女の指先から奏でられるピアノの音色は、美しく結晶されたようで、音はあくまでも「なめらかに歌う」ようで、ピアノ演奏・技巧の難しさというものを聴き手に感じさせない不思議な魅力のあるピアノでした。 初めて彼女のピアノ音楽を聴いたのはアルトゥーロ・グリュミオー(1921-1986 ヴァイオリニスト)と共演した演奏・録音で、ベートーーベンのヴィオリン・ソナタ第5番(スプリング)と第9番(クロイツェル)でした。 グリュミオーのヴァイオリンの美音よりも、心魅かれたのはハスキルの柔らかさに富んだピアノの音でした。 ベートーベンの美しい音楽を、ハスキルの慰めと喜びと優しさに溢れたピアノに、聴くたびに酔っていました。 しかし、彼女のピアノを初めて聴いた時は、彼女はもうこの世にいない人でした。 それから彼女のピアノ音楽をたくさん聴きましたが、今日紹介しますモーツアルトのピアノ協奏曲第20番 ニ短調が、第24番 ハ短調と共に、彼女の最後の録音(1960年11月)になったレコードでした。「モーツアルトの短調」と呼ばれるくらいに独特の楽想のこれらの2曲を、贅肉をそぎ落としたかのようにスリムで、しかも確固たる古典美で音楽を劇的に推進していく、イゴール・マルケビッチ指揮ラムルー管弦楽団と共に紡ぎ出している音楽は、「ピアノだけが慰めだった」というハスキルの言葉そのものを表している、慰めと深い寂寥感、高雅な憂いの漂っているのを感じます。 彼女はこの録音を終えて3週間後に旅立って逝きました。 まるで私たちにお別れを告げる悲しみのような、深い憂いを湛えた遺言のような音楽で、私にとって永遠・不滅のピアノ演奏の一つです。愛聴盤 モーツアルト ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466 クララ・ハスキル(P) イゴール・マルケビッチ指揮 ラムルー管弦楽団(Philips原盤 ユニヴァーサル・クラシック PHCP21013 1960年録音)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日の音楽カレンダー』1857年 初演 リスト ピアノ協奏曲第2番1895年 生誕 クララ・ハスキル(ピアニスト)1912年 生誕 ギュンター・ヴァント(指揮者)1922年 生誕 ピエール・ランパル(不世出のフルート奏者)1967年 逝去 カール・シューリヒト(指揮者)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『その後のギックリ腰』皆様にご心配をおかけ致しております。 また、多くの方々に励ましの書き込みをいただき、ありがとうございます。容態はあまり変わりありません。 相変わらず立ち上がりや起き上がりには、あっちやこっちに顔を向けながら一番いい位置を探しています。 その格好が面白いのでしょう、母は、私が立ち上がるたびに口を押さえて笑っています。今日の大阪は快晴との予報ですので、駅前の医院に行ってほんとに痛み止めの注射を打ってもらいます。 そうすれば痛みもなくなるでしょう。 今日は必ず行きます。(追記)今朝から医院で診てもらいました。 坐骨神経痛の恐れもなく、X線で診る限りは60歳という年齢にしては、きれいな脊椎で心配はないという診断でした。 この痛みはギックリ腰ではなく体を捻ったときに軟骨が少し出て当たっていることから来るもので、この程度の痛みなら注射でなくて痛み止めの薬であと2日間くらいで治るとの医者の見解で、あらたに薬を5日分貰ってきました。 椎間板に異常がないと判ってホッとしています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月07日
コメント(18)
-
プーランク バレエ音楽「牝鹿」 / 20,000アクセス超えました! / ギックリ腰になってしまった!
『今日のクラシック音楽』 フランシス・プーランク作曲 バレエ音楽「牝鹿」1924年1月6日、フランスの作曲家フランシス・プーランク(1899-1963)が書きましたバレエ音楽「牝鹿」がモンテ・カルロで初演されています。当時はセルゲイ・ディアギレフ(1872-1929)の率いる「ロシア・バレエ団」が全盛のころで、この『牝鹿』が初演される11年前の1913年には、ストラビンスキー作曲のバレエ音楽「春の祭典」がピエール・モントー指揮でこのロシア・バレエ団が初演を行い、未曾有の混乱を起した事件は音楽史上あまりにも有名な話です。そのディアギレフが、プーランクのピアノ曲「常動曲」を聴いてバレエ音楽の作曲を依頼して、完成したのがこの1幕合唱付きバレエ音楽「牝鹿」です。 マリー・ローランサンというフランスの女流画家が書いた絵から着想して作曲されたと言われています。 「牝鹿」(レ・ビーシュ)とは「若い娘たち」という意味で、俗語では「可愛い子ちゃん」という意味があるそうです。バレエは18世紀風の家庭のサロンで開かれるパーティが舞台で、そこに登場する3人の男性と16人の女性が部屋の中を漂うかのごとく往来して、次々と踊りを披露するという内容です。音楽は全部で9曲から構成されており、リズミカルな「序曲」から始まり、「ロンド」(これが有名な旋律です)、シャンソン・ダンスの「舞踏歌」、「アダージェット」、「遊戯」、「ラグ=マズルカ」(アメリカのラグタイムとポーランドの舞曲マズルカの融合した音楽)、「アンダンティーノ」、甘美なシャンソン「小舞踏歌」、「フィナーレ」と続く合唱付きのユニークな35分足らずのバレエ音楽です。愛聴盤 ジョルジョ・プレートル指揮 フィルハーモニア管弦楽団『今日の音楽カレンダー』1838年 生誕 マックス・ブルッフ(作曲家)1873年 生誕 スクリャービン(作曲家)1888年 初演 ドボルザーク ピアノ五重奏曲1924年 初演 イベール 組曲「寄港地」1924年 初演 プーランク バレエ音楽「牝鹿」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『20,000アクセス超えました!』2004年8月17日に開設しましたこのページが、今日真夜中の12時ごろに20,000アクセスを超えました。全くの独断と偏見の音楽と花の日記に、これだけの方々にご訪問いただきましたことを深く感謝申し上げます。これからも頑張って更新を続けてまいりますので、何卒よりいっそうのご支援を賜りたく、重ねてお願いとお礼を申し上げます。 ありがとうございました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『ギックリ腰になってしまった!』4日の夕刻、鶏の水炊きに使う野菜を台所で洗っている時のこと。 少しからだ捻って洗った野菜をザルに上げようとしたときに、腰に少し違和感を感じていましたが、そのまま立ち仕事をしていると、段々と腰に痛みが出てきて食事をした後に立ち上がろうとすると腰に痛みが走り、思うように立ち上がれなくなってしまいました。 しばらく布団を敷いて横になったのですが、今度は起き上がりが出来ない。 あっちを見たり、こっちを見たりしながら手をつくところを探しながらようやく起き上がれるという無様な姿になってしまいました。それでもベートーベンの「熱情」ソナタの日記をどうやら書き終えて、寝たのですが5日は横になったり起きたり、冷蔵庫の中の食材がないので駅前まで自転車で買い物に出かけたのが悪かったのか、また痛みがひどくなってきました。今日の日記(プーランク)を書き終えてホッとしています。 叔父さんから貰った痛み止めの薬を飲んでこれから寝ますが、朝の痛みの様子では医院に行って痛み止めの注射を打ってもらおうと思っています。寒さの中の腰の痛みはこたえます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月06日
コメント(18)
-
ベートーベン ピアノソナタ第23番「熱情」 / 福寿草
『今日のクラシック音楽』 ルードヴィッヒ・V・ベートーベン作曲 ピアノソナタ第23番ヘ短調 作品57「熱情」今日は有名なピアニストにちなむ日です。1920年 誕生 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ1931年 誕生 アルフレート・ブレンデル1974年 逝去 レフ・オボーリンこの3名が1月5日に生まれたり、亡くなったりしています。 いままでにベートーベンのピアノ曲を採り上げたのは2回(月光ソナタとピアノ協奏曲第5番)だけでしたので、今日はこれらのピアニストに因んでベートーベンのピアノソナタ 第23番 ヘ短調 作品57「熱情」を採り上げました。J.S.バッハの「平均律クラヴァイーア曲集」が「旧約聖書」と呼ばれ、ベートーベンの書いた32曲のピアノソナタが「新約聖書」と呼ばれ、音楽史上に燦然と輝くピアノ音楽の金字塔のようなベートーベンのソナタの中でも、最高傑作に数えられるピアノソナタが「熱情」です。どの音楽でも副題が付けられている曲には親しみが持てるものです。 音楽には「絶対音楽」と「標題音楽」という大きな分け方がありますが、副題とか標題のない曲よりもあった方が親しみを感じます。 交響曲でもベートーベンの「田園」とかチャイコフスキーの「悲愴」、ドボルザークの「新世界より」などがあります。 聴く前から何となくイメージしやすいのでしょうか。 ベートーベンのピアノソナタにも副題のついている曲が多くあります。 「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」「告別」「テンペスト」そしてこの「熱情」です。しかし、この「熱情」は彼自身が付けたものでなくて、曲のイメージから出版社によって付けられたそうですが、じつに楽想を言いえて妙なる名前です。曲は力強く、情熱の迸りと不屈の闘志のようなものが表現された、ベートーベンの雄渾なピアニズムを明確に表している屈指の名作ソナタだと思います。 この「熱情」ソナタを作曲している頃は有名な交響曲第5番「運命」を書いていた時期「傑作の森」と呼ばれているベートーベン中期の頃で、このソナタはあの5番の「運命の動機」が頻繁に現れてきます。 第1楽章、終楽章(第3楽章)は「熱情」そのものの楽想ですが、私はむしろ第2楽章のアンダンテ・コン・モートの主題が八分音符、十六分音符、三十二分音符に変奏されていくさまの美しさが一番好きなところです。愛聴盤 アルフレード・ブレンデル(ピアノ) 及び ウィルヘルム・バックハウス(ピアノ)(ブレンデルの演奏 Philips レーベル PHCP20013) しなやかで一音一音が研ぎ澄まされたような、知的とも言えるブレンデルのピアノ藝術です。(バックハウスの演奏 DECCA原盤 UCCD70012 1959年録音)正確無比な、堅牢・重厚でスケールの大きさにいつ聴いても圧倒される、まさにこれぞドイツのピアノ音楽という演奏で、最近はこういうピアノ演奏を聴けなくなったのが淋しいかぎりです。 1962年購入のLP盤以来愛聴している録音盤です。カップリングはベートーベン4大ソナタの「悲愴」「月光」「ワルトシュタイン」「熱情」です。『今日の音楽カレンダー』1920年 生誕 アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ(ピアニスト)1931年 生誕 アルフレード・ブレンデル(ピアニスト)1974年 逝去 レフ・オボーリン(ピアニスト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月05日
コメント(10)
-
ペルゴレージ 「マンドリン協奏曲」 / お年玉の由来
『今日のクラシック音楽』 ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ作曲 マンドリン協奏曲 変ロ長調1710年1月4日、イタリアの作曲家ジョバンニ・バティスタ・ペルコレージ(1710-1736)が生まれた日です。彼はモーツアルトにも較べられるほどの有り余る音楽の才能を持ちながら、わずか26歳という若さでこの世を去った作曲家でした。 26年という短い人生で、作曲活動を行なったのは5年間だけだったと言われています。劇音楽や宗教音楽、室内楽に多くの曲を書残しているそうです。 歌劇「奥様女中」や宗教曲「スターバト・マーテル」などは今尚演奏されている傑作です。ところが、その死後に彼の人気は急騰して、色々な偽物作品まで彼の作として出版されたために、後世では彼の音楽の年譜も作成することが難しくなり、謎の多い作曲家となってしまいました。今日はそのペルゴレージの誕生日にちなんで、彼の作曲しました「マンドリン協奏曲 変ロ長調」を聴くことにします。実際には、この曲も確かに彼の作品であるという確証がないそうで、楽想からそうだろうという憶測が定説となり、今では彼の曲となっているそうです。3つの楽章からなる伝統的な協奏曲スタイルで、マンドリンの魅力がふんだんに味わえる音楽です。 明るく、典雅な第1楽章、シチリアーナと呼ばれる情緒いっぱいの第2楽章、マンドリンの独奏がきらびやかな第3楽章の、20分ほどの音楽です。愛聴盤 ジュゼッペ・アネッダ(マンドリン) クラウディア・シモーネ指揮 イ・ソリスティ・ヴェネティ(エラート原盤 BMGビクター B15D-39204 1971年録音)カップリングはC.チェチェレーレ(18世紀)とG.ジュリアーノ(18世紀)のマンドリン協奏曲です。『今日の音楽カレンダー』1710年 誕生 ジョバンニ・バティスタ・ペルゴレージ1881年 初演 ブラームス 「大学祝典」序曲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『お年玉の由来』人は毎年年齢を一つ増えていきます。新しい歳を生きるための生命エネルギーを歳魂(としたま)と呼ばれていて、これを「歳神」から与えられると古代から信じられていて、形にしたものが餅だそうです。古くは小さな丸餅を家族の数だけ神棚に供えて拝礼して、これを降ろして食べていたそうです。これが江戸時代になって「お金」に替わり、親から子供へのお年玉としてあげるようになったそうです。歳神によって家長に与えられた魂が、親から子へ、あるいは主人から使用人へと与えられるようになり、正月に贈られる金銭や物品のすべてを「お年玉」というようになったそうです。年玉は上から下へ贈られるものなので、年長者、例えばおじいさん、おばあさん、に贈るときは「お年玉」と書かずに「年賀」と書くのが作法だそうです。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月04日
コメント(8)
-
チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」 / 残った小餅
『今日のクラシック音楽』 チャイコフスキー作曲 バレエ音楽「眠りの森の美女」チャイコフスキーは、その生涯で交響曲を6曲、協奏曲ではピアノやヴァイオリンなど、それに室内楽作品、管弦楽曲、オペラ、歌曲など数多くの作品を書残していますが、バレエ音楽でも素晴らしい作品を書いています。 所謂「3大バレエ音楽」と呼ばれているもので「白鳥の湖」「くるみ割り人形」そして今日、話題の「眠りの森の美女」の3つです。1890年1月3日このバレエ音楽「眠りの森の美女」が旧ロシアのペテルブルグ・マリンスキー劇場で初演されました。物語はフランスの童話作家ペローが書いた有名な物語で、17世紀ごろの話で、国王に女児が生まれてオーロラ姫と名付けられ盛大な宴会が開かれますが、邪悪な妖精カラボスが招待されなかったので、オーロラ姫に呪いをかけ、その呪い通りに成人になった姫が紡錘で指を指して眠りにつきますが、100年後に狩りに来ていたデジレ王子が「リラの精」に誘われて城に入り、姫を眠りから目覚めさせるという話です。全曲で3時間ほどかかる大曲で、他の2曲「白鳥の湖」「くるみ割り人形」などに較べると、規模が大きく、シンフォニックな響きで、華麗・流麗な音楽が全編に流れています。「序奏とリラの精」「バラのアダージョ」「パノラマ」「ワルツ」など聴きどころの音楽がいっぱいの、チャイコフスキー独特の美しい旋律にあふれたバレエ音楽です。愛聴盤 アンタル・ドラテイ指揮 ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団(Philipsレーベル 466166 1979-81年録音 ヨーロッパ輸入盤)このCDは2枚組みの全曲盤で、華麗で流麗なコンセルトへボウ管弦楽団の演奏がこのバレエ音楽の魅力をいっぱいに引き出して聴かせてくれます。『今日の音楽カレンダー』1843年 初演 ドニゼッティ オペラ「ドン・パスクヮーレ」1890年 初演 チャイコフスキー バレエ音楽「眠りの森の美女」1925年 フルトヴェングラー(指揮者)ニューヨーク・デビュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『残った小餅』この村の神社は、新年の参詣には大晦日に社務所奥にある神殿前に賽銭箱と鈴を移して、参詣客を迎え入れて参拝してもらい、元旦の早朝3時ごろに閉めて、正月の参拝は社務所外で行なってもらいます。 正月からは社務所は無人です。大晦日にほとんどの人が参拝してくれるので、正月3が日はほとんど参拝がありません。 それで大晦日には参拝客に小餅とお神酒を振舞っています。 ところが今度の大晦日は、寒風が吹き荒れて例年の予想参拝客ほどもなく、用意していた小餅がたくさん残ってしまいました。それで役員全員で残った小餅を分けたのですが、我が家ではまるで3年分の正月用の数ほどあって困るくらいになりました。 大晦日にわざわざ和菓子屋に自宅用として頼んだ小餅もあったのですが、その数の3倍ほども貰って帰って来ました。 毎食小餅を食べている正月を過ごしています。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月03日
コメント(14)
-

ワーグナー オペラ「さまよえるオランダ人」
『今日のクラシック音楽』 リヒャルト・ワーグナー作曲 オペラ「さまよえるオランダ人」1843年の今日(1月2日)、リヒャルト・ワーグナー(1813-1883)が作曲しましたオペラ「さまよえるオランダ人」がドイツ・ドレスデン宮廷歌劇場で初演されました。このオペラはワーグナーが書いたロマンテイック・オペラの一つで、オペラ作曲家として世に認められるオペラとなった成功作で、ワーグナーが生涯音楽を通して訴えた「人間の業が愛によって救われる」という考えを表現したオペラです。物語は、16世紀のノルウエーの港で、海の荒くれ男たちでも恐れる幽霊船。 その船長は呪いのために死ぬこともできず、海をさまよい続けています。 ただ7年ごとに上陸することを許されています。 その上陸の際に永遠の愛と誠を持った女性を見つけるまでは、彼は永遠に救済されることのない呪いに縛られています。嵐を避けて碇泊していたダーラント船長は、折からやって来た幽霊船が積んでいる金銀財宝に目がくらんで、娘のゼンタと結婚してくれるようにと幽霊船の船長、オランダ人に申し出ます。 そのゼンダは祖母よりオランダ人の伝説を聞かされて育っていて、いつしかオランダ人を救えるのは自分だと思っていたのです。そこへオランダ人が現れました。 彼女には恋人エリックがいました。 訝しく思うエリックを振り切ってゼンダはオランダ人と結婚しようとします。 しかし追ってくるエリックと、ゼンダの姿を見たオランダ人は絶望して、錨を上げて出航しようと決意します。 自分が背負っている業罰をゼンダに話します。 そして幸福な人生を歩むようにと告げて岸から離れていきます。しかし、ゼンダは狂ったように岩壁を登り、オランダ人への永遠の愛を誓って海に身を投げてしまいます。 すると幽霊船が海中に沈んで行き、そのあとオランダ人とゼンダは浄化されて天に昇って行くところで幕となります。ワーグナーはまだ世に認めてもらえない不遇時代に、ロンドンから帰国の船旅で嵐を避けるためにノルウエーに逃れた時に、船員からこの「オランダ人伝説」を聞いて、ドラマとして実感したので、作曲するきっかけを得たとされています。後に「楽劇」へ、「無限旋律」へと変化して行く前のロマティック・オペラとして書かれているため、音楽は歌謡性に富んでいて聴きやすいオペラとなっています。愛聴盤 ジェイムズ・モリス(オランダ人) デボラ・ヴォイト(ゼンダ) ベン・ヘップナー(エリック) ジェイムス・レヴァイン指揮 ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場管弦楽団・合唱団 (ソニークラシカル SRCR 1872-3 1977年4-5月 N.Y録音) 『今日の音楽カレンダー』 1843年 初演 ワーグナー オペラ「さまよえるオランダ人」1881年 初演 サン=サーーンス ヴァイオリン協奏曲第3番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月02日
コメント(8)
-
シューマン ピアノ協奏曲
謹賀新年新年明けましておめでとうございます。新年を迎えまして、昨年は多くの皆様方にご訪問いただきましたことをここに改めてお礼申し上げます。今年はたくさんの方々の「癒しの場」となれますように願いながら、「毎日日記の更新を続けること」を目標に、好きなクラシック音楽について、できる限り毎日書き綴けていけるように頑張っていく所存です。 四季折々の花の写真も出来る限るアップしてまいります。今年も何卒よろしくお願い申し上げます。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・『今日のクラシック音楽』 ロベルト・シューマン作曲 ピアノ協奏曲 イ短調 作品541846年1月1日、ロベルト・シューマン(1810-1856)が作曲しましたピアノ協奏曲 イ短調 作品54が、ドイツ・ライプチッヒのゲバントハウスで初演されています。シューマンは、ピアノ音楽をこよなく愛した人で、数多くのロマンの香り豊かなピアノ音楽を 書残しています。 ピアノ協奏曲はこの「イ短調」1曲だけが今日では演奏されています。 若い頃には習作として作曲を手がけていたそうですが、この「イ短調」は1841年に「ピアノと管弦楽のための幻想曲」として、1楽章構成で書かれていたのですが後年になって協奏曲の形式として2楽章、3楽章として書き綴って完成されたそうです。曲は華麗なピアノ・カデンツアで始まるヴィルトーゾ的な(巨匠風)序奏から始まり、ロマン溢れる美しい旋律で散りばめられており、ショパンの曲と共に「ロマン派」を代表する美しいピアノ協奏曲です。初演時は、後に音楽史上に残る「夫婦愛」で語られています、愛妻クララ・シューマンのピアノ、メンデルスゾーンの指揮・ライプチッヒゲバントハウス管弦楽団で演奏されたそうです。愛聴盤 ラド・ルプー(ピアノ) アンドレ・プレヴィン指揮 ロンドン交響楽団(DECCA レーベル 466383 1973年録音 旧LONDON レーベル F28L-28012)「千人に一人のリリシスト」というとてつもない例えで賞賛されたラド・ルプーが遺した録音の1枚で、彼の感性を物語るしなやかな、豊かな美音が聴けるアナログ録音時代の遺産だと思います。 録音も非常に優秀で、見事にルプーのリリシズムの溢れるピアノの美しい音を表現しています。『今日の音楽カレンダー』1846年 初演 シューマン ピアノ協奏曲1879年 初演 ブラームス ヴァイオリン協奏曲1894年 初演 ドボルザーク 弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2005年01月01日
コメント(12)
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
-

- 洋楽
- ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・…
- (2025-11-25 04:17:42)
-
-
-

- いま嵐を語ろう♪
- 嵐ライブ2026生配信を見逃さないため…
- (2025-11-23 20:15:02)
-
-
-
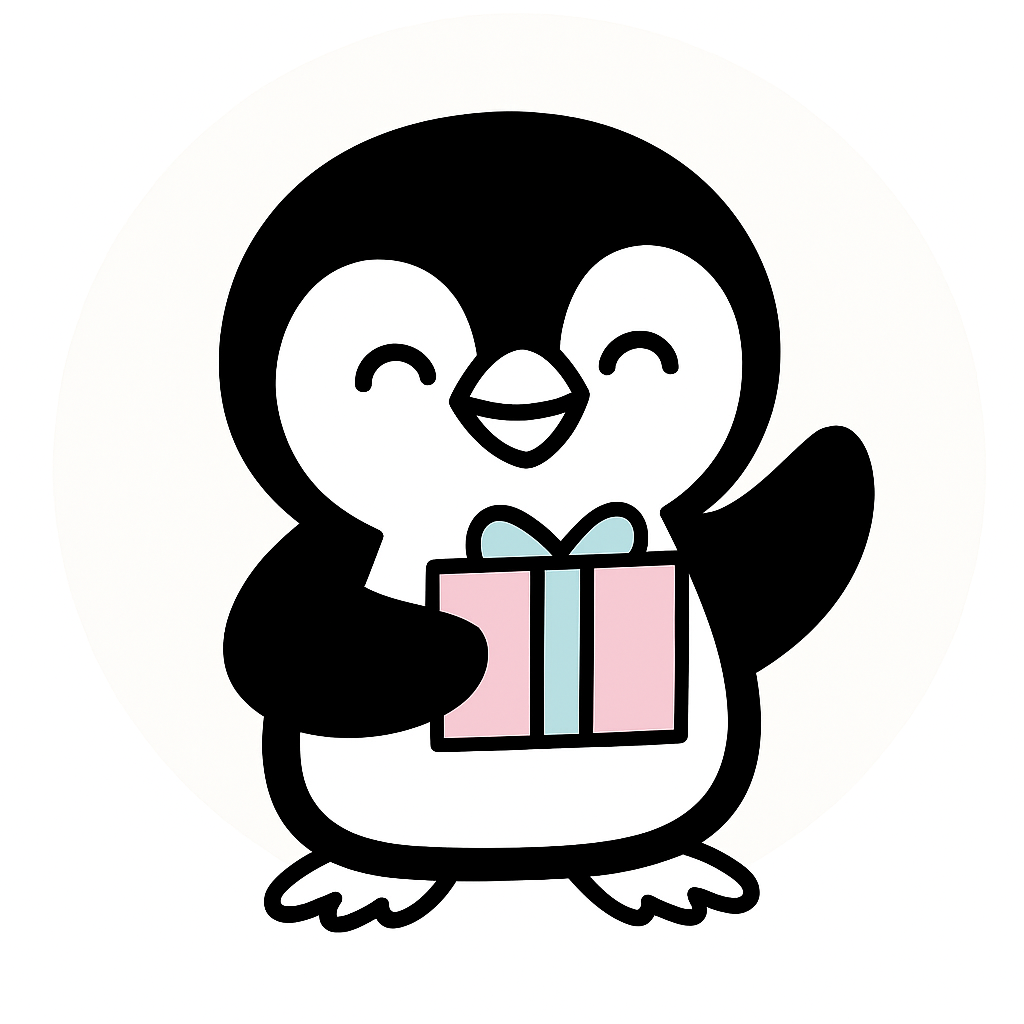
- やっぱりジャニーズ
- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…
- (2025-11-20 16:44:46)
-







