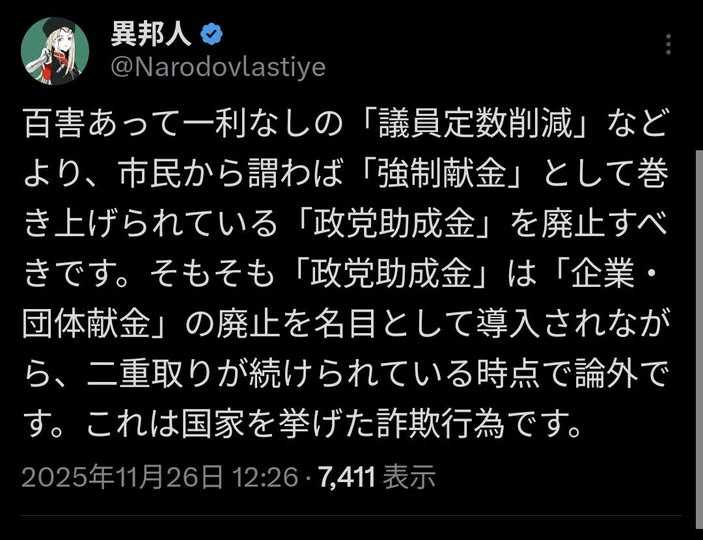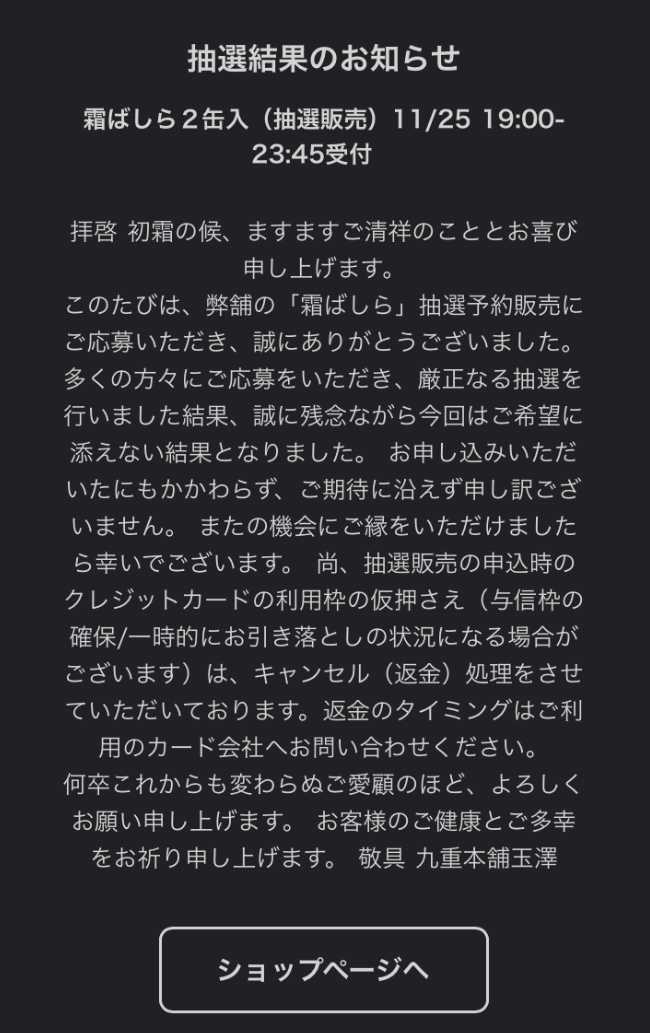全467件 (467件中 1-50件目)
-
休止中のままで申し訳ありません。
みなさんこんにちは。「バス停地名学のすすめ」へご訪問いただき、ありがとうございます。相変わらずの休止状態で申し訳ございません。過去記事でお楽しみいただければ幸いです。尚、本ブログのリライト版として、ライブドア主催の「みちくさ学会」に「バス停」カテゴリで寄稿しております。よろしければ、そちらもご参照下さい。また、こちらを休止中であるにもかかわらず、新たに都電の軌跡を訪ねて歩くブログを開設しています。かつて都心を網羅した全41路線を、歩いて完乗してみようという試みです。ご興味のある方は是非、ご参照下さい。「歩いて完乗 懐かしの都電41路線散策記」ついでながら、私の著書はこちらでご紹介しています。
2011.12.13
コメント(0)
-
もうしばらく休止します
みなさん、こんにちは。ブログの更新が長期にわたり休止中となってしまい、誠に申し訳ありません。諸事情により、再開までもうしばらくお待ちください。尚、ライブドア社主催の「みちくさ学会」にて、私の連載を開始することとなりました。タイトルは本ブログと同じく「バス停地名学のすすめ」です。本ブログの過去のアーカイブから厳選の上、再訪・リライトの上で掲載していきます。ぜひご覧ください。
2010.07.07
コメント(0)
-

第424回 【都電の残像編(78)】 大和町(やまとちょう) 後編
(前回からのつづき)ここには古くから榎と槻の木が並んでいたことから、エンツキ(縁尽)と呼ばれて忌み嫌われ、嫁入りや婿入りの行列がこの下を通ると不縁になるといわれていました。寛延2年(1749)に八代将軍吉宗の嗣子家治に降嫁した閑院宮直仁親王の息女五十宮(いそのみや)の一行や、文化元年(1804)に十一代将軍家斉の世子家慶に降嫁した有栖川宮織仁親王の息女楽宮(さぎのみや)の一行は、縁切榎を避けて中山道西側を迂回する根村道から江戸へ入ったといわれ、文久元年(1861)に孝明天皇の妹和宮が十四代将軍家茂に降嫁した際は、縁切榎を菰で包み隠してしまったと伝えられます。また、女性がこの榎の樹皮を削って男性に煎じて飲ませると、男性から離縁されるという信仰も広まり、離縁の自由を持たない封建制度下の女性に支持されてきたともいわれます。もとは街道西側にあったもので、初代の榎は明治17年の火災で焼失、二代目も伐られ、三代目から現在地に移り史跡として整備されたようです。奥に小さな祠がありますが、その手前には二代目の幹の表皮をコンクリートで固めた石碑が残されています。旧道をさらに進むと、左手の交番の先に「本町にぎわい広場」という小公園がありますが、隅に江戸時代の櫓を模したような建物(倉庫?)が建ち、その扉の部分に『江戸名所図会』から「板橋宿」と「乗蓮寺」の2枚が掲げられています。乗蓮寺は板橋宿第一の名刹として知られた寺で、この先の仲宿商店街の遍照寺の少し先を国道側に入ったあたりにありましたが、都電廃止後の昭和48年、国道拡幅工事の際に板橋区赤塚5丁目へ移転し、現在では東京大仏の寺として知られています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.05.06
コメント(0)
-

第423回 【都電の残像編(77)】 大和町(やまとちょう) 前編
バス停データ◆所在地:板橋区 ◆路線:国際興業バス[赤20]系統他みなさん、こんにちは。都電18系統の残像を辿り、国道17号をさらに南下すると、やがて環七通りと交差する大和町交差点に辿り着きますが、ここがかつての大和町電停跡地であり、現在も交差点の南側に国際興業バスの大和町バス停が立っています。環七通りの開通が、東京オリンピック直前の昭和39年だったため、電車開業時から廃止に至るまでの期間、電停周辺の景観の変遷には著しいものがあったと思われます。交差点から環七通りを西へ少し歩くと、右手方向に富士見街道が分岐していきます。中山道の枝道として古くは練馬道とも呼ばれた古道で、川越街道の下練馬宿方面へと通じていました。地図でその道筋をおおよそ追いかけていくと、下練馬では大山への参詣道であった富士街道に通じていることから、中山道から大山、富士方面への往還の歴史をかすかに感じ取ることができます。交差点の東側で国道と並行する商店街が、旧中山道の道筋です。坂町商店街と呼ばれる通りを歩いていくと、やがて緩やかな下り坂となりますが、ここは古くから岩の坂と呼ばれています。戦前は板橋宿の衰退によりスラム化の進んだ貧民窟として知られたようですが、現在は勿論その面影は一切見られません。そして、坂下左手の一画には、江戸時代から縁切榎と呼ばれてきた史跡が見えてきます。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.05.02
コメント(0)
-

第422回 【都電の残像編(76)】 清水町(しみずちょう) 後編
(前回からのつづき)バス停先の交差点を右へ入ると、どこか懐かしい昔ながらの商店街が西へ続いています。イナリ通り商店街で、街灯に「霊験 水の鎮守さま 清水稲荷神社 参詣道」の文字が見えます。しばらく歩くと、右手にその清水稲荷の境内が見えてきます。国道西側の清水稲荷周辺は、清水町ではなく宮本町になりますが、清水町一帯は、明治の中頃までは前野村と呼ばれたうちの一部で、村内5ヶ所の湧水から清水の地名が生じたといわれます。この清水稲荷も、古くはこの清水町の湧水の傍らに祀られたものと伝えられています。境内には推定樹齢500年ともいわれるイチョウの大木が数本見られるほか、農器具などを収蔵した小さな清水資料館もあります。国道へ戻る途中、改めてイナリ通り商店街をゆっくりと見て歩くと、狭い通りに面した150メートルほどの小さな商店街ですが、そこそこ人通りも多く、地域に根付いた活気のある商店街であることに気付かされます。月に一度の朝市や初夏のほおずき市などが恒例のようで、駅前という立地ではありませんが、各店舗が呼吸を合わせて町おこしに取り組んでいる姿勢が、私のような散歩者にもひしひしと伝わってくる思いがします。ちょうど清水稲荷の向かい側には、「コン太村」の看板を掲げた駄菓子店があり、懐かしいコインゲーム機などを集めた駄菓子博物館として、都電時代にも通じる昭和の香りをぷんぷんと漂わせています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.29
コメント(0)
-

第421回 【都電の残像編(75)】 清水町(しみずちょう) 前編
バス停データ◆所在地:板橋区 ◆路線:国際興業バス[池20]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電18系統の残像を追いかけ、前回ご紹介の蓮沼町交差点から国道17号をさらに南へ歩き進むと、やがて右手から首都高速5号線の高架が近づき、国道の上空をすっぽりと覆い隠すようになります。この先、西巣鴨まで、国道は首都高速の屋根の下が続きます。その首都高速の高架がちょうど国道上に覆いかぶさる位置に、小さな交番があり、その左手から細い通りが国道に並行するように分岐していきますが、これが旧中山道の道筋になります。ここから旧板橋宿や庚申塚を経てJR巣鴨駅前まで、およそ5キロに及ぶ長い旧道区間が続いています。その大半は商店街で人通りも多く、旧品川宿を中心とした東海道の旧道区間同様、散策を楽しむ人の姿も多く見受けられます。早速旧道を歩いてみたい気持ちをぐっと押さえ、もうしばらく我慢して首都高速下の国道を歩いていくと、間もなく国際興業バスの清水町バス停が見え、そのすぐ先の交差点が、かつての清水町電停の跡地となります。清水町は国道東側の町名です。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.23
コメント(0)
-

第420回 【都電の残像編(74)】 蓮沼町(はすぬまちょう) 後編
(前回からのつづき)蓮沼の地名は、多摩川に近い大田区西蒲田にも見られますが、大きな川が永年に渡り氾濫を繰り返したことで流路が変わり、その跡地が沼となり、ハスが繁茂した様子が地名となったものと考えるのが自然かと思われます。蓮沼の集落がもともとは荒川右岸の低地にあり、氾濫を避けて高台のこの地に移った経緯は、前回ご紹介した南蔵院や氷川神社の移転から想定される通りです。都営地下鉄三田線の駅名が蓮沼ではなく本蓮沼となったのは、大田区の東急蓮沼駅との区別のためでしょうか。板橋区成立以前は、志村の大字として、この付近を本蓮沼と称していましたが、これは荒川右岸からの移転により村が低地と高台の二ヶ所になり、低地側の一部が上蓮沼村として独立したのに対し、残りを本蓮沼村としたことに起因しています。昭和7年の板橋区起立後は、本蓮沼のうちの高台部が志村本蓮沼町となり、同36年から現在の蓮沼町のかたちになっています。本蓮沼駅の開業はその後の昭和43年ですから、町名としては既に消滅していた本蓮沼の名を、地下鉄の駅名が復活させた格好にもなっています。因みに、都営地下鉄三田線にはもうひとつ、似たような駅名で蓮根駅があります。こちらは前述の上蓮沼村と根葉村が合併して蓮根村となったことに由来しています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.19
コメント(0)
-

第419回 【都電の残像編(73)】 蓮沼町(はすぬまちょう) 前編
バス停データ◆所在地:板橋区 ◆路線:国際興業バス[池20]系統他みなさん、こんにちは。前回ご紹介した、かつての都電18系統、小豆沢電停跡地から国道17号をさらに南へ歩くと、間もなく左手にしだれ桜の名所として知られる南蔵院が見えてきます。もともとは荒川右岸の低地にあり、八代将軍吉宗が鷹狩りに訪れる際の休憩所にもなっていた由緒を持つ寺院ですが、度重なる川の氾濫を避け、享保9年(1724)に高台のこの地に移りました。その南側には、旧蓮沼村の鎮守である氷川神社があります。こちらも南蔵院とほぼ同時期に、荒川の氾濫被害からこの地に移転しています。これらの動きは、おそらく村そのものが川沿いから高台へと移転したことを物語っているのでしょう。氷川社は氾濫の度に社地を転々としてきたようで、「十度の宮」の俗称があったと伝えられます。やがて国道17号は、都営地下鉄三田線本蓮沼駅のある蓮沼町交差点に辿り着きますが、ここがかつての蓮沼町電停の跡地であり、現在も国際興業バスの蓮沼町バス停が立っています。駅の入口がすぐ目の前であるにもかかわらず、バス停名が都電時代から蓮沼町のまま不変な姿に、私のような散歩者は拍手を送りたい気持ちになります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.15
コメント(0)
-

第418回 【都電の残像編(72)】 志村坂上(しむらさかうえ) その4
(前回からのつづき)かつての都電18系統を辿り、坂上交差点から国道17号を板橋方面へ歩き始めると、すぐに志村のランドマークでもある志村一里塚が見えてきます。一里塚の跡地は全国でも多数確認されていますが、大半は明治期以降の交通事情、特に主要街道の道路拡幅によりその姿を消してしまっている中、この志村一里塚は国道17号の整備に合わせて復元が施され、道の両側にほぼ完全な姿で残された全国でも珍しい事例となっています。板橋宿の入口、平尾の一里塚が日本橋から二里目、ここ志村は三里目となります。東側の塚は、国道の歩道がわざわざ塚を迂回するような形になっており、西側の塚に「国指定史跡 志村一里塚」の碑が立っています。東側には塚に隣接して籠や箒といった竹細工による日用品を扱う古い商家があり、この組み合わせは都電時代から変らぬ景観と思われますが、これらは「活き粋いたばしまちなみ景観賞」にも選出されているとのこと。殺伐とした国道沿いにあって、オアシスのような一里塚周辺の景観は、街道の歴史を後世に伝える意味でも、貴重な存在となっています。一里塚を過ぎ、右手に凸版印刷の工場を見ながら、その角の交差点を右へ入ると、工場裏手の台地下に大きな湧水池のある見次公園があります。「見次」とは変わった地名ですが、古くに「貢(みつぎ)」、すなわち年貢の集積地だったことに由来する地名という説があります。この付近の国道17号東側には小豆沢の地名がありますが、諸説ある小豆沢の地名由来のひとつに、平将門が貢物の小豆を船で搬送中に難破し、この付近に小豆が流れ着いたとする説があるそうで、「貢」つながりの関連地名として、興味がそそられます。かつての都電18系統には、凸版工場の少し先に、小豆沢町電停があり、現在もその跡地には、国際興業バスの小豆沢バス停が立っています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.11
コメント(0)
-

第417回 【都電の残像編(71)】 志村坂上(しむらさかうえ) その3
(前回からのつづき)旧中山道は、これより清水坂の急な下りにさしかかります。江戸を出発した中山道が、武蔵野台地から荒川南岸の低地へ駆け下りる難所として知られたこの坂は、現在でもS字にカーブした急坂で、近くの大善寺の薬師如来を八代将軍吉宗が清水薬師と唱えさせたことが清水の地名、坂名の由来となっていると伝えられます。古くは志村城の千葉隠岐守信胤が坂の補修をしたことから隠岐坂の名があり、現在は国道東側の総泉寺境内に見ることのできる子育地蔵尊が、もとはこの坂沿いにあったことから、地蔵坂の名もありました。坂が左手に大きくカーブするあたりは、旧中山道の江戸から京都までの道中で、唯一富士山を右に見たといわれる場所で、俗に右富士(京都から江戸へ向かう場合は左富士)と呼ばれた名所でもありました。このままもうしばらく旧道を歩き進めたい衝動に駆られますが、この先は都電41系統をご紹介する機会に改めて訪ねることとし、今回は坂上交差点へ戻ります。改めて交差点から坂下方向を見通すと、右手に見える大きな寺院が、総泉寺です。江戸時代、芝の青松寺、高輪の泉岳寺とともに江戸三箇寺のひとつと数えられた総泉寺は、康正2年(1456)に橋場(現在の台東区橋場)に創建されました。幕府からの厚い庇護を受け大きな勢力を持つに至りますが、数度の火災と震災により伽藍を失った後、昭和4年の区画整理で志村のこの地への移転となり、現在山門の奥に見ることのできる大きな本堂は、近年改築されたばかりの新しい建物となっています。境内左手の地蔵堂に安置されている子育地蔵尊が、先ほどご紹介の通り、かつて旧道の清水坂にあったものになります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.07
コメント(0)
-

第416回 【都電の残像編(70)】 志村坂上(しむらさかうえ) その2
(前回からのつづき)志村の地は、荒川南岸の低地と武蔵野台地の接点にあたり、起伏の多い地形が特長となっています。地名は、篠竹が生い茂った場所を意味する「しの村」が変化したものという説がありますが、定かではないようです。国道が台地上から荒川に向けて一気に下るのが志村坂で、昭和30年に開通した都電志村線の延長部(41系統)は、この坂を下って新河岸川を渡す志村橋まで通じていました。志村坂上交差点のすぐ先にある坂上交番の手前で国道から分岐し、左手に入っていく細い通りが、旧中山道の道筋にあたります。特に旧道の案内表示はありませんが、歩道がタイル敷きになっているのが目印です。旧道をしばらく進むと、左手へ別れる道との角に、庚申塔と道標が並んで立っている場所があり、道標の方は現在でも「大山道ねりま川こへみち」と刻まれた文字をはっきりと読み取ることができます。この場所は中山道から相模国(現神奈川県)大山、及び富士山方面へ向かう道との分岐点にあたるようで、道標は寛政4年(1792)、庚申塔は万延元年(1860)のものとされています。武蔵国岩槻(現埼玉県岩槻市)から武蔵府中を経て大山へ至る大山道の一部が、この地を通過していたものとも推測されています。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.04.03
コメント(0)
-

第415回 【都電の残像編(69)】 志村坂上(しむらさかうえ) その1
みなさん、こんにちは。いつも「バス停地名学のすすめ」をご訪問いただき、ありがとうございます。さて、本ブログも今月末をもちまして、開設3周年を迎えることができました。連載回数も400回を越え、都心を中心に、数多くのバス停訪問ミニトリップにお付き合いいただきました。その間、たくさんの書き込みやメールを頂戴し、感謝の気持ちでいっぱいです。これから4年目に突入いたしますが、品川駅前からスタートした【都電の残像編】も、ようやく18系統のご紹介に入ります。その起点の志村坂上が、これから訪ねるバス停ですが、今回は満3周年記念として、全4回シリーズでお届けしたいと思います。それでは早速、お楽しみ下さい。---------------------バス停データ◆所在地:板橋区 ◆路線:国際興業バス[池20]系統他中山道(国道17号)を走ったかつての都電18系統は、姉妹路線の41系統とともに「志村線」の愛称で呼ばれることが多く、「杉並線」こと14系統と同様に、郊外路線的な性格を持ち合わせた系統でした。都心側から次第に伸びてきた線路は、大正元年に巣鴨車庫までが開業。その後、昭和4年に下板橋(後の板橋駅前電停の少し手前)まで、同19年に志村坂上(当初は志村)までが開業しました。志村への延伸にあたっては、沿線住民の協力も大きかったようで、まさに地元に必要とされ、大切にされた路線でもありました。18系統の路線を地図で確認すると、全区間が後の都営地下鉄三田線に踏襲されていることがわかります。その三田線(6号線)の敷設免許が昭和39年に許可されると、翌年から工事が開始されましたが、交通量の多い中山道での工事は渋滞必死と予測され、その工事用地確保と渋滞緩和策として、都電の廃止が決定しました。「杉並線」が地下鉄開業後もしばらく競合関係として存続したのに比べ、「志村線」が工事段階で廃止となったのは、事業者が同じ東京都交通局だったことも一因だったかもしれません。中山道と小豆沢通り、城山通りとの交差点が、18系統の起点、志村坂上電停の跡地です。国道の下には都営地下鉄三田線の志村坂上駅があり、交差点そばには国際興業バスの志村坂上バス停があります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.30
コメント(0)
-

第414回 【都電の残像編(68)】 一ツ橋(ひとつばし) 後編
(前回からのつづき)一ツ橋交差点から白山通りをもうしばらく先へ進むと、日本橋川を渡す一ツ橋の北詰に出ます。かつての都電の線路はここを左折し、日本橋川に沿って神田橋方向へと通じていました。日本橋川の上空は首都高速都心環状線の高架で蓋をされ、日の当らない川面は薄暗く淀んでいますが、一ツ橋は大正14年竣工のコンクリート橋がまだ現役の姿を見せており、都電時代を見つめてきた貴重な土木遺産のひとつにここでも触れることができます。橋は家康の江戸入府の頃に架けられたといわれ、架橋当初は一本の丸木橋だったことがその名の由来といい、徳川御三卿のひとつとなった一橋家は、神田橋にかけての日本橋川右岸一帯に広大な屋敷地を構えていました。橋から下流方向を見通すと、右岸側には江戸城内濠時代の石垣の一部が残され、高速道路下の味気ない景観の中に、由緒ある歴史の一端をかろうじて見ることができます。また、橋の南詰側にある丸紅の敷地内には「一橋徳川家屋敷跡」の碑もあり、説明板には往時の敷地が現在の気象庁から大手町合同庁舎付近にまで及んだことが記されています。一ツ橋というと、一橋大学の名を思い浮かべますが、一ツ橋手前の白山通り西側、現在は学術総合センターや如水会館のある一画が、旧称東京商科大学、後の一橋大学の跡地です。大学は震災による罹災後、国立市へ移転しました。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.28
コメント(0)
-

第413回 【都電の残像編(67)】 一ツ橋(ひとつばし) 前編
バス停データ◆所在地:千代田区 ◆路線:都営バス[都02乙]系統みなさん、こんにちは。池袋駅前と数寄屋橋を結んだかつての都電17系統は、廃止後その代替として都営バス[517]系統に置き換えられ、これが後に[楽67]→[池67]と系統番号を変え、平成2年から春日通りを併走する[都02]系統と統合され、[都02乙]系統として現在に至っています。都電時代の運行区間は徐々に縮小され、昭和57年から池袋駅~一ツ橋間の路線となりましたが、末端区間である春日駅~一ツ橋間は、平日朝3便(土曜日は2便)のみ運行という、およそ生活の「足」としては使えないダイヤがいつまでも続いています。そんな[都02乙]系統の「幻の終点」ともいえる一ツ橋バス停は、白山通り上の一ツ橋交差点にあり、ここがかつての都電17系統の一ツ橋電停の跡地となります。都電全盛期、ここには17系統の他、三田から北上してきた2系統、中山道へ向かう18、35系統が併走していました。交差点角に建つ、重厚かつ瀟洒なレンガ造りの建物が学士会館で、一ツ橋のランドマークとして親しまれています。昭和3年に竣工した震災復興建築のひとつで、戦後はGHQに接収され、将校クラブとして使われた経緯もあり、都電時代をじっと見つめてきただけでなく、洗練された外観の内に昭和史の断片が幾重にも刻み込まれた貴重な近代建築遺産のひとつといえます。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.24
コメント(0)
-

第412回 【都電の残像編(66)】 大塚駅前(おおつかえきまえ) 後編
(前回からのつづき)巨大ターミナル池袋に隣接する立地のせいか、大塚駅の印象はいまひとつ垢抜けませんが、都電の開通年で見ると、大塚駅前が大正2年(旧王子電軌は明治44年)なのに対し、池袋駅前は昭和14年と、大きな開きがあります。もともと、戦前の城北エリアの商業中心地は大塚で、地下鉄丸ノ内線も当初は大塚発着が計画され、東武東上線も計画段階では大塚を起点としたといわれます。北口の、荒川線東側に見える書店の入るビルは、かつての白木屋デパートの建物であり、南口側に残る三業通りの名も、かつて三業地として賑わった街並みの名残りといえます。その大塚駅も、国有化前の日本鉄道による計画では、目白から現在の文京区大塚を経由するルートが検討され、駅は現在の地下鉄丸ノ内線新大塚駅付近に設置される予定だったとされています。それが池袋から巣鴨方面に至るルートに変更され、巣鴨村の一部であった現在地に大塚駅が開業する運びとなりました。本来の大塚から離れた場所に大塚駅が開業してしまったことで、駅周辺は本来の地名である巣鴨や西巣鴨より、大塚の名で呼ばれることの方が多くなり、これが昭和44年の住居表示施行の際、現在見られるような北大塚、南大塚の町名を生む結果となったようです。改札から駅南口のロータリーに出ると、32系統(旧王子電軌)の生まれ変わりである荒川線の電車が、目の前をゆっくりと横切っていきます。その線路の向こう側、現在は都営バス[都02]系統の降車用バス停の立つあたりの路上が、16系統の折り返した大塚駅前電停の跡地となります。先に開業した32系統に遠慮するように、線路は駅前ロータリー手前で折り返しとなり、線路の接続はありませんでした。春日通りへ続く駅前の通りを、大塚駅を背に、16系統の電車は南へと向かいました。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.20
コメント(0)
-

第411回 【都電の残像編(65)】 大塚駅前(おおつかえきまえ) 前編
バス停データ◆所在地:豊島区 ◆路線:都営バス[都02]系統他みなさん、こんにちは。大塚駅前から春日通りを東進し、厩橋で隅田川を越えると一本南の蔵前橋通りにスライドした後、錦糸町駅前まで到達していたかつての都電16系統は、外堀の内側や日本橋、銀座周辺といった都心部から終始距離を置いたルートを取る系統でしたが、上野を中心に山の手北部と下町を東西に繋ぐ役割から、都電路線の中でも主要幹線級の系統として活躍しました。全区間で10キロを越える長丁場ですが、都心部からずれたルートのため一極集中的な利用のされ方ではなく、短区間での乗客の入れ替えが多く見られたというのも、この系統の特徴かもしれません。都電廃止後は、都営バス[516]系統(後に[塚20]系統)として、同一区間同一ルートの代替バスが運行され、これが昭和61年から都市新バス[都02]系統となって現在に至る経緯を見れば、16系統の運行区間が沿線住民の需要に即した的確なものだったことが裏付けられたともいえるでしょう。起点の大塚駅前は、後に荒川線となって生き残る旧王子電軌の32系統が通過しましたが、16系統との線路の接続はなく、山手線高架下に電停を構える32系統に対し、16系統は駅前広場手前の路上で折り返していました。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.17
コメント(0)
-

都電保存車両めぐり(9) 8053号
みなさん、こんにちは。今回は、千葉県八千代市で喫茶店として保存されている、8053号をご紹介します。都電8000形車両は、昭和31年から32年にかけて130両余りが製造されました。都電末期の車両ということで、耐用年数を短くした低コスト車両として設計されたといわれます。現在、完全な姿での保存車両は、この8053号のみとのことなので、大変貴重な一両といえるでしょう。下町の23系統で活躍の後、昭和47年に現役を退いた8053号は、廃車後すぐに譲渡され、千葉県八千代市へと運ばれてきました。当初、喫茶店兼図書館として利用されたそうですが、途中しばらく休業の後に内外装を一新し、平成13年に「トレインカフェ」としてオープン。平成17年に再度リニューアルし、現在見られるような塗色に変更されたとのことです。何より嬉しいのは、外観だけでなく、内部もじっくり楽しめることですね。木立に囲まれた丘の上という立地も、とてもよい雰囲気です。都電の幻想に浸りながら、おいしいケーキとコーヒーで至福の時を過ごせる、夢のような空間です。京成線・東葉高速線の勝田台駅から徒歩10分足らずの場所ですので、お近くの方はぜひ訪ねてみてください。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.15
コメント(0)
-

第410回 【都電の残像編(64)】 呉服橋(ごふくばし) 後編
(前回からのつづき)ここは江戸城外郭門のひとつ、呉服橋門の跡地で、郭内と市街地を結ぶ廓門橋として架けられた呉服橋は、日本橋などと同様に慶長年間(1596~1611)の創架と伝えられ、古くは後藤橋の名があり、呉服橋門外に幕府呉服御用の後藤縫殿助の屋敷があったことに因むといわれます。明治13年、江戸期からの木橋が石橋となり、大正3年からは鋼橋となりましたが、戦後の昭和26年、濠の埋立てとともに撤去されました。橋を越えると、永代通りの左右には呉服町の町名もありましたが、昭和3年に周辺の元大工町や檜物町などと合併し、呉服橋に町名が変わりました。現在のように八重洲1丁目の一部となるのは、昭和29年からです。呉服橋交差点から外堀通りを北へ歩くと、すぐに日本橋川に架かる一石橋があります。大きな石造りの親柱が印象的なこの橋は、江戸時代初期からの古い橋で、橋のすぐ西側が、外堀と日本橋川の分岐点でしたが、呉服橋方向への外堀が埋立てられて後は、神田橋方向への外堀も、日本橋川の一部として捉えられています。江戸時代、橋の北詰には幕府金座御用の後藤庄三郎の屋敷地が、そして南詰には先ほどご紹介した後藤縫殿助の屋敷地があり、「後藤」を「五斗」ともじり、「五斗」+「五斗」で「一石」と名付けたと伝えられます。いかにも江戸っ子らしいユーモラスな命名といえるでしょう。大正11年改架の鉄骨コンクリート花崗岩貼りの橋は、惜しくも平成九年に現在の橋に架け替えられましたが、大きな親柱の一基は残され、都電時代とともに歩んできた橋の面影を後世に伝えています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.09
コメント(0)
-

第409回 【都電の残像編(63)】 呉服橋(ごふくばし) 前編
バス停データ◆所在地:千代田区 ◆路線:都営バス[東20]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電15系統は、九段下から靖国通りに入り、小川町から本郷通りへ、そして大手町から永代通りへと進みました。丸の内1丁目交差点を過ぎ、山手線や新幹線の高架をくぐると、右手に高速バスの集るターミナルが見え、その奥に東京駅日本橋口があります。そしてここに都営バスの呉服橋バス停がありますが、かつての都電呉服橋電停は、この位置ではありません。東京駅前にもかかわらず、都電時代からの呉服橋のバス停名を守り通している姿に、ひとまず敬意を表した上で、さらに永代通りを東へ進みます。間もなく永代通りは、外堀通りと交わる呉服橋交差点に出ます。ここが呉服橋電停の跡地であり、外堀通りに沿って江戸城外濠が南北に水を湛えていましたが、戦後に埋立てられ、橋も濠も現在はその痕跡を留めていません。濠の跡地には大和証券ビルや第一鉄鋼ビルが建ち、地下には首都高速八重洲線が濠跡に沿って通過しています。それでも先ほどのバス停の他、交差点名に呉服橋の名が残り、近くの首都高速の出入口にも呉服橋の名が使われ、地名としては現在もしっかりと定着している感があります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.06
コメント(0)
-

第408回 【都電の残像編(62)】 東五軒町(ひがしごけんちょう) 後編
(前回からのつづき)江戸期、この付近には小日向馬場と呼ばれた馬場があり、その築造のための土取りをした跡地が、土取り御用を果たした5人の者に給され、五軒町の町名が起こったと伝えられます。明治5年から牛込西五軒町、同東五軒町が起立し、同44年に牛込の冠称は外れたものの、当時の町名が現在もそのまま残されています。もともと新宿区北東部の旧牛込区エリアは、古くからの町名が多数残されている特異な地域であり、地図を確認すると、東五軒町の周辺だけでも、水道町、改代町、築地町、白銀町などの町名を見ることができます。本ブログでこれまでにご紹介した山伏町、納戸町なども、このエリアの町名です。神田川を中心にぶらぶら歩いていると気が付きますが、この周辺は印刷や出版、取り次ぎといった本にまつわる会社が多く、大手の巨大なビルだけでなく、中小の印刷、製本業者の工場も数え切れないほど見ることができます。明治期以降、この付近の神田川では紙の原料である「こうぞ」をさらすなどの光景が日常的に見られ、紙産業の発展が著しかったといいますが、そうした歴史と現在の街の表情とは、決して無関係ではないのでしょう。かつての都電15系統は、この先の大曲を経て、飯田橋へと向かいました。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.03.02
コメント(0)
-

第407回 【都電の残像編(61)】 東五軒町(ひがしごけんちょう) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[飯64]系統他みなさん、こんにちは。前回の石切橋から目白通りを歩き進むと、すぐに次の西江戸川橋が見えてきます。江戸川橋より東に位置するのに「西」とはおかしいなと思いますが、橋名は神田川左岸に昭和39年まで、西江戸川町の町名があったことに因んでいます。この付近の神田川には江戸川の別称がありましたが、この先の大曲から下流方向にかけての左岸側には同年まで江戸川町の町名があり、その西隣り故に西江戸川町と称していました。橋を渡って少し歩くと、左手にまたもや「う」の看板を掲げたうなぎ店が見えますが、こちらは明治41年創業の「石ばし」です。その前を通りすぎると、武島町会と書かれた掲示板が目に止まりますが、川沿いの西江戸川町に隣接して、やはり昭和39年までは武島町の旧町名がありました。江戸時代に武島某の屋敷があったことに因むといいますが、町域は東西に細長く、西江戸川町との境界が複雑に入り組んでいたため、当時の地図を見ると、まるで刃こぼれのした刀のような形状が特徴的でした。西江戸川橋の次が小桜橋ですが、この橋の袂がかつての東五軒町電停の跡地であり、現在も都営バスの東五軒町バス停が立っています。東五軒町は、神田川右岸の新宿区側の町名で、地図を見ると西五軒町と東五軒町が目白通りに面して隣接している様子がわかります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.25
コメント(0)
-

第406回 【都電の残像編(60)】 石切橋(いしきりばし) 後編
(前回からのつづき)石切橋を対岸へ渡ると、すぐ右手にうなぎ店「はし本」があります。江戸後期から明治期にかけて、このあたりの神田川沿いには、多数のうなぎ店が軒を連ねていたことで知られたといわれ、この「はし本」も江戸期から続く老舗のひとつです。看板には「うなぎ」と書かずに、うなぎの姿を模した「う」の文字だけを書くのが、古くからの伝統のようです。この付近の神田川左岸の町名は文京区水道で、神田上水とともに発展してきた街の歴史が、町名として現在も生きている様子を見ることができます。地図を見ると、橋の南側が新宿区水道町となっており、異なる区の同じ町名が川を挟んで向き合っています。橋の先を少し歩くと、正面に小さな文京水道郵便局が見えてきます。散策の途中で郵便局を見つけると、はがきに風景印を押してもらうという秘かな楽しみがありますが、この局の風景印の絵柄は、神田川とその周囲の街並みで、上流側から石切橋を捉えた構図に、桜の木と鯉が描かれています。この局では、押印の際に絵柄の意匠説明が書かれた紙を添えてくれますが、それによれば、かつて禁漁区「お留め川」とされたこの付近の神田川には多くの鯉が泳ぎ、川縁は桜の名所だったことを偲び、川とともに歩んできたこの街のさらなる発展の願いを、桜と鯉の絵柄に込めているそうです。石切橋に戻り、首都高速道路に空を遮られた現在の神田川を見ながら、桜並木の続いた在りし日の神田川を思い浮かべて見ます。かつての15系統の車窓風景が、幻影のように私の脳裏を横切っていきます。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.22
コメント(0)
-

第405回 【都電の残像編(59)】 石切橋(いしきりばし) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[飯64]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電15系統は、江戸川橋から目白通りに入ると、ぴたりと寄り添う神田川を左に見ながら、飯田橋方向へと走っていました。現在の江戸川橋から下流の神田川は、高速道路下の日の当らないじめじめとしたイメージでしたが、ここ数年の護岸改修と老朽化した橋の架け替えで、ずいぶんときれいに変貌を遂げました。江戸川橋から歩き始めると、まず最初に見えてくる小さな橋が華水橋で、橋名の由来は定かではありませんが、かつてこの神田川沿いが桜の名所として知られた頃の景観と関係があるのかもしれません。その次の橋が掃部(かもん)橋です。この付近の神田川は、左岸側には歩道がなく、マンションや雑居ビルに混ざって昔ながらの商家や木造アパートなども護岸に面してびっしりと建ち並び、下町的な街の表情を見せています。掃部の名は、近くに吉岡掃部という紺屋が住んでいたことに因むといいます。そのすぐ先が、古川橋です。江戸時代、将軍鷹狩の際の通路として使われていた橋といわれ、幕府管理下の御入用橋だったとされます。このあたりの神田川を、古くは古川と称した時期もあるようで、橋名はこれに因む他、橋の南詰側には、住居表示施行の昭和42年まで、西古川町、東古川町の町名が並んでいました。また、このあたりにはかつて薪の粗朶(そだ)を商う者が多く住んだことから、粗朶町の別称もあり、橋も粗朶橋と呼ばれることがあったといいます。古川橋を過ぎると、次が石切橋で、ここがかつての石切橋電停の跡地であり、現在も都営バスの石切橋バス停が立っています。寛文年間(1661~73)の創架といわれる古い橋で、このあたりの橋としては最も幅員の広い橋だったことから、江戸期には大橋と称したともいわれます。石切とは、すなわち石工のことで、付近にそうした職人が住んだことによる命名と思われますが、こちらもその由来は定かではありません。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.18
コメント(0)
-

第404回 【都電の残像編(58)】 鶴巻町(つるまきちょう) 後編
(前回からのつづき)バス停の先の交差点を左へ入ると、すぐに神田川の一休橋です。一休の名の由来は定かではありませんが、近くに一休蕎麦と呼ばれた蕎麦屋があったとする説や、江戸時代は近くに一橋家の抱え屋敷があり、古くは「いっきょう橋」と通称したことに因むといった説があります。江戸期には関口橋とも呼ばれました。橋は神田川左岸の江戸川公園へ入る人道橋で、南側は護岸から歩道が少し下がっているために階段が設けられ、歩道橋のような具合になっています。その階段下に「昭和一三年 東京市」と刻まれた「一休橋の由来」の碑があり、蕎麦屋説による由来が刻まれています。一休橋から江戸川公園を上流方向に少し歩いたところに、大洗堰の由来を記した記念碑があります。大正2年から始められた護岸改修工事により、大洗堰は史跡として保存されましたが、昭和12年の改修工事により取壊され、翌年に堰の部材を利用した由来碑が東京市により設置されました。しかしこの由来碑も後に失われ、後年その碑文のみが見つかり、再度設置されることとなりました。現在見られるのはこの碑文を嵌め込んだ記念碑です。その後ろ側には、神田上水取水口の石柱が保存されています。角落(かくおとし)と呼ばれた水をせき止める板をはめるための石柱で、公園内に作られた親水池の隅にひっそりと置かれています。江戸川公園は奥へと進むにつれ、目白台の急斜面を利用した立体的な広がりを見せるようになります。護岸に沿っては、桜並木が続くようになりますが、このあたりが毎年春に行われる桜祭りの中心的な位置でもあります。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.15
コメント(0)
-

第403回 【都電の残像編(57)】 鶴巻町(つるまきちょう) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[飯64]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電路線のうち、高田馬場駅前に顔を出した唯一の系統が、15系統です。現在の地下鉄東西線の前身ともいえる路線で、早稲田、飯田橋、大手町、日本橋を経て、茅場町までを結んでいました。また、朝夕のラッシュ時には、永代通りを洲崎まで直通する臨時15系統もありました。この15系統のルートのうち、早稲田付近だけは後の地下鉄ルートと異なり、面影橋~早稲田間で現在の荒川線(当時は32系統)と併走した後、江戸川橋から大曲を経て飯田橋へと至りました。途中、早稲田にある都営バスの早稲田営業所は、かつての都電早稲田車庫の跡地で、営業所の入口部分には、都電時代の敷石が残されています。早稲田から江戸川橋へ向かう途中、外苑東通りが右へ分かれる鶴巻町交差点が、かつての鶴巻町電停の跡地であり、現在もここに都営バスの鶴巻町バス停があります。行政上の町名は早稲田鶴巻町ですが、電停開業当初から早稲田の冠称は省かれ、バス停もそれを忠実に承継しています。旧早稲田村の北部にあたる鶴巻町一帯は、明治の頃までは「早稲田田圃」と呼ばれるような農村形態が続いていました。鶴巻の地名由来については、元禄の頃に小石川村で放し飼いにされていた鶴が飛来して田畑を荒らすため、この地に鶴番人を置いたことに因むとする説と、地名学的に「ツル」は水路のある低地を意味し、「マキ」は牧場を意味することから、そのような土地利用がかつて見られたことに因むとする説があります。江戸時代初期、この付近は蟹川と呼ばれた小流が南から神田川へと注ぎ込み、上野国大胡(現在の群馬県前橋市の一部)から移り住んできた大胡氏(後の牛込氏)が経営する牧場のあった地とも考えられています。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.11
コメント(0)
-

第402回 【都電の残像編(56)】 杉並車庫前(すぎなみしゃこまえ) 後編
(前回からのつづき)桜並木が続く車庫東側の塀際を歩いていくと、ちょうど車庫の真裏に梅里児童公園という小さな公園がありますが、ここはかつて軌道に送電した変電所の跡地のようで、その変遷を伝える貴重な碑を見つけることができましたた。人通りの多い場所ではなく、その存在もあまり知られていないと思われるので、全文をご紹介しておきます。この公園は、昭和四十年に西小沢児童遊園として開設されました。この辺りは、昭和初期まで西小沢と呼ばれ五日市街道と青梅街道の交わる交通の要所でした。ここにあった建物は大正十年に西武軌道の変電所として建てられ、当時にしては珍しいコンクリート造りでした。昭和二十六年に都電杉並線となり昭和三十八年の廃止に伴い変電所は地元の運動により梅里敬老会館として生まれ変わり、作家有吉佐和子の小説「恍惚の人」の舞台にもなりました。平成十年、新敬老会館の建設に伴い撤去され、この公園と一緒になりました。 平成十一年三月 杉並区有吉佐和子『恍惚の人』(昭和四七年)は、認知症や老人介護の問題に正面から向き合ったベストセラー小説で、これまでに何度も映画化、ドラマ化、そして舞台化されてきた作品ですが、作中にはこんな記述を見つけることができます。近所の菓子屋で、挨拶がわりに洋菓子の箱詰めを買ってから、梅里敬老会館を訪ねた。昔は変電所だったという洋風の建物だが、玄関を入るとすぐ目の前に交番のような事務所があって、その中に若い女性がこちらを向いて腰かけていた。路面電車の変電所という小さな存在ではありますが、区の施設として再利用され、小説の舞台ともなり、そしてその歴史が碑に刻まれているという事実の発見は、私のような散歩者にとって、最上の掘り出し物といえるでしょう。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.07
コメント(2)
-

第401回 【都電の残像編(55)】 杉並車庫前(すぎなみしゃこまえ) 前編
バス停データ◆所在地:杉並区 ◆路線:都営バス[渋66]系統他みなさん、こんにちは。前回の成子坂下から青梅街道をさらに西へ進み、鍋屋横丁を過ぎてしばらくすると、中野区を通り抜けて杉並区へと入ります。旧蚕糸試験場跡地の蚕糸の森公園の先が環七通りの高円寺陸橋で、これをくぐると間もなく左手に都営バスの車庫が見えてきますが、ここがかつての都電14系統の杉並車庫、及び杉並車庫前電停の跡地です。都電の廃止後、それまで堀ノ内にあった都営バスの車庫がここに移り、交通局杉並自動車営業所として長く存続していました。その後、管轄路線の縮小などにより支所に降格し、バスの運行が民間委託されるなどの変遷を経て現在に至りますが、車庫入口に立つバス停は、都電時代から不変の杉並車庫前であり、○○車庫前を名乗る電停を受け継いだバス停のうちでは、現在もそのまま存続している唯一の事例となっています。車庫の前身は、大正10年開業の西武軌道の営業所です。奥行きの深いゆったりとした敷地に、飛行機の格納庫のような大きな車庫が特徴だったといいます。都電の車庫につきもののトラバーサーが無かったというのも、担当系統が1路線のみで、在籍した車両数も他の車庫に比べて少なかった故のことでしょう。西武軌道による開業当初、車庫前電停は高円寺と称していました。大正11年開業の中央線高円寺駅より一年早い開業であり、本家高円寺といったところかもしれません。但し、地名の由来である宿鳳山高円寺へは、中央線高円寺駅の方が最寄になります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.02.03
コメント(0)
-

第400回 【都電の残像編(54)】 成子坂下(なるこさかした) 後編
(前回からのつづき)バス停前の青梅街道北側では、大規模な再開発工事が進行中です。つい数年前まで見られた民家やアパートの密集する古色蒼然とした住宅街は一掃され、百人町方面へ抜ける道路も大幅に拡張整備され、街そのものが全く新しい景観に生まれ変わろうとしています。その工事の喧騒を背に、青梅街道を新宿駅方向に歩いてみます。通りは緩やかな上り坂となっていますが、これが成子坂です。明治の末頃まで、この付近は成子町と称し、街道に筵を敷いて商いをしていた源左衛門という男が、店に鳴子を鳴らす紐を下げ、客がそれを鳴らすという光景がこのあたりの名物となり、後に成子の地名が生じたといわれます。他に、田畑で鳥を追い払うための鳴子に因む地名とする説もあるようです。坂の左手に見える大きな鳥居は、成子天神社です。先ほどの再開発工事が境内のすぐ脇まで迫り、社殿周辺も残念ながら静寂とは言い難いですが、創建は延喜3年(903)と伝える古社で、寛文元年(1661)からこの地に鎮座し、成子の鎮守として親しまれています。境内奥には、新宿区内最大級とされる富士塚もあります。成子富士と称し、もともとこの地にあった天神山という小丘を大正9年に改造して築山したものといいますが、残念ながら現在は境内中ほどから奥が立入禁止となり、その姿を見ることはできません。坂の中腹からバス停を振り返ると、絶え間ない青梅街道の車の流れ、街道南側の高層ビル、そしてスケールの大きな再開発工事という景観の中で、ポツンと立つ成子坂下のバス停だけが、旧時代の遺物のようにも見えてきます。=============================おかげさまで、今回で連載400回となりました!ブログ開設当初は、これだけの回数を続けられるとは夢にも思いませんでしたが、日々たくさんの方々にご訪問いただけたことが糧となり、ここまで続けてまいりました。まだまだ訪ねてみたいバス停はたくさんあります。これからも「バス停地名学のすすめ」を、宜しくお願いいたします。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.31
コメント(0)
-

第399回 【都電の残像編(53)】 成子坂下(なるこさかした) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[王78]系統他みなさん、こんにちは。「杉並線」の愛称で親しまれたかつての都電14系統は、新宿駅西口に近いJR大ガードの西側にあった新宿駅前電停から、青梅街道を一直線に西へ下り、荻窪駅前までを結んでいました。都電の営業エリアとしては西に大きくはみ出た路線で、新宿駅前の乗り場は独立し、他の系統との線路の接続も無く、この線のみが狭軌(1067ミリ)を採用していた等、都電の中では異色の存在でしたが、これはその前身が(旧)西武鉄道による軌道線で、昭和26年に東京都が買収した路線であることに起因しています。買収から10年後の昭和36年、青梅街道の直下に地下鉄丸ノ内線の延伸部(当時の呼称は荻窪線)が、新中野まで開業。翌37年には荻窪まで全通し、杉並線との完全な競合関係となりました。急速に沿線人口が増加していた中野区、杉並区の状況を見れば、最早のんびりとした都電に勝ち目は無く、地下鉄開業を境に杉並線の利用者数は激減し、それでも一年以上は持ちこたえたものの、昭和38年11月をもって全線廃止となりました。戦後の都電として、トロリーバス置き換えのため廃止となった江戸川区の26系統を除けば、系統そのものの廃止はこれが最初のことで、9・10系統の青山線迂回に続く大規模な廃止でもありました。廃止当時、新宿~荻窪間に17あった電停のうち、現在も同名のバス停が残るのは3ヶ所です。このうち、まずは地下鉄西新宿駅に近い成子坂下バス停を訪ねてみました。バス停のある西新宿三井ビル前付近が、成子坂下電停の跡地でもあります。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.27
コメント(0)
-

都電保存車両めぐり(8) 7514号
みなさん、こんにちは。今回は、小金井市の江戸東京たてもの園に展示されている、7514号をご紹介します。車体更新前の7500形については、既に7504号や7508号をご紹介済みですが、今回の7514号はワンマン化工事がなされていない車体のため、この形式の「原形」ともいえる姿をとどめている点に注目です。廃車から約20年もの間、荒川車庫で保存されていましたが、平成11年に江戸東京たてもの園に移され、今では同園のシンボル的な存在で、来園者の人気を集めています。管理の行き届いた施設内の展示物というだけあって、塗色も鮮やかで、方向幕やサボなども美しく復原されています。車内には、同形式が活躍した青山車庫時代の6・9・10系統の路線図も掲示され、往時の雰囲気がよく再現されています。この路線図をパッと見て「青山線迂回後だ」とすぐ分かる人は、相当な都電ファンといえるでしょう。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.24
コメント(0)
-

第398回 【都電の残像編(52)】 若松町(わかまつちょう) 後編
(前回からのつづき)かつての都電13系統は、若松町交差点から大久保通りを東へと進みました。現在この交差点には4本の路線バスが通過しますが、残念ながら13系統と同じルートを取る路線はありません。路線バスの大幅な改編が行われた都営大江戸線開業当初、大動脈だった[秋76]系統廃止後の若松町から東の大久保通りでは、市ヶ谷駅経由で新橋駅へ向かう[橋63]系統のみが細々と存続していましたが、やはり路面交通の需要をすべて地下鉄に移すことは利用者の意に反したようで、[秋76]系統のルートを一部補うような形で、大久保駅方面から飯田橋駅へ向かう[飯62]系統が平成14年に新設され、現在に至っています。若松町交差点から北へ向かう通りは、早稲田方面への下り坂ですが、これを夏目坂といいます。この坂の先に喜久井町の町名があり、いずれも夏目漱石ゆかりの地名で、その著書『硝子戸の中』(大正四年)に、こんな記述をみつけることができます。私の家の定紋が井桁に菊なので、それにちなんだ菊に井戸を使って、喜久井町としたという話は、父自身の口から聞いたものか、またはほかのものから教わったのか、なにしろ今でもまだ私の耳に残っている。(中略)父はまだその上に自宅の前から南へゆく時にぜひとも登らなければならない長い坂に、自分の姓の夏目という名をつけた。不幸にしてこれは喜久井町ほど有名にならずに、ただの坂として残っている坂下の早稲田通りと交わるあたりの一角が、夏目家の旧家跡、すなわち漱石生誕の地となります。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.20
コメント(0)
-

第397回 【都電の残像編(51)】 若松町(わかまつちょう) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[宿74]系統他みなさん、こんにちは。前回の河田町交差点から東京女子医大方面へ向かう人の流れを右手に見ながら、かつての都電13系統が走った抜弁天通りを北へ進むと、間もなく大久保通りが東西に横切る若松町交差点が見えてきます。ここが都電時代の若松町電停跡地であり、現在も都営バスの若松町バス停が立っています。都営大江戸線の若松河田駅が、若松町と河田町の二つの町名を合成した駅名であることは説明するまでもありませんが、位置的には前回の河田町バス停の真下に駅があり、若松町バス停からは少し離れています。両バス停が、隣り合った近い距離であるにもかかわらず、若松河田駅前として統合されずに、都電時代の電停名を忠実に承継した姿を保っていることは、本ブログとしては嬉しい限りです。この付近は、元禄12年(1699)頃から開けた町地だったと伝えられ、町名は、ここから正月用の若松を幕府に献上したことに因むといいます。若松町交差点の北西側は、江戸期に三十人組の屋敷地だったことから、牛込三十人町と称していました。江戸期の面影を現在の街並みから探し出すのは不可能と思いきや、交差点手前から細い路地を左へ入ると、その先に江戸期から火除神として祀られた八兵衛稲荷の小さな境内が隠れるように佇み、私のような散歩者にほっと一息つかせてくれます。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.18
コメント(0)
-

第396回 【都電の残像編(50)】 河田町(かわだちょう) 後編
(前回からのつづき)かつての都電13系統廃止後も、この周辺の地域は鉄道の便に恵まれず、都営バスが唯一の公共の足として機能していました。中でも、都電の代替系統だった[秋76]系統は、新宿駅と牛込地区を結ぶ幹線系統として欠かせない存在でしたが、平成12年の地下鉄大江戸線開業により廃止となり、他の関連系統も減便等の措置がなされました。河田の地名は、田地や湿地帯を示すもので、古くは川田ヶ窪町の名もあり、東京女子医大南側から曙橋方面への谷状の地形を見ると、その地名由来にもどことなく頷けるものがあります。牛込地区でありながら、昭和61年の住居表示施行まで市谷河田町と称していたのは、谷地が市谷方面に開けていたことによるのかもしれません。河田町といえば、以前はフジテレビの所在地として知名度が高かったですが、平成9年に同局がお台場へ移転し、街の様相も幾分寂しくなったのではないでしょうか。現に、大江戸線開業の際、駅名は当初から若松町の仮称で決まっていましたが、河田町の衰退を懸念する声から、最終的に若松河田の駅名で決着したといわれます。都電時代からの建築物として、この付近でご紹介しておきたいのは、地下鉄の入口脇にある旧小笠原伯爵邸の建物です。日本では珍しい本格的なスパニッシュ建築で、竣工は昭和2年。大規模な修繕の後、5年ほど前からレストランとして使用されています。お店を予約して店内に入れば、室内の華麗な装飾や中庭、屋上庭園などを楽しめるでしょうが、外観だけでも緑のスペイン瓦や窓の格子など、見どころに溢れています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.13
コメント(0)
-

第395回 【都電の残像編(49)】 河田町(かわだちょう) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[宿74]系統他みなさん、こんにちは。新宿駅前から牛込地区を横断して飯田橋へと抜けたかつての都電13系統は、戦前までは新宿区役所に近い角筈電停を起点とし、現在は遊歩道「四季の道」として整備されている専用軌道を使って東大久保方面へ向かっていました。戦後、11,12系統の新宿駅前電停が、駅東口から靖国通り上に移され、13系統も新宿駅前発着となりましたが、その際、運行経路が四谷三光町電停(現在の新宿5丁目交差点)経由に変更され、従来の専用軌道は、11,12系統の大久保車庫への回送線として使われるようになりました。戦災で焼失した新宿車庫が大久保車庫に統合されたことによる措置で、13系統は新宿駅前への乗り入れと引き換えに、専用軌道を明け渡した格好となりました。現在では貴重な都電の廃線跡となった「四季の道」を抜け、歌舞伎町の裏手から新宿6丁目交差点(本ブログ開設時のご挨拶で触れた新田裏電停がここです)に出ると、その先の文化センター通りが、かつての13系統の専用軌道跡です。右手に見える都営住宅と新宿文化センター一帯が大久保車庫の跡地ですが、それらしき痕跡は皆無でしょう。そのまま直進すると、道幅は次第に狭くなり、やがて職安通りと合流すると、第285回「抜弁天」の項でご紹介した抜弁天交差点に出ます。ここには東大久保電停がありました。そして職安通りは緩やかな下り坂となって左へカーブし、余丁町バス停を過ぎると、間もなく地下鉄若松河田駅の入口が見えてきますが、ここが河田町電停の跡地で、現在は河田町バス停が立っています。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.10
コメント(2)
-

第394回 【都電の残像編(48)】 浅草橋(あさくさばし) 後編
(前回からのつづき)往古の奥州街道は、後の日光東照宮への参詣道として整備され、日本橋を起点に浅草橋、蔵前、雷門、小塚原、千住大橋を経て千住宿、草加、越谷方面へと通じていました。日光街道と呼ばれる道筋ですが、江戸時代は日光道中と称する方が正しかったようです。浅草橋南詰は、浅草口と呼ばれた江戸城外郭門の跡地で、寛永13年(1636)に桝形櫓が造営され、浅草見附として番士が置かれるようになりました。いわゆる江戸三六見附のうちでは、最も外側に位置した見附であり、当初は見附を出るとあたりは人家もまばらな淋しい場所だったといいます。明暦3年(1657)の江戸の大火の際は、現在の日本橋小伝馬町にあった牢屋敷の非常措置として囚人が仮釈放されましたが、浅草口へ押し寄せた囚人たちを番士が集団脱獄と勘違いして門を閉ざしてしまったことから、猛火に追われた市民が避難路を失い、神田川へ落ちるなどして2万人余りの死者を出したと伝えられます。現在は、橋の北詰西側に「浅草見附跡」の碑を見ることができます。浅草橋では、かつての都電12系統の他、25、29系統が交差点を東西に直進、一方で国道6号(江戸通り)の方は22、31系統が南北に直進していましたが、この交差点には岩本町方向から蔵前方向へ曲るレールがあり、普段使われることは無かったものの、都心を周回する花電車の運行や、電車の回送などに使われたといいます。12系統で浅草橋を過ぎると、次の電停は両国橋西詰の両国電停でした。両国というと、隅田川対岸の墨田区側の地名というイメージが強いですが、もともとは両国橋を挟んで東西両方に両国地名はあり、中央区側の両国は昭和46年の住居表示実施により、東日本橋と改称され消滅しました。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.07
コメント(0)
-

第393回 【都電の残像編(47)】 浅草橋(あさくさばし) 前編
みなさん、こんにちは。そして、新年あけましておめでとうございます。本年も「バス停地名学のすすめ」を宜しくお願いいたします。======================================バス停データ◆所在地:中央区 ◆路線:都営バス[東42甲]系統11系統とともに、新宿駅前から新宿通りを東へ走ったかつての都電12系統は、四谷見附から市谷見附を経て靖国通りに入ると、須田町までは渋谷からの10系統と併走し、さらに岩本町、豊島町と進んで、隅田川を渡る両国橋の手前で浅草橋電停に到着しました。神田川に架かる浅草橋の南詰に近く、靖国通りが国道6号(江戸通り)と交差する浅草橋交差点の場所で、神田川対岸の浅草橋駅前電停とは別に、堂々と橋名のみを名乗る電停名には、総武線浅草橋駅より約30年早い明治36年開業の伝統と風格を感じさせました。現在もここに都営バスの浅草橋バス停があり、やはり浅草橋駅前バス停とは別扱いで、都電時代の電停名を忠実に継承している姿を見ることができます。交差点から国道6号を浅草橋駅方向に歩くと、すぐに神田川を渡す浅草橋です。神田川が隅田川に注ぎ込む河口部の柳橋に次ぐ第2番目の橋で、川面を覗けば東京湾へ繰り出す屋形船が多数係留され、いかにも神田川らしい江戸情緒をそそる景観が私のような散歩者を迎えてくれます。この場所は、江戸時代初期の頃から奥州街道に通じる交通の要衝として、重んじられてきました。橋の創架年代は定かではありませんが、慶長年間(1596~1615)の江戸図にその姿を見ることができ、江戸開府とほぼ同時期に架橋されたものと思われます。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2010.01.03
コメント(0)
-
2009年 総さくいん 【た】~【や】行
【た】行つきじ 築地(中央区) 第383回 第384回てんげんじばし 天現寺橋(港区) 第377回 第378回とうきょうこうぐち 東京港口(港区) 第349回 第350回どどばしはちまんまえ 道々橋八幡前(大田区) 第307回 第308回とらのもん 虎ノ門(港区) 第361回 第362回【な】行ないとうまちだいきょうちょう 内藤町大京町(新宿区) 第341回 第342回なんどまち 納戸町(新宿区) 第333回 第334回にのはし 二ノ橋(港区) 第367回 第368回【は】行はなかわど 花川戸(台東区) 第339回 第340回ばばさきもん 馬場先門(千代田区) 第373回 第374回ばんちょう 番町(千代田区) 第331回 第332回ひさまつちょう 久松町(中央区) 第329回 第330回ふるかわばし 古川橋(港区) 第365回 第366回ぼちした 墓地下(港区) 第379回 第380回ほりどめちょう 堀留町(中央区) 第327回 第328回【ま】行もとはちまん 元八幡(江東区) 第297回 第298回 第299回 第300回【や】行やまぶしちょう 山伏町(新宿区) 第335回 第336回よつやにちょうめ 四谷2丁目(新宿区) 第391回 第392回よつやよんちょうめ 四谷4丁目(新宿区) 第389回 第390回*2008年総さくいんは、こちらとこちら*2007年総さくいんは、こちらとこちら
2009.12.30
コメント(0)
-
2009年 総さくいん 【あ】~【さ】行
【あ】行あぶらめんこうえん 油面公園(目黒区) 第315回 第316回いいだばし 飯田橋(新宿区) 第363回 第364回うえのえきまえ 上野駅前(台東区) 第359回 第360回えいたいばし 永代橋(中央区) 第375回 第376回【か】行かきがらちょう 蛎殻町(中央区) 第345回 第346回かなすぎばし 金杉橋(港区) 第353回 第354回かみおおさき 上大崎(品川区)第371回 第372回かんだとみやまちょう 神田富山町(千代田区) 第337回 第338回ぎんざよんちょうめ 銀座4丁目(中央区) 第355回 第356回くがはらしゅっせかんのん 久が原出世観音(大田区) 第305回 第306回くだんうえ 九段上(千代田区) 第385回 第386回けいせいなかぐみ 京成中組(足立区) 第321回 第322回ごてんやま 御殿山(品川区) 第323回 第324回こまごめせんだぎちょう 駒込千駄木町(文京区) 第313回 第314回こまつなぎじんじゃ 駒繋神社(世田谷区) 第303回 第304回【さ】行さかいがわ 境川(江東区) 第325回 第326回さもんちょう 左門町(新宿区) 第343回 第344回しながわえきまえ 品川駅前(港区) 第347回 第348回しばうらにちょうめ 芝浦2丁目 第351回 第352回しばぞのばし 芝園橋 第369回 第370回しばまたたいしゃくてん 柴又帝釈天(葛飾区) 第295回 第296回しぶやばし 渋谷橋(渋谷区) 第381回 第382回しんじゅくおいわけ 新宿追分(新宿区) 第309回 第310回 第311回 第312回すいじんもり 水神森(江東区) 第293回 第294回すいどうたんくまえ 水道タンク前(中野区) 第317回 第318回すいどうたんくまえ 水道タンク前(板橋区) 第319回 第320回すだちょう 須田町(千代田区) 第357回 第358回するがだいした 駿河台下(千代田区) 第387回 第388回せいしょうこうまえ 清正公前(港区) 第301回 第302回*2008年総さくいんは、こちらとこちら*2007年総さくいんは、こちらとこちら
2009.12.29
コメント(0)
-

今年もありがとうございました
みなさん、こんにちは。いつも「バス停地名学のすすめ」をご訪問いただき、ありがとうございます。今年も残すところ、あと3日となりました。年内にもう1箇所はご紹介しておきたかったのですが、取材の時間が取れず、やむなく次回は年明けとさせていただきます。来年は【都電の残像編】をまだまだ続ける予定です。お付き合いの程宜しくお願いいたします。それではみなさん、よいお年をお迎え下さい。*年末好例となりました年間総さくいんを、後日掲載させていただきます。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.29
コメント(2)
-

第392回 【都電の残像編(46)】 四谷2丁目(よつやにちょうめ) 後編
(前回からのつづき)東福院坂は、谷地の寺町を挟んで須賀神社の石段坂(男坂)と向き合う坂で、永井荷風の『日和下駄』にこんな記述のあることを思い出します。東京の坂の中にはまた坂と坂とが谷をなす窪地を間にして向合(むかいあわせ)に突立っている処がある(中略)即ちその前後には寺町と須賀町の坂が向合いになっている具体的な坂の名前が記されていませんが、寺町と須賀町で坂が向き合っている場所といえば、やはりこの東福院坂と須賀神社男坂でしょう。坂を下ると途中の右手に東福院安寿寺があり、これが坂名の由来ですが、須賀神社に祀られている牛頭(ごず)天王から、天王坂の別名もあります。東福院の向かい側に、古びた赤レンガの壁が残る一画がありますが、ここが愛染院です。坂に面した駐車場を抜けて境内に入ると、このあたりの寺の中では比較的大きな本堂の前に出ます。本尊の愛染尊は住職ですら拝すことのできない秘仏だったと伝えられます。墓地には内藤新宿生みの親という高松喜六の墓などがあります。坂下まで来ると、正面奥に須賀神社境内の森が見えています。須賀神社については、第344回「左門町」の項で触れましたので、参照下さい。今回は坂下を左に曲り、四谷寺町をさらに奥へと歩いてみます。ところどころに新しい建物も増えているようですが、全体的な街の印象そのものは、都電時代からさほど大きくは変わっていないのではないでしょうか。通りの右手には細い路地が何本も通じ、その両側に民家がびっしりと並ぶような景観が続いています。やがて真成院という寺の角を左に曲がり、観音坂を上ってみます・・・と、書いていくと際限が無いほど、この街の散策は私のような散歩者にとって興味の尽きない迷宮のような面白さに満ちています。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.23
コメント(0)
-

第391回 【都電の残像編(45)】 四谷2丁目(よつやにちょうめ) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[宿75]系統みなさん、こんにちは。新宿通りを東へと進んできたかつての都電11系統は、青山方面への7系統と33系統が折り返した四谷3丁目を過ぎると、次が四谷2丁目電停です。11系統の代替バスは、後に都市新バス[都03]系統として新宿駅西口と晴海埠頭を結んでいましたが、平成12年に四谷駅以西が廃止され、現在、新宿通りでは四谷3丁目~四谷2丁目間のみが、路線バスの無い空白区間となってしまっています。一時は四谷2丁目バス停も消滅しましたが、平成14年から[宿75]系統が東京女子医大から四谷駅前を経て三宅坂まで延長開業し、津の守坂から新宿通りに出るルートとなったため、四谷2丁目バス停は旧来の位置で復活し、都電時代の電停名をほぼそのままに受け継いでいる新宿通りのバス停は、かろうじて欠落を免れた状況となっています。因みに、「四谷」の表記をよく見てみると、町名は「四谷」であり、JRと東京メトロの駅名は「四ツ谷」となっていますが、都営バスは「四谷」です。都電時代から「四谷」であり、バス停はそれを忠実に受け継いでいるといえるでしょう。甲州街道筋にあたる新宿通りは、南北の谷地に挟まれた尾根状の地形を通過していますが、バス停から新宿方向に少し歩くと、南側の急斜面を谷地へと下っていく東福院坂があります。若葉2丁目から須賀町へと続く谷地は、多くの寺院が集中する四谷寺町でもあり、その入口となる東福院坂を、ひとまずぶらぶらと下ってみることとしました。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.20
コメント(0)
-

第390回 【都電の残像編(44)】 四谷4丁目(よつやよんちょうめ) 後編
(前回からのつづき)新宿通りに面した四谷区民センターの建物の脇に、「都旧跡 四谷大木戸跡」と刻まれた碑が立っています。大木戸の前身は、家康の江戸入府にさきがけて、小田原北条氏の攻撃に参加していた内藤清成が、後の甲州街道と鎌倉街道が交差した現在の新宿2丁目付近に構えていた櫓(やぐら)であり、八王子城の北条氏残党の動きに備えたものでしたが、元和2年(1616)にこの櫓は廃止され、四谷大木戸にその役目を譲ることとなりました。この年は豊臣氏滅亡の翌年にあたり、大木戸は西国の豊臣残党から江戸を守ることを主な目的としていました。江戸へ入る街道筋で大木戸が設けられたのは、表玄関となる東海道の高輪とこの四谷のみです。地形的には、北側の饅頭谷と呼ばれた湿地帯と南側の渋谷川の渓谷に挟まれ、守りの要として最適の条件が整っていました。街道の両側には石垣が築かれ、通行には手形を要し、午前6時から午後6時までを通行時間として、夜間の通行は原則として禁じられました。しかし、天下泰平の江戸の社会に、こうした関所は次第に無用のものとなり、寛政4年(1792)に大木戸は廃止され、明治9年には交通の障害となっていた石垣も撤去されました。大木戸跡の碑と隣接して、高さ5メートル弱にも及ぶ大きな水道碑記と呼ばれる石碑があります。ここには玉川上水開削の歴史などが刻まれていますが、これはこの場所に玉川上水の水番所があったことに由来しています。武蔵野台地に開削された水路を四谷大木戸まで導かれた玉川上水は、承応3年(1654)に完成。大木戸から先は地下の暗渠となって江戸市中に配水されました。この大木戸の暗渠入口に置かれたのが水番所で、水量の調節やゴミの除去が行われていました。四谷区民センターの建物に、東京都水道局新宿営業所が入っているのも、この水番所との縁といえるのでしょうか。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.17
コメント(0)
-

第389回 【都電の残像編(43)】 四谷4丁目(よつやよんちょうめ) 前編
バス停データ◆所在地:新宿区 ◆路線:都営バス[品97]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電11系統、12系統が発着した新宿駅前電停が、東口前から靖国通り上の歌舞伎町入口に移されたのは、戦後の昭和24年のことです。新宿通りの渋滞解消が目的だったようで、後に13系統の始発も統合され、3線発着の堂々とした電停となりました。新宿駅前を発車した11、12系統は、明治通りが交差する四谷三光町から新宿3丁目へ右折。新宿通りを東へと進み、古くは江戸四宿のひとつ、内藤新宿の中心として栄えた新宿2丁目、新宿1丁目を過ぎると、間もなく四谷4丁目電停に到着しました。現在も外苑西通りとの交差点に都営バスの四谷4丁目バス停がありますが、ここに限らず、新宿通りは新宿3丁目から四谷2丁目まで、すべて都電時代から変わらぬバス停名が連続しています。本ブログとしてはどれを取り上げても遜色ありませんが、やはり「大木戸」との関連で、今回は四谷4丁目を訪ねてみることとしました。戦前まで、四谷4丁目電停は大木戸と称し、改称後も都電の車掌は必ず「四谷4丁目大木戸」と告げたといわれ、現在もバス停名の脇には大木戸の三文字がカッコ書きされていますが、それほどに、かつて江戸市中への関所の役割を果たした四谷大木戸の存在は、現在に至るまでしっかりとこの地に歴史の根を下ろしているということがいえるでしょう。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.13
コメント(0)
-

都電保存車両めぐり(7) 6191号
みなさん、こんにちは。今回は、府中市郷土の森公園に保存されている、6191号をご紹介します。分倍河原駅から郷土の森行きのバスに乗り、終点で降りると、目の前の公園から鮮やかな都電イエローが目に飛び込んできます。3年ほど前からボランティアの手で根気よく続けられている修復作業により、遠目には今にも動き出しそうなほど、現役時代を彷彿とさせる雄姿が再現されています。都電の6000形グループは、昭和22年から28年までに290両が製造されましたが、この6191号は昭和45年から荒川線に入り、同53年に廃車となりました。府中市に譲渡されたのが同56年とのことですので、既にこの地でも28年の歳月が経過したことになりますが、手厚い修復の成果は、そんな歳月を微塵も感じさせず、これからも公園のシンボルとして、地域に愛される保存車両の模範を示してくれそうです。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.09
コメント(5)
-

第388回 【都電の残像編(42)】 駿河台下(するがだいした) 後編
(前回からのつづき)都電の歴史を辿っていくと、九段下から駿河台下を経て小川町へ至るルートは、明治37年12月7日に東京市街鉄道が開通させた路線であることがわかりますが、その翌日の12月8日、御茶ノ水から駿河台下を経て錦町河岸へ至る南北のルートが、東京電気鉄道により開通しました。後に外濠線と呼ばれるループ線の一部ですが、戦時下の昭和19年に不要不急路線として廃止され、伝統の路線であるにもかかわらず、戦後の地図には記載されることのない不遇の路線となりました。路面電車のレールまで軍に供出したのかと思うと、当時の金属不足の実情が浮き彫りとなってくる感がありますが、都電では他に、天現寺橋~恵比寿長者丸間や江戸川橋~矢来下間、汐留~三原橋間、数寄屋橋~土橋間など、全部で9区間が不要不急路線として廃止されています。盲腸状の短区間が目立つ中、御茶ノ水~錦町河岸間は異色だったかもしれません。靖国通りを少し歩いてみます。神保町方面は名高い古書店街、小川町方面はスキーや登山を中心としたスポーツ用品店街、そして御茶ノ水方面は楽器店街が形成され、駿河台下交差点はそれらの重心のような位置付けとなり、多くの人通りで賑わっています。明治から大正期にかけて、神田四学と通称された法科の四大学(明治、中央、日本、専修)が、いずれもこの駿河台とその周辺に本拠を置いたことが、駿河台付近の独特な学生街の形成に大きく影響してきたことは間違いないでしょう。「日本のカルチェラタン」といった言い回しも、都電全盛期の頃の学生運動に揺れるこの街の特色から生れた俗称として使われました。かつての都電10系統は、駿河台下から靖国通りを小川町、淡路町と進み、終点の須田町へと向かいました。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.07
コメント(0)
-

第387回 【都電の残像編(41)】 駿河台下(するがだいした) 前編
バス停データ◆所在地:千代田区 ◆路線:都営バス[東43]系統みなさん、こんにちは。九段坂を駆け下りたかつての都電10系統は、靖国通りをさらに東へ進み、専修大学前、神保町を過ぎると、古書店街の尽きるあたりで駿河台下電停に到着しました。御茶ノ水駅から南へ下ってくる通称明大通りとの交差点が電停跡地で、現在は東京駅から本郷通りを北進する都営バス[東43]系統に、都電時代と変わらぬ駿河台下バス停が設けられています。地図を見ると、靖国通りは駿河台下交差点から淡路町交差点付近にかけて、それまで直線だった道路がU字形に湾曲していますが、ちょうどその部分が駿河台と呼ばれる高台の裾を巻いている部分で、少し裏道へ入れば、高台へ上る坂道が幾筋も通じている地勢を実感できます。中でも代表的なのが、明大通りの文坂でしょう。由来が定かではないですが、古書店街に近く、坂上は明治大学や日本大学の校舎が林立する文教地区になっていることを思うと、なんとなくその坂名にも頷けるものがあります。駿河台を古くは神田台と呼んだといいますが、駿河国(現静岡県)から呼び寄せられた徳川家臣団の屋敷地が置かれたことから、駿河台の呼称が広まっていきました。江戸市中の高台といえば、富士の眺望に因んで富士見の地名が生じている事例が多いですが、駿河台も例外ではなく、文坂を上がり始めてすぐの交差点から南西へ下る緩い坂に、富士見坂の名が付されています。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.12.03
コメント(4)
-

第386回 【都電の残像編(40)】 九段上(くだんうえ) 後編
(前回からのつづき)九段上から九段下に向けて下る靖国通りの坂が、九段坂です。この坂は現在でもそこそこ急坂ですが、震災以前はもっと勾配のきつい坂だったようで、明治40年にこの坂を電車が走るようになった当初は、濠端に勾配を緩めた専用軌道を設けて線路が敷設されていました。そもそもは江戸期に坂に沿って石垣の段が築かれ、そこに役人向けの長屋が建ち並んでいたようで、その段が九層だったことが九段地名の発祥とされています。麹町台地の突端部だった九段上は、江戸市中の下町から江戸湾にかけての眺望に優れ、遠く房総半島まで見渡したとも伝えられます。反対に西方に目を向ければ、富士の勇姿をくっきりと捉えることもでき、そのことは靖国神社北側に富士見の町名があることからもうかがい知ることができます。九段坂を九段下に向けて歩いてみると、すぐ右手の千鳥ヶ淵を望む濠端に、石で組み上げられた常燈灯台の姿が見えてきます。明治4年に建てられたもので、品川沖を航行する船の目印となっていたといいます。当時は坂の北側にあったようですが、明治から大正期にかけては東京名所のひとつでもあったようで、九段坂と常燈灯台、そしてその足元を走る電車といった構図の古い絵葉書などをよく見かけます。常燈灯台の先が、北の丸公園の入口となっている田安門です。桜並木の向こうに見えているのが高麗門で、その奥右手には櫓門があり、枡形門が形成されています。田安門前の歩道橋で九段坂の反対側へ渡ると、靖国神社の表参道入口となります。戦時中、都電が九段坂にかかると車掌の「ただいま靖国神社を通過」の声に合わせて、乗客が一斉に拝礼したというエピソードがあるそうです。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.11.29
コメント(0)
-

第385回 【都電の残像編(39)】 九段上(くだんうえ) 前編
バス停データ◆所在地:千代田区 ◆路線:都営バス[高71]系統みなさん、こんにちは。渋谷駅前から青山通りを走った都電には、浜町中の橋行きの9系統と、須田町行きの10系統がありました。明治37年に東京市街鉄道により敷設された路線が前身で、都電にとっては伝統ある名門路線のひとつです。両系統は、青山一丁目、赤坂見附を経て皇居内濠に突き当たる三宅坂まで直進し、そこから9系統は日比谷方面へ、10系統は半蔵門方面へと南北に分かれていました。この名門路線が廃止の憂き目にあったのは、東京オリンピックの準備が大詰めを迎えた昭和38年です。メイン会場となった神宮外苑に近い路線の宿命かもしれませんが、首都高速の建設と青山通りの拡張を急ピッチで進めるには都電はどうしても邪魔という結論になり、青山一丁目~三宅坂間と半蔵門~九段上間がその犠牲となって廃止されました。以後、9系統は六本木~溜池~虎ノ門経由に、10系統は信濃町~四谷見附~市谷見附経由にそれぞれ迂回するようになりました。これが俗に青山線迂回と呼ばれた措置です。青山線迂回前の10系統は、三宅坂から内堀通りを北上し、半蔵門、三番町を過ぎると、正面に靖国神社の大きな鳥居が姿を現し、やがて靖国通りと交差する九段上電停に到着しました。現在、内堀通りに路線バスはありませんが、靖国通りには都営バス[高71]系統があり、都電の電停名を継承した九段上バス停が立っています。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.11.25
コメント(0)
-

第384回 【都電の残像編(38)】 築地(つきじ) 後編
(前回からのつづき)戦後の築地付近の地図を見ると、築地4丁目交差点から南へ延びる新大橋通りに、都電の線路が築地市場へ向けて記されている様子がわかります。市場から都電の路線網を使って都内各所へ配給物資の輸送を行うための引込み線で、荷物を載せる無蓋車に簡単な運転台を付けただけの電車が使われていたといいます。実際に新大橋通りを歩いてみると、地下鉄築地市場駅入口の先に市場の正門が現れ、その南側が青果部の入口となっていますが、都電の線路が市場内へ入ったのはその手前あたりからでしょうか。すぐ先には、汐留貨物駅に通じた旧国鉄の貨物引込み線が市場内に入っていましたが、都電もそれに並行して、市場の奥へと入り込んでいました。都電の線路は道路上であるが故に、廃止となればすぐに撤去されその痕跡はあっさりと消えてしまいますが、国鉄の貨物線の方は、廃線跡の一部が狭い道路として現在も残っているため、私のような散歩者はついつい歩いてみたくなります。朝日新聞社の南側を西へ伸びる貨物線跡を辿っていくと、やがて首都高速を跨ぐ新尾張橋に出ますが、首都高速はかつての築地川の跡で、橋が鉄道橋を道路橋に架け替えたものであることを記した説明板が、橋に設置されています。橋を越えてさらに進むと、汐留の高層ビルの手前で海岸通りにぶつかりますが、ここには貨物線当時の踏切信号器が、往時のままの姿で残され、ひと際目を惹く存在になっています。踏切の保存というのは珍しい事例かと思いますが、貨物線廃止から既に20年以上が経ている現在も、こうした遺構のひとつが街の歴史を語り継ぐきっかけとして大切に守られている姿は、喜ばしい限りといえるでしょう。↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.11.22
コメント(2)
-

第383回 【都電の残像編(37)】 築地(つきじ) 前編
バス停データ◆所在地:中央区 ◆路線:都営バス[都04]系統他みなさん、こんにちは。かつての都電8系統は、天現寺橋から古川沿いを東へ進み、赤羽橋から桜田通りに入ると、神谷町、虎ノ門と北進し、桜田門に突き当たると右折。日比谷、銀座4丁目を経て三原橋を過ぎると、間もなく終点の築地に到着しました。晴海通り上の京橋郵便局前あたりが電停跡地で、現在は都営バスの築地バス停が立っています。築地といえば地下鉄日比谷線の築地駅がありますが、築地バス停には手前の東銀座駅が近く、反対に築地駅へはひとつ先の築地3丁目バス停が便利です。これらの状況は、バス停が都電時代の電停名、及び位置を忠実に承継している証といってもいいでしょう。日比谷方面からは、8系統の他に渋谷駅前からの9系統、新宿駅からの11系統がありましたが、8系統は築地から現在は平成通りと呼ばれる狭い通りへ左折し、茅場町方面へと向かっていました。11系統は勝鬨橋で隅田川を越え、月島方面へ直進しました。また、都電の第一次撤去後の昭和42年12月からは9系統の運行区間が変わり、11系統同様に晴海通りを直進し新佃島へと向かうようになりました。そして茅場町方面へは、錦糸町駅前行きの36系統が築地で折り返していました。晴海通りを東へ歩くと、すぐに新大橋通りと交わる築地4丁目交差点があります。左手は築地本願寺、右手は築地市場に続く場外市場で、築地らしさの中心に位置する交差点ですが、都電との関係では、かつてここから築地市場へと伸びていた引込み線にの存在を忘れてはならないでしょう。(次回へつづく)↑↑↑ブログランキング参加中です。
2009.11.18
コメント(0)
全467件 (467件中 1-50件目)