2011年01月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

真冬の筋肉パンパン見仏記14 烏丸御池 六角堂
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月10日 午後2:30六角堂紫雲山頂法寺 六 角 堂住所:京都市中京区六角通東洞院西入堂之前町248 アクセス:京都市営地下鉄「烏丸御池」駅5番出口から徒歩3分六角さんといわれ親しまれているこの地は聖徳太子創建、いけばな池坊の発祥の地です。境内の中には聖徳太子が沐浴したという池の跡があり、その畔に僧侶が暮らす本坊があったことから「池坊」といわれるようになりました。境内 四十五世専永氏のオブジェ池坊の祖先は、朝な夕なに花を供え、それが時を経て、いけばなの名手として知られ、いけばながひろがったといいます。山門をくぐって境内をご案内します。御本尊は如意輪観世音菩薩さんです。如意輪観世音菩薩御本尊は秘仏でおいでなので、この如意輪さんは御前立ち(おまえだち)といわれる模刻です。ただし厨子の中においでの御本尊は、御丈1寸8分。5.5cmの御丈です。門帳 寺紋・大日輪宝嬉しいですねえ。今回の見仏記初めてのテンプルカーテン&寺紋です。よくみかけるこの幕は五色幕(ごしきまく)といいます。「本堂古跡の石」ですが、京都の中心としてへそ石といわれています。六角堂 手水舎この手水舎の龍のお口はビロビロ~ンとして、おそ松くんにでるイヤミ氏のビロビロ靴下みたいで・・・あ~また罰当たりなことを言ってしまったビロロ~ン六角さんのお賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)はお優しいお顔です。お優しいっていったら興福寺南円堂のおびんずるさんが1番かなおびんずるさま納経所ちいさなお寺さんですが、華やいでいて京都の真ん中にいる感が大きいです。ぐるり池坊のビルとなっており本来はそこそこの広さがあったと思われます。写真を撮り損ねたのですが、門を出て、道を渡ると鐘楼があります。左手ガラス向うはおしゃれな池坊ビルで1階はスターバックスコーヒーです。実はね、ここのガラス張りのエレベーターのボタンをいたずらっ子のように押し続けて上へ下への大騒ぎでトップ画像、六角堂を上からの眺めで撮ったのね。最後の最後はとっても恥ずかしゅうございました。夜行バスで名古屋に出て、滋賀・奈良・京都の見仏記。11のお寺さんを拝観させていただきました。楽しくって楽しくってねえ。王寺の駅前では足がもつれて思いっきりこけちゃいました。が、カメラは死守!16時16分の新幹線に乗って19時30分にはマム家のグレズキッチンで、ビールを飲むマムでした。海龍王寺アップが終わると、ホッとするとともに、もう見仏に出掛けたくなるマムです。完
2011.01.31
コメント(2)
-

今日はポテトングについての考察あるよ・・・のはずなんだけどの巻
指をよごさずポテトチップスが食べられるポテトングなるバカバカしいもの発見。こんなの買う人おるかいな?ってことで、パンのトングでイメージ再現。 味気なさそう!ポテトチップは塩っぱくなった指をなめなめ食べるのが王道でしょっ。ったく。と、パソコンのキーボードを打ちながらトングでポリポリかりかりのマム。あ~、味気・・・・・・・ポリポリ・・・・・・。う!? 味気あるアルよ。その上指先が汚れないから、便利アルねぇ。こりゃあ、いいわあ。結論マムって変節の人!汗合気道寒稽古途中経過・・・昨夜同様絶好調
2011.01.29
コメント(8)
-

雑炊じゃだめっすかぁ?
?和風スープごはん って あぁた!合気道寒稽古途中経過・・・絶好調なり
2011.01.28
コメント(10)
-

恒例の合気道寒稽古で嬉し楽しや幸いナリ
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々の謎→京田辺・観音寺→京都・六角堂2011年01月10日京都のへそ真冬の筋肉パンパン見仏記のアップ途中ですがっ、毎年恒例の合気道の寒稽古がはじまりました。月曜日から日曜日まで、仕事からあがった後、毎日合気道の稽古にはいります。マムは合気道のお稽古するのが本当に本当に大好きで、嬉しくってたまりません。ただし下手なの。笑見仏記は、あますところ京都烏丸御池の六角堂ですが、アップがいつになることやら!明日はちょっと無理。あさってかしあさってかなあ。アップがない日は、あるいは皆様のところに足跡がつかない日は「合気道楽しんでいるんだなあ」って思ってくだされば幸いナ~リ。以上 マムより
2011.01.25
コメント(0)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記13 京田辺観音寺 国宝十一面観音観音
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々の謎→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月10日 午後1:20 京田辺観音寺 観音寺 大御堂息長山観 音 寺住所:京田辺市普賢寺下大門13電話:0774-62-0668要電話アクセス:近鉄京都線三山木駅下車 バス普賢寺下三山木駅より時間的にバスの便がなく、仕方なくタクシーに乗りこみました。歩くと30分以上はかかるでしょう。同志社大学の京田辺校の赤っぽい校舎が見えます。電話で拝観の旨を伝えていたためにご自宅のベルを鳴らすとご住職がすぐにでてきてくださいました。1300年前に天武天皇の勅願により義淵僧正が開基された由緒あるお寺ですが、大伽藍の面影は残念ながらありません。現在は大御堂とよばれる本堂と鐘楼があるのみです。しかし大御堂(本堂)には国宝の十一面観音菩薩さまが祀られています。本堂の脇に伐採された青竹が・・・!初代住職の実忠は東大寺二月堂のお水取りの創始者だった関係で、毎年お水取りに使う松明の竹を送り込む竹送りの行事を行っているそうです。東大寺お水取りのあの松明はこの地区の竹が使われいるのです。「寒いからスリッパをはいたままどうぞ」と、声をかけてくださり、お言葉に甘えます。本堂に入ると、ご住職がこちらでもお経をあげてくださいました。一人で、リュックを背負ってお寺を訪ねてお経をあげていただくのは本当にありがたく、心が解放されるひとときです。こちらが、国宝の十一面観音菩薩さまです。国宝十一面観音菩薩立像 奈良時代(天平) 木心乾漆造りホ~。丸みを帯びられた和やかなお顔だちの十一面観音さまです。揃ったお御足も幼子のよう。画像だと、金銅仏のようですが木心乾漆造りです。興福寺の阿修羅さんや、聖林寺の国宝十一面観音さんと同じような技法です。 滋賀・向源寺 十一面観音菩薩立像 /奈良・聖林寺十一面観音菩薩立像どうですか?この国宝の十一面観音観音さんたち。どのお方も超有名(笑)です。お美しいというと向源寺さんでしょうねえ。迫力やら研ぎ澄まされた感じは聖林寺さん。愛らしい方は観音寺さんです。みなさんは、どなたがお好きですか?マムはお三方にお会いして、一番心に残ったお方は、聖林寺(しょうりんじ)さんの観音様です。実はお意地の悪そうなお顔をしておいでです。お身体つきも、なんだか殿方を惑わすような感じ。マムは苦手なんですが、一番印象に残っているんですよ。不思議ね。よく歩きまわりましたっ!最後です。昨夜門前払いの六角堂です。つづく
2011.01.24
コメント(8)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記12 お友達のカプメイちゃんからの質問にお答えしますの巻
カプメイちゃんからのお題千手観音の背中ってどんな構造なんですか?さてさて、困った質問。寿宝寺さんのお背中はどうなっているのやら???ウンウン唸っても埒があかず不作法を承知で寿宝寺さんに電話っ。ィヤ~、寿宝寺さんのご親切なこと。お堂での説明同様、それはそれはまるで万葉を思い起こすような和らいだお声で寿宝寺さんの千手千眼観音さんのお手々のことを教えていただきました。「観音さまはお御足からお頭までのお身体は1本の木からできておいでですが、1000本のお手々は別です。最初の列のお手々は1枚の板をくりぬいて(彫る)います。次のお手々の列も1枚の板をくりぬいて、次もというふうに列ごとに1枚の板をくりぬいて、それを全部あわせて観音さまのうしろにつけています」こちらの寺庭さんは本当に、この観音さまを愛しんでらっしゃるんでしょうね。説明のはしばしに、観音さんを説明することが喜ばしいことなんだという気持があふれています。お話を聞いていてとても楽しくなりました。一件落着しかし、ちょっと待った~。唐招提寺 千手千眼観音立像じゃあ、唐招提寺さんの千手観音さんはどうでしょうか。昨年、唐招提寺さんの平成の大改修の様子がテレビで放映されました。残念ながらマムは見逃してしまいました。そこで、「私のひとりごと」というブログを開設しておいでの「ぴあの」さんにお願いして写真を借用してきました。ぴあのさんよりの借用です 転載厳禁ぴあのさんよりの借用です 転載厳禁この唐招提寺さんの千手観音さんの御手の作業は非常に神経を使うものだったときいています。この御手は差し込み式のようですね。カプメイちゃんのちょっとした疑問からですが、奥の深い質問でした。これからなおいっそう観音様のお後ろにも気持を注がなくてはね。葛井寺千手千眼観音菩薩う~!?この葛井寺(藤井寺)の千手千眼観音さんのお手々の整然としてきれいなこと。このお背中はどうなのでしょうね。マムの今期の課題ですっ。観音寺さんへ、国宝の十一面観音菩薩さん拝観へまいりましょうつづく1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々→京田辺・観音寺→京都・六角堂注:唐招提寺千手千眼観音さんの解体写真二枚は「私のひとりごと」のぴあのさんからの借用です。転載厳禁です。クリックされるとぴあのさんのぶろぐへジャンプします。*カプメイの独り言はこちらをクリックしてください。
2011.01.23
コメント(10)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記11 京田辺 寿宝寺の千手千眼観音菩薩立像
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々の謎→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月10日 午後12:00 近鉄三山木駅京田辺 マンホール電話で拝観の予約をしたのですが、その時に順路を教えていただきました。「近鉄三山木の改札はひとつです。進行方向に向かって歩くと、大きな車がビュンビュン通る道にぶつかります。そこを東に、東って右です。山に向かってってことです。進むと、横断歩道が2つあるので奥の横断歩道を渡って進んでください。」ハイ、その通りに歩くと寿宝寺さんに5分でつきました。欲を言えば、田辺病院を目安にと付け加えて欲しかったです。もっと貪欲に言えば「格闘技道場」の前を通るって言って欲しかった。笑良い子はこの通りに行くと間違いなく寿宝寺に着くよ~♪開運山寿 宝 寺住所:京都府京田辺市三山木塔ノ島廿番地 アクセス:JR三山木駅より徒歩5分電話:0774-65-3422 拝観:9~17時 (要電話) 本堂寿宝寺さんは何の変哲もないよくある小さなお寺さんと、いってよいでしょう。だけども、本当に1.000本お手をお持ちの千手観音さんでとても有名なお寺さんなんですよ。千手観音さんは40本の手で千手をあらわすものがほとんどで、実際1.000本の手をお持ちの観音さまは、こちらの寿宝寺さんと、奈良の唐招提寺さんと大阪の葛井寺(藤井寺でも可)さんのみです。 左・唐招提寺 右・葛井寺人懐こそうなお顔の寺庭(じてい・住職の奥さま)さんが、心も軽くってな感じで千手千眼観音さんが祀られたお堂に案内してくださいました。お堂には寺庭さんとマムだけ。目の前に1.000本の手を孔雀の羽根のようにきれいに広げられた観音様がおいでです。寺庭さんが般若心経を唱えてくださいました。参拝者にはいつも唱えてくださっているようです。贅沢なひとときです。千手千眼観音菩薩さんは、その御名前の通り1.000の目をお持ちです。どこに?・・・掌にひとつひとつ目が書かれてあるのです。ただし、墨で描かれているためにほとんど消えてしまっています。1.000本の手と1.000の眼でどのようなことも、どのようなものも、漏らさず救済しよとなさるわけです。寿宝寺 千手千眼観音菩薩立像 平安時代作この観音さまは、ちょっと怖いお顔に見えます。このお顔はお昼のお顔で、日が落ちて月明りで拝観すると(寺庭さんが暗くしてくださいます)、これほどにお顔がかわられるか!と、驚くほど慈しみ深い、お優しい顔になられます。あまりの変化にしばし呆然としてしまいます。画像とはまったく違ったお顔です。本当に驚きました。身も蓋も無いことですが、光の加減ですね。能面と同じ作用でしょう。この慈悲のお顔はぜひ皆さんご覧になっていただきたいものです。その昔はこの寿宝寺さんの法要は、お優しいお顔の観音さんの前で、つまり夜、月明かりの中で行われたそうです。マムが見惚れているあいだ、寺庭さんはコロコロとしたお声でお寺の伝来を説明してくださいます。聞くともなしに聞いていると、この寺庭さんはこうやってくる人くる人に丁寧に説明してらっしゃるんだなあ、この観音さんのことが大好きなんだなあというのがよ~く伝わってきて気持がなごみます。もう少しいたかったのですが、そうもいかずお名残りおしい気持でお堂をでてご朱印をいただきました。その時に、電話で順路を「車がびゅんびゅん」とわかりやすく説明してくださった若奥様にお会いしました。お声、説明の仕方から想像通りの可愛い若奥さんでした。この方もいずれ、お堂を案内なさるのでしょうね。お次はお手々の謎へつづく
2011.01.22
コメント(4)
-

魂振りの木(タマフリノキ)
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→お手々→京田辺・観音寺→京都・六角堂2011年01月10日海龍王寺境内 楠いつきても海龍王寺さんのクスノキは立派で、たくさんの葉っぱをつけてユサユサと大らかです。前々から、神社仏閣に大きな楠が多いことになにか意味があるに違いないと思っていました。日本の木彫のお仏像さんの早い年代のもの、例えば法隆寺の救世観音さんとか、お隣の中宮寺の弥勒さんなんかは楠から造られています。だから、多くのお仏像さんに用いられ神聖だから神社仏閣に植えられたかなあ…とマムは漠然と思っていました。でも、解答は出ずじまい。さて、話は変わって、融念寺さんの鼻筋の通った地蔵菩薩さんを調べるために2006年11月号の芸術新潮を読んでいました。まったくの偶然!出てましたクスノキのこと。オ~、当たらずとも遠からず。下記のようなやり取りが芸術新潮にのっていました。質問「現在神社でしめ縄をまわし、神木としてまつられているクスを目にします。このことと、仏像制作とは関係ないのでしょうか?」まるで、マムの心を見透かしたような質問答「日本の古代社会において、クスやツバキ、タチバナなどの常緑樹は魂振り(タマフリ)の木でした。さかんな緑を見ることにより心も体も元気づけられる、霊的な作用があると信じられていました。なかでもクスノキは大木になりやすいので神聖視されやすく、とりわけ落雷をうけたものは神霊の宿る霹靂木(へきれきぼく)として畏怖された。こうした土壌にクスで、仏像を彫る考え方がうけいれられたに違いありません。」京都 青蓮院のクスの大木クスノキは魂振の木なのだそうです。タマフリノキ・・・綺麗な言葉ですね。皆さんも神社仏閣いかれたら、魂振りの木を見上げてしばしご覧になってうやまってください。ちょっと脱線した見仏記でしたっ。さあて、京田辺の千手千眼観音さんで有名な寿宝寺さんへ行きますよっ。つづく
2011.01.20
コメント(10)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記10 海龍王寺四国八十八箇所御本尊
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月10日 午前10時30分 2011年01月10日海龍王寺眞言律宗 海龍王寺住所:奈良市法華寺町897アクセス:大和西大寺駅より奈良行きバス10分弱法華寺前下車すぐ1年ぶりの海龍王寺さんです。こちらは鎌倉期に慶派によって造られた十一面観音菩薩さまが有名ですが、今回、お邪魔したのは観音様もさることながら、先代の住職である松本重信(現ご住職のお祖父さま)が自ら刻まれた四国八十八箇所の御本尊の拝観が大きな目的です。海龍王寺 四国八十八箇所の御本尊(注:海龍王寺さんにお断りして転載しております)昭和28年にこの寺に先代が入られたときの海龍王寺は奈良で一番の廃寺といわれていたそうです。現ご住職のお祖父さまである松本重信氏は、1体1体、お仏像を彫られながら、荒れた寺の復興を誓われたそうです。(注:海龍王寺さんにお断りしてhpより転載しております)お仏像さまはどのかたも一木彫です。海龍王寺にお祖父さまが入寺されて60年。お孫さんにあたられる現在の石川重元ご住職は「祖父が入寺してから約60年が経ち、海龍王寺もようやく多くの方々に知っていただき、参拝の方にも訪れていただくことが出来るようになりましたが、八十八体の仏像の前に座るたび、祖父の思いを伝えていただいているような気がします」と、ご自分のブログに書きとどめていらっしゃいます。八十八体のお仏像さんはいつでも拝観可能です。本堂の右手に安置されています。十一面観音さんともども、お祈りしてくださいね。さて、クスノキです。海龍王寺さんのクスノキは立派です。気がつきませんか?神社仏閣に楠が多いこと。ずっとずっと気になっていたマム。お仏像さんの本を読んで謎が解けました。その理由は・・・次回へつづく*海龍王寺ホームページ*ご住職ブログ注:四国八十八箇所御本尊の写真は石川重元ご住職の許可 を得てHPより転載しております。
2011.01.19
コメント(4)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記9 JR王寺 北口駅前
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅前→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂<前回>融念寺の帰り、王寺駅北口の歩道をテクテク。ふっと歩道の石のオブジェに気が着きました。2011年01月10日 王寺駅北口歩道 トンボか~と周囲を見やると、歩道に点々と石の彫刻が。それもすべて違うの。洗練されたものもあればアニメっぽいのやら、メルヘンを感じさせるものと、とってもバラエティ。でもね、技術がちゃんとしてるのね。素人ぽかったり、稚拙じゃない。それがとっても快適です。公共の場とかにいかにも素人って感じの稚拙な作品が飾ってあると、マムはいつも不愉快になるんです。マムが撮ったものだけで26点もあります。作者はそれぞれ違うようですが、枯れて汚くなったフラワーポットを設置する自治体が多い中、これはとっても素敵なことだと思います。特に作風が自由だというのがいいですね。大きさも、設置の仕方も自由。見ていてとても楽しかったです。マムが撮った中から、アトランダムに数点をアップいたしましょう。王寺駅北口は頑張っています!鼻筋の通った地蔵菩薩さんをお持ちの融念寺のご住職は海龍王寺の石川ご住職の大学の後輩だそうです!知り合いの輪。海龍王寺さんに行きますよ~つづく
2011.01.18
コメント(8)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記8 鼻筋通った斑鳩 融念寺の地蔵さん
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→王寺駅→奈良・海龍王寺→楠→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月10日 午後9時00分 JR大和路線王寺駅 2011年01月10日竜田川王寺駅からテクテク歩きます。10分ほど歩くと大和川に行きつきその川沿いをまた10分ほどさかのぼると万葉のころより歌われた竜田川があらわれます。中学3年の時の古文の先生に佐保山の佐保姫が息を吹きかけると大和が春になり、桜が咲く。竜田山の竜田姫が息をかけると、秋になり紅葉がはじまる、と聞きました。以来、心に常にある川です。2011年01月10日融念寺神南 融念寺住所:生駒郡斑鳩町神南3 電話:0745-75-5031アクセス:近鉄・JR「王寺」駅下車 徒歩25分恵宝殿の拝観は月、水、金(9:00~16:00)拝観料:300円 要電話竜田川から左に本の少しいくと融念寺が見えてきました。おとないをのべるとご住職が気持よくでてこられました。聖観音菩薩像・地蔵菩薩像が安置されている恵宝殿とご住職マムは前々からこの地蔵さまが気になって仕方ありませんでした。重いまぶたに切れ長の目。筋の通ったお鼻。少し微笑むような唇。やっと、お会い出来ました。本来は同寺に近い三室山の中腹に鎮座する神岳神社の神宮寺(神南寺)に安置されていたと言われています。神様ではないかともいわれていますが、確証がありません。↓(参照)【送料無料】神像の美 ¥2.625言われてみれば「僧形神像」のような気がしますね。融念寺恵宝殿蔵 地蔵菩薩立像 平安時代 檜一木造衣の裾をもつお地蔵さまはおられずつまんだためにおこる衣文の優雅なこと。軽やかです。わざわざ、裾をつまむ所作をつけるなどはよほど腕に自信があった仏師なのではないでしょうか。ただ、平安の頃は、鎌倉期のように技に傾倒するよりもっと原初の信仰心のほうが勝っているでしょうから、単なるマムの思いつきなのですが。後ろのドレープ(?といってよいのか)はまるで、古代ギリシャの貴族がまとう衣のように波打ってきれいです。実は後姿を見させていただいのです人懐こいお顔のご住職はニコニコしながら「外国の人が作ったんかなあとも思われます」と言っておいででした。沈鬱なようで、笑んでいるようなお顔にすらりとしたお身体。古代ギリシャかローマのような衣裳。とてもとても不思議な地蔵菩薩立像さんでした。深淵をあらわしているようなお顔のお仏像さま。マムにはそう思えました。拝観出来て、とてもよかったお仏像のひとつです。融念寺さん自体あまり有名ではありませんし、このお地蔵さまも2006年の東博での「一木にこめられた祈り」展での展示でその存在が明らかになったように思います。まだまだ知る人、観る人の少ない融念寺地蔵菩薩立像さんです。どうぞ、足をお運びくださいね。斑鳩のマンホール次回は王寺駅前のステキな石の彫刻をつづく
2011.01.17
コメント(4)
-
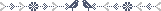
真冬の筋肉パンパン見仏記7 大好きな夜の興福寺南円堂の、、、納所さん
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂<前回>1月9日 午後8:10 奈良興福寺 南円堂法相宗大本山興福寺どんなに疲れていても、いつも夜の南円堂・一言観音堂に来てしまいます。繁華な場所で民間信仰がこれほど根付いている場所はありません。一言さんに願をかけている人。お百度を踏む人。孫を連れてくる人。犬の散歩がてらの人。でも、今夜はとっても寒くて、珍しくこの時間、人がいません。写真を撮っていると、お寺の納所さんが「こんばんは」と声をかけてくださいました。そのお声はとても優しく、お人柄をしのばせるものです。あっ、あの人だ!1年前にマムに親切にしてくださった納所さんです。1年前の1月11日の明け方、この納所さんは三重塔の柵のカギをあけてくださり写真を撮らせてくださった方です。また会えるんじゃないかと思っていたマムは嬉しくって仕方ありません。勿論納所さんは覚えておいでじゃありません。でもね、納所さんったら去年と同じように「三重塔を撮るなら鍵をあけてさしあげますよ」って言ってくださったんですよ。納所さんに、暗闇に浮かぶ建築中の金堂を眺めながら、完成が楽しみねと声をかけると、「僕はあと3年でここをやめるから、残念やけど見られんのです。」と。能天気なマムは「じゃあ、見に来ればいいでしょ」なんて言い放ってしまいました。「そうやねえ」と、納所さんは笑いながら応えてくれたのですが。御名前を教えていただきました。奈良でマムが一番好きな興福寺の納所さん**さん。また会えるに違いない!明日は王子の融念寺をご紹介しましょうJR奈良駅がきれいになったのでびっくりつづく
2011.01.16
コメント(6)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記6 夜の烏丸御池六角堂
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月9日 午後6:30 烏丸御池六角堂には明るいうちに行く予定でしたが大幅に狂っちゃったなあ。行くまいか、行こか・・・。拝観時間をすぎているけど、暗い境内を歩くのも一興。地下鉄烏丸駅5番出口徒歩5分ハイ、門が閉まって門前払いなマムでした。いけばな発祥の地 紫雲山頂法寺 六角堂以上六角堂より笑奈良に帰っちゃいます。今日、はじめての食事です。近鉄京都線特急車中にて。つづく
2011.01.15
コメント(0)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記5 京都 福田寺異形の龍神
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂<前回>1月9日 午後2:50 京都 向日町実はね、みうらじゅんさんがこのお寺さんのことをウエブにチラっとアップされていたのね。「異形」って。異形って言われちゃあ行かないとねえ。フクダデラ!フクダデラは向日町にあります。マムは近江八幡駅の駅員さんに問いましたっ。「もしもし駅員さん。アミホシ線でムコウヒ町に行きます?」駅員さんは言いました。「はい、アボシ線でムコウ町に行きます」。あぼしせんむこうまち網干線向日町!でした。 笑駅から10分弱のはず・・・。迷わぬ先のお巡りさん。交番で聞きました。「フクダデラはどう行けばいいでしょう」と。お巡りさんは言いました。「フクデンジですね」と。ふくでんじ福田寺でした。かさねがさね 笑&恥。テクテクで、途中で迷子になったマムはほかほか亭さんに入って「ふくでんじさんはどこですか」って聞きました。そしたら店主がえらい驚きはって、「車やろ?」っていいはりました。「いえいえ歩きです」と言うと、即座に「そりゃあ、無理や。歩きじゃ到底無理や」ですって。え~~~~~。「近いって聞いたのに」。するとね、店主が、道に出て来て「大変やなあ・・・歩きは無理や・・・・・・」と言いつつ間をおいて、「アソコや」と、笑いながら指さしてくれました。ったく、すぐそこでした。ふたり顔を合わせて大笑いです。イケズヤナア。と、なんだかんだで、おまっとさんでした。西山浄土宗 迎錫山 福 田 寺住所:京都市南区久世殿城町5電話:075-931-2887アクセス:JR向日町徒歩10分弱福田寺さんは奈良時代に行基菩薩さんが開祖されたと伝えられて七堂伽藍を有していたいいますが、現在のお寺は、街中にある普通の小さなお寺さんといえます。電話でおとないをいれていたこともありご住職さんが、気さくに本堂に案内してくださいました。で、なんとこの本堂で、1時間どころか2時間ほどお茶をすすりながら、ついつい四方山話に花が咲き、気がつけば、あたりはうっすら暮れているではありませんか。ご住職は落語とジャズがお好きで、マムと同郷の方。そりゃあ、盛りあがりますわ。それとね、長居したのは808段後遺症で、足がいうこときかなくて立ち上がれなかったってこともありなの。笑福田寺 龍神堂さ、「異形」です。実はこちらの福田寺の雨乞いの龍神さまが「異形の龍神」といわれているのです。このお像はその昔、境内の「板井の井戸」より出現されました。この井戸は京都の名水として昭和30年頃まで水がわいていたとのことです。旱魃(かんばつ)の水不足の時には「雨乞い」の法修が行われ、それは昭和初期まで続いた由。この龍神堂は1年1回8月の法要の日のみ正面の扉を開けるそうです。表の扉をあけると雨が降るそうです。だから普段は開けない。実際、8月の法要の夜は雨が降るとのことです。お待たせしましたこちらが、福田寺の龍神さまです。ハ~~~・・・今まで、拝観した龍神さんには似ても似つかぬお姿に恐縮のマムです。が、後ずさりはならじ!よく観るとっ、ふんどし姿に、膝をつけ、両手を前に差し出す、ぐりぐり目に開いた鼻は、あれれ!上島竜兵ちゃんをおもいおこさせます。勿論、そんなこと、ご親切なご住職には言えません。偶然ですね、りゅうの字がついてるだからと言って敬意がないなんてことはありません。なんともいえない畏敬の念がわいてきます。筋肉隆々としたこの雰囲気、ぐりぐりの目、褌姿は、奈良興福寺の天燈鬼、龍燈鬼を彷彿させますが、興福寺のお像は鎌倉期の作品で、福田寺の龍神像は平安期のお作のようです。尊い菩薩さまの眷属(けんぞく・従者のこと)として作られたのかもしれませんね。興福寺 龍燈鬼像 1215年運慶の子・康弁作造られた当初は龍神さまではなかったでしょうが、雨乞いの神として慕われ敬われて畏れられて今では、立派な龍神様なのですよ。どうですか?異形の龍神様は。*龍神堂には「摩耶夫人像(まやぶにんぞう)も祀られており安産の信仰を集めています。注:拝観される場合は要電話ちょっと遅くなっちゃいました。がんばって烏丸御池までいきましょうかね。つづく
2011.01.14
コメント(6)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記4 近江八幡 長命寺への本当の理由
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂<前回>2011年01月09日 長命寺山門長命寺を訪れた大きな理由は、奈良博物館に寄託されているこの美しい地蔵菩薩立像の本来安置されていたお寺をこの目でたしかめたかった。ということです。滋賀 長命寺 地蔵菩薩立像(奈良博寄託)1254年 栄快作栄快はマムの好きな快慶の弟子です。なるほどなるほど、この美しさは快慶の持ち味そのものです本来のお立ちになるべき場所は、この長命寺さんなのです。この風光明媚にして、冬の寒さの厳しい人を寄せ付けないような山においでだったんだと、空気を身にまとうマム。マムは本堂に参拝すると、地蔵堂はどこじゃ?と、こまねずみのように石段をかけ、坂をのぼります。太郎坊大権現社ここぞと思えば太郎坊大権現社。護摩堂それではと思えば護摩堂。いたるところに石塔やご神体の巨岩。修多羅岩こちらは三仏堂で奥は権現の拝殿だし~~。おっ!井戸でしたっ。と、見つからず本堂で納所(なっしょ)さんに聞いてみると、この本堂内陣にご本尊の観音様とご一緒だったとのことでした。なるほどなるほど。お賓頭盧さまさて、もう一度、長命寺を目にやきつけてこのお山をおりましょう。ヒエ~!下りの石段の怖ろしいこと。ここで、滑り落ちたら、尾?骨折るのは確実。それはそれは、緊張しました。体力も消耗しました。でもね、下りきっても、「ベツニ~」っだったのですが・・・。ここでおきたわけね。便所事件が。バス停前の和式お手洗いにはいって・・・。立ちあがろうとしたら、筋肉が完全にバカになっていて、立ち上がれずにそのまま尻もちをつきそうになったの。手は空をつかみ、目は泳ぎ不様でした。涙背中に背負ってた分厚いリュックが壁にぶつかってマムの体はそこでとまる・・・間一髪でした。笑これが、合図か!急にふくらはぎとももが痛いこと痛いこと。パンパンに張って、まっすぐ歩くこともかなわない見仏記になってしまいました。すごい寒い日らしいのだけれど、歩きまわるマムはポッポと体が火照り近江八幡行きのバス待ちで、竹生島行きの船着き場を眺めながらアイスクリームを頬張るのであった。傍らには、観光バスの西武ライオンバスが竹生島に渡ったお客さんを待っているのであろう。「回送」のマークをつけて駐車している。近江八幡行きのバスはもうすぐ!午後1時28分にくるはずじゃあ。と、道を眺めていると、隣のライオンマークをつけた西武観光バスがぐるっと方向転換して停留所に来たのであった。西武ライオンバスの衣を着た近江鉄道バスでした。さあてと順調です。これから京都に向かいます。つづく
2011.01.13
コメント(4)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記3 近江八幡 長命寺808段の石段
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺1・2→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月9日 午前11:50 長命寺石段前姨綺耶山長 命 寺住所:滋賀県近江八幡市長命寺町157アクセス:JR近江八幡駅より近江鉄道バス20分長命寺下車、石段を徒歩20分JR近江八幡駅からバスに揺られること25分。マムのほかに一人いた乗車客もいつのまにかおりてマム貸し切りバス状態。終着駅の長命寺に着くと、運転手さんが808段は大変だからわき道から行ったほうがいいと、何度もすすめてくれます。でも~・・・。せっかく東京からやってきたのにこの石段をのぼらないなんて、スキーに行ってソリで遊ぶようなものだもの。では、なくて、いつも言っているように、往時の人々の信仰の気持ちをつかみたい。じゃあ、なるべくその人たちがおこなったようにして、少しでも近付いてみたい・・・な、気持かな。石段、一気のぼりのはじまりです。よぉいドン古い石段は高さも、石の種類もまちまちです。20段ほどで、膝が笑だしてきました。マズイ! が、大丈夫です。マム車はエンジンが軌道に乗るとウソみたいに華麗に(笑)動き出すので・・・。聞こえてくるのは竹々のカラカラと鳴る音。雪の落ちる音。鳴く鳥はカラスのみ。結界がみえてきました。この向うは聖域です。奈良の忍辱山 円成寺の勧請縄を思いだします。ここは聖域なのに、だからいやだと言ったとか言わなかったとか、喧嘩しているカップルあり。そりゃあ、半端な気持ちで、そのうえ、そんな靴じゃあ無理だわ!と、追い抜くマム。ふり返ると琵琶湖が空のように見えます。マム車、絶好調です。山門をくぐり更に石段を上がると、「西国三十一番札所 長命寺」明記された石柱があります。本堂?なオブジェお賽銭をいれたら鐘をついていいみたいです。だって賽銭箱が鐘つきのところにあったから・・・いい加減情報です。境内にはいりマムはまたもありとあらゆる石段をのぼりお堂をの前に立ちます。さて、マムがこの長命寺に拝観にきた理由を話しましょう。滋賀長命寺 地蔵菩薩立像つづく
2011.01.12
コメント(12)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記2 滋賀高月 向源寺
1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂1月9日 午前9:00 高月新宿発の夜行バスは午前5時30分にJR名古屋駅に到着。まずマムは駅のマックにて腹ごしらえ。ここの店員さんは東京のマックのこてこてマニュアルと違って少し自然体。う~ん新鮮!駅員さんに「高月」行きの切符をもらって、ホームに行こうとして・・・ハテナ???「高槻」!それでかぁ。異様に切符代が高かったのは。もうすぐ出発だけど、とにかくかえてもらわなくっちゃと、窓口へ。が、なんと打ちこみ最中に窓口パソコンがフリーズしてうんともすんとも言う事聞かないの。あせる駅員、戸惑うマム。で、駅員さんは慌ただしくドアの向こうに消えて返金のお金を握りしめて登場。「間に合わない~」と言うマムに、「まだ間に合う!」と怒鳴る駅員さん。ハイ、滑り込みセーフでした。という、幕開け。 国宝の十一面観音さんで有名な向源寺(渡岸寺観音堂)は、駅より徒歩5分ですが、道がわからず、前行く男性に聞いたらすぐそこでした。びっくりしたのはその男性去り際の言葉。「わざわざ観音さんを見に来てくれてありがとうございます」。お寺さん(お仏像さん)と地元の人が密着しているんですよね。これは守山市の福林寺を訪れたときも感じたことです。これなんですよ!これ!2011年01月09日 向源寺 慈雲山 向源寺(渡岸寺観音堂)住所:滋賀県長浜市高月町渡岸寺215番地アクセス:JR北陸本線「高月駅」下車 徒歩 5 分 向源寺さんの十一面観音さんは日本の国宝十一面観音さん七体のなかで一番お美しいと評判のお仏像さまで、マスコミによくとりあげられるのでご存知の方もおおいのではないでしょうか。琵琶湖随一有名なお仏像さんといっていいかな。 鎮守の天神様 本堂は改修中でビニールシートに覆われていました はっきり言えば、立派なお寺さんというより地方によくあるごく普通のたたずまいといえます。琵琶湖の周りのお寺さんはだいたいにおいてこじんまりとしていると言っていいと思います。でも、でもですね。あらまっ、と驚く素晴らしいお仏像さんをおもちだったりするのですよ。ここいらが、京都とは違うのね。京都は建物とかお庭とか天井に苦心惨憺して、風景としては立派なのにお仏像が今ひとつってことが往々にしてあるんだなあ。 こういう組木がきれいよね。うっとり。な、ことより観音さまにうっとりしましょう。頑丈な慈雲閣という名の収納庫のなかに観音さまはおいでです。 慈雲閣 さ、さ入りましょう。 国宝十一面観音立像 こちらはぐるりと周囲をまわれるので、 後ろのお顔も、とてもよく観ることができます。 優しいお顔の裏は暴悪大笑面(ぼうあくだいしょうめん)怖!平安初期に制作されたといわれ、観音さまと、台座に垂れる天衣も含め、1木の檜から造られています。お姿はインドの神的なものを彷彿させます。耳元にはヒンズー教のシバ神がつけていたという大きな耳飾りがさがっています。 十一面観音さんは本面の頭上に小さく11面を表すのが一般的ですが、向源寺さんの観音さまは本面の左右に大きく2面をお持ちの上に髻(もとどり)を結って冠をつけた菩薩さまがおいでなのも特徴です。 いかがですか?こちらの、観音さまと、奈良の聖林寺さんと京田辺の観音寺の観音さまがよく比べられます。のちほど、観音寺さんの観音さまも紹介いたしますので、どうぞご自分でおくらべください。ただ、写真と実際、自分の目で拝観するお姿は違うと断言しておきます。高月のマンホール 注:国宝十一面観音さん七体は、奈良の法華寺、聖林寺、室生寺、京田辺の観音寺、京都の六波羅蜜寺、大阪の道明寺です。お次は近江八幡からバスに乗って長命寺にまいりましょうか
2011.01.11
コメント(4)
-

真冬の筋肉パンパン見仏記1 はじまり
2011年01月09日 去年の暮よりポカポカ陽気だった東京ですが、急に真冬とういうか本来の気候に。で、毎年この時期に見仏をスタートするマムは、こともあろうか、夜行バスにて8日午後11時50分新宿を出発です。嗚呼、また一睡も出来ないに違いないと後悔すること1000ミリバール(意味不明)。笑寝れないにちがいない。あ~、眠れない。と、「もうまもなく名古屋です」のアナウンスでお目覚め。なんと堂々の熟睡でした。苦笑2011年01月10日 さて、名古屋に着いたマムはJRにて滋賀へと入り808段の石段一気上り。行きはよいよい帰りは怖い・・・そのもの。残雪および氷のはった石段を下りるのは、上りにくらべて極度の緊張を体に強い、なんとお寺さんを下りて入った和式手洗いで、立ちあがることができず、寸でのところで尻もちをつくところでした。恥 2011年01月10日 筋肉パンパンなマムの滋賀、奈良、京都の見仏記がはじまります。先に言っておきますがっ、長くなりそうですじゃなくて、長いですから。2011年01月10日 と、キーボードを打ちこみながら、1月10日午後9時40分ひと風呂浴びて缶ビール2缶めのアタクシです。1月9日滋賀高月・向源寺→滋賀近江八幡・長命寺→京都・福田寺→京都・六角堂→奈良・興福寺1月10日奈良・融念寺→奈良・海龍王寺→京田辺・寿宝寺→京田辺・観音寺→京都・六角堂
2011.01.10
コメント(8)
-

真冬の見仏のはじまりです
お店を閉めて合気道のお稽古をして・・・マム号 マムの相棒マム号にたっぷり靴クリームを塗りました。23時50分の夜行バスで、滋賀、奈良、京都の真冬の見仏に出発です。バスのダイヤもしっかり押さえての綿密なスケジュールをたてる楽しさ! 滋賀(向源寺、長命寺)→京都(福田寺、六角堂)→奈良(融念寺、額安寺)→京田辺(観音寺、寿宝寺)さあて、スケジュールどおりにいくかな!
2011.01.08
コメント(14)
-

え゛~ 烙印をおされてしまって1月4日は**記念日!
2011年01月04日正田醤油本社 群馬県立館林美術館で、至福の時を過ごしたマムは美智子皇后陛下のご本家、正田醤油をチラ見し、館林駅の手前の、ショショショジョジ♪で有名な茂林寺を通過し、気持朗らかに帰路につくのです・・・。 大宮、赤羽、池袋、新宿。順調です。新宿で中央線特快に乗り換えます。特快だと2駅でマムの街に着いちゃいます。リュック背負って基礎英語2をイアーホンで聞きながらつり革も握るマムは颯爽としている。いるはずだっ。そのつもりだっ!ところがっ、目の前に座る年の頃は20才くらいの男の子がなんたることでしょう。こともあろうか、席を立ちながら言うではありませんか。「どうぞお座りください」だ、だ、だ、誰に言うとる。えっ?あ、アタクシと、まわりを見まわすマム。いや~、呆然としちゃいました。思わず、怪我でもしていると思われたかなと居を正すマム。いや、まさか妊婦と見まがわれたか。動転。年寄りに見られたのよ。 あのね、たしかにいつも言いますようにマムは0才か100才といわれたら100才の方に入りますがぁっ。いくらなんでもまだ、席を譲られる年ではない。はず・・・。でも、この若者は意を決してマムに声をかけてくれたに違いない。恥をかかせてはいけないと・・・思いましたよ。アタクシ。でもでも、やっぱりそんな年ではないし、まったく疲れてはいない。抵抗!!!ってことで、丁寧に丁寧にですね、「アタクシは疲れてないアルよ。せっかくお座りになられたのですから、あなたがどうぞお座りくださいアルよ。お気持だけいただくアルかたじけないあるそうろう」と言ってご遠慮させていただきました。2駅だからすぐに降車駅になりました。降り際に再度、「お気持ちとっても嬉しかったです」と声かけたてまつり候。ちっ嬉しくなんかないわい。すんごいショック。この白髪だろうか?この猫背だろうか?このスッピンのせいだろうか?この不幸せ顔のせいだろうか?結果!総合的に見て年寄り。 あなたが席を譲ってくれたから、 2011年1月4日は年寄り記念日
2011.01.07
コメント(10)
-

1月4日 群馬県立館林美術館へ
2011年01月04日群馬館林美術館 群馬県立館林美術館住所:〒374-0076 群馬県館林市日向町2003tel:0276-72-8188(代表) fax:0276-72-8338 館林美術館はとても美しい建物です。 光と風と水を感じます。 この美術館に三輪途道先生の彫刻が寄託されており、そのうちの11点が、4月3日まで展示されています。大きな作品は「父子像」や、「下仁田のおじい」、「下仁田のおばあ」、小品は「縄文からの道」や「猿を待ってた日」等です。下仁田のおじい・おばあは現代の肖像彫刻の白眉だとマムは思っているので、直接、観ることができてそれはもう、穴があくほど凝視透視してきちゃいました。 マム所蔵 なめくじ 個人の方が、三輪先生の作品を収集されていて、それを自分だけで愛でずに、寄託してくださったおかげで、マムは観たことがなかった先生の作品に出会えました。この収集家は、想像ですが、かあちゃん猿の像も収集していらっしゃるのではと思っています。三輪途道 かあちゃん猿 今回は残念ながら出会えなかったのですが、なんとか、この猿の母子像に出会いたいものです。*三輪途道先生公式ホームページ 館林駅よりの巡回バス9:1811:1314:3316:52美術館より駅へ9:2111:2614:3616:55 1月4日編 つづく
2011.01.06
コメント(8)
-

ちょっとニュージーランドに行って来ましたっ
ニュージーランドでポタリングって、、言ってみたかっただけなの。 乳銀杏 2010年12月27日吉祥寺、繁華街。民家の庭先の乳銀杏の大木です。2011年 初ウソ*乳銀杏という名はmomoさんが教えてくれました。
2011.01.05
コメント(10)
-

お節自慢 笑
2011年01月01日お節 夜更かしおよび酒飲のため、イカちゃんもマムも元旦の朝は「遅く起きた朝」になっちゃいました。大急ぎでお節の準備です。作っている経過をちょこちょこお見せしましたが↑こんなふうにしてみました。あとで考えたら椀物は左に置くべきだったかと。まっ、ご愛嬌ってことで。牛タンの味噌漬け 鶏肉巻き 自慢になっちゃいますが、どれも本当においしくできあがりました。特にはじめてつくった鶏肉巻きは上品な味で全員びっくりです。この付け汁がまた絶品で、塩と生姜と白ネギに昆布茶で味付けしたのですが、滋味豊かな、体にとってもよさそうなスープとしていただきました。美味しい物を食べて氏神様にお参りいき 2011年01月01日杵築神社結局、思わず世界の平和をお願いして自己中心なマムは年初から没。嗚呼、今年も中途半端な黒マムと白マムが混在したマムなんだろうなあ。笑
2011.01.02
コメント(22)
-

恭賀新年2011
滋賀三尾神社門帳あけましておめでとうございます 昨日2010年12月31日はユニクロの年末限りのセールに行ってヒートテックのシャツを買ったり、アイスクリームをたくさん買い込んだりと甚だ私的なマムでしたがっ。今年はですねっ景気がよくなればいいなあ合気道が上手になればなあ病気にならないようにね可愛いお嫁ちゃんとか凛々しいお婿どんが来ないかなと、もっと私的なマムですから。告白するならば、いつもいつも世界の平和とかを願ってきたマムですが、もうなんだかこの年になると「もっいいかっ」って思うようになっちゃいました。って言いますか、ちっともかなわないのでまず、身の丈の願いからと・・・。今年は(も?)自己中心で走ってみようと思っております。それでもよろしければ、皆さま、仲良くしてくださいね。笑2011.1.1 兎年
2011.01.01
コメント(14)
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-
-

- 地球に優しいショッピング
- ☆洗たくマグちゃん プラス☆
- (2025-09-04 23:16:08)
-
-
-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪
- ☆木製クリスマスツリー☆
- (2025-11-30 09:05:09)
-
-
-

- ☆手作り大好きさん☆
- 22cmドールスタンドカラーブラウス完…
- (2025-11-30 09:02:43)
-







