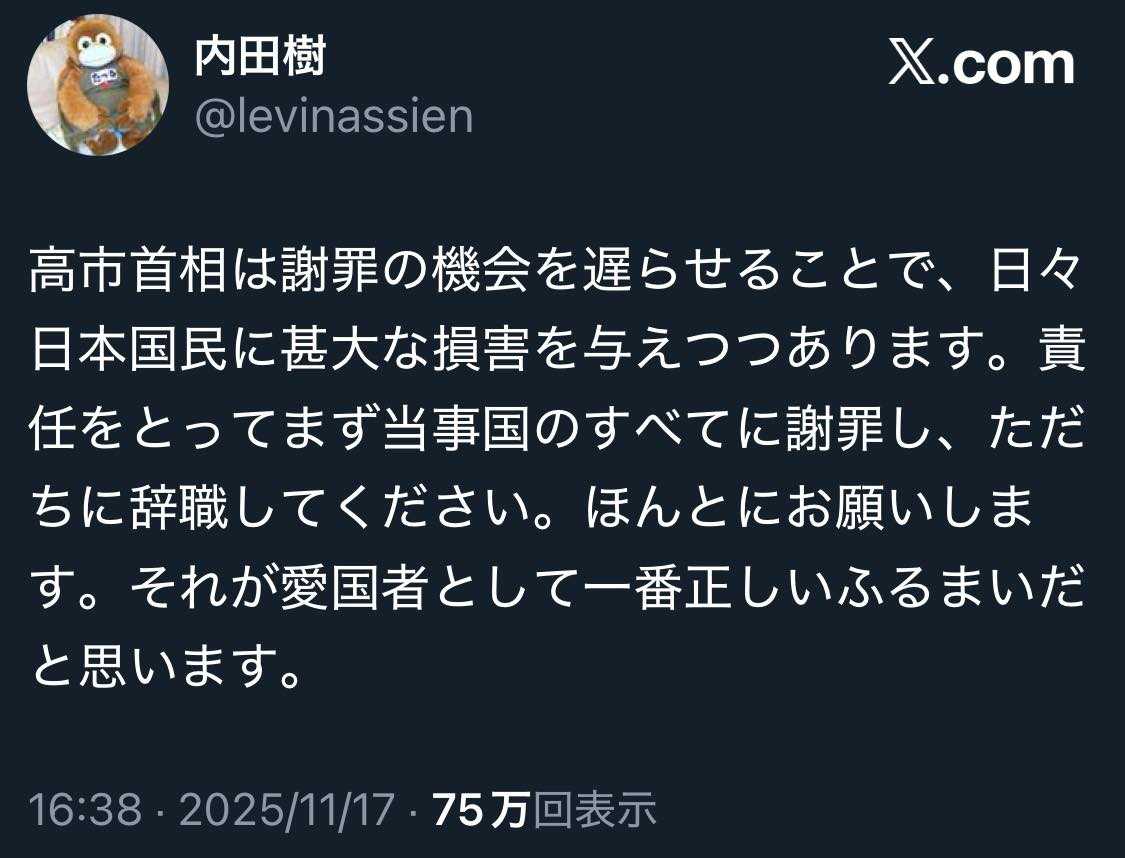2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年01月の記事
全32件 (32件中 1-32件目)
1
-
輝いて生きる
マズローの欲求五段階説の最上位に位置するのが「自己実現」の欲求である。この説によれば、最底辺である「生存」の欲求からは間を通り越して一挙に「自己実現」の欲求に行くことはできないとされている。飢餓に苦しむ社会では、「自己実現」など夢のまた夢。その日一日を生きながらえるのが精一杯なのであり、社会がそれを許さない。これに対して、今の日本はどうか。フリーター等であっても最低限の生活はできる(責任がないぶんだけ気楽かもしれない)し、思ったところにもいける。こんな自由はない。この意味で、もうすでに、日本は「豊かな社会」なのであり、「自己実現」の基盤が成立している社会なのである。人間は、過去から営々と続く歴史の中で、命のたすきをわたされている。その中では、飢餓等に苦しんだまま死んでいった人々も多数いるだろう。今、我々はそういった先人たちのお陰で生きている。現在のように基盤が整っている社会において、その生きている価値に気づかず、瞬間瞬間の尊い時間を無駄遣いし、ただ生きながらえていては、苦しんだだけの社会を生きた人々に申し訳がない。私のセミナーの受講生の一人であるSさんは、何事にも、非常に熱心だ。一瞬一瞬を大切に生きている。彼女は言う。人間は「輝いて生きるのだ」と。本当にそのとおりである。これからは、私も自分に対して、「今日は輝いていたか」を反省の一項目にしようと思う。
2006.01.31
コメント(2)
-
災い転じて福となす。
一昨日より、諸般の事情から、某社からこちら(楽天)に移った。ありがたいことにアクセス等の反応が良い。まさに「災い転じて福となす。」もうすぐ節分。年回りを見る場合などは、元旦が基準でなく、節分が基準となる。もうすぐ運気の流れは転換期を迎えることとなる。
2006.01.30
コメント(0)
-
未来に点を打つ
昨日の「夢の実現」に関して一言。誰もが夢を描いている。しかし、それを全てが実現しているとは言いがたい。それは、未来に点を打っていないからではないか。達成時期を明確にし、未来の時点の視点から現状を直視し、足りないところや課題を抽出して解決していくのである。また、夢は個別的・具体的・ビジュアル的でなければならない、この点は、経営者の経営計画も同様である。漠然とした計画で達成できたためしはない。
2006.01.30
コメント(0)
-
夢の実現
今日は日曜日。ちょっと自分の夢のことを書いてみます。私は、20台後半のときに三つの人生目標を掲げました。1 30歳までに、講演講師をする。2 40歳までに、単独書籍を発刊する。3 50歳までに、大学の講師をする。人によってはなんと「ちっぽけな」と思われるかも知れませんが、20代後半の私にとってはとんでもないことだったのです。実は当時、赤面症でドモリ。人前で話すことなんてとんでもないことだったのです。これは、おかげさまで、29歳で実現したのですが、その後も挨拶などではわずか80人足らずの人の前で1分半話せなかったのですから。現在では1000人以上の方々の前で話す機会もあります。現在の私しか知らない人は「うそだろう」というのですが、事実です。また、この出来事をきっかけに、私は「人間は自分を変えることができる」と実感したのです。次の書籍出版は、ちょっと遅れ、41歳のときでした。その前から分担執筆は何冊が書いていたのですが、単独となると困難を伴いました。当時も不況であり、まして無名人の著作を出版し、売れなければ出版社は大赤字です。実に三つの出版社から断られました。「自費出版だったら」という話もありましたが、その余裕もなく迷っていたところ、ある方を通じて中経出版を紹介され、同社の英断で出版させていただくことができました。その後短期間でたいぶ出版しました(当法人のホームページの「著作集」をご覧ください)。すべて出版社からの依頼でした。一生懸命やっていると応援者が現れてくれるのです。三番目の大学講師の実現は早く42歳から3年間、聖学院大学でお世話になり、今年からは、獨協大学と明治大学大学院(ビジネススクール)で教鞭をとることが決まりました。今年、四回目の戌年を迎えます。その中で、「ああ、人生とは正直だ」と実感しています。また、「原因づくりをひたすら続けることが大切だ」と思っています。数年前より巷では「願望実現」の本等がはやっていますが、その骨子は「潜在意識に夢を叩き込め、そうすれば実現する」というものです。しかし、私の人生経験で得たことは次のような点です。1 潜在意識磨きが大事。汚いところ、耕されていないところ、肥やしのないところに種を蒔いても芽が出ない。2 私欲ではなく公欲の目標が実現しやすい。これは周りが応援してくれるからである。3 ある結果は原因である。次の結果が出るための原因である。4 夢をいろいろな場面で口に出して言う。人前での話や書籍は、拙いかもしれないが、いままで培ったノウハウ等を広めて、悩める人たちのヒントを差し上げたい。大学講師は後進に教えを伝えたい。という一心だったのです。そして、大学講師となれば、人前で話せ、本も書ける人でなくてはつとまりません。つまり、セミナー講師や書籍は、結果として、大学講師の「原因」だったのです。また、すべてにおいて様々な方々からの陰に陽にのご支援や紹介がありました。ご縁です。ありがたいことです。「信なくば立たず」という言葉がありますが、「縁なくば拡がらず」です。我々人間は大宇宙と比べればほんとちっぽけな存在です。しかし、その意識は宇宙と同等であり、拡がってもいます。「夢を実現できる」という人間にしかできない素晴らしい能力を一人ひとりが世のため人のために活かせばどんなにも素晴らしい社会が実現できることでしょう。「夢の実現 それば夢現(無限)」
2006.01.29
コメント(0)
-
古人(いにしえびと)との対話
昨日は、当法人の賀詞交歓会と本年最初の経営研究会を開催した。同会は、地元の企業経営者のために、最先端・本物情報を提供したいという気持ちから始め、早35回となった。ありがたいものである。今回は、経営理念研究の第一人者である佐々木直先生。先生には、『古典経営論』という著書もある。一昨年出会い、昨年は幾度もご指導戴いた。啓発され、仏教等の古典を読み出した。学生時代から社会人なりたてのころは、文庫本だったが、老眼になったこともあり、今では、もっぱら岩波文庫ワイド版である。若いころ気がつかなかった、見過ごしたことが見えてくることがある。仏教の本(「ブッダのことば」など)からは、こんな簡単なこと(しかし継続した実行は困難なこと)をお釈迦様は唱えていたのかと驚くことがある。長年の風雪に耐えた古典に学ぶことは大きい。
2006.01.28
コメント(0)
-
一つの時代が終わり 新たな時代が始まる
中国に古来より伝わる「易学」では、すべてのものごとは生々流転し、極端なことが起きるとそれをピークにして反対の流れが生まれると言われています。つまり振り子のように一方に極端に振れれば、元に戻る力が加わることです。 昨年の総選挙では、思いもかけない自民党の圧勝に終わりました。これは国民が改革を支持したことのあらわれと見ることもできますが、日本はもともと大衆心理操作には弱いように思います。近い歴史をひもといても、消費税導入の際の「マドンナ旋風」です。あのときも立候補者の能力の有無にかかわらず、「消費税反対!」を唱えれば当選してしまうのですから。昨年の場合も、改革や郵政民営化を唱えていれば当選できたように思います。今までは「抵抗勢力」がいるという理由で改革が進まなかったかもしれませんが、今後は言い訳は許されません。そこで、財政再建のために「増税路線」を走ることになり、それが実現したときに国民は「これはないんじゃないの」と失望することになるわけです。 昨年がある極のピークであるとすれば、昨年はひとつの時代の「終わりの始まり」であり、ここ数年掛けて、大きな社会変革が予想されます。 国の財政も伝えるところによれば相当悪化してあり、今後の人口減少社会の到来、団塊の世代の大量定年などを控えて、ここ数年で社会の枠組みが大きく変わっていくことでしょう。法が変わり、制度が変わり、仕組みが変わる。それが大変革の総仕上げですが、私は従来から、この変革は30年掛かるのであるから2006年からは、「制度変革の10年」であると申し上げておりました。最初の10年は「思想の時代」であり、次の10年は「行動の時代」です。最後の10年が「制度変革の時代」なのです。これは明治維新などの歴史を見てもわかることなのです。この意味で、今年は、ひとつの時代が終わり、新しい時代が始まるといえるのです。この荒波の中で、一番大切なことは「時代の流れに抵抗しないこと」です。しかし、その中で「自己の本質」を見失わないことが最も必要なことです。このようなときにこそ、自己の存在意義を今一度再確認すると同時に、今回の制度変革の根底(ほとんどの方々が気がつかないでしょうが私は「変革」より「分断」と認識しています)には「意識の変革」が起こっていることに気づくべきです。簡単に言えば、自己が生かされて生きていることに感謝し、お役立ちさせていただく気持ちが持てるか、ということなのです。「利他の心」といっても良いでしょう。これは企業経営だけでなく、ご自身の人生の経営にも不可欠なのです。(当法人広報誌 念頭のごあいさつより)
2006.01.27
コメント(1)
-
資本主義から信用主義へ
今年5月に予定されている会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃され、一円でも会社が設立できるようになった。従来物的会社の代表である株式会社は債権者の担保として資本金を充実・維持していくことが要請されていたのであるが、この大原則が撤廃されたのである。今回の改正は小資本でも会社が設立でき、その結果多数の起業家が生まれ経済の活性化に結びつくことが期待されているのである。しかし、よくよく考えてみれば、本当の意味で債権者に安心感を与えるのは、「金」ではなく、経営者の人柄や人格ではないのか。すなわち、経営者の信用なのである。この意味で、今回の会社法による、最低資本金制度の撤廃は、今後ますます、「信用」を重視する経済・社会に移行するきっかけとなるように期待したいし、主体者である経営者もこの意識で企業経営に望みたいものである。まさに、今後は「資本主義」から「信用主義」の時代がやってくるのだ!
2006.01.26
コメント(0)
-
財は徳の末なり
ライブドア事件のニュースを見ていて思ったことがある。事件については法廷での結論が出ていないので軽々しく論評できないのであるが、現時点での私個人の感想と思っていただきたい。「世の中は本当に正直だ!」二宮尊徳の仕法の中で、「推譲」というのがある。これは、あまったものを社会に還元していこうという思想であり、だからこそ、利益が必要なのだということである。この「譲道」に対するものが「奪道」がある。奪道に偏ったお金本位のものはつぶれてしまい、本当の繁栄は徳が本で財が末なのである。「財本徳末」は破綻に、「徳本財末」は繁栄になる。(『譲の道』P26)考えてみれば、人生の目的は魂磨き(自己を高めること)と、徳による社会への貢献であり、決して金儲けでも、地位や名誉を得ることでもない。道を踏み外せば目的地に到達できないのは自明の理である。
2006.01.25
コメント(0)
-
経営革新
今日はいつもと違い、近況を記します。茨城県商工会連合会より、シニアアドバイザー就任の要請を受け、昨日はその会議に出席しました。この制度は、創業・経営革新を具体的に支援する専門家で、会員等の要請に応じて、そのアドバイスをするというものです。数年前より国の中小企業政策は大きく変化しました。一言で言えば「弱者保護」から「やる気のある企業に対する支援」へです。経営革新と言っても難しいものではなく、要は「新たな取組み」を行い、ビジネスプランを立案し、業績管理システムを構築することを通じて付加価値や経常利益を高めるというもの。私は立場上、国の政策も理解しうるところにいますが、国がせっかくの政策を立案しても、実行部隊がいなければ、実現は困難です。また、国もパンフレット等を作成し広報しているのですが、一般の中小企業への浸透は未だの感があります。このギャップを埋め、政策を実行して成果を出していくためには、商工会・商工会議所はもとより、我々会計事務所等のいまいっそうの努力が不可欠だと考えています。今回のシニアアドバイザー就任はその具現化に向けていいポジションを預かったと大変喜ばしく思っています。私のライフワークの一つは中小企業経営者に対し、「本当の経営」を伝え、活性化していただくことを通じて日本そのものを活性化することなのですから。
2006.01.24
コメント(0)
-
自己を律する
ソクラテスは「ソクラテスの弁明」において、「人間の最大幸福は日毎に徳について・・・語ることであって、魂の探求なき生活は人間にとり生甲斐なきものである。」とし、「最も立派で最も容易なのは、他を圧伏することではなく、出来得る限り善くなるように自ら心がけることである。」とし、精神的な自己を律し成長させることに人生の目的をおいたのである。部下にとって上司の叱責が「圧伏」とうつるかもしれない。しかし、それは部下の人間的な成長を願ったものなのである。ソクラテスはこうも言っている。「他日私の息子共が成人した暁には、彼らを叱責して、私が諸君を悩ましたと同じように彼らを悩ましていただきたい、いやしくも彼らが徳よりも蓄財その他のことを念頭に置くように見えたならば。」
2006.01.23
コメント(0)
-
過度な商業主義を排す
一昨日、TKC全国会の理事会・政策発表会に参加し、その席上、前国税庁長官大武健一郎氏の講演を拝聴する機会に恵まれた。わずか30分であったが、聞く者の心に「ズシン」と響いたものであった。冒頭の言葉は、最後の言葉であったが、官でもなく民でもない「公」の心を忘れるな、ということであり、自利利他に通ずるものであるとのことである。氏の近著は、「データで示す日本の大転換」。必読である。今回の様々な改革では、確かに勝ち組と負け組が明確に分かれた。これは二極化というより、「分断」といった方がよさそうなほどである。問題は、勝ち組といわれる人や企業の中に、仏教で言う「慈悲の心」があるかということである。確かに自分の努力によって成果を手に入れたものであろう。しかし、日本の社会というシステムがその土壌となっているのではないか。いくら努力をしようとしてもそれを許さない(たとえば、戦時下)社会がある。このように考えれば、成功者も様々な人や社会のお陰があると考えるのが妥当なのである。成功者や勝ち組は、謙虚に、ますます謙虚になるべきであるし、もっと周りに心を配るべきなのである。それがなくては殺伐とした社会になってしまうであろう。
2006.01.22
コメント(2)
-
益がなくても意味がある
現在、経済界、証券界では、「ライブドア・ショック」の話題でいっぱいである。同社は、株価を高くすることで企業買収を重ねて成長を維持してきたのだという。さて、冒頭のことばである。中国歴史小説家の宮城谷昌光氏の小説「晏子」に出てくるものだったように思う。現在はあまりにも、「益」を求めすぎ、益なきものを軽視したために社会の混乱を起こしているのではないか。「益」はなくとも「意味」があることをひたすら行うことが尊いのではないか。判断基準は「尊徳」なのであり、決して「損得」ではない。
2006.01.21
コメント(0)
-
国家の品格
藤原正彦氏の「国家の品格」を読んだ。品位ある国家の指標として、次の四つを上げている。1 独立不羈2 高い道徳3 美しい田園4 天才の輩出このような本を読んでいると、アメリカ追随主義の「変革」は、なんとうすっぺらいものか、と感じてしまう。この本の中で、大正末期から昭和はじめにかけて駐日フランス大使を務めた詩人のポール・クローデルの次の言葉を紹介している。「日本人は貧しい。しかし高貴だ。世界でただ一つ、どうしても生き残って欲しい民族をあげるとしたら、それは日本人だ。」アインシュタインも同旨のことを言っていたように思う。
2006.01.20
コメント(0)
-
明徳
「大學之道 在明明徳 在親民 在止於至善」。大學の言葉である。大學の道は「明徳」を明らかにすることにあり。二宮尊徳が薪を担ぎながら読んでいる書が「大學」だと言われている。昨年は公認会計士や建築士の不正が発覚した。専門家は技術的に素晴らしいから公的な資格を「公共に奉仕」するために与えられている。それを私利私欲のために活用していては情けない。しかし、このような専門家内での「本者」と「偽者」が峻別されるきっかけとして起きた事件ではないかと思われる。専門家の土台は豊かな人間性であり、哲学や理念である。専門家の一人として自戒しなければなるまい。
2006.01.19
コメント(0)
-
十干と十二支
十干とは、天のエネルギーであり、十年で一巡りする。これに対して、十二支は地のエネルギーであり、十二年で一回りする。この差、二年である。この二年を古来の中国の人たちは、天のエネルギーがなくなるという意味で「空亡」と言った。人間は、このように天と地のエネルギーの間で生かされて生きているものなのである。そのなかで、天のエネルギーが枯れる二年間を如何に過ごすかが重要な課題となる。この時期は、自分の精神世界(内面世界)を磨くのが最上とされている。私は運が良かった。そういえば、十二年前も無意識のうちにそうしたし、今回も古典と再び出会った。この巡り合いは「ありがたい」と言うしかない。※本日はTKC茨城支部の賀詞交歓会に参加のため、水戸に行ってきます。
2006.01.18
コメント(0)
-
本当に大切なものは目に見えないんだよ。
確か、記憶に間違いなければ、星の王子様の最後の部分だったと思う。昨日、「中小企業の知的資産経営研究会」に出席してきました。この研究会は、「知的資産経営」を中小企業経営に活かすにはどうしたらいいかを検討するもので、私もその一員に選任されました。どのような大企業も最初は創業者の心の中の夢や理想という目に見えないものが出発点であり、それが具現化する過程が企業経営とも言えるのではないでしょうか。そんなことを考えながら、「星の王子様」の一節を思い出した次第です。21世紀は心の時代と言われ久しいのですが、まさに企業経営でも、「目に見えない部分の重視・活用」が必要とされる時代がやってきたと実感した次第です。
2006.01.17
コメント(0)
-
昔の人は偉かった!
「皆さん方の欧米諸国は非常に素晴らしい物質文明をつくられました。そのことは私ども日本は見習わなければならない。しかし、日本は非常に精神文化を大切にする、そういうお国柄です。これから何年後になるかわかりませんけれども、皆さんたちの物質文化を凌駕するような精神文化の時代がやがてやって来ることを信じております。」(岩倉遣外使節団での伊藤博文の演説要旨)「成長・発展する会社の法則」田舞徳太郎著より。いまの変革は、米国の「物質」部分の直輸入ではないか。いまそこ「新和魂洋才」が必要なときなのではないか。
2006.01.16
コメント(0)
-
一人の目覚めが・・・
「一人の目覚めが百人に及ぶ、百人の目覚めが千人に及ぶ、千人の目覚めが、会社全体に及んで社会に及ぶ。」松下幸之助氏は実に良いことを言っている。世の中の変化なんて、このようなものだと思う。はじめは小さな変化から、過半数を超えると一挙に大きな変化となる。政府が、景気がと愚痴を言ってもしようがない。誰が目覚めるか! 自分しかいないのである。
2006.01.15
コメント(2)
-
世の中は生成発展する
大自然・大宇宙は一瞬たりとも休むことなく生成発展している。大宇宙の中で生かされている存在である我々人間も同じエネルギーを得ているのであるから生成発展するしか道はないのである。生成発展していないとしたら、よって立つべき指針が間違っているか、その指針に従っていないかである。今日一日、自分の良心に照らし合わせて良心に恥じぬ生き方ができたか反省しよう。反省なきところに発展はない。
2006.01.14
コメント(0)
-
万象・万物は我が師なり
人をして語らしめることがある。思い悩んでいるとき、思いがけない人がその解決のヒントを与えてくれることがある。その人をして何者かが語っているとしか思えない瞬間がある。自然界が自然の摂理を教えてくれる。樹や花が語りかけることがある。ああ、何とありがたいことか。万象・万物が私の成長を助けてくれる。万分の一のお返ししかできないかもしれないが、精一杯生きようと思う。
2006.01.13
コメント(0)
-
努力には方向性がある
沖縄に行きたくても千歳行きの飛行機に乗ったら絶対にいけない。一生懸命努力をしてもその方向性が違っていたら悲劇である。努力には方向性がある。現在の努力の方向性が間違っていないか、自問自答しよう。
2006.01.12
コメント(0)
-
心が現象を創る
同じような境遇や状態の中で、ある人は悩み苦しみ、ある人は平然としている。この差は何なのか。実は現象は同じもの。しかし、我々の心はその現象を過去の教育や習慣などのフィルターを通して認識するのである。信号機の青を見ても,実は一人ひとり違った認識である。心というレンズを歪めさせず曇らせずただ現象をありのままに見る、ということが大切なのではなかろうか。
2006.01.11
コメント(0)
-
無常
いったん手に入れたものは自分のもの。永遠に所有しつづけようとする。実はそれが苦しみを創る。苦しみとは思い通りにならないことである。理想と現実のギャップに悩むのである。しかし、この世の存在全てが「常ならむ」ものである。変化が常態なのである。自分の体も死に向かい刻々と変化しつづけているのである。変化が常と感得したとき、何かを得ても有頂天にならず、何かを失っても失望せず、たんたんと人生を歩めるようになる。
2006.01.10
コメント(0)
-
成功するまでやりつづける それが成功の唯一の秘訣である
特に世に頭の良い人ほど先が見えるのか途中であきらめることが多い。しかし、私のような凡人は鈍牛のような歩みで暗闇のトンネルの左右の壁に体をぶつけながらひたすら歩いていくだけである。遠くに、うっすらと見える光明を信じ,ただ歩みつづけるだけである。その光明がはっきりと見えてくる。どんどん大きくなっていく、どんどん光り輝いてくる。さあ、成功は近い。
2006.01.09
コメント(0)
-
良樹細根
人はたいてい目に見える花や葉に賞賛を贈る。しかし、大切なものは目に見えない根っこの部分である。根っこが腐っていては、今仮に美しい花を咲かせようとも数年後それを見るのは難しい。企業も目に見えない理念や社風を大切に育もう。それが長期的に繁栄発展するための唯一の道なのだから。
2006.01.08
コメント(0)
-
青春とは心の若さである(サミュエル・ウルマン)
経営者が経営意欲、情熱を失ったとき、その企業の崩壊の種が蒔かれる。人生に対する希望や夢や情熱を失ったときその人は老いる。これらはすべて心の作用であり,これらを持ちつづけてこそ生き生きと人生を送ることができる。肉体的に年老いても精神面はいつまでも夢を持ちつづける人生でありたい。
2006.01.07
コメント(0)
-
抜苦与楽
自利利他を実践する人生最良の生き方が「抜苦与楽」である。読んで字の如し、「苦」を抜き「楽」を与えることである。「苦」の渦中の中にいる人は「苦」にとらわれてもがき苦しんである。「苦」が自分の心の作用が作り上げた幻であることを理解しようとしない。2500年前に仏陀は「四諦八正道」を唱え、苦に捕われることなく、苦の原因を探り、それを滅し、大いなる道(本当の生き方)に則れと説いたのである。抜苦与楽とは、単に楽を与えるのでなく、自由自在に生きるすなわち、幸福になる方法に気づかせてあげるというのが最も良いのではなかろうか。
2006.01.06
コメント(0)
-
道徳を忘れた経済は罪悪 経済を忘れた道徳は寝言 (二宮尊徳)
二宮尊徳は経営コンサルタントの先駆者であり、各地で村興しの「仕法」を実践し、成果をあげている。そのなかで尊徳は「心田開発」ととなえている。まず自分の心を耕し、やる気をださせ、やる気が出てきた村人たちに具体的なノウハウを伝授していったのである。現代の企業経営にもこれは当てはまる。情熱を失った経営者に最新の経営ノウハウを伝えても全くの無駄である。さて、経済の原義は「経世済民」にあるが、金銭的なことで満足を与えるだけでは我利我利亡者を増やすだけである。そこに一本人として生きる道である道徳が通ってこそ、経済は生きていくのである。しかし反対に、哲学的な話で空理空論を並べ立てても経済の実践に結びつかないものもまた空しいものである。
2006.01.05
コメント(0)
-
自利利他
最澄は「自利利他」を「自利とは利他をいう」と解釈されているそうである。現代風に解釈すれば「あなたの利益が私の利益」「あなたの喜びが私の喜び」ということである。なぜ、他人の利益が自分の利益なのか。肉体としての目に見える存在である人間観のみではこの本質は理解しがたいであろう。しかし、ユングなどは人間の意識を表面・潜在・集合無意識に分類しており,実は本当の自分とは、集合無意識の部分なのである。集合無意識とは、他と根っこはつながっているものである。ゆえに他を利することは自分を利することとイコールなのである。
2006.01.04
コメント(2)
-
掃除の深さと広さは人格に比例する(桜沢如一)
玄米正食であるマクロビオティックを創始した桜沢如一は、単に人々の健康面を考えたのではなく、その活動を通して世界平和運動を展開していったのである。掃除というささいな活動にも祈りを込め、心を込める。その広さと深さはその人の人格の投影である。小さなことに手を抜かずやり遂げられない人が大きいことを成しえようか。
2006.01.03
コメント(0)
-
夫子の道は忠恕なり(論語)
人間としてどのような生き方をすればいいのかという弟子の問いに対して孔子がこたえた言葉である。「忠恕」とはおもいやりとまごころのことである。人間一人ひとりがこのような生き方をしていくとどれほど潤いのある世の中になるだろうか。
2006.01.02
コメント(0)
-
真実は感動とともに伝えられる(森信三)
世の中には、流暢に話す人も多いが、その人から発された言葉が人の心を打つとは限らない。それは単なる「言葉」であって「言霊」ではないからだ。人が動き出すのは「気づき」と「感動」によってであり、どのような朴訥な話し方であっても、その言葉に魂が入っているとき、受け手は感動するのである。そのときに発せられた「真実」が人を動かしていくのである。巧言令色少なし仁。
2006.01.01
コメント(0)
全32件 (32件中 1-32件目)
1