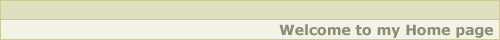全167件 (167件中 1-50件目)
-
実践こそ力なり
絵本探険ツアー、依頼を受けてやらせていただきました。主催者のご縁で来て下される方々との新しい出会い、来場してくださった方たちによって作り出されるムード、それは新しい反応をいただく機会なのです。中には幅広い知識をお持ちの専門家もいらっしゃり、こちらが緊張しましたが、そんな空気が参加した人おのおのに刺激を与えるのですね。やってよかった、楽しかったです!
2006年09月04日
コメント(20)
-
大原照子さんのシンプルライフ
お掃除を切り口に「シンプルライフ」をおすすめしていますが、今日は、まだ知り合ってそんなに長くない方に思い切って自己アピールしてみました。そうしたら「ワア、私の求めているものだわ!」とすぐに意気投合。聞けば、大原照子さんの75歳にしての住宅リフォームをテレビで見たのがきっかけで、今日その本を買ってきたところだったそうです(『55m2の暮らし替え―スローライフの舞台作り』)わたしは大原照子さんの『一つのボウルでできるお菓子』を新刊間もなくのころ手にしました。10年以上も前のことですが、今日のおしゃべりを盛り上がらせるに充分な話題でした。
2006年08月23日
コメント(0)
-
シンプル
シンプルで豊かな暮らしを提案する立場で、おそうじレッスンや、便利グッズのご紹介をしています。オリジナルで制作販売しているのが、「マジック・クロス」台所のスポンジ代わりとして、またお掃除の汚れ取りクロスとして使っていただいています。台所のスポンジがクチャクチャと衛生的でないのと耐久力に不満を感じて、7年前から試作を繰り返してきました。油汚れも、ホコリもコレ一つで簡単に取れて、しかも丈夫で長持ち!汚れたらせっけんで洗えばまた元のように白くなります。このクロスは、説明して渡すより、台所でささっと汚れ落としの実践をお見せするのがいちばんなのです。おそうじ嫌い、洗い物嫌いの主婦が「こんなに落ちるなんて楽しい~!」と、このマジッククロスにほれ込んでくださいました。そして、お家に行くたびにあちらこちらがキレイになっていきました。お掃除は、面倒なのではなくて、落ちる方法に出会えば誰もが楽しくなるものだと思います。
2006年08月22日
コメント(0)
-
意外性の効用
人は驚いたり、今までの価値観で経験出来なかったことに出会うとすごく感激します。この「驚き」や「感動」こそが人を動かす原動力なのだと思います。絵本探険ツアー 目下9月2日と18日のイベントが決まっていますが、私たちにとっては今年に入って3ヶ月以上新作が毎月続いていたこともあって、この1ヶ月その制作に追われないことに少し寂しさを感じてきたところです。私は選書担当ですが、実際の決定権は建築家である夫のヒラメキ度にかかってきます。今日はたっぷりピックアップした絵本から、夫が内容共々自分がどんな見方をするか、をキーワードに絵本の選書をしました。
2006年08月05日
コメント(0)
-
絵本探険ツアー 7月プログラム
好評いただいています 「建築家がガイドする 絵本探険ツアー」7月2日の内容が決まりました。グリム童話 「おおかみと七ひきのこやぎ」 フェリックス・ホフマン 画英語圏の伝承唄「きつねのとうさんごちそうとった」 ピーター・スピア 画場所 TOTO札幌ショールーム
2006年05月25日
コメント(2)
-
せっけんおそうじ
合成洗剤を使わなくなって15年。昨年からはせっけんカスの悩みからも解放されて、液体せっけんもいらなくなりました。こんな便利で安心なメンテナンス、広めたくて活動しています。一般のお掃除やさんは塩素系漂白剤や合成洗浄剤でお掃除が基本ですよね。何とかせっけんおそうじ業が成り立たないのかなあ、と考えています。
2006年05月21日
コメント(0)
-
幼い子の文学
札幌市中央図書館で活動している読み聞かせサークル「おおきな木」7周年を記念して、学びなおしの「一般公開講座」が始まりました。読み聞かせ会のあと2時間、瀬田貞二氏の『幼い子の文学』(中公新書)に沿って、上がった書名を読んでいきます。25名ほどの方が集まり、先週、会のメンバーで割り振りをした本をどんどん読みました。すごいボリュームになってしまいました。難しいと思われた方、ごめんなさい。本当はもっと楽なものなんですよ~ 6月もいらしてくださいね。
2006年05月21日
コメント(0)
-
何と1年半ぶり!
10年続けたラボ・テューターを辞めたのがちょうど一年前の5月末でした。それとイギリスの吟遊詩人ニック・ヘネシーコンサートを企画したのも昨年5月。ニックのご希望で、アイヌ民族の萱野茂さんのご自宅を訪れたのが確か、5月14日。ニックのみならず、同行した私たちにとっても萱野さんとひとときを過ごせた事は本当にありがたいことでした。人生の転換期となっているこの1年、ホームページも日記もどのように向かってよいのかわからず過ごしてきましたが、3月から企画してきたことが少しずつかたちになってきたので思い切って今日ページを開いていじり始めたというわけです。プロフィールやトップページ、ページに多少変化が生じましたので少し手直ししました。写真はもうしばらくお待ち下さい。どんな画像を入れたらよいのかゆっくり考えます。とりあえず私のページのリンクをそのまま残してくださっている方に近況報告をする意味で更新しました。今日はリハビリ。このくらいで失礼します。
2006年05月15日
コメント(0)
-
テレビ番組 生放送体験
たーいへんご無沙汰いたしました。久々の日記更新です。大人向け英語絵本読み聞かせサークル おおきな木 についてのインタビュー番組に出演させていただきました。やはり、「本番」を貰えるというのは、いろんな意味で大変勉強になります。この会の説明は 左のページにもありますが手っ取り早くここにのせます。-----------------------------------読み聞かせサークル「おおきな木」は、札幌市中央図書館で大人向けに英語絵本を読むサークルとして平成12年3月に誕生しました。絵本は小さな子どものためのもの、と思っている方でも、英語で取り組むことで興味を示していただけるのではないかと、平成10年1月に「英語で聞く名作絵本とマザーグース」という勉強会を始めたのがこのサークルの基盤となりました。そして、大人自身が絵本を楽しむ活動があれば、それは子どもに絵本を手渡す大人が増えることにつながると期待しています。読みきかせ会では、イギリスの伝承童謡<マザーグース>も絵本と一緒に紹介しています。日本の童謡と異なり、マザーグースには社会風刺や歴史的事実が歌いこまれ、英語圏の作品を理解するのに役にたつことが多く、また、ことばのリズムを楽しむのに最適なものだからです。名作絵本とマザーグースをお伝えする活動は、まだ試行錯誤の状態ですが、当初の目標である絵本の好きな大人たちの輪が出来ました。100年経ってもすたれない作品になるだろうと、予測して選書するのも活動の楽しみです。このサークルは「聞き手も読み手もともに学びあう」のがモットーです。読み手となってお話を提供する立場になれば、深く読み込み、聞き手として参加すれば、読み手が育ち、読んでもらう楽しみを味わうこともできます。いろいろな立場からかかわれるおはなしの輪、子ども達にも届くよう広げていきたいです。-----------------------------------と、まあ、これが私のことばでいいたかったことなのですが、テレビというメディアは大衆にその存在をお知らせするのが使命なので、あまり専門的な部分を自分のことばで言えないんですね。なぜこの会を始めたか、に対して「自分の体験である絵本の読み聞かせで英語力がついたことを、実践するために」と言い切ったほうが視聴者にわかりやすいんだそうです。「絵本の読み聞かせで英語が身についた」をずばり言うことをリハーサルでためらって別のことを言ったらやはりそれが「筋が通らないので、端的に原稿どおりでお願いします」となりました。お付き合いの長い人からは、「本心ではないという心の中が表情に出ている」なんて感想をいただきました。げー!そうなんだ。わたしはまだVTRを見ていません。まずはあまりテレビで見たい姿ではないし、発表のように練習してきた力を出す、ということでもありませんでしたから。モゾモゾ、、終了後スタッフの方が、「会の趣旨を知っているだけに、すみません」なんて謝ってくださったりしましたが、うーん、仕方が無いですよね。こだわりはありますがこれもTPO。これがきっかけとなって実際に図書館に足を運んでもらえればそれで解決することなのですから。でも、テレビの使命は確実に果たしましたよ。放送直後からよく電話がかかってきます。10本ぐらいありました。ついでに、2月のテーマです。たましいの詩(うた)-北米先住民族のおはなしから-『千の風になって』(荒井満 作)より "I am a thousand winds" 『天の火をぬすんだウサギ』”Fire race” 未邦訳“Ten Little Rabbits“ 大地のうさぎたち『Brother Eagle, Sister Sky 酋長シアトルからのメッセージ』けっこういい感じデース!
2005年01月07日
コメント(0)
-
数をテーマにしたおはなし選び
今日は図書館にて大人向け読みきかせ会でした。テーマは「かぞえる」数字に関する本を集めて読んでいくうち、数え歌はそれなりにありますが、絵本としての面白さ、おはなしの内容も考えて次のような選本になりました。絵本 “Three little kittens”ガルドンの絵ですナーサリーライム One, two, buckle my shoe日本語で 『10(とお)までかぞえられるこやぎ』 プリョイセンのおはなしに 林明子さんが絵をつけました。数をかぞえられるようになった喜びが素直に入って来ます “Cookie Count” サブダの仕掛け絵本 感嘆! “One was Johnny” センダック ナットシェル・ライブラリーより 読み聞かせには、大きな版を使いましたが箱に入った現物のサイズにみんなビックリ! “One Sun Rises” アフリカの動物たちを描いたかぞえうた風のおはなし絵に迫力あって、じっくり楽しめます日々の数字とのおつきあいは、郵便番号・住所・電話番号・暗証番号・口座番号など自分を表す記号としての存在と、モノの値段や支払い金額といったお金に関すること。どうも数字とのおつきあいにあまり嬉しいイメージはなくなってきたこの頃です。「数字」という漠然とした投げかけで本を集め、読んでいくうちにfigure number count が明確になりました。ところで今日はNHK札幌放送局が取材に来てくださいました。どんな形で紹介してくれるのか楽しみです。 感想を掲示板へ
2004年11月20日
コメント(0)
-
マーク・トゥエイン(1835~1910)のことば
「他人から尊敬されないと、私たちは深く傷つくものだ。心の底では自分をそんなに尊敬していないくせに」「人をほめたら、同時にものを頼んではいけない。褒め言葉はただでなければ価値がないのだ」「私の町には、模範と言われた少年がひとりいた。彼は完璧だった。礼儀も、服装も、行いも、信心も。彼はすべての母親達の賛嘆の的であり、すべての子ども達の憎悪の的だった」「人間が善悪を区別できるという事実は、他の生物より知的にすぐれているということを証明している。しかし、人間に悪事が働けるという事実は、他の生物より道徳的に劣っていることを示している」-奈良県で起きた事件、子どもたちに事故がないよう祈るばかりです。古本屋さんで見つけた『マーク・トゥエイン150の言葉』より
2004年11月19日
コメント(0)
-
日本語と英語の読み聞かせ"THE FUNNY THING"
公共図書館で行っている大人向け英語絵本の読みきかせ会でした。テーマは<へんないきもの>ナ―サリーライムを間に入れて次のようなプログラムで行いました。NR Three little ghostesses"GO AWAY, BIG GREEN MONSTER!" By Ed EmberleyNR Wee Willie Winkie『へんなどうつぶ』ワンダ・ガアグさくNR Pat-a-cake"THE FUNNY THING" by Wanda Ga'g読みきかせ会にいらっしゃる方が、事前にテーマの本を読んでくることはまずありません。ですから、初めて出会ったおはなしでもプログラムの流れの中で楽しんでもらえるように順番を組んでいきます。そして読み手は、すらすら読めること以外に、導入やつなぎのトークを考えます。さて、今回の試みは、ワンダ・ガアグ 1929年の作品"THE FUNNY THING"をどうやって紹介するかでした。10分少々かかるお話を小型モノクロ絵本で読み聞かせというのは、無謀です。また、この日本語訳がなかなか興味深く、これは両方の言語を交錯させて大人ならではの楽しみ方を紹介しようという方法を取りました。キーワードがいくつかあります。タイトルの"THE FUNNY THING"は、今まで私たちがであったことのない生き物で、自称「どうつぶ」-英語では“aminal”といいます。そのどうつぶ(aminal)は、おじいさんの作ってくれた<じゃむじる>“jum-jill”を喜んで食べるんです。(<じゃむじる>はジャム汁ではありません。日本語の『汁』を連想しないように。どうです、2冊手にとって読みたくなるでしょう?おもしろいですよ、このお話は。しかも、じゃむじるを食べて成長するのはしっぽーTaleなんです!!
2004年09月11日
コメント(0)
-
『カステラへらずぐち 』
まどさんがつくり、坂田さんがこたえる。現代を代表する二人の詩人によることばあそびを、それぞれ12編ずつ収録したものです。ラボママが「図書館で借りたら、子どもが気に入ってみんなに紹介したい、、」と持ってきて読んでくださいました。大人も子どもも大笑い!そして絵は、ラボ・ライブラリーでおなじみの上矢 津(しん)さんではありませんか!目下ラボ・おざわパーティではロシアのおはなしに取組中。SK-20の3作品は、上矢氏の作品なので、ひとりの人の作品の広さを見るのに絶好の機会です。
2004年09月03日
コメント(0)
-
高校野球北海道が全国制覇!
スゴイ!高校野球日本一!雪国北海道は、どうしても不利というジンクスを破って駒大苫小牧高校が甲子園で優勝!試合は1回から打撃戦で、いくら点をとっても安心することができない展開。見ているほうがこんなに疲れる野球観戦なんて初めてでした。3時間に及ぶ長時間試合にもかかわらず、1球1球を大事にしないといけない、それだけ見ごたえのある試合でした。北の島国北海道に移って10年、四季の生活感覚と物理的・精神的な首都圏との距離感が、北海道のマイナスイメージを心の隙に持つこともしばしば。でもそれは自分が努力しない時の格好の言い訳に過ぎないんですよね。だから地元の高校生の活躍は元気をくれます。さあ、わたしも彼らを見習って、ハンディを言い訳とせず、努力して積極的に立ち向かわなくては!そう、高い目標も努力を続ければいつか身を結ぶ時が来るってね。
2004年08月21日
コメント(0)
-
英語で読む児童文学講座
本業の傍ら、こんな講座を企画しました。絵本と出会い、人と出会い、おはなしを共有して深めていきたいです。1 初級~中級むけ 英語で読む絵本講座小さな子どもたちに愛され続けているおはなしを原語で聞いてみましょう 第1+3 木曜日 12:30-2時 9月~10月 4回講座 絵本を購入する必要はありません基礎講座Aコース スケジュール表 題 名原作初版年度 使 用 絵 本作 者 名 日本語訳者出版社9/2 おかあさんのたんじょうびアメリカ 1932 作・絵 マージョリー・フラック 光吉夏弥岩波書店 19549/16 ガンピーさんのふなあそびイギリス 1970 作・絵 ジョン・バーニンガム 光吉夏弥ほるぷ 197610/7 かいじゅうたちのいるところアメリカ 1963 作・絵 モーリス・センダック 神宮輝夫冨山房 197510/21 か ぶロシア民話 口承昔話英語・ロシア語の語り 内田莉莎子福音館 19622 中級~上級むけ 第2+4+5 木曜日12:30-2時 184ページにわたるペーパーバックを最後まで読み通す達成感は格別ですホワイト作 『シャーロットのおくりもの』 E.B.White “Charlotte’s Web”
2004年08月17日
コメント(0)
-

あべ弘士さんが勤めていた旭川市旭山動物園
今は絵本作家として専業になったあべ弘士さん、1997年までは北海道旭川市の旭山動物園の飼育係さんでした。この動物園、展示の仕方が面白いのなんの。ざわざわは東京暮らし30年ですから上野動物園はおなじみです。アメリカ駐在中には、サンフランシスコ動物園、マリンワールド、海洋哺乳類保護施設、モントレー水族館などなど足繁く通いましたから、動物園の面白さは少し語れると自負しています。旭川にある旭山動物園は、動物をいろんな高さ・角度から見れるように設計に工夫があリます。それと、解説のプレート。飼育係の方が、手書きでわかりやすくその動物達の特性について書いてくれています。この視点がアメリカの子ども向け生物雑誌"Zoo Books"によく似ているのです。ホッキョクグマの泳ぐ所を見て、感激~!あまりに近くで見れて写真はこんな状態です。 トラも活発に動きます。 ショーのような、オラウータンの解説(後ろの人が飼育係さん)とそれに合ったオラウータンの芸のご披露 おとなも子どももうーんと楽しめます。今日は高学年と来年の夏までの計画について話し合いました。パーティ開設10周年おたのしみ記念として、旭川に行こうか、と切り出した所、高校生は即「いい!」といってくれたのでそのほか町おこしになった『剣淵絵本の里』(ここも一日いて飽きない所)に1泊で出かけようか、ということになりました
2004年08月05日
コメント(0)
-
暑いのは苦手
随分日記をお休みしてしまいました。もうひとつのHPは仕事がらみですから、お伝えすることがあると書いています。二つのHPは使い分けられるからこそ必要なのですが、ここのところいまいち、仕事以外のことをこなす元気がないのです。原因は、ずばり、夏だからです。東京生まれの東京育ち、クーラーなしで第2子誕生までいましたから、暑さには結構根性あるほうなのですが、やはり好きでいたわけではないのですね。札幌の冬の雪かきの方がまだ耐えられると感じるこの頃。こなさなければならない仕事を終えるだけで体力・気力を使い果し、夜はとにかく眠ります。眠れる夜の地域に住んでいるだけで幸せなんですけどね。でも気力が萎えると運動不足になってしまい、足がだるいのです。日がかげってきたのでジョギングに出かけてきます。
2004年07月31日
コメント(0)
-
高校野球観戦
徒歩圏内に札幌円山球場があります。札幌に来て10年になりますが昨年初めて入場しました。自分の興味と家族の付き合いばかりでは視野が狭まると思うこのごろ、かかわりさえあればなんでも一度は行ってみようと心がけています。娘の通う学校の野球部が強いようです。春は北海道ベスト4まで勝ち残り、その時に大逆転劇を見て野球ドラマを楽しむようになりました。今日は夏の大会ブロック決勝戦。シードで2回戦からコールド勝ちできたのでいけるかなと思って出かけました。ですが決勝は攻守ともに素晴らしい対戦相手でした。23対0なんて試合もあったから、打つ方もけっこうできるチームなのでしょうが、ピッチャーがよくてなかなか得点に結びつかず、相手に1点を許して迎えた9回。3塁にランナーがいて、ツーアウト・3ボール。見ているほうも緊張!ここで打ったらすごい!ドラマは続くよ、と考えるうちにサイレンが鳴ってしまいました。残念、3年生の夏は終わってしまいました。バッター悔しかったでしょう。わたしも悔しかったですもん。でもあんなに大きな空間で仲間とドラマを共有していくのってすごいですね。スケートも60mx30mをひとり占めしてすごいと思っていましたが、やはり野外スポーツはスケールが違います。お日さまが怖いバルーガですが、日焼け止めをバッチリぬって、タオル巻いて農作業のようなスタイルで出かけました。今日はいい天気です。
2004年07月03日
コメント(1)
-
来週は東京
久しぶりの上京です。19日の土曜日、図書館サークル例会のあと夜の便で札幌を発ちます。介護が必要になった父を見舞い、家の片づけをしてきます。せっかく3泊するのでちょっと外出もしたいな。実家は、東京・江東区。おすすめの場所など周辺の情報提供いただけると嬉しいのですが、、。
2004年06月14日
コメント(3)
-
ガレージセール
ラボ・おざわパーティのおたのしみ基金を集めるため、ガレージセールをしました。リサイクル品の他、手作りのお菓子・お食事品が2時間でバッチリ売れました。14000円の収入です。前日になっていろいろ品物が集まる状態で、まだまだ欲しい人とのめぐり合わせで売れるものがたくさんあります。折りたたみ三輪車、ブランド品ネクタイ、雑貨、子供服、本。たったの2時間で品定めをするのもむずかしかったと思われるほど。皆さんから出していただいたものを見ると、面白いものがたくさんあります。商品を探すことすらしなかった分野のものを見ると、こんな機会に手に触れてみて新しい感覚をもらいます。ガレージセール、いままでは『不用品販売』のイメージだったのですが、「モノとの出会い」「モノを買う行為」について考えると面白い機会です。また、このセールは収入を得たいという動機ではじめましたが、このような場を支えてくれる人たちとの交流も大事な要素だと思います。
2004年06月13日
コメント(0)
-
ストーリー・テリング コンサート
来年の5月にイギリスより、Nick Hennesseyをお招きして札幌公演を行ないます。彼を発掘(?)したのは、愛媛県松山にて文庫活動をされていらっしゃる光藤由美子さんと田村七重さんです。1999年に、南ウェールズ地方セント・ドーナッツ城で開かれた「ストーリー・テリング フェスティバル」に出ていたヘネシー氏のハープとともに語られることばと旋律のハーモニーにひかれ、来日交渉をし2002年に初来日を実現されました。ヘネシー氏のレパートリーは、叙事詩 Epic Kalevala カレワラ(フィンランドの民族叙事詩)物語 Stories The Fisherman and his Wife 猟師とおかみさん The Dauntless Girl 怖いもの知らずの娘 The Old Tramp 放浪じいさん Three Brothers 三人の兄弟 A King of all Ireland アイルランドの王 The Bird of Wax 蝋の鳥そして歌。 時にギターのようにも聞こえる彼のハープとともに歌われる詩の数々。こんなおいしいおはなし、どこからきたとおもいます?ハイ、札幌で語りの活動をして20年の「おはなしかご」さんからです。おはなしに興味があって、英語圏のそれにもかかわっている人、ということで御指名をいただいたのです。こういった英語のおはなしコンサートについて、日本語をどのように入れていったら1回きりの会を楽しめるアイディアをいただきたく、よろしくおねがいします。
2004年05月29日
コメント(0)
-
洋の東西に見るカタツムリ
ここ1-2ヶ月カタツムリが気になっています。それは、カタツムリを見かける季節になったからではなく、日本の童謡、狂言、外国のお話・ナーサリーライムで出会ったからです。来週図書館の大人向け読みきかせ会で読む "When the sky is like lace"(1975 by Elinor Lander Horwitz)に、カタツムリを馬鹿にする所があります。これにちなんでナーサリーライムを見つけると"Four and twenty tailors"。その他にないかなあ、と探しました。以前から、ベアリングールドご夫妻の『マザーグース』3巻が、絶版になっていて購入不可能なのを残念に思っていましたが、このたび鳥影社から『完訳マザーグース』となって1冊の本になって出ました。そしたら、ありました!カタツムリ特集の中から一つ。 だいろ だいろ 穴から出て来い 出て来ないと まっ黒になるまでぶちのめすぞ だいろ だいろ 角を出せ パンをやろ ライ麦もやろこれは、ラボ・ライブラリー『スサノオ』冒頭にある梁塵秘抄からの歌 舞へ 舞へ かたつぶり 舞はぬものならば 馬の子や牛の子に蹴させてん 踏みわらせてん まことに美しく舞うたらば はなの園まであそばせんにそっくりではありませんか!カタツムリに「踊れ」と言ってからかう歌は、『不思議の国のアリス』エビのカドリールの所にもあります。昨日はベアリング-ルドさんの本からこんな発見を頂き、興奮した日でした。
2004年05月16日
コメント(0)
-
久しぶりに滑って転んでとんでまわって♪
大型連休谷間の金曜、いつもなら午前中から出かけて夜9時までの仕事ですが、めずらしくオフです。そして来週の水曜日まで、何か準備をして出かける仕事はお休み。明日の準備に対するプレッシャーもない、開放気分です。ここ1ヶ月ほど山登りや散歩・ジョギングで少しずつ体を動かしてきたので、「今日こそは」とスケート場に出かけました。2月に天然リンクで滑って以来。脚力の衰えは確実に感じましたが、ここ数年まともに滑っていないことを思えば、けがなく汗をかければいいのです。体を鍛えて一心に取り組んでいたころとは比べものにならないけれど、滑る楽しさや嬉しさはより増しているかな。15歳の時、オリンピックで見たロシアペアの滑りが、私をこのスポーツのとりこにさせました。あの日テレビと見ていなかったら、いま私はどんなことを趣味として続けていたのかしら?ひょっとして絵本にも関心なかったりして。久しぶりに全身運動。足よりも腕や、転んでついた手首が痛いな。
2004年04月30日
コメント(0)
-
歩くということ
小さいころ、ずいぶん歩かされました。おなかがすいても、荷物が重くてもタクシー・バスに乗るなんてことはありませんでした。そんな日常に加え、年に数回歩く家庭内イベントがありました。おねだりの品物は10キロほど離れたデパートまで歩いていったら買ってもらえるとか、旅行は幹線のみ乗車し、バスや支線部分の10数キロは荷物を持って歩くのです。たとえば、東海道線の湯河原までは電車に乗り、そこから強羅までは荷物を持って宿泊場所まで歩くのです。今は「バック・パッキング」なんてカッコいいことばが使えますが、何のことはない、貧乏人の節約旅行です。こんな子ども時代をすごした財産といえば、「足は働かずとも収入を生み出す」の精神で交通費節約の根性があるほかに、足と内臓が強いからだをもっていることでしょう。さて、乗り物に不便なところに住み、自分で自由に使える車を持つ身となった今の私ですが、やはり使い方を限っています。子どもの頃乗り物があんなにうらやましかったのになぜ今歩くことを選択するのか、今朝ジョギングをしながら考えました。まず第一に、自分で自分を動かすと言う行為に、生きている証を感じます。そして、歩く速さは人がものを考えたり記憶に刻み込むのに適したスピードだと思います。家でものを考えている事が効率よいかというとそうではないのです。「やることいっぱいある」と仕事ばかりして遅くまで起きていても結局たいした成果が出ない、と感じる事があります。たぶん、大地を踏みしめる事で、大地からいろいろなエネルギーをもらっているんじゃないかな。今日は、朝走ってちょっとした充実感のある日曜日です。
2004年04月25日
コメント(0)
-
♪♪ RHYTHEM-RHYME -TUNE ♪♪
「日本の童謡を最後までうたいましょう」と心がけパーティでも取り上げています。うる覚えだった童謡を調べて最後まで口にしてみて、歌いやすく、覚えやすい事にビックリしています。まさに瀬田貞二さんのことばをお借りして『マジック・アンド・ミュージック』がつまっているのですね。たとえば北原白秋の『ゆりかごのうた』揺籠のうたをカナリヤが歌うよねんねこねんねこねんねこよ揺籠のうえに枇杷の実が揺れるよねんねこねんねこねんねこよ揺籠のつなを木ねずみが揺するよねんねこねんねこねんねこよ揺籠のゆめに黄色い月がかかるよねんねこねんねこねんねこよゆりかごの周りには「きいろ」のイメージがあるんですね。考えてみればゆりかごにおさまるころの人間は、誰もが黄色が似合うとき。おもしろいなあと思いながら歌うと歌詞はすんなり4番まで入り、ふと気がつくと鼻歌になっているんです。ここの所はまっている和田誠さん訳の『オフ・オフ・マザーグース』『またまたマザーグース』。櫻井順さんの作曲で120のマザーグースが120組(人)の人で歌われています。聞いて気がが付いたこと、それはうたの「RHYTHEM-RHYME-TUNE」です。RHYTHEM ことばのリズムが体を動かすもの。RHYME 押韻を感じるとき、絵は描いていない事。だからナンセンスソングがおもしろい。TUNE シンプルサイモンのようにメロディで引っ張っていかれるもの。こんなふうに楽しむ時、あまりことばの意味って考えていないんですね。意味を求める時、頭でっかちになっているんだなあと改めで体感。
2004年04月21日
コメント(4)
-
イメージは五感の総動員
「私のウマは鼻ヅラがしっかり濡れ光り、長い顔にたてがみ、美しい四肢を持ち、いななき、ひづめの音のするものだった」。幼いころ、ウマという名前を覚える前にその生き物の姿や表情がさまざまな形になって脳裏に現われたという。 -今日の朝刊 日本経済新聞コラムより-日本画家 加山又造氏は、ことばという具体的なひとことを発する前にこんなにもイメージを持っていたのです。でもこれは偉大な画家加山又造氏に限った事ではないと思います。わたしたち誰もが母国語を習得するとき、こんな感じで一つずつことばを覚えていくのです。ただこんなに詳しくないかもしれないし、年をとっても覚えていられるかどうかというとそこが凡人と天才の違いだと思います。ことばを音や文字だけで認識するのは簡単。音は耳から、字は目でわかるから。でも生きたことばと表現となるとしっかりしたイメージがないと生まれてこない。イメージは、五感を総動員して浮かび上がるもの。自分に浮かんだイメージを、ことばや動作や音や絵にして人は伝えようとする。五感が衰えないようにちょっと鍛えておくと「感じる人」になって何でもおもしろくなる。>
2004年04月13日
コメント(0)
-
絵本でEnglish
絵本・イソップ童話を英語で読んでます。20-30年以上英語から離れていた方が中心のサークルです。人生経験豊かな方と長い間読み継がれてきたおはなしを共有するのは私にとって学びの時間。3月末でメンバーが減ってしまったので、ご一緒していただける方募集中!
2004年04月12日
コメント(0)
-
10代の感覚
先週誕生日を迎え40代半ばとなりました。最近中学・高校をともに過ごした友が出版界で名前を見るようになり、今の住まいが出身地東京から離れているだけに彼らの作品に出会うととてもうれしくなります。中学時代の友、杉田比呂美は、最近では宮部みゆきの『誰か』の挿絵を担当しました。福音館の月刊たくさんのふしぎ1996年6月号『ダーのウィンのミミズの研究』で彼女の活躍を知りました。中学時代の私はマンガを描くのが好きで、絵の上手な彼女にしがみつくようにして仲良くしてもらったんです。でも縁ってふしぎで、これまた杉田比呂美とずっと連絡を取り合っている中学時代の友人が札幌に転勤で来てばったり公園でであったことで(25年近も会っていない私たち、子連れ姿でお互いに気がつくなんてすごいでしょ!)、連絡がつきました。中学卒業以来この絵本の件まで話をすることはなかったのですが、彼女いわく、「あの頃のことって鮮明な記憶があるよね。今はない風景とか、とくにヘドロ問題の時期だった川のにおいなんか、今はないにおいだけど思い出せるね」高校時代の友人、小池昌代は詩人です。高見順賞を受賞し、活躍を知りました。朝日新聞や日経新聞のコラムを読んで「彼女に連絡とりたいな」と、インターネットで探し出して連絡をとることが出来ました。エッセイ『屋上への誘惑』を読むと、やはりあの時期同じ風景を見て過ごした事がわかるんですよね。それと書いているのは30代・40代になってからとはいうものの、なかに高校時代の彼女はこんなこと考えていたんだ、っていうところが探れます。今朝のNHKで見た直木賞受賞作家の石田衣良。同期生なんだそうです。友人とも「知ってた?」と首をかしげるくらい、タイプの違うところで活動していた生徒だったのでしょう。彼のインタビューを読むと、当時1日3冊本を読むことを目標にしていたという人ですから。ところが、今日テレビに映った一瞬の画像で確信したことがあります。ほんの2秒ほど、彼の小説が写されたのですが、登場人物の名前が同級生女子の名前です。ちょっと変わった名前で、私は彼女のほかにその名前に出会ったことがありません。それで、たぶんここから来ていると、、、。石田氏に伺わなければ確証はありませんが、はたから見た直感。私の時代は、とにかく有名校に進学することが人生の幸せ切符という感じで、親も学校も「1に勉強、2に勉強」で、私はあまりいい想い出がありません。まあ、私にはあまり合わないところだったのでしょうね。あんな空気の中でもちゃんと自分のモチベーションを大切にしていた友が今花開いている姿、うれしいです。
2004年03月30日
コメント(2)
-
札幌は国際交流発祥の地!
ラボ教育センター 北海道支部 国際交流のつどいが開催されました。この夏国際交流に参加する新中1-中2の子ども達を励まし、本人達の志を表明する会です。激励講演においでくださったのは、元北星学園大学学長の土橋信男氏です。氏のお話は、今年国際交流に参加する子どもたちに語りかけるかたちで、地元北海道に誇りを持って交流にむかう気持にさせてくれた素晴らしいお話でした。「ここ札幌は西欧との国際交流発祥の地として日本じゅうから注目されるところです」と始まり、その理由を考えさせられました。札幌農学校(現・北海道大学)日本最初の近代的大学として1876年に設立され、初代教頭William Smith Clark博士を迎えました。これは国立大学1号と思われがちな、東京大学より2年前のことなのです。クラーク氏は英語で授業をし、留学生の受け入れをホームステイで行ないました。岩手県生まれの、新渡戸稲造(5千円札の肖像です!)は、13才で東京英語学校に学び、16歳で学校札幌農学校2期生として内村鑑三らとともに入学しました。その新渡戸稲造は、札幌農学校卒業後、東京大学に学び、日本精神を世界に紹介するために"BUSHIDO"『武士道』を英語で書きました。今よく売れているのは、映画『ラストサムライ』主演のトム・クルーズが日本を理解するために読んだ"BUSHIDO"の翻訳本です。日本人が書いた本を、他の人が日本語に訳しているなんておもしろいですよね。日本についてその民族性や精神的な文化を英語で表したもうひとつの書物をあげました。それはアメリカ人ルース・ベネディクトが書いた『菊と刀』。これについては参加者ご父母や、高大生向けの内容とは思いますが、日本人が無意識に持っている「笑われないように、恥をかかないように」と思って消極的になりがちであることをあげました。余談ですが、3月に集中的に小泉八雲に取り組んだ私としてはこのあたりの話がおもしろくて、日本人の精神構造について考えるなら『甘えの構造』も一緒におすすめしたいなーとニヤニヤしてしまいました。さて、本日最後の決めことばはもちろんクラーク博士の“Boys, be ambitious(少年よ大志をいだけ)”です。
2004年03月28日
コメント(0)
-
高校PTA360人分の昼食作り
学年末子ども達へのプレゼントにPTAで昼食を作りました。調理室は8時過ぎから給食室に変身。私はコロッケ担当。10時までのつもりが、どうにも手を休められず次の方にバトンタッチできるところまでのお手伝いでした。材料も買出しも準備から片づけまでみんなPTAからのプレゼント。コロッケ360個、スパゲティ9キロ、フライドポテト20キロ、と一般の主婦がどうしてこんな量を想像して作業の指示を出せるものか、仕切り役の方にただただ関心。サンドイッチのほかに、くだものやおやつになるものもパッキングして一人一人等分に配ったというのですからびっくり。 学校側も時間協力して、各クラスからの出し物発表ののちの交流昼食会で、先生の物まね上手がいたりで、見ているほうも「あんな子いたの!」と人材発掘の場にもなったようで大変おもしろかったそうです。はじめて中華なべに1.3リットル(1本まるまるですよ!)の油を注いで、泳ぐような油の中で90個のコロッケを揚げました。ちょっと職人気分。
2004年03月17日
コメント(0)
-
おはなしで得られる英語力は?
おはなしをしっかり聞いていくことで身につく英語力ってどんな形であらわれるのでしょう。中学の成績にはあらわれにくいとよく言われます。高校では?長文読解はこなせるけれど今ひとつ表われにくいかな。それに、おはなしはお勉強じゃあないから試験と直結しない、とも。私が英語テストに燃えたのは、もちろん自分の英語力を試したかったから。自分でことばをものにしている自信がなかったから、自分の評価を他人にして欲しかったのです。おはなしで英語を学ぼうと活動をはじめてもうじき10年。もうTOEFLもTOEICも受けていないからテストのような具体的な実力アップのことはいえません。でも英語力は上がっていると思います。どうしてそう思うかというと、本を読んだり、自分の感情を話そうとするとき、相手が受ける意味と自分の思っていることの誤差が少なくなって伝えられるようになっていると感じるからです。スコアや級って何だと思います?自分の使っていることばが他人とある範囲で合致するかどうかを確かめる数字ではないかと思います。いまそのたぐいのテストを受ける気がしないのは、それをもとに夢をかなえられるわけでもないと思うことと、そんな大まかな範囲でことばを見て欲しくないからかな。
2004年03月16日
コメント(0)
-
生放送終わりました!
ラジオ放送のインタビュー 次々と消えていく声で人に伝えていくことの難しさを体験!質問内容に一応打ちあわせがあったものの、生放送ゆえ、質問の内容が微妙に異なる場面がありことばに詰まることもありました。とっさの判断で文章を作っていく中で不適切なことばを使ってしまったりね。録音を聞いてみると、いかに自分のことばが聴き取りにくいか..とほほ。発音と発声は、意識していてもこんなもんなんだ、と実感。何はともあれ、「1回こっきり!」の緊張感から学んだことは大きいです。明日の図書館活動ガンバロー!!それじゃ今日は一日ラボ、いってきまーす!!
2004年03月12日
コメント(3)
-
NHKラジオにて取材
札幌市中央図書館で活動している、大人向け英語による絵本の読みきかせサークル「おおきな木」が、ラジオNHKの取材を受けます。担当の方はすでに図書館の例会においでくださり、わたくしたちの趣旨も把握されての取材と生放送です。地方放送ですが北海道全域に流れます。放送日時は、3月12日 金曜日 朝7:55-8:00 ラジオAM NHK第1 にて電話取材の形で放送です自宅ですが、やはりしっかりお化粧もして服も着替えて臨みたいと計画中!!でっきるっかな~? きいてね!
2004年03月10日
コメント(0)
-
小泉八雲の生涯を4時間で見る
13日図書館の大人向け英語絵本読みきかせ会で、小泉八雲原作の絵本"The funnylittle woman"を読みますので、目下八雲に関する資料に目をとおしてつなぎのことばになるヒントをつかもうと奮闘中です。とっても浅い読み方でお恥ずかしいですが、本は何かのあいまにぱらぱらとめくって、何とかこなしています。映像を見てじっとしているのが好きでないため、なかなか手が出なかった4時間分のVTR「1994年NHK人間大学。」見るのは一苦労だぞ、と思っていたのですが、今日は、計算作業の日。絶対パソコンに触らない(ネットしない)と決心し、リビングでスイッチ・オン!冒頭の隠岐の島のシーンと講師・工藤美代子さんの語り口とその内容は、一気にこのビデオを見る気持にさせました。隠岐の島は、20才の夏、スケートに行き詰まって思い切って練習を休んで旅をしたところ。当時ハーンのことなど全く関心もなく、私の心境はそんなことはどうでもよかったのです。にもかかわらず、私の行程は松江・隠岐の島・そのあと福岡・熊本とまわって、ハーンが、松江→熊本と行ったように、重なってしまいました。私は東京生まれの東京育ちでほかの土地を知らない20才。でも、隠岐の島へ向かう船から見る水しぶきと日本海は、何よりの癒しでした。島ではほとんど歩いてまわり、そこで見た風景は、ほかと比べなくても「心に残る場所」となっています。ハーンは、住むところを変えることによって、成長していった人。それは当時の人間には空間の移動というそれまで不可能だったことが輸送機関の発達により、可能になった時代。めずらしいところへ行って見たこと感じたことを文章にしていくことがマーケットとして英語圏で受け入れられました。彼の大変個性的な能力は、時代の申し子としてハーンを育てたのだそうです。彼女のお話をひとことももらさないで聴き取りたいと思い、ビデオを見ながら音声をMDに入れ、ビデオ終了後は耳から聞いています。4時間で人の一生が集約され、彼にかかわった人たちの一生も見ながら、いろんなことを考えてしまいました。たくさんの刺激を受けて、さて、この感想を日記に、と思ったものの文章力がないただの人は、これで床につこうと思います。 おやすみなさい。
2004年03月08日
コメント(0)
-
講座 英語で読む『ギルガメシュ叙事詩』
大人向け3回講座 「英語で読む リュドミラ・ゼーマン作 3部作絵本ギルガメシュ」が終了しました。最終回の今日は、いつものように日本語絵本の読み聞かせのあと、タイプ打ちしてプリントしたテキストを音読しました。3作目の『さいごの旅』は、日本語に翻訳するにあたって、訳を飛ばした箇所やページが前後するところがあります。たまたま入試休みで参加してくれた高校2年生2名は目ざとくそれらを見つけ「さっき日本語で聞いたときとイメージが違う」と言ってました。若い人たちは感じたことを口にする反応が早い!1時間半の講座は、英語を読みながら翻訳版との解説を入れるだけであっという間にすぎました。3部作をとおしての製作意図や構成、発掘品について話し合えなかったのが残念です。...欲張りすぎですね。今度企画する時は、4回連続講座にして4回目に絵本以外の資料をお見せしようっと!
2004年03月04日
コメント(0)
-
ことばの感性 (パーティ便りより)
マザーグースの日本語訳は、意味を優先させると「チンプンカンプン。何が面白くて500年も歌い継がれるの?」と思います。わらべうたが長い間人から人へ伝えられるその訳は、言語の持っている心地よいリズムにあります。だからマザーグースはぜひ英語で楽しんでほしいと思っています。意味中心の翻訳が多い中、ことばの音にポイントをおいてマザーグースを伝えようと試みたのが和田誠さん『オフ・オフ・マザーグース』(1989)『またまたマザーグース』(1995 ともに筑摩書房)です。出版後、それぞれの訳詞に曲がつき、1977年2月、阪神大震災のチャリティ・コンサートとしてマザーグースコンサートが開かれ、テレビで放映されました。1曲に付きひとりずつ歌手がつくという紅白をしのぐ超豪華コンサートにビックリしましたが、「マザーグースの日本語替え歌遊びなんてつまらない。原語を知って欲しい」と、ビデオを撮ったものの、特に繰り返し見るほどの興味をおぼえませんでした。これが東芝EMIよりCD版になって出ていることを最近フェロウメンバーに教えていただきました。改めて聴いてみて、7年の間に自分が変わったことを気づかされました。日本語のリズムの楽しさのほか、作曲者・歌手も日本人ですので、英語のマザーグースとはまったく別の日本のうたと感じました。ことばのリズムに加え、曲風と歌い方が演歌・ブルース・タンゴ・ロック・オペラありで、「面白い!」と素直に楽しんでいます。この間にどんな変化が私の中にあったのでしょう。振り返ってみると、当時の私はただ英語を吸収したくてたまらなかった時期、英語をたっぷり聞いて反応したい一心で、ことばを「感じる」より「わかる」ことに重きをおいていました。7年の間に、詩に出会い、色々なおはなしに出会いました。そのなかで自分には乏しい日本語力しかないことを知りました。外国語ばかりを追いかけていたけれど、これでは自分の内面的なことは何もないと感じました。何語、ということにかかわらず「ことば」を受け入れていく姿勢と柔らかい感覚、これが「感性」というものではないかと思います。そのせいでしょうか、近頃ではいろんなものが見えたり感じられ、若い時より敏感になっています。
2004年03月03日
コメント(0)
-
図書館にもラボ・ライブラリーが入りました!
ラボ教育センター発行のバイリンガルCD付き絵本、ラボ・ライブラリーが札幌市の公共図書館に入りました。現在登録中で公開にはもう少し時間がかかるそうですが、もう届いており書棚に入るのを待っている状態です。『だるまちゃんとかみなりちゃん』『いたずらきかんしゃちゅうちゅう』『スーホの白い馬』などです。英語・日本語の語り・音楽という三つの音の要素と絵本の視覚要素が組み合わさって一つの作品となるラボ・ライブラリーを一般に公開できるのはうれしいことです。ラボ・ライブラリーに出会って9年。(私はラボ・テューター)それまでも語学テープは、ロシア語・英語と色々集めてきましたが、このシリーズが一番飽きずに聴けます。しかも聴けば聴くほど自分の中に隠れている感性(のようなもの)がむくむくと動き出して、年をとっても楽しみがいっぱいあるのです。この楽しみを共有できる人が増えること、それが私の夢であり、楽しみです。読みきかせ会の人たちにもどんどん聞いてもらいたいなあ!
2004年02月28日
コメント(0)
-
古本屋めぐり
金田鬼一訳のグリム童話集がやっと手元に。数年前、古本屋で見たとき「どうしようかな」と迷い、翌日行ったらもうなかったのです。今日初めて入った本屋さんで見つけました。「もう離さないぞ!」と購入しました。ほんとに上品な日本語。それに漢字の読み仮名の当て方がすごい。グリムは長年、どれを買おうかなと思い迷ってきました。英語で2冊、初版訳が1冊。そのほか絵本でばらばらと。全集をそろえていないので調べものに困るときは図書館へ。でも今年何か縁があるというか、あっという間に3セットそろい、来年あたりグリムをやりたいな、なんて思い始めました。げんきんなもんです。ほかに岩波・中務哲郎氏の「イソップ寓話集」471編 - これはいろいろな翻訳の対照表がついている興味深い編集。「沈黙の春」これは持っているのですが、人にあげられると買いました。(おせっかいだけどね)その他に絵本2冊。3軒回った成果。いい気分で、丸善でも4冊購入。あー、たっぷり買いに走っていい気分。来週は東京に行くので道中の読み物が準備できました。
2004年02月17日
コメント(0)
-
おはなしの百貨店
読み聞かせにかかわる団体が集まって図書館で行うイベント「おはなしの百貨店」。昨年からの企画で、子ども向けにいろいろな形でお話を楽しんでもらおうという趣旨で行われます。昨年は「子ども向けに英語絵本を読むのは私たちの日常活動とは違うかたちになるから参加は難しいね」と見送りました。今年は、日常活動と同じ「大人向け英語絵本の読み聞かせ」で参加する運びになりました。「英語による読み聞かせ」- 多くの方は「英語がわかる人は楽しいでしょうけど」と尻込み、または、「英語がどれくらい聞き取れるかチャレンジする会」と思っていらっしゃるようです。活動の当事者は、英会話の達人でもなく(達人もいらっしゃいますが必要条件ではありません)、英語力を磨くために会で英語のお勉強という雰囲気でもありません(マザーグースを歌ってばかりのお歌の会)。でもみんな英語の絵本を上手に読むんです。聞いてて「楽しいお話だなあ」って伝わるんです。母国語を得ていく子どもが、「日本語力を高めるために」お勉強せずにいろいろと世界を広げるように、たくさんのお話を英語で読んでいく中で自然に英語力をつけて物語を楽しんでます。会員のなかには、「ことばの意味がわからなくても音の流れの中で絵本を見ている、そんな時間のなかにいる自分が幸せ。ここは至福の空間」なんてほめてくれる人もいらっしゃって、それを聞いて私も幸せです。そんな風に感じてくれる人を活動を通じて増やしたいな、と思います。「おはなしの百貨店」大人も来て下さいね!*会を立ち上げたいきさつは、このHP左側にあるページ「英語で聞く名作絵本とマザーグース」「読み聞かせサークル おおきな木」をご覧ください。
2004年02月12日
コメント(0)
-
原書で読む E.B.ホワイト作 『シャーロットのおくりもの』
辞書なしで原書に挑戦、E.B.ホワイト作 『シャーロットのおくりもの』 第3期生が誕生しました。このおはなしは、10年以上前に出会い、英語で年長の子ども(3歳までアメリカで過ごしたた子)に読み聞かせをしたものです。読み聞かせですから、辞書無しです。わからない単語は適当に読みました。それでも毎晩「もっとよんで」とせがむ様子に日本に帰って2年、この子に英語力がそだっているのか、おはなしの力なのかふしぎな気持になったものです。子どものことはさておき、ことばがわからないなりにも伝わるものがある文章に感銘を受けました。ぜひこれを大人として読みたい、こまごまと辞書をひかなくてもストーリーがわかり、メッセージを受け取れる体験を、と講座をはじめて2年、昨日3期目が終了しました。本を読むのは一人で好きな時にできることですが、仲間とともに書いてあることをもらさず音にして最後まで読み通すことで、黙読とは違った達成感が味わえます。また、内容について意見交換をするなかで、ものがたりから伝えられるメッセージもより多く感じることができました。私にとっては5回目の読み通し、まだまだ発見があることにこの作品の強さを感じます。そして読み通していく期間に、必ずドキッとする出会いがあるのです。今回は、『沈黙の春』『センス・オブ・ワンダー』の作者レイチェル・カーソンがホワイトを大変尊敬していたということです。別の用事で久しぶりに『沈黙の春』をめくって、それに気づきました。ついでに、年長でこれを最後まで聞きとおした子は今中学1年。当時の私の期待はどこへやら、教科の英語は苦手科目です。笑えるね!
2004年02月05日
コメント(2)
-
「のはらうた」 詩人 工藤直子さん講演会
詩集「のはらうた」で有名な工藤直子さんの講演会に行って来ました。まずは、「これはお勉強ではありません。今の社会ではなかなか出にくいけれど誰もが持っている『感じる心』 についておはなしします」と始まりました。詩の楽しみ方にはいろんなアプローチがあるという例に、工藤さんの詩にメロディをつけたCDを色々聞かせてくれました。もちろん朗読も。 「もしもこの詩が、手書きの文字で色がついていたらもうそれでイメージができてしまうでしょ。ある意味『活字』っていいんですよね」2時間の講演内容を上手にまとめられないので、以下は私のメモから箇条書きにします。◎ 学ぶ事の一番の動機づけは「楽しむこと」「嬉しいと思うこと」それは<遊び>にある。<ためになる>とか<役にたつ>とかは4番目か5番目のこと。◎ 自分の出会ったものが、「面白いなあ」「いいなあ」と思ったらそれはあなたのもの。ちなみに工藤直子の詩には著作権はありませんので、どうぞご自由にお使いください。◎ ことばは紙の上にくっついているものだけれど、それを読んだり、声に出したり、朗読を聞いたり、演じたり、イメージを絵にしたりいろんな楽しみ方がある。◎ 「読む」とか、「演じる」は、上手だからいいというものではない。気持が伝わるほうがずっといい。◎ よくお母さんが、「自分はダメだから子どもにはできるようになって欲しい」と思って何かを習わせるけれど、一番の方法はお母さん自身がそれを好きになること。◎ 最後に翻訳絵本、エリック・カールの『ゆっくりがいっぱい!』"Slowly, Slowly,Slowly, Said the Sloth"を解説つきで読んでくださいました。「カールさん、思いの限りのslowを集めたもんだから私もゆっくり、のんびり、おっとり、、って集めたのよ」<子どもに何かをさせたいのなら自分がそれを楽しむことが一番> 大人のための英語絵本読み聞かせを通じて、子どもに本を手渡したいと活動している身には大変心強い内容でした。
2004年02月03日
コメント(0)
-
小学校PTAサークルとしての読み聞かせ活動
今日は久しぶりに、小学校の読み聞かせサークルの運営会に出席し、引き続き子ども達への読み聞かせにも参加して来ました。当事者でなくなったせいか、ゆったりと意見交換を聞いてきました。中心になるごく数人を除いては、『好きな時に参加して何かを得て帰る』形にすると、仲間たちは和気あいあいといい雰囲気で、なんとなく持ち寄りのお菓子も豊富で、物事を決めるのにも結構本音を意見として出してるな、という感じが伺えます。娘の通う高校のPTA は、役員選出が強制でないというユニークな組織です。それでも一応活動に必要な人員は確保し(私も入れていただきました)、゛楽しい~とOBまで活動しにきて下さるのですからいかに組織運営が上手かということです。社会に還元される活動参加が、ご奉仕ではなく、自由意志で集う運営を考えることがボランティアのキーポイントなのでしょうね。
2004年02月02日
コメント(0)
-
コマドリ
The north wind doth blow,And we shall have snow,And what will poor Robin do then?Poor thing. ナーサリーライムの1節ナーサリーライムや英語圏のお話によくでてくる Robin コマドリ。イギリスで出版された絵本とアメリカで出版された絵本とでは「なんだか鳥の感じが違うなー」と思っていたらそれもそのはず。コマドリの生息地域はヨーロッパで、アメリカに移民した人たちが故郷の鳥を懐かしがって姿の似ているコマツグミを“Robin”と名づけたんですって。つまり別の鳥を指しているんです。絵本でその違いを見たいと思う方は次の2冊を見てください。イギリス在住の作家が描いた絵本 パット・八ッチンス作 『おやすみみみずく』 “GOOD-NIGHT, OWL!”アメリカ在住の作家が描いた絵本 フェオド-ル・ロジャンコフスキー作 『おおきなのはら』 “OVER IN THE MEADOW”
2004年01月30日
コメント(2)
-
産みの苦しみ
今日は図書館サークルの例会。3月の選書をしなければならないので、昨日からいろいろ読みました。テーマは『むかしばなし』英語で読むので、色々制限がつきます。イギリスのむかしばなし、グリムを主とするヨーロッパのものはいままで取り上げてきただけに、なかなかすんなりと行きません。思い切ってメソポタミアのお話『ギルガメシュ』も考えましたが、三部作ゆえにこれも上手くいきません。煮詰まってしまい、アンソニー・ブラウンのお楽しみ絵本を読んだら、ふと新しいテーマの展開がでてきました。そうは言っても今日行き当たりばったりにでてきたテーマなので、またジャンルを変えて読み込みをしなければなりません。ここ1年、新しく手にとった絵本の数が少ないことを反省。さあ、新しいものを求めて、産みの苦しみです。
2004年01月17日
コメント(0)
-
あらしのあとで
何か絵本の題名って感じのタイトルですが、今日の札幌は昨日までの嵐が去り、道路も夜のうちにずいぶん整備され、ちょっと路面の荒れている普通の日に戻りました。瀬田貞二さんの『幼い子の文学』を久々に読み返し、つくづくすごい方と思うばかりです。 その中で紹介されているアリソン・アトリーの"Magic in my pocket"が現在入手可能です。ふと仕事先の書棚で見つけ、手にとって興奮。検索してみたところ、あったのです。日本語で「チム・ラビット」シリーズが童心社から出ていますが、そこに出てくる詩が英語で読みたかったので手にとって嬉しい1冊です。『幼い子の文学』の中で紹介された、ハーバ-ド・リードのことば、「マジック・アンド・ミュージック」 -いい詩にはふたつが備わっているという表現、心と舌にに響きます。
2004年01月16日
コメント(0)
-
暴風雪のなかで
大荒れの天気の中、午前中は大人の絵本のクラス、午後は体験会、父母会と、冬休み中の割にはしかっりスケジュール。ところが外は悪天候のひどい一日でした。今日のテレビのトップニュースは北海道の悪天候。乗り物はみんな欠航、運休。何の予定も無かったら暗い気持ちで雪かきに終始しなければなりません。 でもそんな中、予定はこなされたのです!!朝の雪かきは吹き溜まりになっていて大変でしたが、時間と場所を約束している以上絶対にその場にいる必要がある、と思って出かけました。タクシーを使ったり、重装備をしたりで、いらしてくださるんです!!新しい出会いもありました。父母会には予想以上の方がおいでくださり、子ども達も楽しく遊んでいきました。嵐にも負けないおはなしの輪、今年はもっと大きく強くなりそう!
2004年01月14日
コメント(2)
-
ジャパンマイコンカーラリー2004のお手伝い
娘の通う高校が会場校となって、ジャパンマイコンカーラリー2004の北海道大会(1/10)・全国大会(1/11)が開かれています。きょうはPTAのお手伝いに行ってきました。会場校とあって、内容と関係の無い部活生徒が借り出されて駐車場整備やお掃除をします。もちろん先生や、関係する学科の生徒たちは昨年から準備にかなりの時間を費やしてきたそうです。その応援として父母がそば・うどん・おにぎり/カレーの昼食を差し入れするのです。高校のPTAは社会人としての情報交換も豊富で楽しい!しかもみんな我が子より若い感覚でPTAで青春しているのです。そのうえOB(PTAの)も楽しそうに手伝いにいらっしゃるのですから、面白い大人の輪がここにあると思いました。確かに笑いの絶えないひとときでした。公立校でこの雰囲気、ありがたいです。
2004年01月10日
コメント(2)
-
北海道のそろばん道路
昨夜から今日にかけて、雪と風の大荒れ天気でした。朝は、風のないうちに雪かき。午後出かけると、道路はどこも「そろばん」のようにぼこぼこ。30キロのスピードでもがたがたゆれて、吹っ飛びそうになるんです。このそろばん路面、除雪車がはいって削ってくれればありがたいのですが、幹線道路の路面削りはめったなことではしませんから、温かくなって溶けない限りはこの調子。つるつる路面、雪が積もったふんわり路面をはじめとして冬の北海道の道路はバラエティに富んでいます。
2004年01月08日
コメント(0)
-
水戸の偕楽園 好文亭
年末年始は、神奈川・東京と実家めぐりをしてきました。今回の帰省は車を足に、フェリーで出かけたので、寄り道を楽しむことができました。仙台から福島県郡山までは浜から入っていきました。素晴らしい景色でした。帰路は、水戸の偕楽園を見てきました。梅林とお庭のつくりが素晴らしいのは有名ですが、わたしはその中にある好文亭という建物を楽しみました。好文亭入り口近くの説明にある「烈公(徳川斉昭)は、礼儀・書道・音楽を学ぶことを重要とした」という一節に、お勉強の苦手な娘は一筋の明かりをみつけたようでした。私もいいなあと思って、この三つの学びの柱を口ずさんでいます。
2004年01月04日
コメント(2)
-
韓国語に挑戦
韓国のおはなし『おどりトラ』を日本語・韓国語で録音されたものを聞いています。1/24にはラボ・テューターの総会で発表するのです。わたしは韓国語を読めませんし・書けません。でも、日本語と対応することばがなんとなくわかってきました。文章で覚えられたのはまだかぞえられるほどですが、新しいことばに取り組む時ってスリリング。考えてみればこれは小学生が英語を覚えて表現しているのと同じこと。読めない・書けない外国語を、見事に覚えてくる彼らの気持とやり方を察するためにはこれはひとつの試練です。聞いても聞いても耳にはいらないことには慣れているけれど、それがあるときストンとからだに入ってくることがあります。そこがつかめるようになると面白くなってくるのですよね~。お正月は上京して2件のお家を訪れるため、大忙しではありますが、楽しみです!
2003年12月28日
コメント(1)
全167件 (167件中 1-50件目)