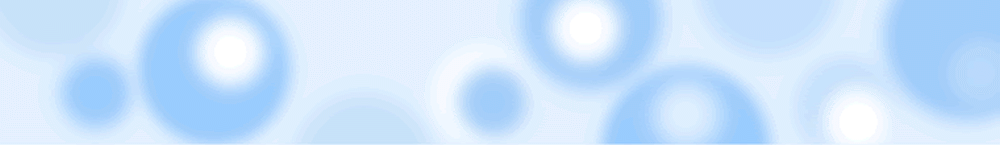PR
カレンダー
キーワードサーチ
 New!
こたつねこ01さん
New!
こたつねこ01さん冬も少しずつ進んで…
 New!
木昌1777さん
New!
木昌1777さん今日のおやつ「くる… New! クレオパトラ22世さん
TOKYOタクシー New! エンスト新さん
山中湖・お宿は「w…
 みぶ〜たさん
みぶ〜たさん子育て支援の見学と…
 7usagiさん
7usagiさんネコ様とガーデニン… 結柄yueさん
お買い物 満々美人 Grs MaMariKoさん
旅人てつきちのトー… Tabitotetsukitiさん
〜旅するように暮ら… tabimizukiさん
サイド自由欄
●現代レイキ
◆土居 裕著
実践レイキヒーリング入門 ・ 癒しの現代霊気法
レイキ宇宙に満ちるエネルギー
●ヘミシンク
★坂本 政道著
楽園実現か、天変地異か
★まるの日 圭著
誰でもヘミシンク・サラリーマン異次元を旅する
●心理学(NLP)
▼山崎 啓支著
マンガでやさしくわかるNLP
▼椎名 規夫著
自分とまわりを変える魔法のNLP実践トレーニング
「多くの人は入院すると病気がよくなると思っています。
若い方はそうなのでしょうが、高齢者は入院によってかえって健康状態を悪くさせてしまうことがある。
安易な入院は控えようと思いました」
このライターの女性の場合は、初期の認知症の親を、専門病院へ検査入院させたことが発端だったようである。
私の父の場合は、ナトリウム不足で立ち上がれなくなり、やむなく入院となった。
グループホームの人もあの手この手で、塩分摂取を試みてくれている。好きな梅干しも、毎回食事に加えてくれた。
でも本人にその塩分を蓄えておくことが出来ないために、結局いくら摂取しても、排出されてしまうわけで‥。
ホームとしては医療関係でないことから、今年の3月に入院という措置になったのである。
それからたった1ヶ月半という入院期間の間に、私や家族の事が分からなくなってしまったのだ。
「退院してホームに戻れば、認知機能は戻ります。」
ホームのグループ長の力強い言葉は、非常に有難かった。
そしてその通りになり、私の名前も思い出したのである。
高齢者で初期の認知症の人は、入院することで寝たきりになり認知症が進んでしまうことが起こる。
他にも骨粗しょう症や、心臓や肺の機能低下、介護度が上がるなど、
高齢者の場合は元気になるはずの入院で、
起こってしまうさまざまなトラブルを考えなければならない。
実は私の父もこの入院がきっかけで、要介護が2から3になった。
認知機能は戻ったのだが、車椅子生活になってしまったのである。
歩くということが、出来なくなってしまったのだ。
老年医学の世界では、こうなってしまうことを、「入院関連機能障害」と呼び、問題視しているという。
入院関連機能障害は、入院のきっかけになった病気とは別に、入院によって新たに生じた機能障害のことを差し、次の例を上げていた。
「肺炎で入院した患者さんが、点滴治療を受けて安静にしていたところ、
意識障害が起こったり、歩行困難な状態になったりして、
退院後に介護が必要になった‥という状態をいいます」
若い人にとっての入院は、病気を治療するという意味合いだけだが、
高齢者にとっては、もしかしたら別の病気を呼んでしまうという、
厄介なものになるのかもしれない。