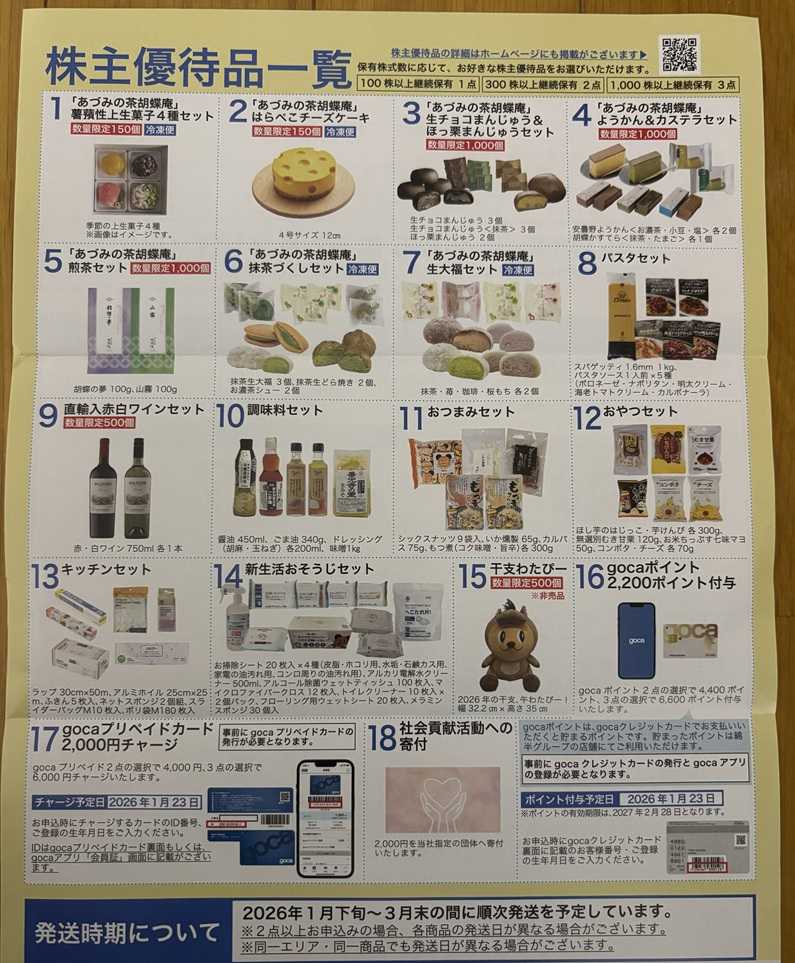2011年01月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
■少額からでも老後資金の準備を
「2010年冬のボーナスと家計の実態調査(損保ジャパンDIY生命)」によると、ボーナスの使い道のトップは「預貯金」(70.6%)で、次いで「生活費の補填」(43.6%)、「ローンの支払い」(32.2%)でした。使い道のトップが「預貯金」となるのは例年と変わりませんが、70.6%という比率は冬のボーナス調査の中でも過去最高であり、家計の多くが、依然、収支のやりくりと将来への備えを優先せざるを得ない状況にあることがわかります。この1月から所得税の扶養控除の一部見直し(18歳以下を対象)の適用が始まりました。また、11年度の税制改正関連法案が政府案通りに成立すれば、23歳以上69歳以下の扶養控除が縮小されます。さらに、給与所得控除も縮小の対象です。給与所得控除はサラリーマンが給与収入額から差し引ける(必要経費)概算の控除額で、この控除額を差し引いた後の金額が給与所得額となります。さらにここから扶養控除や配偶者控除などを差し引いて課税所得額が算出され、これに税率を掛けて所得税額が決まります。家計に与える影響は年収によって異なりますが、子供手当の増額や法人実効税率の5%引き下げの財源として、多くの負担を個人に強いる格好となっており、家計は当面、守りの姿勢を崩すことができないでしょう。国の財政状況や日本経済の将来を自分の家計に結び付けて不安を感じる人が増えてきています。生活を安心させるための社会保障制度のはずが、特に年金制度については大きな不安を感じる人が多いというのが実態です。日本経済新聞が実施した「家計・生活ネット1,000人調査」によると、老後の生活に金銭的な不安を感じているかという質問に対して、「まったく不安を感じていない」あるいは「あまり感じていない」と答えた人の割合は1割強程度に過ぎず、8割を超す人が年金制度へ不安を覚え、自助努力の必要性を痛感していることがわかります。同じネット調査で、老後資金として必要な貯蓄額を聞いたところ、2~3千万円未満という回答が最も多かったようです。子供の教育費や住宅購入資金の準備など、何かと出費がかさみがちで手元資金に余裕のない30~40代は、積立運用を利用するなどして少額でも早い時期から老後資金準備を始めたいところです。老後資金準備には、非課税の貯蓄・投資優遇制度である確定拠出年金(日本版401k)への加入を検討するところから始めると良いでしょう。運用期間中の運用益が非課税で、積立金を受け取る場合も、控除の対象となります(年金として受給する際は公的年金等控除、一時金として受給する場合は退職所得控除)。なにより、掛け金が全額、所得控除になるため、その節税効果は無視できません。勤務先で確定拠出年金制度を導入していない場合でも、独自の企業年金のない会社の従業員は個人型の確定拠出年金に加入することができます。個人型に加入可能な会社員は千数百万人に達すると推計されていますが、実際の加入者数は8万人に満たないという報告もあります。個人型加入資格があるかどうかを一度、お勤め先の担当者に確認してみてはいかがでしょうか。==========================================================ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社ファンドマネージャー 相川雅宏(楽天マネーニュース[株・投資]第91号 2011年1月28日発行より) ==========================================================
2011.01.28
-
■投信に若い世代の資金導入を
日本の投資信託は、2007年10月に純資産総額で82.2兆円のピークをつけた後、2008年秋のリーマン・ショックを受けて2009年1月に49.6兆円まで急減した。その後世界の証券・金融市場の反騰を受けて回復に向かい、2010年4月には65.4兆円まで回復したが、以後、拡大は頭打ちとなり2010年を通じて投信残高は停滞を続けた。投信の拡大が足踏みしているのは、銀行等金融機関による投信販売が伸び悩んでいるためである。金融機関による投信販売は2000年代に入ってからの投信拡大の原動力となってきたが、リーマン・ショック後は頭打ちとなっている。株式投信の販売残高シェアは2003年当時では36%程度だったが、2009年2月時点では53.0%に達し証券会社のシェア46.4%を大きく上回った。しかし直近2010年11月時点ではシェアは47.9%に低下、代わって証券会社のシェアが51.4%に上昇し再び50%を上回った。銀行等金融機関の投信窓販が解禁されたのは1998年末のことだが、それから10年余を経過して、顧客の資産中の預金から投信への移行はほぼ一段落したように見える。個人金融資産中の投資信託の比率は2000年末の2.4%から2007年末には4.7%まで高まったが、これをピークとして2010年6月末では3.4%に低下している。半面、現金・預金の比率は2006年末に50.1%まで低下したものの最近は再び55.8%に高まっている。金融機関による投信販売が伸び悩んでいる背景には、現在の投資信託の主要なマーケットが比較的高年齢層に偏っていることがあると思われる。投信協会の調査によれば、現在投信を保有している投資家の5割は60歳以上の高齢者であり、40歳以下は13%に過ぎない。そうした高齢者が蓄積した金融資産を「貯蓄から投資へ」の流れの中で投資信託に誘導してきたのが、これまでの投信販売、とりわけ銀行窓販だったと言えよう。投資信託が米国のように金融資産中で10%以上もの比率を持つまでに拡大するには、これから金融資産を蓄積する若い世代の資金を投資信託に振り向けてもらうことが必要だ。そのためには投信商品の品揃えについて見直しが求められよう。現在の日本の投信の中心商品は、高利回りを追及する定期分配型など高齢者のインカムニーズに応えたファンドが多いが、これからは、長期の資産形成を目指す若い世代の投資家が、ポートフォリオの中核として長期保有するにふさわしいファンドを開発していくことが望まれる。==========================================================金融アナリスト 新藤正悟(楽天マネーニュース[株・投資]第90号 2011年1月14日発行より) ==========================================================
2011.01.14
全2件 (2件中 1-2件目)
1