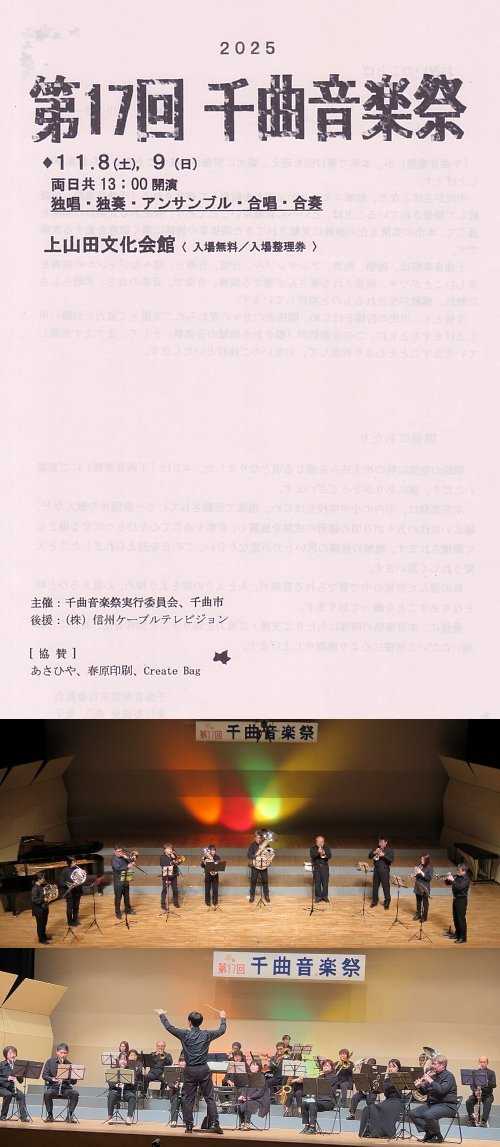2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2004年12月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
おおいっ!
大晦日の日記を、年が明けてから書いています。この日はとにかくたまらんかった…(汗)30日によっつんからある依頼を受けていたのですが、いざ取り組もうとしたら…、なんや、パソコンの調子がおかしいのです。調べてみると…「あれ?ウィルスあるやん…!?」 いつの間に入ったのか、ウィルス検知ソフトに反応が。 そこからが大変でした。 「駆除できません」…やと?! ウィルスバスターでも駆除も隔離もできない!エラいこっちゃ!!感染したファイルを手動で捨てようとしても、捨てることができないのです! フォーマットしかない…?! 絶望的になりながらもリカバリーディスクを入れ、ウィンドウズからなにから全て入れ直しました。外付けのHDにデータを全てバックアップできたのが不幸中の幸いでした。 それから31日まるまる、慣れないためになかなかうまくいかないPCの復旧に費やしたのでした。何回ウィンドウズ入れ直したかなぁ…?(苦笑) K-1でマサトとキッドの試合に感動しながら、ボブ・サップの情けない姿にあきれながら、曙の無惨な負け方に哀れをもよおしながら、夜は更けて新年を迎えました…(涙)。 みなさんも良いお年を迎えられましたか? 新しい年のご多幸をお祈りいたします。また、バニバニを今後ともよろしくお願いいたします。
2004/12/31
-
幸せそうでした
今日はかつての同僚の結婚式二次会に呼ばれていました。なかなか忙しい年の瀬です。 その同僚(女性)は「書家」で、そんな自分が「いちアーティスト」として、現実的にどう生きていくつもりなのかを語ってくれる素敵な人でした。私もまた音楽というアートの世界に憧れ、それと現実とのすり合わせが難しいと思っていたので、彼女が語る生き方にすごく感心したものでした。 久々に会った彼女は少し痩せていて、しかし、ヨン様に扮して登場した旦那さんとともに皆を笑わせている姿は、とても幸せそうでした。 ビンゴゲームでなんと一等が当たり、ウレシイおみやげをもらって帰ることができました。 ネェサン(かつて敬意を込めてこう呼んでいた)、ほんと、いつまでもお幸せに。 私がかつて新任だったころ、同期で入った3人で色々話をしました。私以外の年上の二人を私はそれぞれ「ニイサン」「ネエサン」と呼んでいました。人間不信で、人付き合いが苦手で、社会人として何とかそれを克服せねばならないと心に決めていた自分が必死に使った「大阪流の敬語」、それがこの呼び方なのでした。 これはあの「つんく」氏が、HEY!HEY!HEY!出演時にダウンタウンの二人を「ニィサン」と呼んでいたところから学んだものです。 この、距離感が下手で何が言いたいのかもよく伝えられない私の変な接し方に、嫌がりもせずつき合ってくださったお二人に、今でも私は感謝しています。 2年経ってニィサンが先に他の道へ進まれ、その後ネェサンもまた去っていった職場は、とても寂しいものでした。ですから私もまた4年で職場を変えました。私の職業(あえて明かしませんが)は何より、同僚同士のつながりがなければ絶対に続かない仕事です。他の同僚はもちろんいましたが、私にとっては同期の二人はやはり特別でした。それ以外にも信頼できる同僚はいたのですが、私の心を許した人から次々に辞めていくという現実に、私は職場を移る決心をしたものでした。 人付き合いが苦手だからこそ、人とのつながりからとても多くのことを学ばせてもらっているのは、かつても今も変わりません。 しかし人間不信だった当時の私に、職場の人間関係作りの大切さを教えてくれた二人、特に今回はネェサンの新しい門出に、全力でエールを送りたいと感じました。
2004/12/26
-
「アイーダ」を観ました
劇団「四季」は3度目です。今日は友人にチケットをとってもらって「アイーダ」を観ました。 ミュージカルってすごいですよね。あんなに動きながら歌い、演じ、歌がストーリーの一部として機能するっておもしろい。 なんか今の仕事辞めて、ああいう道に進みたくなった瞬間が何度かありましたよ(笑)。 何にせよ、文化的にクリスマスを過ごせて、久々に「人間的に生きてるなぁ」と実感できました。それこそがクリスマスの贈り物でした。
2004/12/25
-
はじめにきよしのライブ
沖縄から帰ってきたばかりというのに、巷はもうクリスマス。行事多すぎ!なんて思ったりして(笑)。嬉しい悲鳴ですわ。「はじめにきよし」という二人組の「はじめにきよしこの夜」というライブに行ってきました。 基本的にギターとピアニカの二人なんですが、いやいや、すさまじいテクニック…!ピアニカの「新谷きよし」さんの指使いなんてな、もはや天才的です。彼はトークもボケ気味で味のある人なんですが、どれだけボケた発言を繰り返し、相方の「さきたはじめ」さんはおろか観客までも呆れさせながら、曲に入るとバカテクのピアニカを聴かせて(魅せて)くれます。 一方の「さきたはじめ」さんも伴奏でギターを弾くのですが、これまたバカテクです。そしてそして、彼のもう一つの武器が「ノコギリ」です。ミュージック・ソウといって、ノコギリをバイオリン等の弓でひいて音を出すのです。彼のノコギリもまた、「素晴らしい」の一言でした。ウットリします。 彼らのライブは以前、別のところで一度見たことがあるのですが、その時はいろいろなアーティストが何組も出る中のひと組でした。押尾コータローさんやル・クプルも出演し、それぞれに感動したのですが、中でも、あまり期待していなかっただけに、彼らのその高い音楽性に強烈に感動したものでした。CDですでに音楽は聞いていたのですが、やはりライブで見ると全然印象が異なるもんなんだと、その時実感しました。 彼らのすごいところは、バカテクなのに音楽が決してそれを自己主張しすぎないところです。テクニックはあくまで彼らの音楽を表現するために使われていて、決してテクニックをひけらかすことを目的としていません。ミュージシャンの中でもテクニシャンに限って、テクニック先行型の人っているんですよね。でも彼らは違います。確かなテクニックでもって、音楽を高次元で遊び心いっぱいに表現しています。 音楽って、結局はセンスなんよなぁ…とあらためて感じた夜でした。
2004/12/23
-
やっぱヨカッタ沖縄
沖縄レポート その4 この日で沖縄は最後です。 まずは首里城の見学をしました。首里城って、あの城壁や石畳が貴重だってんで、世界遺産に登録されたんですね。建物は改築されて10年ちょっとしか経ってないのに。 いつも思うのですが、首里城って、狛犬や鬼瓦の代わりに龍がたくさんまとわりついてたり赤い瓦だったりするんで独特の雰囲気なんですが、形だけ見たらまるでお寺の形なんですよね。つまり日本のお寺の建築様式の建物で、そのに中国の影響で龍や赤い瓦(中国北京の紫禁城は赤瓦ですもんね)が使われてて、まさに沖縄は様々な文化の融合(それを沖縄の言葉でちゃんぷるーといいますよね)したところなんだなぁと。 そして首里城のあとは国際通りにいきました。 何を隠そう、私のいつも使っている三線は10年前に沖縄に初めて行ったとき、国際通りにある三味線屋さんに飛び込んで買ったものです。以来、2度目に行ったときもその三線を持ってその店を尋ねました。その時もお店のご主人は喜んで下さり、沖縄民謡「安里屋ユンタ」をガチガチに緊張しながら弾いてみせて喜んで頂きました。 そして沖縄3回目となる今回も、三線を持ってその店を尋ねました。「あのお店、まだあるかなぁ…?」との不安を抱きながら横断歩道を渡り、店の近くまで行くと「あ、まだあった!」(苦笑) ガラリと扉を開けると、若い人が二人座って三線を作っていました。10年前に私に三線をお世話して下さったご主人はおじいさんでしたので、もしかしてもう引退されたのかな…?と思って聞いてみると、現在お店にいる方が二代目で、先代のご主人はすでに亡くなったとのことでした(もう4年も前だとか…)。 それでも、私が先代の三線をいまだ使っていること、ストリートで弾いていること、職場でも三線を弾けるということで喜んでもらっていることを先代に変わって二代目にご報告して喜んでもらいました。これがしたかったんですよね。 もう少しで三線をもう一本買いそうになりましたが(苦笑)グッとこらえ、お別れしました。 国際通りでは他に欲しいものがあまり無く、市場へ行く時間がもうなかったので、CD屋に売っていた「神谷千尋」という若手のCDを買って集合場所に集まり、帰ってきました。 この神谷千尋さん、これがイイんですよ~。またライブでも彼女の曲を披露できたらいいんですが、若干22歳で青さはあるものの、私は夏川りみさんよりもハッキリ言って好きです。また興味のある方はご一聴あれ。 ともあれ、これで久々の沖縄旅行が終わり、大いなる学びとともに気分転換も出来、今後の音楽活動の方向性も何となく見えました。 今後の活動や私自身の今後の生き方に反映できればいいなと思います。
2004/12/22
-
大騒ぎ
沖縄レポート その3 さすがに平和平和と学びが続いたんで、この日は遊びの日でした。 沖縄には「世界一」の水族館があるのです。何をもって「世界一」と言うかは色々意見があるでしょうが、「世界最大」の水槽があるのです。 沖縄「美ら海(ちゅらうみ)水族館」に行ってきました。私が初めて沖縄に行ってから今年でちょうど10年。その10年前にも水族館はあったのですが、そこが数年前に改修され、リニューアルオープンしたのがこの美ら海水族館でした。 正直、思っていたほど規模は大きくなく、魚の種類もそんなに多くなかったのですが、さすが「世界一」を誇る大水槽は大した迫力でした。 ジンベエザメが3匹、マンタ(オニイトマキエイ)が3匹くらい(スイマセン、ハッキリしません/苦笑)、その他にも大型の魚たちが悠々と回遊しています。大阪の海遊館もなかなかの大水槽ですが、中身の貴重さでは勝てません。 なかでもニクいのが、大水槽の下に通路をつくり、ジンベエザメやエイたちのお腹側から見上げることができるのですが、その通路、ワキに座るところがあり、クラシック音楽が流れているのです。先日公開された「ディープブルー」という映画がありましたが、ベルリンフィルのオーケストラ演奏と海の生物たちの映像でつくられた癒しの映画でした。まさに「美ら海~」にはその癒しの空間が作ってあるのです。時間があれば何時間でも座っていそうでした(笑)。 午後は沖縄体験ということで、サトウキビ刈りと黒糖作りに挑戦。青臭い黒糖が出来ました(苦笑)。思ったより楽しかったぁ。やっぱ、実際体験するって大切ですね。 夜は同行していた人たちで夜の宴会。 待ってましたとばかりに三線を披露し、それに併せて歌う者、エイサーを踊る者、はたまたハモる者、最後には「花」に手話をつけて発表までしました。 手話ってのはなかなか接する機会がないのですが、寄り多くの人たちと音楽を通して交流していくことを目的としている我々の場合、試みの一つとして興味深い分野だなと、これもまた発見でした。
2004/12/21
-
大いなる学びに その2
沖縄レポートその2 この日は朝からヘヴィでした。「ひめゆり学徒隊」の生き残り、宮良ルリさんのお話を聞いたのでした。 当時の教育を受けていた彼女らは軍国少女として、師範学校に通っていながら18歳で看護婦として病院壕へ配属されます。「女でありながら、国のために尽くすことができるなんて、こんな名誉なことはない!」と思ったと言います。 (「師範学校」とは「教師を育成する学校」のことですから、男女差別がハッキリしていたこの時代に18歳で学校に通っていた彼女らは、いわばこの時代のエリートです。) 沖縄の地上戦が始まり、毎日たくさん運ばれてくる負傷兵の手当てをしながら不眠不休で働き、まさに血と汗と涙と膿と便にまみれたのは彼女らとて同じです。しかし手当てをしようにも薬が無くなり包帯が無くなり食料が無くなり水が無くなり…すべてが底をついていく中で兵隊達の罵声まで浴びながら、「荒れ狂う砲弾の中」を走って食料をもらいに行ったそうです。そんな中で友人が撃たれ、うめく友人の飛び出した内臓を腹に押し込んで縫合していると、友人が「お腹をやられて助かった人は見たことがない。自分ももうダメだろうから、私に使う薬は他の兵隊さんに使ってやって…」と言って死んでいった話とか、友人や兵隊が死ぬときにみんな家族の名前を呼んで死んでいった話とか、壕に爆弾を投げ込まれて両目を吹き飛ばされた友人・両腕がなくなった友人…の話とか、せっかく南部の壕に命からがら撤退し名誉ある死を選ぼうとしていたのに「これで部隊は解散するから、もう自由に何処へでも行け!」つまり「これ以上は邪魔だからこの壕から出て行け」と言われたこととか、ガス弾を投げ込まれて奇跡的に助かったものの周りで死んだ友人達が腐っていく壕の中で何日も隠れていた話とか、足の悪い看護婦とともに逃げていてアメリカ兵に発見され手榴弾で「自決(自爆)」しようと地面に打ち付けたのに不発弾で死ななかった話とか…色々聞きました。 戦争って、悲惨です。「必要悪」だなんてあり得ません。 事実から学ぶって大切ですよ。ホンマ思います。どこぞのタカ派政治家が何と言おうと、どうせその人らはいざ戦争になったら安全なとこにいて、死ぬのは一般人ですから。 宮良さんらは教育の中で軍国主義を学び、お国のために死ぬことを名誉と信じていたのです。中身はホンマにいち一般人です。しかし相手から見れば、抵抗してくる敵の一人としか映らないでしょう。 今イラクで、我々が「テロリストとそれをかくまう連中」と十把一絡げに見なしている人たちって、実際にはいったいどんな人たちなんでしょうね。それを考えずにはおれませんでしたよ。 宮良さんの話を聞いた後に「ひめゆり資料館」を見ると、何が展示されているのかがよく分かりました。資料の中をよく見ると、先ほど宮良さんの話の中で実名があがっていた、死んでいった学友たちの写真が皆展示されているのです。ああ、この人の死に様も、あの人の死に様も、その人の死体が腐っていく様子も、宮良さんはまさに目の前で目撃したんやなぁ…そんなムゴいことってないなぁ…と、つくづく思いました。 午後は、今年8月に米軍の軍用ヘリが墜落した沖縄国際大学へ。 行く前に資料は見ていたのですが、実際に行ってみるとホンマ普通の校舎でした。その辺の小学校・中学校と全く変わらない、町中の住宅密集地の中にある大学です。 そんなトコにヘリが落ちるって…本土の人間には容易には想像できないです。でも、沖縄は東アジア最大のアメリカ軍事基地がある島です。人間のやることですから当然ミスも起こり事故も起きます。つまり、ヘリが落ちるなんていつ起こったって不思議じゃない状況なんですよね。 我々が見学している間にも、頭の上を米軍の戦闘機が飛んでいきました。また沖縄国際大学の屋上から普天間基地が一望できるのですが、それはそれは広大な敷地です。フェンスを挟んだこちら側で住宅が密集しているのに、フェンスのあちら側はほんまに広い。 しかも、その基地は日本人の払った税金で運営されているのです。毎年アメリカに払う「思いやり予算」ってやつです。今の日本は、お金が無くて学校に行きたくても行けない子や、不況でリストラされて自殺する人が毎年何万人もいる国なのに、他国の軍隊にそんな基地を運営するだけのお金を支払い、広大な土地を与えているって、どこをどう考えたら正当化されるんでしょうか?しかも、軍に金を渡すってのは、要するに人殺しに金を渡してるってことです。我々の納めた税金が、人を殺しているのです。 これを言うと、「日本はアメリカに守ってもらってるんだから仕方ない」と言う人がいるんですが…、それは人殺しを他人事と思っている人の、傍観者の意見だなぁと思ってしまいます。その「仕方ない」が、60年前に沖縄の人たちを殺した論理と全く同じだと、私は沖縄戦跡を見、沖縄戦を学ぶ中で痛感したのです。 ついでに極東最大の基地「嘉手納基地」も見ました。頭上を、轟音の戦闘機が飛んでいきました。 沖縄の基地の近くにある学校では、一時間に2度も3度も轟音のために授業が中断されるそうです。学ぶ権利すら侵されてるんやなぁ…。 私は政治家ではありません。一般人です。ですから、金持ちの政治家のリアリティのない傍観論など信用できないし、いち市民として自分の幸せの追求を一番に考えます。 その「市民」の立場を、私は忘れたくありません。だって、私が歌う相手は、大部分が市民なんですから。いち市民として、市民の心に響く歌を歌いたい、それを忘れないようにしたいです。
2004/12/20
-
大いなる学びに その1
なんか久々です。今日は12月23日。 この12月の寒い中を、私は3泊4日の行程で沖縄に行って来ました。そのレポートを、日ごとに追って書き綴ります。 まずは19日から。 「ガマ」って分かりますか?沖縄は珊瑚が隆起してできた島々なので、島のあちこちに自然洞窟があるんですが、沖縄の人たちはそれを「ガマ」と呼ぶのです。 太平洋戦争で日本唯一の「地上戦闘」が行われた沖縄、当時住人達はその「ガマ」へ避難しました。しかし住人だけではなく、日本軍も各地のガマを壕として使用し、戦争末期には住人を追い出して日本軍がガマへ隠れるという、何のために沖縄に行ったんだか分からないような事態まで起こったそうです。 今回の行程では、南部戦跡をいくつもまわったのですが、そのガマの一つ「アブチラガマ(糸数壕)」というところにも行きました。 ここは戦争当時、病院壕として使われたところで、中には井戸やカマドはもちろん、トイレ、ベッドのあった場所、重症患者を寝かせたところ、死体安置(?)所などもありました。 とても狭い入り口を入ると、中はホンマに真っ暗。「黒洞々(こくとうとう)」という表現を体感しました。懐中電灯がなければ絶対に「生きて出ることが出来ない」ほどの闇でした。鍾乳洞でもあるため、足下は湿り、上からは水滴が落ちてきます。 ふと、ガイドさんが照らす懐中電灯の先にあったものは、「歯」…!当時に残された遺骨の一部です。この壕には未だに回収されていない遺骨が眠っているのだとか。 さらに奥に進み、広場でガイドさんが当時の様子を語ってくれます。漆黒の闇の中で、血と汗と涙と膿(ウミ)と便の匂いが充満し、うめき声と叫声と怒号と断末魔が響き、アメリカ軍の投降の呼び声に答えずに手榴弾を投げ込まれて血の海になった中を必死に生き延びた方の話を聞くと、あまりにも悲惨、あまりにもエゲツないその内容に過呼吸を起こす同行者も。 でもそれが戦争の現実。イラクではまさに今、同じコトが行われているのだと思うと、フセインのせいだとか、ビンラディンやアルカイダのせいだとか、テロリストが悪いんだとか、そんな議論以前に、そんな、日本が「しゃあないやん」で済ませていることの向こう側に血みどろの死者達の無念や恨みや悲しみ…が見えてきます。 きっと太平洋戦争当時、アメリカや連合軍側からすれば、沖縄のそんな悲惨きわまりない状態も「しゃぁないやん」で済まされていたことでしょう。 絶対に許せない。 何が許せないか。戦争を肯定したり、「しゃぁないやん」で済ますことが、絶対に許せない。 百聞は一見に如かず。 現地の話を聞き、追体験する中で、その思いを新たにしました。 壕の出口に向かって行くと、天井にドラム缶が張り付いたまま錆びていました。投げ込まれた爆弾の威力で天井に張り付いてしまったのです。人間なんかひとたまりもなかったでしょうね。 人は、自らの痛みを学ぶことでしか、他人を思いはかる心が育たないと思います。日本の被害の歴史を学び、それから加害の歴史を学ぶのも決して遅いことではありません。 これは思想・信条を超えて、我々日本人がもう一度学ばなければならない「事実からの出発」です。 そんな思いを新たにしました。
2004/12/19
-
ありえへん…
人は時として、「ありえへん」死に方をします 具体的にどんな死に方をさしてそう言うかはこの際大した問題ではなく、周りが「えっ!?」「はっ!?」「マジでっ?!」と思わず耳を疑ってしまうような死に方を、ここでは言っています。 …なんか、こんな事書きながら自分自身が混乱しているなぁと思ってしまうのですが、実は先日、90年代を代表するヘヴィメタル・バンドのギタリストが、アメリカでライブ中に撃ち殺されるという事件が起こりました。 90年代とは一般的に、それまでの「華やかなロック」がアメリカ国内の不況とともに否定され、その代わりに「けだるくて暴力的なロック」がリアルな時代を歌っているとして流行した時代とされています(一部では70年代のサイケデリック・ロックの再来とも言われていました)。そのジャンルは「グランジ」と呼ばれ、「ニルヴァーナ」というバンドが始祖と言われます。その後、「オルタナティブ・ロック」というジャンルも流行り、音楽業界は日本も含め、一時「ダル~い…」そのくせいきなり「やたら轟音・爆音!」感じの音楽がトレンドとなりました。それの音に影響を受けたのが日本では「Cooco」だったり、初期の「ブリリアント・グリーン」だったり、一時の「イエローモンキー(「球根」や「So Young」のころ)だったりします。 実はグランジの始祖ニルヴァーナのVo.兼Gt.カート・コバーンも「ありえへん」死に方をした人でした。ジャンキーで躁鬱が激しく、彼はとうとう自らピストルをくわえて自分の頭を撃ち抜いて自殺します。 さて、ここまでは前置き。 先日「ありえへん」死に方をしたのは、そんな「ダルい時代」に危うくツブされかけたハードロック/ヘヴィメタル業界を一笑に付し、自らの音楽を貫くことによってヘヴィメタル再興の道を照らしたバンドのギタリストです。 そのバンドの名は「パンテラ」。殺されたGt.は「ダイムバック・ダレル」です。 アメリカのバンドでありながら、彼らの音は決してパーティ・ロックではありませんでした。90年代の「やたら轟音・爆音」を自らのものとし、時代を象徴する「ダルさ」を「怒号」「暴力的な音」に変えて世の中に叫びました。いくら私がヘヴィメタル好きでも、彼らの創る「殺伐」とした「暴力的」音像はたまらなくシンドいのです。 しかし、音楽的には聴くのがシンドいと思っているにも関わらず、私が彼らをリスペクトするのは、彼らが 1.「時代のトレンド」に決して迎合せず、 2.かといって時代を無視することなく音を吸収し 3.自らの「コレが俺たちだ!」信じる音楽を演り続け、 4.決してファンからそっぽを向かれず、 5.その結果、新しい音楽の流れを創るに至った。というコトです。 その「新しい流れ」とは「ヘヴィロック」と言われ、とにかく「重く」「暗く」「暴力的音像」で「メロディーよりリフ重視」で「殺伐」としているのです。 私はこの新しいトレンドは実はあまり好きではないのですが、あの90年代の悪夢のような「ダルい」トレンドにほとほとウンザリし、しかし多くのバンドがその流行に乗って「ダルく」なっていく中で「トレンドには勝てないんかなぁ…」と絶望的になっていた私に彼らは「自分を信じろ!」「自分の信じる音楽を貫け!」と指し示した、ホント頼れる兄貴達のような存在でした。彼らの存在が私を含め、多くのヘヴィメタル・ファンを励ましたのは間違いありません。 そのパンテラのダイムバック・ダレルが死んだ…!私はある意味、自分の「伝道師」を一人失ったかのようなショックです。 彼らがいたから私は、この日本の今のヒップホップ・ブームなどというトレンドに迎合することのない音楽活動を続けていく心の支えが持てたといっても過言ではありません。(だって、我々の世界はお客あってのものです。弾き語りがすたれ、ヒップホップが流行れば、それを取り入れた方がお客に喜ばれるかも…?なんて弱気にならないとも限りません。もちろんアーティストの中には、ヒップホップを取り入れながら自分たちの新しい可能性を探っている人らもいて、それを否定などしませんが。) しかし、私はヒップホップなど入れたくないのです。魅力あるヒップホップが自分に歌えるとは思えないのです。そんな弱気な私を、精神面で支えてくれたのが「パンテラ」でした。 パンテラはすでに解散し(Vo.が脱退したため)、Vo.だったフィル・アンセルモを除いた3人に、「ハルフォード」というバンドでギターを弾いていたパトリック・ラックマンをVo.に迎えて、新しい「ダメージ・プラン」というバンドで再出発をはかった彼らは、1st.アルバムを出してライブツアーにも出、これからの活躍が期待されていました。 しかしその「ダメージ・プラン」のライブ中に、ダレルは何者かによって射殺され、他のメンバーも怪我をしたとの話です。 おい、アメリカ!なんで「拳銃」という「人殺し」の道具を規制できへんねん!マイケル・ムーアじゃなくたって「おかしい!」って思うぞ! 「護身用」に銃を持たなアカンような国造りすんな! 今回、あらためてアメリカ銃社会に怒りが沸きました。 確かに、「銃社会」が悪いのではなく「犯人」が悪いんだ、という考え方はあります。しかし、国民に銃を持つ権利を与えるなら、言ってみれば「その気になればいつでも人を殺せる」ということですよね。その危険性はナイフ所持なんかとは比べものにならんでしょ。遠くから殺せるんやから。 ほんま、ありえへんわ…くやしいわ… ダイムバック・ダレル氏の冥福を、心よりお祈りいたします…RIP.
2004/12/11
-
やっと落ち着いた
最近、日記を全く更新できませんでした。 というのも、ここのところ仕事が年末にむけて佳境に入っていてずっといっぱいいっぱいの状態、俗に言う「テンパってる」という状態でした(笑)。 しかし、それも先週で一区切りつき、今週からはすこし落ち着いて仕事が出来そうです。 風邪もやっと落ち着いてきました。友人が同じ風邪になってゲホゲホと咳き込んでいるので、きっとうつったんでしょう。うつったから私が治ったのかも…?!ゴメンね。 年末に向け、実はもう一山、大きな仕事が待っているんですが、それは楽しみ半分・心配半分といった感じなので、まぁ何とかなりましょう。 年末に向け、この一年をどう総括するか(もちろん音楽的側面で)、考えましょう。 今年も色々あったなぁ~。このHPを始めたのも一つ、大きなコトです。こんな私の駄文につきあって頂いてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 アンプラのボス、よっつんらが組んでいるバンド「すっからかん」が「社会人バンドコンテスト」に申し込み、見事テープ審査を通過したそうです。おめでとうございます。 何でも、「地球おっさん化計画」なる計画をかかげて(どうやら「温暖化」とかけているらしい…/苦笑)、大会当日には会場に「おっさん化炭素」を充満させるらしい。それを吸えば老いも若きも皆いつのまにか「すっからか~ん すっからか~ん すっからか~んかん」という「すっからかんのテーマ」が頭から離れなくなることうけあい!(笑) 大会の詳しい日程はリンクはっている「よつゆみさんの日記」に書いてあるので、ぜひぜひ皆さんで観に行きましょう! ではでは、今日はこの辺で。PS 先日話題に上った、注目している「CRAFTER」という韓国メーカーのギターを試奏してきました。 音は、…エレアコが前提になって作られてる感じ、かな… 雑誌で見るほどインレイとかが印象的でなかった…残念!でも韓国の寄せ木細工で出来た「山々」のインレイは発想として面白いぞ!今後に期待、斬りィィィィィッ!
2004/12/05
全10件 (10件中 1-10件目)
1