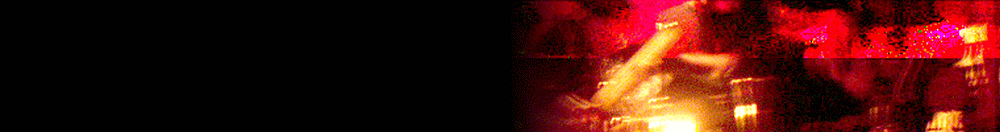2011年01月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
犬のことは人のこと
「犬のことは人のこと」。。。とかつて師匠がおっしゃっていた言葉を思い出す。安楽死の相談が入ったり、噛み犬の処遇について相談が入ったり。。。本当に、「犬のことは人のこと」だ。その犬を作り上げたのは飼い主である人間だからね。人間のことを勉強しないと犬のことは解からない。たかが犬のしつけというだけの仕事なのだけど、この仕事、結構大事な仕事なのかもしれないなと今日は改めて自分がやっている仕事の重さを実感した日。一方では、おやつを持って、「お座り」は、犬の鼻先におやつを持った手を近づけてその手を犬の頭の上やや後方に移動させ犬がおやつを目で追って腰を落としたらご褒美として食べさせる。。。なんてことを言っているトレーナーが居るわけだよね。なんかさぁ、仕事内容から言って全然別の職業っていう気がするんですけど。。。でも、やっぱり「訓練士」つって一括りなんだな。。。爆
Jan 26, 2011
コメント(0)
-
犬と子供
犬と子供と言うのは大人が考えているほどラフな関係では無かったりする。兄弟とか友達とかあるいは兄弟以上の関係だったりする。大人はただペットとして犬を見ているかもしれないけれど、子供は、その犬無くしては自分の世界が成り立たないくらいに犬の存在を大きく考えていたりする。そんなだからね、いくら飼い主だった子供が社会人になって家を出ていたのだとしても年老いた犬があちこち具合が悪くなって安楽死してあげた方が楽なんじゃないかと思っても飼い主だった子供が納得・了解していないのに勝手に安楽死なんかしてしまったりすると親に対して子供が信頼をもてなくなって親子の関係がギクシャクしてしまうことに成るかもしれない危険があるっていうことはよく考えておいた方が良いと思うよ。犬の状態がとても悪くて飼い主だった子供が犬の様子を確認しに戻って来るとまで言っているのだったら戻って確認させて自分でその後のことを決めさせるべきだと思う。犬が自然死するまで子ども自身、仕事をほっぽって付き添っていられるわけではないだろうから子供なりに納得せざるを得ないと思うんだよね。そうなってから、子ども自身が病院に連れて行くなり一緒に付き添っていくなりして飼い主だった子供と犬が最期の別れをちゃんと出来るようにして終わらせるべきだと思う。犬は、最期の最期まで飼い主のことを目で追い飼い主の言葉に耳を傾けているからね。。。
Jan 26, 2011
コメント(0)
-
言葉の使い方
言葉の使い方でその人の人生観が見える。「尊い命」とか「愛情」とか「絆」とかそういう言葉を簡単に使う人は言葉のイメージが持つムードに酔える夢見がちな年頃のまま大人になってしまった人と感じる。それが的をはずしていないと思わせる矛盾だらけのことをやってのけてくれるしね。その手の類は、大して苦労を知らずに育った人だなと思えてあまり信用ならないと私は思う。
Jan 23, 2011
コメント(0)
-
多くを望まない
犬をグレさせてしまう飼い主のお決まりのパターンは自分では大して目新しいことを考えることが出来無い無能さを持ちながら犬には多くを望む飼い主だ。お決まりのパターンをなぞらえるだけで面白みの無い飼い主でありながら相手にはあれやこれやと望みすぎるから犬だってそんな飼い主にうんざりしてしまう。そうなると、犬も得がないことには馬鹿馬鹿しくて動きたくも無くなると言うものだ。相手を変えようとするのではなく自分が変われば相手も影響されて変わる。。。と考えれば相手に望んでばかりいることは大きな間違いだと解かろうというもの。。。相手を変えたければ変えたい度合いに応じてまずは自分が変わらなくてはいけない。そんなことを考えれば、自分を変えることの大変さを知り変わる必要性を自覚している自分でさえ変わることが大変なのにそんな必要性など微塵も感じていない相手に変わるように要求することが如何に間違った馬鹿げた考え方であるかがはっきりすることだろう。自身を変えられない飼い主でありながら犬にはほんといろんなことを望む。そうしたことが如何に自分勝手で思慮の無いことかと思う。
Jan 22, 2011
コメント(0)
-
大事な事
あ、あれって、とっても大事なことだったんだな!?とよそ様のブログから日本と言う国にとってとても大事なヒントが降りてきた。私は犬のしつけを通して自覚が無い多動症状態にある飼い主さんというのにかなりの確率でヒットする。それは、そういう状態にある人は犬と関わったときに犬を壊す傾向が強いから相談にいたるためだろうと思う。かくいう自分も、かつてはそうした飼い主の一人だった。本質的な遺伝とか脳の障害とかによって起きている多動とは異なり日常生活が時間に追われる生活だったりすることで後天的に多動に陥っているだけなのだが、いかんせん、自覚が無く集中力に欠けている自分と言うのに気づかない。そういう飼い主さんがお母さんだったりすると知らずと子供さんにもそうした集中力の欠如や多動状態が起こっていたりする。日々の生活がせかせかと時間に追われ物事の処理がルーティンワークになっていることで頭を働かせなくてもことが進んでしまうといった環境でそうした問題が起き易くなっていたりするためだ。飼い主がせかせかしていることの影響で犬が落ち着きの無い犬精神的な安定度の低い犬が出来上がっている。そうした状況を改善するために犬に「ジッとしていることを義務付ける」というトレーニングを施してもらう様飼い主さんにお話しするのだが、そうして犬に「ジッとしていなさい」というトレーニングを行っているうち飼い主自身、自分が多動であることに自覚が芽生えたりする。それは、犬をジッとさせておくために犬にお付き合いしなくては成らないところそうしたことが苦痛に感じたりすることから自分が多動になっていることに気づかされ、ハッとする。。。といったパターンだったりするのだが、そうして犬のトレーニングを通して飼い主自身の身に起きていた問題に気づくと言うのは飼い主が陥っている危険に警鐘を鳴らすためにその方の犬は、その方のところへやってきたのだなと思えたりする。(余談だがそういう落ち着きの無い犬を肉体を疲労させることで落ち着きを培わせようとすると飼い主自身が多動になっていることも飼い主が犬を破壊していることも気づけないまま問題は犬だったと言うことで片付けられてしまうことになる。)話を元に戻すが、落ち着きの無さだとか集中力の欠如だとかを改善するために行う犬に「ジッとしていることを義務付ける」というトレーニングと言うのは昔、いろんな場面で子供たちに課されていた「正座」と同類のトレーニングと言える。で、犬にそうしたトレーニングを行うにあたり、それにお付き合いしなくてはならない飼い主はまさしく、自ら「正座」を課すことにいたるわけだ。で、その効果は?と言えば、多動に陥っていた自分に気づいたり集中力の欠如が改善されたりする。かつて、日本のいたるところで、「我慢教育」として子供たちに「正座」が課されていたわけだが、いつしか「膝に負担が大きい」とか「我慢」を強いることは精神発達上宜しくないといった理由から、「正座」というものが古く誤った教育方法という位置づけがなされるようになり教育として在った「正座」は「虐待」という位置づけがなされるようになり日本の中から払拭されてしまった。が、今、多動の犬を改善するために人間も「正座」の我慢を自ら課すにいたりそういう機会を設けることは集中力を伸ばすとか多動と言う問題を改善する良い機会であったり自分のそうした問題に気づく機会だったりして、欧米コンプレックスによって虐待視されてしまった「正座」という日本の教育法は身体的にはそういうものだったかもしれないけれど、脳とか精神と言う観点からすればそれはとても大切な内容だったのではないかと犬のしつけから多動に気づかれたと言う生徒さんのブログを見て思った。
Jan 20, 2011
コメント(0)
-
比較
飼い主というのはよく自分の犬を他所の犬と比べたりする。あの子はちゃんとしているのにうちの子は落ち着きが無い。。。とか大抵比較と言うのは自分の犬が他の犬に比べて見劣りしているときにこそ行われやすい。が、比較して、自分の犬より勝っていると判断した犬の飼い主と劣っていると判断した自分の犬の飼い主である自分とを比較しようとしないところがとっても不思議。犬の出来上がり具合と言うのは飼い主の出来上がり具合に比例する。。。っていうそこは見ないところが素晴らしい!
Jan 19, 2011
コメント(0)
-
「頭を使わない飼」い主と、そういう飼い主に育てられた「頭を使えない犬」
頭を使わない(というより「使えない」なのかな?)飼い主は犬には「お散歩」と「運動」という傾向が強いなと思う。別に肉体労働者でもない普通の主婦なのに、なぜか、頭の中は「ドカチン」なの。そういう人に飼われている犬は普段から、頭を使う生活をしていないから犬もやっぱり「ドカチン」で体は筋肉マンなのだけど頭の中は「食欲」だけ。良いか悪いかは別としてそれも一つの飼い方だ。問題は、ドカチンの飼い主のところにホワイトカラータイプの頭脳労働が好きな犬が飼われてしまったりホワイトカラータイプの人間のところにドカチンの犬がやってくることだ。ドカチン飼い主は犬が自分を引っ張りまわしても犬がよその犬に吠え掛かってもそれは犬だからしょうがないと考える。もともと頭を使う作業が嫌いだからそのままそういうものとして受け入れる。よく言えば、鷹揚?寛容?頭の中がドカチンだから力自慢とか周りに牽制かけまくりの喧嘩吹っかけ状態も大して気にならない。不便とも思わず振り回されて自分がスッ転ばされてもそういうもんと思っていたりする。食べ物にウハウハするのも犬だから。。。そんなもんと思っている。犬と暮らすことはお散歩を毎日することだと信じて疑わないしそれだから、律儀なまでに台風が来てても、寒波がきててもお散歩に出る。実に実直だ。一方、ホワイトカラータイプの飼い主は頭使って犬を飼うからお散歩が犬にとって必要なものかどうかをまず考える。考えた結果、必要だと判断すれば何をおいてもそれを実行するし、必要ではないと判断すれば、それをなくしてしまうことに何のためらいも無い。そこに、犬にはお散歩が必要だなどという一般の常識は存在しない。あるのは自分がどう考えたか。。。である。どちらの飼い主であっても犬は順応性が高い動物だし習慣化する動物だからそれなりに生きていられる。
Jan 13, 2011
コメント(0)
-
人の内に潜む「邪」とは?
正しい方向性を正しいと受け入れられない感情や嗜好が優先される我侭さと言い換えることが出来る。問題が解決する方向は問題が解決しない方向より正しいベクトルだというのが一般認識だろうと思う。が、感情や嗜好を優先する人にかかると問題が解決する方向も間違った方向と捉えられたり問題が悪化する方向を正しいと位置づけられる。そういう人にかかっては何が正しいのかの基本が違うところにあるわけでどんな指導者に習っても犬は問題を解決できることには至らない。なぜなら、そういう人がこの人が正しい、この方に習いたいと感じる相手そのものが問題を悪化させる人に他ならないのだから。。。そういう人たちは、良い犬はこういう感じだよと知らされていてもそんな言葉が頭に残らず、いたけだかな生意気な犬の顔や姿が凛々しいとされそういう犬に自分の犬がなって欲しいと願ったりする。要は、やくざをかっこいいと評価する人にいくら律儀で思慮深い犬を説明しても自分が無い軟弱な犬としか見ないということだ。軟弱さの意味をはき違えていることも解らない無知さで我侭さが無い我慢強い犬もそういう人にかかっては「自分の無い犬」という評価が下る。では、そういう頓珍漢な人が考える「自分がある犬」が人間社会で生きるには向かないイヌの本能をバリバリ備えている動物であることについてきちんと考えたことがあるのか?といえばそういう犬が問題を起こすイヌであることにも気づいていなかったりする。問題に振り回されていることを嘆きながらもやくざな犬に成長することを願って問題を強化している原因が自分であることを理解しない。犬は自分が望んだ方向に出来上がっているというとても簡単な理屈がわからない。その頭の悪さを以って、我侭な自分が他者から我慢させられることのストレスの大きさをイヌの身に投影しているためである。犬は我侭な飼い主よりもずっと順応性が高く我慢が我慢ではなく当たり前のことと消化できる動物であることも解っていない。そういう飼い主は飼われている犬の方が性能が上だったりする。
Jan 4, 2011
コメント(2)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
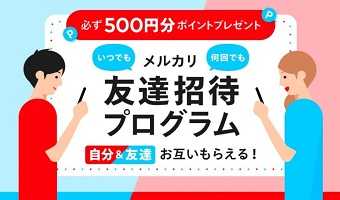
- ポメラニアンとの毎日
- 💝【メルカリ】宛名シール 差出人シ…
- (2024-07-04 08:35:07)
-
-
-

- ゴールデンレトリーバー!
- 【まとめました】大型犬の北海道引っ…
- (2024-09-26 07:44:12)
-
-
-

- 我が家の小鳥
- 天使っちたちの里帰り2025
- (2025-08-16 15:34:32)
-