2024年06月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

映画「グラン・プリ」
「グラン・プリ」 GRAND PRIX(1966)監督 ジョン・フランケンハイマー製作 エドワード・ルイス原案 ロバート・アラン・アーサー脚本 ロバート・アラン・アーサー ウィリアム・ハンリー撮影 ライオネル・リンドン編集 ヘンリー・バーマン、スチュー・リンダー フランク・サンティロ音楽 モーリス・ジャール出演 ジェームズ・ガーナー、イヴ・モンタン、エヴァ・マリー・セイント ブライアン・ベッドフォード、ジェシカ・ウォルター、三船敏郎 アントニオ・サバト、フランソワーズ・アルディ、アドルフォ・チェリ 本編180分 総天然色 シネマスコープサイズ フォーミュラカーが爆走するF1グランプリ・レースに命を懸ける男たちと、彼らを見守る女性たちを描いた映画です。 レースはモンテカルロの公道を走るモナコグランプリから始まり、ベルギー、オランダ、イギリス、イタリアグランプリのモンツァなどを舞台として描かれる。 レーサーのジェームズ・ガーナーとブライアン・ベドフォードが同じBRMチームだったがモナコでの事故でベドフォードが重傷をおい、その原因と責任をとわれたガーナーがチームを追放される。イヴ・モンタンとアントニオ・サバトが同じフェラーリチーム。クビにされたガーナーが三船敏郎が新規参戦した日本のヤムラ(ホンダがモデル)チームに迎えられてレース界に復帰する。 映画は4人のレーサーの、BRMのベドフォード、フェラーリのイヴ・モンタンとアントニオ・サバト、日本のヤムラのガーナーを中心に進みます。 そして、ベドフォードの妻のジェシカ・ウォルターとガーナーとの微妙な関係。モンタンと雑誌記者のエヴァ・マリー・セイントとの恋愛、若いサバトとフランソワーズ・アルディの恋模様などが描かれる。 レース場面の撮影がすばらしく、空撮と車載カメラのドライバー目線による臨場感ある迫力。開巻でのモナコグランプリの市街地を走る描写でまず圧倒され、そのあとは男女の恋愛関係や夫婦の軋轢場面がつづいて、ちょっと退屈気味になってしまった感があるが、クライマックスのイタリアグランプリのデッドヒートと大事故の迫力で盛り返す。 自動車レースを題材にした映画では「栄光のル・マン」(1971)と、この「グラン・プリ」が双璧かと思います。自分としては男女の恋愛ドラマ部分を極力排除してドキュメンタリ調で撮った「栄光のル・マン」の方が好みですが、本作の、現代から見れば古風さを感じるフォーミュラカーの葉巻型デザインに大きな魅力を感じます。事故で火災を生じたときにすばやく脱出できるようにシートベルトは無し。安全性を考慮される以前の型です。 ジェームズ・ガーナーが乗る白いホンダが燃料もれから火災を起こす。その事故現場にむらがって来てカメラに収めようとする奴らを見たイヴ・モンタンが自分のこれまでのレーサー人生に懐疑的になる。 彼らは大事故を期待している。人が死ねば大喜びで、目を輝かしてカメラを向ける。そんな奴らを喜ばすために自分は走っているのか?と。 話が映画からそれますが、事故を期待してレースを見に来る者たちの姿。現在の民放テレビ局の姿勢を連想しました。私は、連日のように悲惨な事故や殺人事件を放送している民放テレビ局のニュース番組にうんざりしています。大事故、殺人事件、大災害のニュース。悲惨であればあるほど彼らは喜々として放送する。 映画のラストで、事故で死んだモンタンの血が着いた両手を掲げてエヴァ・マリー・セイントが「あなたたちはこれが見たいのか!」と絶叫する。「グラン・プリ」の日本公開は1967年2月。私が見たのは金沢ロキシー劇場で1972年6月のリバイバル上映でした。今回は2011年に発売されたブルーレイソフト(1400円で買った)で、約半世紀ぶりの鑑賞です。
2024年06月24日
コメント(0)
-

映画 伊賀の影丸
「伊賀の影丸」(1963 東映京都)監督 小野 登企画 森 義男、安田猛人原作 横山光輝(週刊少年サンデー)脚色 高田宏治撮影 脇 武夫音楽 阿部皓哉出演 松方弘樹、御影京子、山城新伍 吉田義男、北 龍二、高松錦之助 本編69分 モノクロ スタンダードサイズ 東映チャンネルで放送された映画「伊賀の影丸」を録画して鑑賞しました。 1963年(昭和38年)7月に公開された作品。以前に何かで放送された時に見て「なんだこれは?」と思った珍品ですが、今回も同じ印象でした。 横山光輝さんが「週刊少年サンデー」(小学館)に連載していた忍者マンガの同時期の映画化ですが、原作では江戸時代の慶安の頃、公儀隠密の頭領 服部半蔵から密命を受けた影丸たち伊賀忍者が敵の忍者集団と戦う、敵味方がそれぞれの得意とする忍法を駆使して対戦する生き残り合戦を描いたマンガです。 この映画が製作された1963年5月頃?は、マンガでは第二部「由比正雪」連載の終盤から第三部「闇一族」が始まった頃です。 映画は時代設定を変えて、天正10年の本能寺で織田信長が部将 明智光秀の反乱で討たれた直後。 堺を少数の供回りとともに旅行していた徳川家康(北 龍二)が、明智勢に封鎖された街道を避けて伊賀を抜けて浜松へ帰ろうとした時になっています。 冒頭、伊賀の里が甲賀七人衆に襲われて全滅する。百地三太夫の息子 影丸(松方弘樹)が父の遺命によって、徳川家康を守って甲賀七人衆と戦いながら浜松へ送り届けようとする。 原作マンガのような敵味方チームの忍法対戦を描こうとすれば本編69分では足りないだろうが、しかしこの映画は対象観客を誰にしたものなのか? 原作マンガを夢中になって読んでいる少年読者だとすれば、不評を買うのはわかりきったことなのでは? 幼児が対象のような少年合唱団による主題歌。作中に流れる小学校の運動会のような音楽は場面とあわずチグハグ、いかにも幼稚感たっぷり。 原作の第一部「若葉城の秘密」に登場する影丸の宿敵 甲賀七人衆の阿魔野邪鬼を山城新伍さんが気分を出して演じているのが面白いかなと、それだけの作品ではないかと。 時代設定を戦国時代にしたのは、このほうが製作費が安くつくからかも? セットもお手軽なもので、すべて何かの使いまわしで作ったような、低予算映画の見本ですか。
2024年06月13日
コメント(0)
-
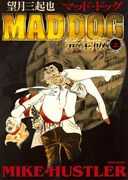
マッドドッグ 第1巻
久しぶりにマンガ本を買いました。「MAD DOG マッドドッグ 完全版 上」(宙出版)全3巻の第1巻。望月三起也さんがマイク・ハスラーの別名で描いた作品です。少年画報社の「ヤングコミック」に1968年~70年まで連載され、ながい間、絶版、幻といわれた作品です。 A5版サイズ、456ページの、紙質は落としてあるみたいだが、分厚くて読み応えのある製本。定価は1528円(税別)とちょっと高めだけど、読みたいと思っていたこともあり、厚くて読み応えあるマンガ本(全19話収録。第11話「可愛い女」は前・後編)が欲しいと思っていた折でもあって、購入した次第です。「ヤングコミック」(少年画報社)が創刊されたのは「ビッグコミック」(小学館)や「プレイコミック」(秋田書店)とおなじ頃で、1968年。当時は月刊だった「ビッグコミック」はわりと買って読んだけれど、「ヤングコミック」と「プレイコミック」を自分で買うのは少なかったように記憶しています。 当時、望月三起也さんといえば、「ケネディ騎士団」「最前線」「秘密探偵JA」など少年誌で読んだ作品しか知らず、似たような絵柄だと思ってもマイク・ハスラーと望月三起也さんが同一人物だとは知らなかった。 アメリカを舞台に、ジョージ・牧という日本人の私立探偵が活躍する、ハードボイルド・コメディ漫画(劇画?)です。 連載時は「狂い犬」というタイトルだったのではないかと思うけど、現在は「MAD DOG マッドドッグ」になっている。ハードなガン・アクションと、お色気のある女性の半裸体がどおんと描かれる。当時の少年誌には不向きで、青年誌が登場した1968年ならではの作品ではないかと。 最近、思うのは、昔のマンガ作品を読むことができないことです。1960年代はむろん、70年代80年代のマンガ本が書店に置いてない。再販されることもなく絶版状態で、たまにマニア向けのがあったりするけど、数千円もする高額のものばかりです。 望月三起也さんだけでなく、松本零士さんのSFや戦記マンガ、水島新司さんの野球マンガにしてもしかり。白土三平、石森章太郎、川崎のぼる、横山光輝さんなど有名作家の作品が書店にないのはなぜだ。ちばてつやさんの「おれは鉄平」や、「愛と誠」(ながやす巧 梶原一騎 原作)など、古本で探すしかないのですかね。
2024年06月10日
コメント(0)
-

映画「獄門島」(1977)
「獄門島」(1977)監督 市川崑製作 田中収、市川崑企画 角川春樹事務所原作 横溝正史脚本 久里子亭撮影 長谷川清美術 村木忍音楽 田辺信一出演 石坂浩二、佐分利信、大原麗子、司葉子 草笛光子、加藤武、東野英治郎、上條恒彦、浅野ゆう子 本編141分 カラー スタンダードサイズ 横溝正史さんの「金田一耕助シリーズ」の映画化作品では、市川崑監督、石坂浩二主演の、1976~1979年にかけて製作された全5作が決定版で、これを凌ぐものは過去にも未来にも存在しないだろうと思います。「犬神家の一族」角川春樹事務所 1976年11月13日全国公開「悪魔の手毬唄」東宝 1977年4月2日公開「獄門島」東宝 1977年8月27日公開「女王蜂」東宝 1978年2月11日公開「病院坂の首縊りの家」東宝 1979年5月26日公開 この5本の映画です。 この度、以前に日本映画専門チャンネルで放送された時に録画してブルーレイにしておいたものを鑑賞しました(ブルーレイ1枚に5作品全部を収録)。「獄門島」は何度も横溝正史さんの小説を読んで、テレビ化された古谷一行さんや片岡鶴太郎さんのを見たりして、すっかりお馴染みな感じで、何回も見たように錯覚していたけれど、意外にも公開時に片町にあった金沢劇場(金劇)で見ていらいの鑑賞かもしれない? 復員船の中で「オレが帰らないと3人の妹が殺される」と言い残して息を引き取った戦友鬼頭千万太の遺言をきいた金田一耕助が獄門島を訪れるのが小説を初め一般的な「獄門島」ですが、この映画では遺言をきいたのは金田一の友人で、その友人から依頼されたことになっています。金田一耕助は戦争に行かなかったのだろうか? この映画が公開されたのは1977年8月27日。直前までテレビの「横溝正史シリーズ」の「獄門島」が全4回で放送されていて、最終回が8月20日。その1週間後の公開です。製作が同じ東宝なので情報のやりとりがあったのだろうか? この映画版「獄門島」は原作との相違がいくつかあり、もっとも大きな違いは犯人が変えられたことです。犯人が異なるというのは公開時の宣伝文句にもあって、横溝正史さんも「私も犯人を知らない」と書いています。この変更された犯人は誰か?というのは、犯人は女性で、有名女優であるのが常識だからすぐに観客にもわかることだけれど。 公開直前まで放送されていた、原作に忠実なテレビドラマと同じ内容で作っても、意味も意外性もないのであえて犯人を変えたのだろうか? しかし、そのために「花子さんを殺したのはあなたですね、和尚さん」のあとで、母と娘が名乗り合い、お涙頂戴ものになってしまった感が出ててしまって、終盤部分が付け足されたようになってしまい、最初から最後までの筋の通った一貫性が失われたのでは? 市川崑監督、石坂浩二主演金田一耕助シリーズ5作品での、個人的な趣味というか感想では、最下位の出来ではないか?と思った「獄門島」です。 でも、現在の日本映画では作りようのない豪華な作品だろうというのは確実に言えるでしょう。了然和尚を演じる佐分利信さんのような重厚な俳優が、現在では皆無です。わき役としても三木のり平さんや大滝秀治さん、小林昭二さん、そして加藤武さんのような味のある人たちのすばらしい演技。 製作費はいくらか知らないけれど、充分な予算と撮影日数、さすが昭和の映画俳優たちがそろった豪華な配役。物語開始時のワクワクする期待感。昔の見ごたえのある映画であることは確かです。
2024年06月05日
コメント(0)
-

片岡千恵蔵の「三つ首塔」
「三つ首塔」(1956)監督 小林恒夫、小沢茂弘原作 横溝正史脚本 比佐芳武撮影 西川庄衛、星島一郎美術 森幹男音楽 仁木他喜雄出演 片岡千恵蔵、高千穂ひづる、三条雅也 中原ひとみ、宇佐美諄、小沢栄、南原伸二、佐々木孝丸 本編88分 モノクロ スタンダードサイズ「三つ首塔」1956年4月26日公開。「三本指の男」(1947)に始まった片岡千恵蔵の金田一耕助シリーズは、この「三つ首塔」が6本目で、最終作となる。この頃になると時代劇映画の製作が再開されていて、片岡千恵蔵は時代劇の方へ活躍の場を戻したようです。 終戦後、映画製作において、GHQ(連合国軍総司令部)により「仇討ちや封建的な忠誠心、愛国心」などを描いてはならないとのお達しがあり、時代劇が作れなくなってしまった。そのために映画会社と時代劇スターたちは新たな路線を開拓しなければならなくなった。 時代劇スターの片岡千恵蔵が主演した現代劇「多羅尾伴内シリーズ」や、この「金田一耕助シリーズ」は時代劇の代替だったんですね。 ある日、文学者 上杉欣吉(宇佐見淳)の屋敷を弁護士の黒川(小沢栄、後の小沢栄太郎)が訪れ、佐竹玄蔵(吉田義夫)という人物がアメリカで事業に成功し巨富の財を築いて亡くなり、遺言で上杉夫妻の養女 宮本音禰(中原ひとみ)に、その全財産を残したと伝える。 相続には条件があり、音禰は高頭俊作という男と結婚しなければならないと。拒否すれば、遺産は血縁者に分配されることになると言う。 数日後、東京会館で行われた上杉欣吉の還暦祝いパーティで高頭俊作と会うことになった音禰は、堀井敬三(南原伸二)と名乗る謎の青年から「俺がいる限り、結婚は出来ない」と声をかけられる。さらにパーティ会場で毒殺事件が起こり・・・。 私は、横溝正史さんの「三つ首塔」はヒロイン宮本音禰を主人公にした冒険小説だと思っています。莫大な遺産を相続することになった彼女の前で連続殺人が起こる。謎の男に犯された音禰は男を恐れながらも魅かれるようになってゆき、殺人容疑者として追われ、男と共に逃避行をつづける。宮本音禰の視点で語られる一人称小説である「三つ首塔」での金田一耕助は物語の終盤での救済者にすぎない。 箱入り娘として大切に育てられたヒロインが、自分が育った世界とは無縁のはずだった「ダークサイド」の世界に墜ちてゆく「冒険小説」。 そんな「三つ首塔」を、片岡千恵蔵のヒーロー、スター映画とするには無理があったのではないだろうか。この映画での音禰はまったくのわき役でしかなく、遺産をめぐっての連続殺人事件を多羅尾伴内か遠山金さんみたいに快刀乱麻を断つように解決するヒーロー映画になってしまい、横溝正史作品らしさが失われてしまっているのでは。 先に見た「三本指の男」と「獄門島 総集編」では、洋装の金田一登場とはいえ、横溝正史作品らしい雰囲気があって、楽しく、面白く見ることができたのに、この「三つ首塔」はただのミステリアクション映画になってしまった感じがします。 片岡千恵蔵さんは「原作者にもうしわけないことをした。金田一耕助は良い恰好しちゃいけないんです。でも当時は着物姿のよれよれ探偵では通用しなかったんです。スマートで格好良くしないとならなかった」というようなことを語っています。
2024年06月04日
コメント(0)
-

片岡千恵蔵の「獄門島」
「獄門島 総集編」(1949)監督松田定次製作マキノ光雄脚本比佐芳武撮影伊藤武夫音楽深井史郎出演 片岡千恵蔵、大友柳太朗、喜多川千鶴 三宅邦子、斎藤達雄、小杉勇、新藤英太郎 本編102分 モノクロ スタンダードサイズ 今年の2月末だったか?ラジオでNHKのニュースを聴いていると、片岡千恵蔵が金田一耕助を演じた「悪魔が来りて笛を吹く」のフィルムが発見されたと言っていました。横溝正史の金田一耕助シリーズを初めて映像化したのが1947年12月に公開された「三本指の男」(原作「本陣殺人事件」)。金田一耕助を片岡千恵蔵が演じ、シリーズ化されて全6作が作られた。第1作「三本指の男」1947年12月9日公開第2作「獄門島」1949年11月20日公開、と「獄門島解明篇」1949年12月5日公開。第3作「八つ墓村」1951年11月2日公開第4作「悪魔が来りて笛を吹く」1954年4月27日公開第5作「犬神家の謎 悪魔は踊る」1954年8月8日公開第6作「三つ首塔」1956年4月25日公開 フィルムが現存するのが「三本指の男」と「獄門島 総集編」、「三つ首塔」の3作だけだったのが、この度あらたに「悪魔が来りて笛を吹く」の16ミリフィルムが見つかった。劇場用映画は36ミリフィルムで撮られるのが通常ですが、16ミリは学校や公民館で開かれる上映会への貸出し用だそうです。 先日、東映チャンネルで放送された「獄門島 総集編」を録画してもらって鑑賞しました。「獄門島」(75分)と「獄門島解明篇」(94分)。それを102分に編集して1950年に再公開されたものです。オリジナル版の方はフィルムが残っていないらしい。 復員船で一緒になった鬼頭千万太が「おれが帰らないと3人の妹たちが殺される。俺のかわりに獄門島へ行ってくれ」と言い残して死んだ、金田一耕助はその獄門島を訪れる。 獄門島では網元の本鬼頭と分鬼頭が対立している。本鬼頭の嘉右衛門、与三松、早苗、三姉妹。分鬼頭の儀兵衛、志保、鵜飼章三。了然和尚、村長、医者の幸庵。駐在の清水巡査、磯川警部など主要人物がそろい、原作から大きくはずれることなく?、ちゃんとした「獄門島」?になっています。「ごくもんとう」ではなく「ごくもんじま」と言ってるのと、三姉妹は殺されるが、俳句の見立て殺人ではないのが特徴。「鶯の身を逆に初音かな」「むざんやな冑の下のきりぎりす」「一つ家に遊女も寝たり萩と月」という其角と芭蕉の俳句が「獄門島」にとって重要アイテムだと思うけど、ビジュアル的にも重要な見立て殺人なのに、それを大胆にもカットしたのはなぜだろう? 大衆娯楽映画に文芸趣味は不要だということか? 金田一耕助のイメージは、1972年の角川映画 市川崑監督・石坂浩二主演の「犬神家の一族」以来、原作どおりの和装スタイルが定着した現代からの視点では、この片岡千恵蔵のダブルのスーツにソフト帽という洋装は奇異に感じるかもしれないけれど、終戦直後のアメリカ統治による新しい民主主義日本の建設といった時代の象徴なのではないだろうか。 それにしても三姉妹の、鬼頭月代、雪枝、花子の狂気を強調した、すさまじいとも言えるような演技。ここまで彼女たちの狂気を観客に感じさせては、殺されても可哀そうだと思わなくなってしまう。あの温厚な早苗さんでさえ「殺したいと思うほど憎んだ」と言う。 鬼頭千万太が復員船で死んだが、分家の一(ひとし)は帰って来た(原作では復員詐欺にあって生きているとだまされ、事件後に戦死が判明した)。それなのに三姉妹が殺され、だけでなく分鬼頭の儀兵衛と志保までが殺される。鬼頭嘉右衛門にとっては邪魔者はすべて消せということなのか。 前作「三本指の男」に続いて、有能な美人秘書 白木静子が登場します。「三本指の男」では東宝からお借りした原節子さん、今作では喜多川千鶴さんが、丸メガネで可愛らしく演じています。
2024年06月03日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ
- 東方神起 キーリング TVXQ! SPECIAL …
- (2025-02-05 00:00:12)
-
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- 【ロボティクスの進化が止まらない】…
- (2025-02-17 14:35:54)
-








