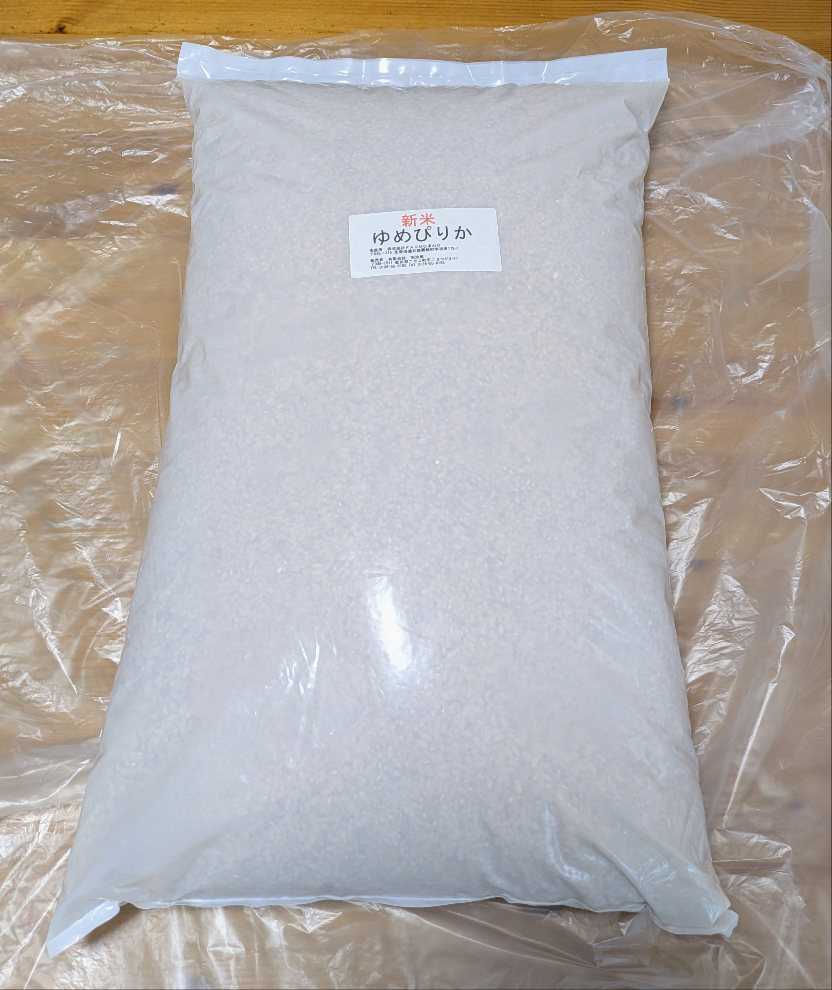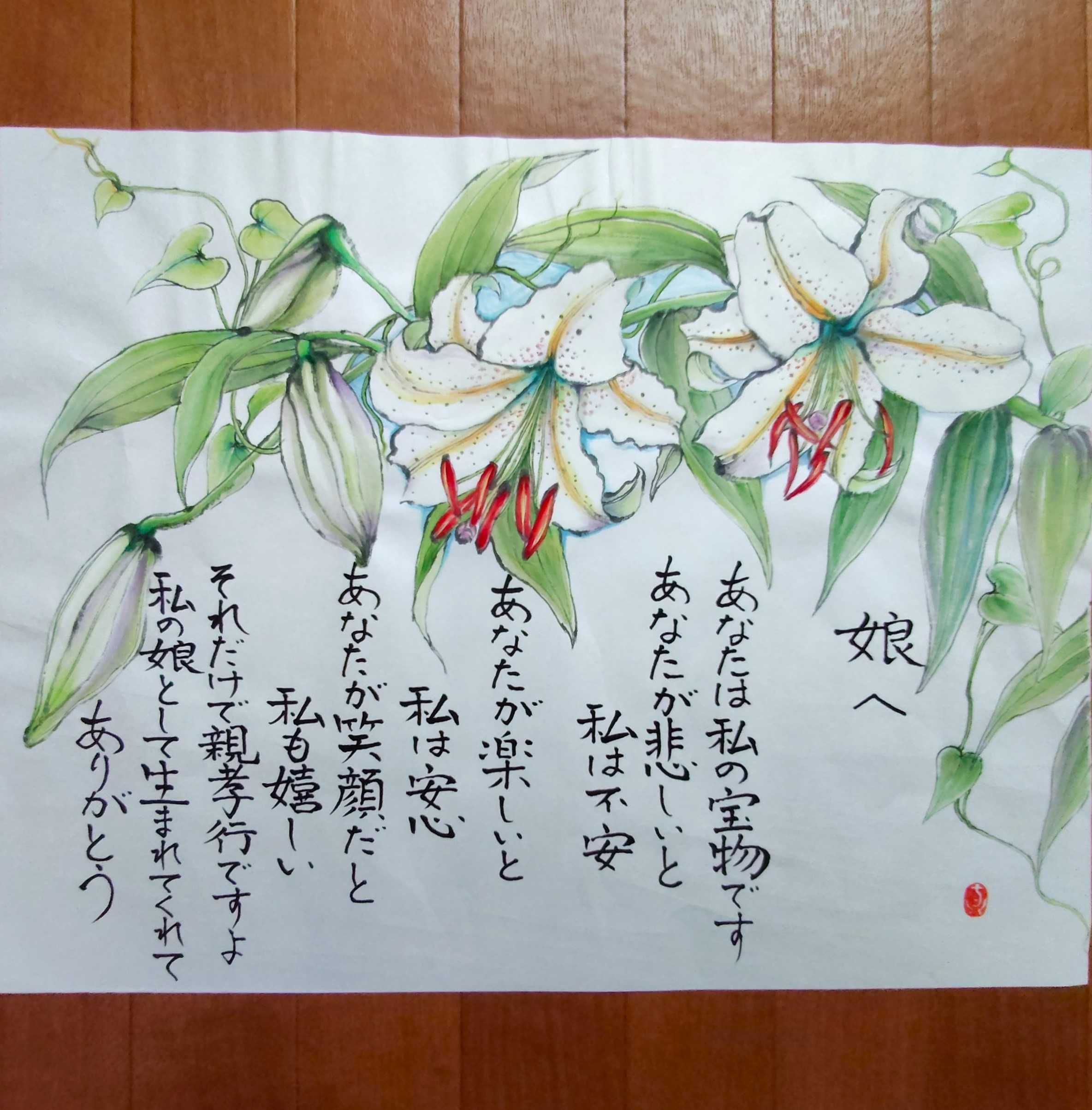2016年02月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-
おじいさん?
今晩は。かなり時代から遅れているようです。携帯は持ってない。当然スマホもない。タップ、フリック?釣り道具?。Skype、LINE、ChatWork、うーーん旨いんか?世の人たちはこういう道具を使いこなしているようです。私は"digital native"ではなくて、"digital naive"でしょうか。
2016.02.29
コメント(0)
-
タイムカードソフト
今晩は。仕事の関係で、パソコンで作業している時間を計測するタイムカードソフトをインストールことになりました。Cというサイトで提供しているタイムカードソフトは、私のWindows 8.1パソコンにはすんなりインストールできました。ただMacのパソコンにはインストールできないケースもあるようです。Lというサイトのタイムカードソフトは、インストールはできましたが、これを使うにはJRE7 Windows x86という昔のJava Runtimeソフトが必要とのことでした。仕方がないので、Oracle Java Archiveを探し、Oracleに自分の身元情報を提供した後、それらしいバージョンのJREをインストールしました。これでちゃんとタイムカードソフトが稼働してくれればいいのですが。個人的な印象ですが、タイムカードソフトにはまだ改善の余地がありそうです。以上
2016.02.29
コメント(0)
-
葬儀の後 (22) 仏具
今晩は。葬儀の後の続き、まだ。熱でぼんやりしながらパソコンに向かっていたら、りーーんりーーん。古い電話の音。弱い声で出ると、仏壇屋さん。仏具を引き取りに来て下さるそうです。この業者さんは葬儀会社と提携しているようで、葬儀の夜にいらして仏具をセッティングし説明してくださいました。申し訳ないことにほとんど頭に残っていなかったことに、後で気づいたのですが。拝借していた段ボール箱を処分していたせいで、おじさん(でも私より若いはず)は、たかつき、おりん、仏様の掛け軸などを手に持ち、神様を封印していた白い紙をはがして帰って行かれました。後には祭壇、提灯、白木の膳、台などが残されました(葬儀会社との契約に応じて、もらえる?仏具と貸与される仏具とがあるようです)。次は春の彼岸、百箇日法要、そして初盆。風邪が治るとありがたいです。今回はここまで。
2016.02.28
コメント(0)
-
葬儀の後 (21) 高額介護サービス費
今晩は。葬儀の後の続き。もう記録しておくことはないだろうと思っていたのですが、今日、市役所から「高額介護サービス費支給---」という郵便物が届いていました。そこで、高額介護サービス費支給制度についてインターネットで検索してみました。-----------高額介護サービス費支給制度:公的介護保険を利用し、自己負担1割(※)の合計の額が、同じ月に一定の上限を超えたとき、申請をすると「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。これは、国の制度に基づき各市町村が実施するもので、個人の所得や世帯の所得に対して上限が異なります。(高額介護サービス費支給制度 【MY介護の広場】: http://www.my-kaigo.com/pub/individual/money/knowledge/koukyou_seido/0401.html-----------故人の場合は、すでに高額介護サービス費支給申請をしていたのですが。その死亡により預金口座は凍結されるので、上記の「払い戻し」ができなくなります。そのため新たな手続きが必要になるようです。この「手続き」は市によって異なるようです。今回はここまで。
2016.02.27
コメント(0)
-
熱、咳、胸痛い
おはようございます。朝から熱があります。咳が出る、胸が痛い、胃腸が弱っている、身体がだるい、というような症状もあります。風邪かインフルエンザのようです。今週の行動を振り返ってみると、22日に別件で医者に行ったので、この時にウィルスをいただいたのかもしれません。経過:2月22日:医者に行く。2月24日:微熱が感じられる。2月25日:熱が上がる。胃腸が弱っている感じ。2月26日:上記に加えて、胸が痛くなる。2月27日:上記に加えて、身体がだるくなる。今年はインフルエンザの流行が遅い、という話も聞きました。丈夫でない方は、人中に出て行くとき注意した方が良いかもしれません。以上
2016.02.26
コメント(0)
-
葬儀の後 (20) 百箇日法要
今晩は。葬儀の後の続き。49日が終わったと思ったら、もうすぐ百箇日法要です。お寺様も親戚の方もはお願いしていません。故人がお彼岸に合せてくれたので、卒塔婆を持って行ってお花とお線香をあげて済ませようと思っていました。が、どうも御膳を用意する必要があるようです。お墓には下手な料理をお供えし、すぐに下げようかと思っています。ハトが汚すので。今回はここまで。
2016.02.26
コメント(0)
-
葬儀の後 (19) 相続登記
今晩は。葬儀の後の続き。故人が家や土地などの不動産を所有していた場合、その登記名義を変更する必要があるかもしれません。当該不動産を管轄する法務局(地方法務局)に電話するか、知り合いの司法書士さんに依頼することになります。法務局(地方法務局)では本人による登記申請について相談窓口を設けているそうなので、手間暇を惜しまない方は自分で相続登記を行うという手もあります。例えば、今回の場合、おそらく以下の書類等が必要になります。1. 被相続人=故人の書類 ・戸籍謄本等 被相続人=故人の出生から死亡まですべてを記載したもの 本籍に変更がある場合は、関係する市区町村すべてに請求する必要があるため、取得に手間がかかります。・被相続人=故人の住民票の除票または、戸籍の附票の除票2. 相続人の方の書類・相続人の戸籍謄本本籍に変更がある場合は、関係する市区町村すべてに請求する必要があるため、取得に手間がかかります。・相続放棄者の相続放棄受理証明書・財産をもらい受ける人の住民票・財産をもらい受ける人の印鑑登録証明書 ・相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)市役所で交付してもらえます。 ・相続する物件の登記簿謄本(不動産の全部事項証明書)・相続関係説明図(戸籍謄本、除籍謄本等の原本還付を受けるため)家計図のようなもの。・司法書士さんなどの代理人に登記手続きを依頼する場合、財産をもらい受ける人=の委任状(認印でよい)上記はあくまでも一例に過ぎません。実際には事例ごとに必要なものが異なります。今回はここまで。
2016.02.26
コメント(0)
-
葬儀の後 (18) 預貯金口座の解約
今晩は。葬儀の後の続き。故人の預貯金口座の解約については、関係する金融機関に問い合わせるとよいでしょう。各金融機関によって対応も必要なものも異なります。必要な書類等としては、例えば次のものがあります。• 解約依頼書(金融機関に備え付けてあります)必要事項を記載し、相続人の印鑑登録した印鑑を押します。• 被相続人=故人の出生から死亡までの戸籍謄本故人の出生から死亡までの戸籍謄本は、取得するのに手間がかかりますので、返却を求めてください。• 相続人の印鑑登録証明書• 相続人の戸籍謄本(必要な場合 = 被相続人の戸籍謄本により、相続人が被相続人の子であることを証明することができない場合)• 相続放棄した人の相続放棄申述受理証明書• 被相続人=故人の預金通帳、キャッシュカード• 相続人の身分証明書(運転免許証や健康保険証)代理人が行う場合は、委任状と代理人の身分証明書• 相続人の印鑑登録した印鑑(印鑑登録証明書に対応するもの)• 被相続人=故人の印鑑(銀行に登録した印鑑?)分からなければ全部持って行くのがよいでしょう。預貯金口座の解約手続きは、金融機関ごとに1件ずつこなして行くほかないので、手間と時間がかかります。今回はここまで。
2016.02.26
コメント(0)
-
葬儀の後 (17) 故人の戸籍謄本
おはようございます。葬儀の後の続きです。故人の財産に関する処分を行おうとする場合、たいてい故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。私の場合、とりあえず故人の死亡時の戸籍のある市役所(またはその支所)に行きました。その際、必要な書類も持って行きました(参考:このブログの「葬儀の後(5)」)。理由を説明して「故人の出生から死亡までの戸籍謄本」のうち、その市役所にあるものをすべて請求しました。得られた戸籍を確認して、ある時期までの故人の戸籍情報が記載されてない場合は、「戸籍謄本郵送交付請求書」を市役所からもらいます。この「請求書」はその前の戸籍情報を保有しているであろう市役所(または市区町村役場)に対して故人の戸籍謄本を郵送で交付してもらうよう請求するために使います。故人の場合は、この戸籍謄本郵送交付請求書が必要になりました。次に前の戸籍情報を保有している市役所に電話をかけて、必要なものを尋ねました。その結果、以下のものが必要であると言われました。 ・戸籍謄本郵送交付請求書 ・定額小為替:3,000円(郵便局で購入) ・本人確認資料(請求者の戸籍謄本のコピーおよび免許証のコピー) ・82円切手を貼った返信用封筒 ・10円切手(必要枚数)* 必要なものは役所によって異なる可能性がありますので、確認した方が良いでしょう。* 実際に使用する定額小為替や10円切手は送付する書類の量によって異なるそうです。使用しなかった定額小為替や10円切手は返送されてきます。定額小為替は郵便局で手数料を支払って換金できるそうです。このように故人が本籍を変更している場合、「故人の出生から死亡までの戸籍謄本」を入手するのは手間がかかります。取得した戸籍謄本は大事に使い回すことが必要です(返却してもらえる場合は返却してもらう)。今回はここまで。
2016.02.25
コメント(0)
-
葬儀の後 (16) 故人の財産
おはようございます。葬儀の後の続き。私は相続放棄をしたので、故人の財産には関係がありませんが。参考までに個人の財産の帰属について若干メモをしておきます。故人の預貯金口座は基本的に解約することになります。これは相続する人が行います。各金融機関によって取扱いが異なるので、故人の預金口座のある金融機関の本支店に問い合わせるのがよいでしょう。故人が家や土地などの不動産を所有していた場合、第三者との法的関係が問題になることも考えられますので、登記名義を変更しておく方がよいかもしれません。これも相続する人が行います。管轄の法務局(地方法務局)に問い合わせるとよいでしょう(裁判所ではありません、念のため)。故人に負債(借金)があった場合、限定承認をしない限り、相続する人が負債も相続することになります。今回はここまで。
2016.02.25
コメント(0)
-
葬儀の後 (15) 四十九日
今晩は。葬儀の後の続き。四十九日法要、実はその前にこの辺りの故人の宗派では、四十九日の前日に「前がんき」(四十九日の前日の看経という意味でしょうか)があります。親戚の方々にまた故人宅に来ていただきました。その翌日、故人宅で四十九日法要を行いました。きれいに掃除したつもりでしたが、漏れがありました。お寺様は玄関からはいらっしゃらず、廊下側から入られるのです。親戚の方が気づいてタオルで水拭きしてくださいました。私もあわてて手伝いましたが。無事に?お寺様にお経をあげていただいた後、お花、お供え、ご位牌などを持ってお墓に向かいました。結構、量がありますので、新聞紙と段ボール箱を2つぐらい用意しておいた方がよいかもしれません。親戚の皆様に車をお願いし、荷物も一部積んでいただきました。が、お墓について忘れ物に気づきました。笠と杖がないのです。仏壇の後ろに置いていたので、忘れたようです。後の車の方が持って来てくださったので、いただいて墓まで疾走しました。お経をあげていただきながら、お骨を納めてもらいました。正面に入れ口があるとは知りませんでした。業者の方を頼んでおいてよかったです。花を供え、線香に火をつけ、御供えを差し上げました(このあたり順番は正確に記憶しておりません)。食べ物はハトが食べるので、持って帰った方がよいと言われていましたが、きれいに忘れていました。気の利く方が段ボール箱に入れて持って帰ってくださいました。その後は予約しておいた近くの割烹で食事。故人の逝去から四十九日まで、周りの方々に助けていただくばかりでした。労力、時間、およびお金もかかります。親戚の皆様も大変だったでしょう。今回はここまで。
2016.02.25
コメント(0)
-
葬儀の後(14) 相続放棄申述受理証明書
今晩は。葬儀の後の続き。相続放棄申述受理証明書の申請について相続放棄に関する回答書を家庭裁判所に郵送してから4、5日後、相続放棄申述受理通知書が送られてきました。これは相続放棄者各人に1通しか来ないので、大切に保管してあります。この通知書に基づいて「相続放棄申述受理証明書」の申請を行いました。この証明書は、例えば相続人が故人の預金口座を解約したり個人が所有していた不動産の登記名義を変更する場合に必要になります。例によって郵送で申請をするつもりでしたので、家裁に電話して必要なものを確認しました。・「相続放棄申述受理証明」の申請書申請書は当該家庭裁判所に備え付けられているのですが、郵送で申請するのでその書類から郵送してもらうのは面倒です。家庭裁判所によってはそのウェブサイトにpdfファイルを掲載しているところもあります。あるいは民間の司法関係者がインターネット上に掲載している書式を利用するという手もあります。私は後者の書類をダウンロードし、家裁の担当者に記載項目を確認してもらいました。当然、ハンコは申述書および回答書に押し、自分で署名しました。・本人の身元を証明する書類運転免許証の写しが好ましいと言われましたが、免許証がない場合は健康保険証の写しでも良いようです。・手数料、申述人一人につき150円の収入印紙。例えば「証明書」を3通申請する場合は、150円 x 3 = 450円の収入印紙が必要になります。・相続放棄者の氏名及び住所を記載し、返信用の切手を貼り付けた返信用の封筒申請書4通までは82円切手で良いようですが、家裁の担当者に確認した方がよいでしょう。* 「相続放棄申述受理証明」の申請をする人や時期に応じて必要な書類などは異なるようなので、必要な場合は家庭裁判所に問い合わせるとよいでしょう。上記の書類などを入れた封筒を家裁宛てに郵送しました。そのまま投函する場合は、82円で送れるかどうか重量を確認した方がよいかもしれません(定型郵便で25グラムまで)。「相続放棄申述受理証明」の申請書を発送してから4、5日後に「相続放棄申述受理証明書」が送られてきました。これで相続放棄者の作業はほぼ終了です。後はこの「証明書」を必要な人に渡すだけです。今回はここまで。
2016.02.25
コメント(0)
-
葬儀の後 (13) 照会書が来た
こんにちは。葬儀の後の続きです。相続放棄申述書を家庭裁判所に送付してから、1、2週間して照会書が家裁から送られてきました。これは相続放棄する人の真意を確認するためのようです。回答書に必要事項を記載し、相続放棄する人が自署し、相続放棄申述書に押したのと同じ認印を押し、書類を完成させ、返送用封筒に入れて投函しました。今回はここまで。
2016.02.24
コメント(0)
-
葬儀の後 (12) 相続放棄申述書
今晩は。葬儀の後の続き。相続放棄申述書の提出私は、家庭裁判所に電話をして必要な書類を確認し、郵送で相続放棄申述書の提出しました。1. 必要な書類は以下のとおりです。1) 相続放棄の申述書 申述書は、全国の家庭裁判所でも配布しています。 家裁のWebサイトからpdfファイルをダウンロードできるところもあります(記載要領も付属しています)。 あるいは他のWebサイトにも掲載されていることがあります。・ 印鑑は認印でよいのですが、その後も回答書や証明書の申請書に同じ印鑑を押さなければならないので、どの印鑑か覚えておいてください。・署名は相続放棄する人がしてください。2) 被相続人の住民票の除票3) 相続放棄する人の戸籍謄本等(抄本は不可です。必ず謄本で取得します。相続放棄する人によって要件が異なりますので、家裁に確認してください。) 上記2.および3.の書類は、相続放棄する人が複数いる場合、個別に提出する必要はありません。・ これら以外にも事案によって必要となる書類があるそうです。相続放棄の申立てにかかる費用 申立人1人につき収入印紙800円分 (収入印紙は郵便局で購入できます。) 連絡用の郵便切手(数百円分。裁判所によって異なるため、申立先の家庭裁判所に直接確認して下さい。) 後々書きますが、収入印紙や切手は、相続放棄申述受理証明書の申請にも必要になります。今回はここまで。
2016.02.24
コメント(0)
-
葬儀の後(11) 相続放棄
今晩は。葬儀の後の続きで、相続放棄の話です。故人には預金と固定資産という財産があり、相続人は複数いました。相続財産を一人の相続人に帰属させるため、私は相続放棄をすることにしました。民法には次のように規定されています。相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条)。条文だけ読むと、家庭裁判所に申述するだけで簡単そうだと思ったのですが、結構手間ががかかりました。大まかな手順は、次のようになります(私は郵送で手続きを行ったので、その手順を記載します)。1. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。2. 家庭裁判所から照会書が送られてきます。3. 回答書を書いて家庭裁判所に送ります。4. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。5. 相続放棄申述受理通知書に基づいて家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を申請します。6. 上記の相続放棄申述受理証明書は、実際に故人の財産を相続する人が、預金の解約や相続による登記に使います。あるいは相続人で相談して遺産分割協議書を作成した方が楽だったかもしれません。いずれにしても「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」、必要に応じて何らかの手続きを行わなければならない、ということは覚えておくとよいでしょう。49日が終わったらすぐに三箇月になりますから。今回はここまで。
2016.02.24
コメント(0)
-
メジロ初見
こんばんは。午前中に近くの田の脇でメジロの群れを見かけました。自分の記録を調べたら2014年には3月6日に初めて見た、と記載されていました。今年は暖かいので早く来たのでしょうか(花の開花が早い?)。ちなみに別の田でヌートリアの子供も見かけました。
2016.02.22
コメント(0)
-
葬儀の後(10)(固定資産税)
おはようございます。葬儀の後の続き。故人が不動産を所有していた場合、固定資産税はどうなるのでしょうか。所有者(故人)が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「相続人代表者指定(変更)届」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。私たちの場合は相続人が複数いたので、市役所から「相続人代表者指定(変更)届」を提出するように求める書類が届きました。届を市役所に提出(送付)すると、その相続人代表者に納税通知書等が送付されることになります。ただし、当然のことながら、固定資産の登記は別途変更する必要があります。今回はここまで。
2016.02.19
コメント(0)
-
葬儀の後(9)(高額医療費)
おはようございます。葬儀の後の続き。故人が高額な医療費を支払っていたときは、高額療養費の払い戻しが受けられます。関係機関から書類が送られてきますので、手続きをするとよいでしょう。今回はここまで。
2016.02.19
コメント(0)
-
葬儀の後(8) (お経)
おはようございます。お経についてこの辺りの私の宗派では、49日まで1週間ごと「おかんき」という儀式をします。これは家族や親戚が集まってお経をあげるものです。前回はお経がまともにあげられなかったので、家族がお経のテープを買ってきてくれました。でもこれは仏壇業者から入手したお経の小冊子とは若干違うものでした。結局、テープに合う情報をインターネットで入手し、ワープロで打ってテープ用の冊子を作りました。またテープとCDラジカセの相性が悪く、テープが絡まるようになったので、改めてお経のCDを買いました。インターネット上にお経のmp4が掲載されていますから、これをダウンロードして利用するという方法も可能かもしれません。今回はここまで。
2016.02.19
コメント(0)
-
ボビー・ワイン(Bobi Wine):ウガンダの歌うあんちゃん
今晩は。YouTubeでボビー・ワイン(Bobi Wine)という歌手の音楽ビデオを見つけました。ウガンダの人です。何を歌っているのかはわかりませんが、ウキウキ身体が動き出すような音楽です。カリブ海辺りの音楽に近いような気もします。ビデオからはウガンダという国の勢いが感じられます。参考まで私の気に入った「カンパラ」、「デンベ」および「パラディソ」のURLを記載しておきます。よろしかったら聞いてみてください。以上--------------参考:カンパラ:Kampala by H E Bobi wine OFFICIAL VIDEO 2015 https://www.youtube.com/watch?v=qQK76i2gptQデンベDembe by H E Bobi Wine official video 2016 https://www.youtube.com/watch?v=7J7b_a2EczEパラディソPARADISO-BOBI WINE https://www.youtube.com/watch?v=shTrm5uPDuE&list=PLXO_O5vRBj-qYnc1y09MkyD2Ar3_As6A9&index=21
2016.02.17
コメント(0)
-
寒い冬でも元気な動物たち
今晩は。たまたま、寒い冬でも元気な動物の写真を見つけました。(Let It Snow! These Pics of Animals Playing Will Warm Your Heart)よろしければ、ご覧になって少し温まってください。ちなみに私のお気に入りは、13番目の雪玉で遊ぶ虎の子です。以上---------参考:Let It Snow! These Pics of Animals Playing Will Warm Your Hearthttp://www.popsugar.com/pets/Animals-Playing-Snow-Pictures-26158986#photo-26158986
2016.02.15
コメント(0)
-
葬儀の後(6) (葬祭費)
こんばんは。葬儀後、市役所に行った日の続き。健康保険から喪主に対して葬祭費が支給される、ということを聞いて、少し喜びながら担当部署に行きました。1. 私の場合は、故人の後期高齢者健康保険証を返却しました。2. 地域の後期高齢者医療広域連合から喪主に対して支給される葬祭費(正式名称は忘れました)の申請手続きを行いました。喪主の通帳及び認印(通帳用の印鑑でなくてよい)などが必要です。申請書に喪主(私)の通帳の番号や記号を記載し、喪主の印鑑を押して、申請書を提出しました。3. 振込希望先が葬儀を行った喪主名義でなかったので、委任状が必要でした。委任状に必要事項を記載し代理人(私)の印鑑を押して提出しました。今回はここまで。
2016.02.13
コメント(0)
-
無料の英語読み物
こんばんは。無料で読める英語の読み物を掲載したサイトを探してみました。・Lit2GoWelcome to Lit2Go ETChttp://etc.usf.edu/lit2go/古典的な名作が著作権フリーで掲載されています。例えば、「不思議の国のアリス」や「オズの魔法使い」・wattpadhttps://www.wattpad.com/home本来は書きたい人や読みたい人のサイトのようですが。私はもっぱら斜め読みをさせてもらっています。当然、著作権フリーではありません。興味のある方はどうぞ。以上
2016.02.13
コメント(0)
-
葬儀の後(7)(年金)
こんばんは。故人の国民年金および厚生年金の関係で、必要書類(葬儀の後(5)を参照)を持って最寄りの年金事務所に行きました。(1) 故人の死亡に関する情報を伝え、各種書類に記入しました。(2) 故人の遺族年金を生存配偶者に受給してもらうのに必要な手続きを行いました。故人の受給していた年金の一部を遺族年金として生存配偶者が受給できる場合がありますが。生存配偶者が厚生年金を受給している場合は、故人の遺族厚生年金と生存配偶者の老齢厚生年金とを比較してどちらかを選択する必要が生じます。年金事務所の担当者がよく説明してくれますので、それに応じて判断すればよいでしょう。今回はここまで。
2016.02.06
コメント(0)
-
葬儀の後(5)
おはようございます。1.初回のおかんきの前だったか後だったか、家族の誰かが、まだ死亡届を出していない、と言い出しました。私も自分で出した記憶がなかったので、あわてて市役所に行きました。しかし、実際には葬儀業者を通じて既に死亡届は提出されていました。2. 死亡診断書の発行後の流れは、次のようになっているようです。(1) 医師の死亡診断書を使って、葬儀業者から市役所に死亡届が提出される。(2) 市役所から火葬許可書が発行される。(3) 市役所では、故人の戸籍、住民登録、印鑑証明などを抹消する。(4) 住基ネットを経由して故人死亡の連絡が、健康保険および公的年金に関連する機関に通知されるらしい。ただし、企業年金関係の機関には連絡されない。3.したがって、故人の死亡後の法的な手続きについては、まず市役所に行って尋ねるのが一番です。市役所では、必要な諸手続きについて情報を提供し、市役所で準備できる書類は、交付してくれます。4. 市役所に出向く前には、次のような書類を準備しておくとよいでしょう。(1) 死亡診断書(2) 故人及び故人の配偶者(生存している場合)の生年月日及び住所などの情報。(3) 代理人(代理人が手続きを代行する場合)の生年月日及び住所などの情報、並びに代理人の身分を証明するもの(例:免許証、健康保険証)、及び代理人の印鑑(4) 返却する書類:故人の健康保険、年金、印鑑登録、マイナンバーに関するもの(5) 喪主の通帳及び認印(通帳用の印鑑でなくてかまいません):健康保険から喪主に対して葬祭費(正式名称は忘れました)がいただけるので、その手続きに必要です。喪主の通帳の番号や記号を申請書に記載し、その印鑑を捺印する必要があります。この手続きは市役所で行います。* (6) 故人の配偶者が生存している場合、配偶者の通帳及び認印(通帳用の印鑑でなくてかまいません):故人の遺族年金を配偶者が受給できる場合は、その手続きのために必要です。この手続きは、年金事務所で行います。今回はここまで。
2016.02.01
コメント(0)
-
葬儀の後(4)
おはようございます。葬儀の後の続き。この辺りの私の宗派では、49日まで1週間ごと「おかんき」という儀式をします。これは家族や親戚が集まってお経をあげるものです。これが結構大変。お茶、お菓子、お土産なども用意する必要があります。家族で分担していろいろ手配しました。初回、お経は仏壇業者からもらった小冊子を利用しましたが、お経など読んだことがなかったのでメロメロでした。今回はここまで。
2016.02.01
コメント(0)
全26件 (26件中 1-26件目)
1