2024年08月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

大河ドラマ『光る君へ』第32回~「誰がために書く」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。いよいよまひろ(吉高由里子さん)が中宮・藤原彰子(見上愛さん)の女房となり、宮仕えが始まったこの回でしたが、個人的にいちばん心に残ったのは、内裏が火事になったときに帝(一条天皇;塩野瑛久さん)が彰子の手を取って一緒に逃げるシーンでした。彰子は打てば響くような返答をする女子ではなく、それどころか弟の頼通からも、ぼんやりした姉上と言われてしまうような女子です。ただ現代でも、男女問わず、ふだんは近くにいても気にも留めない、むしろ意識的に避けているような存在だけど、非常時にその人の意外な内面を知って急に意識する存在に変わった、ということはままあると思います。火事が起こって誰もが我先にと逃げるなか、帝の子(敦康親王)をまず逃がし、自分の安否が確認できるまで待っていた彰子に、帝は「落ちた」と思います。親(藤原道長;柄本佑さん)が藤壺に帝を呼び込もうとあれこれ画策していたけど、それは必要ありませんでした。彰子自身の力(人柄)で帝を引き寄せ、帝にとって形式的ではなく中宮・彰子は心から大事な人だと思わせた流れが見ていて心に残る回でした。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘2年(1005)、帝(一条天皇;塩野瑛久さん)は亡き中宮・定子が遺した脩子内親王(井上明香里ちゃん)の裳着が執り行われました。帝はこの儀式にいまだ公卿に復帰していない藤原伊周を脩子の伯父として儀式に参列させ、さらに伊周を大臣の下で大納言の上に座らせるよう命じたので、公卿たちは内心面白くありませんでした。この帝の伊周への待遇は、裳着で腰結をする左大臣・藤原道長(柄本佑さん)を牽制するためのものでした。脩子の裳着から数日後、道長は土御門殿で漢詩の会を催し、その折に定子の兄弟の藤原伊周と藤原隆家も招きました。会が終わった後で藤原斉信(金田哲さん)は伊周の態度をけなげだと評しましたが、藤原公任(町田啓太さん)は、あれは心の内とは裏腹だろうと考えていました。藤原行成(渡辺大知さん)も公任と同じ意見で、ただ帝がひいきする政敵の伊周を受け入れる道長の度量の広さに感心するのは3人とも同じ意見でした。しかし帝が伊周を重用したい気持ちはますます強くなっていき、伊周を陣定に復帰させたいから公卿たちを説き伏せるよう、道兼に強く要求しました。道長が帝にまひろ(吉高由里子さん)が書いた物語の感想を聞いたところ、帝は読むのを忘れていたと言い、道長はそれを気に入らなかったのだととらえました。そのことを伝えるために道長がまひろの家を訪れたところ、まひろは力が及ばなかったことを道長に詫びつつも、全く落胆していませんでした。まひろにとってその物語は帝のために書き始めたものだったけど、今では自分が書きたいと思うことを書き進めることだけが楽しみになっていたからでした。道長はそんなまひろを理解しつつも、楽しそうに一心に筆を進めるまひろを見て、自分が惚れた女はこのような女だったのかと、しみじみと感じました。少し前に藤原公任は辞表を出していて、帝は公任に翻意を促すため従二位に昇進させたのですが、これは藤原実資(秋山竜次さん)の考えた作戦でした。公任が実資に礼を言っていると藤原斉信がそこに来て、これはごね得ではないかと嫌味を言いました。実資は斉信の機嫌は気にせず、公任と二人で「(公任)従二位、(斉信)従二位、(自分は)正二位」と何度も言って、笑い合っていました。道長の娘で中宮の藤原彰子(見上愛さん)は、亡き定子が遺した敦康親王(池田旭陽くん)を自分のもとで養育していました。この日は道長が敦康のご機嫌伺いで遊び道具を持って藤壺を訪れ、敦康も遊びが気に入って楽しもうと思っていたのですが、突然の帝のお渡りがありました。敦康はちょうど書の稽古の時間で退席となり、道長も退席しようとしたところ、帝が道長を呼び止めました。まひろが書いた物語をようやく読んだ帝は、物語を書いた者のことが気になって、道長にその人物のことを訊ねました。道長がまひろのことを説明すると帝もおぼろげながら記憶にあり、物語に感じる書き手の博学ぶりをたいそう評価していました。帝が物語の続きを読みたい、その後で書き手の女に会ってみたいと所望したので、道長はすぐにまひろの家に向かいました。まひろの家に着いた道長はやにわに「中宮の女房にならぬか」とまひろに言いだし、まひろはわけがわかりませんでした。その後で道長は順を追って、帝があの物語に興味を持って続きを読みたいと所望した、帝は博学なまひろ自身にも興味を持っている、なにより(道長の娘)中宮・彰子のために宮仕えをしてほしい、と要望しました。道長はまひろは帝を藤壺に呼ぶためのおとりだと包み隠さずに言い、娘の賢子と離れたくなければ女童として召し抱える、と言い去っていきました。道長は嫡妻の源倫子(黒木華さん)にまひろのことを話し、道長の考えに倫子も賛成し、夫婦で共に「これが最後の賭け」と腹をくくりました。(一時は彰子のことで関係がギクシャクした二人でしたが、今回は彰子のことで考えが一致し、再び協力体制になりました。)道長から言われた宮仕えの件をどうしたらいいか、まひろは父・藤原為時(岸谷五朗さん)に相談しました。まひろの中では、もう自分が藤壺に上がって働くしかないと考えがまとまっていて、そのことに対しては為時はまだまだ自分だって働けると言いました。しかしまひろが帝の覚えがめでたいというのは悪いことではないと言いました。それでもまひろは賢子のことが気がかりでした。娘・まひろの思いを察した為時は、賢子は宮中ではやっていけない、自分といとが面倒をみる、母を誇りに思う娘に育てるから任せておけ、とまひろに助言しました。しかし賢子は母の事情を簡単には納得できませんでした。(子供の直感で、母は仕方なく働くというより、仕事をしたくてたまらないのだと賢子は感じたと思います。)秋になり、道長のもとに陰陽師の安倍晴明(ユースケ・サンタマリアさん)が危篤という報が入り、道長は急いで見舞いに駆けつけました。晴明は道長に、ようやく光を手に入れられた、これで中宮も盤石、いずれ道長の家から帝も中宮も関白も出る、父・兼家の願いを成し得る、と言いました。しかし続けて、光が強ければ闇が濃くなるからそれだけは忘れないようにと道長に念を押しました。そして「呪詛も祈祷も人の心のありようだから、陰陽師の自分が何もしなくても人の心は勝手に震える。」と忠言しました。最後に晴明は、何も恐れず思いのままにやればいいと道長に助言、晴明との今生の別れを悟った道長は「長い間、世話になった。」と言葉を送り、去っていきました。その後、晴明は自らの予言どおり、この世での命を終えました。一方、伊周を重用したい帝は伊周を陣定に召し出す宣旨を下し、このことは他の公卿たちの大きな反発を招き、何か不吉なことが起きるのではと皆で噂しました。その夜、皆既月食が起き、人々は闇を恐れて内裏は静まり返りました。そして月食が終わる頃、温明殿と稜綺殿の間から火の手があがり、火は瞬く間に内裏に燃え広がっていきました。誰もが逃げ惑う中、帝は我が子・敦康親王の安否が気がかりで、炎の中を中宮・彰子がいる藤壺に駆けつけました。するとそこには彰子だけが立っていて、敦康はもう逃がした、自分は帝の安否が心配でここで待っていた、と帝に言いました。火の手が回って一刻の猶予もない中、帝は彰子の手を取り、彰子をいたわりつつ炎の内裏から共に逃げていきました。翌朝、火事は鎮火したのですが、災いを恐れる人々は内裏への出仕を嫌がり、帝の傍にいるべき蔵人たちや中宮の傍にいるべき女房たちはいませんでした。東宮の居貞親王は「月食の夜の火事は帝の政に対する天の怒り、天が帝に退位を促している」と捉え、道長は反論しますが居貞親王は自分の考えに間違いないと思い込んでいました。その道長は中宮を救ってくれたことの礼を帝に何度も言うので帝はうるさく思い、また伊周は伊周で自分こそが帝の忠臣であると帝に強く訴え、帝はうるさい臣下たちに疲れてしまいました。そして行成が敦康親王の別当として道長に進言していたとき、藤原隆家(竜星涼さん)が突然やってきて話に割り込み、道長への忠義を熱く語り始めました。行成はそれを隆家が道長を取り込むための方便だろうと言うので隆家は思わずカッとなり、危うく殴り合いになるところでした。道長に下がるよう命じられた行成は、強い腹立ちを隠せませんでした。年が明け、いよいよまひろが宮仕えに出立する日がきました。父・為時は、帝に認められて中宮に仕えるまひろは我が家の誇りであると言い、まひろは賢子のことを父といとに頼みました。「身の丈のありったけを尽くして素晴らしい物語を書き、帝と中宮様のお役に立てるように。お前が・・女子であってよかった。」幼い頃から幾度となく「男子であったら」と父に言われてきたまひろにとって、初めて女子であることを良かったと言ってもらえた瞬間でした。そして内裏に入ったまひろを待っていたのは、いかにも気位が高くて気難しいのがわかる先輩女房たちでした。
August 27, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第31回~「月の下で」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。今年の新年から『源氏物語』を題材にしてスタートしたこのドラマが、8月の後半でようやく「いづれの御時にか、女御、更衣あまたさぶらひ たまひけるなかに」 が出てきました。しかもドラマのラストで、まさに キタ━━d(。>∀
August 21, 2024
-

あいち航空ミュージアム に行ってきました
先月の末、大阪に住む姪っ子が子供たちを連れてこちらに帰省していました。姪っ子たちは年に2・3回こちらに来るのだけど、互いの都合でなかなか会うことはできませんでした。でも今回はなんとか都合を合わせられたので皆で一緒にどこかへ行こうということに。そこで私が午前中の仕事を終えてから駅で合流し、私の車で移動して県営名古屋空港のところにある あいち航空ミュージアム に行ってきました。合流して、まずは隣接するエアポートウオーク名古屋のフードコートで食事を。食後は建物がつながっている2階からあいち航空ミュージアムに入りました。中にはいるとまず、航空史に名を残した100機の模型が1/25スケールで精密に作られたものが展示されています。こちらはジャンボ機で、ケース外の展示です。これも1/25スケールです。2階から下を見たら、ブルーの色がきれいな大きいヘリコプターがありました。子供たちの父親は警察官なので、先頭の警察マークを見つけてテンション急上昇♪航空機のエンジンその他、各種部品の紹介です。展示されているヘリコプターの各部の名称の説明板もあります。現・三菱重工業株式会社の小牧南工場で開発され、昭和53年に名古屋空港で初飛行したビジネスジェット機のMU-300です。私たちが行ったときは機内を見学できませんでしたが、ステップがあるということは、曜日や時間によっては見学できるのかな?先ほど2階から眺めた、警視庁が使っていた多用途ヘリコプターEH-101です。こちらは随時、機内を見学できるようです。航空自衛隊でアクロバット飛行をする中等練習機T-4。大人から子供まで大人気のブルーインパルスなので、展示されているのを子供たちもすぐに見つけ、顔出しパネルで記念写真を撮りました。この後、子供たちは夏休みの宿題も兼ねて、2階のサイエンスラボでの工作教室に入ったので、私は30分間、館内をゆっくりと見て回りました。こちらは中型輸送機のYSー11で、昭和37年8月から飛行を開始しました。平成18年に退役しましたが、自衛隊では現在も働いています。こちらは零戦の実物大模型です。2013年に公開された映画『永遠の0』の撮影にも使用されたとありました。この後、工作教室が終わった皆と合流し、お土産屋さんで買い物を。それから帰ろうと思ったのですが、子供たちがエアポートウオーク内で見たある場所に「どうしても行きたい!」と。彼らが一番気に入ったのは、結局エアポートウオーク3階にあるウルトラアスレチック(有料)のコーナーでした。今回は時間の都合もあったので、遊んだは30分コースで。もっとアスレチックで遊びたかっただろうけど、それはまた次回のお楽しみということでヨロシク。
August 13, 2024
-

大河ドラマ『光る君へ』第30回~「つながる言の葉」
2024年NHK大河ドラマ 『光る君へ』 の感想です。今回は全体的に、前回よりも「母」としての在り方や生き方を、登場人物を通して見ていました。中宮であり、帝の子を養育までしているのに、目の前にいても帝の気を引くことができない娘の彰子をなんとかしなければと心を砕くあまり、源倫子(黒木華さん)はやや暴走気味になってしまいました。一方、まひろ(吉高由里子さん)は娘の賢子(福元愛悠ちゃん)の教育や自分が集中したい執筆活動では賢子とうまく波長が合わず、悩みの種になっていました。ただまひろ自身は、幼い頃から母(ちやは)から学問を厳しく言われていたわけではなく、学問好きなまひろは自ら進んで学んでいました。また今行っている執筆活動も、ある部分は生活のためでもあるけど、ほとんどは自分が好きで物語を書いているに過ぎないし、母・ちやはとは突然の別れがくるまでは、母は常に自分の傍にいる存在だったでしょう。だから学問を好まない娘・賢子の気持ちや、母が家にいても傍にいられない賢子の気持ちは、反対の生き方をしてきたまひろにはわからないことだと思います。賢子が起こした火事騒ぎで、まひろは自分の気持ちをどう処理したらいいのか、ずっと考えていたようでした。ただ思ったのですが、賢子が今まで書きためたものを燃やしてしまったが故に、まひろは逆にイチから構想を練り直して新しい物語を書き始め、もしかしたらそれが『源氏物語』になるのではないかと。今までの努力がある事で台無しになった。でもそれ故に、いっそのこと全部やり直すことになり、それが想定外に評判となった。そんな『塞翁が馬』のような展開になるのでは?とこの先を想像しています。RekiShock(レキショック)先生の情報です干ばつが起こった頃(1004年7月頃)登場人物の年齢(満年齢) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #光る君へ 寛弘元年(1004)夏、都は大干ばつに襲われ、大地は干上がって作物は育たず、わずかな水を求めて人々が奪い合いをする有様でした。人々はこのまま日照りが続けば渇き死にをするだろうと覚悟し、僧侶だけでなく民も天に向かって雨乞いをしましたが、雨は一向に降りませんでした。事態の深刻さを憂いた左大臣・藤原道長は陰陽師の安倍晴明(ユースケ・サンタマリアさん)に、自分の寿命10年分と引き換えに雨乞いの祈祷を頼みました。83歳の晴明にとって命がけとなる祈祷が功を奏したのか、都の空に急に黒雲がわきだして、ようやく大雨が降り始めました。人々は歓喜の声をあげ、桶や甕を手に手に外に出て雨水を集め始めました。雨は渇ききった大地と人々の体にどんどんしみ込んでいきました。*晴明神社さんより資料が出ています1004(寛弘元)年、晴明公は干ばつを回避すべく雨降らしの儀式『五龍祭』を行い、見事大雨を降らせた。晴明公はこの功績で朝廷から従四位下という陰陽師として異例の位を褒美として頂戴した。 ⇒ ⇒ こちら この頃、ききょう(清少納言)が藤原伊周(三浦翔平さん)に託して本となった『枕草子』が宮中で評判となり、貴族たちの間で広まっていきました。ききょうが亡き中宮・定子がいた頃の輝かしい日々をつづったこの本を読むと帝(一条天皇;塩野瑛久さん)は定子がそこにいるような気持ちになるとたいそう喜び、定子の兄で一族の権勢を取り戻したい伊周は、帝が定子だけを思い続けるように何かとけしかけていました。定子の弟の藤原隆家(竜星涼さん)は兄のやることと帝の様子を見ていましたが、賛同する気にはなれませんでした。一方、まひろ(吉高由里子さん)は、藤原公任の妻・敏子(柳生みゆさん)のいる四条宮で、6日に一度、女房たちに和歌を教えていました。まひろが和歌の心得や意味を説いていると、暑くてたまらないからと薄着をしたあかね(後の和泉式部;泉里香さん)が入ってきました。敏子はあかねの姿をはしたないとたしなめますが、敦道親王と恋仲で思うままに生きるあかねは気にしてませんでした。またあかねは親王からもらったという『枕草子』の写本をまひろに見せ、宮中で評判ではあるけど自分は好きではないと、率直な感想も述べました。すると敏子が続けて、まひろが書く物語のほうが面白いと言ってくれ、その後はあかねも交えて学びの会が続けられました。姉の定子を今でも強く思う帝に取り入って家の再興を図ろうとする兄・伊周とは違って、弟の隆家は左大臣・藤原道長(柄本佑さん)に付くと決めていました。隆家は時折り道長のもとにふらりとやってきて自分の思うところをあれこれと話し、帝に対しても姉との過去よりも未来を見て欲しいと考えていました。隆家に対して多少の警戒心を持つ藤原行成(渡辺大知さん)は道長に、隆家をあまり信じないほうがよいと進言します。でも道長は、疑心暗鬼は人の目を曇らせる、とほとんど気にしてませんでした。(後世の歴史を知っている私たちは、隆家がやがて大活躍をして道長を助ける、とわかっているから落ち着いて視聴できます。でもそうじゃなかったら行成と同じく、隆家に疑いを持ってしまうかもしれませんね。)帝は亡き定子が遺した敦康親王(池田旭陽くん)を養育する中宮・藤原彰子(見上愛さん)のいる藤壺を時折り訪ねてはいましたが、定子のことしか頭にない帝は我が子の敦康と遊んで成長を見守るだけで、現・后である彰子のほうはほとんど見ようとしませんでした。源倫子(黒木華さん)は娘の彰子がいつも寂しそうで不憫でなりませんでした。(でも、幼い頃から母代わりとなって自分を育ててくれた人(彰子)への思いは敦康の中で特別なものになっていると想像します。なので後でこの敦康が彰子のために何かしてくれそうな予感がします。)ある日、まひろが四条宮での勉強会を終えて帰ろうとすると、あかねが半ベソをかきながらフラフラと廊下の向こうから歩いてきて、酒に酔ってもう倒れそうだったので、とりあえず場所を移して座らせました。あかねが親王と喧嘩でもしたのかと思ったら実はそうで、親王が自分の浮気を疑ったとか、あかねの痴話喧嘩の愚痴をまひろは聞いてやっていました。でもあかねの話を聞いていると、思うままに行動して思うままに自分を語れるあかねが、まひろはどこか羨ましくなりました。さて、左大臣・道長の嫡男・藤原頼通(大野遥斗くん)の教育係の仕事を最初は断った藤原為時(岸谷五朗さん)でしたが、後で娘のまひろに叱られ、家人を養っていくためにも有難く引き受けることになりました。頼通は名門の子弟らしい、賢さに加え師の教えに素直に従い真面目に努力する生徒で、為時もその聡明さを絶賛し、道長も上機嫌でした。そんな時、妻の倫子が帝に謁見した際に、どうか彰子のことを帝から気にかけてやって欲しいと直訴してしまいました。予想外の倫子の行動に道長は驚き、後で倫子をたしなめました。でも「ただ待っているよりはいい」というのが倫子の考えで、道長と倫子の間に溝ができてしまいました。(「ただ待つのではなく自分から」ーーこれは倫子が道長と最初に結ばれたときもそうでしたね。)『枕草子』が宮中で話題になっていることもあって帝の気持ちは亡き定子から離れない、娘の中宮・彰子は帝に一向に振り向いてもらえない、妻の倫子とも夫婦仲がおかしくなって、道長はたまらず陰陽師の晴明に相談しました。晴明は、今の道長は確かに闇の中、でも待って闇を乗り越えれば、いずれ必ず煌々と光が道長を照らす、と言いました。そして道長の顔を見て、今心の中に浮かんでいる人に会いに行け、それこそが道長を照らす光になる、と言いました。ある時の宴にて、道長は若い頃から学問や芸事を競い合い、宮中での仕事を共にしてきた藤原公任(町田啓太さん)、藤原斉信(金田哲さん)、藤原行成らと久しぶりに互いに思うことを語り合う場がありました。昔から道長を見ている3人は、道長が公卿の最高位の左大臣となって娘を中宮にした今でも、思いのほか苦労をしていることを察していました。そこで事態をなんとか打破するために、行成が帝が好む書物があればと言うと、道長はそのような書物を書く者がいるのかと。すると公任が、自分の妻・敏子が行う学びの会で面白い物語を書く女がいると言い、それは(実は道長の思い人の)まひろのことでした。物語を書くようになってからというもの、まひろは執筆に集中しているときは娘の賢子(福元愛悠ちゃん)が何か要求してもすぐに応じられず「後でね」と言うことが多くなりました。母との時間が過ごせず面白くない苛立ちが募った賢子はある晩、母が席を外した隙に母が書いている書に火をつけ、火事騒ぎを起こしてしまいました。火をつけるなど人のやることではない!とまひろは賢子を厳しく𠮟りつけました。傍らで(自分を甘やかす)祖父・為時がかばってくれるけど、母の真剣な怒りに賢子は悪い事をしてしまったと悟り、泣きながら謝りました。翌日、まひろは物語を書き直していましたが、昨夜の衝撃があまりにも大きくて執筆に集中できませんでした。そんな時に道長がまひろの家まで自ら足を運んで訪ねてきました。
August 6, 2024
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
-

- トイプードル大好き
- 犬の体内時計は正確です
- (2025-01-30 09:30:27)
-
-
-

- 猫の里親を求めています。
- *みにゃさんの愛、募集ちぅ-2024年3…
- (2025-01-30 00:32:44)
-
-
-
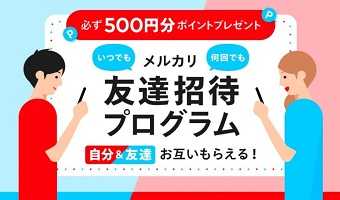
- ポメラニアンとの毎日
- 💝【メルカリ】宛名シール 差出人シ…
- (2024-07-04 08:35:07)
-







