2025年02月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第8回~「逆襲の『金々先生』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は随所で、横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎の、花の井改め瀬川(小芝風花さん)への本人も意識していない思いを感じた回でした。 瀬川の方は重三郎への思いを、ストレートには絶対言わないけど、それらしい言葉は出ていて、重三郎が気がつかないだけで平賀源内(安田顕さん)のようにちゃんと察している人もいます。でも重三郎は自分じゃわかっていないけど、彼の場合ちゃんと行動に出ているんですよね。例えば同じように辛い思いをしている女郎をなんとかしてやりたいと思った時、他の女郎たちにはまず頭で、つまり理性で打開策を考えます。でも松葉屋で瀬川が大変な思いをしていると知った時、重三郎は考えることなくとっさに感情的に言葉が出て身体が動きました。松葉屋の人たちは、今日の重三郎は何か変だとか、あるいは薄々気がついているかもしれませんが。あと鳥山検校(市原隼人さん)という、実に興味深い人物が出てきました。彼は盲の特権を活かして資産形成では大成功しました。そして苦労人ゆえの気配りか、あるいは目が見えないことでの自分への卑下か、自分のせいで瀬川が退屈をしないようにと女性が喜ぶプレゼントを持参します。物腰も柔らかく、花魁に対して敬語で接します。そんな鳥山の優しさに瀬川は「声」で応えました。鳥山にとっては、自分流の心遣いを瀬川がただ喜んでくれたらいいと期待してなかっただろうけど、それが思いがけないお返しがだったと思います。これは瀬川の優しさに、惚れちゃいましたね。さて、今回の中に出てきた小道具についての書き込みがあったので、ご紹介します。*【印刷博物館】~当館が所蔵しているのは復刻版となりますが、『金々先生榮花夢 上・下』をご紹介します。 ⇒ ⇒ こちら *【#大河べらぼう 公式】~『女重宝記』とは ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 地本問屋への仲間入りを賭けて蔦屋重三郎(横浜流星さん)が挑んだ𠮷原細見の「籬の花」の販売は、重三郎の狙いどおり飛ぶように売れていきました。そして重三郎の問屋仲間入りをなんとかして阻止したい西村屋与八は自分たちも「新𠮷原細見」と称する本を出して、町で華々しく宣伝していました。するとそこへ重三郎たちが鳴り物入りで賑やかにやってきて、人々に西村屋の細見を模した箱を見せたかと思うとそれを西村屋の前で二つに割り、自分たちの細見を模したものを大々的に宣伝しました。さらに「瀬川襲名」のことも強調し、町の人々はこぞって重三郎のを求めました。(このシーン、最初は重三郎もわざわざ西村屋の怒りを買うこともないのに、と思ったけど、重三郎は先にこの人に嵌められているから、まあ仕方ないですね。)重三郎が出した細見「籬の花」は人々の評判も良く2倍以上の売れ行きとなり、𠮷原は押し寄せる人々で大賑わいとなりました。𠮷原に来た人々は五代目・瀬川(花の井 改め;小芝風花さん)を一目見ようと花魁道中に押し寄せ、その姿に酔いました。また重三郎は駿河屋の軒先に本屋の屋号として「耕書堂」の名を掲げ、𠮷原の女郎屋の親父衆たちからも本屋の主として認めてもらえました。親父衆も重三郎が一人前となったことを喜んでくれました。その賑わう𠮷原に、やはり“瀬川”のことが気になった平賀源内(安田顕さん)が小田新之助(井之脇海さん)を伴って来ていました。重三郎は瀬川は花の井が襲名したと二人に明かし、源内が会えるよう手配しようとしたのですが、あいにく瀬川は大忙し。うつせみは新之助に会いたがっていましたが、やはり忙しくて落ち着かないのでまた今度となりました。こんなにも𠮷原の町が賑わうのは花の井が瀬川を背負ってくれたからで、自分の作った細見の力ではない、花の井には深く感謝している、どうすれば花の井に報いることができるか、と重三郎は源内に思いを語りました。瀬川が本心は重三郎が好きなんだとわかっている源内は、重三郎に瀬川を身請けしろと言いますが、瀬川の身請け金などとても払えるものではありません。さらに𠮷原の男は女郎には絶対に手を出してはいけないと叩き込まれていると重三郎が説明をすると、瀬川の気持ちを思う源内は虚しさを感じました。さて田沼意次(渡辺謙さん)の方ですが、こちらはしきたりがうるさく無駄な金もかかる社参の支度に追われていて、気分がすぐれませんでした。すると源内が、吉原で瀬川襲名があってその花魁道中を一目見ようと人々が大勢集まり吉原が繁盛している、不躾ながら将軍の道中も民草にはよい見物なのでは?と意次に進言しました。意次がすぐに「社参を見世物にして金を得る場にせよと?」と気がついたので、源内は続けて「これを機に宿場の商いを盛り立てるのはたやすい。かつその銭の出入りを上手く使えば二朱銀への置き換えも進められる。」と進言しました。今まで苦々しく思っていた社参が、逆に経済の発展に利用できるのだと理解した意次は何かを考え始めました。重三郎が松葉屋に本を持っていったとき、ただでさえ忙しい瀬川が面倒な客のために疲れてまだ寝ていると聞き、重三郎は思わず主人の松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)や女将に、そんな客をつけないよう文句を言ってしまいました。それを聞いた松の井(久保田紗友さん)が頭にきて、ならば自分たちなら面倒な客でもいいのか、と重三郎に食ってかかりました。うつせみが二人の間に入って止めましたが、重三郎はその時うつせみの首に変なあざができていることに気が付きました。さらに松の井からは、瀬川を求める客が多過ぎて自分たちだって代わりに相手をしているから大変なんだ、ということも聞かされました。さて牢から解き放ちとなった鱗形屋孫兵衛ですが、鶴屋喜右衛門の助けを借りて起死回生を図っていました。その孫兵衛は、実は須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)の力によって家に戻れたわけで、孫兵衛は重版で手を組んでいた役人に裏切られた、孫兵衛が捕まったのは自分のせいではなかった、須原屋も重三郎を疑ってはいない、ということを重三郎は須原屋の口から聞いて安堵しました。そして重三郎は、ある女郎に本を送りたいから市兵衛に本の相談に乗って欲しいと今日ここに来た理由を話しました。連日連日休む暇なく客が来る瀬川の今宵の客は盲の鳥山検校(市原隼人さん)。盲の頂点に立つ鳥山は大金持ちで下っ端の盲と違って品も良く、初回のこの日は高価なかんざしや鏡と世間で評判の本などを瀬川に土産に持ってきていました。初回の花魁は話もできず瀬川も退屈だろうから、盲の自分に構わず皆で楽しむがよいと鳥山は言い、その心遣いにいね(水野美紀さん)は深く礼を述べました。座敷の皆が喜ぶその光景を見て瀬川が鳥山に声をかけ、自分が本を1冊読もうかと提案、鳥山はそれは吉原のしきたりを破ると遠慮しましたが瀬川は、花魁の姿の代わりに声を楽しんでもらいたいと言い、いねも特別にそれを認めました。瀬川は本の中から『金々先生榮花夢』を選んで鳥山のために読み、鳥山も瀬川の声に聞き入っていました。(鳥山の優しさに、瀬川も優しさで応えたのですね。)重三郎が茶屋に戻ると義兄の次郎兵衛が『金々先生榮花夢』の本を面白がって読んでいたので、重三郎は実はその内容の一部は自分が以前、鱗形屋に出したネタであり、それを鱗形屋が本にしていることを伝えました。自分のネタだけど鱗形屋が面白い本に仕立てていることは重三郎も認めざるを得ないし、鱗形屋のこの本が世間の評判を呼んでいることで重三郎の問屋の仲間入りがどうなるのかを次郎兵衛も案じていました。翌朝、重三郎は瀬川をお稲荷さまに呼び出しました。瀬川はこの本は面白いと感想を述べ、同時に重三郎のことを案じました。でも重三郎は、実はこの先のことをすでに親父衆に相談してあり、計算高い親父衆は自分の味方になってくれていることを瀬川に伝えました。今まで瀬川が何かと助けてくれたから親父衆も協力してくれるようになった、と重三郎は改めて瀬川に礼を言い、1冊の本を手渡しました。それは『女重宝記』という本で、瀬川が名のある人に身請けされた時に世間の常識や考えを知らなくて苦労しないように、という重三郎の思いからでした。重三郎は自分が身請けされて幸せになることを願ってくれていると感じつつ、瀬川は自分が重三郎にとって特別な存在ではなくここにいる女郎たちの一人にすぎないのだと感じて、寂しさと悲しさをごまかして去っていきました。瀬川の気持ちを量りかねた重三郎はお稲荷さまに独り言(=相談)したけど、この時はまだ自分の気持ちにも気がついていませんでした。夏になり、重三郎が店番をしていたら鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が来て、互いに思うところを抱えながら挨拶を交わしました。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)ら地本問屋の仲間6人で𠮷原に来て、突然話し合う場が設けられました。切れ者の喜右衛門が問屋を代表して話し、その内容は孫兵衛が持ち直したので重三郎の地本問屋の仲間入りを断るというものでした。重三郎が自分が出す本は吉原に関わる物だけで皆さんの商売の邪魔はしない、細見もこちらで作ってタダで譲る、だから仲間にと訴えました。それならばと何人かの問屋が考えを変えようとしたら、喜右衛門は話の流れを断ち切り、自分だけで話すからと仲間の皆を退室させました。そして「卑しい外道の𠮷原者」は市中の問屋の仲間にはしたくないという人も何人かいるなど、親父衆の誰が何を言っても喜右衛門はその度に言葉を返して聞き入れませんでした。重三郎は自分たちを毛嫌いする人たちと話し合いをさせて欲しいと訴えました。しかし喜右衛門は「𠮷原の方々とは同じ座敷にもいたくない。」とのことだと言い、その言いぐさに親父衆は皆いよいよ我慢ならなくなりました。その時、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が急に笑いだし立ち上がったかと思うと喜右衛門の傍に立ったので、喜右衛門も笑い返したら・・・!!市右衛門は喜右衛門の首根っこを掴んで力ずくで座敷から引きずり出そうと障子に向かいました。重三郎は他所の人だと市右衛門を止めたのですが大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)は重三郎を押しのけ、障子を開けて市右衛門に道をつくりました。市右衛門は勢いのまま障子の向こうにある階段から喜右衛門を落としました。喜右衛門は階段の下で待っていた問屋仲間のところに転げ落ちていきました。階下から親父衆を見上げる喜右衛門たちに、親父衆は口々に言いました。「俺だってあんたらと同じ座敷にいたくない。」「あんたら出入り禁止な。」「あんたらはもう𠮷原の本は作れない。重三郎しか作れないね。」「黙って大門くぐったら・・。」、最後は扇屋宇右衛門(山路和弘さん)から「二度と出ていけなくなりますからね。」と念押しされ「覚悟しろや、この赤子面!」と市右衛門にダメ押しされました。自分の味方になってくれた頼もしい親父衆でしたが、地本問屋たちとは激しい対立となってしまい、重三郎もこの先のことが少し心配になってきました。
February 27, 2025
-
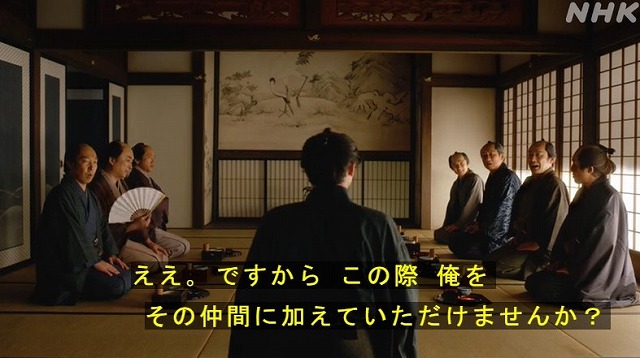
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第7回~「好機到来『籬(まがき)の花』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、私が印象に残ったのは、横浜流星さん演じる蔦屋重三郎という人物の物事の捉え方です。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が役人に捕まったとき、重三郎は自分が知ってて知らせなかったからと、自分が孫兵衛を嵌めたんだと考えました。でもその前に重三郎は、『雛形若菜』の事では世の中の仕組みを知らなかったが故に、あるいは誰からも教えてもらえなかったが故に、孫兵衛たちに嵌められています。逆に孫兵衛は、自分が重三郎にしたことを棚に上げて、重三郎を逆恨みしています。このあたりの個々の性格というか物事の捉え方というか、「自分の無知は反省するけど他を恨まず、そしてまずは行動」というのは、重三郎のように将来、大人物になる人に備わった天与の才なのでしょうか。そしてもう一つ印象に残ったのは、ドラマの中に所々に出てきた女郎たちの恋心です。かをり(稲垣来泉さん)のように重三郎にストレートに好きだという気持ちをぶつける女もいれば、男に身体を売って生きるしかない自分は男を選べない、好いた男がいてもどうしようもないと思う女もいるでしょう。でも本音はやっぱり好いた男と結ばれたい、かをりのような小童なら最初の男はーー。そんな女たちの心の底の思いを重三郎はわかっていて、だから余計に、他者のために動く重三郎は、女たちが男を選べるほど𠮷原を盛り上げたい、という行動力につながっているのでしょうか。ところで、中村蒼さんさん演じる次郎兵衛義兄さん。こういう人、いるんですよね。仕事はあまりできないし好きじゃないけど、仕事ではない部分の人の行動はよく見ていて、経験値も含めてその人の心がなんとなく読めて、先々起こりうる事の予測ができる人が。義兄さんが「危ない」と言ったかをり、この先何かやらかしそうです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 地本問屋の鱗形屋孫兵衛が不正を働いて奉行所に捕らえられたため、孫兵衛が手掛けていた𠮷原細見をどうするか、会所で話し合いが行われていました。そこへ蔦屋重三郎(横浜流星さん)が突如現れ、これからは自分が版元となって細見を出す、自分もこの地本問屋の仲間にして欲しい、と主張しました。もちろん問屋仲間の主たちは一斉に大反対でしたが、それでも重三郎は、自分に任せてくれたら今までの「倍」売れる細見を作ってみせる、そうすればここの皆だって儲かる、と大見栄を切りました。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は、重三郎がそこまで言うのなら倍売れるという細見を作って見せて欲しい、そして本当に倍売れたらその時はここの仲間として迎えると言い、重三郎はその条件を了承して退室していきました。𠮷原に戻った重三郎は、細見が倍売れたら地本問屋の仲間入りができるから、女郎屋の主人たちにも細見を倍、買い取って欲しいと頼みました。主人たちは案の定いい顔はしないのですが、重三郎は𠮷原が自前の本屋を持てることの利を主人たちに説明しました。これが𠮷原を売り込む手段になると理解した主人たちは重三郎の考えに賛同し、重三郎は意気揚々と会合の店を出ていきました。そんな重三郎の背中を見つめる主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)はどこか物憂げで、その理由を扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は問いました。「市中のやつらの話を真に受けていいものか」と市右衛門は心配だったのです。その頃、西村屋の与八は重三郎の思い通りにはさせまいと、孫兵衛が牢にいる間に鱗形屋に行って細見の版木を手に入れようとしました。孫兵衛の妻のりんは固辞しましたが与八は金を積んでしつこく食い下がるので、りんも一瞬は心が動きかけました。でもその時、奥から次男の万次郎が出てきて与八と対面し、これは父でないと決められないときっぱりと断りました。一方、重三郎は鱗形屋の一件でのすっきりしない胸の内を、義兄の次郎兵衛と蕎麦屋の半次郎に聞いてもらってました。その後で重三郎は、細見を倍売りたい、そのためには細見を作る費用を半値にして、もっといい物にして半値で売りたい、と二人に協力を頼みました。そこでまず、どういう細見なら買うかを調べるために三人で聞き回りました。二文字屋のきく(かたせ梨乃さん)にも協力してもらい、人々の意見を調査して回りました。人々の意見から重三郎は、細見にあるのは大見世の女郎ばかりで巷の男が買える女郎が載っていない、ということに気が付きました。そんな話をしつつ次郎兵衛(中村蒼さん)と半次郎(六平直政さん)と歩いていたら、かをり(大文字屋の秘蔵っ子、まだ小童;稲垣来泉さん)が重三郎の背中に飛びついてきました。「細見を持ってきた客が男前だったらタダにしては?」と意見を言いながら、かをりは重三郎が好きなのでしがみついて離れません。女将の志げが飛んできてかをりをきつく叱り(脅し)、ようやく重三郎から離れたので志げはかをりを連れて帰りました。その様子を見た次郎兵衛は「あいつは危ない」と直感しました。(仕事ではまあ頼りにならない義兄さんだけど、こういう勘は鋭いと思います)重三郎たちが店に戻ると小田新之助(井之脇海さん)が来ていました。新之助は今日はうつせみに会いに来たのではなく、重三郎が相談した細見の工夫のことで意見を述べに来てくれたのでした。新之助が細見を薄くすると持ち歩きやすいと提案すると、重三郎はこれなら経費も半分にできるからうまくいくと考え、新之助にも助力を頼みました。そこでまずは、今ある細見を分解して見直し、不要な項目を省いて並べ方や見せ方も工夫してみることにしました。重三郎が地本問屋に仲間入りするのをどうにかして阻止したい西村屋の与八は、細見を出していたもう一人の男・小泉忠五郎と手を組みました。そして与八は忠五郎を連れて𠮷原を訪ね、重三郎の細見を買った店の女郎は『雛形若菜』には使わないことを伝え、吉原に脅しをかけてきました。与八の脅しに屈しようとした親父衆に重三郎は我慢がならなくなりました。「与八は自分が楽して儲けることしか考えていない。女郎たちが体を痛めて稼ぎ出した金が奴らに流れるなんて許せない。女郎の血と涙が滲んだ金で絵や細見や作って女郎に客が群がるようにしてやりたい。女郎にも誇りを持たせてやりたい。」と力強く言い、そして落ち着いた声でさらに続けました。「それが女の股で飯食ってる腐れ外道の忘八の、たった一つの心意気。だから他所に任せてはいけない。吉原自前の本屋が要る。今はその二度とない機会。」と親父衆の心に訴えるように言い、正座して姿勢を改めて「つまらない脅しに負けないで共に戦って欲しい。」と皆に深々と頭を下げました。西村屋に負けたくないこともあるけど、何より吉原の女たち全てを大事に思う重三郎は大見世だけでなく、半値の細見なら買うような男が行けるような安い見世、果ては河岸見世まで吉原の全てを細見に盛り込みたいと考えました。清書を担当する新之助は細かい字を紙にびっしりと何回も何回もと書いているのですが、重三郎が小さな見世まで足を運んで聞き取りをしてくるたびに再び清書の書き直しを頼まれていました。思わずため息が出るけど、新之助は我慢して重三郎に付き合ってやっていました。とはいえ、いくら性格が穏やかで優しい新之助はでも、こうも毎度毎度ちょっとずつのために細かい字びっしりの紙を書き直しをさせられたら、さすがに疲労と我慢が限界になることもあります。一緒にいるのに何を手伝っているのかわからない次郎兵衛は、新之助に怒られていました。また彫師の四五六(肥後克広さん)も、この細か過ぎる字を彫るためにイライラから思わず大声が出て、怒りでノミを飛ばしてました。松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)が重三郎の訴えに感動し、でも今は重三郎の分が悪いという話を妻のいね(水野美紀さん)にしていたら、花魁の花の井(小芝風花さん)がたまたまた耳にしてしまったので、半左衛門は花の井に自分たちも一緒に何か考えよう、と声をかけてくれました。三人で過去の細見を見直して考えていると、いねがふと気がつきました。「細見がバカ売れするのは、名跡の襲名が決まった時さ!」そう言われて半左衛門も思い出しました。「売れた!売れてたよ。染衣が四代目の瀬川が名跡を継いだ時も!」二人の話を聞いた花の井は、何かを決意しました。版木が彫り上がったので、その後はかつて重三郎が窮地を救った「二文字屋」で女郎たちが総動員して手伝い、製本の作業が進められました。そしてどうにか細見が完成し、重三郎はお稲荷さまに本を供えて祈ってました。するとそこに幼なじみの花魁の花の井が来て、うちで女郎の入れ替えがあった、また細見を修正して欲しいと重三郎に紙を差し出しました。重三郎は製本して綴じた後なのにと落胆しましたが、その紙を見るとそこには「花の井改め 瀬川」と書かれていました。そう、花の井は名跡襲名の時は細見が売れるからと、自分が「瀬川」を継いで世の関心を引き、重三郎を助ける決意をしたのでした。ただ瀬川の名は過去に不吉なことがあり、重三郎は心配しました。でも花の井は、自分は自害はしない、自分が豪気な身請けを決めて瀬川をもう一度幸運の名跡にする、と言い切りお稲荷さまに祈りました。𠮷原をなんとか盛り上げたい、それは花の井も同じ気持ちでした。さていよいよ約束の日、地本問屋の皆が集まる中で西村屋与八(西村まさ彦さん)は美しい表紙に白い和紙の覆いをつけた上等な仕立ての細見を披露し、これなら重三郎が敵うわけないと自信満々でした。そして重三郎が大きな行李を背負ってやって来て、どこか自信有り気に皆の前に差し出した細見は、安っぽい表紙に薄っぺらい本でした。皆が嘲笑する中で鶴屋喜右衛門が中を改めると、𠮷原を安見世まで書かれた小さな文字がびっしりと並ぶもので、本の見せ方にも工夫がありました。そして松葉屋の頁を見るとそこには「瀬川」の名があり、一同は驚きました。重三郎は「今回の瀬川のことは𠮷原の外にいる人にはわからなかったこと」と得意げに言い、さらに「この細見を従来の半値で売って欲しい。半値なら巷のありふれた男たちも買うだろう。瀬川の名が載る祝儀の細見を。」と力強く売り込みをかけました。すると重三郎の細見はたちどころに飛ぶように売れていきました。しかし喜右衛門は、まだ何か考えているようでした。
February 20, 2025
-
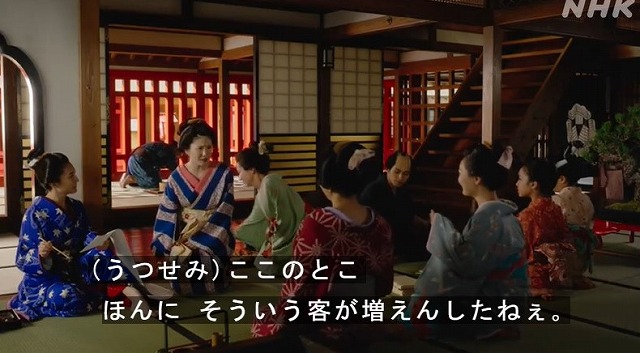
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第6回~「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回のメインの話は一言で言えば “天罰” でしょうか。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)は知識のなかった蔦屋重三郎(横浜流星さん)を陥れ、その後もさんざん彼を利用してきました。重三郎はというと、ある事で自分が孫兵衛に利用されていることを知って強い怒りを覚えるのですが、それでも孫兵衛の今後は運を天に任せようと決めました。そして思いがけない形で孫兵衛の悪事がバレて奉行所に連行されていくという天罰が下りました。重三郎は自分の願望を心に思い描いただけで本当に何もしなかったのですが、それでも心が少し痛みました。そんな重三郎を元気づけてくれた長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)は、実は重三郎と花魁の花の井に乗せられて全財産を𠮷原でばらまいているのに、いい人ですよね。一方、田沼意次(渡辺謙さん)は幕府の財政立て直しのために周囲から嫌味を言われながらも必死に頑張っているのですが、出自が低いことを事あるごとに松平武元(石坂浩二さん)ら名家の出の者たちから嘲笑されます。それでもぐっと堪えて頭を下げて相手を持ち上げ、老中としての仕事を進めていきます。田沼意次と言えば高校の教科書の中では「株仲間、新田開発、蝦夷地との交易」といったキーワードが出てくるので、経済に長けた人だったのでしょう。でも教科書には書かれない、身分社会の中で出自の低さ故の苦労は数知れずあったのだろうと、このドラマを通じて感じています。*番組HPに用語解説が出ています べらぼうナビ「御書院番士」 ⇒ ⇒ こちら * RekiShock(レキショック)先生作成の資料です鱗形屋の偽板が発覚した頃(1775年頃)登場人物の年齢(満年齢) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 鱗形屋お抱えの改となった蔦屋重三郎(横浜流星さん)は吉原細見を改良するために、女郎たちからネタになる話を集めていました。流行に乗って「キンキン」で決めたものの慣れない𠮷原通いで男たちが失敗をする様などを聞いていましたが、幼なじみの花魁の花の井からは「本がつまらない」と意見されていました。そんな時、花魁の一人のうつせみ(小野花梨さん)から、市中に出るなら小田新之助に渡して欲しいと文を託されました。その文には「揚代は自分が払うから𠮷原に来て欲しい」とあり、新之助を慕ううつせみの思いがしたためられていました。鱗形屋に来ていた重三郎は主人の孫兵衛から、何か大当たりするようなものが欲しいと言われましたが、そう簡単にはいきません。そんな重三郎たちのやり取りを隣の部屋で手習いをしながら聞いていた次男の万次郎が「地本は当たってこそだから」と言いました。重三郎が万次郎の手習いを覗くとずいぶんと難しい字を書いていて、万次郎は大きくなったら地本問屋じゃなくて儲かる書物問屋になりたいと言いました。そして「物之本」は地本に比べてものすごい高値で売れるし割よく儲かると父・孫兵衛が言ってたということでした。重三郎はその後で藤八(徳井優さん)と話をし、刷り損じの紙を紙くず買いに出さずに厠の紙に使っていることを知りました。さらに明和の大火(1772)のときに蔵も店も焼けて大損害を被り今も経営が厳しい、重三郎の働きを期待している、と藤八は言いました。さてそのころ江戸から遠く離れた尾張の熱田(現在の名古屋市)では、上方の版元の柏原屋与左衛門(川畑泰史さん)が「早引節用集」の古本を手に取り、店の主人にこれを誰が売っていったのかを訊いていました。売ったのは武士でしたが、与左衛門は裏表紙にある「版元 丸屋源六」という聞き覚えのない名前に怪しんでいました。一方、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)は小島松平家の家老・斎藤茂右衛門(藤本康文さん)から注文を受けたものを届けていました。その中には内密で頼まれた鈴木春信(1770没)が描いた春画の『風流艶色真似ゑもん』もあり、なかなか手に入らない本だったので家老の茂右衛門はこれなら先方も喜ぶと大満足でした。さらに茂右衛門は小声で孫兵衛に「例のアレを倍、頼みたい。当家のような小身の大名にはアレがまことに有難い実入りとなる」と耳打ちし、孫兵衛も近いうちに持ってくると承知していました。ところが孫兵衛たちが帰った後、茂右衛門は家臣から例のアレのことで何か重要な報告を受けたようでした。孫兵衛から派手に当たる何かを考えろと言われた重三郎でしたが、いい考えが一向に浮かばず蕎麦屋の半兵衛や義兄の治郎兵衛に相談していました。治郎兵衛が青本はつまらないと言ったことから重三郎は何か思いつき、翌朝すぐに鱗形屋に向かいました。店に入ると藤八が柱にもたれて寝ているだけで誰もいず、でも奥から版木を摺る音が聞こえてくるので、重三郎はその部屋まで行きました。重三郎が元気よく挨拶をして障子を開けると、中にいた人たちが一斉に慌てて何かを隠すような仕草をし、孫兵衛が慌てて出てきました。孫兵衛は重三郎を別の部屋に連れていって話を聞きました。重三郎は鱗形屋が以前出した青本は評判が悪いから、今の時代に合った面白いものを作り直してはどうかと提案、孫兵衛もそれを受け入れました。さて江戸城内では、田沼意次(渡辺謙さん)は勘定吟味役から御金蔵の金が明和大火の前までの状態に持ち直したと収支上告を受けていました。するといつも意次を見下している老中首座の松平武元(石坂浩二さん)がどういうわけか意次の成果を褒めたたえています。実はそれには目的があって武元は「日光社参」を執り行いたいと言うのですが、徳川家・旗本・諸大名が連なる参詣には莫大な費用がかかるものでした。あの手この手でやっと幕府の財政が立て直せた意次は参詣などやりたくないのですが、武元たちは将軍に取り次ぐようご丁寧に低頭までするので、意次は将軍に社参の話をせざるを得ませんでした。重三郎は孫兵衛と、どうやって青本を作るかで話が盛り上がっていました。その後、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)の店の前を通りがかったとき、店の者がものすごく不機嫌に塩を叩きつけていました。どうしたのかと重三郎が市兵衛にが訊ねると、偽版が出回っている、この本はこの店が作ったのではないかと大坂の柏原屋という本屋が言ってきた、ということで店の者は怒っていたのでした。その話を聞いた重三郎はふと鱗形屋で万次郎が言ってたことを思い出し、もし出版した者が見つかったらどうなるのかと市兵衛に訊ねたら、柏原屋は役人に訴え出るだろう、ということでした。重三郎は鱗形屋で見聞きしたさまざまな状況から、この偽版は孫兵衛だと推察、役人に訴え出れば自分が取って変われる、でも告げ口は嫌だからどうしようかと自問自答していました。でも何もわからないままでは先に進めないから、確かめることにしました。重三郎は鱗形屋に行き、厠を借りるふりをして摺り損じの紙を見て、偽版を出版しているのが孫兵衛だと確認しました。そして戻ろうとした時に通りがかった部屋から話声が聞こえ、声の主は西村屋与八と孫兵衛で、重三郎は「雛形若菜」の件では自分はこの二人に嵌められて、今もなお利用されているのだとわかりました。怒りと悔しさでいっぱいになった重三郎は店を出た足で須原屋を訪ね市兵衛に話を聞いてもらおうとしましたが、この時は結局何も言えずじまいでした。夜、いつものお稲荷様のところでこの件をどうしようかあれこれ悩んだけど、告発は自分の性に合わないと考え、鱗形屋がこの先どうなるかはもう運を天に任せることにしました。意次は将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に、借金を抱える者も多い旗本や諸大名たちの事情も考えて日光社参は執り行わないで欲しいと訴えました。しかし家治は嫡男の家基が社参を望んでいるから執り行うと言います。田沼家の用人である三浦庄司は、これはたぶん白眉毛(武元のこと)が裏から家基の生母の知保の方を動かしているのだろうと考えました。そこで意次は、ならば貧乏大名や貧乏旗本から社参取りやめの嘆願を集めようと考えて、手配するよう三浦に命じました。嘆願書が集まったところで意次は家治にその旨を伝え、社参を取りやめるよう強く訴えました。しかし家治は嫡男の家基から、将軍である自分は意次の言いなりになっている、意次は成り上がりの奸賊であると言われたと伝え、そして家基の世になった時、田沼一派は真っ先に排除されるだろうと警告しました。重三郎は偽版本の件では自分からは何も言わないと決めていたのですが、武家の者が孫兵衛とつながって偽版本を売りさばいているという話は幕府の上の方の役人にまで内密に話が伝わっていました。重三郎が複雑な思いを抱えながら鱗形屋に来て孫兵衛と打ち合わせをしている時に長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)が店に入ってきました。平蔵が地引を求め、差し出された節用集を確認するとそれは偽版本でした。平蔵が「あったぞ!偽版だ!」と叫ぶと店の中に同心たちが一斉に入ってきて、上方の版元の柏原屋から訴えが出ていることを説明して、孫兵衛以下鱗形屋の者たちを全員連行していきました。同心たちが店を調べると蔵には証拠となる大量の版木と摺本があり、重三郎が告発したと思い込んだ孫兵衛は重三郎を逆恨みしながら連行されていきました。板戸が閉め切られた店の前で、平蔵は重三郎に事の次第を話してやりました。柏原屋から奉行所に相談があり、偽版を出している者の正体がつかめなくて訴えられない、でも奉行所のほうも調べようがなくてどうしたものかと思っていたら、この件に関しては何故か上から鱗形屋を調べろと命が下ったと。重三郎は平蔵に、実は孫兵衛のやっていることを知っていたが孫兵衛に危ないとは言わなかった、心のどこかで孫兵衛がいなければ自分が取って代われると望んでいた、でもうまくやるというのは心が堪える、と打ち明けました。そんな重三郎に平蔵は、世の中そんなもんだ、気にするなと言い、持っていた粟餅を「濡れ手に粟餅」と言って重三郎に渡しました。「せいぜい有難く頂いとけ。それが粟餅(うまい話)を落とした奴への手向けだ。」ーーそう言って平蔵は去っていきました。重三郎は店に向かって挨拶をし、粟餅を力いっぱいほおばりました。
February 13, 2025
-
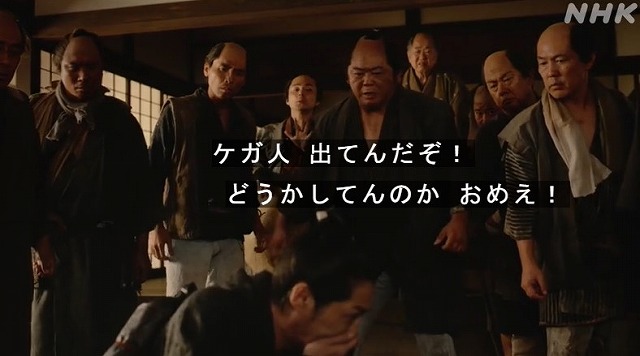
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第5回~「蔦に唐丸因果の夢」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回いくつかの場面で感じたことは、一言で言えば『類は友を呼ぶ』でしょうか。平賀源内(安田顕さん)が金策のために老中の田沼意次(渡辺謙さん)を訪ねた折に、鉱山を開発すれば金属を得るだけでなく、その土地全体で仕事が増え、金を稼げ、道ができ宿場ができ、全体が活性化して幕府にも運上・冥加が入って、といったことを意次は力強く語りました。その次に源内が、日本が開国をすれば人々の目が大きく開け、能力がある者は外国人を相手にいろいろな仕事ができて富を得ることができると言い、意次と源内は実に楽しそうに展望を語り合っていました。今いる場所のうまくいかない現状を変えたい、全体をもっと大きく豊かにしたい、そのためにはどうしたらいいのかを考えたい。気が合うというか、互いに同じエネルギーを持つ者であると感じるのか、自然と惹かれ合うのです。蔦屋重三郎(横浜流星さん)も、住まう世界は違っても𠮷原全体を良くしたいという思いから、自分の仕事じゃないのに奔走し、結局はそれがタダ働きとなって気落ちしても、また気を取り直して進んでいきます。互いにどこか似た者が惹かれ合って集うのです。重三郎のエネルギーが、いつか意次を呼ぶのでしょうか。さて今回から、時代劇の大御所である里見浩太朗さんが須原屋市兵衛の役で登場しました。里見さんもさすがにお歳を召されたし、このドラマでは殺陣はありませんが、それでも里見さんがいらっしゃるだけで江戸時代の雰囲気がグッと出る感じがします。ホント、すごい存在感だと思います。さてこちらでは様々な意見がでていて参考になりますが、今回は特に2月2日に千葉県の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに行かれた方が、主役の横浜流星さんの素顔フォトをUPされてます。すごくいいお顔をしているので、これは必見です。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 平賀源内(安田顕さん)が採掘をさせている秩父の中津川鉱山で火災が起こり、平秩東作から報せを聞いた源内は大急ぎで江戸から秩父に向かいました。10年も山を掘り続けているのに金になる物が掘り当てられない上に事故まで起きて炭鉱の工夫たちはカンカンに怒っていました。もうこの採掘を辞めるという工夫たちをなだめて仕事を続けるよう源内は促すのですが、『災い転じて福となす』というつもりで「めでたく災難」と言って笑ってしまったことで工夫たちの怒りが爆発。源内は殴られながらも「ここは米も取れない土地で金を稼ぐために始めた事」とか言って反論しますが、工夫たちや船頭たちが資本金として源内に渡した大金を、東作を人質にとって10日で返すよう返すように要求してきました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、源内から「耕書堂」という版元の名をもらって錦絵作りに奔走したものの、重三郎では世間に出版できないと言われ、女郎屋の主人たちや鱗形屋の孫兵衛らにはさんざん利用されただけだと知って激しく落ち込んでいました。弟分の唐丸がその孫兵衛から文を預かってきてその内容は、重三郎に鱗形屋のお抱えの「改」になるようにというものでした。その話を聞いた義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)は「たとえ重三郎のタダ働きになっても、本をどんどん売り広めてもらえるならいい話だ」と意見しました。重三郎と次郎兵衛がそんな話をしていると向こう傷の男(高木勝也さん)が店先にふらりと現れ、最初は唐丸(渡邉斗翔くん)が対応しました。でも何か危ない感じがした重三郎が二人の間に割って入り、唐丸には中に入るよう促したのですが、唐丸は自分が相手をすると言い張ります。この男は何か唐丸の弱みを握っているのか、何日か前から唐丸につきまとって金をせびり、店の金を持ってくるよう要求していました。重三郎は唐丸と男の様子を警戒しながら気にしていましたが、そこへフラフラになった源内が何か食べさせて欲しいと飛び込んできました。次郎兵衛がとりあえず向かいの蕎麦屋に案内し、重三郎は唐丸に店番を頼んで源内に同行、蕎麦屋の半次郎(六平直政さん)は源内の事情を興味深く聞いていましたが、案の定その隙に男が店から何か持っていったようでした。そして源内が重三郎のところに来たのは、山の人たちに大金を返すために炭を売りたいから炭屋の株が欲しい、炭屋の株を売りたい人を紹介して欲しい、という理由があったからでした。親父衆から紹介をもらった源内は重三郎と共に炭問屋の山崎屋に向かいました。しかし双方の話があわずにご破算になりました。店を出た後、重三郎は源内に「いつもこんはふうに儲け話を考えて、人と金を集めてなんて危なっかしい生き方をしているのか」と訊ねました。源内は自分を召し抱えてくれる所がないから自分で声を上げるしかないと言い、「しがらみに縛られず自由に生きる=我儘に生きる。ただそれで生活がきつくなるのは仕方がない。」と答えました。源内の話が重三郎の胸に何か響いたのか、重三郎は本屋の株を買おうと考え、そういう話ができる人をだれか紹介して欲しいと源内に頼みました。*平賀源内の士官についての話が番組HPの「べらぼうナビ」に出ています 。 ⇒ ⇒ こちら 重三郎にそう言われた源内は、すぐそばにあった書物問屋に入っていきました。主人の須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)は重三郎が求める「地本問屋の株」と「書物問屋の株」は違うことを教えてやり、鱗形屋や西村屋に「仲間」という言葉で丸め込まれた自分の無知さを悔しく思いました。それでも自分が版元になる方法は何かないのかと市兵衛に訊ねたら、どこかの本屋に奉公に上がって暖簾分けをしてもらうのはどうかと教えてくれました。さて早く金策をして中津川鉱山に戻らなければならない源内は、老中の田沼意次(渡辺謙さん)を訪ねました。500両もの大金をなんとかしてやると言ってくれた意次に源内が深々と頭を下げると、意次は礼を言うのはこっちだと言います。「山で稼げれば土地の者が金を得る。水路が開かれば商いが盛んになり宿場ができて民が潤う。幕府にも運上・冥加が入ってくる。本来なら政でやるべき。」と意次は経済が回る仕組みを広めたいのですが、それは武士のやることではないと批判する、由緒正しい古い人たちを意次は苦々しく思っていました。源内は、ならばいっそのこと開国して誰でもどこでも外国と取引できるようになるといい、そうすれば物の値打ちだけでなく人の値打ちもわかるようになる、通事・造船・塾などいろいろな商売が始まると。意次と源内は二人で語り合いながら、次々と開けていく展望に胸を膨らませて笑い合っていました。しかし現実は、そう簡単にもいかないことも二人はわかっていました。日も落ちて重三郎が店に戻ると、留守番をしていた次郎兵衛は帰き際に重三郎に何か高い本を買ったか?と訊きました。次郎兵衛が「銭箱の金が減っている気がする。」と言うので、重三郎は唐丸が怪しいと感づいたのですが、とりあえずその場はごまかしました。唐丸は頻繁に男に金をせびられるようになり、我慢できなくなってお奉行所に訴えると言いました。でも唐丸の過去を知っている男は「そうなるとこの店がお前をかくまったとして同様に罰せられる」とさらに脅すので、唐丸は男の言う通りにするしかありませんでした。寝る前に二人になったとき、重三郎はこれから鱗形屋に奉公に出て、いつか唐丸を絵師として迎えると約束しました。そして唐丸に、何か隠し事があるのでは?困り事があるなら力になるから、と訊ねましたが深くは追及はしませんでした。翌朝、重三郎が目を覚ますと唐丸の姿はなく銭箱もなくなっていました。重三郎は唐丸を必死に探しますが、唐丸はあの男と会っていました。唐丸が抱えてきた銭箱を見てほくそ笑む男、でもこれでもう重三郎がいるあの店には二度と戻れないのだと覚悟を決めた唐丸は、男に体当たりしてもろとも川に落ちていきました。市中を走り回って唐丸をさんざん探したけど見つからず、夜になって重三郎は店に戻ってきたのですが、何やら人だかりができていました。店には役人が来ていて、向こう傷のある男が土左衛門が上がってその男がこの店の物を持っていて役人が調べている、ということでした。役人が重三郎を疑うような言い方をしたので主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)がすかさず、𠮷原は咎人を突き出す役目も持っているから怪しいやつがいたら自分が奉行所に突き出すと言いました。役人が去った後で、その男と共に川に落ちた子がいると言われているが、もし唐丸が絡んでいたら面倒なことになるからこれ以上騒ぐな、と釘を刺しました。しかし唐丸が姿を消し、銭箱がなくなったことで、憶測も交えた勝手な噂話がどんどんと広まっていきました。重三郎は気持ちの拠り所となるいつものお稲荷さんのところに来ていました。唐丸が描いた絵を見つめながら、これまで唐丸の過去のことをあえて聞かずにいた自分を責めていました。幼なじみの花魁の花の井(小芝風花さん)は、唐丸は今頃きっと幸せしていると言い、そう考えるのが女郎たちの流儀だと言いました。花の井とそんな話をしていると重三郎も希望を思い描くようになり、そのうち唐丸がひょっこりと自分のところに戻ってきてまた絵を描きたいと言うだろう、そして自分が唐丸を謎の絵師として売り出すんだと、あの夜に唐丸と約束したことを語り、お稲荷さんに願掛けをしていました。さてその頃、平賀源内は田沼意次が用意してくれた大金を持って中津川鉱山に行き、工夫たちと話をつけてきました。一方、重三郎も鱗形屋に行って店のお抱えの「改」となることを孫兵衛に伝え、𠮷原に人を呼ぶために働く決意を新たにしました。
February 6, 2025
全4件 (4件中 1-4件目)
1










