全4878件 (4878件中 1-50件目)
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第44回~「空飛ぶ源内」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政5年(1793)、我が子を早産で失ったてい(橋本愛さん)は悲しみに暮れて食事も喉を通らず、たか(島本須美さん)が何を言っても心に響きませんでした。 蔦屋重三郎(横浜流星さん)も何も考える気力がわかず、喜多川歌麿(染谷将太さん)と袂を分かったことを吉原の親父の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)に報告したときも、仕事に対して投げやりになっていました。 店の重苦しい雰囲気を変えようと滝沢瑣吉(後の曲亭馬琴;津田健次郎さん)は、亡き子と婆さまからご加護を得るために写経をしようと呼びかけていたら、そこに大凧を背負った流れ者が店に入ってきました。 男は駿府生まれの重田七郎貞一(後の十返舎一九;井上芳雄さん)と名乗り、自分が書いた浄瑠璃本を重三郎に見せました。なんとか蔦屋で書きたい貞一は、持参した大凧は亡き平賀源内が作った相良凧であり、相良は亡き田沼意次の領地だった、それを袖の下に渡すと言いました。 重三郎の心に平賀源内と田沼意次の存在がよみがえり、すっかり気力の失せていた重三郎の目に光が宿りました。 貞一の話から、実は源内は獄から逃げのびて相良でかくまわれて生きていた、いや、そんなことはないかと思いつつも、重三郎は蘭学者の杉田玄白(山中聡さん)を訪ねました。 重三郎が源内にまつわるうわさとか聞いたことがないかと尋ねると、玄白は重三郎の話をすぐには否定せず、分厚い書物のようなものを取り出して重三郎に渡しました。 さて、ていですが起き上がれるようになったものの何か食べたいという気になれず、そんなところふじ(飯島直子さん)ととく(丸山礼さん)が豪華な菓子の詰め合わせを持って見舞いに来てくれました。 ふじは「子は甘いものが好きだろ?」と言って位牌に手を合わせ、皆でいただこうと言い、ていに菓子を一つとってくれました。女たちの悲哀を嫌というほど吉原で見てきたふじの言葉はていの心に響き、ていはおなかの子の供養と思って菓子を口にしました。あれ以来ずっとまともに食べていなかったていでしたが、菓子の甘さが心にしみて久しぶりに食べ物が美味しいと感じました。 一方、重三郎は玄白から「解体新書」を受け取っていました。これの挿絵を描いた小野田直武という人物は源内から絵を習い、源内が死んだ翌年に急死していました。その小野田は秋田の出なので、重三郎はの朋誠堂喜三二(本名は平沢常富、秋田佐竹家の留守居役;尾美としのりさん)に会い、小野田のことを尋ねると喜三二は、源内は蝦夷に逃げたのでは?とのことでした。 重三郎がこの話を田沼意次に仕えた三浦庄司(原田泰造さん)にすると三浦は、源内はたしかに獄で亡くなったしあのとき意次も嘆き悲しんでいた、と言いつつも源内は今も生きているのでは?と言う重三郎の話を否定はしませんでした。 次に重三郎は大田南畝(桐谷健太さん)を訪ねました。源内の話を大田にしても源内のことには触れたくなさそうでしたが、重三郎が源内のおかげで大田が有名になったことを言うと、態度を改めて何か考え始めました。そして重三郎に源内が描いたという蘭画を渡してくれました。 蘭画をていに見せると源内は絵師になったのでは?と言うので、重三郎は芝居町に出て蘭画風の絵を探しました。町に出ている芝居絵がすっかり地味になったのを残念に思っていたら、後姿が源内とよく似た男を見つけ、後を追いました。結局、男は見失ったのですが長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)に偶然会い、平蔵も誰かを追っているとのことでした。 帰宅した重三郎が町での出来事をていに話していると、ていは草餅を食べながら話に耳を傾けてくれました。食欲も出てやっと元気になったていを見て重三郎は喜びました。そしてていもまた、源内が生きているかもと聞いて活発に動き始めた重三郎を見て安堵しました。 そんなところにみの吉(中川翼さん)が山東京伝(本名は北尾政演;古川雄大さん)を案内してきました。京伝は瑣吉に縁談を持ってきていて、みの吉は何が何でもこの話をまとめた方がいいと後押ししていました。 そのみの吉は、歌麿のいない今この店でできることはないかと考えた案を紙に書いて出してくれました。みの吉を見てていも何か売り出すものはないかと考え、歌麿が最後に渡してくれた恋心の女絵の下絵に、少し手を加えて出すのはどうかと重三郎に提案しました。「何もしないよりはいい」ーーていの言葉に納得した重三郎は下絵に歌麿好みの見事な彫りと摺りを入れるよう注文しました。 そのころ歌麿は地本問屋の皆を吉原の座敷に集めていました。「ここで派手に遊んだ順に仕事を受ける」と言って皆に余興をさせて豪勢に遊び、女郎たちも喜んでいましたが、歌麿自身はちっとも楽しそうではありませんでした。 これが歌麿なりの吉原への恩返しなのか、紙花を撒くことを要求すると何人かが出てきて紙花を撒き始め、鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は歌麿が撒いたほうが座敷が盛り上がる、と言って紙花をわしづかみにして渡してくれました。 そのついでに喜右衛門は重三郎が色付けと歌麿の名入れをした『歌撰恋之部』の絵を歌麿に見せました。これから蔦屋が出すというその絵を歌麿は破り捨てましたが、喜右衛門が間に入ってくれたことに重三郎は礼を言いました。 瑣吉が履物屋の伊勢屋に婿入りする日、重三郎と瑣吉が去った後で店の戸口に青い包みと1冊の黄表紙が置かれていることにていは気がつきました。 重三郎が戻って中を見ると『一人遣傀儡石橋』と書かれた書き物があり、その話の筋書きは田沼意次を象徴する「七ツ星の龍」とか「死を呼ぶ手袋」とか、源内でなければ書けない話でした。さらに中には安徳寺に来るようにと重三郎に宛てたと思われる紙が挟んでありました。 重三郎が安徳寺に行って通された部屋には失脚した老中の松平定信(井上祐貴さん)と相談役の柴野栗山(嶋田久作さん)、元大奥総取締役の高岳(冨永愛さん)、そして三浦と長谷川が待っていました。 高岳は重三郎の前に進み出て手袋を見せました。それは10代将軍・徳川家治の嫡男の家基が鷹狩りに出て急死したときのもので、指先に毒が仕込まれたものでした。 毒を仕込んだのは家斉の乳母だった大崎が怪しいが、この件を追究すれば手袋に関わった田沼意次と高岳が怪しまれることになり黙るしかなかった、と高岳は語りました。 あの事件の折に老中首座だった右近将監(松平武元)の死後、行方知れずになっていた手袋が大崎から高岳→定信に渡され、定信は三浦から、源内が家基急死事件の真相を推測して書いた戯作があったことを聞かされたのでした。 定信は一橋治済(生田斗真さん)のことを「傀儡好きの大名」と呼び、重三郎に呼びかけました。「ここに集った我らは皆、その者の傀儡とされ弄ばれていた。ゆえに此度、宿怨を超えて共に仇を討つべく手を組んだ。蔦屋重三郎、我らと共に仇を討たぬか。」 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇今回、私なりに感じたこと。主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、仕事が行き詰まったところに誕生を楽しみにしていた我が子も失い、まさに精神的エネルギーがゼロになっていました。ところがそんな状態のとき、平賀源内と田沼意次の名を聞いて少し力が湧き、さらに「源内が生きているのでは?」と思った瞬間から、重三郎らしい行動力がグングン出てきました。 かつて心のよりどころとした人が他界して久しく、もう自分の中から消えてしまっていたけど、どん底の今、その名を聞いただけで心が再び熱くなり、体が動くようになったのです。一方、妻のてい(橋本愛さん)も自分の体から子が流れ出てしまい、生きるための気力すら出てきませんでした。でもそれを、ふじ(飯島直子さん)が受け止めてくれました。 吉原でも辛い境遇に嘆き悲しむ女郎たちをたくさん支えてきたふじだからこそ、言えた言葉でしょう。「子は甘い物が好き。」何も食べる気が起きないていでしたが、おなかの子が食べたがっているのだと思うと菓子を口にしようと思い、その言葉で同時に心も温かくなり、少しずつ生きる力が出てきました。 ラストの松平定信(井上祐貴さん)の復讐心も生きる気力にはなるけど、まずはプラスのエネルギーをくれた人たちの存在が復活の気力になるのがいいですね。
November 20, 2025
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第43回~「裏切りの恋歌」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政5年(1793)、喜多川歌麿(染谷将太さん)は義兄・蔦屋重三郎(横浜流星さん)の吉原への借金100両の返済代わりとして女郎の大首絵を50枚描くことになり、吉原で女郎たちの絵を描いていました。しかし吉原では、倹約令のために流行るのは安い女郎ばかりで、高級な花魁たちには声がかからなくて景気が悪い、と親父衆は愚痴ばかりこぼしていました。また江戸市中では、錦絵に描かれた看板娘がいる店では割高な料金を取って商売をしていましたが、奉行所からお叱りを受けて元の値に戻していました。一方、江戸城では老中首座の松平定信(井上祐貴さん)が将軍・徳川家斉(城桧吏さん)にオロシャの来航に伴う海防について報告をしていていました。話の後で家斉は、そろそろ政を定信に頼らず自分で指図すべき、と父・一橋治済(生田斗真さん)から話があったと言いました。しかし家斉は、自分は難しいことはわからないし政に興もわかぬと言い、定信が将軍補佐を外れても政に指図するしくみを作って欲しいとのことでした。定信はそのためにも自分が大老になればいいと考え、徳川御三家尾張の徳川宗睦(榎木孝明さん)に相談しました。宗睦は、大老は「井伊」「酒井」「土井」「堀田」の四家からしか出さぬしきたりがあるから無理だと答えました。しかし定信は、家斉が自分を頼っているからなんとか後押しして欲しい、と本気の覚悟を見せていました。宗睦は、家斉が今まで定信を避けていたのに急接近してきて変だとは感じていました。定信は、オロシャのラクスマンが漂流民を引き渡した後も日本に留まって将軍への目通りを願っていて、開国を要求していると目付の村上義礼(大迫一平さん)より報告を受けました。老中の本多忠籌(矢島健一さん)らはオロシャの要求をのんだほうがいいと考えましたが、定信は彼らを早く帰国させるためにも信牌(鎖国中の日本での長崎の入港許可証)を持たせればよいと考え、幕府の公式の返書をしたためて目付に渡しました。信牌を受け取ったラクスマンはエカテリーナ二世に見せるため、すぐに日本を出てオロシャに戻っていきました。この件を定信は将軍・家斉に報告し、その後で定信はある書状を家斉に渡していました。さて吉原では、歌麿が描いた女郎絵ができあがってきて親父衆たちは喜んでいました。親父衆は昔のにぎやかだった頃の昔話に花が咲き、次の企画は何かないかと盛り上がっていました。重三郎は歌麿が吉原を立て直すと皆に宣言し、親父衆もそれを期待していました。ただ当の歌麿は実は気乗りしていなくて、勝手に安請け合いをする重三郎からますます心が離れていきました。そんな話をしていたらふじ(飯島直子さん)たちが、重三郎の身重の妻のてい(橋本愛さん)のために、赤子の着物やおもちゃなどのおさがりをたくさん運んできました。商売も(歌麿頼みで)上向きになりそうだし、まもなく赤子も産まれてと、重三郎は楽しい未来を想像して笑っていました。しかし大量の仕事を持ってこられるだけで重三郎にいいように使われているようにしか思えない歌麿は、まったく笑う気にもなれませんでした。ある日、重三郎の店に鱗形屋孫兵衛の長男の長兵衛(三浦獠太さん)が『金々先生』の大量の版木を譲るといって持ってきてくれて、重三郎はありがたく譲り受けました。話の流れで長兵衛は弟の万次郎(孫兵衛の次男で西村屋の養子;中村莟玉さん)が歌麿はと組んで仕事ができると喜んでいたと重三郎に伝えました。そんなこと初耳だった重三郎は急ぎ歌麿のところに行きました。歌麿は女たちの「恋心」の大首絵を描き終えて重三郎に渡すと、重三郎は歌麿に好きな女がいるのかと喜びました。やっぱり重三郎には人の微妙な気持ちはわからないなと歌麿は自分の思いをわかってもらう気持ちも失せ、淡々と重三郎には本心は言わない、重三郎とはもう仕事をしない、と伝えました。そして歌麿は看板娘の絵を取り出して重三郎に見せ、これまで重三郎が自分に対していかに軽んじてきたかを訴えました。反省する重三郎ですが歌麿の心はもうすっかり離れていました。歌麿は、西村屋の仕事が面白そうだからやりたい、吉原への恩返しは自分なりにやる、と言いました。重三郎が土下座して「なんでもやるから考え直して欲しい」と懇願すると、歌麿は「蔦屋の店を俺にくれ」と言いました。さすがにそれは無理だと重三郎が断ると、歌麿は「結局はそうだろ?俺の欲しいものはなに一つくれない。妻子を大事にしてやれ。」と言って家を出ていきました。重三郎は、今まで気づかず歌麿に嫌な思いをさせてきたことを詫び、これまでずっと自分についてきてくれたことに礼を言い、歌麿は当代一の絵師だと改めて認め、体は大事にしろ、と文をしたためて歌麿の家に置いてきました。店に戻った重三郎は皆に、歌麿はもう自分の仕事しないと伝え、歌麿が描いた女絵を見せました。それを見たていは歌麿の秘めた恋心に気づきました。しかしこのとき急に産気づいてしまい、急いで産婆(榊原郁恵さん)に来てもらい、重三郎もていと子の無事を必死に神棚に祈りましたが、子は流れてしまいました。さて松平定信ですが、将軍補佐と大老を辞する代わりに大老を拝命する日をいよいよ迎えていました。田安家として将軍を出す夢は叶わなかったが国の舵取りをする役目になれた、と側近の水野為長(園田祥太さん)と共に喜び、江戸城に入りました。将軍・家斉は、定信の早く下城したいという願いについて今も心変わりはないかと念押しし、定信も同意しました。すると家斉は大老を命ずるどころか、ならばこのまま引退せよ、政に関わることなくゆるりと休め、と言い渡しました。一橋治済も、徳川のため、将軍(我が息子)のため、ご苦労であったと、早く下城を促すものでした。定信が茫然自失となって退室したら、襖の向こうから廊下まで皆が揃って高笑いする声が響いてきました。家斉が自分を頼りにしてくれたあの様子も、老中の本多忠籌や松平信明(福山翔大さん)が急に自分に服従するようになったあの様子も、全ては自分を失脚させるためのことだったのか。老中首座となってからは、人々から嫌われても煙たがられても、自分が正しい・やるべきだと思ったことをやり通してきたのだ。それなのに最後はこの有り様。ぶざまでみじめで怒りしかなくて、定信は一人布団部屋であの部屋の皆を呪いながら涙しました。この出来事は、町の瓦版では定信が自ら引退を願い出たとして触れ回られ、人々はこの失脚劇の大喜びでした。そんな折、かつて大奥総取締だった高岳(冨永愛さん)が突然、定信を訪ねてきました。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇前回とこの回で抱いた歌麿の思い。相手が好きな人に限らず、仕事での会社の上司とか、家族間で平気できょうだい差別をする親とか、思いつくまま好き勝手をやってこっちにシワ寄せをかける配偶者や友人とか、etc... 何かにつけて自分が我慢をしてしまう・させられる人の場合、歌麿の気持ちに自分も覚えがあると思った方は多かったのではないでしょうか。この人のために頑張ろう!と思うその相手は、悪い人ではないけれど、独りよがりで、いつも自分に対して勝手な思いこみをして、こちらの気持ちや事情なんかおかまいなしで、あれこれ何かを頼んでくる。言いつけてくる。物事が順調に動いて一人幸せに浮かれていて、こっちは報われない思いを抱えながらも、気持ちに折り合いをつけながら一人引き受けたことを淡々とこなしている。面倒なことや苦労なことは当たり前のように自分に回してきて、楽していい思いをするのはその人が大事に思う他の誰か。私/俺って、便利で都合のいい人なだけ?ずっと我慢を重ねてきたけど、ある日そう気がついたら、心がぶちっと切れるようにその人から心が離れ、その人が目の前で何かやってても何も感じなくなるのですよね。 まあ重三郎の場合はここまで酷くはなくて悪気もなく、まさか歌麿が自分に?という状況もあったでしょう。それでも自分の思い描いたことの実現のために歌麿をさんざん利用し、その分大切にすればまだよかったけど、ないがしろにしてきたことには変わりないですからね。史実でも重三郎と歌麿は一時疎遠になったようですが、脚本の森下佳子氏、こうきたか!と思いました。
November 13, 2025
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第42回~「招かれざる客」
いったい何が起こっていたのか、全くわからないのですが、昨日からずっとパソコンから楽天ブログに入れませんでした。パソコンからは他のサイトには問題なく入れるのに、楽天ブログの管理画面に入れず、今ようやく入れました。では、2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政4年(1792)9月、老中首座の松平定信(井上祐貴さん)のもとにオロシャの船が根室に来航したと報が入りました。オロシャは漂流して助けた日本人(大黒屋光太夫)を送り返しに来ていて、江戸への来航も希望していました。さらにオロシャは王(エカテリーナ二世)からの勅書を持ち、日本との通商を望んでいました。老中の本多忠籌(矢島健一さん)や松平信明(福山翔大さん)は交易を認めようとしますが、定信はオロシャは日本を襲撃しようとしているのでは?と大反対。少し前までは、オロシャの船が江戸の海に入ってきたら国が滅びてしまうと危惧していたのは本多らで、定信は人心がいたずらに混乱すると林子平の『海国兵談』を絶版にしたほうでした。しかし誰よりもオロシャの動向を警戒していたのは定信でした。そんな中、別件で帝(光格天皇)が父・閑院宮に「太上天皇」の尊号を与えるようだと、定信に報が入りました。再び激怒した定信は武家伝奏の正親町公明(三谷昌登さん)を呼び、どうしても尊号を贈るなら向後一切の禁裏御料を打ち切ると公明に伝えました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、尾張に行商に行っている間に母・つよ(高岡早紀さん)が他界していました。それでも商売のほうは少しずつ回復していって、寛政5年(1793)年明けには身上半減が返上できたことを町の人に報告していました。新年にあたり蔦屋の店先には新作の黄表紙や狂歌集がたくさん並び、中でも歌麿(染谷将太さん)の錦絵は相変わらず人気でした。商売がようやく波に乗り出した重三郎は歌麿に仕事をどんどん頼むつもりでいて、ただそれは歌麿の想定以上の量になるので、歌麿は内心困惑していました。2月になり、武家伝奏の正親町公明を江戸城に呼びつけた定信は尊号の件をしつこく問い質していました。公明は帝はもうあきらめたからと釈明するのですが、その態度に苛立った定信は公明らをお役御免のうえ閉門にすると言いました。老中の本多忠籌と松平信明は、武家が公家を処罰するのは良くないと進言しますが定信は、今はオロシャが日本を狙っている非常時、ご公儀と朝廷の不和はオロシャに付け込まれる、何が何でも自分の考えを通そうとします。忠籌と信明は、やり方が強引過ぎて国の中に敵ばかり作っている定信のことを、一橋治済(生田斗真さん)に相談しました。ただ治済は二人の話を聞いているのかいないのか、定信のこととは全く関係ない美人絵を二人に見せて、あることを問いました。この頃、江戸市中では錦絵の題材となった看板娘が世の男たちの関心を集め、男たちが娘たちのいる店に押しかけていました。店側も娘たちの人気を利用して驚くほど値を吊り上げて商売していましたが、それでも人気は衰えませんでした。この状況を見た他の商人たちは自分の娘の絵を描いてもらうよう、こぞって重三郎の店に押しかけました。歌麿はこんなにたくさん描けないと重三郎に訴えます。しかし重三郎は、弟子にあらかた描いてもらって少し手直しして歌麿の名入れをして出せばいい、と聞く耳を持ちません。歌麿がそれは入銀先や客をだますことになるから嫌だと言っても、この流れに乗れば江戸の町全体の経済が回る、そのためのちょっとした方便くらい許される、とどこまでも強引です。歌麿は北尾重政(橋本淳さん)に相談しました。重政は、忙しいと弟子たちに手伝ってもらうことも多いし彼らも喜ぶと言いました。歌麿は、自分は絵を一点一点ちゃんと描きたい、適当になんとかするのではなく本屋にも向き合ってもらいたいと考えていました。でもそんなこだわりを持つのは自分だけなのか?と悩みました。重三郎と歌麿は絵に対して考え方が全く違うのだと、妻のてい(橋本愛さん)は感じていました。重三郎にとって絵は商いの品(道具)であり、歌麿にとって絵は作品であり子のようなものだと。そんな話の流れでていは、子ができたと重三郎に報告しました。絵を弟子に手伝ってもらうのも有りかと思い直した歌麿は、菊麿(久保田武人さん)に下絵を頼み、菊麿も張りきっていました。そんなところに西村屋与八(西村まさ彦さん)が二代目の万次郎(鱗形屋孫兵衛の次男で西村屋の養子;中村莟玉さん)を伴ってやってきました。万次郎は歌麿の『画本虫撰』を見てすっかり心を奪われ、自分が出す新作の絵を是非、歌麿に頼みたいと強く訴えました。万次郎は『当世美男揃え』などの案を持っていて、歌麿もそれは面白そうだと興味をそそられました。歌麿は結局は今は重三郎の仕事で多忙だからと断ったのですが、与八は看板娘の絵を出し、歌麿は重三郎に都合よく使われているのでは?と言い、歌麿の胸に不満の楔を打ち込んでいきました。さて幕閣ですが、本多忠籌や松平信明ら老中が一斉に松平定信に手をついて今までの無礼を深く詫びていました。将軍・家斉からお叱りを受けた、これからは定信に従うと宣言し、その後で市中で流行る看板娘の錦絵を出しました。忠籌は、市中ではこの絵の娘たちを目当てにした男たちが節約を忘れて金を惜しげもなく使い、それにつられて市中の物の値が上がっている、これは「田沼病」では?と報告しました。錦絵を見た定信はなぜか歌麿の名に目が留まりました。一橋治済から何か指令を受けているのか、その様子を見た忠籌は信明に目配せをしました。ところで仕事が順調に動き出したと思った重三郎ですが、人相見からは絵の出し方で苦情が入り、さらに奉行所からは一枚絵には女郎以外の名を書かないよう、お達しがありました。このお達しのために重三郎は仕事をもらっている吉原に大きな迷惑をかけることになりました。駿河屋市右衛門(高橋克実さん)ら吉原の親父たちも不景気で重三郎を助けてやるどころではなく、むしろ重三郎から吉原に借金を早く返して欲しいくらいでした。そこで重三郎が「女郎の大首絵」を提案すると、扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は入銀無しならと条件をつけました。どちらも金がなくて話が進まないので、市右衛門は代替案として入銀無しで錦絵を作り、その分は借金を返済したことにしてはどうかと言いました。この話は結局それでまとまってしまい、歌麿の女郎絵50枚を重三郎の100両の返済とすることになりました。しかし自分に相談なしで、ものすごい負担となる事を勝手に決められてしまった歌麿はたまったものではありません。借金のカタに自分を売ったと歌麿は重三郎に激しく怒りました。それでも重三郎は、これで皆が助かり歌麿の名も上がるからいい話だろ?と一方的に繰り返すだけです。歌麿の気持ちを無視して、ひたすら頼み込むだけです。じきにていに子が産まれると聞いたとき、重三郎はどこまでも身勝手で、重三郎にとって自分は無理難題も頼めばやってくれる都合のいい人ぐらいにしか考えていないのだと気が付きました。歌麿は「仕方がないからやってやる。」と返事しましたが、心は冷えきり重三郎からすっかり離れていました。歌麿との話も押し通して思い通りになり、さらにていのおなかの子も元気で喜び浮かれる重三郎。でも歌麿は、後日訪ねてきた西村屋の万次郎に、今やってる揃い物が終わったら西村屋の仕事を引き受ける、蔦屋の仕事はこれで終わりにする、と伝えました。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
November 7, 2025
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第41回~「歌麿筆美人大首絵」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政4年(1792)、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)が身上半減に罰せられました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)がその理由を尋ねると、幕府から発禁処分となっている林子平の『海国兵談』と『三国通覧図説』を出版したからで、版木も没収されました。市兵衛は幕府の目を気にしながらも、『海国兵談』には皆が知っておいたほうがいいことが書いてあり、本屋は正しい世の中のためにいいことを知らせてやる務めがあるという信念を持っていました。そして引退を決意した市兵衛は「死ぬ前にもう一度、昔の浮かれて華やいだ江戸の町を見たい。」と重三郎に思いを伝えます。若い頃から市兵衛には世話になっている重三郎は、市兵衛の思いを引き継ぐべく、年明けに新作を山ほど出すことを決めました。さて歌麿(染谷将太さん)の描いた大首絵が刷り上がりました。出来栄えを見た重三郎はもう少し華やかさが欲しいと感じたので、人物の背景を「雲母摺」にするとどうかと提案しました。重三郎は歌麿の「十躰」をバカ売れさせて、歌麿を当代一の絵師にしたい、蔦屋の名も上げたい、江戸を湧きあがらせたい、と様々な意欲に満ち溢れていて、歌麿も仕方ないなと思っていました。そんな話をしていたら瑣吉(後の曲亭馬琴;津田健次郎さん)が歌麿に面と向かって「男色か、両刀か?」と絡んできました。歌麿は瑣吉の話をうまくかわしたけど、その様子をつよ(重三郎の実母;高岡早紀さん)が心配そうに見ていました。つよは後で重三郎に、歌麿のためにも思ったままを無神経に言う瑣吉を店から追い出すように言いましたが、人の気持ちにはどこか鈍感な重三郎には伝わりません。つよは歌麿をもっと大事にするよう、重三郎に忠告しました。つよは時折り歌麿を訪ね、歌麿の心の内を聞いてやっていました。重三郎への思いがまだ消えていなかった歌麿。つよは歌麿を気遣っていましたが、歌麿は自分の描いた絵によって自分がこの時代に生きた証が残ればいいと割り切っていました。そんな歌麿につよは「重三郎の義弟だから私の息子だ」と寄り添い、歌麿も「おっかさん」と呼んでつよには心を開いていました。その重三郎ですが、妻のてい(橋本愛さん)が出した本の案の中にこれならいけそうだと思うのを見つけ、ていと共にかつて田沼派で閉門を受けたことのある和学者の加藤千蔭(中山秀征さん)を訪ね、交渉を始めました。ていは、本当は学問を成したい数多いる女子のために、眺めるだけでも楽しい女性に受けそうな本を作りたいと考え、千蔭流の美しい書物を求めたと千蔭に強く訴えました。さて人物の背景を雲母摺にした大首絵が出来上がったので、歌麿も仕上がり具合を見てみました。陽の光で見ても美しいし、暗い所で灯りをともしてかざすとさらに美しい錦絵になり、歌麿も思わず感嘆の声をあげました。後はこの錦絵をどう売り出すか、重三郎は知恵を巡らせていました。一方でそのころ幕閣内では老中首座の松平定信(井上祐貴さん)が水野為長(園田祥太さん)から、老中・本多忠籌(矢島健一さん)たちが新しい一派を作り始めていて、一橋治済(生田斗真さん)に接近している、と報を受けました。本多らは、定信に政を任せておくと本当にオロシャの船が江戸の海に入ってきたら国が滅びてしまう、と危惧していました。報を聞いた定信は激怒しましたが、定信自身も将軍補佐の役割がもうじき終わって今の権力がなくなる立場にありました。そこで定信は徳川御三家で尾張の徳川宗睦(榎木孝明さん)に会い、政での一橋の横槍を訴え、自身も将軍補佐のお役御免が近いことを宗睦に匂わせました。ちょうどそのころ第11代将軍・徳川家斉(城桧吏さん)に嫡男の竹千代が誕生し、定信は祝いに参上した際に「将軍補佐」「奥勤」「勝手掛」の辞職を願い出ました。突然の申し出に驚く家斉、するとそこへ尾張の宗睦が来て、今は日の本の国を立て直しさらに外国の船が日の本を窺っているときであり、この局面を乗り越えられるのは定信だけと進言しました。定信は将軍補佐と勝手掛を続行することになりましたが、これは全て定信と宗睦が密かに打ち合わせた読み通りのことでした。ところで重三郎はというと、市中で大流行りしている人相見を利用して、店に客を呼び込んでいました。そして人相見の後で客に合う錦絵を勧め、錦絵を今買った方には喜多川歌麿先生の名入れが入ると宣伝して、歌麿の名を高めつつ錦絵をどんどん売っていきました。また妻のていは雲母摺の錦絵を見て、背景で印象が変わることに気がつき、次に出す本を文字を白に、背景を黒にしてはどうかと提案、重三郎も賛成し、『源氏物語』の一部を抜粋して千蔭流で書かれた書物の『ゆきかひふり』が出来上がりました。重三郎が本の商談で尾張に向かうことになり、出発の日につよが髪を結い直すと言い出しました。つよは重三郎の髪を結いながら、まだ子供だった重三郎を父母が揃って捨てた(駿河屋に預けた)理由を語りました。つよは重三郎を幼名の「珂理」で呼び、重三郎が強く生きてきたことを認めました。でも同時に、たいてい人は強くなれなくて強がっている、それをわかって有難く思うよう、思いを伝えました。話を聞くうちに気持ちが柔らかくなったのか、重三郎はそれまで「ババア」と呼んでいた母を「おっかさん」と呼びました。息子と母がやっと互いに認め合えた瞬間でした。さてこちらは江戸城で、京から武家伝奏の正親町公明(三谷昌登さん)が使者として来ていて、帝(光格天皇)が父・閑院宮に「太上天皇」の尊号を与える件が、一橋治済を通して話が進んでいるとのことでした。自分が不承知な件が勝手に進んでいて、激怒した定信は治済に会って苦情を言いましたが、治済は定信が将軍補佐として家斉に出した「御心得之箇条」を引き合いに出し、帝が父に尊号を贈ることに定信が反対するのはおかしいと反論しました。しかし定信はそれでも引き下がらず、ご公儀の威信に関わることなので自分に任せて欲しいと言い、尊号をとりやめる文を自らしたためて朝廷に訴えました。そうこうしている最中に、オロシャの船が来航したと報が入りました。(1792年9月、ラクスマン、根室に来航)◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
October 31, 2025
-
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第40回~「尽きせぬは欲の泉」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政3年(1791)老中首座の松平定信(井上祐貴さん)は老中・本多忠籌(矢島健一さん)と松平信明(福山翔大さん)から今の改革が厳し過ぎるからもう少し緩めるよう進言されますが、耳を貸すことなく、さらに厳しくしていきました。そして自分にうるさく言う者たちは遠ざけ、お気に入りだけを傍に置くようになりました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、身上半減の罰を逆手にとった商売も続かなくなりました。そこで次の一手として昔の面白い版木を刷り直して本にしようと考え、鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)に版木を安く売ってほしいと頼みました。喜右衛門は山東京伝(本名は北尾政演;古川雄大さん)の新作が取れたら古い版木を譲ると言ってくれ、二人で京伝を訪ねました。でも京伝は手鎖の刑の後でもう書く気はすっかり失くなり、その代わりに京伝の家に居候している滝沢瑣吉(後の曲亭馬琴;津田健次郎さん)を重三郎に紹介しました。戯作者の瑣吉はやたら気が強くて自信家で、書いた作品も全体に独りよがりでしたが、どこか面白いものを感じました。絵師の勝川春章(前野朋哉さん)が連れてきた弟子の勝川春郎(後の葛飾北斎;くっきー!さん)もかなりの変わり者で、瑣吉とは反りが合わずに会う早々いきなり喧嘩に。でもそんな二人でしたが重三郎にうまく乗せられて、京伝の名を借りた作品を二人で1冊仕上げました。重三郎は新作を持って日本橋に来て以来ずっと良くしてもらっている須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)に相談に行きました。黄表紙を他の国にも売りたいから地方の書物問屋を教えて欲しいという重三郎の頼みを市兵衛は快諾してくれました。ただ狂歌絵本はこれからどうなるのかを考えたとき、絵師の歌麿(染谷将太さん)は栃木のご贔屓のところに行ったきっり江戸に帰ってこないし、狂歌師の宿屋飯盛は江戸払いになっています。黄表紙は教訓的になり狂歌は格調高いものに、錦絵は相撲絵や武者絵が流行りになり、松平定信の望み通りの世になっていってました。(ただ定信本人も少々思うところがあるようです)こんな世の流れの中で歌麿が描いた亡ききよの絵を見た重三郎は、今なら女絵を出せば間違いなく人々の目を引く、歌麿が当代一の絵師になると確信しました。重三郎は、今は自分から遠ざかり絵を描く気力もなくなっている歌麿に、諸々の思いを吹き飛ばして描きたい思いを起こさせる手立ては何かないかと考えました。重三郎はその材料探しに瑣吉と一緒に市中の美人詣でをしました。瑣吉は最近は茶屋のきた(椿さん)や煎餅屋のひさ(汐見まといさん)が美人で評判で男たちに人気とのことでした。これは不景気で吉原に行けない分、巷の美人に男たちが群がるということでもあり、そんなことを考えていたら義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)が蔦屋に来ていて、最近の吉原では相手の人相を見ていろいろ判断する相学が流行りだと教えてくれました。「女絵と相学」ーーこれだ!とひらめいた重三郎は、栃木にいる歌麿に会いに行きました。歌麿は贔屓にしてくれる栃木の釜屋伊兵衛(益子卓郎さん)の家で仕事をしながら世話を受け、静かに暮していました。庭の草木や虫を眺めてふと生命を感じた時、あの時に重三郎から「生き残って命を描くんだ!」と言われたことを思い出しました。そんな時に重三郎が江戸から栃木までやってきました。重三郎は歌麿にまず「鬼の子」と言ったことを詫び、かたくなな歌麿に錦絵を出して欲しいと、手をついて頭を下げて頼みました。歌麿は「金に困った蔦屋を助ける当たりが欲しいだけ。この機に重三郎の名を上げたいだけ。」と迷惑そうに返しました。重三郎は歌麿が以前きよを大きく描いた絵に「婦人相学 清らかなる相」と付箋を付けて出し、こういうのを描いて欲しいと言うと、同席していた釜屋伊兵衛が相学のことを尋ねてきました。重三郎は伊兵衛に、江戸では相学が大流行りの兆しを見せている、相学の本を出すには女のタチを描きわける絵師がいるが、それができるのは喜多川歌麿しかいない、と説明しました。そして歌麿に「どうかお願いします。」と改めて頭を深く下げて頼みました。それでも歌麿はきよのために女は描かないと言うので、重三郎は「歌麿の絵を見たいと思うのは贔屓筋ならみな同じ。自分を見て絵をいっぱい描いてもらったきよは幸せだった。あの世で自慢している。」と思いを伝えました。そして最後に「描くかどうかは歌麿が決めればいい。」と言うと、歌麿は江戸に戻ることになりました。重三郎は歌麿が描くための見本となる女を集めて描かせました。自分が描いた絵に後から後から注文をつけてくる重三郎に歌麿もさすがに時折りは嫌になりました。でも重三郎の「思わずじぃーっと見てしまう絵が欲しい」という言葉に納得したのか、歌麿は小道具を使ったら?とか自分で案を出したりして、作業を進めていきました。ところで、もう執筆活動はしないと決めていた京伝は次の仕事を煙草入れの店を始めることにし、資金集めが必要でした。重三郎と鶴屋喜右衛門が段取りをして京伝の書面会を開くことになり、当日は広い座敷に大勢の贔屓が集まりました。京伝は初めは派手過ぎると気おくれしていましたが、いざ座敷に入って人々から歓声が上がると、やはり気分は良いものです。皆から名入れを求められ、歌を歌って注目が集まると、やっぱり書き物を続けたくなってきました。結果、重三郎に乗せられたかもしれないけど、京伝自身の中にももてたい・書きたいという“欲”があったからでした。同様に、歌麿にも描きたい“欲”がよみがえっていたのでした。そんなことを思いながら重三郎が喜んでいたら、須原屋市兵衛のことで何か報せが入りました。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
October 23, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第39回~「白河の清きに住みかね身上半減」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政2年(1790)最愛の妻・きよを失い半ば狂ったようになった歌麿(染谷将太さん)は何日も食事をとらず、まるできよの後を追うかのようでした。歌麿を案じた蔦屋重三郎(横浜流星さん)は母・つよ(高岡早紀さん)を呼び、つよには少し心を開く歌麿の見守りを頼み自身は仕事がたまっている店に戻っていきました。老中首座の松平定信(越中守;井上祐貴さん)による出版統制が続き、なんとかしなければと考える地本問屋の皆は鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)が代表になって、水面下で奉行所の初鹿野信興(田中美央さん)らとやり取りを重ね、寛政2年10月、正式に地本問屋の株仲間が発足となりました。これにより自主検閲での本の出版が許され、やはり定信の改革のせいで苦しい状況にあえぐ吉原の皆を救うために、重三郎はその内容に好色が含まれる本を出そうとしました。行事の吉兵衛(内野謙太さん)と新右衛門(駒木根隆介さん)はこの本は出せないと判断しますが、重三郎は「教訓読本」の袋に入れて中を見せないようにして出せばいいと強く主張。吉兵衛と新右衛門は渋々認めて出版となりました。重三郎が打ち合わせから帰宅すると、栃木に行く歌麿に同行するためにつよが旅支度をしていました。自分から離れたいと言う歌麿に、あの時の言葉の真意をわかってもらおうと重三郎は歌麿に会いに行こうとしました。しかしつよから、それは重三郎が自分の気持ちを歌麿に押し付けたいだけだと叱られ、重三郎は思いとどまりました。明けて寛政3年(1791)、重三郎は山東京伝(本名は北尾政演;古川雄大さん)が書いた『錦之裏』『仕懸文庫』『娼妓絹籭』の3作を袋に入れて販売し、売れ行きは好調でした。しかし3月、その内容がお上に知られて重三郎と京伝は奉行所に連行され、本は絶版となりました。奉行所での詮議では、重三郎はご公儀を謀ったとして老中首座の松平定信が見分に出てきました。重三郎は定信に対し、臆するどころか皮肉を交えた挑発するかのような物言いで自分の考えを堂々と述べていきました。ただやはり、その不遜な態度は定信のカンに障って怒りとなり、重三郎は引っ立てられて厳しい責めを受けることになりました。夫・重三郎の身を案じるてい(橋本愛さん)のために地本問屋の仲間が公事宿の知り合いの飯盛の男を呼んでくれていました。飯盛は「厳しい裁きは朱子学の説くところと矛盾している。」と教えてくれ、ていは重三郎の命乞いをするために長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)を介して、定信の師である柴野栗山(嶋田久作さん)に会い、栗山に朱子学で問答を挑みました。てい:子曰 導之以政 齐之以刑 民免而無恥 導之以德 斉之以礼 有恥且格栗山:君子中庸 小人反中庸 小人之反中庸也 小人而無忌憚也「重三郎は二度目の過ちであり、赦しても改めぬ者を許し続ける意味がどこにある?」と問いました。てい:見義不為 無勇也重三郎は、女郎は揚げ代を倹約令のために値切られ嘆いていると言っていた、だから本で遊里での礼儀や女郎の身の上などを伝え、礼儀を守る客を増やしたかったのだろう、と栗山に述べました。さらに「女郎は親兄弟を助けるために売られてきた孝の者であり、不遇な孝の者を助けるのは正しきこと。」と考えを述べ、最後に「どうか儒の道に損なわぬお裁きを!」と強く訴えました。その後、それぞれに裁きが下りました。京伝は手錠鎖50日、吉兵衛と新右衛門は江戸所払いに、そして重三郎には「身上半減」という罰が下りました。ただ奉行所のお裁きが下る場であっても重三郎には真摯な態度が見受けられず、ていはたまらず進み出て重三郎に平手打ちをして、いつも自分の考えを言いたいだけだと泣きながら責めました。そして後日、地本問屋の皆に詫びを入れるときでもまたふざけてしまい、その場の誰もが腹立ちの顔になって、ふだん温厚で声を荒げない鶴屋喜右衛門から「そういうところですよ!」と叱られてしまいました。さて身上半減で重三郎の店がどうなったのかというと、金だけでなく店にある全てのもの---看板・のれん・畳・版木・在庫の本など、あらゆる物が半分にされてしまいました。定信の几帳面さに呆れたり、ていは情けなくて涙したり。しかしその様子を見に来た大田南畝(桐谷健太さん)は面白くてたまらず大笑いし、集まっていた町の人たちも笑い出しました。「世にも珍しい身上半減の店」でひらめいた重三郎はこの状況を逆手にとって「罰を受けても生き残る。縁起がいいよ!」と店に残る本を売り出して賑わっていました。その様子は松平定信にも報告が入っていました。定信は「あまりに厳しい処分は朱子学との矛盾を生み、ご公儀の威信を損なう。身上半減を与えられる者こそ賢者にふさわしい。」という栗山の助言を受けいれたのでした。ところでそのころ江戸では押し込み強盗が市中を荒らしていて、強盗は平蔵が捕らえて厳しい処罰をしたものの、この件について老中たちからは定信に、これらは倹約令の反動であり、倹約令や風紀の取り締まりを切り上げるべきだ、と進言がありました。本多忠籌(矢島健一さん)は定信に「帰農令があっても、生活が苦し過ぎる百姓にはもう戻りたくない。人は正しく生きたいとは思わない。楽しく生きたいのです。」と切に訴えました。また松平信明(福山翔大さん)は、このままでは田沼以下の政と誹りを受けると進言し、老中2人の言葉は「自分は常に正しい」と信じて強気で改革を進めてきた定信には堪えるものでした。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇今回、蔦屋重三郎(横浜流星さん)を見てつくづく思ったこと。それは何かにつけてすぐにおちゃらけて笑いを取ろうとする人は、時と状況を間違えるとマイナスになって、周囲を凍りつかせるか怒らせるかになる、ということでした。また奉行所で松平定信(井上祐貴さん)に詮議を受ける場面では、一言一言いちいちカンに触る言い方をして定信を怒らせ、自分で罪を重くしています。重三郎は自分の考えに自信があり、自分が必死に訴えれば相手はわかってくれると信じる人なのでしょう。でも自分に思いがあるように、相手にも思いがあるのです。重三郎の必死の訴えを「受け入れる」かどうかは相手次第です。歌麿(染谷将太さん)は今は聞きたくなくて重三郎から物理的に距離を置いたし、定信は自分に逆らうとは許せん!となりました。このドラマはこれまで、重三郎のプラス思考で困難を乗り越えてきたようでしたが、今回は重三郎のこのおめでたい思考が各所で相手をイラつかせた感じがしました。
October 15, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第38回~「地本問屋仲間事之始」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 のあらすじ及び感想日記です。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政2年(1790)蔦屋重三郎(横浜流星さん)は山東京伝(本名北尾政演;古川雄大さん)が別の本屋から内緒で本をだしていて、しかもそれが倹約令で自分たちを締め付ける老中首座の松平定信(井上祐貴さん)が喜びそうなものであることに腹をたて、京伝とは喧嘩別れの状態になりました。歌麿(染谷将太さん)の弟子の菊麿(久保田武人さん)からきよ(藤間爽子さん)の容態が悪いと聞いた重三郎は、医者を連れてきよを見舞いました。医者によるときよはそう毒(梅毒)に侵されていて治る見込みもないとのことでした。きよが目を覚ましたとき、歌麿は重三郎と話をしていたのですが、その光景を見たきよは激しく心を乱してしまい、歌麿はやむなく重三郎に帰ってもらいました。歌麿は今は愛する妻のきよの看病がなにより大事なので重三郎は仕事を頼むことができず、他の絵師を当たっていました。そのころ市中では倹約令による不景気から町の治安が乱れ、悪玉提灯を手に暴れ回るならず者が各地に続出し、これは松平定信の政が原因と人々にささやかれていました。ただ当の定信は、こうなるのは初めから見込んでいた、田沼病の者たちがあぶり出されたと全く驚いてませんでした。ただ対策の必要はあるので、定信はならず者を取り締まっていた長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)に人足寄場を作って彼らを更生させるよう命じました。平蔵は自分には無理だと固辞しましたが、定信から町奉行にしてやってもよいと言われ、亡き父のためにも役目を引き受けました。さて京伝と喧嘩別れになっている重三郎は今後の仕事のためにも鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)の仲介で京伝と再会しました。重三郎と喜右衛門は京伝に自分たちの仕事を最優先でやることを条件に、作料に加え年30両を支払うと伝えました。しかし京伝は、自分は好きな仕事を楽しくやりたいだけで、世に抗うとか難しい仕事は嫌で、浮雲みたいに気ままに生きていたいと、笑いながら言うだけでした。甘えが許されない吉原の女たちを見てきた重三郎は京伝のそんな態度に腹が立って「気ままに生きていけるのは周りが許してくれてたからだろう!」と怒りを露わにしました。そして「今こそてめえが踏ん張る番じゃないのか?」と京伝に強く迫っていたら喜右衛門が二人の口論を止めました。喜右衛門は奉行所から呼び出しを受け、戯作や浮世絵などを出すときの規制を言い渡されました。それは松平定信が、黄表紙や浮世絵は贅沢品であり世によからぬ考えを刷り込み風紀を乱す元凶と考えたからで、今後一切新しい本を仕立ててはならぬ、とありました。喜右衛門と重三郎は対策のために、すぐに江戸の地本に関わる人たちを一同に集めました。そのお達しの文面から重三郎が出した黄表紙が取締りのきっかけとなったことは明らかで、重三郎は土下座して幾度も謝りました。しかし地本問屋たちの怒りは収まらず、怒号が飛び交いました。喜右衛門は皆を静め、重三郎に何か手立てがあるのか問いました。重三郎はお達しの中にある「新規の仕立てをどうしても作りたい場合は奉行所の指図を受ける」という部分を逆手にとって、江戸中の地本問屋が山のように新作の草稿を抱えて、次々と奉行所に指図を受けに行くのはどうかと言いました。仕事が増えた奉行たちが音を上げて、そのうち指図なしでよいとなるのでは?という考えでした。とはいえ草稿はすぐに作れるものではなく、地本問屋たちはまた声を荒げて批判するばかりなので、その様子を見かねた勝川春章(前野朋哉さん)が戯作や絵師の仲間たちに重三郎の助太刀を呼びかけました。春章たちが協力を申し出るとその様子を遠巻きに見ていた京伝も動き出し、重三郎は嬉しくて目に涙がにじんできました。そして喜右衛門が地本問屋の皆に呼びかけると彼らもここは一つ一緒にやるべきだと思い直し、その後はいくつかの組に分かれて草稿作りが始まりました。後日、地本問屋たちがそれぞれ山のように草稿を抱えて奉行所を訪れて指図を仰ぐと、狙い通り役人は悲鳴をあげました。重三郎は次は長谷川平蔵宣以への根回しを始めました。吉原に呼んでもてなし、平蔵は初めは警戒していましたが美味い酒を飲むと「やはり吉原はいい」と気分を直しました。その時、二文字屋の女将のはま(中島瑠菜さん)と先代のきく(かたせ梨乃さん)が入ってきて、平蔵に50両差し出しました。賄は受け取れないと拒否する平蔵。でも重三郎が、これはかつて花の井のために平蔵が出してくれた金であり、実はそれで二文字屋が救われたのでこれは返金になると説明すると、平蔵は花の井の名で昔を懐かしんでいました。それから重三郎は、人足寄場のお役目のために何かと持ち出しが多い平蔵のために利息として50両を差し出し、さらに駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が50両を平蔵に差し出しました。「倹約が続いてこのままでは吉原も地本問屋もだめになる。人足寄場でならず者を救うように、身を売るよりほかない吉原の女郎たちを救って欲しい。」と市右衛門と重三郎は平蔵に懇願しました。切羽詰まった吉原のために、平蔵は松平定信からある言葉を引き出すように頼まれていました。平蔵は定信との話の中で上方のことを引き合いに出して将軍家の威光を第一とする定信から狙い通りに、地本問屋も株仲間を作り、その中で改めを行って触れに触らぬ本を出す許しを得ました。後日、重三郎と喜右衛門は京伝が本を出した上方の大和田と会い、黄表紙を盛り立てるためにも株仲間に入るよう言いました。しかし大和屋にそのつもりはなく、上方では黄表紙が人気だから安く仕入れさせて欲しい、京伝はこのまま鶴屋と蔦屋のお抱えでいいと決着が着きました。ただ重三郎が定信のお触れへの対処で奔走していたころ、歌麿の妻のきよはあの世に旅立っていました。最愛のきよの死で心の支えを失った歌麿はおかしくなり、きよの遺骸の傍で何枚も何枚もきよの絵を描き続けていました。重三郎が歌麿を力づくで押さえ、傷んだきよの遺骸を弟子の菊麿たちが運び出しました。「お前は鬼の子なんだ。生き残って命を描くんだ。それが俺たちの天命なんだ!」重三郎の言葉を受け入れられない歌麿はわめいて暴れるだけでした。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
October 7, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第37回~「地獄に京伝」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回から感想日記の形式を変えて、全体のまとめを最後にもってくることにします。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇寛政元年(1789)、老中首座の松平定信を皮肉るために恋川春町の『悦贔屓蝦夷押領』を刊行したことで定信の怒りを買い、春町を自刃させてしまった蔦屋重三郎(横浜流星さん)。『鸚鵡返文武二道』を書いた朋誠堂喜三二(本名は平沢常富)は国元に戻ることになり、大田南畝は処罰を恐れて筆をおき、他の地本問屋が抱えていた武家の執筆者たちも次々と本を書くことをやめ、その影響は地本業界を悩ませることにもなりました。あと頼みの綱となるのは町方の執筆者たちで、重三郎は山東京伝(本名は北尾政演;古川雄大さん)の弱みをついて何か書かせることにしました。一方で歌麿(染谷将太さん)は歌麿の絵を贔屓してくれる栃木の豪商・釜屋伊兵衛(益子卓郎さん)から依頼を受け、伊兵衛の屋敷を飾る襖絵を描くことになりました。帰宅して妻のきよ(藤間爽子さん)に大きな仕事をもらったと報告し、きよと一緒にいれば何でもできると幸せをかみしめていましたが、きよの体には何かの病の異変が出始めていました。文武と質素倹約を奨励し遊びや贅沢を禁ずる松平定信(井上祐貴さん)の政策に重三郎らは息がつまる思いで暮らしていましたが、定信は自分が良しとする政策をさらに強化していきました。その一つが「棄捐令」で札差から武家が借りた金を帳消しにさせ、武家の借金を救うというものでした。その案はあまりにも乱暴で他の老中たちは先々を危惧しましたが定信は耳を貸さず、本多忠籌(矢島健一さん)は定信のやり方を特に案じていました。遊びを禁ずる定信のために政策で市中の遊女たちは行き場を失い、大勢の遊女たちが吉原になだれ込みました。また厳しい倹約政策のため吉原全体でも客が減り、貸した金を棄捐令で踏み倒された札差たちも吉原に来られなくなり、吉原の親父衆たちは皆どうしたものかと頭を抱えていました。吉原を救いたい重三郎は歌麿と政演(京伝)を呼び、歌麿には絢爛豪華な錦絵を、政演には倹約のやり過ぎを風刺する話を書くように依頼しました。ところがその時その話を廊下で聞いていたてい(橋本愛さん)が我慢できなくなり、二人にどうか書かないで欲しいと話に割って入ってきました。ていはそれをやると二人だけでなくこの蔦屋もどうなるかわからない、夫・重三郎の吉原を救いたい思いは立派だが所詮は市井の一本屋、自分たちが倒れたら志を遂げられない、黄表紙は今は控えて、人の道を説いた昔の青本でどうかと主張しました。政演は温故知新で青本もいいと賛同でしたが、重三郎はそれでは春町の気持ちが報われないと反対、しかしていは春町は自刃することによってこの蔦屋を守った、春町だってお咎め覚悟のことは望んでいない、と強く言い返ししました。重三郎の頑なな態度を歌麿は、春町や田沼意次や平賀源内らの他、吉原の人たちへの思いを抱えていることも、上からの締め付けは立場の弱い者たちにだんだんとツケが回っていくという重三郎の考えも理解していました。そんな話をしながら政演が歌麿が描いた襖絵を見たとき、歌麿のありのままの心を政演は深く感じていました。新刊をどうしたらと考えた歌麿と政演は後日、重三郎に黄表紙ではないけど女郎と客をネタにした「いい客を増やす、育てる本」を出したらどうかと提案しました。さてそのころ江戸城では、松平定信が大奥の無駄遣いを徹底的になくそうと、反物や小物や参詣や遊山など削れる部分を一覧表に書き記した指図を老女の大崎に渡していました。ただそれはあまりに締め付けが厳しく、大崎は一橋治済(将軍・家斉の実父、生田斗真さん)にこれでは御公儀の威光に関わると嘆願し、治済から定信に話がありました。治済に強気で反論する定信に治済は別件で、朝廷より話がきている帝の父に太上天皇の尊号を贈ることについて問い、定信は御三家とはかったうえでと返答しました。御三家で紀州の徳川治貞(高橋英樹さん)の具合がよくないと聞いた定信は、すぐに見舞いに伺いました。治貞は定信の締め付け的な政に対する周囲の意見を耳にしていて、「物事を急に変えるのは良くない」と和学者の本居宣長が言っていたと伝え、定信の考えは間違ってはいないが急ぎ過ぎると人はその変化についてこられない、と諭しました。治貞は続けて「全ての出来事は神の御業の賜。それを善だ悪だと我々が勝手に名付けているだけだ。己の物差しだけで測るのは危うい。」と定信に説きました。それでも定信は、我が信ずるところを成し得なければならないと治貞に考えを述べました。何日かたって政演(京伝)が新作『傾城買四十八手』を書きあげ、歌麿と一緒に原稿を重三郎のところに持ってきていました。それを重三郎は表情を変えずに読んでいて、廊下を通りがかったみの吉(中川翼さん)に声をかけ、原稿を読んでもらいました。みの吉は重三郎が声をかけたのも気づかぬほど夢中に読み進めていて「自分がこの場にいるみたいだ」と言い、重三郎自身も正直なところ「景色が目にうかぶ」と言い、同じ感想でした。重三郎は政演の才能を認め、原稿を買い取らせて欲しいと深々と頭を下げました。政演は吉原に月の半分ほど通ってしまう惚れた女、座敷餅花魁の菊園(望海風斗さん)がいました。この暮れには年季が明ける菊園は政演に自分を身請けして欲しいと言い、政演に1冊の本を差し出しました。それは当時流行っていた心学の本で、政演と仕事がしたいという他の本屋が菊園に口利きを頼み、礼も弾むとのことでした。一方、江戸城では太上天皇の尊号の件を定信が不承知と返答したことを一橋治済は改めて定信に問うていました。定信はこれは御三家も老中も同じ意見だったから上奏するように決したと言い、定信の生真面目さが治済は面倒なようでした。そこへ老女・大崎が罷免されたと報が入り、それは大崎が不正を行ったことによる定信の判断だったのですが、大崎は一橋治済の腹心でもあったので、治済の内には密かに怒りが湧いていました。明けて寛政2年(1790)正月、蔦屋では新刊が並びました。しかし世は質素倹約で客足は少なく、店は寂しいものでした。そこに鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)が入ってきて、政演が別の本屋から出した『心学早染艸』の本を差し出しました。本の内容は松平定信が喜びそうなものであり、重三郎の考えとは対極のものでした。腹が立った重三郎は吉原にいる政演のところに乗り込みました。「こんな面白い本だと皆が真似をして定信を担いでしまう!」と怒る重三郎に政演は「どっちの味方とかどうでもよくまずは本が面白いことが大事だ!」と反論しました。それでも聞く耳もたずで自分の考えを押し通そうと怒る重三郎に政演は嫌気がさして、もう重三郎の仕事はしないと宣言しました。◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇今回気になったのは、自分の考えを強気でどこまでも押し通そうとする、対極にいる2人の男ーー蔦屋重三郎(横浜流星さん)と松平定信(井上祐貴さん)でした。どちらも聞く耳持たずで、まあ良い言い方をすれば自分という人間に対して自信があって超プラス思考なんでしょう。でも自分の考えが絶対だというのが顔にも現れていました。特に為政者である筆頭老中の定信に対し、彼らなりの人生経験からそれはまずいのではと案じる老中たちがいて、その中でも本多忠籌(矢島健一さん)がここは思い切って進言すべきかと悩む姿が印象的でした。また御三家で紀州の徳川治貞(高橋英樹さん)は遠縁でもある定信に何かと味方してきたけど、ますます勢いで突き進もうとする定信を案じていました。定信を優しく諭しても、定信は「でも自分はこうする」というのが見えて、彼の心に響いていないのが残念そうでした。若さの勢いを案じる人生のベテランさんたち。これはいつの時代も同じ光景があるのでしょうね。ただ物語の流れとは別に、さすがベテランの演技と思ったのが扇屋宇右衛門を演じる山路和弘さん。ラストで重三郎が乗り込んできてドタバタになり、迷惑をかけた隣りの客に謝りながら直しているシーンです。画面手前のメインを壊さないよう、でも「背景の人物たちはこうしている」という動きが印象的でした。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう
October 1, 2025
-
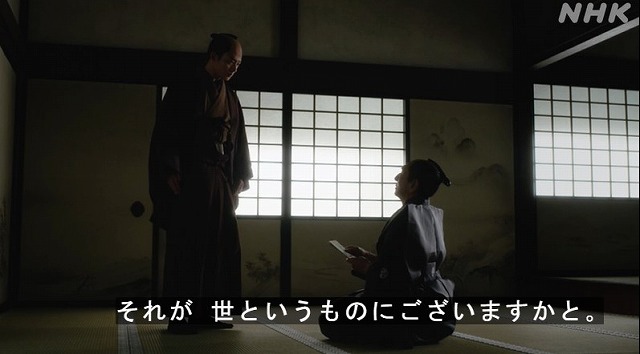
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第36回~「鸚鵡のけりは鴨」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回で感じたのは、上に立つ者の行動の対比でした。松平定信(井上祐貴さん)は怒りに任せて恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)を呼び出して詰問しようと考えます。でも最高権力者の怒りが想像できるから春町はすぐには応じられません。春町の殿・松平信義(林家正蔵さん)は春町を理解し、誇りに思う家臣の一人として、春町を生かすためになんとか守ろうとします。駿河屋市右衛門(高橋克実さん)も春町を逃がそうと、バレたら厳しいお咎めを受けるのを承知で蔦屋重三郎(横浜流星さん)の頼みをきいて、偽の人別を作ってやりました。人生経験と人間性がある信義や市右衛門は、春町を助けてやろうと知恵を巡らせ、定信に嘘の報告をしたり偽の人別を作ったりと自分がやってやれる行動しました。若さと、人生経験が少なくて自分の考えが何でも通ると思う定信は、怒りの勢いで春町の処罰しようとし、でもそれが結果として死を招いたと知って、定信は若さゆえ激しく動揺して後で涙しました。ただ春町が死を選んだのは、我が殿・信義のためかなとも思いました。自分の才能を認めてくれた、自分を誇りに思ってくれた、ギリギリまで自分を守ろうとしてくれた殿です。その殿を守るためにも、思い残すことなく自害を選んだのではと感じました。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 寛政元年(1789)2月、蔦屋重三郎が出した本は世間で大人気となり、飛ぶように売れていましたが、その内容は老中首座の松平定信(井上祐貴さん)の治世を皮肉るものでした。一方、定信のほうは文武に長けた者を登用しようとしても次々と辞退していき、どうしたものかと悩んでいました。そんな折に側用人の本多忠籌(矢島健一さん)の家老が賄を受け取っていると知り、定信は激怒して厳しく叱責しました。ただ忠籌は、今はお役目をもらうと持ち出しが増えるから大したうまみがない、登用したい者が辞退するのはそのためと定信に進言しました。それでも定信は公儀への奉公に対する理想を掲げて耳を貸そうとせず、忠籌は世のことを知って欲しいとばかりに重三郎が出した本を定信に差し出しました。忠籌が差し出した本を読んだ定信は、自分の政が笑いのネタになっているのを見て、これはもはや謀反!と激怒、早速役人を蔦屋重三郎(横浜流星さん)の店に向かわせ、朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)が書いた『鸚鵡返文武二道』他3作の絶版を命じました。定信は喜三二の主家である秋田藩の佐竹義和を呼び出して詰問、激しい怒りで涙する我が殿を見て喜三二はもう筆を折ることにしました。恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)の主の松平信義も定信に呼び出しを受けたのですが、信義はとりあえず春町が病気で隠居したとごまかしました。そんな話をしていたら平秩東作が病だと報が入りました。重三郎は須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)と大田南畝(桐谷健太さん)と共に東作を見舞いました。東作の病は重く、平賀源内が枕元に来たという話をする東作はもう長くないと誰もが感じました。源内は世界がどんどん進むのを肌で感じ、自身もまた新しい世を作り出そうとしていた男で、田沼意次も同じ考えでした。でも松平定信の政で日の本が100年前に逆戻りし、ますます世界から取り残されていく様が悔しくて源内が化けて出てきたのだと市兵衛は思いました。そんな頃、蝦夷地では松前藩の圧政に対してアイヌ人が蜂起し、松前道廣がすぐに鎮圧はしたものの蝦夷の民の恨みは深いと報告がありました。ならばと松平定信はこの機会に蝦夷地を天領としては、と徳川御三家の当主らに進言しました。紀州藩の徳川治貞(高橋英樹さん)は定信に味方してくれましたが、尾張藩の徳川宗睦(榎木孝明さん)は、松前藩は反乱を鎮圧して功を立てたから天領にして所領を取りあげるのはどうかと反対でした。定信はそれでも自説を強く主張しましたが、一橋治済(生田斗真さん)から、その考えは定信が嫌う田沼と同じ、民もそう思っている、と指摘されそれ以上何も言えなくなりました。『悦贔屓蝦夷押領』を読んだ定信は、それが自分の政への痛烈な皮肉であることに気がつき、倉橋格(=恋川春町)の呼出を命じました。呼出に応じて釈明しても下手をすれば自分はお手討ちで主家の小島松平家が取り潰しとなるのでどうしたらと春町が悩んでいたら、いっそ別人になればと重三郎は言いました。それもありかと思った春町は主君の松平信義(林家正蔵さん)に相談、支度が整うまで信義には定信に頭を下げてくれるよう頼みました。信義は、1万石の小名の当家にとって恋川春町は唯一の自慢であり、当主の自分にとっても密かな誇りだった、春町の筆が生き延びるならいくらでも頭を下げると言ってくれました。我が殿の自分への愛情に春町は胸が熱くなりました。しかし時間稼ぎの信義の嘘は定信には通用せず、信義は春町に今すぐ逐電するよう命じました。朋誠堂喜三二が国元に戻る日が近づき、吉原では蔦屋主催の大送別会が開かれ喜三二と縁のあった人たちがたくさん集まりました。互いに酒を酌み交わし賑やかに囃しそれぞれに芸を披露し、そして北尾重政が本の名入れを頼むと他の皆も次々と自分の持ち物に名入れを頼んでいました。吉原の親父衆は皆喜三二の仕事ぶりを讃え、他の人たちも口々にもう一度何か作品をと喜三二に頼んでいました。でもそれは重三郎が江戸を去る自分へのはなむけとして仕組んだんだ、ということも喜三二はわかっていました。宴会の頃合いを見計らって駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が重三郎に声をかけ、二人は座を外しました。人目のない場所で市右衛門が重三郎に渡したものは、春町が逐電するときのための偽の人別でした。重三郎を幼い頃から育ててくれ、厳しかったけど独立した今でもこうして何かあれば危ない橋を渡ることであっても力になってくれる市右衛門でした。顔見知りの多い春町だから気を配るよう言葉を添えてくれる親父様の気持ちを重三郎は有難く思いました。しかし重三郎たちの準備もむなしく恋川春町は一人自害をしてしまいました。朋誠堂喜三二とともに重三郎が春町の弔問に行くと、妻のしず(谷村美月さん)から辞世の句を渡されました。そのとき重三郎は文机の横にあるくず入れの中に破られた文を見つけ、しずの許しをもらって紙片をつなげてみました。復元してみるとそれは重三郎にあてたものでした。「別人で生きることを考えたがもう定信の追及をかわせない、逐電すれば小島松平家、倉橋家、蔦屋だけでなく皆にも類が及ぶ、全てを円く収めるためにはこのオチしかないと。」店に戻った重三郎は春町が一旦は破って捨てた最後の文を皆に見せました。本を書いただけで結果、死に追いやられた春町を思い、皆は悔しさと悲しさでいっぱいになりました。ただ重三郎は春町の髪に豆腐のかけらがいくつも付いていたことが気になっていて、それは『豆腐の角に頭をぶつけて死ね』の言葉を体現したのでは?と山東京伝(古川雄大さん)が言いました。続けて喜三二が「春町は戯作者でありクソ真面目な男だったから最後まで戯けないとと思ったのでは。」と言うと、春町を思い皆は泣き笑いました。男たちは涙と笑いをあの世の春町に手向けました。松平信義は春町の死を松平定信に報告しました。春町は切腹し、最後の力を振り絞って豆腐の入った桶に顔を突っ込んだことを言おうとしたとき、あの男らしいと信義は思わず笑いがこみ上げました。そして「ご公儀を謀ったことを腹を切って詫びたが、春町としては死してなお世を笑わすべきと考えたのでは。一人の至極真面目な男が武家として、戯作者として分をそれぞれわきまえ全うした。戯ければ腹を切らねばならぬ世とは、いったい誰を幸せにするのか。本屋風情の自分にはわからないと言っていた。」と信義は涙をこらえながら重三郎の言葉を定信に伝えました。一人になった定信は布団部屋に隠れ、声を殺して涙しました。
September 25, 2025
-
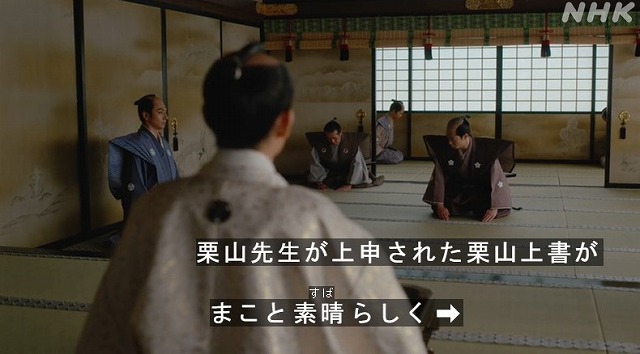
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第35回~「間違凧文武二道」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の中でよく出てきたキーワードの「伝わる」。その言葉を発信した人が思い描く、言わんとすることが必ずしも相手にちゃんと伝わるとは限らないというのはいつの時代にもあることですよね。蔦屋重三郎(横浜流星さん)たちが出版した松平定信(井上祐貴さん)の治世をからかった本は、当のご本人でさえ本にこめられた思いが伝わらない。その定信が自分の治世で据えたい理想の武士像を思い描いて、張りきって文武二道を奨励したものの、にわか仕込みで武芸や学問を始めた者たちには真髄たるものが伝わるはずもなく、できあがるのは勝手な解釈の果てに民を苦しめる使えない者ばかり。前回では、店を守りたいというてい(橋本愛さん)の思いがちゃんと重三郎に伝わったのに、今回はカン違いでも『文武二道』の本がとにかくうまくいったことに味をしめて強気になった男どもに、ていの嫌な予感は伝わらずに出版となってしまいました。思うことを伝えるというのは、難しいものですね。ただ意外だったのが、この時代の武士たちが文武の面でこんなにも緩んでいたことでした。あと50年もすれば幕末の動乱が始まります。幕末のドラマを見ていると誰もがものすごく勉強熱心で、あるいは剣の稽古に励む若者たちがいて、そんな彼らが命をかけてどんどん時代を動かしていきます。まあ逆に考えれば、このドラマの時代がこうだったから、地道に文武に励んできた若者たちが幕末で名を上げたということでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明8年(1788)の年明けに出版した『文武二道万石通』を読んだ松平定信(井上祐貴さん)は本に込められた自分への皮肉に気がつかず、たいそう気に入ってこれからの政にますます意欲が湧いてきました。また定信は阿波蜂須賀家の儒者であった柴野栗山(嶋田久作さん)を第11代将軍・徳川家斉(城桧吏さん)のお抱えに推挙しました。皆が孔子の教えを学び、一人一人が正しき人となり、武術に励んで世に広まる田沼病を根本から治さなければ、と定信は意気込んでいました。そのころ蔦屋では『文武二道』を買い求めて人々が押し寄せていました。店の奥では皆が総出で本の製本をしていて、それでも追いつかないほどの人気ぶりで、重三郎は世の流れが一気に変わるような気さえしていました。町に出ると侍たちは新しい弓を持ち歩いて武芸を語り、学問所で学んだ孔子の論語の一節をそらんじていましたが、武芸も学問もまだ始めたばかりの印象を受ける者が多いようでした。また重三郎も本が飛ぶように売れるのは嬉しいけれど、定信の政をからかっている本の内容が世間の人には全く伝わらず、落胆していました。ただ歌麿が描いた絵は一流の絵師にも劣らないのに値打ちで買えると熊野屋(峯隆太さん)などの豪商(林家三平さん)には評判でした。歌麿(染谷将太さん)が重三郎の店を出た帰り道、急に雨が降ってきたので雨宿りをしたらきよ(藤間爽子さん)が洗濯物を慌てて取り込んでいました。歌麿が手伝いながらきよを見ると、以前幻覚に悩まされたときにここで会ったあの女であることを思い出し、耳の聞こえないきよに必死に伝えました。きよは歌麿があのときの男で本当は優しいなの男だろうと思うと安堵し、落ち着いて自分の仕事を始めました。歌麿はきよを見ているとなぜか心穏やかになり、そしてきよの姿を描きたくてたまらなくなり、夢中で筆を動かしてきよを描いていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は『文武二道』の真意が肝心の定信にも世間にも伝わっていないのにどうにも納得がいかなくて、朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)ら出版の仲間に集まってもらってました。田沼を叩くのをやめると定信へのからかいが露骨にわかってしまう、ではどうしたら?とか皆で考えていたのですが、恋川春町(岡山天音さん)だけは一人不機嫌で拗ねていました。その理由は春町の書いた『悦贔屓蝦夷押領』だけが売れていなかったためで、皆はそれぞれに春町の機嫌をとっていましたが機嫌は直りませんでした。恋川春町(武士で本名は倉橋格)は出仕してもお役目に身が入らず他事を考え、それを小島松平家当主の松平信義(林家正蔵さん)に見られてしまいました。信義は平謝りする春町の顔を上げさせ、春町の本がとびきり面白かった、実に皮肉だった!と感想を伝えました。信義は『悦贔屓』の本の言いたいことを正しく理解してくれて、さらに春町がよくお叱りを受けなかったと味方してくれました。春町は我が殿・信義を信頼して、定信の政をどう思うか尋ねました。信義は「志は立派だが、果たしてしかと伝わるものなのか。」と答え、春町は信義の言葉を深く考えてみました。江戸市中では急に武芸を始めた武士たちがやたら何かと威張り散らし、町の人たちはあちらこちらで酷い目にあっていました。一方、自分の書いた本を我が殿から褒めてもらえて気が済んだ春町は、信義が言ってくれたことを自分なりに解釈して「俺たちのからかいも通じなかったが、定信の志もそううまくは伝わらないのでは。」と重三郎たちに伝えました。「元から文武に励んでおった者は今さら道場に通ったり、本を買ったりしない。今、文武を叫ぶ者はにわか仕込みの新参者だ。」と分析しました。さらに「文も武も修めるには時間がかかるもの。遠からず皆あきてトンチキを作り出して終わるのではないか。」と信義の言葉を伝えました。ところがそんな話をしていたら大田南畝(桐谷健太さん)が駆け込んできて、田沼意次の死を報せ、意次の名誉を取り戻したかった皆は言葉を失いました。さて、誰もが文武に励んで田沼病を治す政策がうまくいっていると思っている定信の元に、将軍・家斉が大奥の女中との間に子をもうけていたという、驚くべき報せがもたらされました。ここのところ学問を怠る家斉に定信は苦言を呈しますが、家斉は「それぞれ秀でたことをすればよい」と聞く耳を持ちません。定信は家斉が御台となる茂姫との婚儀も済まぬうちから他でお子を!と茂姫の実父である薩摩藩主の島津重豪(田中幸太朗さん)に訴えますが、重豪も一橋治済(生田斗真さん)も全く気にしていない様子でした。さらに定信は、質素倹約の旨を皆にきつく言い渡しているのに能舞台の衣装が豪華なことも気になる、賄賂も固く禁じていると二人に意見しました。しかし治済から、定信が10万石と引き換えに老中首座となり思うままに政をしていることを示されると、定信は何も言えませんでした。定信が文武二道を奨励した結果、にわか仕込みで武士としての心構えもなっていない者たちが立場の弱い民たちを苦しめている実態をどうしたらいいのかと、定信は柴野栗山に問いました。栗山は、各々の立場に対する心得を作って書にして将軍・家斉に渡す、初歩の漢文すら読めぬ旗本・御家人も多い昨今、まず武より文、武家としての心得を叩きこむのが良いと進言しました。さらに栗山は自分が湯島聖堂で講釈をしてもよい、定信の『鸚鵡言』を使うと言い、定信は快諾しました。田沼意次の死と共に、もう一つの悲しい別れがありました。歌麿が幼かった頃の数少ない幸せな記憶として残り、歌麿が唯一師事したいと強く願った鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)の突然の死でした。何かにとりつかれたように筆をとって雷獣を描きあげ、絵筆を握りしめたまま絶命してあの世に旅立っていきました。そんな石燕の死の報せと共に、歌麿は一人の女性(きよ)を連れてきていて、誰もが思ったとおりきよは歌麿のいい人でした。歌麿はきよと所帯を持ちたいと言い、きよの絵を描くときのことを楽しそうに幸せそうに語り、そしてきよのために「ちゃんとしたい」と言いました。歌麿は、きよのために名をあげて金も稼いできよを幸せにしてやりたい、今は金が足りないから自分が描いた絵を買い取ってもらえないかと、何枚かの絵を重三郎に差し出しました。それは描くと忌まわしい過去を思い出してしまい歌麿が描けなかった笑い絵で、きよと一緒にいることで幸せな気持ちで満たされて乗り越えることができた、歌麿の思いがつまった絵でした。重三郎は可愛いがった義弟の歌麿の幸せそうな顔が嬉しくて、ご祝儀を含めて絵を百両で買い取ってやりました。秋になり、年明けに出す本のために皆が集まっていました。世間では定信の『鸚鵡言』を使った講義が広まったものの、肝心の受講生たちには正しく理解されず誤った解釈のまま本人や子供たちに伝わっていき、世はトンチキであふれてしまいました。集まった皆はそれを風刺にした草稿を書いてきて、互いに読んで面白いと笑い合い、次はこれでいこうと盛り上がっていました。しかしてい(橋本愛さん)だけは、これはからかいやおふざけが過ぎると危惧して反対意見を言いました。春町が世を諫めたい思いで描いたと言うと、それはからかいよりも更に不遜や無礼として受け取られる、とにかくこれは出せば危ないと反対しました。ところがそこに次郎兵衛が来て、松平定信が黄表紙を贔屓にしていると聞いた話を伝えるものだから男たちは強気になってしまい、本の製作が始まりました。そして天明改め寛政元年(1789)『鸚鵡返文武二道』が出版されました。
September 18, 2025
-
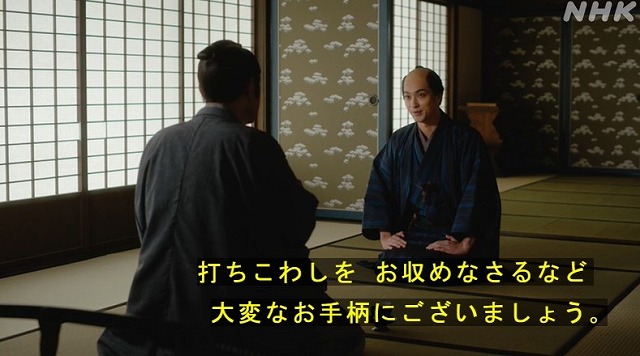
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第34回~「ありがた山とかたじけ茄子」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。1月から始まったこのドラマで9カ月の間、渡辺謙さんが演じてきた田沼意次がこの回でついに退場となりました。うわ~、、なんとも寂しいです。主人公は横浜流星さん演じる蔦屋重三郎です。でも重三郎だけの物語なら、私はたぶん途中で飽きていたことでしょう。それを渡辺謙さん演じる田沼意次が、物語を車の両輪のように安定した形で引っ張ってきたと思っていますから。主人公の重三郎と老中の田沼意次という二つの流れを、脚本の森下佳子氏がまた上手く絡めたなと思います。またこれまでのドラマではほとんど悪者だったというか、田沼意次は良い印象を与える役ではありませんでした。それがこの『べらぼう』の中では、森下氏の脚本と渡辺謙さんの演技と存在感で、見事に変わった感じがします。あの世の意次公も喜んでいることでしょう。史実として田沼意次が領民に好かれていたというのは、『べらぼう』の第17回に出てきました。ただ失脚後の田沼意次は領地没収他をされただけでなく、それまで縁をつないできた者たちが次々と、意次と縁を切って去っていったという史実もあるようです。ドラマではこの回で意次が退場ということで、失脚後の意次の悲哀を描かないようにしたのでしょうか。さて次回からは誰が、重三郎と共にドラマを引っ張っていくのか、興味深いものです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明7年(1787)5月、江戸で起こった打ちこわしを収束すべく田沼意次から協力を求められた蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、見事に意次の期待に応えた働きをしました。側用人の三浦庄司(原田泰造さん)が店に来て、重三郎は過分ともいえる礼を有難く受け取りました。そして老中職を追われた意次が今回打ちこわしを収束させた手柄でいつ老中に戻れるか尋ねましたが、三浦は言葉を濁すだけでした。意次が老中に復帰できたのか気になっていた重三郎のところに使用人のみの吉が読売を慌てて持ってきて、見るとそこには老中首座に松平定信(井上祐貴さん)の名があるものの意次の名はありませんでした。定信があの8代将軍・吉宗の孫であり老中首座に大抜擢されたことなどが瓦版によって瞬く間に市中に広まり、人々の期待は膨れ上がる一方でした。定信はそういった市中での自分の評判をもれなく把握するために、町人に扮した手下を江戸市中にもぐらせていました。また自分の名を上げるための読売を配ることも欠かさず、次のを腹心の水野為長(園田祥太さん)に命じていました。江戸城では第11代将軍となった徳川家斉(城桧吏さん)の元、首座となった定信が張りきって改革を進めようとしていました。定信はこれまで意次が行ってきた政を「田沼病」と呼び、世の中に賄賂や贅沢がはびこったと痛烈に批判しました。そしてこれを正すために万民が質素倹約に務め、祖父・吉宗が行ってきた享保の世に倣うよう、皆に言い渡しました。しかし定信の考えは、肝心の将軍・家斉には息苦しいもののようでした。「住みよい世にするために、万民は質素倹約に励み、それぞれの分を務めよ。」と読売となって世に出た定信の考えは、贅沢な遊びの象徴のような吉原で育ち、その吉原の皆の協力もあって今の地位を築いてきた重三郎にとっては、うんざりするような話でした。しかし妻・てい(橋本愛さん)は定信の考えに賛同でした。定信の考えを「世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するな」と極端な締め付けだと解釈をする重三郎と、前夫が働かずに店の金で遊興三昧し挙句の果てに店を潰した過去があるていは互いに受け入れられず、大喧嘩となりました。重三郎は狂歌の仲間を吉原に集め、歌麿が描いた美しい絵を元にしてこれまでにない豪華な狂歌絵本を作りたいと皆に言いました。皆は定信が出した質素倹約の通達を気にしながらも重三郎の考えを推し進めようとしていたら、大田南畝(桐谷健太さん)が青ざめた顔をして入ってきました。南畝は若年寄の本多忠籌(矢島健一さん)に呼び出され、南畝の「四方赤良」の狂名のことや南畝の狂歌の才能を松平定信が認めていることを聞かされました。しかしその後に差し出された狂歌を南畝が褒めたことで、本多と松平信明(福山翔大さん)は南畝は政に不満があるとみなしました。自分は罰せられるかもと怯える南畝を見て、戯歌一つでこれは見せしめだと皆は警戒心を強めました。松平定信によって田沼派だった者たちは次々と職を追放されていき、市中には「田沼の悪党ども、腐った役人たち」と読売に書かれて広まっていきました。処罰を受けた役人の中には花魁・誰袖を形式上身請けしてくれた土山の名もあり、ただ事ではないと思った重三郎が吉原に行こうとしたら、すでに大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)が店に来ていました。土山が逐電したことにより関わりのあった重三郎も見せしめで罰せられるかもと、妻のていは最悪の事態を想定しました。一度店を潰したていは「今は己の気持ちを押し通すのではなく店を守って欲しい」と重三郎に考えを伝え、重三郎もようやくていの気持ちを理解しました。松平定信を善とし田沼意次を悪とする、この流れができてしまっている今の世でどうやったら店を守れるのか、重三郎は考えました。考えがまとまり重三郎が意次に会いに行くと意次は重三郎の身を案じていました。「田沼様が作り出した世が好きだった。皆が欲まみれで、いいかげんだったけど、心のままに生きる隙間があった。」と意次に思いを伝えました。そして「自分は田沼様の最後の一派として、書をもって今の世の流れに抗いたい。田沼様の世の風を守りたい。」と決意を述べ、ただそのためにはいったん田沼を貶めると言い、意次に許しを乞いました。重三郎の心の内をわかっている意次は「好きにするがいい。」と温かい眼差しを向け、そして共に手を取って涙を浮かべながら笑い合いました。屋敷の廊下に出ると田沼家では家中の役割を皆の入れ札で決めている最中で、この入れ札を国を挙げてやったら面白いだろうと意次が政について思いを寄せていたら、三浦が呼びにきました。それは意次に対する沙汰を伝えに使者の本多が来たということで、大好きな我が殿・意次がどうなるのか、三浦も廊下で覚悟をして聞いていました。重三郎は本作りの仲間を店に呼び、これからはふざけることも許されないような厳しい世の中になる、世の大方も松平定信を支持していると情勢を伝えました。重三郎は、定信の考えは至極全うだと認めたうえで、そんな世はちっとも面白くない、だからこの流れに書をもって抗いたい、と言い一同に協力を求めました。重三郎が作ろうとしているのは、一つは定信が見逃すことを予想して、極悪人・田沼を叩いて定信を持ち上げる本、そしてもう一つは、倹約が流行りの世の中で物凄く豪華な狂歌絵本を作ることで、歌麿が描いた絵に一首入れて欲しいと大田南畝に頼みました。処罰を恐れて承諾できない南畝でしたが、南畝の作り出した天明の歌狂いを守りたいという重三郎の言葉で意を決し、一首詠みました。それを聞いて皆が感想を言い合い、勇気が出た南畝が「屁だ!」と叫ぶと、皆も次々と立ち上がって「屁」を連呼しながら踊って士気を高めました。松平定信は田沼意次に対し、さらに2万7千石の没収と相良城の取り壊しという厳しい罰を課しました。それは田沼の者を叩けば叩くほど民が喜び自分の評判が上がるという、それこそ定信の私情と欲にまみれたものでした。定信は文武出精の者を取り立てようと水野に調べさせていました。しかし泰平の世が続き、実際はほとんどいないというありさまでした。重三郎は鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)を訪ね、歌麿(染谷将太さん)が心のままに描きあげた美しい絵に、歌麿の門出の祝いとして鳥山の言葉が欲しいと頼みました。鳥山は「硯の魂に相談してみないと」と言いながらも、可愛い弟子の歌麿のために快諾してくれました。しかし12月になり、逐電していた土山宗次郎が捕まって公金横領の罪で斬首に、妾の誰袖は押し込めの刑に、松本秀持は土山の監督不行き届きの罪でで百石没収のうえ逼塞と田沼派への粛清は続いていました。そして迎えた天明8年(1788)正月、重三郎はご政道をからかった3冊の黄表紙ーー朋誠堂喜三二・作『文武二道万石通』、恋川春町・作『悦贔屓蝦夷押領』、山東京伝・作『時代世話二挺鼓』を出版しました。そしてかつてないほど豪華な狂歌絵本『画本虫撰』などが蔦屋の軒先を飾りました。
September 11, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第33回~「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今週はまた改行のタグが乱れ、私のパソから思うように書きこみができず、難儀をしておりました。さて今週の中で印象に残ったのは、各所の人々に見られた「交渉」と「説得」でした。田沼意次(渡辺謙さん)が自分の味方である大名・旗本に、今のこの危機を乗り切るためにできる範囲でいいからと、金と米の供出を訴えます。ひもじい思いや搾取される立場になったことがない彼らは、なぜ自分たちが下々のためにそこまで、と反発します。でもその後で、いよいよ自分たちもこの事態の傍観者ではいけないのだとわかり、立場が下がっても世を憂いて皆に必死で訴える意次の土下座の説得でようやく応じました。中盤の、蔦屋重三郎(横浜流星さん)が義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)に助太刀を求め、次郎兵衛の顔で役者の富本斎宮太夫(新浜レオンさん)が動いて、民衆が彼に引き寄せられていく、あの光景は面白いものでした。人間は、不満や怒りといったマイナスの感情をどこかにぶつけているよりも、賑やかで華やかで魅力的な外見や声などに惹かれ、それを追い求めて楽しむプラスの感情を満たしたいのだと思いました。終盤の一橋治済(生田斗真さん)と松平定信(井上祐貴さん)の場面。この二人は互いに、誰かのためではなく、毎度自分の欲のために周囲を動かそうとする雰囲気が出ているので、駆け引きを見ていてもとても疲れる二人でした。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明7年(1787)7月、米があまりにも高値になったうえにお救い米もなく、我慢の限界を超えた民衆が蜂起して江戸の各所で打ちこわしが発生しました。小田新之助(井之脇海さん)は己の主張を幟旗に記し、長屋の皆を引き連れて米を売り惜しみして値を吊り上げた米屋を襲撃しました。義によって天誅を下すと決めた新之助は、打ちこわすだけで盗みはしないよう皆に強く言い聞かせていました。(前回の終わりに「喧嘩をするだけ」とあったので話し合いだけかと思ったら、結局は打ちこわしでした。家の者に危害は加えず盗みもしないけど家中の物を破壊しまくり、この時代の喧嘩はここまで含まれるのですね。)老中たちは北町奉行の曲淵景漸の報で、江戸の各所で打ちこわしが発生したことを知り、襲撃されているのは米を売り惜しみした米屋で、民衆は単なる米欲しさではなく幟を立てて主張をしているとのことでした。田沼意次(渡辺謙さん)は老中たちに打ちこわしが拡大しないよう町木戸を閉め、米屋との喧嘩で召し捕るのはその後にしてはどうかと進言。老中首座の松平康福(相島一之さん)は曲淵にそのように指示しました。康福は打ちこわしのそもそもの原因となっている米がいつ入るのかを意次に問い、(松平定信に裏切られた)意次は返事に窮していたのですが、火急の用が入りその場を一旦退席しました。急ぎ屋敷に戻った意次を待っていたのは蔦屋重三郎(横浜流星さん)でした。重三郎は意次に、意次の嫡男・意知の葬儀で石を投げた男が先日は身なりを変えて奉行所の前で人々を煽っていた、その前は平賀源内の屋敷に武家の姿で出入りしていたことを報告しました。それから重三郎は、頼んだはずの米が出ない理由を尋ね、意次が米の手配に手間取っていると答えるとしばらく考えて、米の代わりに金を出して民衆の気持ちを抑えてはどうかと進言しました。その考えに納得した意次は、重三郎にその内容をまた読売にして配って欲しいと頼み、屋敷に泊まっていくよう言いました。意次は老中・水野忠友に、お救いを要する人数と米と必要な金を見積もるよう、そして田沼派と思われる大名と旗本を一同に集めるよう頼みました。集められた一同に対し、松平康福と水野は出せるだけでいいから米を供出するよう求めましたが、一同はなぜ自分たちが米を出さねばならぬのかと一斉に不満を言いました。しかし町ではまたあの男が人々を扇動していて、召し捕ろうとした奉行所ともみ合いになって同心まで死者が出たと奉行の曲淵から報が入りました。意次は老中に御先手組を出すよう進言、さらに一同には「真にこの騒動を収められるのは“米”!そのために身を切ったならば皆の名は打ちこわしを収めた者として名が残る。」と強く訴え、土下座して皆に協力を求めました。重三郎は打ちこわしがあった町の惨状に心を痛めていました。これは早く騒動を終わらせなければ誰もが不幸だと思い、読売を配るのに何かいい策はないかと考えていました。そこで思いついたのが、義兄・次郎兵衛(中村蒼さん)と役者の富本斎宮太夫(新浜レオンさん)に協力を仰ぎ、賑やかに囃し立てて練り歩き人々の注目を集めることでした。揃いの衣装を妻・ていや母・つよたちに作ってもらい、屋台を出して町に繰り出しました。打ちこわしの喧噪の中で、どこからか聞こえてくる太鼓や鉦の音と人気役者の歌声に、人々は一気に引き寄せられました。重三郎と次郎兵衛の掛け合いで、お上から銀が出てそれが米に代わると聞いた人々は歓喜しました。しかし打ちこわしを扇動していた丈右衛門だった男(矢野聖人さん)はそれを許すわけにはいかず、練り歩く重三郎の背後に忍び寄り七首で刺し殺そうとし、新之助が身代わりに刃を受けました。その後、男が再び重三郎を狙って七首を構えたとき、男の胸に矢が突き刺さり男は倒れました。それは打ちこわしを収束させるために出動した御先手組組頭の長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)の放った矢で、平蔵は騒動を起こさぬよう民衆を鎮めました。主人公の危機一髪を救うヒーローの登場にTVの前で思わず歓声が上がった方も多かったようです。それにしてもこのキメ顔。中村隼人さんをはじめ歌舞伎役者の皆さんは、ここ一番のキメ顔や華やかな演出でホント魅せてくれます。平蔵は刺された新之助を早く医者に診せるよう重三郎に言い、重三郎はこの後のことを次郎兵衛や皆に頼んで行列から抜け出しました。お囃子の楽しさと銀(=米)が出る嬉しさで民衆は今までの不満を忘れ、皆で「銀がふる!」と唱えながら行列に付いていきました。ところが匕首に毒が塗ってあったのか、新之助の具合は急激に悪くなっていき、欲張った米屋やお上はこれで思い知ったと重三郎が励ましても体は動かず、絶え絶えの息の中で新之助は己の最期を悟りました。自分は秀でた才もなく妻子も守れなかった、でも世を明るくするために生まれてきた重三郎は守れて良かったーーそう言葉を残して、ふくと坊が待つあの世に旅立っていきました。さて田沼意次を失脚させた後、一橋治済は松平定信を老中に据えたいのですが、大奥総取締の高岳(冨永愛さん)の同意が得られず話が動かないままでした。そこで治済は大崎(映美くららさん)を呼び、ある物が入った箱を渡して高岳と話をさせたところ、治済の思惑どおり高岳はそれを見て顔色を変えました。それは8年前に10代将軍・家治の嫡男・家基が鷹狩の最中に突然死したときに着用していた手袋で、高岳が家基に贈ったものでした。毒殺が疑われる家基の死で高岳は毒などを仕込むはずもないのですが、潔白の証が立てられない以上、大崎の要求をのむしかありませんでした。白川小峰城にいる松平定信のもとに江戸の打ちこわしが収束したと報が入り、定信は悔しくてたまりませんでした。その頃、江戸では無事に銀の引き渡しが始まって米も集まりだし、また裕福な商人たちの炊き出しも始まって人々は落ち着き、意次は側近の三浦庄司(原田泰造さん)と安堵していました。そんなところに老中・水野忠友が訪ねてきて、大奥の高岳が定信の老中入りを認めたと報せてきました。これで定信は徳川御三家と一橋と、加えて将軍・家斉を後盾にした老中となることになり、さらにその定信は意次を殊の外嫌っているので、意次はこの先はやりにくくなるだろうと覚悟しました。ことが上手く運んだ一橋治済(生田斗真さん)は松平定信(井上祐貴さん)を江戸城に呼び、月が替われば定信が老中になることを伝えました。喜ぶかと思いきや定信はこれを、自分は若輩者で御公儀の仕事をしたことがない、老中になっても思うような政ができない、と最初は辞退しました。しかし話の続きで「老中首座ならばやる」と言いだし、難しいけど治済の力でなんとかするよう迫りました。しばらく考えた治済は言おうかどうか迷ったふりをして、田安家(定信の生家、10万石)を将軍家に献上してはどうか、それならば首座にふさわしいと将軍・家斉(治済の実子)に提案できると定信に返し、予想だにしない展開で定信は何も言えませんでした。喜多川歌麿(染谷将太さん)が重三郎を訊ねると寺にいるとのことで、歌麿は寺に向かいました。自らの手で新之助を埋めた墓の前で重三郎は力無く座り込んでいました。歌麿は墓に手を合わせた後、重三郎に見てもらいたいという「自分ならではの絵」を差し出しました。花や虫が生き生きと描かれたその絵に重三郎はなぜか涙しました。歌麿は「絵は命を写し取るようなもの。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが自分にできる償いだ。」と思いを語りました。そして新之助の人生に思いを馳せ、惚れた女に出会って子も持てて、苦労の中でも楽しいことが山ほどあって、最後は世に向かって主張して己の思いを貫いた、だからとびきりいい顔して死んだだろ?と重三郎に尋ねました。たしかに新之助は今までで一番いい顔していた、それを歌麿に写してもらいたかったーーそんな思いがあふれて重三郎は歌麿の胸で男泣きしました。
September 4, 2025
-
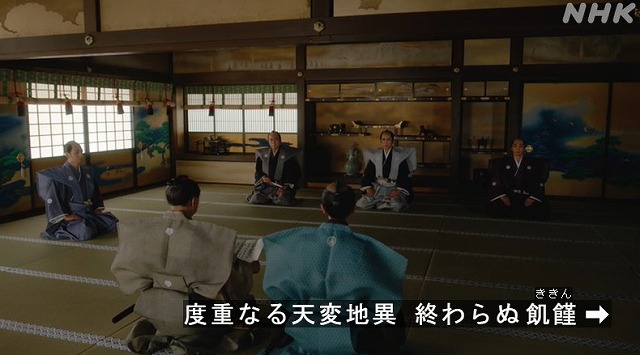
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第32回~「新之助の義」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の物語は自然災害の発生に加えて政局の混乱の中で起こった数多の民衆の困窮が背景にありましたが、その中で私の頭に浮かんだ言葉が「まとうど」でした。自分を庇護してくれてた10代将軍・家治の死によって、人々に誤解され悪口雑言の的になったまま権力を失ってしまった田沼意次(渡辺謙さん)。その意次に味方するがために自身も誤解され、今現在が成功している妬みも含めてちょっとした言葉や行動でも人々の怒りを買う蔦屋重三郎(横浜流星さん)。『まとうど』を調べました。「素直で律義な人。純朴で正直な人。また正直すぎて気のきかない人。」とあり「全人」と漢字で書くことに納得しました。権力を失っても市中の人々にお救い米を出そうと知恵を巡らせあの手この手で行動する意次と、悪いことは全て田沼のせいだと怒り狂う人々を前に、この先が良くなることを信じて人々を説得する重三郎でした。ただ後で思ったのは「万一、例えば交通事情とか何らかの理由であてにしていた米が入らなかった時にどう対処するのか」を二人とも考えていなかったのか?という点です。意次も重三郎も、自分の思い描いた流れで絶対にいけると信じて突き進んで、予定が崩れて大混乱になりました。対立する勢力の妨害など考えてもいなかったのでしょう。そのあたりが二人とも「まとうどの者」なのかなと。まとうどであるがゆえに意次は家治に重用されたけど、家治以外には通用しない性質だったのかなと思いました。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明6年(1786)、第10代将軍・家治の死に伴い老中・田沼意次が辞職し、以降は政局の混乱が続いてその影響は民たちにも及んでいました。頼みの綱としていたお救い米も支給されなくなり、市中の人々の不満はつのるばかりで空腹から殺気立っていました。その意次は自ら身を引くことによって罰を抑えたつもりでしたが、御三家の尾張・徳川宗睦(榎木孝明さん)と紀州・徳川治貞(高橋英樹さん)と水戸・徳川治保(奥野瑛太さん)が出てきて、天変地異や家治の死まで意次のせいであると言い出し、領地の没収や側近の罷免など厳しい追罰を受けていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は朋誠堂喜三二と恋川春町から、田沼派だった松本秀持がお役御免で土山宗次郎がお役替えなど、意次に関わる者までが厳しく罰せられて泡を食っていると話を聞きました。そんな話をしていたら大田南畝(桐谷健太さん)が血相を変えて飛び込んできて、出版物や女郎のことで土山と関わりの深い南畝は大変焦っていました。むろん江戸城内でも田沼派だった者は御三家と一橋治済がどのような出方をするのだろうと誰もが身構えていました。御三家は田沼派の処罰と同時に次の老中として、8代将軍・吉宗の孫にあたる松平定信を推挙してきました。意次と対立する定信の推挙があったことで、老中の松平康福(相島一之さん)と水野忠友(小松和重さん)は大奥総取締の高岳(冨永愛さん)に相談。表では定信をとりまく「黒ごまむすびの会」があり、奥では次期将軍・家斉の乳母だった大崎に取り入る者が増えていると、互いに警戒心を強めていました。そこで御三家と一橋と定信の結びつきをこれ以上強めないようにするため、世の不安で定信の治世に傷がつかぬようにと理由をつけ、まず田沼意次の謹慎を解くよう康福と忠友は一橋治済に申し入れをしました。明けて天明7年(1787)正月、重三郎が新年の祝いとして米と酒を持って小田新之助(井之脇海さん)のいる長屋を訪ねました。人々はすでに粥をすすっていて、話によるとお救い米が出たとのこと。重三郎が祝いで米と酒を出すと人々は初めは歓喜しました。しかし重三郎が田沼意次を称える物言いをすると、自分たちが苦しいのは田沼のせいだと思い込んでいる人々は一斉に不機嫌になり、重三郎は田沼の世で商売が上手くいったのだとも思い込んでいるので、口々に重三郎を責め立てました。この時は新之助が間に入り、自分に免じてと争いにはなりませんでしたが、後で新之助は重三郎に長屋にはもう来ないよう、釘を刺しました。重三郎が帰宅すると三浦庄司(原田泰造さん)が来ていました。重三郎が出す本がすっかり贔屓になった三浦は、今年出した本は全て買い上げてくれたと、妻のてい(橋本愛さん)から報告がありました。そして重三郎が意次の近況を三浦に訊ねると、意次は「雁の間詰め」の一大名になってしまったが、雁の間はちょうど老中たちの通り道になっていて、意次に味方してくれる松平康福と水野忠友老中に「進言」という形で自分の考える策を伝えて(やってもらって)いる、とのことでした。新年にお救い米が出たのもやはり意次の策で、重三郎は安心しました。ただ世間には全く逆で、田沼は米屋や札差と組んで大儲けしていると誤解されて広まっていて、重三郎は悔しくてたまりませんでした。意次が進言という形で政を動かしていることや「裏の老中首座」と言われていることを、御三家のお三方はすでに知っていました。また紀州の治貞は一橋治済に、次の将軍・家斉の実父として果たすべき役割を何と心得るかと問いました。治済は家斉を補佐する松平定信が動きやすくすることと答えましたが、肝心な定信が老中になるかどうかの返事がまだないと治貞は催促しました。治済は早速、老中の二人を呼んで定信の件を問い、水野は先々代の定めがあるし自分たちではどうにもできない、と答えました。しかし治済は、そのような定めは破ればいい、自分は次の将軍の父だと高圧的に言いました。その時、尾張の宗睦が治済に「公に命を下せる立場にはない」と言い、まだ何か言おうとした治済に紀州の治貞はは「見苦しい!」と一喝しました。尾張の宗睦が自室に戻ると田沼意次(渡辺謙さん)が控えて待っていました。宗睦はこの流れは意次が考えた策であることにすぐに気が付きました。意次は滅相もないと否定しながらも、この件で一つ策があると申し出ました。宗睦がその内容を問うと意次は、定信が家斉の後見になれば実父である治済の立場がなくなる、政をしていない治済が家斉や徳川の世のためになるとは思えない、この考えが気に入るなら自分から老中に進言する、と言いました。策を宗睦に認めてもらい、意次は御三家と一橋の連携を切り崩しました。そして4月、家斉は将軍宣下を受けて第11代将軍に、また田沼派の新しい老中の阿部正倫を立て、新将軍の周囲を田沼派で固めました。一方で庶民の暮らしはますます厳しくなるばかりで、いよいよ我慢できなくなった民衆の打ちこわしが5月に大坂で起こり(大坂討毀)、その波は順に全国に広がりつつありました。なんとか米を調達しなければと考えた意次は、松平定信(井上祐貴さん)に援助を頼み込みました。その見返りは定信を家斉の後見に推挙することであり、定信の血縁にもなる紀州の宗睦は意次の意見を後押ししました。定信は後見の話は保留にするが米は送ってやると言い、意次は下がりました。ところが宗睦と二人きりになったとき定信は、米を送るつもりはないようなことを匂わせました。打ちこわしが広がる話を重三郎が店で皆として案じていたら、三浦が店に駆け込んできて、お上の伝達を急ぎ摺物にして欲しいとのことでした。それは打ちこわしを鎮めるための読売で、じきに米が届くという内容でした。しかしもし事がうまくいかなかったら自分たちが人々の逆恨みの的になり店が壊されるという恐れがあり、重三郎が説得しても皆は反対しました。結局、鶴屋喜右衛門の提案で、摺るまでは皆で手伝う、でも読売を撒くのは重三郎が、ということになりました。「二十日には奉行所でお救い米が出る」ーー打ちこわしを起こさせないために重三郎は店の皆で一生懸命に人々に触れ回りました。ところが直前になって定信から米が間に合わないと話があり、意次はとりあえず市中の米屋から押収するよう命じました。しかしそれでも間に合わず、二十日に米が出るのをひたすら待っていた人々は怒りが収まらず、また奉行所の前で「米がなければ犬を食えと言われた」などデタラメを吹聴する者とそれをあおる者がいて、人々の怒号が飛び交いました。何かを決意した新之助が人々を抑え、それを見た重三郎はみの吉に先に戻って打ちこわしに備えるよう命じ、自身は新之助たちを説得に行きました。しかし怒り狂う皆から重三郎は殴られ蹴られ、自分の無力を痛感しました。新之助たちは訴えたいことがあるだけだと理解した重三郎は、布と書く道具を持って再び新之助のいる長屋へ行きました。打ちこわしの準備をしている皆に、自分たちの思いを布に書いて幟を作ってはどうかと提案しました。重三郎は布を贈る代わりに自分の願いも聞いて欲しいと、誰一人捕まらないよう、死なぬようにと皆に訴えました。暴力沙汰にならぬよう江戸っ子の打ちこわしはカラッといって後で笑いたい、と言った重三郎の言葉を受け、新之助は「盗みや暴力がなければ、それは米屋とのただの喧嘩で済む。大した罪にはならぬ。」と理解し、皆を説得しました。そして思いのたけを布に書き、幟をいくつも作って米屋に押しかけました。天明七年五月二十日のことでした。(天明の打ちこわし)
August 28, 2025
-
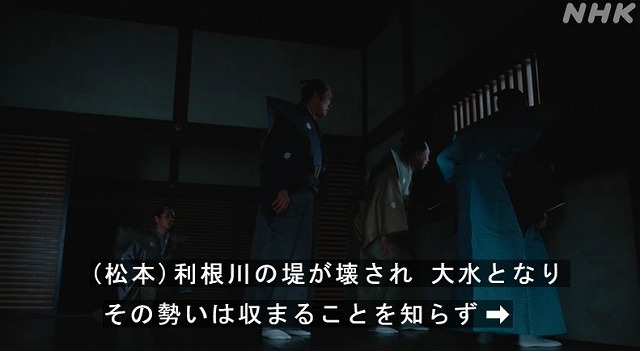
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第31回~「我が名は天」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の中で気になったのは、田沼意次(渡辺謙さん)の突然の失脚と、それに絡む人々の動きでした。意次の政策が通るのは、後盾の徳川家治(眞島秀和さん)あってこそで、その家治さえいなくなればとばかりに一橋治済(生田斗真さん)と大崎(映美くららさん)が暗躍していたように思えました。現代のように科学的な証明がない時代だから、何か事が起これば、それを利用して世論を操作するための噂を作り、もっともらしく語って噂を広めて相手を追い落とすのはやりやすかったかもしれません。地位は下だけど、上の者を操り思い通り動かそうとする治済と大崎。次は何をやってくるのかと、つい考えてしまいました。そしてこの時に起こった関東大洪水に関してです。利根川が決壊して大きな橋を押し流すほどの濁流となり、大水が場所によっては1m以上になりました。私は東京の地形や地名を知らないので実感がわきませんが、東京の地理を良く知る方はなるほどと思われたでしょう。ただ当時の江戸は今のような下水管はなく汲み取り便所で、し尿は農村部での肥料になるため厠に貯められていました。ということは、大水になれば厠からのし尿もあふれて流れ出しているから、長屋の人々が片付けをしているシーンがありましたが、消毒薬もない当時は衛生的にかなり問題があったのでは?と想像しました。ドラマの中で被災した人に飲み水が配られていました。現代では、災害時には一人あたり、1日3Lの飲料水が必要だと言われています。(飲み水1L、調理用1L、手洗いや歯磨き等1L)綺麗な水は、やはり大事ですね。NHKのステラnet のほうで、天明6年(1786)7月の関東大洪水の概要が紹介されています。 ⇒ こちら この大洪水は天明3年(1783)7月の浅間山の大噴火が間接的に関係しているとあり、ドラマの時代背景がよりわかって、大変興味深いです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明6年(1786)7月、連日降り続いた大雨によって利根川が決壊し、江戸の市中にも大水が押し寄せていました。松本秀持(吉沢悠さん)によると、大水によって永代橋や新大橋などの大きな橋まで次々と流され、人の胸の高さまで水がきていて人も家ものまれている場所もある、とのことでした。その報を聞いた田沼意次(渡辺謙さん)は直ちに舟を出して人々を救出するよう指示を出しました。市中の人々も大事な物を高い所に上げたり、家の出入口に土俵を積み上げたりして水が入ってこないよう必死に対策していました。連日降り続いた激しい雨がやんでようやく水が引いたものの、数多の家を失った者がいるため意次はお救い小屋を各所に設けて握り飯や飲み水などを人々に施し、仮住まいの普請を指図していました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)の店は大きな被害を受けずに済んだので、歌麿や小田新之助(井之脇海さん)らに助けとなるものを渡していました。新之助がいる長屋は大水の被害が比較的少なかったので、家をなくした町人や流民たちが来て身を寄せ合っていて、皆で片付けに追われていました。新之助の家に上がって人目がなくなったら、重三郎はふく(小野花梨さん)に妻のていが縫った赤子の着物と、当分の間食べる米を渡していました。ただ長屋の他の皆さんに分けられるほど米はないので、くれぐれも内緒にするよう念を押し、二人も納得していました。あと新之助には紙と筆を用意したうえで筆耕の仕事を依頼し、新之助は有難く請け負っていました。そんな話をしていたら長七が来て、寺で味噌を配っていると教えてくれました。重三郎は帰るついでに施しをしているという寺に寄ってみました。施しを受ける人の中には米がないことに不満をぶつける人もいて、この先は大変なことになりそうだと重三郎は感じました。そんな中で重三郎は笠を深く被って人々の様子をみている侍が長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)だと気がつき、再会の挨拶をしました。「御先手弓頭」に出世した長谷川は市中を見回っていて、最近の江戸市中では盗みや押し込み強盗が増えているとのことでした。ご公儀はお救い米をもう出せないようで人々は困窮していて、長谷川は裕福な町方の助けが頼りだと言っていました。重三郎は寄合で、困っている人たちを助けないかと皆に提案しました。しかし、自分たちのことで精一杯で他を助ける余裕はない、流された渡し場の普請があるし普請のための材料費や手間賃が跳ね上がっている、米だけでなく紙も墨も絵の具もこれからどんどん値上がりする、と誰もが救済に反対でした。そして鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)からは「貸金会所令」のお達しがあったと言われ、被災した直後に人々に知れ渡ったこのお達しは人々の誤解を生んで田沼意次にとって逆風となってしまいました。松平定信を筆頭とする反田沼派の一派からは貸金会所令を直ちに取りやめるよう強く要望が出て、意次がどう説明しても受け入れませんでした。結局は将軍・徳川家治(眞島秀和さん)が裁可を出す月次御礼まで待つことになり、定信は能う限りの大名から取りやめの嘆願を集めると息まいていました。一方、そのころ家治は体調が思わしくなく、知保の方(高梨臨さん)が定信に教わりながら作って持参した「醍醐」を、家治は迷いながらも知保の気持ちを汲んで食していました。重三郎はその後も新之助たちに、米や野菜を目立たぬように援助していました。人々は貸金会所令のことを自分たちを苦しめる悪法だととらえていましたが、重三郎はそれほど悪い法令ではないのではと思っていました。でも新之助は懐疑的で、ふくはこの法令は立場の弱い者たちにシワ寄せがいくことになる、自分はそういう世界にいたからわかる、と言いました。実際、意次は大洪水の後で、米・水・油・材木・船賃などの値上げを禁ずる触れを出していましたが、それを守る者はほとんどいませんでした。そんな話をしていたら赤子を抱えた流民の女が二人、もらい乳にきました。重三郎のおかげでなんとか体がもっているふくは、困ったときはお互い様と他の赤子にも乳をわけていたのでした。知保の方が作った醍醐を食してから、家治は体調が急激に悪くなっていました。月次御礼にも出られず、反田沼派は意次が何か謀ったかと囁いていましたが、稲葉正明が意次を呼びにきたことで誰も何も知らないのだとわかりました。意次も家治も、この件を裏で操るのは一橋治済で、松平定信と知保が作った醍醐で家治が体調を崩したと周囲に話せないことも計算していて、今までに起こったいくつかの不可解な死も治済が裏で操っていると考えていました。家治は、治済が人の命運を操り将軍さえも自分が操る、それは将軍の控えに生まれついた治済なりの復讐だろう、と考えました。家治は自分はまだ生きて守りたいものがあるという強い思いがあり、意次に毒下しの得意な医師を連れてくるよう命じました。大奥では知保の方が、もしや自分が贈った醍醐のせいで家治の具合が悪くなったのかと心を乱していました。しかし大崎は、それを表に出すと醍醐作りに関わった者が何人も処罰されると言って、知保の方を抑えていました。後日、老中首座の松平康福(相島一之さん)の元に大奥から、意次が医師を変えてから家治の具合が悪くなったと訴えがあり、また他方では意次が毒を医師に盛らせたのではないか?という噂まで流れていました。康福は自分たちの身の安泰を図るために、まず意次に登城を差し控えるよう言い、その話の流れで老中を自ら退くことを勧告しました。意次は身の潔白を必死に訴えましたが、城内の皆の空気はもう意次の力ではどうにもならなくなっていて、康福は「全てを失うより、自ら退けば家名も禄も守れる」と意次を説得し、意次もそれを受け入れました。後日、屋敷で謹慎する意次の元に水野が来て、恩貸付金会所と印旛沼干拓の取りやめの決定と、じきに蝦夷の話もなくなることを伝えました。そして水野の様子から家治の容態がかなり悪いことを悟った意次は老中職を辞する決心をし、文を水野に渡しました。天明6年(1786)8月、いよいよ危篤となった家治の枕元に西の丸(次期将軍)の家斉と、その実父の一橋治済(生田斗真さん)らが呼ばれました。家治は絶え絶えの息で家斉に「田沼意次は“まとうど”の者である。臣下には正直な者を重用せよ。」と遺言しました。そして混濁する意識の中で「家基」の名を呼びながら床から這い出て治済のところまでいき、最後の力を振り絞って治済の胸倉をつかみ、目を見据えて「天は見ておるぞ!天は天の名を騙るおごりを許さぬ!これからは余も天の一部となって見ておることを忘れるな・・。」と言い、絶命しました。世の節目となる家治の死の一方で、市中では小さな死がありました。施しの米をもらって新之助が長屋に戻ると、ふくととよ坊が死んでいました。犯人はふくから赤子に乳をもらっていた流民の女の夫で、米を盗みに入ってふくを殺してしまったとのことで、夫婦で必死に許しを乞うていました。米次から報を聞いて駆けつけた重三郎は、もしかしたら自分が援助した米が原因なのかと愕然とし、米欲しさで妻子を突然奪われた新之助は「どこの誰に向かって怒ればいいのだ!」と慟哭しました。(このシーンでちょっと引っかかったこと。ご飯を炊くときにはいい匂いが漂うから、米のことを内緒にしようにも、炊飯の香りであの家には米があることは長屋の人にはわかります。他の長屋の人たちはどんな状況だったのか、妻から米があると聞いただけで盗みに入った流民の男は、あの家には「まだ余分に」米がある、という意味だったのかな?とか考えてしまいました。)
August 21, 2025
-
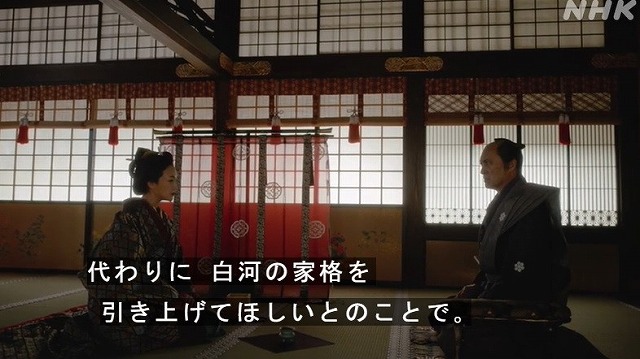
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第30回~「人まね歌麿」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は喜多川歌麿を演じる染谷将太さんが絵師として悩み苦しみ、でもそれが鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)によって救われた場面で、大きな反響がありました。私はクリエイターではないので今一つ気持ちが乗れない部分があったのですが、特に絵描きの方々は歌麿と同じ気持ちになれて、神回ともいえる感動だったそうです。枕絵のイメージから歌麿は辛かった少年時代を思い出し、それから逃れるためにとった行動で幻影に悩まされ続け、自分を失いかけていました。でも自分を可愛がってくれた鳥山石燕と再会し、石燕の言葉から歌麿は、人まねの絵なんかじゃなくて「自分の絵を描きたい」と気がつきました。そして自分が教えを乞う師匠がほしかったのです。幼い頃に自分を救ってくれて面倒をみてくれて、自分の過去を受け入れてくれる蔦屋重三郎(横浜流星さん)はもちろん心から信頼しているでしょう。でも重三郎では絵の世界が開けないのです。過去の自分を思えば落ち着いた暮らしの中で絵が描けるだけで十分に幸せ、と歌麿は今までは思ってきました。でも石燕の言葉で、歌麿は自分に欲があったことに気がついて、師を求め、そして巣立っていきました。義弟・歌麿の成功と幸せを願いつつも、重三郎のどこか寂しそうな顔がよかったですね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明5年(1785)一橋治済は田安家から白河松平家に行き今では当主となっている松平定信に、ご公儀の政に加わるよう呼びかけました。治済は定信の政治手腕を認めていて、血筋も申し分なし、あとは定信の家格を上げることが必要だったので、大奥総取締の高岳(冨永愛さん)を通じて田沼意次(渡辺謙さん)にその旨を伝えました。田安家は後継者がいなくてじきに取り潰しになり幕府の経費が浮くから、取引として代わりに定信の家格を上げてもよいと意次は考え、大奥のほうもそれでよいとの高岳の返事だったので、定信は政の場に出るようになりました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、今度は狂歌絵本を手広くやれないかと考えていて、店に来た北尾重政(橋本淳さん)に相談していました。重政は重三郎の発案に感心しつつ、近頃「人まね歌麿」と世間でも噂になってきている歌麿(染谷将太さん)を売り出したらどうかと提案しました。これは時が来たかと感じた重三郎は、歌麿に重政そっくりの画で描くよう依頼、その後は来客などに歌麿のことを宣伝してもらうよう話していました。また絵本には入金一分で自作の狂歌を一首載せられるのでそれに賛同する人も多く、明けて天明6年(1786)重三郎の店には狂歌絵本が並びました。幕府の政策を吟味し老中に物申すことができる溜間(黒書院溜之間)には定信も並ぶことになりました。定信は早速、今は財政逼迫の折、なのになぜ船まで作って蝦夷に調査に行かなければならないのか、と意次に問いただしていました。定信を納得させるのに一刻かかった意次は、疲れて屋敷に戻ったら家臣たちに愚痴三昧でした。側近の松本秀持(吉沢悠さん)が、蝦夷で大量に米がとれることがわかったと言い、次に定信が何か言ってきたらこのことを言えばどうか、と進言しました。また三浦庄司(原田泰造さん)は重三郎が入金によって本を作っていることを紹介し、これを御公儀でもまねできないかと意次に進言しました。一方、松平定信(井上祐貴さん)は「黒ごまむすびの会」という名で反田沼派の大名や旗本たちを集めて話し合いを重ねていました。彼らの話題の中心は質素倹約の推進の強化や意次の悪口や批判で、人の差配に大奥が力を持つことを知っている松平信明(福山翔大さん)からは、大奥への足掛かりとなる人物は誰かいないかと定信に意見が出ました。そこで定信は知保の方に会い、田沼を追い落とすための力添えを頼みました。人まねの絵ではあっても世間での評判が上がってきた歌麿を、この機会に歌麿を絵師として歌麿ならではの絵を売り出そうと考えました。歌麿は最初は消極的でしたがとにかくやってみることにして、重三郎はまずは枕絵を描いたらどうかと勧め、歌麿も受け入れました。そこで重三郎は(これまで何かと世話になっている)須原屋市兵衛から参考になるよう様々な枕絵を借りてきて、歌麿に見せました。歌麿は一人で描きたいと言って重三郎に出ていってもらい、どんな絵を描こうかとあれこれ思い浮かべました。しかし歌麿が “枕絵” によって思い浮かべてしまうのは、母(向里祐香さん)の愛を求めるあまり母の命じるまま幼い頃から客を取らされて辛かったことや、明和の大火(1772)のときに逃げ遅れた母を見捨てざるを得なくて死なせてしまったこと、自分の過去を知るヤス(高木勝也さん)が執拗に脅してきてヤスを道連れに自分も死のうとしてヤスだけ死なせてしまい、そのためにまた身体を売って生きるしかなかったことでした。そして枕絵を描いていると母とヤスの幻影が現れて苦しめられ、描くたびに絵をくちゃくちゃにしてしまい、何も描けない状態が続いていました。歌麿の様子がおかしいのは重三郎も薄々気がついていましたが、どうしてやることもできませんでした。描けない歌麿はふらりと出かけ、その先の廃屋で出会った見ず知らずの女と男にも母とヤスの幻影を見て荒れ狂い、心配で後を追ってきた重三郎が力づくで歌麿を止めました。歌麿は重三郎に今の自分は何も描けない状況だと打ち明け、歌麿の過去を知る重三郎は歌麿を慰め励まし、とりあえず店に連れて帰りました。ところが店に戻ると、かつて歌麿に絵を教えた鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)が歌麿を訪ねて来ていて、歌麿も一目で石燕だとわかりました。「三つ目」と呼んで可愛がっていた少年(歌麿)と過ごした時間は石燕にとって楽しみでしかたがなく、歌麿がぱったり来なくなってからも、いつ来るかいつ来るかとずっと待ちわびていたのでした。そして今目の前にいる歌麿に「よく生きていた!」と生きていただけでも褒め、あの時がどれだけ楽しかったかと歌麿に思いを伝えました。頃合いを見て重三郎が石燕に挨拶をし、歌麿の絵を見せて助言を求めました。絵を見た石燕は「妖がおる、閉じ込められた妖が出たがって怒り悲しんでいる」と悲しそうに言いました。石燕は歌麿に「なぜ迷う。お前にしか見えないものを、絵師はそれを写すだけでいい。その目にしか見えぬものを現してやるのは、絵師に生まれついた者の務めじゃ!」と歌麿の心に訴えました。石燕の言葉で自分を縛っていたものから解き放たれ、人まねじゃなく自分の絵を描きたいのだと気がついた歌麿は、石燕に弟子入りを懇願しました。自分が歌麿を世に出してやると意気込んでいた重三郎でしたが、歌麿の才能を本当に伸ばしてやれるのは石燕だとわかり、快く歌麿を送り出しました。石燕の元で心が自由になった歌麿をは、穏やかな気持ちで絵を描き始めました。この頃、御公儀からは田沼意次の発案で「貸金会所令」が出されました。その内容は、各地の大名が領民から金を集めて幕府に納める、その金を利息をつけて大名たちに貸しつける、領民たちには後に利息を乗せて返すことにする、というものでした。反田沼派からは、今の時期に領民から金を集めたら一揆が起こる、自分たちで金を集めて幕府に納めて何故また金を借りるのか、寺社・宿場・馬方など集め方が異なり触れが杜撰でこれでは取り立てられない、など意見がでました。松平定信の台頭で苦労する意次を、将軍・徳川家治(眞島秀和さん)は亡き父・家重がいまわの際に遺した「田沼はまとうどの者、正直者ゆえ大事にせよ」という言葉で労わっていました。家治は貸金会所令には若干の不満を感じていましたが、これからの世に適した入り用なやり方、それは世に正直ということだと認めていました。意次は家治の労いに深く礼を述べて安堵しました。しかしそんな時に稲葉正明(木全隆浩さん)が、知保の方との約束の時間だと家治を呼びにきました。家治はここしばらくは知保の方を遠ざけていたのですが、二人の間の子である亡き家基を偲ぶという理由で、また一緒に時を過ごしているとのことでした。知保の方が急に存在を示してきたことで意次は何か嫌な予感がしました。
August 15, 2025
-
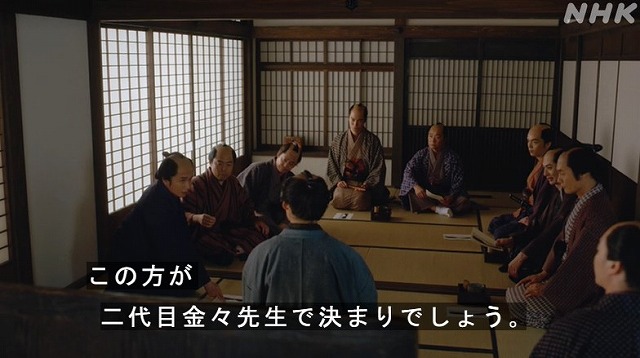
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第29回~「江戸生蔦屋仇討」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話は、蔦屋重三郎(横浜流星さん)とその仲間たちによる「筆の力での仇討ち」でした。世の人々は田沼政治への不満から佐野政言を崇め奉るようになり、それは命を落としたうえに意次の息子というだけで悪しざまに言われる田沼意知と、彼を愛する周囲の人々にとって、たまらなく不本意で辛いものでした。自分にできる形で意知の仇討ちをすると意次と誰袖に約束した重三郎は、仲間たちから知恵を借り、北尾政演(古川雄大さん)の頑張りや仲間たちのフォローもあって、見事に大ヒットとなる作品を作り上げました。本の主人公は世の人々の反感を買わない人物にすることや、今の世の流れを考えて人々に受け入れられるものにすることなど、私は本とか出すわけではないのですが、参考になる話もいろいろありました。でもこういう本が作れたのも、重三郎が日頃から、自分に起こった出来事や相手のことをいちいち悪くとらえなくて、佐野の人生の苦労をおもんばかり、佐野の暗い話を裏返しにするという発想ができたから、と思ってます。つまり、常日頃の心がけというのは本当に大事なのだと。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明4年(1784)田沼意次の嫡男・意知は筋違いの逆恨みを受けて佐野政言に襲われて落命、しかし田沼の失政で生活が苦しくなったと思い込む世の人々は佐野を大明神として崇め奉っていました。その一方で意知との幸せな先々を思い描いていた花魁・誰袖は、意地を失っただけでなく襲った佐野が人々から讃えられていることに耐えられなくなり、昼に夜に呪詛を繰り返していました。誰袖を案じる蔦屋重三郎(横浜流星さん)は誰袖をもう一度笑わせてやりたくて、新たに黄表紙の本を出すことを決意し、絵師や作家の仲間たちを集めていました。話を耳にした鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は集まりの場に来て、鶴屋お抱えの京伝(本名、北尾政演;古川雄大さん)を貸すから是非大当たりの本を出して欲しいと言い、本作りが動き出しました。さて田沼意次(渡辺謙さん)の屋敷の前で行き倒れになった男は、探りのために松前藩に入っていた平秩東作(木村了さん)でした。東作は松前で表の勘定帳と裏の勘定帳を手に入れたものの、それが見つかってしまい、命を狙う追っ手から必死に逃げて江戸までたどり着いたのでした。勘定帳を手に入れることは亡き意知の命であったと土山宗次郎(栁俊太郎)が説明し、これは亡き湊源左衛門と善吉と、なにより意知の血を持って購われたものだから、是非とも蝦夷の上地を成して欲しいと東作は意次に訴えました。この勘定帳を手に入れるために命を落とした皆の思いを知った意次は、直ちに上地を願い出る上書をしたためるよう三浦庄司(原田泰造さん)に命じました。ひと月後、政演(京伝)が作った原稿が出来上がったので重三郎は皆に試し読みをしてもらいました。皆はこんな感じでいいかと考えていたのですが、大田南畝(桐谷健太さん)の評論は今一つでした。妻のてい(橋本愛さん)は田舎の若者を笑うようなこの話のどこが面白いのかわからないと言い、他の皆もあらためて考えたら今の時代に合わないから受け入れられないのでは、と思うようになりました。重三郎は一からやり直すことを決め、政演に作り直しを頼みました。製作の労力が全部無駄になって面白くない政演は、一人退席してしまいました。誰もが腹の底から笑えるような作品とはどんなものなのかと重三郎が考えていたら、様子を見に来てくれた鶴屋喜右衛門から佐野の生前の苦労話を聞き、重三郎は笑いを生み出すための手がかりを思いついたようでした。一方、政演は恋川春町(岡山天音さん)と朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)と一緒に気晴らしをしていて、自分は苦労して大当たりを出したいとかの欲はないと言って笑っていました。その言葉を聞いた春町は我慢がならず、隣室に行き衝立をよけると大量の書き損じの紙が崩れ落ちてきました。それは政演が作品を仕上げるために考えてこだわって幾度も書き直した苦労の跡であり、春町は政演が生真面目な努力家であることを知っていたのでした。重三郎が歌麿(染谷将太さん)と町を歩いていると、聞こえてくるのは意知を斬った佐野を賞賛する声ばかりで、重三郎はいたたまれない気持ちでした。ふと入った鰻屋にちょうど政演たちがいて、重三郎も同席しました。皆の話題は本のネタのことで、重三郎は「苦労した佐野の話を裏返しにーーつまり大金持ちの苦労知らずで世間知らずのバカ旦那に苦い汁を飲ませれば笑える」と提案しました。そこでどういう苦い汁にしようか皆に訊いたら、主人公の“欲”は何か、名を上げたかった佐野とは反対に浮き名を流して周囲から噂されたい、そんな人物にしてはどうかとまとまりました。方向が決まれば各人から次々と案が出て話は盛り上がり、重三郎と政演は再び意気投合していました。物語の方向が決まり、重三郎はネタ集めに回っていました。「浮き名を立てるためには何をやったらいいか」「色男に見られるにはどうしたら」といったことを鶴屋や母親のつやや志げなど周囲の人に訊いて回り、それを政演に伝えていました。ネタを聞いた政演はそれにさらに脚色を加え、くだらない主人公を作ってはそれを想像して二人で笑っていました。初めの頃は書き直しを頼むと不服そうだった政演が、今ではより良い作品にするために喜々として書き直していて、そんな政演の背中に重三郎は悪戯でしなだれていきました。重三郎は主人公の艶二郎の名前のことで、何か思いついて言いたいことがあったようです。(横浜流星さん、こんな表情もするんですね。それと大河ドラマの撮影の時期は、映画『国宝』で歌舞伎の稽古をみっちりやっていたので、しなだれる動きも美しいですね。)松前家の裏勘定書を手に入れた田沼意次は上書をしたためて、松前家の所領を上地する件の裁可を将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に願い出ました。この上地の件は実は家治と意次との間で前もって話がなされていたのですが、家治が上書を手に取って読もうとしたとき、一橋治済(生田斗真さん)が急に目通りを願って現れました。家治と意次は治済が上地を阻止しに来たのかと一瞬身構えました。しかし治済は「上地の件、心より御礼申し上げます。」と快く礼を述べました。治済は我が子が家治の養子になっていて次期将軍となるため、上地で将軍家の所領が増えるのは治済にとっても好都合なのだろうと周囲は考えていました。愛する亡き意知が世の人々から悪しざまに言われる悲しみから呪詛を繰り返す花魁・誰袖(福原遥さん)を案じ、志げ(山村紅葉さん)はある時期は誰袖を四六時中見張って寝ずの番までして、酷くやつれた時もありました。秋になり誰袖も少し落ち着いた頃に、重三郎が自分なりに仇討ちをしてやると手掛けていた黄表紙の『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』が完成し、誰袖のところに来て読んでやっていました。『江戸生艶気樺焼』の内容は、番組HPの「べらぼうブログ」で全ページ紹介されています。 ⇒ ⇒ こちら 重三郎が本を読み終えると、主人公が繰り広げる馬鹿馬鹿しさに誰袖は思わず声をあげて笑い出しました。あの明るかった誰袖が意知の死後は全く笑わなくなりましたが、やっと以前の笑顔が出て重三郎と志げは胸をなでおろしました。誰袖の笑顔を取り戻すことが重三郎に唯一できる仇討ちであり「これでお前の気が済むとは思わないけど呪うのはもうやめないか」と重三郎は言いました。後を追えなかったけど意知(雲助)は許してくださるかと誰袖がつぶやいたら、庭の桜の花びらがひらひらと舞いました。それはあの日、花見の約束をしていた意知からの返事のようでした。(桜は春と秋に二度咲く種類もあるので、それが植えてあったのでしょう)明けて天明5年(1785)『江戸生艶気樺焼』は空前の大当たりとなり、世の話のタネは佐野大明神から仇気屋艶二郎に取って代わりました。誰袖と同様、この本によって心が救われた人物がもう一人、愛息・意知の死を世間からも悪しざまに言われていた田沼意次でした。「粋な仇を討ちやがって。」ーー筆の力で見事に仇討ちをした重三郎に意次は胸のすく思いがしました。
August 7, 2025
-
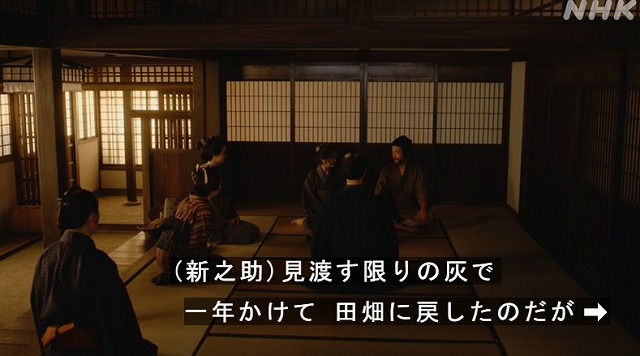
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第28回~「佐野世直大明神」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回でまず感じたことは、情報の伝わり方や人々の価値観が、現代とは本当に違うのだなということです。佐野政言(矢本悠馬さん)が起こした事件と、米価の高騰が何らかの理由でちょうど米価が下がったことと重なり、そのため人々は「佐野様のおかげで米が安くなった」と思い込むようになりました。その時期に起こった自然災害と天候不順で米不足になったのは、理由として成り立ちます。しかしその後で米価が下がったのと佐野の起こした事件とは、全く因果関係はありません。それでも学のある人が少なく、情報も少ない当時の人々は、誰かが言い出したことをそのまま真に受けて思い込んで広めてしまうのでしょうか。現代ならこのような場合はテレビ各局がすぐに取材を進め、専門家から意見を聞いて広めるでしょう。またSNSでも学識がある人たちが納得のいく意見をそれぞれに出してくれるでしょう。お上の政策への不満や怒りや、食うや食わずの日々で気持ちに全く余裕がないときは、何かの拍子に入った話に思わず飛びついてしまうのは現代でもあると思いますが、当時の情報量や濃い人間関係の中ではそれがよりいっそう、強かったのかなと思いました。ところで、終盤の田沼意次を演ずる渡辺謙さんが一橋治済(生田斗真さん)と対峙する場面で、放送38分過ぎからのあの振り向きざまのあの一瞬。渡辺謙さんの振り向く瞬間の間、畳と足袋の衣擦れの音、二人の間合い、そして治済に向かうときの迫力が本当に“カッコいい!”の一言です。なので私もついあの場面を鬼リピして見てしまいます。ベテランの役者さんたちがたくさん登場する大河ドラマでは、メインキャストでもそうでなくても、こうした感動をどこかで与えてもらえます。それが大河ドラマの醍醐味の一つでしょうね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明4年(1784)4月、蔦屋重三郎(横浜流星さん)店に浮浪者の夫婦が現れ、一体誰かと思ったら小田新之助(井之脇海さん)と、足抜けして逃げた女郎のふく(小野花梨さん)でした。食事と風呂をもらって人心地がついた二人はそれまでのいきさつを語りました。江戸から逃れた後、浅間山のふもとで村人に混じって暮らしていたが、前年の浅間山の大噴火で田畑が壊滅状態になり、元々の村人でない二人は村から追い出された、そして重三郎を頼って江戸まで来た、と。何でもやるからここに置いてくれと懇願する二人に重三郎は、「世話になったお方を打ち捨てるなど、人として話にならない」と意知の言ってた言葉を言い、新之助に筆耕の仕事を頼みました。その田沼意知(宮沢氷魚さん)は江戸城内で佐野政言に突然わけもわからずに斬りつけられ、瀕死の重傷を負って田沼屋敷に運ばれてきました。意知は絶え絶えの息で父・田沼意次(渡辺謙さん)に、土山の元にいる誰袖のことと、まだ進行中の蝦夷のことを託しました。愛息・意知に先立たれたくない意次は「自分でやれ!」と意知を力づけました。しかし意知は力尽き旅立ってしまいました。意次は「(命を落とすのが)なぜ俺じゃなくお前なんだ!」と慟哭しましたが、意知の魂は還ってきませんでした。意知を襲撃した政言は即座に切腹となりました。意知を送る葬列は町の多くの人々に静かに見送られました。しかしその途中、一人の男が突然「天罰だ!思い知れ!」と意次の乗る駕籠に石を投げると、それまで静かに棺に手を合わせていた町の衆も急に男に同調し、暴言を吐きながら意次の駕籠や意知の棺に一斉に石を投げつけてきました。意知の棺をかばおうと出てきて(投石を)やめてと群衆に訴えた誰袖にも石が当たり、重三郎は慌てて誰袖を連れ戻しました。「(意知の)仇を討って!」ーー誰袖は重三郎に涙ながらに思いを伝えました。ちょうどこのころ高騰した米が安くなって出回るようになり、米の値と意知の死と政言の切腹は何の因果関係もないものの、田沼の政に不満が溜まっていた民衆は、佐野政言が世直しをしたと思い込むようになりました。重三郎が請け人となって新之助とふくが長屋に移ることになり、三人で一緒に掃除をしてると、重三郎は田沼贔屓なのかと新之助が訊いてきました。新之助は自分も以前世話になった平賀源内も田沼贔屓だったし、戯作や狂歌の者は田沼贔屓が多いことは理解していました。重三郎も人それぞれ考えがあるのは理解しているものの、斬られた方が悪者にされるのは気持ちがついていかない、と答えました。ただふくは、ひもじくて苦しい者は米の値が下がれば斬った人でも拝むと言い、世の人々はそういう考えなのかと重三郎は理解しました。長屋からの帰り道、重三郎はどこかで見た覚えのある男とすれ違いました。牢人風のその男は幟旗を持っていて、気になって後をつけていくと佐野政言の墓所に行き、寺の入り口に「佐野世直し大明神」と書かれた幟を立てかけるとどこかに去っていきました。そのとき重三郎は亡き源内の言葉を思い出し、田沼が悪者に仕立て上げられていると気が付いて、すぐに田沼意次に会いに行きました。愛息を失い憔悴しきった意次に、重三郎は怪しい男のことを伝えました。重三郎の進言を意次は受け流すだけでしたが、かつて平賀源内が罪人となったときに意次は源内を守ろうとしたけど意知が止めた、意知はそれ故に蝦夷地のことは成し遂げようとしていたと重三郎が言うと、意次はそれに対する自分の心の底の思いを語りました。「意知は俺のせがれだっただから俺のせいで斬られた。仇は俺だ!」ーーそう言って自分の刀を重三郎に差し出しましたが、重三郎が「俺は筆より重い物は持たない」と返すと意次は退室を命じました。自分が意知の仇を討つ方法は何かないかと重三郎はずっと考えていて、来客の須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)にも相談していました。市兵衛は、ご公儀のことは本のネタにしてはいけないと釘を刺し、さらに今の世の風潮から佐野を悪役にしたら絶対に売れないと断言しました。重三郎が悔しそうに「本当は善悪が逆なのに」と言うと市兵衛は、世の中が「浅間山が火を噴くのも米の値段が下がらないのも皆、田沼様のせい。佐野が天に代わって田沼様を成敗した!」という筋書きを立てたのだと重三郎を諭しましたが、重三郎は納得がいきませんでした。そんな話をしていたら吉原から志げが血相をかえてやってきました。重三郎が志げ(山村紅葉さん)と共に土山宗次郎に囲われている花魁・誰袖(福原遥さん)のところにいくと、誰袖は一心不乱に呪詛をしていました。重三郎は誰袖から小刀を取り上げ説得しましたが、誰袖は(呪詛で)意知の仇を討って自害してそばに行くと言い張り、その後も石を打ちつけて呪詛を繰り返していました。そんな誰袖の姿を志げは嘆き悲しむばかりでした。重三郎が帰った後で、やはり納得がいかないままではいられないと思ったのか、意次は仇を討つ決心をしました。それは意知が生きていれば必ず成し遂げたであろう蝦夷のことと米のことで、意次は自分がそれを成し遂げ将軍・家治の名とともに意知の名を後世に残して永遠の命を授ける、と家治に誓いました。家治に拝謁した後、意次は一橋治済(生田斗真さん)と廊下ですれ違いました。やつれた自分の姿を見て口先だけの見舞いを言う治済に意次は「何も失ってはいない。意知はこの胸の中にいる。もう二度と毒にも刃にも倒せぬ者となった。“志”という名のもとに。志は己が体を失っても誰かの体の中に生き続ける。」そう言って治済に微笑み立ち去ろうとしました。しかしすれ違いざまに意次は振り向き、治済を見据え、自分にはやらなければならないことが山のようにあると言い、踵を返して去っていきました。(この渡辺謙さんが振り向いたシーン、振り向く瞬間や治済との間合いの取り方や気迫があまりにもカッコよくて、しびれた視聴者も多かったと思います。)重三郎が帰宅すると田沼意次の側近の三浦が来ていて、意次から重三郎への文だと言って渡すと、早々に帰っていきました。その文には意次が「仇を討つことにした。生きて意知が成したであろうことを成していく。重三郎がどんなふうに仇を討つのか、そのうち聞かせてくれ。」とありました。意知が生きていたら成したことーーそれを考えたとき重三郎は、誰袖が意知に身請けされて笑っていたであろう姿を思い浮かべました。意次からの文で重三郎が思いにふけっていたとき、妻のていがそばにいて後ろから文を見ていたことに気がつきませんでした。ていは文を盗み見したことを詫び、でも「お口巾着で。」と決して他言はしないと約束しました。(今で言う「お口チャック」はこの時代なら「お口巾着」ですね)するとそこへ北尾政演(古川雄大さん)が何か面白い話でもあるのか、小走りで重三郎を訪ねてきました。政演は今「手拭合」というのを作っていて、絵心ある人に手拭いの柄を考えてもらい、1冊にまとめようかと思っていて重三郎にも入金を勧めてきました。重三郎は見本の絵を眺めながら一つの柄を手に取り、何かを思いついたようで「こいつならできるかもしれない」とつぶやきました。そのころ田沼屋敷では、意次が土山宗次郎(栁俊太郎)から、蝦夷に下調べに行っている平秩東作から年明け以降の連絡がない、仲介する商人の屋敷の前は松前の役人に見張られていて近づけない、調べたら東作の営む煙草屋が火事で焼けている、と報告を受けていました。するとそこに楠反七郎(宮澤寿さん)が門前に倒れていた者がこれをと言って、油紙で包んだ物を急ぎ持ってきました。油紙の中には帳面が入っていて、意次がそれを見ると・・・。
July 30, 2025
-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その3
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)のご紹介です。前回の日記の続きになります。ところで、なぜ私が家から約1時間とガソリン代をかけて、わざわざここまで通うのか。それはこのモリコロパークが私にとって大好きな場所ということもあるのですが、今通っているスポーツクラブでレッスンを受けている先生から「風景を見ながら散歩するのが、身体にも脳にもいい運動になる」と言われていることがあるからです。近所にも広い公園はあるけどモチベーションが上がらないから、少々ガソリン代はかかるけど、長久手まで行ってあの頃に見た風景を思い出しながら、約1時間園内を歩いているのです。毎日1時間歩くのが良いのですが、ふだんはどうしても運動を忘れるので、せめてこの時くらいはと思ってます。6月第3週の金曜日、この週は6月なのに最高気温が35℃を超える猛暑日を記録する日が続き、さすがに暑いと思いました。でもモリコロパークには目的地まで少し遠回りすればこのような木陰の道もあり、心地よく散策できます。この日は「魔女の谷が見える展望台」に行ってみました。ゴンドラに乗るのにふだんは大人は150円かかります。でも 愛知万博20周年記念事業 をやっている9月25日までは無料で乗れます。暑い日でしたが、ゴンドラ内はエアコンが効いて快適でした。とはいえやはり暑い日なので、いつもの金曜日なら駐車場もそこそこ混みだしているのにガラガラだったし、園内もやはり人がいなくてガラガラでした。ゴンドラを降りて、展望台に進みました。ジブリ映画はほとんど見ていないので、これが何のシンボルなのか、私にはわからないです。これが「魔女の谷」という世界なのでしょうか。ジブリファンの方なら、どの作品のどのシーンに出てきたかすぐわかるでしょうね。左側を拡大しました。右側を拡大しました。この日は何かの工事をやっていたようです。展望台から帰りは歩きで降りて、その後は「日本庭園」の方に行ってみました。木造の建造物や水の流れる音や緑の景色に癒されます。西口駐車場に戻る道です。車は北口駐車場なのでもう少し歩きます。ここは、亡きチビ子嬢と一緒に歩いた思い出の風景です。
July 27, 2025
-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その2
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)のご紹介です。前回の日記の続きになります。6月第2週の金曜日、 愛知万博20周年記念事業 が開催されているモリコロパークに2回目の訪問です。このモリコロパーク、数年前に虹の橋に行った愛犬のチビ子嬢がまだ元気な頃に、年に1回ほど行ってました。私の記憶に間違いがなければ、その頃は駐車場代が1回500円かかったように記憶しています。でも今は、前回行ったときに確認しましたが、平日は駐車場代が1時間30分までは無料になりました。(土日はわからないです)なので我が家からは若干距離があるけど、ちょくちょく行けばいいから、園内を散策して1時間半以内に出る予定で行動しています。いつもの北口駐車場に車を停め、西口駐車場のほうに向かってみました。20周年記念事業の一つとして、愛知県内の12の大学で24の学生チームが参加して作っている 彩の回廊 の作品の一つです。ここは場所の名前が「階段」で、この時は名古屋大学・恒川研究室の学生たちが作った「天翠皿」という作品が展示されていました。遠目ではよくわからないのですが、このような作品です。再生プラスチックを用いた円盤で、雨の日は目と耳で楽しめるとありました。これ、20年前に見た記憶があります。日本ゾーンにあった、からくり人形がでてくるモニュメントです。今でも11時から15時まで、ちょうどの時間に人形が出てくるようです。この時は9時半だったので人形が出るまで待てなくて確認してません。西口駐車場からすぐの西口広場の「こいの池」の前で、池の向こうに見える建物は、左手がアイススケート場で、右手が「ジブリの大倉庫」です。池の横を見ると小高い丘があり、上に上って行けたので行ってみました。いちばん高い所には「モリコロの鐘」があり、パーク内を見渡せます。私の前にいた方が勢いよく鐘を鳴らしたら、かなり響いてました。自然の地形を生かした通路です。モリコロパークはこの木々に囲まれた景色が見られるのがいいのです。ただ自然の中なので、ヘビや虫には注意とあります。林の中を抜けて下に降りていき、東エリアのほうに向かってみました。ここは「猫の城遊具」とあり、いつもなら大人は300円、子どもは100円になっていますが、この20周年記念事業の期間は無料で入れます。ちょうど遠足の小学生が来る前で、人は少なかったです。「猫の城」にはこのように迷路になっている遊具もあり、母子できたどこかの子供さんが遊んでいました。さて出る時間になったので、このエレベーターで北口駐車場に向かいます。この時は午前10時半でしたが、金曜日のせいか、リニモの駅及び北口駐車場の方から続々と来場者がありました。
July 24, 2025
-

愛・地球博記念公園(モリコロパーク)~その1
2025年、今年は大阪で万博が開催されていますね。私は諸事情で今は大阪の往復ができないので万博は行きませんが、行かれた皆さまはそれぞれに楽しんでいらっしゃるようです。そんな私は、地元の愛知県で20年前に開催された『愛・地球博』が今、 愛知万博20周年記念事業 を行っているので、そちらが気になっています。もっともこちらは、20年前の万博の後に整備された愛・地球博記念公園(モリコロパーク)に少し付け足すような形をとっていて、何かパビリオンを新たに建設した、とかではありません。それでも地元愛の強い愛知県人をはじめ、20年前のあの時間が大好きだった人にとっては、懐かしい空間になっていると思ってます。3月25日から開催され、9月25日で終わってしまうというのに、行動が遅い私は6月からやっと行く気になって動きだしました。まずは6月6日に行ったときの、一部の画像です。公園北口の駐車場から入りました。(駐車場からすぐの場所です)平日なのにやけに車が多いと思ったら、どうやらジブリパーク目当ての来場者で、まだ10時過ぎなのに関東・関西・北陸など遠くからの車もたくさんありました。この日は金曜日だったから、遠方からの車も多かったのですね。北口の駐車場から人々が一斉にこちらの方向に進んでいきました。ジブリの映画に出てきた何かの建物のようです。有料かもしれないと思い、私は脇の階段から進みました。下に降りて見上げると、こんな感じです。後で知ったのですが、これはただのエレベーターでだれでも乗れました。(この後、園内を散策していますが、その画像はまた次回に)この日は園内の位置関係がわからないので軽く散策するだけにして、車を停めた北口駐車場のほうに戻ってきました。休憩所にはキッコロがたくさんいました。この周辺に、案内所やお土産店やコンビニがあります。案内所で、愛・地球博らしきものは何か展示してないかと訊ねたら、すぐそこの地球市民交流センターを案内されました。階段を降りるとやや暗い照明の中にこの「地球の樹」がありました。樹の根元の割れたところに入ってみると、モリゾーとキッコロがいました。ただ長らく置いてあったから?それとも元々?背が縮んでました。地球市民交流センターの上に上がると植え込みで整備された通路があり、パーク内全体が見渡せるようになっていました。とりあえず反対側の出口に向かって歩いていたら、モリコロのバスを発見。どんな感じか、次回乗ってみようと思います。植物の植え込みに野鳥のための小屋?もありました。園内の植え込みは係の人が定期的に植え替えを行っているようです。
July 24, 2025
-
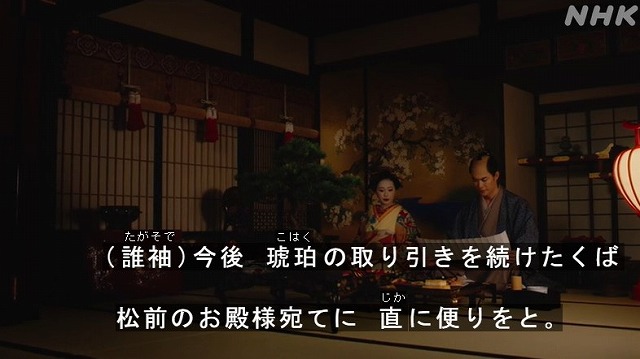
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第27回~「願わくば花の下にて春死なん」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は江戸時代の天明年間に起きた食糧不足による流民や米の価格の問題を見つつ、人間関係が何かの出来事から思いもよらぬ方向に徐々に動いていくのを見たように感じました。権力者を父に持ち、仕事では上から引き立ててもらえて陽のあたる場所にいて、家でも家族間で特別な苦労することもなく、好きになった女との未来を心に描いて幸せそうな田沼意知(宮沢氷魚さん)。片や家としての力は今はなく「田沼は当家の家来筋」と精神的にマウントを取るのを唯一の心の支えとする父・佐野政豊(吉見一豊さん)がいて、でもその父はすっかり耄碌して家では苦労が絶えず、自身も仕事ではうだつが上がらないままの佐野政言(矢本悠馬さん)。将軍の覚えがめでたい意知は政言だけでなく他の者たちからも羨望の的だから、悪意のある噂がいったん流れると次々と尾ひれがついて広まっていきます。そして政言のほうは初めの頃こそ意知の中傷は信じないようにしていたものの、なまじっか意知のそばにいる分、父の期待どおりに出世できない自分の不甲斐なさが少しずつ積もっていき、家での父の介護のストレスが重なって心が折れそうな隙をつくように意知の悪口を吹き込まれ、気持ちがどんどん歪んでいきます。親の過度な期待の重圧に苦しんでいたり、あるいは家族の介護で疲れ果てているものの、自分の苦悩を本人にぶつけられなくて、些細なことがきっかけで恵まれている他人を逆恨みしてしまうことは現代でもよくあることでしょう。そんな精神状態のところに悪意ある噂が次々と耳に入って、政言は凶行に及んでしまった、という流れでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明4年(1784)松前廣年が抜荷の片棒を担いだことから田沼意次が蝦夷地の上地を狙っていることを知った松前道廣は、一橋治済に上地はやめて欲しいと懇願し、事情を知った治済はこのままでは終わらせたくないようでした。そのころの世は前年の浅間山噴火と冷夏の影響で米の値が異常に上がり、その対応に田沼意知(宮沢氷魚さん)は追われていましたが、ようやく対策できてうまくいけば身請けもできると花魁・誰袖(福原遥さん)を喜ばせていました。ところが意知の考案した「米穀売買勝手次第」の策は全く効果がなく米の値は相変わらず高いままで、江戸の町には田沼の悪口を書いた紙が至る所に貼られ、庶民の不満はたまる一方でした。そして江戸には諸国から逃げてきた流民が次々とやってきて、流民を引き取るお救い小屋はすでにいっぱいとなり、行き倒れの流民が町にあふれていました。田沼の失策は人々の間で悪口と話に尾ひれがついた憶測となって広まりました。さらにはこれで大儲けした意知が吉原で紙花を撒いているとまで。そして奉行所から戻った鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)によると、町にあふれかえる流民たちは順にお救い小屋に入れるから待っておれ、とのことでした。立場の弱い者のことがつい気になる蔦屋重三郎(横浜流星さん)は寄合の皆に町で炊き出しをしないかと提案しますが、そんなことをしたら噂を聞きつけて次々と流民が集まってしまうと各々から反対され、鶴屋からは「蔦屋の身代を潰す覚悟があるならご勝手に。」と釘を刺されました。さて田沼屋敷では佐野政豊(吉見一豊さん)が「系図を返せ!」と怒鳴りこんできましたが、田沼意次(渡辺謙さん)は何のことか一向にわかりませんでした。そうこうしていると息子の佐野政言(矢本悠馬さん)が来て、父の無礼を深く詫びながら、強引に父を連れ帰っていきました。意次が政豊の耄碌を笑っていると意知と三浦庄司(原田泰造さん)が、あれはかなり前に意次が池に放り投げたと指摘し、意次はようやく思い出しました。このまま政言を放置できないと思う意知は父・意次に政言を何かで引き立ててやって欲しいと頼みましたが、意次は若年寄になったのだからと政言の面倒を見るよう意知に言いました。意知は政言を徳川家治(眞島秀和さん)の狩りのお供に推挙し、政言は願ってもない誉れとたいそう喜んでいました。しかし狩りの当日、政言の放った矢は獲物を捕らえておらず、意知の呼びかけで再度探したものの獲物も矢も見つかりませんでした。捜索で待たせたことを意知は詫びますが、家治の信頼が厚い意知は「友を信じる心遣いに感服した。」と褒められ、逆にせっかくの好機なのに政言は上様の目にとまる働きができなくて落胆し、その様子をそばで見ている者がいました。政言の一日も早い出世を願う父・政豊は、いつか政言が上様の目にとまったら、せめて自分のこの刀だけでも共に連れていってもらいたいものだ、と期待に胸を膨らませていました。するとそこに、あの狩りの日に同行したという男(矢野聖人さん)が話があると訪ねてきて、政言の矢と獲物らしき鳥を持ってきました。男はあの日、意知がこれを見つけて隠したのを見たと言い、政言は最初はそんな話は信じられないと言いました。しかし男はさらにもっともらしいことを言い、政言の心の中に意知に対する疑心暗鬼がかすかす生じたようでした。(このシーン、政豊役の吉見一豊さんは話に耳も貸さずずっと刀をいじっていて、耄碌して頭の中は自分の思いしかない老人を演じていました。)田沼意次と意知はなんとか市中の米の値を下げる策はないかと家臣たちと苦慮していましたが、米の値は高止まりしたまま動きませんでした。生活するのがやっとの庶民は本など買える余裕はなく、一方吉原では米で大儲けした一部の者たちが景気よく金を使っていましたが、同時に売られてくる女郎が増えたとのことでした。米の高値が田沼親子や花魁・誰袖のことに影響し、そして流民たちのことも心配する重三郎に妻・ていが「町からお上に献策というのも日本橋らしい」と提言し、重三郎は吉原では知らなかった知識を得ました。早速町の旦那衆を集め、庶民が生活苦のままだと自分たちだって商売に困るから献策を考えようと皆に呼びかけました。鶴屋喜右衛門は「お上がもっと身銭をきればいい。お触れだけで事をおさめようなんて虫がいい。」と言い、他の皆もそれぞれに思うところを述べ合い、献策を練り上げていきました。そして策がまとまり、重三郎は田沼意知に会いに行きました。お上が何かの形で米を仕入れ、その仕入れ値で庶民に引き渡したらどうかという話を、意知ははじめお上は商いはできぬと断りました。しかし重三郎は「これは商いでなはく政。食べるのに精一杯になれば庶民は世の中の食べること以外のあらゆることを慎むようになり金の巡りが悪くなる。その流れを断ち切るのは商いではなく政。」と進言しました。その後で重三郎は意知に誰袖花魁の身請けを乞いましたが、意外にも意知はその件ではもう手を打ったとのことでした。意知は、かつて父・意次が平賀源内を救おうとしたのをお家のために見捨てよと自分が止めさせた、蝦夷の上地ことは源内への罪滅ぼし、蝦夷のために尽力してくれた誰袖を見捨てることはできない、と自身の思いを重三郎に伝えました。後日幕閣内での話し合いの折、水野忠友(小松和重さん)から、大坂の奉行所が米穀売買勝手次第を悪用して酷い買い占めを行った悪徳な米問屋をまとめて投獄、20万石の米を召し上げた、と報告がありました。そう聞いた意知は即座に発言を求め、その米を公儀が安く買い上げその値で直に市中に払い下げてはどうかと進言、「これは商いではなく政。飢えに苦しむ民を救い世を救うための政。」と老中たちに訴えました。意知の進言を父・意次は大変満足そうでした。しかし城内では、意知が米で私腹を肥やして吉原通いをしているととんでもない中傷が流れていて、政言も意知を疑うようになっていました。家に戻れば老いた父・政豊を労わる政言でしたが、父はかつて5代将軍・綱吉公から賜った名誉の桜に花が咲かないことに腹を立てていて、政言を愚か者、出来損ないと罵って打ち据えていました。庭での騒ぎを聞きつけて家臣が政豊を引き離し、先日来たあの男がまた佐野家に来ていて政言にある噂を伝えました。田沼意次が預かった大切な佐野家の系図を無きものにした、田沼が寄進した桜は立派に育ち見事な花を咲かせているがあれは佐野家の桜では?と。うだつの上がらぬ自分は父が癇癪を起こせば理不尽に責められる、耄碌した父は咲かない桜に「咲け!」と刀を振り回して叫ぶ。恵まれた意知との違いに政言の気持ちはどんどん暗く歪んでいきました。意知は花魁・誰袖を身請けするために、表向きは土山宗次郎が誰袖を身請けした形をとることになりました。重三郎は餞別として歌麿に描いてもらった誰袖の姿絵を贈り、誰袖は女郎として嫌な客を取るときには重三郎の顔を思い浮かべていたと打ち明けました。大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)は、この吉原はぼ~っとして幸せになれる場所じゃないから女郎たちは誰袖を見習って逞しい腹黒になって欲しいと言い、また重三郎は誰袖の話はここで生きるしかない女郎たちのとびきりの励みになるからいつか本にしたい、とそれぞれに思いを伝えました。やっと吉原を出て幸せになれるーー誰袖は意知と一緒に夜桜見物をする時間が来るのが待ち遠しくて仕方がありませんでした。誰よりも自分の立身出世を願っている老いた父が憐れになり、政言は泣き笑いして自分が佐野の桜を咲かせてみせると父に約束しました。そして何かを決意したように、すっかり古びた父の愛刀を手入れしていました。仕事を終え今宵の誰袖との花見を楽しみに意知が戻ると、政言は意知を呼び止め、思い詰めた面持ちで意知の前に立ちはだかったかと思うと、いきなり刀を抜いて斬りかかってきました。
July 17, 2025
-
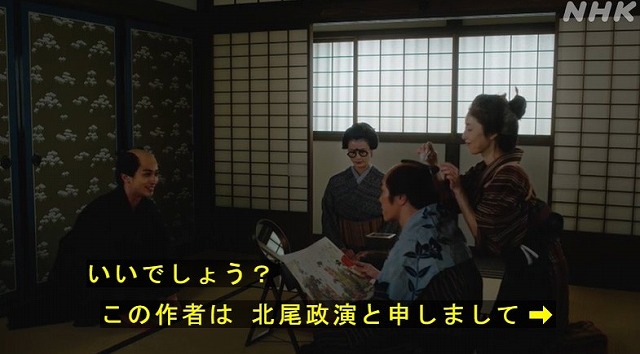
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第26回~「三人の女」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話はタイトルが「三人の女」で本来はそちらのほうがメインの話なのですが、私は無理やり蝦夷地を上地するために画策する田沼意知(宮沢氷魚さん)とその周囲の動きが気になってしまいました。愛する意知のために花魁・誰袖(福原遥さん)は松前廣年(ひょうろくさん)を手玉にとって抜荷をさせるという危ない橋を渡り、意知はそんな誰袖を愛おしく思うようになりました。前回はそんな流れで、誰袖の努力が報われてたのだと思ったけど、この回ではまた流れが変わりました。意知が自分に心を向けてくれたことが嬉しくてたまらない誰袖は、傍目にもわかるほど意知への思いを表し、それは周知のこととなりました。でもそれは、まだすべてが終わっていないのに人のうわさになる油断だったと思います。浮かれた誰袖のことはやがて廣年の耳に入り、自分は誰袖と思い合っていると信じていたからこそ、本当はやりたくなかった抜荷をやってしまった廣年は大きなショックを受けます。事が完全に終わるまでは、自分の本命は松前廣年だと、本人にも周囲にもそう思うように誰袖は振る舞い、言い聞かせておくべきだったと思えてならないのです。信じていた者に裏切られたときの悲しみと怒りと辛さは、女郎をやってきた誰袖なら想像ついたと思うのですが。田沼親子にとって米のことはとりあえず切り抜けたけど、蝦夷の上地のことは危機になり、さらに意知には二人の男の逆恨みの念が付いてしまったようです。次回の展開が恐ろしいですね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)夏、浅間山の大噴火だけでなく冷夏が続いたことによる米の不作と、米商人たちによる市場操作で米の値段が昨年の倍になり、幕閣内でも大きな問題となっていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は日本橋で大店の主となり、たくさんの奉公人や店に集まる仕事仲間たちに出す米代が恐ろしくかかることを知りました。そんな中で重三郎の生みの親だけど彼を幼い頃に捨てたつよ(高岡早紀さん)が息子の出世を聞きつけ、勝手に店にきて我が物顔で上がり込んでいました。重三郎は母親の顔も見たくなかったのですが、事情を知らない(まだ形式上の)妻のてい(橋本愛さん)が親孝行と言ってつよを許してしまったので、重三郎も渋々認めることになりました。でもつよには髪結いの技があり、旅人の髪を直す間に息子の商売の手助けをする機転も利く女だったので、重三郎も少しは母親を見直すことになりました。重三郎が旅人に作品の紹介をしているのを見ていたていは、食事の時に重三郎にこの際だから本や絵のつながりを示した「品の系図」を作ってはどうかと提案し、みの吉(中川翼さん)も重三郎の売り込み方に驚いたと言いました。ていは、皆があれをできるようになるといい、そのための手引き書となる「品の系図」があるといいと進言し、重三郎はその仕事をていに頼みました。この先の店の仕事についての皆のやりとりを歌麿(染谷将太さん)は特に意見をすることなく聞いていたかと思うと、突然この店を出ていくと言い出しました。自分はこの店にいなくてもいいと言う歌麿に重三郎は、主人の義弟として堂々とここに居ればいい、出ていくのは許さないと言いました。しかし歌麿を大事にする重三郎を、ていもまた複雑な思いで見ていました。自分への真剣な思いとそのために抜荷に絡む危ない橋を渡る花魁・誰袖の度量に心を打たれた田沼意知(狂名は花雲助;宮沢氷魚さん)は誰袖を本当に愛おしく思うようになり、誰袖も嬉しい気持ちがつい人前に出るようになりました。花雲助の男前ぶりと誰袖がぞっこんになっていることは女郎たちの間でも評判になっていて、誰袖が自分に夢中になっていると信じ、愛しい誰袖のために無理をして抜荷の仲介までした松前家当主の弟の松前廣年(ひょうろくさん)は、女郎たちの話を耳にして愕然としました。なんとか米を安く買いたい重三郎は駿河屋市右衛門の伝手で、札差の大引赤蔵(林家たい平さん)を紹介してもらいました。吉原に来た赤蔵に引き出物として四方赤良(本名は大田南畝;桐谷健太さん)の直筆の狂歌扇を贈るとたいそうな喜びようで、重三郎が米のことを頼むと赤蔵はおととしの米ならもっと安く卸せると快諾してくれました。重三郎と赤良が米倉に足を運ぶと、その様子から本当は米は余りまくっていて、商人たちが売り惜しみをして値をつり上げているのだろうと感じました。老中・田沼意次は堂島や米問屋や仲買人たちに米の値段を下げるように、市中のつき米屋には仕入れ値で売り渡すよう命じていました。しかしそのお触れに従う店はごくわずかで、人々がそこに買いに行ってもすぐに売り切れてしまい手に入りませんでした。重三郎は、米を生産できない自分たちでも米の値を下げることが何かできないか、米に困れば本なんか買ってもらえない、と赤良に言いました。すると赤良は立ち止まり、空を見上げ両手を広げ「米、来い!」と繰り返し叫び、天に向かって言霊を叫ぶ赤良の姿を見て人々も一緒に叫びました。その姿を見た重三郎は「それだ!」と何か思いつきました。蔦屋の店ではていとみの吉が重三郎に頼まれた系図作りを一生懸命にやっていて、それを見た歌麿は作者と絵師ではなく内容でつなげたらどうか、あと印をつけて区別したらどうかと助言しました。ていは重三郎が「歌麿は当代一の絵師」と言っていたのを思い出し、歌麿は才があるのだと改めて思いました。すると重三郎が大田南畝と宿屋飯盛(又吉直樹さん)を連れて意気揚々と帰宅し、「米の値を下げるために正月に狂歌集を出す。米一粒作れない役立たずの俺たちだから、天に向かって言霊を投げつける。急ぎの仕事だ。」と歌麿に言いました。いつも以上に無理な仕事だとわかっているけど、歌麿は仕方ないと笑って快諾し、その様子をていとみの吉は感心して見ていました。さて江戸城では、徳川御三家の紀州和歌山藩藩主・徳川治貞(高橋英樹さん)が下がらぬ米の値について意見しに出てきて、由々しき事態となっていました。治貞は田沼意次(渡辺謙さん)の政策の「物の流れを良くすれば皆が儲けを得て富み栄える」という点で、市中に米はあれど流通していないことを追究し、このような世を作り出してどのように責めを負うつもりなのだと厳しく叱責しました。意次は平身低頭で、必ず米の値を下げる策を考えだすからしばし時間を!と懇願するしかなく、意知は父のその姿を見て自分も策を考えなければと思いました。意知は重三郎の店を訪ね、米の値を下げるにはどうしたらよいか、商人のことは商人に訊くのが一番だから、と相談しました。同じ思いを持つ重三郎は、実は自分たちは今「歳旦狂歌集」を作っていて言霊でめでたい世を呼んで米の値を下げようという企みをしている、と言いました。意知が重三郎の発想に感心していると「地本問屋内にある株仲間に認めてもらえないと本を流せなかった。仲間なんて潰れたら自由に本を売れるのにと思った。」とつぶやきました。でも、そう聞いた意知は何かひらめいたようで、急ぎ店を出ていきました。その様子を見ていたていは、あのように相当偉い武士ともつながりがある重三郎という男はいったい何者なのか、と思ってしまいました。形式上で夫となった重三郎だけど、彼は自分の予想をはるかに超えた人だったとわかったていは、重三郎に頼まれていた「品の系図」を仕上げるために黙々と作業に取り掛かりました。また歌麿のほうも、何度も入る書き直しに時には苛立ちながらも重三郎のために頑張って仕事をこなし、重三郎は歌麿に心から礼を言いました。すると「ていがいない」と折りたたんだ紙を持ってつよが入ってきて、その紙を広げてみるとそれは見事に整理されて美しく描かれた系図でした。ただ書き置きには「皆様のご多幸と蔦屋の繁盛を心よりお祈り申し上げます。」とあり、ていがこの家を出ていってしまったのだと重三郎直感しました。重三郎はていが向かったであろう寺まで急いで走っていきました。ていが寺に入る直前にどうにか間に合い、つよのためにていに不便を強いていることを重三郎は詫びたのですが、ていの思いは違っていました。「江戸一の利者の妻は自分では務まらない。石頭のつまらぬ自分より、蔦屋の妻にはもっと華やかで才長けた女子がいい。」と言って寺に入ろうとしました。でも重三郎は、自分はていのことをつまらぬ女と思ったことはない、縁の下の力持ちなところも好き、皆のために掃除したり系図作ったり、とていのいい所を並べつつ、なにより「自分と同じ人に出会っちまった」と。そして「この先、何があっても一緒に歩きたい。ていは俺のたった一人の女房。」と言って重三郎が手を差し出すとていはその手を取り、ようやく心を許しました。さて江戸城内ですが、田沼意次は徳川治貞に「米に関わる株仲間を一旦廃してはどうか」と進言し、その理由を若年寄となった田沼意知が「米の値をつり上げる元凶となっている株仲間を一旦は無きものとし、誰でも米を売ってよしとする。そうすると皆が競い合って値を下げるのでは。」と説明しました。こうしてひとまずは難局を乗りきった田沼親子でしたが、廊下を立ち去る意知の背中に恨めし気な視線を送る二人の男ーー佐野政言と松前廣年がいました。
July 10, 2025
-
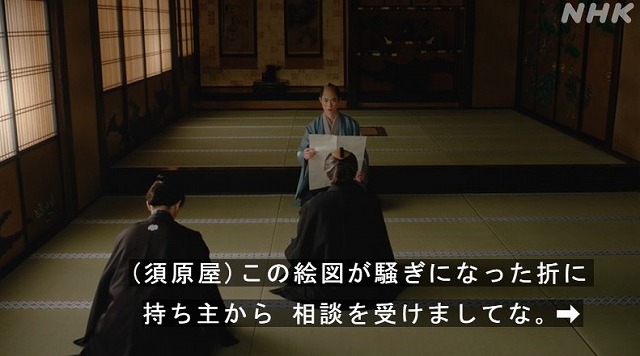
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第25回~「灰の雨降る日本橋」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回の最大のインパクトで感動は、鶴屋喜右衛門を演じる風間俊介さんでした。まさかラストであのような胸が熱くなる展開が待っていたとは、という思いです。喜右衛門は主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)に対し、罠にはめたり意地悪をしたりということは特になかったように思います。しかし重三郎を吉原者として排除し、けっして認めて受け入れることはありませんでした。でも大量の灰を片付けるという面倒な作業を、組み分けして競争することにより人々を夢中にさせ、あっという間に終わらせました。そして競争をあえて引き分けとし、夜は重三郎と自分が出した金で宴を開いて町の皆を楽しませていました。人々を立場や力で無理やり動かすのではなく、自分から動くように仕向け、人々は生き生きと夢中になって動くから作業の能率はUPする。そんな重三郎の手腕を見て、喜右衛門は自分にはない才覚を感じたのでしょうか。今まで生まれ育ちで隔ててきた重三郎を認めて受け入れ始めた瞬間だったと思います。そして認めたら後は早い。町の皆に呼びかけて暖簾を作り、お礼と祝いを快く述べ、今後の期待を伝える。今まで自分を嫌っていた喜右衛門からの、思いがけない言葉と贈り物。これは重三郎も嬉しくて感動で泣けるでしょうね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)、蔦屋重三郎(横浜流星さん)は吉原から日本橋への進出を目指していて、店を買うためにさまざまな方法をやってみましたが、安永7年(1778)に出されたお達しのためにその都度、話が流れていきました。その店はいったんは柏原屋が買ったのですが、その柏原屋が重三郎に自分からこの店を買わないかと言ってきました。重三郎は以前、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)が蝦夷地の絵図を持っていることと、その絵図を田沼意知(宮沢氷魚さん)が必死に探していることを思い出し、市兵衛を通して意知に会いに行きました。市兵衛は意知に、この絵図で仲立ちをしてくれた重三郎が日本橋に店を出すにあたり力添えが欲しいと頼み、意知は快諾しました。(前に重三郎が店に来たときに、何かに使えるかと思ってかわざわざ蝦夷地の絵図を見せてやったりと、市兵衛は重三郎を見込んで可愛がっていますね。)8月になったのに夏らしくない気候の中、浅間山が大爆発を起こしました。江戸には浅間山から大量の火山灰が降ってきたのですが、日本橋の人たちとなんとか仲良くなる手立てはないかと考えていた重三郎はこの降灰を恵みの灰と捉え、大量の古着をかき集めて自分が買ったていの店に行きました。重三郎は店の屋根に上り、瓦の隙間や樋に灰が詰まらないよう古着で覆い、町の皆にも屋根の保護を早くやるよう勧めました。人々は吉原もんの重三郎がこの日本橋にいること云々よりも、今はとにかく重三郎の言うように屋根を覆ったほうがいいと理解し、急いで古着を集めて屋根に敷き始めました。(私は2014年に御嶽山が噴火した時に、火山灰が水を吸うと重く固くなるということを知りました。このまま放置すれば屋根が重たくなり樋が壊れる。重三郎はこのことを本の知識で得ていたのでしょうね。)意知はこのとき吉原に来ていて、店の外に出て屋根を覆ったり灰を片付けたりする手伝いをしていました。意知のことが好きで意知のために命がけの陰の働きをずっと続けている花魁・誰袖(福原遥さん)は意知の活躍を2階から嬉しそうに眺めていたのですが、そのとき他の女郎・わかなみが意知に言い寄るのを見てしまいました。頭にきた誰袖は2階から飛び降り、わかなみと取っ組み合いの大喧嘩を。灰まみれになった誰袖は風呂を浴びて、髪を結わないままの姿で意知の前に出たのですが、意知はなぜか気持ちが乱れすぐに店を出ようとしました。もう1年半もこのようなことをやっていると誰袖が悲しそうに意知に伝えると、意知は誰袖の働きには必ず報いると約束しますが、意知は心をくれないのかと誰袖の気持ちはむなしいままでした。噴火の降灰がようやく収まると、江戸の町はそこらじゅうが灰だらけでした。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)が出てきて、奉行所からのお達しで早急に各店で灰を川や海や空き地に灰を捨てるように、とのことでした。するとそのとき重三郎が声をあげ、皆で一緒に灰を捨てようと言って、突然ほうきで地面に線を引いて行きました。重三郎は町を2つの組に分け、灰を捨てる競争をする、勝った組には自分が褒美で10両出す、と言いました。それを聞いた鶴屋は負けじと自分は25両出すと言い、喜んだ皆は一斉に力を合わせて灰を片付け始めました。大量にあった灰はみるみるうちに片付いていき、灰捨て競争は引き分けとして、夜は皆で仲良く宴となりました。これは「日本橋の人たちと仲良くなるためには」と考えていた重三郎の狙いであり、重三郎は宴では吉原仕込みの芸を披露して皆を楽しませていました。そんな重三郎の姿を鶴屋喜右衛門は離れた場所からじっと観察していて、また重三郎も喜右衛門の視線を感じていたのか時折り喜右衛門のほうを見て様子をうかがっていました。重三郎が店に戻るとてい(橋本愛さん)が畳を拭き掃除をしていたので重三郎も一緒に掃除を始めると、ていは「陶朱公」の話を始めました。ていは話を例えにし、重三郎には移り住んだ土地を富み栄えさせる才覚がある、店を譲るならそういう方にと思っていた、と自分の考えを伝えました。そしててい自身は店を出ていくと言い、そう聞いた重三郎は「陶朱公の女房にならないか。力を合わせて一緒に店をやろう。」と改めてていに求婚しました。しばらく黙っていたていですが重三郎に日本橋での言葉遣いを教え、どうやら重三郎を受け入れたような感じがありました。誰袖は愛する意知のために松前廣年に密貿易をさせようと色仕掛けで廣年に迫り、その甲斐あって廣年は裏取引きをしてきました。しかし自分が危ない橋を渡っているのに誰袖の好意を感じないと廣年が不満をもらすので、誰袖は廣年の機嫌を損ねないよう努める日々が続いていました。そんなある夜、意知が突然誰袖を訪ねてきました。意知が誰袖を求める短歌を扇子にしたためて渡すと、やっと意知が自分に心を向けてくれたことが嬉しい誰袖は、素直に喜びを伝えました。意知は誰袖を女子として受け入れると間者働きをさせるのが辛くなる、しかし蝦夷のことはやり遂げねばならぬ仕事だ、と思いを伝えました。「好いた女子」の言葉に今までの努力が全て報われたと感じた誰袖は、自分の弱さの許しを乞う意知に「形だけでいいから」と膝に枕するよう要求。でもその後、二人には形だけでない時間が流れていきました。さて田沼意次(渡辺謙さん)ですが、蝦夷地の抜荷の絵図が手に入ったことにより、上地の下調べとして意知が蝦夷に間者を放ったと将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に報告しました。そう聞いた家治は、意知を若年寄にしないか、奏者番では表立って政に関わることができぬ、と言いました。意次は父として家治の言葉を有難く思いつつも、さすがに意知には早すぎると辞退しましたが、家治は自分の余命はもう長くないかもしれないと感じていて、意次のこれまでの働きに報いてやりたい思いがあったのでした。そして後日、重三郎とていは正式に夫婦になることにし、祝言を挙げました。吉原の皆も正装して集まり、座敷に入れない人たちは廊下から見ていました。眼鏡をはずしたていはそれは美しい女人で、一瞬誰だかわからないほどでした。固めの杯でていの動きが止まるので媒酌人の扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が声をかけると、それは眼鏡がなかったからでした。眼鏡をかけるといつものていになり、皆もどこか安心しました。ところが祝いの挨拶の後、この祝言の場に鶴屋喜右衛門が訪ねてきました。これまで何度も吉原と対立してきた鶴屋が何しに?と一同は緊張しました。喜右衛門は祝いの挨拶の後に、日本橋通油町として祝いの品を贈りたいと言い包みを差し出しました。重三郎が包みを開けるとそれは鮮やかな青の地に白い蔦の葉が描かれた暖簾で、まさしく重三郎のために用意されたものでした。喜右衛門は、吉原の気風のおかげで灰の片付けが早く楽しく済んだと礼を言い、「江戸一のお祭り男はきっとこの町を一層盛り上げてくれる」と笑顔になり、日本橋に重三郎を快く迎える旨を祝いの言葉にして伝えました。嬉しさで感涙する重三郎、そして駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は鶴屋にこれまでの数々の無礼の許しを乞い、吉原の一同も深く頭を下げました。喜右衛門も頭を下げ、これからはより良い縁を築きたいと思いを伝えました。重三郎は喜右衛門に「頂いた暖簾、けっして汚さないようにします!」と誓い、ていの丸屋が「蔦屋耕書堂」として生まれ変わって店が開かれました。町の人たちが作ってくれた色鮮やかな暖簾がひるがえり、賑やかに囃し立てられた店には次々と客が入っていきました。店の中には景気の良い声が響き、歌麿たちも大忙しで働いていました。しかし一方で浅間山の噴火による恐ろしい事態が迫っていました。
July 4, 2025
-
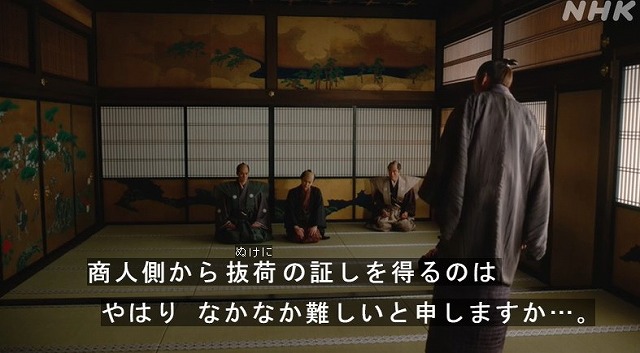
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第24回~「げにつれなきは日本橋」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星さん)と、今は彼を嫌っているけどいずれ妻となるてい(橋本愛さん)がどのように接点を持つのかを注目して見ていました。ていを説得するために重三郎は手立てとなる情報を集めるのですが、でも結局は自分の耳でていの心情を直に聞ける場面がありました。重三郎が心の奥に残る花魁・瀬川への思いを一区切りさせ、ていを新たな人生のパートナーとさせる強力な要因は何か。それは本が世の中で大きな役割を持っていて、身分の高き低きに関わらず、本が人々に知識を与え、世の中をもっと豊かにしていくという思いが互いにあると確信したことで、まさに「同志」を見つけたという感じでした。自分と距離をとる相手が、心情を変化させていくきっかけとなる出来事とは何か、その後の流れはどうなのか。もう国語の物語文を見るような感じです。森下氏の脚本力に期待し、次回の展開を楽しみにしたいと思っています。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)、蝦夷地を上地するための手立てを平秩東作(木村了さん)に探らせていた田沼意次(渡辺謙さん)と嫡男・田沼意知(宮沢氷魚さん)は、上方から戻った東作の報告を受けていました。東作によると、商人側から抜荷の証を得るのは難しい、商人たちと深い話をするとこちらの動きが相手に漏れてしまう、とのことでした。結局、八方塞がりで何も実りがなかったことを、側近の土山宗次郎(栁俊太郎)と東作は意次に詫びていました。さて日本橋への進出を目指す蔦屋重三郎ですが、扇屋宇右衛門からまずは店を買って押さえることが大事だから亀屋を表に出して店を買うよう助言されました。そこで日本橋には吉原者は立ち入ることができないので、買い取りの交渉は亀屋に任せたのですが、すぐ嘘を見破られてしまいました。その後、商人たちの会合で鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は安永7年(1778)に出された「吉原者は見附の内の家屋敷を買えない。市中の方も売れない。」というお達しを皆に再確認させ、日本橋に吉原者が入ると町の格が下がるとも言いました。ただ、てい(橋本愛さん)が皆に詫びて今後のことを頼むときに、韓非子の一節を例えに出して話し始めたら皆は面倒くさそうな嫌な態度になり、話の途中で鶴屋がさえぎってしまいました。亀屋の件が失敗になったので次の手をどうしようか、親父衆は考えていました。若木屋与八(本宮泰風さん)が「丸屋のおかみさん(てい)が欲しくてたまらないものはないか。」と言うと、りつ(安達祐実さん)が「男?」と言ったことで皆は妙に納得してしまい、蔦屋重三郎(横浜流星さん)自身がていに色仕掛けをすればいい、という意見にまとまってしまいました。重三郎が店に戻ると東作が来ていたので、丸屋のていとはどんな人なのかを訊いてみましたが、東作もよく知りませんでした。でも絵師の北尾重政なら知っているかも、と話し始めたらちょうど時間がきたので、東作は吉原のどこかに行ってしまいました。東作が向かった先は、花魁・誰袖(福原遥さん)のところで、客として松前廣年(ひょうろくさん)が来ていました。誰袖は東作を廣年に「琥珀の取引に詳しい人。」と紹介しました。でも生真面目な廣年にはご法度となることはやはり気が進まず、何より兄・道廣に知られることを酷く恐れていました。誰袖がいざとなれば私のせいにすればいいと言うと廣年はようやく安心し、東作の話を聞く気になれました。その様子を座敷の裏にある部屋から覗いていた田沼意知と土山宗次郎は、廣年では大胆なことができなくてどうも頼りないので、いっそ藩主の松前道廣が抜荷の話に乗ってこないかと期待しました。その松前道廣(えなりかずきさん)ですが、余興では相変わらず家臣を鉄砲の的代わりにして遊んでいました。田沼意次は三浦を使って廣年が吉原に出入りしていることを兄であり藩主の道廣に知らせると、道楽で藩の金を無駄遣いをしているのかと道廣は激しく怒りました。鉄砲を向けられた道廣は誰袖に言われていたように誰袖のせいにして兄に許しを乞いましたが、恐怖で発砲される前に気絶してしまいました。丸屋を買うためになんとか女将のていを説得できないかと思う重三郎は重政に会って、ていのことを詳しく知る人がいないか訊ねました。しばらく考えた重政は重三郎に、ていが漢籍を習った寺に行ってはどうかと助言。重三郎がその寺に行ってみると、ちょうどていがいて住職の覚圓(マキタスポーツさん)と何やら話をしているところでした。ていは処分する店の本を寺に寄付し、寺に来る子供たちの手習いに役立てて欲しい、そうすれば本は生きる、と住職に頼んでいました。ていの話を聞いたときに重三郎はふと平賀源内の言葉を思い出し、自分とていは同じ志を持っているように感じました。それからていの身の上話を聞き、重三郎はていの望みがわかった気がしました。重三郎が店に戻った夜、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)と扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が来て「明日、日本橋に乗り込む。」と言いました。親父衆はツテを辿って丸屋の証文を買いあげてあり、これで店の明け渡しを迫る、上品な手じゃないけど他の買い手が決まる前に、ということでした。翌日、親父衆と重三郎は「吉原者出入無用」の立て札もお構いなしに、日本橋の通油町に乗り込んでいきました。(並んだときのこの微妙な位置関係がいいですね。吉原の総代表の扇屋が先頭で、半歩後ろには駿河屋と、和泉屋の葬儀での出来事を一番怒っていた丁子屋長十郎(島英臣さん)、そして他の皆が続くという並びです。そして、ただ並んで歩くだけのシーンがこれほど迫力があってカッコイイとは。ベテラン俳優の皆さんが「乗り込む」という場面の心情や振る舞いを自然と表現できるからでしょうね。)そのころ丸屋では柏原屋との間で売買契約を進めるところで、親父衆はちょうどその時に中に乗り込んできました。鶴屋喜右衛門が吉原のやり方を非難した時、重三郎は自分なら丸屋の暖簾は残すと言い出し、その意味を話すために前に進み出ました。重三郎は丸屋と蔦屋を一つの店にしてはどうかと提案、そして「本当は店を続けたいのでは?」とていに問いかけました。ていはその話は断ったのですが、ならばと重三郎は自分と一緒になるのはどうかと言い出し、建物の売り買いは禁じられているが縁組はお達しに背かない、店を一緒にやるのは当たり前とていに迫りました。しかし縁組の話はていをかえって怒らせてしまい交渉は決裂、吉原の皆はもう引き下がるしかありませんでした吉原に戻った皆は、作戦の練り直しをしました。重三郎の過去に自分の部屋の花魁・瀬川とのことがあったせいか松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)は、なぜ店を一緒にやろうと言い出したのかを訊ねました。ていは自分が店を潰したことを不甲斐なく思っているようだから店を続けられるなら話に乗るかと思った、と重三郎は答えました。するとりつが芸者衆から聞いた噂で、ていの旦那は金目当てでていに言い寄った、それに気付かなかったていが世間体や親のことを考え夫婦になったけど、旦那はすぐに吉原通いを始めて散在して借金までした、という話をしました。そしてりつは重三郎に「独り身の自分につけこむあんたは、ていから見たら前の旦那と同じに見える。」と意見してやり、重三郎は自分の失敗を痛感しました。一方、蝦夷地を上地するために花魁・誰袖を使う田沼意知は、松前廣年の動きがあれからないことが気になっていました。すると女将の志げが慌てて部屋に駆け込んできて、道年だけでなく藩主の道廣も一緒に来たと言い、意知はすぐに隣室に身を隠しました。道廣ははじめは機嫌よく遊んでいたのですがじきに人払いをし、主人の大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)を呼びつけました。道廣は市兵衛に、誰袖の琥珀の直取引を企みを知っていたかを詰問、市兵衛はそこまでの事態は知らなかったと道廣に許しを乞いました。しかし意外なことに道廣は、いっそのこと直取引(=抜荷)を松前家と吉原でやって琥珀で大儲けしないか、と持ち掛けてきました。思いがけない好機が来たと、隠れている意知は息をのみました。さてその頃の江戸ですが、夏になっても肌寒いおかしな気候が続き、また地鳴りもよく起こっていて、人々は不安を感じていました。そんな中、重三郎が出かけようとしたときに柏原屋与左衛門(川畑泰史さん)が店を訪ねてきて、浅間山が火を噴いているらしいと教えてくれました。そして柏原屋は重三郎に、自分から丸屋の店を買わないかと持ち掛けてきました。
June 26, 2025
-
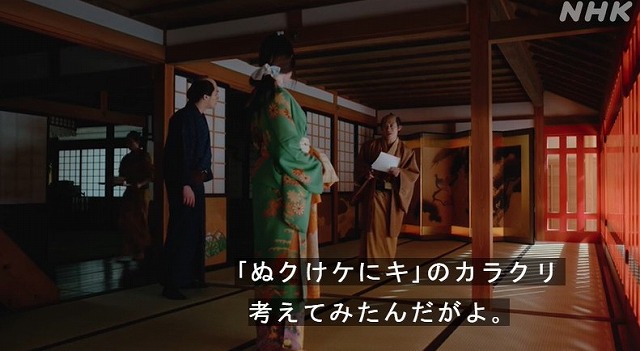
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第23回~「我こそは江戸一利者なり」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、一番感じたのは「人が大きな決断をする時」ということでした。出版の仕事が波に乗ってきた主人公・蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、日本橋に店を構えてそこから本を出したいと思い描きました。しかし、大金が必要なこと、長年の吉原のしがらみ、吉原に店を出してやると声がかかる話は直感的に危ないと感じて引き受ける気になれない、そんな状態が続いていました。でも運命を切り開いて進んでいく者には、ちゃんとその道と機会が用意されているいのでしょうか。重三郎が駆け出しの頃から何かと相談に乗ってくれ、助言もくれていた須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)が、この時も日本橋というい土地の価値を教えてくれて、さらに迷う重三郎を励ましてくれました。大きな賭けで、もし失敗したらという不安や恐れは、「この先何がどうなっても必ず重三郎の傍にいる」と歌麿(染谷将太さん)が約束してくれた事で和らぎ、心の支えを改めて確認しました。でも重三郎の気持ちを固めたのは、世間で冷遇された吉原の親父衆たちの姿でしょうか。自分のことと同じくらいに相手を思う重三郎だから、厳しい世界だけど自分を育ててくれた親父衆を侮辱する世の中を見返してやる、と反発もエネルギーになっていたと感じました。さて、そんな重三郎の前進していく話の片隅で、皆とは違って一人調子の波に乗れず、あきらめや自己卑下のような負の感情を出していた佐野政言(矢本悠馬さん)に、つい注目してしまいました。史実では佐野は間もなくとんでもない事をしでかすのですが、万事控えめで親思いのあの優しい男が、どんな感情の流れであの大事件を起こすのか。ドラマの展開が楽しみであります。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明2年(1782)暮れ、吉原の者も仲間に欲しい田沼意知(宮沢氷魚さん)は蝦夷地を上地する計画を蔦屋重三郎(横浜流星さん)に話し、一緒に仲間になるよう誘いましたが、重三郎はこの話を断りました。この話には花魁の誰袖(福原遥さん)も抜荷で一枚かんでいると重三郎は感づき、危ないからやめさせようと誰袖に忠告したところ誰袖は話をはぐらかし、さらに主人の大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)までこの話に乗り気になっていました。事がうまく運べば、誰袖は好きな男(意知)に身請けしてもらえ、大文字屋には大金が入るので、二人は綿密に計画を練っていました。天明3年(1783)大田南畝(狂名・四方赤良)が世間で大人気となり、ついでに重三郎の名も世間に広まりました。耕書堂では狂歌の指南書『浜のきさご』は飛ぶように売れ、その他の品もとても評判の良いものでした。重三郎は江戸一の目利きの「利者」と呼ばれるようになり、贔屓筋の付き合いや出版の各所での打ち合わせ等で毎日多忙を極めていたので、ふじ(飯島直子さん)たち吉原の女将たちが店を手伝ってやっていました。さてこちらは田沼意次(渡辺謙さん)ですが、自分の理想とする政を推進するためにも、幕府内の要職を自分の身内や考えの近い者たちで固めていました。また意次の嫡男・意知を特例で奏者番に抜擢するなど、意次の勢いは周囲も圧倒されるほどでした。一方で意次に目をかけてもらえなかった一部の者たちは狂歌をたしなみ、意知の側近の土山に近づいて繋がりを作ろうとしていました。土山邸の酔月楼で催される宴会に顔を出した長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)や佐野政言(矢本悠馬さん)らは、350俵の組頭の屋敷とはとても思えぬ豪華な屋敷と宴会にただただ驚くばかりでした。意次の覚えがめでたければこういうこともできるのかと感心しつつ、どうやって土山に近づこうかと考えていたら、平蔵は重三郎の姿を見つけました。平蔵は自分たちを土山に紹介してくれるよう頼み、重三郎は快諾。土山がちょうど大田南畝(桐谷健太さん)と一緒にいたので重三郎は挨拶に行き、平蔵らを紹介しました。ただ平蔵の名を聞いたときに南畝が平蔵の父の話で盛り上がってしまい、うまく自己紹介ができなかった佐野は、自分にはこういう場は合わないからと一人先に土山邸を出て帰っていきました。田沼意知の配下の土山宗次郎は重三郎を仲間に引き込もうと耕書堂を日本橋に出店してはどうかと話をもちかけていました。重三郎はその話に魅力を感じて気持ちが揺らぎましたがそれは断りました。一方、大文字屋と誰袖は松前廣年(ひょうろくさん)になんとかして抜荷をさせようと、いろいろと話をもちかけていました。誰袖はおねだりやら涙目やらであの手この手で廣年に執拗に迫りました。廣年には考えてみるとまで返事をさせましたが、誰袖の思いは万事上手くいけば身請けしてもらえる田沼意知にありました。重三郎は吉原の方から、手間の割には利益が少ない仕事を大量に頼まれていて、渋々引き受けて進めていました。重三郎が日本橋に出店する夢を迷いも含めて思い描いていたら、日本橋の白木屋彦太郎(堀内正美さん)から呼び出しがありました。これはいい話かと重三郎が勇んで行ったら逆で、西村屋の『雛形若菜』のために吉原はもっと協力するように、という話でした。納得がいかない重三郎は、自分たちには何が足りないのかを彦太郎に訊ねました。彦太郎は、耕書堂の錦絵は江戸の外では売れていないことを指摘しました。鶴屋や西村屋には諸国の本屋から大口の買い付けがある、その後は地方の本屋や小物問屋にまで広まる、と説明しました。しかしそう言われても重三郎はなぜか強気で、それならばあっという間に全国に広めてみせると彦太郎にタンカを切りました。さて、錦絵を全国に売ってみせると言ったもののどうしたらと重三郎は考え、まずは江戸市中にやってくる行商人に声をかけて商売をしてみましたが、誰にも相手にされませんでした。そこで須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)に頼み込んでみましたがやはり断られ、でも市兵衛は代わりに重三郎にこの先のことの助言をくれました。「日本橋に出ればこの絵は一発で方々の国に出回ることになる。諸国の商人は『日本橋に店を出せるとなれば一流もの。そこの品物なら間違いない』と買っていく、買ってこい、となる。日本橋に出ればこの絵の話はあっさりと先に進む。他の狂歌本、青本、富本本も流れにのるし、一作につき桁違いの数が出る。」そう聞いても重三郎はまだ決断できませんでしたが、市兵衛は「それでも俺はお前に日本橋に出てもらいたい。平賀源内のためにも。」と重三郎の気持ちを強く後押しをしてくれました。市兵衛の話が頭から離れないままの帰り道、重三郎は和泉屋の店の前を通り、葬儀に向かう親父衆の姿を見送って、遠くからそっと手を合わせました。店に戻ってから、これまで自分が作ってきた本を手に取り、それまでの様々な出来事を思い返していたら、歌麿(染谷将太さん)が声をかけてきました。あの時無理やり和泉屋の荷物持ちをして田沼邸に入りこんで、首尾よく意次と話ができ、意次から言葉をもらえて、それが全ての始まりでした。そして源内と出会い、単に本を売るだけではない大きな志をもらいました。しかし、そんな思いにふけっていたら親父衆が大雨の中をずぶ濡れになって帰ってきて、何かあったのかと重三郎は心配になりました。和泉屋の葬儀の時、親父衆は他の参列者から「吉原もん」と蔑まれ、畳の外の縁側に追いやられる冷遇を受け、雨に打たれて耐えていました。親父衆は「いつものこと」と受け流していましたが、そんな親父衆の背中を見た重三郎は、自分はこのままではいけないと強く思うようになりました。もし失敗したらと不安もあるけど、重三郎の中で日本橋に出る思いが徐々に固まりつつあった時、歌麿が「何がどう転んだって俺だけは隣にいるから。」と言ってくれ、重三郎はようやく決心ができました。翌日、親父衆は集まって世間に対する自分たちの思いを語り合っていました。「貧しさゆえに死ぬしかない子をとにかくここで食わせてやっている。非難するだけの奴らはそんな子らに何かしてやっているのか。」と丁子屋長十郎(島英臣さん)は怒りが収まりませんでした。そんな時、重三郎が中に入ってきました。重三郎は親父衆に改めて、日本橋に出店したい旨を強く訴えました。怒り心頭になった駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は重三郎を激しく折檻して階段落としまでしましたが、重三郎の決意は固いものでした。重三郎は階段を一段ずつ上がりながら市右衛門に訴えました。「俺は忘八だけど、俺ほどの孝行息子もいない。吉原もんが日本橋の真ん中に店を構える。そこで商いを切り回せば誰にも蔑まれないどころか見上げられる。吉原は親無し子を拾ってここまでしてやってる。吉原の門は懐が深いと。俺が成り上がればその証になり、この町で育ててもらった拾い子の大きな恩返しだ。」そう言って重三郎は改めて親父衆に「俺に賭けてください。俺には歌麿がいる。まあさん、春町先生、赤良先生など日の本一の抱えがある。」と訴えました。「俺に足らないのは日本橋だけ。」ーー重三郎の確固たる熱い思いを親父衆はしっかりと受け取り、認めてやりました。そして日本橋の丸屋が売りに出されると情報が入り、どうやったら吉原もんに店を売ってくれるか、それぞれが知っている話から皆で考えていました。「吉原もんには市中の屋敷は売るな」というお定めがあるからやはり無理かと皆があきらめかけた時、扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が一人の男を同行して自信をもって部屋に入ってきました。
June 19, 2025
-
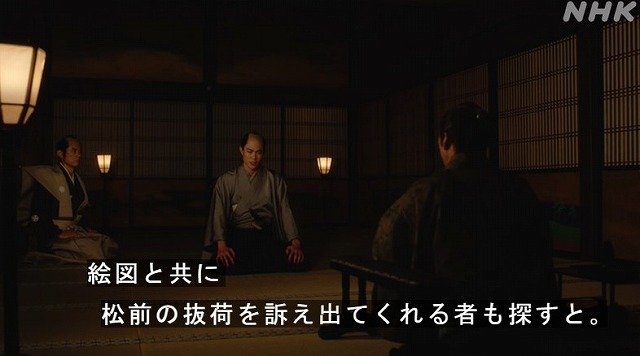
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第22回~「小生、酒上不埒にて」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は、ひと悶着起こして一人卑屈になって籠ってしまった恋川春町(岡山天音さん)を心配する周りの皆が、あの手この手で励まして春町を迎えようとする温かい優しい時間と、蝦夷地を上地するために父・田沼意次(渡辺謙さん)に代わって暗躍する嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)と、意知に無理やり絡んでくる花魁・誰袖(福原遥さん)が起こす緊張の時間が交互にあったように感じました。自分がこの家を継ぐと決意した者は、大一番を迎えた時に自分の力量を試したくなるのか、あるいは周囲の家臣たちに自分の存在を認めさせたいと心のどこかで思うからなのか。これ以上手を出すなと案じる父・意次の思いをよそに、意知はニヤリと不敵な笑みを浮かべる場面もありました。たしかに古今東西を問わず、跡を継ぐ者が常に安全圏にいて、泥をかぶらない苦労知らずだと、下の者は自分に付いてこないかもしれません。とはいえ勇み足をして万一失敗すると、後継者であるがゆえに、お家や親に大きな負の影響を与えるものです。これは単に、敬愛する父・意次のために意知が頑張る、という気持ちから起こっている行動だと願うのですが。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明2年(1782)蝦夷地の上地を狙う田沼意次(渡辺謙さん)がそのことを密かに進めようとしていたら、話をかぎつけた吉原の花魁・誰袖が意次の嫡男・田沼意知(吉原では花雲助;宮沢氷魚さん)に近づいてきました。誰袖は吉原に来る客から秘密を探るから自分を身請けしろと迫りますが、意知はそれを断っていました。意知は上地を強行するために松前藩との抜荷の証を探していて、土山宗次郎の報告によると平秩東作が上方を探っているとのことでした。また意知は『赤蝦夷風説考』を書いた工藤平助を呼び、松前家の当主・道廣を激しく非難する湊源左衛門に対する工藤の考えも確認していました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、先日の狂歌の会でいろいろとうっ憤がたまっていた恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)が座敷で暴れてしまい、果ては自分の筆をへし折ってもう自分は何も創らないと言って一人出て行って しまったことが気になっていました。同じく気にしていた歌麿からも促され、重三郎は春町の家を訪ねました。重三郎は、あの時のことは誰も気にしていない、北尾政演が気に食わないのもわかるけどいきなり怒り出した春町だって悪い、政演を盗人呼ばわりするのは言い過ぎ、などと春町をたしなめたり新作を促したりしました。でも今の春町には重三郎の言葉を受け入れる余地はなく「俺は戯けることには向いてないのだ!」と怒って出ていってしまいました。店に戻った重三郎は歌麿(染谷将太さん)に春町のことを相談しつつ、次の仕事となる朋誠堂喜三二の新作の『長生見度記』の絵付けを頼んでいました。春町風に描くように言われたその新作は書き出しが「友人 恋川春町が作りし無題記を読みつつ」とあり、喜三二の春町への思いを歌麿も感じていました。そんな時、花魁の誰袖が重三郎を呼んでいるとのことで、重三郎は大文字屋まで出向きました。重三郎が大文字屋に入ると誰袖(福原遥さん)が飛びついてきて、抜荷の証を立てるならどうするか?なんて話をいきなりし始めました。誰袖は退屈しのぎに青本を書くネタだと言い、そんな話をしていたら女将の志げ(山村紅葉さん)が差紙が入ったと大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)のところに持ってきました。相手は松前藩の家老で当主・道廣の弟で廣年、格のある花魁を所望しているとのことでした。田沼意知のために松前藩を探ろうとしている誰袖はその話を聞き、願ってもない好機とばかりに自分が座敷に出ると名乗りをあげました。松前藩の家老・松前廣年(ひょうろくさん)は物静かで控えめな男で、座敷遊びに誘われても加わることなく皆の様子を眺めていました。誰袖は初回だけど特別と言って話しかけ、廣年が幼い頃に江戸に出された話とか、金はあまり自由にならないことなどを聞き出していました。誰袖は廣年が手首につけている美しい石を目ざとく見つけ、廣年の手をとりこの石は何なのかと色仕掛けで迫りました。歌麿は朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)の新作に絵付けをするなら喜三二と打ち合わせがしたいからと重三郎に許しをもらいました。でもその実は、自分と同じく春町のことが気になる喜三二に同行してもらって、二人で春町に会いに行くことでした。喜三二は自分の新作は春町の『無題記』にかぶせた物だと言い、歌麿もこれに付ける絵は重三郎の指図で春町風になると言い、その許しを求めました。歌麿に勝手にしろと言う春町は、政演の『御存商売物』は自分の『辞闘戦新根』よりも百倍面白い、自分は絵が下手だ、世はもう自分を求めていないだろうとすっかり卑屈になっていました。喜三二と歌麿は、春町の作品が好きだ、春町がもう書かなくなったら寂しい、春町の作品のあの場面が好きだなど、二人で春町を説得していました。春町に復帰して欲しいと願う二人の熱意が伝わったのか、春町は自分のような辛気臭い男がいてもいいのかと、涙を流してうなだれていました。その頃、重三郎の店では狂歌の会の大田南畝らが来ていて、春町が辞めると重三郎から聞いてあの晩のことを話していたのですが、誰も全く気にしてなく、それどころか南畝は春町の皮肉の上手さを感心していました。そんな話をしていたら喜三二と歌麿が春町を連れて店に入ってきました。元木網が朱楽と南畝を連れて店を出たら春町は改まって姿勢を正し、自分の方から重三郎に詫びを入れようとしたら、先に重三郎が話し始めました。重三郎は折れた春町の筆を返し、もう一度うちで書いて欲しいと頼みました。南畝が春町は皮肉を言う才があると言ってたと伝えると、春町は文字を何かの形に並べたもので自分の思いを書いたと、紙を懐から取り出して見せました。重三郎が感心して笑うと春町は『小野篁歌字尽』を取り出し、このような形で作ったらどうかと自分から提案しました。そう聞いた重三郎は、ならばこれを吉原を舞台にして作ってはどうかと提案し、早速春町のネタ集めが吉原で始まりました。さて誰袖ですが、松前廣年を篭絡してあの石の飾りを手に入れ、文とともにこれが抜荷の証拠だと意知に送り付けてきました。しかし意知は、オロシャ産の物を持っているだけでは抜荷の証にはならないと誰袖に返却し、誰袖にもう間者ごっこをやめるよう言いました。しかしそう言われても誰袖はまだ、自由に使える金が少ないけど本音は吉原でもっと遊びたがっている廣年に抜荷をさせてはどうか、と言ってきました。誰袖は身請けしてくれるなら自分が実行すると言い、意知は危険だからと警告しましたが、どうしても意知に身請けして欲しい誰袖は引きませんでした。誰袖の覚悟を感じた意知は自分の本名を名乗り、見事抜荷の証を立てられたら誰袖を落籍する、と約束しました。さて年も暮れになり、重三郎は世話になった戯作者や絵師や職人たちを労う会を開き、集まった皆はご機嫌に会を楽しんでいました。酒を飲みながら互いに作品を見て感想を言い合うそんな中で、春町が作った『廓ばかむら費字盡(さとのばかむらむだじづくし)』を読んでいた北尾政演(古川雄大さん)は、自分はこっちがよかったと周囲にもらしていました。その様子を離れて見ていた喜三二が春町に徳利を持たせて政演と話してきたらどうだと促すと、春町はバツが悪そうにしながら政演のところに行きました。政演が顔を合わせにくそうに春町の本が面白いと感想を言うと、春町は政演に「いつかそれをかぶせた、もっと深く穿った目で見たそなたの『費字盡』を読みたいから書いてくれ。」と言いました。そして「盗人呼ばわりしてすまなかった」と政演に手をついて謝りました。頭を下げて謝る春町、でも政演のほうは謝られる意味が分からないとばかりの態度で、重三郎の言ったとおり誰も気にしていないとわかり、春町は安心して政演の隣りに座り仲直りしました。しばらくしたら次郎兵衛(中村蒼さん)が三味線を鳴らして出てきて、何事かと思ったら二階から春町がさらし姿で降りてきました。そして皆の前で平賀源内が書いた『放屁論』にでてくる「花咲男」を名乗って「へっぴり芸」を始めました。先日は皆を不快にさせてしまったからそれを挽回しようとしたのか、慣れないお笑い芸を一生懸命やる春町を皆も温かく見守り、そのうち皆も一緒に音頭をとって踊り出しました。宴会を楽しむ皆より重三郎が一足先に退出した時、店の外で以前「花雲助」を名乗っていた侍と会い、重三郎は声をかけました。内密に話ができるようお稲荷さまのところに案内し、重三郎はその時ようやく花雲助が田沼意次の嫡男・意知であることを知りました。意知は周囲の気配を確認したうえで、自分たちがこれから蝦夷地を上地しようとしている、これは源内が最後に口にしていた試みだと重三郎に話しました。「蝦夷地を上地し、国を開き、鉱山を開き、幕府の御金蔵を立て直す。幕府を今以上に揺るぎなき中央の府とし、諸国ももっと豊かな土地に育て上げる。」そう聞いて源内に思いを馳せる重三郎に、意知は仲間になるよう誘いました。
June 12, 2025
-
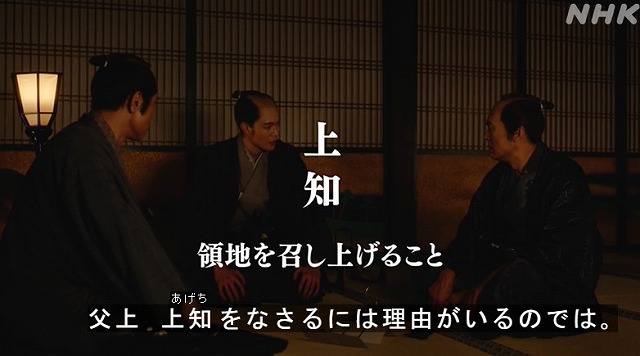
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第21回~「蝦夷桜上野屁音」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、興味深かった展開は、田沼意次(渡辺謙さん)の松前藩の上地の話で、花魁と言えど女郎の誰袖(福原遥さん)が絡んでくるとは、という部分です。まあ現代でも一流の夜の店では、世の中を動かすような大物が出入りするから、誰と誰がつながっているとか、他言無用ではあるけど話は聞いてしまうから、情報は持っているんですよね。ただ見ていてよくわからなかったのは、あの座敷で志げ(山村紅葉さん)が盗み聞きをしていたのはシーンであったけど、田沼意知(宮沢氷魚さん)が抜荷の証拠を探しているのを誰袖がどうして知っていたのか、という部分でした。田沼サイドの情報を漏らす誰かがいるのでしょうか。(ところで誰袖、今まであれだけ蔦屋重三郎(横浜流星さん)にお熱だったのに、急に意知に心変わりしたのでしょうか?) さて、松前道廣役で登場したえなりかずきさん。今までの子役時代からは想像できないワルでご登場です。言い方は優しいけど、やってることは鬼なんですよね。しかもあの場にいた者は意次を除いて皆、あの余興を見て笑っていました。恐怖におびえる妻と許しを乞う夫を見て、心から愉快に思って笑っていた者、あるいは上の者に追従して笑っておかないと次は自分が酷い目に遭うからやむなくそうしている者、いろいろあったと思いますが。ところで、あの射撃の場面についてです。私、射撃場で電子標的の銃で遊んだことがあるのですが、約5kgの長い銃を持ち上げて微動だにせず固定するのはけっこう力が要ります。私の場合、上半身の筋力で銃をしっかり固定できなくてまず持っただけで微動。撃つ前は照準器で合わせて真ん中を狙っていても、撃った瞬間に手がブレて10cmくらい的を外します。だからあれを見ていた者が道廣の銃の腕前を褒めていたのも、そういうことでもあると思いました。こちらは興味深かった情報です。北斎の代表作「冨嶽三十六景」を出版したのは西村屋、広重の「東海道五十三次」出版には初め鶴屋が関わっていました。(途中から保永堂の単独出版に。) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永10年(1781)秋、田沼意次(渡辺謙さん)は側近の三浦庄司(原田泰造さん)から蝦夷地を幕府の天領にしてはどうかと進言を受けました。三浦は先日、伊達家家臣の工藤平助を訪ねた折に平助・著の「赤蝦夷風説考」を読んでオロシヤが日の本と交易をしたがっていることを知り、また広大な蝦夷地には数多の金銀銅山が眠っているらしいと情報を得ていました。主君・意次がその話に興味を持つと、三浦はさらに松前藩から蝦夷地を召し上げ天領にしてはどうかと進言し、意次は早速動こうとしました。ただ嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)は上地は慎重に行ったほうがいいと進言し、自分が上地できる理由を探してくると父を制しました。一方、蔦屋重三郎(横浜流星さん)は『雛形若菜』を出す西村屋を吉原から追い出し、歌麿が描いた『雛形若葉』で歌麿を売り出して、錦絵でも自分の耕書堂の名を上げようとしていました。ところが現実は、年が明けてから西村屋の『雛形若菜』は売れに売れ、耕書堂の『雛形若葉』は二番煎じと人々の評判は悪くさっぱり売れませんでした。また重三郎が絵師として重用していた北尾政演(山東京伝)が鶴屋から出した『御存商売物』の青本が世間で大人気になっていて、吉原の親父衆や重三郎に出仕した人たちはカンカンに怒っていました。そしてこの状況でもついふざけてしまった重三郎は、その後で駿河屋市右衛門(高橋克実さん)から階段落としのお仕置きをくらいました。重三郎が店に戻ると大田南畝と朱楽菅江が来て、これから旗本の土山宗次郎(栁俊太郎)の花見の会に行くと言いました。土山に呼ばれている狂歌の会の人たちが続々とお座敷に向かう中、平秩東作が「花雲助」と名乗る男を連れていました。会が始まりしばらくすると花魁の誰袖(福原遥さん)は初めて見る客の花雲助(実は田沼意知)が気になって仕方がないようでした。そして湊源左衛門が遅れて入室し花雲助の隣りに着座したとき、誰袖から合図された女将の志げがさりげなく湊の背後に移動して話を聞いていたようでした。湊は花雲助に挨拶をした後、蝦夷地を松前藩より召し上げて欲しいと、さらに松前家当主の松前道廣のことを鬼と呼びその悪行を語っていました。松前道廣(えなりかずきさん)は一橋治済に招かれた酒席の場で余興として、粗相をした家臣の妻を庭の木に縛り、その周囲に置いた皿を座敷から鉄砲で打ちぬくという恐ろしい遊びを楽しむような男でした。そしてその場にいた一橋治済や薩摩の島津重豪は、それをやめさせるどころか笑ってその余興を見物し、道廣の銃の腕前を褒めていました。治済からその余興を勧められた田沼意次は、自分の腕前では的を殺めてしまうと固辞しましたが、道廣は的は当家からいくらでも出すと笑っていました。意次はその時の様子を徳川家治(10代将軍;眞島秀和さん)に報告しました。家治は一橋が外様大名と仲が良いのは知れたこと、機嫌良く遊んでいる分には構わないと軽く受け止めていました。意次は家治に、実は松前藩の上地を考えている、そこで港を開きオロシヤとの交易を始め、その先の蝦夷地で金の採掘をすれば幕府の御金蔵を根本から立ち直せる、と考えを伝えましたが迷いもありました。しかし家治は「やるべきである。どんな者が将軍になっても揺るぎない幕府を作る。そのために入用なことであれば。」と意次の考えに同意しました。さて重三郎ですが、大田南畝(桐谷健太さん)らが花見の会の後に店に寄ってくれた時に、『雛形若葉』の失敗などのここの所の低迷を思い、自分は老舗の本屋と比べていろいろ足りてないと本音を漏らしました。でもそう聞いて南畝は、「けど、そこがいいところ。だからこそ新しい発想ができる。細見が薄くなったときは『そうきたか!』と思った」と。一緒にいる朱楽菅江(浜中文一さん)と元木網(ジェームス小野田さん)も、これまでの重三郎の出した本で南畝と同じように思ったと言ってくれました。皆からそう言ってもらえて重三郎も気を取り直し、少し考えて南畝に青本を、菅江や元木網には狂歌の指南書を書いて欲しいと依頼しました。同じ作者が狂歌と青本を書く、狂歌が人気になれば指南書を求める人も増える、という重三郎の発想に皆は感心し、重三郎もだんだん強気が戻ってきました。重三郎は『雛形若葉』を改めた錦絵を出そうと思い、親父衆に相談しました。前回の失敗をふまえることを伝え、承認をもらいました。そのころ歌麿(染谷将太さん)は、西村屋の錦絵のような色がどうやったら出せるのかずっとわからなくて、北尾重政から絵師と本屋が摺師にきちんと「指図」を出せるかどうかで仕上がりは全く変わると教わり、やっと納得のいく色が出せて喜んでいました。そうしていると重三郎が話し合いから浮かない顔をして戻ってきました。その理由は、今度出す錦絵は歌麿でなく政演になったからで、重三郎は手をついて歌麿に深く詫びました。でも歌麿はその件を快く了承してくれ、さらに政演が手が回らなくなった他の仕事を自分が引き受けるとまで言ってくれました。可愛い義弟であり、いつも自分の無理をきいてくれ申し訳なさもある歌麿をこれからどんどん売り出すと、重三郎は固く決意しました。田沼意次は松前藩の上地については将軍・家治から許しが出たと嫡男・意知と側近の三浦に伝えました。そして意知も自分の調べで、平賀源内の片腕だった平秩東作より紹介された土山宗次郎、その者らの仲立ちで元・松前家の勘定奉行だった湊源左衛門に会って話を聞いてきたとのことでした。湊の話によると、松前家の当主の道廣は恐怖政治で藩内ではやりたい放題、さらにご法度の抜荷も行い莫大な利益を得ているよう、なのでこれを理由に上地を命じてはどうか、と意知は父に進言しました。ただそのためには確かな証拠が必要であり、松前と白天狗(将軍・家治が次期将軍として養子に迎えた豊千代の実父・一橋治済)とは殊のほか昵懇、そして家治はそれを承知で「やれ」と命じたと意次は二人に言いました。白天狗や松前に気づかれぬよう抜荷の確かな証拠を集めなければならないけど、意次は意知にはこれ以上関わるなと命じました。しかし意知は父の反対を押し切り、自分がやると言いました。そんな折に花魁の誰袖から文が来て、あの時やはり(志げが)盗み聞きをしていたようで「蝦夷の桜」と匂わせてきました。意知と内密に会った誰袖は「吉原には松前のご家中や蝦夷地の物産を取り扱う者が出入りしている。抜荷の証を探しているなら自分なら力になれるかも。」と言ってきました。そして間者の褒美として自分を身請けして欲しい、と意知に迫りました。重三郎は歌麿を売りだすために会を開き、戯作者や絵師、狂歌師などの関係者だけでなく、それらを志す者なら誰でもどうぞ、という宴会を開きました。その宴会の最中に重三郎は朋誠堂喜三二(平沢常富;尾美としのりさん)に呼ばれ、恋川春町(倉橋格;岡山天音さん)の機嫌を取るよう頼まれました。春町は自分の『辞闘戦』を下敷きにした政演の青本『御存商売物』が一番となったことが面白くなく、この宴会の場でも楽しく盛り上がっている政演が不愉快でしょうがなかったのです。重三郎と喜三二で春町の機嫌を取っていたら周りからは春町は不愉快になるような話ばかり耳に入り、そこへ政演が無神経に絡んできたので、春町はもう我慢できなくなり、皮肉の狂歌を次々と詠みあげ暴れ出しました。興奮して荒れ狂う春町をどう止めたらいいのか、皆が途方に暮れていたときに、次郎兵衛(中村蒼さん)が一発、放屁してしまいました。座敷がしーんと静まり返った後、次郎兵衛が無礼を詫びると、今度は一斉に笑いが起こりました。大田南畝が「俺たちは屁だ~!」と叫んで立ち上がると皆もそれに続いて立ち上がり、座敷では屁を題材にした狂歌をそれぞれが詠みながら輪になり、「へ!、へ!」と叫んで皆で踊り出しました。しかし春町はそんな浮かれた気分にもなれず、重三郎の目の前で筆を折って捨て、一人寂しく宴会場を退室していきました。
June 5, 2025
-
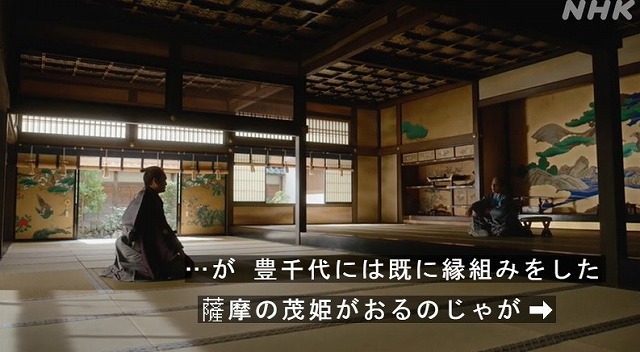
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第20回~「寝惚けて候」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。本屋として波に乗ってきた蔦屋重三郎(横浜流星さん)。自分で本を作りたいと仕事を始めた駆け出しのころは、西村屋与八(西村まさ彦さん)ら市中の大店の人たちに散々いいように利用され、理不尽にも耐えていました。そして今、その重三郎が反撃を開始しました。幼い頃から仕えてきた吉原の親父衆は、今では自分の働きを認めてくれ全面的に味方になってくれています。市中の地本問屋たちは今まで何度も自分の妨害をしてきたから、遠慮なく西村屋の妨害工作をしました。“何事もプラス思考の人間のできた重三郎”だけでなく、もちろん相手は選ぶけど、こういう“仕事を取るために自分から仕掛ける重三郎”という人物像も面白いですね。そして第10代将軍・徳川家治(眞島秀和さん)が、 田沼意次(渡辺謙さん)に対して全幅の信頼を寄せ、意次もその思いに応えようとするシーン。上に立つ者とそれに仕える者の、理想的な関係です。これは胸が熱くなるシーンでした。これが違うドラマとか現実とかで、嫌な見方をすれば、側近が上を操っているというように思えます。でもこのドラマでは、渡辺謙さんがなんとも憎めない田沼意次になっているので、感動になるのでしょう。須原屋市兵衛を演ずる里見浩太朗さんも以下のようにコメントされています。今回は謙ちゃんが新たな意次像を作っていますね」と 里見浩太朗 さん こちら (“謙ちゃん”……里見さんだから許されますね)こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永10年(1781)、10代将軍・徳川家治が実子の後継ぎをあきらめたことにより、田沼意次(渡辺謙さん)は一橋治済(生田斗真さん)に次の将軍は治済の子の豊千代に、御台所は田安家の種姫になったと報告に上がりました。その件を治済は承知しつつも、しかし豊千代には既に縁組をした薩摩の茂姫がいるとのこと。意次は茂姫は側室でどうかと提案、治済も島津にはそう伝えておくとのことでその日は話が終わりました。大田南畝が作品を読んで評論した「菊寿草」で朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』が極上上吉と評されて、版元の蔦屋重三郎(横浜流星さん)は本屋としてますます勢いに乗っていました。そして重三郎は須原屋市兵衛と共に大田南畝を訪ね、その一風変わった大田の魅力に惹かれて話が盛り上がり、次の狂歌の会に顔を出すことになりました。一方、重三郎の躍進が気に入らない市中の本屋たちは陰で「あれはまぐれだ。」と嘲笑してましたが、鶴屋喜右衛門だけは重三郎の動向を警戒していました。そして本屋たちの中には重三郎の本を仕入れたがっている者も多数いましたが、鶴屋ら大店の意向には逆らえず、彼らは不満を持っていました。ある日、重三郎の店に地本問屋の一人の岩戸屋源八(中井和哉さん)が訪ねてきて「見徳」を50部ほど欲しいと言ってきました。重三郎は岩戸屋のことを案じましたが、岩戸屋は「言い訳が立つから大丈夫」と言い、重三郎は「言い訳さえ立てば」と何か考えが浮かんだようでした。一橋治済の子の豊千代の件ではうまく話をまとめたと思った田沼意次ですが、後日、将軍・家治のほう薩摩から茂姫は御台所でなければと申し入れがあり、それは薩摩に嫁いだ浄岸院の強い希望でした。薩摩藩主・島津重豪(田中幸太朗さん)が同席する場で意次は、御台所になるのは宮家もしくは五摂家の姫が習わし、種姫は母・宝蓮院が近衛の出である、種姫は自分にとって有利な方ではないが上様の願いを叶えたい、と述べました。意次が退席して二人になった時、重豪は茂姫は側室でもいいと言ったのですが、治済はこの機会に田安家を除いておきたいので、やはり御台所は薩摩の茂姫と考えていました。重三郎は歌麿(染谷将太さん)に、清長そっくりだけど微妙に違う絵を描かせていて、その理由を「本屋がうちの本を仕入れる言い訳が立つようにしてやる」と言い、歌麿は意味がよくわからないけど作業をしていました。呉服屋の尾張屋彦次郎(大谷廣松さん)が来ている座敷にお邪魔した重三郎はその絵を彦次郎に見せ、一見すると清長の絵だけどまだ名もない歌麿が描くから『雛形若菜』の半分の入金で錦絵を作る、協賛して欲しいと言いました。『雛形若葉』の名で売り出すその本はきっと評判になると重三郎は自信をもって彦次郎に勧め、吉原以外でも売る方法は年明けまでにはなんとかなる、とりつ(安達祐実さん)が説明したので、彦次郎は重三郎に任せると言ってくれました。重三郎が人気の清長とほとんど同じ絵の錦絵を今までの半分の入金で作ることが吉原の客の間で密かに知れ渡り、清長を抱える西村屋与八(西村まさ彦さん)の錦絵は次々と注文が断られていきました。これは何か変だと思った与八はやがてその理由を知ることになり、怒った与八は重三郎の店に文句を言いに来ました。「汚いやり方もありだと教えてくれたのは西村屋さん。それに今度は自分の力で錦絵を売りたい。」と重三郎が答えると、与八は「錦絵の商いはお前が思うほど甘くない。」と言い残して帰っていきました。しかし重三郎たちは、入金のこと以外にも何か仕掛けているようでした。りつたちが仕掛けた罠には、小泉忠五郎が行っていた細見の改めには昔いて今はいない女郎の名ばかり答え、新しい細見を作る面倒を増やすのもありました。そして最大の仕掛けは、鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)らのやり方に不満を持つ岩戸屋源八に密かに何か頼んでおいたことでした。会合の折、新しい細見を買えないことがわかり、岩戸屋が今まで我慢したことの不満を発言したのをきっかけに、本屋たちは一斉に怒りを露わにしました。今や勢いを増すばかりの蔦屋との取引を認めるよう迫り、それができないならと全員が立ち上がると、主導格の喜右衛門はあっさりと認めると言いました。喜右衛門は地本問屋が分裂し、彼らが重三郎と組むことを避けたのでした。会合の後で岩戸屋は重三郎の店に行き、細見と富本本と『見徳』を「約束」として無料で受け取り、重三郎も岩戸屋の働きに礼を言ってました。市中との取引は自分たちの念願と言って、岩戸屋に新作の「むだいき」を見本で渡すと、これは売れると思った岩戸屋は早速30部注文していました。岩戸屋と一緒に来た市中の本屋たちは細見その他を次々と大量に注文していき、帳面を見た義兄の次郎兵衛も驚くほどでした。さて、これで蔦屋は市中の本屋として認められたのか?と気になった重三郎は鶴屋に直接会いに行きました。しかし喜右衛門からは蔦屋のことは仲間として認めないし、重三郎が作る本は何一つ欲しくはない、とまで言われました。そう言われても重三郎は、ならば鶴屋が欲しくなる本を作るべく精進する、と強気で答えて帰っていったのですが、その後で陰で話を聞いていた山東京伝に喜右衛門は戯作をやらないかともちかけていました。さて種姫の母の宝蓮院(花總まりさん)ですが、一橋の豊千代を将軍・家治の後継者とすること、その御台所を薩摩の茂姫とすることだけでなく、その他諸々全てを、田沼意次が裏で糸を引いていると思い込んでいました。そして今度は種姫の縁組が知らぬ間に決まったことに立腹し、大奥総取締の高岳(冨永愛さん)に文句を言いにきました。しかし高岳は種姫はもう将軍・家治の養女だと宝蓮院にはとりあわず、そう話をしていたら知保の方が西の丸を出ることを激しく拒んで抵抗し、騒ぎを起こしていました。 この件も意次からの話だと聞いた宝蓮院は、意次を激しく恨みました。西の丸に豊千代を迎え、茂姫とその生母の富の方も入り、10代将軍・徳川家治(眞島秀和さん)は後継者問題がひと段落して安堵しました。ただ一橋が豊千代の周りを固めたことは不満であり、田沼意次は家治の意に添えなかったことを詫びました。しかし家治は「自分の願いは意次が後の世に残る仕事を成してくれることであり、そのためにはこれがよいというのであれば構わない」と言い、さらに「自分のことはうまく使え。」と意次に対して全幅の信頼を表しました。意次は家治の思いに応えるべく「政は幕閣とその時々に選ばれた能ある役人どもで行える形を作り上げたい。どのような方が将軍になっても決して揺るがぬ政が行えるように。」と改めて決意を述べました。さて重三郎ですが、大田南畝(桐谷健太さん)に招かれ狂歌の会に次郎兵衛(中村蒼さん)と共にやってきました。そこには朱楽菅江ら当代の有名な狂歌師が集まっていて、前半は思ったよりちゃんとした会であったことに重三郎と次郎兵衛は驚きました。でも内容は狂歌らしく、整った文字数の中にも皮肉や笑いがいっぱいでした。夜の酒席になったとき「軽少ならん」の狂名をもつ土山宗次郎(栁俊太郎)が到着し、座はひときわ盛り上がりました。土山はやり手の勘定組頭とのことで、重三郎が「吉原で本屋をやっている」と自己紹介したときに少し興味を持ったようでした。歌人たちから面白い狂歌が次々と出てくる会で重三郎もすっかり楽しくなり、酒も進んでその日は酔っぱらってご機嫌に朝帰りとなりました。
May 29, 2025
-
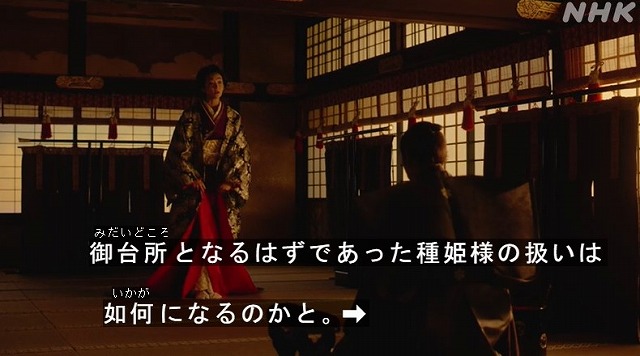
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第19回~「鱗の置き土産」
今週は月火水が仕事と雑用で多忙で日記どころではなく、木曜から金曜の昼頃まで私のパソコンから日記が書けない(改行が無効になる)状態でした。ということで感想日記がいつも以上に遅くなりました。2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話の中でいちばん重きを置かれたのは、主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)がビジネス上のこととはいえ関係がこじれてしまった鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)と和解できたことでしょうか。これには本屋の業界の中で力のある須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)の仲立ちが大きな役割をしました。(力のない者ならいくら正しいことを言っても孫兵衛が耳を傾けなかったかもしれないので。)重三郎にしたら市兵衛が特別なひいき目も偏見もなしに自分と接して評価してくれていて、何かの折には仲介に入ってくれることがすごく有難いでしょうね。そして孫兵衛にしたら、自分の作品に接した重三郎が自分の後を追う者になり、それだけでも十分嬉しいのに、本を広めたい重三郎は夢中で働いて、今や自分を超える存在になろうとしています。わだかまりが解けた今は、兄のような気持ちで彼の今後の成長を見守りたいでしょうね。今の時代でも何かの世界で、自分の教え子や自分の作品や自分のある時の行動に接した者がそれに感銘を受け、その後に自分と同じ道を志してくれると、先達としてはやはり嬉しいと思いますから。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永10年(1781)、10代将軍・徳川家治に実子の後継ぎをもうけてもらうために、田沼意次(渡辺謙さん)は大奥総取締の高岳(冨永愛さん)と共謀し、側室として鶴子を家治の元へ送り込みました。家治は鶴子を気に入り万事うまくいっていると思っていたのですが、それまで家治の寵愛を独占していた知保(次期将軍となるはずだった亡き家基の母)が自害したとの報が。我を忘れて知保のもとに駆け寄る家治、また意次のもとには亡き家基の正室になるはずだった種姫の処遇についての意見書が来ていました。そして間もなく知保が命を取り留めたと報が入り、この騒動は知保とその周囲の者が仕組んだ狂言だと意次と高岳は判断しました。また知保も、服毒したけどそれは薬に詳しい大崎が調合した、死なぬ程度の薬だったと語っていました。一方、店を畳むことを決めた鱗形屋孫兵衛は、嫡男の長兵衛(三浦獠太さん)が細見と次男・万次郎の奉公のことは西村屋与八(西村まさ彦さん)に、黄表紙作者の恋川春町の仕事は鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)にと、病に伏せるの父・孫兵衛に代わって今後のことをお願いしていました。そこへ蔦屋重三郎(横浜流星さん)が入ってきて、細見を西村屋の3倍の値で買う、鱗形屋に今いちばん必要なのは金と考えを述べました。そのやり取りを聞いていた恋川春町(岡山天音さん)は途中で退室すると言い、重三郎は挨拶をして勧誘したのですが、まず現実を見る重三郎はなんでも金と思われているのか、春町は重三郎を毛嫌いしているようでした。重三郎が店に戻ると大文字屋市兵衛の訃報が入り、親父衆たちはかぼちゃの膳で市兵衛を偲んでいました。でも今の親父衆にとって大事なのは、西村屋が吉原でまた勢力を伸ばそうとし、鶴屋喜右衛門も戯作者の芝全交を抱えて人気の青本を出している今、重三郎をどう応援してやるかということでした。そこで朋誠堂喜三二と仲の良い春町をこちらに引っ張ってきたらどうかと案が出て、親父衆はここは吉原だから綺麗どころを並べて春町をもてなしてやると盛り上がっているのですが、残念ながら春町は色香にはなびかない人でした。家でも悩む重三郎を見た義弟の歌麿(幼少期は唐丸)は、春町の絵には独特の味がある、この味は春町の天分だと助言をくれました。さて鶴屋で仕事をすることになった春町でしたが、作の構想に対する考え方が喜右衛門と合わず、気持ちよく仕事ができない状態でした。一方、春町を鶴屋から引き抜く件で重三郎から相談を受けている須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)は、春町と鶴屋はソリが合わないようだから今ならいけるかもしれない、と言ってくれました。「力のある者同士がぶつかるとお互いが潰し合う。」ーー市兵衛は重三郎にそう助言し、重三郎も有難く助言を受け入れ、何か考えてみると言って明るい笑顔で市兵衛に挨拶して店を出ていきました。重三郎と入れ違いに鱗形屋の番頭の藤八が須原屋にきて、自分たちの細見は西村屋に移ったけど今後も変わらず仕入れをお願いしたい、と言ってきました。でも今まで須原屋が仕入れていた細見は、実は重三郎が須原屋に代金を払って内緒で買っていたものだったので、市兵衛は返答に困ってしまいました。店を畳むことにした鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が少しずつ店の片付けを進めていたら春町が来て、自分の作品の感想を孫兵衛に求めました。孫兵衛は春町の、誰もやっていないことをやりたいという気持ちは理解しているものの、今一つ面白くないと正直に感想を述べました。すっかり自信を無くした春町を見て孫兵衛は鶴屋との仲立ちを申し出ましたが、今は立場の弱い孫兵衛を気遣い春町はそれを辞退しました。春町が帰ると今度は藤八(徳井優さん)が須原屋を連れて戻ってきました。市兵衛は孫兵衛に、今まで自分たちがここから買ってた細見は実は重三郎に頼まれたものだった、重三郎は孫兵衛に償いをしていた、と明かしました。孫兵衛が重三郎の思いを悟ったと感じた市兵衛は、ならばここを発つ前に重三郎に償っておきたいものは何かないか?と孫兵衛に問いました。ある日、鱗形屋の長兵衛が父・孫兵衛からだと重三郎に文を持ってきました。その文にはなんと、重三郎が鶴屋から春町を引き抜いてほしいと書いてあり、さらに長兵衛は「重三郎なら誰もやっていない案思を思いつくんじゃないか。」と父からの口上を伝えました。その場に一緒にいた朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)も春町のそういう性格をわかっていて、春町がどうしても自分で書きたくなるような案思を土産に持っていけば鶴屋への義理を捨ててこちらに付くだろうと考えました。そこで重三郎は、孫兵衛に一緒に案思を考えて欲しいと文を書いて長兵衛に持たせ、それを読んだ長兵衛は自分の意が伝わったことを感じて、病の身に急に気力がわいて元気になってきました。その日から吉原では重三郎の周囲だけでなく、女郎たちや主人たちも一緒に案思を考え始め、吉原のあちらこちらで物語の構想が出るようになりました。しかしどの案思もかつてどこかの本で読んだことがあるようなすでに世に出ている話であり、何か新しいものはないかと皆は行き詰まってしまいました。そんな時、歌麿(染谷将太さん)が「いっそのこと、こんな絵を見てみたいといった、絵から考えるのはどうか?」と提案しました。その発想に一同はなるほど!と思って思わず膝を打ち、案思作りは別の方向に一気に盛り上がっていきました。そして喜三二を介して重三郎と会うことになって、100年先の誰も見たことがない江戸を描かないかと言われ、本心はやりたくて心が揺らぎました。でも鶴屋への義理が捨てられなくて葛藤していました。そのころ江戸城では、将軍・徳川家治(眞島秀和さん)は後継者問題では、もう実子をあきらめて養子を迎えることを決意していました。田沼意次は必死に説得しますが、因縁のある自分の血筋を絶ちたい、これ以上若い命を失いたくない、と決意は固いものでした。しかし同時に、父・家重と自分の治世を支えたのは亡き松平武元や意次であり、彼らの忠誠心や知恵を認めていました。「10代将軍の自分は凡庸だったが、今日の世の繁栄を作った“知恵袋”の田沼意次を守ったと後の世に評されたい。血筋は譲るが“知恵”は譲りたくない。」ーー家治の心からの思いを知った意次は感涙が止まらず、これからも変わらず終生一身を賭して仕えることを改めて家治に誓いました。さて春町ですが、新しい何かを作りたいという思いがついに鶴屋への義理が勝ってしまい、鱗形屋孫兵衛のところに不義理をすると詫びにきました。孫兵衛にしたらこれは計画通りのことなのですが、春町は知らないままでした。また孫兵衛は、これで重三郎がますます市中から嫌われると案じていましたが、重三郎は自分のことは気にせずうまく立ち回るよう孫兵衛に言いました。孫兵衛は今まで重三郎を逆恨みして意地悪してきたことを詫び、でも重三郎はその気持ちを汲んでお互い様だと流しました。そして今の店を引き払って引っ越すという孫兵衛は、重三郎にもらって欲しい物があると言って、包みを渡しました。それは重三郎が幼い頃に初めてもらったお年玉で買った本の版木で、その本は重三郎の本屋としての原点でもありました。孫兵衛は自分の作った本を読んで本が好きになり本屋になった重三郎を思うと嬉しくてたまらず、二人は互いに喜びの涙が止まりませんでした。そしてある日のこと、重三郎の戻りを待ちわびていた義兄の次郎兵衛が、ある冊子を重三郎に見せました。それは大田南畝が作品を読み比べて評価を入れた「菊寿草」という本で、そこには朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』が極上上吉と評されていました。あのとき腎虚の恐怖と戦いながら書いた作品が最高評価を得て、喜三二本人はもちろんのこと重三郎や周りの皆も嬉しくて、皆で喜びにわきました。
May 24, 2025
-
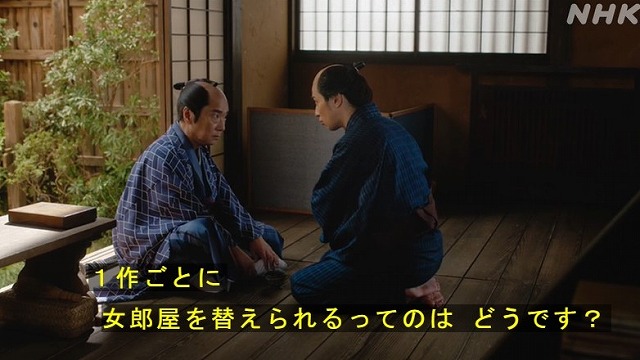
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第18回~「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この世で生きてふだん何気なく生活していると、人というものは不思議な縁で結ばれているものだと時折り思うことがあるのですが、この回ではまさにそれでした。少年だった唐丸(渡邉斗翔くん)が横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎の前から姿を消して、その後も行方知れずとなっていたけど、唐丸を呼ぶ重三郎の思いがことさらに強かったのでしょうか。町で見た絵をきっかけに、すっかり大人となった唐丸(染谷将太さん)と再び巡り合うことができました。捨吉と呼ばれて身を隠して生きている唐丸は、幼い頃から今で言う親からの児童虐待を受けて育ち、それでも子供にありがちな母への思慕がまさって、過酷な日々を耐え抜いて生きていました。しかし結果的に母とその男を死なせて、かつ自分だけが生きていることに自責の念もあり、まともじゃない生き方を耐えるしかありませんでした。そんな唐丸が重三郎に心を開いてからの、ふつうの人として生きられるようになるまでの、“チーム吉原”の連携プレーは見事なものでした。特にふだんは言葉が少ないふじ(飯島直子さん)が、夫・駿河屋市右衛門(高橋克実さん)を説得する場面では、胸がすくように感じた視聴者も多かったことでしょう。そして、これまたふだんは頼りになるかどうかわからない次郎兵衛(中村蒼さん)が機転を利かしたカバーもあり、唐丸は「勇助」として再び重三郎の傍に戻ってこれました。この勇助がやがて喜多川歌麿として世にでてくるのですね。江戸中期の文化での有名人が次々と出てくるこのドラマ。見ている高校生は日本史の文化史への理解が深まりますね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永9年(1780)、出版の仕事が波に乗り出した蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、本を出すことにますます意欲的になっていきました。吉原の馴染み客で重三郎が出す本も書いてもらっている朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)に、次の正月には青本を10作出したいと頼みましたが、10作はとうてい無理だと喜三二は断りました。ならばと重三郎は喜三二に、書くなら吉原に「居続け」でもよい、さらに1作ごとに女郎屋を変えると破格の条件を出し、喜三二は喜んで引き受けました。ただ重三郎は最近市中に出回る何種類かの絵に、作風は違うのに同じ「豊章」の名があることが気になっていました。こんなことができるのは、この吉原で弟のように可愛がっていたけど何年か前に突然行方をくらましたあの唐丸しかいない、と重三郎考えました。豊章の名を頼りに探してみたらその男は自分の想像とはかけ離れた人物でしたが、もしかしたら唐丸はこの男の陰にいるのではと考えました。なんとか唐丸らしき男の居場所をつきとめて重三郎が訪ねると、捨吉(染谷将太さん)と名乗るその男は、最初は重三郎を知らないと言い張りました。それでもしばらく経って捨吉の部屋に上がり込んだ重三郎は、そこに並べられた絵を見て、本人が否定しても捨吉は唐丸だと確信しました。陰の絵師をしながら一方で色の客をとる、そんな暮らしから捨吉(唐丸)を救ってやりたいと思う重三郎ですが、捨吉は自分は好きでこの暮らしをしているからと言い張り、どこまでも重三郎を拒否しました。捨吉の気持ちがわからない重三郎は、いね(水野美紀さん)に相談しました。色を売るのは女だけでなく男でも地獄の商売、でもそれをあえて選ぶ人の中には「罰を受けたい子」がいる、といねは言いました。いねの言う罰とは、自分のせいで大事な人が死んだ時とかに、自分のような者は酷い目に遭って当然、自分なんか早く死ねばいい、そう思うことでした。捨吉はそう考えているのかと、重三郎は思い当たりました。松葉屋で居続けをしながら張りきって執筆していた喜三二ですが突然「腎虚」になってしまい、気力も萎えて執筆活動ができなくなっていました。ある晩、喜三二は自分の身体が突然回復する夢を見たのですが、それは怖ろしい顛末を迎える夢で、喜三二は恐怖から目が覚めてしまいました。目が覚めてあれは夢で良かったと思いつつも、自分の身体がまだ治ってなかった現実に喜三二は激しく落胆でした。でもふと「これも夢?」と思ったとき、喜三二の頭の中には突然物語が浮かんできたので、身体を起こして急ぎ筆をとり物語を書き始めました。いねの話から重三郎は、捨吉(唐丸)には他者に言うこともできないくらいの相当に辛い過去があったのだろうと考え、でもやはりこのまま放っておけなくて、唐丸が使っていた前掛けと筆を持って捨吉を訪ねました。捨吉はようやく重い口を開き、重三郎に自分の過去を語り始めました。夜鷹の母親は自分が生まれたことを呪っていた、幼い頃から母親の罵声を浴びて育ってきた、7歳を過ぎたら色の客を取らされて嫌でたまらなかった、でも金を稼ぐと母親の機嫌が良くて自分も逆らえなかった、身体に痣やコブができるほど殴られたこともあった、と。でもある日、鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)という人物と出会い、不思議な老人だったけど自分(唐丸;渡邉斗翔くん)に絵を教えてくれて何度か会うようになって、楽しくてたまらない時間だった、と語ってくれました。石燕先生は絵の勉強のために自分のところに来いと言ってくれた。でも母親がそれを許すはずもなく、しばらくしたらあの大火が起こり、建物の下敷きになった母親を見捨てて逃げた、とにかく逃げだしたかった、後になって怖くなり自分が生まれたのは間違いだと思った、吉原は俺にとって夢のような場所で生まれ変わったつもりだったけど、あの男が現れ過去を知られたくなくて言いなりになった、一緒に死ぬつもりであの男を川に突き落としたけど悪運強く自分は助かってしまった、と。唐丸の壮絶な過去を知り、重三郎は言葉を失いました。それでも唐丸に、俺を言い訳にして生きろ、母親と男が死んでもお前が悪いとは思わない、そして「俺はお前を助ける。」ーーそう言って唐丸が使っていた筆を差し出しました。唐丸はようやくここから抜け出す決心ができ、あのとき重三郎に連れられて大火から逃げてきたように、再び重三郎と一緒に吉原に向かって走り出しました。さて重三郎は唐丸を𠮷原に連れてきたものの、人別のない唐丸はこのままでは表に出ることができません。そこで駿河屋市右衛門(高橋克実さん)に情をもって唐丸を養子にしてくれるよう頼み込んだのですが、市右衛門は激怒して受け入れてくれません。するとそこにふじ(飯島直子さん)が来て、重三郎に1通の書状を渡しました。それは唐丸が再び生まれ変わるための人別で、ふじが取ってくれたものでした。市右衛門がそれでまた吉原に何かあったらどうする!と怒ったとき、ふだんは言葉少ないふじが夫・市右衛門にタンカを切りました。「あの子は重三郎がずっと待ってた大事な子、何かあったら何とかするものだ。」ーーそう勢いよく言いつつ、夫・市右衛門の思いもちゃんと汲んでいました。そしてふじは重三郎に「行け」と手で合図を送り、重三郎もそれに応えました。唐丸の人別を受け取った重三郎が急ぎ店に向かうと、いなくなった唐丸(捨吉)を追ってきた北川豊章(加藤虎ノ介さん)が来ていて、店先で次郎兵衛(中村蒼さん)と言い合っていました。捨吉は自分のものだと主張する豊章に重三郎はあの人別を差し出し、「(行方知れずになってた)俺の義理の弟だ」と説明しました。重三郎から突然、作り話を振られた次郎兵衛でしたが、機転が利く次郎兵衛はうまいこと話を合わせ、重三郎が人別を取り出すと唐丸もそれとなく話を合わせたので、豊章は納得せざるを得ませんでした。豊章は自分が引く代わりに仕事を要求し、重三郎もそれに応じました。豊章が帰ってやっと人心地ついた勇助(唐丸改め)は、生まれて初めて手にした自分の人別をしみじみと眺めていました。そこへ重三郎が「“歌麿”はどうだ?」と勇助に画号を提案してきました。もしかしたら公家の落とし胤という噂がたって、ついには勇助が内裏に絵を描くことになるかも、と期待して笑っていました。そして改めて勇助を見つめ「お前を当代一の絵師にするという、あの時の約束を守らせてくれ。俺のために生きてくれ。」と思いを伝えました。勇助もまた「義弟が義兄さんの言うことに逆らうわけにはいきませんね。」と涙ながらに返し、二人は義兄弟として再び一緒に生きていく決意をしました。
May 14, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第17回~「乱れ咲き往来の桜」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)が、耕書堂としていよいよ波に乗ってきました。ただ今までの回を見てきても、重三郎はけっしてただ運がいいだけの者ではなく、吉原で親父衆に仕えながら、でも自分のいる場所の「全体」を良くしたい思いが、誰かとの縁をつくり、だんだん大きくなってきた人なのです。思ったことを即実行に移してエネルギッシュに動き回り、七転び八起きしながら、うまくいったら周囲への感謝を。成功する人はこういった思考があるのでしょうね。田沼意次(渡辺謙さん)の経済政策や領民から慕われるお殿様の人物像も面白いものでした。あと意外な展開だったのが、駆け落ちした小田新之助(井之脇海さん)と花魁うつせみ改めおふく(小野花梨さん)の行く末でした。足抜け女郎の末路は悲惨なものになるのが一般的だけど、これはもう例外的なラッキーでしょう。平賀源内のツテがあり、新之助は読み書きを教えられる、おふくも花魁だったからある程度の教養はある。なにより二人には「時代の流れ」が味方しました。この時代でも、汗水たらしてひたすら働く百姓に見切りをつけて江戸に出る者が多かったのですね。農村での働き手が足りず、身元のことをうるさく言われることはなく、朝から晩まで働く百姓でもおふくにとっては女郎よりはうんとマシだし、何より好きな男とずっと一緒。実際にこういう事例があったのかどうかはわかりませんが、安心した視聴者も多かったのではないでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永9年(1780)正月、蔦屋重三郎は10冊もの新作を一挙刊行し、重三郎の店の認知度は急上昇しました。さらに吉原まで行かなければその本が買えないので、重三郎の店は老若男女の客で連日大賑わいとなっていました。これだけ忙しいなら誰か人を雇えばとも言われましたが、重三郎の意識の中にはもしかしたら唐丸がここに戻ってくるのでは?という予感があったのでした。(ナレーションの綾瀬はるかさんがたまに、人間には姿が見えない九郎助稲荷として、スマホという現代のツールを持って登場します。ふざけた大河と思う人もいるかもしれないけど、綾瀬はるかさんなら許されると思ってしまいます。)一方、田沼意次(渡辺謙さん)は城中で、誰が西の丸の座(次期将軍)に色気を見せるか、密かに探っていました。しかし現将軍・徳川家治の弟の清水重好にはその気がなく、一橋治済(生田斗真さん)にもその気はないようでした。そして稲葉正明の報告によると、徳川御三家の尾張・紀伊・水戸には次期将軍として養子に出せる男子が一人もいないとのことでした。こうなると治済が言ったように、いよいよ将軍・家治が自身で子をもうけるしかなく、意次は大奥総取締の高岳と示し合わせて側室となる女子を用意しました。はじめは拒否していた家治でしたが、鶴子と名乗るその女子が自分が深く愛した亡き御台とよく似ていたため、家治は鶴子に心惹かれたようでした。本屋として順調に進んでいるかと思われた重三郎でしたが、それが気に入らない古くからいる市中の本屋たちからはさまざまな妨害を受けていました。そんな話を次郎兵衛たちと話していたら店先に編み笠で顔を隠した旅姿の男がふらりと現れ、その者は以前うつせみと恋仲になって果てはうつせみを足抜けさせて逃亡している小田新之助(井之脇海さん)でした。重三郎は新之助を外からは見えない奥の部屋に通し、近況を聞きました。うつせみはふくと名を改め、二人で亡き百姓をやって暮らしているとのこと。そして新之助が持っていた本の中に、子供が読み書きを習ったり商売や農業などの知識も学べる「往来物」があり、しかもそれは江戸の本屋を通す必要がない物なので、重三郎は自分の商売を広げる勝ち筋を思いついたようでした。重三郎が思いついた勝ち筋とは、遠方から江戸に来て吉原に寄った客で往来物に関わりそうな客を親父衆に紹介してもらい、それぞれの職種について往来物への意見を求めるということでした。越後から来た長谷川には米のことを、信濃の豪商の熊野屋(峰竜太さん)には商売全般のことをなど、今世に出ている往来物についてそれぞれ問うと、客は誰もが嬉しそうに自分の思うところを語ってくれました。ただ重三郎のその動きを、市中の本屋の回し者が密かに探っているようでした。版木の彫師の四五六(肥後克広さん)は少し前に市中の本屋の鶴屋喜右衛門たちから、重三郎の仕事は引き受けないようにと脅されていました。でも実はその後で重三郎から大口の仕事を請け負っていて、市中の本屋からの仕事は逆に断るようになっていました。不審に思った鶴屋が西村屋与八と一緒に四五六を訪ねると、四五六は重三郎となんと毎年20両の契約を結んでいて、仮に仕事がなくても毎年20両は約束されているので、もう他の仕事はなくてもいいとのことでした。四五六は重三郎の心意気に応えるかのように、自分の手を痛めてまで硬い桜の版木で文字を掘ってくれていました。そして同時にそれは、自分の彫った版木は我が子のようでずっと大事にしたいという思いもあったのでした。「この子(版木)には、この子を娘のように思う親父が山のようにいる。」重三郎の言葉に四五六は涙ぐみながら喜んでいました。そして往来物の新しい本ができあがり、重三郎が意見を聞いて回った客たちに新しくできあがった本を礼として何冊か渡すと、客たちは誰もが「本をもっと持って来い。俺がまとめて買い取ってやる。」と喜んでいました。そう、重三郎が吉原に来る旅の客に意見を聞いて回ったのは、彼らを本作りに関わらせるためでした。自分が関わった本といういのは誰かに自慢したいし勧めたいのが人情。関わった人は味方となって販売の拠点となり、重三郎の狙いどおり、売り先は加速度的に増えていき、独自の販路を開拓できたのでした。さて田沼意次ですが、領国の遠江の相良に視察に出ていました。船が着きやすい港や東海道に出やすい田沼街道の影響もあり、港に近い市場は多くの人々で賑わっていました。意次を案内する井上伊織(小林博さん)も「ロウや塩はもはや相良の名産」と誇らし気で、意次も満足そうでした。そんなとき数名の村民が意次らを追いかけてきて呼び止め土下座し、何事か?もしかして直訴なのか?と思ったら……我がお殿様に美味しい魚を献上したい一心の漁師たちでした。相良には名産品があって百姓たちは豊かになる、整った港や街道で商人たちも潤う、運上・冥加が入るので藩の財政も豊かになり百姓を苦しめることはない、など相良では意次の治世に不満を持つ者はいないとの報告でした。そう聞いて意次の頭に浮かんだのは、ハゼの木(ロウの原料)を植えることや先に街道や港を整えることを意次に進言した平賀源内のことでした。「まず民が富む仕掛けを作る。そうすれば田沼は自ずから富むことになる。」ーー今や領地の相良は自分と源内の思い描いた通りの国となり、意次は源内を思って感慨にふけっていました。江戸の藩邸に戻った意次は、政の改革に意欲的に取り組んでいました。三浦庄司(原田泰造さん)は、幕閣中の要職をすべて当家の係累や能ある者で固めきる、と嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)に説明しました。意次は意知に、相良では自分と源内の考えた通りに金が巡っている、でも江戸府内や天領はうまくいかない、それは幕閣での自分の力が足りないからであり、日の本全体を豊かにするために自分の力が及ぶようにしたい、と説明しました。しかし意知は父・意次の不在時に来ていた佐野政言のことが気になります。父に家系図の件も含めて佐野を何かの要職にと伝えるのですが、意次は佐野のことをまったく意に介していないようでした。さて重三郎ですが、江戸の外に何か所か販路を開拓できて、さあ次はどこに販路を広げていこうかと考えを巡らせていました。重三郎の意識の中には、今まで自分はいろんな人に助けられてきた、でも自分はまだ何も恩返しをしていないという思いがありました。「耕書堂を日の本一の本屋にするしか道がない。それが恩に報いる道。」ーーそれが重三郎の強い思いでした。あるとき本を眺めていたふじ(飯島直子さん)が絵を見て画風が気になりました。重三郎が調べてみると「北川豊章」の名があり、以前市中の本屋でも何種類かの絵に「豊章」の名があったことを思い出しました。これはもしかして唐丸が?!ーー重三郎の推測がますます強くなっていきました。
May 8, 2025
-

ネモフィラ〜戸田川緑地公園(名古屋市港区)
前回の日記の続きです。4月の前半に名古屋市港区にある戸田川緑地公園に行ってみたかった理由は、他のSNSでこの公園にネモフィラが一面に咲き誇るがあるのを見たからです。桜もそうですが、小さな花が一斉に咲いていると、一つの柔らかい色の集合体が美しく映えるのです。ネモフィラがつくる優しいブルーの絨毯。それを期待して行ってきました。サイクルモノレールの後、ネモフィラが咲いている場所を探していました。その途中、甘い香りが漂ってきて、それはこの子たちからでした。ネモフィラの丘?に着きました。私がSNSで見たときはたしか一面ブルーだったけど、ここは思ったより咲いていなくてまばらでした。でも丘を一周すると、反対側は一面咲き誇っていました。このブルーの絨毯を見たかったのです。青い小さな花をアップで。陽光があると一段と綺麗になります。快晴の日に来れてラッキーでした。丘の上にある休憩所です。ここに座ってのんびりと上から一面のブルーの絨毯を眺めるのもいいですね。そして多くの人が目指したのは、この風景です。桜が満開のときだけ見られる、ネモフィラと桜のコラボです。ブルーの中にときどき白いネモフィラも混ざっていました。ネモフィラを堪能した後、園内を一通り見学して帰りました。ここを出る前にもう一度、桜と戸田川を撮ってみました。
May 1, 2025
-

桜 2025〜戸田川緑地公園(名古屋市港区)
4月の前半の某日、この地方では早咲きの桜はもうこれで終わりだろうと思い、そして別の目的も兼ねて、名古屋市港区の戸田川緑地公園に行ってきました。この戸田川緑地公園は国道1号線と国道302号線が交差する場所にあり、この日は名古屋市内を抜けて国道1号線のほうから入りました。この公園に着くまでの道は私の生まれ育った地域を通っていくので、懐かしい風景や市バスに乗っていて何度も聞いた地名にノスタルジーを感じていました。そしてたどり着いた緑地公園。長年、名古屋にいたのに来たのは初めてだったので、目的の場所より一番遠い駐車場に入れていました。まあ日頃は歩くことが少ないからいい運動でしたが。駐車場を出て橋を渡った左手にあったエリアへ。ここは「とだがわ生態園」で、大きいレンズを装着して、園内に飛来する鳥を撮っている人が何人かいました。生態園を軽く見た後は、道路を渡って南側のエリアへ。園内のレイアウトがわからないので、とりあえず川沿いに歩きました。桜の風景を求めてか、平日だったけどわりと人が来ていました。桜を背景に記念写真を撮っている人があちこちにいました。今回の目的その1「サイクルモノレール」が見えてきました。1人1周100円で、こどもランド内にあるけど大人1人でも乗れます。チケットを買って乗り場へ。私が乗ったときは空いていてすぐに乗れました。こんな感じでモノレールを自分で漕ぎながら進んでいきます。このモノレールは、桜の季節には足元に見えるこの桜の風景が有名なのです。桜の向こうに見えるのが戸田川です。ただ桜が綺麗なポイントでは、モノレールを停めてホントゆっくり撮る人もいて、後続がつっかえていました。私が1周して戻った11時頃は、30分くらいの乗車待ちがありました。後で聞いた話では、先日の土日では乗車に2時間待ちの人もあったとか。人気の飲食店と同様、混んでいるときはある程度は気遣いがあったほうがいいと思います。
April 29, 2025
-
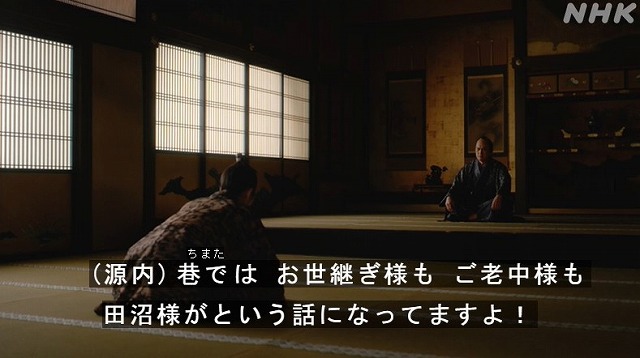
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第16回~「さらば源内、見立は蓬莱」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回で安田顕さんが演じてきた平賀源内が退場となるのですが、私はドラマの進行の中で感動というより、いろいろと考えてしまいました。源内が大工の久五郎(齊藤友暁さん)が持ってくる煙草を吸うにつれ、本人の自覚もなく徐々に身体の変化が起こってきます。やたら気分がハイになったり怒ったりと喜怒哀楽の変化が激しくなり、幻聴が聞こえたり。何かの麻薬と思われるのですが、さらに牢に入ってからの異様な寒気は禁断症状か?と。ドラマ内でも「薬」と言っていたので何かを使ったのでしょうが、調べても私では何かはわかりません。だけど源内の晩年の様子と言われている事柄から、上手くドラマを作るのだなあと思っていました。そして田沼意次(渡辺謙さん)と一時期は喧嘩別れの状態になったけど、表向きは互いに和解するなんてことはなかったけど、心の中では互いに理解し合い、互いに自分のできる方法で相手を守ろうとしていた姿には心を打たれました。それにしても渡辺謙さんの田沼意次は、優しい男ですね。ドラマの後半で蔦屋重三郎(横浜流星さん)が老中である自分にあれだけ言いたい放題言ったら、重三郎がその場で無礼討ちになるのもありでしょう。でもそれを聞き捨て、自分が世間から悪者にされても良しとしたのですから。話は戻りますが平賀源内。今までのドラマではイチ登場人物という感じでした。でもこのドラマの森下氏の脚本と安田顕さんの演技で、見事なまでに心に残る人物となりました。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永8年(1779)2月、第10代将軍・徳川家治の嫡男の家基が鷹狩の最中に急死、家基の母の知保の方は老牢中の田沼意次(渡辺謙さん)が家基を殺したのではないかと強い疑いを持っていました。老中首座の松平武元は意次の潔白を知保の方に悦明すると言ってくれていたのですがその武元も急死し、事件の証拠となるはずの手袋もなくなっていました。人々は全ては意次が事件の黒幕であるとまことしやかに噂し、その話は城内にとどまらず市中にも広まっていました。将軍・家治の判断でこの事件は幕引きとなったのですが、世間の人々から悪く言われている意次を案じる平賀源内(安田顕さん)は納得がいきません。源内は自分が事件の真相を調べると主張しますが、双方の立場や感情のこじれから、意次と源内は喧嘩別れの状態になってしまいました。さて、出版への意欲がますます高まる蔦屋重三郎(横浜流星さん)は機会があれば市中に行って芝居を見に行き、座元の話ぶりや芝居の内容を参考にして何かに使えないかと考えたり、その脚本家や演者たちと交流を持って次に出す本のことを考えていました。この日は浄瑠璃作家の烏亭焉馬と縁ができ、そのことを富本豊志太夫(寛一郎さん)や名見崎徳治(中野英樹さん)と話していました。でも平賀源内の話題になったとき二人はいい顔をせず、源内が今「不吉の家」に住み、巷では狐がついているとまで言われていると重三郎は知りました。重三郎が源内を訪ねると、世話人の久五郎(齊藤友暁さん)が案内してくれて、家の中には丈右衛門というもう一人の客もいました。丈右衛門は用が済んですぐに帰っていき、重三郎の訪問を源内はやけに機嫌良く迎えてくれました。大工の久五郎は手土産に煙草を持って頻繁に源内を訪ねているようで、久五郎が出す煙草を源内はすごく気に入っているのですが、重三郎はこの屋敷の外にまで漂う独特の香りが気になっていました。ある夜、源内に仕事を頼んでおいた丈右衛門(矢野聖人さん)が訪ねて来ていて、源内は最初は上機嫌で丈右衛門を迎えていたのですが、彼が源内のエレキテルは効果がないという世間の評判を話すと源内は激高しました。源内をなだめようと久五郎はいつもの煙草を差し出し、源内が少し落ち着いたら丈右衛門は退室し久五郎が送っていきました。二人がいなくなると広い屋敷のあちこちから源内を罵る声が聞こえてくるのですが源内が探し回ってもそこには誰もいませんでした。しばらくして戻ってきた久五郎に源内が図面のことで突っかかっているとなぜか帰ったはずの丈右衛門がいて、源内を気絶させました。久五郎は「話も煙草もよく効いた。後は自害に見せかけるだけ。」と言い、二人は最初から源内を罠にかけていたのですが、その直後に久五郎は丈右衛門に斬られ、斬った刀は源内の手に握らされました。源内は久五郎を斬った下手人として捕らえられ投獄されていました。この事件はまたたく間に世間に広まり、重三郎は急ぎ源内がいた屋敷に駆けつけて頼んでおいた草稿を手に入れようとしたのですが、屋敷を見張る役人から渡されたのは書き出しとも思える紙が1枚のみでした。一方、田沼意次は夜中に密かに奉行所の牢獄に行き、源内から直接話を聞きました。源内はあの時のことは自分でもわからないと言い、丈右衛門の話をすれば意次は屋敷の普請のこともそんな男のことも知らないと言いました。源内は自分は何者かに嵌められたと悟りつつ、幻聴のことや覚えがない人殺しのことを伝え、自分は何が夢で何が現かわからないと涙ながらに意次に訴えました。意次はそんな源内の手を牢越しに取り顔に触れさせ、自分は確かにここにいると伝えると、絶望の中にいる源内は声をあげて泣きました。源内の無実を晴らすために、意次はこの事件に関して三浦庄司(原田泰造さん)に調べさせていました。三浦の話から意次の嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)は、側近の松本秀持の用人に丈右衛門という人物がいるが、何者かが丈右衛門を名乗り偽りの普請話を源内に頼んだ、という結論を得ました。意次は松本を呼んで奉行所に調べさせようとしましたが、意知はそうすると松本をこの事件に巻き込むことになる、松本の命も危なくなる、将軍・家治が幕引きを命じたのにまた幕が開いてしまう、と強く反対しました。意知の言い分はもっともだと考えた意次は、これ以上動くことはしませんでした。源内の投獄に納得がいかない重三郎は須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)と共に田沼意次に直訴に行きました。重三郎は不審な点を訴え、源内の家に1枚だけ残っていた草稿の書き出しを意次に渡すと、意次はその紙に書かれた文章に釘付けになりました。市兵衛も源内の刀のことや酒のことで不審だと強く訴えますが、その草稿を読んだ意次の様子がおかしいと感じた重三郎は、意次の考えを訊ねました。意次は今の源内は以前の我らが知る源内ではないと言い、そんな話をしていると源内が獄死したという報せが入りました。その場にいる誰もが驚きを隠せない中、退室しようとする意次に重三郎は思わず立ちあがり意次を追いかて問い詰めようとしました。無礼者!と家臣たちに取り押さえられる重三郎に意次は否定もせず「俺と源内の間には漏れてまずい話など山ほどある!何を口走るかわからぬ狐憑きは怖ろしいからな。」と言い、そんな意次を重三郎は「この忘八が!」と罵りました。退室した後、意次は源内が遺したあの1枚の草稿を焼き捨てるよう命じて三浦に渡したのですが、その文章を読んで意友と三浦は源内の真意を知ったのでした。徳川家基と松平武元の急逝をめぐる一連の騒動の中で意次と源内が喧嘩別れのような状態になった時、源内は意次を悪者にしてやる!と捨て台詞を吐いて姿を消しましたが、源内は意次が言葉に出せない部分をちゃんとわかっていました。重三郎から頼まれた草稿には手袋の事件を題材に、意次と彼を悪者にする悪党を、そして事件の真相に気が付く自分を登場人物にし、世に出そうとしていました。意次もまたあの時、源内の身を案じて事件から切り離そうとしていたのでした。安永8年(1779)の年の瀬、小雪が舞う牢の外を源内が凍えながら眺めて一句詠んでいると、そこに1杯の茶が差し入れられました。その頃、徳川御三卿の一つの一橋治済(生田斗真さん)は、屋敷の庭で所々に血のついた文字が書かれた紙の束を家臣が燃やすのを眺めながら、「薩摩の芋はうまいのう。」と満足気に焼き芋をほおばっていました。(これまでに治済と源内との関わりは全く描かれていません。なのに治済の意味ありげな表情で、多くの視聴者は治済が源内の死と、さらに家基の死とも関連があるように想像してしまいます。生田斗真さん、焼き芋を食べただけでこれほど視聴者を怒らせる男になったのですね。)重三郎と市兵衛は源内が埋葬された場所に行き、冥福を祈りました。墓の前から動こうとしない重三郎に市兵衛が声をかけると、自分は源内が死んだとは思っていない、誰も亡骸を見てないということはもしかしたら誰かが源内を逃がしてくれているかもしれないと、「分からないなら楽しいことを考える」という重三郎の流儀を語りました。市兵衛は重三郎の考えを受け入れつつ、それなら自分は「平賀源内を生き延びさせる。」と言いました。それは市兵衛が源内の本を出し続けるという意味でした。「自分が死んでも源内の心を生かし続けることができる。」ーー市兵衛の言葉に重三郎は涙が止まりませんでした。重三郎は「書を持って世を耕し、この日の本をもっともっと豊かな国にする。」という意味を込めて店の名をつけてくれた源内の言葉を改めてかみしめました。年が明けた安永9年(1780)正月、重三郎は青本の他10冊もの新作を一挙に刊行しました。
April 24, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第15回~「死を呼ぶ手袋」
楽天さんのこのブログ、私のパソコンからようやく以前と同じ状態で使えるようになりました。この2週間はいったいどこで何が起こっていたのか、全くわかりませんが、ともあれホッとしました。2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は終盤で、田沼意次を演じる渡辺謙さんと、松平武元を演じる石坂浩二さんが魅せ場を作ってくれました。これまでの回の中で、いつも意次を成り上がり者と見下し、意次の考えややることにはいちいちケチをつけ、時には無理難題を言って意次を悩ませる。意次は武元には毎度ストレスMAX状態だけど、それでも身分の差で自分が頭を下げる、そんな日々でした。その政敵とも思えた武元が、一大事件の場面でまさかの自分の味方となり、意次の今までの働きも賛同はできなくてもちゃんと理解はしてくれていました。双方の誤解が解け、わだかまりがなくなった後の一服の茶は、互いにうまかったでしょうね。石坂浩二さんと渡辺謙さんの、お二人のレジェンドが作り上げた空気感に、多くの視聴者が画面から目を離せなくなり、思わず緊張してしまっただろうと想像します。そして一方で、一橋治済を演じる生田斗真さん。この方は『いだてん』で三島弥彦を演じていました。天狗倶楽部では「我らはスポーツを愛し、スポーツに愛され」のセリフと共に「奮え~~~!」とポーズを決める爽やかな好青年を演じていました。それが『鎌倉殿の13人』でなんか嫌な役柄を演じ、この『べらぼう』ではさらに癖のある人物を演じるようです。私は生田さんの、若さあふれるあの爽やかな弥彦が好きだったのですが、今回は何を考えているのかわからない、暗躍して陰でニヤリと笑う場面が多そうな予感がします。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼうやっと相思相愛の女と一緒になれたと思ったら、ほんのひと時の幸せの後で瀬川は一人で出て行ってしまい、蔦屋重三郎(横浜流星さん)は何をやるにも気力のわかない日々を過ごしていました。一方、平賀源内(安田顕さん)新しく迎えた弟子の裏切りに会い、また源内が発明したエレキテルが世間ではまがい物と呼ばれ、気持ちが荒んで粗暴になり、市中の人々に迷惑をかける日々を送っていました。重三郎はその場面に出くわし、源内をなだめた後で須原屋市兵衛を訪ねました。凋落した鱗形屋孫兵衛の少しでも助けになればと鱗形屋の吉原細見を市兵衛のほうで買い取ってもらい、それを自分が買い取っていたのです。ある日、朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)が重三郎に会いに来て、今の鱗形屋は青本を出す余裕がないから、重三郎が青本を出さないかと話を持ち掛けてきました。重三郎は自分と組むと市中では本が売れなくなると喜三二に伝えたのですが、喜三二は「売れる売れないはどうでもいい。一番楽しく仕事ができる重三郎と一緒にやりたい。」と言ってくれました。そんな話をしていたら北尾政演(後の山東京伝)がやってきて自分が絵を描くと言い、重三郎の協力者はだんだん増えていきました。重三郎は店を面白い本でいっぱいにしたいと義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)に夢を語り、青本をやる決意を次郎兵衛に伝えました。10代将軍徳川家治の嫡子・徳川家基(奥智哉さん)は、最近は経済に関する事を熱心に学ぶようになっていました。もっともそれは自分が経済を知れば父・家治が重用している田沼意次を遠ざけることができるという考えによるものなのですが、自分が将軍となった暁には8代・吉宗公のように自ら政の舵を取りたいという思いがあり、家基を幼い頃から見てきた松平武元(石坂浩二さん)は胸が熱くなりました。そして家基は間もなく正室になる種姫から贈られた鷹狩り用の手袋を手にはめて意気揚々と鷹狩に出かけました。ところがその次期将軍たる家基が、鷹狩の最中に急に倒れこんで帰らぬ人となる事態が起こりました。(安永8年、2月)我が子・家基の急逝に半狂乱になった知保の方は田沼意次(渡辺謙さん)が毒を盛ったと騒ぎたて、周囲の者たちも憶測をまことしやかに噂していました。平賀源内はオランダ製の機器をまねて作ったものを意次に見せに来て、その折に今の日本が品物代として海外に大量の金銀を出している現状を伝えました。さらに源内は、日本の津々浦々にある価値の高いものを掘り起こし、売り出して海外に売りつけるような改革が必要だと意次に進言しました。一方、将軍・家治は我が子・家基の急逝に納得がいかず、松平武元と田沼意次にこの一件を徹底的に調べ直すように命じました。ただどうやって家基に毒を盛ったのか、意次がその方法が全く見当がつかなくて悩んでいたらちょうどそこに源内が来ました。意次は源内にその非凡な頭脳でこの一件を考えるよう頼み、源内も自分の要望を後できいてもらうこととして、意次の頼みを引き受けました。早速鷹狩りの現場に行った源内は、吾作(芋洗坂係長さん)の話を聞いて家基の死因に気が付きました。そのころ重三郎は本屋の仕事が少しずつ動き出していて、朋誠堂喜三二もよく重三郎の店に顔を出していました。ある日、喜三二が来た折に重三郎は自分が書いた文章を喜三二に見せ、ある人と一緒に考えた物語だけど自分には文才がないからこれを元に一作仕上げてほしい、これはとびきりいい物に仕立てたいから、と頼みました。そんな重三郎に喜三二は「だったらなおのこと、もうひと粘りして自分で文章を考えたほうがいい。その人のためにも。どうにもならなきゃ俺が最後は仕立ててやるから。」と助言しました。家基に毒を盛った方法は、江戸城内で調査書を読んでいた松平武元が、意次より先に気が付いていました。鷹狩りの現場から戻った源内が意次に、家基の手袋に毒が仕込まれていてそれは爪を噛む癖のある家基になら仕掛けられる、と報告しました。意次は西の丸にいる長谷川平蔵宣以に手袋を取り戻すよう命じましたが、家基があの日身につけていたものは全て生母の知保の方が手元に置き、それを数日前に松平武元が引き取った、とのことでした。そう報告を受けた意次は激しく動揺し「終わったか。」と呟きました。田沼意知(宮沢氷魚さん)がその意味を父・意次に訊ねると、あの手袋は大奥総取締の高岳に頼まれて意次が用意したものなので、それが武元の手にあるということは、意次が毒を盛った犯人にされてしまう、ということなのでした。そんな話をしていると、田沼邸に武元からの使者がきました。意次は武元の屋敷に呼ばれて茶室に通され、武元は人払いをしました。意次が緊張の面持ちで挨拶をすると武元は、自分の体調が良くなくて呼び出してすまなかったと、意外にも低姿勢でした。そして話はいよいよ本題に入り、武元はあの手袋を意次の前に出しました。意次は手袋に関することを丁寧に説明し、武元も手袋には種姫以外の誰かが毒を仕込んだのだろうと自論を述べました。そして、では誰が毒をとなったとき武元は意次の方に体を向けて見据え、意次がいよいよかと構えたら「そなた以外の誰かであろう。」と。自分を必ず犯人に仕立て上げるであろうと予想していた武元の意外過ぎる返答に意次が驚きの表情を隠せないでいると、武元は声をあげて笑いました。「わしに疑われると思うておったか。まあ、そうであろうな。」と日頃の意次に対する態度を武元自身もわかっていました。意次は、なぜ犯人が自分ではないと思ったのかを武元に訊ねました。すると武元は、もし意次が犯人ならこの手袋を自分に押さえられるような無様はしないと言い、でも自分を見くびるなと念押ししました。武元は「そなたは気に食わぬが、これを機に追い落としをすればまことの外道を見逃すことになる。わしはそれほど愚かではない!」と真剣に怒りました。意次は自分が愚かだったと武元に詫びて許しを乞うと武元は、検校らを捕縛した際の意次の家基への諫言は忠義者の証だと言いました。ただそう言いつつも武元は、世の大事をなんでも金とする意次の考えは好かぬ、いざというときに金ではどうにもならないこともある、と意次に念押ししました。武元と意次の双方の誤解が解けた後、この一件をこれからどうするかを、二人で遅くまで話し合いました。意次の身を案じていた意知や三浦庄司(原田泰造さん)に、武元との話し合いの結果を伝えました。武元は自分を疑っていなかった、一旦調査を止めて真犯人が動くのを待つ、将軍・家治には自分から事の次第を伝え、自分を疑う知保の方には武元が自分の潔白を説明してくれる、と意次は皆に伝えました。今まで意地悪ばかりしてきた武元が最強の味方となってくれたことで皆は安心し、思わず笑いがこぼれました。しかしその夜、病状が悪化した武元が急死し、武元の部屋にあったあの手袋は誰か女が持っていってしまいました。
April 17, 2025
-
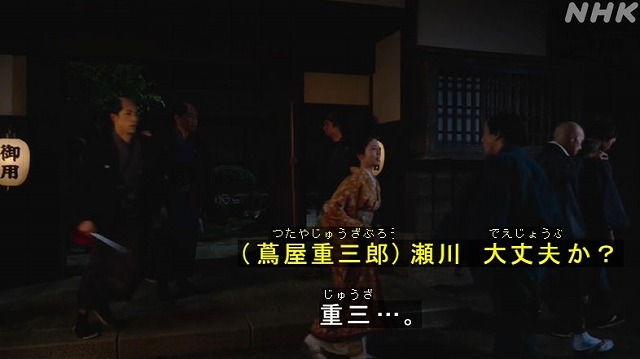
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第14回~「蔦重瀬川夫婦道中」
私のパソコンからこの「日記を書く」に入ると、初めは今まで通りだったのが、なぜか保存→修正で改行のタグが消えていました。(文章も画像も数珠つなぎ状態)やむなくちょっと面倒だけど他の方法で日記を作ることができるので作業していたら、数時間後になぜかまたいつものように使えるようになっていました。いったい何が起こっているのか、さっぱりわかりません。さて、2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回ではなんといっても後半に、市原隼人さん演じる鳥山検校がお白洲の場で、最愛の妻の瀬以(小芝風花さん)を離縁という形で自由にする姿に心を打たれました。莫大な金を積んで吉原から瀬以を身請けし、妻となってからは瀬以の望むことはなんでも叶えてきました。ただ一つ、吉原(重三郎)への思いを除いては。でも最後は、離縁という形で瀬以を身も心も開放しました。まあそりゃ状況的には、この先は自分の財産が没収されてしまうから瀬以を養えないでしょうっが。でもそんなことは抜きに、鳥山はただ瀬以を解放しました。その後の瀬以はおそらく、あの時に激しく嫉妬した重三郎のところに行くとわかっていても。やっと結ばれた蔦屋重三郎(横浜流星さん)と瀬川(瀬以)でしたが、ほんのひと時の幸せの後は、別れでした。幼い頃から吉原で一緒に育ち、互いに魂の片割れのような存在だったけど、ほんの一瞬、夫婦になるという願いが叶ったことを思い出にして、瀬川は去っていきました。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永7年(1778)鳥山検校(市原隼人さん)の手下に連れられて屋敷に来た蔦屋重三郎(横浜流星さん)でしたが、理由はわかりませんが屋敷の前に役人がいて中に入れず、そのうち鳥山らが連行されていきました。その時に瀬以(小芝風花さん)も一緒に連行されていて、重三郎が役人にその理由を問うと重三郎も関係者だと思われて連行されてしまいました。奉行所では重三郎は関係ないと証明されたのですが、瀬以をかばうために吉原者として自分も関わったと嘘の証言を。そのことで騒動になり、重三郎は後で主の駿河屋市右衛門からこっぴどく叱られ、止めに入ってくれた扇屋宇右衛門からもその嘘で吉原に類が及ぶことになるから気を付けるよう注意されました。ただ鳥山たちの件とは別に、重三郎は今の茶屋で本屋を兼業するのではなく、そろそろ自分の店を持ったほうがいい状況になってきました。その援助を親父衆に頼もうと集まりに顔を出し、短歌のやり取りをしていました。重三郎は親父衆から後押しを認めてもらえ、さらに主の市右衛門には証人になるのを頼むことができました。(こうして即興で一句ひねることができるなんて、親父衆も重三郎も教養が高いのですね。女郎屋の親父衆は三味線の稽古や学問や世の中の仕組みの勉強などで、毎日それなりに忙しかったようです。)鳥山の妻として捕らえられた瀬以ですが一旦は釈放され、鳥山の吟味が終わるまで松葉屋の寮に預かりの身となりました。重三郎は寮に本を置きに来た折に、年明けに茶屋の2件隣りで店を出す話をし、瀬川(瀬以は吉原では瀬川)に自分と一緒に店をやらないかと持ち掛けました。瀬川はまだ鳥山の妻の身なのでどうにもならないのですが、重三郎はせめて楽しい事を考えようと瀬川に言い、二人で空想をして楽しんでいました。(場末の河岸女郎屋では病気になった女郎は空いている場所で寝ているしかなかったのですが、松葉屋のような上級の女郎屋では、ちゃんと病気の女郎を療養させる寮があるのですね。)二人でそんな話をしていたら、寮の管理人のはつ(長野里見さん)から手助けを求める声がかかり、重三郎と瀬川が行きました。抱えて連れてこられた松崎(新井美羽さん)は子を堕ろした後の具合が良くなく、盲の鳥山のところで見聞きした瀬川は鍼を打つといいと助言しました。重三郎はいね(水野美紀さん)に平賀源内が作ったエレキテルはどうかと聞くと、いねはあれはまがい物だときっぱり言いました。重三郎が寮の女郎たちに本を持ってくると、重三郎と瀬以は二人での話につい夢中になり、声が大きくなって二人で話が弾んでしまいました。その楽しそうな様子を、少し回復して起き上がれるようになった松崎は冷ややかな目で見ていました。内心、瀬川が憎らしくてしょうがなかった松崎は、ついに瀬川に刃物を向けて怪我を負わせてしまいました。いねから折檻を受ける松崎を瀬川はかばうのですが、松崎は自分がこうなったのは瀬川の夫(鳥山)のせいだと逆に怒りをぶつけました。そんな松崎に瀬川は、自分だって武家のせいでここに売られてきて苦労した、恨みの因果を巡らせても仕方ないと考えを伝えました。この当時の遊女の妊娠や堕胎について、 You Tube のほうでRekiShock(レキショック)先生が解説動画をUPしています。 ⇒ ⇒ こちら 動画の中にある言葉です。「客をとって稼がなければならない遊女にとって、妊娠は粗相。(意訳)」ーー力のない者にとって、辛い時代だったのですね。預かりの身となっていた瀬川についに奉行所から呼び出しがかかり、夫・鳥山と共に裁きを受けることになりました。瀬川に対しては、検校の妻として贅沢三昧したのは許し難き悪行なれど遊女の憐れな身の上、二度と遊興はしないようにと無罪に。ただその後に、鳥山とは離縁するように言われ、それは鳥山の意思でした。このまま鳥山と別れてはいけないと思った瀬川は、鳥山に話をしたいと奉行に願い出て、奉行も許可しました。瀬川は夫・鳥山に「今まで何度も深く傷つけてしまったのに、私の望みは何でも叶えてくれた。私は本当に幸せな妻だった。」と鳥山の背中越しに心の底からの思いを伝えました。鳥山からの離縁状を持って瀬川は吉原に戻りました。もう女郎でも誰かの人妻でもない瀬川は晴れて自由の身となり、重三郎は嬉しくて人目もはばからず思わず瀬川を抱きしめました。やっと思いを遂げた若い二人を、蕎麦屋の半次郎(六平直政さん)は温かく見守っていました。瀬川は物語の構想を考えながら、自分は本当に鳥山には大事にしてもらったと重三郎に伝えました。「巡る因果は恨みじゃなくて恩がいい。」ーー幼い頃から瀬川の苦労をずっと見てきた重三郎は、今度は自分が瀬川を大事にすると心から誓いました。重三郎は茶屋の2件隣りに自分の店を持つにあたり、主の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)に、瀬川と所帯を持つことを報告しました。ただ鳥山の妻だったことで世間にも吉原内にも瀬川を恨む者がたくさんいることを案じる市右衛門は、瀬川と夫婦になることには大反対でした。しかし重三郎は、逆に吉原の界隈のほうが門番がいて瀬川が安全であること、瀬川の面倒をみれば吉原は「困った女を助ける場所」と世間の“忘八”の親父たちへの見方が変わり、吉原者は「四民の外」という世間の扱いも変わる、と重三郎は主張しました。市右衛門は、世間の目は厳しいことを重三郎に念押しし、二人が所帯を持つことを認めました。一方、違法な荒稼ぎで財を蓄えた検校たちを一斉に取り締まったことを、田沼意次(渡辺謙さん)は将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に報告しました。そして接収した証文から、幕府が金額を見直した後に幕府が取り立てを行う、と伝えました。家治は「道理に従い、苦しむ者たちを救いつつ、幕府の金蔵も潤す。」と意次の考え気に入り、認めました。この件では思い通りに事が進んだ意次は、家治に晴れやかに年の瀬の挨拶をして退室していきました。大晦日の夜、除夜の鐘が響く中、人々は年の瀬の行事を楽しんだり、あるいは忙しく新年を迎える準備をしていました。瀬川も除夜の鐘を聞きながら、いろいろあったこれまでの自分の人生を振り返っていたのですが、『青楼美人合姿鏡』を読み返したときに重三郎が描く夢の話を思い出し、曰くつきの自分がこのまま重三郎の傍にいてはいけないと思うようになりました。年が明けた翌朝、瀬川は一人で松葉屋の寮を出ていきました。重三郎に残した文には、重三郎の夢を現にするために自分は出ていく、私のことは案じるな、重三郎のおかげで女郎の闇に堕ちずに済んだ、ありがとう、とありました。市中を一日中探し回った重三郎でしたが瀬川は見つからず、幼い日に渡したあの赤本だけが机に残されていました。
April 11, 2025
-
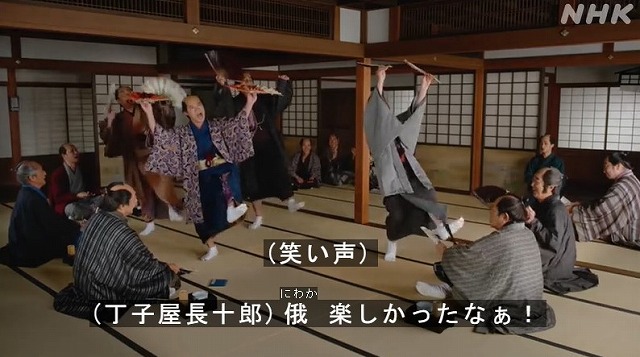
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第13回~「お江戸揺るがす座頭金」
4月2日より私のパソコンからこの楽天ブログの「日記を書く」と「編集する」にずっと入れなかったのですが、今朝試しにやったら書く方に入れました。この期間、いったい何が起こっていたのか、私にはさーーっぱりわかりません。でもとにかく動いたので、ドラマ感想日記の続きを書いて上げることにします。2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。江戸時代の後期ともなると、世の中は平和で安定していて文化は発展していったのですが、その陰では武士の生活が成り立たなくなっていた一面もあったのですね。田沼意次と言えば、歴史の教科書的には簡単に政策が書かれていて、そしてドラマ等ではほとんどが悪役のイメージに描かれていました。でも渡辺謙さん演じる田沼意次はなぜか魅力的で、つい心情的に味方をしたくなります。1月からのこれまでの話を見ていても、何かの出来事をきっかけに今問題となっている事の打開策を考え、そのために必要な情報を適した人物に集めさせ、タイミング良く実行していくのです。今回は、甥・意致の西の丸でのお役御免が、鳥山検校(市原隼人さん)の摘発につながっていくとはまったく想像してませんでした。脚本の森下佳子氏は、以前の『直虎』のときには好きになれませんでしたが、今回はドラマの展開にグイグイと惹かれてしまいます。これが森下氏の脚本力なのですね。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永6年(1777)秋、俄祭りで対立してとことん競い合った大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)と若木屋与八(本宮泰風さん)でしたが、祭りが終われば打ち解け合う仲になっていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は道陀楼麻阿こと朋誠堂喜三二と吉原の新しい案内本作りに乗り出していました。重三郎が親父衆に呼ばれていくと、以前は重三郎の作った薄い細見は取り扱わないと言っていた若木屋が薄いのも欲しいと言い、重三郎は順調に仕事を進めていました。一方、重三郎と対立している鱗形屋がまた偽版を作る騒動を起こし、その裁きが年の瀬に下って、版木と摺本は召し上げの上、実行犯の手代の徳兵衛は江戸十里四方から追放、鱗形屋孫兵衛は監督不行き届きで罰金20貫文となりました。鱗形屋は年が明けても店を開けられず、孫兵衛は親しい西村屋や鶴屋に青本の一部を買い取ってもらって収入にしていました。重三郎もせめて細見は自分が取扱って鱗形屋の助けになればと考え孫兵衛を訪ねましたが、かえって怒りを買ってしまいました。やむなく市中の本屋で唯一重三郎が頼めそうな須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)を訪ね、事の仔細を話して須原屋を通して細見を買ってもらうようにしました。鱗形屋が悪事に手を染めた理由ーーそれは「座頭金」が原因でした。座頭というのは検校を頭とする当道座に属する下位の盲人のことで、お上からは生業として金貸しを許されていました。その最高位にある鳥山検校(市原隼人さん)は、かつては𠮷原の女郎だった瀬以(小芝風花さん)を身請けして妻としていました。瀬以をこよなく愛する鳥山は瀬以を喜ばせたくて、好きなだけ着物を作るように言うのですが、自分はもう十分してもらっていると感じる瀬以は、どうか吉原に残る女郎たちに着物を作ってやって欲しいと願い出ました。瀬以の望むことは何でも叶えるとしている鳥山はそれを受け入れました。この頃ですが、武士も金策に困って生活できず、果ては旗本の娘でも借金のかたに売られているという事態も起きていました。それば幕閣の中でも対策が問題となっていて、老中首座の松平武元は毎度のように老中の田沼意次(渡辺謙さん)を足軽上がりと見下しながら綺麗ごとの無理難題を押し付けるだけでした。意次が帰宅すると甥の田沼意致(宮尾俊太郎さん)が来て、西の丸でのお役御免になったことを報告、このままでは田沼家の存続も危ういと感じた意次は、座頭金を調べることで武士を救済しようと考えました。松本秀持(吉沢悠さん)には当道座の金の流れを調べるよう命じ、長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)には西の丸にいる者で座頭金に手を出している者を探り、平蔵の働きぶりを見せるよう命じました。さてこの頃、重三郎には北尾重政(橋本淳さん)が連れてきた弟子の北尾政演(後の山東京伝;古川雄大さん)との出会いがありました。若いのに達者な絵を描く政演を重三郎もすっかり気に入り意気投合。今度、吉原で遊びたいと言う政演は、手持ちの細見には気になった事が細かく記録されていて、重三郎も感心していました。またこの時『辞闘戦新根』の話題が出て、重三郎も本の面白さを絶賛。ただ本に鱗形屋の名が入っているだけで避けられているという現実も知りました。鳥山検校は本が好きな妻・瀬以のために、屋敷に書庫を用意しました。様々な種類のたくさんの本を見て思わず喜びの声をあげてしまう瀬以でしたが、自分の何気ない言動が夫・鳥山への配慮を欠くことも気づいていました。また鳥山も、妻・瀬以が自分に対しては吉原の者たちといる時のような心からの笑いがないことで、瀬以を責めてしまいました。時が経てば瀬以も鳥山を心から愛するようになるでしょうが、すぐには気持ちがそこまでには至らないことを理解できない鳥山は、嫉妬して怒って瀬以を書庫に閉じ込めてしまいました。勘定方の松本に当道座の金の流れを調べさせていた田沼意次は、鳥山検校が成している莫大な財や、座頭金に手を出した武家が借金を返せず家督を乗っ取られているという報告を聞いて、実態に驚愕しました。そこへ長谷川平蔵が急ぎで入ってきて、将軍・嫡男の徳川家基がいる西の丸で、小姓組で家基もお気に入りの森が逐電したという報せを持ってきました。そこで意次は松本に森を探して捕らえてくるよう命じ、松本は平蔵と共に退室していきました。意次は森忠右衛門(日野陽仁さん)・森震太郎(永澤洋さん)親子の件で将軍・徳川家治(眞島秀和さん)と徳川家基(奥智哉さん)に進言を願い出ました。坊主頭で現れた森親子に家基は驚愕、忠右衛門は自分の禄では家族を養えない、息子の震太郎が役職につけるよう賄の金を座頭金から借りた、しかし役職には就けず、あらゆる努力をしたが結果こうなってしまったと説明しました。意次は、生真面目な森がここまで追い詰められた、森と同じ道を辿る可能性のある者が西の丸にこれだけいる、と家基に資料を見せました。「将軍家は己の旗本すら養えていない。今の制度のままでは旗本八万騎を養えない。この国の行き方を決める上様だからこそ現実を知ってもらいたい。」と意次は家治に進言しました。意次はさらに、これをふまえて高利貸しを行って凄まじい財を成している検校たちを一斉に取り締まりたい、と家治に願い出ました。神君・家康公が決めた盲を守る制度をあくまでも守るべきと松平武元は主張しますが、意次は自分は徳川の世を守りたい、不当な手口で財を成した検校はもはや弱い者ではないと強く主張、家治にもそれを認めました。鳥山は瀬以が大事に持っている古い本が重三郎からのものであることを手下に確認させ、重三郎を屋敷に連れてくるよう命じていました。鳥山は短刀を持って瀬以のところに行き、重三郎とのことで状況次第では瀬以を不義密通の罪で斬ると言います。瀬以は身の潔白を主張しますが、心はまだ重三郎にあると、そして瀬以を骨の髄まで女郎だと言いました。瀬以は、吉原で辛かったけど重三郎が心の支えになった、でも鳥山がこの世で誰よりも自分を大事にしてくれていることも、自分が鳥山を傷つけてしまっていることもわかっている、己の心はどうしようもないと訴えました。そして鳥山に、自分を信じられないならどうぞこのまま命を取ってくれと鳥山の短刀を抜き、自分の胸に当てました。そんな頃、重三郎が屋敷に着きましたが、屋敷の前にはなぜか役人がいて中に入れませんでした。
April 10, 2025
-

桜 2025〜味美二子山古墳(愛知県春日井市)/日吉神社(愛知県清須市)
桜シリーズ、第3段です🌸🌸🌸先週の土曜日、ちょっと用事があったので、出かけたついでに寄り道しました。まずは春日井市の二子山古墳がある公園に。ここは周辺を含めて味美古墳群になっていて、公園内は複製のハニワや資料館があります。今回は桜を見たかったので、画素は少しです。🌸名鉄 小牧線の味鋺駅が近いので、電車と桜がコラボできます。🌸この桜並木の右手に、前方後円墳があります。この後、清須市方面に向かいました。清須城のところは桜の花見客でものすごい渋滞になっています。なのでそちらには近づかず、少し離れた日吉神社に寄ってきました。清洲山王宮 日吉神社https://hiyoshikami.jp/ここは戦国時代の愛知県が生んだ三英傑織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に縁がある神社です。🌸日吉神社に入ると、まずこの石橋が目に入ります🌸本殿を左右で守るお猿さま。 寒くないよつにコートをかけてもらってます。🌸花手水が綺麗でした。🌸後で知ったのですが、前日に活けたばかりだったそうです。🌸神社の奥にあるお稲荷さま。🌸立ち並ぶ赤い鳥居です。 京都の伏見稲荷大社のような規模はないけど、 あちらは観光客でスゴイことになっているので、 私はこちらで落ち着いて参拝したいです。
April 9, 2025
-

桜 2025〜ライトアップの五条川(愛知県岩倉市)
花見シリーズ、第2段です🌸愛知県内には桜の名所はたくさんあります。ただ私はこの尾張地方にずーっと暮らしていながら、なぜか岩倉市の五条川には行ったことがありませんでした。先日、仕事が休みで朝一番で名古屋城に行った日の夜、思い立ってホント勢いでライトアップの五条川を見に行きました。五条川の桜は名鉄・犬山線の岩倉駅あたりから、国道41号西の大口町あたりまで、かなり長く川沿いに植えられています。今回、私は初めてだったので、岩倉駅から歩いて5分というアクセスの良い、岩倉側にしました。金曜日の夜、平日だけどすごい人出でした。🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
April 8, 2025
-

桜 2025〜名古屋城
私のパソコンからこちらの日記が書けなくなって1週間。いろいろ試しましたが、やはりパソコンからはできないようです。昨年春にパソコンが動かなくなって、甥っ子に直してもらったとき、今年に入ったら買い替えようかと話していました。しかし!、昨年末から私の仕事が激減してしまい、現在は買い替えはとてもできない状況です。なので、大河ドラマの感想日記は、しばらくお休みすることにしました。👛余裕ができてパソコンを買い替えたら、また復活する予定です。ということで、スマホからの投稿です。先週、天気が良くて仕事がなかった日に、名古屋城に行ってきました。名古屋城と満開の桜🌸🌸🌸本当に最高でした😊🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
April 7, 2025
-

カフェのアヒルさんと、我が家のスモモちゃん(スマホから)
私のパソコンから、楽天さんの日記が作れなくなっています。 これは私のパソコンが不調なのか?楽天さんのほうで何かあるのか?なので、ちょっと小ネタで動物さんたちを😊こちらは我が家のスモモちゃんです🐱そんなにゴハンを食べてないと思うのだけど、なぜかこんなに丸々と💦某アヒルカフェにて🦤🐔
April 3, 2025
-
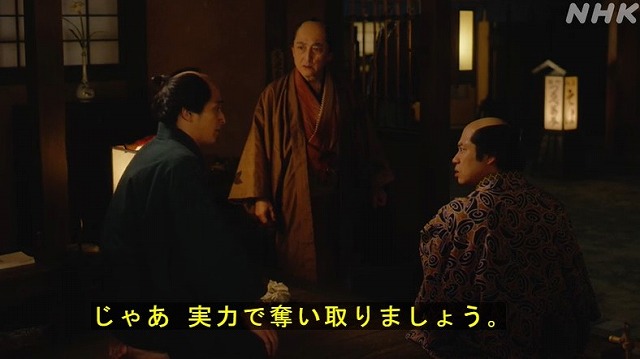
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第12回~「俄なる『明月余情』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。俄祭りをテーマにしたこの回はなんといっても、後半30分からの大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)率いる大文字屋と、若木屋与八(本宮泰風さん)率いる若木屋との、両者の踊りの対決が見物でした。あのシーンがスゴイと思ったのは私だけではなかったようで、放送終了後にはSNS各所で “ダンスバトル” と話題になりました。どこかの記事にありましたが、このダンスバトルを撮るために、俳優さんたちは稽古がとてもキツかったとか。でもこれだけ視聴者の注目を集め感動を与えられたら、厳しかった稽古も報われたでしょうか。ちなみにこの俄祭りに関する特別映像が、3月28日金曜日の午後10時から、「100カメ」の番組の中で紹介されるそうです。⇒ ⇒ こちら さて、もう一つ話題になったのが、筆名では「朋誠堂喜三二」を名乗り、実は秋田佐竹家の留守居役という平沢常富を演じる尾美としのりさんです。尾美さんは毎回クレジットに名前が出てくるのだけど、いったいどこで出演しているのか、第9回あたりまで毎回わかりませんでした。でもそれは私だけでなく、ネットの皆さんも同じ思いだったようで「尾美さんを探せ」になってました。出るのはほとんど一瞬で、尾美さんほどの役者さんがセリフもない通行人とは考えられませんでした。でも逆に、それが視聴者の関心の一つになり、そしてドラマの中では主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)に「あー、あの時の!?」と思い出させるネタになり、こういう方法もあるのかという感じでした。ドラマ製作側もそれをわかっていたようで「これまでの 尾美としのりさん出演シーンをまとめました」と出ています。 ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永6年(1777)年明け、馬面太夫は富本豊志太夫を襲名し、蔦屋重三郎(横浜流星さん)が権利を得た直伝の本は飛ぶように売れていました。ただ富本本と同時に青本も巷では人気となっていて、青本の作家の恋川春町と朋誠堂喜三二は鱗形屋が抱え込んでいました。一方、吉原のほうでは8月に行われる祭りをどうしようかと親父衆の中で話が出ていた時に、何かと対立する若木屋与八から廻状がきて、それは今まさに親父衆が話し合っている俄祭りのことでした。若木屋は昨夏に大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)が言いだしたことをそっくりそのまま自分の名で提案し、またこの時に西村屋は錦絵で『青楼俄狂伝』を出すと言い、これに賛同する者は金2両を添えて申し出を、とのことでした。自分の仕切りで祭りをやりたかったのに、若木屋に持っていかれて怒り心頭の市兵衛に、重三郎は「実力で奪い取ろう」と進言しました。吉原の馴染みの客の平沢常富は実は秋田佐竹家の留守居役で、平沢は重三郎の才能を買ってくれていました。その平沢が重三郎の後ろ盾になると言ってくれたことで市兵衛は強気になり、廻状の趣旨に賛同した、自分たちも参加するとして、金を持って若木屋与八(本宮泰風さん)のところに行きました。とはいえ対立したまま市兵衛と与八はどちらも譲らず双方が優位に立とうとし、互いに悪口を言い合い、果ては喧嘩になるところでした。重三郎は平沢常富から、町が割れるのも悪くない、対立して張り合えば祭りがどんどん盛り上がるとは教わりましたが、それどころではありませんでした。芸事にも詳しい平沢は早速、吉原で祭りの相談役となりました。市兵衛と与八の間では踊りの師匠の争奪戦をしたりと対立は相変わらずであり、また西村屋は吉原に偵察を送りこみ、重三郎の行動を見張らせていました。そんな頃、重三郎が平賀源内を訪ねると源内は不在で、小田新之助(井之脇海さん)が急遽注文が入ったエレキテル作りで忙しそうでした。重三郎は源内がいる千賀道有の屋敷に行き、源内の用事が済んだ後で重三郎が祭りで人を呼び込むものを書いて欲しいと頼むと、自分は今忙しいから朋誠堂喜三二に頼むといい、と言ってくれました。重三郎は最初「朋誠堂喜三二」と言われても誰のことかわかりませんでしたが、源内から言われていろいろ思い出し「朋誠堂喜三二=平沢」だと理解しました。重三郎が平沢のところに行って「朋誠堂喜三二先生!」と呼びかけると、平沢は慌てて重三郎を口止めしました。平沢は、自分が喜三二だと世間にばれると武士として上からお叱りを受けるし、扶持の他の稼ぎは建前では禁じられている、とのことでした。重三郎が平沢にうちで青本を書いてもらえないかと頼むと、青本は去年もうたくさん書いたし、ネタがないからやりたくないと。そこで重三郎が、この祭りの裏側をネタにしたらどうかと提案すると、平沢は次々と物語が思い浮かんできました。でも書くのは気が進まないと言うと重三郎は、本ができた暁には吉原をあげて平沢をもてなすと約束し、平沢もその気になってきました。平沢は実は朋誠堂喜三二として、恋川春町(小島松平家、内用人の倉橋格)と共に、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が出している青本の作者でした。平沢が最近、重三郎と親しく話をしていると聞きつけた孫兵衛はなんとしても平沢を重三郎に取られまいと、妻のりん(蜂谷眞未さん)以下子供たちも含め、家族総出で、青本を出すのは自分のところだけにして欲しい、これで鱗形屋が持ち直さなければ一家離散で後がない、どうか我らを救って欲しい、と土下座して平沢に頼み込みました。平沢は重三郎とも仕事をしたいと思いましたが、迷ったあげく今回は鱗形屋の頼みを受け入れることにしました。平沢は「勤めが忙しいからしばらくは吉原には行かない。でも祭りは楽しみにしている。」と重三郎に文を送り、重三郎も鱗形屋とのことを察しました。そこへ市兵衛が血相を変えて店に来て、ちょうどふらりと現れた富本豊志太夫(寛一郎さん)に助けを求めました。話によると若木屋は祭りの踊りで市兵衛の大文字屋と同じ演目の「雀踊り」を選び、さらに振り付けを藤間勘之助に頼んだ、とのことでした。そう聞いた太夫は、ならばこちらは西川扇蔵に頼むと言ってくれました。一方、重三郎は留四郎も気になるほどこの祭りの宣伝に積極的ではありませんでしたが、西村屋が錦絵で客を呼んでくれている、その上で来た客が耕書堂を覚えて帰ってもらう方法を考えている、と留四郎に返しました。(引いた目で見るーー重三郎は須原屋市兵衛の教えを取り入れていますね)吉原での祭りの準備は着々と進み、若木屋与八と大文字屋市兵衛相変わらず顔を合わせると互いに牽制の応酬でした。そしていよいよ祭り開きとなり、複数の演目に出る次郎兵衛(中村蒼さん)は張りきっていました。祭りはひと月続き、この間は切手は不要で女性客も大歓迎であり、さまざまな出し物が仲ノ町を埋め尽くします。訪れた人々は芝居を見物したり、一緒に歌って踊って楽しんだりしていました。さてこの日のために稽古を重ねた市兵衛たちの大文字屋が登場しました。しかし踊り出してすぐに向かい側から、与八が率いる若木屋が踊りながら現れ、2つの組が正面からぶつかることになりました。与八たちがほぼ同時に出てきたことに市兵衛は抗議しましたが、与八がそれを受け入れるはずがなく、2つの組は左右に分かれて進みました。しかし市兵衛と与八のにらみ合いは続き、他の踊り手たちはその場にいるのも居づらくなり次々と脇へ。どちらも負けたくない二人はしまいには、互いにガンを飛ばし合いながら二人だけで踊るという展開になりました。祭り見物に来ていた勝川春章(前野朋哉さん)は重三郎の茶屋で、湖龍斎が描いた錦絵を悔しそうに見つめていました。重三郎が春章に、錦絵は無理だけどひと月続く祭りの様子を墨摺りで俄の絵を描いてはどうかと提案、春章も描いてみたくて気持ちがのってきました。そんなところに平沢が訪れ、平沢は重三郎との約束を反故にしたと頭を下げて謝ってくれました。平沢の事情を理解している重三郎は自分のほうが無理を言ったと詫びました。平沢が安心し、そして祭りを楽しんでいる様子を見て重三郎は、急ぎで祭りの絵本を出すことになったから序だけ書いて欲しいと改めて伺いました。皆の期待を感じた平沢は快諾し、春章の絵と共に『名月余情』と名付けられた祭りの興奮が伝わる素晴らしい冊子ができました。『名月余情』は俄の土産にと飛ぶように売れていきました。大文字屋市兵衛と若木屋与八の張り合いは祭りの間じゅうずっと続き、日を追うごとに激しくなっていきました。はじめは市兵衛と与八だけの張り合いだったのがだんだんと大文字屋と若木屋との張り合いになっていき、より人々の目を引くように着物を脱いで踊ったりなど、互いに趣向を凝らしていました。祭り見物に来た人々はこの張り合いを見て楽しみ、あるいは鳴り物に合わせて集団の外で一緒に踊ったりして楽しむようになっていました。そんなこんなで連日盛況のまま、祭りもいよいよ最終日を迎えました。雀踊りは人々の間では「喧嘩雀」と名付けられどんな形で終わるのか、人々はその登場を待ちわびていました。どちらの踊りがより人々を楽しませるかの戦いは、双方もう手を尽くした感じとなり、30日間よくやったと市兵衛と与八は互いに思うところは同じでした。そこで最後の一手として、二人は手に持っていた花傘と扇子を互いに交換して、二つの組が並んで踊ることになりました。見物の人々はその姿に粋を感じ、誰もが心地よい感動を覚えました。やがて踊りは大文字屋と若木屋が入り乱れた形になり、見物していた人々も自然と踊りの輪の中に入っていきました。客に促されてその踊りの輪に入るつもりで外に出たうつせみは、人混みの中にかつて足抜けまで図った思い人の新之助を見つけました。松の井から「祭りに神隠しは付き物。お幸せに。」と言われ、新之助の元へ駆け寄り、人混みに紛れて二人はそのまま門の外に出ていきました。
March 26, 2025
-
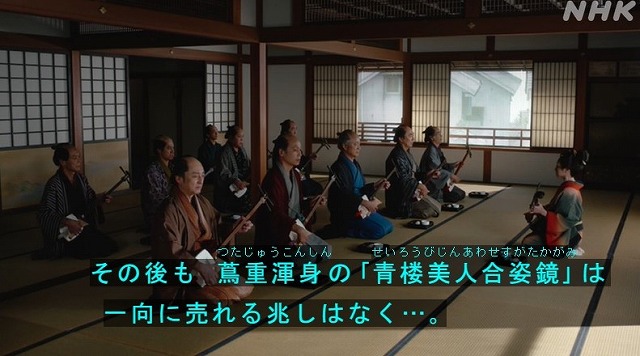
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第11回~「富本、仁義の馬面」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の話の中で全体を通して感じられたキーワードは「男なら」だと思いました。𠮷原からは絶対に外に出られない女郎たちの涙を見た富本豊志太夫(寛一郎さん)は「男なら断れない」と。主家の家老が鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)に酷いことをしたのを「忘れるのは男ではない」と、その埋め合わせを心に決めた倉橋格(岡山天音さん)。でも私はがいちばんグッときたのは、身請けした瀬以(小芝風花さん)を心から愛する鳥山検校(市原隼人さん)の言葉と行動でした。たとえ自分の気の進まないことでも、瀬以が望むことならば、少し時を置いて考えて、自分なりに納得できるとなったら行動しているのです。「そなたの望むことは全て叶えると決めた。」これはもう感動のセリフでした。周囲から大事にされるのが当たり前の人には、あるいは幸せに常に満たされている人には、この言葉の重大さがわからないと思います。でも女郎だった瀬以には、何より有難い言葉でしょう。地位が低い女郎は男に金でいいように扱われ、血のにじむ努力をして花魁になっても、自分は男の名誉欲を満たして話のネタになるだけでした。でも鳥山は、心から自分を大事にしてくれて、何かあればそれが言葉や行動となっているのがわかります。心の中にはまだ蔦屋重三郎(横浜流星さん)がいて思いを消すことはできないけど、自分のために鳥山に無理をさせたくない、鳥山を悲しませたくない、旦那様として仕えたい、そういった思いは瀬以の中にあると思います。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 花魁・瀬川の身請けの旅立ちと共に蔦屋重三郎(横浜流星さん)が大々的に売り出した女郎の絵本の『青楼美人合姿鏡』。しかしこれは鶴屋喜右衛門が予想したとおり、高価で庶民に売れるようなものではなく、本の製作のために重三郎に金を貸している女郎屋の親父衆は、本が売れないことに苛立っていました。そんな折に若木屋の与八は、先日この親父衆と決別した鱗形屋と組むと宣言し、吉原の中に対立ができてしまいました。そして重三郎はというと、『青楼美人』が売れない代わりにこの本を馴染みの客に配って返済金代わりにして欲しいなんて言うものだから、親父衆は怒りの三味線かき鳴らし。(今で言うブーイングか・笑)重三郎はその後は主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)から、毎度の怒りの階段落としをくらいました。安永5年(1776)4月、江戸城では8代将軍・吉宗公以来48年ぶりとなる日光社参が出立、出立だけで12時間もかかる大掛かりなものでした。𠮷原から出られる大文字屋市兵衛やりつらは道中の見学に出ていて、彼はその長い長い行列と人々の歓声から何かをひらめいたようでした。一方、重三郎は市中の本屋で唯一自分と関わりを持ってくれる須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)に、『青楼美人』が思うように売れなくて親父衆への借金だけが残ったと愚痴をこぼしていました。須原屋市兵衛はそんな重三郎を「𠮷原を昔のように憧れの場所に戻したいなら、一度くらいのつまづきでしょげることはない。」と励ましていました。重三郎が親父衆に呼ばれて行ってみると、そこでは𠮷原に人を呼ぶために“俄”の祭りを開いてはどうかと話し合われていました。そしてその祭りに世間で人気の馬面太夫を呼びたい、でも親父衆の中には太夫への伝手がない、平賀源内や勝川春章(『青楼美人』を描いた絵師)なら伝手があるかもしれないから重三郎から当たってくれないか?ということでした。りつ(安達祐実さん)は重三郎が豊志太夫のことを全く知らないので、次郎兵衛(中村蒼さん)も連れて浄瑠璃を見に行くことにしました。重三郎は芝居の前に立ち寄った本屋で浄瑠璃の正本を見て、「直伝」の文字があるものとないものに気がつき、直伝があるものは浄瑠璃の本元の太夫の許しを得ているものだ、とりつから教わりました。芝居小屋に入ると中は豊志太夫と役者の門之助を贔屓する主に女性の客であふれ、浄瑠璃が始まるとその世界に重三郎も思わず引き込まれてしまいました。これは何としてでも豊志太夫を𠮷原の祭りに呼びたいと思った重三郎は、太夫が外に出てくるのを待ち、自己紹介して交渉しました。しかし太夫はなぜか𠮷原を嫌い、そして太夫には鱗形屋孫兵衛がぴったりと付き添い、太夫をどこかに連れて行ってしまいました。鱗形屋の行動と、太夫は間もなく「富本豊志太夫」を襲名する予定という話からりつは、鱗形屋は太夫からの直伝の正本を狙っていると考えました。そう聞いた重三郎の頭の中には、自分が太夫から直伝を取りつければ𠮷原が繁盛するに違いないと空想が浮かびました。ただ太夫の襲名の話は、実はこの時また白紙に戻されていたのでした。𠮷原を嫌う豊志太夫をなんとか𠮷原の祭りに呼びたい重三郎は、伝手を頼って平賀源内(安田顕さん)の元を訪れていました。しかし源内は何かの実験に夢中で(たぶんエレキテル)で重三郎のことは眼中にないので、後で小田新之助(井之脇海さん)から伝えてもらうことにしました。その新之助はというと、本気で惚れた女郎のうつせみをいつか身請けするときのために、今は少しずつ金を貯めているとのことでした。またうつせみの方も、いつか𠮷原を出られた時のために近頃は和算の本を借りて読んでいると重三郎から聞かされ、新之助は安堵しました。(高校の歴史の教科書に「平賀源内、エレキテル=摩擦発電機」とキーワードが欄外の注釈で出ていました)重三郎が吉原に戻ると店にはりつが待っていて、豊志太夫が𠮷原を嫌う理由がわかったと、教えてくれました。太夫はまだ売れてなかった頃、門之助と一緒に役者の素性を偽って𠮷原に遊びに来たものの身上がばれてしまい、その時に若木屋から酷いことを言われたあげく門外に叩き出された、という過去がありました。その話を聞いた重三郎は、なぜ役者が𠮷原の出入りを禁じられているのだろうと思ったのですが、次郎兵衛は「役者の分は四民の外だから」と、りつは「放っておいたら人気で稼げる役者に皆が憧れ、まともに働くやつがいなくなる。だからお上は役者の身分を下げている。」と説明しました。ならばどうやって太夫を説得しようかと思ったとき、大文字屋の市兵衛が慌てて駆けつけ、重三郎に「いい手がある!」と言いました。市兵衛が考えたのは、浄瑠璃の元締めは当道座であり、それはつまり鳥山検校(市原隼人さん)、鳥山は花魁の瀬川を身請けしているからそれを伝手にすればいいのでは、ということでした。市兵衛と一緒に鳥山を訪ねると、すっかり良家の奥方らしくなった瀬川が先に顔を出し、久しぶりの再会となりました。「瀬以」と名を改めた瀬川は重三郎と会って昔に戻った気がして嬉しかったのか、軽口を叩き合いながら声を上げて笑っていました。廊下まで響く瀬以の笑い声は、瀬以が花魁だった時も妻となった今でも、鳥山が聞いたことのない楽しそうな声でした。鳥山が現れ市兵衛と重三郎が挨拶をすると、鳥山は重三郎の声で瀬川を𠮷原まで迎えに行ったときの記憶をたどっていました。市兵衛は豊志太夫の当道座襲名の許しを乞いましたが、鳥山は気が進みません。そこで重三郎は一度太夫の声を聴いて欲しいと進言、重三郎の願いを叶えてやりたい瀬以(小芝風花さん)は自分も浄瑠璃に行きたいと鳥山に願い出ました。鳥山は人が多い所は苦手だとやんわり断りつつ、それでも瀬以が望むのなら行くと応えました。鳥山の意にそぐわぬことはしたくないと困った瀬以を見た重三郎は、突然無理なお願いをしたことを鳥山と瀬以に詫び、渋る市兵衛を連れて帰っていきました。鳥山は重三郎と瀬以の言葉から、どちらも相手の立場を思いやっていて、二人が互いに特別な感情を持っているのだと感づきました。𠮷原に戻った重三郎は、自分に甘えてくる女郎のかをり(稲垣来泉さん)とのやりとりの中で、豊志太夫(寛一郎さん)を呼び出す方法を思いつきました。重三郎はりつと大文字屋市兵衛と共にで偽りの理由で太夫と市川門之助(濱尾ノリタカさん)を向島の座敷に呼び出し、かつての無礼を代わりに詫びた後に、特別に連れ出した女郎たちに会ってやって欲しいと懇願しました。女郎たちは喜んで太夫と門之助をもてなし、もてなされる二人も楽しんでいたのですが、思いの他早くお開きを命じられ、女郎たちはがっかりでした。名残惜しそうな女郎たちの様子を見計らって重三郎は、ほんの少しでいいので富本を女郎たちに聞かせてやって欲しいと太夫に頼み、太夫も快諾しました。りつと市兵衛が奏でる三味線で太夫が歌い、門之助が舞い、本物の浄瑠璃を目にすることができた女郎たちは感動で涙が止まりませんでした。ほんの座興程度の歌と舞いで涙する女郎たちに二人は驚きましたが、女郎たちは𠮷原からは出られないから芝居も観たことがなく慣れていないと重三郎から聞かされ、二人は言葉を失いました。重三郎は二人の前に進み出て姿勢を正し、𠮷原には太夫の声を聞きたい女郎が千も二千もいる、それで救われる女がいる、どうか女郎たちのためにも祭りでその声を聞かせて欲しい、と重三郎は懇願しました。すると太夫は重三郎が言い終わるのを待たず「やろうじゃないか。」と。「こんな涙見せられて、断れる男がどこにいる。」と快諾し、門之助も太夫と同じ気持ちでいました。そんな話をしていたら留四郎が突然入室し、手には鳥山の文を持っていました。その文には「検校率いる当道座は太夫に『富本豊志太夫』の襲名を認める」とあり、さらには「太夫の声を聞いて決めた」とありました。盲ゆえ、たくさんの音が出る場所を嫌う鳥山でしたが、密かに芝居に出向いて太夫の声を確かめていたのでした。瀬以が鳥山に礼を言うと「そなたの望むことは全て叶えると決めた」と。その言葉を有難く感じた瀬以は鳥山に「瀬以は、ほんに幸せ者にございます」と礼を言いましたが、その表情は喜びにあふれたものではありませんでした。重三郎は太夫に直伝を是非自分にと強く願い出て、了承をもらいました。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)も太夫に強く訴え、重三郎に任せれば市中に売ることはできないと念を押しました。しかし太夫は、だったらなおさら重三郎を助けてやりたいと言い、「それが男ってもんだろ?」と謎めいた言葉を残して去っていきました。孫兵衛が帰宅すると小島松平家の内用人の倉橋格(岡山天音さん;『金々先生栄花夢』の作者)が来ていて、次男の万次郎と遊んでくれていました。万次郎に座を外させ孫兵衛が倉橋に挨拶をすると、倉橋は姿勢を正しました。「当家の家老がそなたにまことに酷いことをした。それを忘れるなど男のすることではない。」と言い、孫兵衛は胸が熱くなりました。これより重三郎は富本正本に、孫兵衛は青本にそれぞれ力を入れていくことになりました。
March 19, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第10回~「『青楼美人』の見る夢は」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)が吉原の絵本を作ることでまた一回り大きな人間になっていくのが話の筋なのですが、私はそれよりもドラマの登場人物がいったいどんな人なのかが気になりました。時代劇の大御所、里見浩太朗さん演じる須原屋市兵衛は平賀源内(安田顕さん)と親しく交わり、源内が老中の田沼意次(渡辺謙さん)とつながっていて、意次に重用されていることも知っています。また鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)の事件のときには、世間にはわからない武家が絡んだ裏の真相も知っていて、悪者にされた重三郎を安心させてやってました。須原屋市兵衛はこのドラマではどういう人物なのでしょう。さて、それとは別に今回から登場した若木屋与八を演じるのが本宮泰風さんで、ちょっと感激していました。その昔、里見浩太朗さんが主演の『水戸黄門』を見ていた私は、助さん役で本宮さんの実兄の原田龍二さんを長年見ていたので、ホント兄弟そっくりだと。若い頃はマイルドな顔立ちの兄に比べて、本宮さんはやや恐い感じがしました。でも年齢が上がった本宮さん、風格が出てカッコイイですね。今回は女郎屋の主人の役ですが、長身で腕っぷしも強いので、どこかで殺陣や乱闘を見てみたいものです。話がそれてスミマセン。番組ラストの瀬川(小芝風花さん)の花魁道中。白無垢姿はいつになく美しいものでした。昨年の『光る君へ』では平安貴族の雅な美しさを堪能でき、今年はそういったシーンは望めないかなと思ってましたが、今回の小芝風花さんの身請け(嫁入りと同等)のシーンは格別なものでした。またどこかでこんなシーンがあったらなと思ってます。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 妹・種姫との会話から「江戸城に田安の種を撒こう」と思いついた田安賢丸(寺田心さん)は、母・宝蓮院(花總まりさん)と共に江戸城に行き、10代将軍・徳川家治の嫡男の徳川家基(奥智哉さん)を訪ねていました。将棋の盤を囲む家基と賢丸の姿を見て宝蓮院は、賢丸は8代将軍・吉宗公の同じ血を引く者として家基を支えるつもりでいたのに、年の暮れには陸奥に行かなければいけない、家基の傍にはゆくゆくは出自が低いと嫌うあの田沼意次の息子がつくのか、と嘆いていました。知保の方(高梨臨さん)は老中首座の松平武元(石坂浩二さん)にどうにかならぬのかと相談、武元は一つだけ手があると答えました。一方、𠮷原では女郎屋の親父衆が集まって𠮷原細見をどう売りさばこうかなどいろいろ話し合っていて、身請けされる瀬川の最後の花魁道中となる暮れに女郎の錦絵も出すよう、重三郎に命じていました。親父衆は対立する市中の本屋を潰してやりたいと考えているのですが、𠮷原には親父衆とは別の女郎屋の主人の集まりもあり、その主導者の若木屋与八(本宮泰風さん)は親父衆が吉原への出入り禁止とした本屋の一人の西村屋与八(西村まさ彦さん)を密かに引き入れていました。若木屋与八は親父衆が吉原を勝手に仕切っていると反発し、ここの集まりの皆はこれからも市中の本屋たちと付き合っていくと決めました。女郎の錦絵をどうやって出そうかと悩んだ蔦屋重三郎(横浜流星さん)市中に出てあれこれ考えていたら、自分が作ってあの時には飛ぶように売れた細見が一斉に捨てられているのに遭遇しました。市中では対立する𠮷原の本は取り扱わないとなり、さらにそのいきさつ話には尾ひれがついて完全に𠮷原が悪者になっていました。この先どうしたものかと重三郎が悩んでいたら平賀源内とばったり会い、その源内は須原屋市兵衛と待ち合わせしていたので、重三郎は源内と市兵衛と歩きながら本のことで相談を持ち掛けました。源内と市兵衛の用事が済むのを待つ間、重三郎は店の見物をして歩き、そこで役者絵が売られているのが目に留まりました。その絵は今人気の春章の画風に似せた絵でしたが、役者絵には役者のふだんの姿がなぜないのか、重三郎はふと気になりました。そうこうしていると用事を済ませた平賀源内(安田顕さん)と須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)と合流できたので、重三郎は小料理屋で二人に話を聞いてもらいました。市兵衛は、事を収めるなら重三郎が改めに徹すればいい、と言いました。でもそれは重三郎にとって元の木阿弥になるだけだと言うと、話を聞いていた源内が「もう自分のやりたいことをやったら?」と意見しました。重三郎のやりたいこと、それは𠮷原を江戸っ子が憧れる場所にすることでした。𠮷原を一流の遊び場にする、花魁は男にとって高値の花、女郎たちも辛いことより楽しいことが多い、そんな場所にしたいと夢を語りました。そして話の流れから、作った𠮷原の絵を将軍に献上できないか?せめて将軍が目にしたという噂だけでもあれば𠮷原の格が上がる、と考えました。重三郎の夢の話に二人も乗ってきて、源内を通じて老中の田沼意次までは届くので、源内も協力することにしました。重三郎が吉原に戻って女郎の絵本を将軍に献上するという話を親父衆に相談すると、だれもが驚きそんなことはできるわけがないと反対しました。そこを重三郎が、源内を通せば田沼までは届く、将軍に献上したと箔がつけば本は間違いなく売れる、と説明すると親父衆たちもいろいろ気づき始めました。𠮷原の格が上がる、客筋も良くなり落ちる金も増える、豪気な身請けが増える、その絵本を瀬川の最後の花魁道中に合わせて売れば皆が買い求める、という展開が親父衆の頭の中にも描かれ始めました。しかしそのためには上等な本にしなければいけないから百両かかると重三郎が言うと皆は一斉に手の平を返しましたが、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が自分が五十両もつから残りを皆にお願いしろと助け舟を出してくれました。ただしこの金は貸し付けだと言い、重三郎も売ってみせると宣言しました。女郎の絵を描くにあたり重三郎が『一目千本』の時に描いてもらった北尾重政(橋本淳さん)に頼んだら、近所だからと絵師の勝川春章(前野朋哉さん)も一緒に連れてきてくれました。絵本には女郎たちのふだんの姿も載せたい重三郎は、親父衆に許可をもらって二人をあちらこちらに案内していました。*番組HPの【べらぼうナビ】に、北尾重政と勝川春章について載ってます。 ⇒ ⇒ こちら 北尾重政と勝川春章による吉原絵本が完成したので、重三郎は平賀源内の力で老中の田沼意次(渡辺謙さん)に会いに行きました。重三郎が説明を始めると意次は意外にも重三郎のことを覚えていて、同行した駿河屋市右衛門と扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は苦虫を嚙み潰したようでしたが、重三郎は調子にのったいつもの物言いで、意次も愉快そうでした。そして瀬川の話になると意次は、瀬川の道中の話で自分たちも「社参」を見直すきっかけになった、恩を返すと言い、絵本の将軍への献上を快諾してくれました。意次が吉原絵本の献上に参上すると将軍・徳川家治(眞島秀和さん)から想定してなかった話を聞かされました。田安家の種姫を家治の養女にし、いずれは家基の正室にするということでした。先日、田安賢丸の白川行きを無しにするよう嫡男の家基が言いだし、意次を重用する件でも家基は将軍である父を批判、賢丸の件が無理なら種姫をということで、老中首座の松平武元の進言もあり、家治それを受け入れたのでした。これで賢丸は次期将軍の義兄となり、種姫が子を産めば田安家は盤石に。賢丸が江戸城に田安の種を撒いて芽を出させると考えたのはこのことでした。意次の嫡男・意知は、まだ先の話だから案じなくてもと考えましたが、意次はこの話を聞いた者たちは先の明るい田安のほうになびいていく、田沼から人が離れていってしまう、と危機感を持っていました。そしていよいよ瀬川(小芝風花さん)が身請けされて吉原を出ていく日がきて、新しくできた女郎絵本を手に親父衆も準備に取り掛かりました。今日みたいな日に瀬川と会うのは良くないと思った重三郎は、松葉屋の主人の半左衛門に、絵本を瀬川に渡してもらうよう頼みました。でも半左衛門は二人は互いに気持ちにケリをつけていると考え、自分で渡してくればいいと、瀬川に会うことを重三郎に許可しました。これから着ていく白無垢の前でたたずむ瀬川に重三郎は声をかけ、餞別として絵本を瀬川に渡しました。本を開くと自分が載っていることに驚く瀬川。そして頁をめくっていくとそこには女郎の日常が描かれ、ここでこんな楽しい時間もあったのだと気がつき、思わず涙しました。重三郎は吉原を女郎たちが堂々と生きる場所にしたいと夢を語り、そしてその夢は瀬川も同じで二人で見た夢だっただろ?と贈る言葉にしました。安永4年(1775)12月、七つ刻になり、白無垢姿となった瀬川の最後の花魁道中が始まりました。親代わりの松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)といね(水野美紀さん)、瀬川の付き人だった若い女郎や禿が付き添い、仲ノ町通りの端から端まで練り歩いてその美しい姿を披露しました。通りに並ぶ大勢の見物客からは次々と瀬川への掛け声がかかり、その旅立ちを皆が祝福していました。また松の井や常盤木ら数多くの花魁が道中に加わり、道中に花を添えました。大門の前に立つ重三郎を見たとき、瀬川は最後に二人で語り合った吉原への夢と、重三郎がこの夢をずっと追いかけることと、この夢が自分と重三郎をつなぐ唯一のものであることを思い出していました。大門のところで瀬川は吉原の皆に別れを告げ、かすかに微笑み合った重三郎とはそのまますれ違い、門の外で待つ鳥山検校の元に行きました。そして瀬川が門を出て間もなく、重三郎らによる絵本の売り出しが呼び声と太鼓の音で賑やかに始まりました。幼なじみの花魁で、一緒にはなれない運命だったけど、瀬川は自分にとって誰よりも大事な女なんだと気がついた重三郎は、瀬川へのはなむけになるよう精一杯本を売り込み、人々は先を争うように女郎絵本を買い求めました。しかしその喧噪を聞いていた鳥山は、重三郎の声に何かを感じたようでした。そしてこの絵本は市中でも須原屋の市兵衛は取り扱ってくれて、市兵衛の店では人気の本になっていました。
March 12, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第9回~「玉菊燈籠 恋の地獄」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は、話の中心は蔦屋重三郎(横浜流星さん)と瀬川(小芝風花さん)の恋物語でしたが、𠮷原では許されないそれを、他者には知られないように収めた松葉屋の主人・半左衛門(正名僕蔵さん)と女将のいね(水野美紀さん)の手腕に見入ってしまいました。「亀の甲より年の功」でしょうか。もちろん松葉屋としての利益もあったでしょう。でも若い二人が一時の激情に流されて𠮷原の御法度を破って互いに人生を台無しにしないよう、精神的には一番キツイやり方でそれぞれの立場を自覚させ、恋の炎を消してやりました。やり方は鬼かもしれないけど、もし半左衛門といねが若い二人に対して憎さが先立ったら、二人のやりそうなことはお見通しだからわざと逃亡させ、後で捕まえて激しく折檻をしたでしょう。でもそれはせず、それぞれに現実を思い知らせ、二人に考えさせたのです。またちょうどというか、うつせみの逃亡が先にあったので、二人が考えを改める要因にもなったのですが。甘いゆるいことを言っていたら統制がとれない𠮷原の世界では「忘八」にならざるを得ないと女郎屋の主人たちですが、幼い頃から見守ってきた重三郎と瀬川は、やはり情がわく部分があるのでしょう。親のいない女たちや男たちの親代わりなのでしょうね。*上記番組HPの【べらぼうナビ】に「玉菊燈籠」と「通行切手」についての説明があります。 ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 先日、いつものお稲荷さまのところで瀬川(小芝風花さん)となんとも歯切れの悪い別れ方をした蔦屋重三郎(横浜流星さん)。ある日、小田新之助(井之脇海さん)が茶屋に来て自分と互いに思い合う女郎・うつせみのことについて重三郎に話をしていました。その時、瀬川が花魁道中で現れたのでその行方を追っていくと、盲の客の鳥山検校(市原隼人さん)を出迎えて座敷に案内するところでした。瀬川が客の鳥山と触れ合うのは花魁としてふつうのことなのに、今日の重三郎はそれを目の当たりにしたときに今までとは違う複雑な思いがしました。重三郎は製本の仕事をしようと思ってもなぜか瀬川のことが頭をよぎって全く身に入らず、眠れぬ夜を過ごしていました。翌朝、女郎屋の親父衆のところに打ち合わせに行ったとき、重三郎は瀬川に鳥山から身請けの話が出ていることを知りました。そう聞いて気持ちが乱れた重三郎は、その場は笑ってごまかして出直すことに。店に戻ったら新之助がいて、重三郎に相談があるとのことで外に出ました。新之助は自分のために辛い思いに耐えているうつせみを身請けしたいと思ったのですが、重三郎からその額を300両と聞いて自分には無理だと悟りました。新之助は「金のない男の懸想は花魁にとって幸せになる邪魔でしかない」と言い、重三郎もそれに相槌を打つしかありませんでした。瀬川は重三郎にとって幼なじみの花魁で今まではただそれだけだったのだけど、瀬川が身請けされると聞き、重三郎はこのまま瀬川が吉原から去ってしまうのに耐えられなくなりました。重三郎は瀬川をいつものお稲荷さまに呼び出し、はじめは照れ隠しで仕事の話と鳥山を卑下することで瀬川を引き留めようとしました。でも瀬川から私を利用するなと怒られて、重三郎はようやく「行かないでくれ。俺がお前を幸せにしたい。」と己の本心を打ち明けました。重三郎は瀬川の年季明けには請け出すと言い、重三郎の自分への気持ちに嘘がないとわかった瀬川は重三郎に心変わりをしないことを約束させました。互いに思い合っていることを確信できた二人は心から笑い合いました。重三郎と一緒になるために𠮷原に残る決心をした瀬川は花魁の特権を使って、松葉屋の主人の半左衛門(正名僕蔵さん)と女将のいね(水野美紀さん)に、鳥山からの身請けを断りたいと申し出ました。しかし話は身請け証文にまで進んでいて、今さら断れないといねは激怒です。半左衛門が穏やかにその理由を尋ねると、瀬川は用意してあった理由をよどみなく語り、いねは「よ~くわかったよ」と嫌味っぽくその場は認めました。いねは瀬川にマブができた、相手は重三郎だと見抜いていて「正面きっての掟破りだ。バキバキに折檻してやる。」と厳しい表情になりました。そしてまさを呼び、瀬川の行動を監視するよう命じました。まさの尾行に感づいた瀬川は、当分は会わないよう重三郎に伝えました。二人は周囲を欺き続け、また鳥山が来ても瀬川は座敷に出なくなりました。いねが鳥山に瀬川はひどい風邪で来られないと伝えると鳥山はその嘘を感じ、自分は振られたのかとつぶやきました。破格の条件を示す鳥山を絶対に逃がしたくない半左衛門といねは、なんとかその場を取り繕うのに必死でした。重三郎の主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は、もしかしたらこの件に重三郎が絡んでいるのではと思い半左衛門に訊ねました。半左衛門は否定はせずに、でも大ごとにならぬよう、まだうちに任せてくれと言って出ていきました。鳥山に限らずこの先だれが身請け話を持ってきても瀬川は断る、と見抜いているいねは、二人をあきらめさせるのにはあの方法しかないと決めました。いねはまず瀬川に次から次へと客を取らせました。瀬川の襲名披露や瀬川になってからの着物や調度品に恐ろしく金がかかった、身請けを断ったからにはガンガン稼いでもらう、瀬川のためならいくらでも金を出す客がいる、外に出ないよう離れで客を取ればいい、と。過酷ないねのやり方に瀬川は、先代の悲劇をもう一度繰り返すのかと言ったのですが、いねは先代の瀬川が可哀想だなんて毛筋も思ってないと言います。さらに「あれは松葉屋の大名跡を潰してくれた迷惑千万な馬鹿女。」とまで言い、瀬川に仕事を言い渡して出ていきました。一方、半左衛門は瀬川と3人で話をするからと重三郎を呼びつけていました。重三郎が松葉屋に来ると離れの座敷に案内され、障子の向こうで人の声がするので昼見世だとは思ったのですが、半左衛門がわざと障子を少し開けた向こうにいたのは、客を取っている最中の瀬川でした。好きな男にはこの姿は見られたくなかった瀬川、惚れた女のおつとめの姿は見たくなかった重三郎。半左衛門はお前らのことはわかっているとばかりに、重三郎に畳みかけます。「これが瀬川のつとめ。年に2日の休みを除いては。お前はこれを瀬川に年季明けまでずっとやらせるのか?」そして半左衛門は重三郎の肩をポンと叩き、「今、お前にできるのは何もしないってことだけだ。」と諭すように念押ししました。重三郎は何も言い返すことができず、ただ立ち去るのみでした。重三郎がやりきれぬ気持ちを抱えて茶屋に戻ると新之助が来ていて、連れの女に玉菊燈籠を見せてやりたいらしく重三郎に通行切手を求めました。その夜、重三郎は通行切手があれば瀬川と二人で𠮷原から逃げられるとふと思いつき、ニセの通行切手を作って瀬川に渡す本にはさみました。しかし重三郎が思い描いていた逃亡を、その夜に新之助とうつせみがすでに実行し、二人は少しでも遠くにと急ぎ逃げていきました。翌日、重三郎が松葉屋に貸本を勧めに行ったとき、ちょうど瀬川が出てきたので重三郎は声をかけ、通行切手を挟んだ本を瀬川に渡しました。本に挟まれた物を見て瀬川が驚いていると、女将のいねがうつせみの名を叫びながら出てきました。うつせみがここにもいないとわかるといねは足抜け(逃亡)だと断定して、男衆にすぐに追うよう命じました。夜通し逃げた新之助とうつせみ(小野花梨さん)でしたが、二人とも追っ手にすぐに捕まってしまいました。𠮷原に連れ戻されていねに折檻されるうつせみは、ただ幸せになりたくてと自分の思いを訴えましたが、いねに一蹴されました。「幸せ?こんなやり方でなれるわけないだろ。追われる身になってどこに住むのか。人別(戸籍みたいなもの)や食い扶持はどうするのか。仕事がなくて男は博打、女は夜鷹、ろくな暮らしができなくて、それが幸せか?!」重三郎から足抜けを提案されている瀬川は、いねのうつせみへの言葉を殊の外、重く受け止めていました。一方、重三郎は新之助から「自分が弱くて、己の不甲斐なさに耐えられず、うつせみに逃げようと誘った。」と聞かされ、自分を振り返っていました。そしてどんなに思い合っていたとしても、自分たちが一緒になろうとすると互いに不幸になるだけで幸せはないのだと、重三郎と瀬川はそれぞれに思うようになりました。瀬川は女将のいねに、先代の瀬川のことを訊ねました。「あの妓があんな死に方をしなければ、きっと何人もの女郎が瀬川になって、豪儀な身請けを決めて大門を出ていった。あの妓のせいで女郎たちは瀬川になれなくなり松葉屋は身代金を失った。だからあんたが瀬川を幸運の名跡にしたいと言ったときは嬉しかった。これでみんな救われると。」いねは瀬川を諭すようにさらに続けました。「𠮷原は不幸なところだけど、人生をがらりと変えるようなことが起きないわけじゃない。そういう背中を女郎に見せる務めが瀬川にはあるのでは?」重三郎と瀬川はそれぞれに、もう自分たちが一緒になるのは無理であると悟り、瀬川は他の女郎たちのためにもと鳥山からの身請け話を決めました。瀬川は重三郎から渡された本にあったニセの通行切手を破って密かに返し、そして馬鹿らしいけど夢を見て面白かった、とびきりの思い出になったと、本の感想を言うふりをして礼を言い、重三郎も瀬川の意思を悟りました。程なくして瀬川の身請けが身代金1400両で正式に決まりました。(女郎にとって身請けは嫁入りと同じなのですね。婚礼の白無垢を用意し、身代金は結納として納め、部屋の主人と女将は親代わりとして正装をして挨拶をするのですね。)
March 5, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第8回~「逆襲の『金々先生』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は随所で、横浜流星さん演じる主人公・蔦屋重三郎の、花の井改め瀬川(小芝風花さん)への本人も意識していない思いを感じた回でした。 瀬川の方は重三郎への思いを、ストレートには絶対言わないけど、それらしい言葉は出ていて、重三郎が気がつかないだけで平賀源内(安田顕さん)のようにちゃんと察している人もいます。でも重三郎は自分じゃわかっていないけど、彼の場合ちゃんと行動に出ているんですよね。例えば同じように辛い思いをしている女郎をなんとかしてやりたいと思った時、他の女郎たちにはまず頭で、つまり理性で打開策を考えます。でも松葉屋で瀬川が大変な思いをしていると知った時、重三郎は考えることなくとっさに感情的に言葉が出て身体が動きました。松葉屋の人たちは、今日の重三郎は何か変だとか、あるいは薄々気がついているかもしれませんが。あと鳥山検校(市原隼人さん)という、実に興味深い人物が出てきました。彼は盲の特権を活かして資産形成では大成功しました。そして苦労人ゆえの気配りか、あるいは目が見えないことでの自分への卑下か、自分のせいで瀬川が退屈をしないようにと女性が喜ぶプレゼントを持参します。物腰も柔らかく、花魁に対して敬語で接します。そんな鳥山の優しさに瀬川は「声」で応えました。鳥山にとっては、自分流の心遣いを瀬川がただ喜んでくれたらいいと期待してなかっただろうけど、それが思いがけないお返しがだったと思います。これは瀬川の優しさに、惚れちゃいましたね。さて、今回の中に出てきた小道具についての書き込みがあったので、ご紹介します。*【印刷博物館】~当館が所蔵しているのは復刻版となりますが、『金々先生榮花夢 上・下』をご紹介します。 ⇒ ⇒ こちら *【#大河べらぼう 公式】~『女重宝記』とは ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 地本問屋への仲間入りを賭けて蔦屋重三郎(横浜流星さん)が挑んだ𠮷原細見の「籬の花」の販売は、重三郎の狙いどおり飛ぶように売れていきました。そして重三郎の問屋仲間入りをなんとかして阻止したい西村屋与八は自分たちも「新𠮷原細見」と称する本を出して、町で華々しく宣伝していました。するとそこへ重三郎たちが鳴り物入りで賑やかにやってきて、人々に西村屋の細見を模した箱を見せたかと思うとそれを西村屋の前で二つに割り、自分たちの細見を模したものを大々的に宣伝しました。さらに「瀬川襲名」のことも強調し、町の人々はこぞって重三郎のを求めました。(このシーン、最初は重三郎もわざわざ西村屋の怒りを買うこともないのに、と思ったけど、重三郎は先にこの人に嵌められているから、まあ仕方ないですね。)重三郎が出した細見「籬の花」は人々の評判も良く2倍以上の売れ行きとなり、𠮷原は押し寄せる人々で大賑わいとなりました。𠮷原に来た人々は五代目・瀬川(花の井 改め;小芝風花さん)を一目見ようと花魁道中に押し寄せ、その姿に酔いました。また重三郎は駿河屋の軒先に本屋の屋号として「耕書堂」の名を掲げ、𠮷原の女郎屋の親父衆たちからも本屋の主として認めてもらえました。親父衆も重三郎が一人前となったことを喜んでくれました。その賑わう𠮷原に、やはり“瀬川”のことが気になった平賀源内(安田顕さん)が小田新之助(井之脇海さん)を伴って来ていました。重三郎は瀬川は花の井が襲名したと二人に明かし、源内が会えるよう手配しようとしたのですが、あいにく瀬川は大忙し。うつせみは新之助に会いたがっていましたが、やはり忙しくて落ち着かないのでまた今度となりました。こんなにも𠮷原の町が賑わうのは花の井が瀬川を背負ってくれたからで、自分の作った細見の力ではない、花の井には深く感謝している、どうすれば花の井に報いることができるか、と重三郎は源内に思いを語りました。瀬川が本心は重三郎が好きなんだとわかっている源内は、重三郎に瀬川を身請けしろと言いますが、瀬川の身請け金などとても払えるものではありません。さらに𠮷原の男は女郎には絶対に手を出してはいけないと叩き込まれていると重三郎が説明をすると、瀬川の気持ちを思う源内は虚しさを感じました。さて田沼意次(渡辺謙さん)の方ですが、こちらはしきたりがうるさく無駄な金もかかる社参の支度に追われていて、気分がすぐれませんでした。すると源内が、吉原で瀬川襲名があってその花魁道中を一目見ようと人々が大勢集まり吉原が繁盛している、不躾ながら将軍の道中も民草にはよい見物なのでは?と意次に進言しました。意次がすぐに「社参を見世物にして金を得る場にせよと?」と気がついたので、源内は続けて「これを機に宿場の商いを盛り立てるのはたやすい。かつその銭の出入りを上手く使えば二朱銀への置き換えも進められる。」と進言しました。今まで苦々しく思っていた社参が、逆に経済の発展に利用できるのだと理解した意次は何かを考え始めました。重三郎が松葉屋に本を持っていったとき、ただでさえ忙しい瀬川が面倒な客のために疲れてまだ寝ていると聞き、重三郎は思わず主人の松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)や女将に、そんな客をつけないよう文句を言ってしまいました。それを聞いた松の井(久保田紗友さん)が頭にきて、ならば自分たちなら面倒な客でもいいのか、と重三郎に食ってかかりました。うつせみが二人の間に入って止めましたが、重三郎はその時うつせみの首に変なあざができていることに気が付きました。さらに松の井からは、瀬川を求める客が多過ぎて自分たちだって代わりに相手をしているから大変なんだ、ということも聞かされました。さて牢から解き放ちとなった鱗形屋孫兵衛ですが、鶴屋喜右衛門の助けを借りて起死回生を図っていました。その孫兵衛は、実は須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)の力によって家に戻れたわけで、孫兵衛は重版で手を組んでいた役人に裏切られた、孫兵衛が捕まったのは自分のせいではなかった、須原屋も重三郎を疑ってはいない、ということを重三郎は須原屋の口から聞いて安堵しました。そして重三郎は、ある女郎に本を送りたいから市兵衛に本の相談に乗って欲しいと今日ここに来た理由を話しました。連日連日休む暇なく客が来る瀬川の今宵の客は盲の鳥山検校(市原隼人さん)。盲の頂点に立つ鳥山は大金持ちで下っ端の盲と違って品も良く、初回のこの日は高価なかんざしや鏡と世間で評判の本などを瀬川に土産に持ってきていました。初回の花魁は話もできず瀬川も退屈だろうから、盲の自分に構わず皆で楽しむがよいと鳥山は言い、その心遣いにいね(水野美紀さん)は深く礼を述べました。座敷の皆が喜ぶその光景を見て瀬川が鳥山に声をかけ、自分が本を1冊読もうかと提案、鳥山はそれは吉原のしきたりを破ると遠慮しましたが瀬川は、花魁の姿の代わりに声を楽しんでもらいたいと言い、いねも特別にそれを認めました。瀬川は本の中から『金々先生榮花夢』を選んで鳥山のために読み、鳥山も瀬川の声に聞き入っていました。(鳥山の優しさに、瀬川も優しさで応えたのですね。)重三郎が茶屋に戻ると義兄の次郎兵衛が『金々先生榮花夢』の本を面白がって読んでいたので、重三郎は実はその内容の一部は自分が以前、鱗形屋に出したネタであり、それを鱗形屋が本にしていることを伝えました。自分のネタだけど鱗形屋が面白い本に仕立てていることは重三郎も認めざるを得ないし、鱗形屋のこの本が世間の評判を呼んでいることで重三郎の問屋の仲間入りがどうなるのかを次郎兵衛も案じていました。翌朝、重三郎は瀬川をお稲荷さまに呼び出しました。瀬川はこの本は面白いと感想を述べ、同時に重三郎のことを案じました。でも重三郎は、実はこの先のことをすでに親父衆に相談してあり、計算高い親父衆は自分の味方になってくれていることを瀬川に伝えました。今まで瀬川が何かと助けてくれたから親父衆も協力してくれるようになった、と重三郎は改めて瀬川に礼を言い、1冊の本を手渡しました。それは『女重宝記』という本で、瀬川が名のある人に身請けされた時に世間の常識や考えを知らなくて苦労しないように、という重三郎の思いからでした。重三郎は自分が身請けされて幸せになることを願ってくれていると感じつつ、瀬川は自分が重三郎にとって特別な存在ではなくここにいる女郎たちの一人にすぎないのだと感じて、寂しさと悲しさをごまかして去っていきました。瀬川の気持ちを量りかねた重三郎はお稲荷さまに独り言(=相談)したけど、この時はまだ自分の気持ちにも気がついていませんでした。夏になり、重三郎が店番をしていたら鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が来て、互いに思うところを抱えながら挨拶を交わしました。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)ら地本問屋の仲間6人で𠮷原に来て、突然話し合う場が設けられました。切れ者の喜右衛門が問屋を代表して話し、その内容は孫兵衛が持ち直したので重三郎の地本問屋の仲間入りを断るというものでした。重三郎が自分が出す本は吉原に関わる物だけで皆さんの商売の邪魔はしない、細見もこちらで作ってタダで譲る、だから仲間にと訴えました。それならばと何人かの問屋が考えを変えようとしたら、喜右衛門は話の流れを断ち切り、自分だけで話すからと仲間の皆を退室させました。そして「卑しい外道の𠮷原者」は市中の問屋の仲間にはしたくないという人も何人かいるなど、親父衆の誰が何を言っても喜右衛門はその度に言葉を返して聞き入れませんでした。重三郎は自分たちを毛嫌いする人たちと話し合いをさせて欲しいと訴えました。しかし喜右衛門は「𠮷原の方々とは同じ座敷にもいたくない。」とのことだと言い、その言いぐさに親父衆は皆いよいよ我慢ならなくなりました。その時、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が急に笑いだし立ち上がったかと思うと喜右衛門の傍に立ったので、喜右衛門も笑い返したら・・・!!市右衛門は喜右衛門の首根っこを掴んで力ずくで座敷から引きずり出そうと障子に向かいました。重三郎は他所の人だと市右衛門を止めたのですが大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)は重三郎を押しのけ、障子を開けて市右衛門に道をつくりました。市右衛門は勢いのまま障子の向こうにある階段から喜右衛門を落としました。喜右衛門は階段の下で待っていた問屋仲間のところに転げ落ちていきました。階下から親父衆を見上げる喜右衛門たちに、親父衆は口々に言いました。「俺だってあんたらと同じ座敷にいたくない。」「あんたら出入り禁止な。」「あんたらはもう𠮷原の本は作れない。重三郎しか作れないね。」「黙って大門くぐったら・・。」、最後は扇屋宇右衛門(山路和弘さん)から「二度と出ていけなくなりますからね。」と念押しされ「覚悟しろや、この赤子面!」と市右衛門にダメ押しされました。自分の味方になってくれた頼もしい親父衆でしたが、地本問屋たちとは激しい対立となってしまい、重三郎もこの先のことが少し心配になってきました。
February 27, 2025
-
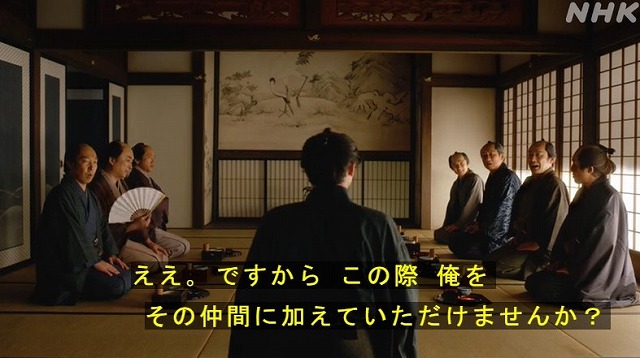
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第7回~「好機到来『籬(まがき)の花』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、私が印象に残ったのは、横浜流星さん演じる蔦屋重三郎という人物の物事の捉え方です。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)が役人に捕まったとき、重三郎は自分が知ってて知らせなかったからと、自分が孫兵衛を嵌めたんだと考えました。でもその前に重三郎は、『雛形若菜』の事では世の中の仕組みを知らなかったが故に、あるいは誰からも教えてもらえなかったが故に、孫兵衛たちに嵌められています。逆に孫兵衛は、自分が重三郎にしたことを棚に上げて、重三郎を逆恨みしています。このあたりの個々の性格というか物事の捉え方というか、「自分の無知は反省するけど他を恨まず、そしてまずは行動」というのは、重三郎のように将来、大人物になる人に備わった天与の才なのでしょうか。そしてもう一つ印象に残ったのは、ドラマの中に所々に出てきた女郎たちの恋心です。かをり(稲垣来泉さん)のように重三郎にストレートに好きだという気持ちをぶつける女もいれば、男に身体を売って生きるしかない自分は男を選べない、好いた男がいてもどうしようもないと思う女もいるでしょう。でも本音はやっぱり好いた男と結ばれたい、かをりのような小童なら最初の男はーー。そんな女たちの心の底の思いを重三郎はわかっていて、だから余計に、他者のために動く重三郎は、女たちが男を選べるほど𠮷原を盛り上げたい、という行動力につながっているのでしょうか。ところで、中村蒼さんさん演じる次郎兵衛義兄さん。こういう人、いるんですよね。仕事はあまりできないし好きじゃないけど、仕事ではない部分の人の行動はよく見ていて、経験値も含めてその人の心がなんとなく読めて、先々起こりうる事の予測ができる人が。義兄さんが「危ない」と言ったかをり、この先何かやらかしそうです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 地本問屋の鱗形屋孫兵衛が不正を働いて奉行所に捕らえられたため、孫兵衛が手掛けていた𠮷原細見をどうするか、会所で話し合いが行われていました。そこへ蔦屋重三郎(横浜流星さん)が突如現れ、これからは自分が版元となって細見を出す、自分もこの地本問屋の仲間にして欲しい、と主張しました。もちろん問屋仲間の主たちは一斉に大反対でしたが、それでも重三郎は、自分に任せてくれたら今までの「倍」売れる細見を作ってみせる、そうすればここの皆だって儲かる、と大見栄を切りました。鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は、重三郎がそこまで言うのなら倍売れるという細見を作って見せて欲しい、そして本当に倍売れたらその時はここの仲間として迎えると言い、重三郎はその条件を了承して退室していきました。𠮷原に戻った重三郎は、細見が倍売れたら地本問屋の仲間入りができるから、女郎屋の主人たちにも細見を倍、買い取って欲しいと頼みました。主人たちは案の定いい顔はしないのですが、重三郎は𠮷原が自前の本屋を持てることの利を主人たちに説明しました。これが𠮷原を売り込む手段になると理解した主人たちは重三郎の考えに賛同し、重三郎は意気揚々と会合の店を出ていきました。そんな重三郎の背中を見つめる主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)はどこか物憂げで、その理由を扇屋宇右衛門(山路和弘さん)は問いました。「市中のやつらの話を真に受けていいものか」と市右衛門は心配だったのです。その頃、西村屋の与八は重三郎の思い通りにはさせまいと、孫兵衛が牢にいる間に鱗形屋に行って細見の版木を手に入れようとしました。孫兵衛の妻のりんは固辞しましたが与八は金を積んでしつこく食い下がるので、りんも一瞬は心が動きかけました。でもその時、奥から次男の万次郎が出てきて与八と対面し、これは父でないと決められないときっぱりと断りました。一方、重三郎は鱗形屋の一件でのすっきりしない胸の内を、義兄の次郎兵衛と蕎麦屋の半次郎に聞いてもらってました。その後で重三郎は、細見を倍売りたい、そのためには細見を作る費用を半値にして、もっといい物にして半値で売りたい、と二人に協力を頼みました。そこでまず、どういう細見なら買うかを調べるために三人で聞き回りました。二文字屋のきく(かたせ梨乃さん)にも協力してもらい、人々の意見を調査して回りました。人々の意見から重三郎は、細見にあるのは大見世の女郎ばかりで巷の男が買える女郎が載っていない、ということに気が付きました。そんな話をしつつ次郎兵衛(中村蒼さん)と半次郎(六平直政さん)と歩いていたら、かをり(大文字屋の秘蔵っ子、まだ小童;稲垣来泉さん)が重三郎の背中に飛びついてきました。「細見を持ってきた客が男前だったらタダにしては?」と意見を言いながら、かをりは重三郎が好きなのでしがみついて離れません。女将の志げが飛んできてかをりをきつく叱り(脅し)、ようやく重三郎から離れたので志げはかをりを連れて帰りました。その様子を見た次郎兵衛は「あいつは危ない」と直感しました。(仕事ではまあ頼りにならない義兄さんだけど、こういう勘は鋭いと思います)重三郎たちが店に戻ると小田新之助(井之脇海さん)が来ていました。新之助は今日はうつせみに会いに来たのではなく、重三郎が相談した細見の工夫のことで意見を述べに来てくれたのでした。新之助が細見を薄くすると持ち歩きやすいと提案すると、重三郎はこれなら経費も半分にできるからうまくいくと考え、新之助にも助力を頼みました。そこでまずは、今ある細見を分解して見直し、不要な項目を省いて並べ方や見せ方も工夫してみることにしました。重三郎が地本問屋に仲間入りするのをどうにかして阻止したい西村屋の与八は、細見を出していたもう一人の男・小泉忠五郎と手を組みました。そして与八は忠五郎を連れて𠮷原を訪ね、重三郎の細見を買った店の女郎は『雛形若菜』には使わないことを伝え、吉原に脅しをかけてきました。与八の脅しに屈しようとした親父衆に重三郎は我慢がならなくなりました。「与八は自分が楽して儲けることしか考えていない。女郎たちが体を痛めて稼ぎ出した金が奴らに流れるなんて許せない。女郎の血と涙が滲んだ金で絵や細見や作って女郎に客が群がるようにしてやりたい。女郎にも誇りを持たせてやりたい。」と力強く言い、そして落ち着いた声でさらに続けました。「それが女の股で飯食ってる腐れ外道の忘八の、たった一つの心意気。だから他所に任せてはいけない。吉原自前の本屋が要る。今はその二度とない機会。」と親父衆の心に訴えるように言い、正座して姿勢を改めて「つまらない脅しに負けないで共に戦って欲しい。」と皆に深々と頭を下げました。西村屋に負けたくないこともあるけど、何より吉原の女たち全てを大事に思う重三郎は大見世だけでなく、半値の細見なら買うような男が行けるような安い見世、果ては河岸見世まで吉原の全てを細見に盛り込みたいと考えました。清書を担当する新之助は細かい字を紙にびっしりと何回も何回もと書いているのですが、重三郎が小さな見世まで足を運んで聞き取りをしてくるたびに再び清書の書き直しを頼まれていました。思わずため息が出るけど、新之助は我慢して重三郎に付き合ってやっていました。とはいえ、いくら性格が穏やかで優しい新之助はでも、こうも毎度毎度ちょっとずつのために細かい字びっしりの紙を書き直しをさせられたら、さすがに疲労と我慢が限界になることもあります。一緒にいるのに何を手伝っているのかわからない次郎兵衛は、新之助に怒られていました。また彫師の四五六(肥後克広さん)も、この細か過ぎる字を彫るためにイライラから思わず大声が出て、怒りでノミを飛ばしてました。松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)が重三郎の訴えに感動し、でも今は重三郎の分が悪いという話を妻のいね(水野美紀さん)にしていたら、花魁の花の井(小芝風花さん)がたまたまた耳にしてしまったので、半左衛門は花の井に自分たちも一緒に何か考えよう、と声をかけてくれました。三人で過去の細見を見直して考えていると、いねがふと気がつきました。「細見がバカ売れするのは、名跡の襲名が決まった時さ!」そう言われて半左衛門も思い出しました。「売れた!売れてたよ。染衣が四代目の瀬川が名跡を継いだ時も!」二人の話を聞いた花の井は、何かを決意しました。版木が彫り上がったので、その後はかつて重三郎が窮地を救った「二文字屋」で女郎たちが総動員して手伝い、製本の作業が進められました。そしてどうにか細見が完成し、重三郎はお稲荷さまに本を供えて祈ってました。するとそこに幼なじみの花魁の花の井が来て、うちで女郎の入れ替えがあった、また細見を修正して欲しいと重三郎に紙を差し出しました。重三郎は製本して綴じた後なのにと落胆しましたが、その紙を見るとそこには「花の井改め 瀬川」と書かれていました。そう、花の井は名跡襲名の時は細見が売れるからと、自分が「瀬川」を継いで世の関心を引き、重三郎を助ける決意をしたのでした。ただ瀬川の名は過去に不吉なことがあり、重三郎は心配しました。でも花の井は、自分は自害はしない、自分が豪気な身請けを決めて瀬川をもう一度幸運の名跡にする、と言い切りお稲荷さまに祈りました。𠮷原をなんとか盛り上げたい、それは花の井も同じ気持ちでした。さていよいよ約束の日、地本問屋の皆が集まる中で西村屋与八(西村まさ彦さん)は美しい表紙に白い和紙の覆いをつけた上等な仕立ての細見を披露し、これなら重三郎が敵うわけないと自信満々でした。そして重三郎が大きな行李を背負ってやって来て、どこか自信有り気に皆の前に差し出した細見は、安っぽい表紙に薄っぺらい本でした。皆が嘲笑する中で鶴屋喜右衛門が中を改めると、𠮷原を安見世まで書かれた小さな文字がびっしりと並ぶもので、本の見せ方にも工夫がありました。そして松葉屋の頁を見るとそこには「瀬川」の名があり、一同は驚きました。重三郎は「今回の瀬川のことは𠮷原の外にいる人にはわからなかったこと」と得意げに言い、さらに「この細見を従来の半値で売って欲しい。半値なら巷のありふれた男たちも買うだろう。瀬川の名が載る祝儀の細見を。」と力強く売り込みをかけました。すると重三郎の細見はたちどころに飛ぶように売れていきました。しかし喜右衛門は、まだ何か考えているようでした。
February 20, 2025
-
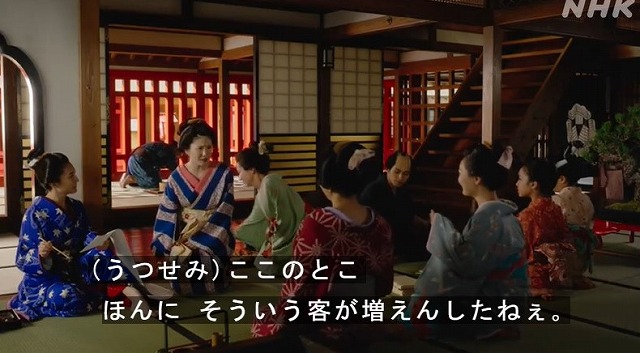
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第6回~「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回のメインの話は一言で言えば “天罰” でしょうか。鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)は知識のなかった蔦屋重三郎(横浜流星さん)を陥れ、その後もさんざん彼を利用してきました。重三郎はというと、ある事で自分が孫兵衛に利用されていることを知って強い怒りを覚えるのですが、それでも孫兵衛の今後は運を天に任せようと決めました。そして思いがけない形で孫兵衛の悪事がバレて奉行所に連行されていくという天罰が下りました。重三郎は自分の願望を心に思い描いただけで本当に何もしなかったのですが、それでも心が少し痛みました。そんな重三郎を元気づけてくれた長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)は、実は重三郎と花魁の花の井に乗せられて全財産を𠮷原でばらまいているのに、いい人ですよね。一方、田沼意次(渡辺謙さん)は幕府の財政立て直しのために周囲から嫌味を言われながらも必死に頑張っているのですが、出自が低いことを事あるごとに松平武元(石坂浩二さん)ら名家の出の者たちから嘲笑されます。それでもぐっと堪えて頭を下げて相手を持ち上げ、老中としての仕事を進めていきます。田沼意次と言えば高校の教科書の中では「株仲間、新田開発、蝦夷地との交易」といったキーワードが出てくるので、経済に長けた人だったのでしょう。でも教科書には書かれない、身分社会の中で出自の低さ故の苦労は数知れずあったのだろうと、このドラマを通じて感じています。*番組HPに用語解説が出ています べらぼうナビ「御書院番士」 ⇒ ⇒ こちら * RekiShock(レキショック)先生作成の資料です鱗形屋の偽板が発覚した頃(1775年頃)登場人物の年齢(満年齢) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 鱗形屋お抱えの改となった蔦屋重三郎(横浜流星さん)は吉原細見を改良するために、女郎たちからネタになる話を集めていました。流行に乗って「キンキン」で決めたものの慣れない𠮷原通いで男たちが失敗をする様などを聞いていましたが、幼なじみの花魁の花の井からは「本がつまらない」と意見されていました。そんな時、花魁の一人のうつせみ(小野花梨さん)から、市中に出るなら小田新之助に渡して欲しいと文を託されました。その文には「揚代は自分が払うから𠮷原に来て欲しい」とあり、新之助を慕ううつせみの思いがしたためられていました。鱗形屋に来ていた重三郎は主人の孫兵衛から、何か大当たりするようなものが欲しいと言われましたが、そう簡単にはいきません。そんな重三郎たちのやり取りを隣の部屋で手習いをしながら聞いていた次男の万次郎が「地本は当たってこそだから」と言いました。重三郎が万次郎の手習いを覗くとずいぶんと難しい字を書いていて、万次郎は大きくなったら地本問屋じゃなくて儲かる書物問屋になりたいと言いました。そして「物之本」は地本に比べてものすごい高値で売れるし割よく儲かると父・孫兵衛が言ってたということでした。重三郎はその後で藤八(徳井優さん)と話をし、刷り損じの紙を紙くず買いに出さずに厠の紙に使っていることを知りました。さらに明和の大火(1772)のときに蔵も店も焼けて大損害を被り今も経営が厳しい、重三郎の働きを期待している、と藤八は言いました。さてそのころ江戸から遠く離れた尾張の熱田(現在の名古屋市)では、上方の版元の柏原屋与左衛門(川畑泰史さん)が「早引節用集」の古本を手に取り、店の主人にこれを誰が売っていったのかを訊いていました。売ったのは武士でしたが、与左衛門は裏表紙にある「版元 丸屋源六」という聞き覚えのない名前に怪しんでいました。一方、鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)は小島松平家の家老・斎藤茂右衛門(藤本康文さん)から注文を受けたものを届けていました。その中には内密で頼まれた鈴木春信(1770没)が描いた春画の『風流艶色真似ゑもん』もあり、なかなか手に入らない本だったので家老の茂右衛門はこれなら先方も喜ぶと大満足でした。さらに茂右衛門は小声で孫兵衛に「例のアレを倍、頼みたい。当家のような小身の大名にはアレがまことに有難い実入りとなる」と耳打ちし、孫兵衛も近いうちに持ってくると承知していました。ところが孫兵衛たちが帰った後、茂右衛門は家臣から例のアレのことで何か重要な報告を受けたようでした。孫兵衛から派手に当たる何かを考えろと言われた重三郎でしたが、いい考えが一向に浮かばず蕎麦屋の半兵衛や義兄の治郎兵衛に相談していました。治郎兵衛が青本はつまらないと言ったことから重三郎は何か思いつき、翌朝すぐに鱗形屋に向かいました。店に入ると藤八が柱にもたれて寝ているだけで誰もいず、でも奥から版木を摺る音が聞こえてくるので、重三郎はその部屋まで行きました。重三郎が元気よく挨拶をして障子を開けると、中にいた人たちが一斉に慌てて何かを隠すような仕草をし、孫兵衛が慌てて出てきました。孫兵衛は重三郎を別の部屋に連れていって話を聞きました。重三郎は鱗形屋が以前出した青本は評判が悪いから、今の時代に合った面白いものを作り直してはどうかと提案、孫兵衛もそれを受け入れました。さて江戸城内では、田沼意次(渡辺謙さん)は勘定吟味役から御金蔵の金が明和大火の前までの状態に持ち直したと収支上告を受けていました。するといつも意次を見下している老中首座の松平武元(石坂浩二さん)がどういうわけか意次の成果を褒めたたえています。実はそれには目的があって武元は「日光社参」を執り行いたいと言うのですが、徳川家・旗本・諸大名が連なる参詣には莫大な費用がかかるものでした。あの手この手でやっと幕府の財政が立て直せた意次は参詣などやりたくないのですが、武元たちは将軍に取り次ぐようご丁寧に低頭までするので、意次は将軍に社参の話をせざるを得ませんでした。重三郎は孫兵衛と、どうやって青本を作るかで話が盛り上がっていました。その後、須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)の店の前を通りがかったとき、店の者がものすごく不機嫌に塩を叩きつけていました。どうしたのかと重三郎が市兵衛にが訊ねると、偽版が出回っている、この本はこの店が作ったのではないかと大坂の柏原屋という本屋が言ってきた、ということで店の者は怒っていたのでした。その話を聞いた重三郎はふと鱗形屋で万次郎が言ってたことを思い出し、もし出版した者が見つかったらどうなるのかと市兵衛に訊ねたら、柏原屋は役人に訴え出るだろう、ということでした。重三郎は鱗形屋で見聞きしたさまざまな状況から、この偽版は孫兵衛だと推察、役人に訴え出れば自分が取って変われる、でも告げ口は嫌だからどうしようかと自問自答していました。でも何もわからないままでは先に進めないから、確かめることにしました。重三郎は鱗形屋に行き、厠を借りるふりをして摺り損じの紙を見て、偽版を出版しているのが孫兵衛だと確認しました。そして戻ろうとした時に通りがかった部屋から話声が聞こえ、声の主は西村屋与八と孫兵衛で、重三郎は「雛形若菜」の件では自分はこの二人に嵌められて、今もなお利用されているのだとわかりました。怒りと悔しさでいっぱいになった重三郎は店を出た足で須原屋を訪ね市兵衛に話を聞いてもらおうとしましたが、この時は結局何も言えずじまいでした。夜、いつものお稲荷様のところでこの件をどうしようかあれこれ悩んだけど、告発は自分の性に合わないと考え、鱗形屋がこの先どうなるかはもう運を天に任せることにしました。意次は将軍・徳川家治(眞島秀和さん)に、借金を抱える者も多い旗本や諸大名たちの事情も考えて日光社参は執り行わないで欲しいと訴えました。しかし家治は嫡男の家基が社参を望んでいるから執り行うと言います。田沼家の用人である三浦庄司は、これはたぶん白眉毛(武元のこと)が裏から家基の生母の知保の方を動かしているのだろうと考えました。そこで意次は、ならば貧乏大名や貧乏旗本から社参取りやめの嘆願を集めようと考えて、手配するよう三浦に命じました。嘆願書が集まったところで意次は家治にその旨を伝え、社参を取りやめるよう強く訴えました。しかし家治は嫡男の家基から、将軍である自分は意次の言いなりになっている、意次は成り上がりの奸賊であると言われたと伝え、そして家基の世になった時、田沼一派は真っ先に排除されるだろうと警告しました。重三郎は偽版本の件では自分からは何も言わないと決めていたのですが、武家の者が孫兵衛とつながって偽版本を売りさばいているという話は幕府の上の方の役人にまで内密に話が伝わっていました。重三郎が複雑な思いを抱えながら鱗形屋に来て孫兵衛と打ち合わせをしている時に長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)が店に入ってきました。平蔵が地引を求め、差し出された節用集を確認するとそれは偽版本でした。平蔵が「あったぞ!偽版だ!」と叫ぶと店の中に同心たちが一斉に入ってきて、上方の版元の柏原屋から訴えが出ていることを説明して、孫兵衛以下鱗形屋の者たちを全員連行していきました。同心たちが店を調べると蔵には証拠となる大量の版木と摺本があり、重三郎が告発したと思い込んだ孫兵衛は重三郎を逆恨みしながら連行されていきました。板戸が閉め切られた店の前で、平蔵は重三郎に事の次第を話してやりました。柏原屋から奉行所に相談があり、偽版を出している者の正体がつかめなくて訴えられない、でも奉行所のほうも調べようがなくてどうしたものかと思っていたら、この件に関しては何故か上から鱗形屋を調べろと命が下ったと。重三郎は平蔵に、実は孫兵衛のやっていることを知っていたが孫兵衛に危ないとは言わなかった、心のどこかで孫兵衛がいなければ自分が取って代われると望んでいた、でもうまくやるというのは心が堪える、と打ち明けました。そんな重三郎に平蔵は、世の中そんなもんだ、気にするなと言い、持っていた粟餅を「濡れ手に粟餅」と言って重三郎に渡しました。「せいぜい有難く頂いとけ。それが粟餅(うまい話)を落とした奴への手向けだ。」ーーそう言って平蔵は去っていきました。重三郎は店に向かって挨拶をし、粟餅を力いっぱいほおばりました。
February 13, 2025
-
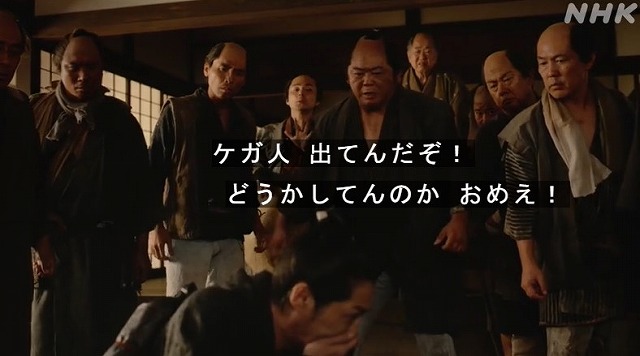
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第5回~「蔦に唐丸因果の夢」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回いくつかの場面で感じたことは、一言で言えば『類は友を呼ぶ』でしょうか。平賀源内(安田顕さん)が金策のために老中の田沼意次(渡辺謙さん)を訪ねた折に、鉱山を開発すれば金属を得るだけでなく、その土地全体で仕事が増え、金を稼げ、道ができ宿場ができ、全体が活性化して幕府にも運上・冥加が入って、といったことを意次は力強く語りました。その次に源内が、日本が開国をすれば人々の目が大きく開け、能力がある者は外国人を相手にいろいろな仕事ができて富を得ることができると言い、意次と源内は実に楽しそうに展望を語り合っていました。今いる場所のうまくいかない現状を変えたい、全体をもっと大きく豊かにしたい、そのためにはどうしたらいいのかを考えたい。気が合うというか、互いに同じエネルギーを持つ者であると感じるのか、自然と惹かれ合うのです。蔦屋重三郎(横浜流星さん)も、住まう世界は違っても𠮷原全体を良くしたいという思いから、自分の仕事じゃないのに奔走し、結局はそれがタダ働きとなって気落ちしても、また気を取り直して進んでいきます。互いにどこか似た者が惹かれ合って集うのです。重三郎のエネルギーが、いつか意次を呼ぶのでしょうか。さて今回から、時代劇の大御所である里見浩太朗さんが須原屋市兵衛の役で登場しました。里見さんもさすがにお歳を召されたし、このドラマでは殺陣はありませんが、それでも里見さんがいらっしゃるだけで江戸時代の雰囲気がグッと出る感じがします。ホント、すごい存在感だと思います。さてこちらでは様々な意見がでていて参考になりますが、今回は特に2月2日に千葉県の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに行かれた方が、主役の横浜流星さんの素顔フォトをUPされてます。すごくいいお顔をしているので、これは必見です。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 平賀源内(安田顕さん)が採掘をさせている秩父の中津川鉱山で火災が起こり、平秩東作から報せを聞いた源内は大急ぎで江戸から秩父に向かいました。10年も山を掘り続けているのに金になる物が掘り当てられない上に事故まで起きて炭鉱の工夫たちはカンカンに怒っていました。もうこの採掘を辞めるという工夫たちをなだめて仕事を続けるよう源内は促すのですが、『災い転じて福となす』というつもりで「めでたく災難」と言って笑ってしまったことで工夫たちの怒りが爆発。源内は殴られながらも「ここは米も取れない土地で金を稼ぐために始めた事」とか言って反論しますが、工夫たちや船頭たちが資本金として源内に渡した大金を、東作を人質にとって10日で返すよう返すように要求してきました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、源内から「耕書堂」という版元の名をもらって錦絵作りに奔走したものの、重三郎では世間に出版できないと言われ、女郎屋の主人たちや鱗形屋の孫兵衛らにはさんざん利用されただけだと知って激しく落ち込んでいました。弟分の唐丸がその孫兵衛から文を預かってきてその内容は、重三郎に鱗形屋のお抱えの「改」になるようにというものでした。その話を聞いた義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)は「たとえ重三郎のタダ働きになっても、本をどんどん売り広めてもらえるならいい話だ」と意見しました。重三郎と次郎兵衛がそんな話をしていると向こう傷の男(高木勝也さん)が店先にふらりと現れ、最初は唐丸(渡邉斗翔くん)が対応しました。でも何か危ない感じがした重三郎が二人の間に割って入り、唐丸には中に入るよう促したのですが、唐丸は自分が相手をすると言い張ります。この男は何か唐丸の弱みを握っているのか、何日か前から唐丸につきまとって金をせびり、店の金を持ってくるよう要求していました。重三郎は唐丸と男の様子を警戒しながら気にしていましたが、そこへフラフラになった源内が何か食べさせて欲しいと飛び込んできました。次郎兵衛がとりあえず向かいの蕎麦屋に案内し、重三郎は唐丸に店番を頼んで源内に同行、蕎麦屋の半次郎(六平直政さん)は源内の事情を興味深く聞いていましたが、案の定その隙に男が店から何か持っていったようでした。そして源内が重三郎のところに来たのは、山の人たちに大金を返すために炭を売りたいから炭屋の株が欲しい、炭屋の株を売りたい人を紹介して欲しい、という理由があったからでした。親父衆から紹介をもらった源内は重三郎と共に炭問屋の山崎屋に向かいました。しかし双方の話があわずにご破算になりました。店を出た後、重三郎は源内に「いつもこんはふうに儲け話を考えて、人と金を集めてなんて危なっかしい生き方をしているのか」と訊ねました。源内は自分を召し抱えてくれる所がないから自分で声を上げるしかないと言い、「しがらみに縛られず自由に生きる=我儘に生きる。ただそれで生活がきつくなるのは仕方がない。」と答えました。源内の話が重三郎の胸に何か響いたのか、重三郎は本屋の株を買おうと考え、そういう話ができる人をだれか紹介して欲しいと源内に頼みました。*平賀源内の士官についての話が番組HPの「べらぼうナビ」に出ています 。 ⇒ ⇒ こちら 重三郎にそう言われた源内は、すぐそばにあった書物問屋に入っていきました。主人の須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)は重三郎が求める「地本問屋の株」と「書物問屋の株」は違うことを教えてやり、鱗形屋や西村屋に「仲間」という言葉で丸め込まれた自分の無知さを悔しく思いました。それでも自分が版元になる方法は何かないのかと市兵衛に訊ねたら、どこかの本屋に奉公に上がって暖簾分けをしてもらうのはどうかと教えてくれました。さて早く金策をして中津川鉱山に戻らなければならない源内は、老中の田沼意次(渡辺謙さん)を訪ねました。500両もの大金をなんとかしてやると言ってくれた意次に源内が深々と頭を下げると、意次は礼を言うのはこっちだと言います。「山で稼げれば土地の者が金を得る。水路が開かれば商いが盛んになり宿場ができて民が潤う。幕府にも運上・冥加が入ってくる。本来なら政でやるべき。」と意次は経済が回る仕組みを広めたいのですが、それは武士のやることではないと批判する、由緒正しい古い人たちを意次は苦々しく思っていました。源内は、ならばいっそのこと開国して誰でもどこでも外国と取引できるようになるといい、そうすれば物の値打ちだけでなく人の値打ちもわかるようになる、通事・造船・塾などいろいろな商売が始まると。意次と源内は二人で語り合いながら、次々と開けていく展望に胸を膨らませて笑い合っていました。しかし現実は、そう簡単にもいかないことも二人はわかっていました。日も落ちて重三郎が店に戻ると、留守番をしていた次郎兵衛は帰き際に重三郎に何か高い本を買ったか?と訊きました。次郎兵衛が「銭箱の金が減っている気がする。」と言うので、重三郎は唐丸が怪しいと感づいたのですが、とりあえずその場はごまかしました。唐丸は頻繁に男に金をせびられるようになり、我慢できなくなってお奉行所に訴えると言いました。でも唐丸の過去を知っている男は「そうなるとこの店がお前をかくまったとして同様に罰せられる」とさらに脅すので、唐丸は男の言う通りにするしかありませんでした。寝る前に二人になったとき、重三郎はこれから鱗形屋に奉公に出て、いつか唐丸を絵師として迎えると約束しました。そして唐丸に、何か隠し事があるのでは?困り事があるなら力になるから、と訊ねましたが深くは追及はしませんでした。翌朝、重三郎が目を覚ますと唐丸の姿はなく銭箱もなくなっていました。重三郎は唐丸を必死に探しますが、唐丸はあの男と会っていました。唐丸が抱えてきた銭箱を見てほくそ笑む男、でもこれでもう重三郎がいるあの店には二度と戻れないのだと覚悟を決めた唐丸は、男に体当たりしてもろとも川に落ちていきました。市中を走り回って唐丸をさんざん探したけど見つからず、夜になって重三郎は店に戻ってきたのですが、何やら人だかりができていました。店には役人が来ていて、向こう傷のある男が土左衛門が上がってその男がこの店の物を持っていて役人が調べている、ということでした。役人が重三郎を疑うような言い方をしたので主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)がすかさず、𠮷原は咎人を突き出す役目も持っているから怪しいやつがいたら自分が奉行所に突き出すと言いました。役人が去った後で、その男と共に川に落ちた子がいると言われているが、もし唐丸が絡んでいたら面倒なことになるからこれ以上騒ぐな、と釘を刺しました。しかし唐丸が姿を消し、銭箱がなくなったことで、憶測も交えた勝手な噂話がどんどんと広まっていきました。重三郎は気持ちの拠り所となるいつものお稲荷さんのところに来ていました。唐丸が描いた絵を見つめながら、これまで唐丸の過去のことをあえて聞かずにいた自分を責めていました。幼なじみの花魁の花の井(小芝風花さん)は、唐丸は今頃きっと幸せしていると言い、そう考えるのが女郎たちの流儀だと言いました。花の井とそんな話をしていると重三郎も希望を思い描くようになり、そのうち唐丸がひょっこりと自分のところに戻ってきてまた絵を描きたいと言うだろう、そして自分が唐丸を謎の絵師として売り出すんだと、あの夜に唐丸と約束したことを語り、お稲荷さんに願掛けをしていました。さてその頃、平賀源内は田沼意次が用意してくれた大金を持って中津川鉱山に行き、工夫たちと話をつけてきました。一方、重三郎も鱗形屋に行って店のお抱えの「改」となることを孫兵衛に伝え、𠮷原に人を呼ぶために働く決意を新たにしました。
February 6, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第4回~「『雛形若菜』の甘い罠」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回はドラマでも小説でもよくある、主人公が一旦は失意のどん底に落ちる、という回でした。主人公の蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、明るい性格で行動力もあり、頭の回転が速くてなにより弱い者たちを思う優しさがあります。そしてふだんはポジティブシンキングで、少々の苦労や障害なら気持ちを切り替えて乗り越えていきます。でも今回の流れは、さすがに重三郎でも堪えたというか心が折れる事態だったでしょう。上に逆らえない下っ端の悔しさを十分に味わわされて、これから徐々に力を持つようになるのでしょうか。ただ、いくら重三郎のサクセスストーリーが面白いとしても、やはりそれだけでは1年間続く大河ドラマとしては物足りないものです。その部分を渡辺謙さん演じる田沼意次と、意次に関連する徳川家の政の部分で面白くなっていると思います。田沼意次というと、これまでの時代劇ではあまり良い印象がなかったのですが、渡辺謙さんが演じるせいか、このドラマでは意次から目が離せない感じです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #べらぼう #大河べらぼう 安永3年(1774)秋、蔦屋重三郎(横浜流星さん)があちこち奔走して作った『一目千本』によって𠮷原は賑わいを取り戻しました。女郎屋の主人たちは次の一手として女郎たちの錦絵を出そうと考えたのですが、『一目千本』の時と同様、自分たちは金を出さずに女郎たちに入銀させ、そして動き回ってそれを作るのはやはり重三郎でした。しかし女郎たちからは、そんなに簡単に入銀はできないと反発され、そのことを義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)に愚痴をこぼしました。弟分の唐丸(渡邉斗翔くん)が女郎たちなら簡単に稼ぐのでは?と訊ねるので、次郎兵衛と重三郎は「客の支払いから店の取り分が持っていかれ、他にも着物や身支度に金がかかり手元にはほとんど金が残らない。」と説明してやりました。同じ頃、徳川御三卿の田安家では当主の治察が急逝し、半年前に白川松平家へ養子に行った弟の賢丸は、後継ぎがない田安家のことを考えていました。そこで賢丸は老中首座の松平武元から大奥総取締の高岳を通じて将軍・徳川家治(眞島秀和さん)を動かし、自分を田安家に戻すよう動いていました。家治から賢丸を田安家に戻すと聞かされた田沼意次(渡辺謙さん)が家治にその真意を訊ねると「賢丸の気持ちを考えると」という思いからでした。半年前に賢丸を白川へ養子に出すように家治を動かした意次でしたが、その場は一旦は家治の意向を受け入れました。御三卿として維持するだけで10万石も与えている田安家を、幕府の倹約令にならって潰してしまいたいと意次は考えていました。そこで最後の手段ともいえる危ない賭けを意次はやることに決め、父・意次の意を汲んだ嫡男の意知が何か秘密裏の行動を始めました。一方、錦絵を作るのに誰かに出資させる方法が何かないかと考えていた重三郎が鱗形屋で孫兵衛に相談し、それからふらりと大道芸人たちが集まる両国に来ると、そこで平賀源内(安田顕さん)とばったりと会いました。重三郎と近況の話をしながら源内が両国を歩いていたらふと、かつての自分の思い人だった菊之丞のことを思い出す場面がありました。その話を聞いていたら重三郎は錦絵の資金集めをする方法を思いつき、源内に礼を言って走って𠮷原に戻っていきました。重三郎が去った後、源内は編み笠を深くかぶった男(実は田沼意知)から内密に、意次からの言伝と荷物を受け取りました。両国から戻った源内は助手の小田新之助(井之脇海さん)と共に、本の綴じ紐を解いて中をばらしたり、墨の濃淡を調べたりと、何やら作業を始めました。一方、錦絵の資金集めのために着物を売り込みたい呉服屋から入銀させるという妙案が思いついた重三郎は早速、女郎屋の主人たちに話をしました。主人たちは何やらひそひそ話をして重三郎の案を認めることにし、重三郎が話をもってきやすいよう𠮷原に呉服屋の客が来たら重三郎を呼ぶことにしました。この日から重三郎は呉服屋が訪れる𠮷原中の座敷を飛び回ることになりました。重三郎は頃合いを見計らって呉服屋の客に話を持っていくのですが、どの客も皆「親父に相談する」「考えておく」といった具合で、頑張って座敷を盛り上げて客の機嫌をとっても色よい返事はもらえませんでした。*吉原の芸者に関する事が番組HPの「べらぼうナビ」に出ています。 ⇒ ⇒ こちら 重三郎が疲れ果てて戻ると、ちょうど主人の駿河屋市右衛門(高橋克実さん)がいて、呉服屋から思うように入銀させられないことを相談しました。市右衛門は、名の通った女郎がいない、あれは菊之丞だから流行った、そして重三郎自身にも名がないと的確な助言をくれ、重三郎はまだまだ自分の考えが甘いことを痛感しました。(なんだかんだ言って市右衛門は重三郎が可愛い)するとそこへ錦絵で有名な西村屋の与八(西村まさ彦さん)が突然現れました。与八は大文字屋で錦絵の話を耳にした、自分はその話に一枚噛みたい、自分がいれば市中に錦絵を広めることもできる、と言いました。与八の出現で話が急に大きくなった重三郎は大喜びで、別の場所でもっと話を進めようと言う与八と一緒にどこかへ行ってしまいました。そんな二人の後姿を市右衛門はいぶかしげに見送っていました。西村屋の参加により呉服屋から次々と入銀が集まり、さらに西村屋の計らいで絵師は美人絵を得意とする礒田湖龍斎に決まりました。与八はさらに重三郎に、自分の版元印を作るよう提案しました。湖龍斎の墨による見事な下絵が完成し、その預かった下絵を店に持って帰ると唐丸が食い入るように夢中になって見ていました。自分の版元印の名を平賀源内に考えてもらおうと思った重三郎が源内を訪ねると、源内は唐丸に絵を教えてやるとか玄関先で話はするものの、新之助がなにやらバタバタしている室内を見せようとはしませんでした。やっと中に入れてもらった重三郎は版元としての名(堂号)のことを源内に相談、しばらく考えた後にいい名が浮かんだ源内はすぐに紙に書いて渡してくれました。素晴らしい名を源内につけてもらって喜びにあふれて重三郎は店に戻りました。ちょうどその時に猫が花瓶を倒したので片付けようとしたら、その濡れた敷物は湖龍斎に描いてもらったあの大事な下絵の入った包みでした。義兄の次郎兵衛が包みを花瓶の敷物にしてしまい、包みの中にある大事な下絵は水に濡れて墨がにじんでしまいました。一体どうしたらいいのかと重三郎が困り果てていたら、唐丸が試しに自分が直したいと言い出し、唐丸に任せてみることにしました。すると唐丸は下絵と全く変わらない見事な絵を描きあげました。それを見た重三郎は唐丸の才能をひしひしと感じ、自分が唐丸を当代一の絵師にしてやると約束、重三郎の言葉を胸に唐丸は残りを全部描き直しました。唐丸の頑張りでなんとかその後の作業が進められ、下絵の件も皆にばれずに済み、重三郎は心からホッとしました。さてその頃の田沼意次はというと、実は平賀源内には覚書の細工を頼んであって、それが仕上がってきたので確認をしていました。まるで最初からこう書かれてあったかのような出来栄えに、田沼意知(宮沢氷魚さん)も側近の三浦庄司(原田泰造さん)も驚きを隠せませんでした。三浦がこの文書は細工前に誰かが見ていたのでは?と気になって意次に訊ねたら、意次はこれは書庫で分厚く埃をかぶっていたから賢丸をはじめ誰も手にとってはいないだろうと答えました。その細工された文書を持って、意次は田安賢丸(寺田心さん)を訪れました。「跡を継ぐ者がいなければそのまま当主を置かず、お家断絶とすること」と書かれてあり、賢丸はにわかに信じられない思いでした。この件に関して意次は、先代の将軍・家重だけでなく、賢丸が尊敬してやまない8代将軍・吉宗のことも説明に織り交ぜ、上手いこと作り話を展開しました。老中首座の松平武元(石坂浩二さん)がそのような話は知らないと言うと意次は、全ては本丸での出来事だから西の丸にいた武元にはわからない、と答えました。さらに意次は、賢丸がこの文書を読んでないことを確認し、実は上様(現将軍)も吉宗公の考えは知らなかったと、文書の信憑性を持たせました。そして田安家のこの先は賢丸次第と言い、文書を回収して退室していきました。さて、源内から「耕書堂」という立派な版元の名をつけてもらって印も作った重三郎は、出来上がった錦絵を持って意気揚々とお披露目の場に向かいました。ところがその場には、西村屋の与八がなぜか鱗形屋孫兵衛(片岡愛之助さん)と鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)を連れてきていて、二人の同席を願い出ました。錦絵の見事な出来に呉服屋の一同は感嘆の声をあげ、重三郎も満足でした。しかし与八がそこから先の錦絵の販売は西村屋だけの版元とすると突然言いだし、業界の決め事で重三郎の名(耕書堂)は入れられないし、市中では売ることはできないと、鱗形屋と鶴屋が説明を加えました。この錦絵のために奔走して苦労したのは重三郎一人であり、さすがにこの件では重三郎は後に引けずに冗談じゃないと怒りをぶちまけました。しかし主人の駿河屋市右衛門から「𠮷原のためだ」と言われ、これまで𠮷原のために頑張ってきた自分だからと、泣く泣く引き下がりました。ただ実はこの件は重三郎の知らない所で、鱗形屋と西村屋が裏で結託していて、重三郎はこの二人と女郎屋の主人たちに利用されただけだったのでした。
January 29, 2025
全4878件 (4878件中 1-50件目)
-
-
- ◆かわいいペットと泊まれるお宿~◆
- 「🐾愛犬と一緒に山の温泉へ🏞️|湯山…
- (2025-03-30 09:00:10)
-
-
-
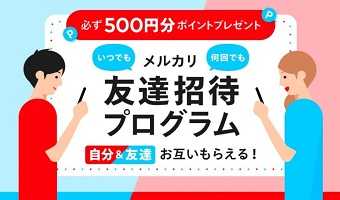
- シーズー大スキ♪
- 💝【メルカリ】サンキューシール か…
- (2024-07-04 08:34:48)
-
-
-

- ゴールデンレトリーバー!
- 【まとめました】大型犬の北海道引っ…
- (2024-09-26 07:44:12)
-








