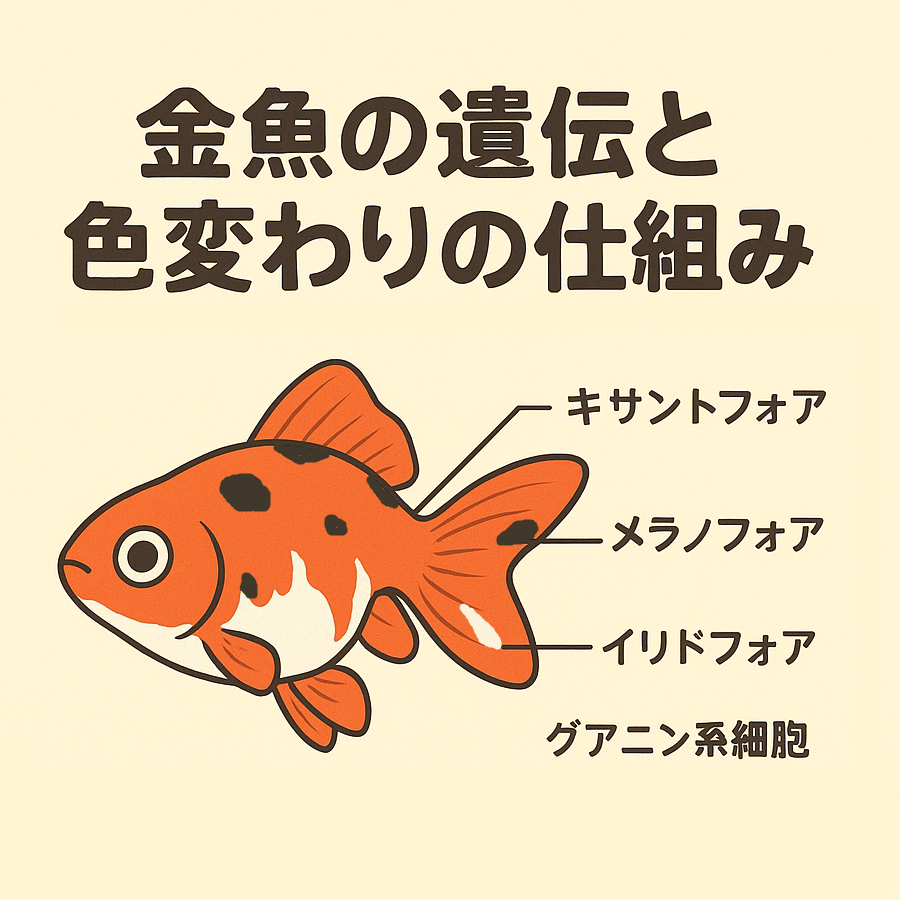2025年09月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
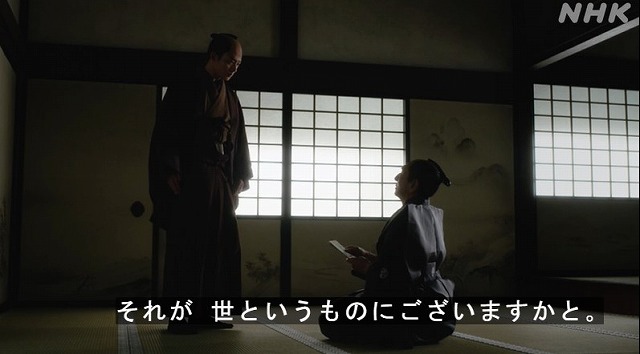
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第36回~「鸚鵡のけりは鴨」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回で感じたのは、上に立つ者の行動の対比でした。松平定信(井上祐貴さん)は怒りに任せて恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)を呼び出して詰問しようと考えます。でも最高権力者の怒りが想像できるから春町はすぐには応じられません。春町の殿・松平信義(林家正蔵さん)は春町を理解し、誇りに思う家臣の一人として、春町を生かすためになんとか守ろうとします。駿河屋市右衛門(高橋克実さん)も春町を逃がそうと、バレたら厳しいお咎めを受けるのを承知で蔦屋重三郎(横浜流星さん)の頼みをきいて、偽の人別を作ってやりました。人生経験と人間性がある信義や市右衛門は、春町を助けてやろうと知恵を巡らせ、定信に嘘の報告をしたり偽の人別を作ったりと自分がやってやれる行動しました。若さと、人生経験が少なくて自分の考えが何でも通ると思う定信は、怒りの勢いで春町の処罰しようとし、でもそれが結果として死を招いたと知って、定信は若さゆえ激しく動揺して後で涙しました。ただ春町が死を選んだのは、我が殿・信義のためかなとも思いました。自分の才能を認めてくれた、自分を誇りに思ってくれた、ギリギリまで自分を守ろうとしてくれた殿です。その殿を守るためにも、思い残すことなく自害を選んだのではと感じました。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 寛政元年(1789)2月、蔦屋重三郎が出した本は世間で大人気となり、飛ぶように売れていましたが、その内容は老中首座の松平定信(井上祐貴さん)の治世を皮肉るものでした。一方、定信のほうは文武に長けた者を登用しようとしても次々と辞退していき、どうしたものかと悩んでいました。そんな折に側用人の本多忠籌(矢島健一さん)の家老が賄を受け取っていると知り、定信は激怒して厳しく叱責しました。ただ忠籌は、今はお役目をもらうと持ち出しが増えるから大したうまみがない、登用したい者が辞退するのはそのためと定信に進言しました。それでも定信は公儀への奉公に対する理想を掲げて耳を貸そうとせず、忠籌は世のことを知って欲しいとばかりに重三郎が出した本を定信に差し出しました。忠籌が差し出した本を読んだ定信は、自分の政が笑いのネタになっているのを見て、これはもはや謀反!と激怒、早速役人を蔦屋重三郎(横浜流星さん)の店に向かわせ、朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)が書いた『鸚鵡返文武二道』他3作の絶版を命じました。定信は喜三二の主家である秋田藩の佐竹義和を呼び出して詰問、激しい怒りで涙する我が殿を見て喜三二はもう筆を折ることにしました。恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)の主の松平信義も定信に呼び出しを受けたのですが、信義はとりあえず春町が病気で隠居したとごまかしました。そんな話をしていたら平秩東作が病だと報が入りました。重三郎は須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)と大田南畝(桐谷健太さん)と共に東作を見舞いました。東作の病は重く、平賀源内が枕元に来たという話をする東作はもう長くないと誰もが感じました。源内は世界がどんどん進むのを肌で感じ、自身もまた新しい世を作り出そうとしていた男で、田沼意次も同じ考えでした。でも松平定信の政で日の本が100年前に逆戻りし、ますます世界から取り残されていく様が悔しくて源内が化けて出てきたのだと市兵衛は思いました。そんな頃、蝦夷地では松前藩の圧政に対してアイヌ人が蜂起し、松前道廣がすぐに鎮圧はしたものの蝦夷の民の恨みは深いと報告がありました。ならばと松平定信はこの機会に蝦夷地を天領としては、と徳川御三家の当主らに進言しました。紀州藩の徳川治貞(高橋英樹さん)は定信に味方してくれましたが、尾張藩の徳川宗睦(榎木孝明さん)は、松前藩は反乱を鎮圧して功を立てたから天領にして所領を取りあげるのはどうかと反対でした。定信はそれでも自説を強く主張しましたが、一橋治済(生田斗真さん)から、その考えは定信が嫌う田沼と同じ、民もそう思っている、と指摘されそれ以上何も言えなくなりました。『悦贔屓蝦夷押領』を読んだ定信は、それが自分の政への痛烈な皮肉であることに気がつき、倉橋格(=恋川春町)の呼出を命じました。呼出に応じて釈明しても下手をすれば自分はお手討ちで主家の小島松平家が取り潰しとなるのでどうしたらと春町が悩んでいたら、いっそ別人になればと重三郎は言いました。それもありかと思った春町は主君の松平信義(林家正蔵さん)に相談、支度が整うまで信義には定信に頭を下げてくれるよう頼みました。信義は、1万石の小名の当家にとって恋川春町は唯一の自慢であり、当主の自分にとっても密かな誇りだった、春町の筆が生き延びるならいくらでも頭を下げると言ってくれました。我が殿の自分への愛情に春町は胸が熱くなりました。しかし時間稼ぎの信義の嘘は定信には通用せず、信義は春町に今すぐ逐電するよう命じました。朋誠堂喜三二が国元に戻る日が近づき、吉原では蔦屋主催の大送別会が開かれ喜三二と縁のあった人たちがたくさん集まりました。互いに酒を酌み交わし賑やかに囃しそれぞれに芸を披露し、そして北尾重政が本の名入れを頼むと他の皆も次々と自分の持ち物に名入れを頼んでいました。吉原の親父衆は皆喜三二の仕事ぶりを讃え、他の人たちも口々にもう一度何か作品をと喜三二に頼んでいました。でもそれは重三郎が江戸を去る自分へのはなむけとして仕組んだんだ、ということも喜三二はわかっていました。宴会の頃合いを見計らって駿河屋市右衛門(高橋克実さん)が重三郎に声をかけ、二人は座を外しました。人目のない場所で市右衛門が重三郎に渡したものは、春町が逐電するときのための偽の人別でした。重三郎を幼い頃から育ててくれ、厳しかったけど独立した今でもこうして何かあれば危ない橋を渡ることであっても力になってくれる市右衛門でした。顔見知りの多い春町だから気を配るよう言葉を添えてくれる親父様の気持ちを重三郎は有難く思いました。しかし重三郎たちの準備もむなしく恋川春町は一人自害をしてしまいました。朋誠堂喜三二とともに重三郎が春町の弔問に行くと、妻のしず(谷村美月さん)から辞世の句を渡されました。そのとき重三郎は文机の横にあるくず入れの中に破られた文を見つけ、しずの許しをもらって紙片をつなげてみました。復元してみるとそれは重三郎にあてたものでした。「別人で生きることを考えたがもう定信の追及をかわせない、逐電すれば小島松平家、倉橋家、蔦屋だけでなく皆にも類が及ぶ、全てを円く収めるためにはこのオチしかないと。」店に戻った重三郎は春町が一旦は破って捨てた最後の文を皆に見せました。本を書いただけで結果、死に追いやられた春町を思い、皆は悔しさと悲しさでいっぱいになりました。ただ重三郎は春町の髪に豆腐のかけらがいくつも付いていたことが気になっていて、それは『豆腐の角に頭をぶつけて死ね』の言葉を体現したのでは?と山東京伝(古川雄大さん)が言いました。続けて喜三二が「春町は戯作者でありクソ真面目な男だったから最後まで戯けないとと思ったのでは。」と言うと、春町を思い皆は泣き笑いました。男たちは涙と笑いをあの世の春町に手向けました。松平信義は春町の死を松平定信に報告しました。春町は切腹し、最後の力を振り絞って豆腐の入った桶に顔を突っ込んだことを言おうとしたとき、あの男らしいと信義は思わず笑いがこみ上げました。そして「ご公儀を謀ったことを腹を切って詫びたが、春町としては死してなお世を笑わすべきと考えたのでは。一人の至極真面目な男が武家として、戯作者として分をそれぞれわきまえ全うした。戯ければ腹を切らねばならぬ世とは、いったい誰を幸せにするのか。本屋風情の自分にはわからないと言っていた。」と信義は涙をこらえながら重三郎の言葉を定信に伝えました。一人になった定信は布団部屋に隠れ、声を殺して涙しました。
September 25, 2025
-
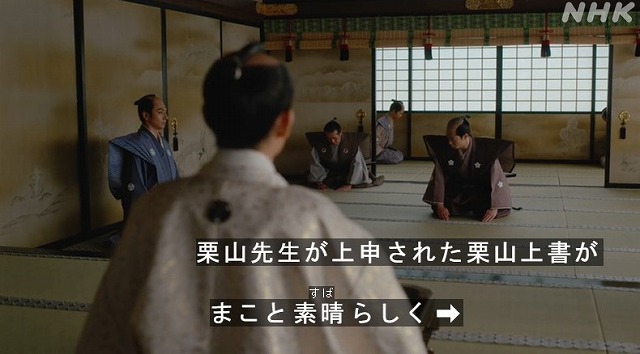
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第35回~「間違凧文武二道」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回の中でよく出てきたキーワードの「伝わる」。その言葉を発信した人が思い描く、言わんとすることが必ずしも相手にちゃんと伝わるとは限らないというのはいつの時代にもあることですよね。蔦屋重三郎(横浜流星さん)たちが出版した松平定信(井上祐貴さん)の治世をからかった本は、当のご本人でさえ本にこめられた思いが伝わらない。その定信が自分の治世で据えたい理想の武士像を思い描いて、張りきって文武二道を奨励したものの、にわか仕込みで武芸や学問を始めた者たちには真髄たるものが伝わるはずもなく、できあがるのは勝手な解釈の果てに民を苦しめる使えない者ばかり。前回では、店を守りたいというてい(橋本愛さん)の思いがちゃんと重三郎に伝わったのに、今回はカン違いでも『文武二道』の本がとにかくうまくいったことに味をしめて強気になった男どもに、ていの嫌な予感は伝わらずに出版となってしまいました。思うことを伝えるというのは、難しいものですね。ただ意外だったのが、この時代の武士たちが文武の面でこんなにも緩んでいたことでした。あと50年もすれば幕末の動乱が始まります。幕末のドラマを見ていると誰もがものすごく勉強熱心で、あるいは剣の稽古に励む若者たちがいて、そんな彼らが命をかけてどんどん時代を動かしていきます。まあ逆に考えれば、このドラマの時代がこうだったから、地道に文武に励んできた若者たちが幕末で名を上げたということでしょうか。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明8年(1788)の年明けに出版した『文武二道万石通』を読んだ松平定信(井上祐貴さん)は本に込められた自分への皮肉に気がつかず、たいそう気に入ってこれからの政にますます意欲が湧いてきました。また定信は阿波蜂須賀家の儒者であった柴野栗山(嶋田久作さん)を第11代将軍・徳川家斉(城桧吏さん)のお抱えに推挙しました。皆が孔子の教えを学び、一人一人が正しき人となり、武術に励んで世に広まる田沼病を根本から治さなければ、と定信は意気込んでいました。そのころ蔦屋では『文武二道』を買い求めて人々が押し寄せていました。店の奥では皆が総出で本の製本をしていて、それでも追いつかないほどの人気ぶりで、重三郎は世の流れが一気に変わるような気さえしていました。町に出ると侍たちは新しい弓を持ち歩いて武芸を語り、学問所で学んだ孔子の論語の一節をそらんじていましたが、武芸も学問もまだ始めたばかりの印象を受ける者が多いようでした。また重三郎も本が飛ぶように売れるのは嬉しいけれど、定信の政をからかっている本の内容が世間の人には全く伝わらず、落胆していました。ただ歌麿が描いた絵は一流の絵師にも劣らないのに値打ちで買えると熊野屋(峯隆太さん)などの豪商(林家三平さん)には評判でした。歌麿(染谷将太さん)が重三郎の店を出た帰り道、急に雨が降ってきたので雨宿りをしたらきよ(藤間爽子さん)が洗濯物を慌てて取り込んでいました。歌麿が手伝いながらきよを見ると、以前幻覚に悩まされたときにここで会ったあの女であることを思い出し、耳の聞こえないきよに必死に伝えました。きよは歌麿があのときの男で本当は優しいなの男だろうと思うと安堵し、落ち着いて自分の仕事を始めました。歌麿はきよを見ているとなぜか心穏やかになり、そしてきよの姿を描きたくてたまらなくなり、夢中で筆を動かしてきよを描いていました。蔦屋重三郎(横浜流星さん)は『文武二道』の真意が肝心の定信にも世間にも伝わっていないのにどうにも納得がいかなくて、朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)ら出版の仲間に集まってもらってました。田沼を叩くのをやめると定信へのからかいが露骨にわかってしまう、ではどうしたら?とか皆で考えていたのですが、恋川春町(岡山天音さん)だけは一人不機嫌で拗ねていました。その理由は春町の書いた『悦贔屓蝦夷押領』だけが売れていなかったためで、皆はそれぞれに春町の機嫌をとっていましたが機嫌は直りませんでした。恋川春町(武士で本名は倉橋格)は出仕してもお役目に身が入らず他事を考え、それを小島松平家当主の松平信義(林家正蔵さん)に見られてしまいました。信義は平謝りする春町の顔を上げさせ、春町の本がとびきり面白かった、実に皮肉だった!と感想を伝えました。信義は『悦贔屓』の本の言いたいことを正しく理解してくれて、さらに春町がよくお叱りを受けなかったと味方してくれました。春町は我が殿・信義を信頼して、定信の政をどう思うか尋ねました。信義は「志は立派だが、果たしてしかと伝わるものなのか。」と答え、春町は信義の言葉を深く考えてみました。江戸市中では急に武芸を始めた武士たちがやたら何かと威張り散らし、町の人たちはあちらこちらで酷い目にあっていました。一方、自分の書いた本を我が殿から褒めてもらえて気が済んだ春町は、信義が言ってくれたことを自分なりに解釈して「俺たちのからかいも通じなかったが、定信の志もそううまくは伝わらないのでは。」と重三郎たちに伝えました。「元から文武に励んでおった者は今さら道場に通ったり、本を買ったりしない。今、文武を叫ぶ者はにわか仕込みの新参者だ。」と分析しました。さらに「文も武も修めるには時間がかかるもの。遠からず皆あきてトンチキを作り出して終わるのではないか。」と信義の言葉を伝えました。ところがそんな話をしていたら大田南畝(桐谷健太さん)が駆け込んできて、田沼意次の死を報せ、意次の名誉を取り戻したかった皆は言葉を失いました。さて、誰もが文武に励んで田沼病を治す政策がうまくいっていると思っている定信の元に、将軍・家斉が大奥の女中との間に子をもうけていたという、驚くべき報せがもたらされました。ここのところ学問を怠る家斉に定信は苦言を呈しますが、家斉は「それぞれ秀でたことをすればよい」と聞く耳を持ちません。定信は家斉が御台となる茂姫との婚儀も済まぬうちから他でお子を!と茂姫の実父である薩摩藩主の島津重豪(田中幸太朗さん)に訴えますが、重豪も一橋治済(生田斗真さん)も全く気にしていない様子でした。さらに定信は、質素倹約の旨を皆にきつく言い渡しているのに能舞台の衣装が豪華なことも気になる、賄賂も固く禁じていると二人に意見しました。しかし治済から、定信が10万石と引き換えに老中首座となり思うままに政をしていることを示されると、定信は何も言えませんでした。定信が文武二道を奨励した結果、にわか仕込みで武士としての心構えもなっていない者たちが立場の弱い民たちを苦しめている実態をどうしたらいいのかと、定信は柴野栗山に問いました。栗山は、各々の立場に対する心得を作って書にして将軍・家斉に渡す、初歩の漢文すら読めぬ旗本・御家人も多い昨今、まず武より文、武家としての心得を叩きこむのが良いと進言しました。さらに栗山は自分が湯島聖堂で講釈をしてもよい、定信の『鸚鵡言』を使うと言い、定信は快諾しました。田沼意次の死と共に、もう一つの悲しい別れがありました。歌麿が幼かった頃の数少ない幸せな記憶として残り、歌麿が唯一師事したいと強く願った鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)の突然の死でした。何かにとりつかれたように筆をとって雷獣を描きあげ、絵筆を握りしめたまま絶命してあの世に旅立っていきました。そんな石燕の死の報せと共に、歌麿は一人の女性(きよ)を連れてきていて、誰もが思ったとおりきよは歌麿のいい人でした。歌麿はきよと所帯を持ちたいと言い、きよの絵を描くときのことを楽しそうに幸せそうに語り、そしてきよのために「ちゃんとしたい」と言いました。歌麿は、きよのために名をあげて金も稼いできよを幸せにしてやりたい、今は金が足りないから自分が描いた絵を買い取ってもらえないかと、何枚かの絵を重三郎に差し出しました。それは描くと忌まわしい過去を思い出してしまい歌麿が描けなかった笑い絵で、きよと一緒にいることで幸せな気持ちで満たされて乗り越えることができた、歌麿の思いがつまった絵でした。重三郎は可愛いがった義弟の歌麿の幸せそうな顔が嬉しくて、ご祝儀を含めて絵を百両で買い取ってやりました。秋になり、年明けに出す本のために皆が集まっていました。世間では定信の『鸚鵡言』を使った講義が広まったものの、肝心の受講生たちには正しく理解されず誤った解釈のまま本人や子供たちに伝わっていき、世はトンチキであふれてしまいました。集まった皆はそれを風刺にした草稿を書いてきて、互いに読んで面白いと笑い合い、次はこれでいこうと盛り上がっていました。しかしてい(橋本愛さん)だけは、これはからかいやおふざけが過ぎると危惧して反対意見を言いました。春町が世を諫めたい思いで描いたと言うと、それはからかいよりも更に不遜や無礼として受け取られる、とにかくこれは出せば危ないと反対しました。ところがそこに次郎兵衛が来て、松平定信が黄表紙を贔屓にしていると聞いた話を伝えるものだから男たちは強気になってしまい、本の製作が始まりました。そして天明改め寛政元年(1789)『鸚鵡返文武二道』が出版されました。
September 18, 2025
-
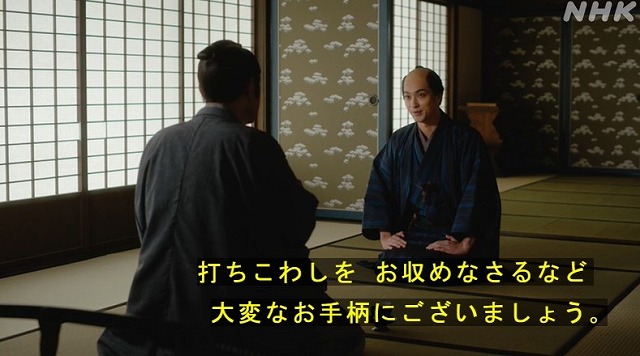
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第34回~「ありがた山とかたじけ茄子」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。1月から始まったこのドラマで9カ月の間、渡辺謙さんが演じてきた田沼意次がこの回でついに退場となりました。うわ~、、なんとも寂しいです。主人公は横浜流星さん演じる蔦屋重三郎です。でも重三郎だけの物語なら、私はたぶん途中で飽きていたことでしょう。それを渡辺謙さん演じる田沼意次が、物語を車の両輪のように安定した形で引っ張ってきたと思っていますから。主人公の重三郎と老中の田沼意次という二つの流れを、脚本の森下佳子氏がまた上手く絡めたなと思います。またこれまでのドラマではほとんど悪者だったというか、田沼意次は良い印象を与える役ではありませんでした。それがこの『べらぼう』の中では、森下氏の脚本と渡辺謙さんの演技と存在感で、見事に変わった感じがします。あの世の意次公も喜んでいることでしょう。史実として田沼意次が領民に好かれていたというのは、『べらぼう』の第17回に出てきました。ただ失脚後の田沼意次は領地没収他をされただけでなく、それまで縁をつないできた者たちが次々と、意次と縁を切って去っていったという史実もあるようです。ドラマではこの回で意次が退場ということで、失脚後の意次の悲哀を描かないようにしたのでしょうか。さて次回からは誰が、重三郎と共にドラマを引っ張っていくのか、興味深いものです。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明7年(1787)5月、江戸で起こった打ちこわしを収束すべく田沼意次から協力を求められた蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、見事に意次の期待に応えた働きをしました。側用人の三浦庄司(原田泰造さん)が店に来て、重三郎は過分ともいえる礼を有難く受け取りました。そして老中職を追われた意次が今回打ちこわしを収束させた手柄でいつ老中に戻れるか尋ねましたが、三浦は言葉を濁すだけでした。意次が老中に復帰できたのか気になっていた重三郎のところに使用人のみの吉が読売を慌てて持ってきて、見るとそこには老中首座に松平定信(井上祐貴さん)の名があるものの意次の名はありませんでした。定信があの8代将軍・吉宗の孫であり老中首座に大抜擢されたことなどが瓦版によって瞬く間に市中に広まり、人々の期待は膨れ上がる一方でした。定信はそういった市中での自分の評判をもれなく把握するために、町人に扮した手下を江戸市中にもぐらせていました。また自分の名を上げるための読売を配ることも欠かさず、次のを腹心の水野為長(園田祥太さん)に命じていました。江戸城では第11代将軍となった徳川家斉(城桧吏さん)の元、首座となった定信が張りきって改革を進めようとしていました。定信はこれまで意次が行ってきた政を「田沼病」と呼び、世の中に賄賂や贅沢がはびこったと痛烈に批判しました。そしてこれを正すために万民が質素倹約に務め、祖父・吉宗が行ってきた享保の世に倣うよう、皆に言い渡しました。しかし定信の考えは、肝心の将軍・家斉には息苦しいもののようでした。「住みよい世にするために、万民は質素倹約に励み、それぞれの分を務めよ。」と読売となって世に出た定信の考えは、贅沢な遊びの象徴のような吉原で育ち、その吉原の皆の協力もあって今の地位を築いてきた重三郎にとっては、うんざりするような話でした。しかし妻・てい(橋本愛さん)は定信の考えに賛同でした。定信の考えを「世のため死ぬまで働け、遊ぶな、贅沢するな」と極端な締め付けだと解釈をする重三郎と、前夫が働かずに店の金で遊興三昧し挙句の果てに店を潰した過去があるていは互いに受け入れられず、大喧嘩となりました。重三郎は狂歌の仲間を吉原に集め、歌麿が描いた美しい絵を元にしてこれまでにない豪華な狂歌絵本を作りたいと皆に言いました。皆は定信が出した質素倹約の通達を気にしながらも重三郎の考えを推し進めようとしていたら、大田南畝(桐谷健太さん)が青ざめた顔をして入ってきました。南畝は若年寄の本多忠籌(矢島健一さん)に呼び出され、南畝の「四方赤良」の狂名のことや南畝の狂歌の才能を松平定信が認めていることを聞かされました。しかしその後に差し出された狂歌を南畝が褒めたことで、本多と松平信明(福山翔大さん)は南畝は政に不満があるとみなしました。自分は罰せられるかもと怯える南畝を見て、戯歌一つでこれは見せしめだと皆は警戒心を強めました。松平定信によって田沼派だった者たちは次々と職を追放されていき、市中には「田沼の悪党ども、腐った役人たち」と読売に書かれて広まっていきました。処罰を受けた役人の中には花魁・誰袖を形式上身請けしてくれた土山の名もあり、ただ事ではないと思った重三郎が吉原に行こうとしたら、すでに大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)が店に来ていました。土山が逐電したことにより関わりのあった重三郎も見せしめで罰せられるかもと、妻のていは最悪の事態を想定しました。一度店を潰したていは「今は己の気持ちを押し通すのではなく店を守って欲しい」と重三郎に考えを伝え、重三郎もようやくていの気持ちを理解しました。松平定信を善とし田沼意次を悪とする、この流れができてしまっている今の世でどうやったら店を守れるのか、重三郎は考えました。考えがまとまり重三郎が意次に会いに行くと意次は重三郎の身を案じていました。「田沼様が作り出した世が好きだった。皆が欲まみれで、いいかげんだったけど、心のままに生きる隙間があった。」と意次に思いを伝えました。そして「自分は田沼様の最後の一派として、書をもって今の世の流れに抗いたい。田沼様の世の風を守りたい。」と決意を述べ、ただそのためにはいったん田沼を貶めると言い、意次に許しを乞いました。重三郎の心の内をわかっている意次は「好きにするがいい。」と温かい眼差しを向け、そして共に手を取って涙を浮かべながら笑い合いました。屋敷の廊下に出ると田沼家では家中の役割を皆の入れ札で決めている最中で、この入れ札を国を挙げてやったら面白いだろうと意次が政について思いを寄せていたら、三浦が呼びにきました。それは意次に対する沙汰を伝えに使者の本多が来たということで、大好きな我が殿・意次がどうなるのか、三浦も廊下で覚悟をして聞いていました。重三郎は本作りの仲間を店に呼び、これからはふざけることも許されないような厳しい世の中になる、世の大方も松平定信を支持していると情勢を伝えました。重三郎は、定信の考えは至極全うだと認めたうえで、そんな世はちっとも面白くない、だからこの流れに書をもって抗いたい、と言い一同に協力を求めました。重三郎が作ろうとしているのは、一つは定信が見逃すことを予想して、極悪人・田沼を叩いて定信を持ち上げる本、そしてもう一つは、倹約が流行りの世の中で物凄く豪華な狂歌絵本を作ることで、歌麿が描いた絵に一首入れて欲しいと大田南畝に頼みました。処罰を恐れて承諾できない南畝でしたが、南畝の作り出した天明の歌狂いを守りたいという重三郎の言葉で意を決し、一首詠みました。それを聞いて皆が感想を言い合い、勇気が出た南畝が「屁だ!」と叫ぶと、皆も次々と立ち上がって「屁」を連呼しながら踊って士気を高めました。松平定信は田沼意次に対し、さらに2万7千石の没収と相良城の取り壊しという厳しい罰を課しました。それは田沼の者を叩けば叩くほど民が喜び自分の評判が上がるという、それこそ定信の私情と欲にまみれたものでした。定信は文武出精の者を取り立てようと水野に調べさせていました。しかし泰平の世が続き、実際はほとんどいないというありさまでした。重三郎は鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)を訪ね、歌麿(染谷将太さん)が心のままに描きあげた美しい絵に、歌麿の門出の祝いとして鳥山の言葉が欲しいと頼みました。鳥山は「硯の魂に相談してみないと」と言いながらも、可愛い弟子の歌麿のために快諾してくれました。しかし12月になり、逐電していた土山宗次郎が捕まって公金横領の罪で斬首に、妾の誰袖は押し込めの刑に、松本秀持は土山の監督不行き届きの罪でで百石没収のうえ逼塞と田沼派への粛清は続いていました。そして迎えた天明8年(1788)正月、重三郎はご政道をからかった3冊の黄表紙ーー朋誠堂喜三二・作『文武二道万石通』、恋川春町・作『悦贔屓蝦夷押領』、山東京伝・作『時代世話二挺鼓』を出版しました。そしてかつてないほど豪華な狂歌絵本『画本虫撰』などが蔦屋の軒先を飾りました。
September 11, 2025
-

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第33回~「打壊演太女功徳(うちこわしえんためのくどく)」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今週はまた改行のタグが乱れ、私のパソから思うように書きこみができず、難儀をしておりました。さて今週の中で印象に残ったのは、各所の人々に見られた「交渉」と「説得」でした。田沼意次(渡辺謙さん)が自分の味方である大名・旗本に、今のこの危機を乗り切るためにできる範囲でいいからと、金と米の供出を訴えます。ひもじい思いや搾取される立場になったことがない彼らは、なぜ自分たちが下々のためにそこまで、と反発します。でもその後で、いよいよ自分たちもこの事態の傍観者ではいけないのだとわかり、立場が下がっても世を憂いて皆に必死で訴える意次の土下座の説得でようやく応じました。中盤の、蔦屋重三郎(横浜流星さん)が義兄の次郎兵衛(中村蒼さん)に助太刀を求め、次郎兵衛の顔で役者の富本斎宮太夫(新浜レオンさん)が動いて、民衆が彼に引き寄せられていく、あの光景は面白いものでした。人間は、不満や怒りといったマイナスの感情をどこかにぶつけているよりも、賑やかで華やかで魅力的な外見や声などに惹かれ、それを追い求めて楽しむプラスの感情を満たしたいのだと思いました。終盤の一橋治済(生田斗真さん)と松平定信(井上祐貴さん)の場面。この二人は互いに、誰かのためではなく、毎度自分の欲のために周囲を動かそうとする雰囲気が出ているので、駆け引きを見ていてもとても疲れる二人でした。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明7年(1787)7月、米があまりにも高値になったうえにお救い米もなく、我慢の限界を超えた民衆が蜂起して江戸の各所で打ちこわしが発生しました。小田新之助(井之脇海さん)は己の主張を幟旗に記し、長屋の皆を引き連れて米を売り惜しみして値を吊り上げた米屋を襲撃しました。義によって天誅を下すと決めた新之助は、打ちこわすだけで盗みはしないよう皆に強く言い聞かせていました。(前回の終わりに「喧嘩をするだけ」とあったので話し合いだけかと思ったら、結局は打ちこわしでした。家の者に危害は加えず盗みもしないけど家中の物を破壊しまくり、この時代の喧嘩はここまで含まれるのですね。)老中たちは北町奉行の曲淵景漸の報で、江戸の各所で打ちこわしが発生したことを知り、襲撃されているのは米を売り惜しみした米屋で、民衆は単なる米欲しさではなく幟を立てて主張をしているとのことでした。田沼意次(渡辺謙さん)は老中たちに打ちこわしが拡大しないよう町木戸を閉め、米屋との喧嘩で召し捕るのはその後にしてはどうかと進言。老中首座の松平康福(相島一之さん)は曲淵にそのように指示しました。康福は打ちこわしのそもそもの原因となっている米がいつ入るのかを意次に問い、(松平定信に裏切られた)意次は返事に窮していたのですが、火急の用が入りその場を一旦退席しました。急ぎ屋敷に戻った意次を待っていたのは蔦屋重三郎(横浜流星さん)でした。重三郎は意次に、意次の嫡男・意知の葬儀で石を投げた男が先日は身なりを変えて奉行所の前で人々を煽っていた、その前は平賀源内の屋敷に武家の姿で出入りしていたことを報告しました。それから重三郎は、頼んだはずの米が出ない理由を尋ね、意次が米の手配に手間取っていると答えるとしばらく考えて、米の代わりに金を出して民衆の気持ちを抑えてはどうかと進言しました。その考えに納得した意次は、重三郎にその内容をまた読売にして配って欲しいと頼み、屋敷に泊まっていくよう言いました。意次は老中・水野忠友に、お救いを要する人数と米と必要な金を見積もるよう、そして田沼派と思われる大名と旗本を一同に集めるよう頼みました。集められた一同に対し、松平康福と水野は出せるだけでいいから米を供出するよう求めましたが、一同はなぜ自分たちが米を出さねばならぬのかと一斉に不満を言いました。しかし町ではまたあの男が人々を扇動していて、召し捕ろうとした奉行所ともみ合いになって同心まで死者が出たと奉行の曲淵から報が入りました。意次は老中に御先手組を出すよう進言、さらに一同には「真にこの騒動を収められるのは“米”!そのために身を切ったならば皆の名は打ちこわしを収めた者として名が残る。」と強く訴え、土下座して皆に協力を求めました。重三郎は打ちこわしがあった町の惨状に心を痛めていました。これは早く騒動を終わらせなければ誰もが不幸だと思い、読売を配るのに何かいい策はないかと考えていました。そこで思いついたのが、義兄・次郎兵衛(中村蒼さん)と役者の富本斎宮太夫(新浜レオンさん)に協力を仰ぎ、賑やかに囃し立てて練り歩き人々の注目を集めることでした。揃いの衣装を妻・ていや母・つよたちに作ってもらい、屋台を出して町に繰り出しました。打ちこわしの喧噪の中で、どこからか聞こえてくる太鼓や鉦の音と人気役者の歌声に、人々は一気に引き寄せられました。重三郎と次郎兵衛の掛け合いで、お上から銀が出てそれが米に代わると聞いた人々は歓喜しました。しかし打ちこわしを扇動していた丈右衛門だった男(矢野聖人さん)はそれを許すわけにはいかず、練り歩く重三郎の背後に忍び寄り七首で刺し殺そうとし、新之助が身代わりに刃を受けました。その後、男が再び重三郎を狙って七首を構えたとき、男の胸に矢が突き刺さり男は倒れました。それは打ちこわしを収束させるために出動した御先手組組頭の長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)の放った矢で、平蔵は騒動を起こさぬよう民衆を鎮めました。主人公の危機一髪を救うヒーローの登場にTVの前で思わず歓声が上がった方も多かったようです。それにしてもこのキメ顔。中村隼人さんをはじめ歌舞伎役者の皆さんは、ここ一番のキメ顔や華やかな演出でホント魅せてくれます。平蔵は刺された新之助を早く医者に診せるよう重三郎に言い、重三郎はこの後のことを次郎兵衛や皆に頼んで行列から抜け出しました。お囃子の楽しさと銀(=米)が出る嬉しさで民衆は今までの不満を忘れ、皆で「銀がふる!」と唱えながら行列に付いていきました。ところが匕首に毒が塗ってあったのか、新之助の具合は急激に悪くなっていき、欲張った米屋やお上はこれで思い知ったと重三郎が励ましても体は動かず、絶え絶えの息の中で新之助は己の最期を悟りました。自分は秀でた才もなく妻子も守れなかった、でも世を明るくするために生まれてきた重三郎は守れて良かったーーそう言葉を残して、ふくと坊が待つあの世に旅立っていきました。さて田沼意次を失脚させた後、一橋治済は松平定信を老中に据えたいのですが、大奥総取締の高岳(冨永愛さん)の同意が得られず話が動かないままでした。そこで治済は大崎(映美くららさん)を呼び、ある物が入った箱を渡して高岳と話をさせたところ、治済の思惑どおり高岳はそれを見て顔色を変えました。それは8年前に10代将軍・家治の嫡男・家基が鷹狩の最中に突然死したときに着用していた手袋で、高岳が家基に贈ったものでした。毒殺が疑われる家基の死で高岳は毒などを仕込むはずもないのですが、潔白の証が立てられない以上、大崎の要求をのむしかありませんでした。白川小峰城にいる松平定信のもとに江戸の打ちこわしが収束したと報が入り、定信は悔しくてたまりませんでした。その頃、江戸では無事に銀の引き渡しが始まって米も集まりだし、また裕福な商人たちの炊き出しも始まって人々は落ち着き、意次は側近の三浦庄司(原田泰造さん)と安堵していました。そんなところに老中・水野忠友が訪ねてきて、大奥の高岳が定信の老中入りを認めたと報せてきました。これで定信は徳川御三家と一橋と、加えて将軍・家斉を後盾にした老中となることになり、さらにその定信は意次を殊の外嫌っているので、意次はこの先はやりにくくなるだろうと覚悟しました。ことが上手く運んだ一橋治済(生田斗真さん)は松平定信(井上祐貴さん)を江戸城に呼び、月が替われば定信が老中になることを伝えました。喜ぶかと思いきや定信はこれを、自分は若輩者で御公儀の仕事をしたことがない、老中になっても思うような政ができない、と最初は辞退しました。しかし話の続きで「老中首座ならばやる」と言いだし、難しいけど治済の力でなんとかするよう迫りました。しばらく考えた治済は言おうかどうか迷ったふりをして、田安家(定信の生家、10万石)を将軍家に献上してはどうか、それならば首座にふさわしいと将軍・家斉(治済の実子)に提案できると定信に返し、予想だにしない展開で定信は何も言えませんでした。喜多川歌麿(染谷将太さん)が重三郎を訊ねると寺にいるとのことで、歌麿は寺に向かいました。自らの手で新之助を埋めた墓の前で重三郎は力無く座り込んでいました。歌麿は墓に手を合わせた後、重三郎に見てもらいたいという「自分ならではの絵」を差し出しました。花や虫が生き生きと描かれたその絵に重三郎はなぜか涙しました。歌麿は「絵は命を写し取るようなもの。いつかは消えていく命を紙の上に残す。命を写すことが自分にできる償いだ。」と思いを語りました。そして新之助の人生に思いを馳せ、惚れた女に出会って子も持てて、苦労の中でも楽しいことが山ほどあって、最後は世に向かって主張して己の思いを貫いた、だからとびきりいい顔して死んだだろ?と重三郎に尋ねました。たしかに新之助は今までで一番いい顔していた、それを歌麿に写してもらいたかったーーそんな思いがあふれて重三郎は歌麿の胸で男泣きしました。
September 4, 2025
全4件 (4件中 1-4件目)
1