2025年06月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-
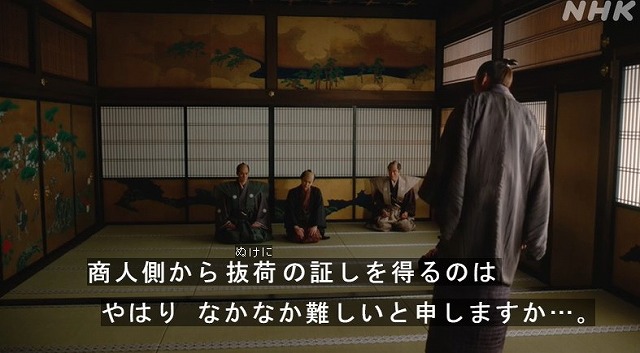
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第24回~「げにつれなきは日本橋」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。この回は、主人公・蔦屋重三郎(横浜流星さん)と、今は彼を嫌っているけどいずれ妻となるてい(橋本愛さん)がどのように接点を持つのかを注目して見ていました。ていを説得するために重三郎は手立てとなる情報を集めるのですが、でも結局は自分の耳でていの心情を直に聞ける場面がありました。重三郎が心の奥に残る花魁・瀬川への思いを一区切りさせ、ていを新たな人生のパートナーとさせる強力な要因は何か。それは本が世の中で大きな役割を持っていて、身分の高き低きに関わらず、本が人々に知識を与え、世の中をもっと豊かにしていくという思いが互いにあると確信したことで、まさに「同志」を見つけたという感じでした。自分と距離をとる相手が、心情を変化させていくきっかけとなる出来事とは何か、その後の流れはどうなのか。もう国語の物語文を見るような感じです。森下氏の脚本力に期待し、次回の展開を楽しみにしたいと思っています。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明3年(1783)、蝦夷地を上地するための手立てを平秩東作(木村了さん)に探らせていた田沼意次(渡辺謙さん)と嫡男・田沼意知(宮沢氷魚さん)は、上方から戻った東作の報告を受けていました。東作によると、商人側から抜荷の証を得るのは難しい、商人たちと深い話をするとこちらの動きが相手に漏れてしまう、とのことでした。結局、八方塞がりで何も実りがなかったことを、側近の土山宗次郎(栁俊太郎)と東作は意次に詫びていました。さて日本橋への進出を目指す蔦屋重三郎ですが、扇屋宇右衛門からまずは店を買って押さえることが大事だから亀屋を表に出して店を買うよう助言されました。そこで日本橋には吉原者は立ち入ることができないので、買い取りの交渉は亀屋に任せたのですが、すぐ嘘を見破られてしまいました。その後、商人たちの会合で鶴屋喜右衛門(風間俊介さん)は安永7年(1778)に出された「吉原者は見附の内の家屋敷を買えない。市中の方も売れない。」というお達しを皆に再確認させ、日本橋に吉原者が入ると町の格が下がるとも言いました。ただ、てい(橋本愛さん)が皆に詫びて今後のことを頼むときに、韓非子の一節を例えに出して話し始めたら皆は面倒くさそうな嫌な態度になり、話の途中で鶴屋がさえぎってしまいました。亀屋の件が失敗になったので次の手をどうしようか、親父衆は考えていました。若木屋与八(本宮泰風さん)が「丸屋のおかみさん(てい)が欲しくてたまらないものはないか。」と言うと、りつ(安達祐実さん)が「男?」と言ったことで皆は妙に納得してしまい、蔦屋重三郎(横浜流星さん)自身がていに色仕掛けをすればいい、という意見にまとまってしまいました。重三郎が店に戻ると東作が来ていたので、丸屋のていとはどんな人なのかを訊いてみましたが、東作もよく知りませんでした。でも絵師の北尾重政なら知っているかも、と話し始めたらちょうど時間がきたので、東作は吉原のどこかに行ってしまいました。東作が向かった先は、花魁・誰袖(福原遥さん)のところで、客として松前廣年(ひょうろくさん)が来ていました。誰袖は東作を廣年に「琥珀の取引に詳しい人。」と紹介しました。でも生真面目な廣年にはご法度となることはやはり気が進まず、何より兄・道廣に知られることを酷く恐れていました。誰袖がいざとなれば私のせいにすればいいと言うと廣年はようやく安心し、東作の話を聞く気になれました。その様子を座敷の裏にある部屋から覗いていた田沼意知と土山宗次郎は、廣年では大胆なことができなくてどうも頼りないので、いっそ藩主の松前道廣が抜荷の話に乗ってこないかと期待しました。その松前道廣(えなりかずきさん)ですが、余興では相変わらず家臣を鉄砲の的代わりにして遊んでいました。田沼意次は三浦を使って廣年が吉原に出入りしていることを兄であり藩主の道廣に知らせると、道楽で藩の金を無駄遣いをしているのかと道廣は激しく怒りました。鉄砲を向けられた道廣は誰袖に言われていたように誰袖のせいにして兄に許しを乞いましたが、恐怖で発砲される前に気絶してしまいました。丸屋を買うためになんとか女将のていを説得できないかと思う重三郎は重政に会って、ていのことを詳しく知る人がいないか訊ねました。しばらく考えた重政は重三郎に、ていが漢籍を習った寺に行ってはどうかと助言。重三郎がその寺に行ってみると、ちょうどていがいて住職の覚圓(マキタスポーツさん)と何やら話をしているところでした。ていは処分する店の本を寺に寄付し、寺に来る子供たちの手習いに役立てて欲しい、そうすれば本は生きる、と住職に頼んでいました。ていの話を聞いたときに重三郎はふと平賀源内の言葉を思い出し、自分とていは同じ志を持っているように感じました。それからていの身の上話を聞き、重三郎はていの望みがわかった気がしました。重三郎が店に戻った夜、駿河屋市右衛門(高橋克実さん)と扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が来て「明日、日本橋に乗り込む。」と言いました。親父衆はツテを辿って丸屋の証文を買いあげてあり、これで店の明け渡しを迫る、上品な手じゃないけど他の買い手が決まる前に、ということでした。翌日、親父衆と重三郎は「吉原者出入無用」の立て札もお構いなしに、日本橋の通油町に乗り込んでいきました。(並んだときのこの微妙な位置関係がいいですね。吉原の総代表の扇屋が先頭で、半歩後ろには駿河屋と、和泉屋の葬儀での出来事を一番怒っていた丁子屋長十郎(島英臣さん)、そして他の皆が続くという並びです。そして、ただ並んで歩くだけのシーンがこれほど迫力があってカッコイイとは。ベテラン俳優の皆さんが「乗り込む」という場面の心情や振る舞いを自然と表現できるからでしょうね。)そのころ丸屋では柏原屋との間で売買契約を進めるところで、親父衆はちょうどその時に中に乗り込んできました。鶴屋喜右衛門が吉原のやり方を非難した時、重三郎は自分なら丸屋の暖簾は残すと言い出し、その意味を話すために前に進み出ました。重三郎は丸屋と蔦屋を一つの店にしてはどうかと提案、そして「本当は店を続けたいのでは?」とていに問いかけました。ていはその話は断ったのですが、ならばと重三郎は自分と一緒になるのはどうかと言い出し、建物の売り買いは禁じられているが縁組はお達しに背かない、店を一緒にやるのは当たり前とていに迫りました。しかし縁組の話はていをかえって怒らせてしまい交渉は決裂、吉原の皆はもう引き下がるしかありませんでした吉原に戻った皆は、作戦の練り直しをしました。重三郎の過去に自分の部屋の花魁・瀬川とのことがあったせいか松葉屋半左衛門(正名僕蔵さん)は、なぜ店を一緒にやろうと言い出したのかを訊ねました。ていは自分が店を潰したことを不甲斐なく思っているようだから店を続けられるなら話に乗るかと思った、と重三郎は答えました。するとりつが芸者衆から聞いた噂で、ていの旦那は金目当てでていに言い寄った、それに気付かなかったていが世間体や親のことを考え夫婦になったけど、旦那はすぐに吉原通いを始めて散在して借金までした、という話をしました。そしてりつは重三郎に「独り身の自分につけこむあんたは、ていから見たら前の旦那と同じに見える。」と意見してやり、重三郎は自分の失敗を痛感しました。一方、蝦夷地を上地するために花魁・誰袖を使う田沼意知は、松前廣年の動きがあれからないことが気になっていました。すると女将の志げが慌てて部屋に駆け込んできて、道年だけでなく藩主の道廣も一緒に来たと言い、意知はすぐに隣室に身を隠しました。道廣ははじめは機嫌よく遊んでいたのですがじきに人払いをし、主人の大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)を呼びつけました。道廣は市兵衛に、誰袖の琥珀の直取引を企みを知っていたかを詰問、市兵衛はそこまでの事態は知らなかったと道廣に許しを乞いました。しかし意外なことに道廣は、いっそのこと直取引(=抜荷)を松前家と吉原でやって琥珀で大儲けしないか、と持ち掛けてきました。思いがけない好機が来たと、隠れている意知は息をのみました。さてその頃の江戸ですが、夏になっても肌寒いおかしな気候が続き、また地鳴りもよく起こっていて、人々は不安を感じていました。そんな中、重三郎が出かけようとしたときに柏原屋与左衛門(川畑泰史さん)が店を訪ねてきて、浅間山が火を噴いているらしいと教えてくれました。そして柏原屋は重三郎に、自分から丸屋の店を買わないかと持ち掛けてきました。
June 26, 2025
-
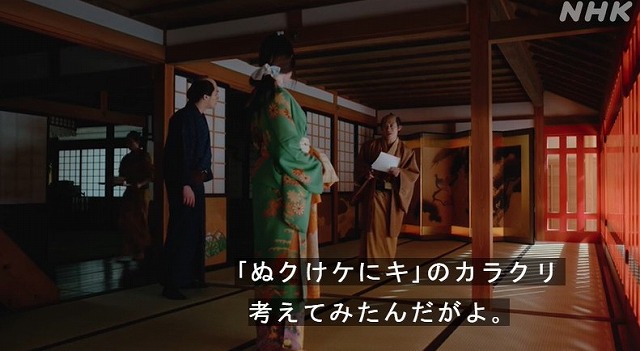
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第23回~「我こそは江戸一利者なり」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、一番感じたのは「人が大きな決断をする時」ということでした。出版の仕事が波に乗ってきた主人公・蔦屋重三郎(横浜流星さん)は、日本橋に店を構えてそこから本を出したいと思い描きました。しかし、大金が必要なこと、長年の吉原のしがらみ、吉原に店を出してやると声がかかる話は直感的に危ないと感じて引き受ける気になれない、そんな状態が続いていました。でも運命を切り開いて進んでいく者には、ちゃんとその道と機会が用意されているいのでしょうか。重三郎が駆け出しの頃から何かと相談に乗ってくれ、助言もくれていた須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)が、この時も日本橋というい土地の価値を教えてくれて、さらに迷う重三郎を励ましてくれました。大きな賭けで、もし失敗したらという不安や恐れは、「この先何がどうなっても必ず重三郎の傍にいる」と歌麿(染谷将太さん)が約束してくれた事で和らぎ、心の支えを改めて確認しました。でも重三郎の気持ちを固めたのは、世間で冷遇された吉原の親父衆たちの姿でしょうか。自分のことと同じくらいに相手を思う重三郎だから、厳しい世界だけど自分を育ててくれた親父衆を侮辱する世の中を見返してやる、と反発もエネルギーになっていたと感じました。さて、そんな重三郎の前進していく話の片隅で、皆とは違って一人調子の波に乗れず、あきらめや自己卑下のような負の感情を出していた佐野政言(矢本悠馬さん)に、つい注目してしまいました。史実では佐野は間もなくとんでもない事をしでかすのですが、万事控えめで親思いのあの優しい男が、どんな感情の流れであの大事件を起こすのか。ドラマの展開が楽しみであります。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明2年(1782)暮れ、吉原の者も仲間に欲しい田沼意知(宮沢氷魚さん)は蝦夷地を上地する計画を蔦屋重三郎(横浜流星さん)に話し、一緒に仲間になるよう誘いましたが、重三郎はこの話を断りました。この話には花魁の誰袖(福原遥さん)も抜荷で一枚かんでいると重三郎は感づき、危ないからやめさせようと誰袖に忠告したところ誰袖は話をはぐらかし、さらに主人の大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)までこの話に乗り気になっていました。事がうまく運べば、誰袖は好きな男(意知)に身請けしてもらえ、大文字屋には大金が入るので、二人は綿密に計画を練っていました。天明3年(1783)大田南畝(狂名・四方赤良)が世間で大人気となり、ついでに重三郎の名も世間に広まりました。耕書堂では狂歌の指南書『浜のきさご』は飛ぶように売れ、その他の品もとても評判の良いものでした。重三郎は江戸一の目利きの「利者」と呼ばれるようになり、贔屓筋の付き合いや出版の各所での打ち合わせ等で毎日多忙を極めていたので、ふじ(飯島直子さん)たち吉原の女将たちが店を手伝ってやっていました。さてこちらは田沼意次(渡辺謙さん)ですが、自分の理想とする政を推進するためにも、幕府内の要職を自分の身内や考えの近い者たちで固めていました。また意次の嫡男・意知を特例で奏者番に抜擢するなど、意次の勢いは周囲も圧倒されるほどでした。一方で意次に目をかけてもらえなかった一部の者たちは狂歌をたしなみ、意知の側近の土山に近づいて繋がりを作ろうとしていました。土山邸の酔月楼で催される宴会に顔を出した長谷川平蔵宣以(中村隼人さん)や佐野政言(矢本悠馬さん)らは、350俵の組頭の屋敷とはとても思えぬ豪華な屋敷と宴会にただただ驚くばかりでした。意次の覚えがめでたければこういうこともできるのかと感心しつつ、どうやって土山に近づこうかと考えていたら、平蔵は重三郎の姿を見つけました。平蔵は自分たちを土山に紹介してくれるよう頼み、重三郎は快諾。土山がちょうど大田南畝(桐谷健太さん)と一緒にいたので重三郎は挨拶に行き、平蔵らを紹介しました。ただ平蔵の名を聞いたときに南畝が平蔵の父の話で盛り上がってしまい、うまく自己紹介ができなかった佐野は、自分にはこういう場は合わないからと一人先に土山邸を出て帰っていきました。田沼意知の配下の土山宗次郎は重三郎を仲間に引き込もうと耕書堂を日本橋に出店してはどうかと話をもちかけていました。重三郎はその話に魅力を感じて気持ちが揺らぎましたがそれは断りました。一方、大文字屋と誰袖は松前廣年(ひょうろくさん)になんとかして抜荷をさせようと、いろいろと話をもちかけていました。誰袖はおねだりやら涙目やらであの手この手で廣年に執拗に迫りました。廣年には考えてみるとまで返事をさせましたが、誰袖の思いは万事上手くいけば身請けしてもらえる田沼意知にありました。重三郎は吉原の方から、手間の割には利益が少ない仕事を大量に頼まれていて、渋々引き受けて進めていました。重三郎が日本橋に出店する夢を迷いも含めて思い描いていたら、日本橋の白木屋彦太郎(堀内正美さん)から呼び出しがありました。これはいい話かと重三郎が勇んで行ったら逆で、西村屋の『雛形若菜』のために吉原はもっと協力するように、という話でした。納得がいかない重三郎は、自分たちには何が足りないのかを彦太郎に訊ねました。彦太郎は、耕書堂の錦絵は江戸の外では売れていないことを指摘しました。鶴屋や西村屋には諸国の本屋から大口の買い付けがある、その後は地方の本屋や小物問屋にまで広まる、と説明しました。しかしそう言われても重三郎はなぜか強気で、それならばあっという間に全国に広めてみせると彦太郎にタンカを切りました。さて、錦絵を全国に売ってみせると言ったもののどうしたらと重三郎は考え、まずは江戸市中にやってくる行商人に声をかけて商売をしてみましたが、誰にも相手にされませんでした。そこで須原屋市兵衛(里見浩太朗さん)に頼み込んでみましたがやはり断られ、でも市兵衛は代わりに重三郎にこの先のことの助言をくれました。「日本橋に出ればこの絵は一発で方々の国に出回ることになる。諸国の商人は『日本橋に店を出せるとなれば一流もの。そこの品物なら間違いない』と買っていく、買ってこい、となる。日本橋に出ればこの絵の話はあっさりと先に進む。他の狂歌本、青本、富本本も流れにのるし、一作につき桁違いの数が出る。」そう聞いても重三郎はまだ決断できませんでしたが、市兵衛は「それでも俺はお前に日本橋に出てもらいたい。平賀源内のためにも。」と重三郎の気持ちを強く後押しをしてくれました。市兵衛の話が頭から離れないままの帰り道、重三郎は和泉屋の店の前を通り、葬儀に向かう親父衆の姿を見送って、遠くからそっと手を合わせました。店に戻ってから、これまで自分が作ってきた本を手に取り、それまでの様々な出来事を思い返していたら、歌麿(染谷将太さん)が声をかけてきました。あの時無理やり和泉屋の荷物持ちをして田沼邸に入りこんで、首尾よく意次と話ができ、意次から言葉をもらえて、それが全ての始まりでした。そして源内と出会い、単に本を売るだけではない大きな志をもらいました。しかし、そんな思いにふけっていたら親父衆が大雨の中をずぶ濡れになって帰ってきて、何かあったのかと重三郎は心配になりました。和泉屋の葬儀の時、親父衆は他の参列者から「吉原もん」と蔑まれ、畳の外の縁側に追いやられる冷遇を受け、雨に打たれて耐えていました。親父衆は「いつものこと」と受け流していましたが、そんな親父衆の背中を見た重三郎は、自分はこのままではいけないと強く思うようになりました。もし失敗したらと不安もあるけど、重三郎の中で日本橋に出る思いが徐々に固まりつつあった時、歌麿が「何がどう転んだって俺だけは隣にいるから。」と言ってくれ、重三郎はようやく決心ができました。翌日、親父衆は集まって世間に対する自分たちの思いを語り合っていました。「貧しさゆえに死ぬしかない子をとにかくここで食わせてやっている。非難するだけの奴らはそんな子らに何かしてやっているのか。」と丁子屋長十郎(島英臣さん)は怒りが収まりませんでした。そんな時、重三郎が中に入ってきました。重三郎は親父衆に改めて、日本橋に出店したい旨を強く訴えました。怒り心頭になった駿河屋市右衛門(高橋克実さん)は重三郎を激しく折檻して階段落としまでしましたが、重三郎の決意は固いものでした。重三郎は階段を一段ずつ上がりながら市右衛門に訴えました。「俺は忘八だけど、俺ほどの孝行息子もいない。吉原もんが日本橋の真ん中に店を構える。そこで商いを切り回せば誰にも蔑まれないどころか見上げられる。吉原は親無し子を拾ってここまでしてやってる。吉原の門は懐が深いと。俺が成り上がればその証になり、この町で育ててもらった拾い子の大きな恩返しだ。」そう言って重三郎は改めて親父衆に「俺に賭けてください。俺には歌麿がいる。まあさん、春町先生、赤良先生など日の本一の抱えがある。」と訴えました。「俺に足らないのは日本橋だけ。」ーー重三郎の確固たる熱い思いを親父衆はしっかりと受け取り、認めてやりました。そして日本橋の丸屋が売りに出されると情報が入り、どうやったら吉原もんに店を売ってくれるか、それぞれが知っている話から皆で考えていました。「吉原もんには市中の屋敷は売るな」というお定めがあるからやはり無理かと皆があきらめかけた時、扇屋宇右衛門(山路和弘さん)が一人の男を同行して自信をもって部屋に入ってきました。
June 19, 2025
-
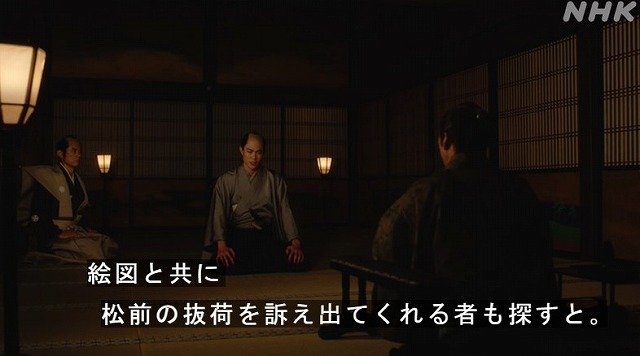
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第22回~「小生、酒上不埒にて」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回は、ひと悶着起こして一人卑屈になって籠ってしまった恋川春町(岡山天音さん)を心配する周りの皆が、あの手この手で励まして春町を迎えようとする温かい優しい時間と、蝦夷地を上地するために父・田沼意次(渡辺謙さん)に代わって暗躍する嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)と、意知に無理やり絡んでくる花魁・誰袖(福原遥さん)が起こす緊張の時間が交互にあったように感じました。自分がこの家を継ぐと決意した者は、大一番を迎えた時に自分の力量を試したくなるのか、あるいは周囲の家臣たちに自分の存在を認めさせたいと心のどこかで思うからなのか。これ以上手を出すなと案じる父・意次の思いをよそに、意知はニヤリと不敵な笑みを浮かべる場面もありました。たしかに古今東西を問わず、跡を継ぐ者が常に安全圏にいて、泥をかぶらない苦労知らずだと、下の者は自分に付いてこないかもしれません。とはいえ勇み足をして万一失敗すると、後継者であるがゆえに、お家や親に大きな負の影響を与えるものです。これは単に、敬愛する父・意次のために意知が頑張る、という気持ちから起こっている行動だと願うのですが。こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 天明2年(1782)蝦夷地の上地を狙う田沼意次(渡辺謙さん)がそのことを密かに進めようとしていたら、話をかぎつけた吉原の花魁・誰袖が意次の嫡男・田沼意知(吉原では花雲助;宮沢氷魚さん)に近づいてきました。誰袖は吉原に来る客から秘密を探るから自分を身請けしろと迫りますが、意知はそれを断っていました。意知は上地を強行するために松前藩との抜荷の証を探していて、土山宗次郎の報告によると平秩東作が上方を探っているとのことでした。また意知は『赤蝦夷風説考』を書いた工藤平助を呼び、松前家の当主・道廣を激しく非難する湊源左衛門に対する工藤の考えも確認していました。さて蔦屋重三郎(横浜流星さん)ですが、先日の狂歌の会でいろいろとうっ憤がたまっていた恋川春町(本名は倉橋格;岡山天音さん)が座敷で暴れてしまい、果ては自分の筆をへし折ってもう自分は何も創らないと言って一人出て行って しまったことが気になっていました。同じく気にしていた歌麿からも促され、重三郎は春町の家を訪ねました。重三郎は、あの時のことは誰も気にしていない、北尾政演が気に食わないのもわかるけどいきなり怒り出した春町だって悪い、政演を盗人呼ばわりするのは言い過ぎ、などと春町をたしなめたり新作を促したりしました。でも今の春町には重三郎の言葉を受け入れる余地はなく「俺は戯けることには向いてないのだ!」と怒って出ていってしまいました。店に戻った重三郎は歌麿(染谷将太さん)に春町のことを相談しつつ、次の仕事となる朋誠堂喜三二の新作の『長生見度記』の絵付けを頼んでいました。春町風に描くように言われたその新作は書き出しが「友人 恋川春町が作りし無題記を読みつつ」とあり、喜三二の春町への思いを歌麿も感じていました。そんな時、花魁の誰袖が重三郎を呼んでいるとのことで、重三郎は大文字屋まで出向きました。重三郎が大文字屋に入ると誰袖(福原遥さん)が飛びついてきて、抜荷の証を立てるならどうするか?なんて話をいきなりし始めました。誰袖は退屈しのぎに青本を書くネタだと言い、そんな話をしていたら女将の志げ(山村紅葉さん)が差紙が入ったと大文字屋市兵衛(伊藤淳史さん)のところに持ってきました。相手は松前藩の家老で当主・道廣の弟で廣年、格のある花魁を所望しているとのことでした。田沼意知のために松前藩を探ろうとしている誰袖はその話を聞き、願ってもない好機とばかりに自分が座敷に出ると名乗りをあげました。松前藩の家老・松前廣年(ひょうろくさん)は物静かで控えめな男で、座敷遊びに誘われても加わることなく皆の様子を眺めていました。誰袖は初回だけど特別と言って話しかけ、廣年が幼い頃に江戸に出された話とか、金はあまり自由にならないことなどを聞き出していました。誰袖は廣年が手首につけている美しい石を目ざとく見つけ、廣年の手をとりこの石は何なのかと色仕掛けで迫りました。歌麿は朋誠堂喜三二(本名は平沢常富;尾美としのりさん)の新作に絵付けをするなら喜三二と打ち合わせがしたいからと重三郎に許しをもらいました。でもその実は、自分と同じく春町のことが気になる喜三二に同行してもらって、二人で春町に会いに行くことでした。喜三二は自分の新作は春町の『無題記』にかぶせた物だと言い、歌麿もこれに付ける絵は重三郎の指図で春町風になると言い、その許しを求めました。歌麿に勝手にしろと言う春町は、政演の『御存商売物』は自分の『辞闘戦新根』よりも百倍面白い、自分は絵が下手だ、世はもう自分を求めていないだろうとすっかり卑屈になっていました。喜三二と歌麿は、春町の作品が好きだ、春町がもう書かなくなったら寂しい、春町の作品のあの場面が好きだなど、二人で春町を説得していました。春町に復帰して欲しいと願う二人の熱意が伝わったのか、春町は自分のような辛気臭い男がいてもいいのかと、涙を流してうなだれていました。その頃、重三郎の店では狂歌の会の大田南畝らが来ていて、春町が辞めると重三郎から聞いてあの晩のことを話していたのですが、誰も全く気にしてなく、それどころか南畝は春町の皮肉の上手さを感心していました。そんな話をしていたら喜三二と歌麿が春町を連れて店に入ってきました。元木網が朱楽と南畝を連れて店を出たら春町は改まって姿勢を正し、自分の方から重三郎に詫びを入れようとしたら、先に重三郎が話し始めました。重三郎は折れた春町の筆を返し、もう一度うちで書いて欲しいと頼みました。南畝が春町は皮肉を言う才があると言ってたと伝えると、春町は文字を何かの形に並べたもので自分の思いを書いたと、紙を懐から取り出して見せました。重三郎が感心して笑うと春町は『小野篁歌字尽』を取り出し、このような形で作ったらどうかと自分から提案しました。そう聞いた重三郎は、ならばこれを吉原を舞台にして作ってはどうかと提案し、早速春町のネタ集めが吉原で始まりました。さて誰袖ですが、松前廣年を篭絡してあの石の飾りを手に入れ、文とともにこれが抜荷の証拠だと意知に送り付けてきました。しかし意知は、オロシャ産の物を持っているだけでは抜荷の証にはならないと誰袖に返却し、誰袖にもう間者ごっこをやめるよう言いました。しかしそう言われても誰袖はまだ、自由に使える金が少ないけど本音は吉原でもっと遊びたがっている廣年に抜荷をさせてはどうか、と言ってきました。誰袖は身請けしてくれるなら自分が実行すると言い、意知は危険だからと警告しましたが、どうしても意知に身請けして欲しい誰袖は引きませんでした。誰袖の覚悟を感じた意知は自分の本名を名乗り、見事抜荷の証を立てられたら誰袖を落籍する、と約束しました。さて年も暮れになり、重三郎は世話になった戯作者や絵師や職人たちを労う会を開き、集まった皆はご機嫌に会を楽しんでいました。酒を飲みながら互いに作品を見て感想を言い合うそんな中で、春町が作った『廓ばかむら費字盡(さとのばかむらむだじづくし)』を読んでいた北尾政演(古川雄大さん)は、自分はこっちがよかったと周囲にもらしていました。その様子を離れて見ていた喜三二が春町に徳利を持たせて政演と話してきたらどうだと促すと、春町はバツが悪そうにしながら政演のところに行きました。政演が顔を合わせにくそうに春町の本が面白いと感想を言うと、春町は政演に「いつかそれをかぶせた、もっと深く穿った目で見たそなたの『費字盡』を読みたいから書いてくれ。」と言いました。そして「盗人呼ばわりしてすまなかった」と政演に手をついて謝りました。頭を下げて謝る春町、でも政演のほうは謝られる意味が分からないとばかりの態度で、重三郎の言ったとおり誰も気にしていないとわかり、春町は安心して政演の隣りに座り仲直りしました。しばらくしたら次郎兵衛(中村蒼さん)が三味線を鳴らして出てきて、何事かと思ったら二階から春町がさらし姿で降りてきました。そして皆の前で平賀源内が書いた『放屁論』にでてくる「花咲男」を名乗って「へっぴり芸」を始めました。先日は皆を不快にさせてしまったからそれを挽回しようとしたのか、慣れないお笑い芸を一生懸命やる春町を皆も温かく見守り、そのうち皆も一緒に音頭をとって踊り出しました。宴会を楽しむ皆より重三郎が一足先に退出した時、店の外で以前「花雲助」を名乗っていた侍と会い、重三郎は声をかけました。内密に話ができるようお稲荷さまのところに案内し、重三郎はその時ようやく花雲助が田沼意次の嫡男・意知であることを知りました。意知は周囲の気配を確認したうえで、自分たちがこれから蝦夷地を上地しようとしている、これは源内が最後に口にしていた試みだと重三郎に話しました。「蝦夷地を上地し、国を開き、鉱山を開き、幕府の御金蔵を立て直す。幕府を今以上に揺るぎなき中央の府とし、諸国ももっと豊かな土地に育て上げる。」そう聞いて源内に思いを馳せる重三郎に、意知は仲間になるよう誘いました。
June 12, 2025
-
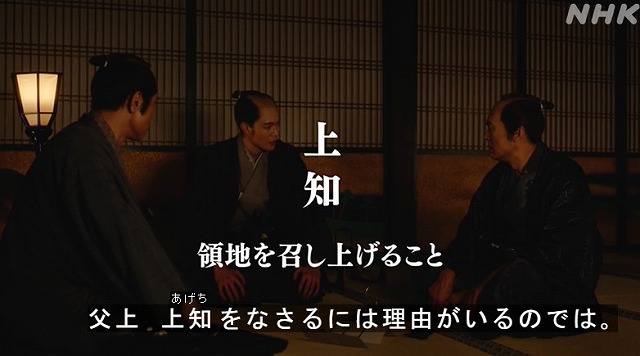
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第21回~「蝦夷桜上野屁音」
2025年NHK大河ドラマ 『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 の感想です。今回、興味深かった展開は、田沼意次(渡辺謙さん)の松前藩の上地の話で、花魁と言えど女郎の誰袖(福原遥さん)が絡んでくるとは、という部分です。まあ現代でも一流の夜の店では、世の中を動かすような大物が出入りするから、誰と誰がつながっているとか、他言無用ではあるけど話は聞いてしまうから、情報は持っているんですよね。ただ見ていてよくわからなかったのは、あの座敷で志げ(山村紅葉さん)が盗み聞きをしていたのはシーンであったけど、田沼意知(宮沢氷魚さん)が抜荷の証拠を探しているのを誰袖がどうして知っていたのか、という部分でした。田沼サイドの情報を漏らす誰かがいるのでしょうか。(ところで誰袖、今まであれだけ蔦屋重三郎(横浜流星さん)にお熱だったのに、急に意知に心変わりしたのでしょうか?) さて、松前道廣役で登場したえなりかずきさん。今までの子役時代からは想像できないワルでご登場です。言い方は優しいけど、やってることは鬼なんですよね。しかもあの場にいた者は意次を除いて皆、あの余興を見て笑っていました。恐怖におびえる妻と許しを乞う夫を見て、心から愉快に思って笑っていた者、あるいは上の者に追従して笑っておかないと次は自分が酷い目に遭うからやむなくそうしている者、いろいろあったと思いますが。ところで、あの射撃の場面についてです。私、射撃場で電子標的の銃で遊んだことがあるのですが、約5kgの長い銃を持ち上げて微動だにせず固定するのはけっこう力が要ります。私の場合、上半身の筋力で銃をしっかり固定できなくてまず持っただけで微動。撃つ前は照準器で合わせて真ん中を狙っていても、撃った瞬間に手がブレて10cmくらい的を外します。だからあれを見ていた者が道廣の銃の腕前を褒めていたのも、そういうことでもあると思いました。こちらは興味深かった情報です。北斎の代表作「冨嶽三十六景」を出版したのは西村屋、広重の「東海道五十三次」出版には初め鶴屋が関わっていました。(途中から保永堂の単独出版に。) ⇒ ⇒ こちら こちらでは様々な意見がでていて参考になります。 ⇒ ⇒ #大河べらぼう #べらぼう 安永10年(1781)秋、田沼意次(渡辺謙さん)は側近の三浦庄司(原田泰造さん)から蝦夷地を幕府の天領にしてはどうかと進言を受けました。三浦は先日、伊達家家臣の工藤平助を訪ねた折に平助・著の「赤蝦夷風説考」を読んでオロシヤが日の本と交易をしたがっていることを知り、また広大な蝦夷地には数多の金銀銅山が眠っているらしいと情報を得ていました。主君・意次がその話に興味を持つと、三浦はさらに松前藩から蝦夷地を召し上げ天領にしてはどうかと進言し、意次は早速動こうとしました。ただ嫡男の田沼意知(宮沢氷魚さん)は上地は慎重に行ったほうがいいと進言し、自分が上地できる理由を探してくると父を制しました。一方、蔦屋重三郎(横浜流星さん)は『雛形若菜』を出す西村屋を吉原から追い出し、歌麿が描いた『雛形若葉』で歌麿を売り出して、錦絵でも自分の耕書堂の名を上げようとしていました。ところが現実は、年が明けてから西村屋の『雛形若菜』は売れに売れ、耕書堂の『雛形若葉』は二番煎じと人々の評判は悪くさっぱり売れませんでした。また重三郎が絵師として重用していた北尾政演(山東京伝)が鶴屋から出した『御存商売物』の青本が世間で大人気になっていて、吉原の親父衆や重三郎に出仕した人たちはカンカンに怒っていました。そしてこの状況でもついふざけてしまった重三郎は、その後で駿河屋市右衛門(高橋克実さん)から階段落としのお仕置きをくらいました。重三郎が店に戻ると大田南畝と朱楽菅江が来て、これから旗本の土山宗次郎(栁俊太郎)の花見の会に行くと言いました。土山に呼ばれている狂歌の会の人たちが続々とお座敷に向かう中、平秩東作が「花雲助」と名乗る男を連れていました。会が始まりしばらくすると花魁の誰袖(福原遥さん)は初めて見る客の花雲助(実は田沼意知)が気になって仕方がないようでした。そして湊源左衛門が遅れて入室し花雲助の隣りに着座したとき、誰袖から合図された女将の志げがさりげなく湊の背後に移動して話を聞いていたようでした。湊は花雲助に挨拶をした後、蝦夷地を松前藩より召し上げて欲しいと、さらに松前家当主の松前道廣のことを鬼と呼びその悪行を語っていました。松前道廣(えなりかずきさん)は一橋治済に招かれた酒席の場で余興として、粗相をした家臣の妻を庭の木に縛り、その周囲に置いた皿を座敷から鉄砲で打ちぬくという恐ろしい遊びを楽しむような男でした。そしてその場にいた一橋治済や薩摩の島津重豪は、それをやめさせるどころか笑ってその余興を見物し、道廣の銃の腕前を褒めていました。治済からその余興を勧められた田沼意次は、自分の腕前では的を殺めてしまうと固辞しましたが、道廣は的は当家からいくらでも出すと笑っていました。意次はその時の様子を徳川家治(10代将軍;眞島秀和さん)に報告しました。家治は一橋が外様大名と仲が良いのは知れたこと、機嫌良く遊んでいる分には構わないと軽く受け止めていました。意次は家治に、実は松前藩の上地を考えている、そこで港を開きオロシヤとの交易を始め、その先の蝦夷地で金の採掘をすれば幕府の御金蔵を根本から立ち直せる、と考えを伝えましたが迷いもありました。しかし家治は「やるべきである。どんな者が将軍になっても揺るぎない幕府を作る。そのために入用なことであれば。」と意次の考えに同意しました。さて重三郎ですが、大田南畝(桐谷健太さん)らが花見の会の後に店に寄ってくれた時に、『雛形若葉』の失敗などのここの所の低迷を思い、自分は老舗の本屋と比べていろいろ足りてないと本音を漏らしました。でもそう聞いて南畝は、「けど、そこがいいところ。だからこそ新しい発想ができる。細見が薄くなったときは『そうきたか!』と思った」と。一緒にいる朱楽菅江(浜中文一さん)と元木網(ジェームス小野田さん)も、これまでの重三郎の出した本で南畝と同じように思ったと言ってくれました。皆からそう言ってもらえて重三郎も気を取り直し、少し考えて南畝に青本を、菅江や元木網には狂歌の指南書を書いて欲しいと依頼しました。同じ作者が狂歌と青本を書く、狂歌が人気になれば指南書を求める人も増える、という重三郎の発想に皆は感心し、重三郎もだんだん強気が戻ってきました。重三郎は『雛形若葉』を改めた錦絵を出そうと思い、親父衆に相談しました。前回の失敗をふまえることを伝え、承認をもらいました。そのころ歌麿(染谷将太さん)は、西村屋の錦絵のような色がどうやったら出せるのかずっとわからなくて、北尾重政から絵師と本屋が摺師にきちんと「指図」を出せるかどうかで仕上がりは全く変わると教わり、やっと納得のいく色が出せて喜んでいました。そうしていると重三郎が話し合いから浮かない顔をして戻ってきました。その理由は、今度出す錦絵は歌麿でなく政演になったからで、重三郎は手をついて歌麿に深く詫びました。でも歌麿はその件を快く了承してくれ、さらに政演が手が回らなくなった他の仕事を自分が引き受けるとまで言ってくれました。可愛い義弟であり、いつも自分の無理をきいてくれ申し訳なさもある歌麿をこれからどんどん売り出すと、重三郎は固く決意しました。田沼意次は松前藩の上地については将軍・家治から許しが出たと嫡男・意知と側近の三浦に伝えました。そして意知も自分の調べで、平賀源内の片腕だった平秩東作より紹介された土山宗次郎、その者らの仲立ちで元・松前家の勘定奉行だった湊源左衛門に会って話を聞いてきたとのことでした。湊の話によると、松前家の当主の道廣は恐怖政治で藩内ではやりたい放題、さらにご法度の抜荷も行い莫大な利益を得ているよう、なのでこれを理由に上地を命じてはどうか、と意知は父に進言しました。ただそのためには確かな証拠が必要であり、松前と白天狗(将軍・家治が次期将軍として養子に迎えた豊千代の実父・一橋治済)とは殊のほか昵懇、そして家治はそれを承知で「やれ」と命じたと意次は二人に言いました。白天狗や松前に気づかれぬよう抜荷の確かな証拠を集めなければならないけど、意次は意知にはこれ以上関わるなと命じました。しかし意知は父の反対を押し切り、自分がやると言いました。そんな折に花魁の誰袖から文が来て、あの時やはり(志げが)盗み聞きをしていたようで「蝦夷の桜」と匂わせてきました。意知と内密に会った誰袖は「吉原には松前のご家中や蝦夷地の物産を取り扱う者が出入りしている。抜荷の証を探しているなら自分なら力になれるかも。」と言ってきました。そして間者の褒美として自分を身請けして欲しい、と意知に迫りました。重三郎は歌麿を売りだすために会を開き、戯作者や絵師、狂歌師などの関係者だけでなく、それらを志す者なら誰でもどうぞ、という宴会を開きました。その宴会の最中に重三郎は朋誠堂喜三二(平沢常富;尾美としのりさん)に呼ばれ、恋川春町(倉橋格;岡山天音さん)の機嫌を取るよう頼まれました。春町は自分の『辞闘戦』を下敷きにした政演の青本『御存商売物』が一番となったことが面白くなく、この宴会の場でも楽しく盛り上がっている政演が不愉快でしょうがなかったのです。重三郎と喜三二で春町の機嫌を取っていたら周りからは春町は不愉快になるような話ばかり耳に入り、そこへ政演が無神経に絡んできたので、春町はもう我慢できなくなり、皮肉の狂歌を次々と詠みあげ暴れ出しました。興奮して荒れ狂う春町をどう止めたらいいのか、皆が途方に暮れていたときに、次郎兵衛(中村蒼さん)が一発、放屁してしまいました。座敷がしーんと静まり返った後、次郎兵衛が無礼を詫びると、今度は一斉に笑いが起こりました。大田南畝が「俺たちは屁だ~!」と叫んで立ち上がると皆もそれに続いて立ち上がり、座敷では屁を題材にした狂歌をそれぞれが詠みながら輪になり、「へ!、へ!」と叫んで皆で踊り出しました。しかし春町はそんな浮かれた気分にもなれず、重三郎の目の前で筆を折って捨て、一人寂しく宴会場を退室していきました。
June 5, 2025
全4件 (4件中 1-4件目)
1










