PR
X
Category
カテゴリ未分類
(52)木の話
(52)OLD ASHIBA 製作事例&トピックス
(731)◇国産杉 商品製作事例など
(300)WOODPRO Shop&Cafe
(74)環境問題について
(58)徒然なるままに
(627)DIY
(127)WOODPROのこと
(96)仕事に関連して
(51)ちょっとおでかけ
(546)こんなお店 どんなお店
(9)社員旅行
(43)コンサート 展示会
(53)日本のこと 世界のこと
(87)我が家のこと
(66)私の住む町とその周辺
(66)本のこと 映画のこと など
(56)今日の一枚
(201)建築・街並み
(2)Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Comments
Freepage List
カテゴリ: 本のこと 映画のこと など
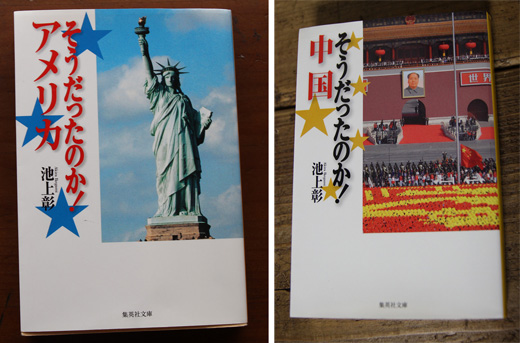
もめる少し前のことですが、「そうだったのかアメリカ」と「そうだったのか中国」を読みました。
ともに、ブックオフで買ったものですので、安上がりです。
確かに、アメリカのことも、中国のことも、知っているようであまり知らないですね。
特に現代史というのは、学校の授業でも尻切れトンボの犠牲になる部分ですし、断片的な情報が知識をなっているだけです。
その意味で、整理して理解してみるにはいい本でした。
池上彰さんの本は始めて読みましたが、とても分かりやすいですね。
中国のデモの際に問題になる「愛国無罪」という言葉。
国を愛するがゆえのあらゆる行動は罪にはならない、という意味ですが、この言葉が生まれたのは1936年。
既存の秩序を護ろうとする勢力に対し、それを打破しようと勢力が掲げたスローガンであったものが、いつしか、反日(=愛国)のためなら、何をしてもいい、という意味に置き換えて使われるようになったといいます。
今回のデモは、単純に反日とか、尖閣問題というだけでなく、「格差社会」に対する抗議だという見方もありましたが、「愛国無罪」という言葉は、中国にとっても諸刃の刃なんですね。
今後、どうなっていくのか、気になります。
アメリカの「銃社会」というのがしばしば問題になりますが、なんで一般人に銃を持たせるのだろう?と日本人なら誰もが思います。
武器は「権力」の専有物であって、一般人には持たせない、というのが専制国家においてはあたり前でした。
民衆に武器を持たせれば、反乱が起こります。
民衆に武器を持つ権利がないということが「階級支配」の象徴でもありました。
しかし、自由の国アメリカでは、国の始まりから「専制的なもの」がありません。
そのため、「武器を持つ権利」=自由の象徴、階級支配からの解放の象徴でもあるんですね。
だからこそ、アメリカ建国の際に、自らの手で自らを守るために「武器」を持つこと、というのは「権利」として憲法で保障されたということです。
「銃」の問題というのは、アメリカという国の成り立ちそのものと深く関連したデリケートな問題なんですね。
本日もご訪問ありがとうございます。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本のこと 映画のこと など] カテゴリの最新記事
-
「侍タイムトリッパー」を見てきた。 2024/11/28
-
今ごろ「オッペンハイマー」を見てきまし… 2024/07/16
-
森永卓郎「書いてはいけない」を読んだ 2024/07/08
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










