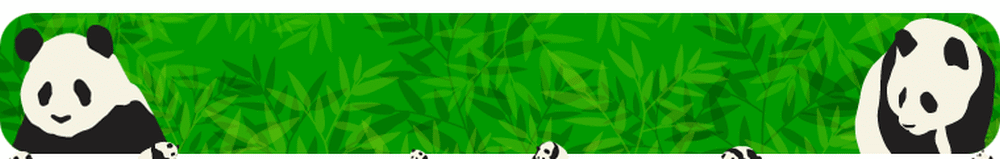2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年11月の記事
全13件 (13件中 1-13件目)
1
-

「おぉ~っ…!」って言ってくれる事うけあい
まぁとにかく、下の写真をご覧下さい。 人からいただいた物なんですが… 何と、これ、急須なんです。 なかなかキッチュでしょ? かなりリアルな手の形に「おぉ~っ」と唸ったあなた、もう一度よく見て下さい。 なんと、フタの部分は猿(孫悟空)の頭! という事は…、これって? お釈迦様の手 有難い事です。阿弥陀仏~。人気blogランキングへ
2005年11月28日
コメント(3)
-
通っぽく見える(?)テクニック
出張とか入って何日も更新出来ないまま、先に件のお茶屋さんに行く機会が来てしまいました。と言っても、今回は自分の用事ではなく人様のお手伝いです。 日本の岐阜県で中国茶のCafeを経営されているご夫婦と仲良くさせて頂いているのですが、今回中国茶の買い付けにいらっしゃったので、仕事の合間を縫って(というか社長に内緒で)通訳兼道案内をした次第です(社長、すんません)。《無断ですがちょっと宣伝》=NATURAL GROUP= 岐阜市内及び近郊に3店舗展開していらっしゃいます。どのお店も面白く個性的なお店だと思います(私は1件しかお邪魔してませんが…)。お近くにお立ち寄りの際は、是非!URL:www.natural-group.com《宣伝終わり 本編へ戻ります》 そうして例のお茶屋さんへ行くと、いつもの老板娘が迎えてくれました。リクエストに応じて数種類のお茶を出し、テイスティングを行います。 老板娘「ヤオシャンしてみますかぁ?」 熊猫&ご夫婦「ヤオシャン?」 老板娘「えぇ、ヤオシャンって言うのはねぇ、『揺香』って書くんだけど、お茶の香りを確かめる方法なのよぉ…」 熊猫「なるほど、せっかくだからお願いします」 得意の蓋碗にお湯を入れて、温めます。そしてその中にお茶の葉を入れる。ここまでは、お茶を淹れる時と同じです。 そうして蓋碗を持ち上げると、軽快に蓋碗を振り始めました。約1~2秒。振り終わると、蓋を開けて香りを嗅がせてくれました。 熊猫&ご夫婦「おぉ~……」 普通にお茶を淹れた時よりも、より強くお茶の香りを感じる事が出来るようです。そして「賭場でサイコロが入った壺を振るお姐さん」(今時の人は知らなかったりするんでしょうか、ひょっとして…)のような動作がかっこいい…。 また、滅多にやらない所が、どことなく「通」を感じさせる雰囲気を醸し出しています。よし、今度どこかでやってみようっと。人気blogランキングへ
2005年11月23日
コメント(0)
-

金秋・上海の旨いもの
秋も深まり、次第に寒くなってきた上海。そんな上海で旬の味と言えば、やっぱり「大閘蟹」こと、上海ガニでしょう。特にこれから12月中旬位にかけてのオス蟹は、最も美味と言われています。 そこで、我が家でも早速季節の味を頂く事に。嫁さんと嫁さんの両親(上海人です)が市場で上物を仕入れてきました。 嫁さんの両親曰く、「上海ガニは、陽澄湖(上海郊外、ほとんど江蘇省の蘇州市手前にある昆山市に位置する湖)のものが良いと言われているが、今では有名になりすぎて高いばかりだ。他の産地のものでも十分に美味しいものが沢山あるんだが、目利きが難しい。見分けるコツは…(話が非常に長いので割愛させて頂きます)(両親の話 終)」 早速、家で茹でて頂きます。先ずは、総出でカニ掃除。歯ブラシでハサミの毛の部分を中心に綺麗にしていきます。中国各地のホテルから持って帰って来た、使い捨ての歯ブラシが大活躍です。写真を撮るのを忘れた事をひどく後悔…。 死んだ蟹は身の中のタンパク質が急速に変質して臭くなってしまう為、必ず活きた物を調理するそうです。但し買って来たものは足とハサミをタコ糸で縛ってあるので、すかさず目の部分を指で軽くつついて活きている事を確認(ちょっと可哀想)。 15分から20分ほど茹でて、完成!!今日はおとなしく茹でられた蟹ですが、時々縛ってあるタコ糸を解いて脱走しようとした跡がある蟹もいる事があります(すごい生命力です)。 大きさ的にはこんな感じです。日本人の感覚からするとかなり小さいですが、上海の人達は、実に器用に食べていきます。何でも達人の域に達する人は、カニ1匹をキレイに食べた後、その殻で元のカニの姿をほぼ復元できるそうです。嫁さんとそのご両親は、さすがにそこまでは行きませんが、とにかく食べるのが早い!と言うか、私が遅い(泣)!! 上の写真は、オスの蟹です。いつか改めて正しい食べ方も紹介したいと思いますが、今日のところは冷めない内に蟹ミソと「蟹膏」と呼ばれる蟹の精子の濃厚な味を堪能して、「ご馳走様でした!!!」人気blogランキングへ
2005年11月16日
コメント(1)
-

緑茶の道は険しい?
今日は、ちょっと浮気して他のお茶屋さんへ。と言うのも、今まで学んだお茶は『青茶』と呼ばれる烏龍茶の親戚のようなお茶ばかりだった為。福建省出身のお茶屋さん(で、しかも地元には自社の茶園まで持っている所)だけに、青茶に対する愛情も深く、紹介して貰ううのはことごとく同じ系統のお茶ばかりだったので、今回は上海の地元の人が専ら飲んでいる緑茶にこっそりと挑戦してみようか、という訳です。 近所の他のお茶屋さんを見てみると、龍井茶に碧螺春、太平猴魁…と。実に色々な緑茶が売られていますが、その中で江西省産の緑茶を発見。普段よく聞く産地の物でないだけに、興味津々です。しかもパッケージには「人民大会堂(日本の国会議事堂に相当)」で使われている、と書いてあります(本当かどうかはこの際どうでもよし)。という事は… 中国政府御用達? 取り敢えず飲んでみようと思ったのですが、やはり御用達だけに(?)試飲は「NG」。せめて気分だけでも味わおうと思い、2ランクほど落ちるお茶(それでも50gで15元(=約220円)する)を購入して家で飲んでみる事に。 店で言われた通りに、60~70℃位のお湯で淹れます。お湯の温度が高すぎると、お茶の葉の渋みも一緒に出てくるので、中国緑茶特有の「清香」を十分に楽しむ事が出来ないのだとか。しかもこちらの人達は、グラスで緑茶を(もちろんHOT)頂く事が多い。これは、お茶の葉が開いていく過程で「ジャンピング」と呼ばれる(お茶の葉がお湯の中で上下に動く)現象を楽しむ為。…中国の茶道なんでしょうねぇ…。 1分ほど待っていると、だんだんと葉が開いて来ました。…が、 開いた葉の内側はちょっと焦げているのか少し黒い。………騙された?………。 それでも、更に待つ事1分ほどで、だんだんと緑茶らしい色が出て来ました。写真ではちょっと赤みがかってしまいましたが、私の撮影技術の限界ですil||li _| ̄|○ il||li さあ、気を取り直して、味の方は… うん、なかなかイケる。 釜煎り特有の香ばしい香りと緑茶の濃い味が口の中いっぱいに広がります。しかも、商品名に「八杯香」とあった通り、数杯淹れてもしっかり香りがします。 う~ん、なかなか侮れない中国緑茶。やっぱり、今度改めてしっかり学んでみなくては…。人気blogランキングへ
2005年11月15日
コメント(0)
-

マンゴープリンと三鮮ワンタン
久しぶりに街中を歩きました。 食事もまだだったので、何を食べようか迷っていたんですが、香港デザートのお店があり、そんなに混んでもいない様子だったので、入ってみる事に…。 最近では、香港風の飲食店もすっかり上海の外食産業の1ジャンルとして定着しているみたいで、そんな中でデザート屋というジャンルは、a)デザートの専門店とb)デザート+軽食の店というバリエーションを見せているようです。恐らく、上海では未だに「専門性よりもバラエティー」なのかもしれません。私が入ったのは、b)の方の『糖潮(TangChao)』という店です。 そこで、写真のような『マンゴープリン』と『ワンタン』を頼んでみました。 マンゴープリンは、上に乗っているココナツのシャーベットのようなもの(私の予想ではココナツジュースとココナツチップを交互に重ねて凍らせた物)と、周りにかかっているマンゴーソースとが、バランスの良い甘味と酸味を出していて、私はなかなか良いと思いました。運ばれてきた時に写真を撮るのも忘れて、先に一口、二口食べてしまっている所から、美味しさが伝わったら幸いです(笑)。 ワンタンの方は、俗に言う「三鮮ワンタン」。プリプリのエビ剥き身が平均2粒/1ヶ入っており、豚ミンチとミニ帆立と上手くマッチしており、言う事なし。でも、一緒に食事した嫁さんに言わせると「白ゴマが入ってたらperfect!」だそうな。スープは、恐らくほぼ間違い無く、「出前一丁」なんですが、ゴマ油の香りと薬味として使われている「黄ニラ」と「小ネギ」で、本格的にアレンジされていました。あと、中国のレタスもよく合うもんだなぁ、と感心。値段は、どちらも20元(¥300弱)と、上海にしてはちょっと高めなんですが、たまになら食べに来てもいいかな、という感想を持ちました。でも店員の態度は少し悪め(=中国標準?)なので、(自分自身が)機嫌の悪い時は行かない方がいいかもです。 人気blogランキングへ
2005年11月14日
コメント(0)
-
気軽に楽しく覚える中国茶-凍頂烏龍茶-
ようやくお茶屋さんを訪れる機会に恵まれ、今日は第2種類めのお茶について教えて貰う事が出来ます。…でもその前に、前回買い忘れた鉄観音茶(毛茶)を購入。…これで、この秋に飲むお茶はもうOK。 今日は店主は不在。店主に負けない位お客さんをもてなすのが好きな「老板娘」(=店主の奥さん)に色々説明して貰いました。 老板娘「凍頂烏龍茶って言うと、やっぱり台湾の物がいいから、台湾のやつを淹れましょうねぇ…」福建省の訛りがきついせいか、話す速度もイントネーションも、何だかより人懐っこく聞こえます。 老板娘「この間飲んだ鉄観音に比べると、より一層香ばしさが強いかしらねぇ…。あ、そうそう、『タンペイ』の程度も鉄観音より念入りに行われるしねぇ…」 熊猫「どうもすいません(って、これは『三平』…古っ!)。あの、タ…、『タンペイ』って何ですか?」 老板娘「あぁ、『炭焙』って書くんだけど、木炭を使って火入れをする事なのよ。…」 熊猫「炭焙って、全ての烏龍茶で必要な工程なんですか?」 老板娘「必ずしも必要では無いのよ。でも、電気やガスを使って火入れをするのは、殆どのお茶で行われるものなのよぉ。でも、鉄観音や凍頂烏龍茶などは木炭を使う『炭焙』でないと、どうしても美味しくはならないのよねぇ…。あ、そうそう、『炭焙』って言うと、もっと面白いのもあるんだけど…(と言いながら早速奥の方から別のお茶を出そうとする)」 熊猫「いやぁ、それは次回以降の楽しみに取っておいて頂いても宜しいでしょうか…?」 老板娘「あら、そぉ?…」 とにかくお客さんとお茶を飲みながら話をするのが大好きだとの事。私自身福建省はまだあまり行った事が無いんですが、きっとこんな風にのんびりとお茶を飲み、話しをしながら、ゆっくりと時間が流れて行くのを楽しむもんなんだろうなぁ…。 この老板娘、話は「おっとり」としていますが、お茶を淹れる手際の良さはさすが本職、福建省人が特に好んで使う『蓋碗』という蓋付きの湯呑を急須代わりに、お茶を淹れてくれます。「これを使いこなせると、きっと『中国茶の達人』っぽくて格好いいだろうなぁ…でも、この前一回真似して火傷したしなぁ…」などと考えている内に、お茶の香りが広がってきました。 なるほど、鉄観音に比べると、香りによりキレがあるといった印象を持ちました。口当たりは少しトロっとしていて香ばしさが口の中にも広がります。 老板娘「でしょぉ、このまろやかさが、海抜の高い山地で採れる『凍頂烏龍茶』の持ち味なのよぉ…」 老板娘、今日も色々と勉強になりました。最後は覚えたての福建語で「トォリャ(漢字では『多謝』って書くのかな?)!」と挨拶。*注:福建省の言葉は、かなり難し(い、と言われている)く、そのバリエーションも豊富らしいので、この言い方は福建省全体で通じる訳ではないとの事。因みに老板娘の故郷は「武夷山」の近くとの事。《今日のまとめ》1.海抜の高い山地で採れる凍頂烏龍茶は、キレのある香りと口当たりのまろやかさが持ち味。2.木炭で火入れされた「炭焙」が美味しさの秘訣 人気blogランキングへ
2005年11月11日
コメント(0)
-
勢いに乗って、今度は回鍋肉!
昨日の麻婆豆腐が思った以上にまともに出来たので、今日は勢いに乗って回鍋肉(huiguorou)にチャレンジしてみました。キャベツと昨日のトウバンジャン、麻婆豆腐で使ったひき肉の残りを使う事にしました。何か、ちょっとさばけた主婦になった気分…。 昨日と大きく違うのは、今日は敢えて作り方を検索しないで自分の感覚だけで作ってみる事にした点。(なので、本当は回鍋肉と呼んではいけない料理なのかも知れません。でも、一応回鍋肉を作ったつもりなので、勘弁してやって下さい) キャベツとタマネギを炒めてトウバンジャンを…、でも少し辛味が足りなかったので韓国のコチュジャンを少し足す事に。そう言えば、味噌は離れた所の物同士を合わせると美味しいって、何かの本で読んだような…、あ、あれは味噌ラーメンの味噌だったっけ。ま、いいや。ついでに日本の味噌もちょっと足してしまえ。 出来上がりは昨日以上にいい感じ。今日は昨日よりもよく出来たので、思い切って80点つけてしまおう。人気blogランキングへ
2005年11月10日
コメント(0)
-
晩御飯に麻婆豆腐を作ってみました
珍しく、自炊する事にしました。 何故か家に豆腐があったので(と言うか、味噌汁を作ろうと思って買ったのですが、「厚揚げ」がなかなか見つからなかったので予定を変更して)麻婆豆腐を作ってみる事にしました。 これまで「丸●屋」等のインスタントものを使ってなら作った事もあったんですが、本格的(自分にとっては)なものにチャレンジしてみるのは初めてです。うろ覚えの知識を頼りに「ひき肉と、トウバンジャン(四川風豆味噌・辛い)何かがあればいいかなぁ…」等と独り言を言いながらスーパーで買い物を終えて帰って来ました。 さて、作ろうと思った矢先に、ふとパソコンが目に入りました。「あ、ネットで作り方検索すれば 良かったんだ」 我ながらいい事に気付いたんですが、その直後に、「いい事」に気付くのが遅すぎた事を後悔する事に…。 「材料一覧は…トウバンジャン、ひき肉、長ネギ、テンメンジャン… 「あ゛っ!半分位の材料が(正しく)無い…」 慌てて代替の材料を探しました。・長ネギ→小ネギを多めに使う事で誤魔化す・テンメンジャン→日本風の味噌でも良しと 書いていたので、白味噌+ 砂糖+みりん風調味料で代替・オイスターソース→…、見なかった事に(汗) 結果は写真のようになりました。思ったよりまともに仕上がって、まァ良かった、良かった。 点数を付けるとしたら、水分が少し多かったので、76点!人気blogランキングへ
2005年11月09日
コメント(0)
-
近くて遠いお茶屋さん
先日買い忘れた鉄観音(本当に買い忘れていた)を買いに行かねばと思いつつ、何かと他の用事に流されて結局今日も行けずじまい。なかなか思うように行きません。 地下鉄に乗っていけば、30分も掛からないのですが、この数日出かける先が別の方角のせいもあって、なかなか重い腰が上がりません。 「明日こそは…用事が終わったら、 いや、何とかして… 出来れば…ね」 いや、決して行きたくない訳ではありませんよ。何と言っても、行けば美味しいお茶と気さくなご主人達、そして私の未だ知らないお茶が待っている訳ですし。よし、週末に行く事に決めた!! 人気blogランキングへ
2005年11月08日
コメント(0)
-
上海のお茶事情
今日は、上海のお茶の消費事情などをほんのちょっと紹介してみたいと思います。 先日からいきなり始めた「気軽に楽しく覚える中国茶」なんですが、私が住んでいるのは上海市。紹介した「安渓鉄観音」は福建省のお茶です。では、地元上海の人達が普段飲んでいるお茶は?と言うと、大部分の人は「龍井(longjing)」や「碧螺春(biluochun)」又は「炒青(chaoqing)」と呼ばれる、釜煎り緑茶の類を好んで飲んでいます。毎年春先になると、お茶屋さんの店先では、大釜でお茶の葉を煎りながら素手でかき混ぜる豪快なデモンストレーションを見る事が出来ます。但しこれらのお茶は、いずれも上海地元のお茶ではなく、浙江省や江蘇省、安徽省等の「近場で他所の土地」のものばかりです。 それでも、1600万人程の人口がおり、経済発展の著しい上海市は、お茶の一大消費市場であり、中国各地の優れたお茶が集まる集積地でもあります。外国人観光客や台湾・香港等の華僑だけではなく、地元民(上海人)の中にも消費能力が向上している事を背景に、積極的にいろんなお茶を買い求めるようになってきているようです。 街中にある「茶館(喫茶店)」でも、緑茶以外に烏龍茶・鉄観音茶・中国紅茶など、様々なお茶を楽しめるようになっています。但し、良いもの(お茶の葉)は、各自がお茶屋さんで購入して自宅で楽しんだりお客様をもてなす為に使用するのがほとんどのようです。
2005年11月07日
コメント(0)
-
気軽に楽しく覚える中国茶-安渓鉄観音-
昨日(11/4)の続き。【気軽に楽しく覚える中国茶】というテーマで、親しくして貰っているお茶屋さんから手ほどきを受ける事に。第一弾は、秋深まるこの時期に美味しい、と言われている『安渓鉄観音』にしようと決定。福建省の南部・泉州市から内陸に少し奥まった位置にある安渓県で採れる鉄観音は中国国内に留まらず、世界的にも有名なお茶であり、中国に旅行で来た方の半数以上はお土産として買った事もあるのではないでしょうか。熊猫「鉄観音と言えば秋が旬なんですよね?」店主「うんにゃ、違う。鉄観音は四季を通じて採れるお茶で、美味しいのは秋だけでなく春に採れるお茶もなかなかイケルんだなぁ。夏茶と冬茶は良いものが少ないので購入する時は注意が必要やね。特に夏茶は風味がすぐに落ちてしまうので、冷蔵庫で保管の上早めに飲むように心がけんといかんぞ」なるほど、一年中供給できるから大量のお土産物としても売られているのか…(勝手な推測)。でも、そうすると、お土産用のお茶は(値段も比較的安いであろう)夏茶や冬茶をたくさん使っているんだろうなぁ…。ま、安渓産でない鉄観音茶使ってる可能性もオオアリですが…。そんな事をじっくり考える暇も無く「要毛茶、浄茶?」と聞かれる。「毛茶?浄茶?」「あのねぇ、毛茶って言うのは、【梗】という茎の部分が付いたままのもの。浄茶は、梗を取ったもの。日本のお客さんは、濃い目の味が好きみたいなので、毛茶かなぁ…」因みにこの「毛茶」「浄茶」という言い方は鉄観音の専門用語と言っても良い言葉らしい。私がお世話になっているお茶屋さんでは「毛茶」も「浄茶」も同じ値段との事ですので、お好みで選べば良しです。そこで、下の写真のような毛茶を淹れてもらう事に。流石は秋茶、さっぱりとした香りが広がってきました。飲み口もなかなかすっきりとしていて、いい感じです。でもやっぱり実際に飲んでみないとなかなか美味しさは伝わらないのかも。開いた葉が滑らかで多少弾力のあるものが良い葉なのだそうです。購入時にテイスティングさせてくれるお店も多いので、1~2回淹れた後のお茶の葉をチェックしてみると良いでしょう。《今日のまとめ》1.鉄観音は秋茶と春茶がGOOD。より香りを重視するなら春茶がベスト。2.味重視なら毛茶、よりすっきりした飲み口重視なら浄茶。ふむふむ…。なかなか良く分かりました。それじゃあ、再見!…あ、自分用の鉄観音買うの忘れた!次回からは、先に買うもの買ってから教わろうっと。
2005年11月05日
コメント(1)
-
RE: 4日の日記
ようやくブログのテーマを一つ決めました。【気軽に楽しく覚える中国茶】とでも題して、私自身の中国茶学習の成果を週イチか月1~2回位の割合で記していければと思います。今、日本でも愛好家が多いと言われており、旅行に来た方のお土産の中でも上位を必ず占めると言っても良い中国茶ですが、専門的なウンチクはなるべく専門の所に任せるとして、「中国茶を楽しむ」スタンスで書いていきたいと思います。以前から興味を持っていながら、ほんの「さわり」程度しか学習しなかった中国茶を『ちょっと』本格的に勉強してみようと思い立ち、決心が鈍らない内にと、日頃から懇意にしてもらっているお茶屋さんへ行って来ました。このお茶屋さん、福建省出身のご夫婦と親戚の人達でやっているんですが、行くと必ず「請坐,喝茶(ハイ、座って。ほら、お茶飲んで行きなさい。)」と人懐っこくお茶を勧めてくれます。四方山話をしながら、今日も1リットル位お茶を飲んだんじゃないでしょうか…。(いつも美味しいお茶を頂いている上に「中国茶の事を色々教えて欲しい」等とお願いするなんて、厚かましいにも程がある)とも思いましたが、有難い事に快諾して頂きましたので、「それでは遠慮なく」という事で色々と教わる事にしました。その第1弾は、明日にでもUPしたいと思います。あしからず。
2005年11月04日
コメント(0)
-
1日の日記
今日から11月になってしまった。新しい月、新しい気持ちでがんばろうっと!
2005年11月01日
コメント(1)
全13件 (13件中 1-13件目)
1