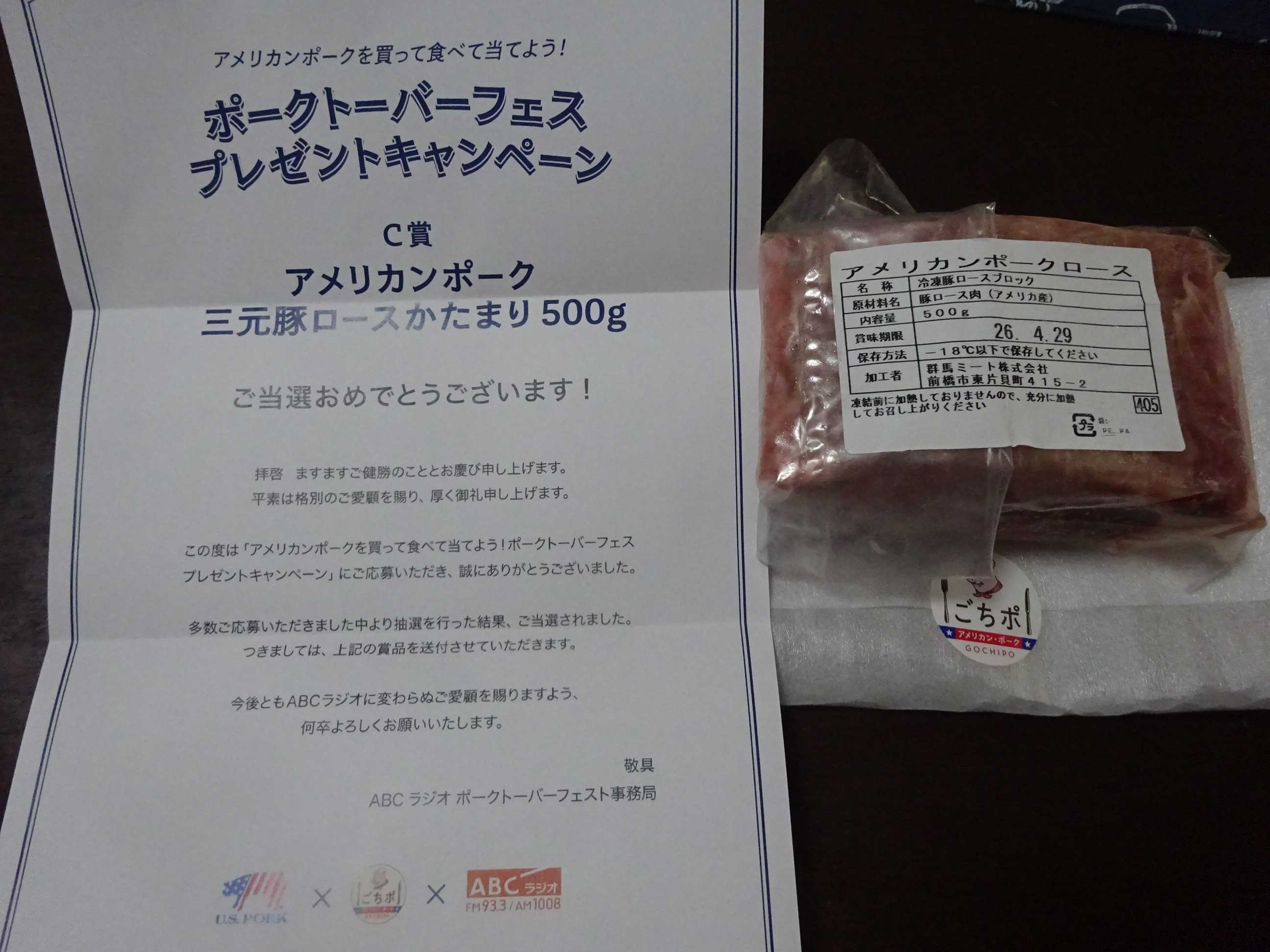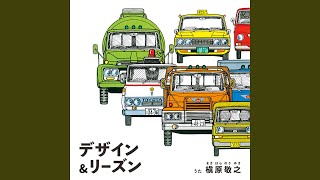2015年01月の記事
全31件 (31件中 1-31件目)
1
-
コーラスライン その6
自分の技術を一定水準以上になるよう努力したことが生きる条件になっているのだ。 その技術水準が高ければ高いほど、それにそれを相手にアピールし、受け入れてもらえる自己演出力が高いほどより魅力的、つまり自分が実現したいことに近い仕事を得られ、それに伴い高い報酬も得られる可能性が高いという世界がそこにはあるのだ。 格差という現実を受け入れざるを得ない社会があり、その社会で生きていこうとする人はその前にできるだけ若い時期にできるだけ高いスキルを獲得しておく必要がある。
2015年01月31日
コメント(0)
-
コーラスライン その5
しかし、そのオーディションに選ばれなかった人たちには何もないのである。 努力しても、実力があると自負していても前者のスター級の人たち以外あるいはコーラスラインと言われる後者にしかなれない人たちがいる。 この公演でスター級となっても次の別の公演でそうなるとは保証されない。 これがアメリカのショービジネスの実態であると今から30年前に知った。 さらに勉強してこのシステムが何もショービジネスの世界だけに留まらないで多くの異なる世界にあることも知った。
2015年01月30日
コメント(0)
-
コーラスライン その4
コーラスラインの前で練習できるのは台詞(セリフ)のあるスターと言われる人たちでメインとなる人たちと公演で目立つ存在である。 このクラスでもメインとそうでない人たちの間で台詞の多少、衣装の格差など様々な区別がある。 コーラスラインの後で練習する人たちは歌の合唱する人々と同じく後方に位置し、そのラインを決して超えないことを条件にして目立たないことも要求されながらもそこにいることを許されるだけなのである。 後者の人たちも当然オーディションで選ばれるのである。 つまり始めからから目立ってはいけない存在といえる。
2015年01月29日
コメント(0)
-
コーラスライン その3
配役を用意し、その役にふさわしい人を選別するのがプロデュースする側の人物、一般的にはプロデューサー、デレクターなどとその名称がある。 それに応募し選ばれる行為がオーディションと呼ばれる。 十分に訓練を積んだ技倆を持って役を勝ち取るのだ。 そのためには一回だけ行われる模範演技を見て、オーディション会場でそれを忠実になぞるのが最低限の合格の目安となる。 競合相手が多い場合はそれにプラスアルファの要素が加わっていることが必須条件になる。
2015年01月28日
コメント(0)
-
コーラスライン その2
初演は1975年7月25日である。 そのヒットを受けて10年後の1985年に監督のリチャード・アッテンボローにより映画化、公開されたものである。 「コーラスライン」とは、稽古で舞台上に引かれるラインのことで、コーラス、つまり役名のないキャストたちが、ダンス等でこれより前に出ないようにと引かれる。メインキャストとコーラスを隔てる象徴ともなっている。という事実が映像を通じてわかる。 ミュージカルというのは基本的に一回限りの雇用契約を結ぶためのオーディションというセリでその行為が行われる。
2015年01月27日
コメント(0)
-
コーラスライン その1
コーラスラインってご存じだろうか? 元来はミュージカル用語の一つだ。 ラインは線。 コーラスは合唱、さらに進んでバックグランド・ヴォーカルと云われる。 直訳的には合唱というイメージから敷延してバックつまり後方で団体で唱(うた)うということになる。 しかしミュージカルのそれはそんな意味ではない。 それを物語る映画をその昔に観たことがある。 ズバリ、「コーラスライン」というタイトルの映画である。 元はマイケル・ベネットの原案・振り付け・演出によるアメリカはニューヨークのブロードウェイの劇場で上演された公演である。
2015年01月26日
コメント(0)
-
マイ インポッシブル ドリーム その2
等身大のキャンバスに描かれた和装の婚礼服姿の女性がそこから抜け出て洋装のウェディングドレスへ変身する過程がまるでスローモションのようにグラデーションがかかって行くシーンだった。 私の理想の顔立ちのうら若い女性の匂い立つ美しさとこの人のために献身しようと覚悟を決めた花嫁の凛とした物腰はそれこそ絵にも描けない美しく清楚なものだった。その女性が私に対して僅かに微笑みかけたところで覚醒した。心の深奥にはこんな憧れの気持ちがあることに気づき我ながら面映ゆいと感じた。 午後8時30分頃から10時15分頃にかけて眠りについていた。 その眠りから覚めようとする前の数分間の夢の内容らしい。
2015年01月25日
コメント(0)
-
マイ インポッシブル ドリーム その1
それは美しい夢だった。 もう二度と見ることができないものと言える。 普通、夢はモノクロームで見ると言われているがそれは極彩色のものだった。 その内容は私が果しえなかったものである。 もうじきそれは薄れてゆき、やがて記憶にすら残らないものになる。 そうなる前にあらすじを著わしておかねばならない。 ふとある女性と付き合うことになりその花嫁姿を描きとめる役割を負わされた私が見事な絵を描き上げたところで終わるものだった。 私の役割はそれ以外に判然としない。 それに釈然としない思いも残る。
2015年01月24日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その7
住民が健全に生活なり、職業が営まれてこそ地域は維持できる。それが根本である。 この根本を忘れた行政はもはや行政に値しない。 それを許したのは酷な言い方で批判される対象になるかもしれないが住民である。 それは混乱の中で無理だったのならこの文章で取り上げた有識者は何をしたのかという事である。 なんだかまとまりのないものになったが、20年が過ぎて阪神淡路大震災の被災者の一員として未だあの出来事を総括出来ない私自身を投影しているのかもしれないと思う今日この頃である。
2015年01月23日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その6
その場に最適な”解”を見出せなかったものを物語るといえるだろう。 今になればあるいはある程度時間がたった段階で欠落していたものがなんであるかというものが浮かび上がるのである。 それが住民参加という事であるのは言うまでもない。 それが民主主義というものである。 その場を作ってきた住民の意思を尊重せずして、その後の順調な運営は望めない。 事実、合意なき、強引な公権力の意思による計画は進行していったが仮借ない施策は保護なり育成とはほど遠いと住民は感じ、その場に見切りをつけて去って行った。
2015年01月22日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その5
特にいまなお復興どころか復旧をも成し遂げていない長田区の新長田地区の現状である。 その弥縫策としてのあるいはマスコミ対策として若い吏員に住民との話し合いの場を設けそれを続けているとの映像も流されることもある。 震災特例措置の策定、さらには実行過程においても有識者はその及ぼす結果について予測も可能だったろうし、それを指摘したものもいたと思う。 しかし実際には震災特例措置で計画されたものはその後の予算を膨らませながら実行され、現状を現出させた。 その実態は復旧どころか後退というべきものと言えるだろう。
2015年01月21日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その4
緊急措置という名の法律で許された枠内の時間の制約でその枠外でできなかったものやそれまで出来なかった計画をこれ幸いとして押し込み実行するのである。 そうではないと抗弁するが実際にはそうであったと当時の状況からみて判断せざる得ないという見方もある。 その計画の立て方は予め想定して準備してあった如く震災特例の名のもとにそれの指示する期間内に策定、実行された。 その後20年経っての結果がマスコミにここ数年よく取り上げられるようになった現状である。
2015年01月20日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その3
それを実行に移させ社会を安定の方向に向かわせることができたら、並行して最善の復旧計画を建て、住民と行政の対等な意見交換の場を設けることを提言し、住民にそのための必要な知識を教授する。 後者の行為を行わないと圧倒的に知識量が蓄積しているあるいは行政経験のある行政側と意見を交換することはできないからだ。 有史以来上意下達、知らしむべし寄らしむべからずとの立場で行政を行ってきた立場の人たちはその独特の感覚でその場を乗り切ろうとする習性がある。
2015年01月19日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その2
最後のカテゴリーの住民については殆(ほとん)ど取り上げられることはない。 緊急時の措置として当時の法律の枠組みに合わせるためとして強引に計画を策定し実行したものもあるという。 そのことを今になって批判しているマスコミがある。 有識者という存在は何であるかという事を今思わざるを得ない。 私が考える有識者は未曽有の社会の混乱の中で無私の立場で冷静沈着に当時のあらゆる現象を分析し、できるだけ早期に社会を落ち着かせる手段を見出(みいだ)し、公権力に提案することができる人たちある。
2015年01月18日
コメント(0)
-
阪神淡路大震災20周年祈念日を迎えて その1
2015年が始まって半月が過ぎた。 昨年末から風邪を引き込み体調が思わしくない。 そんな中で是非書かねばと頭を振り絞って、むりやり紡いだ文が以下のものである。文章の体(てい)をほとんどなしていない。 命なき被災者を想うとそうならざるを得ない。 しかし、何か記録することが義務と感じるのも事実である。 阪神淡路大震災の祈念日の頃によく取り上げられるようになったのが復興住宅とそこに住む住民のことと自力で住環境を整えた住民と其れさえもかなわなかった住民のことである。
2015年01月17日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 <全文>
「限界だぁ」 と言う人がいる。 それはその人がこれまでの経験に照らして少し無理をした時に発する言葉であって傍目から見ればたいした経験でないことが多い。達人とか名人とか言う人はある技術についての普通に求められる水準を人生の早い時期に突破し、それで生活出来るクラスからより高い水準を求め努力し続けるか、それまでに得た水準を保持してゆくために体力・気力を養っている人達なのだ。 早い時期に求められるべき水準を得るためには天性の才能が備わっていない限り時間をかけるか特別の鍛錬をするか、それを得るための新しい発想を生み出す必要がある。 後者も一種の才能であることは言うまでもない。 それが出来ない場合は前者の時間をかけるという繰り返し練習することで水準に達するしかない。 これが凡人と呼ばれる普通の人の技術の習得方法である。 求められる水準に達してからが「限界」という言葉を使える入り口に立った時と言えると思う。 その時その技術のみを追求していこうとするといずれ限界がくる。 その時に挫折と言う言葉が脳裏に浮かぶ。 其れで良いと言う人は普通の生活をするもそれ以上の水準には昇れない。 ただ熟練という鍛錬による他の人の譏(そし)りを受けない程度の技術水準より少しクラス越えのそれがあるだけである。 一定の水準があると評価された時から関連分野かあるいはかけ離れた分野に興味を示しその分野の求められる水準くらいまでに達する努力を行う。 そのことでその技術取得だけでは得られない発想が生まれることがある。 そのことに気づけない人は凡人で終わる。 世に一流と言われた人達は本業以外に何かしらの技術習得に努力し、更に極めた人達と言える。 よく言われたことだが「旦那衆」と呼ばれた人達は代々かあるいは一代で財産なり家業を得ることが出来た人達である。 その人たちでの集まりで一芸を披露する必要に迫られることもあったが意識せずしてクロスオーバーによる効果を得ていたと思うのである。もちろん楽しんでいたこともあろう。 それよりも本業で食べて行けるだけの努力をしている時にその努力の行い方を平行して会得しているのである。 その方法は個々人によって様々であろうが技術取得の技術は体得しているのである。 それに気づいた時から他の技術も習得したい欲求が生まれて来た人は上の伝(でん)で言うと本業でも更に上のレベルを狙える人であると言うことも出来るだろう。 クロスオーバーで得られた発想を活かして本業にその味を加えた作品を創ることでその世界にそれまでなかったものを披露することができる。 そしてそれが評価された場合その世界の持つ意味が拡がる可能性をもつことになる。 もしその世界が世間的認知が低い場合、それが認められることでレベルアップが行われることになる。 但し、その技術を認める人の度量が必要なのである。 それがなければ価値そのものが認められることはないし、世の中の役に立つこともない。 文化レベルの高い社会であればそれが認められる可能性は高い。 だから幕末から明治時代になるまでの短期間の内に西欧化という近代化を達成したその時代の指導者の力量はすごいと言うべきである。その後の日本はそれに慢心し、いつしか緊張感を失い、方向性を見失って亡国の道を辿ることになった。 本当に正しく国を導いて行けるだけの人物を見いだす人物の養成を怠った結果といえる。 江戸時代には世襲が有ってもそれを準備していて幾らでも人材はいたのである。多少走りすぎたきらい(傾向)がある。少し元に戻りたい。 クロスオーバーすることで有る技術の新しい世界を切り開きその業界なり世間に認知されたら、その勢いを更に加速し、いつしか中心人物に時間をかけてなって行く。 その間更に良いモノを創り出そうとする意識のもとに自己研鑽をも平行して行うのである。 それはより高みを目指す中で生まれてくる観念である。その中に天才と呼ばれるタイプがいて、それを評価出来る人物が同時にいれば時代を画することが出来る。そうでない場合は異端者となり、存在の幅は狭まる。運が良ければ後代に再評価される。 評価された者に触発されて次代の人材が育つことになる。この時に「爆発」と言うか集団の「限界」突破となる。勿論、個々人の「限界」突破は個人なり、集団内の相互努力による「限界」突破を助長しておく必要がある。 その水準が高ければ高いほど次のレベルにより早く達することができ、世間的にもその存在理由なり、存在価値が高まるのである。 そして集団が、個人が高い意識レベルを常に意識することで高みへの挑戦する意欲を失わなければ、そしてそれを評価する人達が存在していればその中からその時代の極限状況に挑戦したいとする人物が出てくるだろう。 勿論それをサポートする人達がいることが前提条件である。 その内の何人かがそれに成功する可能性がある。成功すればその技術史に確実に残ることになる。
2015年01月16日
コメント(0)
-
理不尽というか不合理と言うか その1
ある病気で内科医院に月に2回ほど通っている。お薬手帳と言うのがあって、毎回それに調剤された薬の名称印刷した小札を貼付する。 それの情報管理料をしっかり支払わされている。 病状の変化がないから毎回種類の薬を同じ数量、医院近くの調剤薬局で購入するのである。 それでいて同じ内容の小札を交付される。支払いは3割だがそれを負担するのである。 金額にすれば100円程であるが同じ内容のもとのを貼付するのは全くのムダである。
2015年01月15日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 その9
勿論それをサポートする人達がいることが前提条件である。 その内の何人かがそれに成功する可能性がある。成功すればその技術史に確実に残ることになる。限界と極限の差 試論 その8
2015年01月14日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 その8
評価された者に触発されて次代の人材が育つことになる。この時に「爆発」と言うか集団の「限界」突破となる。勿論、個々人の「限界」突破は個人なり、集団内の相互努力による「限界」突破を助長しておく必要がある。 その水準が高ければ高いほど次のレベルにより早く達することができ、世間的にもその存在理由なり、存在価値が高まるのである。 そして集団が、個人が高い意識レベルを常に意識することで高みへの挑戦する意欲を失わなければ、そしてそれを評価する人達が存在していればその中からその時代の極限状況に挑戦したいとする人物が出てくるだろう。限界と極限の差 試論 その7
2015年01月13日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 その7
クロスオーバーすることで有る技術の新しい世界を切り開きその業界なり世間に認知されたら、その勢いを更に加速し、いつしか中心人物に時間をかけてなって行く。 その間更に良いモノを創り出そうとする意識のもとに自己研鑽をも平行して行うのである。 それはより高みを目指す中で生まれてくる観念である。その中に天才と呼ばれるタイプがいて、それを評価出来る人物が同時にいれば時代を画することが出来る。そうでない場合は異端者となり、存在の幅は狭まる。運が良ければ後代に再評価される。限界と極限の差 試論 その6
2015年01月12日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 その6
だから幕末から明治時代になるまでの短期間の内に西欧化という近代化を達成したその時代の指導者の力量はすごいと言うべきである。その後の日本はそれに慢心し、いつしか緊張感を失い、方向性を見失って亡国の道を辿ることになった。 本当に正しく国を導いて行けるだけの人物を見いだす人物の養成を怠った結果といえる。 江戸時代には世襲が有ってもそれを準備していて幾らでも人材はいたのである。多少走りすぎたきらい(傾向)がある。少し元に戻りたい。限界と極限の差 試論 その5
2015年01月11日
コメント(0)
-
限界と極限の差 試論 その5
クロスオーバーで得られた発想を活かして本業にその味を加えた作品を創ることでその世界にそれまでなかったものを披露することができる。 そしてそれが評価された場合その世界の持つ意味が拡がる可能性をもつことになる。 もしその世界が世間的認知が低い場合、それが認められることでレベルアップが行われることになる。 但し、その技術を認める人の度量が必要なのである。 それがなければ価値そのものが認められることはないし、世の中の役に立つこともない。 文化レベルの高い社会であればそれが認められる可能性は高い。限界と極限の差 試論 その4
2015年01月10日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 全文
一字違いで大違いと言うことがある。 表題に掲げた「もゆ」と「もえ」は漢字で表記すると次のようになる。 「燃ゆ」と「燃え」である。 その意味は前者が「燃えてしまった」であり、後者が「燃えてている最中」である。2015年度のNHKの大河ドラマのタイトルが「花燃ゆ」である。 ヒロインは幕末の志士に大きな影響を与えた攘夷思想家の吉田松陰の妹である杉文と言う。 前宣伝を見ると兄の意思を継ぎ、その思想を次代を担う当時の若者たちに伝え励ました人物であるとある。 となればこのタイトルの持つ意味が解かろうというものだ。 志士となっていく若者に兄のそばにいて会得したものを彼らを育てる過程で植えつけ、その人数を殖やし、時間を経て、その者たちが大きな勢力となろうとする時精神的支柱の一つとなったと解することが出来る。 完成と言う意味での完了形としての「燃ゆ」であり、女性を意味する「花」を冠すしたと推測させるものである。随分前の大河ドラマにヒロインが主人公と初めてなった「花の乱」があり、それに倣ったのは言うまでもない。 ちなみにヒロインは足利義政の夫人の日野富子だった。 「もえ」は上の他に「萌え」とも表記できる。現代ではこちらの方が人口に膾炙(かいしゃ:広く知れ渡る。)しているだろう。 むしろ、若者文化を解するための「キーワード」と言ってよい存在である。 この言葉が注目されてから10年ほどになる。ワンディケイド(One decade:10年) 上の杉文の時代から150年を経ている。「萌え」の本来の意味は植物の生長過程での「芽生え」を意味する。ところが若者文化の中では熱中するの意味が強いことを意味することもあって「燃え」の意味も包含する。 その若者文化とはミレニアムを経て数年間の後日本の東京の秋葉原に集う草食系と呼ばれる体力はないが異様にパソコンに強い男子がその性向から男女間の交渉に手前で立ち止まりメイドカフェのメイドでその処理を満足させる時の感情を指すと筆者は解している。具体的に表現すると小女(しょうじょ)がママゴトスタイルと表徴する洋エプロンを着用し、メイドという扮装(ふんそう)で食事や飲み物を運んでくるメイド喫茶でその少女のしぐさや言動、扮装に「萌え」るのだ。 私がこの世に生を受ける前の昭和30年代初めまで『赤線地帯』というのがあったと歴史の本に記されている。そこは金銭で男の欲望の一つが処理できる場所だったとある。 それが歴史の転機により公の存在でなくなり、男女同権の思想の普及により、威張っていた男は絶滅した。 相反して女性の勢いが強くなっていった。 少なくとも表徴上はね。 猛々しさは影を潜め、時代の進展により男の子が「女々しく:死語」なっていった。 そのトドのつまりが草食系男子と言える。 メイド喫茶の元祖があるのをご存じだろうか。 歴史を繙(ひもと)くと大正デモクラシーと呼ばれた時代の庶民文化の流れの中に「メイドカフェ」というのがある。単に「カフェ」と言う場合もある。 もともとはフランス語でコーヒーを飲む場所意味するカフェサロンである。 その中でキモノに洋風のエプロン姿で男性客を酒食でもてなしたから扮装から「メイドカフェ」と呼ばれるようになったとある。喫茶ではなくお酒等を提供する場所だったのである。 現在でいうところのバーであり、高級クラブ(若者が踊るクラブではない大人の社交場)がそれにあたる。 100年を経て登場したのが似て非なるメイド喫茶である。 何が違うのかと言うと感情の入れ方の方である。 今のそれは「萌え」であり、一方的に奉仕されることを欲し、後者は恋愛そのものを愉(たの)しむのである。そして前者は10代後半であり、後者は20代半ば以降の男性が通うという違いがある。前者は現実では実現できそうもない「傅かれる(かしずかれる)」という言葉や所作を味わえるという時代錯誤を経験できるのである。 何とも奇妙な現象と映るむきもあろう。 その中には疑似恋愛と言う要素も介在することはない。 ひたすらありもしない妄想の世界を楽しんでいるのである。その費用は学生だから小遣いと言う形で親が負担するのである。 その大半を現代の若者文化が生み出したアイドルの応援のために費消する。 あるいはアルバイトで汗を流したことで得た報酬をそれに充てても惜しくないという面々も少なくないと伝えれられている。 そのアイドルを応援することを「推し」と言い、その成長過程を楽しむという側面もある。 これは彼らが幼少の頃より慣れ親しんだRPG(ロールプレイングゲーム)にその秘密が隠されている。 これについては後日説いて行けたらと思っている。
2015年01月09日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その8
何とも奇妙な現象と映るむきもあろう。 その中には疑似恋愛と言う要素も介在することはない。 ひたすらありもしない妄想の世界を楽しんでいるのである。その費用は学生だから小遣いと言う形で親が負担するのである。 その大半を現代の若者文化が生み出したアイドルの応援のために費消する。 あるいはアルバイトで汗を流したことで得た報酬をそれに充てても惜しくないという面々も少なくないと伝えれられている。 そのアイドルを応援することを「推し」と言い、その成長過程を楽しむという側面もある。 これは彼らが幼少の頃より慣れ親しんだRPG(ロールプレイングゲーム)にその秘密が隠されている。 これについては後日説いて行けたらと思っている。
2015年01月08日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その7
現代でいうところのバーであり、高級クラブ(若者が踊るクラブではない大人の社交場)がそれにあたる。 100年を経て登場したのが似て非なるメイド喫茶である。 何が違うのかと言うと感情の入れ方の方である。 今のそれは「萌え」であり、一方的に奉仕されることを欲し、後者は恋愛そのものを愉(たの)しむのである。そして前者は10代後半であり、後者は20代半ば以降の男性が通うという違いがある。前者は現実では実現できそうもない「傅かれる(かしずかれる)」という言葉や所作を味わえるという時代錯誤を経験できるのである。
2015年01月07日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その6
メイド喫茶の元祖があるのをご存じだろうか。 歴史を繙(ひもと)くと大正デモクラシーと呼ばれた時代の庶民文化の流れの中に「メイドカフェ」というのがある。単に「カフェ」と言う場合もある。 もともとはフランス語でコーヒーを飲む場所意味するカフェサロンである。 その中でキモノに洋風のエプロン姿で男性客を酒食でもてなしたから扮装から「メイドカフェ」と呼ばれるようになったとある。喫茶ではなくお酒等を提供する場所だったのである。
2015年01月06日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その5
私がこの世に生を受ける前の昭和30年代初めまで『赤線地帯』というのがあったと歴史の本に記されている。そこは金銭で男の欲望の一つが処理できる場所だったとある。 それが歴史の転機により公の存在でなくなり、男女同権の思想の普及により、威張っていた男は絶滅した。 相反して女性の勢いが強くなっていった。 少なくとも表徴上はね。 猛々しさは影を潜め、時代の進展により男の子が「女々しく:死語」なっていった。 そのトドのつまりが草食系男子と言える。
2015年01月05日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その4
ところが若者文化の中では熱中するの意味が強いことを意味することもあって「燃え」の意味も包含する。 その若者文化とはミレニアムを経て数年間の後日本の東京の秋葉原に集う草食系と呼ばれる体力はないが異様にパソコンに強い男子がその性向から男女間の交渉に手前で立ち止まりメイドカフェのメイドでその処理を満足させる時の感情を指すと筆者は解している。具体的に表現すると小女(しょうじょ)がママゴトスタイルと表徴する洋エプロンを着用し、メイドという扮装(ふんそう)で食事や飲み物を運んでくるメイド喫茶でその少女のしぐさや言動、扮装に「萌え」るのだ。
2015年01月04日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その3
それに倣ったのは言うまでもない。 ちなみにヒロインは足利義政の夫人の日野富子だった。 「もえ」は上の他に「萌え」とも表記できる。現代ではこちらの方が人口に膾炙(かいしゃ:広く知れ渡る。)しているだろう。 むしろ、若者文化を解するための「キーワード」と言ってよい存在である。 この言葉が注目されてから10年ほどになる。ワンディケイド(One decade:10年) 上の杉文の時代から150年を経ている。「萌え」の本来の意味は植物の生長過程での「芽生え」を意味する。
2015年01月03日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その2
となればこのタイトルの持つ意味が解かろうというものだ。 志士となっていく若者に兄のそばにいて会得したものを彼らを育てる過程で植えつけ、その人数を殖やし、時間を経て、その者たちが大きな勢力となろうとする時精神的支柱の一つとなったと解することが出来る。 完成と言う意味での完了形としての「燃ゆ」であり、女性を意味する「花」を冠すしたと推測させるものである。随分前の大河ドラマにヒロインが主人公と初めてなった「花の乱」がある。
2015年01月02日
コメント(0)
-
「もゆ」と「もえ」 その1
年頭のご挨拶をすべきなのですが割愛します。年末に連続してアップしているものをいったん中止します。出来たてのほやほやなので湯気がでている文章をアップします。 一字違いで大違いと言うことがある。 表題に掲げた「もゆ」と「もえ」は漢字で表記すると次のようになる。 「燃ゆ」と「燃え」である。 その意味は前者が「燃えてしまった」であり、後者が「燃えている最中」である。2015年度のNHKの大河ドラマのタイトルが「花燃ゆ」である。 ヒロインは幕末の志士に大きな影響を与えた攘夷思想家の吉田松陰の妹である杉文と言う。 前宣伝を見ると兄の意思を継ぎ、その思想を次代を担う当時の若者たちに伝え励ました人物であるとある。
2015年01月01日
コメント(0)
全31件 (31件中 1-31件目)
1