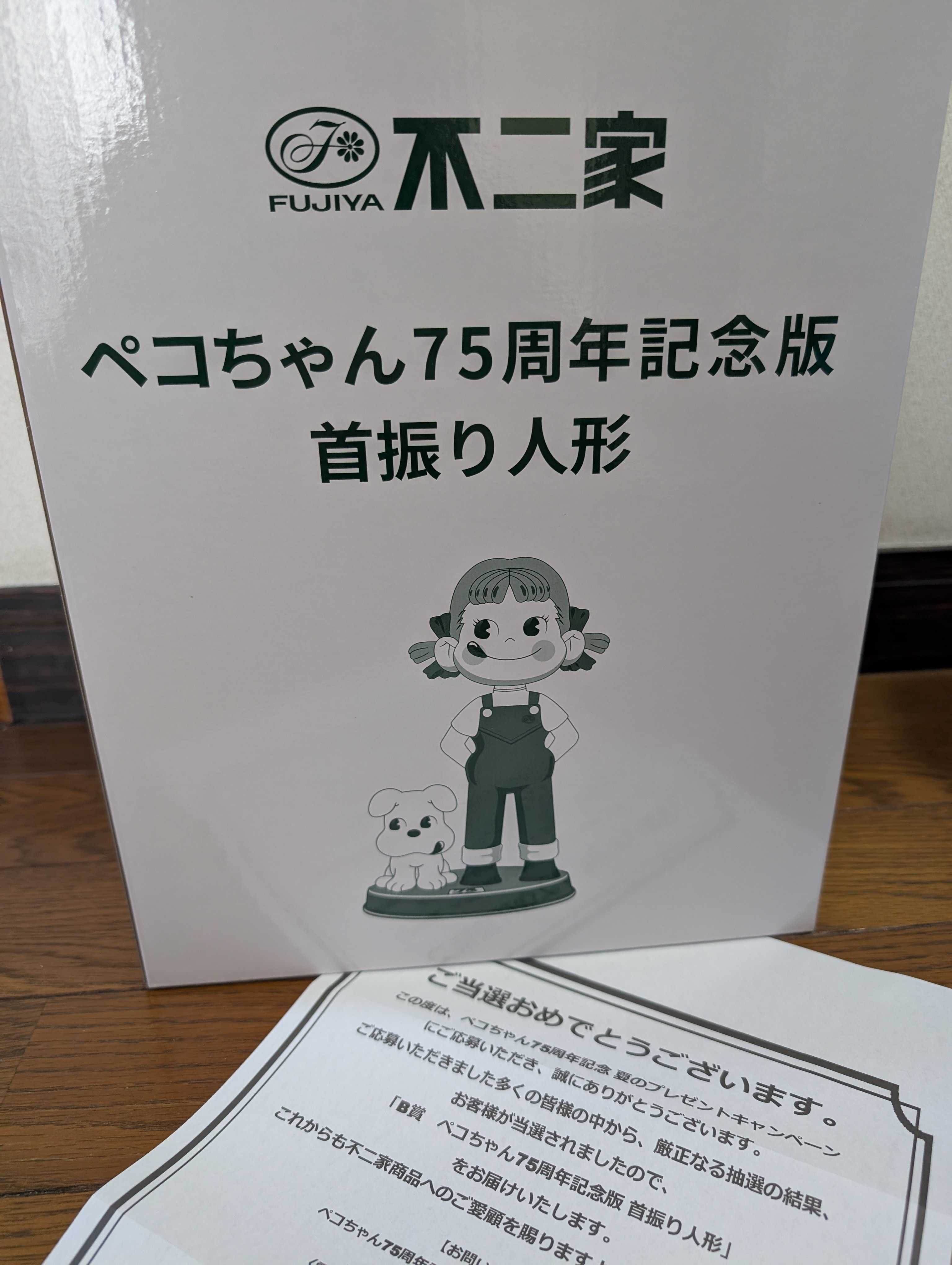2016年03月の記事
全21件 (21件中 1-21件目)
1
-

マルタ騎士団のシンボル
先日ゴゾ島の「青の洞窟」を紹介したついでに、ゴゾ島のお隣のマルタ島で見つけた、いくつかのシンボルをご紹介しましょう。まずは有名なマルタ騎士団のシンボル(紋章)。結構あちこちで見かけます。同じ十字でも、尖端が二つに割れているところがオシャレですね。マルタ騎士団は、キリスト教カトリックの騎士修道会で、正式には、ロードス(ギリシャ)及びマルタ(マルタ共和国)におけるエルサレムの聖ヨハネ病院独立騎士修道会と言います。歴史的には、12世紀の十字軍時代のパレスチナで発祥した「聖ヨハネ騎士団」(テンプル騎士団、ドイツ騎士団と並ぶ、中世ヨーロッパの三大騎士修道会の1つ)が現在まで存続したものであるとされています。国家ではないものの、かつて領土を有していた経緯から「主権実体」として承認している国(イギリス、イタリア、スペイン、ロシアなど)もあるそうです。国際連合では「オブザーバーとして参加するために招待を受ける実体(entity)あるいは国際組織」として扱われており、「加盟国」とも「非加盟国」とも異なる立場であるそうです。何か面白い組織ですよね。領土なき「国家」というか、複数の国にまたがって存在する実体とは。そうした結びつきを何百年も維持できるのも、やはり紋章(シンボル)の力があるからではないでしょうか。
2016.03.31
コメント(0)
-

波勝崎の猿たち
地元の人が面白いというので、堂ヶ島の後は、西伊豆・波勝崎に野生の猿を見に行きました。伊豆国立公園「波勝崎」です。既にお猿さんが出迎えてくれていますね。奇岩の景勝地でもあります。餌付けもしていますが、基本的に野生の猿です。波勝崎一帯には300匹ほどの野生の猿が暮らしており、それが二グループに分かれて生息しているそうです。で、その二グループのうちどちらかが山にいるときは、もう一つのグループがこの海岸に来て、ローテーションで餌付けされているようです。餌付けしている売店の扉の前で、餌をくれるのを待っている猿。扉が開くのを待っているわけですが、ちゃんと厳しくしつけれらていて、扉が開いても決して中に入ろうとはしませんでした。こちらの猿も餌が降って来るのを待っているわけです。かわいい子連れの猿。こちらは看板を持って、ちゃんと観光PRをしていますね。好奇心旺盛の子ザル。この一帯は民家がないため、猿が人間と敵対することなく生息することができるようです。ここに車で来るまでの道路の真ん中にも、まるで警戒心のないサルたちが寝転んで昼寝をしておりました。
2016.03.30
コメント(0)
-

トンボロとトンビ
堂ヶ島クルーズの後は、陸地からトンボロを見学します。フランスのモン・サン=ミッシェルのように、干潮時に陸地と島が砂州でつながれる現象をトンボロ現象といいます。現在こそ橋で結ばれていますが、江の島なんかも昔はトンボロ現象が観測できたそうです。そしてここ堂ヶ島でも、ちょうど干潮時間となり、砂州が現れてきました。それが次の写真です。出来たばかりの砂州の「橋」を、恐る恐る渡り始めた人も見受けられました。その時、ちょうどトンビ君がこちらに向かって飛んできたので、それを正面から撮影します。正面から見たトンビの顔は、結構かわいいですね。その昔、タヒチで撮影した、正面から見たサメの写真を思い出しました。どちらもかわいい顔をしていますね(笑)。散歩の最後は、昨日紹介した「青の洞窟」を陸地から撮影。この洞窟が海につながっているわけです。明日は波勝崎の猿をご紹介しましょう。
2016.03.29
コメント(0)
-

日本にもあった「青の洞窟」
翌日は堂ヶ島クルーズ。予定にはなかったのですが、どういうわけか急きょ、決まりました。久しぶりのクルーズです。まずはクジラ岩。確かにクジラのように見えますね。続いて龍紋のある岩。この自然の紋様は、アイルランドの古代遺跡ノウスの壁面に描かれた蛇の紋様に似ています。こちらがその蛇の紋様。で、こちらは海鵜です。ちゃんと指の指す方角を向いていますね(笑)。最後はクルーズのハイライトとなる「青の洞窟」。イタリアのが有名ですが、マルタ島のお隣のゴゾ島にも青の洞窟「碧い窓(アズール・ウインドウ)」がありました。それがこちら。どちらもきれいな青い海でした。
2016.03.28
コメント(0)
-

達磨山から堂ヶ島へ
これまで達磨山から撮影した風景写真をいくつか紹介しましたが、実は山頂ではなく、中腹の展望台から撮影しています。で、本当の達磨山はこちら。まるでイギリスの田舎の丘のような雰囲気があります。このなだらかな山の頂上に立てば、360度のパノラマが広がっているわけです。ただし、この日は風が強かったので、山頂までは登りませんでした。沼津市の戸田(へだ)港を眼下に見下ろします。そのまま伊豆半島の西海岸を南下。堂ヶ島です。その海岸で見つけたイソヒヨドリ。この日は堂ヶ島で宿泊しました。旅はまだ続きます。
2016.03.27
コメント(0)
-

富士山を見ながら空中散歩
3月23日に達磨山に行く途中、普段なら素通りする静岡県三島市のスカイウォークに初めて立ち寄りました。富士山を見ながら渡る吊り橋のことです。こちらがその吊り橋。遠くに富士山を見ながら渡ります。人が大勢歩くと結構左右に大きく揺れますから、ちょっとした”空中散歩気分”に浸れるわけですね。吊り橋のちょうど真ん中付近で立ち止まって下を撮影。さすがに足が少しすくみます。それでもこの日は富士山がよく見えておりました。ちょっとした観光スポットになっているようです。
2016.03.26
コメント(0)
-

天空の城「富士山」
時は移って3月23日。再び達磨山に登ります。そのときの写真がこちら。この日は2月7日に比べて下の方はガスが掛かっていたため、愛鷹山すらよく見えませんでしたが、富士山の頂上付近だけは綺麗に見えておりました。まるで天空にそびえる富士山ですね。
2016.03.25
コメント(0)
-

達磨山から見た淡島
昨日に続いて、達磨山から見た風景。中央に見える、円錐形の島は淡島です。駿河湾の湾奥にある内浦湾と江浦湾の境となっている、静岡県沼津市にある島です。日本神話に登場する淡島は和歌山県和歌山市友ヶ島の神島などに比定されていますが、この淡島の由来は不明です。ちょっと謎に満ちていますね。利島のミニチュア版の島に見えます。
2016.03.23
コメント(0)
-

達磨山から見た愛鷹山
新しいシリーズを始める前に、先月(2月)7日に伊豆半島の達磨山に登った際に撮影した写真をご紹介しましょう。達磨山は、静岡県沼津市と伊豆市との境界にある標高982メートルの山です。山容が、座禅をしている達磨大師に似ていることから名づけられました。天城山に天狗の二男(万二郎岳)と三男(万三郎岳)が住んでいる一方、長男の天狗が住む山であるとの言い伝えから、万太郎(番太郎)とも呼ばれています。とにかく見晴らしがいいところです。安房国、武蔵国、相模国、甲斐国、信濃国、伊豆国、駿河国、遠江国、三河国、尾張国、美濃国、伊勢国、伊賀国の13国が見渡せることから、十三国峠とも呼ばれているそうです。その達磨山から見た愛鷹山です。駿河湾の対岸になだらかな山容を誇っていますね。その山中には、見たこともないような巨石群が眠っているといいます。この日は雲があって見えませんでしたが、晴れていれば愛鷹山の左奥に富士山が現れます。
2016.03.22
コメント(0)
-

現代人の作った「天」と「地」のシンボル
古代人が使ったシンボルをざっと見てきましたが、現代人もシンボリックなモニュメントを設置するのが好きですね。どの程度、意識して作ったかはわかりませんが、円や球は「天」のシンボルです。その球体の置かれた四角い台座は「大地」のシンボル。すなわち前方後円墳と同様に、天地が合わさるシンボルとなるんですね。で、このモニュメントの前で記念撮影すれば、天地人となるわけです。
2016.03.21
コメント(0)
-

「ビク石(石谷山)」のビク石
これが「ビク石山」のビク石です。遠目に見ると、富山県平村の天柱石に似ています。山頂から少し下ったところに鎮座しています。近づくと・・・・・かなり大きいことがわかります。まるで垂直の壁のよう。下から見上げます。大きすぎてカメラのフレームには収まりきれませんでした。
2016.03.19
コメント(0)
-

ビク石山頂の巨石群2
ビク石山頂にある巨石群です。こちらは大名石。 頂上付近では一際目立っていました。どちらを向いても奇岩だらけで、その存在感はなかなかのものです。次はいよいよ、ビク石という山の名前の由来となった巨石「ビク石」を紹介します。
2016.03.17
コメント(0)
-

ビク石山頂の巨石群
静岡県藤枝市のビク石の続きです。本来なら、八十八石を見た後、そのままビク石登山に向かうのでしょうが、再び八十八石の駐車場まで戻ります。というのも、ビク石の頂上付近までは車でも行けるからなんですね。前回(2008年8月)、晴美鳥さんとビク石に登った時は、妖精のピクシーの撮影に成功したことは『異次元ワールドとの遭遇』でも紹介しました。こちらがその写真です。羽の生えた妖精だと思ったら、「羽」は「耳」であることが後で”判明”しました。この写真はビク石の中腹の巨石の前で撮影したものですが、今回は車での登山であるため、この場所には立ち寄りませんでした。車で狭い山道を登って行くと、頂上のそばの駐車場に到着。見晴らしの良い場所に出ます。これがその時の写真です。目を凝らすと、富士山も見えていました。上の写真の中央左奥です。ちょっと雲に隠れていますが、こちら側から富士山を見ると、頂上に一つコブがあるように見えます。そして、こちらが、頂上の少し手前にある「宮石」です。次回は頂上の巨石群と山の名前となったビク石をご紹介しましょう。
2016.03.16
コメント(0)
-

ビク石の麓に広がる巨石・奇岩群「八十八石」
先月(2月)26日、天気が良かったので、静岡県藤枝市のビク石に行って来ました。まずは「玉露の里」から、ビク石の麓にある「笹川八十八石」に向かいます。梅が満開。里山の風景ですね。こちらは河津桜。そして次は御茶畑です。静岡らしい風景ですね。そうして到着したのが巨石群が広がる「八十八石」。おむすび石。数えたことはありませんが、こうした巨石の奇岩が八十八くらい集まっています。(続く)
2016.03.13
コメント(0)
-

「世界文明を築いたのは日本のスメル族だった!!」
本日発売の『月刊ムー4月号』に私が書いた「歴史を覆す古史古伝 正統『竹内文書』の謎」が掲載されております。巻頭カラーの総力特集で、22ページ分あります。「正統竹内文書」にご興味がある方は是非お読みください。そのほか、個人的には、水木しげるが1980年と1992年に「ムー用」に書いた『沼の主』と『沖縄大紀行』の再録付録が面白かったです。水木しげるには子供のころ、かなり影響を受けました。ムーは37年前(1979年)に創刊された、日本では最長寿のオカルト雑誌ですね。共同通信記者時代の1984年にムーから取材を受けたこともありました。10年間続けば上出来と言われる雑誌出版界で、これだけ長く雑誌発行を継続するのは大変なことです。よく頑張っているなと思います。
2016.03.09
コメント(0)
-

赤い竜のシンボルの行方
イギリスの国旗であるユニオン・フラッグ(ユニオン・ジャック)は三つの王国の象徴の組み合わせですが、その中に入っていない国がウェールズです。まずはウェールズの国旗から紹介しましょう。こちらです。赤い竜なんですね。ローマ軍がもたらしたドラゴンのシンボルを、ローマ軍撤退後に勢力を伸ばしたブリトン人(前ローマ時代にブリテン島に定住していたケルト系の土着民族)とサクソン人(ドイツ地方で形成されたゲルマン系の部族)がそれぞれ「赤い竜」「白い竜」として使ったことが由来のようです。で、この赤い竜と白い竜の戦いは、アーサー王がサクソン人を破ることによって「赤い竜」が勝利して決着したということです。赤い竜はブリトン人であるウェールズ人の象徴・化身なんですね。ラグビーのウェールズ代表の愛称も「レッド・ドラゴン」です。ウェールズは「ドラゴン=ハート(精神)の国」とされています。私が学生時代に組んでいたテニスのダブルスのパートナーも、この「ドラゴンハート」を持つカーディフ(ウェールズの首都)出身のイアンでした。バックハンドのハイボレースマッシュが彼の武器で、ずいぶん助けられました。それはそれとして、どうしてウェールズのシンボルが外されたかというと、ウェールズは13世紀末という早い時期にイングランドに服属し国権の一体化が進んでいたためだそうです。そう言えば、イングランドの国旗は竜退治で有名なゲオルギウスの十字ですから、竜の意匠を国旗に入れたら相性はあまり良くなかったでしょうね。で、イギリス人は遊び心を持っていますから、スコットランドが独立した後に、ウェールズの国旗の緑の部分を入れて新しい国旗を作ってみたのだそうです。それがこちらです。ちょっと歯抜けの国旗みたいですね。国旗のデザイン性を見る限りは、スコットランドは独立しない方がよさそうです。
2016.03.08
コメント(0)
-

「十字」分断の歴史
昨日のブログで紹介した、アイルランド、そしてアイルランドの守護聖人である聖パトリックのシンボルとみなされている「聖パトリック十字 (Saint Patrick's Cross)」。1783年にアイルランド王国の筆頭騎士団として創設された聖パトリック騎士団の勲章として使われていたことから、アイルランドのシンボルとされ、連合王国の旗に組み込まれたのですが、イギリスからの完全独立を主張するアイルランドのナショナリストはこれを認めているわけではありません。イギリスが勝手に決めたものであるとして拒絶しているんですね。その代わり、アイルランドの国章はこちらで決まっています。イギリスの国章にも組み込まれているハープですね。さて、いろいろと物議を醸しているイギリスの国旗「ユニオンジャック」。スコットランド人は、自分たちの聖アンドレの十字がイングランドのセント・ジョージ・クロスによって分断されるこの構図が嫌いなので、こんなデザインも用意していたようです。すると、今度はイングランドのセント・ジョージ・クロスが分断されてしまいますから、イングランド人は納得いかないでしょうね。それはそれとして、ユニオンジャックには、一つ足りない国旗があるように思いませんか。それは次回説明しましょう。
2016.03.07
コメント(0)
-

三人の聖人と三つの十字の合体
聖アンドレ(セント・アンドリュー)の十字は、現在もスコットランドの国旗として使われています。こちらがそうですね。ラグビーやサッカーの国際試合で使われているので、お馴染みです。これに対してイングランドの国旗はこちら。ゲオルギオスの十字(セント・ジョージ・クロス) と呼ばれる白地に赤い十字の旗です。ゲオルギオスは、キリスト教の聖人の一人。ドラゴン退治の伝説で有名な軍人です。302年、ローマ軍のキリスト教徒をすべて逮捕してローマの神々に捧げなければならないという命令が下ったときに、ゲオルギウスも逮捕されて棄教を強要されますが、拒んで殉教したといわれています。そしてこのゲオルギオスの十字と聖アンドレの十字が合体してできたのが、初代ユニオンフラッグです。1603年に制定されたそうです。でも、これだと現在のユニオンフラッグ(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の国旗、つまりイギリスの国旗のことです)に比べて、何か足りないですよね。そう、この旗にアイルランドを象徴するとされている聖パトリックの旗が加わります。そして出来上がったのが、こちら。現代のユニオンジャック(ユニオンフラッグ)ですね。
2016.03.06
コメント(0)
-

聖アンドレの十字
金字に赤色の立った獅子というスコットランドの国章と並ぶシンボルにクロスがあります。それがこちら。扇風機ではありません。天上からぶら下がっていた巨大なクロスです。とにかくクロスといったら、スコットランド。そしてそのクロスが象徴するのは、こちらです。先日紹介した国章の下に描かれていたもので、キリストの十二使徒の一人でスコットランドの守護聖人であるセント・アンドリュー(聖アンデレ)を象徴しています。聖アンドレは、ギリシアのアカイア地方でX字型の十字架で処刑され、殉教したことになっています。その聖アンドレの十字架とスコットランドの関係は何かというと、9世紀にスコットランド系ピクト族の王フングスがイングランド系のウェスト・サクソン王アセルスタンに攻められたとき、援軍に駆けつけたスコットランド王アカイウスが戦いの前夜、光り輝く聖アンデレ十字の夢を見たことに由来するそうです。夢の翌日の戦いでスコットランド側は大勝利。このことに感謝し、フングスはセント・アンドリューの寺院を建立すると共に、セント・アンドリュー・クロスを自らの象徴としました。またアカイウスも、セント・アンドリューに因んだ勲章(後にスコットランド最高勲章となるシッスル勲章)を制定したとのことです。ゴルフの全英オープンでよく使われる同名のゴルフコース「セント・アンドリューズ」も聖アンドレに因んだ地名から取っています。アンドリューズと複数形になっているのは、「アンドリュー」の子孫という意味に由来します。
2016.03.05
コメント(0)
-

ひな祭りに梅が満開
ひな祭りの今日、我が家の枝垂れ梅がほぼ満開となりました。写真は昨日のですが、こんな感じで見事に咲いております。今年は暖かい日が続いたので、例年よりも一週間ほど開花が早かったように思います。梅の花の蜜を求めて、朝は多くの鳥たちの訪問を受けるので、とても賑やかです。
2016.03.03
コメント(0)
-

スコットランドの国章とパブ「レッド・ライオン」の関係
スコットランドの国章はイギリスの国章の「盾」の中の右上に描かれていることは前回のブログで紹介しましたが、写真ではよくわからなかったと思われますので、ちゃんとご紹介しましょう。こちらがスコットランドの国章です。金地に赤色の立ったライオンとアザミの花と「フル―・ドゥ・リ(ユリ科のアヤメ)」。フル―・ドゥ・リはフランスの王権の象徴でもあります。スコットランドとフランスは昔から古い結びつきがあったんですね。アザミが使われているのは、アザミを素足で踏んだ敵兵が痛さで叫んだお蔭で敵に奇襲をかけて勝利を得たという故事があり、スコットランドを守った花として好まれているからのようです。中央の立ったライオンのモチーフは、プジョーのエンブレムにも使われていますね。獅子王と呼ばれたスコットランド王ウィリアム1世(1143年 - 1214年)が制定したものです。しかもこのレッド・ライオン(赤いライオン)のデザインと名前は、イギリスのパブでも広く使われています。どうしてイングランドのパブにもスコットランドの国章のシンボルである赤いライオンが使われているかというと、諸説ありますが、子供がいなかったエリザベス1世の後を継いで1603年にイングランドの王座に就いたスコットランド王ジェームズ六世(イングランド王としてはジェームズ1世)が、スコットランドの王がイングランドの王になったことを知らしめるため、公共の場所(パブのことです)にこのシンボルを配したからだとの説があります。そういえば、エイヴベリーの大ヘンジの中央にあるパブもレッド・ライオンでした。こちらです。道路を隔てたすぐそばにはストーンサークルが配置されています。5000年前の古代遺跡の中にもスコットランドが浸透しているわけですね。このレッド・ライオンは、エイヴベリーに来たときには必ず立ち寄る場所でもあります。ところで最初に紹介したスコットランドの国章はどこで撮影したかというと、こちらです。スコットランドのスターリング城の客間だったか居間の暖炉の上に掲げられておりました。
2016.03.02
コメント(0)
全21件 (21件中 1-21件目)
1