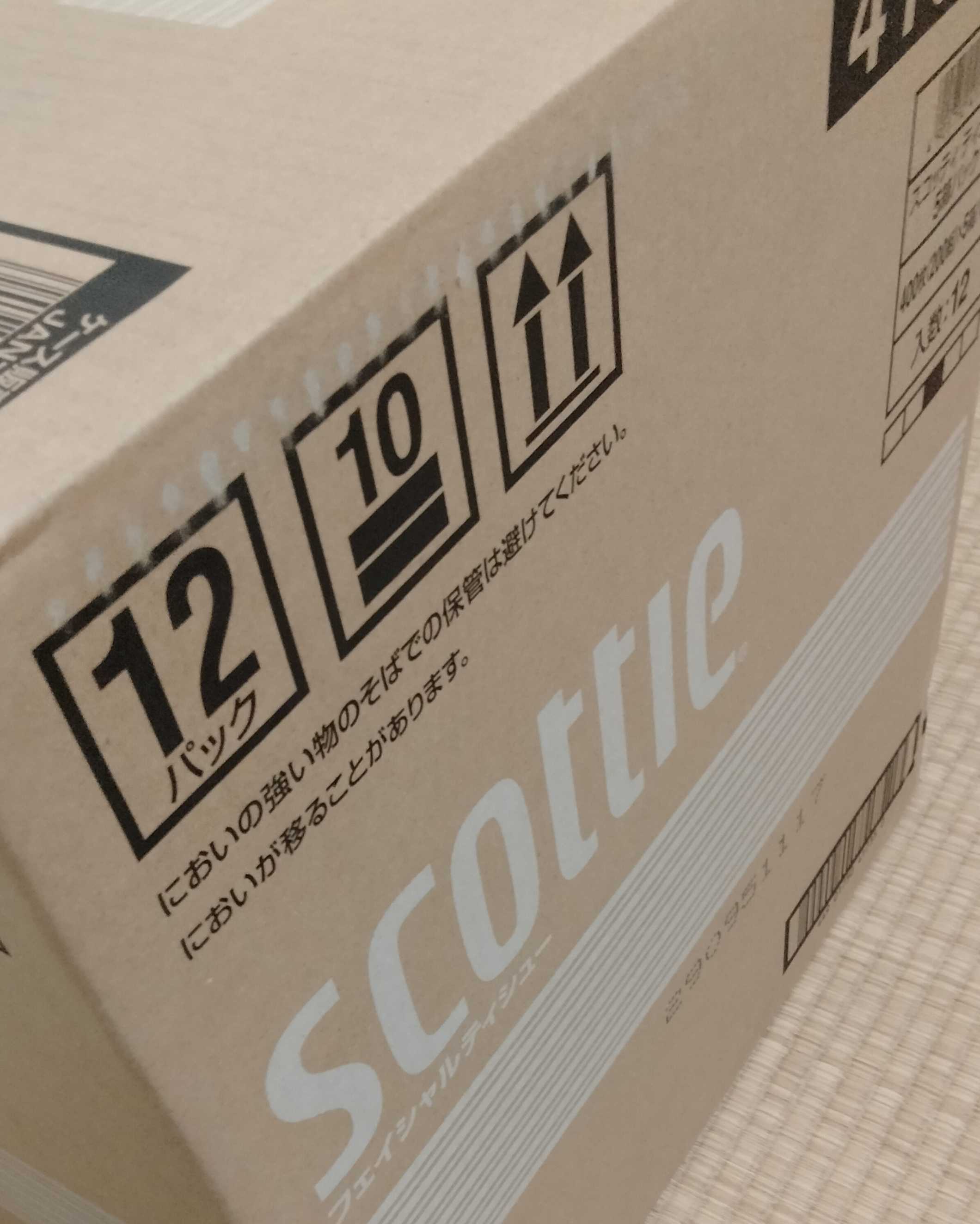2016年02月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

イギリスの国章に込められた思い
古代人の使ったシンボルの話を続けてきましたが、ついでに現代人が使っているシンボルについても言及しておきましょう。その最たるものが、国旗や紋章ですよね。まずはこちら。これはイギリスの国章ですね。王立植物園「キュー・ガーデン」の門に施されていました。左のライオン(獅子)はイングランドを、右のユニコーンはスコットランドを象徴します。で、ライオンとユニコーンが真ん中の盾を支えているという図式で、その盾の上には王冠が載せられています。この写真からはわかりずらいですが、盾には四つのシンボルが描かれています。左上と右下の対角線上にあるのは、イングランド王室の紋章である黄金の獅子三頭。右上の獅子(本来は金の地に赤い獅子)はスコットランドの紋章、左下の竪琴はアイルランドの紋章です。盾の下には通常、バラ(テューダー・ローズ)、アザミ、シャムロックが描かれ、それぞれイングランド、スコットランド、アイルランドを象徴します。また、盾の周囲には、フランス語で 「HONI SOIT QUI MAL Y PENSE」というう標語が記されています。「悪しき思いを抱く者に災いあれ」という意味のことわざで、一種の呪術の言葉でもあります。まあ、このようにしてイギリスを守る必要があったんですね。ところで、スコットランドを象徴する右のユニコーンですが、凶暴な聖獣であるため、鎖でつながれているんですね。写真で、左の後ろ足に絡みついているのが鎖です。スコットランドが独立しないように、仕掛けられた鎖なのかもしれませんね。
2016.02.29
コメント(1)
-

コンパスと定規、キャンベルとマクドナルド
次もオークニーの博物館で撮影した石板です。残念ながら資料がないので、時代と出土場所はわかりません。かなり新しい時代(10世紀以降?)に彫られた石板だと思いますが、現代の彫刻と説明されても違和感がありませんね。鳩のような鳥が描かれており、その下にはコンパスと分度器を併せたような幾何学模様が施されています。波形や円、葉形(唐草模様)のイメージも描かれていますね。シンボルのオンパレードという感じがします。その中でも面白いのが、「コンパスと分度器」のようなシンボルです。どこかで見たことがありませんか。そう、「コンパスと定規」のフリーメイソンのシンボルですね。そういえば、昨年たまたま訪れたスコットランドのお城でも、このシンボルを見つけました。中央に「五芒星」とともに「コンパスと定規」の勲章が置かれていますね。ほかにもこのようなコインが展示されておりました。コンパスの上には団結と秘密の保持を示すとみられる「握手」が、その上には「剣」と「太陽」のようなシンボルが描かれています。この「太陽」は、古代エジプトのアテン神のシンボルと同じですね。アテン神といえば、多神教文明の中で起きた一神教の宗教革命「アマルナ革命」を思い出しますね。非常にユダヤ教的な性質を感じます。コンパスの両側の灯篭か燭台のようなものの上には「G」と「M」が描かれています。「G」は神(GOD)とか、幾何学(geometry)、栄光(Glory)、寛容( Grandeur)などを意味する記号とされています。「M」は石工(mason)のことでしょうか。あるいは『ダヴィンチ・コード』的にマリアのMだったりして。で、このフリーメイソンのシンボルを有するのはどこのお城かというと、グラスゴーの北西に位置するアーガイルにあるインヴェラリー城です。アーガイル侯爵として知られるキャンベル氏族のお城です。アメリカの「キャンベル・スープ」創業者ジョセフ・キャンベルとつながりがあるかどうかは不明です。このお城の写真を見てすぐに、どこかで見たことがあると思った人はかなりの英国ドラマ通です。そう、あの『ダウントン・アビー』に出てくるローズ・マクレアのマクレア家のスコットランドの別荘として登場したお城なんですね。といっても、撮影は裏口を正面玄関に見立てて行われたそうです。その裏口がこちら。キャンベル氏族は、もともとスコットランド氏族内で「イングランド寄り」とされていました。その中で、1692年に起きたのが、グレンコーの虐殺です。イングランド政府内強硬派とキャンベル氏族を中心とするスコットランド内の親英勢力の手によって、マクドナルド氏族の村であるグレンコー(スコットランド)で起きた虐殺事件です。この事件でマクドナルド氏族が事実上の「だまし討ち」にされて殺されました。キャンベル氏族は、虐殺に加担したことを機にスコットランドの氏族社会で孤立を深めていきました。今はそうではないらしいですが、20世紀後半ぐらいまでは、グレンコーやマクドナルド氏族系のパブなどの多くで「行商とキャンベルはお断り」の札が掲げられていたそうです。時代が変わって、それがアメリカで、「マクドナルド(ハンバーガー)」と「キャンベル(スープ)」の戦いになったのだとしたら、それはそれで不思議な因縁を感じますね。
2016.02.27
コメント(0)
-

スコットランドの古代遺跡から見つかった「日の丸」
オークニー諸島本島にある博物館ではもう一つ面白い石板が展示されていました。古代スコットランドの「日の丸」です。本来なら「カップ&リングマーク」に分類されるべきものですが、巨大な石板に彫られているので、存在感がまるで「日の丸」です。このマークは、国旗か部族の旗のの代わりだったのかもしれませんね。また同博物館には次のような展示もありました。古代人の石板ノート(メモ帳)です。ルーン文字(西暦2世紀ごろから使われはじめたゲルマン人が用いた古い文字体系の音素文字)でしょうか。かなり細かい線刻が施されています。5000年前の遺跡は、後の人たちにとってもキャンパス替わりに使われていますから、上から重ねて刻まれていくこともあります。上の写真の線刻も、西暦2世紀以降の比較的新しいものではないかと思われます。
2016.02.25
コメント(0)
-

飛騨地方から見つかった謎の「石冠」と「御物石器」
北陸から中部地方の縄文遺跡から見つかった石冠と御物石器をご紹介しましょう。私が撮った写真が見つからなかったため、吉朝則富氏の『幸福な縄文』というエッセイから転載させてもらいました。上の二つが石冠で、一番下が御物石器です。いずれも岐阜県から出土したもので、上から順番に神岡町山田、丹生川村下上野、下呂町乗政でそれぞれ見つかりました。縄文晩期の作品と見られています。今でこそすり減って模様が見えなくなっていますが、かなり精巧な紋様が彫られていたように感じます。次のスケッチは『野々市町御経塚遺跡』からの転載です。右上の御物石器に分類できると思われる「比良型呪術石器」には綺麗な紋様が彫られていますね。その下の石冠にも線刻が見られます。次は『飛騨国府シンポジウム、古代の飛騨、その先進性を問う』からの転載の転載(孫引き)です。左上の岐阜県丹生川村から出土した石冠には明確なシンボルが彫られていることがわかります。また、多種多様な紋様や形の石製品が製造されたこともよくわかりますね。こうした石製品は、特殊な祭祀に使われたであろうと推測されているだけで、その形態、機能、起源については謎に包まれています。それは先に紹介したオークニー諸島の石製品も同様です。右の石製品が縄文の石冠に似ているように感じられるんですよね。同じ用途であった可能性もあります。少なくとも、両手で持ったり、片手で持ったりできる突起が付いている形態には類似性があります。この飛騨地方の石製品に刻まれた紋様や、その形態については、詳細な資料が手に入り次第、このブログでも紹介、解説していきたいと思っています。
2016.02.24
コメント(0)
-

古代スコットランドの遺跡で見つかった「達磨」
石冠や御物石器のいい写真が見つからないので、とりあえず、オークニー本島の遺跡から出土した面白い土偶を紹介します。古代スコットランドの達磨です。まさに「達磨」ですね。かわいい目が付いています。オークニー本島カークウォールにあるオークニー博物館に展示してあったパネルを撮影したもので、パネルには地元では「ブロガー・ボーイ」というニックネームが付いていると書かれていました。ここには書かれていませんが、おそらく5000年前のストーンサークル「リング・オブ・ブロガー」の周辺から見つかったものだと思われます。
2016.02.23
コメント(0)
-

5000年前に使われていた「サイコロ」
岐阜や北陸の縄文遺跡で見つかっている石冠や御物石器と、オークニー諸島から出土した石製品の比較をする前に、もう一つ同諸島の出土品と、縄文遺跡の出土品で類似性が見られるものをご紹介しておきましょう。それがこちらです。骨を削って作った「サイコロ」と思われる道具です。これも公式ガイドブック「スカラ・ブレイ」に掲載されているものです。このサイコロと似たものが、東北の大湯環状列石から見つかっています。前にも紹介しましたが、「計算器」とされる土板です。骨と土で材質は違いますが、5000年前ごろには、数値を表す道具が世界的に普及していたのかもしれませんね。
2016.02.20
コメント(0)
-

オークニー諸島「スカラ・ブレイ」から出土した謎の石製品
約5000年前の遺跡スカラ・ブレイから出土した石製品です。スカラ・ブレイの公式ガイドブックの写真をコピーしたものです。レプリカとは書いていないので、これは本物の写真と思われます。それにしても、非常に洗練された幾何学的な石製品ですね。今度写真を載せるつもりですが、一番右の石製品などは、岐阜県など中部地方の縄文遺跡から見つかっている「石冠」と呼ばれる石製品に非常によく似ています。縦五段、横7段の碁盤目と三角形を基本にした図形のコンビネーションは見事です。何かの占いをするためのものでしょうか。中央下の石製品も変わっていますね。右側はよくわかりませんが、左側には四つの突起が付いていて、中央部分は縦溝5本と横溝4本が2セット彫られているように見えます。一見すると、手榴弾です。その上の多面体は機雷でしょうか。もちろん戦争の道具ではなく、スピリチュアル的な道具として使われたように思われます。あるいは遊び道具?いったいどういう使われ方をしたのか、非常に興味があります。(続く)
2016.02.19
コメント(0)
-

オークニー諸島の遺跡から見つかった土器片と縄文土器
ブリテン諸島最北のスコットランド・オークニー諸島にある5000年前の遺跡「スカラ・ブレイ」。宇宙的な立体図形の石製品が出土している一方で、見つかった土器を見ると、非常に縄文土器に似ています。まずはこちらをご覧ください。スカラ・ブレイから出土した陶器の一部です。縄紋ではなく溝を掘ってつくった紋様ですが、モチーフ的にかなり似た感じを受けます。次に紹介するのも、スカラ・ブレイで見つかった土器片の数々です。こうした縄紋を使っていない土器片を見ると、1万6500年前の縄文遺跡から出土した土器を思い出します。青森県津軽半島の大平山元1遺跡の土器です。オークニー諸島の土器に関しては、日本の東北、北海道の縄文遺跡から見つかった土器とかなり類似性があるように思われます。一方、石製品に関しては日本の中部地方の縄文遺跡から見つかったものと似ているように思われます。次回からは、それをさらに詳細に見て行きましょう。
2016.02.18
コメント(0)
-

5000年前の遺跡から見つかった宇宙的な立体図形
今日紹介するのは、オークニー諸島で発掘された石製品を復元したレプリカです。オークニー本島にある「鷲の墓」と呼ばれる5000年前の遺跡に併設された資料館に展示されている石製品のレプリカを撮影したものですが、右から「正四面体」、多面体、それに球状の石製品が並んでいます。このように綺麗な状態で見つかった石製品は少ないと思われますが、5000年前当時からかなりの加工技術と立体的に優れた概念を持っていたことが偲ばれますね。右の正四面体の石に刻まれた渦巻き文様も見事です。アイルランド・ニューグレンジの羨道墳入り口前に置かれた巨石に刻まれた紋様と同質のものが、ここに描かれています。すなわち宇宙の三原則。繰り返し、対称性、同質結集ですね。やはりかなり宇宙的なモノを感じます。五千年も前に、既にこのような作品を造っていたとは、驚くほかありません。
2016.02.16
コメント(0)
-

オークニー諸島で見た巨石と夕陽のコラボレーション
さて、今度はスコットランド最北のオークニー諸島へと移動します。ここの遺跡からは、紀元前3100年から同2500年までの非常に高度で洗練された作品が多く出土しています。これまで紹介した模様やシンボルは、どちらかと言うと平面的なものが多かったですが、ここで注目されるのは立体図形です。たとえばこのような石製品が見つかっています。多面体ですね。もっと洗練された正四面体も見つかっています。でもそうした立体シンボルの話をする前に、今日はオークニー本島のストーンサークル「リング・オブ・ブロガー」で撮影した夕陽と巨石のコラボ写真をご紹介しましょう。息を呑む美しさです。立石の造形も、バラエティーに富んでいて見事ですね。次回からはオークニーの古代遺跡で見つかった「立体的なシンボル」を主に取り上げて行きます。
2016.02.14
コメント(0)
-

岸壁に刻まれた岩絵が奏でるシンフォニー
キルマーティン渓谷から100キロほど南東に移動すると、同じスコットランドのイースト・エアシャーに「バロッホミルの岩絵」があります。キルマーティンの岩絵は平らな岩盤に描かれていましたが、こちらは岸壁に岩盤に彫られた岩絵です。人間の顔のように見える岸壁に、無数のカップマークやリングマークが彫られています。もっと近づいてみましょう。ここまでダイナミックに描かれると、ほとんど音符のように見えてきます。岩絵の交響曲が聞こえてきそうですね。
2016.02.11
コメント(0)
-

キルマーティン渓谷アフナブレックの岩絵
今日ご紹介するのは、キルマーティン渓谷アフナブレックの岩絵です。上の写真の岩盤にマークが彫られています。約5000年前の作品であるとみられています。すぐに見つかるのは同心円マーク。六重の同心円ですね。たくさん花丸をもらった気分になります。ちなみに「六」は、滝とか穴の意味があり、集中のシンボルでもあります。ちょっと薄くなっていますが、他にも同心円のマークがありますね。また同心円の側には、4つのカップマークが意味あり気に彫られています。。「4」は人間関係の意味で木のエネルギーを表します。丸はリーダーシップですから、4人のリーダー格の人間が重要な役割を果たしたことを示しているように思われます。
2016.02.08
コメント(0)
-

岩に刻まれた5000年前の古代人の「歴史書」
キルマーティン渓谷の中でも、最も壮麗な岩絵が刻まれているのが、今日紹介するキルミカエル・グラッサリーです。この柵に囲まれた一枚の平たい岩には、無数の彫刻が彫られています。制作されたのは、紀元前3500年~同1000年の間ではないかとみられています。主にカップマークとリングマークの組み合わせですが、三つのカップマークを丸で囲んだ彫刻も見られます。さらによく見ると・・・上の写真の中央右斜め上には、逆S字マークのようなシンボルも見えます。こうしたシンボルの意味ですが、私はやはり古代人が彼らの歴史物語を記したように感じられます。時系列的には、小山を正面にして左から右に時間が流れます。二番目と三番目の写真で言えば、上から下ですね。最初はシンプルなカップマークが続きますが、やがてそれが大きなグループになり、他のグループと合流。時間が経過すればするほど、より複雑なグループを形成するようになった様を描いているのではないでしょうか。それぞれのカップはそれぞれの家族や部族に対応し、それが歴史として刻まれたのではないかと私は見ます。岩絵は古代人の歴史教科書みたいなものだったのかもしれませんね。(続く)
2016.02.07
コメント(0)
-

スコットランド西部にあるキルマーティン渓谷の岩絵
スコットランド西部にあるキルマーティン渓谷には、古代のシンボルが刻まれた巨石群をいたるところに見ることができます。まずは最もシンプルなカップとリングマーク。ゲール語なので何と発音するのかよくわからないのですが、Baluachraig(バルアックレイグ?)の岩に刻まれたマークです。約5000年前の作品であるとみられています。丸い窪み状に彫られたものがカップマークで、中央のカップマークの外側に彫られた輪がリングマークと呼ばれています。上の写真のカップマークの配列は北斗七星に似ています。リングマークには同心円のものと、渦巻き状に近いマークも見られます。上の写真のリングマークは二重の同心円でしょうか、それとも渦巻き型?ちょっと長年の年月が経って薄くなっているので、わかりずらいですね。こうしたシンプルなカップマークとリングマークを見ても、その配置には意味が込められていたと考えられます。一つの見方は星座ですが、もう一つの見方は家族間(家系)や家族の中の人間関係を表した系図のようなものであると見ることもできますね。次はキルマーティン渓谷にあるもっと複雑な岩絵のシンボルを見てみましょう。(続く)
2016.02.06
コメント(0)
-

「のっぽのメグ」に刻まれた同心円マーク
スコットランドではないのですが、スコットランドに極めて近い、イングランド北西部のカンブリア地方にある有名なストーンサークルをまずご紹介しましょう。ここにはスコットランドの巨石に刻まれたシンボルと同じシンボルが見つかっています。巨石遺構の名前は「のっぽのメグとその娘たち」です。牛と巨石。イギリスでは見慣れた風景です。この巨石はストーンサークルを形成する立石の一つで、全体ではこうなっています。ストーンサークルの外側に一際目立つ立石が配置されています。上の写真の左端に移っている立石です。この外側の立石が「のっぽのメグ」で、ストーンサークルを形成する石がその娘たちなんですね。これが高さ3・6メートルの「のっぽのメグ」です。岩肌をよく見ると、同心円が薄くなったのも含めて5、6個刻まれていることがわかります。丸は天のシンボルでリーダーシップを表します。五重となった同心円は自由のシンボルでしょうか。特別な石であったことが紋様からも読み取れますね。このストーンサークルは道路も横切っています。楕円形のサークルの長径は約100メートルあります。エイヴベリーの大ヘンジもそうでしたが、サークルが巨大すぎて、迂回することができなかったのかもしれませんね。
2016.02.05
コメント(0)
-

カルナックの列石と「マニオの森の巨大メンヒル」
フランス・ブルターニュ地方の巨石の岩絵からスコットランドの巨石の岩絵に進む前に、ブルターニュ地方で撮影した他の巨石群について簡単に紹介しておきましょう。ブルターニュ地方で最も有名な巨石群が、カルナックの列石です。カルナックの列石は、巨大なメンヒルが総延長およそ4キロにわたり数列に並んでいる、壮大な巨石遺構です。主に三つの列石群からなり、西から順にメネク列石(長さ約1167メートル、幅約100メートル、立石数1169個)、ケルマリオ列石(長さ約1120メートル、幅約101メートル、列石数1029個)、ケルレスカン列石(長さ約860メートル、幅約139メートル、立石数594個)となっています。いずれも古い場合は紀元前5000年、遅くとも紀元前3000年から同2000年ごろに建造されたのではないかと考えられています。上の写真は、確かケルレスカン列石です。カルナックには単独の立石もあります。ケルレスカンの列石のそばのマニオという森の中にある「マニオの大メンヒル」です。高さ約6メートルあります。で、このメンヒルを見ると思い出すのが、スコットランドのアウター・ヘブリディーズ諸島のルイス島にあるメンヒルです。「The Trushel Stone(トラシェルの立石)」と呼ばれています。高さは約6メートル。正確に測ると「マニオの大メンヒル」のほうが50センチほど高いようですが、ほぼ同じ大きさなんですね。見上げたときの感覚がほぼ同じなので、連想ゲーム的に、この二つのスコットランドとフランスのメンヒル(立石)が結びつくわけです。と、スコットランドの立石に話を振ったところで、次回からはスコットランドの岩絵を詳しく見て行こうと思っています。
2016.02.04
コメント(0)
-

石に刻まれた古代人の「足跡」
これもカルナックの博物館で撮影したものですが、どこで発見されたかは覚えておりません。でも面白いので掲載しますね。足形です。文字通り、岩に「足跡」を残したわけですね。まるでハンコみたいです。同じモチーフの「足跡」は北海道の縄文遺跡でも見つかっています。既に紹介した写真ですが、縄文時代早期後半(紀元前5000年)の垣ノ島B遺跡から出土された足形付土版です。「足」は木のエネルギーで、人間関係を象徴します。足には人間関係の「ぬくもり」みたいな感覚がありますね。特定の人に対する「愛おしさ」が伝わってくるようです。
2016.02.02
コメント(0)
-

石に刻まれた古代の歴史と予言?
カルナック博物館では、次のような面白い線刻模様の巨石も展示してありました。フラッシュ撮影した際、展示の内容を書いた案内板が反射してしまい、どこの遺跡の石なのかわからなくなってしまいましたが、カルナック周辺の遺跡で見つかった石のレプリカとみられます。それにしても、かなり複雑な線刻模様です。おそらく文字に極めて近いシンボルなのではないでしょうか。ネイティブ・アメリカンのホピ族も、このようなシンボルを書いて、彼らの過去と未来の歴史(予言)を刻んでいたように記憶しています。私がここから受ける印象も同じで、何か時系列的なモノを伝えようとしていたように感じられます。
2016.02.01
コメント(0)
全18件 (18件中 1-18件目)
1