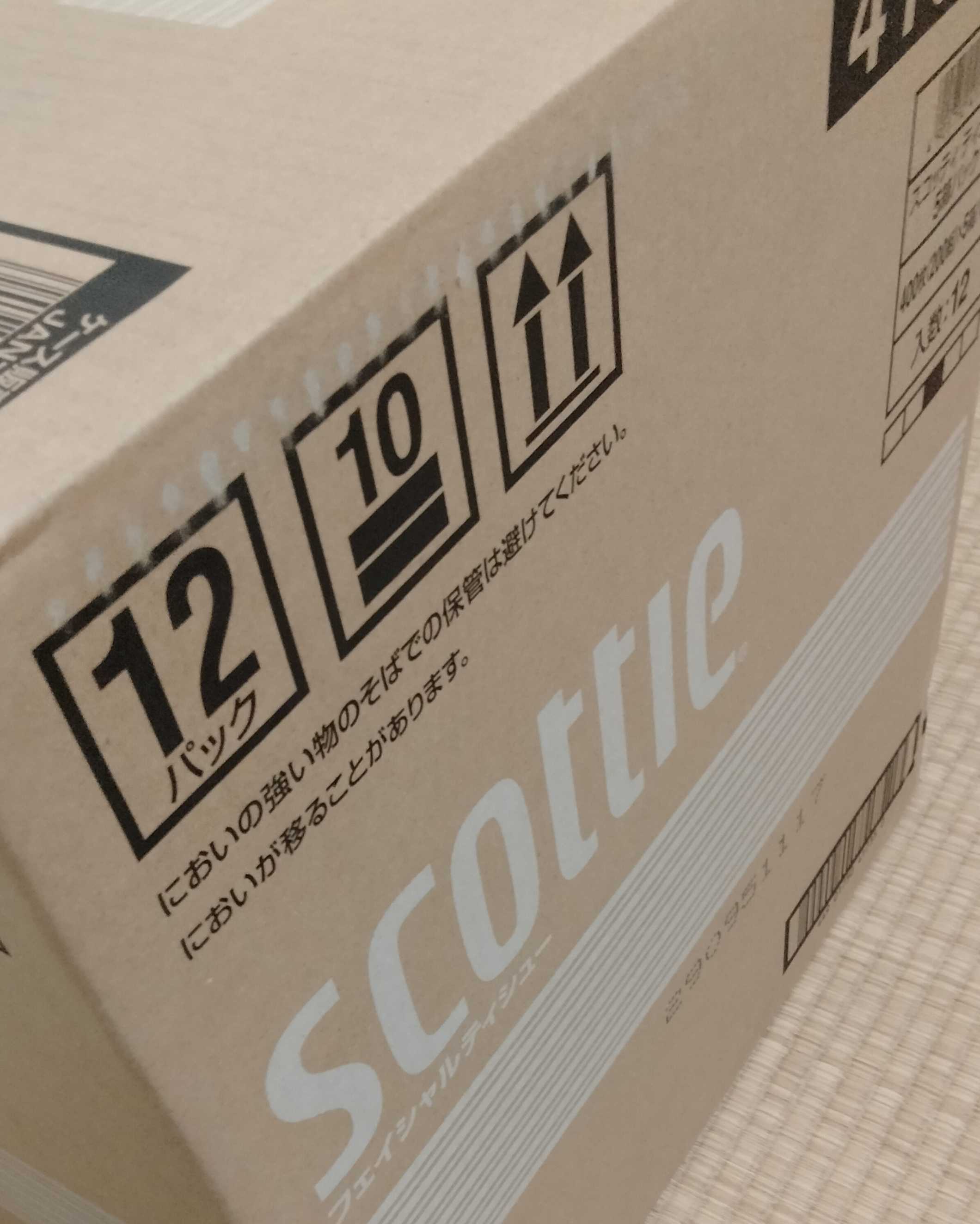2016年07月の記事
全24件 (24件中 1-24件目)
1
-

アイルランド見聞録28(ノックナレア登山)
翌6月5日。雨の予報もあったのですが、曇り空のスタート。晴れる可能性もあったので、予定通りノックナレアに登ることにします。キャロウモアから半島の先の方へと進み、ノックナレア登山口にある駐車場に車を止めます。駐車場はガラガラ。天気がどうなるかわからないので出足が鈍かったのでしょう。その後快晴になるのですが、この日は日曜日ということもあり、登山から戻ってきたら駐車場はいっぱいになっていました。ノックナレアの案内板。頂上までは45分くらいかかります。段々晴れてきました。麓だと近すぎて、女王マイーヴの墓が見えませんね。最初はなだらかな、このような道をずっと進みます。途中、牛さんたちに歓迎?の挨拶を受け・・・ドンドン進むと、やがて急な坂道に。天気も快晴となり、気温が上昇。汗が滲んできました。(続く)
2016.07.31
コメント(2)
-

アイルランド見聞録27(キャロウモア遺跡群の撮影)
薄日が差してきたので、この日のうちに撮影できるものはしておきます。というのも、五年前の前回はスライゴ―の郊外にある、巨大な古代遺跡が点在するキャロウキールを訪れたものの、雨に降られてあまりいい写真が撮れなかったからです。そのキャロウモアに向かいます。まだ曇っていますが、遠くに日が降りているので撮影を開始します。」その光がもう少し広がって来たので、再び撮影。手前がキャロウモアのストーンサークルで、遠くに見える丘が標高327メートルのノックナレア。ノックナレアの頂上には「女王マイーヴの墓」があります。丘の上にある、出べそのように出っ張っているがその墓です。引き返そうとしたら、さらに日が差して来ましたので、キャロウモア巨石群中央にある石塚を撮影します。キャロウモア遺跡群の外れにあるドルメン。最後に再び、マイーヴの墓があるノックナレア。このマイーヴの墓は本当に遠くからでも見ることができます。キャロウモアの遺跡群と一体的に造られていることは明白ですね。翌日、もし晴れたら、この山に登ってみることに決めました。(続く)
2016.07.30
コメント(0)
-

アイルランド見聞録26(ベンブルベンの麓)
北アイルランドのドラムスキニーのストーンサークルを見た後、雨が降ってきたこともあり、この日の宿泊先であるスライゴーへと急ぎます。再びアイルランドに入って、脇目もふらずにひたすら南下。イエイツの心の故郷とされるスライゴ―に到着しました。ここには二連泊します。その宿屋から見た風景。遠くにベンブルベンというスライゴーを代表する山が見えます。雨が止んでちょっと日が差してきたので、撮影します。標高は526メートル。イェーツは子供時代によくここで過ごし、「Under Ben Bulben(ベンブルベンの麓)」という詩も書いています。Under bare Ben Bulben's head In Drumcliff churchyard Yeats is laid. An ancestor was rector there Long years ago, a church stands near, By the road an ancient cross. No marble, no conventional phrase; On limestone quarried near the spot By his command these words are cut: Cast a cold eye On life, on death. Horseman, pass by!岩肌がむき出しのベン・ブルベンの崖の下、ドラムクリフの教会墓地にイエイツは眠る。先祖はその教区の牧師であった。今となっては遠い昔の話。近くには教会があり、道端には古い十字架が立っている。大理石でもなければ、常套句も刻まれていない、近くで切り出された石灰岩の墓碑に故人の意思により次の言葉が刻まれている冷ややかな目を向けよ、生と、死に。馬に乗る者よ、通り過ぎよ!で、実際にベンブルベンの麓にはイエイツが眠る墓がドラムクリフ村の教会の墓地にあることは、五年前のブログでも紹介しましたね。これがその時の写真です。詩に書かれていた通り、最後の三行(Cast a cold eye On life, on death. Horseman, pass by!)が刻まれていますね。一種の遺言詩のようなものです。日の光が幾筋も降りてきました。(続く)
2016.07.29
コメント(0)
-

アイルランド見聞録25(ドラムスキニーのストーンサークル)
いただいた地図の巨石遺構探しはこれぐらいにして、次に再び北アイルランドに入り、ドラムスキニーという町を目指します。途中、景色のいいところで写真を撮りながら・・・・ドネゴールを通り越して、北アイルランドのドラムスキニーの近くまでやって来ます。ドラムスキニーの町の外れに教会があるのですが、その反対側の牧草地に三本の立石を見つけたので、車を止めて撮影。列石ですね。後で調べたらMontiaghroe(モンティアグロー)の列石と書かれていました。この場所からドラムスキニーのストーンサークルまでは3キロほどです。ドラムスキニーのストーンサークルに到着。手前の石で囲まれた土盛がケアン(石塚)で、その向こうに直径約13メートルのストーンサークルがあります。そしてちょっと変わっているのが、ストーンサークルの右側の列石です。列石だけをアップにしてみましょう。小さい石ですが、一直線に並べられていますね。直線の長さは15メートルあります。衛星写真で見ると、ほぼ南北線上に並んでいるように見えます。次の写真は、ストーンサークルの石のアップ。人影みたいに見えますね。ストーンサークルと石塚が作る中心軸の傾きを見ると、冬至の日の出か夏至の日の入りと関係がありそうな並びになっておりました。やはり天体の動き(あるいは季節)と密接に関連した儀式のようなことが執り行われていたのではないでしょうか。今から4300年ほど前に造られたのではないかとみられています。(続く)
2016.07.28
コメント(0)
-

アイルランド見聞録24(ケルト十字と王宮の墓)
グレン・コラムキルの村には、このような石柱が立っておりました。キリスト教文化の十字と、ケルト文化の円が合体した、いわゆるケルト十字ですね。キリスト教流入後、ケルト文化との融合のシンボルとして出現しました。もらった地図に描かれた巨石遺構は、この村から南西に約3キロ海岸線を下って再び内陸に2キロ進んだところにあります。地図によると、全部で4つの巨石の墓(Megalithic Tomb)と一つの立石があることになっていますが、見つかりません。車を路肩に止めて、地元に人に道を尋ねます。すると、地元の人でも見たことがないというんですね。だけど一つだけ「巨石の墓」の場所を知っているというので、その場所まで案内してくれました。車を空き地に止めて、小川の流れる小道を進みます。すると、目の前に「巨石の墓」が現れました。荒野の真ん中にポツンとある巨石遺構です。「Court Tomb(王宮の墓あるいは広間のある墓)」と呼ばれる、回廊と広間のある「巨石の墓」に分類されています。どういう意味があるかわかりませんが、「Cloghanmore(クロガンモア)」という名前が付いています。奥にある石室の墓。こちらは広間です。中央に巨石が置かれているのが印象的ですね。(続く)
2016.07.27
コメント(0)
-

アイルランド見聞録23(林の中の立石と大渓谷のパノラマ)
翌6月4日の土曜日。アーダラのゲストハウスを発つときに、ゲストハウスの御主人とその息子さん(と言っても30代とみられますが)と一緒に、五年前の話をして盛り上がり、長時間話し込むことになりました。私が古代の巨石遺構を探査しているのだと告げると、非常に興味を持ってくれて、昔息子さんがお父さんからもらったという古い地図を見つけてくれて、私にくれると言います。そして地図上に記された立石などについて、父親のほうが説明。親子共に古代の巨石には興味があり、地図上の巨石を訪ね歩いたことがあるのだと言います。そのような貴重な地図をもらったので、お礼に私の本『竹内文書と平安京の謎』を差し上げて、内容を説明すると、二人とも驚いていました。特にイギリスのシルベリー・ヒルとマーリンの丘が緯度で秒数も一致することや、ナスカの地上絵やエジプトのピラミッドも精密に測量されて遺構が配置されていることを知って、特に驚嘆したようです。名残惜しかったのですが、二人に別れを告げて、地図で教えてもらった巨石探しに出かけます。アーダラ郊外の自然はとても綺麗です。町のはずれの川を渡ったところに車を駐車して、立石があるという場所を目指します。上の写真の橋を渡った右手の林の中に、目指す立石があるようです。その林の中に分け入って進みます。最初は気が付かつかずに通り過ぎてしまったのですが、振り向くと林の中に立石が立っておりました。長方体と球のセットになっていますね。ほとんど地元の人も行かないような場所でひっそりと立っている立石ですが、今でも存在感があり、威厳を保っているように感じました。もらった地図に示された巨石遺構はこれだけではありません。上の写真の立石はアーダラの町のすぐ外れにありましたが、次に目指したのは、アーダラから西南西に30キロ近く離れたグレン・コルム・キルのそばにある巨石遺構です。グレンゲッシュ・パスという道路を通って行くのですが、途中、地元の言葉で「グレアン・ガイス(あるいはゲイス)」(白鳥の渓谷)を通って行くとつづら折りの難所があります。そしてそれを登りきると、素晴らしい見晴らしが待っています。これが白鳥たちの渓谷ですね。渓谷自体が白鳥が羽根を広げたような形になっているからか、それともハクチョウたちがたくさんいたから名付けられたのかは、わかりません。とにかく壮観な眺めでした。ちなみに氷河が作った渓谷です。45分ほど運転したでしょうか、ようやくグレン・コルム・キルに到着します。崖の上に見える塔は、ナポレオン時代にフランス人が攻めてこないか見張った信号所(見張り塔)だそうです。(続く)
2016.07.26
コメント(0)
-

アイルランド見聞録22(アーダラの定宿)
五年前に訪れたドルメンなどを訪ね歩いているうち、宿屋へのチェックイン時間(通常午後2時)となりましたので、この日の宿泊先であるアーダラのゲストハウスに向かいます。実は五年前にもこのゲストハウスに泊まっています。町の中心地からちょっと離れた丘の中腹にあります。ゲストハウスに到着。庭にバラ園のある静かなゲストハウスです。部屋からの眺めはこんな感じ。西洋シャクナゲが満開となっていますね。このゲストハウスの夕食を予約します。夕食までは時間があったので、近くの海岸まで車ででかけて、散策します。家族連れが浜辺でのんびり過ごしていますね。まだ冷たくて泳げませんが、海はとっても綺麗です。再びゲストハウスに戻って、夕食まで部屋でのんびりします。音楽祭のプログラムで、このゲストハウスでもライブがあります。夕食の後、食堂隣のバーでギターの弾き語りの生演奏を聴いて楽しんだ後、就寝しました。(続く)
2016.07.25
コメント(0)
-

アイルランド見聞録21(アーダラ)
レタケニーからアーダラまでは車で一時間ほど。お昼前にはアーダラに到着します。宿屋にチェックインするには早すぎますから、まずはツイード工房を見学します。昨日写真で紹介したトゥリオナ・デザインの工房です。快く機織り作業を実演してくれます。写真撮影もOKなので、何枚か撮らせてもらいました。横糸を付けた木製の道具が、目にも留まらぬ速さで縦糸の間を右へ左へと駆け抜けて行きます。上の写真で言うと、中央付近を通過中の木の色をした透明の物体が横糸を付けた道具です。道具の名前はわかりませんが、手織り機ですから、手でこの道具を左、右と飛ばすわけです。その時同時に動かすのが、足。足業と手業が絶妙に合わさってツイードが織られていくわけです。アーダラではちょうど町を挙げての音楽祭の最中で、町のあちこちに世界中の旗が掲げられていました。ほかの工房なども見て歩きましたが、それでも時間が余ったので、アーダラの郊外にあるドルメンを見に行くことにしました。ロバですね。ロバの向うの丘の上に、ポツンと立っている巨石構造物がドルメンです。
2016.07.24
コメント(0)
-

アイルランド見聞録20(レタケニー)
ゴースの花が咲く季節になりました。この日(6月2日)はレタケニー泊です。レタケニーは、アイルランド北部のドネゴール地方にある一番大きな都市です。街中に入ると、あちらこちらにショッピングエリアがあります。早目にホテルに着いたので、午後の残り時間はショッピングに費やしました。その中で、あるお店の女主人が話し好きで、ちょっと話し込みます。はるばる日本から来たなら、どこどこへ行きなさいとか、いろいろとアドバイスをくれます。ショッピングの後は、そのアドバイスに従って、海岸線をドライブ。紹介されたレストランで夕食を取り、この日は早目に休みました。翌6月4日は、同じドネゴール州のアーダラへ。ご覧のように、ツイードの名産地です。(続く)
2016.07.23
コメント(0)
-

アイルランド見聞録19(ベルタニー・リング)
この日の宿泊先であるアイルランドのレタケニーに行く途中、最後に立ち寄ったのは、ベルタニー・リングと呼ばれるストーンサークルです。車を止めた場所から林の中の歩道を5分ぐらい歩くと、開けた原っぱのような場所にベルタニー・リングが見えてきます。こちらがそのストーンサークルの写真。ここでも空の雲がリング状に並んでいますから、天と地でシンクロが起きていますね。よく見ると、南東の離れた場所にポツンと立石が立っています。上の写真で言うと、リングの左に写っている立石がそれです。近づいて撮影します。これって、どこかで見たことありませんか。そう、ストーンヘンジのヒールストーンに似ています。ちなみにヒールストーンの写真はこちらです。日時計であると同時に、夏至の日の朝、ストーンヘンジの中心から見ると、このヒールストーンから日が昇るんでしたね。ストーンヘンジのランドマーク的な役割を果たしていました。ベルタニー・リングのこの立石も、おそらく冬至の日の出や夏至の日没と関係があるのだと考えられます。案内板によると、このリングは64個の立石から成っています。ただし、どうやらオリジナルは80個の立石があったようです。建造年代ははっきりとはわかっていませんが、このタイプのストーンサークルは紀元前1400年から同800年のものが多いそうです。建造目的もわかっていませんが、太陽や月の観測をして、何らかの宗教的儀式をやったのではないかとみられると書かれていました。その案内板には、スコットランドで見られるようなカップマーク(カップ状の窪み)が彫られた石もあるとも書かれていましたので、探します。すると、ありました。こちらがそのカップマーク付の立石です。中央右側の石の側面にびっしりとカップマークが彫られているのがわかります。空には鳳凰のような雲も舞っておりました。(続く)
2016.07.22
コメント(0)
-

アイルランド見聞録18(オガム文字の刻まれた立石)
ビーグモア・ストーンサークルから約6・5キロ離れた場所に、オガム文字の刻まれたアガスクリッバ・スタンディング・ストーンがあるというので、立ち寄りました。アイルランドの南西部にはたくさんオガム文字の石碑はありますが、北アイルランドでは珍しいので貴重です。こちらがそのオガム文字の立石。例によって牧場の中にあるので、牛さんたちを気にしながら、立石のある現場に近づきました。で、どこにオガム文字があるかというと、次の写真の右の側面です。・何本かの横線が引かれているのが見えますね。これがオガム文字です。立石がいつからあるのかはわかりませんが、文字自体は西暦300~400年ごろ彫られたとみられています。文字を持たなかったケルト人たちがキリスト文化流入後、ラテン文字を基にして造った文字だと考えられています。ちなみに下から上に読みます。そしてここには何が書いてあるかというと、アルファベッドで「OTETTO MAQI MAGLANI」。マグラニの息子という意味だそうです。何でもかつて、地主がこの立石を撤去しようとしたら、大洪水となり家屋や家畜に多大な被害が出たそうです。地主が撤去を断念すると、再び平穏な日々となったとか。そう言えば、岐阜県恵那市の笠置山の麓にも、オガム文字が彫られているのではないかされる「オガム岩」がありました。拙著『竹内文書の謎を解く』の178~180ページに掲載されています。その写真を見ると、確かにオガム文字に似た線刻が刻まれていますね。一体、誰がいつ、何の目的で何と刻んだのでしょうか。オリジナルの写真が手元にないので、今度探し出して、このブログでも紹介いたしましょう。(続く)
2016.07.21
コメント(0)
-

アイルランド見聞録17(真脇遺跡の環状列柱とブリテン諸島の環状列石)
先日、諏訪大社の御柱祭りを特集したテレビ番組を見ていたら、縄文時代には山を聖なる場所ととらえ、その山から神を降ろす自然信仰があり、その信仰がそのまま残ったのが御柱祭りではないか、とする説を紹介しておりました。非常にいいところを突いていますね。で、番組では、その傍証の一つとして、能登半島の先端近くにある真脇遺跡の環状列柱を挙げていたので、早速見に行ってきました。どうして傍証となるかというと、真脇遺跡の環状列柱には明確に方位があるからです。環状列柱の正面入り口から奥の二本の柱を見ると、その場所で特に目立つ山がちょうど二本の柱の真ん中に見えるんですね。つまり山を神聖なものとして崇め、その山を環状列柱の中心軸に据えることで、神を呼び込もうとしたというわけです。先日撮った写真がこちらです。入口の四本の柱と奥の二本の柱の真ん中に、目立つ山の頂が見えるように環状列柱が配置されていたことがわかりますね。その地域で一番目立つ山や一番高い山から一種のエネルギーを持ってくることが「高み結び」を使ったラインの目的でした。やはり古代人は、現代人の目には見えないエネルギーの流れを感じ取っていたのではないでしょうか。目をブリテン諸島に転ずると、ハーラーズのストーンサークルも同じようなことをやっていました。こちらですね。二本の立石の中央にチーズリングという奇岩のある山の頂が見えるように立石が配置されています。昨日ご紹介したビーグモア・ストーンサークルも同様です。こちらをご覧ください。二本の立石の中央に、遠くの目立つ山が見えるのがわかりますね。これによって、山と立石を結んだラインができます。私の説では、こうしたラインはエネルギーを呼び込む導線の役割をします。この場所には、ほかにもたくさんこうしたラインが引かれていました。つまり立石を配置することにより、四方八方からエネルギーを呼び込んでいたと考えられるわけです。その装置の一つに列石もあります。地図を見ると、北東から南西に向かって並んでいますから、夏至の日の出ラインだと思われます。太陽神のエネルギーを導入するラインだったのではないでしょうか。ところで、上の写真では二本の列石に呼応するかのように、空に二筋の雲のラインが出来ているように見えます。ここにも天と地のシンクロニシティがありますね。(続く)
2016.07.20
コメント(0)
-

アイルランド見聞録16(ビーグモア・ストーンサークル)
ビーグモア・ストーンサークルは、環状列石をはじめとする巨石遺構の宝庫のような遺跡です。まずは全体図をご覧ください。なんとストーンサークルが7基、石塚(ケアン)が12基も建造されているのがわかります。このほかにも列石や立石などが所狭しと並んでいるんですね。まずはこちら。入口のそばにあるストーンサークルです。高さはそれほどありませんが、見事な弧を描いています。次はさらに奥にあるストーンサークル。これも綺麗なサークルです。空にも環状の雲が出ていますから、天と地でシンクロしている感じがしますね。それに「北アイルランドで最も暗い空」とは思えないほど、見事に晴れていることがよくわかります。近寄って拡大写真を撮ると・・・中央付近に中心、あるいは観察点を表わすかのように、小さな立石が立っていることがわかります。最後はいちばん奥にある二つのストーンサークル。一番初めの地図で言うと、左下に描かれたFとGのストーンサークルです。手前のストーンサークルの右奥には、地図では10番として描かれている石塚も写っています。石塚の周りにはヘンジ(環状の土手と溝)が造られています。このほかにも三つの平行な列石が築かれるなど、高度な測量の結果とみられる巨石群の配置を窺うことができました。(続く)
2016.07.19
コメント(0)
-

アイルランド見聞録15(ベルファストと北アイルランドの天気)
北アイルランドの首都ベルファストに立ち寄るのは初めてです。写真は撮り忘れたためありませんが、住みやすそうな街でした。かつてはここを舞台にして、アイルランド統一を掲げるナショナリストと、イギリスとの統合を主張するユニオニストの血で血を洗う抗争が続いた時期もありましたが、今は昔と言ったところでしょうか。ただし、まだ火種は残っているようです。ところで北アイルランドでは、スコットランド同様に独自の紙幣を発行しています。英ポンドとして使うことができるのですが、ロンドンなどイングランドで使うと嫌がられることは以前紹介した通りです。そのことについてベルファストの人に聞いたら、やはり英本土で口論となることが多いそうです。法律的にはイングランドでも使えるのですが、拒否する人が多く、いざこざが絶えないとか。ちなみに日本人観光客が北アイルランドやスコットランドの紙幣を日本に持ち帰っても、日本円に両替することは無理なようです。だから、記念として取っておくのでなければ、北アイルランド紙幣は使い切ることに越したことはありませんね。さて翌6月2日。この日も快晴となりました。まずクックスタウンに立ち寄って地図と情報を仕入れ、郊外の立石を見つけます。このような立石はこの辺りにはごろごろしています。次に立ち寄ったのは、以前紹介したことのあるビーグモア・ストーンサークルです。空にはカニの形をした雲が出ていますね。本当にいい天気です。でも、これって滅多にないことなんです。その証拠がこちら。ビーグモア・ストーンサークルの案内板の下の方に「北アイルランドで最も暗い空の地方」と書いてあります。つまり滅多に晴れない、ということです。そう言えば、前回は雨が止むのに一時間ここの駐車場で待つことになりました。でもその後は快晴。二度とも晴れるということは、かなりありえないほどラッキーであったということになりますね。天気の神様に感謝です。(続く)
2016.07.18
コメント(0)
-

アイルランド見聞録14(バリノー・ストーンサークル)
ダウス羨道墳を見た後は、ボイン渓谷の遺跡群を後にして、この日の宿泊先である北アイルランドのベルファスト方面を目指します。アイルランドから国境を越えて北アイルランドに入ると、これまでのメートル表示がマイル表示へと変わります。5年前は制限速度が「時速50キロ」なのに、周りの車が急にスピードを上げて走り出したように錯覚しました。その錯覚の原因は、もちろん50キロだと思っていた制限速度が50マイル(約80キロ)だったからです。今回はそのような混乱もなく、キロからマイルへと頭の中で切り替えました。ただし、アイルランドでの制限速度は、日本の道路に比べて時速20キロぐらい速い設定になっているよう思います。特に田舎道の制限速度は場所によって80キロですが、あのように狭くて見通しのきかない道を80キロで走行するのはほとんど自殺行為です。カーブで対向車が来たらまず避けられませんから。そのことをダブリンのタクシーの運転手に話したら、タクシーの運転手でも田舎の狭い道は80キロでは飛ばせないと話していました。日本だったら、時速40キロの道路という感じの狭い田舎道です。さて、実は、ベルファストに行く前に、もう一か所寄り道をしました。それが北アイルランドのダウンパトリック郊外にあるバリノー・ストーンサークルです。駐車場からは7~8分ほど歩かなければなりません。このような道をひたすら歩きます。そして到着。綺麗なストーンサークルです。左端には方角を示すとみられる立石も立っています。案内板の図を見ると・・・基本的に二重の環状列石になっており、中央には盛り土があるようです。なくなった立石もあるようですが、それでも保存状態はまずまずです。見事な弧を描いていますね。大きな環状列石の直径は約33メートル。約50個の立石から成る環状列石の複合遺跡です。いつの時代に造られたのかはわかっておりませんが、新石器時代に建造され、いくつかの部分は後に付け加えられたのではないかと見られているようです。この日はタラの丘から始まって、ボイン渓谷の三つの羨道墳、そしてバリノー・ストーンサークルを見て回りました。その後、宿泊先のベルファストに。結構ハードな日程でした。(続く)
2016.07.17
コメント(0)
-

アイルランド見聞録13(ダウス羨道墳)
しばらく所用でブログをお休みしておりましたが、アイルランド見聞録を再開します。一般の観光客はまず訪れることのないダウスの羨道墳に到着したところまで紹介しました。再び掲載しますが、これがダウス羨道墳です。右端の中央下には門番の羊が写っていますね。ちょっと目にはただの丘ですが、全体はこのようになっています。二つの墳墓を持つ、巨大な構造物です。ニューグレンジと同様に5000年前にはできていたとみられています。羨道墳の入口がこちら。中には入れませんが、図を見ると、かなり内部は広くなっているようです。後代の人は貯蔵庫にしたと書かれていました。墳墓の上に登ると・・・やはりかなり遠くまで見えることがわかりますね。樹木が邪魔をしているため、ニューグレンジやノウスの羨道墳は確認できませんでした。この羨道墳の周囲も115の縁石で固められていたそうです。そのうち15の縁石にシンボルが刻まれていたと書かれています。こちらが露出した縁石。かなり風化しており、オガム文字のような線刻はありましたが、はっきりした模様は確認できませんでした。(続く)
2016.07.16
コメント(0)
-

アイルランド見聞録12(ダウス羨道墳へ)
一般的な観光客はニューグレンジとノウスの羨道墳は訪問します。ところが、ダウスの羨道墳を訪れる人は極めて稀です。というのも、ビジターセンターからのツアーがないからなんですね。ダウス羨道墳には自分の足か車で行かなければなりません。ビジターセンターからダウスまでは、直線距離では1・5キロほどですが、道路を行くと2・5キロはあります。つまり、歩くと往復で1時間はかかるということです。そこで車で行くことにしたのですが、羨道墳のある場所はビジターセンターから見るとボイン川の反対側にあります。私たちの車はビジターセンターの駐車場に止めてありますから、ダウスに行くには、川を渡る必要があるわけですね。ビジターセンター前の橋を渡ればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ビジターセンター前の橋は車は通れません。人が渡るための橋なんですね。ということは大きく迂回しないと、対岸に行けないことを意味しています。どっちに迂回すればいいのか。手元の地図や私のナビではわからなかったので、とりあえず来た道を川沿いに車で戻ることにしました。ところが行けども行けども対岸に渡る橋はありません。15分ほど運転してようやく橋を見つけました。で、今度は、橋を渡ったのはいいものの、どんどん川から離れて行ってしまうんですね。何度も川に近づこうと右折をしては行き止まりという作業を繰り返して、ほとんど諦めかけたとき、何とかノウスやニューグレンジのある羨道墳群のある場所にたどり着きました。おそらくビジターセンターを出発してから一時間は経っていたと思います。ビジターセンターから歩くのと、時間的にはいい勝負だったことになりますね。そうした苦労の末に訪れたダウスの羨道墳がこちらです。ガイドもおらず、ほとんど整備されておりません。その替わりに羨道墳を守っているのは羊さんたち。あちこちに糞の地雷を落として、見知らぬ人物の侵入を防いでおりました。立札が無ければただの牧草地の小山のようです。本日のもう一枚はこちら。ビジターセンターから見たニューグレンジ(中央奥の丘の上)です。手間にボイン川が流れています。ニューグレンジもビジターセンターからの直線距離は1・5キロほどですが、歩くと3キロはあります。近くに見えても、意外と遠いんですね。(続く)
2016.07.10
コメント(0)
-

アイルランド見聞録11(ニューグレンジ羨道墳)
ビジターセンターに戻ると、次のニューグレンジ行きのバスが出るまで少し時間があったので、ビジターセンターの中で買い物をします。まだ持っていなかったノウスとニューグレンジのガイドブックをそれぞれ購入。食堂もあるので、軽く食事をしました。そうこうするうちに、バスの出発時間となります。バスで五分ほどのとろこにあるニューグレンジに到着。ニューグレンジはノウスよりも有名ですから、かなり混んでいます。写真で見てもわかるように観光客で結構混み合っています。皆、ガイドが来るのを待っているところですね。この日も大勢の人が訪れたので、二つのグループに分かれてツアーをすることになりました。ニューグレンジは有名すぎることもあり、ちょっと説明を端折りましょう。これが羨道墳の入口と、入り口の前にある巨石です。いつ見ても模様が素晴らしいですね。冬至の日の朝、この入口を通して、羨道の一番奥の部屋に朝日が差し込む設計になっています。羨道墳の中は残念ながら撮影禁止なので、写真はありません。羨道内の壁の岩にも、渦巻きなどの模様が彫られていました。羨道の外は写真撮影ができましたから、外の縁石に彫られた印象的な模様をご紹介しましょう。まずはこちら。左側の三角形の市松紋様のような模様が面白いです。三角形は火と情熱のシンボル。並々ならぬ熱意が感じられます。中央は逆回転する二つの渦巻きが描かれています。いわゆる隼人紋ですね。相手のエネルギーを吸収して逆にはね返す力があるとされています。その下には、二重の菱形があります。これは三角形を二つ重ねた紋様であるとも解釈できますし、形が正方形に近いことから母なる大地と受容のシンボルであると解釈することもできそうです。続いてこちら。ちょっとかすれた部分もありますが、ここには多種多様なシンボルが描かれています。渦巻き、菱形、カップマーク、同心円。カップマークが三つ並んだ部分などを見ると、スコットランドの巨石に刻まれた紋様と酷似していますね。彼らが当時、ブリテン諸島全体を一つの文明・文化圏にしていたことを示すものです。ニューグレンジの説明はこのぐらいにしておきましょう。次はダウスです。(続く)
2016.07.09
コメント(0)
-

アイルランド見聞録10(ノウス羨道墳の西の入り口)
ガイドの公式の説明はノウス羨道墳の上で終わります。このツアーでは、大体現地で50分ほど滞在できます。ガイドの説明が30分、その後の自由時間が20分といったところでしょうか。この残りの20分の時間を利用して、ノウス羨道墳をぐるっと回って縁石の模様を写真に収めます。その中でも、既に紹介したもの以外で特に印象深かったのがこちらです。下の半分が同心円紋で、上の半分には線状の×印のような刻印がみられます。剥がれ落ちたのか、削り取ったのか、あるいはそのように彫ったのか。興味深いですね。とにかくこのように興味深いシンボルが、ほとんどの縁石に彫られているところがノウスの遺跡の凄いところです。次はこちら。波形と丸と同心円のコンビネーションで結構複雑な模様を形成していますね。波は風で自由のシンボル。丸は天でリーダーシップのシンボルです。すると中央の大きな同心円は、自由の風に乗って(あるいは帆船に乗って)力強いリーダーシップを持った人物が現れたことを示しているのでしょうか。で、次は西の羨道墳の入口です。東と同様に、入り口の前には立石などの巨石構造物が置かれていました。こちら側は入れませんが、中を覗くとこのようになっておりました。そうこうしているうちに、あっという間に出発時間です。バスに乗り込んで再びビジターセンターに戻りました。(続く)
2016.07.08
コメント(0)
-

アイルランド見聞録9(ノウスからの風景)
階段を登ってノウス羨道墳の頂上に立つと、当時の人々がどうしてこのような巨大な建造物を造ったかがよくわかります。とにかく見晴らしがいいんですね。360度見渡せる絶好のロケーションにノウス羨道墳は造られました。この羨道墳の上からニューグレンジが見下ろせることは既に紹介しましたね。今回もその写真をお見せしましょう。中央の丘の上に建造されているのがニューグレンジの羨道墳です。ノウスの羨道墳から1200メートル離れた場所にあります。本来はもう一つのダウス羨道墳も見えるはずなのですが、木立に視界を阻まれて今では視認できなくなっています。ノウス羨道墳から2700メートル離れたダウスも小山の上に建造されていますから、それぞれの地域で最も目立つ丘の上に三つの羨道墳が造られたわけです。その理由は当然、どこからでも視認できるように建造したからだと考えられます。つまり目立つ山と山を結ぶという「タカミムスビの法則」を使っている可能性が非常に高いんですね。その証拠がこちらです。って言っても何のことだかわかりませんよね。実は上の写真には約16キロ離れたタラの丘がはっきりと写っているんです。その部分を拡大してみましょう。塔のように見えるのがタラの丘の中腹にある教会で、タラの丘はこんもり茂った森の向うにあるのだと、ノウスのガイドは話していました。ということは、ボイン渓谷の三つの羨道墳を築いた人たちは、タラの丘に建造物を築いた人たちと頻繁に連絡を取り合っていた可能性が高いことになりますね。5000年前には既に、高みと高みを結んだ巨大な社会共同体が存在していたとみることもできます。次の写真の風景もノウス羨道墳の上からの眺めです。ボイン渓谷を流れるボイン川が写っています。何千年も後代になってからは、この丘はバイキングの襲来に備える見張り台の役割を果たしていたであろうことが容易に想像できますね。(続く)
2016.07.07
コメント(0)
-

アイルランド見聞録8(ノウスの衛星墳)
ノウス羨道墳のもう一つ大きな特徴は、中心の羨道墳の周りを取り巻くように、小さな衛星墳が17基も建造されていることです。現存していませんが、このほかにも3基の衛星墳があったのではないかと考えられています。衛星墳の写真です。右端に写っているのが中央の羨道墳で、衛星墳はそのすぐ脇に建造されていることがわかりますね。単体で撮ると、こんな感じです。衛星墳は、中央の羨道墳と同様に羨道のある場合が多いです。それを非常によく表した図がポール・フランシス氏が書いた公式ガイドブック『ノウス』に掲載されていますので、紹介しておきましょう。正確な衛星墳の配置や、2番や15番などの衛星墳に羨道があることがよくわかります。東南方向に衛星墳がないのは、破壊されてしまったからでしょうか。ガイドから衛星墳の説明を受けた後、いよいよ中央のノウス羨道墳の上に登ります。ちゃんと階段が付いていて、見学客は誰もが登れるようになっているんですね。というのも、このノウスの羨道墳は14~15世紀まで丘の上に住居が建てられて、使われていたからです。ノウスの案内板には次のようなイラストが描かれていました。羨道墳の上に住居が建造され、馬車でも通れるような道が築かれていることがわかります。後世の人間が古代人の重要拠点を再利用や活用するのは、イギリスの「聖マイケルライン」も同様でしたね。現在では14、5世紀の人が造ったとみられる、羨道墳の上に昇っていく坂道を再利用して、見学者のための階段を造っているわけです。(続く)
2016.07.06
コメント(0)
-

アイルランド見聞録7(ノウス羨道墳の内部)
それでは、ノウス羨道墳の中に入って行きます。中に入ると、見学用に特別に造られた展示室があります。その展示室に展示された説明板を利用して、ボイン渓谷の三つの羨道墳の概要を説明しましょう。これは上から見た三つの羨道墳を重ねたもので、上からノウス、ニューグレンジ、ダウスです。これを見てもわかるように、ノウスには東と西に入口があり、羨道は中央付近まで延びています。だけど、わざと貫通しないところで止めていますね。あるいは貫通させた後に埋めたのかもしれません。それにしても、非常に正確に羨道を造ったことがわかります。次にニューグレンジは南東に入口があり、直径の三分の一ぐらいのところまで掘り進んでいますね。一番奥まったところが十字の石室になっている所は、ノウスの東の羨道と構造は一緒です。最後にダウスは、南西に二つの羨道があります。でも、距離は非常に短いですね。この三つの羨道墳を見て、すぐにお気づきだと思いますが、この三つの羨道墳は綿密かつ複合的に設計されて造られています。つまり決してバラバラに、無計画に設計されたわけではないんですね。ノウスの羨道は春分と秋分の日没と日の出の太陽光を呼び込む施設であり、ニューグレンジは冬至の日の出、ダウスは冬至の日没の光が入って来る場所に羨道墳の入り口を造っています。おそらくこうすることによって、三つの羨道墳で正確に「春夏秋冬」の儀式を執り行っていたのではないかと思われます。また展示されたパネルには、次のようなものもありました。ノウス羨道墳の出土品です。真ん中の出土品は、東の羨道の一番奥右側の石室から見つかった「石のたらい」です。石に刻まれた同心円と平行線のラインが印象的ですね。そして写真右上の出土品はかなりユニークで、かつ洗練されています。拡大するとこうなります。最初写真を見たときは猿か何かの石のお面なのかと思いましたが、実はこれは、何かを砕いたり叩いたりするための工具である鎚鉾の頭の部分だそうです。穴の開いた部分に棒などを通して固定すれば、鎚鉾の出来上がりです。ほぼ対称に描かれた逆回転の渦巻きが彫られているなど、かなり文化的に貴重な鎚鉾のように思われます。我々見学者が入れるのは、この見学者用の展示室まで。石室までは行けないようになっているんですね。ただしノウスではニューグレンジと異なり、写真撮影が可能なので、奥の石室へと続く羨道を撮影することはできました。中央の石室まで約40メートル、この羨道が続いています。入り口に近いこの場所からは奥の石室は見ることはできませんでした。(続く)
2016.07.05
コメント(0)
-

アイルランド見聞録6(ノウス羨道墳の縁石とその模様)
既にノウスの縁石に刻まれたシンボル模様は紹介しましたが、もう一度今回撮影した写真を使って説明しましょう。ノウスの羨道墳の縁石は全部で127個あります。その大半に明確なシンボルが刻まれているんですね。まずは特に有名なシンボルが刻まれた縁石です。東の羨道入口の前にある縁石から数えて、時計回りに4つ進んだ縁石です。中心の点から放射線状に、まるで太陽光線のような直線が刻まれていることから、「日時計」とか「暦」と呼ばれています。右上には渦巻き紋が見られますね。次は「波」もしくは「蛇」と渦巻き紋。で、最後は未紹介だと思いますが、東の羨道入口に置かれた縁石と立石です。縁石には同心円ではなく、角ばった四角のような図形が入れ子状態で描かれています。四角は大地。安定と受容力の象徴でもあります。次は羨道墳の中に入って行きましょう。入り口は、上の写真の階段を下りた先にあります。(続く)
2016.07.04
コメント(0)
-

アイルランド見聞録5(ノウスの羨道墳)
さて、再びアイルランドです。ノウスの羨道墳で、ガイドの説明が始まったところからでしたね。ガイドの説明を要約すると、ざっとこんな感じです。約6000年前、新石器時代の人々がそれまでの狩猟生活から農業を営む生活に転換、このボイン渓谷に定住するようになりました。定住が始まると、人々の共同作業が増えて、作業効率が上がり、余暇も増えます。その余った時間を使って、人々は巨大な構造物の建造に着手しました。それが約5000年前に完成したとみられるノウスの巨大羨道墳というわけですね。しかもノウスはその後西暦1000年ごろまで、ほぼ継続的に重要な拠点として使われてきた形跡があるそうです。つまり定住が始まってから5000年間もノウスはアイルランドの中心地であったと解釈できるわけです。そのような歴史の変遷を説明しながら、ガイドは次に羨道墳の周囲に配置された127個の縁石について解説していきます。今日の写真は再びノウスの羨道墳です。羨道墳の左下に人が写っていますから、どれだけ大きいかがわかりますね。高さ約12~15メートル、上から見た形は楕円形で、長径は約100メートル、短径は約80メートルあります。(続く)
2016.07.03
コメント(0)
全24件 (24件中 1-24件目)
1