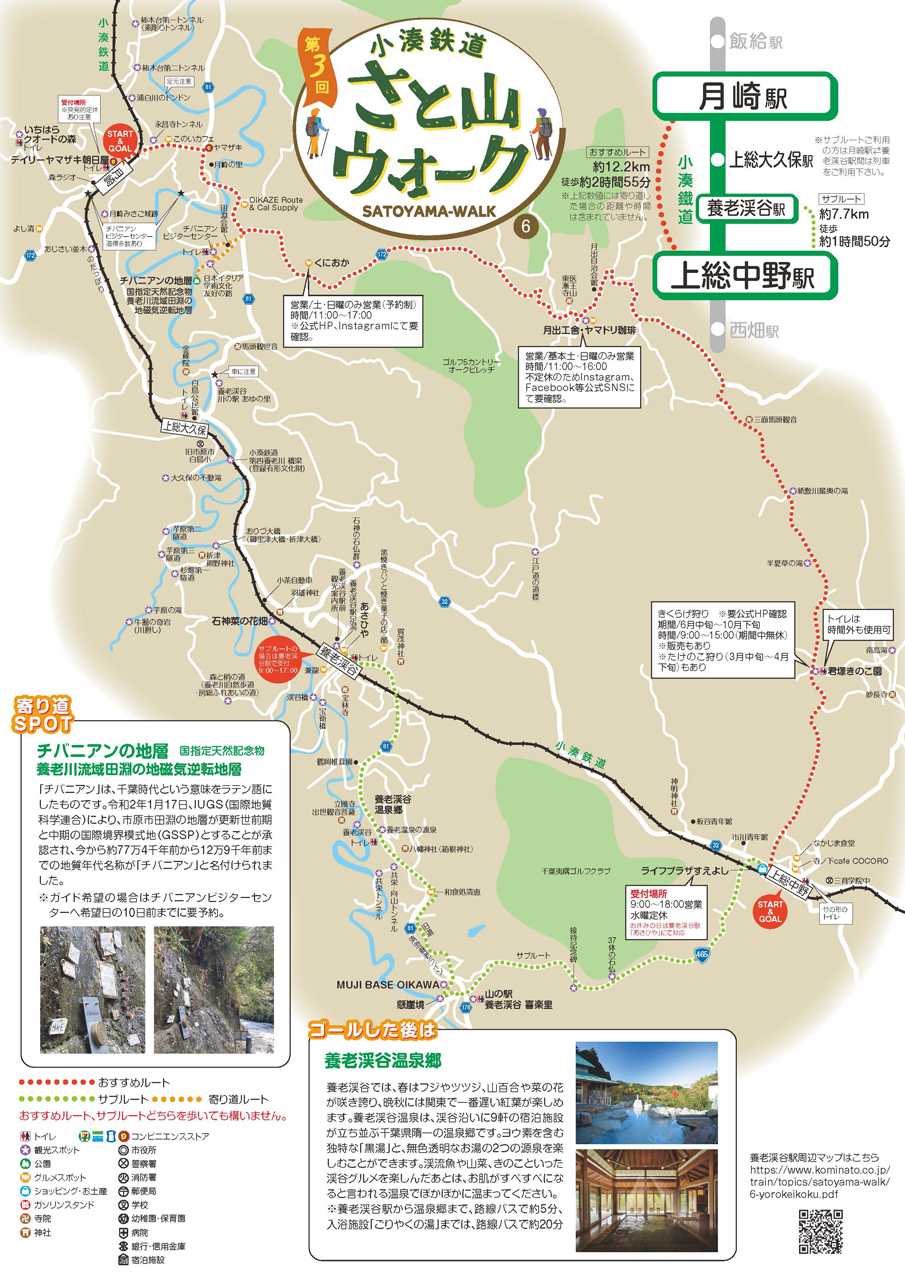2013年08月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
買主に賦課金が課される可能性と土地の隠れた瑕疵(否定)
土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において、上記売買の当時、買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえないとされた事例(最高裁 平成25年3月22日第二小法廷判決)「事案の概要」本件各土地は、H土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業の施行地区内に存しており、仮換地の指定を受けていた。Xらは、平成9年4月から平成10年9月にかけて、Yらから、その所有する本件各土地をそれぞれ売買により取得し、その頃、代金の支払、引渡し、登記の移転のいずれも完了した。ところが、その後、H組合が開始した保留地の販売状況が芳しくなかったため、H組合は、平成13年11月から平成14年1月にかけて、総代会において、組合員に賦課金を課する旨を順次決議し、Xらに賦課金を請求するに至った。そこで、Xらが、賦課金が発生する可能性のあった本件各土地には、民法570条にいう隠れた瑕疵があったと主張して、Yらに対し、瑕疵担保責任に基づく損害賠償を求めたのが本件である。「判旨」土地区画整理事業の施行地区内の土地を購入した買主が売買後に土地区画整理組合から賦課金を課された場合において、土地区画整理組合が組合員に賦課金を課する旨を総代会において決議するに至ったのは、上記売買後に開始された保留地の分譲が芳しくなかったためであり、上記売買の当時、土地区画整理組合において組合員に賦課金を課することが具体的に予定されていたことは全くうかがわれないこと、上記決議が上記売買から数年も経過した後にされたことなど判示の事情の下においては、上記売買の当時、買主が賦課金を課される可能性が存在していたことをもって、上記土地に民法570条にいう瑕疵があるとはいえない。判例タイムズ1389号91頁
2013.08.30
-
訴訟上の和解の成立過程での弁護士の説明義務違反
交通事故と医療過誤が競合した場合において、被害者の代理人である弁護士が、訴訟上の和解により加害者から損害賠償金の支払いを受けるにあたり、医療過誤による解決金受領の事実を説明すべき義務を怠ったとして、加害者の保険会社から被害者の代理人であった弁護士に対する不法行為による損害賠償請求が認容された事例(東京地裁平成24年7月9日)「事案の概要」本件は、交通事故で死亡した被害者の相続人らの代理人である弁護士が、医療過誤に基づく解決金6600万円を病院から受領したことを秘したまま加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起し、訴訟上の和解に基づき損害賠償金9000万円の支払いを受けたことが、損害の二重請求をした不法行為に当たるとして、賠償責任保険金として賠償金を支払った加害者の保険会社が、被害者の代理人であった弁護士に対し、7260万円の損害賠償を求めた事案である。「判旨」交通事故と医療過誤が競合して被害者の死亡の原因となった本件の場合、被害者の死亡による損害については、原則として、民法719条1項の共同不法行為ないしこれに準ずる法律関係として、交通事故の加害者の損害賠償債務と医療過誤による損害賠償債務とが連帯債務となり、交通事故の加害者は、被害者の死亡による損害の賠償が医療過誤に基づきされたときは、その部分について債務を免れることになる。そして、多数発生している交通事故の事例において、加害者においても医療過誤の可能性を疑うことがあり得るとしても、現実に医療過誤が認められ医療機関による損害賠償あるいは交通事故の加害者から医療機関への求償請求がされることは、社会的には稀な事例である。交通事故の加害者やその訴訟代理人の立場において、被害者側から何ら説明がないときでも、医療過誤による損害賠償がされていることを予測して賠償の有無を積極的に問い合わせたり調査したりすることを期待することは、極めて困難であるといわなければならない。まして、本件の場合には、裁判所も、医療過誤による損害賠償の可能性を全く考慮に入れないまま和解案を提示しているのであり、法律専門家である弁護士の被告は、そのことを和解案の内容から当然に知ることができた。共同不法行為の連帯債務関係に関する法律を熟知している弁護士である被告としては、訴訟上の和解により和解契約を締結するに際し、民法及び民事訴訟法に定める信義則上の義務として、医療過誤による連帯債務の弁済の事実を知らないことが訴訟経過から明らかな契約の相手方である加害者ないしは裁判所に対し、病院からの解決金の支払の事実を説明し、その情報を提供すべき義務があるというべきである。したがって、この義務を怠って訴訟上の和解を成立させ、和解に基づく損害賠償金の支払いを受けたときは、その行為は不法行為としての違法性を有する。判例タイムズ1389号235頁
2013.08.27
全2件 (2件中 1-2件目)
1