2007年01月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
指名競争入札に参加させないことが違法とされた事例
1月22日に掲載した水戸土浦支部の判決は違法性を否定したが、最高裁平成18年10月26日判決の場合は違法性を肯定した。徳島県の旧木屋平村の発注する公共工事の指名競争入札に昭和60年ころから平成10年度まで継続的に参加していた建設業者Xが同11年度から同16年度までの間、村長から違法に指名を回避されたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、合併により木屋平村の地位を承継した美馬市に対し逸失利益などの損害賠償を求めた事案。地方公共団体の長は、指名競争入札において入札に参加できるすることができる者の資格を定め、公表しなければならないが、その資格を有する者のうちから入札に参加させようとする者を指名するに当たり誰を指名するかのの基準については、その基準を定めたときには公表しなければならないと規定されているにとどまる。(公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律 同法施行令)また、所定の事由に該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札に参加させないことができると定めている(地方自治法施行令において準用)ほかは、指名停止、指名回避の基準について法令の規定はない。したがって、1指名競争入札に参加できる者の資格をどのように定めるか2 指名の選定基準や指名停止・指名回避の基準を定めるかどうか3 指名にあたって具体的にどの業者に指名するかについては各地方公共団体の長の裁量にゆだねられている。しかし、地方公共団体の締結する契約について、公正性、透明性、経済性などが確保されなければならないことからすると、地方公共団体の長が恣意的な指名又は指名停止・指名回避をすることは許されず、このような場合は裁量権の逸脱・濫用として国家賠償法上違法となることがあるものと解される。本件において、平成11年までの指名回避は理由があるが氏名回避の期間が最長1年と定められていたことから平成12年以降Xを指名しなかった措置が問題となった。被告は、村では従来から村内業者では対応できない工事についてのみ村外業者を指名し、それ以外は村内業者のみを指名していたところ、Xは村外業者であることが判明したので指名しなかったと主張し1審は村の要綱では村内業者と村外業者とを定義しているが入札参加資格では両者をまったく区別していないしXが村の区域内に主たる営業所を有していないとはいえないとして平成12年以降の措置を違法とした。2審の高松高裁は村内業者に限定した運用に合理性がありXは村内業者でないので違法ではないと判断した。最高裁は、村内業者にのみを指名するという運用は要綱などに明定されていないし、村内業者の客観的判断基準も明らかにされていないこと、指名についての上記運用および上記業者が村外業者に当たるという判断が合理的であるとし、そのことのみを理由として村の上記措置が違法であるとはいえないとした原審の判断には違法がある とした 判例タイムズ1225号 210頁
2007.01.31
-
ロックアウトが使用者の正当な争議行為として認められた例
本件は、生コンクリートの製造販売業者であるYにおいて運転手等として就業していたXらが、時限ストライキ等の争議行為に対してYが行ったロックアウトの期間中の賃金を請求した事案であり、ロックアウトの正当性が争点である。第1審は本件ロックアウトは正当であるとして請求を棄却したが、原審は本件ロックアウトの正当性を否定し、原告らの賃金支払請求を認容すべきものとした。しかし、最高裁平成18年4月18日判決はロックアウトの正当性を認め、賃金の支払いを不要とした。ロックアウト(作業所閉鎖)とは使用者が争議を有利に導くためその相手方である被用者らに対し事業所から閉め出すなどして被用者の提供する労務の受領を集団的に拒絶することをいい、使用者の争議行為の一態様とされている。その一般的な許容性及びその正当性の判断基準に関しては、最高裁昭和50年4月25日判決、昭和55年4月11日判決、昭和58年6月13日判決をはじめとする判例がある。その要点は1労働者の争議行為により使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合に は、衡平の原則に照らし、勢力の均衡を回復するための対抗手段として相当性を認められ る限り、使用者の争議行為も正当なものとして是認される。2ロックアウトが正当な争議行為として是認されるかどうかは、労使間の交渉態度、経過、 労働者側の争議行為の態様、それによって使用者側が受ける打撃の程度等に関する具体 的な諸事情に照らし、衡平の見地からみて対抗防衛手段として相当と認められるかどう かによって決すべきである3このような相当性が認められる場合には、使用者は、ロックアウト期間中の賃金支払義務 を免れる。本判決もこの判例法理に依拠した上で、本件ストライキの態様とこれが被告の事業に及ぼした打撃の程度等の客観的事情等を中心に考慮して、本件ロックアウトを正当としたが、使用者である生コンクリート製造販売業者にとって、協同組合における取引慣行上、時限ストライキがされただけでYは受注全部の返上を余儀なくされ、それを見計らってXらはストライキを解除し、労務の提供ありとみざるを得ない状態に入る、しかし、Yの事業は閉店休業の状態にあるから、労務提供に経済的価値はなく、賃金負担によりYは多大な損害をこうむるという関係にある。これはロックアウトによる対抗が法律的、合理的な意味を持ち、したがってその正当性が肯定されるべき典型的な局面であるということができる。昭和50年の丸島水門事件判決の前後を通じ、ロックアウトを正当とする結論が採られた事例は上告審でも下級審でもごく僅かのようである。その中にあって、反対の評価をした原審の判断を覆して第1審の判断を正当とするものであり極めて重要な事例判断である。 判例時報1949号 162頁 頭注
2007.01.30
-
「相続させる」趣旨の遺言による相続と代襲相続
代襲相続とは、被相続人が死亡する前に、相続人に死亡や廃除・欠格といった代襲原因が発生した場合、相続における衡平の観点から相続人の有していた相続分と同じ割合の相続分を代襲相続人に取得させる制度父が死亡する前に息子が死亡していた場合、その息子の子が父に対する関係で代襲相続人となり、息子が有していた相続分と同じ割合の相続分を孫が取得する。東京高裁平成18年6月29日判決は、父がすでに死亡し、母夏子が遺言を書いて、6名の子供について、母の有する不動産と預貯金について6名の子に取得させる遺産を指定していた。ところが、その子供の一人である秋子が母の死亡する前に死亡しており、秋子の子である孫がいたので、その孫が秋子が相続する遺産をそのまま相続できるとして、それを争う他の相続人に対し確認の訴えを提起した事件である。遺贈の場合は、民法994条1項により受遺者の死亡により遺贈は効力を失うと規定されている。本判決は、この点について。遺贈が相続人のみならず第3者に対しても行うことができる財産処分行為であって、その性質から見て、受遺者が被相続人より先に死亡したからといって、被相続人がその子に対しても遺贈する趣旨と解することはできないものだることから、受遺者の死亡により遺贈の効力を失うのであり、他方、遺産分割方法の指定は相続であり、相続の法理に従い代襲相続を認めることが代襲相続の制度の法の趣旨に沿い、相続人間の衡平を損なうことはなく、被相続人の意思にも合致するとして、遺産分割方法の指定がなされた場合を遺贈に準じて扱うべきでないとして、秋子の孫の請求を認めた。遺言には誰々に何々を「相続させる」と記載されているが「相続させる」遺言について、その法的性質をめぐって種々の議論がされ最高裁平成3年4月19日判決は、遺贈とは別個の法的性質、効果をもつ遺言であることを明らかにし、最高裁平成14年6月10日判決は、相続させる遺言による権利の移転は、法廷相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはないとして、相続させる遺言によって不動産を取得した相続人が登記なくして法定相続分につき差し押さえをした債権者に対抗できるとし、遺贈とは異なる扱いをすることが明らかにされている。本判決中にも引用された登記先例があり、遺言書中に相続人が被相続人より先に死亡した場合は被相続人である子に代わって相続させる旨の文言がない限り、受遺者の場合と同視して遺言が効力を失うという回答がされている。本判決とは異なる。上告されている。 判例時報1949号34頁
2007.01.29
-
民事再生法119条2号の共益債権
民事再生法119条2号は、再生債務者の業務に関する費用は、再生債務者の事業の再生を図るために不可欠の費用であるとして共益債権として認められているところ、本件はライセンス契約の年間最低保証ロイヤリテイがこのような費用に当たるかが争われた事案である。X ライセンサー Yライセンシー のライセンス契約Yに対し民事再生手続開始決定Y 民事再生法49条に基づいてライセンス契約解除ライセンス契約は、XがYに対しプロサッカーチームにかかる商品を独占的に販売する権利等を付与し、これに対しYはXに対し年間最低保証ロイヤリテイとして5年間にわたって各年分割して一定額を定めて支払い(更に四半期ごとに、その25パーセントを後払いではらう)、これとは別にランニングロイヤリテイとして商品の販売価格の5パーセントを支払うが、これは各契約年度の終了後、年間最低保証ロイヤリテイを超えた場合に支払うことが合意されていた。Xは、1 民事再生手続開始決定日及び解除の日の属する四半期の年間最低ロイヤリテイは民事再生法119条2号の共益債権である 2 解除後契約終了までの年間最低保証ロイヤリテイ相当額の損害を被ったところ、同請求権は再生債権である と主張したこれに対し東京地裁平成17年12月27日判決(再生債権査定異議等事件)は1については、年間最低保証ロイヤリテイとランニングロイヤリテイの精算方法の差異等から年間最低保証ロイヤリテイは、Yが取得する当該契約年度における独占的権利設定の対価でありすでに発生している請求権であると認定した上、共益債権に当たらないと判断した。2についてはXの損害の発生は認められないとしてXの主張を退けた。控訴されている。 判例タイムズ1224号310頁 頭注
2007.01.27
-
職場のパソコン 出会い系に登録 大量私用メール 懲戒解雇 有効
専門学校の教職員として雇用されていた原告が、同学校から貸与されていた業務用パソコン及び同大学のメールアドレスを使用して、いわゆる出会い系サイトに登録し、同サイトで知り合った女性らとの間で大量のメールを送受信したこと(平成10年9月21日から平成15年9月3日までの受信記録が1650余件、平成11年5月18日から平成15年9月4日までの送信記録が1330余件あったところ、いわゆる出会い系サイト関連と判断される受送信記録が、それぞれ各800余件に達しており、しかも、その約半数程度が勤務時間内に受送信されていた。)を理由として、学校から懲戒解雇されたことに対し、原告が、同懲戒解雇は解雇権の乱用であって無効であるとして提訴された。原審は、懲戒解雇をもって臨むのは過酷にすぎ、本件懲戒解雇は解雇権の濫用として無効であるとした。福岡高裁平成17年9月14日判決は原判決を取り消し、原告の請求を棄却した。上告されている。 判例タイムズ1223号188頁
2007.01.26
-
大学院に在学中の学生についてなされた懲戒退学処分が有効であるとされた事例
私立学校である学校法人が設置する大学院 経営情報学研究科経営情報学専攻に在籍のX平成13年6月29日付で懲戒退学処分Xは懲戒処分該当事由がない 手続き的にも違法がある として提訴原判決Xは本件大学院の学則に定める懲戒事由である「本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者」という要件に該当するとして、本件懲戒処分は適法・有効であるとした。X控訴。一審判決同様原告の請求を認めなかった。その事実認定の概略Y1大学はその学則70条3項4号(本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者)に該当するとして、本件懲戒退学処分をなしているところ、同号に係る退学処分は、同学則が予定している懲戒処分の中でも、被処分者である学生につき、その社会的身分を一方的に剥奪することになる関係で、極めて重大な影響を与えるものである上、懲戒として行われる以上、被処分者に対する制裁としての性格を帯びることなどからすれば、Y大学が同号の懲戒退学処分を行うには、その懲戒事由の該当性の存在についてはもとより、その合理性及び相当性についても慎重な検討が求められるというべきである。これを本件についてみると、Xは、Aを始め自らの考えや行動に反対する態度を示したり、意見を述べる院生に対し、執拗に攻撃的かつ威圧的態度をとったり、他の院生らが訴訟制度に精通していないに藉口して、民事訴訟の提起や刑事手続上の告訴の手段を取ること、そのため、これらの院生の中には、Xによって、法的手続を取られるのではないかという不安を感じるものがいたと推認されること、また、Xは授業中に当該授業内容とは直接関連しない事項についての質問を繰り返したり、他の受講者の存在を無視するかのように教官と議論を始めるなどして、他の学生の受講意欲を失わせ、また、担当教官による授業の円滑な遂行を妨げているところ、このようなXの受講態度は、Xの学習意欲の発露というよりは、むしろ授業の円滑な遂行それ自体を妨害する意図からなされていたと推認されること上記のようなXの態度に起因する不安感ないし恐怖感から、Xと同じ授業に出席することをためらう学生が少なからず存在していたこと、Xは、Bに対して、金銭を対価としての交際を求めるなどしていたほか、他の女子学生に対しても、電子メールを送付したり、個人的な関係構築を迫るような発言を行っており、これら女子学生らを困惑させていた等の事情が認められる。 と認定した。 東京高裁平成18年5月30日判決 上告されている 判例タイムズ1223号 227頁
2007.01.25
-
新築マンションの共用部分の瑕疵 補修後でも価値の減少あり
マンションの共用部分の瑕疵が、補修後も区分所有権の交換価値を低下させていることを理由として、売主の瑕疵担保責任が認められた例新築マンションの共用部分である外壁タイルに大規模な補修工事を要する瑕疵がある場合に補修によりその機能上の問題が解消された後においても、その瑕疵に起因して一般的に受ける不安感・不快感が認められることにより、区分所有権の交換価値が低下しているなどの判示の事情の下では、区分所有者は、売主の瑕疵担保責任に基づき交換価値の低下分について損害賠償を請求することができる。福岡高裁平成18年3月9日判決 判決は確定1審は、財産的損害につき、本件補修工事後に交換価値の下落が存在していることを認めるに足りる証拠はないとし、また慰謝料につき、民法416条2項にいう特別損害にあたるところ、売買契約締結当時に予見できたとはいえないとして原告の請求を全部棄却した。福岡高裁は財産的損害について、原告らに40万円から111万円の損害を認め、慰謝料につき20万円から30万円の請求を認め、弁護士費用は10万円から23万円を認めた。 判例タイムズ1223号205頁
2007.01.24
-
固定資産税の課税標準である土地の価格
最高裁平成18年7月7日判決固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうものであり、これを当該土地から得ることのできる収益を基準に資本還元して導き出される価格をいうものと解することはできず、また、一般に取引価格は、上記の価格以下にとどまるものでなければ正常な条件の下に成立したものとはいえないということもできない。固定資産税の課税標準である土地の「適正な時価」に関しては、正常な条件の下において成立す取引価格、すなわち、客観的交換価値と解する見解が裁判例においても学説上も多数を占めていたが、収益還元価格と解する異説もみられた。本件の原判決は、この異説に立っていたものである。このような形勢にあって、最高裁平成15年6月26日判決は「土地に対する固定資産税は土地の資産価値に着目し、その所有という事実に担税力を認めて課する一種の財産税であって、個々の土地の収益性の有無にかかわらず、その所有者に対して課するものであるから、上記の適正な時価とは、正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格、すなわち、客観的な交換価値をいうと解される」と判示した。この平成15年判決後も、正常な条件の下に成立する土地の取引価格すなわち客観的交換価値とは、一般に、収益還元価格を超えない価格であり、取引事例等から認識される実勢価格が収益還元価格をこえている場合には、それは正常でない条件の下で形成された価格であるという趣旨をとなえて原判決を支持する見解があったが、本判決で否定された。 判例タイムズ1224号217頁 頭注固定資産税における時価を争う場合の手続きの仕方については、本ブログ2006年9月8日欄を参照されたい
2007.01.23
-
市の発注する公共工事の入札に指名しないとしても不法行為が成立しないとされた例
X1からX3はY市の発注する公共工事の氏名競争入札に参加していたY市所在の業者であって、Y市から指名業者として選定されることによって公共工事を請け負うなどしてきたものであるが、Y市の市長が市長に当選した後は、指名業者として選定されることがなくなった。Xらは1 Y市の入札参加選定等取扱要綱の指名基準を充足し、従前からY市の公共工事を行ってき た実績のある業者なのであるから市長に「Xらを指名しなければならない義務」がある などとして、市長にはこの義務に違反した不作為による不法行為が成立する。2 市長がXらを指名業者として選定しなかった不作為は、裁量権の限界を逸脱して違法なも のであるなどと主張してY市に損害賠償を求めた。水戸地裁土浦支部平成17年4月4日判決は、1の点につき、地方公共団体における指名競争入札が客観的に公平かつ公正に行われるべきことは法の要請するところであり、また地方公共団体の長らもそのような法の要請に従って指名競争入札制度を運用する責務があるとした上で、当該地方公共団体の長らが負うべき前記責務は、その住民らとの関係で負担する一般的抽象的なものにすぎないのであって、そのことから当然に、当該長らの特定の業者に対する個別具体的な法的義務が基礎づけられるわけでないなどとした。そしてY市が行う指名競争入札において、Xらを入札参加者として指名しなければならないといった法的な作為義務を導きだすことはできないから、この作為義務に違反したことを根拠とする不作為による不法行為が成立することはないと結論付けてXらの請求を棄却した。なお、2の点につき、市長には前記取扱要綱による指名基準によりその裁量権の範囲を制限されているから、これに敢えて違反して、恣意的に、参加する資格を有する者のうちの一部の者を排除したり、一部の者を偏重したりする行為を行った場合には、その裁量権を逸脱するものとして違法の評価を受ける余地もあるが、Y市の指名競争入札の制度において入札参加者の選定は、市長は構成員となっていない選定委員会が実質的に行うのであるから、入札参加者の選定に当たって市長の恣意的な判断が入る余地がないと認められること、Xらが入札参加者として選定されなかったことは、公共工事の入札制度の改善や公共工事の減少の結果であるとも考えられることなどを指摘して、市長の不作為が裁量権の限度を逸脱して違法となるとはいえないと判示している。 判例タイムズ1218号 229頁 頭注
2007.01.22
-
元請契約締結前の下請業者の工事の準備行為と工事中止
下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の仕事の準備作業を開始した場合において施主が下請業者の支出費用を補填するなどの代償的措置を講ずることなく施工計画を中止することが下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行為に当たるとされた事例最高裁平成18年9月4日判決建物の建具の納入等についての下請業者が施工業者との間で下請契約を締結する前に下請の仕事の準備作業を開始した場合において1 竣工予定時期に間に合うよう下請の仕事を完成するためには、施主が施工業者を決定す る前に上記準備作業を開始する必要があったこと 2 施主は設計管理者の説明を受けて、下請業者に上記準備作業の開始を依頼すること及び 依頼後は別の業者を選ぶことができなくなることを了承していたこと 3下請業者は、設計管理者から、上記のとおり施主の了解があった旨の説明を受けるととも に、直ちに上記準備作業を開始するよう依頼を受けたことから、上記準備作業を開始し たことなどの判示の事実関係の下では、下請業者が上記準備作業に要した費用等につい て設計管理者で負担するとの説明を受けていたことなどの特段の事情のない限り、施主 が、下請業者において下請け契約を確実に締結できるものと信頼して支出した費用を補 填するなどの代償的措置を講ずることなく、将来の支出に不安定な要素があることを理 由として施工計画を中止することは、下請業者の信頼を不当に損なうものとして不法行 為に当たる。1審は被告大学の一方的な建築計画の中止は下請け業者の信頼を損なうものであり、不法行為を構成するとして、下請け業者の損害賠償請求を一部認容した。2審は下請業者と被告大学の間では契約の締結が予定されておらず、両者の間では契約締結上の過失が妥当する場面ではない。設計管理者との間で解決すべき問題であるとして原告の請求を棄却した。最高裁は上記のとおり判示して2審の判決を破棄し、特別な事情の有無、損害の範囲について更に審理を尽くさせるために原審に差し戻した。 判例タイムズ1223号131頁 頭注Xの開発、製造したゲーム機を順次XからY、YからAに販売する旨の契約が締結に至らなかった場合においてYがXに対して契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任を負うとされた事例 最高裁平成19年2月27日判決 判例時報1964号45頁
2007.01.20
-
過払い金の利息は年5分か年6分か
利息制限法所定の制限を越えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権における民法704条の「利息」の利率が、民法法定利率の年5分であるか,商事法定利率の年6分であるか宮崎簡易裁判所の判決に対する上告審にあたる福岡高裁平成18年6月29日判決は、次のとおり、商事法定利率年6分を適用すべきであるとした。商法514条が規定する「商行為によって生じた債務」とは、現存の債務そのものが直接商行為によって生じたことは必要でなく、商行為によって生じた債務が変形したもので、これと実質的同一性を有すると認められるものを含むと一般的に解されており、商行為たる金銭消費貸借契約に関する利息契約に基づくいわゆる利息制限法違反の超過利息による過払い金の不当利得返還債務にも、実質的同一性を有するものとして同条の適用を認め、更には、これに従たる権利である民法704条所定の利息についても同条の適用を認めるのが相当であり、このことは、民法704条所定の利息が目的物についての収益を考慮したものといわれている実質からしても、相当と解される。この点について、最高裁の判例はなく、下級審の判例は分かれている。商行為の問題について最高裁昭和55年1月24日判決判例タイムズ409号73頁は、消滅時効の期間が問題となった場面であるが、「商法522条の適用又は類推適用されるべき債権は商行為に属する法律行為から生じたもの又はこれに準ずるものでなければならないところ、利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権は、法律の規定により発生する債権であり、しかも商事取引関係の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨からみて、商行為によって生じた債権に準ずるものと解することもできない。としており、これとの関係は検討を要する点であろう。なお、付属的商行為には、契約のような法律行為に限らず、事務管理・催告・通知などの準法律行為から、支払・受領などの事実行為も含まれると解されている。 判例タイムズ1224号268頁 頭注最高裁は年5分が相当とした 最高裁平成19年2月13日判決
2007.01.19
-
不正競争による侵害の差止請求の管轄裁判所
岐阜市に住所のあるX会社は、工作機械と工具を接続するミーリングチャックという製品を販売、輸出している。大阪市に住所のあるY会社は、Xの行為が不正競争防止法2条1項1号の「不正競争」にあたると主張して問題とする構えをみせていた。そこで、XはYに対し「YがXに対して本件製品の販売又は輸出について不正競争防止法3条1項に基づく差し止め請求権を有しないこと」の確認を求める訴えを名古屋地裁に起こした。Xは名古屋港から本件製品を輸出していることから、この地を管轄する名古屋地裁は、本件訴えにつき、民事訴訟法5条9号(不法行為に関する訴えは不法行為地を管轄する裁判所に提起できる)により管轄権を有すると主張した。これに対しYは、これを争い民事訴訟法16条1項又は17条により、Yの住所地を管轄する大阪地裁への移送を求める申立をした。第1審は移送の申し立てを却下した。第2審の名古屋高裁は、「現行法上、不法行為の効果として原状回復請求権又は差し止め請求権が発生することが一般的に承認されていると解することは困難であり、本件の不正競争防止法に基づく差し止め請求権についても、個別的な法律に基づいて物権的請求権に準ずるものとして認められているにとどまるから、本件訴えは、民事訴訟法5条9号所定の「不法行為に関する訴え」には当たらないとして第1審の決定を取り消して大阪地裁に移送した。これに対しXは最高裁に許可抗告を申し立てた。最高裁平成16年4月4月8日決定民事訴訟法5条9号は不法行為に関する訴えにつき、当事者の立証の便宜を考慮して、不法行為があった地を管轄する裁判所に訴えを提起することを認めている。同号の趣旨等にかんがみると、この不法行為に関する訴えの意義については、民法所定の不法行為に基づく訴えに限られるものではなく、違法行為により権利利益を侵害され、又は、侵害されるおそれのある者が提起する侵害の停止又は予防を求める差し止め請求に関する訴えをも含むものと解するのが相当である。と判示し、原決定を破棄差し戻した。従来は判例学説とも積極説と消極説に分かれていたが、決着のついたものである。本決定の射程距離について、物権,人格権など排他的権利の侵害の差し止め請求に及ぶか否かという問題があるが、本判示からすると積極に解してよいであろうと評されている。 判例タイムズ1184号 加藤新太郎判事の解説
2007.01.18
-
再生手続における営業譲渡
再生手続開始決定がなされると、収益可能な事業も価値の劣化により存続困難となることがある。このような場合、再生債務者が第3者に営業譲渡をすることにより事業の存続を図ることが有益である。また、債権者も営業譲渡代金を原資として早期に一括弁済を受けられる。そのため、営業譲渡は倒産処理の方法として有用とされている。ところで、再生手続開始決定により事業の価値は急激に劣化するのが通常であるから、営業譲渡は早期に行われる必要がある。そこで、民事再生法は再生計画案の決議前でも裁判所お許可を得て営業譲渡を行うことを認めた(民事再生法42条)営業譲渡の許可は再生債務者の事業の再生のために必要であると認められる場合に限ってなされる。(42条1項ただし書き)具体的には、再生債務者の信用は失われているが、営業譲渡を受ける第3社の下では事業の存続を図ることができる場合等である。もっとも、再生債務者が株式会社である場合、株主保護の観点から、営業譲渡には株主総会の特別決議が必要とされている。しかし、定足数要件を満たさない等の理由で株主総会の特別決議が成立しないことが考えられること、債務超過に陥っている株式会社の株主は実質的な持分権を失っているといえるから保護する必要性が乏しいことから、民事再生法は株主総会の特別決議に代わる裁判所の許可(代替許可)の制度を設けた(43条)代替許可の要件は、1 再生手続開始後に再生債務者がその財産をもって債務を完済することができないこと2 営業譲渡が事業の継続のために必要であること の2つである。再生手続における財産評定は、原則として処分価値で行うが、必要である場合には継続企業価値で行うことができるとされている。(民事再生規則56条1項)ところで株主の議決権を失わせることを正当化する根拠は、株主が実質的な持分権を失っているといえることであるから、処分価値を基準にすれば債務超過となる場合であっても継続企業価値を基準にすれば債務超過とならない場合には、株主は実質的な持分権を失っているとは言えない。よって、上記1の要件該当性は、継続企業価値を基準として判断すべきであるとする見解が有力である。2の要件該当性については、株主保護の観点から、営業譲渡しないと早晩廃業に追い込まれざるを得ない事情にある場合に限るとする見解がある一方、倒産処理における営業譲渡の有用性を考慮すれば、上記の場合に限ることなく、営業譲渡をしなければ当該営業の価値等に大きな変化が予想される場合も含むべきであるとする見解がある。東京高裁平成16年6月17日決定は、営業譲渡しないと当該事業が遅かれ早かれ廃業に追い込まれる場合や、当該営業の資産的価値が著しく減少する場合に限る。として、原決定の代替許可を取り消した。 判例タイムズ 1184号224頁 頭注
2007.01.17
-
外国国家の民事裁判権免除が認められた例
外国国家の民事裁判権の免除については、絶対免除主義を制限免除主義の立場があるとされる。我国においては大審院が絶対的免除説の立場を明らかにして以来、絶対免除主義をとるものが多かったが、そのような状況の下で最高裁平成14年4月12日判決判例タイムズ1092号107頁。この最高裁判決は、大審院の判例を実質的に変更し、制限免除主義への途を開いたと理解する見解が有力であり、その後の下級審判例には、制限免除主義を採ることを明示するものがあった。そのような中で、東京地裁平成17年12月27日判決は制限免除主義を採ることを明示したものである。本件はサウジアラビアが我国における大使館用の土地建物を取得するにあたり、原告と被告との間で、土地建物取得の仲介契約及び取得費用融資の仲介契約を締結したと原告が主張して被告に対し報酬4億8000万円余請求するものである。被告は外国国家の民事裁判権の免除の主張をした。判決は、これを認め訴えを却下した。 判決は確定。ア、外国国家の民事裁判権免除については、外国国家た自発的に応訴するなどの例外的場合 を除き、原則としてすべての国家行為について民事裁判権が免除されるという絶対的免除 主義と国家行為を主権的行為と商業取引などの私法的行為・業務管理行為に分け、主権的行 為についてのみ民事裁判権の免除を認める制限免除主義があるが、制限免除主義を採るのが 相当である。イ、制限免除主義を採った場合の主権的行為と業務管理行為の区別については、外国国家の行為 の性質の外、外国国家の行為の動機・目的を総合的に考慮して判断するのが相当であるが、こ の場合に考慮すべき動機・目的は、国家機関の内部におけるものでは足りず、当該行為の内容 として客観的に表示されていることが必要である。ウ、本件仲介契約は・・・・・外交目的を有する国家の主権的活動という側面が強く、原告もそのこと を承知の上で、本件各仲介契約を締結している。したがって、本件は、国家の主権的行為であるから、被告に民事裁判権は及ばない。 判例タイムズ1223号287頁 頭注
2007.01.10
-
公共施設の使用料 免除のできる場合
普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設として公の施設を設けるものとされ(地方自治法244条1項)公の施設の設置及びその管理に関する事項は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除き、条例でこれを定めなければならないとされている(同法244条の2第1項)ところ、住民等が公の施設を利用する場合の使用料の額やこれを免除する場合の要件等についても、公の施設の設置及びその管理に関する条例で定めるのが通常である。そして首長等が、条例中の使用料免除規定に基づき、公共施設の使用料免除ないし減額することはそれほど稀ではないと考えられるが、使用料の免除の違法性が認められた裁判例は、これまで公刊されたものとしては元町長の町民葬を執行した葬儀委員会に対し、式場である公民館の使用料の免除が争われた事例、神社の祭典実行委員会による学校施設の使用料を免除したことが争われた事例がある程度である。名古屋高裁平成17年4月13日判決は、条例において「特別な事由」があると認めたときは免除ないし減額できる旨の定めが置かれている場合において「特別な事由」に該当するのは当該事業ないし催しに対する地方自治体の関わり合いの程度、主催者の性格及び主催者と地方自治体の関わりの程度、当該事業ないし催しの目的・内容、当該事業ないし催しにつき主催者が使用料免除を受けつ必要性の程度等の事情を総合考慮し、公益性の観点から使用料を免除する必要性ないし相当性が特に高いと認められる場合を意味すると解されると判断したものである。本件は、三重県南勢町の住民である原告が、南勢町長において、南勢町文化協会等が南勢町町民文化会館で主催したチャリテイショーの使用料とその準備のための使用料等につき、条例で定める特別な事由に該当しないとして、地方自治法242条の2第1項2号に基づき、町に代位して免除額と同額の損害賠償を求めた事案である。特別な事由に該当しないという結論である。 判例タイムズ 1223号170頁 頭注
2007.01.09
-
ソープ嬢として雇用するに当たっての前貸し金が公序良俗違反とされた事例
原告はソープランドの経営者被告Y1と被告Y2は、その当時立川市内のホストクラブに客として煩瑣に通っており、同クラブに対する未払の遊興費として、被告Y1において150万円、被告Y2において50万円の各返済債務を負っており、同クラブから、再三にわたりその返済を強く求められていた。被告らは、ホストクラブのホストAから、風俗店で働いてでも前記債務を返済するよう求められたため、その返済に窮し、原告の店舗に赴いた上で、原告に対し、ソープ嬢として稼動する期間の給料の前借りを求め、翌日原告から、本件店舗のソープ嬢として雇用された。この雇用にあたり、原告から被告Y1は現金150万円を被告Y2は現金50万円を、それぞれ一旦手渡されたが、これらの現金200万円は、その場に同席したAがすべて持ち帰り、ホストクラブに対する前記債務の返済等に充てられた。被告らは平成15年11月2日以降、本件店舗内の客室個室に泊り込み、同月4日からソープ嬢として客との間で売春を行った。11月6日午後、被告らは、本件店舗が警察による強制捜査を受けたことにより、同店舗を出た。原告が前貸金の返還を求めたのに対し、東京地裁平成17年11月30日判決は、ソープ嬢として雇用するに当たっての前貸しとして締結された消費貸借契約について、売春の助長につながり、また、被告らの性的自由を侵害し、束縛するものであるとして公序良俗に違反するとして原告の請求を棄却した。控訴されたが、控訴棄却され確定している。 判例タイムズ1223号200頁
2007.01.06
-
民事再生手続が開始されたゴルフ場経営会社に対し会社更生手続開始申立がなされた場合
民事再生手続が開始されたゴルフ場経営会社に対し会社更生手続開始申立がなされた場合会社更生法は、会社更生手続がすべての担保権を手続内に取り込み、租税債権の行使にも制約を加えるなどの強力な効力を有する手続であることにかんがみ、更生手続を破産、民事再生法、特別清算等の他の集団的債務処理手続よりも優先させるいわゆる更生第1主義を採用している。(法50条1項)しかしながら、更生手続開始申立に対する裁判を行う時点において、裁判所に他の集団的債務処理手続きが係属しており、その手続によることが債権者の一般の利益に適合する場合は、これに反してまで更生手続を開始する必要性に乏しいことから、当該事由は更生手続開始申立の棄却事由とされており(法41条1項2号)その限度において更生第1主義が変更されているものといえる。ここで、の集団的債務処理手続によることが「債権者の一般の利益に適合する」といえるか否かについては、一般論としては、企業の規模・形態・業種・財産状態、当該手続の進捗状況等に鑑み、当該手続によるほうが弁済率、弁済期等の点で債権者に有利であるか否かによって判断すべきものと解されている。大阪地裁平成18年2月16日決定は、1最大債権者かつ担保権者であるCが更生手続を望んでおらず、再生手続の遂行に協力する姿勢 を示しており、再生手続によればCとの間で別除権協定を締結し、別除権不足額部分約423億 円の債務免除を受けることが確実であるのに対し、更生手続によると、Cから債権全額約427 億円が主張されることにより弁済率が低下するおそれが高いこと2債権者の多数を占める会員債権者の多くも再生手続による自主再建を望んでいること3現時点においてゴルフ場が円滑に運営されていること4再生手続においても経営責任の明確化は可能である 等の理由により再生手続によることが債権者の一般の利益に適合するとして更生手続開始申立を棄却した。 判例タイムズ1223号 302頁 頭注
2007.01.05
-
自己破産 自由財産の範囲の拡張の是非が問題となった事例
人破産の場合、財産を全部投げ出すが、借金も免責にしてくれというもの自由財産とは、投げ出す財産に入らないもの破産法34条3項に自由財産の範囲が記載されている破産法34条4項は平成16年改正後の破産法において初めて認められた制度自由財産の範囲の拡張 この是非に関する判例の集積が待たれるX 平成17年6月末日 勤務先退職 退職金受領平成17年11月8日 破産開始決定 Xは、上記退職金の残額528万7674円を含む合計606万8907円の現金を所持しており、上記破産手続開始申立に際し、上記現金から破産法34条3項1号所定の自由財産99万円を差し引いた507万8907円を破産手続予納金として裁判所に納付した。その上で、Xは、裁判所に対し、法34条4項に基づき、本件退職金の4分の3に相当する396万5680円について破産財団に属しない財産とする旨の申立をした。同申立の骨子は1 退職金債権はその4分の3に相当する部分が破産財団に属しないこととされているところ (破産法34条3項2号 民事執行法152条2項)本件退職金は、現に支払われて現金化したとは いえ、他の一般財産と混同することなく同一性を保たれて保管されていることから、これ を退職金債権と同視することができる2 Xは無職であって当分の間収入がなく、ほかにみるべき資産がないなどというものである。原審は、退職手当の支払を現に受けた後に当該退職者が破産宣告を受けたときは、同退職手当相当の金員は破産財団を構成するとの最高裁平成2年7月19日判決を引用して1の理由を排斥2の理由についてもXは46歳で健康にも問題がないなどの事情によれば破産手続開始決定による一時的な困窮を救済するための必要性があるとまでいえないとして本件申立を却下X 高裁へ抗告 高裁の決定は破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が破産財団に属するとの原則(破産法34条1項)にもかかわらず、同条3項所定の財産が何らの手続も要せず一律に自由財産とされている趣旨について、破産者の生活の維持を図り、経済的生活の再生の機会を確保する点にあると解釈する一方、同条4項による自由財産の範囲の拡張の是非をめぐる判断には裁判所の裁量の余地が認められるとはいえ、自由財産の範囲の拡張については、これを認めることにより配当原資の減少という不利益を被るはずの破産債権者において意見を述べる機会もなければ、自由財産の範囲を拡張する旨の決定に対して不服を申し立てることも許されないことを指摘した。本決定は、このような自由財産をめぐる制度内容をじかれこれ考慮した上で、破産者の生活維持は、原則的には法34条3項所定の自由財産でもって図られるべきであって、自由財産の範囲の拡張には、相応の慎重な態度で臨まなければならないとの判断枠組みを示した上で、本件抗告を棄却した。 福岡高裁平成18年5月18日決定 判例タイムズ1223号298頁 頭注退職せずに破産するというのがベターこの場合、現時点で退職したらでるであろう退職金の8分の1が破産財団を構成するとするのが実務
2007.01.04
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-
-
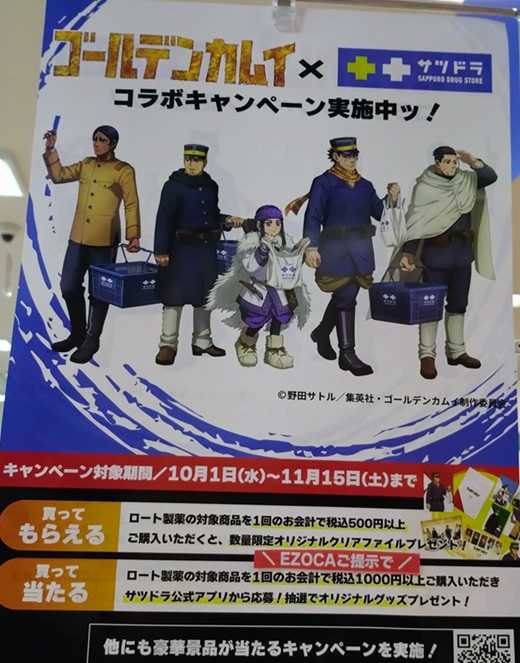
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-

- ビジネス・起業に関すること。
- 生きがいの見つけ方
- (2025-11-16 10:51:00)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-







