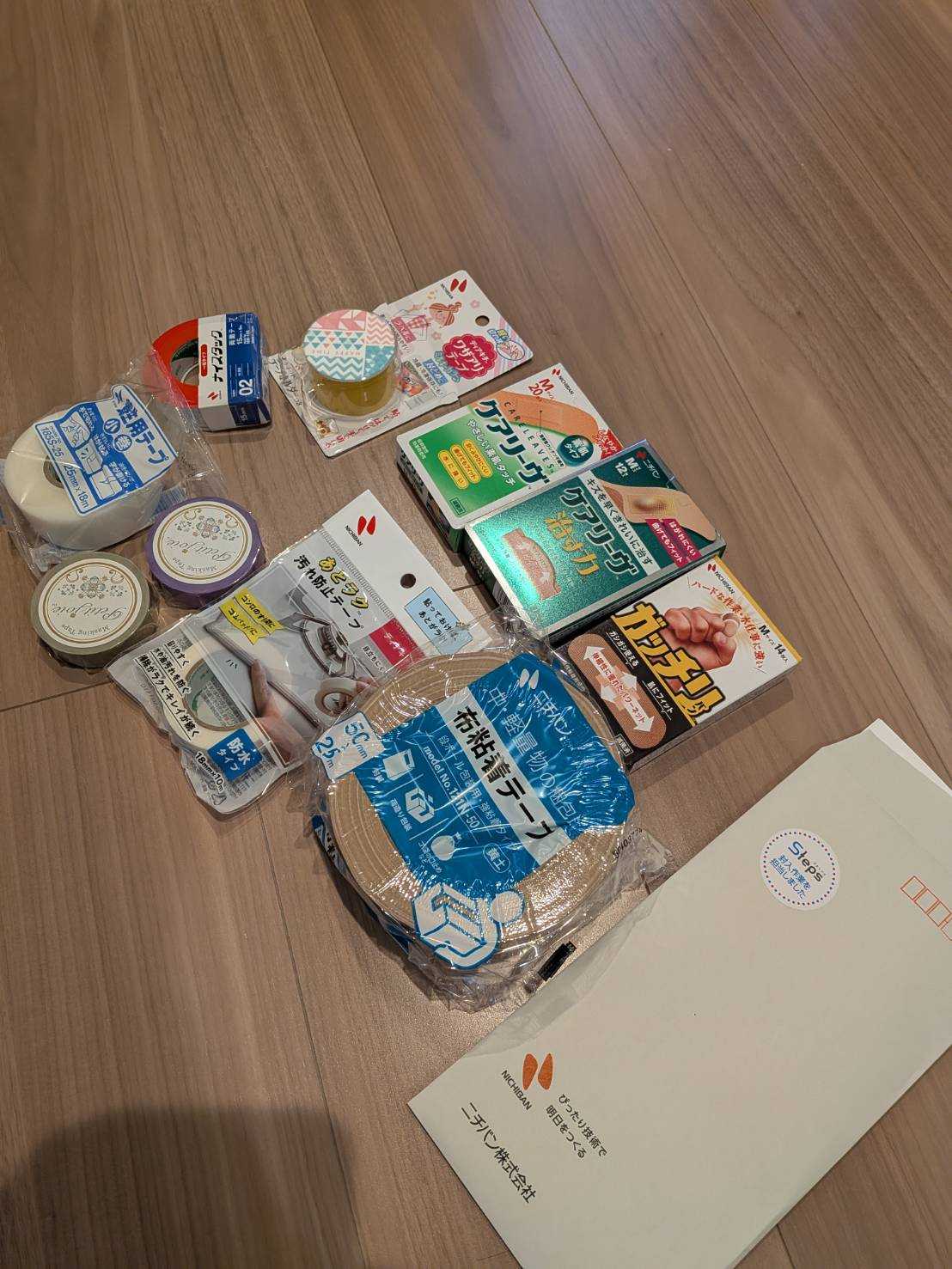2012年01月の記事
全2件 (2件中 1-2件目)
1
-
商品先物取引に係る不法行為に基づく損害賠償金(和解金)が非課税所得に該当するか
商品先物取引に関し商品取引員から不法行為に基づく損害賠償金として受け取った和解金が、平成22年法律第6号による改正前の所得税法9条1項16号、平成22年政令第50号による改正前の所得税法施行令30条2号の非課税所得に当たるとされた事例(名古屋地裁 平成21年9月30日判決) 「事案の概要」Xは、平成13年4月23日から平成14年7月2日までの間、Aに委託して商品先物取引を継続的に行い、1281万5795円の損失を被ったところ、平成15年2月25日、Aとの間で本件先物取引に関して、和解金457万0455円の支払義務があることを認めること等を内容とする和解契約を締結し、同年3月14日、本件和解金の支払いを受けた。Xは、本件和解金を所得に計上せずに平成15年分の確定申告を行ったところ、処分課税庁から、本件和解金を雑所得として計上すること等を内容とする更正処分及びこれに伴う過少申告加算税賦課決定処分を受けたため、本件更正処分のうち納付すべき税額を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分の取り消しを求めて、本件訴訟を提起した。 「判旨」施行令30条2号は、「不法行為その他突発的な事故」と規定しているのであり、「不法行為その他の突発的な事故」と規定しているのではない。法令における「その他」と「その他の」の使い分けに関する一般的な用語法に照らせば、同号において「不法行為」と「突発的な事故」は並列関係にあるものとして規定されていると解されるのであって、文言上、同号にいう「不法行為」を被告が主張するように限定的に解すべき根拠はない。また、不法行為の態様が、突発的な事故ないしそれと同様の態様によるものであるか、又はそれ以外の態様によるものであるかによって、当該不法行為に係る損害賠償金の担税力に差異が生ずるものではないから、損害賠償金が非課税所得とされている立法趣旨に照らしても、同号にいう「不法行為」は突発的な事故と同様の態様によるものに限られると解する理由はない。本件和解金が不法行為に基づく損害賠償金に当たるものであることは、前述のとおりであるから、本件和解金は施行令30条2号にいう「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」に当たるというべきである。判例タイムズ1359号137頁
2012.01.31
-
転付命令発令の審査と差押えの競合
裁判所は、転付命令発令の審査に当たって、差押えの競合の有無を審査する必要はないとされた事例(東京高裁 平成23年2月16日決定) 「事案の概要」本件は、相手方(債権者)が、供託金の還付請求権及び供託利息払渡請求権を差押債権として、債権差押及び転付命令を得たところ、抗告人(債務者)が、相手方は、原決定より前に発令された債権差押及び転付命令により、原決定と全く同一内容の決定を得ており、既に差押債権について転付を受けていることから、重ねて転付を受けることはできないと主張して、原決定の取り消しを求めた事案である。「判旨」転付命令発令の要件としては、実体法上被差押債権が存在することは要件と解すべきではないし、裁判所は、差押えの競合の有無を審査する必要もないというべきである。なぜなら、債権差押命令の発令に当たっては被差押債権の存在は要件ではないし、転付命令申立時にそれを要求することは、一貫しない上、当事者に困難を強いるばかりでなく、執行裁判所の審理も煩瑣となり、迅速な転付命令の発令が阻害されることになるからである。また、このような扱いにより、仮に被差押債権が存在しないため転付命令が空振りあるいは無効に終わったとしても、格別の実害は生じないし、差押債権者もそれを覚悟して申立をしているといえるものである。さらに、民事執行法53条が不動産について、民事執行規則147条2項が電話加入権について、それぞれ民事執行手続中に換価対象物が滅失等により存在しないことが判明した場合、当該執行手続自体を取り消す旨定めているが、一般の債権執行についてはそのような規定がないことからしても、上記のような解釈が裏付けられるということができる。判例タイムズ1358号244頁
2012.01.12
全2件 (2件中 1-2件目)
1