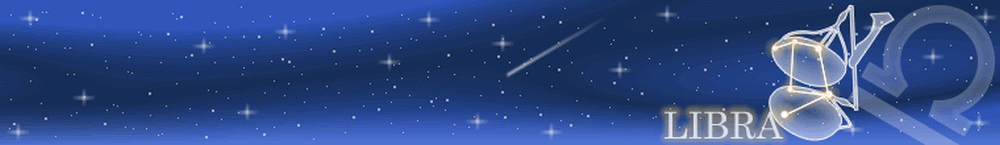全91件 (91件中 1-50件目)
-
人類がはじめて目にする光景
数日前の事ですが、夕暮れ時にふと空を見上げると三日月と宵の明星である金星が並んで見えて、藍色になった空の中できれいに輝いていました。こういう光景をしばらくじ~っと眺めていると、不思議と心が落ち着いてきて透明になっていき、自分が自然と一体になっていくような不思議な感覚になりました。私達は(宇宙ステーションにご滞在中の方々を除くと)ほぼ全員が地球の表面上に暮らしています。そして地球の表面上から見る光景しか自分の目で見る事はできないのですが、地球の外へ一歩離れて見ると、そこには地球上で普段目に光景とは全く違う世界を目の当たりにする事になります。最近は惑星探査機が何機も太陽系の中を飛ぶようになって、地球上とは全く違う世界の画像を目にする機会が少しずつ増えてきましたが、探査機が撮影した地球上とは全く違う光景の画像を見た瞬間、「ここはこんな世界になっていたのか!」という、生まれて初めて見る世界を目の当たりにする瞬間の新鮮な驚きと感動を感じる事があります。またその画像を見た瞬間に、自分自身が今住んでいる世界を認識している感覚が、ガラガラっと崩れて変化するのも感じとる体験もしている気がします、こうした驚きの画像を眺めているうちに「ここはどんな世界なのだろう?、そばに行って間近で見てみたらどんな感じがするんだろう?」という好奇がむくむくと沸き上がってくるのも感じることがあります。(まあ、これはただの観光客気分になっているだけなのかもしれませんが........。)昔だったらこういう体験は、本格的な探検家や冒険家の方だけが味わえた体験だったのかもしれませんが、それをお茶の間のテレビやパソコンの前に座っているだけで、世界中の人がほぼ同時に味合わえるようになったのは、なんて有り難い事なんだろう!と思うこともあります。という事で少し前のニュースに属する画像もありますが、ここ最近で「おお!」と感じられた光景の中から、現在冥王星を目指して飛行中の探査機ニューホライズンが木星に立ち寄った時に撮影した画像を紹介してみます。(ちなみに今回はリンクボタンにTargetタグを入れてみましたので、リンクをクリックすると別ウィンドウがパッカンと開くようになると思います。)「噴火する衛星イオの火山のアニメーション映像」白黒のややぼんやりした画像ですが、イオの火山の噴火の様子を初めてアニメーションの映像として見た時に「おおっ!」という驚きを感じました。この映像を見てると火山の噴火というよりも巨大な噴水を見ている感じがします。実際に間近で見てみるとさぞかしすごい光景なんだろうなあと想像してしまいました。「噴火するイオの火山のカラー画像」こちらはカラーの画像です。イオの夜の側で火山の火口が赤く光っているようです。「木星の地平線から登る衛星エウロパの画像」これも地球上では見ることができない光景です。将来木星の観光ができるようになった時は、観光客の人達はこういう幻想的な光景を自分の目で見ることができるようになるのかな?。「木星の中赤斑の画像」以前のブログにも書いた事のある木星の中赤斑の拡大画像です。この渦巻き一個が地球よりもでかいサイズです。この光景も間近で見るとさぞからすごい迫力だろうなあと思います。でも迫力がありすぎてその場にいてず~っとみてると気持ち悪くなってくることもあるかもしれないなあと想像してしまいました。ちなみにこれらの画像を撮影したニューホライズンは、去年の1月に打ち上げられ、ほぼ1年後の今年2月にはもう木星に立ち寄ってこれからの画像を撮影してました。この時、木星の引力を利用してさらにぐ~んと加速して冥王星を目指して飛んでいきました。ニューホライズンはこれまでの探査機の中では史上最速だそうですが、それでも冥王星に到着するのは2015年になるそうです。ちなみにこの探査機は現在この位置にいるそうです。今から8年後に人類が初めて目にすることになる冥王星はどんな姿をしているのだろう?とあれこれ想像しながら、画像が届くその日を楽しみに待ってみることにします。
2007.05.23
コメント(50)
-
ハビタブルゾーンにある地球型の惑星が見つかった!!
子供の頃から高校生ぐらいの頃まで、夜中になると自分の家の屋根に登って星を眺めていることがよくありました。当時は田舎に住んでいたので、空もそこそこ暗くて天の川もそこそこ見えていました。屋根に寝っ転がりながら天の川をぼ~っと見ていると、あそこに見えている星のどれかに自分とおなじような生命は住む惑星はあるのかな?と想像していたことがありました。でも実際にその惑星を見つけようするのは至難の技で、何十年も前からあ~でもない、こ~でもないといろんな観測方法が試されても見つけることができず、誤報の発表も何度も繰り返されてきたので、当分惑星が見つかる事はないだろうなあと思っています。そして実際に太陽とは別の恒星を回る惑星が見つかったのは、今から10年ちょっと前の1995年頃の事でした。太陽系以外の惑星がはじめて観測されたというニュースが飛び込んできた最初は半信半疑でしたら、それが本当らしいと分かってきた時は「おおっ!」と驚いてしまった事がありました。それ以来、別の太陽系の惑星が少しづつ見つかるようになってきましたが、観測技術の制約がまだまだあるので、今のところ見つかるのは恒星のすぐ近くを回るを回っていて、灼熱の恒星の熱であぶられて回っている巨大なガス惑星という異様な惑星ばかりでした。これはこれで「こんな惑星が存在していたのか!」と驚かされたのですが、生命が住めそうな地球のような惑星が見つかるのはもっとずっと先だろうなあと思っていました。なので昨年末に打ち上げられた惑星探索用の観測衛星「コロー(COROT)」ならばひょっとすると見つかるかも.......、と密かな期待をかけていました。実際、今月に入ってこのコロー衛星さんが最初の惑星をみ~つけたというニュースが入ってきていたので、この衛星で地球型に近い惑星が見つかることがあるかもという淡い期待を頂いていました。「系外惑星探査衛星COROTが初の惑星発見、予想以上の精度を発揮」ところが、先月にこの探査機の観測とは全く別のところから、地球型の惑星が見つかったというニュースが流れてきました。「液体の水、そして生命が存在する可能性も―地球にとても「近い」系外惑星、発見」ついでなので国立天文台(NAO)のプレスリリースも紹介しておきます。「ハビタブル・ゾーンにある地球型の系外惑星、発見か?」まさかこんなに早く地球型の惑星が、しかも20光年というご近所さんに(といっても光速度で飛んで行っても20年かかる距離ですが.....)見つかるとは思っていなかったので、これまた「おおっ!」と驚いてしまいました。さてそれではどんな惑星なのかな?と興味津々でニュースリリースの内容を見てみたら、どうやら地球の5倍の重さがあるそうなので、残念ながら人間はこの星に移住するのはちょっと厳しいかもしれないなあと思いました。でも、もしこの星の上に生命が生まれたとしたらものすごく強靭な体になるだろうと思うので、この星の生命がもし地球上にやってきたらまるでスーパーマンのような存在になるかもしれないなあと訳の分からない想像をしてしまっていました。ついでにこれを発見したのはチリにあるEOS(ヨーロッパ南天文台)の望遠鏡なのですが、EOSから出されたプレスリリースを紹介してみます。(これがニュースの元ネタだと思います。)「Astronomers Find First Earth-like Planet in Habitable Zone」そしてこちらに観測者が今回の発見を語っているビデオ映像がありましたので紹介しておきます。「今回の発見の紹介映像」もっともらしいアニメ映像で、雲と大地のある惑星の想像図のシーンまで出てきて面白かったですが、今回は実際にこういう惑星の模様まで観測できた訳ではありません。現在分かっているデータ、プレスリリースの中や紹介映像の中にもでていた、恒星の明るさの変化のグラフのカーブだけだったりします。今の観測技術で手に入れられるのはたったこれだけのデータなのですが、ほんのわずかと傍目には思える観測データ(微かな手がかり)から、まるでシャーロックホームズさんのように推理を重ねながら(でもきちんと論理的に裏付けをとりながら推理しています)こういう風な惑星になっているに違いないという結論を出しています。そして今回見つかった惑星については、これからいろんな観測が行われていくと思いますが、いつかこうした詳細な惑星の画像データを手に入れられるようになるといいなあ、また実際に人間がそこへ行けるような日がくるといいなあと、子供時代と同じようにあれこれと想像を巡らして楽しんでしまいました。観測技術の進歩により人類が今まで全く知らなかった世界が少しずつ見えてくるのは、私にとってはいつも驚かされるワクワクする体験だったりします。今この分野はすごく面白い発見が次々なされているので、これからどんなことが分かってくるのか楽しみに見守っていようと思います。
2007.05.13
コメント(0)
-
サングラスで立体視
久しぶりの書き込みです。しばらくお休みしていたと思ったらもう4月も半ばになってしまいました。以前やってた仕事の関係で立体視に興味をもっているのですが、普通のサングラスを使った立体視の実験をしているページがありましたので紹介してみます。「サングラスだけでお手軽飛び出すメガネ」青と赤の色をつけたメガネや、偏向ガラスや液晶シャッターのたメガネで立体的に見るのは体験したことがありましたが、普通のサングラスを使うと(普通に見てる状態よりも?)立体的に見えるとは知りませんでしたまたこのサイトにはどんな雰囲気で見えるかを体験できるかもしれないデモ映像もありました。(但し、立体的に見えてしまう原理については私自身は調べてないので、このサイトに書かれていた説明があってるかどうかはく分かりません。)これを読んでへえ~面白そうと思ったので、新幹線に乗って出張する機会があった時に実験してみようと思ったのですが、仕事で出張する時は普段サングラスをかける事はないので、うっかり忘れてしまいました。(笑)来週末にもまた東京に出張する機会があるかもしれないので、次回は忘れてないでサングラスを持って行って、道中の新幹線の中でも試してみようと思います。(笑)
2007.04.14
コメント(1)
-
2次元の写真を立体的に見せる方法
写真を立体的に見せる手法はいくつかありますが、一般的にはステレオカメラなんかのように視点を変えてとった2枚の写真を並べ、それぞれの写真を左右別々の目で見ることで立体的に見るというパターンが多いようです。IDEA*IDEAというサイトを見ていたら、普通のカメラ?で撮影した写真をちょっとした工夫で立体的に見せるテクニックを紹介していて、これが面白い!と思ったので紹介の紹介をしてみます。これは視点を変えて撮った2枚の写真を切り替えながら表示させると立体的に見えてしまうというものだそうで、写真の切り替え自体はGIFアニメで実現しているようです。「ちょっとしたアニメーションで立体的に見えてくる写真いろいろ」ちょっと目が疲れるかもしれませんが、これを見て「へえ~!」と感動してしまいました。(ホログラムを見る時に左右を少し動かしながら見ている感じに似てる気がしますが、こちらの方がずっと鮮明に見えるせいか新鮮な驚きを感じてしまいました。)どうやら2枚の画像を切り替えて表示させていると脳の中で3次元の形に画像が補正されるそうで、それで立体として見えてくるらしいです。(と、サイトの説明書きにありました。)ずっと以前に3次元スキャナというものを開発してたことがあって、そのせいで立体的に見るという手法には以前から興味をもっていたのですが、こういう脳の認識の仕組みを利用して立体的に見る手法というのは初めて知りました。(というよりも、私が知らなかっただけか?)この手法だったら、それこそカメラ屋さんに売ってる外部ストロボをとりつけるバーみたいなものに、外部レリーズ端子つきのデジカメなんかを2台取り付けるだけで、ステレオカメラがお手軽に一丁上がりという風になりそうな気がするし、撮影そのものもそこそこお手軽にできそうな気がします。それに2台のカメラを取り付ける間隔を変えれば、立体の奥行きの見え方も変わってきそうだし、2台だけでなく3台以上のカメラで撮ってみるとカクカクした画像ではなく、なめらかに動く映像として作れそうな気もします。(この考え方をさらに進めていくと映画「マトリックス」を撮影した特殊撮影の手法みたいに、くるりと1回転する画像を立体視的に見せる形で作れるかもしれませんね。)もしこのサイトをヒントに、ディテールの詳細な立体の視画像や、滑らかに動く立体視アニメを作られた方が誰かおられましたら、「こんなん作ったよ~」と教えて頂けるとすごく嬉しいです。
2007.02.19
コメント(1)
-
昼間も見えていた?明るく輝くマックノート彗星
ほぼ一ヶ月前の事になってしまいましたが、先月の1月半ばから後半にかけて、夕焼け空の空にすばらしく明るく輝くマックノート彗星と呼ばれるようになった彗星の姿が見えていました。先月の中旬頃に、東京で開催されたとあるセミナーに参加していたのですが、ホテルに帰ってインターネットに繋いでみると、ちょうと太陽に最も接近した頃のマックノート彗星の姿が太陽観測衛星SOHOの視野の中に捉えられていて、「おおっ!」と感動してしまっていた事がありました。以下はホテルで見て感動していた頃の彗星の姿です。「太陽に最接近した頃の強烈な太陽の光にじりじりと焼かれている彗星の姿」(画面中央の黒い円は強烈な太陽の光を遮る遮光板ですが、この中に描かれている白い丸い円の線が太陽の輪郭に相当します。この画面の左側に強烈な太陽の光に焼かれる彗星の姿が映し出されています。)そしてこの彗星は太陽の回りを数日間かけてくるりと回っていきました。以下はSOHOと呼ばれる太陽観測衛星が撮影した、太陽のすぐそばを霞めて飛んで行く彗星をアニメーションにした姿です。「太陽の回りを回る彗星の姿のアニメーション画像」そして太陽に焼かれた後の彗星は大量のガスを放出して、夕焼け空に明るく輝き、すばらしい尾を引く姿を見せてくれました。一番明るく輝いていた頃のマックノート彗星の姿は、残念ながら日本からは見えませんでしたが、オーストラリアあたりの南半球ではすばらしい光景が見えていたようです。以下は明るく輝くようになったマックノート彗星の紹介記事です。「40年ぶりの大彗星、マックノート彗星(C/2006 P1)」そして最も明るく輝いていた頃は、目を凝らせば?青空の中に彗星が見えている時期もあったそうです。(私は見てなかったのでどれくらいの感じだったかは分かりませんが)以下に昼間?に撮影した彗星の写真を紹介してみます。「青空の中に浮かんで見える彗星」それから南半球で見えていた彗星の写真集をご紹介してみます。これらの写真を眺めていたら、オーストラリアまで出かけて彗星を見に出かけていきたかったなあとしみじみ思いました。「マックノート彗星の写真を集めたページ」このページ中で、人物が一緒に写っているこの写真の雰囲気が結構気に入ってしまいました。「人物と一緒に写った彗星の姿」これは広角レンズで撮った見事な尾の写真です。「最も雄大に見えていた頃の尾の写真」(この写真を見ていて、なんだか地球でない別の惑星の光景を撮影したような、SF風の雰囲気も感じてしまいました。)こちらの尾の写真もすごくきれいに撮れている気がします。この光景は是非とも見たかったぞと思いました。「雄大な尾の写真:その2」今回は南半球まで行って彗星の姿をこの目で見る事が出来なかった買ったのはすごく残念でした。自分の時間を今よりも自由にできるような生活を早くしてみたいと真剣に思ってしまいました。(笑)
2007.02.06
コメント(0)
-
SETI@homeに再び参加
連休中に昨年のメールを整理していたら、SETIi@homeプロジェクトチームから、プロジェクトに再び参加してみませんかというお誘いメールが何度か届いていた事に気がつきました。このプロジェクトが今も進行中だったのを知って「懐かしい~!」と思いながら再び参加してみる事にしました。SETI@homeというのは、球外生命体(宇宙人)が発する電波信号を探してみようというプロジェクトです。1999年からスタートしていて、映画コンタクトの舞台にもなったアレシボ天文台で観測した電波信号を解析して、地球外生命体が発している電波信号を見つけだそうと試みるプロジェクトなのですが、地球外生命体かどうかの判定をするためには膨大な量の電波信号のデータを解析する必要があります。このため世界中にあるパソコンの空き時間を使わせてもらって、電波信号の解析の計算してしまおうというのがSETI@homeプロジェクトの特徴にもなっていて、自分のお家にあるパソコンを宇宙人からの電波信号を探す計算をさせる事でプロジェクトに参加することができます。このプロジェクトの実施期間は3年ぐらいだった思うのですが、それが終わった後も少し形を変えながらSETI@homeプロジェクトはずっと続いていたようで、たま~にニュース記事で「宇宙人からの信号が見つかった!」という誤報が流れる事もあって、思わずにやりとしたこともありました。(笑)「SETI@home、謎の信号を受信--異星人からの通信の可能性も」「SETI@Homeの謎の信号、異星人からの通信ではなかった」またここまで書いているうちに、私が学生だった数十年前に大学の図書館で「さびしい宇宙人」という本を読んだことがあったのを思い出しました。この本の中では、私達のいる地球以外に文明を持つ星はこの宇宙にあるのだろうか?、ひょっとしたら私達はこの銀河系で文明を持つに至った、たっだ一つの宇宙人なのだろうか?、ということを真剣に議論していた本だったのですが、この銀河系の中に私達以外の宇宙人が見つかるか確率は文明の存続期間に大きく左右されることが書かれていました。そして以前書いたブログに理化学研究所の岡ノ谷の講演の事を書きましたが、岡ノ谷さんが講演の最後で「文明を持ってしまった人類は短命な種に終わってしまうのだろうか?」と謎掛けをしてくれた事も思い出してきました。このSETI@homeのプロジェクトで、果たして宇宙人からの信号を捉えることができるのかどうかは分かりませんが、SETI@homeプロジェクトがこれからも続いてくれる事を祈りつつ、プロジェクトに参加していこうと思います。ついでに、SETIについては以下の日本惑星協会のページに解説がありましたのでご紹介しておきます。「SETIとSETI@homeについて」
2007.01.07
コメント(0)
-
サンタさんのソリの航跡を捉えた?
先週のことですが、ヨーロッパ南天文台(ESO: European Southern Observatory)に設置された全天の星空を撮影できるカメラMASCOT(Mini All-Sky Cloud Observation Tool)に眩しい航跡がを描く物体が捉えられたというニュース記事がありましたので紹介してみます。「サンタのそりには早すぎる?ESOのカメラが上空にとらえたもの」このニュースのページにも怪しい謎の物体の写真がありましたが、こちらにもそれらしい連続写真の画像が掲載されていました。「サンタさんのソリの航跡?の連続写真』(画像に写っている星座が左右逆というか、東西逆?になってるのがちょっとだけ気になりましたが、こういう風に撮れるカメラなのかな?)この怪物体が突然空に現れた時の様子はニュース記事によると、「約45分にわたって明るい線を描いた後、たなびく雲のような姿に変わってしまった。」と書かれていました。これはいったい何なんだ?!と驚いたESOの人たちが調べているうちに、このお騒がせ物体は12/18に打ち上げられた日本のH2ロケットの航跡だと分かったそうです。(タイミング的に見て、衛星分離の時の噴射ガスが見えていたのかな?と想像してみましたが、よく分かりません。)でも、明るい航跡を見つけた時のESOの人たちのあれは何だ?と驚いて慌てている様子を想像していたら、なんだか笑い出しそうになってしまいました。
2006.12.24
コメント(2)
-
ヒトはどうして言葉を持つようになったのか?
「ヒトはどうして言葉をしゃべれるようになったのだろう?、そしてヒト以外の動物はどうして言葉をしゃべれないのだろう?」という疑問が子供の頃にたま~に浮かぶことがありました。そして「どういう過程で言葉を持ち、喋れるようになっていったのだろう?」と不思議に思いながら、あれこれといろんな想像をしていた事がありました。同じような疑問をもっている人は結構いるらしくて、いろんな分野の研究者がそれぞれ個性的なアプローチのしかたでこの疑問を解いてみようと、今もいろんな研究者が研究を続けています。でもいろんな仮説は作られはするものの「どうやらこういう事らしい」と多くの研究者が同意するほどの仮説までは出てきていない状況のようです。先月はじめに、理化学研究所の脳科学総合研究センター、生物言語研究チームの岡ノ谷さんという研究者の方の講演を聞く機会がありました。岡ノ谷さんは動物のコミュニケーションについての研究をされている方ですが、私が子供の頃に頂いていた疑問を解こうとしている研究を講演の中で紹介してくれました。岡ノ谷さん自身は小鳥の歌(特に十姉妹の歌)の研究を皮切りに、動物のコミュニケーションの研究をずっと続けてこられてきて、今ではヒトの言葉がどのように獲得されていったのかというテーマにまで広げて研究を続けているそうです。今回の講演ではは動物のコミュニケーションと人間との言葉の違い、どうして人間は言葉を獲得するようになったのかについて、岡ノ谷さんの仮説を交えながら現在の研究の現状を紹介してくれましたので少しだけ書いてみます。講演では、そもそも動物の鳴き声と人間が話す言葉はどこが違うのかというところから説明をしてくれましたが、まず「単語に意味がある」、「単語の組み合わせをしている」というところから違っているそうです。鳴き声を出す動物の多くは状況に応じた声を出す事がありますが、それ以上のはっきりした意味を持つ事は少ないようです。一方、人間の喋る言葉は単語に分解できて、今現在こうして文字で書いているようなシンボル性と象徴性という「意味」を持っています。また多くの動物の鳴き声はある出の決まったパターンになっていますが、一部の動物については鳴き声のフレーズ(単語)を組み合わせた文法構造を持っています。この文法構造を持っている動物は人間を含めて限られた種類しかいないそうです。そして人間が言葉を話せるようになった原因の一つとして「呼吸を意図的に操作できる脳の回路を持つようになった」というイベントを挙げられていました。私達はごく自然にやっていますが、実は呼吸を意図的に制御できる動物はすごく少ないそうで、これができるのはクジラの一部の種、鳥の一部の種、霊長類ではただ一種類しかいないそうです。クジラや鳥は水中や空中で性格な呼吸の制御をする必要があったのでそれに適応していくうちに、意図的に呼吸を制御する脳の回路が形成されていったそうです。じゃあ霊長類はどうなんだろう?、どうしてヒトだけ呼吸を制御できるようになったのだろう?とすごく不思議な気がしてきました。岡ノ谷さんはこうした疑問について「産声仮説」という仮説を立てて説明をされていました。生まれたばかりの赤ん坊の脳のいろんな機能部位に配線が繋がっているそうですが、その後の成長していく過程で使わない機能の間の配線はいらないものとしてどんどん整理されていくそうです。ヒトは他の動物に補食される危険が減ってきた結果、進化していく過程で鳴き声で親を制御することを行いはじめた結果、生まれた直後は脳のあらゆる部分に張り巡らされていた配線のうち、呼吸を制御する脳の回路部分の配線が消えずに残るようになったのではないかというものでした。(実際に同じ霊長類で比べてみても人間の乳児はものすごくよく泣くそうです。)講演の中で、生後三日くらいの赤ん坊の鳴き声と生後一ヶ月くらいの赤ん坊の鳴き声の録音を聞かせてもらったのですが、最初は単調に泣いているだけだったのが、一ヶ月経つと意図的な鳴き方に変わっているのが分かり、なるほど~と思いました。(母さんが赤ちゃんの鳴き声にいろんな反応を示しているうちに、赤ちゃんの方も意図的な鳴き声にだんだんと変わっていくそうです。)という感じの話しが沢山出てきてすごく面白いと思った講演でした。ただし岡ノ谷さんの仮説自体はすごく自然なように私には思えましたが、まだ状況証拠しかないので、これが正しいかどうかまでは今のところ証明されてはいません。(というよりも、きっちり証明するのはすごく難しそうという気がします。)好奇心をお持ちの方は、人がどんな風にして言葉を持つようになったのかいろいろ想像してみるのもいいかもしれません。そして動物が鳴き声を出すようになったのは、恐竜の時代のおそらく1億年以上前からだと言われていますが、言葉をしゃべる動物が現れたのはここ10万年くらいのつい最近の事のようです。言葉を獲得してしまったヒトという動物は、他の種からみればあっと言う間に文明を作り上げ、地球上のあらゆるところに広がって住み着いて、今では宇宙の入り口までたどり着いてしまいました。どうもこの動物は他の種とは全然違う道を歩んでいるような気がします。このままずっと存続していけるのかどうか、それとも短命に終わるのかが気になってくるところです。岡ノ谷さんは講演の最後で、「ヒトが言葉を持ってしまった事は、個人としては幸せだったけど、種としては果たして幸せなことだったのだろうか?。ひょっとして短命に終わる種になってしまうのではないだろうか?」という言葉で締めくくられていました。これから我々はどうなっていくのだろう?と、あれこれと想像してしまった講演会でもありました。
2006.12.16
コメント(2)
-

月に願いを
来年にJAXAが打ち上げ予定のセレーネという名前の月探査衛星に、メッセージを載せようというキャンペーンをやっていますので書いてみます。「セレーネ「月に願いを」キャンペーン」セレーネは月がどのようにして作られたのかを調べたり、月の資源探査をするかなり本格的な科学衛星のようです。うまくいけばこの衛星の探査によってこれまでよく分からなかった月のいろんな情報がだんだん分かってくるかもしれません。7月ごろに開催されたセレーネ探査機のシンポジウムをたまたま聞いていた事があったんですが、セレーネの大きさは推進材も入れると重さ3トンになるかなり大きな衛星で、いろんな簡素機機材や子供衛星がこれでもかとばかりにてんこもりに搭載されていて、ハイビジョン映像を撮影する機能まで搭載されていました。(この衛星で月のどんな風景を生中継してくれるのか楽しみです。)このシンポジウムにはNASAや中国、インドの宇宙関係者も参加してて、おれたちゃ月に行くぞ~とばかりに、それぞれの国の月探査計画が表明されていて、これからいろんな国との間で宇宙開発の競争が始まっていきそうな気がしました。ついでなので、セレーネシンポジウム会場で休憩時間中に撮った写真を掲載してみます。会場にはセレーネの模型も展示してありました。このこのキャンペーンの紹介を見てて、数年前に星の王子様キャンペーンに応募した事を思い出しました。この時は世界中から集まった88万人分の署名の載せたハヤブサ探査機は宇宙へ旅立ち、無事小惑星の地表に署名を刻んだターゲットマーカーを降ろしてくれました。この時すごくワクワクした記憶がありますので、今回のキャンペーンにも応募をしてしまいました。自分の名前が宇宙へ行くのはセレーネがうまく打ち上がればこれで2回目になりますが、そのうち自分の体も宇宙へ行きたいなあと思っています。
2006.12.09
コメント(0)
-
太陽観測衛星「ひので」が観測した太陽表面の画像
「ひので」と名付けられた太陽観測衛星で撮影された画像が国立天文台のひので衛星のページに掲載されていましたので紹介してみます。「「ひので」搭載可視光・磁場望遠鏡の初期成果」このページの中にカルシウムH線で観測したという太陽表面のムービー画像のリンクがあったのですが、このムービー画像が太陽表面の動きを鮮やかに捉えて見えていて、まるでよくできたSF映画の1シーンのような印象的な映像になっていました。「太陽表面のカラーのムービー画像」(通信速度が早いネットワーク環境だと滑らかに動いて印象的に見えます)以前のブログでも紹介した事のあるひので衛星が撮影した彗星の日面通過の画像を見た時もここまで撮れるようになったのか!という驚きを感じましたが、同じような感動をこの動画を見た時にも感じてしまいました。ここまでの解像度で撮影できる「ひので」衛星は、現在のところ太陽観測に関しては世界最高レベルの観測性能を持っているそうです。この衛星がこれからどんな新しい発見をもたらしてくれるのか、たぶんこれから何年かの間に発表されていくであろう研究成果の内容を楽しみに待っていようと思います。
2006.12.02
コメント(0)
-
イルカ型のボートを作ってしまった人
イルカ型のボートを開発してしまった人の記事というか写真がニュースのサイトに掲載されていましたので紹介してみます。「フォトレポート:水上と水中を自在に泳ぐイルカ型ボート」このページにはイルカ型ボートがジャンプしている瞬間の良く撮れた写真が掲載されていて、この写真を見た瞬間に「ここまで思い切ったデザインで作ってしまう奴が世の中にいたのか~!!」と、思わず感動してしまいました。このボートを作ったのはInnespace Productionsという会社らしいのですが、未来的なSF的なデザインの小型ボートをいくつか設計して開発してきている会社のようです。その昔に川崎重工が開発したジェットスキーをはじめてみた時も、その遊びの発想と思い切ったデザインにここまでやるのか!と驚かされたことがありましたが、今回のイルカ型のボートと紹介されているページをはじめた見た瞬間に同じようなインパクトを受けました。また紹介されている写真をみてたらプロペラがないので、まさか本当のイルカみたいに身をくねらせながら推進しているんじゃないだろうなあと思ったのですが、ロータリーエンジンを搭載とかいう記述があったのでたぶんウォータージェット推進みたいなものなのかなとあれこれと想像してしまいました。背びれの部分はシュノーケルになっているようなので、水中には短時間しか潜れなさそうですが、すごく楽しい遊びができそうだなあと思いました。これは機会があれば是非とも1回は乗ってみたいと思いました。
2006.12.01
コメント(0)
-
水星の日面通過
11/9の早朝に水星が太陽の前を通って見える水星の日面通過を見る事ができました。この日面通過の画像を紹介したサイトをいくつか眺めていたら、その中に「おおっ!」と目を引く画像がありましたので書いてみます。「太陽観測衛星「ひので」がとらえた水星の太陽面通過」(JAXAのサイト)「「ひので」衛星が見た「水星の太陽面通過」」(国立天文台のサイト)これらのページで紹介されているのは、先々月の9月末に最後のM-5ロケットで打ち上げられたひのでと名付けられた太陽観測衛星から撮影した画像です。上のサイトの中に、この衛星で撮影した拡大画像が紹介されていて、以下の拡大映像を見た時にある種の「!」という言葉にならない驚きを感じました。「太陽の前を横切る水星の拡大画像」この画像を見た瞬間に、これまでの太陽観測衛星ようこうで撮影していた時の画像よりも解像度が上がり、水星の形がはるかに鮮明になって写っている事にまず驚きました。(ここまでの鮮明さで太陽の像を撮影するのは地上の望遠鏡では難しいと思います。)そして太陽が惑星と比べてどれくらい大きい天体であるのかは数字の上では知っているつもりだったのですが、こうして実際の大きさを比べる機会ができてみると、あらためてそのでかさぶりを実感して、「でっけ~!」と驚いてしまいました。こういう研究の最前線で新しい発見をしていくことのできる科学観測衛星をJAXAの宇宙科学研究本部がずっと打ち上げ続けてきた事にも、改めてすごいことだと感心しながら眺めていました。この衛星を使ってこれからどんな新しいことが見つかってくるのか、今後のひので衛星の観測を楽しみにしています。
2006.11.09
コメント(0)
-
コンタクトジャパン7
今から約十年くらい前にコンタクトという映画を見た事がありました。この映画はSETIの研究をしている天文学者が主人公の映画で、地球外の文明とのコンタクトする体験を描いていました。この映画は私が勝手に師匠と思っているカールセーガンさんが書かれた小説が原作になっていました。コンタクトの原作も映画も面白くて好きだったのですが、この映画を見たほぼ10年後にあたる先週の3連休の日に地球外文明とのコンタクトをシミュレーションするイベント「コンタクトジャパン7」に参加する機会がありましたので、その事を書いてみます。コンタクトジャパンというイベントには、今回はじめて参加したのですが、地球以外の星に生命が生まれて、もしその星の生命体が知性をもつようになったとしたら、そこにはどんな文明が構築されるのだろうか?という事を、参加者が夫々の創造力を駆使しながら議論しあいながら文明の姿を構築していくイベントでした。議論の最初はα星とβ星という2種類の仮想の恒星系を仮定し、その回りを回る惑星系の簡単な概要データと、夫々の惑星上にそれぞれ知性を獲得した仮想の生命体の特徴がアウトラインとして書かれた資料が主催者から渡されました。この資料を元に、この生命体が知性を獲得したとしたら、どのようなコミュニケーションが発生し、どんな原始社会が構築され、どんな文明化の過程を辿るかという事を2つの性質の異なる星系にそれぞれ2チームずつ、合計4つのチームに参加者が分かれて議論をしていく事になりました。最初に主催者側から与えられていたのはβ星の1年や1日の長さ、地軸の傾き、大陸の形状という基本データでした。ここからは、その星の姿を構築し、大まかな気候変動の範囲まで想定していきました。私自身はこの手の計算方法をほぼ完全に忘れてしまっていたので、すごくショックを受けたのですが(笑)、幸い天文学の研究者の方がグループに参加しておられたので、その方が概算で素早くいろんなデータの計算してくれて、β星のおおよその姿が描かれました。また生命体についてのアウトライン的な基本資料も渡されたので、こちらの資料からは参加者みんなでいろんな想像をしながらβ星に住む知性をもった生命体の姿を描いていきました。こういう生命体だと、どのようなコミュニケーションの形体をとるのか、その生命体の家族構成はどのような姿になるのかという事を想像力を駆使しながら議論をして、文明化される前の原始時代の社会生活はどのようなものになるのか、どのようにしてその惑星に広がり、どのような文明化の過程を辿るのかの仮想の文明の歴史を構築していきました。この作業の過程では、私自身がこれまでにどこかで見たり読んだりした事のある人間の文明の歴史の知識、類人猿から古代人類に進化していく過程の知識、地球の気候変動の知識を総動員しながら考える事になりました。同時に自分の持つ想像力もほぼ全て駆使しながら真剣に考える事になり、グループのメンバーとの間で議論しながら文明の姿を構築していく過程はすごく楽しいものになりました。大げさに言えば「世の中にこんな楽しい事があったのか!」と思いながら、時々大笑いしながら議論を進めていきました。また、参加者の皆さんはこの生命体を宇宙に進出させたいと思っていたので、この生命体が惑星の外へ出かけたいと思うためには、どのような動機が必要になるのかをみんなで考えながら話し合い、β星の恒星系に惑星間の文明を構築できたところまでたどり着いたところで、その星の星系外から知的存在らしき存在がβ星の星系外に接近しているというイベントの発生が主催者から知らされました。その後は、参加者の皆でその惑星の生命体になりきり、その存在に対してどのような対応をするかの議論が始まりました。自分たちはとはおそらく全く異質の知的存在の可能性があるため、どのような存在なのかの情報をまず収集するため、様々な観測機器をその知的存在に向けて観測をはじめ、様々な異なるタイプの無人探査機を接近させて偵察行動を行いました。(どのような探査が技術的に可能かという議論の過程では、天文学の研究者の方の意見をたくさん出してくれたので、かなり現実的な探査計画のシナリオができあがったように思いました。)私自身は相手の意図が全く読めない異質な存在が自分たちの恒星系に接近していくることについてすごい不安感を感じてしまい、相手の探査と偵察をすると同時に、相手の迎撃も想定した軍事オプションのプランを準備する事と、なるべく自分たちの住む惑星から離れた距離で相手を迎え撃てるようにする提案もしてしまいました。この事については、後で振り返って自分自身で驚いてしまいました。恒星間を渡ってきた存在に対して、その文明の技術レベルでの軍事オプションのプランが採用しても、それが通用するかどうかは疑問符がつきそうな気もしますが、自分たちが住む星にもし何かあったらという恐れと不安感が先に出てきてしまいました。この感覚と感情は一体何だったんだろう?と後で考え込んでしまいました。その後、その知的存在の正体は「な~んだ」というオチがつきましたが、もし何らかの存在が太陽系に接近してくることが分かった時に、地球人はどのような反応をするのだろうかという事を、イベントが終わった後もあれこれと考えていました。そしてイベントの最後では、それぞれのチームが独自に構築した文明の姿がプレゼンテーションされていきました。それぞれのチームの発表を聞いていると、構築された文明の姿が全く異なっていたので、そういう方向で考えたか~と、これもまた感心しながら楽しく聞く事ができました。........という感じで普段は全く考えた事もなかった事を真剣に大まじめに議論するという、知的な遊びを思う存分体験できたすごく楽しい三日間を過ごすことができました。たぶん今回のような議論を本当に真剣にやろうとしたら、幅広い知識と本当の意味での教養が要求されるんだろうなあと思いましたが、これと同時に、好奇心と探究心と想像力を駆使しながら議論を楽しんでいる人たちが沢山いる事を今回はじめて知ることができて、この面でも嬉しい体験となりました。さらに今回は参加者の中に、恐竜の想像図のイラストを描いている山本聖士さんという方がおられたのですが、イベントの期間中にこれまでに描かれたイラストの原画の展示とポストカードの即売会をしてくれました。そしてポストカードの原画の中にあった一枚で、プレシオサウルス?のカラーの挿絵が気に入ってしまいました。山本さんと話をしているうちに気がついたら生まれてはじめて画家の方から絵を買ってしまっていて(笑)、楽しいおまけの体験もすることがでラッキーでした。(さてと....、これから原画を納める額縁を買わなくては。どんな額縁が会うのかなあ?.....。)という感じで、よく分からないものの、なんだか楽しいなあと思えるような体験が少しずつ増えてきている事を実感した三日間にも感じられて、良い時間を過ごせたなあと思いました。
2006.11.07
コメント(0)
-
達人になれるレッスンの方法?
日経サイエンスという雑誌の先月号をぱらぱらと見ていたら、面白そうな以下の記事が目に留まったので書いてみます。「チェス名人に隠された才能の秘密」この記事には最近の心理学の研究成果の応用の一つとして、達人になるためのレッスン方法についての解説記事が書かれていました。例えばピアノ練習の上達のパターンを例にとってみると、最初の習いはじめの頃はぐんぐん上達する人が多いのですが、だんだんと上達する速度が落ちてくることが多いそうです。これは最初の習いはじめのころは全てが挑戦的な課題になるけれども、それに少し慣れてきた段階で練習内容のレベルおなじだと、それが挑戦的でなくなるので上達する速度も鈍ってくるという事らしいです。ところが天才と呼ばれる人たちは、その時その時のレベルから見た難易度の高い課題を次々に設定し、それに挑戦し続ける事で自分の能力をぐんぐん伸ばしていくそうです。例えばピアノの練習をまた例にとると、普通の人は2、3年経つと上達する速度は頭打ちになってくる人が多いそうですが、音楽学校の生徒は学校から出される難しい課題を次から次へとこなさないといけない環境にいるので、普通の練習をしている人よりも早くピアノ演奏の腕が上達していくことが多いと書かれていました。そしてまた子供の頃からこうした環境を作ってやれば、その子供はその道の達人に成長しやすいという事も書かれていました。日経サイエンスの記事ではタイガーウッズを例に子供の頃から練習している効果を紹介していましたが、そう言う意味ではイチローなんかもそれに近いのかもしれないなあと思いました。という事でこの記事を読むまではスポーツや音楽なんかは才能が必要な職業なのかなと半ば諦めていたところがあったのですが、人間の脳の学習の仕組みに会わせた練習方法を取り入れることで、やり方によっては結構いい線までいけるのかも知れないと思うようになりました。実は昨年からピアノを独学で練習をはじめていて、ついでに声楽のレッスンも受けはじめていました。大人になった今からスタートしても果たしてどこまでうまくなれるのかなあといった、やや懐疑的な見方をしてしまうところがあったのですが、ひょっとすると自分もまだまだ可能性を伸ばす余地があって、練習方法によっては結構いいところまでいけるかも.......と調子良く思えるようになってきてしまいました。(笑)最近はダンスのレッスンもはじめているので、こうしたお気楽な習い事でも挑戦的な課題を設定して取り組む練習方法に変えてみるのもいいかも知れないと思うようになりました。さてさて、果たしてどんな効果が得られるのか、ちょっとしたお楽しみ気分で取り組んでみようと思います。
2006.10.27
コメント(2)
-
ブラックホール回りの時空の歪みを観測できた?
今月はじめに科学観測衛星すざくがブラックホールの回りの時空の歪みを観測したというプレスリリースがJAXAから出ていました。このプレスリリースに興味を持ったので少し書いてみます。(ちなみに「すざく」は以前ブログでも書いた事のあるM-Vロケットで、昨年打ち上げられた観測衛星です。)「ブラックホールに迫る「すざく」衛星」ブラックホールはあまりにも重力が強すぎて何でも飲み込んでしまうので普通は観測できないのですが、ブラックホールにガスがのもすごい勢いで落ち込む時にX線を発するのでそれと分かるそうです。すざくは宇宙で飛び交っているX線を精度よく観測できる科学観測衛星で、ブラックホールの回りの強い重力による空間の歪みによって、X線がぎゅぎゅっと曲げられたと考えるとうまく説明できる高精度のデータが観測されました~という事が今回のプレスリリースに書かれていました。時空の歪みによってX線が曲げられたと仮定してその方向に考えをどんどん押し進めていくと、今回の観測により得られたデータのパターンを調べていくことで、ブラックホールの回転速度や、物質がブラックホールへ吸い込まれていく時の角度も測定できるようになりま~すというのが今回の発表のキモのようでした。プレスリリースに掲載されていたグラフを見ると普通とは明らかに違うグラフのパターンが見えますね。(プレスリリースにはそれらしい想像図もつけてサービスしてくれているのもナイスだと思いました。)でも実際にその現場にいって空間が歪んでいる様子を見た人も、X線が曲げられて進んでいく様子を見た人も今のところ誰もいません。その現場に出かけていく技術的な手段も今の人間は持っていないようです。(凄まじいX線が出ている現場なので、たとえ見に行けるようになったとしても、危なくて近寄れないと思いますが......。)でもその代わりに、ある意味ではこうしたちょっとした手がかりのように見えるデータから、あ~でもない、こ~でもないと考えながら、そこでは何が起こっているんだろうと想像力を駆使していろんな仮説を立てて考えていくという事を研究者は行っています。そうして自分が立てた仮説が正しいのかどうかを少しずつ確かめながら分からなかった謎を解いていったり、新しい発見を少しずつしてくことで、少しずつサイエンスの知識が蓄積されていきます。私自身はこうしたサイエンスの分野の活動というの「は好奇心」という人間の基本的な欲求の一つを元にして、代々2000年近く続けられてきた一種の文芸活動の一つだと思っています。そういう意味では文学や音楽や彫刻や絵画や演劇と同じ種類の活動と思っているのですが、このプレスリリースを見た時にとうとう時空の歪みの観測結果まで推論するようになってきたのか~!とある種の感動を覚えてしまいました。天文学の分野に限らず、ここ数年「お~っ!」と驚かされる発見が増えてきたように感じていて、いろんなサイエンスの分野の研究が進展していく様子を見ていると、すごいワクワク感を感じることがあります。これからもサイエンスのいろんな分野の研究が進んでいく様子を楽しみに見守っていこうと思います。
2006.10.27
コメント(0)
-

双眼鏡・望遠鏡サミット2006
子供の頃から何故か星を見上げるのが好きで、子供の頃に実家の屋根に上って星を見上げていたり小さな天体望遠鏡で星を覗いていたことがよくありました。この趣味は今でも続いていて、たまにですがオープンカーに天体望遠鏡を積んで星を見にでかけることがあります。先週はそうした星を見る趣味の人たちが集まる双眼鏡&望遠鏡サミット2006というイベントに参加してきましたので紹介してみます。今回参加したイベントは大きな天体望遠鏡や巨大な双眼鏡を自作して星を眺めている人たちが年に1回、全国から集まってきて自分たちの作った望遠鏡を紹介しあうくるという集まりです。主催されているのは、御自身でも屈折望遠鏡としては世界最大級の双眼望遠鏡を自作された服部さんという方で、双眼望遠鏡の名前をとったBigBinoというサイトを運営しています。「BigBinoのページ」普通の望遠鏡は筒が1本だけあって片目で覗くようになっていますが、双眼望遠鏡は天体望遠鏡の筒を2本並べてあって、両目で覗けるように制作されいます。(双眼鏡の一種と思ってもらってもいいと思います。)双眼望遠鏡を解説したページを以下に紹介しておきます。「双眼望遠鏡の解説ページ」ということでユニークな天体望遠鏡や双眼望遠鏡を制作している方たちが日本にはたくさんいるのですが、そういう方たちが今回全国から愛知県のスターフォレスと御薗という天文台の施設に集まってきてお披露目会をしてくれました。このイベントは毎年開催されていて、参考までに昨年に開催されたイベントリポートのページを紹介しておきます。「第8回双眼鏡・望遠鏡サミットのイベントレポート」ということで今回のイベントの紹介ですが、大きな天体望遠鏡や相眼望遠鏡がたくさん集まってきました。こんな感じで天文台の中庭のようなところに望遠鏡が並べられていて、夜はこれらのたくさんの望遠鏡で星を見せてもらうことができます。すごくユニークな望遠鏡がたくさん集まってきているのですが、こちらは主催者の一人である服部さんのBigBinoの写真です。直径25cmのレンズの屈折望遠鏡を二本並べています。(レンズはロシアの科学アカデミーに制作してもらったそうです。)この望遠鏡で覗かせてもらった両目で見るオリオンの大星雲はすごく奇麗で、この奇麗さは写真では味わえない世界のような気がしました。こちらは今回のイベントで一番口径の大きかった55cmの反射望遠鏡の写真です。この望遠鏡で見せてもらった白鳥座の網状星雲はレースのような流れるガスの姿がはっきり見えてやはりすごく奇麗でした。星を追尾するモーターがついています。鏡以外はほぼ全て自作されていて、モーターの制御回路も自作で、プリント基板も御自分でプリントのパータンを印刷して制作されたそうでした。(すげ~)昼間は参加者が持参した望遠鏡を説明していく自己紹介イベントが行われていました。ユニークなエピソードが次々と披露されていて聞いてるこちらも楽しかったです。こちらは口径30cmくらいの反射望遠鏡を自作された方の望遠鏡紹介の時の写真ですが、よく見ると望遠鏡の部品の一部がなべかまで作られていました。(笑)部品を取り外すとこんな風におなべの中にコンパクトにあっと言う間に収納できるようになっていて感動してしまいました。(笑)こちらは一夜明けた朝の風景です。朝の霧がかかっています。星を見てる途中で何故かたくさんの流星が飛んでいることに気がついたので、途中から自分の車の屋根を開けてシートをリクライニングさせながら、朝まで星を眺めていました。(オープンカーはこういうことができるのでいいですね。)後で調べたらどうやらオリオン座流星群が突発的な活動をしていたようで、アストロアーツのサイトで流星群のニュース記事が出ていました。「【速報】オリオン座流星群が突発出現」ただ朝方はうとうとしてしまっていたので、流星出現のピークの頃を見逃してしまったのはやや残念でした。(それでも沢山の流星を眺めることができたのはラッキーでした。)満天の星空の下で静かに星を眺めながら、時々飛んでいく流星をみていると、心が静かに、透明になっていくような気がしました。すごく気持ちのいい時間を過ごせた三日間でした。
2006.10.25
コメント(0)
-
M-Vロケット後継機の開発
今日届いたJAXAのメルマガを読んでいたら、M-Vロケットの後継機の開発をしているプロジェクトマネージャのコラムが掲載されていて、そこに書かれていた前向きな文章が印象的だったので紹介してみます。M-Vロケットは、50数年前に開発がはじまったペンシルロケット開発の流れを組む固体燃料ロケットで、固体燃料ロケットとしては唯一惑星探査機も次々と打ち上げてきて、個体ロケットとしては世界最高のペイロード比(ロケット全体の重量に対する、打ち上げる衛星の重量の割合。いわゆるロケットの打ち上げ性能です。)を持つと言われています。ところが、このM-Vロケットの運用を終了するというプレスリリースが7月頃に出されていました。運用終了の理由の一つはM-Vロケットの打ち上げコストだったそうですが、100億円の開発費をかければ打ち上げ費用を半額にできるという試算もあったそうですが、こういう開発の方向は採用せずにM-Vロケットよりも打ち上げ能力の低いロケットを新規に開発する事にするようです。(新規にロケットを開発するとなると、それこそ開発費は100億円では済まないだろうし、それで開発するのがM-Vよりも低いとなると、どういう方針に決定されたのかよく分からなくなります。)そして先月のM-Vロケットの打ち上げを最後にM-Vロケットの運用を終了してしまいました。このため、今現在は打ち上げ可能なロケットはH-IIAの1機種した存在せず、残りのロケットはこれから開発するという事になっているようです。このブログ自体も実はM-Vロケットの打ち上げシーンを見ていてうちに、ブログを書いてみようかなと思うようになったのがきっかけで、書きはじめた事もあったので、さてこれからどうなるのかな?とやや気にはなっていました。という事で説明のための前置きが長くなりましたが、こういう状況でM-Vロケットの後継機を開発せよろ言われたら、あまり面白くない状況と捉えてしまったとしても、そのエンジニアの気持ちはよく分かる気がします。ということで前置きが長くなってしまいましたが、こうした状況にも関わらずメルマガに掲載された次期個体ロケット開発のプロジェクトマネージャの文章を読んでみると、元気いっぱいの文章が書かれていました。その文章には「小型ロケットを開発すればこれまでのM-Vロケットよりも打ち上げ回数を増やして科学衛星をたくさん打ち上げられるし、打ち上げの運用コストを減らす工夫をするには、打ち上げの機会を増やせる小型ロケットを使う方が都合が良い」と書かれていて、現在の状況を前向きに捉えて開発を進めて行こうとしている姿勢が読み取れる気がしました。今までいろんな宇宙開発の本を読んだり、いろんな話を興味を持って聞いてきた印象としては、どの時代、どの国においても、宇宙開発に携わっている人たちは、厳しい状況に置かれてもへこたれず、いつも前向きに物事を捉えて前進しようとする考え方の人たちが多かった気がしています。(これが一番極端に出ていて印象的なのはソビエトの初期のロケット開発の総指揮をとっていたコロリョフさんや、ナチスドイツでロケットの開発をしていたフォンブラウンさんかなと思います。)私が宇宙開発に妙に心引かれるところがあるのは、こういう現場の人たちと開発のリーダーが多いせいかもしれないと思う事もあります。そうした気質を持つガッツのある開発リーダーの一人が、新しいロケットの開発に向かおうとしている様子を感じて、なんだか新しいロケットの開発を応援してみたくなってしまいました。ともあれ、これからの新しいロケットの開発で、どんな新たな挑戦とどんな新たな開発の道筋が作られていくのか、見守っていきたいと思います。
2006.10.24
コメント(0)
-
ジェットパックを背負った人々
ギズモードジャパンのサイトにジェットパックコンベンションの記事が載っているのを見つけてこれは面白い!と思ったので紹介してみます。この記事の写真を見ているうちに、ロケットを背負った主人公が空を飛び回るロケッティアという映画があったのも同時に思い出してしまいました。こうした背中に背負って飛ぶタイプの空飛ぶ道具の事をジェットパックと呼ぶそうですが、このジェットパック野郎達が集まる大会が先月開催されていたようですので紹介してみます。「Rocketbelt Convention 2006」(このサイトではRocketbeltと表現してるようです。)実際にはロケットを背中に背負ってしまうと、そもそもロケットなので推力の制御は難しいだろし、うっかり足をロケットが噴射してる炎に近づけたらあっちっちと火傷しそうな気もしますが、こちらの大会では圧縮した気体(空気?)を詰めたボンベを背負って気体を噴射しながらが空を飛んでいるようです。(これだったら空気を詰めたらまだすぐに飛べそうだし、取り扱いも簡易で安全そうですね。)そう言えば子供の頃に小型化したジェットエンジンを背負って空を飛んでいる人の映像をTVで見たような記憶もあったなあと思い出してきました。(この時の開発では確かDARPAが資金を出してような気もします。)この大会の写真集がflickerにも投稿されていましたので、こちらも紹介してみます。ここに投稿された写真を見てると空を飛んでいる雰囲気がなんとなくわかるかもしれません。「大会参加者の試運転中?の画像」「飛び上がる瞬間の画像」(回りにいる人は耳を塞いでいるので、音は結構うるさいのかもしれません。)「空中に浮かんでいるシーンその1」「空中に浮かんでいるシーンその2」これらの写真を見てるうちに、取り扱いを容易にして安定して飛べるようになって、だれでも簡単にスーパーマンみたいにで簡単に空が飛べるようになると結構楽しい世界になるかもしれないなあと思いました。航続距離をもう少し伸ばせるようになって、ジェットパックを背負って自宅から空を飛んで通勤するのが一般的になったりすると、その頃には満員電車の交通渋滞も少なくなるかもしれないし、みんな自由にいろんなところに文字通り飛んでいけるようになるといいなあとも思ってしまいました。普通のビルの玄関は大抵1階に作られていると思いますが、これが屋上にも作られるようになったりするかもしれないなあと想像していたら、遅刻しそうになった人は仕事をしているビルの階に窓から直接飛び込んできたり、六本木ヒルズのような高層ビルだと出勤時や退社の時刻になるとビルから人がどわ~っと飛び上がる光景が見られたりするかもしれないなあと、いろんな想像が浮かんできてしまいました。
2006.10.14
コメント(0)
-
ナイスでかっこいい自動ドア
ギズモードジャパンというサイトでナイスな自動ドアの映像が紹介されていて、その映像を見たら「おおっ!、かっこいい!」と思ってしまったので紹介してみます。「SF映画みたいな開き方をするドア(動画)」こういうものを実際に作ってしまう発想はすごく気に入ってしまいました。ドアの開く音もSF映画っぽくて雰囲気そのものが「すげ~、かっこいい!」と思いました。このドアを実際に作ってしまったのは田中製作所という会社だそうです。この会社のサイトに製品紹介のページがありました。「新発想自動ドア」自分の会社や自分の家にこのドアをつけてみたら楽しそうだろうなあと思いました。私はこういうのを見てしまうとなんとなく親近感が湧いてついつい応援してみたくなるところがあります。何か良いアイデアを思いついた方はここの会社に連絡をされてみるといいかもしれませんね。
2006.10.04
コメント(0)
-
新型グライダーの進空式
ご近所のグライダークラブのみんなでお金を出し合って、ドイツのシュンプヒルト社というグライダー製造会社に新型グライダーを発注していたのですが、その機体がようやくグライダークラブに到着しました!。それを記念して先週の日曜日に進水式ならぬ進空式をやっていたようです。「進空式の日記」残念ながら私は参加できなかったのですが、グライダークラブの日記をみていたらすごく楽しそうな写真が掲載されていたので、うわあ!、いいないいな!と思ってしまいました。そういえばいろんな週末の用事が重なりっぱなしで、よく考えたら今年はまだ一回もグライダーに乗っていませんでした。来週も別の用事が入ってしまったし........、う~む、残念。(笑)新しいグライダーのオーナーの一人にもなったことだし、なんとか時間の都合をつけて飛んでみたいと思います。やりたい事はいっぱいあるのに時間がないのは困ったもんだと思ってしまいました。
2006.10.03
コメント(0)
-

火星の人面岩
小学生の頃に火星探査機バイキングが打ち上げられ、火星に着陸しました。この探査機は火星の地表に着陸するランダーと火星の周回軌道を回るオービターがセットになっていました。バイキングのランダーが撮影した火星表面のカラー画像をはじめて見た時は子供心にもある種の感動を感じた事がありました。それからしばらくは新聞にバイキングのランダーとオービータ撮影した画像が載るたびに、その記事を読んでいた時がありました。その頃に紹介された記事の中で「なんだこれは?」と首を捻ってしまったのが、オービターが撮影した以下の火星の地形の画像でした。当時のNASAはこれを人の顔に似た岩と紹介していましたが、当時の子供の画像認識能力ではあまり人の顔には見えませんでした。ご近所の悪ガキ達も人の顔には見えへんわ~という意見が多かったようで、その頃は「たまたまそういう風に見えているだけじゃ~ん」と思いましたが、今こうして改めて見てみるといろんな想像をしてしまいそうな画像だと思いました。これはピラミッドに違いないとか昔の都市の跡だとか、いろんな人がこの写真を見てる想像を逞しくしていたようですが、今この画像を見ているとそういう風にあれこれ想像したくなる気持ちはすごくよく分かるなあと思いました。(笑)(そう言えば、数年前に制作されたとある火星探検のSF映画の元ネタにもなっていた気もします。)その後数十年経って、数年前くらいから火星探査機がたくさん飛ぶようになって、火星のより詳しい地形の写真がたくさん撮影されるようになりました。そして人面岩についても詳しい映像が見えるようになってきたら、ただの錯覚でした~ということになってしまいました。(ちょっと残念)この人面岩の詳しい地形の画像がヨーロッパ宇宙機関(ESA)のニュースサイトに最近掲載されましたので紹介してみます。この画像はESAが打ち上げたマーズ・エクスプレスという探査機から撮影された画像です。「Cydonia - the face on Mars」この探査機は高解像度ステレオカメラを搭載していて、火星の地形を立体的に撮影していけるようになっているそうです。(この撮影装置の原理の説明はまだ読んでないので、どんな風に立体形状を計測しているのかはよく知らなかったりします。(笑))日本語の紹介記事はこちらで読めます。「マーズ・エクスプレス画像集:火星の顔」現在火星の周回軌道には探査機が4機回っていて、地表にはマーズローバーの探査者が2台動き回っています。その中でも最新の探査機は、「マーズ・リコナサンス・オービター」で今年3月に無事火星に到着しました。この探査機は少しずつ軌道を低くしていて、来月あたりから本格的な観測を行うようになるそうです。この衛星は火星の地上にある数十センチメートルの物体をまで識別できるそうなので(その名の通り、まるで偵察衛星みたいですね。)今までにない詳しい地形の画像を送ってくれるそうです。さて、この衛星がどんな不思議な画像を送ってくれるのか楽しみにしています。
2006.10.02
コメント(0)
-
宇宙ステーションからのブログ更新
宇宙ステーションに滞在中のアンサリさんが宇宙からブログを更新してくれています。(何の気なしにブログの更新をされてるようですが、この更新データはこんな経路で通信されているんだろうなあ想像してみたら、これはすげ~と勝手に感動してしまいました。)という事でなんだかこのネタばっかり書いてる気がしますが、ご本人が実況中継してくれてる宇宙ステーションの生活の様子を読んでいたらなんとなく臨場感があって、へ~、こんなかんじなのか~、妙に感心しながら読んでしまいました。(笑)最初の頃は宇宙酔い?みたいな症状が出たり、頭に血がのぼったり背中が痛くなったりしてたようですが、今はもうすっかり?回復してるようです。ちなみに今日のブログでは、歯磨きやシャンプーのしかたなんかの日常生活のお話が書かれていました。それによると歯磨きについては、歯を磨き終わった後の歯磨き粉を飲み込んでしまうようです。(よく考えたら、そもそも無重量状態で上下はないので、水を流すこと自体ができなさそうですね。)そしてシャンプーをする時は水の固まり?(water bubbleと書いてたけどどんなのだろう?)をゆっくりとやさしく頭の上にもっていって洗うそうですが、ちょっと揺れるとすぐに小さな水の固まりになって飛び散ってしまうそうです。(なんだかシャンプーのたびにアクロバットをしているようなイメージが浮かんでしまいました。(笑))宇宙空間では髪の毛は短い方が便利だそうですが、以前、髪の毛が長いまま宇宙飛行をしていた女性飛行士がいたような気がしたけど、この人ははてどうしていたのだろう?と首をひねってしまいました。後は長距離電話で地上とお話をしていたり、メールも使ってるし、iPodを聞きながら寝袋で寝ていたりと、ちょっと雰囲気は違うけど地上にいる時とそんなには違わない生活ができているようです。ちなみに宇宙ステーション滞在中の写真もflickrの写真集にアップロードされていました。今から数年先後にはアンサリさんの後に、どれくらいたくさんの宇宙旅行者が続いているんだろうかと、ブログを読みながらいろいろ想像してしまいました。
2006.09.25
コメント(0)
-
大学生が作った宇宙船「Nova 1」号
ケンブリッジ大の二人の学生さんが、1000ポンド(約20万円)で宇宙船を開発しました~という記事を見て「おおっ!」と思ったので紹介してみます。「宇宙から見たリアルな地球の画像、イギリスの大学生が自作の宇宙船で撮影」この記事のページには宇宙船からデジカメで撮ったきれいな地球の画像も貼付けられていました。記事を読んでもらえれば分かると思いますが、今回開発したのは宇宙船というよりも気球と呼んだ方が実態に近いと思いますが、これで成層圏の高さである高度32Kmの高さまで飛んでいるそうです。成層圏に気球を打ち上げる実験はいろんなところで、普通にやられていると思いますが学生さんが大学の研究室の予算の範囲内で作ってしまうようになったのは、すごいなあと思いました。(ちなみに7月頃にJAXAの宇宙科学研究本部の公開を見学してた時も気球の展示をしてましたが、こちらもすごく面白い!と思いました。)ついでにニュース記事のページからもリンクが張られていますが、以下のページにこの気球から撮った写真が集められていましたので、紹介しておきます。「Nova 1 photo selection」気球から撮った写真を見ると地球が丸く見えていて空は真っ黒に写っていました。これらの写真をじい~っと見てたら、あともう少しで宇宙に手が届きそうな気もしました。今回は気球から低予算で小型ロケットを打ち上げる研究の一環だそうです(ちなみにこの「宇宙船」の名前は「Nova 1」だそうです)が、大学の学生がこういう事を普通にやりはじめているのを見ると宇宙が少しづつ身近なものになってきているんだなあと思えてきて、少しワクワクしてしまいました。
2006.09.22
コメント(0)
-
アンサリ御一行様、宇宙ステーションに到着~
アンサリさんのブログのページを見てたら、宇宙ステーションとのドッキングに成功して、無事到着しました~という書き込みがあって、あれ~?もう着いたのか~と思ってしまいました。たぶんNASATVの実況中継を見ながら本人ではなく別の人の書いていたんだと思いますが、興味深かったので紹介してみます。「Docking Successful」また以下のページにはソユーズ打ち上げのYouTubeの映像が掲載されていましたので紹介してみます。「Soyuz TMA-9 Launch」この打ち上げ映像を見ていたら、手に汗を握るという感じはあまり受けなくて、なんとなくですが、安定した打ち上げだなあという印象を受けてしまいました。また今回は来ておられるかどうか分かりませんが、前回のオルセンさんの出発の時はJTBの宇宙旅行ツアー担当の方がソユーズロケットの出発を見守っていました。以前のブログでも書いたJTBの宇宙旅行の説明会に参加した時に、ソユーズロケット発射の様子を見ていた担当方が出てこられて宇宙旅行ツアーの説明をしてくれたのですが、ソユーズロケットが発射する時のバリバリという音がものすごかったと感想を述べられていました。そしてついしばらく前まで記者会見で話をして人が、ソユーズロケットに乗って宇宙へ出かけていく様子を目の前で見た時にすごく感動したと言っておられたのを、打ち上げの映像を見ていて思い出してしまいました。ついでにJAXAのページにも今回のソユーズ宇宙船のミッションを説明したページがありましたので、こちらも紹介しておきます。こちらは日本語なので読みやすいかもしれません。「国際宇宙ステーションのクルー交代/ソユーズ宇宙船交換ミッション(13S)」ここのページにはフォトライブラリへのリンクがありますが、奇麗に撮った写真が並んでいました。「ソユーズ宇宙船ミッションのフォトライブラリ」こういうページを見ているうちに、私も早く宇宙へ行ってみたいぞと思ってしまいました。
2006.09.20
コメント(0)
-
アンサリさん宇宙ステーションに出発
アンサリさんが宇宙旅行に出かけたようです。アンサリさんのブログを見てたら、ピーターさんという人が実況中継のようなブログ記事を書いていました。これによると、どうやらアンサリさんの乗ったソユーズ宇宙船は無事地球の周回軌道に乗ったようです。またフリッカーの彼女のページには、打ち上げ前の彼女の写真が投稿されていましたので、こちらも紹介してみます。「Space Explorer's photos」こういう情報がほぼリアルタイムで見られるようになったのはすごいなあと感心しながら写真を眺めていました。アンサリさんはこれから宇宙ステーションに向かいますが、宇宙ステーションには約1週間くらい滞在するそうです。去年宇宙ステーションに旅行に行ったオルセンさんの話では、毎日メールが打てたし、家に電話をかけられたので地球上にいるのとほとんど変わりなく過ごせたそうでした。(ただ子供に「パパいまどこにいるの?」と電話で聞かれた時は、う~んと答えに詰まってしまったそうでした。(笑))榎本さんは今回は残念ながら宇宙に行く事はできませんでしたが、こういう旅行が早く普通にできるようになって、ハワイに行くような感覚で「ちょっと宇宙まで行ってきま~す」と言えるようになるといいなあと思ってしまいました。
2006.09.18
コメント(2)
-
光り輝くお洋服
フィリップス社が光る服というのを開発していて、そのプロモーション映像があちこちでインターネットに流されています。このプロモーション映像の雰囲気がなんとなく私の感覚とずれる気がして、見ててすごく愉快に思ったので紹介してみます。「フィリップス社の光る衣料?のプレスリリース」プレスリリースのページにもリンクが張られていますが、YouTubeにプロモーション映像が投稿されていました。あちこちのサイトで紹介されていたので、もうご存知の方も多いかもしれませんが、ついでに紹介してみます。「YouTubeに投稿されたプロモーション映像」私自身も光る物が好きで、ちょっと変わった光るうちわや、光るバッジとかを見ると、気がついたら買ってしまってる事がありますが、映像を見ていて「ここまでやるのか~、う~む」と唸ってしまいました。(笑)そしてさらに最近は人の感情を反映して光るお洋服というのも開発したそうで、そのプレスリリースも出てました。「Philips clothing prototypes light up to reflect the ‘emotions’ of the wearer」この服がどんな風に光るかは、以下のページがわかりやすく並べて紹介してくれていました。「感情によって色が変わる服」パーティーなんかに着ていくとすごく目立ちそうな印象ですが、何かのきっかけで問いつめられたりすると、嘘発見機状態にもなるかもしれないなあとも思いました。(笑)デートをする時なんかにうっかり感情を反映して光る服をなんかを着ていったりすると、ここぞとばかり問いつめられたりして、やや不便な状況になるかもしれませんね。(爆)さて、これは何につかえるのだろう?としばらく考えていましたが、アーティストがパフォーマンスしたり、俳優が演技する時に着るといいかも知れないと思いました。でも毎日演技してて今日はいまいち調子が出んな~という時にバレバレになるかもしれないので、手が抜けなくて大変になるかもしれません。(笑)後は遭難した時の救助用ジャケットや、消防士さん、夜間の道路工事の人(既に別の種類の光る服をつけてる人がいるかな?)あたりかなあと思いましたが、考えてみるといろいろアイデアが浮かんできそうです。何かいいアイデアを思いついた方はフィリップスに連絡してみるといいかもしれません。(連絡先は紹介したフィリップス社のプレスリリースのページに書かれていました。)
2006.09.18
コメント(0)
-
宇宙腰痛
今月に宇宙ステーションに行く予定だった榎本さんが、健康診断で問題が見つかって宇宙旅行が延期になったのは残念でした。その代わり、バックアップクルーとして待機していたアニューシャ・アンサリさんが宇宙ステーション滞在9日間の旅行に参加することになったそうです。。アンサリさんは女性では史上はじめての宇宙旅行者になるそうですが、この事が書かれた記事を見つけましたので紹介してみます。「世界初の女性宇宙旅行者が国際宇宙ステーションへ」アンサリさん自身もすごく魅力的な人物なのですが、今回は別のところに興味が行ってしまいました。今回のアンサリさんが参加する宇宙ステーションの9日間の旅では、いろんな生理学的な実験に参加するそうなのですが、その中に「宇宙での腰痛の調査」の実験に参加するという説明が書いてあったので「ええっ?」と思って驚いてしまいました。この解説記事によれば、宇宙飛行士はよく腰痛を経験しているそうです。(全然知らなかった)普通に考えたら、無重力状態の中にいるので、てっきり腰痛からは解放されるものだと思い込んでしまってました。実際に先月のブログにぎっくり腰の事を書いていた時は、「宇宙クリニック」のようなものを作ったら良さそうだなあと、腰痛に悩まされながら単純に考えていました。でもどうやら宇宙へ行っても特有の「宇宙腰痛」になることがあるという話を読んで、宇宙のクリニックにきて腰痛になったので、なんだかしゃれにもなってないし、つまらんなあと思ってしまいました。(笑)この「宇宙腰痛」の原因はまだよく分かってないらしいですが(だからアンサリさんが自分の体を使って実験する事になってます)、背骨を固定するある筋肉の働きが弱まるからではないかという仮説があるそうです。という事なので、今回の生理学的な実験でどんな事が分かるのか、それとも分からないのか興味津々に思ってしまいました。どうやら無重力の空間では私の知らない不思議な事がいろいろと起こるようです。私自身もまだ腰痛の不安を抱えているので、何か新しい事柄が見つかって、腰痛を解消する手段なんかが考案されたらいいだろうなあと思ってしまいました。ちなみにアンサリさんは9月18日に地球を出発する予定になっているそうです。今回の実験結果は公表されるかどうかは分かりませんが、何らかの成果はでるのか、それとも出ないのかといったあたりも興味津々で見守ってみようと思います。
2006.09.14
コメント(0)
-
地球型惑星の3兄弟
以前に「だんご三兄弟」という歌が流行っていたことがあった気がしますが、私達のいる太陽系の中で金星、地球、火星の3つの岩石の固まりの惑星は、その大きさ、軌道ともまるで三兄弟のように似通っています。実際、三つの惑星が誕生した当初は、どの惑星も水をたたえていた時期があるのではという学説もあって、その環境もかなり似通った星としてスタートしていたのかもしれません。でも金星についてはある時から温室効果の暴走がはじまってしまいました。現在では地表の気圧は90気圧で、地表の温度も約400度という灼熱地獄の惑星になっています。火星についても、昔は水をたたえていたという証拠がたくさん見つかってきましたが、今は砂漠の惑星のように乾いていて、呼吸すらできないくらい薄い大気しかない惑星になっています。一方、現在の地球は、みなさんもご存知の通り現在も豊富な水をたたえた惑星の姿をしています。それぞれ似通った星として、その環境も似通った状態からスタートしたと思われるのに、今では三つの惑星ともそれぞれ性格が全く異なる惑星になる運命を辿っていきました。そして地球自身についても誕生当時は生命の全く住めない死の惑星でした。それから環境の激変を何度も経験して現在の姿になっています。地球が現在の姿になるまでには、灼熱地獄だった時代もあれば、全地球が分厚い氷に覆われた氷の惑星になっていた時代や、大規模な噴火が起こったり、巨大な隕石が空から落ちてくる突発的な破壊的なイベントも何度も経験してきました。また地球上に誕生したと思われる生命自身も、当初の生命にとっての毒ガス(酸素)を全地球的にまき散らして、大量の嫌気性の微生物を死滅させたりする、生物同士のすさまじい生存競争を繰り返してきました。そして地球に生まれた生物達も地球の環境に大きな変化を加え続けてきて結果、現在の姿になったとも言えます。そしてこれまでの長い年月の間、地球は生命を育んで育ててきましたが、そういう生命を育む歴史もあと数億年で終わりを告げるという事も分かってきました。今から数億年後には太陽の輝きは徐々に徐々に強くなり、未来の地球は現在の金星のような灼熱の惑星となっていきます。そして少なくとも地表は生命の住めない惑星になっていきます。(地殻の奥深くに住む微生物達はそうなってもしぶとく生き残りそうですが......。)三兄弟の星がどうしてこのように異なる運命を辿ることになったのか、そして地球自身もどんな環境の変化を経験して、これからどんな変化を経験していくのかについて、ここ十年くらいで急にいろんな事が分かるようになってきました。そして私自身も数年前からこうした地球の歴史や太陽系の歴史にすごく興味をもつようになりました。これから気が向いたらこうした事も時々ブログに書いてみようと思います。ついでなので、太陽系の惑星の姿についてビジュアル的にうまくまとめて紹介してくれているページを紹介しておきます。「JSTバーチャル科学館:惑星の旅」このサイトはよくできてると思いますが結構凝った作りで重いめのサイトなので、速めのブロードバンド回線向きのページかもしれません。操作は最初はちょっとわかりにくいかもしれませんが、試行錯誤でブラウジングしてみて下さい。(笑)
2006.09.13
コメント(0)
-
個人で買えるジェット戦闘機風?飛行機
個人でも買えそうなジェット戦闘機風の飛行機が来年発売予定というニュースを見かけたので紹介してみます。「ジェブリン・ジェット、民間でも購入可能な唯一のジェット戦闘機」アメリカのアビエーション・テクノロジー・グループ社という会社がイスラエルで開発した訓練用のジェット戦闘機をベースに開発してるそうです。ビジネスジェット機として販売するそうですが、見かけもそうだし、元々の機体からしてジェット戦闘機そのものという印象ですね。(笑)ただ戦闘機と言えば当然軍用機なので、今まではたとえお金を持っていても個人で買うことは難しかったかもしれません。(払い下げの中古の軍用機ならあったかもしれませんが......)民間でも新車の状態でこういう飛行機が買えるにようになると聞くと妙にワクワクしてしまいました。現役の軍用機ほどの運動性能はないかもしれませんが、写真で見る限りではジェットエンジンのパワーにものいわせてけっこう振り回せそうな雰囲気も感じたので、遊んでみるのにはちょっと面白い機体かも知れない思ってしまいました。(笑)また上のページで紹介されている写真を見ると、昔のF5Eタイガー戦闘機を現代風に小型化したような印象を受けてしまいましたので、ついでにF5Eの写真も紹介しておきます。「F5Eタイガーの写真集」ちなみにお値段は2500万ドルだそうなので、普通のサラリーマンが今すぐ気軽に買えるという雰囲気ではかも知れません。ちょっと話はずれていくかもしれませんが、こういうのを見ていたら、気軽に乗る飛行機という意味ではライトプレーンあたりがバイク感覚で乗れそうなので、こちらもいいかも知れないと思っているうちに、カタログ風のページを見つけたのでこちらも紹介してみます。「ウルトラライトプレーンのカタログ」
2006.09.08
コメント(2)
-
空飛ぶ自動車の実現を目指す新たな挑戦?
自動車のように走れて、飛行機にもなる乗り物というのは、技術者を引きつけてやまない魅力あるコンセプトのようで、昔から何度も何度も開発のトライが続けられてきました。実際にこれまでも地上は一応走れるし、空中もなんとか飛べるといったレベルの乗り物は開発されていた事はありました。でもそれは「一応」地上を走れるし、「一応」は飛べるというレベルに留まっていて、自動車としても飛行機として見ても性能は中途半端で、実用的な乗り物としての完成度はいまいちだったものが多かったように思います。でもここ最近はいろんな技術が進展してきて、新たな空飛ぶ自動車の試みがここ数年でいくつかはじまってきているようです。最近、Terrafugiaという会社が「Transition」という空飛ぶ自動車を開発しているというニュース記事を見つけましたので紹介してみます。「空飛ぶ車か、路面走行可能な飛行機か--米新興企業がフライトシミュレータを考案」実際の性能は記事の内容だけからは分かりませんでしたが、空を飛んでる時以外はじゃまになるだけの翼はたたんでおくというのは悪くないアイデアかも知れないと思いました。この車兼飛行機の使い方としては、普段は車のガレージに置いておいて、飛行場までは車のように運転していって、飛行場についたら滑走路から飛び立つというイメージを考えているようで、そこそこ堅実な使い方を想定しているのかな?という印象を受けました。こういう空飛ぶ車というのは昔からいろんな映画の中でもガジェットとして登場してきましたし、こういう乗り物ができたら是非とも乗ってみたいと思っている人は今でも多いのかもしれません。日本でもこういう乗り物を開発してみたいと夢を膨らませている人がいて、今住んでいるところにわりと近いところにある岐阜県工業会というところで「ミラクルビークル」という名前の空飛ぶ自動車の開発を数年前にやっていたことがありました。こちらの自動車兼飛行機の開発状況は現在ほとんど話を聞かないので、どうなっているのかよくわかりませんが、以前に見かけた事のあるニュース記事を紹介しておきます。「【レポート】空飛ぶ自動車「ミラクルビークル」(1) 空も飛べて道路も走れる工夫の数々」(ミラクルビークルの開発が現在どうなっているのか知っている方がおられましたが、教えて頂けるとありがたいです。)一方こちらはアメリカの会社になりますが、その名もスカイカーという空飛ぶ自動車を開発している(た?)moller社も結構有名だったと思いますので、こちらも紹介してみます。去年見たニュース記事ではすぐにでも販売しそうな勢いだったような気がするのですが、こちらも現状はどうなっているのかよく分かりません。ちなみにこの会社は私が子供の頃に空飛ぶ円盤形の飛行機を作っていて、子供心にも「うわあ~すごいなあ!」とワクワクしてニュース写真なんかをその当時見ていたような記憶があります。「空飛ぶ円盤形飛行機?XM-4 Skycar」ついでにモレラー社のページには、わりと最新型機に近いM400のホバリングテストの写真が掲載されていましたのでこちらも紹介してみます。「Still Images:Hover Test」垂直離着陸ができるようになれば、離着陸の時以外は長い翼は必要なくなるそうなので、こちらはこちらで良いアイデアなのかもしれませんね。さて、21世紀はこちら乗り物が普及するところまでいくのかどうか、その進展を興味深く見守っていこうと思っています。こういう乗り物が普通に運転できるようになったら楽しいだろうなあ。
2006.09.07
コメント(0)
-
個人用飛行船
以前に書いたブログでパーソナルヘリコプターを開発している日本の会社を紹介したことがありましたが、個人用の飛行船を開発している会社を紹介してみます。飛行船を開発しているのは、アメリカのスカイヨット社という会社で、開発中の飛行船を「the Personal Blimp」(個人用軟式飛行船?)と名付けていました。この会社の飛行船を簡単に紹介してくれている日本語の記事がありましたので以下に紹介してみます。「自家用飛行船スカイヨット」今までは飛行船と聞くとツエッペリンNT号みたいに、ヘリウムガスを入れて浮き上がるタイプを自分の頭の中でイメージしてたんですが、こちらの飛行船は熱した空気で浮力を得るタイプみたいです。(こういう個人用でヘリウムを使うと、ヘリウムの代金だけで結構しそうな気がします。)このスカイヨット社のギャラリーのページには飛行船を膨らませていく様子の写真がありました。それの写真を見てたら、熱気球とかなり似てる気がしました。でもプロペラがついていてて、自力で推進できるので普通の気球と比べると運動性能はかなり良さそうな印象です。ちなみにスカイヨット社のホーページには静かな乗り物だよ~んと紹介されていました。こういう飛行船でスカイヨットという名前の通りの、ヨットを操船する雰囲気でのんびりと空の旅を楽しめると、さぞかし気持ちいいだろうなあと思いました。
2006.08.30
コメント(2)
-
ぎっくり腰
最近、お友達の小町さんのブログで録音のビジネスをはじめた事を紹介して頂いたんですが、つい数日前に講演会の録音の仕事をしてた時に録音機材を詰めたかばんを持ち上げようとした拍子に腰を痛めてしまいました。(爆)新しい自分の仕事をはじめた時にさてどんな事が起こるのかな?....と、わくわくしながら仕事はじめていたのですが、予想もしなかったところから伏兵さんがお出ましになられて、講演会の翌日から二日間くらいはぎっくり腰状態で動けなくなっていました。(笑)それ以降しばらくは強制的にず~っと横になる羽目になったので、溜まっていたSF小説やミステリーやサスペンス物といった小説を一気に何冊が読む事ができてすっきりできたのはよかったのですが、体をちょっと動かそうとすると腰がピキーンと痛くなるのは、やはり面白くないなあと思いました。そこで腰痛を和らげる方法はないかなあと考えているうちに、以前ブログに書いたJTBの宇宙旅行の説明会の事を思い出してきて、無重力空間で腰の治療なんかができたら快適でいいかも知れないなあと思ってしまいました。この時の宇宙旅行の説明会では、宇宙ステーションに1週間滞在してきたオルセンさんの体験談を紹介してくれたのですが、オルセンさんの話では無重力状態での睡眠はすごく快適だったそうでした。それだったら、腰を痛めた人も無重力の状態なら快適に過ごせるかもしれないなあと思って、宇宙クリニックのビジネスを実現するにはどんな事が技術的に実現できればいいのだろうかと、あれこれと考えていました。(笑)そうして考えているうちに、何年か前に宇宙ホテルの構想がいくつか発表されていたのも思い出してきたので、こういう宇宙ホテルの中にテナントとしてクリニックを入れさせてもらえるといいかもしれないなあと思いました。(笑)でも宇宙ホテルに行くためには、今のところロケットを使う事になるので、打ち上げ時にかかるGで余計に腰痛が悪化するかも知れません。(実際、比較的にゆっくり目に打ち上げているスペースシャトルでも3Gがかかっているそうです。)そうなると、これも以前にブログに書いた事のある宇宙エレベータで宇宙まで上がっていくのかいいのかも知れないと思いました。でも無重力状態にずっといると、今度は骨からカルシウムが溶け出していくそうなので、長期間の滞在には向いていないかも知れません。となると、宇宙ホテルの構造物の一部か全部を回転させて人工的に重力を作ってリハビリも兼ねた施設を作った方がいいかも知れないと思いました。という感じで、もう少しいろいろと考えてみようかと思ったところで、ほぼ腰の痛みがとれてきて歩けるようになってきたので、この辺で考えがストップしてしまいました。(笑)強制的に寝る羽目になってるうちに、何かいいアイデアを考えてみようと思ったのですが、もう一歩いいネタが出てこなかったのはちょっとだけ残念でした。(笑)宇宙関係のビジネスは、技術的な実現手段がまだ出そろってないので、今の時点で無理矢理実現しようとすると莫大な費用がかかってしまいます。採算のとれそうな事業は今の時点では限られたものになるかも知れません。という事は逆に誰もまだ誰もビジネスとしてはじめていないという事でもあるので、アイデアだけでも考えてみるいいチャンスなのかも知れないと思いました。ただ宇宙クリニックに関しては、地上でもいいクリニックがたくさんありますのっで、今の時点でたくさんのお金を払ってわざわざ宇宙クリニックに行く必然性は殆どないかも知れません。(笑)でもこういう事を考えのが好きな方で、いいネタを思いつかれた方は、特許だけでもとっておかれても面白いかも知れないと思いました。
2006.08.29
コメント(0)
-
はみごにされた惑星
二日前に国際天文学連合(IAU)の2006年度の総会で惑星の定義を再検討する議論の話をブログに書いていていました。それ以来、さてどんな結論がでてくるんだろう?と半分は野次馬気分で興味津々で議論の様子を眺めていました。その後あっさりかどうかは分かりませんが、定義が決まってしまったようです。「【速報】太陽系の惑星の定義確定」(もっともめるかと思っていたのに......ちょっと残念。(笑))結局、冥王星は惑星の定義からは外されてしまったようで、私達のいる太陽系では、太陽の回りを回る惑星は水金地火木土天海の8惑星とする事に決まったそうです。冥王星は、はみごにされた形になり、第十惑星と言われていた「2003 UB313」と仮の名前を付けられていた天体と会わせて、まぼろしの惑星となり、代わりにdwarf planet(矮小惑星?、どんな訳語になるんだろう?)という名前が付けられることになり、海王星より遠方にあって太陽の周りを回っている天体の1種族に分類されることになりました。冥王星が発見された1930年当時、地球と同じくらいの大きさではないかと想像されていて、当時のSF小説の舞台にもなっていましたが、その後の観測技術の進歩で冥王星は以外と小さくて地球の月の三分の二くらいの大きさしかないことも少しずつ分かってきました。元々冥王星の軌道自体も他の惑星と変わっていることは発見当時から分かっていて、なんだか変だとも言われていましたし、最近の観測技術の進歩でやっぱり冥王星は他の惑星とはちょっと違うんじゃないかという議論が強く言われるようになってきてました。なので、今回の惑星の定義の見直しで、太陽系の天体の分類はほぼすっきりした定義になった気がします。でも未だに冥王星は、ハッブル宇宙望遠鏡で見てもぼんやりとした小さなしみのようにしか見えない、遠くて謎の多い天体でもあります。この冥王星の探査を目的に今年1月「ニューホライズンズ」という惑星探査器が打ち上げられました。これまで打ち上げられた探査機の中でも最も早いスピードで太陽系内を飛んでいますが、それでも冥王星に到着するのは2015年になる予定です。「ニューホライズンズ」、新世界に向けて飛び立つ」dwarf planetとはまだ耳慣れない名称ですが、ネーミングはともかくこうした分類によって私たちの住む太陽系の姿のイメージはまた少しだけ明確になってきたように思えました。そして今回の冥王星の惑星騒ぎを見ているうちに、人類がこれまでに集めていた知識が実際の自然さんの実態とちょっとだけずれていることが分かってきて、自分たちの知識を実態に合わせて書き換えようとしている瞬間をみんなに実況中継して見せてくれているというイメージが浮かんできました。そう言う世界中のみんなが見ていたという意味では、ちょっとしたエポックメイキング的な出来事だったのかも知れないなあとも思いました。と書いているうちに、早速、国立天文台では惑星の定義のQ&Aが書き換えられていましたので紹介してみます。(素早い!!)「国立天文台 「よくある質問」 惑星の定義とは? Q&A」以下には国立天文台の台長である観山さんの談話が掲載されていました。(ムービーで見れるようになってたので、驚いてしまいました。)「惑星の定義」について (映像での解説)」こうして世界中の研究者がお互いに議論を続けながら、ゆっくりと、少しずつ、でも着実に人類の知識を集積し続けるという活動が、サイエンスのいろんな研究分野で日夜行われています。こうした知識の集積活動を通じて、私達は自分達の住んでいる世界がどんな世界なのかも少しずつ明確にしていこうとしているのかも知れないと、ふと思う事があります。そして時々ですが、自分たちがどこからやってきて、これからどこへ向かおうとしているのか、その答えの一部も少しずつ出し始めているのかも知れないなあと、思いを馳せていたりする事もあります。こういうところが、私がサイエンスの活動に心引かれる理由の一つになっているのかも知れません。
2006.08.25
コメント(3)
-
一人乗りヘリコプター!
今年のグッドデザイン賞にノミネートされた作品を展示・デモする「グッドデザイン・プレゼンテーション」が現在東京ビックサイトで開催中です。私のいる会社も最近開発した商品を今回出展しているのですが、それはおいといて(笑)、一人乗りヘリコプターをここに出展している人がいた!!、というニュース記事を読んでおおっ!と驚いてしまいましたので紹介してみます。「自転車感覚で乗れる1人乗りヘリコプター」これは開発したのはゲン・コーポレーションという日本の会社だそうで、この一人乗りヘリコプターは社長の趣味で開発したと記事には紹介されていました。(笑)記事を読んでるうちに日本人でもちゃんとこういうユニークなものを作っている人が探せばちゃんといるんだ~!と、嬉しくなってしまいました。ただ残念ながら航空法だかなんだかの法規制により、高度5m、時速10kmでしか飛べないそうです。(性能的には最大高度1000Km、時速90KmまでOKだそうです。)このヘリコプターは2重反転プロペラを使っていて、125cc 2気筒の水平対向エンジンを4基搭載、レギュラーガソリンで飛ぶ結構本格的で性能も実用レベルに近いもののようです。実際にもう買っちゃってる人がいるそうで、既に4台売れているそうです。ニュース記事には消防のレスキュー隊に使えるんじゃないかというコメントもありましたが、この記事を読まれた方で「こういう用途に使うといいんじゃないかと思いかれた方は、ゲン・コーポレーションに連絡をとってみられるといいかもしれないと思いました。私自身もこういう事を考えるのが大好きなので、使い道のアイデアをちょっくら考えてみようと思います。(笑)ちなみにこの一人乗りのヘリコプターの名前は「GEN H-4」だそうで、少しだけ機体の情報を紹介しておきます。販売価格:360万円 (エンジン単体でも販売しているそうですが、強力なラジコン用エンジンになりそうですね。 ご興味のある方は製品紹介ページを参照して下さい。)販売方式:キット形式で組立てはお客様が行うそうです。 また日本国内での飛行にあたっては航空局の許可が必要だそうです。機体緒元:機体高さ 約2.4m ローター径 4.0m 乾燥重量 約75kg 飛行速度 時速10キロ 最大離陸重量 160kg 図面等は「機体緒元のページ」を参照してみて下さい。 ブレードとエンジンと、機体の操縦法法についても、おおよその説明が記載されています。 以外とコンパクトに作られていて、お手軽そうな印象ですね。気が向いたら買ってみようかと思ってしまいました。(笑)
2006.08.24
コメント(0)
-
若田さん、野口さんの素敵な応援
以前に宇宙旅行ツーアの説明会みたいになってしまったトークショーの事をブログに書いたことがありました。このトーショーの時に、榎本大輔さんという方がロシアの星の街で訓練している様子も紹介されていました。この時説明をしてもらったJTBの宇宙旅行ツアーには宇宙ステーションに1週間滞在するツアーも含まれていて、榎本さんは宇宙ステーションの1週間の滞在ツアーへの参加を目指しています。榎本さんはこのツアーに参加するため半年間ほど星の街で宇宙飛行士と同じような訓練を受けていて、来月の9月にはいよいよ宇宙ステーションに行ける予定でした。でも出発前の健康診断で不合格が出て飛行は延期になり、代わりにアヌーシェ・アンサリさんというバックアップの女性が、こちらも女性の民間人としてははじめて宇宙へ行く事になったそうです。(これはこれで素晴らしい事だと思いました。)榎本さんはさぞかしがっくりきているかと思っていたら、スペースシャトルでもう宇宙に行ったことのある若田さん、野口さんが榎本さんが滞在している星の街のアパートに遊びにきたという記事が榎本さんのブログに書かれていました。簡単な紹介文でしたが、読んでてナイスで素晴らしい応援だと思いました。元気づけられた?榎本さんも「やっぱり諦めないぞ」とブログにも書かれていました前回宇宙旅行のツアーに参加していたオルセンさんも健康診断で不合格が出て飛行が延期になった事がありましたが、それでもあきらめずに1年間後の昨年に再度チャレンジして無事宇宙へ行けたことがありました。彼らは民間の宇宙旅行としてはパイオニアにあたる人たちだと思いますが、今すぐ宇宙に行こうとすると、いくつかの困難を通りぬける必要があるのかも知れません。でも彼らがあきらめずに道を切り開いてくれているおかげで、普通の人が普通に宇宙旅行できる日は少しずつ近づいてきている気がします。私自身も自分が死ぬ前には宇宙へ行きたいと思っている一人ですので、これからもこうした彼ら彼女らを応援していこうと思っています。
2006.08.24
コメント(0)
-
プラネットとプルトン?
最近ニュースでも報道されてますが、現在国際天文学連合(IAU)という天文系の学会の国際的な総会で、今まで曖昧なままだった惑星の定義きっちり定義しようという議論がされているようです。現在提案されている原案はこれまであったプラネットという惑星の用語の他にプルトン(Pluto-like objects:冥王星のような天体という意味?)という天体の分類用語を作ってしまおうというものだそうです。「The IAU draft definition of "planet" and "plutons"」今まで私達のいる太陽系では、太陽を回る天体として水金地火木土天海冥という九つの惑星とその回りを回る衛星、それ以外は小さな岩の固まりような小惑星と、氷の固まりのような彗星が回っているイメージで天体を分類してきました。観測技術がどんどん進歩してくると、惑星と小惑星の中間の大きさの天体もどんどん発見されるようになってきました。こういう新しい天体が発見されるようになって分かってきた事は、人間がどう分類しようと、小さな石ころのような大きさから木星くらいの大きさまでのいろんなサイズの天体はバラエティ豊かに自然に生まれてきているので、それをある大きさ以上の天体を惑星と呼ぼうと決めても、必ずどっちつかずの中間の大きさの天体が存在するということなんじゃないかと、私なんかは勝手に思うようになりました。例えば、冥王星は発見当時は地球と同じくらいの大きさと想像されていましたが、実はそれよりもずっと小さな天体だったという事がだんだん分かってきました。そして冥王星の回りを回るカロンという天体も発見されましたが、これは最初の観測で想像されていたよりも実際は大きな天体らしいという事も分かってきました。どうやら冥王星とカロンは宇宙戦艦ヤマトに出てきたガミラスとイスカンダルのようにお互いの回りの回り合ってる双子の天体に近そうだという事も分かってきました。そうすると双子の兄弟なんだから、冥王星を惑星と呼ぶんなら双子の弟?も惑星と呼ばないと可哀想なんじゃないか(可哀想という表現は私しか言ってないかもしれませんが......(笑))という議論も出てきてるようです。そして冥王星軌道の外側には、冥王星と同じくらいか、ひょっとすると冥王星よりも大きな天体が続々と見つかってきています。こうして話がだんだんとややこしくなってきたので、この際だから惑星の定義をはっきりさせようという事で今回の原案が作られたそうですが、元々はバラエティ豊かに存在している天体のうちあるものを惑星と呼ぼうと人間が勝手に決めようとしてるだけの話なので、今回がんばって定義し直して、それじゃあこういう天体はど~するんだ?という話はたくさん出てきそうな気がします。案の定?、議論は紛糾しているようで(笑)、その様子?が以下に紹介されていました。「「惑星」の定義、国際天文学連合総会での議論続く」それによると冥王星型の天体をプラネットではなくプルトン(なんだそれは?)と呼ぶ事にしようという提案については、反対意見多数でまとまらないそうです。(笑)私個人としては、私達のいる太陽系については「水金地火木土天海冥は惑星だ~!」と言い切ってしまえばもういいじゃ~んと勝手に思ってしまいました。(笑)というのは惑星の定義をはっきりさせる作業は、なんとなくもうサイエンスの話ではなくなってきてるような気がしてて、どちらかと言えば、地球上の海に囲まれた陸地を「島」と呼ぶか「大陸」と呼ぶかという話とほぼ同じレベルの地政学的な話になってきてるんじゃないかという気がします。それに私達のいる太陽系だけでもこれだけ揉めてるんだから、これから見つかってくるかもしれない近隣の恒星を回る「惑星」に至っては、それこそ恒星のサイズからしてまちまちなので、「この天体はどう分類する?」というややこしい天体がさらに続々と見つかってきそうな気がします。もうこの際、太陽系以外の恒星を回る「惑星」がどんどん見つかってきたら、新しい陸地を発見した時にこれを島と呼ぶか大陸と呼ぶかを決めるような雰囲気で、「これは惑星!」と分類していけばそれでいいじゃ~んと勝手に思ってしまいました。(笑)......と思っていたら、「第十惑星」と言われる天体「2003 UB313」を発見したMicheal Brownさんも、「惑星」は冥王星を外して8個でいいじゃ~んと言っているというニュースも出てきました。「2003 UB313発見者、惑星の新定義に異議「第十惑星にならなくてもいい」」この分類は結構すっきりしてる気がします。地球上の陸地のうちこれだけを「五大大陸」と呼ぶ事にしようという分類法に近い気がするので、もうこれでいいのではないかと思いました。でもこういう事を冷静に言ってるMicheal Brownさんも、面白がって言ってる私も、残念ながらIAUの会員ではありません。総会での最終的な結論は8/24に出されるようですが、ニュースのサイトで見るとIAUの方々はヒートアップして熱い議論を戦わせている?ようなイメージを持ってしまいました。(実際にはどんな雰囲気で議論しているかは分かりません。(笑))果たしてIAUで結論が出るのかどうか、そして出るのならどんな結論になるのか興味津々で見守っていようと思います。
2006.08.23
コメント(0)
-
実験室で作るブラックホール?
私達の住む世界はどんな構造になっているだろうという問題は、昔から人を捉えて話さない問題のようです。これまでにいろんな人が、いろんな想像を膨らませて、どうなっているのだろう?と考え続けてきました。私達の住む宇宙や空間はどのような構造になっているのだろうかという研究はたくさんされてきて、我々の住む宇宙はこうなっているかもしれないという仮説もたくさん生まれてきました。でもその仮説を検証するためには今の人間の技術レベルでは生み出せないような膨大なエネルギーを使った実験が必要なので、その殆どは正しいかどうかを検証することができないまま理論的な仮説に留まっていました。ところが最近になってこうした事情が少し変わるかも知れない出来事が起こってきました。現在、2007年夏の実験開始を目指して、ヨーロッパのCERNという研究所でLHC(Large Hadron Collider)というちょ~巨大な加速器の建設が進んでいるのですが、この加速器は膨大なエネギーを生み出すことのできる超巨大な実験装置でもあります。(話は関係ないところに飛びますが、CERNは今皆さんがこのページを見るのに使っているWebブラウザが初めて開発された研究所としても知られています。(1990年の事でした。))LHCは1周が27km(山手線の長さと同じくらい?)の地下トンネルを建設してそのトンネルの中に陽子を通して加速してやる超巨大な実験装置で、これを使うと陽子ビームを7兆電子ボルト(7TeV)のエネルギーまで加速させることができます。ここまで加速させた陽子同士を正面衝突させると、その瞬間に人類が一度も到達したことのなかった膨大なエネルギーが生み出せるようになります。「最極微の世界に迫るLHC計画(1)」そしてたくさんある宇宙論の仮説の中に「膜宇宙(braneworld)」という考え方があるのですが、この仮説からはLHCで生み出すことのできるエネルギーのレベルで、ブラックホールを人工的に製造することとができるかもしれないという結論が導き出されてくるそうです。このブラックホールを作る実験については、Steven B. Giddingsさんの書かれた論文が面白かったので紹介してみます。「Black holes in the lab? 」これはどちらかと言えば論文というよりエッセイに近いようですが、英語の苦手な私でも四苦八苦すればなんとか読めそうな(笑)、面白い文章で書かれていました。この実験室の中で作れるかも知れないブラックホールについてはいろもの物理学者さんという方が、こちらも分かりやすくかつ愉快な文章でうまくまとめて説明してくれているページがありますので、ご紹介しておきます。「実験室のブラックホール」数年前にこの実験室の中でブラックホールを作れるかも知れないというお話をはじめて聞いた時に「なんだと~!!」とそのぶっとびの発想に驚愕したことがありました。どうやら人間はいつのまにかこうした検証ができる手段を持つまでになっていたようです。この実験のお話は日経サイエンスの去年の号にも記事が載っていましたので、こちらも紹介しておきます。「ブラックホールを製造する」これまでブラックホールをネタにしたSF小説はいくつかありましたが、もしこの「LHC」の実験で本当にブラックホールを作る事ができたら、世界中の研究者にすごく大きなインパクトを与える出来事になるかも知れません。今から1年後に開始される予定の実験をわくわくしながら見守っていようと思います。
2006.08.13
コメント(7)
-
目標!、スーパーカミオカンデ、て~!!
ここ十年くらいでサイエンスのたくさんの分野でいろんな研究が急に進みはじめているなあという印象を持つことがあります。高エネルギー物理の分野もその一つかも知れません。この分野でもここ最近いろんな事が分かってきて、そしていろんな新しい発見をしようと次々とユニークな実験装置が作られているようです。その中の一つでこれは面白い!と思った一つの実験がありましたので紹介してみます。「大強度陽子陽子加速器を用いた次期ニュートリノ振動実験計画」これは東海村で建設中の陽子シンクロトロンという大強度の粒子加速からニュートリノビームを発射して、295Km離れた岐阜県神岡町に建設されたスーパーカミオカンデという5万トンの水をたたえたチェレンコフ光検出器にニュートリノを打ち込もうというものでした。このニュートリノビームの発射装置も結構ものものしい雰囲気で、これを見てるうちに、なんだかエバンゲリオンに出てきた粒子加速器を思い出してきてワクワクしてしまいました。(笑)「ニュートリノビームの発射装置の図」カミオカンデは上岡鉱山の跡地の地下に1000mに建設されていて、東海村の発射装置から発射されたニュートリノビームは、直線距離で295Kmの地球の内部を直進していきます。「ニュートリノビームが進む経路の図」ただニュートリノ自体は物質に当たってもほとんど反応しないスカスカの粒子なので、エバンゲリオンに出てきたようば侵略者にビームを当てても実際には効き目はあまりなさそうです。(笑)でもこの実験によって、今までは質量がないかも知れないと言われていた事もあるニュートリノの質量を決定したり、なぜ我々の宇宙には反物質が存在しないのか、そしてなぜ我々の住んでいる宇宙は今のような姿をしているのかといった問題の手がかりが得られるかもしれないそうです。私達が今住んでいるこの世界はどのようにして出来上がったのか?、そして私達は今どのような世界に住んでいて、私達の住んでいる世界はこれからどのように変化していくのか?、といった疑問は大昔からいろんな人が考えていた根本的な問題の一つかもしれません。こうした実験がいろんな形で行われるようになって、問題と取り組める手がかりとなるデータが少しずつ集まってくると、こうした根本的な問題にも少しずつ答えが見えはじめてくるのかもしれません。この実験は2009年からはじめるようなので、結果が出るのはまだ少し先になるようだし、どんな結果が出るかも分かりませんが、今からわくわくしながら見守っていこうと思います。
2006.08.11
コメント(0)
-
ドイツから新型機のグライダーが到着~!
2年くらい前からドイツに注文していた新型グライダーが先月日本に到着しました!!。ご近所にグライダーのクラブ(大野グライダークラブ)があってここのクラブのメンバーになっているのですが、このクラブではほぼ毎週週末に河川敷でグライダーを飛ばしています。このクラブのメンバーが2年前にシンジケートを結成して新車のグライダーを購入する事になりました。(私を含めてサラリーマンの人が多くて一人では買えないので共同購入という形をとりました。)グライダーを注文した先はドイツのシュンプヒルト社というグライダーを作っている会社です。今回購入したのはDUO-DISCUS xTという新型の機体で、グライダーの胴体の中にプロペラを収納できる結構凝って機構がついていて、それでいて美しい機体です。私はカタログの写真を見ただけでしびれてしまいました。(笑)「DUO-DISCUS xTのカタログ」また昨年の9月頃にはグライダークラブのメンバーが何人かシュンプヒルト社へ買い付け旅行?に行ってきてて、この時のクラブのメンバーが書いた旅行記を見直してみたら、ああ楽しそうだなあ、いいないいなと思ってしまいました。「ドイツ旅行記」現在、注文した機体は日本に無事到着して、埼玉?の大利根飛行場においてあるそうです。ご近所のグライダークラブのブログに日本に到着した機体の写真を最近載せてくれていて、その写真を見てるだけでもワクワクしてきてしまいまあした。「大野日記」とはいうものの、実を言うと操縦練習の方はずっとご無沙汰の状態で、今年はもう半分をすぎたというのにまだ一回も空を飛んでいません。(笑)しかも今の私の操縦の技量は水平飛行をしてゆっくり旋回をするだけでもいっぱいいっぱい(爆)という状態なので、もうすぐ新型の高性能の新しい機体も入ってくることだし、そろそろ操縦の練習も再開して、自由に大空を飛べるようになりたいなあと思っています。でも今は死にそうに暑いので、練習を再開するのはもう少し涼しくなる秋頃あたりからかな?...........(笑)新しい機体がクラブに到着する日を今から楽しみにしてます。
2006.08.04
コメント(0)
-

ISASの研究所公開写真その2
前回に引き続き宇宙科学研究本部(ISAS)の研究所公開の写真を掲載してみます。ソーラーセイルの展示太陽からの風を受けて航行するソーラーセイルの展示がありました。天井から垂れ下がっている銀色の布みたいなものがソーラーセイルの素材です。いかにも手作りという雰囲気の展示を見てたら、どこかのバザールか大売り出しの光景みたいに見えてきました。ソーラーセイルの後ろには太陽発電衛星の大売り出しの垂れ幕もあるし(ちょっと違う?(笑))将来宇宙旅行が一般的になったらソーラーセイルの帆も、どこかのホームセンターの大売り出しで売られるようになるんだろうか?と一瞬思ってしまいました。LUNA-Aのペネトレーターの展示月面に打ち込むペネトレーターの展示がありました。LUNA-Aは宇宙から月面に地震計を打ち込み、月の地震を観測して、月がどうしてできたのかという謎を解こうという野心的な探査計画です。でも宇宙から月面にこのペネトレーターを打ち込む時に1万GというすごいGが発生するので、中の観測機器がそれに耐えられるようにするための開発が大変なようです。赤外線カメラのデモ展示なんだかSF映画「プレデター」に出演してた宇宙人さんが見てた光景みたいですね。自分の腕をカメラの前にかざすと腕の中の血管がはっきりと透けて見えたので、俺の腕は血管が浮いてるのか~と思ってしまいました。(写真に写っているのは別の人の腕です。(念の為))衛星管制室の展示衛星管制室を模擬した部屋が作ってあって、管制室のモニタの前で記念写真を撮るサービスがありました。ちょうど親子が記念写真を撮っていて、子供がなかなかかわいいと思いました。(天才少年用に、子供用の制服があるのかと一瞬思ってしまいました。(笑))垂直に離着陸ができるロケットの展示サンダーバード1号みたいに垂直に離着陸するロケットが展示されていました。この展示を見てるうちに、これをそのまま発展させていくと弾道飛行できる観光用宇宙船ができるかな?と思ってしまいました。そしてよく見ると既に乗客が乗っていました。人工衛星の表面に貼付ける保護膜?の展示人工衛星の表面には金色に光るアルミ箔のようなものが張られていますが、どうしてあんな色に見えるのかを教えてもらいました。今まではてっきり高級そうに見えるので金色の膜を貼付けてるんだと思っていました。(笑)宇宙蚕の展示狭い宇宙空間で食料を自給自足する宇宙農業の研究でカイコを飼う宇宙農業の研究をしてるそうでした。佃煮にするとおいしいそうで、見学者に食べさせていました。(笑)それじゃあ蚕の糸を使えば宇宙で服も作れますよね~と冗談で言おうとしたら、隣で本当に糸をつくる展示をしてたので驚いてしまいました。
2006.08.04
コメント(0)
-

ISASの研究所公開
JAXAの宇宙科学研究本部(ISAS)の研究所公開日に見学をしてきました。土曜日だけの公開だったのですが、その日の見学者は19000人いたそうです。(どうりでたくさんの人がいたと思った。)こういうのを好きな人は以外と多いのかもしれませんね。楽しかったのでその時に撮った写真の一部を掲載してみます。まずは現在地球に帰還させようと奮闘中の惑星探査機「はやぶさ」の実物大模型?。小さい衛星と思っていたけど実物は結構大きかったんですね。「はやぶさ」が着陸した小惑星「イトカワ」の模型の展示よ~く見ると小惑星の表面に小さな「はやぶさ」さんが........見えないかな?。私の名前も刻まれたターゲットマーカーの模型。本物のターゲットマーカーは小惑星「イトカワ」の表面にそっと置かれてました。気球の展示コーナーでは気球の材料を使って風船を作ってくれる?サービスがありました。よくみると会場のあちこちに風船を抱えた人々が........うっかり手を離すと、あらら~..........こんな宇宙生物が登場する特撮映画が昔あったような気が.....他にも写真をいくつか撮りましたが、続きはまた次回のお楽しみ。
2006.08.03
コメント(0)
-
M-Vロケットの後継
先週、M-Vロケットの運用終了というニュース記事を見て、あらら~と思ってしまった事がありました。「JAXA、M-V後継の次期固体ロケットについて説明」M-Vロケットは固体燃料ロケットとしては、たぶん世界で最もすぐれた性能のロケットで、かつ他ではどこも開発していないタイプのすごくユニークな存在だったと思います。また、このロケットがあったので、科学衛星打ち上げの分野では前人未到の成果を出し続けることができて、世界中の宇宙開発の関係者からも一目置かれる存在になっていたと思います。ニュース記事を見てると、今後は大中小の3つのタイプのロケットを開発していくそうですが、個体ロケットはこれから需要が増える?小型衛星の打ち上げに用に開発をしていくと書かれていました。でも中型のロケットはまだ開発中で姿を表していないし、小型衛星の需要はあるのかどうかはっきりしないし、その手の衛星はずっと小型のロケットでお手軽に打ち上げてしまいそうな気もするので、さてどうなのかなあと思いました。市場に需要があるのかどうか分からないリスクのある技術の開発は私もやってきた経験がありますが、この手の開発の方向性を考える人は、プロフェッショナルマネージャとしての経営能力とクリエイティブに考える力を総動員して考える状況になりそうな気がします。現場の研究者や技術者達が長い間辛抱強くがんばって育ててきてくれてたおかげで、現在いる場所までたどり着いた技術が、これからどう展開されていくのか、見守っていこうと思います。
2006.08.02
コメント(0)
-
水面に浮かぶ文字/空中に浮かぶ絵の表示装置
ニュースのページでいろんな新製品紹介の記事を見ていたら、面白い二つの表示装置の記事が最近目に止まりました。そのうちの一つは円形の水槽の水面を波立たせて、文字や絵を浮かべる表示装置の記事でした。「水面に絵・文字くっきり ホテルなどに売り込み 三井造船と大阪大」(ヤフーのニュース記事に出ていましたので、見られた方も多いかもしれません)ニュース記事と写真を見てる限りでは定常的に水面上にずっと固定した形を浮かび上がらせ続けるのは難しそうな気がしましたが(もしそれができたらすごい!!)、水面上に指定した文字や絵の形を自由に浮かび上がらせることができるそうです。元々この水槽はアメーバ水槽と呼ばれていて、自然の海で発生している波の形を自在に再現して、船舶や海上の構造物にどのような力がかかったりするのかを研究する目的で開発していたらしいです。「大阪大学で開発したアメーバ水槽の紹介ページ」この水槽の技術を元に三井造船昭島研究所では、いろんな文字や絵を水面上に再現できるよう、大学と共同で開発したのが今回発表された水槽らしいです。昭島研究所のページにあったPDF資料には、実際のサンプルル画像がいくつか掲載されていました。いろんな表示例のの画像を見ていたら「おおっ!、こんな事ができるのか」と驚いてしまいました。もう一つ、やはり「おおっ!」と驚いてしまった表示装置は、何もない空中に画像を表示させるディスプレイでした。YouTubeに分かりやすくてすごく面白い表示装置紹介のデモ映像が投稿されていました。デモ映像の中には映画スターウォーズで、レイア姫の画像が空中に浮かび上がって表意されるシーンが挿入されていて、そのイメージに重ね合わせる形で製品紹介のデモ映像が表意されていて、未来的なイメージを醸し出していた気がします。この表示装置を開発したのはIO2Technology社というベンチャー会社?のようです。この装置の表示原理は分かりませんが、でも映像を見ていたら薄い空気の流れを作ってそこにスモークマシン作ったスモークを流して、そこにプロジェクターから映像を投影してのかなといった事を勝手に想像してしまいました。私自身もこういうのは大好きで、一見何に使えるのかはっきりとは分からなくても「こういう原理をこう応用すると、こういう事をできそうだ」と分かった時点で、それを実現するために一生懸命作り込んでしまった気持ちは、すごくよく分かるような気がしました。日本の大学や会社の研究所でも、基礎的な成果としての開発したプロダクトレベルでは、これらの製品のようにすごく面白くてユニークなものが結構あると思います。(実際にたくさん見てきました)でもこれまでの経験では、その大半は世に出る前に消えて無くなってしまっていたなあという気がします。さらにそれが商品という形になった後も、それが世に広まっていくには、また別のハードルをたくさん超えていく必要があります。私が研究所にいる時にはあまり気がついてなかったんですが、ここ数年ビジネスのお勉強をしていると、そうしたハードルの数々がだんだんと見えてきた気がしました。私の過去の経験でも相談を受けた段階で、既に製品化が終わって商品の形になってしまっていて、その前の企画の段階で相談してくれてば...... と唸ってしまったケースもありました。今回紹介した製品については、結構気合いを入れてよく作り込んである印象で、発送がユニークな製品のような気がしました。これからこれらの製品がどんな展開をされていくのか、興味津々で見守っていこうと思っています。
2006.07.26
コメント(0)
-
自分の分身(ドッペルゲンガー)がもし目の前に現れたら!
小さい頃に、どらえもんの主人公であるのび太くんが体験したように、ある日突然目の前に自分の分身のようなものが現れたどんな気部になるのかなあと想像していたことがありました。アンドロイドロボットの研究をしている大阪大学の石黒さんという研究者の方がいるのですが、その方が自分自身の見かけそっくりに作って、しかも自分の動までそのままコピーして、いわば自分の分身(ドッペルゲンガー)のようなロボット「ジェミノイド」(HI-1)を開発されました。数日前にそのコピーロボットのデモを紹介するニュースのページを見ていたら、これがすごく印象的に思えたので書いてみます。この記事の中にはジェミノイドのデモ映像があったのですが、その映像をみた瞬間に「おおっ!」と驚きながら見入ってしまいました。この映像を眺めているうちに、子供の頃に想像していた事のあるのび太くんの思い出が浮かんできました。以下にデモの映像を紹介してみます。「自分の分身(ジェミノイド)と並んで喋っている石黒さん」(画面左下の「【動画】」と書かれているリンクをクリックすると動画の映像を見る事ができます。)「ジェミノイドが口パクで喋っているアップの画像」(同じく「動画」リンクをクリックしてみて下さい。なんとなく不気味なようでいて、でも不思議な存在感を感じてしまいました。)「操作していない間も動き続けているジェミノイドの映像」(やはり画面左下の「動画」ボタンをクリックしてみて下さい)一見して分かる通り、石黒さんの開発されたジェミノイドはご本人の動作をそのままコピーしているそうですが、ややぎこちないものの、普通の作り物のロボットでは今まで感じたことのなかった不思議な存在感を感じてしまいました。実際にジェミノイドを開発した石黒さんも、ロボットを操作していると自分がそのロボットになったように感じるとコメントされていたそうです。この映像を見ていたら、いろんな想像があれこれと浮かんできて、将来、多くの人がジェミノイドというドッペルゲンガーを持つのが普通になってしまった時代がもしやってきたとしたら、その時には世の中の光景あどんな風に変化するのだろうかと思ってしまいました。最初に頭にうかんだのはダブルブッキングしてしまったり、自分がいきたくないところには、ドッペルゲンガーを行かせたりするようになるかもしれないという想像でした。例えば会社に行きたくない人はドッペルゲンガーに会社に出勤させたり、逆に家庭にドッペルゲンガーを置いておいたり、留守番をさせたりするようになるのかなあ?、またはドッペルゲンガー同士で半分バーチャルにデートしたりするようになると、どんな光景になるんだろうとか想像してしまいました。(笑)それ以外に、病気や事故で歩けなくなってしまった人たちが、自分の代わりにこうしたドッペルゲンガーに世界旅行に出かけてもらったり、ドッペルゲンガーを通して外の世界とコミュニケーションをとったしたり、生身の身体で行くと危険な場所にドッペルゲンガーに冒険をさせたりするかも知れないなあと想像が浮かんできました。ひょっとするとドッペルゲンガーばっかりのパックツアーなんかができると愉快かも知れないと想像してしまいました。(笑)ここではあえて書きませんが、これ以外にも山ほどややこしい話がでてきそうな気がしました。だんだん想像していくと、思考が明後日の方向に飛んでいくような気がしますのでこの辺でやめておきますが(笑)、ドッペルゲンガーのいる風景が日常の見慣れた光景になってしまった時に、人々はどんな形態のコミュニケーションをとるようになるのだろう?......と、いろいろな想像をしてしまいました。誰かこういう世界を舞台にSFか何かの物語を書いてくれないかなあと思いました。(もしそういう物語りを書かれる方がおられましたら、アイデアのネタ出しには喜んで協力させて頂きます。(笑))
2006.07.25
コメント(0)
-
地球よりも大きな二つの大渦巻きが並んだ!
先月に木星の大赤班と中赤班の二つの大渦巻きが接近している事を書きましたが、今月に入っていよいよ二つの大渦巻きが接近して並びはじめました。二つの渦が近づいた時に、お互いに引き寄せ合って合体するような一大スペクタルなイベントが起こらないかなあと、実はちょっとだけ期待していたのですが、今回は二つの渦はそのまま何事もなく通り過ぎそうな感じです。(やや残念(笑))という事で二つの渦巻きが並んでいる様子がよくわかりそうな画像を時々探していたのですが、ジェミニ望遠鏡のサイトに接近の様子が分かりやすい画像が掲載されていました。「大赤班と中赤班が接近している様子の画像」この画像をじ~っと眺めながらあれこれと想像していると、木星の間近に出かけていって、側で見てたらさぞかし不気味な光景に見えるだろうなあ~と思えてきました。(地球よりでかい大渦巻きというのがどんな風に見えるものなのか、一度近くで見てみたい気がしています。)皆既日食が起こる時に皆既日食の見える場所に出かけていって見学する観光ツアーが今でもありますが、気軽に宇宙に行けるような時代がきた時は、こういうイベントが太陽系の中で起こったりすると、同じように木星の大渦巻きを見に出かける観光ツアーのようなものが流行るかもしれないなあと思いました。地球に接近する彗星なんかが現れた時に、彗星を間近で見学するようなツアーをやったり、さらに気軽に太陽系内を旅行して回れるようになったら、土星の輪を間近で見るツアーみたいなものが流行るようになると、楽しそうだなあとあれこれ想像してしまいました。ちなみにジェミニ望遠鏡の画像については、以下のアストロアーツのニュース記事が日本語で読みやすい解説になってるかもしれません。「対等さをアピール?木星の中赤斑、大赤斑に並ぶ」実は今回は、上のニュースサイトの記事を見てはじめて、ジェミニ望遠鏡のサイトに木星の大赤班と中赤班の接近した画像が掲載されている事を知りました。こういうニュースサイトは面白そうなイベントを分かりやすく解説してくれているので、お手軽でちょうどいいのかもしれません。ちなみにこの画像を撮影したジェミニ望遠鏡はハワイにある日本のすばる望遠鏡とほぼ同じ口径8mの望遠鏡で、北アメリカと南アメリカに全く同じ構成の望遠鏡が2台設置されています。これがジェミニ(双子)望遠鏡の由来にもなっているそうです。
2006.07.23
コメント(0)
-
宇宙エレベータ(軌道エレベータ)を実現しようとしてる人たち
ふと見に行ったRobinさんという人のブログに宇宙エレベータの本が紹介されていたので、宇宙エレベータの事を書いてみます。私が宇宙エレベータのイメージをはじめてリアルに思い描くようになったのは、学生の頃に読んだアーサーCクラークさんの「楽園の泉」というSF小説の本がきっかけでした。(同じ頃にチャールズシェフィールドさんも同じようなネタでSF小説を書いていて、当時それも読んでいたはずですが、こちらは何故かあまり記憶に残っていませんでした。)しばらく前に風の谷のナウシカで出てきたメーベを作ろうとしてる人の事を書いた事がありましたが、こういう人が世の中に本当にいると知った時は驚いた事がありました。飛行機や宇宙を飛ぶロケットもそうなのかもしれませんが、ある魅力的な概念やイメージを提示された時に、これを実際に実現してみたいと真剣に考えて、実現するまではあきらめない人たちどこからか必ず現れてくるようです。宇宙エレベータもその魅力的な概念もその一つかも知れないなあと思う事があります。実際に何十年も前からこれを実現するためにはどうしたらいいかを真剣に考えている人たちが世界中にいました。でも今までは軽くて強度のある素材が見つからなかったので、技術的に実現する目処が全く立っていませんでした。(実現するためには10万キロの長さのエレベータを建設する必要があって、それだけの長いと大抵の素材では強度が足りなくて、自分自身の重みに耐えきれずにケーブルが切れてしまうためです。)学生の頃からサイエンス系の雑誌を時々読んできましたが、軽くて強度のある材料が見つかると、たまに宇宙エレベータの建設材料として使えそうかどうかといったネタの記事あったような気がしますが、残念ながら今までは十分な強度のある素材が見つかっていませんでした。ところがここここ十年くらいの間に突然にカーボンナノチューブという素材が見つかりました。まだ大きな素材を作る技術は存在してませんが、こういう材料をずっと探していた宇宙エレベータ屋さん達は、急に活気づいてきてカーボンナノチューブの素材を使った実現イメージを考えはじめるようになりました。以前に私が勝手に想像していた宇宙エレベータのイメージは、バベルの塔をずっと細長くしたような巨大で大規模なイメージでしたが、ここ数年の間に最近出てきたカーボンナノチューブを使った宇宙エレベータ実現イメージは、宇宙から幅1mくらいのリボンを垂らして、そのリボンをローラーで両側から挟みこんで昇っていくシンプルなものでした。このイメージを見た時に、今まで自分が持っていた重厚長大な宇宙エレベータのイメージがすっかりひっくり返ってしまってずっこけそうになりましたが、私の頭の中で「そうか、こうやって実現していくんだ」という、より現実的なイメージに置き換わってしまいました。ここまで具体的な実現イメージが出来上がってくると、真剣に考える人たちがどんどん増えてきます。実際にNASAではスペースエレベータを実現した人に賞金を出すようになってきて、宇宙エレベータを開発するリフトポート社という会社まで設立されてしまいました。「スペースポート社のページ」(会社の名前がナイスですね)ちなみにこの会社のページにはアドバルーンからつり下げたリボンを登らせるデモの画像も紹介されています。そして去年は、第一回の宇宙エレベータコンテストが開催されました。「第一回宇宙エレベータコンテストのニュース記事」今はまだささかやかな規模のコンテストのようですが、これから少しずつ大規模なものに変わっていくんだろうなあと思います。ずっと昔から鳥のように飛んでみたいと思って試行錯誤していた人間がとうとう空を飛ぶ飛行機を作ってしまったように、宇宙エレベータもそうした実現への道のりを、現実的なステップで歩みはじめたのかも知れないと思いました。
2006.07.22
コメント(0)
-

深海魚展を見に行ってきました
千葉県立中央博物館というところで深海魚展をやっていましたので、恐竜博に引き続いて見に行っていました。しんかい6500の窓から見える生物達はどんな世界なんだろう?と思ってわくわくして生きましたが、変な生き物がいっぱい展示されていました。実を言うと深海魚の世界は実はあんまりよく知らなかったりするので、撮ってきた写真の一部だけ紹介してみます。(笑)でかい深海魚がいっぱい展示されていました。わけわからないサカナさんもいっぱい展示されていました。こちらはまるでエイリアンみたいな風貌をしたサカナさん。小さいからまだいいものの、こんなのが潜水艇の窓の外にいたらさぞかし怖いだろうなあと思いました。これはでかいダイオウイカの展示です。昔どこかの海岸で打ち上げられていたものをレプリカにしたものだそうです。泳いでいる時にこんなのに遭遇したら怖いだろうなあと思いました。(思考が現実化してしまうと怖いので、ありありとそのシーンを想像してみるのは止めておくことにしました。)こちらは足の方から眺めたダイオウイカさんの勇姿です。これはおまけの写真ですが、恐怖のダイオウイカさんの側で大胆にも昼寝をしている方がおられました。昔のモンスター映画でよくあったシーンではこういう人が最初の犠牲者になっていたような気が......。
2006.07.18
コメント(0)
-

恐竜博を見てきました
最近は運動不足気味という事もあって、散歩を兼ねて恐竜博というイベントの展示を見てきました。毎年やっているイベントらしいですが、以前から見てみたいと思っていたスーパーサウルスという全長33mの骨格をはじめて間近で見る事ができました。子供に返ったような気分で「でけ~!」と言いながら、ワクワクしながら見入ってしまいました。こちらがスーパーサウルスの骨格の展示です。でかすぎてこの角度からでは全身が入らなかったので、胴体から後ろの方を撮っています。(笑)後ろの垂れ幕には骨格から復元したスーパーサウルスの在りし日の想像図が描かれています。こちらは頭の部分です。スーパーサウルスの頭蓋骨が見入っているのは、頭の部分を復元したCG映像の姿です。この映像も結構迫力がありました。ちなみにスーパーサウルスはまだ一部の骨しか見つかってないそうですが、どれでも岩の中から骨を取り出してクリーニングするのに6年かかっているそうでした。こいつらがのっしのっしと歩いていた当時の地球はどんな風景だったんだろうと想像していました。ついでに、こちらは会場で売っていたスーパーサウルスシュークリームこちらはスーパーサウルス葛饅頭なかなかやるなあと思いました。(笑)
2006.07.17
コメント(0)
-

「日本沈没」を見てきました
2ヶ月前のJAMSTECの研究所公開の時に、リメーク版の「日本沈没」の映画を監督した樋口さんと田所博士(ではなくて平さんという研究者の方)のトークショーを聞いていた事がありました。この時のトークショーで樋口さんが、映画にかける思いや撮影の裏話なんかを、平さんと楽しくやりとりをしている様子を見ていて、この映画に興味をもってしまいました。「トークショーの感想ブログ」今日(7/15)はこの「日本沈没」の映画の公開日だったのをふと思い出して映画を見に行ってきました。映画自体は映像もドラマの部分もよく出来ている印象で、涙がほろりと出てくるシーンもいくつかあって、良い映画になっているのではないかと思いました。そして日本が沈没するメカニズムもけっこうそれらくしく説明されていました。ネタバレになりますので、ここでは説明はしませんが「その手で来たか~、なるほど~」と、思いながら興味深く見ていました。ちなみにこの日本が沈没するメカニズムは平さんが案をいくつか考えて、樋口さんにメールで送ったら「それはいいですね~」と採用になったたそうでした。この映画の中に登場するJAMSTECの深海潜水艇の格納庫や、わだつみ2000、わだつみ6500も実物を、研究所公開の時にそばで見ていたので、興味深く眺めていることができました。この映画を見ていたら、しんかい6500で深海に潜ってみたいなあと思いました。ついでなのでJAMSTEC見学の時に撮っていた写真の一部を紹介してみます。しんかい6500(映画ではわだつみ6500で登場)の写真です。しんかい2000(映画ではわだつみ2000で登場)の写真です。どちらの潜水艇も、映画ではある重要な役割をしています。ついでに先ほどJAMSTECのページに見に行ってたら、映画の撮影協力のページがありました。他のJAMSTECのページと少し雰囲気が違っていたので、ちょっと愉快に感じました。「JAMSTEC、映画「日本沈没」の撮影に協力」「日本沈没」試写会の時の舞台挨拶のレポートもこちらのページに出ていました。試写会の雰囲気がなんとなく伺えて楽しいレポートに思えたので紹介しておきます。「七夕親子試写会」
2006.07.15
コメント(0)
-
経営者とラボの関係(存在意義)
社会人になってはじめての仕事は、企業の研究所で研究員として働く仕事でした。当時配属された会社の研究所はいろんな分野(情報系、半導体、ロボット等の機械系、AV関連等)の研究室が一つの建物に入っていて、比較的こじんまりとした研究所ではありましたが、私にとってはおもちゃ箱の中にいるようなすごく楽しい環境でもありました。その研究所も今では全く形を変えてしまい、その会社自体も今は離れてしまっていますが、企業にとっての研究所はどういう形が理想型だったんだろうと、今でもふと考える事があります。たまたまCNET Japanというニュースサイトで、ニュース記事を読んでいたら「技術と事業を結びつける鍵--「ラボ」の存在意義を検証する」という内容のレポート記事がありました。この記事がふと目に留まりましたので、トラックバックの練習も兼ねて書いてみます。(うまくできるかな?)この記事は5月に開催されたNew Industry Leaders Summit(NILS)で「LAB(ラボ)-新しいR&Dマネジメントの考察」と題したセッションの開催された時のレポートでしたそのセッションでは、インターネット技術を駆使してビジネスを展開する3社の代表が技術戦略を語っていたそうで、レポート記事を読んでいると、経営幹部と技術者との間の距離がすごく近い印象を受けました。セッションに出ていたのはインターネットの技術を元に事業を展開している会社ばかり(楽天、NTTレゾナント、サイボウズ・ラボ、ECナビ)だったので、なおさらそうなんだろうと思うのですが、私が以前にいた環境とは少し違っている印象でした。これまでの自分の経験から、技術を主体にする会社の経営者は技術の詳細は分からなくても構いませんが、技術の本質的な部分は理解している必要があって、さらにその上に経営のプロとしての部分を厳しく試されるんだなと思うようになってきました。シリコンバレーでは新しい技術を元に起業する会社がたくさんあって、それを支援するベンチャーキャピタルの環境も整っていますが、それでもその多くの会社は途中で消えていくのを観察してきました。今まで世の中になかった技術を持って、自分たちで市場を作って(または見つけて)事業を成功させて、それを世の中に広めていくのは並大抵の事ではなくて、それに至るまでに存在するたくさんのギャップを乗り越えていく必要があります。(このテーマだけにしぼった本も存在するくらいです。)会社の将来をその技術の事業展開にかけて経営をしていこうとすると、世の中の流れを見通す力、その技術の将来性を信じる力、事業化やマーケティングセンス、優秀な様々な分野の人を集めてくる力や人間的な魅力といった、経営者としての自分自身の能力を総動員していく必要があるんだと思います。でもそうした側面は経営者や企業家としての醍醐味の部分でもあるのかも知れないと思っています。これまでもたくさんの技術が生まれては消えて、あるものは広まっていく姿を見てきましたが、これからも誰がどんな形でどんな技術を世の中に出して、誰がそれを広めていくのか、これからも展開されていくたくさんのストーリーを見守っていこうと思います。
2006.07.14
コメント(0)
全91件 (91件中 1-50件目)