PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(11)Interior
(35)Travel
(91)Travel(ベトナム)
(41)Travel(フランス)
(65)Travel(ハワイ・NY)
(36)Travel(タイ)
(82)Travel (イタリア&シチリア)
(47)Travel(チェコ)
(11)Travel (インドネシア、バリ)
(18)Travel(日本)
(38)Travel(日本、九州)
(39)Travel(日本、中国地方)
(30)Gourmet (Asian)
(10)Gourmet (Japanese)
(11)Gourmet (European)
(23)Gourmet (Sweets)
(71)Gourmet (Curry)
(18)Gourmet (Others)
(7)Gourmet(荻窪)
(13)Gourmet & Shop (西荻窪)
(8)Gourmet(阿佐ヶ谷)
(3)Gourmet & Shop (吉祥寺)
(6)Recipe
(6)Essay
(137)Movie
(158)Movie(フランソワ・トリュフォー)
(3)Movie(ジャン・ピエール・メルヴィル)
(3)Movie (アンドレ・ユヌベル)
(4)Movie(フェデリコ・フェリーニ)
(10)Movie(エットレ・スコラ)
(1)Movie(ドミニク・サンダ)
(3)Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)
(1)Movie(ルキーノ・ヴィスコンティ)
(4)Movie(ジュード・ロウ)
(12)Art (ジャン・コクトー&ジャン・マレー)
(12)Art(オペラ・バレエ・ミュージカル関連)
(6)Figure Skating
(26)Figure Skating(2008-2009)
(90)Figure Skating(2009-2010)
(49)Figure Skating(2010-2011)
(71)Figure Skating(2011-2012)
(1)Figure Skating(2013-2014)
(21)販売書籍のご案内
(1)Figure Skating(2014-2015)
(28)Figure Skating(2015-2016)
(8)フィギュアスケート(2016-2017)
(4)Travel(日本、関東)
(7)フィギュアスケート(2017-2018)
(12)Figure Skating(2018-2019)
(6)Figure Skating(2020-2021)
(3)Figure Skating(2021-2022)
(10)猫
(5)Figure Skating (2023-
(4)手塚治虫
(49)購入履歴
【楽天ブックスならいつでも送料無料】最新!自動車エンジン技術がわかる本 [ 畑村耕一 ]
★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん
★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌
★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ
★西川 羽毛布団 シングル 綿100% 掛け布団 フランス産ホワイトダウン90% 東京西川 日本製 増量1.3kg羽毛布団 西川 シングル 東京西川 あったか増量1.3kg フランス産ホワイトダウン90% DP400 綿100%側生地 日本製 リビング 冬用 厚手 暖か 掛布団 掛け布団 ふとん シングルロングサイズ ぶとん
★羽毛肌布団 肌掛け布団 西川 イギリス産ダウン85% 0.3kg 綿100%生地 洗える シングル 西川20日限定★P10★ 羽毛肌掛け布団 ダウンケット シングル 東京 西川 洗える 羽毛布団 夏用 イギリス産ホワイトダウン85% ふんわり『0.3kg』 側生地 綿100% 日本製 肌掛けふとん バイオアップ加工 ウォッシャブル 薄手 薄い 肌
★羊毛 寝心地抜群!ボリューム厚い!いい寝心地DX!西川の敷布団 シングル 巻綿ウール100%で暖かい!さぁ!春活★最大5000円クーポン [古布団回収特典付] 敷布団 シングル 西川 羊毛 敷き布団 ボリュームデラックス 厚みしっかり 硬め 暖かい羊毛100% 巻綿 ウール100% 防ダニ 抗菌 綿100% 日本製 ふとん 東京西川 リビング シングルロングサイズ
カテゴリ: Movie
『Le Bossu(直訳はせむし男)』はポール・フェヴァル原作のルイ王朝華やかな時代の騎士道物語。フランスでは非常に人気があり、何度も映画化、テレビ化されている。映画での主だった作品としては、以下の3本がある。邦題は公開当時の時代を映していておもしろいが、原題は全部Le Bossu。
1944年 ジャン・ドラノワ監督、ピエール・ブランシャール主演、邦題『血の仮面』
1959年 アンドレ・ユヌベル監督、ジャン・マレー主演、邦題『城塞の決斗』
1997年 ド・ブロカ監督 ダニエル・オートゥイユ主演、邦題『愛と復讐の騎士』(ロードジョー公開はなし)
1959年のジャン・マレーは、父アルフレッド・マレーの死、兄アンリ・マレーの死、ジョルジュ・ライヒ(レーク)との別れなど、精神的にどん底で、経済的にも苦境にあった。この年、マレーは映画を1本しか撮っていない。それが『城塞の決斗』(フランスでの封切は1959年11月26日で、何の因果かジェラール・フィリップの亡くなった翌日)だったのだが、この映画で演じたアンリ・ド・ラガルデール役は、批評家からも観客からも喝采で迎えられ、騎士道時代劇映画にジャン・マレーあり――をフランス中に知らしめる結果となった。
そのときの様子を伝えるコクトーの電報と手紙は、喜びに満ちている。
「電報 君のラガルデールは、最高にうるさい人たち相手に勝利を収めました。ぼくが目を覚ましたら感動を伝えてほしいとアラゴン(=ルイ・アラゴン、詩人)がマドレーヌ(=コクトーの家政婦)に電話を寄こしました。月曜に映画を見ます。くちづけを送ります。ジャン」
「1960年1月27日 ぼくの善良な天使 せむしはあの瘤にラガルデールの巻き毛と同じくらいの夢を入れて運んでいます。君は2倍素晴らしかった。客席は賞賛の叫びをあげています」
フランスでのルイ王朝時代の騎士道物語というのは、日本のチャンバラ時代劇のようなもので、常にコンスタントな人気がある。また、周期的に大ブームが起こり、続けて同じような作品が量産されることもある。フランスではちょうど60年代初めにこの騎士道物語ブームが起こり、マレーはその波にのった。1960年にはコメディタッチの『怪傑キャピタン』に主演、これも観客の爆笑を誘って大ヒットとなり、1961年には同じような娯楽時代劇を1年で数本封切るという人気ぶりになる。19世紀のロマン派長編小説を下敷きにした騎士任侠劇というのは、もともとはかつてコクトーが『 ルイ・ブラス 』で描いた世界で、実際『怪傑キャピタン』には『ルイ・ブラス』とそっくりなシーンがかなりある。
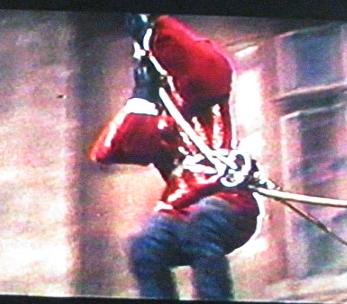
この綱につかまっての振り子移動は『ルイ・ブラス』そのもの( 5月24日のエントリー の写真参照)
そのあと窓ガラスを割って逃げる展開も同じ。ただし、『怪傑キャピタン』ではキメ台詞がある。

『ルイ・ブラス』公開当時は、イタリア・ネオレアリズモが隆盛を極めていたころでもあり、『ルイ・ブラス』は異色作品扱いだった。10年以上たって、ようやく世間がコクトーに追いついてきたのだ。それについてマレーは新聞紙上に発表したエッセイで、コクトーの先見の明を称えている( 5月26日のエントリー 参照)。
娯楽映画のヒットとともに、マレーの経済的苦境も嘘のように霧散し、長年マレーの浮き沈みに付き合ってきたマネージャーのリュリュは胸を撫で下ろす。またしても、マレーが「不当なほど幸運」であることが証明されたのだ。60年代の初めの騎士任侠映画とそれに続くファントマ・シリーズでマレーはひと財産作ってしまう。
騎士道時代劇に対するフランス人の愛着については、1995年にジャック・ペランがフランス映画史100年を記念して製作した『リュミエールの子供たち』(1995年)で、次のように解説している。「 フランス映画の持続性、それはヒーローが登場する大衆文学を映画化することで、義憤を覚える山賊や無欲の仇討ちを描くことでもあった 」。
『リュミエールの子供たち』は、1885年のリュミエール兄弟のシネマトグラフの発表と公開上映を「映画誕生の年」と位置づけたうえで、100年におよぶフランス映画の歴史を概観し、選りすぐりの307本から名場面を抜粋して編集した作品。ちょうど『ニューシネマ・パラダイス』で、ペラン自身が演じた大人になったサルヴァトーレ(トト)が最後に観ていた、ラブシーンをつなげたフィルムと同じようなカットの連続になっている。ジャン・マレー主演の映画は5作品入っているが、そのうちの2作がこの「ヒーローが登場する大衆文学の映画化」した騎士道時代劇に分類される『城塞の決斗』と『怪傑キャピタン』だった。
日本では文学の香り高いコクトー・ワールドの住人としてのみ扱われがちなジャン・マレーだが、フランス映画界での位置づけは日本でのイメージとは若干違うことが、この選択からもわかる。もちろん、コクトー自身が、「マレーはあまりに強烈に私の作品と同化しているので、そこにはあたかもコノハムシと木の葉の区別がつかぬような不可思議な関係が成り立っている」と言ったように、誰よりもコクトーは自身の戯曲・映画にマレーを必要とした。
『双頭の鷲』の再演にあたって、年齢を理由にスタニスラス役を拒むマレーに、何度も役を受けてくれるよう頼んでいたのもこの時期(詳細については 5月20日のエントリー 参照)。
1961年には、かつて『悲恋(永劫回帰)』で一世を風靡した黄金コンビ、ジャン・ドラノワ監督、ジャン・コクトー脚色で、マレーをクレーヴ公にキャスティングした『クレーヴの奥方』が封切られるが、皮肉なことにラファイエット夫人原作のこの文学の薫り高い作品は、マレーの同時期の他の痛快娯楽時代劇ほどは観客に受けなかった。コクトーは、こうした風潮に対し、「すばやい接触ばかりを望む今の観客には、クレーヴの愛は理解できない」と失望をもらしている(ただ、クレーヴ公に扮したマレーの演技についてはマレーへの手紙で絶賛した)。もともとコクトーは1945年にはすでに、ドラノワと『クレーヴの奥方』の打ち合わせをしていた。実に15年越しでようやく映画化まで漕ぎつけた思い入れのある作品だっただけに、残念な結果だっただろう。
だが、モチロン、尊敬するジャン・コクトー作品へのオマージュとしてジャック・ドゥミー監督が作った『 ロバと王女 』(1970)ではさりげなく、こんな台詞もある。↓

ちなみに、赤の王子様に扮しているのは、ジャック・ペラン(右)。
『双頭の鷲』をマレーに蹴られたコクトーは、次に『ルノーとアルミード』の再演――しかも、舞台美術はエドゥアール・デルミットで――を考えてくれるようにマレーに懇願を始め、マレーを困らせている。コクトーは、仕事でひとり立ちできない養子のデルミットの将来を非常に気にかけ、なんとかしようと一所懸命だった。
一方で、マレーのほうがコクトーに対して望んでいたのは、一緒に仕事することではなく、私人としてのコクトーとできるだけ長くプライベートな時間を過ごすことだった。「 ジャンの友情が絶えず生きる力を与えてくれる。私たちは可能な限り、頻繁に会っていた 」(ジャン・マレー自伝より)。
何度となくコクトーに同居をもちかけるマレー。かつては「多忙」を理由に、遠ざかったミリィ・ラ・フォレの別荘にも、この時期のマレーは時間を見つけては足繁く通い、コクトーに会っている。
ミリィからマルヌへマレーが戻ったあとに、コクトーが書いた手紙。
「ミリィにて ぼくのジャノ 君が帰ったあと、恐ろしいほどの悲哀と孤独に苛まされました。このぼくの発作に対しては、賢明なドゥードゥー(=デルミット)の心をもってしても、手の施しようがないのです。確かに君の言うとおりです。このような『相互訪問は耐えがたく、2人は一緒に生活すべき』なのです。去っていく君の後姿を見ると、ぼくは空虚さの中に落ち込んでいくようでした。君は君で別の空虚に」「君は毛皮の手袋を忘れて行きました。君の手袋をもって部屋に入り、頬ずりしながらむせび泣きました」
忘れられた手袋に頬ずりしながら泣くというのは、コクトーがマレーに出会う前に書いた『白書』の一場面が現実にすべり出してきたようでもある(この手袋の場面については 3月26日のエントリー 参照)。
仕事でスペインに行ったコクトーのマレーへの手紙。
「1961年8月9日 いつもお互い、そばにいるべき2人なのに、君から不当に遠く隔てられ、2度と見ることもないだろうと思っていたスペインに、ぼくはいます。進めば進むほどぼくたちの存在が散り散りにされ、君の面影がますます遠のくことが悲しくてなりません。これはありきたりの悲劇ではないのです。ぼくたち2人を結ぶ絆は断ち切られることはなく、お互いが遠ざかるほど苦痛とともに引っ張られるのですから」
(上の2通の手紙のうち、ミリィからのものは『ジャン・マレー自伝』『ジャン・マレーへの手紙』の2つに掲載。8月9日付けのスペインからの手紙は自伝にのみ掲載)
「2人は一緒に生活すべき」「いつもお互いそばにいるべき」と言いながら、マレーからの同居の申し出をはぐらかすコクトー。それは、マレーには知られたくない――少なくともコクトーは知られたくないと思った――秘密があったからだった。
<明日は『リュミエールの子供たち フランス映画100年の夢■』を紹介します。コクトー&マレーはあさってから再開>

リュミエール兄弟によって最初の映画が公開されてから100年。この作品はその記念すべき日から現在に至るまでのフランス映画1世紀を綴った・・ビデオによる”映画辞典”!■
1944年 ジャン・ドラノワ監督、ピエール・ブランシャール主演、邦題『血の仮面』
1959年 アンドレ・ユヌベル監督、ジャン・マレー主演、邦題『城塞の決斗』
1997年 ド・ブロカ監督 ダニエル・オートゥイユ主演、邦題『愛と復讐の騎士』(ロードジョー公開はなし)
1959年のジャン・マレーは、父アルフレッド・マレーの死、兄アンリ・マレーの死、ジョルジュ・ライヒ(レーク)との別れなど、精神的にどん底で、経済的にも苦境にあった。この年、マレーは映画を1本しか撮っていない。それが『城塞の決斗』(フランスでの封切は1959年11月26日で、何の因果かジェラール・フィリップの亡くなった翌日)だったのだが、この映画で演じたアンリ・ド・ラガルデール役は、批評家からも観客からも喝采で迎えられ、騎士道時代劇映画にジャン・マレーあり――をフランス中に知らしめる結果となった。
そのときの様子を伝えるコクトーの電報と手紙は、喜びに満ちている。
「電報 君のラガルデールは、最高にうるさい人たち相手に勝利を収めました。ぼくが目を覚ましたら感動を伝えてほしいとアラゴン(=ルイ・アラゴン、詩人)がマドレーヌ(=コクトーの家政婦)に電話を寄こしました。月曜に映画を見ます。くちづけを送ります。ジャン」
「1960年1月27日 ぼくの善良な天使 せむしはあの瘤にラガルデールの巻き毛と同じくらいの夢を入れて運んでいます。君は2倍素晴らしかった。客席は賞賛の叫びをあげています」
フランスでのルイ王朝時代の騎士道物語というのは、日本のチャンバラ時代劇のようなもので、常にコンスタントな人気がある。また、周期的に大ブームが起こり、続けて同じような作品が量産されることもある。フランスではちょうど60年代初めにこの騎士道物語ブームが起こり、マレーはその波にのった。1960年にはコメディタッチの『怪傑キャピタン』に主演、これも観客の爆笑を誘って大ヒットとなり、1961年には同じような娯楽時代劇を1年で数本封切るという人気ぶりになる。19世紀のロマン派長編小説を下敷きにした騎士任侠劇というのは、もともとはかつてコクトーが『 ルイ・ブラス 』で描いた世界で、実際『怪傑キャピタン』には『ルイ・ブラス』とそっくりなシーンがかなりある。
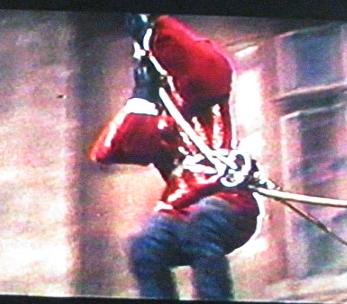
この綱につかまっての振り子移動は『ルイ・ブラス』そのもの( 5月24日のエントリー の写真参照)
そのあと窓ガラスを割って逃げる展開も同じ。ただし、『怪傑キャピタン』ではキメ台詞がある。

『ルイ・ブラス』公開当時は、イタリア・ネオレアリズモが隆盛を極めていたころでもあり、『ルイ・ブラス』は異色作品扱いだった。10年以上たって、ようやく世間がコクトーに追いついてきたのだ。それについてマレーは新聞紙上に発表したエッセイで、コクトーの先見の明を称えている( 5月26日のエントリー 参照)。
娯楽映画のヒットとともに、マレーの経済的苦境も嘘のように霧散し、長年マレーの浮き沈みに付き合ってきたマネージャーのリュリュは胸を撫で下ろす。またしても、マレーが「不当なほど幸運」であることが証明されたのだ。60年代の初めの騎士任侠映画とそれに続くファントマ・シリーズでマレーはひと財産作ってしまう。
騎士道時代劇に対するフランス人の愛着については、1995年にジャック・ペランがフランス映画史100年を記念して製作した『リュミエールの子供たち』(1995年)で、次のように解説している。「 フランス映画の持続性、それはヒーローが登場する大衆文学を映画化することで、義憤を覚える山賊や無欲の仇討ちを描くことでもあった 」。
『リュミエールの子供たち』は、1885年のリュミエール兄弟のシネマトグラフの発表と公開上映を「映画誕生の年」と位置づけたうえで、100年におよぶフランス映画の歴史を概観し、選りすぐりの307本から名場面を抜粋して編集した作品。ちょうど『ニューシネマ・パラダイス』で、ペラン自身が演じた大人になったサルヴァトーレ(トト)が最後に観ていた、ラブシーンをつなげたフィルムと同じようなカットの連続になっている。ジャン・マレー主演の映画は5作品入っているが、そのうちの2作がこの「ヒーローが登場する大衆文学の映画化」した騎士道時代劇に分類される『城塞の決斗』と『怪傑キャピタン』だった。
日本では文学の香り高いコクトー・ワールドの住人としてのみ扱われがちなジャン・マレーだが、フランス映画界での位置づけは日本でのイメージとは若干違うことが、この選択からもわかる。もちろん、コクトー自身が、「マレーはあまりに強烈に私の作品と同化しているので、そこにはあたかもコノハムシと木の葉の区別がつかぬような不可思議な関係が成り立っている」と言ったように、誰よりもコクトーは自身の戯曲・映画にマレーを必要とした。
『双頭の鷲』の再演にあたって、年齢を理由にスタニスラス役を拒むマレーに、何度も役を受けてくれるよう頼んでいたのもこの時期(詳細については 5月20日のエントリー 参照)。
1961年には、かつて『悲恋(永劫回帰)』で一世を風靡した黄金コンビ、ジャン・ドラノワ監督、ジャン・コクトー脚色で、マレーをクレーヴ公にキャスティングした『クレーヴの奥方』が封切られるが、皮肉なことにラファイエット夫人原作のこの文学の薫り高い作品は、マレーの同時期の他の痛快娯楽時代劇ほどは観客に受けなかった。コクトーは、こうした風潮に対し、「すばやい接触ばかりを望む今の観客には、クレーヴの愛は理解できない」と失望をもらしている(ただ、クレーヴ公に扮したマレーの演技についてはマレーへの手紙で絶賛した)。もともとコクトーは1945年にはすでに、ドラノワと『クレーヴの奥方』の打ち合わせをしていた。実に15年越しでようやく映画化まで漕ぎつけた思い入れのある作品だっただけに、残念な結果だっただろう。
だが、モチロン、尊敬するジャン・コクトー作品へのオマージュとしてジャック・ドゥミー監督が作った『 ロバと王女 』(1970)ではさりげなく、こんな台詞もある。↓

ちなみに、赤の王子様に扮しているのは、ジャック・ペラン(右)。
『双頭の鷲』をマレーに蹴られたコクトーは、次に『ルノーとアルミード』の再演――しかも、舞台美術はエドゥアール・デルミットで――を考えてくれるようにマレーに懇願を始め、マレーを困らせている。コクトーは、仕事でひとり立ちできない養子のデルミットの将来を非常に気にかけ、なんとかしようと一所懸命だった。
一方で、マレーのほうがコクトーに対して望んでいたのは、一緒に仕事することではなく、私人としてのコクトーとできるだけ長くプライベートな時間を過ごすことだった。「 ジャンの友情が絶えず生きる力を与えてくれる。私たちは可能な限り、頻繁に会っていた 」(ジャン・マレー自伝より)。
何度となくコクトーに同居をもちかけるマレー。かつては「多忙」を理由に、遠ざかったミリィ・ラ・フォレの別荘にも、この時期のマレーは時間を見つけては足繁く通い、コクトーに会っている。
ミリィからマルヌへマレーが戻ったあとに、コクトーが書いた手紙。
「ミリィにて ぼくのジャノ 君が帰ったあと、恐ろしいほどの悲哀と孤独に苛まされました。このぼくの発作に対しては、賢明なドゥードゥー(=デルミット)の心をもってしても、手の施しようがないのです。確かに君の言うとおりです。このような『相互訪問は耐えがたく、2人は一緒に生活すべき』なのです。去っていく君の後姿を見ると、ぼくは空虚さの中に落ち込んでいくようでした。君は君で別の空虚に」「君は毛皮の手袋を忘れて行きました。君の手袋をもって部屋に入り、頬ずりしながらむせび泣きました」
忘れられた手袋に頬ずりしながら泣くというのは、コクトーがマレーに出会う前に書いた『白書』の一場面が現実にすべり出してきたようでもある(この手袋の場面については 3月26日のエントリー 参照)。
仕事でスペインに行ったコクトーのマレーへの手紙。
「1961年8月9日 いつもお互い、そばにいるべき2人なのに、君から不当に遠く隔てられ、2度と見ることもないだろうと思っていたスペインに、ぼくはいます。進めば進むほどぼくたちの存在が散り散りにされ、君の面影がますます遠のくことが悲しくてなりません。これはありきたりの悲劇ではないのです。ぼくたち2人を結ぶ絆は断ち切られることはなく、お互いが遠ざかるほど苦痛とともに引っ張られるのですから」
(上の2通の手紙のうち、ミリィからのものは『ジャン・マレー自伝』『ジャン・マレーへの手紙』の2つに掲載。8月9日付けのスペインからの手紙は自伝にのみ掲載)
「2人は一緒に生活すべき」「いつもお互いそばにいるべき」と言いながら、マレーからの同居の申し出をはぐらかすコクトー。それは、マレーには知られたくない――少なくともコクトーは知られたくないと思った――秘密があったからだった。
<明日は『リュミエールの子供たち フランス映画100年の夢■』を紹介します。コクトー&マレーはあさってから再開>

リュミエール兄弟によって最初の映画が公開されてから100年。この作品はその記念すべき日から現在に至るまでのフランス映画1世紀を綴った・・ビデオによる”映画辞典”!■
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.09.22 16:53:56
[Movie] カテゴリの最新記事
-
祝! 米アカデミー賞、ヒース・レジャー+… 2009.02.24
-
ジャン・マレーによる「ファーリー・グレ… 2008.09.18
-
ジャン・マレーとの出会い――フランコ・ゼ… 2008.09.17
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









