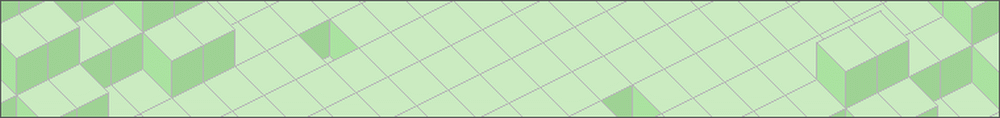2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2005年04月の記事
全43件 (43件中 1-43件目)
1
-
清原500本塁打。。。
~史上8人目の達成と、地元紙の『正平調』というコラムの上に。その中で、本人のコメントが載っていたので、そのまま引用させて頂きます。 『絶対に打ちたい数字だった、2000安打もうれしかったが、今日はさらにうれしい。故障や試合に出られなかったりで、弱気になったこともあった。支えてくれた家族やファンがいなければ不可能だった。いろいろな人に感謝したい。』 更に、清原選手の紹介として、『清原は大阪・PL学園高から86年にドラフト1位で西武入り。1年目に新人最多タイの31本塁打を放って新人王に輝き、通産100号、200号を史上最年少で記録した。97年に巨人移籍後は故障に苦しみ、昨年は40試合出場に終わり引退騒動も起きた。進退を懸けた今季は開幕から4番に座り、快調に本塁打を量産している。』 37歳というのがプロ野球選手としては決して若くはないとは思うけど、これからも活躍して欲しい。いや、そのためにも故障などにも気をつけて欲しい。 さて、今日の『正平調』にはベトナム戦争のことが取り上げられている。 『「ノー・モア」は「二度と繰り返したくない」という意味である。被爆国日本では「ヒロシマ」「ナガサキ」が、この言葉に続く。米国ではおそらく、「ベトナム」を付ける人が多いだろう◆双方で30万人もが死亡したベトナム戦争が終わって、きょうで30年になる、これでもかこれでもかと軍隊を送り込みながら、米国は敗れた。巨額の戦費で大国は疲弊し、国民の体も心も大きく傷ついた◆それから30年、筑波大・松岡完教授の「ベトナム症候群」(中公新書)にこんな話がある。戦争の十数年後、地図上でベトナムを正確に示せた国民は、3人に1人だった。米国がどちらの側で戦ったか知らないのも同じ比率。いやおうなく風化が進む◆ただし、米国民はいまも、一人残らず「ベトナム探知キット(装備)」を持っているという。海外で紛争が起き、米国の介入の是非が問われた場合、それが「第二のベトナム」に陥らないかどうかが国民の判断基準、という意味である◆だから政府は、国民の反発を招かないよう米兵の死傷をできる限り減らしたい。被害が大きい地上戦を避け、空爆などに頼るのはそのためだろう。最近では遠隔操作のロボット兵器まで開発された。しかし空爆などが増えれば民間人の犠牲も増えていく◆イラク戦争での民間人の犠牲者数を推計する団体がある。そのウェブサイトを見ると、2万人を優に超え、米兵の十数倍に達する。米国が悪夢から解放されようとすれば、別の悪夢が地上でうめく。「ノー・モア」は、まだ遠い。』
2005.04.30
コメント(2)
-

4月27・28日共通のお弁当
昨日(28日)は何だかいきなり暑くなってしまって、少し走らせては停まり、少し走らせては停まりの配達がとても厳しいものになってしまって、夕食を終えて、片付けたらゴロンと横になってしまった。。。サイトにも入らずにそのまま休んでしまい、書き込んでくださった皆さんのところへもお伺いすることが出来ませんでした。益々暑くなるのに、今からこれでは先が思いやられる5年目の春。。。 献立は、豚肉入り野菜炒め、エビフライ(横付けに出し巻き卵)、ポテトサラダ。添えの野菜はエビフライにレタス。メインが野菜炒めのため、果物は付きません。◆豚肉入り野菜炒め。。。材料は、キャベツ、玉葱、人参、ピーマン、もやし、豚肉、ロースハム。玉葱、人参は皮を剥いて、ピーマンは種を取って、キャベツとそれぞれ同じ幅、同じ長さに切り揃える、もやしは袋から出して3つぐらいにざくっと切って水にさらして水気を切っておく。豚肉は食べ易い大きさ、ロースハムは肉とほぼ同じぐらいに切って、油を敷いた鍋で豚肉から炒めて、人参、玉葱を加え、酒、中華味、薄口醤油で味を調える。ほぼ火が通ったところへもやしを加え、最後にピーマンを加えて火を止める。◆エビフライ。。。冷凍のエビフライを熱した油で揚げるだけ。横付けの出し巻き卵も冷凍のを湯煎して、8つ切りに。◆ポテトサラダ。。。材料はじゃがいも、ミックスベジタブル。ジャガイモは皮を剥いて大きさを揃えて切ったのを水にさらしてから茹でて水気を飛ばして、熱いうちに酢を数滴たらして、マッシャーでつぶしておく。ミックスベジタブルを塩茹でして冷ましておく。じゃがいもが冷めたらミックスベジタブルを合わせて、塩、コショー、マヨネーズで和える。メインは野菜炒めなので、たっぷりと。左側にレタスを敷いて、エビフライを二つ、空いたスペースに出し巻き卵を。3番目にはポテトサラダを。野菜炒めに使う玉葱は八百屋さんからはもう新玉葱が届くので、かなり甘味が出るのに、まるで溶けた様に無くなってしまう。ピーマンは余熱で火が通ってしまうので、最後に入れると色鮮やかさが残る。でも、食べるときには色が変わるかな?でも、こればかりは。。。エビフライは一人二尾なので、対角線上に並べないと入らない。出し巻き卵の位置も空きスペースに。ポテトサラダのミックスベジタブルにはどうしても人参の赤が目立ってしまうけど、これを程好く混ぜるのは至難の業?それにしても、野菜炒めに豚肉と更にロースハムが加わるのはかなり贅沢な一品。
2005.04.29
コメント(2)
-
今日付けの地元紙の『正平調』には。。。
日本中を震撼とさせた、こんな事件のことが述べられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『新幹線の「安全神話」が、当然のことのように語り続けられていた1999年のことだった。突然、科学・技術への不信が噴き出す事故が相次ぎ起こった。3件も連続発生したため“三点セット”などと呼ばれた◆東海村の燃料製造会社で起こった「臨海事故」H2ロケットの「打ち上げ失敗事故」。それに、新幹線トンネル内のコンクリート壁の「連続剥落(はくらく)事故」。どれも、起こるはずがないと皆が思っていた。だから「安全神話」であった◆しかし、そんな「安心・安全空間」に大きな亀裂が走った。さまざまな調査が行われ原因究明が進んだ。その結果は、それぞれ耳を傾ける内容だったが、一つ、印象に残ったのが、科学評論家村上陽一郎さんの言葉だった◆それは「メンテナンスの重要性」ということだった。なんだ、と思いそうだが、単なる修理というう意味ではない。考え方、つまり思想の問題だ。従来の「安全水準」を持続、発展させるための心構えと手段は十分講じられていたかを問うていた◆新しい物づくりには膨大な資金を投入するが、その安全管理にも開発・製作と同等の情熱、経費をかける姿勢が必要だというのだ。その思いを一瞬でも忘れると、神話は崩れる。効率や費用対効果優先の一方で「メンテナンスの対応」が薄れる現状に警告を発していた◆尼崎JR脱線事故犠牲者が増え続ける。震災を思いだし、その度に瞑目(めいもく)する。事故現場となった「魔のカーブ」での「メンテナンスの思想」はどうだったか。あらためて問いただしたい。』 そして、社説欄では治療とケアに全力を尽くせという表題でこの様に。 『押しつぶされた車内に、まだ乗客が取り残されている。依然、連絡のとれない人もいる。遺体安置所には身元確認に訪れる家族や友人の姿が耐えない。疲労がにじむ。 尼崎市のJR脱線事故は、重苦しく、もどかしく、やるせない思いが募る。関係者の心痛は察するに余りある。 あの日の朝、元気に家を出た家族が変わり果てた姿で戻ってくる。悲しさ、つらさは言い表せまい。難病を克服し、これからという人もいた。運び込まれた病院で、まだ意識の戻らない人もいる。 犠牲者が百人にものぼる惨事を前にして、今なすべきことの一つは救出・救助と身元の確認作業を急ぐこと、負傷者の治療やリハビリに全力を挙げることだ。 事故に巻き込まれた恐怖で、あるいは友人や身内を亡くした悲しみやショックで、心に深い傷を負った人は多いだろう。深刻な状態になる前に、心のケアにも万全の体制で臨んでほしい。 4年前の池田小学校の事件では、現場の状況が凄惨(せいさん)だったため、救急隊員の精神的ダメージが問題になった。仕事柄、見過ごされがちだ。今回の救出も長時間の緊張を強いられる中で行われており、活動の終了後、十分な配慮が必要だろう。 事故災害で、一度にこれほど多くの死傷者に対応したケースは、阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件以来だ。 医療関係者によると、今回は衝突時の強い衝撃と車両の破壊に伴い、乗客の負傷の部位や種類や程度はさまざまだった。頭部や胸部に外傷を負った人が少なくない。震災で一般に知られるようになったクラッシュ症候群も多くみられた。体を長時間圧迫されることにより、救出後に血中のカリウム濃度が上がり、死に至るものだ。 初期の緊急対応を誤ると、手遅れになるケースも少なくなかった。 兵庫医大の救命救急ぃが、現場で治療に当った医師からの情報でクラッシュ症候群と見抜き、搬送される間に機器を取り揃えて処置し、救った。そんな例もある。 現場で救助活動に加わった救急隊員や医師は約4百人に上る。わずかなすき間から点滴や水を補給し、救出後、素早く搬送した。現場と医療機関の連携が比較的うまくいったのは震災の教訓があったからだ。 精神面のケアなどは、息の長い対応が求められる。相談を待つのではなく、医師の方から出向いていく姿勢がほしい。 今回の事故は医療を必要とする人が多く、処置内容も多岐にわたる。治療を受ける側に立ったきめ細かな対応が必要だ。』 また、土井たか子氏現場を視察として、 『尼崎JR脱線事故を受け、社民党の国会議員や地元県・市議らでつくる「JR福知山線列車脱線事故国会調査団」は27日、尼崎市内の事故現場を視察した。団長を務める土井たか子前党首は、押しつぶされた車両などの惨状に「遺された家族のことを考えると、言葉を失う」と語り、「こういう事故を二度と起こさないよう全国的に取り上げていかなければならない問題だ」と話した。 また、新社会党兵庫県本部(原和美委員長)は同日、JR西日本に対し、遺族や負傷者、電車が激突したマンション住民に迅速に万全の補償を行うことなどを申し入れた。』とありますが、言えるべき立場の人がどんどんこうした声を挙げて欲しい。 この、列車脱線事故の犠牲者が余りにも多いこと、事故そのものが考えられない結果を招いてしまったことなどから、全国の注目がこちらに集まるのは無理からぬことで、私自身は国民の注目の陰で、何かが行われる気がしてしょうがなかった。案の定、郵政民営化法案が国会に提出されることになった。そのことも社説で触れられていましたので、ここに引用させていただきます。 『国会でまっとうな議論を これだけ妥協を重ねて、狙い通りの民営化といえるのか。 政府は27日、自民党の党内手続きが終了したのを受け、郵政民営化関連六法案を閣議決定した。 法案の中身は、先の「骨格」からさらに後退した。民営化会社の株式持合い問題は自民党との調整で「連続的保有を妨げない」との玉虫色の表現が盛り込まれた。 金融のユニバーサル(一律)サービスを維持するため新設する「地域・社会貢献基金」は、1兆円から最大2兆円まで増額された。郵貯、保険料者と窓口会社の代理店契約も、民営化移行期間(10年)を超えて長期化することを容認した。 しかし、これらは郵政民営化の根幹にかかわる問題であり、こうした条項を基に都合のよい解釈がまかり通るなら、実質的に今の郵政公社と変わらないことになる。 政府の郵政改革の最大の目標は郵貯、保険の金融業務にあったはずだ。郵貯、保険の巨額の資金を官から民へ移し、政府の財政赤字の補てんや財政投融資の安易な財源にさせないことが狙いだった。 そのためには、民営化後の金融二社が持ち株会社などから完全に自由になることが求められた。ところが、株式の持ち合いだけでなく代理店契約の延長まで認めて、そうした政策目的を実現できるだろうか。 自民党が一体経営に最後までこだわったのは、金融業務が最大の利益源であり、これらを手放すと郵便局全体の存廃問題にかかわってくるとみたからである。 「地域・社会貢献基金」の増額も同じ理由からだ。過疎地の郵便局維持という大義名分の下に、増額は、実は都市部の特定郵便局の存続を狙っている。 民営化によって、銀行などとの競争で落後した都市部の特定郵便局はリストラの対象になりかねない。それを基金の活用で防ぐというのが、特定郵便局を支持母体とする自民党郵政族の腹づもりだろう。 郵政民営化がこんな形で不完全なものとなったのも、小泉首相や竹中郵政民営化担当相らが「なぜ郵政の民営化が必要か」の目的をはっきりさせず、技術的な方法論に終始したことが大きい。 郵貯、保険の民営化は、一方で、これら二社が新たに自らのリスクで資金の運用を行わなければならないという難しい問題も抱えている。 政府、自民党はこの巨大な公営企業の軟着陸に責任ある処方せんを示したと、胸を張って言えるか。国会では、きちんとした議論を一からやり直すべきだ。』 何だか。。。民営化された当時の国鉄には動労、国労なんてあったし、電電公社にしたって、電通、全電通なんてあったし、郵政にしたって、全逓、全郵政なんて労働組合があって。。。 何故か労働組合を二つに分けて、第一、第二組合を組合同士で闘わせていたきらいがあった。郵政などの場合も、集配業務をしているような普通局の場合、ほとんどが全逓組合員。ところが、私が勤めていた特定郵便局の局員はほとんどが全郵政の組合員。全逓の組合員が特定郵便局の局長になるなんて有り得ないことだった。ところが、全郵政の組合員といえば、ゆくゆくは特定郵便局の局長にだってなれるわけ。同じ労働組合なのに。この仕組みが全く納得が行かない。しかも、労働者としての権利を勝ち取る闘いに明け暮れていたのは勿論全逓組合員だった筈。ただ、今の仕組みはどうなっているのか全くわからないし、そんなことを辞表を出して22年も経つ私が言うのも変だけど。。。 ただ、赤字国債ばかりを立て続けに発行している国にとってはあの郵貯、簡易保険で集めたお金というのはかなり魅力のはず。。。 職員にしたって、国家公務員として働いていて、急に明日から民間に。なんてことになったら、待遇も何もあったものではない。。。確かに窓口そのものは何も国家公務員じゃなくても。とは思う。でも、職員たちの給料がそのまま国家財政を圧迫しているとは私にはとても思えない。独立採算制なんだから。違うのかな?
2005.04.28
コメント(2)
-
淡路島最南の海岸線をひた走りに走る。。。
コースの配達を担当して、余りにもお天気のお良さに疲れ果ててしまった感じ。いつも、車を停めさせていただくところには車が停めてあったりして、方向転換するのに苦労したり、一番長く歩く距離のところは相棒さんが届けてくださったので、今日は歩くつもりでスニーカーを履いて出勤したけれど、急な坂がある所を二箇所回っただけ。それでも坂が急なので足が突っ張ったりする。 空が青いと海の色の綺麗なこと。サーフィンを楽しんでいる若者を見つけたので、波など出ているのかな?と思ったら、大阪湾側に近づくにしたがって、白い波が立っている。流石にサーファーはよくご存知なんだ。と感心させられる。まだまだ波は冷たいだろうけど、サーファーにとってはそんなこと関係ないのかな? 月曜、火曜日と連続で外出した母から夜になって電話。明日も出かけたいのだという。午前中の時間を取られるのは私にはとてもきついけど、こればかりは仕方が無い。家までタクシーを呼んで、今度は最寄りのバス停からバスで。と母は言うけれど、歩くのさえおぼつかないのに、危なっかしくて見ていられない。時間にして、50分は母の為に時間を割くことになる。50分。。。されど50分。 約束の時間は午前11時30分。実家へこの時間に着こうと思えば、こちらを11時には出る羽目になる。出勤はお弁当の数が一番少ない木曜日だから、家を午後1時前には出れば良いことだから十分に間に合う。母を目的地で降ろして、お昼を食べてそそくさと出勤することに。何だか。。。食べた後は少しくつろぎたいのに、これで立派な宗教団体だというから尚更腹が立ってくる。人の都合など全く考えないのだから。何の為の宗教なんだろうと思ってしまう。ただ、母が頼りにしているのなら仕方が無いし、母には生きがいになっているのなら。と少々多目に見ているつもりでも、午前中の時間は。。。なるべくなら好きな様に使いたいのに。と、こんな勝手を言ってると、お子さんがいらっしゃる方には笑われてしまうのかな? 昨日の話になるけど、以前にも書いたボランティアさん。。。何と4人も来られた。。。栄養士さんが休まれることはわかっていたけど、その代わりにちゃんと、特別養護老人ホームから栄養士さんが来てくださった。 3人でも多いと思っていたのに、4人では。。。でも、実際何人来られるかはそのときになってみないとわからないのだとか。なるほど盛り付けのときの人手はとても助かるけど、下準備のときはまな板も包丁も数は揃っていない。本来、生野菜の下準備用、加熱・消毒済み用、肉、魚下準備用とそれぞれ2枚、2本ずつしかないので4人が一斉に厨房へ入られると。。。しかも、「次、何しましょ?」攻め。一応、月曜日に一度作ったそのままの献立ではあるけれど、レシピを見て今何をすれば良いのかの判断などまるでつかない人ばかり。却ってこちらが疲れるばかり。本当は和やかに作業を進めるべきだけど、こちらが作業をしているときに聞かれても、即答できなかったりする。一体、いつまでこんなことが続くんだろう。何だか疲れがピークに達している気がする。 ボランティアの人たちの顔ぶれも毎回違うので、いわば初めての人がまだまだこれからも来られる様子。ボランティアの人たちにお願いするならするで、せめて私たちの意見も聞いてからにして欲しかった。。。と、今更言っても遅いけど。年末までこんなことが続くのなら、本当にどうにかなりそう。
2005.04.27
コメント(0)
-
今日の地元紙の『正平調』というコラムには。。。
こんな風に述べられていましたので、そのまま引用させていただきます。 『JRの脱線事故の犠牲者が増え続ける。なぜ自分の家族が?惨事に遭遇した遺族らは、そんなつらい問いかけを重ねているだろう◆昨年亡くなった米国の精神科医キューブラーロス博士の分析を思いだす。病状を知った末期患者の心理を5段階で説いた有名な分析である。否定する。起こる。なにかにすがる。それが不可能だと分かると、うつ状態になる。そこを抜けてやっと事態を受け入れ、残された人生を有意義に生きようと考える◆博士の分析を読んだとき、こう思った。患者の肉親も同じような心の格闘をしていくのではないか。なぜ自分の身内が…と現実を否定し、なにかに怒りをぶつけ、落ち込む、家族の死を受け入れるのにも長い時間が必要ではないのか◆しかし闘病と違って、事故や災害で身内を失った人には、そんな心の準備期間がない、ジャンボ機の墜落事故がそうだった。月日がたっても死亡した男性のゴルフバッグを玄関に置く遺族がいた。生活に穏やかさが戻っても、心の底では亡くなった事実を拒んでいるように見えた◆連日の脱線事故報道で遺族の表情を紙面でみていると、その記憶がよみがえる。いまは奥歯をかみしめ、噴き出しそうな激情を懸命に抑えつけている。しかし納得できないだろうし、認めたくない死だろう。その思いをずっと引きずらないかとの懸念が残る◆JR事故を受け、兵庫県や尼崎市が心のケアの相談窓口を設けた。遺族や負傷者が立ち直るには、心の格闘を重ねていく時間がいる。みんなで支え、見守りたい。』 いつもお邪魔させて頂いている『リリークソプラノ』さんが、紀宮様のお言葉として、美智子様のことを述べられたお言葉の中から、特に気に留められたお言葉として日記に載せていらっしゃいましたが、この『みんなで支え、見守りたい。』という一文で、全く同じことなんだ。と『リリークソプラノさん』が書かれた日記のことを思い出しました。脱線事故の原因を明らかにして、二度とこの様な悲惨な事故が起こらない様、事故を未然に防ぐ方法を見出して欲しい。改めてご遺族の方の心痛はいかばかりかと無念でなりません。 また、今日の社説ではJRはすべてを明らかにとしてこの様に述べられています。 『脱線事故捜査 尼崎市のJR脱線事故は死者が70人を超えた。車両にはまだ乗客が閉じ込められており、死傷者はさらに増える見込みだ。 兵庫県警は、JR西日本の京橋電車区など7カ所を家宅捜索し、運行記録や勤務日報の任意提出を受けた。無理な運転や運行管理に手抜かりがなかったかを調べるためだ。事実上の強制捜査であり、警察の厳しい姿勢を示しものといえる。 JRは全面的に協力すべきだ。運転状況など正確な情報が明らかにされないと、事実の解明にはつながらない。 実際、JR側のこれまでの説明とは異なる新たな事実が分かった。 電車が送れる原因となった、伊丹駅でのオーバーランの距離が当初発表の8メートルは誤りで、実際は40メートルだった。運転士が「短くしてほしい」と頼んだらしく、車掌と二人で口裏を合わせたという。 運転士は過去3回、訓告などを受けていた。オーバーランしたこともあり、新たな処分を恐れたのかもしれない。 虚偽情報に加担した車掌は、乗客からオーバーランによる遅延のおわびの社内放送を要求されていた。いずれも、乗務員としての適正が問われる行為だ。 こうした一連の経緯をみると、JRは運転士の適正判断や指導を軽く見ていると疑われても仕方がないだろう。 事故の原因はまだ不明だ。だが、警察によると運転士は事故直前に時速108キロのスピードで走っていた。カーブの制限速度を40キロ近く超えていたことになる。運転士のあせりが速度超過を招き、事故に結びついたとすれば、乗務員の教育、乗務管理のあり方を含め、JRの責任は免れない。 JR総連が、安全軽視の企業体質が背景にあるとの声明を出したことも驚きだ。身内の労働組合が会社の体質を批判するというのは余程のことである。 事故が起きたカーブには脱線防止のガードや、制限速度を超えた際に働く新型の列車児童制御装置もなかった。 ミスを補う装置は必要だ。だが、それを生かすかどうかは、結局、人である。 「人間というのはどうしようもないくらい不思議な行動をとったり、判断ミスをしてしまう現実があり、それをどのように分析していくかという課題は、手つかずの状態…」。「安全学の現在」(青土社)で評論家の柳田邦男さんが語っている。 直接の脱線原因にとどまらず、それをつくりだした人の問題にも立ち入って究明すべきだ。そのためにも、JRがすべてをオープンにする姿勢が欠かせない。』 実は昨日、母を実家から同窓会の会場への送迎バスを待つ集合場所へ送ったあと、いつもの薬局へ寄って列車脱線事故の話になって、薬剤師さんも何か以前に神戸から大阪へ向かうのに、JRを利用したところ、電車が遅れていたために、約束の時間に間に合わなかったことがあったのだとか。それも尼崎駅でのことだと。事故があった前日に私は(当日の日記にも書いていますが)姫路へ行くのにJRを利用した。ところがこれまた尼崎駅構内で線路内立ち入りがあって、安全確保の為にと、新快速の車両がそのまま各駅停車になってしまうということに遭遇してしまった。尼崎駅には一体何があるんだろう。あの、白い車だって妙な場所に停まっていた気画するし、実際電車が脱線したからぶつかったものなのかどうかはわからないけれど、何か妙なことが起こり過ぎる気がする。この辺のことは事故とは直接の関係が無いのだろうか。。。?マンションにお住まいの人たちだって、確かまだ避難されているのですよねえ。とんでもない話。二度とこんなことがない様、安全にはいくらお金をつぎ込んでも無駄ではないと思うのですが。いよいよ犠牲となられた方が90人へと膨らんで、まだまだ増えそうな勢い。何だか。。。やりきれません。
2005.04.27
コメント(0)
-

4月25・26日共通のお弁当。。。
月曜・火曜日共通の献立は大抵月曜日にUPするようにしていましたが、皆さんがご存知の通り、昨日午前9時過ぎに起きた列車脱線事故のことが余りにもショックで、仕事から戻りましても何もする気が起こらずにいました。改めて犠牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申しあげます。 さて、献立は、筍ご飯、天ぷら、含め煮、辛子和え。添えの野菜はレタス、果物はオレンジ。◆筍ご飯。。。材料は筍の水煮。実際月曜日はご飯と一緒に炊き上げましたが、今日は筍だけを甘辛く煮込んで炊き上げたご飯にまぶしたいと思います。三つ葉の茎も刻み込んで。三つ葉はお弁当に盛り付けてからトッピング。◆天ぷら。。。材料は、ロールイカ、魚、さつま芋。ロールイカは冷凍の物を水にさらして解凍し、包丁で切れ目を入れたのを食べ易い大きさに削ぎ切りにする。さつま芋は皮を寅縞に剥いて7ミリぐらいの輪切り。今日の天ぷらは3種類。◆含め煮。。。材料は鶏もも肉細切れ、高野豆腐、人参、れんこん。高野豆腐は戻したのを水の中で軽くすすぎながら絞って長い方を二つに切って、更に二つ切りを今度は斜めに切る。人参は食べ易い大きさに乱切り。れんこんは皮を剥いて酢水から茹でておいたのを、薄い乱切りに。出しを煮立てて、砂糖、酒、みりん、醤油で味付けした煮汁を沸騰させ鶏もも肉を加えて色が変わったら人参、れんこんを加え、人参に火が通ったら高野豆腐を加えて煮含める。◆辛子和え。。。材料は焼き穴子、きゅうり、オオバ。焼き穴子を熱しておいた天板に並べて150度ぐらいで10分ぐらいのオーブンであぶったのを1.5センチ幅に切り揃えておく。きゅうりは薄切りスライスにしたのに塩をまぶしてしんなりさせ、塩を洗って水気を切っておく。オオバは細切りにしておく。材料を合わせて、普通のお浸しぐらいの味の合わせ醤油に水溶き辛子を合わせたのを和えてアルミカップに入れておく。ご飯に混ぜ物があるときは横に長い形のお弁当箱を使うので、画像がうまく入りませんが、右側にオレンジを置いてレタスを敷き天ぷらを。右の下隅にコーナーを合わせる形にアルミカップに入れた辛子和えを。真ん中の上には柴漬けを、下に含め煮。左側に筍ご飯を入れて上には三つ葉をトッピング。何とまぁ、美味しそう♪ 今日は母の同窓会。実家へ行って、母を集合場所まで送ることに。会場へはここからの方がはるかに近いけど、母は皆さんと一緒にバスで行くというので、実家まで。取敢えず行って来ます。
2005.04.26
コメント(2)
-
ただただ驚いています。。。
今朝はNHKの連続テレビ小説が終った時点で家を出て、実家へ行って母を乗せて一旦洲本市へ。家を出て暫くしてから、いつも無線でお喋りしている人の声。車の運転が怪しいおばちゃんの会話で盛り上がっている。何でも反対車線へ斜めに車を停めたりするもので、他の車の通行の邪魔になっていたとのこと。。。 朝、そんな会話をしたばかりで家に戻って、乾燥機に放り込んであった寝具類を畳んでテレビ(勿論NHK)を点けたら大惨事の模様を伝えている。 何と、線路際にあったマンションにまで電車がぶつかって見るも無惨な姿になっている。 カーブとスピードと、白い車を発見したときの急ブレーキとが重なってとんでもない遠心力が働いたのかなぁ。 この時点で死者が16名とのこと。心からご冥福をお祈りします。 昨日も尼崎駅で線路内に立ち入りがあったとかで山陽線はかなり遅れていたけれど、一体何があったのか。。。まるでわからない。でも、かなりのスピードが出ていたのはどうやら間違いはなさそうな。 乗っていた人が、身体が宙に浮いたとのこと。何だかやり切れない事故。 自然災害の犠牲者もたまらないけれど、こんな人為的なミスでとんでもない事故が起きてしまうのもたまらない。。。 先頭車両なんかに乗るものじゃない。。。とはあの信楽鉄道の正面衝突事故があったときに思ったことだったけど、何だか電車に乗るのが怖くなってしまう。どうか二度とこんな事故が起きない様。。。 そういえば、交通事故などでも、ほとんどの原因がスピードの出し過ぎによるものなんですよね。運転するということ。くれぐれもスピードには気をつけたい。
2005.04.25
コメント(0)
-
大好きなヤクルトスワローズの。。。
古田敦也さんが2000本安打を達成されました。本当におめでとうございます! 実は、古田さんのことを意識し始めたのは、無線のお友達が私のことを「古田さんに似てる」と仰ったことから。タレ目(古田さんファンの方には本当に申し訳ありません)だというところが似ているのかな?ぐらいにしか思っていませんでした。でも、古田さんの選手会会長としての働きもそうだし、大学、社会人へと進んでからのプロ入り2000本安打は快挙とも言える出来事。 さて、ある人曰く、「奥さんのことは好きじゃない」と。私の場合、実は「平成教育委員会」のアシスタント役をしていらっしゃった頃、「素敵な人だなぁ」と思ったことがきっかけで、その後古田さんと結婚されて、そんなこともあってから古田さんのことも、頑張って欲しいなぁ、と。プロ野球選手の奥さんは本当に大変だと思うけど、ある旅の番組でこれまた「キーハンター」(わからない人もいるんだろうなぁ。。。)以来のファン(NHKのアナウンスもされてた時代があったということも理由の一つかも)でもある野際陽子さんととても素敵に番組を進めていらっしゃる。。。素敵な人の笑顔は奪って欲しくないなぁ。だから是非古田さんにも頑張って欲しい!なんて言ったら変かな?
2005.04.25
コメント(0)
-

展覧会を2会場回りました。。。
夫、姪夫妻とその娘は義姉宅での7回忌の法要に出かけ、余りにもお天気が良いものだから、家でじっとはしていられなくて、思い立って姫路市立美術館での葛飾北斎の展覧会、明石市立文化博物館での竹久夢二の展覧会を。 先ずは家を出て、洲本高速バスターミナルから高速バスに乗るかどうしようか散々迷って結局は、お天気に誘われたのと、先日JG6TYNさんが送ってくださった、私が大好きな「さだまさし」のCDを聴きながらの運転なら楽勝♪な気がして、一気に岩屋まで車を走らせることに。船場の駐車場は満車。歩いて数分の所に別の市営駐車場があると聞いて、急遽そちらへ車を移動することに。さて、船に乗ったのが11時40分。13分後には明石へ着くので、運転に余裕がある人なら絶対に船がお勧め。勿論、橋を渡って、神戸市でも明石市でもスイスイと運転出来る人なら問題は無いのですが。ただ、車で橋を渡ると目を剥くほど取られるので、私は船を利用。明石の街をそぞろ歩いて先ずは腹ごしらえ。食後にホットコーヒーも頼んでしばしくつろぎタイム。おもむろにお店を出て明石駅へ。 切符を買ってホームへ上がると、何と物凄い人。明石駅も西明石駅も、確か新快速と普通とではホームが違う筈。姫路まで行くのなら断然新快速が便利。と思ってそのホームへ上がったら、大勢の人だかり。何か、事故があったらしく、悠に30分は遅れているとのこと。新快速は来たけれどJRの都合で各駅停車になってしまう。こればかりは仕方が無い。電車に乗ったのは確か1時前だったのに、姫路へ着いたら間も無く2時という時間。慌ててしまった。先に明石でゆっくりと竹久夢二の展覧会を観ておくべきだったかな?と、後悔したけれど、ひたすら大手前通りを歩いてお城の近くまで。公園を突っ切って近道と思しき角度で突き進む。目指す市立美術館が見えてきた。 携帯でお城と、ポスターを撮ってみたけれど、お城は思う様にいかない。遠過ぎるせいもあるのかな? ひとしきり葛飾北斎の世界に浸かり、今度は明石市を目指して元来た道を歩く。途中で右へそれてお城の中を歩いてみる。そして、写したのが人だかりしているお城の写真。 姫路駅構内で相棒さんが好きそうなお煎餅のお店があったのでお土産にと二袋買い求め、切符を買って目指す明石市へ。 やはり、連休中じゃなく、日曜日に来たのが正解だったとつくづく思う。夢二の世界を堪能して、ちょっと喉を潤したくなって、横の喫茶&レストランで、美味しいオレンジケーキとアイスコーヒーを。うっかりとこの画像はありませんが。そして出たところで見つけた、マジックローズと書かれた札が立っている花。私にはもの珍しく思わず携帯を。 ひたすら明石駅を目指して歩いていたら、行きのときにも監督の声が飛んでいた、小学校のグランドに少年野球と思しき少年たちがグランドに散っている。思わず立ち止まってしばし観戦。ただ、道路を隔てていたので、これも距離的にとても無理なものがあったけど。監督の褒め方というのがとても素晴らしいな。と思いながら記念に一枚。。。 さて、肝心の絵の感想。。。北斎の場合は約200年は前になるのかな?それにしても凄い技術を持った人なんだなぁ。と、改めて感心させられるばかり。芸が細かい。細か過ぎる。。。夢二さんのはやはり独特の目の表情が忘れられない。ただ、本の表紙を飾ったのや、楽譜の表紙が展示されていて、とても新鮮で驚いた。それぞれに思う存分堪能することが出来て本当に良かった。やはり、こうした展覧会は一人で心行くまでじっくりと鑑賞するのが一番かな? 日曜日の夜は「義経」も楽しみの一つ。タイピングしながら左側においているテレビ画面にチラチラと目をやりながら。。。なもので今から入浴タイム。またまた皆さんのところへはお邪魔出来ずにいますが、取敢えず入ってから考えることにします。ごめんなさい。ただ、明朝は母を眼科医院へ連れて行く約束にしているのと、調理師の国家試験のことを問い合わせ出来る栄養士さんが、洲本保険所へ転勤になったことで、母を乗せたままそちらへも立ち寄ることになるので、またもやサイトには入れないかもしれませんが。。。と、言い訳ばかりで本当にごめんなさい。
2005.04.24
コメント(2)
-
今日付けの地元紙の『正平調』というコラムに。。。
住まいから、家族関係のことについて述べられていて、とても興味を惹きましたので、そのまま引用させて頂きます。 『30年も前になろうか。コーヒーのCMに登場して以降、その有名なキャッチコピーから「違いの分かる建築家」といわれた。前日亡くなった清家清さんのことだ◆住まいの変革者、インテリア革命家と持ち上げられる一方でなお日本の伝統にこだわりすぎるとの批判も受けた。最近、この「清家住宅」が見直されている。先日の本紙文化面にも、芹沢俊介さんのそんな評論が載った◆清家住宅の“違い”を一言でいうのは難しいが、要は、家全体をワンルームとみなすことだった。プライバシーも重要だが、こと夫婦間では不要との立場を取った。夫婦一体という日本の伝統的家族像を全面に出した◆もう一つの違いは、一部屋になったスペースを臨機応変、幾通りにも使い分ける工夫である。これを「舗説(ほせつ)」といった。都市の狭い家でも日本人の暮らしに合った住空間を随時、作りだせる。神戸出身らしく、欧米のモダンデザインを追いながら、伝統、和風にこだわった◆その“モデルルーム”が東京の自宅だ。一度、見せてもらった。畳に車輪がついていた。自由に動かし、舗説を容易にするためだ。台所は部屋全体が見渡せる中二階に。ご自身の仕事場は、その下の反地下部。妻の下が最も落ち着くといっていた◆家族関係の希薄化は、住構造のせいともいう。適度なプライバシー空間と、適度な解放空間。住まいの機能性を高め、家族の絆も強める。清家住宅の見直しは「あらゆる違い」に気付こうとする、時代の必然かもしれない。』 今日は義姉宅の7回忌の法要があって、先ほど夫と姪夫妻、姪の娘が出かけたので、私はこんな天気の良い日に家にじっとしていられなくて、ちょっと橋を渡って姫路まで行こうと思ってます。北斎の展覧会があるし、姫路の新緑をこの目で楽しみたいし。帰りは明石で夢路さんにも逢ってこようと思います。というわけで、またもや家出ということになります。お伺い出来ないままですが、わがままな管理人をお許しください。一人で歩いて歩いての一日を楽しんで来ます♪
2005.04.24
コメント(4)
-
先日から紙上を賑わせている。。。
「特勤手当」について、22日付の地元紙の社説欄にはこんな風に述べられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『「公費」の感覚がないのか 「時代に合わないものが多い」と批判が集まっている地方公共団体の特殊勤務手当だが、兵庫県内のいくつかの自治体では、支給の金額や方法を条例に定めず、規則だけで運用していることがわかった。 地方自治法には、給料や手当、旅費の額や支給方法は「条例でこれを定めなければならない」という規定がある。議会のチェックを受けない「規則」による運用は、違法な公費支出である可能性が高い。 本紙の調査では、西宮、川西、三田、高砂、赤穂、洲本の6市が、いずれも40年以上前から、条例に基づかない特勤手当を支給していた。6市の合計額は、2003年度だけで約8億7千万円。とくに金額が大きい西宮は、1市だけで10年間に約50億円を支給していた。 これは、各手当の内容や金額の妥当性を論じる以前の、根本的な欠陥である。 職員の給与や給付を条例で定めたものだけに限る「給与条例主義」は、地方自治法だけでなく、地方公務員法でも明確に規定された、公務員の“常識”である。「知らなかった」では済まされない。何故、何十年もの間、見過ごしてきたのか。 兵庫県は近く、県内前市町の特勤手当の実態調査を行うという。条例の有無だけでなく、対象や金額、支給方法も含めた全体像を明らかにしてもらいたい。 いや、それ以前にまず、各自治体が、地域の住民に対して、自主的に情報を公開すべきではないのか。 特勤手当の種類や額は、それぞれの自治体が地域事情に合わせて設定することで、全国一律である必要はない。とはいえ、住民の理解や納得を得るのが大原則である。行政当局が、その手当が本当に必要だと思うならば、条例化の手続きをとり、堂々と住民に指示すればよい。 ただし、条例にあれば、全て正当化できるわけでもない。条例に基づく特勤手当であっても、社会常識からずれていたり、ほかの手当や給与と二重取りになっているものがたくさんある。規則から条例に、という原則は当然として、手当そのものの必要性を問い直さなければならない。 それにしても、一連の職員厚遇問題に向き合う自治体の姿勢には、緊張感がなさすぎる。自分たちの給与や手当が公費で賄われていることの意味を、もっと自覚してもらいたい。議会の責任も重い。 表向きは、行財政改革の必要性を声高に叫びながら、自分たちの懐にかかわる部分ではお手盛りだらけ、というのでは、住民の信頼が失われていくばかりだ。 先ほど、公民館講座となった、「コーラス」の申し込みと、「源氏物語講座」というのに興味を引かれたので、南淡の方まで行ってみた。給油の必要もあったので、以前お世話になっていたスタンドへも寄ろうと、先ずは「コーラス」の申し込み。これは地元の公民館。そして一路南淡へ向けて車を走らせる。給油が終って南淡公民館へ。ところが事務所には誰も居ない。折角出かけて来たのに。連絡のしようもない。月曜日が休館なら勤務の途中に立ち寄るしかない。何だか。。。折角南あわじ市ということになって、市全体に募集がかかったからと興味を惹いた講座の申し込みをしようと出かけて行ったのに。。。 特勤手当とは直接関係はないにしても、窓口の職員は一人ぐらい配置して欲しい。土曜、日曜にしか動けない人だっているんだから。ヤル気をそがれてしまった感じで、とても残念。 私が郵便局を辞めて既に22年になろうとしているので、事情は随分違うかも知れないけど、郵便局自体は独立採算制を取っていたから、国民の税金はビタ一文使うことは無かった筈。(少なくともそう思いたい)ただ、私が勤務していたのは無集配特定局だったから、赤い自転車が一台。。。と、私は事故で走るときは局長の奥さんのママチャリを愛用していたけど。 ボールペンも替え芯を買って交換していたし、スティックのりみたいなのは使えなくて、大きなプラスティックの入れ物に入ったのりを買ってそれを、使い切ってしまったクリームなどの入れ物に入れ替えて使っていた。勿論、お客様にもそういったのりを使っていただくことに。現金書留封筒などの封をするのに、こうしたのりは必要だったから。 届いた郵便物の封筒は内部で使うときは必ず2回は使いまわしをしていたし、勤務していた頃は貯金・保険の窓口は正午から30分間完全に閉めていたから、勿論そのときは窓口は消灯。 備品とかに使う経費は極力抑えていたと思うし、それが当たり前だったし、裏面が白い紙などは必ずメモにしていた。。。紙1枚買うのさえも金額にすればかなりなものだったと思う。 給与面での削減が無理なら、せめて経費での削減は出来ないものなのか?と。ボールペン1本に至るまで、市民の血税で賄われているのだから。ここは、出せる膿は全部出して考えを改めて欲しい。
2005.04.23
コメント(4)
-
一昨日届いた郵便物は。。。
「淡路音楽祭」で歌うための楽譜だとばかり思い込んでいて、今日になって開いてみたら、何と「第九合唱団員募集」チラシと申込書。申し込み期限は5月10日までとなっている。私が参加している、こちらの地区の合唱団の参加募集のチラシは、やっと今日になって折り込みされていた。 今年から公民館講座となって再出発することになり、南あわじ市全市に募集をかけたいとのことで、「印刷が出来上がるまで待ってください。」だったため、全く動きが取れなかった。講座が始まるのは5月から。で、コーラスのみ、先生のご都合で、5月だけは第二、第三週の練習となることは前回の「淡路合唱祭」の時点でわかっていたこと。申し込み書は公民館へ赴かないといけないので、窓口にもその「第九」の募集チラシは置いてあったらしいから、歌いたいと思う人なら目にするだろう。とのこと。こちらのコーラスの練習が始まるのが5月の12日ではどうにもならない。。。さて、私たちのグループからは何人が参加することになるのかな?と、その前に、肝心のグループへ顔を出すかどうかもわからないのですが。 毎月第一、第三木曜日の夜8時から。講師の先生は前年と同じだということだけど、始まっていきなり8月6日に行われる「淡路音楽祭」の練習となるので、初心者の方は随分戸惑うことになりそうな。。。練習するのは「動物のカーニバル」サン・サーンスが作曲した、「動物の謝肉祭」から組曲風にアレンジされた、とおっても素敵な曲。 実は、今新たに参加し始めたコーラスグループに以前参加していたとき、洲本吹奏楽団とジョイントで演奏したことがある。とっても素敵にアレンジされていたけど、アレンジされた先生は既に他界。今度はどんな楽譜を使うことになるのか、私は練習用にその楽譜が届いたとばかり思っていたのになぁ。 「淡路音楽祭」ではいくつかのグループが合同で演奏することになっていて、普段の練習はおのおののグループで。何回かは合同練習の時間も取られそうな。と、そこまではまだ話は進んでいないけど。ここへ「第九」の練習が加わると。。。何だか、今年はコーラス三昧の年になりそうな。。。 「音楽って素晴らしい♪」というか、最初はイラク問題に関して新聞記事を見つけては載せていくつもりで始めた日記。タイトルは「まあちゃんて?」ということにして、サブタイトルを「音楽って素晴らしい♪」にしていたのが、結局日記がそのままブログという形になって日記として書いていたイラク問題に関しての新聞記事やら、ブログやらごっちゃになってしまいましたが、今日は久々に地元紙の「正平調」というコラムでイラク問題に関して書かれていましたので、そちらのブログに書いてみました。お時間ありましたら、そちらのブログも覗いてみてください。 さて、昨日は『然心塾』(サイト名にもなっています)を主宰しておられる、角田宏先生の「環境心理学」の授業。「環境心理学」というのは、本当に新しい分野ですが、1970年になって、世界の関心が公害問題へと向けられたことがきっかけになって起こった学問で、人間と環境を一つの系として扱う実証科学{様々な人の作用(感情・行動・経験)を関連させた科学的知識の発展を目指す}とあります。早いハナシが“快適な施設を作るために”とでも言いましょうか。良かったら皆さんもお訪ねしてみてください。。。
2005.04.22
コメント(2)
-

4月20・21・22日共通のお弁当
献立は、肉団子甘酢あん、フルーツサラダ、菜種和え。添えの野菜はレタス、果物は、2番目にフルーツサラダが入るので、つきません。◆肉団子甘酢あん。。。材料は、市販の肉団子、玉葱、人参、ピーマン。市販の肉団子は一人当たり5個ずつ、素揚げにする。玉葱は皮を剥いて細切りに、人参は皮を剥いて、玉葱と同じぐらいの細さの千切りに。ピーマンも同様に種を取って同じぐらいの千切りにしておく。野菜を軽く炒めて砂糖、酢、醤油を合わせた甘酢を加え、野菜がしんなりしたところでと水溶き片栗粉でとろみをつけ、揚げた肉団子を加えて味を馴染ませる。◆フルーツサラダ。。。材料は、マカロニ、きゅうり、バナナ、缶詰のみかん。マカロニはたっぷりのお湯で茹でておく。きゅうりは薄切りスライスにして、塩を馴染ませてしんなりさせてから、塩分を洗い流して水気を切っておく。バナナは、1%の塩水につけて変色をふせぎながら3ミリぐらいの厚さに切り揃えておく。みかんの缶詰を開けてシロップは捨てて水分を切っておく。材料を混ぜ合わせて、塩、コショー、マヨネーズで和える。◆菜種和え。。。炒り卵を菜の花に見立てて、ほうれん草のお浸しに混ぜ合わせたもの。材料はほうれん草、卵。先に卵を割りほぐして炒り卵を作って冷ましておく。ほうれん草を食べ易い長さに切って水にさらし、たっぷりのお湯で茹でて、冷水にさらし、水気を切って冷めた炒り卵と混ぜ合わせたのを、醤油とみりんで味を調えた合わせ醤油を加えてお浸しにする。千切ったレタスを敷いて、肉団子の甘酢あんを。細切りにした野菜をたっぷりかけて。左側にはマヨネーズで和えたフルーツサラダを。レタスの量にゆとりがあれば、こちらにもレタスを敷く。3番目には菜種和えを。フルーツサラダに入れるバナナは余り薄く切り過ぎても扱い難いので、5ミリぐらいが良いのかな?1本切る間だけ塩水につけておいて、水気を切りながらボールに取って行って、あまりビチャビチャにならない様に気をつける。菜種和えは、ほうれん草の水分が出てしまうので、盛り付ける寸前に醤油を合わせる。メインの甘酢あんの味は酢が利いているので、他の味が幾分薄く感じられるかな?お漬物は相変わらず桜漬け。色合いが綺麗なので重宝するのですが、母などは一番食べ難いのだそう。たまには変えた方が。でも色合いが。。。 今日は臨床福祉心理士の2回目の講習。朝は6時58分、最寄りのバス停発の高速バスに。だから起きたのが5時半。あたふたと用意をして、結局PCを開く間も無く家出。幸い、夫が6時には起きてくれたので、夫が食べた分の後片付けも済ませることが出来た。洗濯物は昨夜のうちに片付けておいたのでやれやれ。 今日は「環境心理学」なる単位。耳新しい言葉だし、確かに、一口に「環境」といっても余りにも範囲が広過ぎる。しかも、宿題の答えが出せる様にということで、正午の10分前には早退しなければならない私のために、先生も大慌てで何とか宿題が解ける様に講義を進めてくださる。 たかが10分、されど10分で、この時間に出ないと、お手洗いにも行けなくなってしまう。そそくさとパンを買って、朝自販機で買ったお茶と一緒にバスの中でバスが発車するまでの間に食べてしまう。本当に慌しい。 さて、今日の講義の中で気になったこと。それは勿論環境問題のこと。あれは串本町でしたか。何か珍しいイソギンチャクが見つかったということ。ただ、これは熱帯の国でしか見つけられない種類なのだそうで、それだけ海水温が上がったせいだということ。ということはそれだけ地球温暖化が進んでいるということ。毎年かどうか、放映されるNHKの「紅白歌合戦」の途中で出て来る南極越冬隊のシーン。ここ数年は様子がまるで違ってて、氷に閉ざされていた筈の地面に土が表れ、草の芽が出ているということ。こんなにも地球温暖化は進んでいたのですね。 1970年といえば、大阪で万国博覧会が開催された年ですが、同時に、環境問題にも目を向け始められた年でもあったんだと。 別の意味で、限りある資源の話。全ての量が10としたら、既に7までは使い尽くしているのだとか。 一時、森林破壊に繋がると、割り箸や、紙製品の使用を禁じるみたいな動きがあったみたいですが、何もしないで放っておくことの方が、ずっと森林破壊に繋がること。森林保護が保たれてこその森林破壊打破であること。などなど。。。 ガソリンスタンドへ行けば軒並み「原油価格高騰」のポスターが目につきます。一体どこまで高騰が続くのか、全く分からない状態。でも、淡路島などの場合は、車は決して贅沢品じゃないんですよね。10分待てば次の電車が来る。といった様な都会では、ある意味車は贅沢品扱いになるかも知れませんが。となれば、やはりクリーンな燃料を使う術をいち早く取り入れなければ。。。 昨日は昨日で、淡路島の最も南の海岸線をひた走りに走るコースの配達を担当して、運転に疲れ、今日は今日で結構厳しいスケジュールでしたので、書き込んでくださった人へのresも遅れてしまうと思いますが。。。申し訳ありません。
2005.04.21
コメント(0)
-
開いた口が塞がらない。。。
とは、このことだろう。と、その前に、今朝方起こった、福岡西方沖の地震。余震とみられる揺れが何度も襲っているみたいですが、皆さんのところには被害などはありませんでしたでしょうか。 さて、昨日も報道されていましたが、公務員厚遇はここまでも。ということで、地元紙には、こんな風に載っていました。 『徒歩でも通勤手当て 総務省調査 274市町村、旧緑町も 全国の274市町村が、徒歩で通勤する職員にも通勤手当を支給していることが19日、総務省の調査で分かった。 調査は1月1日現在で、支給している市町村は全体の約1割に当たり、最も高いのは月額5750円だった、地方公務員の手当をめぐっては、“お手盛り”などの批判もあり、総務省は運用の見直しを求めた。 調査は、地方自治体に不適切な諸手当の支給の見直しを要請している同省が初めて実施した。 274市町村の内訳は市が141、町村が132で、政令指定都市では北九州市だけが支給していた。都道府県別では愛知が38市町村とトップ。福岡が28、埼玉が23。北海道と東北6県など計16道県の市町村は支給していなかった。兵庫では西宮市、川西市、猪名川町、緑町(合併した現南あわじ市、現在は廃止)が支給していた。 国家公務員の場合は通勤距離が片道2キロでは通勤手当の対象にならないが、274市町村のうち244市町村が2キロ未満でも支給していた。支給額が最も高いのは愛知県碧南しの月額5750円で、安いのは北九州市の同100円。多くの市町村が千~3千円だった。』 何とまぁ。そして、社会面にはあしき習慣半世紀放置 西宮市特勤手当て 「白紙委任の典型」 オンブズマン当局と議会を批判の様な見出し。そのまま記事を引用させて頂きます。 『半世紀以上、条例に基づかず、規則に「白紙委任」した特殊勤務(特勤)手当の支給を続けていた西宮市。担当者は「特勤手当は多岐にわたり、すべてを条例化すると膨大になる」と釈明した。新たに特勤手当を設ける場合は、事前に市議会の制服議長らに説明していたともいうが、各地で同様の問題に取り組む市民オンブズマンなどは「白紙委任の典型」と批判。「公金意識を欠き、チェック機能も働いていない」と市当局と議会の責任を指摘している。 ■問題視せず 西宮市職員の給与条例ができたのは1951年。以来、特勤手当については支給額や種類が明示されないまま、一度も改訂されていない。 「庁内でも問題視されることはなかった」と同市職員課。その理由として、条例化すると膨大な量になる→規則も公開しており、市民が点検できるーを挙げた。 だが、特勤手当の種類が多い兵庫県や神戸市などは細目まで条例化している。市長の専決事項となる規則は、「密室で決まるため、労使癒着の温床になっている」と専門家は指摘する。 ■議会 同課によると、市は組合との妥結内容を毎回、市議会の正副議長、各会派幹事長に報告。「新たに特勤手当を設けるときも議会の理解は得ていると認識していた」と話す。 これに対し、魚水けい子議長は「条例化の必要があるとは知らなかった。議長も反省しなければならない。手当の細かい内容は議員もよく分からないのが実情。条例化すればきちんと点検できる」。別の市議も「本来は議会で議論すべき内容を馴れ合いで決めていたことになる。早急に条例化すべき」と話した。 ■丸投げ 「規則への丸投げ。白紙委任の典型だ」。名古屋市民オンブズマンの新海聡弁護士は指摘する。 条例に規定すべき内容を規則に「白紙委任」したケースは、地方自治法違反として各地で訴訟となっている。 同オンブズマンが02年、名古屋市が条例で金額規定していない市議の費用弁償半年分(約5千万円)の返還を求めた訴訟(最高裁で係争中)。違法性に気付いた同市が起訴直前に条例化に踏み切るなどしたため、一審はオンブズマン側の敗訴となった。 しかし、判決は「支給額は予算の範囲内で市長が定める」とした条例を「地方自治法の趣旨に反し無効」とも判断した。 「水面下の調整で税金の使い方を決める手法は法律上、認められていない」と新海弁護士。「議会も市当局も公金という意識が欠如している」としている。(企画報道班)条例と規則…条例は憲法94条で「地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定できる」と規定され、議会の議決が必要。一方、条例の下に位置付けられる規則は、地方自治法15条で「地方公共団体の長は法令に反しない限り、その権限に属する事務の規則を制定できる」とあり、首長の専決事項。』 そして、職員互助会への公費支出 姫路市に税務調査なる見出し。こんな風に載っていました。 『公務員の厚遇問題で、姫路市が姫路税務署の税務調査をうけていることが19日、分かった。 職員の掛け金と市からの公費で運営される福利厚生組織「市職員互助会」について、退職者への退職生業資金や永年勤続職員への旅行クーポンなどの支給が、給与所得とみなされて課税対象になるかどうか、検討しているとみられる。 同市人事課によると、調査は今年2月に始まり、2001年度から3年分の決算書などの帳簿類を提出。互助会事業全般が対象になっているとみられ、同課は「当局の調査結果を待ち、適正に対処したい」としている。 同市は同互助会に対し、04年度で約2億2千7百万円を補助。退職生業資金については、03年度で退職者132人に計約1億千3百万円を支給した。ほかにも、退職時などに旅行クーポン支給などを行っている。 批判の高まりを受け、現在、互助会の事業を見直し作業中。05年度予算では公費支出を約1億円減額した。退職生業資金も04年度の支給を一時凍結している。』 今日の随想欄には、川柳作家のやすみりえさんが桜降ると題して、こんな風に述べられています。さて、福岡では相変わらず余震が続いているみたいですが。。。 『今年も夜桜の下で“お花見句会”を開きました。 詠む人の個性によって桜の咲き方もさまざま。メンバーの詠んだ句では「春の風ふわりと吹いて髪飾り」。これは、はらはらと舞い散る花びらが女の子の髪にちょこんと乗っかった可愛らしい様子です。他にも「なぜ散るのさくら舞う中まちぼうけ」といった春の陽(ひ)の切ない想いを詠んだ句も。咲き方だけでなく散り方もさまざまですね。 全部で30句ほど集まった桜の句の中で私が秀句に選んだのは「妖艶を潜ませている冬の枝」という一句。満開の桜の華やかさに思いを重ねて詠んだ句が多かった中で、この句は冬の厳しさをじっと耐えている桜を表現しています。だからこそ満開の姿はこんなにも美しいのだと、短冊から目をあげて頭上の桜をじっと眺めたひとときでした。 震災から10年目の神戸の街にも美しい桜が咲き誇り、春のうららかな街並みを歩きながら私はこんな一句を詠みました。 桜降る 大地の温み 踏みしめて(りえ) 私は桜を眺める時、その木の増したからぐっと見上げるのが大好きです。満開の桜にたっぷりと包まれているような木がするのです。神戸の街にも、悲しみの雨が降るばかりではなく柔らかな心温かい花びらが降り注ぎ、あの震災からずっと頑張ってきた人々を包んでくれますように。 あの日、失ってしまったものはあまりに多すぎるけれど、それに負けずに神戸の地からたくさんのことを発信していきたい。そんな願いを込めた私の春の一句です。』 この「やすみりえ」さんのことはNHKテレビの午前11時過ぎから始まる番組の中で、1日だけ川柳を扱う日があって、それで顔を覚えました。確かに、桜も降るんですね。 さて、郵政民営化が叫ばれて久しいのですが、やはり、利権に絡むことで今になって反対を唱える議員さんたちが多いのでしょうか?私自身は、『逓信』とか『郵政』という言葉は残しておいて欲しいと願っています。ただ、郵便貯金や簡易保険で扱うお金が全部特殊法人へ流されているとしたら、そして、その特殊法人へ天下りしているのが議員さんたちだとしたら。。。あながち小泉さんがやろうとしている改革ははずれではないのかな?とも。 ここ32年の間に結婚という事情があって、すっかり変わってしまった、アマチュア無線の従事者免許証。昔は自分の写真と免許証に割り印がしてあって、桜のマークに郵政大臣の文字。値打ちがあったんだけどなぁ。今は、ラミネートになっちゃったもんなぁ。。。“逓倍”という言葉に使われる例の「逓」と言う文字。。。電波とは切っても切れない文字なんですよね。昔は逓信省だったのがいつの間にか郵政省に、そして、今や総務省だもんなぁ。せめて郵便局の名前は残しておいて欲しいなぁ。
2005.04.20
コメント(0)
-
ものづくり現場に広がる派遣、請負労働。。。
今日付けの地元紙の地域総合版のニュース&ニュース欄では、こんなタイトルが目を惹きましたので、そのまま引用させて頂きます。 『昨年3月の法改正で製造業への労働者派遣が解禁され、ものづくりの現場にも派遣や請負など非正社員の活用が広がっている。1つの職場で習熟を重ねるのと違い、派遣会社などの指示でさまざまな仕事に携わる。企業側は人件費を削減でき、働く側にも正社員やパート意外の道が開けるのが利点だが、兵庫県内の現場をあるくと労使双方の不安も聞こえてくる。(経済部 長尾亮太) 企業側 人件費削減に利点 技術蓄積難しく 労働側 好きな仕事選べる 生活の不安、常に 県内にある三菱電機の工場でモーターの組み立てに携わる中年男性は、請負会社と契約している。8年前、病気で京都のホテルを大社。回復したが復帰できず、請負労働を選んだ。 立ち仕事はきついが、工夫して作業時間を縮めるなど難しい工程に挑み、「やりがいを感じている」。だが契約は、請け負った業務が終わるまで。別の向上で携帯電話の部品を検査していたときは、生産終了で契約が打ち切られた。 「仕事の技術の蓄積も、ある日突然なくなる」-。そんな不安を、常に抱える。ボーナスや退職金、昇給はなく、経済的に子育ても難しいため、「若者は正社員になりたがっている」。 派遣労働の場合、1年間働けば受け入れ先は正社員として雇い入れる義務が法で定められている。しかし請負労働にはそれもない。 相生市の造船業・青木鉄工。石川島播磨重工業相生事業所の造船撤退で、かつて2百人いた正社員は50人に減った。 一方、請負や派遣などの非正社員は現在、34人。業績や仕事に応じて人数を変えるため、重要な工程は任せない。森田文蔵社長は「ものづくりを肌で学んだ社員が減り、技能を伝えていけるのだろうか」と危機感を抱く。 だがアジア各国との競争は激しくなるばかり。社会保険料負担などが不要な点は大きな魅力だ。目の前の収支を考えれば、非正社員依存の構造は変えられない。 派遣労働の利点を使いこなすのは、伊丹市のメーカーで出荷に携わる女性。派遣労働暦が10年近い。神奈川県出身。販売や事務、半導体製造などに携わり、昨年末に伊丹へ。正社員としての就職は難しくても、派遣なら仕事は多いという。 雇用契約は派遣先でなく派遣会社と結ぶため、派遣先の環境改善を訴えやすいのも魅力といい「人間関係など派遣会社が間に入って解決してくれる、休日の新生もしやすい」。 賃金も「年齢に関係なく仕事の内容で決まる」ので不満はない。一番満足なのは「いつでもどこでも働け、やりたい仕事を選べる」点だ。 社員が一企業に定年まで勤め上げ、熟達した技を次代に伝える。日本経済の成長を支えた製造業の構図だ。 だが退職社員の補充として派遣や請負など非正社員の活用が製造現場で広がれば、社内の技術蓄積は難しくなる。 2002年の県内の非正社員は約77万人。1997年から14万人増えた。一方、正社員は約144万人で16万人減った(総務省調べ)。目先の収益改善へ企業がリストラを進めた結果だが、働き方の変化に合わせた次代の発展の構図は、まだ見えない。 請負労働…請負業者が別の企業から発注を受けた仕事に携わる働き方。発注企業とは契約関係がないため、発注企業による指揮命令や労務管理は禁じられている。一定期間働いても、受け入れ先が正社員として雇い入れる義務はなく、派遣同様、契約後も雇用される保証はない。 派遣労働…派遣業者に雇われ、派遣先の指示を受けて働く形態。派遣先は、一定期間(製造業は1年)を超える場合は正社員としての雇用を義務付けられる。仕事内容や労働条件などを契約で明確にでき、希望に応じた働き方ができる反面、短期の場合、期間後も雇用される保証はない。』 そして、今日付けの社説欄では、反日デモを扱って、経済活動に波及させるなと述べられていましたので、引用させて頂きます。 『中国で広がる反日でもは3週目の土、日もさらに拡大し、日本の進出企業への影響も心配される事態となってきた。 中国最大の経済都市・上海市で、日経コンビニの店舗が襲撃を受け、一時休業した。日本料理店や外食チェーンも投石などの被害に遭った。デモに遭遇した日本車は物を投げつけられたり、横転させられたりもした。 広東省にある電子部品メーカー、太陽誘電の現地法人向上では、2千人の労働者による大規模なストライキがあった。労働者らは日本製品ボイコットや歴史教科書問題、日本の国連安全保障理事会常任理事国入り反対などを訴えた。 工場の窓ガラスが割られ、食堂施設が壊される騒ぎになったため、工場側の通報で治安要員が鎮圧にあたり、装甲車も出動したという。 反日デモがここまでエスカレートすると企業としても手の打ちようがあるまい。破壊活動やストライキは企業活動とは無縁の原因で起きており、嵐の過ぎるのを待つのみである。 社会主義国である中国での経済活動に特有のリスクを「チャイナ・リスク」という。日本の企業も中国進出に当ってはこれまで、ある程度の覚悟をしていた。それは一方的な政府の方針変更で被る不利益などだ。 だが現在、市場経済化を進める中国政府が進出企業に打撃を与えるような行動をとることは、ほとんど考えられない。新たなリスクとも言うべきは、今回のような民衆の暴動による企業活動の不安でもある。 そこでデモを先導している中国の若い人たちによく考えてもらいたいのは、今、行っていることが果たして中国の国益になるかどうかということだ。 不買運動の対象になっている日本製品の多くは中国人労働者が生産した「メード・イン・チャイナ」の製品である。 日本と中国や今や経済的に切っても切れない関係にあり、不買や排斥運動は自らにはね返ってくる問題でもある。 中国が今後も高度成長を続けるのに、日本などの積極的な投資が必要なことは言うまでもない。特に資源多消費型の中国の成長の阻害要因にもなっている環境問題の克服には、省エネ技術をはじめ日本の協力が欠かせないはずである。 カントリーリスクのある国への投資に企業が二の足を踏むのは日本に限らず、やむを得ないことだ。政治的な問題と経済とを区別する冷静な対応を求めたい。』
2005.04.19
コメント(4)
-

4月18・19日共通のお弁当。。。
献立は、エビカツ、焼き豚入り和風サラダ、焼き豆腐の胡麻味噌かけ。添えの野菜は、エビカツにレタス、プチトマト。果物はキウイフルーツ。◆エビカツ。。。市販の冷凍のものを揚げるだけ。◆焼き豚入和風サラダ。。。材料は、焼き豚、キャベツ、きゅうり、人参。焼き豚はフライパンで軽くあぶってキャベツと同じぐらいに切り揃えておく。キャベツは、5ミリ幅で3センチぐらいに切ったのをたっぷりのお湯で塩茹でして、水気を切っておく。きゅうりは薄切りスライスにして、塩をまぶしてしんなりしたら、水で洗って塩を抜いて水気を切っておく。人参は皮を剥いて大き目の千切りにしたのを、塩茹でして水気を切っておく。具材を混ぜ合わせて、フレンチドレッシングに炒り胡麻、薄口醤油で味を調えたので和える。◆焼き豆腐の胡麻味噌がけ。。。焼き豆腐は4つ切りにして、昆布を敷いた水から入れて軽く茹でておく。炒り胡麻、味噌、砂糖、みりんなどを合わせて胡麻味噌を作り、茹でた焼き豆腐に添えて盛りつける。4つ切りにしたキウイを置いて色紙切りにしたレタスを敷いたところへエビカツを盛りつけて彩りのプチトマトを飾る。左側には、焼き豚入り和風サラダを。3番目には焼き豆腐の胡麻味噌がけを。エビカツだけではメインとしてはかなり物足りないので、レタス、プチトマトなどでサラダっぽく盛りつけたけれど、どうかな?焼き豚サラダは何が何だか分からない画像になってしまいましたが、フレンチドレッシングに、胡麻と薄口醤油を加えるところが和風っぽい?3番目には焼き豆腐の胡麻味噌がけを。かけるとお弁当の蓋にくっついてしまうので、空いたスペースへ。プチトマトの赤が目を惹くお弁当に。
2005.04.18
コメント(0)
-

今年も咲いたよ♪
いつも素敵な花の画像を送ってくださる、“しまちゃん”に教えて貰ったと思ったんだけど、名前忘れちゃって。。。でも、今年も咲き始めたのを見つけて、思わず携帯を近づけてみました♪ 独創的な国語教育研究家 大村はまさん死去 98歳などと地元紙の三面記事の隅っこに載っている。。。 『新聞、雑誌を教材に取り入れるなど、独創的な授業で知られた国語教育研究家の大村はま(おおむら・はま、本名浜=はま)さんが、17日午前2時50分、くも膜下出血のため横浜市緑区の横浜新緑総合病院で死去した。98歳。横浜市出身。 1928年に東京女子大を卒業後、旧制諏訪高女(長野県)などの教師を歴任。戦後は、80年に退職するまで、東京都内の公立中学校の教壇に立ち「生涯一教師」を通した。 課題(単元)の取り組みに新聞や雑誌の切り抜きを使い、学級新聞の制作で読んだり書いたりする力を付けさせる独創的な授業は「大村単元学習」と呼ばれ、教育界に影響を与えた。教え子は5千人に上るともいわれる。 63年、教育界で功績のあった人に広島大が贈るペスタロッチ賞を受賞、72年から大村はま国語教室の会を主宰し、後進の指導に当たった。著書に「大村はま国語教室」「授業を創る」「教育に魅力を」など。』と紹介されていました。独創的であれ何であれ、読んだり書いたりする力を付けさせることに力を注がれたということに、とても注目したいと思います。やはり、最終的にはこの読んだり書いたりする力がものを言うのではないでしょうか。受験にしても、問題文が読めない、理解出来ないのでは答えを導き出すことは出来ません。勿論、計算力も必要です。。。惜しい人がまた一人。。。心からご冥福をお祈りします。 NHKの朝の番組で、血圧のことを取り上げていたと思ったら、先ほどから「ダンス体操」なるものが始まった。私の左側にあるテレビからは、森山直太郎(漢字間違えていたらごめんなさい)さん歌う「さくら」が心地良く聞こえてくる。何と、その歌に合わせて、本当に気持ち良さそうに身体を動かしている。ダンス体操。。。私には、歌を聴いている方が気分良いけれど、この歌に合わせて体を動かすことを考えられた人も凄いなぁと。歌詞にぴったりの身体の動き。参った!これなら、全く苦にならずに身体を動かすことが出来そうな♪
2005.04.18
コメント(0)
-
地元紙の子育て欄で。。。
「石田ひかりの まあるい子育て」というコラムを見つけた。これが何と15回目。しかも、今回が最後。。。今まで全く気が付かなかったのが残念。隅から隅まで眺め回していたつもりだったのに、これは何としたこと、情けない。 これからもよろしくねとして、今日はサブタイトルに親の「仕事」と書かれている。そのまま引用させて頂きます。 『この子たちの幸せな未来のために、今、私たちがすべきこと、出来ることは何だろう。それを考えることが「命」をこの世に誕生させた私たち親の責任であり、何よりも大切な仕事だと思う。私は日々、そのことを考えている。 悲観的な考えばかりが浮かんでしまうのが現実だ。地球規模の問題には気後れしてしまいそうになるが、身の回りの小さな積み重ねが必ず結果に結びつくと信じて、あきらめてはいけない。 今、地球がおかしい。私たち人類に対して「怒っている」ように見える。それは戦争、異常気象、災害などの悲しい形で現れている、思わずテレビを消してしまうほど残酷なニュースも、毎日の様に流れている。私は毎晩、眠る前に心から祈る。何も恐れず、大の字になって眠る二人の娘の顔に、涙さえ浮かべながら。それほど私は平和に対する危機感と責任を感じている。 「この子たちの未来が、幸せでありますように。楽しいことがたくさんありますように。平和の世の中になりますように」。 日本も世界も、こんなに物騒になるとは想像もしていなかった。それだけに感じる驚きと悲しみ。どうか未来が今より平和でありますように。そのために、私たちが出来ることは何ですか?誰か教えて下さい。 二人の子供の「親」になった32歳の今、愛するものがあるほど人は強くなれること、それと同時に深い悲しみを背負う機会が増えたことを実感する。この子たちの存在が私にはかけがえのないものであり、心から癒され、見ているだけで泣けてくる。 小さな手で、ぎゅうっと握り返してくる力の強さ、何時間でも抱っこしてほしいとせがむそのエネルギー。汗びっしょりになっておっぱいを飲むけなげさ。私の人生で、ここまで私を必要としてくれる人があっただろうか。私は居場所をやっと見つけた。私はここにいよう。 娘を抱っこしながら、その温もりを抱きしめながら私は願う。毎日幸せありがとう。どうかどうか健康でいてね。お母さんも頑張るね。ずっとずっとよろしくね。(女優)』 そうなんだ、石田ひかりさんて、あの女優の石田ひかりさんなんだ。と、ここまで読んでやっと納得。。。頑張って~☆ 見過ぎれば非行原因になるタイトル、「テレビ」を考えるシンポ。放送倫理・番組向上機構の青少年委員会が開いたシンポジウム「テレビは子どもたちに何ができるのか」=東京都千代田区の千代田放送会館の写真入りで、こんな記事が載っていました。 『テレビが生まれて50年余り。NHKと日本民間放送連盟でつくる「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の青少年委員会が、テレビと子どもに与える影響調査から、番組内容や視聴時間の長さに酔っては、問題行動に発展しかねないことも報告された。 調査は、首都圏に住む約780人を対象に、小学5年生だった2001年2月から4年後の中学2年生までを追跡。喫煙、万引きなどの非行や、子どもだけでゲームセンターに行く「社会的ルール違反傾向」と、テレビや生活習慣、家庭環境、友人との関係などの関係を調べた。 その結果、出演者が笑いを取るために暴力を振るうシーンを認めたり、長時間テレビを見続けたりすることが非行へつながりかねないとして、テレビの間接的な影響も指摘された。 この調査結果を受けたシンポジウムでは、テレビの直接の影響だけでなく、生活習慣やコミュニケーションのあり方なども問題視された。千葉大の藤川大祐・助教授(教育方法学)は、子どもたちの就寝時間が遅くなっていることを「深刻な問題」として、テレビ局が大人向けに制作した夜の番組を子どもが見ることを放置する親を批判した。 テレビプロデューサーの大山勝美さんも、PTA活動に参加した経験を踏まえながら、「好きなようにしていいと甘やかすことを、自主性と錯覚している親が多い。子どもが将来、責任ある成人になるという自覚がない」と主張した。 一方、ジャーナリストの江川紹子さんは、携帯電話が普及したことで、目的の相手以外と話す機会がなくなることを例示しながら、「情報が増えたのに反比例して、人と人との生のコミュニケーションが減少したと思う」と懸念も。 また、テレビやインターネットなどの付き合い方について教育するメディアテラシーについて、藤川助教授は「学校の授業でかなり取り入れてきている。今後、メディアへの理解がさらに進めば、テレビとも賢く付き合えるようになるのではないか」と楽観的な見方を示した。 さらに、江川さんは「子どもたちが将来を考えるヒントになるようなものを、テレビはもっとたくさん提供してくれたら」と、テレビ局に注文した。』 子育て世代に“魅力的” 西宮市人口県内3位という見出しが目についたので。(但し、これは12日付けの地元紙になりますが) 『西宮市の人口が尼崎市を上回り、兵庫県内の市で3位に浮上したことが11日、両市がまとめた4月1日現在の推計人口で分かった。西宮は46万945人、尼崎は46万263人で、682人の差となった。 西宮は阪神・淡路大震災前の1994年は約42万4千人で、震災の年は約39万人に落ち込んだ。その後、マンションの建設ラッシュなどで子育て世代を中心に転入者が増加した。 一方、71年のピーク時は55万人超だった尼崎は、企業の市外流出などで90年に50万人を割り込み、98年には姫路市に抜かれ県内3位に。しは企業の誘致策を講じているが、人口増にはつながっていない。 西宮市企画総括室は「市の魅力が評価された」と分析、一方で、児童急増による校舎不足や保育所の待機児童問題の弊害も表面化しており、「住民サービスの質を落とさないよう努めたい」としている。(薮中伸一)』 人口が多いことが、そのまま住み易いかというと、問題も山積だったり。かといって少ないから良いとは言えないけど、これからの時代を担う子どもたちが健やかに育つ環境であって欲しいと願う。 テレビに関しては、私の場合は、演じる役柄に興味があったりするけれど、たまに行く機会があった、小児科併設の病院(亡父を点滴に連れて行った)などでじいっとテレビに釘付け状態の子どもがいたことを思い出した。ラジオならじっと見つめるなんてことはあり得ないけれど。。。そして、なぜかくだらない番組ほどボリュームが大きかったりする。静かに音楽を聴く。。。たまにはこんな時間があっても良いのじゃないかなぁ?テレビも良いけどたまには親子で新聞を読むとか、そうしたことも必要なんじゃないかなと。。。 ネットもそうだけど、大人向け、子供向けがあることも何か問題な気がする。万人向けの番組って無理なのかなぁ?と、一人で居るときはNHKをBGM代わりにしていたりする私ですが。CMのときにやたらとボリュームが大きくなって驚くことがあって、NHKなら大丈夫かな?と。ならラジオでも構わないわけですが。
2005.04.17
コメント(4)
-
美容院とマッサージと。。。
午後1時に予約を入れた美容院へ着いたのは12時半近く。幸い空いていたので直ぐに手入れをして貰えることに。本当にお天気が良くて、店内は明るくて気持ち良かった♪カットとカラーをお願いして、終ったのは3時前。駐車場で鍼灸院さんへ電話をしたら、午後5時ならということで、先日来母に頼まれていた買い物を済ませて一路実家へ。 母は一人でテレビの野球中継を観戦中。母のお気に入りは勿論ジャイアンツ。山深い土地のこととて、昔はテレビのチャンネルは奇数しか映らず、テレビ放映されていたのがジャイアンツの試合だったことにもよるのかな?何しろ、王、長嶋を搬出したチームなんだから無理も無いと言えば言えないことは無いけど。 私が台所へ行ってインスタントのコーヒーを入れて居間に戻ると、母は何故かテレビを消している。話がしたかったからかも知れないけど、私はお構いなく電源を。4チャンネルでは万田久子さんが刑事の役で登場している。 実家がある地区では20日の夜にご近所が集まって講をすることになっていて、4月は実家が担当。もてなすというほどのことは無いけれど、お寿司を出すことになっているらしく、その手配は出来たと母は安心しきっている。母に頼まれていたのはデザート代わりのフルーツが入ったゼリー。お茶を出すのも大変だと心配だけど、お茶の用意だけしておいて、後は来てくださった人に任せるのだとか。 先ずお茶を出して、お寿司そしてまたお茶、デザート、そして帰り際にはまた別の飲み物を用意するのだとか。一人では大変だと思うけど、皆さんが手伝ってくださるのなら。と私も居合わせたことはない。 女性ばかりが集まっての雑談は夜の11時を過ぎることもあるとか。井戸端会議に花が咲いて、知識の豊富さに驚かされる母。勿論、この席では、政治談議など先ず出て来ない。だから良いのか悪いのか。母はこの集まりをさも一大事の様に考えていて、随分早くから心配そうに「4月はうちだから」と何回も話してくれる。一人で住んでいる身には仕方がないのかな?買い物だって、行くとなればタクシーで出かけなければならないのだから。 隣家のご主人(神戸住まい)が亡くなったこと、父の妹が訪ねてくださったこと。などをひとしきり話して、時間も経ったので、私は鍼灸院目指して実家を出た。すると、駐車場には車が一台。施術中だといけないと思って、同じ道を行ったり来たり。約束の時間になっても事情は変わらないので、携帯で連絡を。 「車は構わないから来てください。」とのこと。何だか時間を損した気になったけど、肩凝りをほぐして貰いたくて来たのだから、そのまま帰るわけにもいかない。お喋り兼リラグゼーション兼。。。肩の凝りをほぐしてもらってスッとしたところで終了。 家を出たのが正午過ぎ。帰宅出来たのが午後7時前。夫には随分長い美容院だと思われているかも。。。
2005.04.16
コメント(4)
-
今年の子どもの日は。。。
亡義父の13回忌。来週は親戚の法要ということで、夫は朝から床屋へ行くと、何だかそわそわしている。午前10時にならないと始まらないからと、出かけてみたら、午後からの方が都合が良いとのこと。夫が午前中に居ないなら、私は午後からにしようと思って予約を入れたら午後1時。二人とも家を空けてしまうことになるけど、これは仕方が無い。 7回忌のときは。。。私には突然の入院だった。近所の人にもナイショだったので、大事な法要のときに居ないなんて。と、散々非難を浴びたらしい。オマケに、この7回忌と、親戚の葬儀が見事に重なってしまった。法要は早くから予定されていたし、仕方が無いので法要を済ませてから夫は悔やみに行ったらしい。 この騒動の中、私はただひたすら病院に。正直、助かったと言えばおかしいけれど、親戚が集まる席は何かと気を使う。法要前夜には近所の人が集まってくださって回向。そのお茶汲みの役は。。。それも義母方の親戚が買って出てくれたらしい。本当に有り難い。 さて、7回忌と葬儀が重なったのだから、その6年後の13回忌とあちらの7回忌が同じ年ということに。今年はもう夫だけの列席ということで私はやれやれというところ。 と、同時に、あの夜中の腹痛騒ぎからもう6年にもなるんだ!と改めて実感する。手当てが遅れていたら、この世には居なかったかも知れないのだから、命の恩人である夫には感謝に絶えない。 直ぐに更新するつもりで、なかなか更新が叶わないフリーページにも記載していますが、腹痛というのは実際に中を開けてみなければわからない。なんてことがあって、侮れないものなんだな。と。尋常でない痛みのときはやはりここは医師の診断を仰ぐべきだと実感した、私には事件だったし、こんなときに一人暮らしだったらと、つくづく夫には感謝。命があるからこんなことも出来るわけだし。。。 書き込みしてくださった方へのresは美容院から戻ってからになりますが、毎度言い訳ばかりで、本当にごめんなさい。。。
2005.04.16
コメント(0)
-
薬剤師さんに薦められて。。。
新しく開院した、循環器内科専門医院へ行くつもりでさて家を出ようとしたところへの電話。役所から、先日提出した家族の障害者年金の現況届けに記載ミスがあるとのこと。訂正して貰うには、洲本市まで行かなければならない。でも、向こうも急ぐみたいな雰囲気なので、ここは仕方が無いので一旦役所で書類を受け取って、それから循環器内科の受付だけ済ませて洲本市まで車を走らせる。 精神神経科専門の病院の待合室は患者でごった返していて、かなり時間がかかりそうだったけど、受付の女の子をつかまえて事情を説明してみる。今の患者さんに5分はかかり、その後。。。などと言葉を濁されてしまう。何とか数分以内には訂正した書類を頂けそうなので、喫茶コーナーで待つことに。 思ったよりも早く訂正済みの書類を先ほどの受付の女の子が届けてくださる。有り難い♪頼んでおいたアイスコーヒーを飲み干すのももどかしく、急いで帰途に。 役所では、担当の女性が電話中とのことで、別の女性に書類を渡して、私は急いで受付を済ませておいた医院へ。早速呼び出し。結局は初診ということもあり、採血の結果を待って薬の処方をしましょう。とのこと。やはり婦人科疾患のことを伝えておいて良かった。卵巣が一つしかないこと。子宮は全摘術を受けたこと。。。コレステロールが高目なのはこの卵巣が一つしかないことと大いに関係がありそうな気がしたので。 血圧が高目だと思ってはいたけれど、診察を待つ間に洲本市まで往復して、役所へ書類を届けて。。。精神的にも安定する筈が無い。。。と、結局は薬を出したくないという先生で本当に助かった。血液検査の結果がわかるまでに、何回か自分で血圧測定をしてみてください。と言われたぐらいで、心配していた頭痛は肩凝りから来ているのでしょう。ということで、処方されたのは凝りをほぐす塗り薬のみ。薬剤師さんは一安心といった感じだったけど、さて、血液検査の結果やいかに。 金曜日の夜は新しく参加し始めたコーラスの練習。練習が終わって帰宅後入浴。金曜日の夜ということもあってすっかりくつろいで、先ほどメールの返事をし、サイトへ入ったばかり。 書き込んでくださった皆さんには本当に申し訳ありませんが。。。お弁当の数の多い金曜日の仕事が終ってやれやれというところ。コーラスの練習自体は金曜日の練習の方が断然楽しい。ただ、前から参加しているグループが発表した「落葉松」を10月の自主公演に演奏したいとの希望がたくさん。前回は女声三部編成だったけど、これが混声四部ということになると。。。でも、編曲は勿論、随分違うんだろうなぁ。女声三部のときは担当したのがメゾソプラノだったからなぁ。まぁ、これも勉強かな? 洲本市民会館が12月で閉鎖され、新しく建設された体育館を兼ねたホールがこれから使われることになるとかで、12月4日には「第九」演奏会でその幕を閉じるとのこと。5月10日が団員の締め切りで、火曜日が練習日になるとか。さて、指揮者に朝比奈千足氏をお迎えすることが決定されているとのこと。確かに「第九」は魅力があるけれど。。。8月6日は「淡路音楽祭」10月23日は「自主公演」。。。どうしようかなぁ。独身だったら間違いなく参加してると思うけどなぁ。
2005.04.15
コメント(4)
-

4月13・14・15日共通のお弁当。。。
献立は、中国風蒸し魚、コロッケ、菜の花胡麻和え。添えの野菜はコロッケにキャベツ。メインがあんかけ風なので果物は付きません。◆中国風蒸し魚。。。材料は、白身魚の切り身、干ししいたけ、筍の水煮、人参、葱。白身魚は皮を下にしてバットに並べ、軽く塩をまぶして蒸し器に入れて、20分蒸す。干ししいたけはぬるま湯で戻して千切りにしておく。筍の水煮は袋から出して軽く洗って千切りにし、暫く水にさらしておく。人参は皮を剥いて千切りに。葱は斜め切りにしておく。しいたけの戻し汁に少し水を加えて中華味、塩、コショー、醤油などで味を調えた煮汁に切った材料を加え、材料に十分火が通ったところへ、水溶き片栗粉でとろみをつけて火を止め、最後に葱を散らしておく。少しコショーをきかせた味に仕上げる。◆コロッケ。。。冷凍のものを熱した油で揚げるだけ。斜め切りにして盛り付ける。添えのキャベツは7ミリぐらいの幅、3センチぐらいに切り揃えて、塩茹でして、水気を切っておく。◆菜の花の胡麻和え。。。菜の花は束ねられたのを5等分ぐらいに切って水にさらして塩茹でし、水気を切っておく。白胡麻を炒って、みりん、醤油で味を調えた合わせ醤油に胡麻を加え、水気を切っておいた菜の花を加えて味を馴染ませておく。蒸した魚を身を上にして盛り、上から具をたっぷり目にあんをかける。運搬の事情があるので、汁気を少なく。左側にはキャベツを置いて、二つに切ったコロッケを盛る。3番目には菜の花の胡麻和えを。白身魚は業者に任せたのが届くので、重さは同じでも見た目大きかったり小さかったりがあるけれど、こればかりは。。。コロッケは斜め切りにしたのを切れ目を並行に並べるよりは、少し角度をつけた方が綺麗かな?葱は全体量が少ないので、斜め切りに。 ボランティアって何だろう。。。?今まで数が多い火曜日、金曜日は特別養護老人ホームから強力な助っ人が入ってくださった。それが、どういうわけか、町村合併があった途端、ボランティアに頼むことに。しかも3人。これは地区にもよるけど、私たちには2人の方が実は有り難い。 手伝ってあげてる。。。と思われる人。一緒に勉強させて貰ってると思われる人。ボランティアさん同士の意思統一が全く図られていないから、こちらも戸惑うばかり。何をお願いしていいのやらいけないのやら。現場の意見は全く無視にここまで進んで来たけれど、時間に遅れてくるのまで「ボランティア」さんなんだから。と言われては、開いた口が塞がらない。何も任せられないのなら、そのつもりで私たちが頑張れば良いことだけど。。。と、ストレスは溜まる一方。どうしてこんなことになってしまったんだろう?町村合併の弊害がこんなところにも。
2005.04.14
コメント(0)
-
高知県で始まったという。。。
「“食”の授業で子どもの体を守れ」と題した報道を今朝NHKでやっていた。生活習慣病予防のことが叫ばれて久しいけれど、瘠せ過ぎだとか、太り過ぎの子どもは何年か前と比べて確実に増えているのだとか。中でも5歳で35キロという女の子の登場には驚いた。明らかに生活習慣病そのもの。予備軍とか、そんな生やさしいものじゃない。一体、こんなになってしまった原因はどこにあるのだろう。側に居た母親は、ご褒美にと、直ぐにジュースやアイスを与えていたのだとか。また、最近は、スナック菓子でお腹を膨らませて、肝心の食事で栄養を摂れていないというパターンも多いのだとか。 私とて、人に言えた義理ではないけれど、スナック菓子に含まれる塩分たるや、相当なものだと思うし、脂肪分だって侮れない。また、ジュースやアイスなど、口当たりの良いものには、たっぷりと砂糖が使われている筈。食べるな。とは言わないけれど、お砂糖を舐めているのと同じようなつもりになれば、ジュースをお茶に変えることは容易に出来そうな気がする。 また、最近は家庭の事情とかがあって、家庭でも十分な食事が与えられていなかったりということもあるようで、家庭にも踏み込んだ栄養食事指導を心がけて行きたいと、その栄養教諭(栄養士)さん。 文部科学省においても、全国的に早い時期に各地域でのそうした取り組みに力を注ぎたいとのこと。 子どものうちから生活習慣病に冒される。。。などということはやはりこれは余りにも大きな問題な気がする。
2005.04.14
コメント(4)
-

淡路島最南の海岸線を。。。
ひた走りに走るコースの配達を担当して、やはり温暖だとつくづく思う。波は静かだったし、本当に気持ちの良いドライブコース。ただし、やはり命懸けで下りてこなきゃ行けない部分を除いては。 私には本当に珍しい丈の低い椿。綺麗な花が開いていましたので。それと、これまたとても低い丈のアイリス。間も無く花が開きそうな大きな蕾を見つけたので。こういうのを見つけるとホッとしますね。 温暖だし、目の前は海そして背景に山々が連なって、ウグイスの声も本当に間近に聞こえてきて、本当にのどかな気分。通勤でいつも海を眺めているけど、それは福良湾の海。やはり、ここへ来るとはるかかなたに大阪南部多奈川の火力発電所辺りが見えるし、思わず、♪う~みは ひろいな おおきいな~♪と歌が出てしまいそうな。
2005.04.13
コメント(0)
-
銀行巡りをしてから。。。
JAで給油を。今日は水曜日だから、車が連なっている。見たらティッシュの箱が並べられている。20リットル以上で卵が1パックだったり、ティッシュ5箱だったりするみたい。 本当は車の為にも余計な物は積み込まないで、軽くしておくのが燃費にも良いらしいけれど、私は空になってしまうのが怖くて、目盛りが半分以下になった時点で給油してしまう。空に近い状態でなんて怖くて走れたものではない。 どんなに燃費が悪くても、最低1リットル当たり10キロは走れるのに。と夫は言う。その夫はガス欠で姪に輸送を頼んだ経験の持ち主。こんな目には遭いたくない。配食の車にしても然り。半分以下を示していたら満タンにしておくことに。次に使う人も安心して走り回れるというわけ。 ふと目をやると、軒並み4月5日の時点より5円の値上げ。それでも農協なら安いのだとか。窓も丁寧に拭いてくださった。おまけに卵を1パック。水曜日に給油する人が集中するのも頷ける気がしました。 先ほど、臨床福祉心理士の第一回の講義で出された宿題に目を通していて、ヒーリングという言葉につまずき、検索していて、素敵なサイトを見つけましたので、早速お気に入りリンクさせて頂きました。セルフヒーリングというサイトです。皆さんも良かったら癒されてみてください。。。 昨日、一日降り続いた雨は夜になってやっとおさまり、今日は青空が広がっています。太陽が顔を覗かせると何だかホッとしますが、北に面した窓際でタイピングしていると、やはり背中は寒々とした感じ。皆様もどうぞ気温の変化でお風邪など召されません様。。。
2005.04.13
コメント(4)
-
今日付けの地元紙『正平調』というコラムには。。。
中国で起こった反日デモ。関連しているわけではないけれど、こんなことが述べられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『福岡県大牟田市で今月から始まった映画がある。「ひだるか」という。地元の方言で「ひもじくてだるい」という意味である。 戦後最大の労働争議「三池争議」(1959~60年)を背景にした物語だ。阪神間を中心に活動するピアニスト岡本美沙さんが主役を演じる。映画は大阪や京都も巡回する予定だが、受け皿となる実行委員会づくりがこれからなので、日程は未定という。 その大牟田市で一昨日、争議の中核にいた三池炭鉱労組が解散した。2万人を超えた労組員も、分裂や解雇などで最後は14人。「劣悪な環境の中で闘いつづけることができたのは仲間がいたから」とあいさつをする人も腕組みでうなずく人も、ともに白髪が目立つ最後の日となった。 エネルギーの中心が石油へ移る節目での争議だった。合理化を進める経営側。解雇反対の労組。激しい対立は「総資本対総労働の対決」とまで言われた。その渦の中にいた労組の終幕だったから、深い感慨を覚えた関係者は、兵庫県内でも多かっただろう。 炭鉱は8年前に閉山した。三池炭鉱労組員はその後、組合の活動記録などを残すための作業を続けていたという。150箱以上の段ボール箱には、大争議だけでなく、戦後最悪となった63年の炭じん爆発事故などの資料も含まれる。 派遣社員などが増え、労組員が減り続ける現代から見れば、遠い光景と映るかもしれない。しかし、段ボール箱には「日本の戦後」がぎっしりと詰まる。耳を近づければ、「忘れるな」の声が聞こえてきそうな。』 そして、今日の社説には、中国は事態の収拾を図れとして、この様に述べられています。 『中国各地の反日行動がエスカレートしてきた。先週末には北京で大規模な街頭デモが起き、一部の参加者が日本大使館や大使公邸に投石するなど暴徒化した。反日デモは他の都市にも拡大し、日経スーパーや日本料理店などが被害に遭っている。 きわめて憂慮すべき事態だ。週が明けて騒ぎはひとまず収まったようだが、今週末に予定するデモへの参加呼びかけも伝えられる。過激な行動をくり返させないよう、中国側の対応を強く求めたい。 反日行動の背景には、日本の国連安保理常任理事国入りや歴史教科書への反発があるようだ。靖国神社参拝を続ける小泉首相への反感、不信も底流にあるのだろう。 しかし、理由は何であれ、こうした破壊行為は許されるものではない。今回、とりわけ納得し難いのは、警備に責任を負う中国政府の動きである。 町村外相の抗議に対し、中国の王毅大使は「秩序の維持に努めた」などと説明したが、本当にそうか。警官隊が暴徒の投石を制止しようともしない。むしろ、黙認を与えているとしか思えない情景だった。 こうした行動が中国国民を代表しているわけではあるまい。苦々しく見ている人も多いはずだ。しかし、小さな反日の火が拡大しやすい状況にあることは、十分に認識しておく必要があるだろう。 大きな要因が1990年代から進められた「愛国主義教育」だ。デモ隊の中心を占めたのは、厳しい対日姿勢を教え込まれた若い世代だった。加えて、インターネットの普及がある。約9千万人という世界第二の利用者を抱える中国では、ネットが世論形成の機能を持ちつつあるという。 だが、筋違いの反日行動が放置されるようでは、日本側にも中国に対する反発が高まりかねない。そうした悪循環は日中の経済関係に深刻なダメージを与え、互いの国益を害するだけだ。中国の国際的な評価にも傷がつくのではないか。 先月、温家宝主将が日中関係の建て直しに向けた3つの原則を示している。これを受け、町村外相の訪中が決っていた。こうした改善への機運を損なうような事態は一刻も早く解消しなければならない。 たしかに、日中間には見解が異なる難題が山積するが、あくまで外交を通じた話し合いで合意点を探るべきものだ。 予定された外相会談のほか、今月下旬のアジア・アフリカ会議での日中首脳会談も、ぜひ実現させる必要がある。中国政府には、冷静な対話を可能にする環境づくりに指導力を発揮するよう、望みたい。』 過去に遡って、日本が中国に対してしてきたことの反省も忘れてはいけないと思うけど、この線引きは一体どこで出来るのだろう。本当は一番仲良くしなければいけない筈のお隣の国。。。敵対心ばかりが膨れ上がっては問題が。ここは両国が納得の行くかたちで矛を収めて欲しい。。。
2005.04.12
コメント(2)
-

4月11・12日共通のお弁当。。。
現在、携帯からのメールの受信にかなり時間がかかっていて、朝送ったのもまだ届いていないといった状態。ウィルスメールがかなりサーバーに悪さをしたとのことで、それを知らせるメールがつい先ほど届いたばかり。なので、画像は届き次第掲載させていただきます。 献立は、炒り鶏煮、出し巻き卵、きゅうりとチリメンジャコの酢の物。◆炒り鶏煮。。。材料は、鶏肉細切れ、ごぼう、じゃがいも、人参、板こんにゃく、グリンピース。ごぼうは皮を剥いて、水から酢を加えて下茹でして、薄く切っておく。ジャガイモ、人参は皮を剥いて乱切りに。板こんにゃくは袋から出して、サッと洗って下茹でしたのを36切りに。グリンピースの水煮は缶から出して、塩茹でしておく。熱した鍋に油を敷いて、鶏肉から炒めていく。こげ色が付いたら、板こんにゃく、ごぼう、人参を加えて更に炒める。ある程度火が通ったらジャガイモを加え、酒、砂糖、しょうゆ、みりんで味を調えて、煮立ったら火を弱めて落し蓋をして更に煮含める。◆出し巻き卵。。。冷凍のものを湯煎し、袋から出して8切れの斜め切りにして、一人2切れずつ。オオバを敷いて盛り付ける。◆きゅうりとチリメンジャコの酢の物。。。材料は、きゅうり、若布、チリメンジャコ。きゅうりはへたをとって薄切りスライスにしたのに塩をまぶしてしんなりしたら、水で洗って塩を飛ばして十分に水気を切っておく。若布は水で戻して小口切りにしておく。チリメンジャコは熱湯をかけて埃を落としておく。砂糖、酢、薄口醤油で合わせ酢を作ったところへ材料を加えて混ぜ合わせる。 今日は出し巻き卵を半分しか湯煎していなくて、盛り付ける時点になって慌てた。いつもは一切れしか入れないので、勘違い。何故か冷凍庫に満杯になっていた出し巻き卵は20本入りの箱が3箱。これは余りにも多過ぎて、他の物が入らないし、何が何だかわからない有様になっていて、冷凍庫の通風孔が完全に塞がってしまっている。で、わけを話して特別養護老人ホームへお引取り願うことに。と、先日使った皮付きフライドポテトも3袋。暫く使う予定が無いので、これもお引取り願う。水曜日から使う予定のコロッケがもう届いている。業者さんも使う量は大体わかっている筈なのに、冷凍庫にぎっしり詰め込まれても必要なものを出せなかったりする。 と、携帯からの画像が全く受信出来ない状態で、受信出来次第載せることにします。携帯からの画像が届いたのは、出かける直前になってから。ということで、こんな時間になってしまいましたが。それと、ご飯は「わかめご飯」だったことを忘れていて、何か黒いものが混じっていて変な感じですが、炊いたご飯に若布のふりかけを混ぜ込んでいます。メインは、炒り鶏煮。彩りにグリンピースを散らして。左側にはオオバを敷いて出し巻き卵を。3番目にはきゅうりとチリメンジャコの酢の物を。炒り鶏煮にジャガイモを使うのは初めての経験。同じ煮汁で炊いた方が美味しいけれど、煮崩れの心配があったので、別の鍋で炊きました。板こんにゃくも味を染み込ませるために別に炊いた方が良かったかな?数の多い火曜日は先ず回転鍋で出し巻き卵を湯煎して、それから炒り鶏煮をする予定。(と、火曜日になってからの画像のUPで、妙な具合ですが)
2005.04.11
コメント(2)
-
母を眼科医院へ。。。
連れて行く約束を昨日からしていて、その前に3月に20日間も入院していたことを全く知らなかった、母には兄嫁になる人が、今度人工透析をしなければならないと聞いて、先に母の実家へ寄ってご機嫌伺いをしようということに。なもので、家を8時半には出て、一旦実家へ行き、母を乗せて母の実家へ。 その伯母は比較的お元気そうで何よりだった。20日間の入院の間に、透析の回数を調整したり、症状が軽減できたとしたら凄いことだと思う。この先、週に何回透析に通うことになるのか、決定されるのはこれからなのだとか。ひとまずお目にかかることが出来て一安心。 たまたま大安吉日ということで、今度はまた国道沿いにある父の弟が入院している病院へ立ち寄ることにする。寝たままの叔父に母が声をかけると、大きく目を見開いて、何か喋ろうとするけれど、気管切開をしている叔父には声にならない。もどかしいけれど、意思表示の仕方も今ひとつはっきりしない。でも、顔は艶が良くて、こころなしか、少しふっくらしたような。これで二本足で立つことが出来たらと思う。まだまだ時間はかかりそうだけど、絶えず誰かが声をかけてやるのが一番かも知れない。時間が作れたらまた声をかけに行こうと思う。 父は血圧がどうということは無かったけど、祖父がかなり血圧が高目だったことから、やはり私も要注意ということに。祖母は父が12歳のときに心臓を患って他界してしまったので、兎に角、色白だったらしいことしか私にはわからないけど、血圧が高いことが心疾患に影響していたとしたら。。。余り良い気はしない。 湿り気を含んだ気持ちの悪い空気とは一転して、今日は北からの風が冷たかったりする。私にはこれくらいの気温の方が気持ち良い。生暖かいのはどうもいけない。 母は、行きたいと思っていたお見舞いを2件済ますことが出来て満足気。帰りは一人でバスに乗って、自由な時間に最寄りのバス停まで。降りたところにスーパーがあって、そこへ立ち寄って買い物をするのも楽しみの一つ。タクシー乗り場はそのスーパーの直ぐ近く。運転手さんとも顔馴染みになっていて、帰る方向はもう覚えられているらしく、先日は、途中の病院で降りるという人と相乗りさせてくれたのだとか。障害者手帳を持つ母には、バス代は半額。タクシー料金は1割引になるのだとか。多くの人の世話になりながら、今日も母の一日が終わる。。。
2005.04.11
コメント(2)
-
今日付けの地元紙の教育欄に。。。
アマチュア無線家としても、とても興味深い記事が載っていましたので、そのまま引用させて頂きます。理科の散歩道その202回目。通信技術の歴史 有線をへて、電波使う無線へとして。。。 『「狼煙(のろし)から何を思い浮かべますか?旅が好きな人ならば能登半島最北端にある禄剛崎(ろっこうざき)灯台のある所でしょうか?歴史もしくは通信手段に興味のある方ならば、煙を上げて情報をやりとりしていた昔の通信手段でしょうか? 通信手段も、古くは煙などの利用から有線での電信や電話をへて、現在は無線通信が全盛の時代です。映画「スタートレック」を見てすごいなと思っていた携帯電話も、普及台数から単純に考えると、日本人の2人に1人が持っている時代となっています。 有線での電話や電信の始まりは、1825年の電磁石の発明からです。モールスはこれを使って電流を切ったり流したりして電信機を作りました。アメリカでは45年にこの電信機を使って実際に電報のやりとりが始められ、76年には電話が登場して有線通信が確率しました。 通信に電波が使われるようになったのは、96年にマルコーニが無線通信の実験に成功してからです。マルコーニは送信機に火花放電を使い電波を発生させました。受信機にはコヒーラーという装置を使いました。コヒーラーは、ガラス管に細かい粒の金属の酸化物が詰まっていて、電波を感じると粒どうしのさびがはがれて電流が流れ、通信が終わると本体をハンマーでたたくことによって粒をずれさせて電流を止める装置です。 家の中の短い短距離での送受信からはじまった実験も、1901年にはイギリス~カナダ間、約3500キロメートルの無線通信をやってのけることとなります。カナダ側では大きな凧のアンテナで受信したそうです。第一報は「S」の通信でした。マルコーニは無線通信の技術を確実なものにさせた功績によって、ノーベル物理学賞を受賞しています。 彼は、イギリスで電信会社をおこしますが、既存の有線の通信業者から猛烈な反対を受けます。陸上での通信事業には参入することができなかったため、有線での通信が不可能であった船を対象にして事業を進めました。当時世界中に広がっていたイギリス領の各地の海岸に無線の陸上局を設置して、船との間の交信に力を入れました。 1912年のタイタニック号の事故は、映画にもなって大変よく知られています。この船にはマルコーニ夫妻が招待されていたのですが、子どもの発熱で乗船しなかったので難を逃れたようです。 この事故に関しては、貨物船から危険を知らせる無線連絡があったにもかかわらず、タイタニック号が無視したため、惨事が大きくなったとも言われています。すばらしい技術があってもそれをわれわれがどう使うかということが問われているのは、昔も今も変わらないようです。(県立尼崎西高校 浅井尚輝)』 更に、甲南大学 知の散歩の25回目として、理工学部 情報システム工学科教授 岳 五一氏がこの様に。。。 『日々進化を続ける情報化社会。新しい技術やサービスが次々に登場する中、最も注目されているキーワードの一つが「ユビキタス」だ。 「ユビキタスとはもともとラテン語で『いたる所』といった意味です。インターネットは広く普及していますが、山奥や砂漠などのへき地、海上など利用できない場所もまだ多い。そうした場所の制約や、時間の制約も超え、あらゆる人や物が結びつく情報をやりとりできる社会、それがユビキタス情報社会です」 -すでに、携帯でメールや画像をやりとりしたり、外出先でノートパソコンを使ってネットを見たり、情報のやりとりをしたりすることが日常化していますが… 「そのほかにも、例えば基地局やアクセスポイントなどのインフラには依存せず、端末のみでネットワークを即座に構成するアドホックネットワークなどはシームレスなユビキタス基盤のネットワークといえますし、家電製品とネット技術を融合して、外出先から冷蔵庫の中身を確かめたり、テレビの番組の録画予約をしたりするといったことを実現する情報家電ネットワーク、自動車のカーナビの技術を応用、危険物の信号を送受信して事故を防止したりできる車車間ネットワークなど、有線から無線、ネットワークから端末、認証、データ交換等を含め、さまざまなネットワーク技術が結集してユビキタス情報社会が実現します」 -実現への課題は? 「例えばユビキタスを実現するために欠かせないのが無線通信技術ですが、そもそも無線通信で使える周波数帯域は限られています。同時に同じ周波数で2人以上の人が通信すると混信してしまいますから、周波数帯域を複数のチャンネルに、あるいは時間的に符号に分割して使っていたりして、多重化という工夫が常になされています。しかし、従来は文字や音声だけだった送受信データが、動画なども扱うようになり、今後はデータ量の大幅な増加が見込まれているのです」 「そこで、限られた周波数を有効利用していく技術が重要になります。例えば通信が混む時間帯や経路も、空いている時間帯や経路もある。それを解消するには、混み具合を予測し、付加を分散させて、多様なサービスを提供できるシステムを作る必要がある。また不確定な要素が多く含まれる情報通信システムが本当に効率的に動くかどうかを評価する手法の研究や新しい伝達方式の開発、システムの性能を解明することなどが、私たちが手がけている仕事。だれもが手軽に、いつ、どんな場所からでも情報を得たり、お互いに円滑にやりとりできる社会の実現を目指して研究を進めています」』『従来の伝統も大切に 「岳五一」という名前の字面と「がくごいち」という日本語読みの音の印象からは屈強な男性を想像しがちだが、ご本人は笑顔のすてきな女性。しかし、ネットワークと情報社会の未来への語り口はたいそうエネルギッシュだ。 北京出身。中国清華大・電子工学科を津。京都大学大学院工学研究科博士課程単位習得。工学博士。(財)京都高等技術研究所主任研究員、甲南大学理学部応用数学科教授などを経て、現在甲南大学理工学部情報システム工学科教授、知的情報通信研究所所長。 大の読書好きでもあり、若者の活字離れ、インターネットへの没入には危惧を抱く。「私もネットの開発に携わってはいますが、従来の伝統も捨てるべきではないと思います。過去の遺産も尊重しながら新しいものに取り組むことが、今の時代を生きる上で大切ではないでしょうか」』 更に、こんな記事が目に留まったので、そのまま引用させて頂きます。 『考え合う輪 広がった 命の尊さ胸に刻むとして、淡路市と神戸市で3月25~28日に開かれた「防災世界子ども会議2005inひょうご」。日本を含む12カ国の小学生から高校生まで計60人が、防災や災害救援について話し合い、学んだ。福岡県西方沖地震が20日に起きたばかりだけに、会議は熱を帯びた。参加した子どもたちは会議から何を得て、今後にどうつなげようとしているのか。議論や報告を振り返った。(岩崎勝伸) ▽違いの発見 同会議は、インターネットで学校間の国際交流を広めるNPO法人「ジェイアーン」(本部・神戸市中央区)などからなる実行委員会の主催。昨年9月から国内外54校、千人以上の子どもたちが事前学習を始め、今回の会議はその代表が半年間の取り組みを発表する場でもあった。 地震の発生メカニズムを調べたり、防災マップを創るなど、成果が次々と報告された。非常用持ち出し袋の中身をテーマに選んだ神戸市西区の市立樫野台小学校の児童たちは、事前学習でイラン、ルーマニア、フィリピンの留学生を招いた経験を発表。「聖書を持ち出す」「ナイフが必要」などの意見があったといい、袋の中身がその国の宗教や風土とかかわっていることを浮き彫りにした。 また、昨年12月のスマトラ沖地震による津波で親類を亡くしたインドネシアの高校生、ムハマド・イクバル君は「津波が何か分からないまま、多くの人が亡くなった。学校では災害から身を守る方法は学ばなかった」と報告。日本では、阪神・淡路大震災など災害のたびに被害が集中する高齢者らの対策が課題となっているのに対し、インドネシアでは多くの子どもが命を奪われた状況も訴えた。 防災のあるべき姿は、国や地域の社会的な背景や想定される災害によって違い、答えは一つではない。子どもたちはそのことにも気付いた。▽強いきずなを力に 迎えた最終日。会議としての宣誓文を発表することになっていた神戸市垂水区の県立舞子高校環境防災科新3年生、中野元太君は「議論をしていく中で多種多様な意見が出された。その時、私たちは宣誓文以上に大切なことがあることを知った」と、壇上で話始めた。 そして「ここで議論をやめて宣誓文を作るより、何ができるかを考え、議論し、共有し続けることが大切。きょうを防災について考える出発の日として、これからも活動を続ける」。そう結んだ。 会場では、参加者が抱き合って別れを惜しむ姿があちこちで見られた。それぞれの国に帰った後も、スマトラ沖地震で被災した子らのために街頭募金を行うほか、ネットで情報交換しながら、各地の防災や将来の災害救援でも協力して行動を起こすという。 元高校教諭の岡本和子実行委員長は「子どもたちは国が違っても、命の尊さと仲間の大切さは変わらないことを胸に刻んだ。この会議で結んだ強いきずなは将来、きっと大きな力になる」と期待している。』 国が違っても。。。将にその通りだと思う。ここへ来て、日中関係が一層深刻化。。。などとささやかれているけど、根底にあるものはなかなかぬぐいきれないものがある。。。
2005.04.10
コメント(0)
-

湿り気交じりの南風独特の。。。
いや~な空気が立ち込めていましたが、実家へ電話をすると兄からも何の連絡も無いとのこと。で、今日は頑張って心理学の勉強をしようと諦めかけたところへ、今度は兄からの携帯。丁度、実家へ着いたところだという。何か買って行くものは無いかどうか確かめて、急遽実家へ向いて出かけることに。 夫は今日も仕事で既に出勤済み。家から一番近いショッピングセンターに寄って、先ずはお寿司コーナーで出来上がる時間を聞いてみると、1時間はかかるとのこと。仕方がないので、スーパーで出来合いのお寿司を買うことに。父のお供え用にと、よもぎ餅と柏餅を購入。 実家へ着くと、母がすき焼きに入れる野菜を切っているところだった。母が1人暮らしになってから、鍋とかすき焼きとかをする機会も無いだろうと、3人揃ったときにはすき焼きとか鍋を囲むことになる。冷凍庫に入っていた肉も急いで解凍。余り良い肉ではなくても、3人で囲むとまた格別。お肉よりも野菜が美味しかったりする。後になって母が糸こんにゃくを入れ忘れていたとぼやいていたけれど、ひとしきり食べたらもう十分に満足。私には柔かく、肉の出しが染みた「ふ」が一番美味しかった気がする。玉葱もすき焼きには欠かせないけど、この時期、玉葱は滅多にお目にかかれない。今のものは殆どが悪くなってしまって食べる部分が無かったりする。いくら保存が良いといっても、それは品物による。新玉葱が出始めるには、まだ一月はかかりそう。 最近は一人暮らしには本当に便利になったと思うのがすき焼きの出し。市販のもので十分美味しく食べられたりする。最も、私などは高くて手が出せないけど。一回で使い切るには十分だったりする。確かに、酒、砂糖、しょうゆ、みりんなどを合わせていたら、出費はそんなに変わらないのかな?一から揃えるならそれぞれ買う方が安いけど、案外、こんな調味料でも肉じゃがに使えたりするし、便利なのかも知れない。かさばらないのが有り難い。 実は、お祭りはこの地区でも同じ日となって、午後から獅子舞が各家庭を回って、玄関先でカツカツと歯を合わせる仕草をしてくれる。これは縁起物ということで、どの家庭でも嫌がるところはない。そして、お礼の花(熨斗袋に入れたお札)を渡すしきたりになっている。この時間のことが気になって、実家を午後2時には出たけれど、その後、どうしてもお祭りの画像が撮りたくて、思い切って出かけてみる。 少しはお祭りらしい雰囲気が出てるかな?刺繍がご自慢だという、実家がある集落のだんじりにはカバーが掛けられていて、残念ながら撮影出来ませんでした。本当なら、桜と、赤い布団がマッチして本当に綺麗な画像になる筈だったのですが。。。私が子どもの頃に比べたら随分露店も少なくなって、ちょっと寂しい気が。花見客が多いことには驚いたけど、今日の場合は風もあったし、食べ物の露店にはちょっと意地悪なお天気だったかも。心配された雨はどこへやら。何とか一日持ってくれて、だんじりを雨で濡らすなんてこともなくて、素晴らしいお祭りが出来たと思う。祭礼団の皆さん、そして、獅子舞を繰る皆さん、お神輿担当だった厄年の皆さん、一日お疲れ様でした!
2005.04.10
コメント(0)
-
各地で花見が行われていますが。。。
夕方になって、鹿児島で悲しい事件があったとのこと。新学期を迎えたばかりなのに、4人の尊い命が犠牲になってしまいました。危険な場所への立ち入りを禁止することは出来なかったのか、はたまた、防空壕の中で何が起こったのか。二度とこの様な悲しい事故が起きません様に。。。 暖かい春の一日、まるで初夏を思わせる様な。。。桜の花見を他所に、お天気が良い休日は主婦には本当に目が回る様な忙しさ。結局、PCを立ち上げたのがこんな時間。。。 さて、今日付けの地元紙のくらし欄に寄り添い 向き合う 自殺遺族の連携をと題して、東京・渋谷の「自死遺族支援にむけて遺族会のつながりを!」と題したシンポジウムが行われたことが伝えられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『家族を自殺で亡くした遺族の支援をテーマに、東京都内でシンポジウムが開かれた、偏見などから、悲しみや苦しさを表に出しにくい人たちに、どう向き合うのか。遺族も参加した会場では、支え合う必要性と課題が浮き彫りとなった。 主催した特定非営利活動法人(NPO法人)「自殺対策支援センター ライフリンク」(東京都、清水康之代表)には多くの反響が寄せられ、支援グループのネットワークづくりが始まろうとしている。▽話せる場欲しい 「ここに来るべきか迷った。自分の気持ちを打ち明けてはいけないと思って、妻は誰にも本心を分かってもらえないまま、死んでいったから…」 うつむいたまま、やっと口を開いたのは、さいたま市の遺族の男性。思いがあふれ、言葉が続かない。でも誰も無理に引き出そうとはせず、黙って耳を傾けた。 会場の東京・渋谷の代々木オリンピックセンター。手探りで支援活動を始めた人ら、約200人が詰め掛けた。グループに分かれ、遺族らが思いを語る時間もあった。 「(家族の自殺を)打ち明けるのは勇気がいる」「安心して話せる場所がほしい」。ぽつりぽつりと出る言葉ににじむのは、孤立感だった。▽周囲5人が衝撃 1人が自殺すると、周囲の5人が強い衝撃を受けるといわれる。年間の自殺者は、1998年から6年連続で3万人を突破。その間だけでも、約100万人が深刻な影響を受けていることになる。 遺族の立場でパネリストを務めた、大阪府吹田市の佐藤まどかさんは、中学3年の時に父親が自殺した。 「なんで私の家に起こったの?どうして私の父が…と考えてばかりだった。いま、こうして話していても、しんどくなってくるんです」。現実に向き合うことが、どれほど難しいか。素直な言葉に、会場でうなずく参加者も多かった。 しかし同NPOによると、支援する会や自助グループは、全国に10ほどにすぎないという。 そうした実態を数年前に調査した国立精神・神経センターの川野健治心理研究室長もパネリストとして参加。「遺族や地域の実情に応じた支援が求められる。数を増やすだけでなく、それぞれが経験を蓄積し連携する必要がある」と指摘した。▽孤立を実感 遺族らの実情から、支援の課題まで議論が広がったシンポ。締めくくりで、支援活動を続けている遺族の女性が「ある意味で、人を助けるなんてできないのかもしれない。ただ、何かしてあげようとは考えず、じっと寄り添ってくれるだけでいい」と実感を込めた。 その後、同NPO法人には200件以上の問い合わせが相次いでいる。「近くに遺族の会があれば紹介してほしい」「自分も協力したい」といった内容が多いという。 清水代表は「すがるような思いでかけてこられる方が多く、切迫感を感じる。皆さん電話一本かけるのにも、勇気を振り絞っていて、孤立しているのを実感する。全国各地に遺族の会ができるようにしたい」と話している。同NPO事務局は電090・7815・7320』 一人で悩んでいないで、どうか。。。と願わずにいられません。
2005.04.09
コメント(4)
-
淡路塾事情の下になりますが。。。
地元紙地方版の今日は役割 受験と教育の受け皿にとしてこんな風に述べられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『「もう学校だけで受験戦争は乗り切れない」。3月下旬、県立高校の合格発表を無事終え、ある中学校のベテラン教諭がつぶやいた。 悲観的とも映るこの一言。あきらめ気味にこう話す高校教諭もいる。「今は塾に受験指導をしてもらわなければいけない時代だ」 教育現場で何が起きているのか。それを解くカギのひとつが中学校の内申書にある。 県教委は2004年度から、内申書に「絶対評価」を導入した。他の生徒との比較ではなく、学習目標を達成できたかで評価する。各校、教諭で基準が違うため、生徒たちに不安が広がった。 対する塾。複数校の生徒が集まり、自分が全体の中でどの位置にいるか確認できる。志望校を決める際の大きな判断材料になるというわけだ。 3年前の2月。公立学校の完全週5日制実施を前に、文部科学省が全国の塾代表らを集めて会議を開いた。 従来の方針を変え、塾を「学校外の教育機会」と評価。土曜日の受け皿となることを期待したのだ。「今の子どもにとっては、塾が唯一の放課後の居場所」。そう話す教師もいる。 塾の役割と子どもたちを取り巻く環境の変化。小学校の新入生には先ず、勉強よりしつけが第一課題となった。相次ぐ不審者の学校侵入事件で、安全対策も急務だ。「学校はまるで便利屋。本来の機能が果たせない」と教諭の一人は言う。 ある高校教諭によると「学校は友だちと会い、部活動をする場。勉強は塾で」と割り切る生徒が増えたという。 それだけにとどまらない。「今の若い親は学校だけでは物足りないと感じ、ブラスアルファを求めてくる」と塾の関係者。子どもの生活全般を指導する業者もいる。 ある塾の経営者はこう指摘した。「『教育を食い物にしている産業』などと批判されるが、人が集まるのは社会で必要とされていることだ」 詰め込み学習の場から教育空間へ。今夜も子どもたちがそこに向かう。 写真に添えられた言葉には、壁に貼られたスローガン。塾で教えるのは科目だけではない』 そして、ト~ク&ト~クというコラム欄には、地域コミュニティーとスポーツと題して、神戸製鋼ラグビー部ゼネラルマネジャー 平尾誠二さんが、「楽しむこと」が原点として、この様に述べていらっしゃいました。 『子どもがスポーツを始めると、親は「根性がつく」「あいさつができるようになる」と感激する。でもそれは少しおかしな考え方だ。 スポーツをするのはそれ自体が楽しいからであって、忍耐や礼儀作法は副産物にすぎない。スポーツの本来の意味は気散じ。これからはその原点に回帰していくだろう。 従来のスポーツは学校と企業を基盤にし、選手はそこで協調性や忍耐を培った。だが、今の時代にはそぐわない。最近は若い選手がどんどん海外に出るが、金銭が目的ではなく、さらに上のレベルでプレーすることが動機となっている。 日本では試合に出ない選手が「一生懸命練習しており、海外から来た選手は不思議に思うようだ。私も控え選手がチームをサポートする役割を否定はしないが、スポーツはゲームの中で自分を磨くのが原点。みんなが試合に出る環境を工夫してつくれば、スポーツの価値も向上するだろう。 アテネ五輪のころから日本のコーチの質も変わってきた。良いコーチに共通するのは怒鳴らないこと。選手の話を良く聞き、その中から本質的な課題を見抜くタイプだ。 私も子どものラグビーを指導していて気付いた点が2つある。まず反発心のなさ。われわれのころのように、怒鳴られて「なにくそ」とは思わずただ落ち込んでしまう。それなら褒めて自発的に向上させる方が効果的だ。 もう1つは連鎖の低下。学生時代は試合に負けると全員で泣き、チームの一体感にもなっていた。しかし、今は選手それぞれ感じ方が違う。指導者は無理に一つにまとめず、個々に対応した方がよい。指導者には、話す内容の説得力よりも、相手が理解しているかどうかを把握する洞察力が求められる。 スポーツをするのは、生活を豊かにするためであり、生きていて楽しいと感じるためだ。コミュニティーを基礎とした、そんな柔らかなスポーツ観が、もっと広まればと思う。(2日、加古川市立総合体育館の開館記念講演で)(まとめ・渡辺裕司)』 褒めることで自発的に向上させる。。。褒めて育てるということがどんなに素晴らしい効果をもたらすか。。。実は先日から読んでいる、「子どもが育つ魔法の言葉」の中にも出て来ますね。 幸せな幼年時代として、 『人に誉められたとき、恥ずかしがったり卑下したりせずに、素直に感謝して喜べる人に育ってほしいとわたしは思います。親に誉められて育った子どもなら、きっとそうなることでしょう。自分のよさを親に誉められて育った子どもは、この世の中のよさも認められる子になります。日々の暮らしのなかで、子どものよい面を少しでも多く見つけ出してください。そうすれば、子どもは幸せな幼年時代を送ることができ、後の人生の幸福も約束されるに違いありません。』と述べられていました。そして、「子は親の鏡」と題された詩の最後には、『和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる』と。。。 子どもたちを導いていくのはやはり、一番身近なところにいる家族なのではないかな?と。そんな風に思いましたので、引用させていただきました。
2005.04.08
コメント(2)
-

4月6・7・8日共通のお弁当。。。
献立は、豚肉の中華風旨煮、鶏レバー甘辛煮、ピーナッツ和え。添えの野菜はメインが煮物なので、付きません。果物は、ピーナッツ和えで代用。◆豚肉の中華風旨煮。。。材料は、豚もも肉薄切りスライス、白菜、干ししいたけ、青葱。ロールイカ、厚揚げ。干ししいたけを戻して、大き目に切っておく。ロールイカは冷凍のものを解凍して、裏側に飾り包丁を入れて干ししいたけと同じくらいの大きさに切り揃えておく。青葱は斜め切りに。白菜は食べ易い大きさに切り揃えておく。厚揚げは三角のものなら半分に切っておく。豚もも肉薄切りスライスを更に食べ易い大きさに切り、熱した鍋に油を敷いて、豚肉から入れて炒める。豚肉にある程度火が通ったところで酒を加え、ロールイカを入れて更に炒め、厚揚げ、干ししいたけを加えて炒める。白菜を加えて火を通し、しいたけの戻し汁、塩、中華味、薄口醤油などで味を調えて、味を馴染ませる。材料に十分火が通ったところで、水溶き片栗粉でとろみを付け、最後に青葱を加えて火を止める。◆鶏レバーの甘辛煮。。。材料は、鶏レバー、板こんにゃく、しょうが、グリンピース。板こんにゃくを袋から出してサッと洗って下茹でしたのを大きさを揃えて切っておく。大体16切りぐらいに。しょうがは皮を剥いて千切りにしておく。鶏レバーの脂の部分を取り除いて水洗いしておく。板こんにゃくは別に出し汁、酒、砂糖、みりん、薄口醤油で味を調えた煮汁で味を馴染ませる。別の鍋にしょうがを加えた煮汁を作り、鶏レバーを煮る。グリンピースの水煮缶を出して、塩茹でしておく。盛り付けるときに、最後にグリンピースを散らす。◆ピーナッツ和え。。。ジャガイモの皮を剥いて、大きさを揃えて銀杏切りにし、水にさらしてあくを取ったのを、水気を切って素揚げにする。市販のピーナッツバターをみりんで伸ばし、好みで砂糖を加えたもので和える。アルミカップに入れて盛り付ける。添えにシューマイを一人2個ずつ蒸しておく。厚揚げは一人一切れを必ず加えて、豚肉の中華風旨煮を。何故か人参を使わないのが珍しいけど、青葱の色が鮮やかで食欲をそそる。左側に、板こんにゃく、鶏レバーを盛り、鶏レバーに七味を振り、グリンピースを散らす。3番目にはアルミカップに入れたピーナッツ和え。空いたスペースにシュウマイを2個。切り込み作業そのものはそんなに沢山ではないつもりが、ジャガイモだったり、しょうがだったり。しょうがを先に千切りにしておかないと、鶏レバーを煮ることが出来ない。鶏レバーの脂を取るのを担当した人とは別に手早くしょうがを千切りにしておきたい。また、板こんにゃくに味を馴染ませたいので、下茹ではキチンと済ませておきたい。画像にしてみると、色合いが何だかもう一つだったかな?目では綺麗に見えたんだけど。。。板こんにゃくと鶏レバーの色合いが似ているせいもあるのかな?3番目のところに盛り付けたピーナッツ和えは、何だかシュウマイばかりが目だってしまったけれど。 朝は5時半に起きて、朝ごパンの用意をして、息をつく暇もなく出かける準備を。結局、一便早いバスに乗ることが出来て、三ノ宮でコーヒータイム。おもむろに会場まで歩く。ビルの6階へ上がると、何と先生が既に待機してくださっていた。部屋は14号室。日曜日に説明会に参加した人数とは大違いで、先ずは自己紹介から。私の場合は、正午前には部屋を出たいので、いつも出口に一番近いこの席で。と主張しておいた。 カウンセリングとは何ぞや。と言う形で講義が始まり、前もって申し出ていた通り、三ノ宮12時20分発の高速バスに乗り込むため、正午を10分残して席を立つ。バスは予定通り出発。バスに乗り込む前に買っておいたパンと、会場のビルにあった自販機で買ったお茶で簡単なお昼。時間的にどこかのお店で。というわけにも行かず、こればかりは仕方が無い。 明石海峡大橋を渡るバスは風でハンドルが取られそうになるくらい。でも、予定していた時間より随分早く最寄り駅に到着。それから車に乗り換えてひたすら職場へ。午前中を三ノ宮で過ごしていたとはとても思えない早さ。自分でも驚くほど疲れは出なかったから、やれやれ。これから後7回(7月まで月に2回)はこんな生活になるけど、気温が上がったら歩くのも大変かな?でも、やると決めたのだから、何とか無事に終了したいと思う。 夕食後、慌てて今日の日記だけ書き込んで、今から入浴。というわけで、PCタイムは余力があれば。にしたいと思います。申し訳ありません。。。
2005.04.07
コメント(0)
-
午後5時までは通行止めだった。。。
淡路島の最南の海岸線をひた走りに走るコースのとある場所。今までは昨年の台風23号の影響で土砂崩れがあって、ずうっと工事中だった道路が今日はやっと通行止めの看板が外されていた。まだまだ機材は置いたままだから、工事そのものはまだまだ続くのかも知れないけど、久し振りに利用者さんのお宅まで届けることが出来た。今までは、午後5時を回らないと歩くに歩けないからと、わざわざ通行止めの看板が立てられる場所まで歩いて私たちが到着するのを待っていてくださった。これで完全復旧したわけではなく、まだ瓦礫に埋もれたままの場所が。フォークリフトを使って貨物を積み下ろしするときに使う様なコンパネみたいな感じの、それこそ軽四以上に重い車だと絶対にずり落ちそうな仮の橋が置かれたまま。スリルがあるどころの話ではない。一つの橋を渡り切ったと思ったら、次は瓦礫のままのでこぼこ道。それから二つ目の橋を。で、行くときは仕方がないので、この仮に置かれた板製の橋を二つ通過して、次の場所へ移動するときは、片側が断崖絶壁になった様な狭い道を下ることになる。ここは完全な一方通行。仮設の信号機が設置されていて、×になっていると5分は待つことになる。例えば残り10秒というところで車の姿が見えないときは絶対に大丈夫。なんてことはなくて、これには驚かされたことがある。だから、ここは辛抱強く待つしかない。 たまたま利用者のお宅の近くで工事をしていたと思われる作業員を乗せた車が後ろにピタッとくっついて信号が変わるのを待っている。ここは待つしかないのだから。信号が〇印に変わっていざ出発。。。後にピタッとくっついて待っていた筈の車がなかなかやってこない。やはり、余り鼻先をつけると悪いと思ったのか、かなりの距離を置いてやって来る。この恐怖の坂を下り切ったら今度は海岸線を更に東へ。もう、この頃には後方にいた筈の車の姿は見当たらない。確か、軽四だったと思ったけどなぁ。 そして、またヘアピンカーブの様になった上り坂を上って行く。ここまで来れば、前の橋を渡れば洲本市に入る。それこそいつ崩れてもおかしく無い様な壁の様になった気味の悪い土砂を左手に見ながらひたすら上る。右側はやはり断崖絶壁。でも道端には桜が何本か。はやり壁の様な土砂に遮られるためか、桜は他の場所とは違い、チラホラ咲き。 初めて走ったときは、この坂の上に人が住んでいるなどとはとても信じられなかった。家を建てる材料を運ぶのさえ大変だと思うのに、案外瀟洒な家が建てられていたりするから、本当に不思議。坂の上のお宅へお弁当を届けたら、担当したコースの配達は無事終了。帰りはひたすら海岸線を走ることになる。 今度は海を左手に見ながら、海岸線の地形に沿う形で道路が付けられていて、勿論、海には護岸用のテトラポットがいくつも並べられている。砂浜ではないので、せいぜいサーフィンを楽しむぐらいしか出来ないかも知れないけど、やはり淡路島には何といっても海が似合う。 冬の冷たい風は、雪国東北に住む人が驚く程本当に冷たい。どうかすると、水仙が咲いても風は冷たかったりする。外に出ようなんて気になれたものではない。それでも、今日は沢山の蛸壺を運んでいる車に出会って、いよいよそういうシーズンでもあるのかな、と。山ではウグイスが気持ち良く声を響かせている。本当にのどかな空気。でも、実際は枇杷なども断崖になった様なところに植えられていて、袋掛けの作業だけでも大変だろうと思う。若者が勤めに出る方を選ぶのも仕方がないのかな。そして、枇杷の値段が高いことも何となく頷ける気がする。配食の仕事でなかったら、恐らくは走ることなど無い道。同じ淡路島にもこんなところがあるんだ!と、つくづく思う。と同時に、道路の維持管理作業なども大変だろうな。と。車だから文句も言わずに走ってくれるけど、これを歩いてとなれば、本当に大変。それにしても、あの木の仮橋は一体いつまで渡ることになるのかなぁ。今にもずれ落ちそうな気がして、とても往復する気になれない。確かに、崩れ落ちた大きな岩盤をどかすことから始めなきゃいけないだろうから、完全復旧にはまだまだ時間がかかりそう。作業自体も危険極まりないだろうし、作業に当たられている人には本当に有り難いと思う。
2005.04.06
コメント(2)
-
今日付けの地元紙の『正平調』というコラムに。。。
とても興味深いことが述べられていましたので、そのまま引用させて頂きます。 『時計の広告用写真では、針の角度が社によって決っているそうだ。たとえばセイコーは10時8分だしシチズンは10時9分という。 共通するのは、長針と短針がともに上向きだということである。「時計の表情がきりりと締まって美しく見える」瞬間とかで、セイコーでは昭和初期からずっとこの角度だという。(織田一郎「時計の針はなぜ右回りなのか」) 時計の表情ではないが、新聞も眉がいつもキュッと上がっているみたい、と言われたことがある。「硬い」との声も聞く。新聞は社会を映す鏡。社会がギスギスしていると、ついつい悲しい出来事などが目立つことも理由の一つだろう。 日本新聞協会が「HAPPY NEWS」を発表した。心の温まる記事を読者が選ぶ初めての企画で、大賞になったのは福井新聞の記事。盗難被害を受けた、島でたった一人の警官が「島民が盗むはずはない」と調べを進め、犯人はカラスだと突き止める短い記事である。島民と警官との信頼関係を感じた女性読者が推薦した。 人物や団体を選ぶ賞には、環境防災科の生徒らが新潟県中越地震の被災高校生との交流を重ねた兵庫県立舞子高校も選ばれた。阪神・淡路大震災を機にできた専門学科で、その幅広い活動が読者の目にとまったようだ。伝えてきた側としてもうれしい賞である。 大賞を推薦した女性は「ほのぼのニュースが当然の世の中に」と書き添えた。新聞の眉が10時8分ばかりでなく、ときには8時20分に。そうありたいし、鏡に映る社会がそうなればと願う』 私自身は、八の字眉で怒っても怒った様に見えない。随分損をしている気がするけど、こればかりはしょうがない。でも、本当は笑うことの方が健康にどれだけ優しいか。。。本当は心の中も8時20分ぐらいでいるのが、病気を寄せ付けないのかも。 また、淡路版には「淡路塾事情 上 通塾率「6~8割」ともとして、こんな風に載っていました。 『「遊ばへん?」「あかん、きょう塾やから」 子どもたちの間で、こんな会話が日常化するようになったのは、いつごろからだろうか。 NTT西日本が発行する淡路地方の電話帳「タウンページ」で塾の項目をみると、その数ざっと80校。看板をあげない個人塾を合わせれば、100~150校はくだらないともいわれ、小中高の数をはるかに上回る。 塾業界に追い風が吹いたのは2002年。文部科学省による学習指導要領の改定だ。学校での「学習内容3割減」というニュースに保護者の不安感が高まり、生徒数が一気に3~4割増えた塾もあった。 島内の児童、生徒の通塾率は6~8割ほどとみられる。平均週2回程度通い、費用は月2万~3万円。淡路島の場合、ここ2、3年は同居の祖父母が強力な“スポンサー”になっているケースが多く、通塾回数は増える傾向にあるという。 最近の人気は個別指導。なぜかー。 「人生における勉強の重要性があいまいになり、できる子とできない子の差が広がっている」。塾の関係者は背景についてこう説明する。 しかし一方で、個別指導は「わがままな子が増えた証拠」との見方も。「学校では一斉授業が成り立たない」と指摘する声も少なくない。 個人塾が多い淡路島。同業者の一人は「島内に職種が少ないため、ライフスタイルに合わせて少ない費用で始められるからでは」と分析。開校には資格や審査もいらないため、自宅の一室を解放したり、自営業の傍ら手がける新規参入組が後を絶たないという。 かといって塾を取り巻く現実は厳しい。少子化の波を真っ向から受け、「受験バブル」が崩壊。生徒数は年々減少傾向にあり、生き残り競争が激しい。 別の同業者は言う。「一年半ほどで姿を消すところもある」 塾。いわば子どもたちの進学教室だが、さて淡路島の現状は。新学期を控え、今どきの塾事情を追った。(萩原 真)』 私自身は、塾という形のところへ通ったのは、算盤とピアノだけ。学習塾へ通う人は私の年代では殆どいなかったから驚く。どういう事情が子どもたちを塾へと駆り立てるのか。。。親たちにとっては家でダラダラと過ごすのは見るに忍びないかも知れないけれど。。。と、体力を鍛える水泳教室なども言ってみれば塾ということになるのかなぁ。確かに、厳しい受験戦争に耐え抜く体力をつけておくことも必須条件になりつつあるのかな? それにしても、限りあるだろう家計費の中で、子どもたちの教育費に掛ける割合といったら、一体どの位になるのだろう。簡単に親にはなれないわけがこんなところにもあるのかな。。。?
2005.04.06
コメント(0)
-

4月4・5日共通のお弁当
献立は、照り焼きハンバーグ、中華和え、牛乳寒天。添えの野菜はレタス、牛乳寒天にチェリー。◆照り焼きハンバーグ。。。市販の冷凍ハンバーグを熱した天板に並べてこんがりと焼いたのを、砂糖、醤油、みりんなどで味を調えて水溶き片栗粉でとろみを付けたタレにくぐらせて、照りを出す。人参のグラッセは、人参を3等分に切って、更に太さを揃えて切って、塩茹でしたのをバターで炒めて砂糖で味をつける。皮付きポテトは、市販のものを熱した油でカラッと揚げるだけ。◆春雨の中華風酢の物。。。材料は、春雨、きゅうり、薄焼き卵、ロースハム。春雨をたっぷりのお湯で茹でて、3センチぐらいの長さに切り揃えておく。きゅうりは薄切りスライスにして、塩をまぶしてしんなりしたら十分に塩を流して水を切っておく。薄焼き卵を分量の卵を溶いて焼いたのを8ミリ幅ぐらい、長さ3センチぐらいに切り揃えておく。ロースハムは薄焼き卵と同じくらいに切り揃えておく。砂糖、酢、薄口醤油、こしょう、ごま油などで味を調えた合わせ酢に材料を加えて味を馴染ませておく。卵は冷めてから加えて混ぜ合わせる。◆牛乳寒天。。。棒状になった寒天を一本あたり800ミリリットルの水分になる割合で、ちぎって煮溶かし、寒天が綺麗に解けたら砂糖を加え、砂糖が溶けたら牛乳を加えて一煮立ちさせて粗熱を取ってから型に流し込んで冷やし固める。缶詰の赤いチェリーを添えて盛り付ける。例えば50人分だと、寒天を6本。水が2800ミリリットル。牛乳が2リットル。砂糖は300グラム程度加えて、好みで加減する。寒天が十分に溶けてから砂糖、牛乳を加えないと固まらないので注意する。レタスを敷いたところへ照り焼きハンバーグをおいて、皮付きポテトのフライ、人参のグラッセを彩り良く盛りつける。皮付きポテトは大きいのと小さいのをバランス良く組み合わせて盛り付ける。なるべく隙間が無い様に盛り付け方を工夫しないと、貧相になってしまうので気をつける。左側には春雨の中華風酢の物を。これも春雨の白、ハムのピンク、卵の黄色、きゅうりの緑がバランス良く入る様に注意しながら盛り付ける。3番目には牛乳寒天を。赤いチェリーを飾って出来上がり。牛乳寒天は少し甘目に仕上げた方が美味しいかな?こればかりは好みなので、あっさり味が好きな人はお砂糖を控えると良い。あらかじめ、牛乳寒天を用意しておくと、後は春雨、人参を茹でるのと、フライドポテト、人参のグラッセ、照り焼きハンバーグ用のタレと、コンロを使う作業ばかりになるので、相当段取り良くしないと進まない。調理作業そのものは簡単だけど、照り焼きハンバーグの盛り付けに案外手間がかかったりする。 今日の日を選んで、先日亡くなられた方のお参りに行っておいて良かったと思う。ご主人にもお逢い出来て、懐かしいお話や、写真を拝見することが出来た。遺影を改めて拝見して、まだ信じられない感じ。 ご主人の話では、ときどき腹痛があったのだとか。肺にまで転移するほどだったのだから、大腸に出来た癌は相当悪さをしていたのだと、改めて思う。大きな病院が良いからと、わざわざ大鳴門橋を渡って徳島まで診察に行っていたのに、結局見つけてくれたのは、家から程近い心療所の先生だったとのこと。やはり、かかりつけの医者というのが一番何でも知っているということになるのかな?普段から何か異変を感じたら、気軽に相談出来る人の存在は大きいと思う。 船に乗っていらしたというご主人は、こまめにお料理もするし、洗濯だって苦にはならないのだとか。でも、やはり一人でご飯を炊いて、職場にも顔を出してというのが何だかわびしいとのこと。 入院が決ってわずか1ヵ月で逝ってしまった人。。。何だか、今でも「只今!」と、どこかへ旅行にでも出かけていたみたいに、フッと帰って来そうな気がして仕方が無い。でも、ここはどうか安らかに。。。と願うばかり。私とは一回りしか違わないのに、まだまだ頑張れる人だったのに、残念で仕方が無い。
2005.04.05
コメント(0)
-
間も無く。。。
先日亡くなられた方のお宅へお邪魔することになっています。明日が35日の法要とかで、たまたま前日にお参りすることが出来るのは偶然でもありますが、通夜には余りにも大勢の人が詰め掛けており、ゆっくりとお話することも出来ず、とても残念に思っていたところでした。 本当に、食べることには気を使っていらっしゃったのに、こんなにもあっけなく。と思うと残念でたまりません。血圧が高いことを気にはしていらっしゃったけど、婦人科疾患なのか、それとも膀胱なのかと心配しながら結局悪さをしていたのは大腸癌。。。本当に仕事に熱心でとても明るい声で皆さんを温かく包んでくださる、厨房のお母さん。といった存在だったのに。。。 トマトなどの栽培をされて、見事に実ったトマトを何度か頂いたことがあるけれど、将に太陽の恵みそのもの。という味がしていた。お孫さんの話をするときは本当に嬉しそうに目を細めて。。。 まさか、こんなに早く逝ってしまうだなんて、誰が想像し得ただろう。ご夫妻二人暮しだったから、今度はご主人がとても寂しい思いをされる。本人は病気から解放されてやっと楽になれたかも知れないけど、やはり遺された人にはたまらない。 癌は早期発見で手当てすればそんなに怖い病気ではないと聞くけど、やはり医師から告げられたら平静ではいられないかも知れない。彼女のどこが一体癌細胞に活力を与えてしまうことになったのか、全く信じられないことばかり。どうぞ安らかに。。。二度と声さえも聞くことが出来ないというのは本当に寂しい。。。
2005.04.05
コメント(0)
-

長い間有り難う、そしてこれからも。。。
1月11日より、三原郡4町が合併して南あわじ市発足に伴い、各町社会福祉協議会も一本化されることになり、今まで特別養護老人ホームの栄養士さん、ならびに管理栄養士さん、厨房職員さんに何かとお世話になっていた配食サービス。南あわじ市誕生に伴い、特別養護老人ホームが民間の病院が管理する、社会福祉法人の傘下に入ることになり、1月末日を持って厨房職員さん、3月末日を持って管理栄養士さんが、配食サービスと関わりを持たないことになってしまうことになり、今夜は新しい栄養士さんの歓迎会と、お世話になっていた栄養士、管理栄養士さんのお礼を兼ねた会食があった。 私は、迷いに迷ったけれど時間までにはゆとりがあったので、一旦自宅へ戻り、洗濯物を片付けたり、仏壇のものを下げて洗ったり、布団を敷いたりとバタバタして、(夫の夕食はそもそも一時帰宅が予定外だったこともあり、全く眼中に無し=姪がお好み焼きの準備をしてくれて、結局は夫が焼くことになったらしい)もう一度車に乗って待ち合わせの場所へ。 事務を専門にやってくださっている人の行きつけのお店。活きの良い魚料理が自慢のお店というだけあって、メバルの煮つけが絶品だった。カレイの姿造りと、その後の骨のから揚げ、そして目を見張ったのは、『びっくり握り』こればかりはお店自慢の握りとあって、9人で5つ頼んだけれど、4つがやっと。で、その映像が 柔か目に炊いたご飯に、鮭の塩焼きをほぐしたものを混ぜ込んで、かなり大き目の三角握りに、丸ごと刻み海苔をまぶしつけた感じ。それにしても、正味1合はありそうな大きさ。隣りにたまたま急須があったのと比べてもその大きさたるや、目を見張るばかり。丁度、カップルなどだと、一通りのお料理を頂いて、最後の締めには二人で丁度良いくらい。最初からこのお握りが目的なら、食べたり飲んだりするのを控えておかないととても食べられたものではない。このお店の自慢料理の一品だとか。それにしても大きい。魚料理がご自慢とあって、造り、煮付け、から揚げ共に絶品だった。また、蛸とさつま芋の天ぷら。さつま芋をスライスではなく、大きい短冊に切ったのを揚げるというのも珍しい食べ方。何しろ揚げたてだからまずいわけが無いけれど。ビールは、生と瓶。勿論、アサヒとキリンからセレクト出来るのがうれしい。お酒なども好みに合わせて選べるところが嬉しい。まだ今の時期、熱燗が美味しかったりする。お酒が美味しいから食べられるのか、肴が美味しいからお酒が進むのか。。。熱いお茶はほうじ茶が出て来るところがまたたまらない。 これで縁が切れてしまうわけではないので、厨房は厨房としてこれからも色々と交流が持てたらと思う。先日亡くなった人のお参りに明日の午前中3人でお宅へお邪魔する予定。くしくも翌日の水曜日が35日の法要に当たるのだとか。 というわけで、明日の午前中もそんなにのんびり出来るわけではないので、今夜のうちにresを片付けてしまいたいところですが、時間も時間ですので。。。
2005.04.04
コメント(0)
-

皆さん、楽しいひとときを有り難うございました♪
昨日は、臨床福祉心理士の講習を受ける前の説明会の二回目。その後ランチタイムを一緒に。ということで、私のためにわざわざ大阪からも駆けつけてくださって、11ヶ月ぶりのミニオフ会。ウタさんご夫妻、うきうきさん、そしてmomoさん、本当に有り難うございました♪画像掲示板へ、早速うきうきさんが画像を届けてくださいましたので、こちらでも紹介したいと思います。 甘鯛のカブトには驚いたけれど、カブトに続く身でグラタン風にしたものを巻いていました。勿論、頬肉も美味しく頂きました♪先ずはわけぎのぬた。イカが柔かくて、とても美味しかった。この写真のもので、1600円とはとてもお手ごろだと思いませんか?大根を桜の花びらにかたどって、淡いピンクに。また、人参なども桜の花びらに。器にもとても凝ってて、私には今年初物になる筍もとても柔かく煮て。ご飯はあれは何の炊き込みだったのかなぁ?最後のデザートも目を楽しませてくれる、イチゴのソースがかかって栗も入った手作りプリン?家ではとてもここまでは出来ません。。。お腹も膨れたところで、次なる目的地は。。。と、カラオケに興じることに。歩いて5分とかからなかったかな?ドリンク飲み放題で、何でも280円という手軽さ。私自身は、普段はコーラスばかりなので、みんなで歌うからこわくない。みたいな部分があって、カラオケは得意じゃないけど、結婚されたというお二人のために、「愛の讃歌」を熱唱させていただきました。どうぞ、末永くお幸せに。。。距離的には、案外、淡路島の南の方に住んでいる私の方が遠いかも知れないけれど、三ノ宮へは高速バスを利用すると、最寄りのバス停から1時間10分ほど。そのバス停までは、家から5分とかからないので、案外、私の方が便利なのかも。神戸市内に住んでいても、JRとか阪急沿線でなければ、色々乗り継いだり大変みたいで。大阪市内から駆けつけてくださった人なら尚更。。。地下鉄、JRと乗り継いで。ということになるので、こんなときは私が一番便利なのかも。それにしても運賃は私がダントツだったりするのかな?回数券を利用しないとまともでは片道1950円。明石海峡大橋が架かるまでは、フェリーが唯一の手段だったから、安かったけどなぁ。でも、そのフェリー乗り場まで我が家からだと車で1時間近くかかってしまう。まぁ、バスに乗りさえすれば、到着まで乗り換え無しで行けるというのは確かに有り難い。 朝、家を出るときは傘が必要だったのが、帰りには傘が必要ではなくなり、バスを降りる寸前になって雨脚がきつくなって来たけれど、神戸の街を歩いている間は、傘など全く必要ではなかったのが良かった。流石に神戸の街と思えたのは、小さなギャラリーが多いこと。何でも絵になるんだ。と改めて感動させられたり、素敵な色使いに感動させられる。 カラオケで2時間たっぷり楽しんで、間にドリンク、デザート、コーヒーまで飲んでたったの1100円は絶対に安い。こういうときは歌わなきゃ損なんですね。って、相変わらずレパートリーが少ない私。何か十八番でも練習しとかなきゃ。本当に、楽しい時間を有り難うございました。。。
2005.04.04
コメント(2)
-
学習セミナーの2回目。。。
心理学とは何か。ということについて基本的な説明会というのが2回あり、今日はその2回目。先週は木曜日の講座の時間に合わせて1便早い高速バスに乗ったけど、今日は開始時刻に間に合えば。と、30分だけゆっくり目。 昨夜から降り出した雨は今朝になって雨脚が強くなった気がするけど、風はおさまったみたいで、これなら傘をさしての移動も苦にならないかな。高速バスの最寄りのバス停まで車で5分とかからない。船でしか渡れなかったときのことを思うと本当に有り難いと思う。バスにさえ乗れば後は運転手任せで一眠り出来てしまう♪ 全く未知だった分野に首を突っ込むことになって、取敢えずは初級から。でも、熱心な人は1年かけて、上級まで進んでしまうのだとか。仕事の関係もあって、午後からは全く時間が取れないので、私には初級がせいぜい。後のことはそれから考えることにしよう。 『物質的な豊かさだけでは真に世界の平和の確立や人々を幸せにすることができず、反対に心は益々飢餓状態に陥っているのが現状である、福祉の更なる充実は、心の豊かさを抜きにして語ることはできず、心の豊かさの欠如とその回復は、国民全体の問題でもある、同時に一般住民一人ひとりの心理学的問題であるし、心の意識改革の必要性も指摘される。 障害を抱えながら、その人らしい生き方・存在のあり方を探求し、自分らしく生きる喜びや生活の質の向上実現を目指す人たちを、援助する学問であるといえよう。諸科学の援助を得て学際的なアプローチがより効果的であることが明白であろう。 福祉心理学は、社会的弱者を対象とするが故に、援助を求める人たちと心の中心層で触れ合う努力をしながら、共に生き、共に成長し、共に老いるという感情移入した主観の共有も考慮しなければならない。』 先週のセミナーで頂いた、「楽しい遊戯療法ハンドブック」の中にこのように述べられていました。 そしてまた、『人がなす問題行動の根底には、全て愛情不足が要因として作用していると考えます。全ての人は、愛情希求的であり、幻想我として全能感を追い求める存在なのです。自分の存在を認めてもらいたい、認知してもらいたい、親や先生に本当に生身に向き合ってもらいたいのです。 私は夢見る。かってのように、自宅の茶の間が自分を表現し・自分の存在感を感じられる居場所として再生できることは可能なのであろうか。家族がこまやかな愛情でつながり、尊敬しあう憩いのオアシスとして復活することは彼岸なのだろうか。』と。 配食サービスの仕事では直接関わりがあるとも思えませんが、自分自身を磨くという意味でもとても興味を惹きましたので、8月までの月2回、この『社会福祉心理士(初級コース)』を受講することになりました。 今日のセミナーが正午過ぎで終る予定で、三ノ宮でネットで知り合ったお友達とランチの予定。これは今日のイベントの最大の楽しみ。11ヶ月ぶりの再会になる人、初めてお目にかかる人。一日家を離れることになりますが、書き込んでくださった人へのresは戻りましてからにさせていただきます。。。
2005.04.03
コメント(0)
-
どうぞ安らかに。。。
こよなく猫を愛していらっしゃった、“猫のかわらばん”の「ゆり」さんが他界されたことを、今知るに及んでとても驚いています。とめどなく涙が溢れて、悲し過ぎる事実に遭遇して、ぼう然自失状態。。。 私自身も猫が好きということで、サイト名に『猫』という言葉を発見して、思わずお邪魔させて頂いたことがきっかけでしたが、こんなにもあっけなく。。。と、実は「ゆり」さんはあくまでも猫好きな人という認識しかなく、ただ知っている趣味としてはゴルフ。私とは違って、スポーツで身体を動かすことが大好きな人という印象でした。 ネットでトラブルがあったときに、「たかが遊びのこの世界。。。」という「ゆり」さんの言葉がどんなにか私を慰めてくれたことでしょう。 美人薄命とは言いますが、遺されたご家族の皆さんには悲しみに打ちひしがれていることと思います。どうか「ゆり」さんのためにも、ここはお元気でとお祈りするばかりです。「ゆり」さん、どうぞ安らかにお眠りください。。。
2005.04.02
コメント(4)
-
「卯月の随想」として。。。
昨日付け地元紙の文化欄に旬を楽しむと題して出久根達郎氏がこのように述べておられました。 『若いころは生意気で、へそまがりだったから、人と同じ真似をするのを好まなかった。花見も、咲いている最中は、出かけない。終るころ、友人たちと行くのである。桜は散った花びらが美しい、とうそぶきながら、池や堀に散り敷いたさまを眺めて、悦に入っていた。 さらに花が散ったあと、がくについている松葉のような赤いしべが、こぼれる。これが風流だ、と桜の木の下にたって、しべが落ちるのを喜んだ。俳句をたしなみ友人が、「桜しべ降る」という季語があることを教えてくれたのである。 物好きが講じて、桜は葉桜に限る、とその時期に、桜並木を散策した。これは1回で、こりた。全員が首や背中にかゆみを覚えたからである。しべではなく毛虫が降ることを知らなかった。 近ごろの私は、外出をおっくうがるようになった。もはや、残花やしべの雨を見に出ることはない。若い時分は若いなりに、季節感を楽しんでいたのだな、となつかしくなる。今はテレビで、世間の春を知るのみである。近所を歩けば、季節の花々がさいているのに、桜だって結構あちこちにあるのに、見たいと思わないのである。テレビで見たから、もういい、という気になっている。 季節の移りかわりに関心がなくなるとは、どういうことなのだろう。老いた証拠か。いや、老いた方が季節に敏感になるはずで、いとおしむ気持ちになるのではないか。 私の母はすでに「見ぬ世の人」であるが、晩年、異常に旬の食べ物に執着した。「今日、口にしないと、来年は食べられないかもわからないからね」と言うのである。確かに高齢者には先の保証はない。 そこでカミさんは、せっせと旬の物の料理をこしらえて、膳に上せた。 山椒の芽が出れば、摘んですりつぶし、ミリンで味つけした味噌に混ぜ、山椒味噌にする。道ばたに咲くタンポポを見つければ、根ごと掘って、花はおひたしに、葉は菜飯に、根茎は油いためにしたり、キンピラに作る。 母に饗するのみだから、量は必要ない。タンポポが2~3本あれば、十分である。野草料理はむしろちょぴりの方がおいしい。カミさんにすれば、「ままごと遊び」のような日々であったろう。母は喜んだ。 「春って、おいしいねえ」と目を細める。「春はいろんな物があって、うれしいよ。一年中、春であればいいねえ」と言う。 「それじゃ同じ物を食べ続けることになる」と笑ったら、ああそうか、とうなずいた。 「あのころは一番季節を感じましたね」とカミさんが当時を思い出して、しみじみとつぶやいた。「年寄りと一緒だったからね」とうなずきながら、カミさんが昔ほど、旬の料理に熱心でないことを残念がる。(作家・古書店主)』 菜の花のお浸し。。。ジャガイモだって新ジャガがそろそろ出回る頃かな?玉葱もそろそろ。。。と、淡路島のはまだまだ先の話ですが。春キャベツはやわらかくて、そのままでも美味しいけれど、芯は驚く程硬い。こういうのも薄くスライスして、茹でれば甘くて美味しい。筍の木の芽和え。。。そろそろかな?土筆は。。。私自身は調理したことが無いので全く未知の世界。。。でも、タンポポにそんな食べ方があっただなんて全く知りませんでした。
2005.04.02
コメント(4)
-
昨日付け地元紙の『正平調』というコラムに。。。
『「ミカドハオホトノゴモリヌ」。そんな、古色蒼然たる敬語がある、「オホトノゴモル」は、寝るの敬語で「ヌ」は、完了の助動詞。「天皇はおやすみになりました」ということだ。 これが英語になると「彼は寝た」。シンプルでいいが日本人の物言いとしてなじまない。「お上」への“へつらい”が独特の敬語になったともいわれるが、ちょっと違うらしい。動物の世界で強敵に対し「敵対せず」という意思表示に似て、身を守るための道具として敬語は発生したという(城生はく太郎「日本語研究所」) 韓国をはじめベトナム、チベット語などにも敬語がある。それらの人たちの、敬語は、ちょっとした「暮らしの知恵」でもあった。そこから、相手に対する尊敬語・謙譲語や、物、事柄に対して丁寧語が生まれた。もっとも権威保持のために、上から強制したこともある。 城生さんによると、敬語とは「相手を不愉快にさせないよう工夫された表現」だがその敬語が乱れ、相手を不愉快にさせることがよくある。「今おっしゃられたことは」など二重敬語を使われると、どぎまぎするが、一方で気にせぬ人も増えた。 「お会いする」「お食べになる」も、本来は変則使用らしい。「お」は、そんなところに付けないものだし「お目にかかる」「召し上がる」という敬語があるのに使われず、廃れていく。 中山文部科学相が敬語表現の指針について文化審議会に諮問した。確かに敬語は日本文化でぜひ守って欲しいが、あまり「お上」から押し付けにならぬように…。』 敬語も重複して使ってしまっては、滑稽になってしまうのかな。丁寧過ぎる。。。これは気をつけなければ。「お会いする」という言葉などは無意識に使ってしまうかも知れない。私の言葉で不愉快に思われた人、随分いらっしゃるんだろうなぁ。ごめんなさい。。。 神戸史学会賞 淡路の2人にとして、 『兵庫県内の歴史研究に功績のあった人を顕彰する第26回神戸史学会賞に淡路を代表する研究者の武田清一さんと浜岡きみこさんが選ばれた。4月3日午後1時から、洲本市塩屋1の市立図書館視聴覚室で贈呈式と記念講演、受賞者の武田さんが復興に尽力した連琴の演奏がある。(大国正美) 史学会賞は、雑誌創刊百号を記念して1979年に創設。兵庫県内を対象にした研究だが、全国的にもレベルの高い賞として知られる。 武田さんは教諭の傍ら、55年から古文書学集会を開催、淡路の古文書10万点を整理、散逸を防いだ。中には江戸幕府の文庫として江戸城内にあった柴野栗山文庫も。これらを活用した『近世淡路考』『続・近世淡路考』『村落の歴史』など、多くの著書がある。 浜岡さんは分権だけでなく伝説や民俗学、地名研究など、幅広い手法で研究。特に地名と考古学を合わせて30年がかりで古代の津名郡衙の所在地を推定、近年の発掘調査で浜岡さんの説の正しさが立証された。『一宮町史』『淡路の力石』など著作多数。贈呈式の後武田さんが淡路の古文書、浜岡さんが淡路の弁財天についてそれぞれ新しい見解を講演する。 また、江戸時代の淡路出身の奥野友桂が創設、武田さんが復元した25弦の“幻の琴”連琴の演奏が花を添える。 連琴は、13弦の琴よりも小型で、音が小さくはかないのが特徴。奥野友桂は京都で連琴をひろめ晩年洲本で弟子を育てたがその後廃れていた。8年前に京都に残されていた連琴をもとに、武田さんが復元。洲本高校箏曲部が演奏に取り組み、2001年には継承グループも発足した。』 浜岡きみ子さんのお名前は、参加しているコーラスグループと同じ講座の一つとして、「道を楽しむ会」を主催されていたので聞いたことがある。緻密に調べ上げて立てられた説が正しいと立証されたのだから、喜びは相当なものだったと思う。長年の努力の積み重ねがこうした賞へも結びついた。30年がかりという数字にも、驚かされるばかり。母とは3歳しか違わないのに、こんな凄い人がいらっしゃったんだ。と思うと、感激というよりも、むしろ喜びに近い気持ちで一杯。どうぞこれからも益々お元気でご活躍を。とお祈りせずにはいられない。
2005.04.01
コメント(2)
全43件 (43件中 1-43件目)
1
-
-

- ☆手作り大好きさん☆
- リカちゃんサマードレス完成 その3
- (2025-02-17 20:34:02)
-
-
-

- 風水について
- 引っ越しの際に必携の風水本 難しい…
- (2025-02-17 11:20:07)
-
-
-

- 仕事しごとシゴト
- 怒濤のごとく・・・ 〜仕事の大波に…
- (2025-02-17 17:20:47)
-