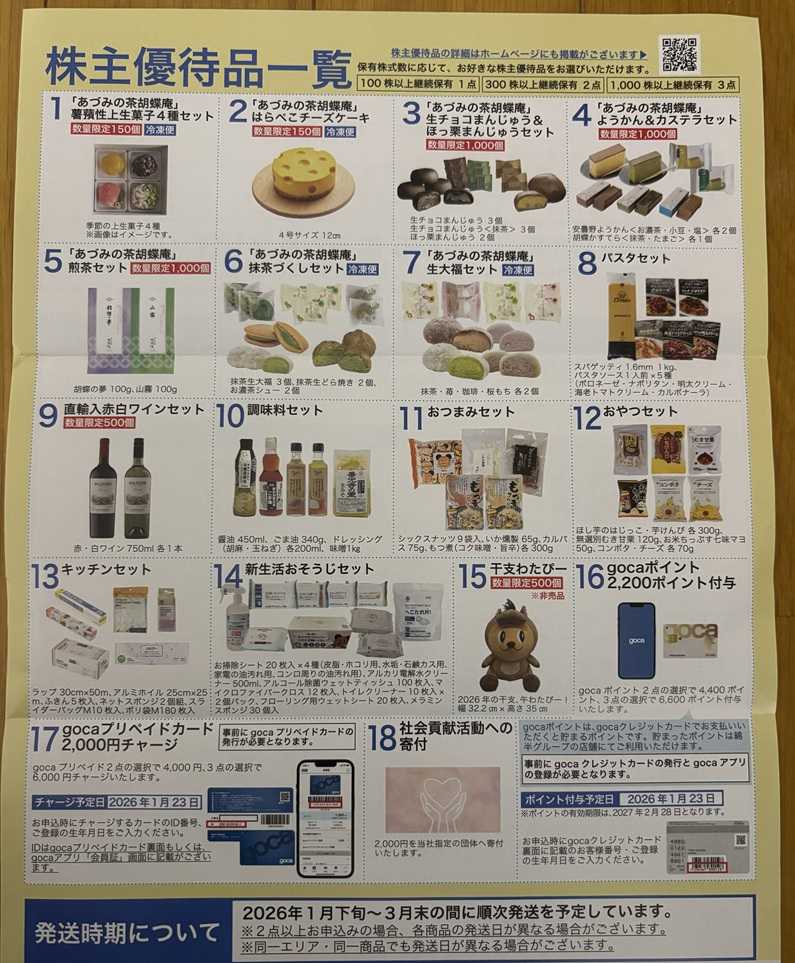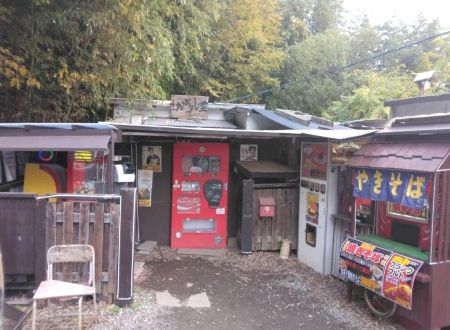2010年06月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
癖
入会して3年の私が書くのはちょっとおこがましいのだが・・・ 広友会では、ピアノ伴奏曲を歌う時にある「癖」がある。 それは、歌のテンポが遅れること・・・ この原因は、ピアノの音を聴いてから歌いだすことが考えられる。 当然、ピアノと同時に声を出さなければ、歌の方が「聴く」という 行為が入る分遅れる・・・ ただし、本番だけはその「癖」は私が経験したステージでは消えて いる。 練習時と本番の集中力の違いか!
2010.06.28
コメント(2)
-
歌いすぎ
昨晩の練習で、指揮者が「歌いすぎ」と頻繁に注意していた。今回の定演ホールは、かなり残響があるホールということらしい。もし、60人の男声が残響の多いホールで歌いすぎたらどうなるか?ということで、軽く、鼻歌程度(ただし、良い発声で)で十分届く・・・・うーん・・・力技厳禁・・・さて、残りの練習は、定演前日の7時間となってしまった。私個人としては、ほぼ歌えるようになっているのだが、まだ少し不安な部分もある・・・あと、一週間・・・自習しなければ・・・汗・・・
2010.06.27
コメント(0)
-
練習時の立ち位置
私の練習時の立ち位置は、基本的に指揮者から見て左端の最前列・・・最前列は、指揮者の指示が見やすいこと・・・(身長があまり高くないため・・・汗・・・)左端は、全体の音が聴きやすいため・・・と屁理屈を書きましたが、本当の理由は、まわりを囲まれるのが苦手・・・左端の最前列ならば回りに人が少ない。ただし、定演の並びは練習時とは異なり、それぞれの曲に応じて決定することになりますが・・・汗・・・ .
2010.06.25
コメント(0)
-
ステージ上の服装
昨年の定演では、1,2ステージが黒シャツ、黒ズボン、3、4ステージが礼服に蝶ネクタイで歌った。今回は、黒シャツ、黒ズボンとポロシャツ、黒ズボンと決まった。黒シャツの場合は、特に問題はないのだが、ポロシャツの場合、裾の処理をどうするか・・・合宿では、ズボンの外に出すということで一応決まったのだが、反対意見(裾をズボンに入れる)も出ている。私自身、普段はズボンの外に出して着ているのだが、すこし気になったのでネットで調べると公式な場では、ズボンに入れる方が一般的になっている。うーん、まあ今週末には多数決で決まるだろう・・・私は、柄の入っていないポロシャツは持っていないので、購入が必要・・・汗・・・
2010.06.24
コメント(0)
-
パートバランス
今回の定演にオンステする人数は、概ね以下のようになった。T1 13人 T2 15人B1 16人B2 17人合計61人ベース系に対してテナー系が若干少ないのだが、人数だけでみると、ほぼ良いバランスだと考えられる。しかし、実際の声量を比較すると低音の響きが圧倒的に響いてくる。その響きにテナー系が対抗しようと力んでしまうと、胸声におちて、それぞれのピッチが揃わなくなってしまう。特に、トップテナーはベース系の声量に対抗するのではなく、ベース系が作り出す土台の上に軽やかに乗って歌うようにしなければならないと思っている。
2010.06.23
コメント(0)
-
発声崩壊
合宿2日目練習を録音した音源を聴いた。 午後の練習時に指揮者から・・・ 「TOPお疲れですか?声の響きがいつもと違っていますよ」 という指摘を受けた。 それは「海鳥の詩」を歌っている時、私自身ピッチが ぶら下がっていたり、上づったりしていた。 原因は、発声が胸声になっていたようだった。 「海鳥・・・」は、30年前の大学グリーのとき、すべて 胸声で歌っていた曲・・・ 20人近いベースの大音量に刺激され、力が入り30年前の発声 に戻ってしまったようだ。 うーん・・・気をつけなければ・・・
2010.06.22
コメント(0)
-
合宿終了
昨日、一昨日、トータル13時間の強化合宿練習が終わった。その練習で見えてきたことは、個人的に「歌」になってない曲がけっこうある。これは、私自身の練習不足が原因・・・定演まで、あと2週間、残された時間は少ないが頑張らなければ・・・汗・・・
2010.06.21
コメント(0)
-
演奏会の目的
私が、30年ぶりに合唱を復活させたのは、3年前「のだめ・・・」の「楽しい音楽の時間」に影響されたから・・・そして、広友会で2回の定期演奏会にオンステした。広友会は、幸いなことに会員数が多いため、けっこう立派なホールで演奏会を開くことができる。しかし、一般会費のほかに演奏会費用が約30000円必要となる。では、何故「演奏会」を開く必要があるのだろうか・・・私の個人的な思いであるが、それは「楽しい音楽の時間」を感じるため・・・たしかに、通常の練習でも音楽は出来てくるし、練習自体も「楽しい音楽の時間」だと思う。しかし、演奏会は歌う人だけでなく聴衆も存在する。聴衆も音楽に参加する。この関係が「楽しい音楽の時間」をつくっているのだと思う。そして、それが成功するためには歌う手が「どれだけ音楽と向き合ったか」が重要・・・(すっかり「のだめ・・・」に影響されていますが・・・汗・・・)さて、明日、明後日は強化合宿・・・自分が出来るだけ音楽と向き合ってみたいと思う。
2010.06.18
コメント(0)
-
第28回定期演奏会
第27回定期演奏会まであと半月ほどになった。それと平行して第28回の選曲が進められている。今回1ステージだった、客演指揮者N先生のステージを2ステージにする。のこり2ステージは、今年振った2人の指揮者で1ステージづつ担当する。客演指揮者の1ステージは、今年のマリア賛歌を踏まえて外国曲とする。全4ステージのうち1ステージは、今年の「ふるさとの四季」のように観衆の知っている曲のステージとする。のこり2ステージは、邦人作曲家(古典、現代)とする。今週の合宿で、先生から候補曲の提案があり、そこである程度決定する。
2010.06.17
コメント(2)
-
暗譜
今まで私が参加した広友会のステージで、全員暗譜でオンステしたのは、一昨年の東京都合唱祭と東京都男声合唱フェスの2回だった。その他は、定演を含めてすべて譜持ちでオンステ・・・本来は、すべて暗譜でオンステするのが理想なのだが、一般の合唱団で、練習は週1回3時間。会員の年齢も高齢化、出席率の低さ・・・などの理由で譜持ち。昨年、一昨年の定演は、私個人としては、ほぼ暗譜で歌えたのだが・・・今年は出席率の低さの影響で譜面に頼らなければちょっと厳しい状況・・・とくにラテン語のアベ・マリアは厳しい・・・汗・・・
2010.06.16
コメント(0)
-
発声について
大学グリー時代TOPテナーの私は、ほとんど胸声で歌っていました。一般的な曲の場合、ファルセット(頭声)を使うことはほとんどありませんでした。3年ほど前、今の合唱団に入会した当初も大学時代の発声で歌っていたのですが、古典のポリフォニー曲の練習時にいままでの胸声主体の発声では、音楽にならないことに気が付きました。いろいろ調べてみると、頭声を主体とした発声にたどりつきました。胸声から頭声にひっくりかえるポイントがなくなる。今の私の発声は、声帯のポジションはすべてファルセットで歌っています。昔の胸声主体の発声と比較すると、出る音域はほとんど変わらないのですが、喉や声帯にたいする負担がかなり軽減されていると思います。
2010.06.14
コメント(0)
-
強化合宿
昨晩は、「北陸にて」の練習だった。狙っていたソロは、指揮者の意向で他団体から若い人が助っ人で歌うことになった。・・・残念・・・いよいよ今週末は、八王子で強化合宿・・・練習は2日で13時間・・・通常練習が1回3時間なのでやく4回分・・・昨年は、OBステージがあったので、直前強化合宿は計画されなかったので、久々の合宿となる。実際の練習は13時間なのだが、それにプラスして土曜の夜には懇親会・・・ここで飲みすぎると次の日が・・・汗・・・
2010.06.13
コメント(0)
-
音取り方法
定演まで1カ月を切った段階で、音取りに関する話題はどうかとも思ったのだが・・・しかし、アンコール曲の音取りが残っているので・・・汗・・・皆さんは、新譜の音を取る時どのような方法で練習しますか?私個人としては、キーボードーあるいは、音取りの音源を使います。全体練習時では、指揮者によっては「移動ド」を使う場合が時々あるのですが、私はこの移動ドが苦手です。したがって、楽譜に階名を書き込まなければ読めません。(ハ長調は除く)発声については、いろいろ研究して学生時代の発声を改良することができました。しかし移動ドは・・・汗・・・
2010.06.11
コメント(2)
-
追い込み
いよいよ、定演まで1カ月を切った。 今後の練習予定は・・・ 6月12日(土) 3時間 19日(土)7時間 20日(日)6時間 (19、20は合宿) 26日(土)3時間 7月3日(土)7時間 4日(日)本番 うーん、ハードスケジュール・・・汗・・・
2010.06.10
コメント(0)
-
TOPの課題
先週の練習は、定演1カ月前ということもあり、けっこう厳しい練習だった。 その中で、TOPの課題がいろいろあった。 まず、練習出席率の低さによる音程の不確実さ・・・ TOPの音程は、他パートと比較して楽・・・これは、主にメロディを 担当していることと、一番上を歌うことがあると思う。 これが、低出席率の原因のひとつだと思う。 私自身も、今回事情があり出席率が悪くなっている。 次に、発声法の違いによりピッチがそろわないこと・・・ 今年は、練習でヴォイストレーニングをほとんどやっていない ことも一つの原因だと思う。 しかし胸声主体で学生時代から歌っている人に、頭声にして と言っても本人がその気にならなければ無理・・・ あと1カ月かあ・・・汗・・・
2010.06.08
コメント(0)
-
ソロのp
今回の定演で歌う、多田武彦作曲「北陸にて」の1曲目「きつねにつままれた町」では、冒頭が4小節のテナーソロになっている。このソロ、誰が歌うかまだ決まっていないのだが、自分が歌うと考えて楽譜を見ると強弱記号が「p」となっている。そのソロを引き継ぎバリトンがtuttiのppで歌う。さて、ソロはどれくらいの「p」で歌えば良いのか・・・素直に考えるとバリトンのtuttiのppの倍くらいか・・・まあ、私が歌うかどうかわからないのでまあ良いか・・・と言いながら、正直このソロ狙っているのですが・・・汗・・・
2010.06.04
コメント(0)
-
fff
「海鳥の詩」の終曲、「北の海鳥」の最後はfffとなっている。このfffについて指揮者から面白い指示があった。学生や若い人の団体では、このfffは力まかせに出しても良い・・・(私が学生の時も当然そのように歌った)でも、この会では力まかせではなく、今までのいろいろな人生経験を考えてこのfffを歌ってください。という指示だった。さて、どうやって表現するか・・・
2010.06.02
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1