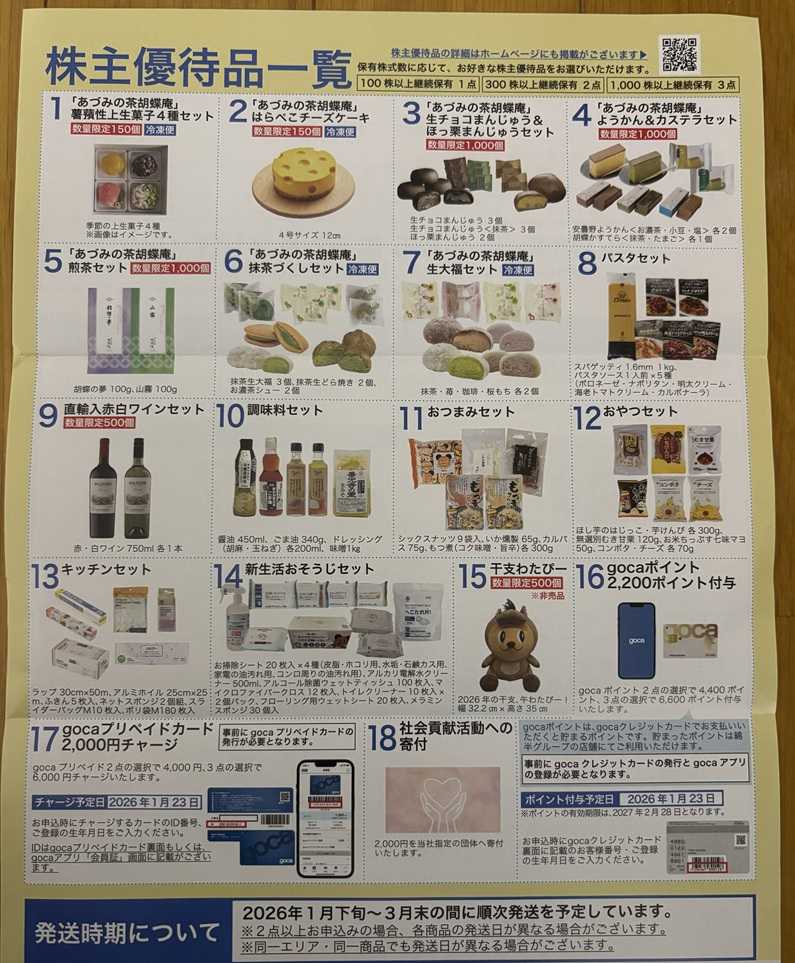2008年01月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
コバンザメ唱法
合唱のアンサンブルにおいて、音を確認するためテンポをゆっくり歌う場合の注意点として・・・人の出した音に合わせてコバンザメのように歌わないこと、この唱法がなぜいけないか・・・それは、コバンザメのように後をついて歌っているうちに、自分が音が取れていると勘違いしてしまうこと。アンサンブル練習において、自分から声を出していれば間違えた場合、「あっ、違う」と自分自身がビックリし脳に刺激を与え正確な音になっていく・・・藤井先生談・・・ 合唱と独唱の違いとして、一人ではけっして伸びないロングトーンや響きの厚み、助け合いや「合わせる」ということが可能となる。しかしこれは「本番」のこと・・・練習のときには、自分から積極的に歌い「恥をかく」ことにより上達していくのだと思う。
2008.01.31
コメント(2)
-
今週末も・・・
トップテノール特別パート練習が、夜のアンサンブルの前に午後1時から4時間弱ほど計画されている。 先週もパート練習をやったのだが、やはりいろいろ音が不安定な部分があった。こうやってパートで音を確認するのは大切なことで演奏の質にもかかわってくると思う。自信がなく不安な部分をできるだけなくして行きたいと思う。
2008.01.29
コメント(2)
-
終電
先週の土曜日は、練習のあとに臨時総会もあったことから時間が長引き、終わったのが9時半すぎになってしまった。そして、その後例によって居酒屋でお酒の時間になったのだが、いつもよりスタートが遅かったことと、総会の件で盛り上がったことが重なって店を出たのは11時を超えてしまった。その後、駅で電車待ちをしている間、線路を挟んで向こう側のホームにいたメンバーと一緒にエールを歌った。 このように盛り上がったあと、乗り換え駅で改札に向かう私の目の前で電車が発車するところで、そこでのアナウンス・・・「本日の上り最終電車です」・・・がーん・・・終電に乗り遅れ・・・汗・・・
2008.01.28
コメント(2)
-
パート練習
明日の練習は、いつもの通り夜6時から9時までなのだが、その前に午後1時からトップだけのパート練習が追加された。 私がこの合唱団に入って1年ちょっとになるのだが、トップ単独のパート練習というのは、実は初体験となる。今までは、練習効率の関係からかテナー系とベース系という2分割のパート練習が行われてきた。たしかに場所や指導する技術系のメンバーの関係もあり仕方ない部分もあったのだが、音を確認するためには単独の方がやりやすいと思う。 アンサンブル練習では、はっきりしなかった部分を確実にし演奏を充実させるようにしたいと思う。
2008.01.25
コメント(2)
-
ちょっと残念・・・
というか、よかったというか・・・ 前回の日記で書いた東京新聞をゲットした。新聞の1ページを使いクッレルヴォ交響詩のイベントの特集を掲載していた。 掲載された写真には、合唱団では端っこで歌っていた人が写っていなかった・・・汗・・・ 東京新聞のホームページで上記特集が見れますので、よかったら見てください。 http://www.tokyo-np.co.jp/article/forum/list/CK2008012302081747.html http://www.tokyo-np.co.jp/article/forum/list/CK2008012302081746.html http://www.tokyo-np.co.jp/article/forum/list/CK2008012302081748.html
2008.01.23
コメント(0)
-
東京新聞
明日、1月23日の東京新聞朝刊に、昨年末に出演した東京新聞フォーラムのクッレルヴォ交響詩の特集記事が掲載される。出演者としては非常に楽しみ♪ それにしても、まさかこんな形で新聞に自分が載るとは・・・うーん、すこし不思議な感じ・・・ ところで、今回この企画に参加して「東京新聞」が「中日新聞」の子会社ということを初めて知った・・・汗・・・
2008.01.22
コメント(2)
-
慣れ
昨日は、午後からの練習で、「水と影」と「遊星ひとつ」の練習だった。 「水と影」は、作曲者でもありピアノも弾いていただく寺嶋先生との初合わせだった。さすがに初めて合わしたので、こちらの練習不足もありリズムが合わない部分がけっこうあった。それで定演までに追加練習を2回行うことになった。 6時からは、「遊星ひとつ」の練習・・・これもかなりの難曲であるのでなかなか苦労している。その練習のなかで、藤井先生から「慣れ」について以下の指摘を受けた。 音が取れた当初は、正確にピッチを保とうとして歌うのでわりと良いハーモニーになるのだが、ある程度曲に「慣れ」てしまうと、なんとなくという感じで歌ってしまい、ハーモニーが濁る。この合唱団の欠点・・・ ということで、練習した曲について、いろいろ問題点が明確になってきた。 定演まであと1ヶ月・・・その問題点を解決して行きたいと思う。
2008.01.20
コメント(0)
-
初顔合わせ
明日は、午後1時から夜9時までの長時間練習! そして、メインとなる第4ステージでピアノを演奏する寺嶋先生との初顔合わせがあるようだ。 ということで、順番をすっ飛ばして第4ステージの紹介を先に・・・ 水と影、影と水(ロルカ詩、長谷川四郎訳 寺嶋陸也作曲) 一曲目 「馬にのったドン・ペドロ」 演奏時間約8分 ニ曲目 「グラナダと1850」 演奏時間約2分 三曲目 「スペイン警官隊のロマンス」 演奏時間約13分 全部で演奏時間が25分近くにもなる大曲・・・ そして、ピアノが作曲者寺島先生、指揮が藤井宏樹 実はこの曲、2001年に早稲田グリーの委嘱初演された曲で、出版社から発行された楽譜はなく、作者自身の手書きの楽譜で広友会が発行している。 現状としては、1、2曲目は、ほぼ出来上がっており(一昨年の男声フェスで2曲目、昨年の合唱祭で1曲目を歌っている)3曲目を練習中という感じ・・・ 歌っている感じとしては、音の動き、リズム、ハーモニーともに非常に難曲であり、広友会としても非常に苦戦している。しかしながらトップテナーとしては、非常に歌っていて気持ち良いというか、歌いがいがある曲・・・最高音としては「h」まで出てくるのだが、声楽的に考えられて作られており、高音域の連発というような演奏者に苦痛をしいるような感じはない。しかも、藤井先生いわく通常では書かないようなハーモニー進行であり「狂気、血なまぐさい」というような感じ・・・ たしかに、歌いこんでいくほど力が入ってくる曲だと思う。演奏者としてどこまで表現できるか・・・とても楽しみなステージだと思っている。
2008.01.18
コメント(0)
-
マンチュヤルヴィ作曲「Die Stimme des Kindes」
この曲は、第二ステージの1曲目(予定) 演奏時間は約5分、1998年に作曲された現代曲でカウンターテナー2パートを含む計8パートで歌詞はドイツ語・・・ カウンターテナー1の最高音は「ハイG」でほとんどソプラノの音域になっている。男声合唱で混声合唱の音域を歌うという、けっこう無茶な曲だと思う。 当初は、「トップ病患者」である私にとっては、内声パートを歌うこと自体苦痛だったのだが、音が入ってくるにつれて他パートとのハーモニーがけっこう気持ちよくなってきた。曲が出来上がっていくにつれて、面白くなってきているのも事実・・・ 最高音が高いので、第一ステージの「エレミア哀歌」より聴いていただく方には違和感を与えてしまうかもしれない。あるいは、今まで聴いたことのない音色を楽しんで頂けるかも・・・このあたりは、聴き手の感覚にゆだねるしかないかも・・・大多数の人に支持してもらえる曲ではないかもしれないが、面白いと思っていただければ・・・って感じかな・・・
2008.01.16
コメント(0)
-
ウィリアム・バード作曲「エレミア哀歌」
そろそろ定演まで1ヶ月と少しとなってきた。そこで、ここでは定演曲の紹介・・・というか、歌っていての感想などについて書いてみたいと思う。 全4ステージ構成となる予定なのだが、そのステージ順に書いていこう♪ まずは第一ステージ、ウィリアム・バード作曲「エレミア哀歌」・・・ 演奏時間は、約11分・・・ 作曲されたのは、約400年前、日本で言えばちょうど戦国時代から江戸時代初期に当たる。カウンターテナーを含めた5声部のポリフォニー合唱曲(アカペラ)・・・ポリフォニーとは、各声部がそれぞれ独立したメロディラインを歌い形になっている。 私の担当するトップテナーの最高音は「G」、最高音部のカウンターテナーは「ハイC」となっている。通常のカウンターテナーの最高音にしてはさほど高くなく、トップテナーに至っては、「G音」は歌っていて一番気持ち良い音域、しかも「第九」のような高音域連発もなく音の動き、ハーモニー、リズムも特に難しくはない。しかしながら歌ってみると・・・難しい・・・特に今までの胸声に頼った歌い方では、歌えない・・・私に発声についていろいろ考えさせた曲であり、「発声改良」の原点となっている。それは私個人だけではなく、合唱団全体の発声も改良している・・・そして、その「発声改良」のある程度の結果が定演では出せると思う。 今までになかった男声合唱のハーモニーが届けられたら・・・と考えている。
2008.01.14
コメント(0)
-
飲みすぎ・・・汗・・・
土曜日の練習後、例によって居酒屋で合唱談義に花を咲かせた。そして、その後意気投合した同じパートの方と私の行きつけのバーへ2次会に繰り出した。そして、そこでも同じように合唱の話を中心に盛り上がり、結局3時過ぎまで飲んでしまった。お酒の量としては通常の1.5倍くらいだろうか・・・なんとか無事に帰宅したのだが、今日(というかもう昨日か・・・)は二日酔いでほとんど一日ベットの上で過ごしてしまった。うーん・・・ ところで、定演に向けての練習状況は着実に進んでいるような感じだ・・・私自身苦手だったマンチヤルビの曲も音がほとんど入ってきて歌えるようになってきたのだが、問題はフインランド語とドイツ語だな・・・全体も出席率が良いこともあり、発声も安定してきて、この団特有のハーモニーが鳴って来ている。それにしても曲が完成に近づくと歌っていても楽しくなってくる。 さて、今度の土曜日は13時~21時までの長時間練習で、しかも藤井先生の指導となっている・・・楽しく歌えるように自習をしておかなければ・・・汗・・・
2008.01.13
コメント(2)
-
立ち位置
今の合唱団に入って、3回のステージを経験した。私が歌った位置は、2回が最前列の左端、残りが中段のセカンド寄り・・・私にとって歌いやすかったのは「最前列左端」・・・真ん中に入ったときは、曲の出来具合の関係もあったのだが、いろいろな声が聞こえ過ぎて集中出来なかったような感じで歌いにくかった。 端っこの場合、自分のパートはあまり聞こえないが他パートが積み上げるハーモニーが全体のまとまりとして聞こえてくる。また、クッレルヴォのようにオケとの共演の場合は、オケの音も含めて全体の響きとして聞こえてくる。ホールの響きにもよるかもしれないが、私にとっては端っこの状況の方が歌いやすいようだ・・・
2008.01.11
コメント(4)
-
前回練習の録音
を聴いた。参加人数が今までで一番多かったこともあるのだが、なかなか良い響きが出ていたと思う。合唱団としてバードのエレミア哀歌を主体として取り組んでいる「発声改良」の成果が出てきたような感じだ。 50人で歌う、古典のポリフォニー・・・今回の定演での重要なステージだと私は思っている。 他のステージも、この曲の発声を基本にして歌われる。さあ どこまで作り上げていけるか・・・頑張ろう♪
2008.01.09
コメント(0)
-
初練習
先週の土曜日は、今年の初練習+新年会だった。さすがに定期演奏会まで一ヶ月半となり、ほぼフルメンバーでの練習だった。 練習は、当初の予定を変更して「遊星」以外3ステージ分の定演曲の通し練習だった。ほぼ完成している曲、まだまだの曲といろいろあったのだが、難曲ぞろいの定演レパにしては完成度が上がってきたように思う。残り一ヶ月半の練習で集中して仕上げていけば私自身としては、なんとか全ステージ歌いきることが出来そうだ。だた、発声のフォームだけは崩さないように注意をする必要があると思う。 練習後の新年会も、30人以上の参加でけっこう盛り上がっていた。毎回のことではあるが、練習後の「お酒」は楽しい・・・
2008.01.07
コメント(2)
-
のだめ
昨晩の「のだめ」・・・またまた感動させてもらった・・・原作の雰囲気を壊すことなく、原作の二次元の表現から実際の役者が演じる三次元・・・いや、素晴らしい音楽も加えた「四次元」の表現は、とてもよかったと思う。 今回、千秋が観客から「ブラボー」をステージ上で受けたとき、また、自分の演奏の評価として、「とても感動した」という言葉を受けたときの千秋自身の心情・・・クッレルヴォで演奏者としてステージ上や後での観客の評価など同じ経験をしたことにより、とても共鳴を受けた・・・ やはり「音楽」は素晴らしい♪
2008.01.05
コメント(2)
-
明日は・・・
今年最初の練習となる。第25回定期演奏会まであと一ヶ月半となった。個人的な状況としては、バード、水と影、については、ほぼ音が入り歌えるような状態だと思う・・・ただし、ここ3ヶ月ほど歌っていないのは多少心配だが、一回入ってしまえば大丈夫だと思う。 遊星に関しては、前回定演でもやっている曲なので今のところ練習回数が少ない・・・ただ、私のように前回定演に立っていない人間にとっては非常に厳しい曲・・・しかし、私が歌うパートは通常のトップなので音もけっこう入ってきていると思う。 問題はマンチヤルビの2曲・・・明日の練習にそなえて自分で頑張らなければ・・・ ここですこし愚痴のコーナー・・・ 先月の遊星の練習での技術系からの一言・・・「遊星に関しては、前回定演に立っていない方にとっては非常に厳しいと思いますが、まわりが歌えるから大丈夫ですよ」 周りができるからって、歌えるようになるわけでもないし・・・周りの音を聴いてから声を出すつもりもない・・・合唱は、一人一人が歌えなければダメだと思うし、逆に言えば、そんな音楽をつくるのに不必要な声を出すつもりはまったく無い・・・なにが「大丈夫」なのか・・・ ところで、本当に周りは歌えているのですか? (あくまで愚痴のコーナーなので適当に流してください)
2008.01.04
コメント(0)
-
新年
明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 さて、今年第一回目の日記になるのだが・・・ 年末から大晦日にかけて、見ていたテレビの中で非常に衝撃を受けた番組があった。それは、NHKのドキュメンタリーで2007年に「チャイコフスキーコンクール」のヴァイオリン部門で1位になった神尾真由子さんの特集・・・21歳の女性が音楽と向き合う姿・・・「天才」と一言で片付けてしまえばそれまでなのだが、「天才」になるためには努力が必要ということを改めて感じた。 しかし、一番感動したのは、彼女が奏でる「音」・・・1音1音が強く心に残るような「音」・・・ ヴァイオリンと歌とでは違うかもしれないが、音を出すことは同じ、私も「感動する音」を目標にしたいと思う。 (初っ端から音楽ネタ・・・汗・・・)
2008.01.02
コメント(2)
全17件 (17件中 1-17件目)
1