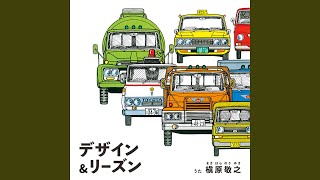2010年08月の記事
全46件 (46件中 1-46件目)
1
-
フルオーケストラの壁
壁シリーズの第二段です・・・汗・・・2007年12月、当時音楽監督だったF先生の指導する合唱団のうち、男声とアイノラ交響楽団との共演、シベリウス作曲の「クッレルヴォ交響詩」ステージには、約80人のフルオーケストラ、その後ろに約70人の男声合唱団・・・この演奏会のゲネプロが終わったあとの、F先生の指示は・・「音量のリミットをはずしてがなり散らせ」・・・ここからは私の推測であるが、大編成オケの圧倒的な響き・・・これに合唱団員が萎縮することがないように、今まで積み重ねてきた発声をベースに気迫を加えることによる効果を計算した上での的確な指示だったのだと思う。その結果「柔らかくてしかも豊かな音量」という難題をクリアできたのではないかと思う。
2010.08.31
コメント(0)
-
壁
合唱祭やコンクール、他団の定演を客席で聴いて時々感じることがある。 それは、ステージと客席の間に「壁」を感じること・・・ ステージで歌っている側の音量不足もあるのだが、歌う側の「気持ち」も伝わってこない場合もある。 はたして、自分たちの演奏は、その「壁」を超えて客席まで伝わっているのだろうか? この壁を越えなければ、観客との一体化は無理・・・ 観客との一体化の次の段階は・・・ 指揮者の目標は、「はるか向こうの存在と合唱する」 ホールの外の並木、風、雲、夕映え、闇の空、そして星たち、 さらには、その背後においでになるはずの神さまと。 そういう存在に声を出させて合唱させてこそ、 人間たちの合唱団なのではないでしょうか
2010.08.30
コメント(0)
-
アンサンブル・トレーナー
先日の練習は、7月の定演が終わってから、音取りを続けていた松下耕作曲の「そのひとがうたうとき」の1番と3番のアンサンブル練習だった。 練習を担当したのは、アンサンブル・トレーナー・・・ 以前、音楽監督制の場合は、団内指揮者がある程度の曲造りを行い、月1回の音楽監督の練習に備えるという形を取っていた。 そして、音楽監督制を辞めた昨年からの練習は、「アンサンブル・トレーナー」という役職を新たに設け、パート練習から音取り、そしてアンサンブルの骨格部分造りを行って指揮者に渡すという形式に変わった。 こうやって文章に書いてみると、団内指揮者がアンサンブル・トレーナーに名前が変わっただけのような感じなのだが、以前の団内指揮者は、定演のステージを持つ「指揮者」になったため、アンサンブル・トレーナーという重要な役職が新たに造られた。
2010.08.30
コメント(4)
-
東京都男声合唱フェスティバル
次回、広友会がオンステするイベントは、 東京都男声合唱フェスティバル 11月23日(祝)浜離宮朝日ホール 略して"男フェス"。東男の集まる熱い一日。連盟加盟や都道府県も問わず、4名以上の男声合唱を楽しむグループであれば性別も問いません。参加団体の互選により人気投票が行われ、1位になった団体は次年度の大会に招待されます。また毎年公募による合唱団を組織、著名な先生をお呼びして指揮をしていただき、最後を飾ります. 参加する団体は、50団体以上・・・丸一日男声合唱三昧となります。 昨年は、たしか4票を頂き、2位タイでした。 私が広友会に入会したのは、2007年11月・・・さすがにその年のオンステはせず、客席で聴いていたのですが、参加合唱団の多さに驚きました。 東京には、こんなに男声合唱団があるんだ・・・汗・・
2010.08.29
コメント(2)
-
発声法の教科書
私の胸声(実声)主体の発声法を、改良するために参考にしたのは、当間先生のHPと、その参考文献となっている、 リードの「ベル・カント」唱法(その原理と実践) ○[コーネリウス・L・リード 渡辺東吾訳 音友1986年(原書は1950年)] この本は、声楽が最も盛んになり完成した、17世紀のルネッサンス・バロック期の発声法について書いてある。 声の「ひっくりかえり」を無くしたい方、高音域を楽に歌いたい方にお勧めの文献です。
2010.08.27
コメント(0)
-
観客との一体化
私が、今回25年以上のブランクの後、合唱を復活させた後のいろいろなステージで観客と一体化できたなと思った(もしかしたら自己満足も入っているかも・・・)ステージは、 ・今年の7月 東京都合唱祭 海鳥の詩、3、4曲目 ・2008年 東京都合唱祭 シェナンドアー ・2007年 アイノラ交響楽団との共演でシベリウス作曲「クッレルヴォ交響詩」およびアンコールの男声合唱付きフィンランデア これは、もちろん私自身の感覚で書いています。 もちろん、他にも良い演奏だった曲もあったのですが、観客との一体化ができたと思ったのは以上の曲でした。 今後も、上記に書いた曲以上の演奏をしたいと思っています
2010.08.27
コメント(0)
-
組曲と曲集の違いについて
今、手元に2冊の楽譜がある。 男声合唱組曲 「海鳥の詩」 男声合唱曲集 「そのひとがうたうとき」 組曲と曲集の違いって、何だろう? 私の勝手な推測では、 組曲は、最初の曲から最後の曲まで曲順通り演奏して一つの音楽になる。 曲集は、同じ作詞家の、それぞれが独立した曲を集めたもの。ということは全曲演奏しても良いし、抜粋演奏しても良い。 という感じかな?
2010.08.26
コメント(0)
-
ステージ途中での拍手
昨年の定演、第3ステージは4曲、その3曲目が終わった時、2,3人の観客の方から拍手があった。 そして、今年の定演、第4ステージは6曲、その2曲目が終わった時、同じように拍手があった。 上記のステージは、組曲ではなく、いろいろな曲を集めて演奏したステージ 歌っている方としては、邪魔なような、嬉しいような複雑な気持ち・・・ 指揮者は、もちろん無視をして先を進めたのだが・・・ そういえば、学生時代にもおなじようなことが・・・たしか日本民謡を集めたステージだったのだが、1曲目から拍手がおこり、それに対して指揮者の先生は無視せずに指揮台を降り観客に礼をした。結局、そのステージは全曲、礼をすることになってしまった。
2010.08.25
コメント(0)
-
声量のバランス
先月の合唱祭の講評や感想が、まるで「褒め殺し」状態で、私が今まで歌った4回の合唱祭のなかでも一番好評だった。 前の日記では、その講評や感想のなかにある「ダメ出し」に関して書いた。 なので、今回は「好評」だった理由を考えてみると・・・ まず、当然のことだが、2週間前の定演の中の2曲、ほぼ曲自体はメンバーのなかに入っている。 定演では、ホールの残響が長いため、若干声量を抑えて歌っていたのだが、合唱祭のホールは、ほとんど残響がない・・・ということは、声量を抑える必要はない。ということで、各パート気持ちよく歌っていたのだが、定演での各パートの声量のバランスは崩さずに歌ったことが考えられる。 すなわち、各パートの音量バランスを崩すことなく、自然に演奏に厚みを持たせることが出来たからだと思う。
2010.08.24
コメント(0)
-
漂流
先日の練習は、「そのひとがうたうとき」の3曲目、音取りのパート練習・・・と言ってもテナー系とベース系の2班に分かれての練習・・・ その後、全体で母音唱・・・最後に歌詞つけして終了・・・TOPとしては、歌えるところと、まだ音が不安定な部分がはっきりしたので、次回までに復習をして歌えるようにしておこう。 その後、15分くらい会議を行い練習終了 その後、いつもの中華料理屋で1時間ほどのアフター・・・ また、来週には、いろいろ会議が行われるようだ。 今、この合唱団は、明確な行き先を(途中の寄港地を含む)見失って現在「漂流」中・・・ 来年の定演用の楽譜は、全てそろったのだが・
2010.08.23
コメント(0)
-
合唱祭の講評
先日歌った東京都合唱祭の講評(専門家)と感想(各合唱団)が、メーリングリストで流された。 歌ったのは、海鳥の詩より3、4曲目 2週間前に定演で歌っていたこともあり、自分なりにはけっこう満足できるステージだった。 専門家の講評や感想は、とても好評だった。 ただ、少数ではあるが、ダメ出しされていた個所もあった。私たちにとってはその少数意見が重要・・・そのポイントは・・・ ・TOPテナーの発声が揃っていない ・曲の立ち上がりが揃っていない 私自身、いつも感じているところであるが、どうやって修正していくか・・・ 簡単に言ってしまえば、「発声を揃えれば良い」「指揮者の棒に合わせて自分から歌って行くこと」だと思うのだが・・・
2010.08.22
コメント(0)
-
2週間ぶりの練習
今日の夜は、2週間ぶりの練習・・・しかし、また会議が入っている。 合唱団を運営していく上で、会員の意見を求める必要があることは仕方ないと頭では理解しているのだが・・・ まあ、愚痴はこれくらいにして・・・ 現在練習中の松下耕作曲「そのひとがうたうとき」 1曲目の音取りが終わり、2曲目をとばして3曲目の音取り中・・・ 音源は全曲あるので、聴いてみた・・・ 今の状態での感想は、今まで私が歌ったことのないタイプの歌・・・ 曲の感じは「可愛くて、おしゃれ」 歌詞は谷川俊太郎の詩から、地球や全てのものに対する「愛」が表現されている。 なかなか良い曲だと感じている。
2010.08.21
コメント(0)
-
文化会系か体育会系か
私は、中学生時代は吹奏楽部だった。音楽関係なので文化会系だったのだが、体育会系の要素(先輩、後輩関係)もけっこうあったと思う。 大学時代は、男声合唱団・・・体育会系の要素は、中学時代と同じ・・・学年による上下関係は当然のことながら存在していた。 では、今はどうかと考えると、広友会全体では決まりがあって、若い人にも、年配の方にも名前を呼ぶときは「さん」をつける。先輩・後輩的な関係を排除しようとしている。なので、全体的には文化系だと思う。 ただ、全体的と書いたのは、部分的には同じ大学からの先輩・後輩関係が部分的ではあるが残っている。 私の場合は、とくに先輩はいないので、けっこう大きな顔(声も)をして歌っている。
2010.08.20
コメント(0)
-
練習の録音
私は、曲が8割くらいの出来になったとき、ボイスレコーダーで練習を録音する。 レコーダーを置く位置は、指揮者の後ろ・・・ 目的は・・・ ・音程やリズムなど基本的なところで間違いはないか ・全体のアンサンブルの自分の声のバランスの確認 ・指揮者の指示の確認 などなど、けっこう有効な練習の復習になると思う。
2010.08.20
コメント(0)
-
声のひっくりかえり
発声改良を行う前、私の声のひっくりかえる高さは、B~H・・・ なので、男声4部のTOPテナーとして、ほとんどファルセットを使う必要はなかった。 広友会に入った当時も実声でガンガン歌っていた。 そこに現れたのは、バードのエレミア哀歌・・・カウンターテナーを含む男声5部・・・パート再編のとき私は、高音域ファルセットの使い方がうまくないので、TOPテナーになった。一番上を歌いたがる「テナー馬鹿」だった私にとっては、微妙な気持ちだったが仕方なかった。 そして、相も変わらずエレミア哀歌も実声で歌っていたら、どうにもアンサンブルがうまくいかない・・・自分がガンガン歌っているとき他のパートの音が聞こえない・・・ポリフォニー音楽では致命的・・・ 自分の影響でアンサンブルがうまくいかない・・・他の方からも指摘され、落ち込み、今のままではまずいので、いろいろ調べて発声改良を行った。
2010.08.19
コメント(0)
-
練習日
次の練習まで、木、金、そしてやっと練習日の土曜日・・・二週間ぶりに歌えるか・・・そういえば前回の総会で積み残した議題がある。うーん、歌える時間が減ってしまう。出来れば、歌う前に決着をつけ、その後練習にした方が良いと思う。そうでないと、2回連続1時間押しになって、アフターに行けていない・・・ ところで、広友会の練習は、基本的に土曜日の午後6時から9時の3時間となっている。 サラリーマンにとっては、一番行きやすい時間だと思う。
2010.08.18
コメント(0)
-
発声改良の結果
前回書いた発声改良の結果について、 長所 ・ピッチが下がらなくなった。 ・無駄な力は、入らなくなり、リラックスして歌えるようになった。 ・他パートや自分のパートの音が聴きやすくなった。 ・実声が必要な場合、とくに問題なく切り替えられる。 ・「声のひっくりかえり」が無くなった。 短所 ・息の量が必要になるため、息が不足する。 こんな感じかな・・・汗・・・
2010.08.17
コメント(0)
-
実声からファルセットへの移行
ここから書くことは、当間先生の合唱講座(HP)を参考にして、私が行っている発声法です。あくまで、私の発声で他の人に合うかどうかはわかりません。 声帯の状態について言葉の定義をしておきます。 実声・・・声帯に力を入れて圧縮させている状態 ファルセット・・・声帯をストレッチ(引張)している状態 実声からファルセットへの移行は、声帯に力が入って圧縮している状況から、まったく逆の引張の状況への移行、このときに「声のひっくりかえり」が発生します。 では、その「ひっくりかえり」をなくすにはどうすれば良いか。 答えは、すべてファルセットの声帯の状況で歌う。ただ、最初はファルセットは細く芯のない声になるかも知れません。そこで、そのファルセットを強化する。 これが今の私の発声法です。もちろん曲として実声を使わなければならない場合もありますが、そのときは当然実声で歌います。 詳細は、当間先生のHPを参考にしてください。 http://www.collegium.or.jp/~sagitta/ocm_homepage/html/kouza.html
2010.08.17
コメント(0)
-
明日に架ける橋
私は、ビートルズ世代のちょっと後になる。中学の時からS&Gのファンになり、はじめて買ったLPレコードもS&Gだったと記憶している。S&Gの曲のなかでも「明日に架ける橋」が、もっとも好きな曲だった。大学4年のとき、副指揮者のステージで「ポピュラーソング集」をやることになった。そのなかに「明日に架ける橋」も入った。顧問の先生の編曲により全ての曲は歌ったのだが、「明日に架ける橋」の編曲は、1番がソロとピアノ、2番がソロとピアノとハミング、3番が合唱とピアノという編曲になっていた。そして、私がソロを担当した忘れられない曲のひとつ・・・ .
2010.08.16
コメント(2)
-
反省会の必要性
広友会には、定演についての技術的反省会が無い。 定演を境に年度を区切っており、予算や決算、出席状況などの事務的処理に関しては「総会」で質疑応答があり、決定する。 しかしながら、定演に関する技術的な反省は、行われていない。 音楽監督制の場合は、責任はすべて音楽監督のところにあり、音楽監督と一部の技術担当の会員で行われてきたと思うし、それで問題は特になかったと思う。 私は、定演CDを聴いた今の状況で、定演に関する技術的総括を会員全員で行う必要があると思う。 合唱団の技術的レベルを上げるために・・・
2010.08.16
コメント(2)
-
誰でも知っている歌
今の選曲方針では、1ステージを「誰でも知っている歌」入れることになっており、先日の定演では、「ふるさとの四季」来年は寺嶋陸也編曲の「ふじの山」(明治、大正の唱歌集)が選曲されている。 童謡・唱歌であれば、たしかに「誰でも知っている曲」に該当すると思われる。 まあ、来年まではすでに決定しているため、良しとして・・・ 次をどうするか・・・例えば、宮崎駿映画アニメソングとか、ミュージカルナンバー、ビートルズやカーペンターズ・・・こんな感じになるのか・・・ 何か情報があれば、教えてください。
2010.08.15
コメント(0)
-
ショウボート
大学時代、先生の編曲により歌った「オールマンリヴァー」・・・当時は「ザッツ・エンタテインメント」の一部で紹介されているのは知っていた。 今では、古い映画のDVDが500円で手に入るため、4年くらい前にゲットし見た。 なかなかの名作ミュージカルであるのだが、使われている曲も良い。 ところで、このミュージカルを作曲したのが、ジェローム・カーン・・・ そのジェローム・カーンの伝記映画「雲流るるままに」も500円DVDで発売されている。これも、なかなか良い映画・・・ そういえば、広友会では以前ミュージカルのステージを定演で歌ったことがあるそうだが、この曲が入っていたかは不明・・・汗・・・
2010.08.15
コメント(0)
-
揃った音楽と動く音楽
うーん、いつもの土曜日なら、そろそろ練習に出かける時間なのだが・・・ 昨年度の東京都合唱コンクールを聴きに行き感じたことなのだが、合唱には2つの演奏タイプがあるように感じた。 それは、「揃った音楽」と「動く音楽」 「揃った音楽」とは、歌い手の音程、リズム、発声、声量、音色(これは、揃えるのは難しいかも・・・)、曲解釈の各要素を、各パートできっちり揃えた音楽 「動く音楽」とは、歌い手の音程、リズム、曲解釈は揃えるのだが、他の要素、発声、声量、音色は、曲解釈をベースにして歌い手それぞれが廻りの音を聴きながら「自分の歌を歌う」・・・それを聴いていた私は、「動く音楽」を感じた。 先日の合唱祭でも、その「動く音楽」を聴くことができた。 けっして、「揃った音楽」を、否定しているわけではないが、私個人的には「動く音楽」の方が気に入っている。
2010.08.14
コメント(0)
-
目標
今日は、お盆休みのため練習はお休み・・・ いつもの練習がないのは、なんとなく寂しい・・・ 特に、先月行われた定演の総括がまだ終わっていない。 「音楽監督制」を辞めて最初の「定演」そこで発生した問題点。 今後、広友会は、どんな合唱団を目指すのか?会員一人一人考えていく必要があると思う。 私としては、1年に1回の定演を目標にし、聴きにきて頂いた観衆の方と一体となった「楽しい音楽の時間」をつくって行きたいと思っている
2010.08.14
コメント(0)
-
練習出席率
先日行われた総会で、練習出席率の話がでた。全体では76%、パート別では、一番成績の良いのがベースで80%、残念ながらワーストはTOPテノールで72%・・・他の合唱団の出席率はわからないのだが、平均的には、まあまあ良い数字だと思う。 今回、私はすこし体調を崩していたため、多分50%くらいの出席率だったと思う。 しかし、なんとか全ステージ大きな事故もなく、歌いきることが出来てほっとしている。 今回の経験で分かったのだが、いかに普段の練習が大切かということ、そして練習自体が楽しいということだった
2010.08.13
コメント(2)
-
合唱団の個性
当間先生のHPに「音色」について書かれています。 http://www.collegium.or.jp/~sagitta/ocm_homepage/html/kouza_backnumber/kbn22.html 「音色は個性」 音程やリズム等、合唱に必要な揃えるべき要素とは別に「音色」があるということだと思います。 ということは、その個性の集まりが「合唱団の個性」になるのではないかと思います
2010.08.13
コメント(0)
-
個人の責任
広友会では、自習用に演奏曲の音源を作成している。その上で、一週間に1回の3時間の練習でも音取りをしている。 他の合唱団では、音程とリズムは各個人の責任として音は取れているという前提で練習を行うところもあると聞く・・・ 当然、各個人で音取りが終わっていれば、最初から全体でのアンサンブル練習が可能で、非常に効率も良いと思うが、個人の負担は大きくなると思う。 まあ、広友会は30年以上現在の方法でやってきているし、今後も同じ方法で進んでいくのだと思う。ただ、出席できなくて音取りが終わってしまったら自分で自習するしかない。 昨年度の出席率は、全体で76%・・で、一番出席率の悪いのは言うまでもなくTOPテナー・・・72%・・・汗・・・
2010.08.12
コメント(0)
-
練習会場
広友会の練習会場は、決まった場所はなく、都内のいろいろな施設を利用している。以前は、会員の会社の会議室を使わせてもらっていたようなのだが、セキュリティの厳しい現在では無理な話・・・ しかも、練習状況によって、パート練習用に2部屋とか、ピアノが必要とかいろいろ違ってくる なので、会場係の方には、大変なご苦労をかけている。 もちろん練習会場によって、残響は違ってくる。歌う方にとっては、いつも同じ状況の方が、慣れて歌いやすいのだが、逆に考えれば、違った場所での練習は、いろいろな状況にも対応できる練習にもなると思う。 本番のホールでは、当日リハ以外通常は練習できないのだから・・
2010.08.12
コメント(0)
-
25年間の空白
私の合唱歴は、大学時代の6年間と広友会の4年弱・・・合計10年・・・大学卒業から広友会に入会するまで約25年間の空白がある。広友会という、30年以上の歴史のある一般社会人合唱団に入って、最初はついていくのに必死だった。たまたまパートがTOPテナーということもあり、音取り段階ではそんなに苦労は無かったのだが、実際にアンサンブルに入ると、胸声しか使えない力まかせの発声では、アンサンブルを壊す声でしかなかった。また、当時は音楽監督制であったため、「遊星ひとつ」という難曲や、カウンターテナーの入る曲で内声パートも経験した。発声の方は、なんとか改良しアンサンブルを壊すことは無くなったのだが、まだまだ25年の空白を埋めることは出来ていないと思う。これからも、いろいろ吸収して25年の空白を埋めていきたいと思う
2010.08.11
コメント(2)
-
発声の弱点
私の発声法は、声帯をストレッチし息で支える。すなわちファルセットのポジションで歌っている。 この発声は、のどに力をいれていないので、高音域になってもわりと楽に声を出すことが出来る。 また、最初からファルセットのポジションをとっているため、実声で歌っていてファルセットに切り替えるときの「声のひっくりかえり」がおきない。 ただ、この発声は「息」で支えているため、実声で歌う場合と比較して息が多く必要になってくる。 しかし、音楽的にどうしても繋げなければならないフレーズもあるため、どうしてもカンニングブレスが頻繁に必要になってくる。もう少し、息の量があれば良いのだが・・
2010.08.11
コメント(0)
-
今週は
お盆なので、今週の土曜日は練習が休みになっている。合唱祭も終り、8月から新年度・・・そして、新しい曲との出会い・・・松下耕作曲 「そのひとがうたうとき」今1曲目の音取りが終わって、3曲目の練習となっている。松下作品は、前回のアヴェ・マリアに続いて2曲目となる。まだ、音取りの段階だが、けっこう良い曲だと感じている。とくに3曲目は、曲集のタイトルになっているくらい・・・頑張って、練習しておこう・・・汗・・
2010.08.10
コメント(0)
-
良く通る声
最近、動画サイトで一人で各パートを歌った「多重録音」がある。 当然、一人で歌っているので「声質」は同じなので、歌い手が上手であれば綺麗なハーモニーになる。ただ、私的には生演奏では不可能なので、ちょっと不自然な感じがする。 それと比較して通常の合唱は、いろいろな「声質」を持った楽器=身体の集合体だと思う。 各パートで発声を統一し「声質」をできるだけ揃え、ピッチを合わせる。それでも歌い手自身の楽器が違うので完全に合わせることは不可能だと思う、とくに大人数の場合は・・・ 「声質」の一部に入るかもしれないが、「声の通り」・・・これも楽器の性能によって変わってくると思う。 定演のCDを聴いていると、よく通る声の人が「芯」となって聴こえ、そのまわりに厚みのあるハーモニーが鳴っている・・・いや、「芯」というかメロディ担当パートの声なのか・・・ いずれにしても、各パートには「芯」となる声は必要だと思う。
2010.08.09
コメント(0)
-
定演CD
昨晩の練習時に、定演CDの配布があった。 家に帰って聴いてみると・・・ 演奏中に客席で携帯の呼び出し音が鳴る・・・という事故以外は、ほぼ練習の成果はある程度出せたと感じた。 残響が長いホールということで、音量を抑えて歌った効果もあったように感じた。 ただ、その分「男声合唱」の魅力のひとつである、「迫力」がイマイチ出せなかったのは残念・・・ 新体制によるスタートの定演・・・音楽監督制を辞めて得た「自由」ただし、この「自由」には、今後、広友会がどのような合唱団を目指すのかということを、会員ひとりひとりが考えていく必要があると思う。
2010.08.08
コメント(0)
-
パート練習
広友会では、練習会場の都合により、ベース系とテナー系の2班に分かれてパート練習を行う。 昨年度は、指導者の不足等の事情により、パート練習はあまり出来なかった。そのため、音取り等が効率の悪い結果となってしまった。 その反省を生かし、現在は新曲の音取りをパート練習で行っている。 そして、時間があれば、ある程度全体での曲つくりが出来た段階で、再度、歌い方等の練習をパートで行うのが理想だと思うのだが・・・ 週1回、3時間の練習で1年に1回の定演では、なかなか難しい面もあると思う
2010.08.07
コメント(0)
-
愛唱曲がない
広友会では、多田先生に作曲して頂いたエール「ディオニュソスの息子達」がある。しかし、その他に皆で歌う「愛唱曲」が無い・・・原因は、広友会自体、どこかの大学のOB合唱団ではなく、いろいろな大学等から集まっていることで、なかなか一緒に歌える曲がない。また、ここ10年ほど定演で歌った歌は、難しく愛唱曲には向かないようだ。
2010.08.07
コメント(0)
-
名古屋地区大学合唱連盟
通称「合連」タイトルが正確かどうか、今となっては不明なのだが・・・要は、名古屋地区の大学合唱団の集まり・・・そして、夏休みにこの「合連」が企画するキャンプが行われる。その規模は、(うろ覚え)700人くらいが参加してそれを、15人前後のグループに分けて、ユニホームを造ったり食事の段取りなど一か月前から準備を行う。そして恵那で行う。最後のキャンプファイヤーは、盆踊り、フォークダンス(倍速マイムマイムは大変・・・)そして最後は、全員合唱で夕方6時から11時くらいまで行った。今となっては、学生時代の思い出・・・・・・・・・・「合連」・・・・・・さすがに、もう無くなっただろう。
2010.08.06
コメント(0)
-
碑
8月6日、広島に原爆が落とされ多くの命が失われた日・・・ その中で、広島2中の1年生全員の命が失われた。それを題材にした曲がレクイエム「碑」 私は、この曲を大学5年の時に歌った。たしか全9曲、演奏時間は40分を超える大曲で、ものすごくストレートにその悲劇を歌っている。 広友会は、広島メンネルコールの東京部会からスタートした。「碑」は、その広島メンネルが初演している。 音楽は、私たちの知らないところでも、繋がっているのかもしれない。
2010.08.06
コメント(0)
-
エレミア哀歌再・・・
3年前の第25回定演で歌ったのが、バード作曲「エレミア哀歌」・・・私が発声改良するきっかけとなった曲。 来年の第28回定演で歌うのが、タリス作曲「エレミア哀歌1」 この曲は、5声部のポリフォニー・・・楽譜には「アルト」と書いてあるパートは、カウンターテナーが担当する。 通常、広友会は男声4部のパートなので、あらたに他パートからカウンターテナーが歌える人を集めることになる。 私の場合バードのときは、通常のTOPテナーを歌った。 さて、今回はどちらになるのか・・・
2010.08.05
コメント(2)
-
心に残る歌
私の合唱経験(大学6年、広友会4年)で演奏した曲のなかで、心に残っている歌を挙げると・・・・シベリウス作曲「クッレルヴォ交響詩」これは、オケと男声合唱とソロの共演、全5楽章で男声合唱は、3、5楽章で共演、全80分の大作・マンチュヤルヴィ作曲 Die Stimme des Kindes(幼子の声)はじめての内声パート・・・ハモリを制御する楽しさを体験・多田武彦作曲 「柳河風俗詩」広友会での初ソロ・石井歓作曲「枯れ木と太陽の歌」大学1年で歌った、ソロを失敗・・・いつかリベンジしたい・バード作曲「エレミア哀歌」発声改良をするきっかけの曲・広瀬量平作曲「海鳥の詩」大学、広友会で歌う。・山田耕作作曲「赤とんぼ」大学2年、初のソロ成功・三善晃「遊星ひとつ」広友会で歌う・・・難曲こんな感じですね
2010.08.05
コメント(0)
-
ハモネプ
>ハモネプとは、アカペラのコーラスにスポットを当てた企画。楽器を使わずに声だけですばらしいハーモニーを奏でる高校生を中心とした若者のパフォーマンスを応援していこうという番組。 リードボーカルやコーラスパートだけでなく、ベース音、ドラム音、ボイスパーカッションが加わり、本物のバンドさながらのサウンドを奏でる。という番組で、私もときどき見ているのだが、ほとんどのグループに対して「ハモってないよ~」とテレビに向かって言っている・・・汗・・・たまに、合唱をやっている高校生も出てくるのだが、なんか雰囲気が合わない。マイクを通しての歌となるため、どんな発声で歌えば良いのか・・・多分、上手で歌のうまいリードがいて、音程の良いコーラスと、すごいボイスパーガッションがいれば優勝できる・・・かな・・・
2010.08.04
コメント(2)
-
大学グリーの衰退
約30年前、私が学生時代は、ほとんどの大学に「合唱団」があった。 ・・・大学グリー全盛時代・・・ ところが、一部の大学を除き、今は私の学校も含めて合唱団が無くなってきている・・・高校以下は、Nコンなどで盛り上がっていると思うのだが・・・ 何故だろう・・・理由を考えてみると・・・ まず、大学は自由であること・・・いろいろな部活やサークルがあり、もちろん部活等に無理に参加する必要がないことが考えられる。 それと、「趣味の多様化」ということもあると思う。 高校までに、Nコン等で燃え尽きてしまうのだろうか
2010.08.04
コメント(2)
-
夏合宿
夏になると、大学時代の合宿練習を思い出す。日程は、たしか4泊5日・・・場所は、上松・・・中央線で名古屋から2時間程度だったと思う。合唱三昧の5日間・・・最終日前夜は、宴会となり声を潰してしまうのが例年・・・汗・・・
2010.08.03
コメント(0)
-
ステージ衣装
合唱祭やコンクール、演奏会を見ていると、女声合唱は綺麗でカラフルなドレスでそろえてオンステしている合唱団が多い。 混声合唱団は、男声が礼服に蝶ネクタイ、女声は白いブラウスと黒スカートのパターンが多いと感じる。 男声合唱団の場合、礼服に蝶ネクタイ、黒服に黒ズボン、ステージによっては、カラフルなポロシャツに黒ズボン・・・ こうやって並べてみると、合唱団の個性が出せるのが、女声合唱団だと思う。どうやって衣装を決めているのか? そして、自由度がないと思われるのが、混声合唱団・・・男声が派手な衣装が無理なため女声も白黒にしないとバランスがとれないと思う。 今回の定演では、3ステージが黒服に黒ズボン、1ステージがカラフルなポロシャツに黒ズボンでオンステした。
2010.08.02
コメント(2)
-
なぜ男声合唱なのか・・・
私の卒業した大学は、工業大学の土木工学・・・30年前は、今と違ってクラスに女子はいなかった。 したがって、部活の合唱団は当然、「男声合唱団」・・・ それから25年・・・「のだめ・・・」の影響で音楽を復活させようと考えたとき、やはり大学で6年歌った「男声合唱」・・・ そしてネットで調べて見学に行ったのが「メンネルコール・広友会」だった。そして、その場で入会を決めた。 何故、混声合唱が対象になかったか・・・それは、今まで混声合唱は歌ったことがなかったこと・・・混声のテナーは内声になり、男声のTOPテナーと役割がまったく違うことがあった。 まあ、ここまできたら、このまま男声合唱のTOPテナーで歌って行きたいと思っています。
2010.08.02
コメント(0)
-
定期演奏会アンケート
第27回定期演奏会のアンケートが廻ってきた。 結果としては、概ね好評だったのだが、ホールや並び方の影響に関しての指摘があった。 演奏については、ホールの関係で音量を抑えたこともあり、迫力不足という指摘もあった。 また、しっかり書いて頂いた方は、曲によっていろいろなコメントを書いていただいた。 まあ、人それぞれの「好み」の違いにより意見も変わってくる・・・ あとは、録音CDを聴いて反省点を考えていく必要があると思う。自分で演奏したのだから失敗した点もある程度分かってはいるのだが・・・汗・・・ 今後の広友会の音楽の方向性については、会員が「歌いたい歌」と聴衆が「聴きたい歌」のバランスをアンケート結果や録音CDを考慮していく必要があると思った。
2010.08.01
コメント(0)
-
音取り
昨晩の練習は、松下耕 作曲 谷川俊太郎 作詞「そのひとがうたうとき」の3曲目「そのひとがうたうとき」だった。先週までは、1曲目の「わたしたちの星」で、この曲は歌詞付けまで進んでいる。2000年前後に混声や女声で造られた曲を2010年に男声版の曲集として出版された曲で、4曲目の「信じる」は、平成16年のNコン中学生の部の課題曲・・・まだ、2曲しか練習をしていないのだが、歌った感じはなかなか良い曲だと思う。私自身、松下耕の作品を歌うのは、今回の定演で歌った「アヴェ・マリア」に続き2曲目となる。さて、松下耕の世界を、広友会でどのような表現ができるか・・
2010.08.01
コメント(0)
全46件 (46件中 1-46件目)
1