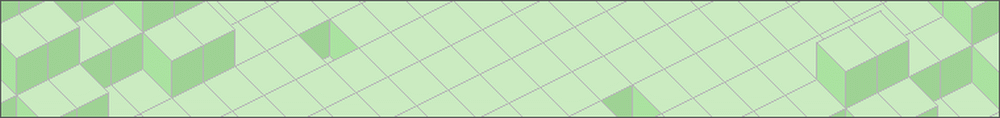2012年03月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

自慢話についての心遣い
世の中には.人が羨むほどの自慢話を持っている人が多いと思う。 自慢話は自分からしてはいけないのではないだろうか。その話の 内容が相手にとっても、良いことだとしても押しつけの印象を与え 反感を招くことがあるからである。 自慢したいことは、人に誇れることである。しかしながら、話し方に よって、人に嫌がれることになったりする。人から要求されていない のに、自分から一方的に話すのは、最悪の結果にしかならない。 自分が何か善行をしたときも同様である。自分から先に公表した のでは、自分の名を売るためにしたとしか思われても仕方がない。 秘密にしているうちに人が知るようになり、仕方なく事実を認める ような心遣いが欲しいものである。 だから、自分の自慢話は、言わないでいたほうが良い。黙って いれば、人からの評価も上がるが、自分から言ってしまえば、マイナス の評価しか受けないだろう。
2012.03.29
コメント(0)
-

物事がうまくいかないとき文献から学ぶことが多い
何かをするときどうしてもうまく行かないような場合は、文献から解決の 糸口をつかむことができますね。 ◆太陽は日々新しい。 「太陽は日々新しい」。これは、古代ギリシャの哲学者ヘラクレスの 言葉である。 一度や二度の失敗で気にする必要はない。 「失敗をしない人は常に何事も成し遂げられない」(フェルブス) 「間違いと失敗は、私達が前進するための試練である(チャニング) 物事を達成しようとするときには文献に学び前進することが必要と 思います。
2012.03.25
コメント(0)
-

日常生活のしきたり(14)
3月度は確定申告や留学生の就労ビザーなどの業務がピークとなった ことにより、ブログへの書き込みができなくて残念な有様になってしまい ました。 本日からしばらく日常生活のしきたりに触れて行きたいと思います。 先ずは、間近にひかえた4月の行事「花見」のしきたりについて歴史的な 背景を調べて見ました。 花見で愛でる桜は、もともとは梅だったそうです。時代から見ると、奈良 時代は梅で花見をおこない、平安時代になってから桜に変わったようで です。 奈良時代には、「万葉集」に花見ということばが出てきているが、 この時代に愛でたのは、桜でなく梅などあったとのことです。 花見の対象が梅から桜に変わったいきさつは、812年(弘仁3)年、 嵯峨天皇が神泉苑で桜の花を楽しむ宴を催してからとなっているとの ことです。この宴を催すために、御所の庭において、梅の木が桜に 植えかえられたと言われております。 桜の花が咲く頃は、丁度稲の 種蒔きの時期に当たることから、古くから、桜は稲の象徴とされ、 満開の桜は秋の豊作の兆しとして喜ばれており、こうした豊作への 願いと花見が結びつき、次第に桜が定着していったと見られております。
2012.03.24
コメント(0)
-

希望ということばの英語による表現から
希望ということばの英語による表しかたは色々あると思います。 希望のことを英語では「HOPE」として表現しています。 その一つの表し方として、希望を実現するのに必要なことを4つの 頭文字によって表現した興味あるものがあるようです。 「H」 HEALTH 健康 「O」 OPPORTUNITY 機会 「P」 PARENTS 両親 「E」 EQUALITY 平等
2012.03.07
コメント(0)
-

生きていくには自分にふさわしいライバルが必要である
自分の一つの信念をもって人生を歩んで行くには、ライバルが 必要ではないだろうか。その事に関して作家藤本義一様の金言が 示唆に富んでいるので、触れて見ました。 その金言の引用から「ライバルを持っていない人は、島影さえ見えない 大海のただなかにポツンと浮かぶ舟のようなものである。前進している のか、後退しているのかさえ分からない頼りない人生である。それは おそらく味気のない人生だと思う」 自分にふさわしいライバルと切磋 琢馬しながら、人生を踏み出していくことが人間の成長には必要なことと 考えます。
2012.03.06
コメント(0)
-

日常生活のしきたり(13)
もう日にちは過ぎてしまいましたが、ひな祭りにまつわる しきたりです。 3月3日のひな祭りは、昔から伝わる女の子の祭りです。 この祭りに関する迷信には「祭りが済んだら、直ぐに雛人形 をかたづけないと婚期が遅れる」というものがあります。 きやらびかで美しさのあるお雛様を少しでも長く飾っておきたい のは人の人情であると思いますが、この迷の中にこそ、元来の ひな祭りのルーツがあると言われております。 いにしえのひな祭りは「流し雛」という形であったとのこと である。その中味は、紙や粘土で作られたひな人形を形代と して、娘の代わりに見立てることによって、病気や災難を娘の 代わりにこの形代に引受でもらうことにしたのである。 そしてそれから、厄を引き受けた雛を、毎年 川に流すしきたり なったのである。 しかしながら、江戸時代になると、高価なひな人形が開発され、 事情が変わってひな人形を川に流す代わりにしたということである。 長く飾っておくと、厄がながれない→災難がふりかかる→婚期を 逸す、というしきたりになったと伝えられているのです。 。
2012.03.04
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 万歩計
- こんなに歩いている!
- (2025-01-23 22:18:25)
-
-
-

- 入浴後の体重
- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…
- (2025-06-30 17:00:00)
-
-
-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…
- 治らないと諦めていた症状が完治した…
- (2025-05-21 00:28:42)
-