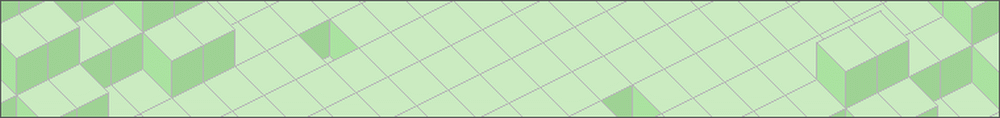2013年01月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
不幸な中におもしろみを見付ける努力をしよう
一年中晴れだったら、つまらない。人生においても、そのように 一年中ハッピーなことだけでは、人間として、幅広い、魅力ある心 はうまれてこないのではないでしょうか。生きていく上には、苦しい ことや、不幸なこともあります。 高杉晋作という人は、最期のとき、「面白き、こともなき世を面白く 住みなすものは、心なりけり」と、言い残しているそうです。面白くない 世の中を、自分の心ひとつの持ち方で、面白くすることができること を教えているように思います。この様な努力をすることは尊いこと です。
2013.01.31
コメント(0)
-
高山での水の沸騰現象について
高い山に登って水を沸かすと100度以下でも沸騰してしまうし、 ご飯も普通に炊いたのでは生煮えになってしまうのは、良く知られ ていることです。これは、標高の高いところでは気圧が低いために、 水の沸点が低くなることによると云われています。 それでは、気圧が低いと、温度が低くてもどうして水が沸騰する のか疑問がわいて来ます。沸騰とは、水の中から水蒸気の泡が 発生してくる現象です。水の中の泡が潰れないためには、外からの 押す気圧と、水蒸気が中から押し返す力が等しくならなければなら ない。すなわち、地上の気圧は、約1気圧なので、地上では1気圧 の時の気圧と100度のときの水蒸気の圧力がバランスしている ことになります。 気圧が1気圧より低くなれば、つり会う水蒸気の圧力も小さくなり、 低い温度での水蒸気の圧力でもつり会うことになります。だから、 100度以下でも沸騰してしまうことになります。
2013.01.30
コメント(0)
-
自分の殻にとじこもったときの対処法
生きておりながら、自分が死んでしまったつもりになったらどう なるのでしょうか。 自分の生命を投げ出して見る。そうすると、 そこに、生き生きとした世界が現れてくる。つまり、自分の人生を 全く別の気分で生きられるのではないでしょうか。 劣等感がつのったり、何か自信をなくしたりして、消極的になり、 自分の殻に閉じこもって、とても苦しい状態に陥るときがあると 思います。しかし、この様なとき、一度、思い切って死んだつもりに なって全力を振り絞るならば、必ず、新しい活力を発揮できるものと 考えます。
2013.01.29
コメント(0)
-
花粉が人の役に立っていることは
花粉はアレギー体質の者にとっては、厄介なものようですが、ある 一面では非常に人間の役に立っていることを知りました。 花粉を包んでいる硬い膜は大変腐りにくく、例え土壌のなかに1億年 以上も埋もれていても、その姿は変わらないそうです。また、花粉の 表面には植物の種類ごとに違った形の模様がついているので、その 模様を調べることによって、それが何の植物の花粉であるかが分かる ことになります。 この様に、花粉を調べることは、人類の歴史や太古の気象の研究 に役立つばかりでなく、石油資源などの地下資源を発見する手がかり にもなっているということです。
2013.01.28
コメント(0)
-
人はそれぞれ天から与えられた役割を持って生きているものと思う
私達が人との関係をトラブル無く生きて行くには、言葉使いを 丁寧にし、礼儀正しく人と対応していけば人からあまり文句を言 われることはないと思います。 けれども、話しを会社の上司に向けてみるとそうではない。 ちょっと位が上になると、下の者に対しては結構威張り出す人が 多いのではないでしょうか。こちらが丁寧な口調で話しても、「君の 報告はなんと分かりにくいことか。もっと感単にでききないのか」と 大声でどなる。これを聞くと、こちらはカチンと頭にきて、こんな無礼 なヤツとは一緒にいたくないと思う時があるのではないでしょうか。 このようなとき、いつまでも不機嫌な状態でいると修行がたりないと 見られても仕方のないことです。だから、自分の考え方を変えてみる ことが必要と思います。 自然界に目を向けると、美しい花も毒の花も、自然の生命です。 自分の気に入らない上司も、気に喰わない上司も、みんな天から 与えられた「役目」を申し使っていると思えばいいのです。 無礼な上司に出合ったなら、この人は、天から悪役を命じられて いるのだ。ご苦労様という気持ちをもつことにしたらどうでしょう。 そうすることが、嫌いな人を許せる対処法になると考えます。
2013.01.27
コメント(0)
-
人が得意になって話しているときに耳を傾けるマナー
人が面白いことを得意になって話しているときに、よく口出しをして 話しを横取りする人を見かけることがあります。 人が話しているときに、口出しをして邪魔するのは、マナー違反と云う べきではないでしょうか。 その上に、話しのオチまで取り上げようとするのであれば、相手の 不快を買うのは間違いのないことでしょう。人が面白そうな話しをして いるときは、それは相手の「独演会」だと思って耳を傾ける必要が あります。下手な野次を入れても行けないし、オチまでもすっぱ抜く のはもってのほかと云わざるを得ません。最後の話しを聞いてから、 面白がるのが、相手を喜ばせる方法ではないでしょうか。 あくまでも、話しをしている人が主役であるのですから、相手の 顔が立つように、話しを盛り上げて行くべきであると考えます。
2013.01.26
コメント(0)
-
大きな声を出して不安を吹き飛ばそう
人は誰でも人生を歩む上に色々な場面に遭遇して、自分の心の に悩みや不安を抱くときがあるものと思います。このような場合、 この不安をどのようにして捨てきる力を身につけるかが重要なこと ではないでしょうか。 例えば会社勤めを例にしてみるとします。同じ会社に長く働いて いると、いやな気持ちや思いが出てくることがある。また、将来性に 目をむけたときにこの会社はどうなるのだろうか。そんなことが何気 なく気になってくる。個人で自分自身の過去を悔やんでも、また、将来 を気に掛けたとしても、会社の運命には全く関係ない。それなのに、 一人で悩んで疲れ果ててくる。更には、上司とうまく行かないときもある。 同僚の意地悪に出合うこともあるでしょう。このような状態の時は、重く のしかかっているプレッシャーを、「カーツ」と大声で叫んで、吹き飛ばす 力を身につけることが必要なことではないでしょうか。
2013.01.25
コメント(0)
-
花のすべtが良い香りを放つとは限らない
花はどれでもいい香りがするものと思いがちですが、中には 「腐った魚」のにおいがする花があることを知って驚きました。 花屋さんの鑑賞用の鉢植えや、花壇の花ばかり見ていると、 花はすべて美しくかぐわしいものと思いがちです。しかし、野生の 花は美しく飾りたてていないどころか、悪臭を放つ花もあるそう です。その中の一つにサトイモ科の一種の花(ショクダイオオ コンニャク)は、色が「肝臓」にそっくり似ていて、においは「腐った 魚」にそっくりです。ハエが卵を産みつけるというのですから、その にほいのほども想像できます。こうなると、花のようないい香りという 言葉は当てはまらない気がします。
2013.01.24
コメント(0)
-
出目金の生態について
出目金の目はどうして飛び出しているのか不思議に思います。 これは意外と簡単なことで、突然変異によるものと云われております。 出目金のルーツは、フナの一種の淡水魚だそうです。歴史的にみれば ふるい時代より中国で観賞用として飼われていて、日本には約1500年 前に入ってきたということです。 このフナは長い年月をかけて突然変異を繰り返してきて、紅色、白色、 紅白混じり、ヒレのかたたちの変わった品種、大きさも様々な金魚が生 まれたそうです。 その中にあって、左右両眼の飛び出したものに品種 改良を加えて現在の出目金が誕生している経過を辿っていると云うこと です。
2013.01.23
コメント(0)
-
世間体にとらわれない価値観を持とう
若いときにはあまり気にしないことですが、年をとってくると、他人 から、よいとか悪いといわれるとすごく気にして消極的な思考にはし り、必要以上に劣等感を抱いてしまうようなことがあるのではないで しょうか。 このようなときに対応する思考として「不思善・不思悪」の言葉が あることを知りました。これは、禅語の中にあるそうです。内容は、 あまり、しっこく、あれがいい、これは悪いと世間の評価によって、 自分を痛めてはいけないと云うことで、善とも思わず、悪とも思わ ずに、世の中の善悪を超越したところに、自分自信の心のなかに、 自由自在な自分らしい善悪の判断が生じてくるというものです。 人生を歩んでいくときの一つのガイダンスになるのではないで しょうか。
2013.01.22
コメント(0)
-
お酒を飲むときの豆知識
私はお酒が欠かせない程の呑み助ではなく、時たまたしなむ程度です。お燗をして呑みときは決まりごとがあるようです。「燗は人肌がいい」とよく言われていることです。それは、温まった徳利の底に触れて見て、手と同じくらいの温かさが一番うまいと酒通の者が言っていることです。人には好みもあることだし、酒の種類によることもあるでしょうから、あまりこだわりすぎても良くないと思われるので、一応の知識として心得ておく程度にしたいものです。
2013.01.21
コメント(0)
-
他人の灯りに頼らず強く生きる心掛け
人は誰でも気が重たく沈んでしまうときがあるのではないでしょうか。 そのような時、自分ではなんとか気持ちを切り替えて、明るくしようと するけれども、暗いままである。 なぜそのようになるのでしょうか。それは、幼少のころから、他人に ばかり頼って生きてきているからなのではないでしょうか。 お釈迦さまの言葉に「自灯明じとうみょう」があるそうです。これは、 決して、他人の灯明を頼りにしてはいけない。自分の心の中に、ポッと 小さな灯明をつけなさい。他人からもらう光だけでは、いつのとき消さ れて真っ暗になるかわからないという意味です。 結局のところ、いざというときには、他人に頼らなくても、自分一人で なんとか心強く生きる心構えが必要であることを教えてくれているもの と思います。
2013.01.19
コメント(0)
-
緊張するときに起こるドキドキのわけは
人は激しい怒りを感じたり興奮したときや、恐怖を感じたりした ときなどに、ドキドキと心臓が音を立てて鼓舞する現象が起きます。 これは、どの様な仕組みになっているのでしょうか。これは、人間 が生まれてときから持っている本能的な現象と言われています。 私達の意志とは関係なく、勝手に交感神経とアドレナリンというホル モンが共同し、敵からの攻撃に対応出来るような準備を整えている ということです。 交換神経は、副交感神経と共に自律神経と言われています。 この2つの神経が相反対のはたらきすることから、私達の身体の バランスが正常に保たれているのです。本当に優れたメカニズム を感じます。
2013.01.18
コメント(3)
-
サツマイモの出身地をさぐる
寒い時期になると石焼き芋が冬の風物詩となってきます。 木枯らしの中でホクホクしたお芋は美味しいものです。 このサツマイモは、よく調べて見るとインカ帝国の出身のようです。 コロンブスが新大陸を発見した後、インカ帝国を征服し、インカ人を 大虐殺したピサロが、その土地から持ち返ったものだそうです。 その外には、タバコ、トウモロコシ、ジャガイモ、バナナも一緒に持ち帰 ったと言われています。 その後、中国、琉球を経て17世紀はじめごろに日本に入ってきた ということです。寒いときは、美味しいサツマイモを食べて元気をつけ たいと思います。
2013.01.17
コメント(0)
-
安らかさを身につける心構え
生活して行く上で相手と口論し、相手も傷つけたり、自分も不愉快なったりすることもあるのではないでしょうか。職場においては、同僚と、家では家族とぶっかる。その大方の原因は、考え方が違ったしまったことによると思われます。現代の人が、安らかさと和みを失っている原因は、極度に自分の考えにとらわれすぎているからではないでしょうか。だから、自分の考えにあまり深く取りつかれない臨機応変の心の持ち方を身につける必要があるように思います。
2013.01.16
コメント(0)
-
ポジテイブな心を抱こう
一日中をできるだけ元気で明るい言葉を使って過ごしておれば、 その一日は明るい生活をおくることができる。逆に、一日中、暗い 言葉、悲しい言葉、寂しい言葉を使っていると、悲観的になって しまうと言われています。 一般的に欝になるような人は、よく日記を傾向にあるそうです。 その中に書かれている言葉は、殆どが、自分で自分を苦しめる ような内容になっている言われています。自分はタメとか、自分 ほど不幸な人間はないというようなことです。やがては、不安な 底に落ち込んでしまう。はたから見ると、タメでも不幸でもないの に、事実が肯定的に見えてことない状態です。 ともかく、余計なことを言わずに、事実を事実として受とめれば、 楽しい心の持ち主へ進展していけるのではないでしょうか。
2013.01.15
コメント(0)
-
人生を楽しめない相手について
世の中にはいろいろな人がいるものです。その一つにやきもちを やく人があります。人の喜びに、一緒に喜んでくれたらよさそうなもの であるが、やきもちをやくだけではなく、意地悪を仕組んでくることです。 この様な人は、「やきもちなんか止めてよ」とか、「意地悪はみっとも ないよ」などといくら諭しても効果はないようです。人の喜びに、やき もちをやく人は、自分の人生を楽しめない人と見てよいのではないでし ょうか。それどころが、人の心を暗くしてしまう人のようです。 やはり、高い幸福感を抱き、心豊かで明るい人を相手にするほうが、 人生を楽しめるものと考えます。
2013.01.14
コメント(0)
-
何事も前向きに受けとめて生きて行こう
「日々是好日」と言うことば、すでに使い尽くされて言葉で ある けれども、今一度 この言葉をかみしめて前向きに生き て行きたいと思います。 嫌なことがあった日も、嬉しいことがあった日も、それは 二度と繰り返すことのない大切な一日であると言うことです。 その日を「好日」とするかどうかは、自分自信の心の中にある のです。 仮に同様なことが起きてしまったとしても、それを受け止める 心次第により、全くイメージは違ってくるのではないでしょ うか。 起きてしまった事は変えることはできないけれども、それを どの 様にとらえるかは、すべ て自分できめることができる のです。 生きている以上は、今日一日を「好日」として前進して いきたいものです。
2013.01.13
コメント(0)
-
縁起を担ぐ鏡開きの話題から
1月11日と言えば鏡開きのしきたりがある日本です。 お供えしていた鏡餅を割って、おしるこなどに入れてたべるのが「鏡開き」 です。年神の象徴と言われる鏡餅を食べることで、神の力をわけてもらおう とする行事です。この行事を歴史的に見れば、平安時代にの宮中で、歯 を丈夫にすることによって長寿を願う「歯固めの儀」が発展して鏡開きの 儀式へと移り変わったものではないかと見られています。 この鏡開きと言われている所以は、縁起を担いでのことだそうです。 実のところ、年神の象徴を「割る」というのでは、罰当たりのことです。 それゆえに、運が開くというように、おめでたい「開く」としたそうです。 以上新年のしきたりを話題にしました。
2013.01.12
コメント(0)
-
人間の歯ぎしりをするときの噛む力に驚く
人間が歯ぎしりするときの型は、おおよそ3種類あると言われていますす。 それらは、「すり合わせ型」、「カチカチ鳴らす」、「食いしばる」とうことです。 「すり合わせ型」は、虫歯治療の詰め物が会わずに起きることが多く、 「食いしばる型」は、ストレスや内向的な性格によること、「カチカチ型」は、 どちらの理由にも当てはまるようです。 歯ぎしりは、眠っているときだけにできて、起きているときにやろうとしても うまく出来ない不思議のものです。眠っている間に、無意識のうちに偉大な 力を発揮する様態です。 もの食べる時には、お煎餅をたべるときは10キロ、食バンで30キロの 力しか必要としないけれども、歯ぎしりをするときは、驚くことに60~80キロ の圧力がかかっているそうです。アゴに疲れの弊害がこないようにすべきで しょう。
2013.01.11
コメント(0)
-
クジラは広い海の中でどの様にして仲間と連絡を取り合っているのか
クジラは人間と同様に哺乳動物で知能度も高いと言われています。 それから、地球上に現れた生物の中で最も巨大な生物と見られていま す。 恐竜との比較では、一番大きな恐竜と言われているブラキオサウルズ では全長25メートル、体重は80トンに対して、シロナガクジラは、全長30 メートル、体重は130トンとうことですから、その巨大さが分かります。 このような巨大なクジラが海の中でどのようにして仲間と連絡を取り合って いるのか興味あるところです。 クジラは超音波をだして広い海域の中で仲間との連絡をとる習性があると いうことです。外部から見えないけれども、クジラは非常にすぐれた耳(鼓骨 胞ここつほう)を持っており、これにより、お互いが発信する信号音をつかま ることが出来ることです。 これはある調査による話しですが、マッコウクジラで1万メートル、群れを つくっているイルカで800メートルも離れた出来事をキャッチ出来るということ です。クジラの偉大な生息の状態をみることが出来た次第です。
2013.01.10
コメント(0)
-
漢方薬のとりすぎには注意が必要
漢方薬には、西洋の医学薬品と異なり、副作用の弊害はないにように言わ れておりますが、その薬のとり方や摂取量によっては問題があるということ なので注意が必要と思います。 薬そのもの副作用ではなく、選び方を誤るとトラブルを起こすこともあると いうことです。 例をあげますと、冷え性をなくすために血液の循環を良くする ことを目指して飲んだところ、むくみが生じてしまったことがあることです。 漢方薬では症状に応じて薬を決めるのではなく、原因となる体質に応じて 決めるため、ただ単に冷え性といっても、誰にでも同じ薬が効くわけてはない 。血行をよくすればいいのか、身体の中の水分を出せばいいのか判断しない と、薬が悪影響を及ぼしてしまうそうです。そのほか複数の漢方薬を同じ時に 服用してしまったことにより、体調を崩してしまうこともあるそうですから、摂取 の仕方には十分留意していきたいと思います。
2013.01.09
コメント(0)
-
記憶力の改善へとつながる工夫
何か業務に使う資料を覚えておかなければならないとき、黙読と音読と はどちらが記憶に残りやすいのでしょうか。 良く調べてみると、静かな部屋で黙読をするよりも、音読のほうが効果 のあることが分かりました。 人間の記憶力というものは、刺激する感覚が多いほど高められ、記憶 が頭にのこるということです。黙って目で文字を追うだけでは、視覚だけ しか刺激されていないことなり、人間の持っている五感も宝の持ち腐れ になってしまう。 それに対して音読のほうは、視覚は声を出すときの唇や舌の感覚、 自分の声を聞く聴覚も刺激されることになるので、記憶の効果が上が るということです。 更に徹底してやるのであれば、音読しながらメモを取ることです。 書くときの手先の感覚、そしてメモした文字でさらに視覚を刺激すること ができます。読むだけより、書きながらのほうが効果があることは多くの 方が体験されることと思われますが、この様な生理学的なうらづけもある ことを認識して、記憶力の向上への工夫とされたらいかがでしょうか。
2013.01.08
コメント(0)
-
ワインのビンにまつわる工夫とは
ワインのビンは上げ底になっていることをお気づきではないでしょうか。 これは中味をケチっているわけではなく、それなりの理由があるそうです。 お酒は外部から与えられた刺激によって微妙に変化するので、容器に 様々な工夫がなされているそうです。ビールを例にとれば、ビールは直接 日光に当てると風味が壊れてしまうため、あのような暗褐色のビンに入れ あることです。 ところで、ワインのビンが上げ底になっているのは、長時間貯蔵すると 沈殿するタンニンや酒石で、ワインが濁るのを予防するための工夫という です。ビンの底が平らだとグラスに注ぐとき、濁りが全体に混ざっていまう が、上げ底にしておくと周囲の窪みに濁りが沈殿して全体が濁らないから です。ですので、ワインを買うときには、ビンが上げ底になっているものを 選ぶのが好ましいこではないでしょうか。
2013.01.07
コメント(0)
-
納豆には多くに菌が含まれていることを学びました
日頃良くご飯に掛けて食べる納豆には夥しい菌が含まれていること を専門家に教えてもらいました。 先ずは納豆の作り方から行きますと、白大豆を良く煮てワラに包み、 2日以上寝がせる。適温は40~42度。こうすることによって、ワラに 付いていた納豆菌が増殖し、大豆が発酵してネバネバになり独特な においをものになったのが納豆ということになります。 それでは、納豆菌がどれぐらい入っているかと言うことになりますが、 なんと100グラムの中に1000億弱の生きた菌がが含まれているそう です。そして納豆を食べると、生きたまま腸に送られて、腸のなかでも 働くそうです。 その主な働きは、ビフィズの増殖を助ける、ビタミンの合成を助ける、 後から食べてやってきた食べ物の消化を促す、悪玉の細菌の活動を 抑えるなどの素晴らしい働きをすることになります。 1000億種の生きた菌を食べていることを思えば、気色が悪くなる ように感じるかもしれませんが、健康のための菌なら、楽しんで食べる べきではないでしょうか。
2013.01.06
コメント(0)
-
お風呂に入ると指先がシワシワとなる現象は
プールやお風呂に長い間入っていると指先がシワシワとなる現象が起き ます。これは、どの様にしておこるのでしょうか。 これは、皮膚の表面から水分が浸透することによって、皮膚の表面の 一部は伸びるけれども、その下の部分には変化が起こらないので、しわに なるということです。 手や足の皮膚のところでは、この変化が激しいので目で見ることが出来る のですが、この現象と同じような変化は、わずかであるが、どの皮膚の所でも 起こっているということです。
2013.01.05
コメント(0)
-
筋肉疲労の治し方について
私の趣味の一つにマラソンがあり、いつも筋肉疲労には関心をもっています。 スポーツ医学によれは、筋肉や靱帯の疲労には「アイシング」という治療 法を取り入れているそうです。これは、専用のアイスバッグやコールドスプレー で冷やして血管を収縮させ、腫れや炎症を和らげてやる方法だそうです。 具体的な例として良く見かけるのは、プロ野球の選手が試合後、利き腕の 周りを、大量のアイスバッグを巻き付けて冷やしている光景です。 このアイシングは、普段の筋肉疲労の緩和にも役立てることができます。 使う材料は、ビニール袋に氷を入れたもの、又は紙コップに水を入れて 凍らせたものでも良い。氷がない場合は、冷たい濡れタオルでも良い。 これらを駆使して筋肉にあてるか、こすることによって効果が得られること です。又、アイスマッサージをした後に、次は暖めるということを交互に 繰り返す「温冷療法」も効果的な方法と言われております。
2013.01.04
コメント(0)
-
飲んだヒールはどのくらいの時間で処理されるのか
私はビール党というわけではありませんが、飲んだアルコール分が 体内で処理されるのをビールを例にして調べてみました。 ビールの320ミリリットルぐらい飲んだ場合には、胃に入ったアル コール分一部は、粘膜の細胞を通って血管に入ることになります。 ここでの吸収スピードははじめ早く、30分以内に25%のアルコールが、 吸収されるそうです。しかし、次第にスピードが落ちて、1時間ぐらいで 30パーセントの吸収が完了すると言われています。残りは小腸に向かう 事になっているそうです。もっとも、胃の中に食べ物があればゆっくりと、 胃がカラッポならば早く小腸に送り込まれるようです。 アルコールの処理完了までの所用時間は、何も食べなかった場合に は、3時間30分、食べながら飲んだ場合は、6時間以上かかるそう です。
2013.01.03
コメント(0)
-
お正月に関する話題から
正月になると、初夢を見たかと聞かれることがあります。この初夢は 年はじめの行事が1月2日からとなっていることから、この日に見たの を初夢と一般的には言われているようです。 そこでこの初夢についての古くからの歴史的な背景を話題にして見る ことにしました。 「一富士、二鷹、三なすび」に代表される初夢は、運勢を予測すると 言われています。最も縁起の良い夢が「富士山」、二番目が「鷹」、 三番目が「なすび」いわれる理由は、徳川家康の好物にあやかった ものだそうです。家康の好物を夢に見れば、天下人となって家康の ように出世できると考えられていたようです。 それでは、初夢はいつ見る夢なのかということになります。 これにはいろいろな説があるようで、大晦日の夜とか、1月3日の夜とか、 節分の夜というようなことも言われています。 しかし、一般的には、1月2日の明け方に見た夢のことを指すのが多い ようです。書き初めや稽古事のように、何かをはじめて行うのは、1月 2日からという風習があったことよると見られています。そこから1月2日 に見る夢こそ、その年を占う「初夢」とされたということです。 私は、縁起の良い夢をみることはできなかったのは残念ですが、仕事 の夢ばかりでした。仕事の効率化に取り組んで行きたいと思います。
2013.01.02
コメント(0)
-

2013年の新年を迎えて
恒例により近くの神社で初詣をすませ、初日を拝み新年を迎える ことができました。 本年は余裕をもって業務に取り込めるよう計画面で工夫改善を はかっていきたいと思います。 先ずは正月三が日は家族と共におせち料理を楽しく召し上がり ながら過ごすことにしています。 おせち料理といえば、正月の定番と見られていますが、もともとは、 おせち料理とは、「お節供(オセック)」 のこととされており、季節の節目 (フシメ)となる節目に神に供える行事であったそうです。 神への供物である「お節供」は、神への感謝と共に、五穀豊穣、子孫 繁栄をお願いする意味合いが含まれているそうです。神にお供えした 後、家族揃っていただくということです。節目と言えば、元日の外に 五節句(人日、上巳、端午、七夕、重陽)が当たります。現在でも、 上巳(3月3日)や端午(5月5日)などには、ひな祭りや端午の節句と して祝う風習が残っています。そのうちで元日だけが、特別におせち 料理を用意するのは、その年の初めの節目である元日が重要視され ているからです。 また、おせち料理の中味を見れば、分かるように、どれも日持ちする 料理ばかりとなっています。これは、神への感謝ともに、正月くらいは 日常家事で多忙を極めている女性が骨休みできるようにとの意味あい もあるようです。
2013.01.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 医療・健康ニュース
- マイクロプラスチックが、流産をうな…
- (2025-11-02 21:08:34)
-
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- 歯医者さんや歯について~
- 歯の治療(令和7年11月)
- (2025-11-18 11:30:04)
-