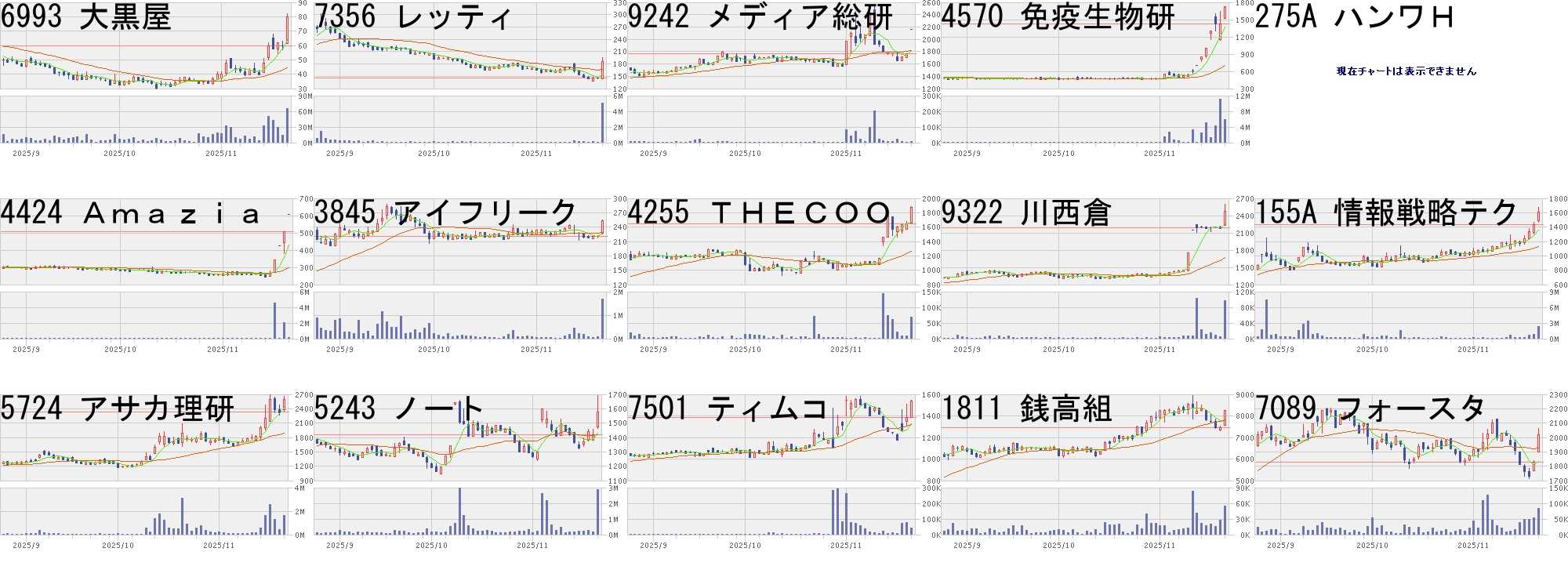2005年10月の記事
全5件 (5件中 1-5件目)
1
-
空の中
「怪獣と青春ものを足して空自で和えた」と作者の有川浩氏が後書きで言う怪快作、それがこの「空の中」です。有川氏は電撃文庫から「塩の街―wish on my precious 」でデビューした、いわゆるライトノベル作家ですが、「空の中」は文庫ではなくハードカバーで、中には一枚のイラストも入っておらず、ライトノベルらしさを極力廃したつくりになっています。比較的年配の方でも手に取りやすい本と言えるでしょう(笑)。 高知沖、高度二万メートル付近で相次いで起きた謎の飛行機事故。事故調査は難航し、事故原因の特定すらできない中で、事故で殉職したパイロットの息子、斉木瞬は奇妙な生物を拾います。クラゲに似ている事から「フェイク(もどき)」と名付けられたそれは、空を飛び、電波を操作して、携帯電話を通じて人と会話できるほどの知性の持ち主。「彼」は父親を亡くしたばかりの少年にとって、かけがえのない友となっていきますが、彼の幼馴染みの少女、天野佳枝は、その入れ込みように不安を覚えます。 一方、最初に事故を起こした国産超音速旅客機開発チームの青年、春名高巳は、自衛隊機が事故を起こした時、その僚機として飛んでいたパイロット、武田光希に話を聞きに行きます。実は妙齢の美女であった光希は、トラウマからか事故に付いて話す事を拒みますが、高巳の度重なる訪問に何時しか心を開き、遂に二人は事故状況の再現を目指して、その空域へ向かいます。 そこで彼らが出会ったのは、全長60km余りもの巨大な未確認飛行物体。電波や音波を含む「波長」という概念を自在に操作し、高度2万メートルに浮かぶそれは、一つの巨大な未知の生命体です。謎の飛行機事故は、空中でこれと衝突したのが原因でした。 高巳たちとの接触により、その生命体は岐阜県各務原の自衛隊基地上空に出現。世界中をパニックに陥れます。日本政府は自衛隊を通じて「白鯨」、転じて「ディック」と名付けられたそれに対し、共存に向けた話し合いを開始しますが、世界は「白鯨」が脅威となるのではないかと恐れ、日本に駆逐を要求します。 また、国内でも最初の事故で死亡した乗務員の遺族が設立した「白鯨」追放を目指す反白鯨団体「セーブ・ザ・セーフ」も出現し、世論は混乱。そして、ついにアメリカはディックへ向けて核ミサイルを発射してしまいます。ところが、核攻撃ではディックは死なず、無数の固体に分裂した彼らは、人類に報復しようと襲い掛かってきます。空を自在に飛び、「波長」を操作してレーザーやマイクロ波ビーム、高圧電撃を放ってくる彼らに自衛隊は全く歯が立たず、日本は壊滅の危機に。その時、瞬のもとにいた「フェイク」は…… 極端なネタばれを避けてストーリーをダイジェストすると、こんな感じでしょうか。この後もディックとフェイクの関係や、分裂したディックを元に戻し、人類と「白鯨」の間に停戦を成立させようとする高巳たち対策本部の話、フェイクを味方につけるため、瞬を取り込もうとする「セーブ・ザ・セーフ」の動きなどを軸として話は動いていき、クライマックスを迎えるのですが、圧巻なのは最後の一文です。「これが書きたいがためにこの話はあったのか!?」と思わせるようなすごい一文なのです。いや、それ自体はとても平凡な文章なんですけどね。これはぜひ実物を見て確かめていただきたいと思います。 作者自身が言っているように、この小説は「怪獣もの」でもあります。しかし、どういうわけか話全体の雰囲気は非常に明るく、怪獣ものらしい「脅威」はあまり感じられません。一応、日本中の都市が一斉に「白鯨」に襲撃され、街が廃墟と化し、人がバタバタ死んでいくような描写もあるのですが、全体として感じる「明るい透明感」とでも言うべきものは、あまり変わりません。 怪獣であるディックたち「白鯨」が高度な知的生命であることや、主人公である二組のカップル……特に大人サイドの二人の喜劇じみたやり取りがそうした印象を生むのかもしれませんが、やはりこれは作者の有川氏が作品全体に「空」のイメージを強く与えている事にあるのでしょう。 こうした作風を生かすには、イラストなどは却って邪魔になります。この作品がハードカバーで出た事は、読み手に与えるイメージを大事にするという点では大成功だと思います。 また、次作である「海の底」を読めば、本作との対比からイメージがよりくっきりと浮かび上がるかもしれません……という事で、さっそく「海の底」レビューへどうぞ(笑)。
2005.10.21
コメント(0)
-
海の底
「怪獣とほのラブと自衛隊」という三題噺だった「空の中」に続く有川浩氏のハードカバー第二作が「海の底」です。一応「怪獣」「ほのラブ」は維持されていますが、本作では自衛隊よりも機動隊の方が主役かもしれません。 米軍の基地祭で賑わう横須賀の街。停泊中の海上自衛隊潜水艦「きりしお」では、艦きっての問題児である夏木と冬原の二人の三尉がヒマを囲っていました。 その時、突然艦に緊急出港命令が出ます。しかも、「出港が不可能なら、艦を放棄して退避せよ」という、どう見てもただ事ではなさそうな一文を添えて。命令通り緊急出港した「きりしお」ですが、直後にスクリューが何かを噛んで航行不能になります。艦を放棄し、脱出しようと外へ出た乗員たちが眼にしたもの。 それは、1メートルはあろうかという巨大なザリガニのようなエビの大群でした。慌てて逃げ出した乗員たちですが、夏木と冬原、それに艦長は基地祭に来て取り残された13人の子供たちを見つけ、その救助にかかるも、退路をエビに断たれてしまいます。彼らが逃げ込める場所は今出てきたばかりの「きりしお」艦内だけ。しかしエビの足は予想外に速く、艦長は若者たちを逃すために残り、帰らぬ人となってしまいます。 その頃、市街地も阿鼻叫喚の有様となっていました。エビのハサミは人体程度はやすやすと真っ二つにし、襲われた横須賀市民は次々にエビの犠牲になっていきます。遂に機動隊が出動するも、エビの堅い甲羅は盾で殴ったくらいではやすやすとは砕けず、負傷者が続出します。 県警の明石警部補は高圧電流帯を作ってエビのそれ以上の侵攻を阻止する作戦に出て、これを成功させますが、市の中心部は完全にエビの占領下に置かれ、数万体のエビと機動隊が電流帯を挟んで睨み合うという奇怪な状況に陥ります。 事態を受けて本庁からやってきた参事官、烏丸と明石の意見は一致していました。「警察力での対処は不可能であり、自衛隊の出動が必要である」です。しかし、政治的問題から、早期の自衛隊出動は不可能。しかも、烏丸は「エビ駆除のために米軍が横須賀市街を爆撃する計画を立てている」という情報を入手していました。二人はインターネットのミリタリーマニアたちと協力し、爆撃作戦の前触れを探りつつ、エビに対処していく事になります。 自衛官たちと子供の逃げ込んだ「きりしお」でも問題が起きていました。子供たちの間での人間関係はあまり良くなく、特にいじめっ子グループのリーダー、圭介は夏木たちにも反抗ばかりする問題児。叱られた事を逆恨みした圭介は、携帯電話でテレビ局に「自衛官が子供を虐待している」というタレコミをして、夏木たちに一杯喰わせようと目論みます。 そして、爆撃のタイムリミットが迫る中、それを阻止し、自衛隊の投入を政府に決断させるべく、烏丸たち、警察の現地警備本部は敢えて屈辱的な姿を晒す覚悟を決めていました。エビの正体は? 自衛隊は投入されるのか? 爆撃は阻止できるのか? 「きりしお」艦内の15人の運命は?「空の中」に比べると、かなり「重い」作品です。早々にエビの襲撃が始まって、血しぶき飛び散るかなりスプラッターな展開がありますし、日本の危機管理のどうしようもなさも、これでもかと描写されます。子供たちの人間関係もなかなか重苦しいです。 ですが、「空の中」同様、作品全体にイメージを埋め込む作者の手法はここでも健在です。今回は「海底」なわけですが、人っ子一人いなくなり、静寂の中、巨大エビだけが我が物顔にのし歩く横須賀市街は何やら異世界の海底を連想させますし、その中で取り残された「きりしお」も、救援を待つ沈座した潜水艦のようです。 ですが、最後まで重苦しい話というわけではありません。事態が解決に向かい始めた後の、一気呵成とも言うべき展開は、それまで「海底」の雰囲気に浸っていた読者の気持ちをすっきりさせてくれる事請け合いです。それだけに、なお余計に中盤の展開の重さが引き立つとも言えます。 なお、今作の登場人物で好きなのは、やはり本庁の烏丸参事官ですね。若手エリートという設定ですが、こうした作品にありがちな、現場の足を引っ張る「机上だけのエリート」ではありません。現場に理解を示し、しかしエリートらしい傲慢さで横車を押す事もできる。むやみやたらと威張った人間ではありますが、その威張り方には筋が一本通っていて好感が持てます。こんな人近くにいたら大変でしょうけど(笑)。 見事に「空」「海」を書き分けた有川氏。次の作品はやはり「陸」でしょうか? 新たな一本が待ち遠しい作家です。
2005.10.21
コメント(0)
-
「黎明の戦女神」第2巻
以前一巻のレビューを書いた「黎明の戦女神」も無事二巻が発行されました。文明崩壊後の世界を舞台にした戦国絵巻も新たな展開を見せ、徐々に崩壊した世界の様子や、生き残った混世魔(カオス)たちの目的について触れられるようになります。 一巻で北関東に覇を唱える大領主、鯰田とその腹心で混世魔の彩子を倒した「繚乱の軍団」。その活動に目をつけたのが、「中央」と呼ばれる謎の勢力。彼らは大崩壊によって消滅したはずの高度文明を未だに保持しており、「中央」に認められた勢力は乱世統一に向けて一歩前進すると噂されています。 繚乱の軍団長・藤沢梓と主人公の峠正樹はこの中央からの招待を受け、彼らが差し向けた船で西へ向かいますが、そこへ大崩壊に伴う地殻変動で出現した駿河湾沖の新島を根城にする海賊、雷鮫の船団が襲ってきます。辛くもこれを撃退した梓は、船団のリーダー、真鈴に自分たちの仲間にふさわしい素質を見出します。 ようやく到着した「中央」は、旧大阪市中心部にあって、確かに滅びたはずの科学文明を保持していましたが、その武力は決して強大なものではありません。最初は居丈高に自分たちへの臣従を要求してきた「中央」のリーダーに対し、梓は「中央」が各地のリーダーの権力を裏付ける権威……かつての天皇家のような存在になることで、その生き残りを図るほうが賢明だと主張。彼らを説得する事に成功します。「中央」との友好関係を確保し、ひとまずの目的達成を果たした梓は、雷鮫の船団を仲間に引き入れるべく、武器商人松古井の船で彼らの本拠地へ潜入します。その時、梓一行の襲撃に失敗した真鈴は、粗野な対立派閥のリーダーと結婚させられそうになっていましたが、間一髪、式場へ乱入した梓に救われます。 救われた真鈴は、梓が私利私欲で戦っているのでもなければ、自分たちを強制的に配下に組み込もうとしているのでもないと知り、梓なら信頼できると、同盟を組む事を了承しました。 その頃、繚乱の軍団にとっては西の雄敵とも言うべき領主、タイガーは名古屋近辺を統治する中部最強のリーダー、明倉景(みくら・みかげ)の大攻勢を受け、梓に同盟と援軍を求めてきました。景は梓と同年代ながら、彼女に匹敵するカリスマと、崩壊前は大商社の社長令嬢だったという経歴を生かして揃えた強大な軍事力を誇る領主。梓はタイガーが敗れれば自分たちも危ういと考え、元から同盟関係にあった房総半島の領主、南郷朱美率いる「黒潮の軍団」、そして雷鮫の船団と共にタイガー軍支援に回ります。 しかし、タイガー軍は苦戦を強いられていました。景の配下にある混世魔がタイガー領と明倉領の国境線となっていた浜名湖の湖面を能力で固化し、大軍を突入させたためです。自然の防壁を無効化されたタイガーに対し、梓は敵軍を領内深く引きずり込んでその戦力を分散させた上で、精鋭を率いて敵本陣を突き、景を討ち取る奇襲作戦を提示。自ら指揮をとります。 そして、正樹も景の混世魔が戦局に介入してこないように、一騎打ちを挑んでいきます。 一巻では旧神奈川近辺だけが舞台だった作品世界も、二巻に入り、旧東海道地域全域へと広がりを見せてきました。かつての戦国時代でも、旧東海道といえば織田・豊臣・徳川の戦国三傑を生み出した土地ですが、この世界でも乱世の覇を賭けるに相応しい強豪のひしめく土地となっています。 人を服従させるのではなく、心服させて味方につけていく梓が豊臣秀吉なら、ライバルとなる「もう一人の戦女神」、明倉景は織田信長といったところでしょうか。苛烈な態度で敵も味方も邪魔するものは踏み潰し、力ずくで服従させる彼女は、まさに悪の覇王と呼ぶに相応しい、強烈な個性の持ち主です。 タイガーは詳しく描写するとネタばれになってしまうのですが、イメージ的には北条早雲が近いような気もします。家康的キャラは……まだいませんね。 こうした個性的な面々に加え、三巻では東北の覇者・伊達の登場が予告されています。東北で伊達と言えば、かの「遅れてきた戦国大名」、独眼竜こと伊達政宗。伊達政宗は作者の中里氏が愛して止まない武将だけに、「黎明の戦女神」世界における伊達も、政宗のイメージを引き継ぐ存在として縦横に活躍してくれそうです。 戦国と美少女と近代兵器と近世戦術の入り混じる「なんでもあり」の世界。今後も目が離せない作品として注目していきたいと思います。
2005.10.12
コメント(0)
-
架空戦記コンベンション「IFCON」探訪記
10月9~10日にかけて東京で行われた架空戦記オンリーコンベンション「IFCON-5」に行ってきました。 コンベンションというのはあるジャンルの小説・ゲームなどのファンによるイベントの事で、SFファンなどは良く熱心にコンベンションを開いており、アメリカなどでは半世紀を越える伝統のあるコンベンションも存在します。 この「IFCON」は2000年に始まり、まだ6回目と歴史は浅いのですが、集まる人たちのパワーと熱気は他のどんなイベントにも劣るものではありません。 さて、この架空(仮想)戦記とは、「あの時こうしていれば、あの兵器があれば、あの人が生きていれば」などの、実際の歴史にはなかった様々な要素を元に「あの戦争の趨勢は変わったのではないか?」という可能性について描くジャンルの小説です。書店に行くと、戦艦大和や零戦が表紙を飾っている小説が置いてあるのを目にする事もあるかもしれませんが、それがだいたい架空戦記のコーナーです。 これら架空戦記は豊田有恒氏の「タイムスリップ大戦争」(1975年)や、高木彬光氏の「連合艦隊ついに勝つ」(1979年)と言った作品が元祖と言われており、その後は檜山良昭氏の「本土決戦」「大逆転」シリーズなどで細々と続いていたのですが、1990年に荒巻義雄氏の「紺碧の艦隊」が発表され、一躍ブームを迎えるに至りました。 それから15年が経ち、毎月のように新人がデビューしていた90年代ほどの激しいブームは過ぎ去りましたが、今もなお架空戦記は発表され、こうしてコンベンションに来る熱心なファン層も存在するようになりました。 こうした歴史はさておき、「IFCON」自体は、昼間企画としては架空戦記に関わる業界の方々(作家、イラストレーター、編集者など)を呼んでのインタビュー、トークに始まり、夜は好きな作家を囲んでの夕食会、そして作家やファンがそれぞれの専門知識を生かして行う様々なイベントと、肩の凝らない内容になっています(笑)。 真面目な内容のものとしては、軍事アナリスト・高貫布士氏の中国情勢分析「アナリストが語る中国」。高貫氏は軍事に関するムック本の監修をするほか、自らも仮想戦記を手がけ、その軽妙な語りには定評のある人物。今回も真面目なテーマながら、時には会場の爆笑を誘うユーモア溢れる分析を展開し、来場者に感銘を与えていました。 また会場が熱気に包まれた企画としては、「プロジェクト×(バツ)」。架空戦記をテーマに「プ○ジェクトX」風味の感動できるエピソードを考えようという企画です。 以前のこの企画からは、「ソ連・フィンランド戦争に参加した日本人義勇軍が、九七式大艇を改造した爆撃機でモスクワを攻撃し、戦争を終わらせようとする」という作戦があったと仮定し、そのためにひたすら氷の張った湖で着水面を開けるために氷を割りつづける人々の姿を描いた話や、「イタリアに侵攻されたエチオピアで、王女を助けて決死の防衛戦を繰り広げる日本人軍事顧問」の話など、熱く感動できる話が多く生み出されてきたのですが、今年のテーマは南極。参加者が出した様々なネタをまとめた結果「倒産直前のインチキな会社が、一発逆転を狙って南極の油田を掘りに行く。それは戦時中にドイツ軍が発見したものの、その場所が不明になったもので、アルゼンチンに逃げていたナチス残党も行方を追っていた。調査部隊は首尾良く油田を再発見するが、会社が国税庁の査察にあってしまう。 その結果、会社に資金を供与していたユダヤ系資本もこれを知り、モサド(イスラエル情報局)のナチス・ハンターが油田へ向かう。調査隊のリーダーは迫り来る脅威を前に、モサドとナチス残党の対立を収め、油田開発ができるか?」 という展開の「白瀬油田を開発せよ~氷原の友情~」という話が出来上がりました。 そして、お笑い企画の代表が「架空戦記三題噺」。 皆さんも子供の頃に、三枚のカードに「誰が」「何処で」「何をした」を書いてシャッフルし、その結果できる奇妙な文章を見て楽しむ遊びをした事があるかと思いますが、これはその架空戦記版。「人物・兵器」「地名・事件」「煽り文句」を組み合わせ、その結果できる奇妙な架空戦記のタイトルから、中身を想像して遊ぶというコーナーです。 これは毎年爆笑必至の企画で、これまでも「栗田健男 大和に乗って総選挙出馬」「バイオ南雲 ミュンヘン爆撃」「ハルゼー、ランパブ突撃!」など、とても中身の想像がつかないけったいなタイトルが生み出されてきたこの企画ですが、今年も飛ばしていました。今年特に印象に残ったものを上げてみますと……「シベリア超特急・山下将軍VS村上ファンド」(山下将軍がフィリピン財宝を元手にマネーゲームで村上ファンドと戦う話らしい)「感動! フランスの飛行機が空を飛んだ!」(占領中に途絶えていたフランスの飛行機業界を復活させる話。ちょっと感動系)「山本五十六:アラスカに自由を! 山口多聞:ワロタ」(どうやら軍令部のチャットの1コマらしい) などなど、抱腹絶倒の怪文が多数生み出されました。 夜通し楽しんだ後は、閉会式。参加者の投票で2004年度の作品・シリーズから大賞が選出され、厳かに(?)「IFCON」は無事終了しました。 架空戦記と言うと、いまいちマイナーと言う宿命からはなかなか逃れられないジャンルではありますが、「IFCON」にはそれをものともせず、熱く楽しんでいるファンが多くいます。もし架空戦記をお読みの方で、普段周りに自分以外のファンがなかなかいない、という方はぜひ参加してみては如何でしょうか?
2005.10.10
コメント(5)
-
集団的自衛権
集団的自衛権、と言う言葉があります。自衛権は国家が敵国からの攻撃を受けた際に、これに対して反撃を行っても良い、という権利を示すものですが、これに集団的という言葉がつく場合、ただ自国のみならず、同盟を組んでいる友好国が攻撃を受けた際も、これに対して反撃を行う事ができると言うことになります。 つまり、集団的自衛権とは、複数の国が同盟を組む事で、敵勢力の侵略に対しては団結して立ち向かう事を意味しています。 日本は自国が攻撃を受けた時だけ反撃できる権利(個別的自衛権)は行使する事ができるとしていますが、集団的自衛権に関しては、憲法上の制約から、持っていても行使できない、としています。 そのため、日本が唯一軍事的に同盟を結んでいるのは日米安全保障条約で結ばれているアメリカ一国のみで、しかも、かつては日本に対して軍事的攻撃があった場合、米軍は日本に協力する事がうたわれていましたが、日本はアメリカが攻撃された場合に支援を行う義務を持っていませんでした。このため、日米安保条約は片務的と言われています。 この状態は、冷戦中は有効でした。日本とアメリカの共通の仮想敵国としては、ソ連と言うあまりにも強大でわかりやすい相手がおり、日本が単独で戦争を挑めるような相手ではなかったので、どうしてもアメリカを頼りにして防衛戦略を考える必要がありました。 ところが、冷戦が終わってみると、ソ連(ロシア)の脅威が激減した代わりに、中国と北朝鮮が日本の脅威としてクローズアップされ始め、対ソを一義としていた時代よりも、事態は複雑なものになりました。 そこで、97年になって日米の間に新しい防衛協力の指針(ガイドライン)が制定されます。新ガイドラインでは、日本領土への直接侵攻時だけでなく、日本領域(領土・領空・領海)周辺で何らかの軍事的危機(周辺有事と言われます)が勃発した場合、日本はこれに後方支援を行う事が決まりました。 つまり、アメリカとの関係に限って、事実上集団的自衛権を行使する事が容認されたと言えます。 前線での戦闘任務でこそありませんが、自衛隊が米軍の後方支援を行えば、米軍と戦っている相手から見て戦闘行為と同じであり、自衛隊も攻撃を受ける恐れが出てきます。 また、周辺有事が台湾海峡危機と第二次朝鮮戦争を念頭に置いているとされることから、米軍との集団的自衛権拡大は、中国や北朝鮮を刺激し、戦争の危険性を高めるものだと言う声もあります。加えて、周辺有事の定義は地理的概念を含むものではないため、無制限に拡大解釈され、世界中の米軍が絡んだ紛争に、自衛隊が手伝いで借り出されるのではないか、という意見も存在します。 果たして、集団的自衛権とは戦争を誘発する危険な存在なのでしょうか? 結論から言ってしまうと、集団的自衛権にはそのような「戦争を誘発する」側面はありません。むしろ、戦争を抑止するために「行使する」事を宣言しておくのが集団的自衛権の実体です。 集団的自衛権の利点はいくつかありますが、わかりやすいものを上げてみましょう。 一つには、軍事費を抑制する事ができる、という事があげられます。これを架空の国家間関係で解説してみましょう。 ある地域にA国と言う国があります。A国はその地域最大の軍事力を持っています。このA国の軍事力を10とします。 A国の隣国として、1の軍事力を持つB国があります。B国はA国ほどの国力を持っていません。個別的自衛権だけで対処しようとすると、3くらいの軍事力を持ちたいのですが、それでは国が破産してしまいます。 そこで、B国は同じA国の隣国で、それほど軍事力を持てない中小国のC国、D国、E国に安全保障条約の締結を申し出ます。仮に四カ国のどれかが他の国から侵略された場合に、残り三カ国が協力して侵略軍に対抗する、という内容です。そして、この四カ国の軍事力は合計すると4になります。 これで、四つの国はそれぞれ1の軍事力しかないにも関わらず、侵略があった場合には4の軍事力をあてにできる体制(集団安全保障体制)ができ、自国で無理をして3の軍事力を備える必要がなくなります。つまり、軍事費の伸びを抑制できるわけです。 次に、集団安全保障によって自国が侵略を受ける確率が下がります。上の例で行けば、B、C、D、Eは単独ではA国の10分の1の軍事力しかありませんから、単独では到底対抗できません。しかし、集団安全保障の成立によって、A国から見ればどこの国をせめても自国の5分の2に達する軍事力による抵抗を受けることになります。 軍事的な常識では、攻撃側は防御側の三倍の戦力を必要とするとされますから、仮にA国が全力を動員したとしても、同盟を結んでいる四カ国を屈服させるのは、相当に困難な事になります。つまり、B、C、D、E国は個別的自衛権のみを行使するよりも、自国の独立を維持する事が容易になります。 このように集団的自衛権を行使する事は利点も多いのですが、行使に当たっては気をつけなくてはならないことは数多くあります。 まず、同盟参加者間の協調体制がしっかりしている事です。足並みが乱れていては共通の敵に対して各個撃破の隙を与える事になります。 好例は戦国末期、織田信長に対して行われた包囲網でしょう。甲斐武田家、越前朝倉家、石山本願寺など戦国有数の大勢力が参加したこの大同盟は、上手く行けば織田信長を葬る事が十分可能な勢力を持っていました。 しかし、武田信玄の病死などの不運もあり、足並みを揃えられなかった大同盟は、信長の巧みな政戦両略に分断され、敗れ去る事になります。逆に信長と同盟していた徳川家康は、不利な状況下でも織田家としっかり歩調を合わせ、包囲網の打破に多大な功績を残しました。 次に、同盟参加者は利己的にならず、相応の役割を果たす必要があります。織田-徳川同盟もそうですが、互いに苦労を分かち合う姿勢を見せる事が、同盟の絆を強いものとします。なお、「相応に」とは「平等に」と言うことではありません。参加者がそれぞれの能力に合わせて、できる事を尽くすと言うことです。 これが失敗に終わった好例は、古代ギリシアのデロス同盟でしょうか。対ペルシアを目的としたギリシア諸都市国家の同盟として成立したデロス同盟は、各国が資金を供出してアテネの海軍を強化し、それによってペルシアの侵攻を防ごうと言うものになります。そして、サラミスの開戦でギリシア艦隊はペルシア艦隊を打ち破り、その脅威を退けます。ここまでは「アテネ=軍事力、諸都市=資金」という能力分担は上手く行っていました。 ところが、ペルシアの脅威が薄れた後も、アテネは同盟の解消を認めず、強化した海軍力を背景に公然と他の諸都市への圧迫を強め、実質的なギリシアの盟主になりおおせます。アテネが利己的な方向に走ってしまったことにより、デロス同盟はアテネが独裁体制を敷くためのからくりに変質してしまいました。 最後に最も重要なポイントとして、同盟は全ての参加者にとって利益をもたらすものでなくてはなりません。この場合の利益とは、経済的なそればかりを指すものとは限りません。 これが上手く行った良い例が、日英同盟です。日本は自国の独立を守るために英国の持つ資金力、情報、資源をあてにする事が出来ました。そして、英国は日本の軍事力を利用して、自分の極東権益にとって脅威となるロシア帝国の南下を阻止する事が出来ました。しかし、日本がその後極東で力を強めて英国の脅威になってくると、この同盟は解消の方向へ向かいます。 逆にいえば、同盟を維持すると言うことは、その国との友好関係を維持・発展させていくと言うことでもあります。 では、現実の日米関係を見てみると……これは結構上手くやっていると評価できると思います。戦後60年にわたって、日本とアメリカは良く協調できています。貿易摩擦などの対立点もありましたが、少なくとも破局に至るような深刻な対立は避けられてきました。「相応の役割を果たす」事や、「お互い利益を得る事」も上手く出来ています。日本はアメリカに国防の一部を負担してもらう事で、軍事的負担を軽く済ませることができましたし、アメリカは日本と言う政治的に極めて安定した同盟国を得る事で、全世界的に軍事力を展開させる事が容易になりました。 これはアメリカにとっては無理に自衛隊を前線に出してもらうよりも余程ありがたいことで、それ故に自衛隊が海外に出るようになった現在も、アメリカが戦闘部隊の派遣を依頼してくる事はありません。「アメリカが前に立ち、日本が後ろから支える」と言う構図が最良の役割分担だと認めているからです。 そして、現在の所、私はこの「アメリカと協力しての集団的安全保障」が、日本にとって最適の選択だと考えています。先日の日記で白物さんより「中朝韓へ集団安全保障体制の相手を組み替えるという選択肢も考えられるのではないでしょうか。地球半周という一番遠い国であるアメリカとの集団安全保障体制よりも、よほど自然な状態に思えます。」という指摘を受けましたが、同盟とは近隣かどうかではなく、利害が一致し、協調しやすい相手と結ぶものであり、地理的な条件は最優先事項とはなりえません。 仮に中朝韓と同盟を結ぶ事を検討したとしても、この三国が極めて強い反日感情の持ち主であり、分裂しがちな国論を「反日」を含む「諸外国への敵意」で纏める傾向の強い事を考えれば、彼らが同盟相手としては不適であるというのは明らかです。こうした姿勢が是正されない限り、日本が中朝韓と同盟する、などというのは時期尚早という他ありません。 ともあれ、集団的自衛権を持ち、それを行使できる体制を整える事は、一国のみで防衛を成し遂げようとするよりもローコストな選択であり、戦争を未然に抑える可能性が高いという点で、リスクも低いお得な選択肢であると思います。スイスのように個別的自衛権を極め、重武装で要塞化した国土に篭もるのも一つの見識ではあるでしょうが、核兵器や徴兵制導入の是非を問われると言う点では、あまりお勧めできないと私は考えます。 本当の意味で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意」するのであれば、「平和を愛する諸国民」との連帯である集団的自衛権は不可欠なものであり、その行使を認めないとする現在の憲法は改正するべきです。
2005.10.03
コメント(2)
全5件 (5件中 1-5件目)
1