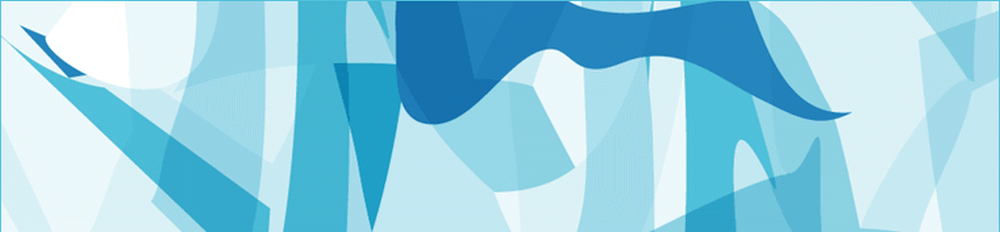2016年02月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
「感情労働と看護」武井麻子先生の講演会、自分の看護生活での幾多の悩みの意味を理解することができた。その1.
先週の金曜日、「感情労働と看護-人相手の仕事はなぜ疲れるのか」という研修会が区内であった。 ここ数年、職場で時々起こる人間関係に関係するごたごた。普段研修会なぞには参加しない同僚を誘って出かけて行った。 武井麻子先生の「感情労働と看護」という著書は、題名だけで興味を持ち10年以上前に購入したが、その頃の私にとっては難解で読了をあきらめたがいつかは理解する時期が来そうな気がして本箱で鎮座している。 先生の雰囲気は知的かつ厳しさを感じさせられた。事前に渡されたレジュメを見ると、今まで、そして現在さえもされている看護教育の「共感」「傾聴」「受容」などという言葉にも批判的であった。 看護という仕事は、「鎮痛剤を患者さんに渡す時でも、相手の痛みを知りこの薬を飲むとどのくらいの時間で治まるのでお飲みいただけませんか」とか「痛みが軽くならないときにはまたすぐにナースコールを押してくださいね」などという対話を通して、自分自身を道具として働きかけて初めて看護になる。 私が受けた看護の基礎教育は40年ほど前だけど、「患者さんの前で泣くな!何かトラブルを起こしても決して謝るな、一人の人に時間をかけ過ぎず公平に看護をしなさい」などであった。建前は公平だけど、「やだな」と思ったり「ひいきしたくなってしまう」のは自分自身の感情としてごく普通のもの。しかし、そういう自分自身のいろいろな感情を押し殺していることがひどく疲れを増してしまうことのつながってしまう。そういう仕事が看護をはじめとするケアの仕事だという。 「感情労働とは、感情労働の不可欠な要素として適切/不適切な感情表出が規定されており、それに沿って感情を管理することが求められる職業」と規定されている。 看護の基礎教育で教えられる感情のルールとして、共感的理解、傾聴、受容。先生は「共感的理解なんて嘘っぱちだ。とりあえず傾聴しましたという表現をする者がいるが、とりあえずの傾聴なんてありえない」と一言で看破していた。 このような感情ルールを、本物の良い看護師になるために、深層演技をする。感ずべき感情を感ずるように、感ずるべき感情を感じないように、感情を引き出したり、加工したり、押し殺したりする。さらに「共感的理解」「傾聴」「受容」の努力をする。道場でするのではなく、客観性と根拠を持つ判断を。 これとは別に、現実の看護労働の現場では、もう一つの感情ルールが存在する。能率よくてきぱきと。間違えたりミスをしない、感情的になってはいけない、常に冷静で知性的に。 基礎教育で教わった看護師像と現場での労働では非常にギャップがある。24時間、3交代か2交代でチームでケアを行い、そのうえ入院期間も1週間以内。臓器移植でも3日間という医療機関もあるという。 さらに良い看護師であるために深層演技をするので、例えば「思いやりのある人のふりをする」「冷静で知性的のふりをする」「厳しい人、怖い人のふりをする」。病棟ではこのような役割分業をしているので、優しい看護師がいられるのは厳しい看護師がいるからこそとの説明があった。 自分自身の感情を変える作業や「いやだな」という感情を作業を続けていると、「ドキドキして眠れない」「怖いからあの部屋に行きたくない」など、の気持ちが強くなるが、感情ルールとは別な気持ちなのでなかなか同僚に話すことが難しくなる。 入院期間が非常に短縮され、先週の日勤でケアした人が次の出勤日にはもう退院していたなどということが急性期医療をしている病院では普通のことになってしまっている。患者を理解しようとしても短時間の接触時間ではなかなか難しい。 医療機関の現場では、あるべき看護師像を患者から期待され、実際のケアは決められた時間内にミスをせずに遂行しなければならない。看護教育で教わった看護師になろうとする努力をしていると現場では時間内に終わらせなさいとか別のプレッシャーで追いつめられる。 看護業務になれるまでの、新人からの数年間で看護師を辞めていく看護師はまだまだ多い。 先生のお話をききながら、「あの頃はそうだったなぁ」と新人でダメダメ看護師時代を思い出していた。
2016年02月23日
コメント(6)
-
東京国立博物館のギャラリートークと国立か家具博物館のディスかビバリートーク。
自宅から上野まで、地下鉄とJRで1時間もかからない。 科博では土日に11時と14時から研究者による30分コースで2題のディスカバリートークがある。出かけるかどうか少し迷ったがやっぱり気分転換も兼ねて9時過ぎに出発。 両博物館共に友の会会員なので、入場料は不要。 先週もディスカバリートークに参加したのだが、常連さんが沢山いらっしゃるようで先週方にお見かけした方が何人もいらしていた。 今日のお題は、1.大陸のでき方 2.海藻の多様性 中学、高校と理科関係の教師がどうしても好きにならずずっと不勉強。一回ごとにお聞きする話は皆新鮮。陸地を構成する岩石の90%は花崗岩で、海底の岩石は100%玄武岩だという。46億年前はすべて海底だった地球が何億年もかけて陸地ができ、現在でも新たな陸地が形成されているという。 登山をしていたころ、この山は昔は海だった、というような話をきいたのだが、陸地はすべて昔海だったんだとやっと知ることになった。甲府盆地は1500年かけて陸地になり、丹沢山地は700万年かけて出来上がったという。 どういう過程で、玄武岩から安山岩になり、花崗岩に変化していくかについてはまだまだ仮説の段階だと。 マントルが冷却するスピードは一般的に100万年で20度から30度だと言われているが、丹沢は100万年で600℃という世界最速の冷却スピードだったという。まだ仮説の段階だが、「地球」という海底探索船で現在目下研究中という。 実家の前を流れる鼓川という笛吹川の支流の川岸には花崗岩(その頃は御影石と教わった)が多く、夏などは水遊びをした後に大きな石に横たわり青空を仰ぎながら水で冷えた体を温めた。花崗岩が地球の中心から何千万、何億年もかけて地球表面に存在していたなんて。 今住んでいるこの地が、かっては海の底だったなんてなんかロマンチック。 私のような理科についてほとんど無関心だったものにとって、科博は宝島みたいなところ。でも、約1時間以上研究者のお話をきき続けていると、脳疲労が高まって、講師の方に対して申し訳ないが眠気が襲ってきた。 科博で見たいところがまだまだ沢山ありすぎるのだが、もう集中力がなくなってしまって、東京国立博物館に移動。 15時からは、東洋館でギャラリートーク。お題は「七宝饕餮紋卣」にみる清工芸の精華」という難しい題。 七宝は装飾技法のひとつで、清王朝は工房を宮廷内に作り、古代の祭礼儀式を再現するうちに装飾品として珍重されその時代の最高技術が過去の技術を超越する作品を作り上げ、新たな芸術の進化を遂げたという。 饕餮紋は獣面紋ともいわれ、獣面がいくつも重ねられ、雷紋など非常にユーモラスで色彩豊かな紋様であった。細部まで非常に徹底したデザインと繊細な紋様が組み合わされ、色彩の豊多とデザインの全くスキのない構成。時間さえあればずっと見続けても飽きてしまわないような作品。 最後の「卣」とは、青銅器時代の儀式に使う酒器だという。古来のものを新しい技術で新たな創作をすることでさらに優れた作品に作り上げていく。 古今東西、芸術家の創作意欲が無限であることを改めて感じられた。 日本の工芸家も中国や朝鮮からの芸術品を見ることによって、創作意欲を高めて新たな日本の風土からつかんだものを新しい作品に昇華させていったのに違いない。 いろいろな作品を見ていると、国立近代美術館の工芸館に行きたくなった。 お休みの日は、仕事とは一旦脇に置いて、自分の好きなことをするほうがなんか元気が出てくる。 来週はベッド上と車いす姿勢の調整方法の研修なので、また休日が仕事関係になってしまうのだけれど、お家を一歩踏み出すことで、新たな境地が開かれていくことを期待していこう。
2016年02月21日
コメント(2)
-
出そうか、出すまいか。迷いに迷っている異動希望。
年度末には恒例の年度末面接がある。 上司や同僚の無責任的な仕事内容に、怒り心頭で何度も退職を考えた一年。 ところが、昨日訪問した患者さんから「4月には人事異動があるの?毎年、毎年知り合いになった看護師さんたちが辞めていくので心配なの。せっかくいろいろ話すことができるようになった看護師さんが辞めていくのは寂しいわ」って。 確かにここ2年間の間に、4人の看護師が退職し、3月には退職が決まっているものが1名いる。 この方のケアはややこみいっていて、適切なケアができるようになるまで2回か3回の同行訪問が必要になる。もし、私が異動したらこの方が在宅療養を開始してからお付き合いしてきた看護師は0になる。この方のケアができるものは今のところ5名。そのうちの1名が退職するので、もし私が異動したら3名になってしまう。 今まで多くの患者さんに慕われて信頼されている医師が何人も退職していった。患者さんがいるからこそ医師なのに、どうして退職してしまうのだろう、と疑問だった。 でもここ数年、職場のゴタゴタが一向に解決に向かわず、残業を認めない上司がいるとケアの手抜きを平気でする同僚が続出したり、医師の指示変更を確認もせずに前回と同じ誤った処置をしても平気でいたり、こんな同僚とはもう一緒に働きたくないという気持ちがどんどん膨らんできた。 それでも、私はやっと看護の仕事が大好きになり、訪問した患者さんに少しでも楽になっていただいたり、悪化する状態変化があれば医師に対しても遠慮することなく主張することは平気でできる。直接談判することも医師だろうと薬剤師だろうと、患者の利益になる可能性があれば遠慮して黙っているほうが有害だと思う。 30年前は、医師の報告することを上申と言っていた。なぜ、患者さんのケアの責任を担っている看護師が医師に対して「上申」というへりくだりすぎる言葉を使うのだろうと疑問だった。もちろん、医師は医療チームのリーダー的役割を持つので、敬意をもって主張することは大事であるが、封建時代のごとく間違った指示でも殿様の言うことなら従うみたいな関係性は間違っていると思う。だから、意識的に医師に対して患者情報を伝えるときには、報告とか連絡という言葉を使っている。 同僚に対しては横柄な態度をとる看護師が、上司だったり医師だったりすると途端にへりくだった態度の豹変する。そういう態度を目にすると、誰のために仕事をしてお給料をもらっているんだと怒りがこみあげてくる。誤ったケアをしたら、そのケアに対しての報酬を自分で負担しなさいよ!って叫びたくなるが、そこまではまだしたことはないけど。 そんなこんなで、4月からは「移動できなければ体制が整った時点で退職するつもり」と宣言する予定だった。 でも、患者さんから寂しくなると言われてしまうと、同僚や上司がどうであろうとこの場所で働き続けるしかないかなとも思う。 同じ職場に何年もいることは、患者さんに対しても職場の維持にも弊害があることも多い。 もう7年も同じ職場なので、やっぱり異動希望を出そうかな、どうしようかとまだ思案中。 うーん、悩ましい。
2016年02月18日
コメント(10)
-
3連休の三日間、連続してお出かけ。
なんだか元気になってきて、怒り虫も治まってきて朝も起きられるので、連休初日の土曜日には東京国立博物館の「始皇帝と大兵馬俑展」に出かけてきた。 始皇帝という人物については、名前こそ知っていたがどういう存在だったかは全く知らず。 紀元前という日本がまだ縄文時代から弥生時代の時代に、非常に写実的な兵馬俑の姿は今そこにその兵がいるかのような臨場感があり、馬も生き生きとしていて中国の方が中国の文明や文化に誇りを持っているのもうなづける。もうその時代に漢字があり、始皇帝は度量衡、貨幣の統一、文字の統一を行い中央集権国家を作った。貨幣も日本の和同開珎や寛永通宝にもその形が踏襲され、日本の平安時代以来の中央集権国家もこの中国の支配体制の影響を受けた。 残念ながら、始皇帝は権力を誇示するために万里の長城を築城したり、農民の過大な負担を強いて反乱を呼び起こし41歳という若さで亡くなり、死後3年後に秦は滅んだ。 日本でも豊臣秀吉が神となり神社にまつられたり、徳川家康が日光東照宮でまつられたり、権力者は自己顕示欲が強い。 年貢を納める農民により政権の経済的基盤が成り立つのに、自己顕示に相当の額の支出をすることを進めて行うことは為政者としてどうかと思う。政権基盤を盤石にするための手段ともいえるかもしれないが、その時代の権力者は政権の維持を第一に考えがちだったのかもしれない。 二日の日曜日は、国立科学博物館の「渋川春海と江戸時代の天文学者たち」を観たくて、またまた上野に。この日は5月上旬の温かさという気象予報もあり薄着で出かけて行った。 渋川春海は非常に実証的で、平安時代から800年も続いた暦を夜空の観測に基づいて暦を改定することの心血を注いだ。中国暦のずれをただすために天体観測をして、展示されている「天体分野の図」などは非常に精密で、しかも天体観測の結果61もの新しい星座を発見したという。 正確な暦を作るために、オランダ語が得意でもないのに、天文学の翻訳と研究で41歳という若さでなくなってしまった。1608年にはオランダで初めて望遠鏡が作成され、徳川家康にも献上されたという。その後日本の技術者も望遠鏡を作成できるようになり、江戸時代は天文学が非常に進み、天文方といういう役人にとどまらず各地で天体を観測する人が増え、江戸城にも天体観測所が設けられたという。 高橋至時というと、伊能忠敬の天文学の師匠として有名だが、その後も天文学者は幕府の天文方として活躍して、徳川吉宗の命であった暦が天保暦として日の目を浴びることになった。 展示されていた天保暦を見ると、95%くらいは読めず。江戸時代の寺子屋をはじめ庶民にも許された教育システムが各藩にいきわたり、現代人の私には読解困難が暦が庶民のものになっていたことの素晴らしさを思う。 連休三日目の今日は、東京ドームで行われている「世界らん展日本大賞2016」に出かけてきた。 バラも素晴らしいが、ランの素晴らしさもバラに劣らず素晴らしい。洋ラン、和ランなど、その形状と色の複雑さ、形の繊細さ、初めて見るラン展ですっかりランの魅力にとらわれてしまった。 世の中にもこれほどの美しいものが沢山あるのですね。 野生の春蘭もエビネも盗掘されて、今では絶滅の恐れもあるともいわれている。 胡蝶蘭を初めとする洋ランの豪華さはすごいものだが、私はやっぱり春蘭やエビネなどの和ランが好きだ。 朝9時半過ぎに会場について、5時半までずっとコンデジで写真を撮りまくった。 美しいものをみると、元気になるものです。 連休の三日間、お出かけ続きだったので、どこにもよらず帰宅。 やっと出かけられる元気が戻ってきて、とりあえずホッとできた三日間でした。
2016年02月15日
コメント(6)
-
人生に大先輩と受け止めていろいろなお話を聴かせていただく。
Rさんは、戦前に生まれ非常に優秀でいつも学年のトップ。作文も書道も弁論も得意で、何回となく表彰されたという。 敗戦後価値観の大転換で何を信じて生きていけばよいか非常に迷い、戦後の学制改革で女子も進学できるようになって大学に進み、ここでも首席であったらしい。 残念なことに、世の中は優秀な女子学生が大学を卒業したとしてもそれ相応の待遇をしてくれることはなく、ずいぶん葛藤して数年職業婦人と過ごしたがお見合いで結婚して、夫の事業を支えながら5人の子供を育て上げた。 夫は職業軍人上がりのエンジニアで仕事に夢中でいくつかの特許をとったこともある方だったという。 工場の拡張のために借金を重ね、その借金を返済するために、企業内の食堂で100人規模の賄いをしたりして、夫の借金を返済してしまった。 弁が立つので、地域の役職をいろいろ引き受けたり、PTAの役員を引き受けたり公私ともに多忙な日々を過ごしたという。 夫の工場が都内から他県に移転して、その移転から数年で夫が脳卒中になりご本人も会社の役員にもなっていたので、工場の閉鎖の整理とまたまた借金の返済が相当あったのだという。 夫の看病をしながら、仕事を続けて、15年看病の後にご主人が永眠。 それから数年後、ひどい貧血が分かり精密検査を受けたら進行した大腸がんと分かり、手術して人工肛門を造設した。人工肛門の位置がお臍の上なのでご自分で管理できず、退院後は便漏れのために皮膚炎が悪化して再入院。 子供たちも皆働いており、人工肛門の装具交換のために訪問看護を受けるようになった。 ケアをしながら、どのような人生を送ってきたか、その時自分はどんな決意をしたかなど問わず語りでいろいろ教えていただく。 どのような気持ちで人生の困難を受け止めてきたかなどは、自分がどう物事を受け止めていけばよいかの教えをいただけているようなもの。 両親も叔父や叔母たちも向こうの世界に逝ってしまっているので、身内から人生訓を聴く機会はなくなってしまったが、人生の大先輩からお話を伺うことができる今の仕事は、ケアをするだけでなく、様々なお話を聴ける機会が多く非常に充実した時間でもある。
2016年02月11日
コメント(6)
-
最期の三日間。娘や孫に見守れて静かに息をひきとっていったHさん。
91歳のHさんは江戸時代からご商売を続けてきた老舗で、Hさんの弟が6代目だという。 商家のお嬢さんなので、三味線、小唄、お琴、日本舞踊、小唄など様々な習いものを小さいころからしてきたという。地方出身のご主人とは学童疎開で出会ってご夫婦になったとか。 江戸っ子気質で、白黒をはっきりして、きりりとしたご性格だったという。 杖を使って出かけられる頃は、家にいるのは大嫌いでいろいろなところにお出かけをしたり、長唄をお師匠さんに習ったりして忙しい生活をしていたのだそう。 「だったら病院で生活するなんてお嫌だったんでしょうね」と娘さんに尋ねると「病院なんか大嫌いですよ」と。 入院中も、お見舞いに行くご家族に「いつ返してくれるんだい、うそつきはやめてちょうだい」と言い続けていたそう。 娘さんたちも姪御さんもこのHさんに対して敬意と愛情をもって接しておられ、看護師からケアの方法を伝えるとその通りのことをやろうとするお気持ちを率直に示して下さった。 残念ながら、退院した二日目から呼吸状態が低下し、食欲がなくなり、誤嚥をしたりなど病状の変化が速く、退院三日目には呼吸困難が起こり、在宅酸素でも酸素治療も始まった。食べる量も極端に少なくなり、冷たい氷だけは口に入れることができた。 4日目には全身清拭、全身の皮膚の保湿などができたが、5日目は血圧が低くなり始め、6日目はとうとう目をうっすらあげられるくらいになり、血圧は触診で収縮期血圧が58/、酸素飽和度は測定困難、脈拍と呼吸状態は規則的で安定していたが血圧が低いことからそうそう長くないことが予測できた。 ご家族に週単位というより、二三日もしくは四五日といった日単位で臨終が訪れる可能性があり、できるだけご本人のそばにいて体をそっと触れてあげたり、褥瘡の悪化を防ぐために体で一番重い骨盤の下に手を入れて除圧を図るように勧めた。 その夜お孫さん二人は一晩中Hさんのそばにいてずっと体に触れながら、呼吸が止まると呼びかけたりしてくださっていたという。娘さん三人も交代でそばにいて一晩を過ごされ、喘ぐような苦しそうな呼吸をすることなくスーッと息が止まったという。 朝方6時間半に呼吸停止となり、緊急携帯に連絡にあり訪問。すでに呼吸も心音も停止していた。 大便が出ていたので、お尻をきれいにして訪問診察医が来るのを待ち死亡確認をしていただいた後にお口をきれいにして入れ歯を入れ、背中に貼ってあった床ずれ予防のフィルムを張り替え、ご家族と一緒に体をきれいにした。 退院してからちょうど一週間のご自宅での生活であったが、娘さん、息子さん、お孫さん、曾孫さんに囲まれスーッと息をひきとられお顔は穏やかで苦しむことなく最期を迎えられたことでご家族皆さんが涙ぐまれながらもほっとされていた。自宅に帰ってきてちょうど一週間、ご家族にとっては心理的にも肉体的にも大変だったが理想的に最期を迎えられ母親のために本当によかったとおっしゃっていただいた。 退院しての一週間の間、会わせたい人と全員と会うことができ、ご家族に囲まれ過ごされた。 ご家族の介護力があると、住み慣れた自宅で最期の時期にご家族に囲まれ穏やかで温かい雰囲気の中過ごすことができる。 訪問介護や訪問看護を利用して、一人でご自宅で最期を迎えることができる方もいる。 超高齢者のターミナルケアは、状態の変化に応じてケア方法をご家族に説明して、ご家族が直接にケアに参加して見守ることができることが大切だと思う。 きりりとしながらも穏やかなHさんにお顔を拝見させていただいて、一生懸命に生き、ご家族を育まれて生きていらした人生の重みを感じさせていただいた。 Hさんのご冥福をお祈り申し上げます。合掌。
2016年02月08日
コメント(8)
-
高齢者のターミナルケアを思う。
94歳の女性。 子供が6人、孫が16人、ひ孫が4人。 ひどい貧血のために入院したものの、本人の負担が増すような検査は望まず、輸血を2回して、食事をとれないので入院中は中心静脈栄養で栄養管理をしていたが、これ以上入院したくないと中心静脈栄養の針を抜き自宅に帰ってきた。 点滴も望まないとのことで、家族一人一人が最期を自宅で迎える用意があると医療従事者は考えがちだが、実際嘔吐したり、呼吸が苦しいと本人が訴えた時、それが死にゆく一過程だからと見守る心の用意をしている家族はなかなかいない。 病院で最期を迎える方が圧倒的に多いので、どのような過程で最期が訪れるかを心得ている人が少ないのは理解できる。 だからこそ、訪問診察があり、訪問看護があるのだと思う。 家族が最期を自宅で過ごさせたいと考えた時、それを支える専門職はどのようにサポートをしていけばよいのだろうと、臨死期の方の訪問をするたびに思う。 半年とか一年とかの期間で少しずつ状態が悪化していくのであれば、家族の気持ちの変化に対応して少しずつ話し合いをしながら、呼吸の見方とか、意識の変化とか丁寧に説明できる時間的余裕がある。 一日とか二日とか、一週間とかの短期間で最期を迎えてしまう方が増えてきており、何からどう説明していくかなかなか難しい。 一応「お看取りについてのパンフレット」を家族に渡しておいて、最期の時期の身体の変化やその状態に応じた対応について述べられてはいるのだけれど、数日で理解していただくことは難しいし、家族との信頼関係が成立しているかどうかわからない関係で、そういった微妙なことを話題にするには、ある意味力量がないとできない。 一分でも一時間でも生きていてほしいという気持ちと、呼吸が苦しそうとかそういったつらいことは少なくしたいという気持ちは、矛盾してはいるけれども、ごく自然なご家族の思い。 そういうご家族の思いを慮りながら、でも率直に最期の過ごし方を家族としてどう送るかの話をするしかない。 大切にしてくれるケアをしてくれる看護師と思われるような丁寧なケアをしながら、家族の理解に通ずるような説明をして、やって見せて、やっていただいて、家族がケアすることに自信を持っていただく。 そんな気持ちで仕事をしているつもりなのだけど、苦しそうな家族の身体に触れることも怖くって、看護師のしたケアの後に何もできずに24時間以上、姿勢を変えていないこともある。 家族として残された時間はそうそうないのだから、家族に患者さんのケアに参加できるようになってほしい。 今日もそんな気持ちで19時過ぎまで働いたけれど、私がそれを現実にできるようになるには、まだまだ道は遠い。
2016年02月06日
コメント(10)
-
この間の労働基準法違反の諸問題について、組合の専従役員と話し合い。
現在の職責者になってから、就業時間を超えて仕事をしているのを見て、見ぬふりをして仕事をさせておいて、仕事が遅いから時間外はつけないとか、1時間もかかる仕事ではないから30分しか認めないとか、そんなことが続いている。 業務について不慣れならば、しっかり教育なり指導をして身につけられる期間を職員と相談して、どうすればよいのかを確認していけばいいだけの話だけど、教育を一切しないで、実際業務をしているのを知っていながら、時間外業務の指示をしないでいる。そのくせ、許可を求めない時間外は認められないと公言する。 職責者が仕事をしているのを知っていて仕事をしている場合は、時間外の指示があったものとみなして時間外を請求できる。しかも1分でも時間外業務をするとしたら、カットせずに請求できるように法的には保証されている。 ある職員は法定休日に仕事を命じながら、実際は3時間かかったのに当日の患者カルテを見てどのようなケアをしたのかを確認しないまま、この仕事は2時間で済むはずだからと職員の目の前で時間外を職責の個人的見解で削除。 法定休日に仕事をさせておいて、代休をつけられないからと約半日の仕事をしたのに代休をつけない。 勤務予定表は、当月の初日に提示するありさま。観劇の切符をとれないし旅行の予定もできない。 有給休暇は、本人の申し出があればよほどの事情がなければ認められるはずなのに、希望は一か月に2回だけだからそれ以上はダメとか。さらに、勤務予定の前日に仕事が少なくなったので、明日は休んでと本人の希望で休むのではなく、職責者の希望で休ませる。 ご自分は真っ先に休み希望を入れて、5連休とか長い休暇を率先して休んでいる。 訪問看護記録は当日に記録をするのが原則なのに、翌日休みなのに記録をしないで帰宅してしまう。 今始まったことではないのだけれど、こんなことがこの職責が異動してからというもののずっと続いている。 あまりの酷い労務管理が続いているので、やっと同僚がそろって組合に相談に行った。 組合の専従と書記長が同席していて、看護部の理事にまず質問状を出してどのような対応をするかということになった。 職責を含めて常勤看護師が3人の時には、職責も他の職員同様に土日の携帯当番も行っていたし、普段の訪問もほぼ他の同僚と同じように仕事をしていたので、休み希望が無理なこともあったけど、少ない人数で仕事をしているので有給休暇を自由にとれないのもやむを得ないと承知していたのだけれど。 時間外業務が発生せざる様な仕事はお断りしていたし、基本は時間内に仕事が終わるように業務を組んでいた。 確かに、常勤職員が増えれば仕事が増えるのは当然のことだが、同じ職員なのに土日勤務がない人がいたり、月に何回も土日勤務をする人がいたり、緊急携帯当番の日数も平等ではない。 そんなことが数え切れないほどあって、やっと組合に集団で話し合いに行った。 看護部の幹部は一時期3年程、医療系の組合の専従経験もある人なのに、どうして労務管理の基本的なことを部下に指導していないのかが不思議で仕方がない。 立場が変われば、見解も変わるという典型例なんだろうな。
2016年02月04日
コメント(2)
-
白色ワセリンの効果。唇の渇きも指先や爪の乾燥もささくれも予防できる。
以前にも白色ワセリンの効果については書いた記憶があるが、最近はリップクリームは全く使わず。 唇の皮膚は縦に皺があるので、白色ワセリンを米粒か小豆大にとって唇を縦方向にマッサージを繰り返す。特に夜寝る前には丁寧にマッサージをしながら塗って、朝起きたら同じように塗り、洗面後にも同様に塗り、出勤前にも再度塗る。これだけすると、日中は昼休みに同様に塗るだけで唇の荒れは完全に予防できる。 朝シャンと洗面の前には、植物オイルで頭皮のマッサージと顔のマッサージをして、顔についてはクレンジングクリームで再度マッサージをする。洗顔は普通の石鹸を大きな泡立てようの布を使いホイップクリーム位に泡立てて洗面器に泡をためておいて、洗髪をしてトリートメントをつけて3分後くらいに、トリートメントを37度のお湯で十分に流してから、泡立てておいた石鹸で決して力を入れずに丁寧に洗った後、十分に泡を落とし切る。 自分でまだ化粧水は作っていないのだけど、市販の肌の負担をかけない成分ができるだけ少ない化粧水をたっぷり顔に浸透させてから植物オイルを薄くのせてよくなじませてから、UVクリームを塗るだけ。 乳液を使わなくなってから肌のあれがなくなり、多少はシミがうすくなってきた感じ。 皮膚には自然に皮脂が分泌するような機能が備わっているので、乳化するための界面活性剤が入っている乳液はお肌を荒れさせる原因になるという。 そんな話を美容院で教えてもらってから、乳液の使用を中止している。 白色ワセリンは、市販の一番安いもので、50gで税込みで390円くらい。皮膚科でプロペトといって通常のワセリンを精製したものは、さらに肌に優しいそうだ。 ハンドクリームも高価なものは1000円近くする。資生堂の撥水効果のあるものとか結構いいものがあるのだけれど、夜寝る前に白色ワセリンを使って爪や爪の周りの甘皮を丁寧にマッサージして、さらに皮膚のしわは横に走っているので、縦にマッサージするのではなく皺の方向に丁寧にマッサージをすると、仕事がら日中にケアの前後に何回も消毒剤入りの石鹸を使ったりアルコールが入っている消毒剤入りのものを何回となく手から手首まで何回も塗り込むのだけれど、白色ワセリンでマッサージするようになってからささくれもできず手荒れもなくなった。 ワセリンは軟膏の基材になっており、傷のある皮膚にも使える。そのうえ、そうそう高いものではないので、けちけち使わなくても済む。 荒性の方で、ワセリンにアレルギーがない方なら、寝る前のお肌のお手入れに白色ワセリンを使ってみるもの良いかもしれない。
2016年02月04日
コメント(4)
-
今年の冬はやせ我慢を貫くことにした、ガスストーブを使わずに冬を越せるかの実験。
昨日は急にお休みになり、美容院でヘヤーカットをしてから神保町のアウトドアショップで買い物。 この時期は、春物の商品に切り替えるために昨年の春冬商品が格安になる。一番の狙いはメリノウールの半そでや長袖。15000円ほどのものが約半額になるのでワゴンセールのものを見極めてサイズを確認して半袖Tシャツを2着、長袖を1着購入。モンベルのゴアテックスのレインウェアのズボン、ゴアテックス用の撥水スプレーを2缶。 ここ3年程、ユニクロの下着を着ていたのだけれど、大体1,2年で着られなくなるのでお値段ははるのだけれどアウトドア用のものに戻ることにしたのだ。ブラック企業との評判もあり、ちょっと買う気にはなれなくなったのも事実。 ディスプレイを見てみると、メリノウールの下着にウールのシャツ、フリースの中着に羽毛の上着。 これを見て、冬の寒さを乗り越える重ね着のアイディアを思いついた。 以前、外来で働いていたころ、冬になるとお年寄りの方は五枚とか六枚とか重ね着をしていたことを思い出した。そうだ、寒さ対策には重ね着をすればよいのだと思いついた。 冬山用のタイツにフリースのズボンに羽毛のズボンで下衣は完成。メリノウールの下着にフリース2枚を重ね着して、シュラフを腰に巻き、ひざ掛けを肩に巻いて、湯たんぽにひざ掛けをかければ暖かい。 掃除や洗濯をするときには、ひざ掛けを肩に羽織ってマフラー用にピン止めみたいなものでずり落ちないようにすれば大丈夫。 窓にプチプチを貼ったこともあって、室温が10度以下になる日も少ない。 今年はガスストーブを使わないで、冬を乗り越えようと決断。 まぁ、押し入れからガスストーブを出すのが面倒ということもあるんだけれど、これで冬を乗り越えられそう。
2016年02月04日
コメント(8)
-
認知症徘徊による列車事故の家族責任を考える。
JR東海の認知症の方が徘徊により列車事故にあったことにより、家族に賠償責任が要求されており、85歳の妻に360万円の賠償責任が負わせられている。 確かに列車事故によりそのために輸送機関は多額の損失を被る。 しかしだ、新聞報道の写真を見る限り改札を入らなくても線路に入りやすくなっているという設備の問題は一切不問。危険な行為が起こることが予想されるとしたら、高い柵を設けるとか扉をつけて常に施錠しておくとかそういう危険回避をする責任が輸送機関にあるのではないか。 誰でも入れてしまうような施設の在り方が問題にならないことが、不思議で仕方がない。 徘徊する可能性のある方を24時間監視するなんて不可能に近い。それも85歳の妻。ご自分のことだけでも行えるのがやっとだろうし、トイレに行くのだって時間がかかったり、居眠りをしてしまうことだってあるだろうし。24時間監視するなんて、できるはずがない。 施設構造が認知症のある方に対しての設備を設けていないことが大問題なのだと思う。超高齢社会になって認知症の方が400万人とか500万人とか言われている時代に対応をしていない、そういうことを考えもしていないJRって、やっぱり殿様商売の感覚がないんだろうか。 行政責任は問われていないが、認知症の方を地域全体で支えるとか、GPS機能をさらに発展させてそういう方が危険地帯に近づいたらアラームが鳴るとか、いろいろな企業が徘徊する方に対しての様々な商品を開発してほしい。
2016年02月02日
コメント(12)
-
トーハクで初もうで、久しぶりに東京国立博物館へ。
東京国立博物館では、毎年一月にその年の干支にちなんだ催しものや展示がある。 昨日はもう1/31なので、「猿の楽園」の展示の最終日なので、出かけてきた。 天気も良く比較的暖かく、久しぶりの上野は落葉樹の葉っぱがほとんど落ちきっていて冬の樹木が美しかった。 「猿の楽園」は2階の一室にあり、かわいく微笑んでいるお猿さんとか、刀のつばに透かし彫りのサルとか、群れている猿が遊んでいる絵とか、じっくりと見ているとあっという間に時間が過ぎて、なんだかお腹がすいてきたなぁと気が付いたときにはもう午後3時。 9時半ころにはもう博物館にいたので、5時間余り見続けていたのだ。 東京国立博物館には本館、東洋館、平成館があって、東洋館の地下にはミュージアムシアターがある。入館料とは別に500円かかるのだけれど、凄い映像で美術品の解説が行われる。今回は「色絵月梅図茶壷」「八橋蒔絵螺鈿硯箱」。 茶壷の厚みをCTで計測したり、高精細カメラ2台で全周を撮影して、さらに梅の幹と枝と、雲を別々の映し出すなどすごいこと凄いこと。 仁清も光琳も名前だけは知っていた芸術家だけれど、ここまですごい技術とデザイン力があったのかと感嘆しきり。 帰りには、いつもの文化亭で「634 ムサシビール、生ビールの大ジョッキ」を飲んで帰宅。 あーぁ。いい一日でした。
2016年02月01日
コメント(4)
全12件 (12件中 1-12件目)
1