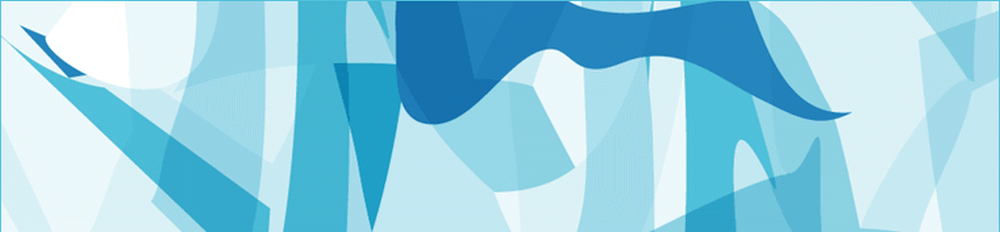2016年01月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
一か月ぶりに電車でGO! 清瀬で呼吸リハビリの研修会。
東京清瀬市の複十字病院の呼吸ケアリハビリセンターの部長に千住秀明先生が昨年の4月に就任して、「東京夢塾」が立ち上げられ、私も11月から月一回の研修に参加している。 講義が1時間半、実習が1時間強。参加費は3000円。 昨年の暮れから不調が続き、今日の天気予報も雪になるかもしれないということで、今回はもう参加できないかと心配だったが、何とか不調から脱出できてやっと電車に乗る元気が出てきた。 電車で出かけるためには、洗面や着替え、荷物の用意、お金をおろすなどいろいろなことをしないと出かけられない。そもそも起きださないと始まらないので、起きるのが億劫なら玄関を開けるのも面倒。 だらだらでも起きだすことができて、今日の天候を考えて着替えたりコンビニでお金をおろしたり。 引きこもっているときは、普段普通にできていることさえできないので、駅まで歩いていくのさえ億劫で億劫で仕方がない。久しぶりに地下鉄の階段を下りながら、やっと普通のことにそうそうエネルギーを使わなくできるようになったことがうれしかった。 途中、一駅先の病院の売店で来週の月曜日に患者さんに使ってみたい医療材料を買ってついでに昼食も食べて、池袋経由で清瀬駅に。研修の開始時刻の5分前に会場について、約3時間眠気に襲われることなく学ぶことができた。 千住先生は、大学院に進むために放送大学で大学卒業の資格を取りその後に大学院に進み、長崎大学の大学院に修士課程と博士課程を作り上げ後輩の育成を率先して行ってきた方。研究も臨床も大好きで、講義も非常に面白く、さらに実習指導もとても具体的で、患者さん本位の姿勢が一貫していて患者さんのためにどう医師に提案していくかなど何事もとっても前向き。英語論文もしっかり読んでおられてその博学ぶりもすごい。 私のような初心者の質問に対しても、分かるように丁寧に説明してくださる。 呼吸リハビリの一つである呼吸介助は患者さんの身体に、ケアを提供するものの両手掌を使って行うのだが、身体全体の重心移動を両手掌に伝達させて、患者さんの呼吸を手掌で感じ取って相手の呼吸状態に合わせて行うことが必要となる。 そのためには脇を広げ肘を曲げて行う必要があるのだが、普段の看護ケアでは脇を締めて行うことが多いので、この脇を広げて肘を曲げるという体の動き方が非常に難しい。呼吸介助を始めたころは、自分の手首が硬かったり腕が短いためにうまくできないのかと誤解していてどうすれば手首の柔軟性を増すことができるのか悩んだ。 前回12月の研修でこの動作の方法を教わり、手掌を患者の胸郭にトータルコンタクトして、介助する方向に重心移動をすることを指摘していただき今日の実習では、多少はこの動作を行うことができるようになった。 ほんの小さな一歩だけれども、何かができるようになるって心底嬉しい。 岩登りの時に、一歩足を上げられる喜びを感じた時のような嬉しさだ。 とにかく一歩踏み出せて、私にも新年がやってきたみたい。
2016年01月30日
コメント(8)
-
水、木、金と熟睡できて、元気回復。
火曜日にメンタルクリニックを受診して、眠剤をアマバンにロヒプノール2mgを追加されて、水曜日の夜から服用してしっかり眠れて木曜日の朝は6時前に気持ちよく目覚めて朝食を食べられるし朝シャンもできた。 朝の「仕事行きたくない」症状もすっかりなくなり、久しぶりに始業時間の8時40分の15分前に出社できた。 サインバルタも1capから2capに増えて、日中も元気に働けた。 よく眠れるということはうつ状態を改善するために必須条件なんだと痛感。プリプリ虫も収まって、嫌だ厭だ顔を観たくないと感じていた上司との会話もイライラすることなく平気でできた。 土日は連休だけど、今朝の目覚めもよくゴミ出しはできるし、たまりにたまった洗濯もできた。 こんなに数日の内服薬の変更で億劫感がこんなにも早く改善するとは。 主治医が鬱状態でも怒りっぽくなるのは情緒が不安定になるからだと説明してくれたけれど、今回は身をもって体験。 ここ2年くらい、夏場は調子が良くなってついついメンタルクリニックを中断したり、お薬を飲んだり飲まなかったりをしがちであった。夏は日照時間も長いことで、多少はうつ状態が改善するのかもしれないけれど、そのことと服薬を中止することは別問題だったんだ。 もともと私は感情を表現することが苦手で、嫌な感情が起こっていても自分で気が付きにくかったり、世間話をすることも下手。そういう私が、プリプリすること自体、気分障害が起こっていることなのだと思う。 9月頃より、休日に研究会に行ったりして初めて会う方の前で平気で質問できたりするのも、やや軽躁状態であったのかもしれない。 自分の気分の変化を自覚することってなかなか難しい。 軽躁状態なのを、鬱が治ったと誤解するのも自分の感情を適確にとらえられないということなのだ。 暮れからの絶不調がやっと収まって、やれやれの週末。 今日はこれから美容院に行って、清瀬で行われる呼吸器リハビリの研修会に行く予定。やっと休日にお出かけをする元気が戻ってきてほっとする土曜日の朝が来た。
2016年01月30日
コメント(6)
-
自分のことだからわかりにくいのか、第三者の客観的見解って大事。
昨年末からの超絶不調。暮れにサインバルタ1CAPが追加されたが、この一か月ばかり改善の兆しなし。 洗濯も買い物もゴミ出しも面倒くさくって、先週末は食料がなくなって寝起きのバサバサの髪の毛を気にする気持ちにもなれなくって近所のコンビニに買い出し。お店の中の鏡の中の自分は、髪の毛がツンツン立っている。レジの女性がなんとなくよそよそしかったのは、外見を少しも気にしない私の姿のせい? こんな状態をそのままにしてはいけないと思ったけれど、朝は起きたくないし、仕事は休みたくて休みたくって仕方がなくって8時過ぎにやっと起きだす始末。もう二三日でお薬がなくなるのに、今日受診するかどうか決めかねている。午後三時過ぎになってやっと少し元気が出てきて、とりあえず今日受診しなければ大変なことになりそうでやっとクリニックに受診の予約の電話を入れる。 たまたま午後は2件だけの訪問で済んだので、夕方6時前によっこらしょと気持ちがやっと動き出してクリニックに行くことができた。 先週は予約していたのに連絡を入れずにキャンセルをしたので、居心地が悪いけれど診察券を受付に出す。 主治医は以前からマイナス現象に焦点を当てないので、中断したことを気にしていたけれど、いつものように「どうだった?」と一言。 暮れからずっといろいろなことが面倒で面倒で仕方がなく、仕事の日にも出勤したくなくって出勤したくなくっていやいやながら何とか仕事だけは続けていたことを伝える。 「それって億劫感が増しているってことじゃないの」って先生。 「去年の秋の好調が嘘みたいに、数年ぶりの不調です。プリプリ怒りっぽくなっていたし、軽躁だったんでしょうか。自分では鬱が治ったと思っていたのに、サインバルタを再開してもさっぱり気分が良くならないんです」って私。 「うつ状態になっても情緒不安定になるので、怒りっぽくなりますよ。去年の秋の元気さは軽躁だったかもしれないね」と先生。 「自分ではすごく毎日が楽しかったんですけど、ちょっと怒りっぽくなったのが怪しかったんですけど」と私。 「元気が良すぎるのも問題かもしれないね。夏から薬も飲まなかったりしていたよね。やっぱりお薬は続けていたほうがいいんじゃないの」と先生。 「アモバンを22時ころ飲んでも眠れないので、1時ころまで眠れないともう一錠アモバンを飲んでも眠れないし、ベゲタミンBを半錠飲むと翌日の昼過ぎまでなんとなくボーっとしていて休日は二日でも三日でも起きだせないんです」と私。 「鎮静がかかってしまったかもしれないね。ロヒプノールのほうがいいかもしれないし、エビリファイは軽躁状態に効果があるんだけれど、ね。サインバルタ1capでは元気が出ないのかもしれないから2cap にしてもよいかもしれないけど。どうする?」って先生。 「しっかり睡眠をとりたいのでロヒプノールとサインバルタを増やして様子を見たいです。それでもだめなら、ジプレキサとかエビリファイを追加するってしてもよいですか。2週間様子を見て、また診察を受けるってことでいいですか」と私。 「そうだね、様子を見てまた考えようね」って先生。 主治医と5分ばかり話をして、自分のことだけど気分の変化ってなかなか自分では状態の変化をとらえきれないと思う。軽躁状態なのに、鬱が治ったって誤解しまくりだったし、気分障害って本当に厄介。 仕事は70点くらいでできていたと思うっていうと、すかさずに「60点がやっとって感じだったんじゃないの」って先生の一言。 本当に自分のことを客観的にとらえるって難しいもんだとつくづく。 何もかもが面倒って言うのは、億劫感だって気が付く始末だしね。ひどい鬱の時には食欲が全くなくなって好物を食べても砂を噛むような感じだったのだけど、食べ物がおいしくって食欲があることで安心していた私は全く愚かしい。 ここ一年以上、一か月に一回の受診にしていたけれど、また2週間に一回の受診間隔にして様子を見ていくことにした。 何回も症状が良くなったり悪くなったりしていたのに、それでも鬱が治ることを望んでいた私。再発を繰り返すうつ病(気分障害)は治療の継続が必要と何回も説明を受けていたのに、それでもなお治ることを捨てきっていなかった私。今回のことを忘れないようにして、治療をしっかり続けなくっちゃね。
2016年01月26日
コメント(2)
-
安ければそれでいいのか。夜行バス事故を思う。
スキーバスの深夜の交通事故で15人(若者と運転手を担当していた方)がなくなった。 またか、と思った方は私を含めてたくさんの方が感じたことだと思う。 スキー場までの往復の料金が2万円を満たない額。夕方に都内を出て、翌早朝にスキー場につく。 JRと最寄りの駅からスキー場までの往復の交通費を考えると設定された料金は格安だ。利用された方々が、料金がどのような支出で構成されるかは考えもしないと思う。運転手二人の賃金(深夜手当も含む)とガソリン代、高速料金、バスの維持費などを含めて料金が適正かどうかなどと誰も考えはしない。 そのうえ、その会社がどのような雇用条件で運転手を雇っているか、どのような教育をしているかなどはさらに考えもしないだろう。 自分だって、スーパーでもやしを買うとしても、その製造過程や生産者が正当な利益を得ているかも考えもせず、一番安い値段の店舗で買うこともしばしば。 新聞報道だけでしか情報はないわけだが、65歳のその運転手は大型バスの運転に対して不安を表明していたのだという。しかも、その運転手の方の遺体の引き取り手がないのだという。 新しい技術、この場合は大型バスの運転、を獲得するにはそれ相応の訓練期間が必要だし、本人の不安がなくなるまで指導する立場の方が同乗するのは当たり前だと、顧客の立場ならそう願いたい。 新聞報道だけでは、どのような賃金体系か、どのような教育期間があったかなど全く不明だが、この運転手が不安を抱えながら業務についていたのは疑う余地がない。この方の年齢を考えると、もう年金を受給できるはずだが、経済的な面でも不安定だったのだろうか。 消費者としては、できるだけ安ければそのほうが良いに越したことはないが、そういう心理を悪用して、その業につく労働者の生活や人生を踏みにじっていることにつながっているとしたら、安いことだけで商品を買ってしまう消費者としての良心はどうなるのだろうか。 社会が拡大すればするほど、ブラックボックスも拡大して何が善か悪かも判然としなくなってしまう。 だからこそ、法律があったり様々な規制があるのだけれど、民間活力とか規制緩和とか、そういうことが社会の活力を増大させると公言していた方々は、こういった事態が何例も続くことをどう考えているのだろうか。 ブラックバイトとかブラック企業とかの情報も時々報道されている。そういう報道を知ると、その企業のものを買わなくなってしまう。某ユ○ク○にたいしても、すっかり興ざめしてしまってこの3年間は購入していない。 消費者が賢くなるってどういうことなのだろう。 消費社会になる前は、良いものを大事に使うということが当たり前であったように思う。小学生の頃はズボンも靴下もつぎを当てて履いていたし、それが当たり前だったし恥ずかしくもなかった。いつの間にか、必要以上にものを買ってしまうことが身についてしまった。 労働者の権利を守ることは消費者の権利も守ることにつながる。 だとしたら、その対価もしっかり支払わなければならないのではないかと思う。
2016年01月25日
コメント(9)
-
とうとう一か月、休日引きこもりの日々。
先週の土曜日から3連休であったけど、眠剤の効果もあって、この3連休も昏々と眠り続けて今朝の5時過ぎにやっと「起きてみようか」という気持ちが動き出した。 年末からの超絶不調の理由は何だったろうかと振り返ってみると、一言でいうと「人として尊重されない」という不満だったのだと気が付く。 上司や同僚の他者のことを屁とも思わないような乱暴な言動で私の心は萎えてしまった。自分に自信があれば、他者が自分のことをどういおうと、どんな罵倒をされようとも、胸を張って生きられるものだが。 今の私は、理不尽だと思う言葉であっても、その言葉を跳ね返せずにちょっとでも受け入れて、自分の元気をどんどん使い果たして、落ち込んでしまう。 過剰な自信は自分に対しても他者に対しても害になることもあるだろうけど、不当と思える言葉にでさえ揺れてしまう自分は、正当な自信もなかったんだ。 暮れからの2連休も、3連休もみんな自宅引きこもり。掃除もゴミ出しも空き缶だしもみんな嫌。洗濯機を回すことはできるけど、洗濯ものを干すのが面倒でやっと今朝になってやっと洗濯機を一回ししてやっと干せた。暮れからのたまりにたまったゴミも70Lのごみ袋に三つ。 生きているとやはり身体も生活も排泄をきちんとしないとダメなんだなぁ。 ただただじーっとして暮らしていたので、電気代もガス代も昨年同月比20%減。でも、こんなのは節電した結果ではなく、生き生きと暮らさなかったという生活の結果でしかなく、全然嬉しくもなんともない。ただただ、食事も作らず、洗濯も掃除もしなければ電気もガスも使うはずがなく、引きこもり生活をした結果というわけ。 どういう言葉や態度が他者の尊重を表現することになるのだろう。 自分に対する扱いはひどくても、ひどくされても、でもその人の人格を尊重したりその人の言動を尊重するなんてことができるのだろうか。 他者に対してひどい言葉を、たとえ噂話でも吐き出すと、なんだか自分の怒りの感情に振り回されたりして嫌な感情が結構保続してしまうのだ。 だから、気分転換が必要になるのだけれど、怒りってエネルギーのレベルが高いので、いったん燃え盛ってしまうとなかなか火が消えないので困る。 本当は思春期や青年期にこういった人間関係のノウハウについては勉強しているものだろうけど、その大事な思春期青年期にはやりたいことばかりで人間関係になんか気にもしていなかったので、今頃悩まされている。 人を純粋に人として尊重できるようになる。 今年の一番の課題はこのことです。
2016年01月19日
コメント(4)
-
老いていくこと、死にゆくことをどう受け止めればいいのだろう。
人の生き方は本当に一人一人が個性的で比較をすることは難しいものだと思う。 職業柄、5年、10年と患者さんとお付き合いすると、老いていくこと、死にゆくことを自明の理として受け止められずに、努力さえすれば何事も克服できるという万能感に裏打ちされた努力至上主義の方とお目にかかることがある。 脳梗塞や脳腫瘍になっても麻痺という現実の自分を受け止められずに、ひたすらにリハビリを追い求める方。努力しても努力しても障害の程度はそうそう改善しないまま、もっともっと努力すれば何とかなるという信念にとらわれて新たな障害を呼び起こすほどにむちゃくちゃに努力して絶望に陥る人。 末期の悪性腫瘍で、消化も排泄ももうコントロールが難しくなっているのに、高額な代償医療に巨費を投ずる人。 能力もあり、努力も人一倍でき競争社会の中で生き残ってきた人ほど、努力すれば報われるという生き方をされる人が多いように思う。 懸命に努力して、その結果を手中にできた人は、次から次へと努力することが可能で簡単に諦めたりしない。 私なんぞは、貧乏な家に生まれ、そうそう能力があるわけではないので、小学生のころからいくつもの諦めを通り過ぎてきた。自分の実力に見合ったような選択しかしてこなかったし、この世にはどうしようもないことばかりというような思いにとらわれることもあった。 だからだろうか、90歳を超えるような方が、努力すれば老いも何とかやり過ごせるというような思いを持っていると聞かされると、90歳までご自分が努力を続けられて克服できると考えていることがすごいことだと感じいってしまう。 自分は幼いころからあきらめの思いを抱えて暮らし続けてきたので、運命というものがあるとしたら、そういうものにも抵抗はしないでしょうがないと思うことで、なんとかやり過ごしてきた。 人生80年時代になっているけれど、地球46億年の歴史を考えると、自分の人生の80年なんてそうたいしたこともないのだと思う。これから働けなくなって、いろいろと体が不自由になって、他の方の援助を受けざるを得なくなった時、そういう自分の在り方を素直に認めて、他者の支援を素直に受け入れて老いて死にゆくことができそうな気がするような、できそうもないような。 多分、自分のことだから大した努力しないうちに、しょうがないと諦めてさっさと次のステージに向かっていくに違いないように思う。 運命を受け入れるとか受け入れないとかという小難しいことではなく、もっと単純で簡単に結論に達するような気がする。 これから、どんどん老いを重ねていくわけだが、自分がどのように老いていけるのか、非常に興味深い。
2016年01月15日
コメント(2)
-
情報の南北問題。
仕事以外はすっかり引きこもり状態になってしまって、BS、CSを中心にテレビ見放題の毎日。 BSでもCSでも、ニュースと言ったら記者クラブ発表のようなものばかりだし、映画にしても米映画ばっかりで、たまに仏や英のものがある程度。映画と言ったらサスペンスもの、殺人などの犯罪事件がらみのものばかり。世界全体が、英米中心で回っているわけでもないのに、どうしてこうも英語を介した情報ばかりなのだろう。 確かにグローバル社会であるわけだから英語を使いこなせることは必要だが、なぜ言語も文化も英語中心の情報しかないのかと不思議に思う。 ドラマに関しては韓国のものが多いのだけど、北欧とか中南米諸国のものとかをなぜ日本で報道しないのだろう。中国やインドの現代映画はきっといいものが多いのだろうけど、ほとんど見かけない。 私も、アジアの言葉や北欧の言葉は全く関心がなかった。ドイツ語をちょこっと位であとはもっぱら英語を学ぶばかりだったのだけれども、英米追随から脱却するなら、英語以外の言語を学びその国と人と仲良しになり互いの立場を学びあうしかないのだと思う。 昔一緒に働いた医師が、糖尿病を専門に臨床と研究を続けている医師なのだが、フィンランドの患者教育や医療の在り方の素晴らしさを知って、12年間フィンランド語を学び現在もなお一年に数回フィンランドを訪問しているのだという。 敗戦から80年代くらいまでは、西洋先進諸国の素晴らしさばかり強調され、西欧に追いつけ追い越せでやってきたのだろうけど、21世紀は英米だけを目指すだけでは足らないのではないか。アメリカの格差社会は日本をはるかにしのぐ酷さだし、ゆりかごから墓場までともてはやされたイギリスの医療もどんどん崩されている。 それでもアメリカのようになりたいと思っている人はどのくらいいるのだろう。 巨大国家の巨大権力で他国にずかずかと土足で入り込むような国はもうお手本ではないのだと思う。 英語を学ぶ意味を否定するつもりはないが、西欧先進国以外の言語を学ぶ人が増えてほしいし、世界の様々な国の情報を得て優れた文化をどんどん紹介してほしいと思う。 自分を自ら様々な国の状況を自ら得るような努力をしていきたいと思う。
2016年01月14日
コメント(2)
-
年末年始は超絶不良、朝起きられないし仕事にも行きたくない毎日だった。
12月の中旬に三日酔いしてから超絶不良。 眠剤を服用しても寝つきが悪く、朝も起きられずBSの「朝が来る」を見てやっと何とか起きだして、嫌だ厭だとつぶやきながら何とか洗面をして始業時刻数分前にやっと職場につくありさま。 11月と12月の初旬はあんなに元気に過ごせたのに、あっという間に不調の日々に変わってしまった。 職場がゴタゴタするのは毎度のことなのだけれども、2枚舌、3枚舌の上司と付き合うのは、「過去と他人は変えられない」と思うのだけれども、結構しんどいし他の同僚がみんな不満に思っていることを知ると、こんな職場で働くのは耐えられないと思えてしまう。 職場は仕事で団結するものだとは、働き始めてから先輩や上司から言われていることなのだけれども、こう長く不調が続くのは久しぶり。 20代のころは自分の力量のなさや患者さんの状況があまりにもひどすぎて、そういうことだけでも結構胸が苦しくなって眠れなかったり気持ちが沈み込んでしまったりしたものだけれど、職場のゴタゴタで気持ちが滅入るのは今までそうない経験。 仕事納めの日に年末年始の休みがはっきりしたりして、他の同僚も腹を立てたまま新年に突入したようだが、私も同じで、目出度くもない正月になってしまった。 間違っていることを正々堂々と間違っていますよと指摘することさえも難しい上司って何だと思う。一から十までいろいろと不満を持たれる上司ってそうないような気もするし、人生初体験の日々。 自分も気分屋さんであるけれど、そうそう人の話を聴かない日々が続くことはないのだけれど、どうしたもんだか。 やっと今朝になって、少し調子が戻ってきてちょっと元気になってきた。 これから上昇気流がやってくるのか、まだまだJカーブになれないで不調が続くのか、元気になれるって自信がないなぁ。
2016年01月11日
コメント(6)
-
やせ我慢はまだ続く。
この冬は暖冬と言われ、確かにまだ早朝の室温が10以下にならない。 長起きてお湯を沸かして緑茶を飲み、湯たんぽの湯を沸かし返していると、その際使っているガスのエネルギーでお部屋の温度が一二度上がる。 正座をしているテーブルの下に湯たんぽを置きひざ掛けをかけておくとポカポカしてくるので暖房は不要。 速乾吸湿の下着+ヒートテック+ウールのシャツ+フリースのジャケットを着ると寒くない。 朝から少し厚着をしていると室温12℃位では手もかじかまないので字を書いたり本を読むこともできる。 体を暑さにさらすと体温調節機能が高まるといわれるが、寒さにさらしていると体温調節機能も高まってくるようで、暖冬のせいもあるのだけれど、今年はマフラーも帽子をかぶらずに過ごせる。 室温が15度あればちょっと熱いくらいにも感じて、フリースは脱いでしまう。 職場は21度くらいで保たれているので、家で過ごす枚数の衣服を着ていると暑いので、やはりフリースは脱ぎ、袖は肘の上までまくって過ごしている。 現在は機能性の高い繊維が開発されていることもあって、衣服を適切に選択できればそうそう暖房を使わなくても過ごせるのではないだろうか。母が作ってくれた半纏なんてもうお古になってしまって活躍の場はなくなったが、新素材繊維をうまく使った衣服を着まわせば、暖房費を削ったとしても生活できそうな気がする。 要するに、自分で作る体温という熱をうまく封じ込めて活用できればいいことだから。 といったことで、我が家はガスストーブをまだ使っていません。 暖冬が一番の原因なのですが、ね。
2016年01月08日
コメント(4)
-
労働と休日の区別ってなかなか複雑。
訪問看護ステーションでは、利用者の24時間対応をするために、自宅待機だけれど休日に緊急連絡用の電話を持つことが月に6日ほどあり、その休日に働いた時間に対する労働時間をどう考えるかがまだはっきりした考えに及ばず。命令する側と命令される側とでも解釈が違っている。 法定休日日に出勤する時間は、予め予定されていた仕事なので通勤時間は労働時間に入らないという上司。休みの日に働かせられていて実質半日以上仕事で費やされるので労働時間とみなすべきでは、という労働者。 通勤時間が短い場合は、10分前後で問題にならないが往復2時間かかる人にとっては法定休日なのに実質休んではいないことになる。 35%増し賃金が支払われているのかということがまず第一の確認事項。 自宅待機中に利用者から呼ばれて訪問した場合は、携帯電話で連絡があった時間を起点として帰宅までの時間が時間外として認められる。法定休日の場合は、どうなるのかということは不明。 自宅から直接利用者宅に行った場合は、その時間も時間外になるが、事務所にいったん出勤して利用者宅に向かったときはどうなるのか。 何を労働するかの判断はなかなかややこしい。 振替休日と代休とは意味が違うとか、時間外労働をしていても「あなたはまだ力がないから時間外は認めない」というのはどうもNGらしいし。 労働と休日をどう考えるか、休憩時間はどう使ってもよい時間なのだが電話に出たり来客対応したりすると休憩時間にならないとも。仕事に関する労働とみなすこととして、制服への更衣、職場の清掃、書類の出し入れなども労働として扱われるという。 何を労働とするのかということ自体、メンバーの中でも解釈がまちまちなのでまずは学習をするしかないと思う。 正しい法的知識を得て、日々の労働を考えられるようになれるのが一番いいのだ。
2016年01月06日
コメント(4)
-
どうして、年続き暮れから年初めに職場のトラブルが起こるのだろう。
仕事納めの日のすき焼き鍋絵パーティが全然盛り上がらなかった。 その原因は、12月の中旬からの日曜日の仕事の待遇についてであった。 たまたま処置で日曜日には訪問看護をしなければいけない患者さんが4,5名となり、日曜出勤ではなく時間外手当で対応することになった。時間外手当の場合は、自宅を出勤してから帰宅するまでが手当の範囲となる。振替休日をつけられないので時間外手当で仕事をしてくれと言われたのに、4時間以上働かせたのに振替休日はつかず、しかも実際どのようなケアをしてどのくらい時間がかかったか確認をしないまま、目の前で2時間しか認められないと宣言したという。 ご自分は、介護休暇をとっているために短縮時間勤務をしていたり、携帯当番をせず休日出勤もしない。訪問をメンバーの4分の一ほどで、ケアに時間がかかる人には一切担当していない。年末年始休暇中も一日も出勤せず。年末年始休暇中でも保険請求のため、今までの上司は二日ほど勤務して休暇明けには他の事業所に請求に関する書類を発送していた。 年末年始休暇が最終的にはっきりしたのは、仕事納めの日だし、田舎に帰ろうにも親戚の家に暮れに連絡をするのはあまりにも失礼だし、ホテルの予約をとることもできないし、結局今年のお正月は故郷に帰るのはあきらめた。 業務になれない職員に対して、仕事が遅いから時間外を認めないと言ったりもしているという。 就職時に、どのような業務がありどのような教育をするといった計画は示されず。労働契約にもそういったことは一切示されていない。パソコンに不慣れな職員に対して、時間内に教えることはできないから自分で勉強してといったという。 こういったいわば業務命令的は発言は、職場の会議でメンバーに提起しているわけではなく、一人一人と個人的に命令しているので、だれがどのような指導を受けたのかは全く他のメンバーは知らないでいる。職場全体で話し合うときにそういった肝心なことは一言も通達せず、一人一人で個別に交渉しているから、同じ労働条件で働くべきところを個別の労働条件になってしまっている。 12月にそういったことが続いたので、仕事納めの日にはみんな不機嫌で同じ鍋をつつく気にもならなかったのだという。 労働基準法とか労働契約とか労使協定とか、そういったことをみんなが学習して賢い労働者になるしかないのだと思う。
2016年01月05日
コメント(4)
-
BSフジ「北限に生きる」を観て。
今年は申年。 申年の年明けにふさわしく「北限に生きる」という青森県脇野沢でのニホンザルの生態をおったドキュメント番組。 日光でも高知県でも長野県でもニホンザルの猿害についてはここ十数年しばしば報道される。広葉樹林を広域に伐採して森林面積が減少するとともに、観光資源として餌付けがされた結果としてサルの生息数が増えて農作物を荒したりすることが増え、 その結果人間に対する被害を減少するために捕獲して殺処分するサルが一年で日本全国で2万頭を超えるという。サルを退治する犬「モンキードッグ」を養成したり、農地を広くして電気策で畑を囲ったり。 ニホンザルの研究は京都大学をはじめ進んでいるはずの日本が、北限のサルとして観光資源にしたこと自体、生態系を無視した無策だとしか思えない。野猿公苑と称して(なんと株式会社)餌付けをすることに、どのような政策的根拠があったのだろうか、と疑問に思えて仕方がない。 動物園で飼育することと、野生の動物に対して餌付けをする違いを全く考えもしなかったのだろうか。 狸やリスにえさを与えたりすることも結果としてその動物が自然の力で生き続ける力を奪うだけのことだと思う。何万年も自然環境の中で生き抜ける力があるのに人間の気まぐれで一時的作為的な「保護」は、結果としてその動物種の生存を脅かすものにつながってしまう。 人口が増えると人間が住む場所を拡大しなければならないために、人間以外の生物種の生存を脅かす。日本でもアジアでもアフリカでも。それぞれの縄張り(国家という枠組み)を守り発展させるために無くならない戦争。 文明も文化も人間の欲望と、それを支える知恵と知識(科学の進歩)の集積で成り立ったものに違いないが、誰もが必要以上の富を得ようとするとしたら地球資源の枯渇は目に見えている。かといってどこで線引きするかという問題は非常に微妙で困難だとも思う。 「北限の生きる」は、ニホンザルの生態を24年間も追跡した報道で、サルの社会の階層性とか人間により生存を脅かされる実態とか非常に考えさせられた。 今日が仕事始めで、何やら波乱含みの年明けになってしまったが、自分の本分とはなにか、もう一度じっくり考えてみたいと思った正月二日であった。
2016年01月02日
コメント(15)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 新型コロナウイルス
- まさかのコロナ感染2回目!バトンツ…
- (2025-11-20 21:00:50)
-
-
-

- 喘息・橋本病・胃潰瘍・筋緊張型頭痛…
- 治らないと諦めていた症状が完治した…
- (2025-05-21 00:28:42)
-
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/26(水)・「1・0増」(´;…
- (2025-11-26 12:00:01)
-