全1967件 (1967件中 1-50件目)
-

〝はやいうちに縫合”が大事
エミューの皮膚がめくれた部分。ずいぶんと大胆にバカっと皮膚がめくれ、皮下組織が露出しています。ポタポタと血も垂れているため、止血処置して、すぐに縫合しました。皮下組織をあわせ、口内に傷が到達していないか確認します。皮膚をよせて、くっつけます。何事もなければ、2週間程で抜糸できればOKです。エミューをはじめ、鳥さんたちは、とても薄い皮膚をしています。何かの衝撃でバサッと皮膚が裂けめくれることがあり得ます。それが体幹だと自分のくちばしでいじって、傷口の状態をよりを悪化させることもあります。中でもエミューのような大型鳥類は、動きがとても力強く、激しいため、裂傷がたまにあります。これは、エミューあるあるかもしれません。皮膚が裂けたとき、それは、人間も動物たちも同じで、できるだけ早いうちに、できるだけキレイな状態で、縫合してあげるほうが傷の治りがはやいです。時間が経ってカピカピに乾いてしまった皮膚や雑菌に汚染された皮下組織の状態では、その後の治りが悪いです。皮膚がめくれたら、早めに縫合。これ大事です。
2025年10月04日
-

~できるだけストレスなく~
お泊りのわんちゃんをご紹介します。15歳の老犬ワンコです。以前は、ガウガウ犬で触ることもなかなか難しいわんちゃんでしたが、歳をとって、ゆったりとした性格になり、おっとり、のんびりくつろぐことが目立つ生活スタイルになりました。飼い主さんも預けられるかな~どうかな~と心配されていましたが、のんびりなりにも体調に問題なく、ワンコ自身のペースを保ってあげさえすれば問題なく、お留守番生活ができるでしょうと判断しました。こうした老犬たちは、一日のほとんどを寝てすごします。でも、かといって、ずっと寝たっきりだと関節がかたまり、動けなくなります。適度に起きたり、歩いたりして、体を動かすことが大事です。そして、ときどき、ゆっくりとお散歩に行き、おひさまに当たることも大切です。この老犬ワンコもどのような感じで過ごさせてあげようか思案した結果、お部屋の犬舎には入れずに、ある程度、自由に動き回れる環境で過ごさせてあげることにしました。日中は、窓越しに太陽の光があたるところで、夜は、待合室の広いところにタオルケットを敷いて、寝たり歩いたり、起きたり食べたり、老犬ワンコのペースで過ごせるようにしました。そうしたところ、日中は、自分の気に入った場所でスヤスヤ居眠りしたり、顔をあげて、周りを観察したり、マイペースな時間を過ごしています。中でも、ごはんタイムになるとその気配を察知してか、、、むくっと起きだし、お母さんの用意してくれた手作りごはんを楽しんでいる感じがとても印象的です。持ち込みごはんは、ドライフードと冷凍した手作りごはん。そして、おやつのパン。手作りごはんは、丁寧に一食分ずつに分けて冷凍したものをご持参いただきました。毎食、こちらで解凍して混ぜて、愛情たっぷりのごはんが完成です。老犬ワンコも食べなれたいつもの味を楽しんでいる様子です。お外でしか排泄しない子なので、一日、何度かお散歩にでかけます。地面の匂い、草花の匂いを嗅ぎまわるのが好きで、ゆっくりとした歩調で、五感を働かせながら進む老犬ワンコです。お預かり中、何度もニコニコ笑ってくれる老犬ワンコ。できるだけストレスなく過ごせることを意識してお預かりしています。がんばれ、老犬ワンコ。そして、これからもお母さん、お父さんたちとハッピーに過ごしてね。
2025年09月27日
-

お馬のシャンプー
今日は、お馬さんをシャンプーしました。声をかけたら、次男が喜んで手伝ってくれました。マッサージしながら背中、お腹、お尻、足を洗い、シャワーでながし、ブラシをかけて水を切り、タオルで吸水し、ブラシを目の細かいものにかえて最後にまた毛並みを整えて、しゅーりょう~。手伝ってくれた次男。ほとんどを「オレがやる、オレがやる。」と言って、進んでこなしてくれました。次男のそのまなざし。それはそれは、真剣そのもの。自分の手元に 一点集中。その手つき、腰の落とし方。真剣です。丁寧に、一心不乱に取り組む様子は気持ちがこもっていてすばらしい。お馬さんもまだ子供。次男もまだ子供。お互い、通ずるものがあったのでしょうか。お馬さん、キレイになって、すっきりしたね。ずっと暑い日が続いてたからさっぱりしたね。ぱっちりおめめでいい顔しています。
2025年09月17日
-

爪切り VS 柴ワンコ
おばあちゃんとふたり暮らしの柴ワンコ。「爪を切って欲しい」との依頼をいただいたので、さっそくご自宅に伺いました。玄関先で、おばあちゃんといっしょに柴ワンコの爪切りを試みるも、、、さすがは柴犬、嫌がって逃げ回ります。おばあちゃんもそれを制止しようとしますが、なかなか言うことを聞いてくれません。そりゃそうですね。おとなしく爪を切らせてくれるワンコのほうが少数派です。ってことで、一旦、病院に連れて帰ることにしました。後部座席に柴ワンコ。そのとなりに手伝いに付き添ってきてくれた次男。ふたり仲良く座ってます。「落ちないように見ててあげてね。」病院にとうちゃーく。診察台の上に。ついでに体重測定。少し体重減ったかな。さて、ひととおりチェックして、いざ、本題の爪切りに。意外とすんなり、切れました。ちょいちょい足を引っ込めて嫌そうにはしましたが、3分ほどで すべて切れました。診察台の上。診察台の上ではおとなしく切らしてくれる。診察台の上。そこは、ワンコにとっては、緊張の場所。診察台の上。そこは、抵抗できない場所。診察台の上。そこは、ワンコたちにとっては、独特の場所で、どうしても、体がフリーズしちゃう場所でもあります。言い換えれば、緊張のあまり、おとなしくなってしまう場所でもあります。その逆で、緊張のあまり、暴れてしまったり、咬みついてきたりするケースもありますが、この柴ワンコの場合は、体フリーズのタイプ。上手に切らせてくれて、喜んで車に乗って帰りました。自宅に送り届けると玄関先では、おばあちゃんが柴ワンコの帰りを待っていてくれました。おばあちゃんのうれしそうな顔に迎えられて、老齢の柴ワンコもまたうれしそうにしていました。柴ワンコとおばあちゃん、正味1時間程の別れ。1時間、お互いに離れているだけでも、なんとなく心がざわざわするのでしょう。1時間ぶりに再会するときは、それはそれはうれしそうにしていました。そんな空気に触れることができて、それはそれでこちらも幸せでした。「おりこうだったね、柴ワンコ」「バイバイ、またね。」
2025年09月11日
-

老犬ワンコ、退院しました。
先日ご紹介しました柴ワンコ、元気になって退院しました。下を向いたうつむき加減の沈鬱な表情とはぜんぜん違って、時折、元気に笑ってくれるようになりました。ご老体なので、これからも要注意ではありますが、自分の足で立って、自分で歩いて、楽しくお散歩に行って、匂いチェックできて、うんちおしっこもいつものようにできて、ごはんが食べたいという意欲が湧いて、自分の口からごはんが食べれて、それが一番いいことです。うれしそうな笑顔も確認できました。これからも老犬生活をエンジョイしながらがんばって生きましょう。今しかない時間を大切にしながら、ひとつひとつの問題を解決していきましょう。一番は、柴わんこの心と体です。「うれしい」、「楽しい」をひとつでも多く増やして、細胞のひとつひとつが喜べるような生活ができたら最高ですね。心から健康でいられることを願います。ごはんをしっかり食べて、足腰健康に過ごして欲しいと思います。柴わんこの頑張りに拍手。長い入院生活、よくがんばったね。
2025年08月31日
-

「長男」と「ラマ」
ならんでいるふたりは、「長男」と「ラマ」です。こうして見ると・・・うん、うん。なかなかの様になってます。格好良く、似合ってます。こうしてみるとラマと長男、同じ背丈です。目の高さ、鼻の高さ、同じです。怖がらずにリードをひくさまは、小学生にしては、堂々と誘導してて、立派です。長男もですが、よくよく考えれば、ラマも立派です。大型動物が人間を信頼している様もまた感動します。どんな生き物もそうですが、大型動物が本気を出せば、人間なんて、いちころです。大型動物のひと蹴りで、吹っ飛ばされます。ひと咬みで、血みどろにされます。ひと頭突きで、骨折です。本気をだして人間に向かってきたら、そのパワーの差は歴然。でも、それを分かっていながらもちゃんと人間に心を寄せる姿はほのぼのしてていいものです。
2025年08月29日
-

「先生、うちの子、突然歩けなくなりました。」
入院中の柴ワンコをご紹介します。15歳の柴犬くんです。ある日突然、急に歩けなくなって、ごはんも食べなくなったのが来院されたはじまりです。よく見ると眼が揺れていて、頭が傾いていて、体全体がフラフラしています。ごはんにも全く興味関心を示さない様子なので、入院となり、すぐに治療を開始しました。写真からもわかるように来院から数日間は、表情なく、反応もなく、うつむきかげんで沈鬱な様子でした。しかし、治療を進めていくうちに今ではだんだんとワンコらしい表情が見えてくるようになりました。食べられなかったごはんは、シリンジを使って食べさせてあげながらだんだんと食器から直接食べる練習を続けています。立つ練習をしながら、もう一歩、自力で歩く練習をしています。できれば、お散歩中にウンチ・おしっこをしてほしい。寝ながら垂れ流しではなく、自分の意志で排泄してほしい。自力で立って、したい場所で排泄するか、オムツの中で排泄するか、寝たまま垂れ流しで排泄するか、、、この3つは、大きな違いです。介護する側もされる側もできるだけ自分の足で立って自分で排泄したいものです。できるだけ自分の口と舌を使ってごはんをすくい食べたいものです。できるだけ補助なしで自分の足で立って前に進んでほしいものです。少し前の普通の暮らしにもどれるように柴ワンコ、リハビリ中です。最後に、カメラ目線で「がんばるよ」と柴ワンコの表情が伝えてくれました。それまで、一切、カメラに対しての認識がありませんでしたが、偶然かどうか、、、ちょうどこちらのカメラの方をチラッと見てくれました。あともう少し、あともうすこし。リハビリがんばっていい表情でお家に帰ろうね。柴ワンコ、がんばり中です。
2025年08月20日
-

泡・あわ・アワ
泡・あわ・アワ誰かわからなくなるくらいの大量の泡。兄弟同士、泡を器用に使って遊び合いっ子。ふわふわで気持ちよさそう。末っ子は、泡を使っておままごと。しゃぼん玉プールに行き、全身泡だらけになってはしゃぐ子供たち。ふつうのプールとはまたひと味もふた味も違った楽しみ方がありました。辺り一面、泡・あわ・アワ。フワフワしてて、雪が舞うように、細かいしゃぼん玉が降り注いでいました。もの珍しさから子供たちのテンションもマックスです。ついでにこの日限りの手作りスライダーを楽しんだり。浮輪の上に乗って滑ることでより加速がつくようです。着地点でスピードに乗ったままダイブ!夏休みの思い出。いい思い出になったかな?
2025年08月17日
-

お盆中のホテル犬
お盆期間も終わりに近づいてきました。飼い主さんのお迎えを待ちわびたわんこたちがいろんな表情で過ごしています。このチワワっ子たちもそんなわんずのひとりです。空き時間に変身写真を撮って遊んでみました。かわいいですね。その気になってまんざらでもなくポージングしている様がこれまたかわいい。お写真は印刷してプレゼント。みんなおりこうさんにお留守番できたね♪
2025年08月16日
-

~天然の笑顔~
子供たちを 川に連れて行きました。 山の中。 周囲を取り囲む木々のおかげで 暑い日差しがさえぎられ、 流れる川の冷気で冷やされたそよ風が 木々の間を通って流れ込み、 天然の扇風機のようで気持ちよく、特別な空間がうまれていました。 川の流れにまかせて〝プーカプーカ” 浮いて流れたり、 岩場の上から ”ザブーン”と飛び込んでみたり、 〝よーいドン”で 水の抵抗に負けずとかけっこしたり。兄弟姉妹で協力して 新しい川遊びを考案しながら 子供たちの子供たちなりの遊びを楽しんでいるように見えました。自然と顔の筋肉がくだけて、 自然と笑顔がこぼれていました。これぞ天然の笑顔です。 自然には、 自然と人を笑顔にさせる魔法があると 思います。
2025年08月02日
-

手作りごはん持参のホテル
コーギーわんこがお泊りにきました。お泊り中の食事はできるだけいつもの食餌内容と同じものを、とお伝えしています。ドッグフードのみの子もいれば、パウチの子もいれば、手作りごはんの子もいれば、蒸した野菜をトッピングの子もいれば、かつおぶしやささみふりかけをトッピングの子もいれば、パン食の子もいれば、おやつメインの子もいれば、おまかせコースの子もいれば、日替わり、気分次第メニューの子もいます。いろいろです。人の食生活がいろいろであるのと同じようにわんこの食事内容、食事パターンもいろいろです。その内容が良い悪いは置いといて、このやり方が100%正解!というのはないように思います。その子その子にあったものを、、、が大事です。さて、このお泊りコーギーわんこのケースでは、飼い主さんは、ドライフードと手作りごはん(トッピングに)と白ごはんとパンのおやつを持参されました。1日2回のごはんタイムにあわせて、いつもと同じようにお皿に盛りつけます。とっても美味しそうに食べてくれました。特に、手作りのトッピングごはんを見つめる瞳はとてもキラキラ輝いていて、ニコニコ喜んでいるように見えます。お泊り中、飼い主さんと離れる不安は少なからずどのわんこにもあるはずです。そのストレスをできるだけ少なくするためにどんなものも持ち込み自由にしています。お気に入りのぬいぐるみ、使い慣れたタオル、好きなおやつ、いつも使う食器、冷凍した手作りごはん、匂いのついた毛布など、持参される方は考えていろいろ持ってみえます。素泊まりでなんにも必要ない、どこでも寝れるおおらかな子と寂しさや不安から体調を崩してしまう子までわんちゃんのタイプはいろいろだと思います。いつもと同じものを食べられる喜びを大事に。飼い主さんの愛情がたっぷり込められたごはん。留守中、そんな大好きなごはんを食べてコーギーわんこは元気に過ごしています。そのうれしい笑顔を大事に過ごさせてあげたいです。
2025年07月31日
-

スギナの水滴
早朝、足元にこんなキレイな光景を見つけました。スギナの先っちょに水滴がいっぱいついていてとても美しかったので思わず、写真におさめました。足元のスギナ、どのスギナを見ても先端にいっぱいの水滴をつけています。水滴がキラキラしてキレイです。朝日と重なってイルミネーションのようにピカピカ輝いているようにも見えます。この現象、朝露がついているのではなく、スギナが自分で放出した水分だそうです。夜の間に吸収した水分のうち余分な水分を葉の先端の水孔という小さい穴から排出している現象でこのようにいくつもの水滴が見えるそうです。逆を言えば、これだけの大量の水分を夜の間に吸収しているのですね。まるで、一本一本のスギナが各々、小さなシャボン玉を吹かせているようですね。とてもキレイな写真が撮れました。目線をずらすと、おっきなアリが枯れ葉の上にいました。これまた、存在感のあるアリさんです。お尻に毛が生えていて、触角がながーーーくて。。。スギナの水滴。案外、近くでも見られるはずです。もし見つけた際は、よーく観察してみてくださいね。キラキラ、ピカピカ、キレイです。
2025年07月30日
-

小さな命のハムちゃん
ハムちゃんがやってきました。 体、、、、というより、 全身、体中がカイカイのハムちゃんです。かわいそうに・・・ ゴロンと裏返ったときの お腹の皮膚、 真っ赤かです。あと、耳の入口がボコボコで 耳介周囲もかゆそうです。診察中、 常に体をかきつづけてました。 心休まる暇もないほど 常にカイカイ。 かゆみのせいで、 寝れてなさそう・・・なくらい。 とにかく、 常にかいてる。 ハムちゃん、 じっと落ち着ける余裕がないので 皮膚の状態を写真に撮ろうとしても ピンボケばかりです。表情もどこか しんどそうで、いつも背中を丸くしてうつむき加減です。沈んだ暗い表情で、目に輝きがない感じ。触るにも暴れてじっとしてません。触れようとしても必死の抵抗でバタバタと嫌がります。そして、とにかく痒くてイライラしています。さてさて、どうしましょうか。。。わんこやにゃんこと違い、35gほどの小さい動物にできることは、限られています。とても小さい命です。あまり過度のストレスはかけたくありません。その分、慎重に大事になります。このハムちゃんのケースでは、内服薬と外用薬を処方し、経過を観察することにしました。人間でもかゆみって、ものすごいストレスですよね。蚊にさされただけでもすっごいかゆい。そのときのかゆみのストレスって・・・それが もし全身だったら・・・想像しただけで、つらいです。小さな命、少しでも良くなってストレスが減って、気持ちも明るくなって欲しいです。
2025年07月23日
-

もういっちょ、マダニ
もういっちょ、前回に引き続き、マダニの症例です。写真のチワワっ子。左耳の前側に”プチッ”っとした 黒い粒、見えますでしょうか?これ、マダニです。一見、ホクロかゴミのように見えますが、よく見るとマダニだと分かります。マダニの頭部は、しっかりとチワワっ子の皮膚の中にガブリと食い込み入っているので、頭を振ったり、ちょっと掻いただけではそう簡単に取れない構造になっています。でも、前回もお伝えしたように、マダニの唾液には麻酔物質が含まれているため、咬まれたチワワっ子は痛みを感じず、それどころかほとんど気づかない感じです。これは、人のケースも同じです。蚊やノミに刺されたらあんなにもかゆみを感じるのに。マダニに咬まれても気づかないとは・・・生き残るために構築されたすごい能力です。マダニ。言葉では聞くけど、実際に見たことのある方は少ないはず。。。でも、まあまあ、そのへんの草むらに生息している生き物です。写真のケースのようにあなたの体、あなたのペットに、黒い粒がポチッとあったら・・・一度はマダニを疑ってみましょう。
2025年07月20日
-

~この黒い物体、なぁに?~
ペットの体に付着した丸い黒い物体、なぁに?動かないし、ペットが体をブルブルしても取れる様子なし。「はじめは イボかなと思って、気にしませんでした。」「デキモノかなと思って、様子みてました。」「なんだか昨日より大きくなってる気がして・・・」だいたいの飼い主さんはこうおっしゃいます。この黒い丸い物体の正体は、マダニです。最近は、ちょいちょいニュースにもなっているあのマダニです。写真は、ペットの体に頭を突っ込んで血を吸っているところです。なので、はじめの小さいうちはペットの被毛の中にうもれてマダニがどこにいるかは見つけにくいですが、血を吸って大きくなればなるほど、目立つようになります。アップ写真をよく見るとマダニの足が確認できるはずです。マダニは、草むらにいます。田畑やあぜ道、公園、河川敷、裏庭などに生息しています。動物の血液をエサとしているため近づいてきた動物に寄生して吸血します。犬猫はもちろん、野生動物や人にも寄生します。マダニの唾液には麻酔物質が含まれているため、マダニに咬まれてもほとんど気づきません。なので、マダニは咬みついたまま数日間、血を吸い続け、まん丸に大きくなります。この状態が写真のような状態です。最近ニュースになっているのは、このマダニから感染した病気についてです。SFTSウイルスをもったマダニに咬まれることで感染する病気についてです。SFTSは、「重症熱性血小板減少症候群」といって、SFTSウイルスによる感染症です。わんこやにゃんこだけでなく、人もかかる感染症です。重症化すると死亡することもあります。熱がでたり、元気がなくなったり、食欲がなくなったり、下痢や嘔吐がおきたりもします。こうした感染症を防ぐには、第一に、飼っているペットたちのマダニ対策を行うことです。マダニ対策としては、まずは定期的な予防薬をおすすめします。薬の種類によって、投与頻度は異なりますが、月1回から数か月に1回、継続して薬を飲ませてあげましょう。口からの投薬が難しいペットには背中に垂らすタイプもありますので、それぞれのペットにあったお薬を選びましょう。マダニ。まずは、対策が大事です。できる対策を行って、人もペットも命を守りましょう。
2025年07月19日
-

~転んでも、転んでも~
飼い主さんが入院されているためその間、当院でお預かりしてお世話をしている老犬ワンコ。高齢のワイマラナーくんです。老犬なりに手をかけてあげる必要があるため、私がしていることの見よう見まねで子供たちもお世話を手伝ってくれています。一番下の末っ子も体はまだ小さいものの、ワンコをつないだリードをしっかりと手に持ってお散歩を手伝います。ワンコか4歳児かどちらが散歩させられているのか、似たような背丈( ^)o(^ )ですが、とりあえず、4歳児の方は、道で転んでも、絶対にリードをはなすものかと”ギュッ”とリードを手に持って、ワンコをコントロールしています。たくましいものです。15歳のワイマラナーくん。高齢のため、足どりも時折おぼつかないヨタヨタですが、がんばって歩いています。排泄は、寝床でもどこでも所かまわずしちゃうのでそれなりに手はかかりますが、まだまだ元気でいて欲しい。元気でいることで飼い主さんにも元気を分けてあげて欲しい。「お散歩いきたーい」と催促もします。「ごはんたべたーい」と要求します。『〇〇したい』と自己主張できるのは大事なことです。動物たちは、人の助けがないと生きていけません。歳をとるとなおさらです。足腰立たず、おしっこが垂れ流しになったり、軟便になったり寝たきりで床ずれができたり、流動食の準備が必要になったり、ボケちゃったり、、、まあ、いろいろと手はかかります。動物たちは、人の助けがないと生きていけません。高齢で寝たきりになるとなおさらです。でも、そうなるまでの十数年間は、むしろ人間が動物にいっぱい助けられてきた側だと思います。その動物がそれまでの間に与えてくれた癒しやパワー、エネルギー、知識、学び、笑い、喜びは果てしないものです。そのときは、いっしょにいることが当たり前すぎてなかなか気づかなかったかもしれないけど、動物たちから受け取った恩恵の積み重ねは果てしないものです。だからこそ、老後ぐらいは、「ありがとう」の気持ちでいっぱい手をかけてあげて欲しいものです。いっぱいとたくさんの人の愛情をおすそ分けしてあげて欲しいものです。末っ子は、お散歩に行って疲れたのか、その後、恐竜のフィギュアを抱っこしながら眠ってしまいました。「リードをはなすまい!」と一生懸命、気を使い、神経をすり減らしたのでしょうね。転んでも、転んでも、リードを持ち続ける4歳児。将来がたのもしいです。
2025年07月06日
-

「先生、うちの子、毛が生えてきました。」
皮膚病で脱毛が目立ちかゆみに悩まされていたモルモットちゃん。1ヶ月ほどの間、お風呂に通っていただき、すっかり良くなりました。一カ月前とは違い、一気にモフモフ毛が生えてきてフサフサになりました。以前は、痛々しくも炎症をおこした地肌が見えていましたが、新しい毛が生えて体全体が毛で覆われるようになりました。ハゲが目立っていたお尻も毛並みが美しい光沢ある毛で覆われモルモットらしくなりました。<Befor> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓<After>上手にお風呂に入れたね。上手にシャンプーできたね。上手に通えたね。おりこうモルモットちゃんのお話でした。よかったね。バイバイまたね。
2025年07月06日
-

みゅーちゃんから学ぶこと
院内のミューちゃんが卵を産みました。初産卵です。人間よりも大きな鳥。その正体は、エミューです。でっかい鳥を見つけてみなさんびっくりされますが、あれは、ダチョウですか?クジャクですか?あれ、なんですか?と聞かれること多々ですが、答えは、エミューです。ダチョウというとみなさん、パッとイメージが湧きやすいようですが、エミューは、世界で2番目に大きい鳥。そのため、世界で一番大きい鳥である有名どころのダチョウの裏に隠れた存在で、微妙な地位に位置する動物ですが、実は、実は、その生態は、最も恐竜に近い動物といわれるくらいたくましく、たくさんの不思議と謎につつまれた生き物です。みゅーちゃんももともとは院内で、卵が孵化してこの世に誕生しました。そのみゅーちゃんがおとなになり、3歳にしてはじめて卵を産みました。エミューのオスメスの区別は見た目では判断できません。おとなになってからの独特の鳴き声や産卵の有無からオスメスが分かります。もともと鳴き声からうちのみゅーちゃんは、メスだろうと予想ついていましたが、卵を産んだことでメスであることが決定付けられました。みゅーちゃんは、おんなのこ。ちなみに、エミューの卵とダチョウの卵を並べて比べてみました。緑色がエミューの卵。白色がダチョウの卵。こうして並べて比べてみるとダチョウのほうがもっともっと大きいことが分かります。卵が大きいということは生体も大きくなります。みゅーちゃんでも鳥でありながら、とても大きい体をしているなと感じますが、ダチョウは、これ以上にもっともっと大きい動物であることが分かります。エミューの卵は、ニワトリの卵の10個分、ダチョウの卵は、ニワトリの卵の30個分に相当します。それが分かるとダチョウって、はるかに大きい動物なんですね。
2025年06月24日
-

モルモット、はじめてのお風呂♪
今日は、皮膚病のモルちゃんがお風呂に入りにやってきました。なかなかの可愛さです。飼い主さんにお話をうかがってみるともう半年以上前からこの状態とのこと。皮膚がかさつき、毛が抜け、フケがでて、ここ最近は、痒さのあまり、口で皮膚をかじり、かきこわして出血し、汁もでてくるらしく。あれよあれよという間に体の後ろ半分の毛はだいぶ抜け落ちていてスカスカの状態になったとのことです。毎日みているとその経過、その以上に気づきにくいですが、パッと見、その第一印象はモルちゃんの腰からお尻部分にかけての毛の薄さと全体的な皮膚のガサガサゴワゴワさでした。モルモットだと本来なら波打つ毛がフサフサ生えてモサモサに体全身を覆っているはずですが。お薬を飲ませるのもモルモットという特徴を考えるとなかなか難しそうです。そこで、入浴治療を試してみることになりました。モルちゃん、上手にシャンプーできて、入浴もできました。途中、不安からキューキュー鳴くこともありましたが、なだめながら進め、おだやかに行うことができました。とってもお利口さんに治療をうけてくれました。モルちゃん、ごくろうさま( ^)o(^ )えらかったね。また今度、会おうね。フサフサの毛が生えてきますように・・・がんばろ。
2025年06月05日
-

相思相愛(15歳のワイマラナー)
これまた、先日、一本の電話がありました。「15歳のワイマラナー、しばらくあずかってくれる?」ワイマラナーのような超大型犬で15歳といったらけっこうな高齢犬です。なかなかのご長寿犬。よくよくお話をうかがってみると飼い主さんが入院されるとのことで、面倒をみる人がいないとのこと。急なことで飼い主さんも困った様子。ってことで、おじいちゃんワイマラナー、しばらく当院でお泊りすることになりました。誰にでもこういうケースはありえる話です。皆が健康であることが一番の望みですが、どうしようもないことだって、誰しもあることです。飼い主さんの身からすれば、自身の体も大事でしょうが、こういうときってそれ以上にペットのことを心配してしまうものです。入院中、病床に横になりながらも、大事なペットのことが気になってしまうものです。大切なことは、飼い主さんが一日も早く、元気になること。飼い主さんが がんばれば、ワンコもがんばり、ワンコが がんばれば、飼い主さんもがんばれるはず。飼い主さんが喜べば、ワンコも喜び、ワンコが喜べば、飼い主さんも喜べるはず。飼い主さんが安心して過ごせれば、ワンコも安心でき、ワンコが安心して過ごせれば、飼い主さんも安心できるはず。相思相愛ですね。お互い離れ離れになって寂しいこと間違いなしでしょうが、どこか、いつも心の中でつながっていることをパワーにして、ワンコも飼い主さんも安心して過ごしてほしいものです。15歳なので、歳相応にときおりフラフラとおぼつかない足取りでお散歩に出かけています。それでも、一日3回、4回、お散歩に出たがるので、元気なものです。飼い主さんと再会できる日を心待ちにしているのは誰よりもワンコが一番強い気持ちでいます。笑顔で会える日を楽しみに今しばらく、もうしばらく、がんばろうね。
2025年05月31日
-
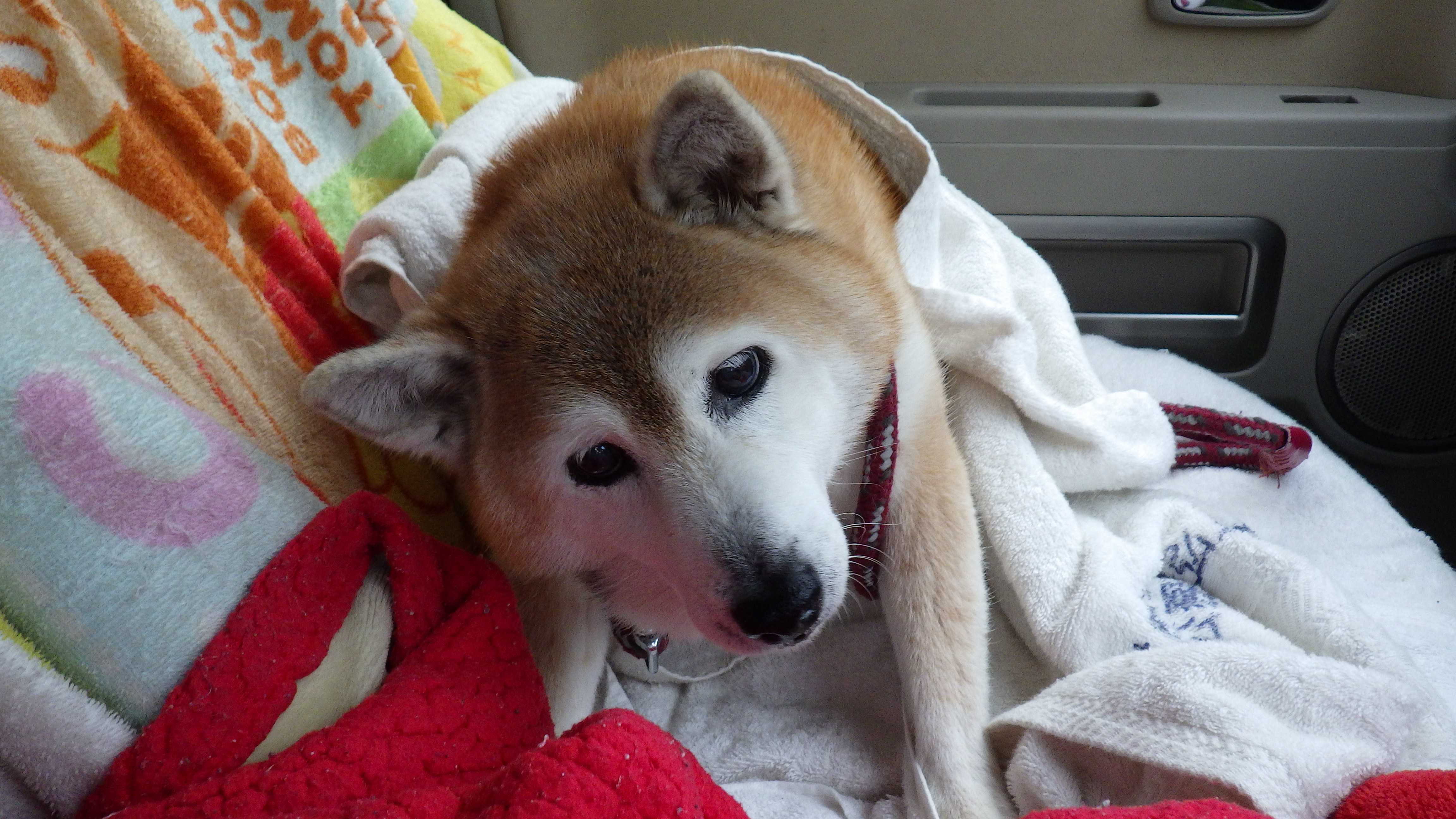
「先生、うちの子、突然、頭が傾きだしました。」
10日ほど前、こんな電話がありました。「先生、うちの子が突然おかしいんです。」「急に、ぐるんぐるん回転しだして・・・」「頭はかたむいてるし、ごはん食べないし、大好きなおやつも食べないし・・・」あわてた様子で電話がかかってきました。病院に連れて来るのもなかなか難しそうなので、往診に行くことにしました。お家へ伺ってみると、部屋の隅っこのほうにうずくまった柴ワンコがいました。確かに、、、パッと見た瞬間に感じました。とても立てる様子ではない・・・頭をかしゃげて、体も斜めに傾かせて、フラフラとよたついていました。パニックになっているのか、興奮しているのか、息づかい荒く、視点も定まらない様子でした。わんちゃんの飼い主さんはお歳を召されたおばあちゃん。とてもおばあちゃんひとりではこんな状態のワンコの面倒が見れない・・・と困った様子でご相談いただきました。ってことで、そのままワンコをタオルでそっと包んで車の助手席に乗せ、ゆっくりと病院まで連れて帰ってきました。助手席に乗って。しばし、病院で治療を行いながら面倒をみていきます。こういうケース、全体的に柴ワンコに多いです。印象としては、長生きした日本犬に断然多いです。しかも、ある日突然・・・っていうケースが。ごはんが目の前に置かれていても、認識できていませんでした。一見、座っているように見えますが、頭が右に傾き、そのうち 体も右に傾き、そのまま右側にゴロンと転げていきます。点滴と注射の治療を続けながら、しばらくは 院内で預かり生活。日々、上手に治療を受けてくれています。それから10日経った今。柴ワンコは、着実に、回復に向かってがんばっています。頭の傾きが徐々に戻りはじめ、一歩、二歩、歩けるようになり、嗅覚も戻ってきました。がんばろうね、柴ワンコ。早く元気になって、おばあちゃんを喜ばせてあげよ。おばあちゃん、お家で待ってるよ。老犬になるといろいろとあるもんですね。
2025年05月27日
-

ワラビー VS うさぎ
はじめまして。こんにちは。うさぎさんのもとに来客がやってきました。お互いの鼻をつきあわせ、くんくんごあいさつ。来客者のワラビー。うさぎが敵ではないと理解して、うれしそうに 跳びはねてみせます。うさぎさんの周りを跳びはねながらぐるぐる回ります。ぴょん、ぴょん、ぴょん。うさぎとはまた違ったジャンプの仕方で。跳躍力がすばらしいです。どちらも同じ草食動物。主食は、牧草。だからなのか、特にケンカするでもなく、攻撃するでもなく、お互いの受け入れた様子。ともだちになれたかな。異種の動物がはじめて出会い、互いを受け入れるというのは、見ていてとても微笑ましいことですね。よかったね、ワラちゃん。よしよし。
2025年05月24日
-

~ウサギさんにも希望の光を~
黒うさぎちゃん、腰が悪いので、先日、車イスを造ってあげました。本人(ウサギ)も車イスに乗っていたほうが快適なようで、楽しそうに、また、のんびりと時間を過ごしています。車イスに乗ったままごはんを食べたり、水を飲んだり、日常を過ごすことにだいぶ慣れてきました。排泄物もちょうど両後肢の間に落ちるので被毛が汚れるのを回避できます。ウサギさんを飼われている方は少なくないですが、実は、腰部や後肢の不自由なウサギさんが意外と多いです。後躯麻痺あるいは、不全麻痺で過ごしている子も多いです。だいたいは寝たきりや、足を引きずっての生活を選択せざるを得ないことも多く、どうしようもなくなって看護・介護生活に尽力されている飼い主さんも多いでしょう。でも、あきらめることなかれ。と思います。寝たきりじゃない選択肢もあります。歳か、病気か、事故か、さまざまな要因で、後肢に障がいがあるウサギちゃんたち。こんなふうにしたら、生活が少し明るくなるよ、楽しくなるよ、というのをお伝え出来たらと思います。車イスに乗って日常生活を過ごしたり、お散歩にいったり外の空気を吸わせてあげたり。歳をとって、病気になって、体が不自由になって、「かわいそうだね。」という目で見られるよりも車イスに乗って、「かわいいね。」という目で見つめられたほうが本人(ウサギ)もうれしいと思います。体が思うように動かないから「かわいそう」なんじゃなくて、体が不自由でもこんなにも前向きにがんばって生きているんだよ、というところを褒めてあげて欲しいです。ワンちゃんも、ネコちゃんも、ウサギさんも、モルモットちゃんも、もしかして、ヤギさんやブタさんたちも後肢が不自由になってあきらめるのではなく、車イスという選択肢があることをお伝えできたらうれしいです。どんな動物にも希望の光を。動物たちは、基本、ポジティブで、明るいです。車イスに乗って、うれしそうにしているウサギさんを見て、こちらまで心がうれしくなりました。動物たちの介護、看護、なかなか大変なこともあるでしょうが、その時間って、一生のうちのごくわずかしかないから、より大切に、より濃く、より笑顔で過ごしてほしいです。
2025年05月22日
-

肛門嚢ハレツ
猫ちゃんのおしり。尻尾を上に持ち上げると、肛門横の皮膚が裂けて、その下の真っ赤な筋肉が露出しているのが分かるでしょうか?これが、ペットを飼っているみなさんなら一度は耳にしたことがあるかもしれない・・・「肛門嚢破裂(こうもんのうはれつ))」です。ワンコもニャンコも肛門の横に「肛門嚢」という袋があります。左右1対の2つ袋があります。今回の猫ちゃんのケースでは、そのうち右側の肛門嚢が破裂したケースです。ご覧いただいてわかるように痛々しいです。ネコちゃんは、気にしてしきりに患部を舐めまわしますが、舐める行為がさらに傷口を広げることになり、皮膚がズルむけて、筋肉がむき出しになり、出血も増し、余計に細菌感染が広がって、悪化します。この症例でも舐めたことによって、患部が広がったように思います。ネコちゃんの舌はザラザラとした特有の構造をしているため、舐めることで、余計に傷口が広がるようになっています。ここまで患部が広がると縫合するしかないです。ある程度、傷口が小さければ、その必要はなく、乾いて瘡蓋ができるのを期待しますが、ここまで大きいとそれも難しいです。手術糸で縫うのか、金属で縫合するのかは、そのときの状況次第です。傷の状態以外にネコちゃんの性格とか、気質、年齢も含めて。患部にバイ菌がたくさん入り込んでいるので、患部をよく洗って縫合し、抗生剤と痛み止めを投与します。3日、1週間、10日、2週間と経過を見ていくとだんだんと患部の状態は良くなってきます。ただし、その間、患部を舐めないように気を付けることもとっても重要です。腫れと赤みと痛みが落ち着き、皮膚の状態が良くなったところで抜糸をします。抜糸をしてから2~3日、問題ないかを確認したら治療は終了です。今回のネコちゃんは、イヤイヤ言いながらも飼い主さんの保定とよしよしで、嫌な治療も我慢してくれたので経過がスムーズでした。お家での治療管理も適切でした。飼い主さんのご協力があってこそだと思います。ありがとうございました。でも、そもそも、なぜ、どうして、肛門嚢がハレツするのかは、またの機会にお話しします。ネコちゃん、がんばったね。バイバイ、またね。このネコちゃん、ちょっとしたツンデレタイプで、治療後はなかなかの愛嬌ある表情を見せてくれました。
2025年05月21日
-

犬はベロンで、猫はザラッ、〇〇〇はペロペロ。
新しい子が仲間入りしました。ロールカーテン越しに何やら黒い影。。。外の景色を見たいのか、日の光にあたりたいのか、窓際にみえる動く影。このシルエット、何の生き物でしょう。さてさて、ちょっとずつ開けてみましょう。ちら、ちら、ちら、ちら、ちら・・・・ででーーーん。正体は、ウサギさんでしたぁーーーウサギは、ウサギでも、デカウサギ、ジャイアントウサギさんです。これでも、まだ子供です。子供なのに すでに大きいです。いったいどのくらい大きくなるのでしょうね。それもまた楽しみです。おっきな耳。その大きさは、人の手のひらよりもデカいです。心はとても穏やかな印象です。体が大きくて迫力がありますが、こういうデカウサギさんはその体の大きさに比例して、心も大きいです。心の器が大きくて、どっしりかまえています。ためしに 寝っ転がって、デカウサギさんの口元に顔を近づけてみるとクンクン鼻先を近づけて匂いを嗅いだ後に、顔を舐めてくれます。その舌ざわり。。。ワンコやニャンコとはまた違う感触。ワンコがベロンで、ニャンコがザラッなら、ウサギは、ペロペロという感じがします。一般的にウサギという生き物は、機嫌が悪いときはまあまあ危険です。噛みつき、引っかき、跳びはねます。本気で興奮したときは、とても手がつけられません。「大丈夫だよ。 よーしよしよし。」そう心の中で唱えながら、口元に顔を近づけてあげるとあったかい小さな舌でペロペロと舐めてくれます。かつて、ムツゴロウさんがライオンと遊んだ時と同じように。ムツさんは、ライオンとじゃれ合うときに自分の顔をライオンの口の中に入れていました。もし、そのときライオンが口を閉じれば、頭をもぎ取られて終わりです。顔面を引き裂かれて終わりです。でも、ムツゴロウさんは、自分は危害を与えない人間だということを身をもってライオンに伝え、まるで、猫とでもじゃれ合うかのようにライオンといっしょにたわむれていました。それと同じかどうかは微妙ですが、ウサギも同じ。ウサギに本気で顔面をかじられれば皮膚がさけます。本気で、引っかかれたら目ん玉やられます。だから、大丈夫だよ~とともだちになるつもりで接することができれば、ウサギは、ペロペロしてくれます。ポイントは、「よーしよしよし」です。ジャイアントウサギさん。なかなかの迫力ですが、おっとりしていて、ドデーーンとしたおおらかさがあって、行動パターンがとても面白いです。見ていて飽きないです。子供たちもそんなジャイアントウサギさんに興味津々でお水やごはんをあげたり、床の掃除をしたり、自分たちで考えてできることを手伝ってくれています。ジャイアントウサギさん、迫力ある体格と穏やかな性格がとても魅力的です。
2025年05月02日
-

ネズミ捕り・・・
全身、 まるっと全身、 ネズミ捕りにかかった猫ちゃんが やってきました。 シャワーで洗い流そうとしてもとれず・・・ バリカン刈けて きれいにしようとしても難しく・・・ 他院で、油をつけてとってみたらとすすめられ・・・ ってことで、 困った様子で うちに来ました。半ノラ、半お家みたいな感じで生活しているため、 人馴れしていないのが心配でしたが、 上手に診察台の上に乗って 大人しくしていてくれました。 えらかったね。 そもそも、 今どき、 ネズミ捕りって、、、 なぜそこで猫が被害にあうのだろう、、、 運悪く、猫ちゃんがそのワナの場所に入った? 猫ちゃんが通りやすそうな場所にワナが置いてあった? どこかで誰かが仕掛けたものなんだろうけど、 実際に設置してあるネズミ捕りを目にしたことがないので、 どういった状況で引っかかっているのか不思議です。 被害にあう猫ちゃんは年間に数匹、 必ず毎年やってきます。 今回のケースは 頭もお腹も足も背中も尻尾も 全身なので、 被害が大きいです。鼻や口がふさがってなければ命に関わることはほとんどありませんが、皮膚炎を起こすことは考えられます。相手がネズミ捕りの粘着物質なので、ここからの治療は時間がかかります。この日は、ただれている皮膚の治療をかねて、抗生剤、抗炎症剤等の注射をし、粘着物質を取る作業を施しました。 がんばれ、猫ちゃん。 しばらくは不自由かもしれないけど、 全身もとに戻るまで がんばって。
2025年04月29日
-

ボクとアリクイくん
ボクとアリクイくん。アリクイくんが近づいてきた。↓ ↓ ↓アリクイくん抱っこ。↓ ↓ ↓Tシャツの匂いチェック。↓ ↓ ↓かわいいなぁ。↓ ↓ ↓背のびぃーーーー↓ ↓ ↓ボクの友達。アリクイくん。ボクのからだのあちこちをクンクンチェック。そこらじゅう臭いをかいでは、長い舌を出してペロペロ。ペロペロ。犬のようにベロ~ンという大胆さもなく、猫のようにジャリッというざらつき感もなく、もっとソフトにこちょばすかのようにペロペロペロッと細かな動きで細く長~い舌を巻き付かせるかのように器用に動かして唾液をつけてくる。匂いはあまりない。でも、とにかくくすぐったい。ソフトな舌あたりでこそばゆい。アリクイに体中を舐められるとボクはこんな顔になる。ボクの体にアリはいない。でも、アリクイくんはしきりにボクの体を舐めてくる。いっしょうけんめい舐めて来る。どうやらボクの体はアリのようにおいしい味がするらしい。くすぐったいけど、がまんする。アリクイくんがそれを望むなら、ボクの体がおいしいなら、ボクはくすぐったいのをがまんする。だって、ボクの大事なともだち。アリクイくんだから。
2025年03月13日
-

思いっきり雪遊び パート1
高速道路を走っていると遠くの方に雪山が見えました。よく知った道を途中でおりて、みんなで寄り道しました。積もり積もった雪は物珍しく、子供たちは いっきに興奮モード。どこまでもつづく一面の銀世界に向かってまっしぐら。よっこいしょ。雪をかかえてみたり、道に寝そべってみたり。取っ組み合いしたり。そのまま雪のベッドに寝て見たり。子供たちの雪遊び。みんな元気です。その様子を見てるこっちは めっちゃ寒いです。「なんで半袖なの!?」 ↓「だって 熱いんだもん。」「なんで素手なの!?」 ↓「だって そのほうが雪玉作りやすいんだもん。」そりゃそうかもしれんけど・・・、子供たちの頑丈な体と元気さにビックリします。思いっきり走って、 キャッキャッはしゃいで、真っ白い雪のでっかいキャンバスの上にいっぱいの足跡をつけ 遊んでいました。積もった雪は深く、どれだけ掘っても どれだけ踏みあさっても白、白、白。都会の雪解け道のように真っ白な雪が泥だらけに汚く染まることはありませんでした。子供たちが言いました。「大人は雪が嫌いだけど、 子供は雪が大好きだよ。」 って。たしかに。。。自分も子供のとき 確かにそうだった。何が楽しいかわかんなかったけど、とにかく 雪遊びは楽しかった。雪合戦、雪だるま作り、ソリすべり、かまくら作り、雪に埋もれてかくれんぼ、雪を食べたり、雪の料理でおままごとをしたり、雪を固めてかばんに詰めて家まで持って帰ったり、たくさん降った分だけ遊びのバリエーションが増えていたのを思い出します。自分もついつい子供たちの無邪気さにさそわれて久しぶりに 雪玉を作って投げ遊びました。ぶつけあったり、誰が一番遠くまで投げられるか競ったり。子供に負けてらんねぇと血が騒ぎ、ついつい本気になってしまいました。見てるだけだとブルブル寒さが身に沁みましたが、いざ本気で遊んでみると体はポカポカ熱くなるものですね。久しぶりに雪で遊んでもらいました。いや~ 楽しかったです。
2025年02月18日
-

おサルのシャンプー!?
今日は、キンカジューのシャンプーDAYです。 キンカジューはとても毛が密で、クマを触ったときのようなモコフワな肌ざわりの生き物です。クマというのも当然で、別名をHoney Bear(蜂蜜熊)といいます。サルと見間違える方も多いほど、様相、格好はサル似ですが、生態はサルとは無関係の生き物です。ハニーベアというだけあって、甘い物が大好きです。 さて、そんな独特の生き物ですが、数あるシャンプー剤の中から2~3本選んで体を洗います。キンカジューは人間の手にしがみつく習性があるので、腕に巻き付かせながらシャンプーします。もともと毛が黄茶色なので、見た目できれいになったかどうか微妙ですが、さっぱりとしました。一般的なふれあい動物園では、参加する動物たちをこのように事前にシャンプーしてきれいにしてから連れて行くことも多いです。 動物たちは、人間と違い、シャンプーの意味「体をキレイにする」という意味が理解できていません。そんな動物たちを相手にするには、 ワンコやニャンコをシャンプーするとき同様、お互いのコミュニケーションが大事な気がします。
2025年02月02日
-

アリクイの歯って・・・
子供たちがアリクイの食事風景を観察しています。世間一般にはなかなかお目にかかれないめずらしい光景だと思いますが、我が家ではこれが当たり前です。とは言っても、子供たちは 目の前の動物が「アリクイ」という種類の動物であることを知りません。子供たちの心の中は、また何か見慣れない動物がやってきたなぁ~と いったところでしょうか。。。。。アリクイは何をどうやって食べるのでしょうか。。。アリクイには、実は 『歯』 がありません。「えっ!?知らなかったぁ~」という方も多いはず。そうなんです。筋肉質で、こんなごつい体つきをしていますが、歯がありません。変わった動物ですね。不思議な生き物ですね。アリクイの食事を用意するのも準備するのも他の動物に比べて まぁまぁ大変です。けっこう、時間と労力を使います。何をどうやってあげようか、調理しようか考えます。歯がないので、すべて舐めて食べます。舌でなめすくう、なめとるといった感じです。舌でといっても、舌がこれまた長ーいです。20センチ~30センチくらいあるでしょうか。びっくりするぐらい長いです。それを器用に使って、ペロペロして食べます。生きていくために そのように進化したのでしょうが、生きていくためのすごい知恵ですね。この長い舌を使って、一発で大量のアリをからめとり食べるのですから。子供たちも真剣です。目の前の見慣れない生き物が何やら得体の知れない物を食べているのですから。それも、ひたすらペロペロと。何をしているのか、どうやって食べているのか、要観察です。世の中、大勢いる子供たちの中で、このようにアリクイを身近に感じ、観察できる幼児はそんなに多くないと思います。こんな体験がどんなに貴重で、どんなに珍しいことで、どんなにすばらしいことか、彼ら子供たちが大人になったときにようやく理解するに違いありません。身の周りに当たり前にいろんな動物たちがいますが、それがあまりにも日常の当たり前のことすぎてあまり実感、驚きがないようです。動物たちとともに過ごす中で、世の中には多種多様の生き物たちがいることを知り、それぞれに興味関心をもって、動植物、環境全体を学んでいって欲しいなと思います。
2024年12月12日
-

〝よーしよしよし”
ちょっとかわった動物がやってきました。キュートな瞳にちっこいおてて、おちょぼ口で、ながい尻尾、わりと大きいピンと立った耳。元気なく、いつもの食餌量の5分の1ほどしか食べないため点滴しました。ワンコやニャンコに点滴するのとは違い なかなか難しいです。こういった生き物は触られるだけでストレスになることも多いです。ストレス過多でパニックになると大変です。あんまりストレスをかけすぎず、そっと触って、相手のペースにあわせるのが大事です。うさぎも同様、その典型例で、恐怖を感じさせるとジャンプして逃げ回り、パニックになります。動物種によって動きも性格も大きく違うので、慣れない動物の場合は触ることすら大変です。でも、こんなときやっぱり思い出すのはムツゴロウさん。「よーしよしよし」と言いながら相手の体をなでまわしどんな動物とも仲良くなってしまうその姿には尊敬の念が絶えません。「よーしよしよし」ムツゴロウさんの手にかかればどんな動物もときにはライオンをもあっという間に手なずけてしまう。本当に唯一無二の存在だと思います。「よーしよしよし」みなさんもいろいろな動物と対面したとき、あるいはご自宅のペットやご近所のペットを手なずけたいとき、「よーしよしよし」という愛情いっぱいの心で接するのがいいかと思います。動物は人間の心をズバッと見抜きます。バレバレです。邪心をなくし、心を空の空の空にして、「大丈夫だよ~、大好きだよ~」と手のひらから伝えるように触ってあげると相手に届くかも。そしたら、相手の脳内には幸せホルモン(オキシトシン)が分泌され、仲良くなれる。人間と動物、異種の生き物なんだからその過程でトラブルがあるかもしれないけど、噛まれてもそれは仕方のないこと。ムツゴロウさんはこんなことを笑いながらお話されるような方でしたね。「よーしよしよし」あたりまえのことだけど、この気持ちは人に対しても動物に対しても大事ですね。
2024年09月08日
-

初! スイカ割り
「ねぇ!スイカ割りしたいっ!」子供たちのリクエストにこたえて、Let’s スカイ割り。運よく、ちょうどいただいた小玉スイカがあったので保冷ボックスに入れて、田舎へGo!暑かった~けど、子供たちの熱気とやる気はもっと熱い。まずは、お兄ちゃんたちから順番に。反則ないようにしっかりと頑丈に目隠しして準備OK!大きな竹の棒をよいしょと持ち上げ、スイカめがけて”えい、やー”下の子たちには難しいのでハンディキャップで目隠しなしバージョン。兄ちゃんたちがやっていたのを見て、見よう見まねに初めてのスイカ割りに挑戦する下の子たち。意味が分かっているのかいないか・・・訳わからないまま〝んーーーっと、よいしょーっ”パカ~ン といい具合に割れました。その後は、みんなで 真っ赤なスイカにむしゃぶりついて種とばし。あっ、塩を忘れたね。でも、まぁいいか。暑い夏と子供たちのやる気と汗と笑いがちょうどいい調味料になってよりおいしいスイカになりました。そして、周りのアリさん、虫さんたちもスイカの汁のおこぼれを狙って列をつくっていたね。みんなおいしいっていってたね。夏が暑い理由は、子供たちがスイカをよりおいしく食べられるようにするためかもしれないね。
2024年08月25日
-

「今日はボクが作るから。」
この日、長男が「今日はボクがごはんつくるから。」となぜか気合十分!張り切って、料理をしはじめました。「ママ、 ぎょうざの皮ってある?あと、ちくわ。それと、チーズ。そーせーじもね。今日はボクが作るから。」なぜかわからないけど、何がそうさせたのか、この日だけ、突然気合のスイッチが入りました。あ~~、指切りそう。包丁が指をかすりそうで、見てるこっちの方がこわいです。自分で何を作るのか頭の中で試行錯誤、想像しながら作っているようでした。上手に並べて、「ママ、できたよ。 これ焼いてね。」焼き3分。おいしそうです。すぐにひとつ、味見でいただきました。味もバッチリ。いい感じに仕上がっていました。もうひとう、もうひとつ、、、自然とおかわりしたくなるような味と食感でした。弟にも食べさせ、自分も食べて、満足した様子でした。自分で作って、他の人に「おいしいね」って言ってもらえた時の気持ち。それがどんなうれしいものかをしっとりと感じているように見えました。自信につながって、また何か作ってくれるとうれしいな。
2023年11月13日
-

大事な思い出にするんだよ
「運動会 がんばるぞーーー」この日は、朝から風が強く、とても肌寒い日となりました。空は曇り空。時折、太陽が顔を見せるものの、とても風が冷たい。前日から、明日大丈夫かな、、と心配してましたが、前日降った雨が校庭に残ることもなく、どうにか開催されました。今年はコロナ禍中のような人数制限がなく、また、学年ごとに時間を区切っての開催でもなかったため、校庭には 大勢の人が集まることとなりました。校庭にいる生徒&保護者の数、あわせて 約2000人。この大勢の人の中から、自分の子供を探すのも一苦労。はじめは興味ありげにグランドを眺めていた弟たちもどこにお兄ちゃんたちがいるか分からず、そのうち飽きて地面をイジイジ。。。。。観覧席の場所取り合戦もひそかに激しくなり、わが子を探す保護者、カメラにおさめようとベストポジションを確保しようと奮闘する保護者、幼児の世話に手をやいて、観戦になかなか余裕がもてない保護者、周囲にはいろいろな保護者の姿がありました。さぁ、綱引きです。この中のどこにいるでしょうか、、、、、なかなか難しいです。さぁ、玉入れです。この中のどこにいるでしょうか、、、、、うーーーん。みんな同じ格好、昔のように、体操服に 名前やクラスが書かれたゼッケンもついておらず、特徴がないので、分かりづらいです。さぁ、大玉転がしです。グラインド一周、ぐるっと生徒が囲んで大玉を転がします。赤い帽子の頭がたくさん並んでいます。うちの子はどこかな?さぁ、100メートル走です。「がんばって 一番とる!」と宣言していた長男。何番目に走るのかなと目を凝らして探しているとたまたま、自分の目の前に列をなした生徒たちが並びました。おおおおおっと、いたぁーーーーーー!こちらの存在に気付き、チラッと振り向く長男。赤い靴に、赤い靴下、これを目印にその姿を目で追い続けました。さぁ、腰に手をやり順番に出発です。一番向こうのほうから出発して、こちらにゴールするようです。遠すぎて、姿が小さすぎて、どこにいるのか見失いそうです。赤い靴に 赤い靴下。ずぅーーーっと目で追って、目の前でゴーーーール!途中は、見逃しましたが、ゴールしたのは分かりました。目の前でのいきなりゴールでしたが、うん、確かに一番だった。一番最初にゴールテープをきった気持ちはどう?完走した順から座って待機。カメラを最大限にアップして、〝パシャ”嬉しそうです。よかったね。満面の笑み。よかったね。よく頑張りましたね。さて、その頃。お兄ちゃんたちのがんばりには目もくれず、開放された体育館で走り回ってはしゃぎ遊んでいる保育園組の弟たち。観戦してるだけじゃ飽きちゃって退屈で仕方ないのでしょう。こうしているほうがいいようでした。体育館で遊び、花壇の土のところで虫を探して遊び、運動会よりもそちらに夢中のようでした。さて、2時間ほどで運動会も終わり。タイムスケジュールは、コロナ禍のときのように時短そのままだったように思います。あっけないような、物足りなりないような、、、、、自分たちが子供の頃はお弁当持って行って、みんなで食べたり、応援合戦があったり、保護者や地域住民の参加があったり、教職員の登場があったり、なんだかんだともうすこし内容が濃かったように記憶しています。いいのか わるいのか、いろいろな行事が簡素化され、どこかさびしいような気もします。ともあれ、今の子供たちにとっては、これが〝ふつう”で、 昔と違うという認識はないでしょう。今の時代の運動会。よくがんばったね。大事な思い出にするんだよ。
2023年11月11日
-

【パート2】先生!おしりから何か出ています。
今回は、「先生!おしりから何か出ています。」のパート2。前回のパート1をまだお読みでない方はこちらをクリックどうぞ。↓↓↓先生!おしりから何か出ていますさて、今回は、前回をふまえてのパート2。同じように、「おしりから何か出ています。」という主訴で患者さんが来院されました。(ここからは いつものように症例の写真が登場します。 苦手な方はご遠慮ください。)患者さんは、小型犬のわんちゃんです。そのときの様子がこちら。↓ ↓ ↓ ↓ ↓角度をかえて、もう2枚。たしかにまるい大きな物体が陰部から出てますね。これはいったいなんでしょうか。出産途中のようにも見えます。角度を変えて、横から見てみましょう。おしり全体が、おしり全部が突出しています。ちょっと、出産とは違うようです。出産では、ここまで大きくお尻が突出しないです。では、毛を刈ってみます。上から順に、、、尻尾があり、肛門も確認でき、大きなふくらみがあり、その下に、陰部から物体が突出しています。毛を刈ってみてもっとよく分かりましたが、突出部分は かなり大きいです。突出した部分の上部は、内出血を起こしています。内側からの圧迫がだいぶ強いのでしょう。さて、あらためて、一体これは 何でしょうか?みなさんには、問題をだしたまま続けますが、写真はこの先、この答えが分かった上で手術で摘出したものをお見せします。術中の写真が、苦手な方はご遠慮ください。消毒して、手術の準備をします。電気メスを使いながら、切開をします。皮膚を大きく切開して、腫瘤物を確認します。根本のほうをたどりますが、どんどん大きい物が出てきます。ひと塊になっていますが、血管が多数走行しているため、出血量も多いです。止血を繰り返しながら、腫瘤物を取り出します。大人の手の握りこぶしと比べるとその大きさが分かると思います。体重2キロの小型犬のお尻にこれだけ大きなものがあったら・・・・・想像してみてください。切開部分を縫合して、手術は無事終わりました。写真で見るとあっけないかもしれませんが、時間的にはだいぶ時間経過しています。個人的には、まれにみる大きな手術のひとつで、自分の生涯で同じ症例に出会うことは二度とないだろうと感じるくらい、めずらしい手術になりました。これが取り出した腫瘤物です。直径10センチ以上もあります。さて、ここで復習です。先生!おしりからなにか出ていますパート1でお伝えした腫瘤物。あの腫瘤物は、膣粘膜が過形成したものでしたね。さて、ちょうど時期が重なったので、そのときの腫瘤物と今回摘出した腫瘤物を並べて、比べて見ましょう。向かって右がパート1、左が 今回摘出したパート2の腫瘤物です。このふたつ。実は、もとは同じものです。どちらも膣粘膜が過形成したものです。つまり、右の状態を 放っておくと、だんだんとでかく大きくなり、左の状態になります。それにあわせて、外観的にも突出部分がだんだん大きくなる、というわけです。右の状態だと、無麻酔で、数分で、処置完了ですが、左の状態まで放っておくと、大規模な手術になり、もちろん、麻酔も必要、出血も多く、術後の管理も大変で、命に関わる問題になります。同じ病気でも、軽いうちから早めに治療するか、元気に日々ふつうに過ごしているうちは放っておいて、後で 大きく治療するか、その選択は ご家族の意向に左右され、処置も治療も結果も それに合わせていろいろなんだなということをあらためて実感させられました。何が正解かは分かりませんが、それぞれの飼い主さんがいて、それぞれの価値感があって、それぞれの状況があって、それぞれにとりまく環境があって、それによって、答えはばらばらです。そのかわり、どういう選択肢があるのかということを自分の持っている引き出しを開いて、いろいろな選択肢を提供し、アドバイスするのがこちら側の使命だなと学ばされます。ともあれ、今では、どちらのわんちゃんも元気にしています。こういう病気はあるんだな、と知っておくのも損ないかと思います。ペットたちの日々の健康管理にお役立てください。
2023年11月10日
-

カバの口は、バカでかい。
カバのお口。まじまじと見たことありますか?水の中も余裕でもぐれるカバ。でっかくて、迫力あって、生きた化石のような容姿をしています。水の中が好きなカバ。「こっち おいで~」「あーーーーーんしてぇ~」カバが 〝ガバッ” っと口を大きく開けました。でかっ!すごい迫力!カバの口の中って、こんなんです。知ってました?口の中は、ブヨブヨしててまるで木の枝のような歯をしていますね。優しい目に、小さな耳も特徴的です。今の世の中にこういう動物たちが生きていることはとても素晴らしいことです。絶滅することなく、これからもずっとずっと生き続けて欲しい種です。最後にもう一度。「お口開けてぇ」いろんな動物を観察していると知らないこと、発見すること、初めて見るものがいっぱいでとてもワクワクします。
2023年11月07日
-

ツンツン、コンコン
温めていた卵、まさに今、孵化しようとしています。毎日、毎日、気にしながら、卵をあたためています。産んだ親ではないけれど、気分は、まるで親になった気分です。温度は大丈夫?湿度は大丈夫?そんなことを考えながら、温めます。抱卵、転卵、放冷、検卵を繰り返します。あんまり気にしすぎて、触りすぎるのもNG。ツンツン、コンコン、中から振動が加わって、卵に孵化する印がつきました。さぁ、ここからです。がんばってうまれてこいよ~見ているだけでワクワクします。みなさんもご存じ、卵の中はもともとは黄身と白身。そこからなぜ! どうして! どうやって!この中で生命が誕生、確立し、成長し、形となり、うまれる・・・不思議です。卵の中で営まれる生命の誕生。卵の中はまるでちっちゃな宇宙のようです。温度も湿度もそうですが、ありとあらゆるすべての条件がそろわないと孵化しません。あらゆる条件がそろわないといくら有精卵であっても生き物としての形になりません。人間の子宮の中で起きるようなことがこの小さな卵の中で起きているわけですから、そう考えるととっても神秘的です。卵からうまれる生き物にはなにがあるでしょう?例えば、、、インコ。カメ。フクロウ。ニワトリ。イグアナ。ペンギン。ヘビ。ダチョウ。カラス。ヤモリ。フラミンゴ。ワシ。カメレオン。カモノハシ。いろいろありますね。いろんな動物がいて、その数だけいろいろな産まれ方があって、実におもしろい。孵化する瞬間は、がんばれよ~って声をかけたくなります。
2023年11月05日
-

先生!おしりから何か出ています。
「おしりから何か出ています!」そんな主訴で患者さんが訪れました。診察台の上のワンコ。おしりをこちらに向けてもらって。確かに、何か出ています。肛門(腸)ではなく、膣のほうです。わんちゃんの膣から まあるい血管まじりの組織がでてきています。表面はしめっていて、毛はありません。皮膚ではありません。ひっぱっても とれません。奥の奥に 根っこがあるので、膣の中とつながっています。さて、この物体の答えは、膣です。膣脱とはまたちょっと違いますが、膣の一部が大きくなって、外部に出てきたものです。過形成した膣の一部です。このままほっといてもいいですが、ほっといてもだんだんと大きくなります。それと、おすわりしたときに床にあたり、こすりつけるので、表面から出血したりもします。そしてそれをまた気にして、わんちゃんが舐め壊したりもします。おしっこの出口でもあるので、大きくなっていくほどおしっこがしづらくなったりもします。はじめは小さい出来物でもみるみるうちに大きくなってくるので早めの処置がおすすめです。小さいうちだと無麻酔で診察ついでに、診察台の上で処置が可能です。なので、このわんちゃんもその場で処置しました。根っこを確認して、それと一番大事なのは、尿道の位置です。尿道の出口は膣の中にあります。そこを見落としてしまうとあとでおしっこがでない・・・ということもあり得ます。外尿道口を確認して、そこを傷つけないように根っこ部分を結紮します。その後、出来物だけを切除します。最後に切り口からの出血がないかを確認して止血します。切除した出来物です。ウズラの卵よりは大きいです。この病気。はじめて見る方が多いかもしれませんが、まあまあよくある症例です。処置後の投薬としては抗生物質、止血剤、抗炎症剤、消炎鎮痛剤、、、、これらをその子の必要性に応じて処方します。処置後は、そのまま帰宅して、普通の生活をおくってOKです。家庭では、排尿時の異常がないかどうか、日常生活で気にする素振りがないかどうか、観察していただければOKです。ということで、昨日は、~鼻水~のお話をしましたが、今日は、~おしり~のほうのお話をさせていただきました。いつもは見ないところだと思いますが、わんちゃんたちのお尻も ときどきは異常がないか観察してあげてくださいね。
2023年11月04日
-

~鼻水注意報~
鼻水を垂らしてやってくる子が増えています。寒さが徐々に増してきて、人の世界でもそうですが動物の世界も同じで、風邪引きさんが増えています。動物には動物の風邪ウイルスが存在します。鼻炎や気管支炎や肺炎や・・・例えば、写真のワンコ。鼻水ダーダーです。鼻水、くしゃみ、咳でやってきました。ここまではっきりと特徴的に白い膿性鼻汁が垂れて見えるのもめずらしいです。よく見られるのは透明だったり、もっと水っぽかったりします。透明ではなく、「白色」というのは透明よりも重度と判断します。細菌感染がおきているほど、浸出液から膿性の鼻汁に変化するため、透明 → 白色 → 黄白色 → 赤色まじり となるほど病状は重度になります。わたしたち人間も鼻水、くしゃみ、咳はつらいですよね。ワンコも同じです。つらいです。悪化すると、肺炎になったり、熱が出たり、食欲がなくなったり、口を開けて息をするようになったり。ここまでくると入院になってしまいます。点滴をはじめ、注射や点鼻点眼薬、吸入を用いて抗生剤、気管支拡張剤、去痰剤、ビタミンC剤、インターフェロン製剤、抗炎症剤などの薬剤を使用して治療します。聴診やレントゲン撮影、白血球数のカウント等の検査でも病状を判断します。聴診で 肺(呼吸)の異常音が聞こえたり、レントゲン写真に気管支や肺の炎症像が見えたり、血液検査での白血球数が増えていたりするときは 要注意です。大事なのは、重症化する前に「あれ?」っと思ったら早め早めの受診を心がけることです。今一度、わんちゃんねこちゃんたちに「鼻水」がでていないかお顔をよ~くみて観察してみましょうね。これからの寒い本格的な冬に備えて人もペットも日々の体調管理をしっかりと行いましょう。
2023年11月03日
-

まるまると、ぷくぷくと
子供たちが飼いだしたカブトムシたち。飼い始めた当初は、買ったばかりの頃は、一生懸命世話をしたり、観察して楽しんだりしてたけど、最終的には結局、こちらが世話をするはめになる。夏が終わり、寒くなり、誰もカブトムシのことをそれほど気にかけなくなりました。夏に卵を産み、それが孵化し、幼虫となったカブトムシの子供たち(過去ブログ:大量にウネウネ)。その世話をしているのは 結局、私。ひそかに日々の成長を楽しみながら見守っています。ときどき寝床を変えてあげたり、栄養のある餌にしてみたり。あの小さかった幼虫がみるみる大きくなって、今では こんな感じです。毎日、いっぱい食べて、いっぱいウンチして。まるまると、ぷくぷくとしてますね。この先、頑張って寒い冬を乗り越えてほしいと思いながら見守っています。これからサナギになり、あのカブトムシになり、、、いったいどんな変態をするのか それまた不思議な世界です。
2023年11月02日
-

ハッピー??ハロウィーン
ハローウィン当日。子供たちがマントに帽子、杖を作って変装ごっこで楽しんでました。この日の記念に写真を撮ろうとカメラを向けました。真顔なので、「笑って♪」とニコニコ笑顔を誘うと↓ ↓ ↓ ↓ ↓顔をくしゃくしゃにして笑いの表情をつくってくれました。とはいっても、意識しすぎた結果、なんだか苦しそう・・・・もう一度。「笑ってこっち向いて♪」さっきより余計に苦しそう。。。「おーい、笑って♪」しんどそう。。。。。そのうち、全く笑顔じゃなくなってきました。とりあえず、、、表情を意識しすぎて、苦しそうな笑顔。これが、彼の精一杯の笑顔。表情筋が疲れてきたようなので、ここで終わり。ハッピーハロウィンのこの日、ハッピー??と つっこみたくなるような笑顔でした。
2023年10月31日
-

先生!皮膚をつきやぶっています。
こちらの生き物。↓ネズミちゃんです。なんといっても「出っ歯」が特徴です。でも この出っ歯、よく見てみてください。写真を拡大してみると、上下とも皮膚をつきやぶって、出ています。そうなんです。この出っ歯、上下とも唇の上下から皮膚を突き破って飛び出ているのです。大きく飛び出した歯は、地中で土を掘るのに使います。堅くて丈夫で、スコップの役割をします。誰もが知っている地中で暮らすモグラは、手を使って土を掘ります。でもこのネズミは、この歯を使って土を掘り、何百メートル、何キロもの長い長いトンネルを掘って暮らしています。ではなぜ、皮膚を突き破って歯が飛び出ているのか。。。それは、口を大きく開けなくても 土を掘れるようにするためです。このような口の構造のおかげで、口を閉じたまま、出っ歯をスコップとして器用に使って土を掘ることができます。口を閉じたまま土を掘れるので、口の中には 土が入りません。土を掘るために口を大きく開けていたら、口の中が土まるけになりますよね。それを避けるためにこのような口の構造になっています。すごいですね。生き物の進化って。さて、出っ歯が特徴のこのネズミちゃん。見ての通り、毛がありません。つまり、はだかです。なので、このネズミの種類は、「ハダカデバネズミ」といいます。裸(ハダカ)と 出歯(デバ)で ハダカデバネズミ。そのままですね。覚えやすいです。ハダカデバネズミはとても不思議な生き物で、研究者たちの間では注目されている謎多き生き物のひとつです。実は、寿命が約30年と とても長いです。一般的なネズミは、約2~3年ほどです。みなさんがペットとして飼うハムスターもそのくらいですよね。それが、このハダカデバネズミは 30年と 超ご長寿です。なので、長生きの研究、老化耐性の研究としても注目されています。そしてもうひとつ。高度な社会生活を営んでいます。群れの中に階級があり、一番上が 女王ねずみ、二番目が 王様ねずみ、三番目が 兵隊ねずみ、4番目が 働きねずみ となっています。蜂(ハチ)の社会と似てますね。女王ねずみは、一番大きく、子供を産むのは 女王ねずみしかできません。そして、その相手になるのが、王様ねずみです。他の兵隊ねずみや働きねずみたちにもオスメスありますが、子供を産めない体になっています。しかし、女王ねずみが死んだとき他のねずみが女王ねずみになりますが、そのとき女王ねずみに選ばれたねずみはそこで子供を産める体になり、体もデカくなります。不思議ですね。ひとつの群れの中にいるハダカデバネズミは、基本的に全員が血縁関係者となります。つまり、親子や兄弟、家族の中で交配が繰り返され増えていきます。一般的な種では、こうしたケースでは、奇形が増えやすくなりますが、ハダカデバネズミではそういった傾向がみられません。これもまた不思議な点のひとつです。3番目の階級の兵隊ねずみは、食べられる役割をもっています。もし巣穴にヘビなどの天敵がやってきたとき。兵隊ねずみは、率先して食べられに行きます。食べられている間に、他のねずみたちが穴をふさぐなどして 内部への敵の侵入を防ぎます。食べられることでその間、時間かせぎするのですね。自分を犠牲にすることで、敵から仲間を守るというすさまじい役割を持っています。その下の階級の働きねずみは、女王ねずみが産んだ子ねずみの世話や保温、巣穴の掃除やエサの採取など、周りの雑務をこなします。これらの階級に従った役割がそれぞれのねずみに存在します。とても高度で複雑な社会システムだと思います。そしてもうひとつ。先ほどお伝えしたように 寿命が約30年にもなります。一般的に長生きすればするほど「ガン」が発症しやすくなりますが、ハダカデバネズミは、「ガン」に非常になりにくい生き物です。少し前までは、絶対にガンにならないといわれていたくらいです。動物としてとても特異的な体質だと思います。長寿の研究もそうですが、ガン予防、老化防止などの医学的な研究としての注目度も高まりつつあります。
2023年10月29日
-

女なのに男!?
こんな症例をご紹介します。女の子のワンちゃんです。陰部のところに何か出来物のようなものが見えます。よく見ると、陰茎のように見えます。これは、半陰陽という先天性の疾患が考えられます。まれですが、でもすごく有名な疾患のひとつです。このワンちゃんはまだ子犬です。女の子なので、将来的に避妊手術をするとはっきり分かりますが、半陰陽のわんちゃんは、避妊手術でお腹を開けると子宮の先に、卵巣ではなく精巣がついていたり、お腹の中に卵巣と精巣の両方があったりします。外からの見た目、つまり ワンコの外観はメスですが、体の中はオスということになります。半陰陽のわんちゃんは、膣から陰茎(ペニス)が出ているため、その飼い主さんが動物病院にいらっしゃったときは、はじめに、「膣から何か腫瘍のようなものが出ています。」という主訴で来院されます。膣から何か出ている・・・・・・もちろん、腫瘍のこともありますし、良性の出来物のときもありますし、膣脱や膣の過形成のときもあります。そして、その原因のひとつが半陰陽のときもあります。いろんな可能性を疑って、確定診断につなげますが、こんな疾患があるんだなということを知っておくだけでも価値があると思いますので、みなさんも頭の隅っこに入れておきましょう。ちなみに、この疾患は、人間にもあります。自分は、獣医師であり、人間の医者ではないので詳しくは語れませんが、おそらく、想像するに、不妊の原因やいじめ、差別の原因になったりでもっともっと大きく深い内容になると思います。ワンちゃんたちにこういう子がいるように社会の中でもこういう人たちがいるという知識を持つことも人として大事なことだと思います。
2023年10月27日
-

自然と笑顔に・・
先日、知り合いのおじちゃんから 「今日は移動動物園やってるからおいでよ。」とお誘いの連絡が入り、顔を出しに行ってきました。おじちゃんとは もうかれこれ20年くらいの付き合いになるでしょうか。動物についていろんなことを話せる動物つながりのひとりです。この日は、早朝から設営をし、動物たちを運んで準備したとのこと。『動物をみたいだろう』という私の想いを察して、わざわざ電話をくれたことがうれしく、すぐに 子供ふたりを連れて出発。現場に向かいました。ちょうどお天気もよく、動物たちにとっても 最高の天候でした。到着して間もなく。動物たちを見ただけで、自然と笑顔になる子供たち。腰ひけてるけど、なんとかがんばってあげてみよう。驚かせないようにそぉ~っと近づくんだよ。柵ごしならこわくないからにんじんあげれるよ。どんだけ~得体の知れない見たことない生き物。ギュウしちゃダメだよ。そぉ~っとだよ。なんこれ?ピヨピヨ?カメさん?こわいよ~ママ、助けてぇ~はじめまして、こんにちは。ジュースいる?ぜんぜん動かないからつまんないーー。どうやって触ったらいいの?触ったら、トゲトゲチクチクしたよ。痛いからムリーーーでかっ。ねぇ、動いてるよ。すごいよ♪どこまで運んでくれるかな。子供たちには、いろんな感情と表情が見られ、動物たちに囲まれ、自然と笑っていました。自分もふだんから 一日中、動物たちと接している身ですが、それでもやっぱり動物は飽きないです。動物たちは私を飽きさせないです。いいですね、生き物は。人を自然と笑顔にさせてくれます。たくさんの人を自然と笑顔にさせてくれますね。でも、大事なことのひとつは、どれだけの笑顔を人間に与えたとしてもその前提として、動物たちも幸せでないといけないということだと思います。人間の幸せが、動物の幸せに、そして、動物たちの幸せが、人間の幸せにつながります。自分もこれから先、動物を通して、生き物を通して、多くの人に笑顔を届けられるような人に、そして、多くの動物たちに笑顔を与えられるような人間になりたいと思います。
2023年10月25日
-

いろいろ4匹
今日の院内の様子。お昼のお遊びタイム。犬?猫?ん???パッと見、???ですが、よーく見ると、左端から順番に、、、犬、犬、ブタ、猫 です。〝ブーちゃん(ブタ)~”こっちを向いて、「何かくれるの?」と何か食べたそうな表情で近寄ってきてくれました。〝よしよし、いい子だね。”ブーちゃんは とにかく鼻がいいです。〝おーちゃん(黒チワワ)~”名前を呼んで 頭をヨシヨシしてると背後から黒猫のうっちゃんが はがいじめのタックルをしかけてきました。この2匹はいつもこうして遊んでいます。でも、お互いに 傷をしない程度にちゃんと手加減して取っ組み合いをします。猫の方は、爪を出さずに猫パンチや後ろ足のキックをしかけ、犬の方は、遊び噛みで猫の首元をガブガブします。犬猫同士で、これ以上しちゃダメという加減を知っています。〝太郎ちゃん(茶チワワ)~”舌がびろ~んと出っぱなしのお年寄りのおじいちゃん犬です。お年寄りで、取っ組み合いができる体ではないので、みんなちゃんと遠慮してそっとしていてくれます。なので、おじいちゃんは自分のペースで、周りと遊べます。〝うっちゃん(黒猫)~”もともとはノラ猫ちゃん。体中、とりもちまみれ&車にひかれて前足を骨折して運ばれてきました。生後2か月ほどの時に保護されて、それから当院で育ちました。院内猫の中では、一番愛想が良くて、一番活発なやんちゃっ子です。遊びたくってしょうがない感じ。か弱かった幼き頃が嘘のようです。いろいろ4匹で、お遊びタイム。異種の動物たちが同じ環境にいて同じ時間を過ごすというのはとてもほのぼのしていていいものです。お互いにいじめることもなく、干渉しすぎることもなく、お互いに遠慮もあり、興味もあり、匂いをかぎあって、距離を縮めたり離れたり、平穏な関係で刺激しあって、いい感じです。猫はブタを目の前にして 何を思い、、、犬は猫を前に 何を感じ、、、ブタは自分とは違う姿形の生き物を見て どう理解しているのか、、、不思議です。人間 対 動物 も面白いですが、動物 対 動物 を観察するのも 面白いです。動物園に行っても、それぞれ個々の動物種が 個別に展示され、複数種での関係性が観察できません。人間も含め、異種の動物種どうしが、どうふるまい、どう接しているか、どう感じているか、どう挨拶するか、そういうお互いの関係性を観察することもときには とても面白いです。
2023年10月23日
-

お馬さんも秋を食べるよ
秋を感じてますか?ワンちゃんとのお散歩中、秋を見つけてられていますか?長かった夏がやっとやっと終わって迎えた秋。人も動物たちも体の健康のために、秋を感じてあげることが大事です。五感&第六感で四季を感じることで体調が整ったりもします。現代のワンちゃんたちは、年中家の中にいて、寒い&暑いがないために、換毛がうまくできない子がいます。夏になっても冬毛が抜けず、秋までだらだら毛抜けが続いたり、冬になっても体温を守るためのモコモコ冬毛が生えてこなかったり、換毛が上手に出来ていない子がいます。そしてそれが皮膚病の原因にも体調の不良にもつながったりします。さぁっ、ペットたちと、秋を感じに出かけましょう。外に出て、思いっきり深呼吸して、体の中に秋の空気を取り入れましょう。いろんな秋の形を目で感じ、肌で感じ、匂いで感じ、音で感じ、味覚で感じましょう。『秋を体で感じること』それこそが、健康のための『最高のスパイス』になると思います。足元に落ちている落ち葉はありますか?真っ赤に色づく紅葉の葉っぱはありますか?見つけたら、ギュッと踏みしめ、フワッとにぎってみましょうね。そして、この秋の落ち葉。動物たちもハミハミ食べたりします。お馬さんもそのひとり。土を舐め、木をかじり、草木を食べます。ハラハラと上空から落ちて来る葉っぱで遊んだり、足元に敷き詰められた落ち葉をベットにして寝っ転がったり、落ち葉のじゅうたんの上を駆けまわったり、パクパク食べて味わったり、お馬さんもヤギさんもブタさんも 動物たちみんな秋の訪れをを喜んでいます。よーくよく考えたら、虫さんたちもそうですよね。落ち葉の中にはたくさんの虫さんたちが宿っています。落ちてきた葉っぱを巣まで運んだり、重ねたり、上手に噛みちぎって細かくしたり、これからの冬に備えるための材料にしていますね。自然界では秋の訪れを喜ぶと同時に、秋を上手に利用して、次にやってくる冬のための準備をしているように感じます。もうすぐやってくる冬のために、わたしたち人間も秋を感じにでかけましょう。
2023年10月22日
-

ワンワンいなり
毎週日曜日&祝日は、子供たち男子3人衆がドッチボールの練習&大会に出かけていきます。普通の日は、朝から夕方まで一日中練習があり、ときには遠くまで遠征があったり、しょっちゅうあちこちで大会があったりで、早朝5時、6時、眠たい目をこすりながら出かけていきます。一人は保育園児、二人は小学1年生と4年生、朝早くから眠たかろうに、、、それでも行かなければ監督に怒られると言って、半分寝たまま車に乗り、現地へ向かいます。親の仕事にあわせた生活をさせているため、夜寝る時間も毎日12時過ぎです。睡眠時間が少ない中、小さい体で、大したもんだと思います。一日中練習して帰ってくる姿を見て、親以上に体力があり、頼もしく思います。そんな頑張る3人衆のために自分もまたお弁当を作ってあげないとな・・・と眠たい目を擦りながら、夜中起きてがんばります。何を作ろうか、、、日々、考えますが、時々は、、、たまには、、、練習の合間に 見て楽しい、ニコッと楽しめるようなお弁当を作ってあげようと、思考を凝らします。自分なりに、動物に関することなら得意なので、今回は、動物を作ることにしました。その名も、ワンワンいなり。↓ ↓ ↓ ↓ ↓ワンワンいなりと言っても、犬用のいなりではありません。犬の形をした おいなりさんです。一番手前の子がリーダー。2列目の2匹は、優等生。一番後ろの列の3匹は、おちゃらけ組です。これらをお弁当箱につめて、完成です。子供たちは、完成品を知りません。お昼、お弁当箱を開けて ニコッと笑って、パワーをもらってくれたらうれしいです。さぁ、出発です。現地まで1時間かかります。毎回、練習が終わって帰ってくると、「監督に怒られた」「もう辞めたい」と泣きじゃくる子、「試合で年上の子のボールをキャッチできた」とうれしそうに話す子、「ママ、お弁当つくってくれてありがとね」とお礼を言ってくれる子、さまざまですが、つらい、つらい、言いながら、その中で自分たちの役割や楽しみをもって頑張ってる姿は私自身の励みにもなります。今日も一日、かんばれよ~3人衆。
2023年10月21日
-

狼爪が2本!?
まずは、下の写真から。↓ ↓ ↓ ↓ ↓ワンコの後ろ足です。後ろ足を 裏返しにして、肉球側を撮影した写真です。狼爪(ろうそう)が 2本あるのが分かるでしょうか?人間の指をあてている部分がソレにあたります。これを見て、ピントくる人は、スゴイッ!後ろ足に狼爪2本。はじめて見る方はびっくりされますが、そういう犬種がいるのです。その犬種が何犬か分かりますか?ここで狼爪について、少しだけ触れておきます。ワンコにもニャンコにも ありますね、狼爪。一番内側の少し高い位置についている指の爪。人間の親指に相当する部分ですね。ワンコもニャンコも 通常、前足には狼爪がありますね。では、後ろ足はどうですか?お家のワンコ、ニャンコを観察してみましょう。通常、後ろ足には 狼爪ないですよね。一般的に、ワンコもニャンコも指の数は、前足が5本で後ろ足が4本ですね。でも、先ほどの写真のワンコは、後ろ足の指が6本です。そして、6本中の2本が狼爪です。そういう犬がいるのか!?と驚かれるかもしれませんが、この犬種の場合は、これが普通なのです。不思議ですね。狼爪は、その昔、ゴツゴツした岩場を駆け上がったり、降りたりするときに役立っていたといわれています。前足の狼爪の場合は、今でも、おやつ、ガムを噛んだり、おもちゃで遊んだりするときに前足で物をつかむ際のひっかかりとしての役割を持っています。前足の狼爪を使って、上手にホールドしているワンコを見ます。では、後ろ足の狼爪はどうでしょうか。現代の環境下では、常に平坦な道を歩く生活が普通で、岩場で獲物をつかまえたり、険しい道を駆け上ったりすることもなく、ほとんどその狼爪は役に立っていませんね。ほとんどの犬種に置いて、こうした環境下の長い歴史の中で、後ろ足の狼爪は退化していきました。その結果、今では 生まれつき後ろ足の狼爪がない、後ろ足の指が4本のワンコがほとんどです。仮に、狼爪を含め5本指で生まれてきたとしても生まれてから数日で狼爪の指を切除されてしまうことがほとんどです。それは、ブリーダー側の判断でもあり、もともと血統書を発行するための犬種標準があるので、その基準にあわせて、狼爪をカットしないと血統書を発行してもらえない、つまりは、犬種として認めてもらえない、あるいは、販売できない、販売価格が下がるといったことがおきます。これがまたブリーダーさんたちにとっては死活問題となるため、基準に合わせる形をとって、狼爪を持って生まれてきた子はそれを切除するということになります。で、冒頭の写真の話にもどります。この写真の犬種は、グレートピレニーズです。ピレちゃんは、さきほどの決められた犬種基準において、2本の狼爪を持つことがスタンダードとして望ましい姿とされています。たとえばジャパン・ケネル・クラブ(JKC)、ここでのスタンダートは、「グレートピレニーズの後ろ足には、 2本のしっかりとした狼爪がある。」とされています。そのため、狼爪を持ってうまれてきても残すことになり、長い間、それが守られ続け、今に至ります。はじめにお見せした写真、答えは グレートピレニーズです。犬種によって、指の数が違う。動物によって違うのは分かるけど、犬種によって違うとは。これって、とても不思議なことですね。びっくりですね。衝撃ですね。グレートピレニーズは、親指が2本ある。。。これを読まれた方は、このことを もう忘れないはず。。。ピレちゃんの場合、指が6本あっても異常ではないですよ。
2023年10月19日
-

まるで3兄弟
3頭のお馬さんたち。愛想よくこちらを見ています。3頭お行儀よく並んでいます。似てるから兄弟かと思っちゃうけど、実は 兄弟じゃない。私の方を見つめて離れない。かわいい。「バイバイ、またね。」そう言って 別れを伝えると、一番右の子が「バイバイ、ヒヒーーーン」とお返事してくれました。とってもキレイな歌声で、ヒヒ~~~~~ン って。やっぱりかわいい。
2023年10月17日
-

大量にウネウネ
夏の間 世話していたカブトムシ。ある日、メスがいたケースを観察していて、卵がポツポツ産まれているのを発見しました。白いちいちゃな丸。ハッキリとした白色。すぐに分かりました。ポツポツと周りに3粒ほど見えます。そのうちメスのカブトムシは命を落とし、毎日ゼリーをあげる必要もなくなり、お世話をしてあげることもなくなり、ケースは蓋をしたまま 放っておきました。夏も終わり、さぁ、そろそろケースを整理しようかなと思い、並べてあった飼育ケースのひとつひとつを片付けていきました。土を捨て、、、、、ケースを洗い、、、、、ひとつひとつ進めていくと、、、、あるところで驚きの光景が! ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ケースの蓋を開けたらこうなってました。いやぁ~まぁ~驚きです。あまりにもびっくりしすぎて一瞬フリーズしました。目の前で何が起きているのか・・・思考が一瞬止まりました。た・た・た・た・た・大量のカブトムシの幼虫がいました。しかもそれなりにもう大きいです。このケースの中で自分が知らないうちにさっきの卵から孵化して育っていってたということになります。まさかこうなるとは予想していなかったですが、卵を見つけてから 1ヶ月ほどでこうなりました。びっくりですね。みんなウネウネ元気にしています。しかし、ここで気付いて本当によかった。幼虫の周りは、全部 幼虫たちが排泄したウンチです。全てウンチです。この黒い粒々全部、ウンチです。全てウンチ。エサがちっともありません。このままだと幼虫が死んでしまうところでした。すぐに幼虫を救い出し新しい、広いお家を作ってあげました。数にして 20匹ぐらいいるでしょうか。なんのへんてつもない普通の小さな飼育ケースからはじまり、1匹のカブトムシが産んだ卵からまさかこんなにたくさんの幼虫が孵化するとは思ってもいませんでした。ここからの成長、また楽しみに観察してみたいと思います。
2023年10月15日
全1967件 (1967件中 1-50件目)
-
-

- (o>ロ<)o多頭飼いのダックス大好…
- みるの旅立ち
- (2025-09-26 14:59:18)
-
-
-

- M.シュナとの生活♪
- メイの命日にハイビスカス メイの意…
- (2025-01-27 21:53:40)
-
-
-

- 愛犬との今日の出来事
- モアナ (+難易度5、ヒルトン小田原…
- (2025-11-29 00:02:18)
-








