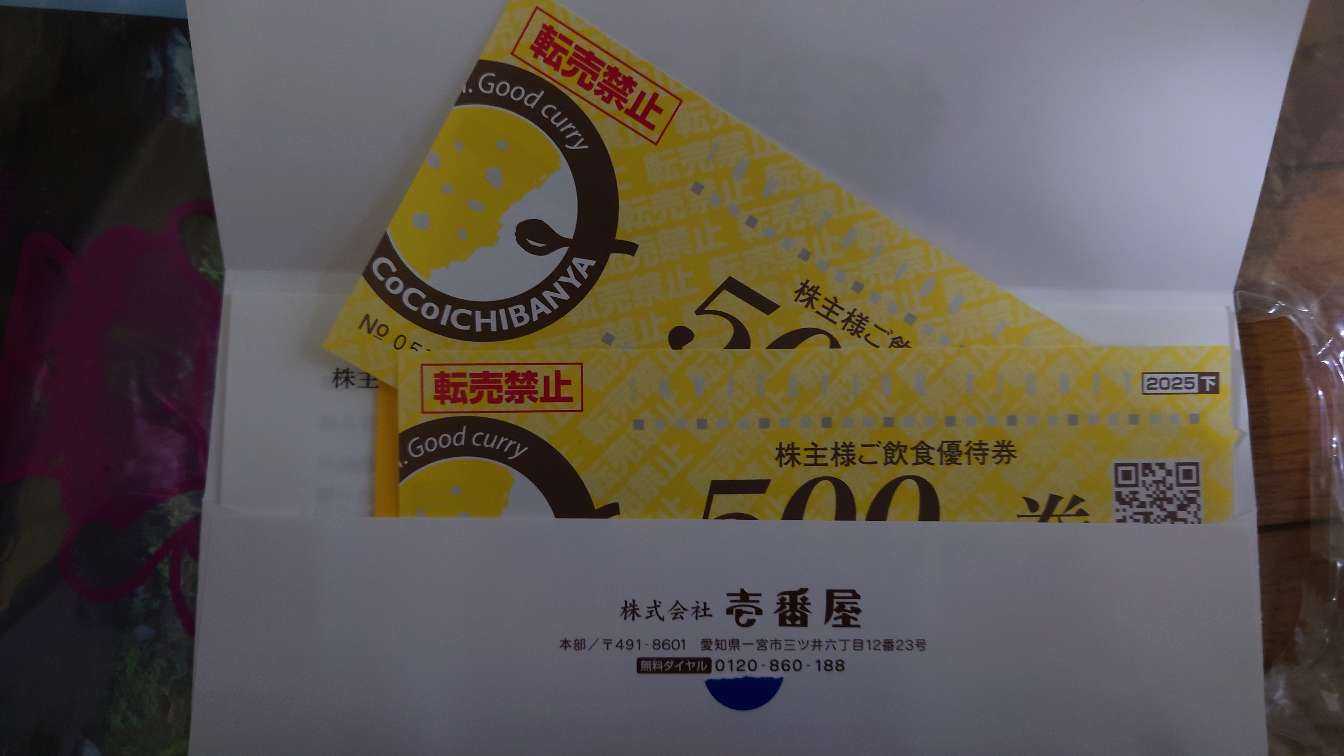2009年02月の記事
全51件 (51件中 1-50件目)
-
老老看護
高校時代の知人の妹さんから、私の同級生夫婦が老老看護で共倒れするのではないかという心配のメールが入った。看護されているお母さんが息子(友人)以外の看護を嫌がるとか、看護する夫婦もお寺ということもあって体面を気にするところもあるのか、他人の手も借りずに2人で看護をしている。そのあげくは、2人とも限界にきて共倒れしそうだという。よその問題に口出しするのは難しく手をこまねいています。厚生労働省の2007年国民生活基礎調査結果では、親族が同居して在宅介護を行っている世帯での老老介護(65才以上の人が高齢者を介護)の割合が推計47.6%と、約半数に上ることがわかりました。なお、介護する側の年齢を60歳以上とした調査ではなんと半数以上が「老老介護」であるという結果が出ました。高齢の夫婦や親子において妻が夫の介護を、息子が母の介護というケースなど様々なケースがあり、家族が共倒れする危険性や介護疲れによる心中事件や殺害などもあることから大きな社会問題となっています。
2009.02.28
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
「人生に臨むにあたって大切なことはただ一つ。志を立てることだ」と昔の人は言ったが、サラリーマンにこそ「なぜその仕事につき、何を実現したいのか」という志を持って欲しいと思います。なぜなら、現在では一つの企業が世の中に及ぼす影響は計り知れず、高い志を持って仕事を「志事」にしていく必要性が高まっているからです。「志」は「武士の心」と書きます。「武士の心」とは「義」であり、「美しくあれ」ということです。「義」の反対は「利」で、どうしても醜くなりがちです。義は儒教の主要な思想「五常(仁・義・礼・智・信)」の一つで、正しい行いを守ることであり、人間の欲望を追求する「利」と対立する概念として考えられました。人のいわば本性である利欲を殺して意志の力で義を引き寄せ、行動目標もしくは正義へのバネとするもので、義を行うのは心情としては我慢を要し辛いことです。しかしながら、義がなければ組織も人間も美しくありません。美しさがなければ、一時的にスポットライトを浴びたとしても、泡沫のようなもので永遠性はありません。これからの世界を動かす君たちには、大きな志を持って欲しいと思います。
2009.02.28
コメント(0)
-
過疎化の図式
昨日 若者と話をして気になり過疎化で検索してみるといろんな問題提起がなされているが、それらに共通することは次のような図式になります。定住就業機会の不足⇒人の流出と高齢化⇒地域経済の衰退・農漁村の荒廃・教育・医療・インフラの崩壊etc確かに農漁業では食えない現実があるが、それ以上に現代人の幸せ感の変化があり、それが現在の農山村や漁村では満たされないために人の流出、特に若者の流出が起きるのだと思います。そこで、彼には図表の4点、「一人ひとりが求める幸せの姿」を明確にし、「その幸せを実現する土俵=島のあって欲しい姿」と「島の現状」を明らかにした上で、その両者のギャップである「問題→課題」の全体像をまず押さえるために、島の人たちと話し合うようにサジェッションしました。このことは何の問題にも当てはまることだが、個人的な問題意識に基づいた部分的な問題を「あーだ、こーだ」と議論するのではなく、まず全体像を明らかにして見える化を図ることが大切です。それを通して意識の共有化ができれば、後は優先順位をつけて実行あるのみです。
2009.02.27
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
ひょっとしたら、死ぬまで一生涯実現しないかもしれないような大きな志と夢を持つことです。そういうものに向かってチャレンジしていれば、どうでもいい小さなことに悩んでいる暇などないはずです。例え若い時には志を持っていたとして、出世もしたいし、家族ができれば生活も大変などと人生設計に束縛され、志もいつかは忘れてしまうのが人間です。薬害エイズを公表した川田龍平さんは、「大人たちに何を期待するか」と問われて、「何のために仕事をしているのかを考えてほしい」と訴えました。厚生省も製薬会社も、医者も学者も、ごく普通の人で悪人でもありません。誰もが、当初は薬や医療を通じて病気の人を救いたいという尊い志があったはずなのに、自利に迷って薬害を隠して多くの人を不幸に陥れてしまいました。政治家だけでなく、志がないサラリーマンが増えた結果、儲けるだけの仕事、給料をもらうだけの仕事になり企業の姿勢も卑しくなってきました。その結果が、公害の垂れ流し、薬害の隠ぺい、食品の偽装表示、リコール隠し、詐欺まがいの商法、贈収賄の横行です。僅かな不正利益で会社を潰してしまったり、数十万円のお金をもらって職を失う公務員も後を絶ちません。
2009.02.27
コメント(0)
-
隠岐の島をご存じですか
今日はサラリーマンを辞めて隠岐の島の活性化に取り組んでいる若者(学生時代に面倒を見た)に会いたいと言われ3時間ばかり話をしました。隠岐の島海士は人口2400人余(最盛時7000人)、町おこしで140名のUIターンがあったそうで、彼らもIターンです。ご多分に漏れず老齢化が進んでいて、お嫁さんを探すのも大変です。私の周りには、志だけで世間なみの生活もできない若者も多いが、まず自分が世間並みの生活ができないことにはどんなに良いことも長続きできないと言っています。地域の活性化が言われるが、最も大切なことは地元の人たちに自信を持たせることだと思います。そのために、自分たちが築いてきた誇れるモノに気づかせること。そのためにまず聞きボランティア隊を募って、お年寄りからいろんなことを聞き出してデータベース化することを勧めました。それらを体系化して見える化を図り、それと島外の人の求めるモノとのマッチングを図ることが大切だと思います。一度島まで来て欲しいと言われても、行くだけで1日仕事、その時間がまず問題です。生産物にしても、注文はネットで可能になっても物流をどうするかという問題が立ちはだかります。それが最大のネックになるのだが、マイナスをプラスに転換する智慧が求められます。そんなことを楽しみながら考えてみたいと思います。
2009.02.26
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
人間にとって最も大切なことは、最後は志の問題だと思います。志によって、毎日の時間の使い方、仕事の仕方、対人関係、立ち居振る舞いなどに自ずと違いが現れます。そんな日々の小さな積み重ねが人生を形作っていきます。志が低ければ、志の低い考え方に支配された毎日を送ることになります。逆に、志が高ければ、自分の人生を意味あるものにしようとして毎日を生きていくから、人の心に残る高尚な生涯を後世に残すことができると思います。例えば、金儲けだけが人生の目標の人なら、全てがお金中心に廻り、株や金融、経営など実利的なことは勉強しても、世界の中の日本はどうあるべきか、人はいかに生きるべきかなどということには目もくれないと思います。一方、「生きているのは慈悲や愛のため」というマザー・テレサやナイチンゲール、「何のためでもない法(仏法)のためである」であると言った鑑真などのように、社会のため人類のためなどという大きな志をもっている人なら、自然と人の生き方などに関心が向けられるはずです。経済活動をするにしても、自社の利益だけでなく、地域の人たちや日本だけでなく世界の人たちを幸せにするのだという観点から物事を見るので、不祥事も起こさないと思います。
2009.02.26
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
好きな相手と結婚したらうまくいくかというと、必ずしもそうではないように、仕事にしても選択してからの姿勢が大切です。ジャズダンサーとして押しも押されない第一人者の女性は、踊り始めたころは決してダンサーとしてやっていける体の条件を持ち合わせず、劣等生のレッテルを貼られていました。そのうえ、踊り始めて15年ぐらいたったころ、大きな壁にぶつかって自由に踊れなくなってしまいました。それまでは寝ても覚めてもダンスのことだけで、上手く見せようとか、人にほめられる踊りをしようとしていた。すると、どうしても自分の器以上のものを見せようとする。これでは、ある一定のところまでなら通用するが、それ以上となると通用しない。あるとき、「私は私、どうあがこうと、それ以上の私を見せようと背伸びしても仕方がない。人間、裸になればいいんだ。どうぞ私をじっくり見てください」という心境になり開き直った。そうしたら、スーッとわけもなくその壁が乗り越えられたといいます。私たちは、ややもすれば寝食も忘れて努力すればするほど早く上達すると考えがちだが、血眼になりすぎてもダメで、ゆったりとした精進が大切です。
2009.02.25
コメント(0)
-
生と死は表裏一体
「おくりびと」がアカデミー賞を取り、生と死が話題になっています。私たちは、生まれたからには必ず死にます。ですから、死ぬことに対する恐怖がいつでも人間をとらえて放しません。だが、そんな誰にも分かりもしない明日を恐れてもしょうがありません。「死を恐れるな。恐れるのは死ではなくて、死の準備のないことだ」と松下幸之助も言ったが、死の準備とは生きている間は精一杯生き切ることだと思います。青春に胸ふくらます若人が、きたるべき人生に備えていろいろと計画するのも、これもまた死への準備にほかなりません。若人の生の謳歌は、自分では意識していなくても、よりよく死ぬために、よりよく生きようとする本能の現れだと思います。生と死は表裏一体です。生きる準備、そして死ぬ準備ができているということ、それはようするに死生観の確立ができているということだと思います。長谷川伸さんは次のように言われました。結局、死ぬということと生きるということは同じなんだよ。生きるということは、その者が存在した価値を遺すということじゃないかね。どんな仕事でもよい、世のため人のために役立つことを自分の生きてきた証拠として遺すこと、それが生きるということじゃないか。有名になるとか、財宝を遺すとかいうのではなく、人々の心の中に何かを遺すということが生きるということだろう。それができれば、死んでいても生きているのと同じだろう・・・。この世に存在するものには総て寿命があり、時が来たれば消滅します。それがいつであるかを、くよくよと思い煩うのは愚かなことです。その日まで、自分の花を一生懸命に咲かせればいいのです。そんな、素晴らしい詩が、机の引き出しの隅から出てきました。小さな花であっていい 人の目に触れない花であっていいよく咲いたと神様からほめられるようにこの世に生きている限り 一生懸命努力して花を咲かせたい
2009.02.24
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
さあ、あなたのなりたい姿を思いっきり膨らませ総合的に判断してみて下さい。人間の思いは風船のようなもので、どんどん膨らませることも、小さく萎んだままにしておくこともできます。大きな夢に、諦めずに挑戦し続けることでしか輝かしい人生は開けてきません。大風呂敷でも良いから、大きな夢を描いて自分を創っていくことが大切です。あなたの「やりたいこと」には、どんな才能が必要でしょうか。「やりたいこと」とあなたの「良くできること」が一致すれば、それはあなたのはまり役だから前進あるのみだが、不得手な才能を必要とする場合にどうするかです。完全無欠な人間など存在せず、誰にも得手不得手があります。必要な資質が部分的に欠けている場合は、メインのもの以外であれば、お互いに欠点を補い合い、シナジー効果で1+1が3にも4にもなる相棒を見つければいいのです。長所だけを見つめてそれを限りなく伸ばしていき、決して人後に落ちない優れた能力を獲得することができたら、短所はその人の愛嬌や面白みに変わります。自分のメインとなる資質が、自分としてはあまり魅力を感じない分野に向いている場合は、その分野の意義やビジョンを考えてみて得心することです。
2009.02.24
コメント(0)
-
出会いは神様の贈り物
このところ飲み会が続き持病の腰痛もなかなかスッキリとはしません。でも、出会いは魔力で止められないのですね。今日も、知人のお孫さんがベトナムで知り合って結婚したカナダの夫を連れてくるので東山を眺めながらの飲み会です。昨日観た「ローマの休日」ではないが、出会いは神様の贈り物と思う。そう言えば、次のような詩が思い浮かびます。今日私は友を見つけたそれとも彼が私を見つけたのかあるいは運命、偶然、事件前世の約束なのか私たちは小さな二つの星でその軌道が時の始まりに やがて来る季節に交わるように定められていたのか?その答えは永久にわからなくとも少しも構わない。なぜなら本能が私に教える私たちの友情が 養分を吸い上げて力強く育ってゆくことを友の定義はやさしくないけれどもそれが私にとって意味するものはある人のことを思いいまこの瞬間も再会の日を待ち望んでまた合う日まで日にちと時間を指折り数えることを(小説『エネルギー』より)◆昨日のイタリアの夕べより
2009.02.23
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
誰もが何らかの欠点を持っているが、それはマイナスではなく個性なんだとありのままに受け入れ、そのままで幸せになれる道を見つけることが大切です。例えば、足の悪い人が、足の悪いことを嘆いたり親を恨んでも意味がありません。現実をきちんと受け止め、「自分はスポーツが好きだが、野球やサッカーの選手にはなれない。だがコーチやトレイナー、解説者などにならなれる。そこで、理論を学び、選手の分析技術を身につけて、選手上がりの人とはひと味違ったコーチになろう」などと決めればいいのです。今治西高の曽我健太君などは、事故で膝から下が義足だが、夏の甲子園愛媛大会予選3回戦では3打数2安打で2盗も決めコールド勝ちに貢献しました。前年は救援投手もこなしました。スタンドで観戦するお父さんは、「義足のことをくよくよしていたら今の息子はないと思う。他人に勇気を与えるまで成長してくれて嬉しい」と語ってみえました。自分が自分である証を見つけ、「自分は自分であればいい」と得心したとき、イライラや欲求不満は消えて、心安らかに「明るく、楽しく、心豊か」に命輝いて生きていけます。
2009.02.23
コメント(0)
-
今日も楽しい会が
今日は3時からイタリア料理店を借り切って映画(自転車泥棒・ローマの休日)とイタリア民謡、それにパーティーと延々9時前まで行います。京都のリタイヤー組は70才を過ぎてもお元気で、毎週何らかの名目をつけて飲み会をやっています。そんな会に、若い人たちも顔を出し楽しいものです。京都はお茶屋さんも盛んで、元々サロン文化の地ともいわれ、いろんな人たちが交じり合ってワイワイとやっています。ある女性をたきつけて現代版サロンを目論んでもいるのですがどうですか?フランスのサロン文化は、ルイ14世の時代ヴェルサイユ宮殿から始まり、18世紀になると上流夫人たちがこぞってサロンを開いた。これらのサロンでは自由で批判的な精神が愛され、思想はわかりやすい会話のなかで伝えられていき、フランスのみならずヨ-ロッパ全体に大きな影響を及ぼした。パリのサロンを見たジャン.ジャック.ルソーは、「パリでは女性なしには何もできない!」と語ったように、新しい思想や文化は、女性たちの開くサロンによって生み出され、大きく花開いた。こうした自由の思想は、自由な市民の社会をめざすフランス革命へと発展していく。そんなサロン文化こそ京都にピッタリです。自由な気風が残っていて、あちらこちらで緩い集まりがありワイワイガヤガヤやっています。◆長岡天神の池ノ端にて頑張る若者
2009.02.22
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
自分を良く知るために、自分の特徴をできるだけ沢山書き出してみよう。1.両親や友人たちに聞くのもいいし、性格検査に書いてあることで「うん、そうだ」と思う言葉を抜き出してみるのも良いでしょう。2.欠点をポジティブに置き換えてみる。例えば、ゴーンさんのように「せっかち」→「迅速な行動力」と長所に焦点を当てる。3.自分の好きな人や嫌いな人を思い出し、何故そう思うのかを考えてみる。一般的には、人間は自分に似ている人を嫌う傾向があるので、嫌いな人の性格を観察して見るのも参考になるかも知れません。まず、そうやって何十も書き出してみることが大切です。なぜなら、初めに出てくるものや長所は建前的なものや人聞きの良いきれい事が多いが、一度行き詰まってから出てくるものには本音に近いものが多いからです。次に、人間の性格は思考と言葉と行動に現れ、それらが微妙に組み合わされて、様々な人間の特性は創り上げられていくので、「感情や思考特性・コミュニケーション特性・自己行動特性・対人行動特性」の項目に分類してみて、「結局、私はこんな人なのだ」と短く、歯切れの良い言葉でまとめてみてください。
2009.02.22
コメント(0)
-
渡月橋とエコ発電
今日は腰痛が酷くなり掛かり付けの長岡天神の整体へ行く。長岡天神の池ノ端では梅が満開。若者2人が寒い池の畔でギターの路上ライブ。若いと言うことは素晴らしい。希望が一杯だ。帰りに渡月橋の手前で紅梅の写真と撮る。ところで、渡月橋の照明は小水力発電でまかなわれていることをご存じですか?橋の上流にある堰に落差1.74m、最大出力5.5キロワットの発電機が設置されています。
2009.02.21
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
性格は、その見方や活かし方によって、長所は短所、短所は長所となります。例えば、「勇気」は一歩踏み外せば「粗暴」になってしまうし、「話し好きな人」は人の話を聞かない「自分勝手で嫌な人」になってしまいます。逆に、「せっかち」も見方を変えれば「迅速な行動力」につながり、「わがまま」も「自律性がある」といえます。ようは、それが生きる時と場と状況が問題なのです。日産自動車のカルロス・ゴーンさんは、「集中力や信念の強さ、せっかちなことが自分の特徴だと思うが、せっかちは状況次第では強みにも弱みにもなる。会社が迅速な変化を求められている危機的な状況では強みかも知れない」と言うが、せっかちさが日産を急激に立ち直らせる原動力にもなったといえます。エリザベス女王から有名な化学会社の元重役が勲章を授与されたとき、時の首相だったエリザベス・サッチャーさんは彼の首に勲章を掛けながら、「若いとき、あなたの会社を受験して不採用になったの」とささやいた。会社で調べてみると、「容姿端麗・頭脳明晰」だが「個性が強すぎ協調性に欠ける」として不合格にしていました。だが、彼女は、その強い個性を生かして首相となり、停滞していたイギリスを活性化させたのです。
2009.02.21
コメント(0)
-
死を見つめて考えた幸せ
東京から来た若者との再会が楽しく、昨日もつい飲み過ぎてしまいました。この歳になると、2日続けての午前様は少し堪えます。飲み屋で知り合った同い年の方がガンで亡くなったことを知り、死を身近に感じることが多くなりました。43歳の時に乳ガンを患った奥井さんの次のような投書を見つけました。乳ガンを患い摘出手術を受けるまでは、生と死、人の幸福について考える機会はほとんどありませんでした。今思えば、なんと漫然と暮らしていたのかと感じます。まだ自分に時間が残されているうちに気づいたのは、病になったことによる幸いと言えるかもしれません。誰も死から逃れることはできません。死を見つめることで、人間関係の彩りが鮮やかになりました。幸せとは何かを考えたときにたどり着いた答は、人のために何かをすることでした。自分にどんな才能があり、なにができるかはわかりません。私なりに模索していくしかありません。死を意識した結果、身辺整理をし、不要なものをそぎ落とす。そうすると、物に囲まれて暮らしていると見落としがちになることに気づき、心が研ぎ澄まされ、広がっていくのを感じます。両手で抱えられる物は有限ですが、心を広げて包み込む能力は無限だと感じています。自分の心をどれだけ深く広くのばせるか。それが死と向かい合う私の課題でもあり、楽しみでもあるのです。誰もが死を意識することなく生きているが、それは奥井さんも言われているように、生をも意識せずに生きていることにつながります。私たちも、死を意識することでもっと生を見つめたいものです。
2009.02.20
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
どのような職業に就けるかはIQ(思考力)に依存するが、その後成功するか否かはEQ(感情力)に依存すると言われます。何故なら、仕事とはチームワークが原則で、良い人間関係を創り出すにはEQ度が大切だからです。芥川龍之介も「性格が運命を作る」と言ったが、それは性格がその人の行動に影響を与え、普段の行動がその人の習慣となり、習慣がその人を運命づける体質となるからです。そうやって出来上がった体質(その人らしさ)は、人間の内なる本能的な反応で、どんな方法で強制しても基本的には変えることはできません。意識的に多少は抑制できたとしても、盆栽のように不自然にひねったり曲げたりしていると、必ず何処かで我慢の限界がきて爆発するときがあります。残虐な犯罪も、ある意味ではその一つの現れであるように思います。どんなことでも面白くないときは、それは基本的には自分の気質に合っていないからです。人生を楽しく過ごし、自分の才能を伸ばしたいと思ったら、「私は私」と言えるものを自分自身で良くわきまえて、それが生きる場を見つけることです。
2009.02.20
コメント(0)
-
天体ショー ダイヤモンドリング
このところまた寒くなってきましたね。物書きにとって半ば職業病にちかい腰痛が気になり始めました。行きつけの整体に行けば直ぐ良くなるのですが、なかなか予約のタイミングがあいません。長時間あぐらをかいて酒を飲むのはあまり良くないのですが、昨晩も延々と5時間もおしゃべりをしながら飲んでしまいました。今日も、東京から若者が来るので夕方から飲むことになっています。学生時代にはいつもおごってもらっていたから、おごらせて下さいと嬉しいことを言う。6年かけて大学を卒業し、就職して3年、忘れずに電話をしてきてくれるその気持ちだけで嬉しいですね。ところで月観測衛星がとらえたダイヤモンドリング素晴らしいですね。自然の造形にハッとさせられます。
2009.02.19
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
大切なことは、何処に位置を占めれば1等賞を取れるかを戦略的に考え、自分が重要視される場を自ら創り出すことです。戦略とは、いかにお客さまにとって新鮮な価値を創り出してライバルに勝つかです。それにはどこで戦うか、つまり土俵の選定が一番大切です。あなたの能力を最大限に発揮できて、しかも自分も楽しめる場を探すことが大切です。誰もが狙う場は競争が激しいので、競争者が少ない隙間市場を狙うとよい。能力は、円筒形で【円の面積×深さ】だと考えると分かりやすい。10の能力の人が100の能力の人に勝つには、相手が10の広さのことを10の深さでできるのなら、自分は1つのことに絞り込んで15(同じ10では総合力の高い者に負ける)まで深めればいいのです。範囲を絞り込んで深く掘り下げて専門性を高めることが、凡人が天才に勝つ唯一の方法です。誰もが大学に進むこれからの時代は、なり手の少ない伝統産業や職人の世界もかえって狙い目かも知れません。君たちに大切なことは、「皆で渡れば怖くない」と皆と同じ道を目指すのではなく、「私の前に道はない。私の後に道ができる」オンリーワンの生き方です。
2009.02.19
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
世の中に溢れているものは競争も激しく価格競争になりがちだが、手に入り難いものには高い値段がつくのが世の常で、自分の能力も希少性が大切です。ありふれた能力であったとしても、現代は価値観が多様化しているので、狭い分野に於ける珍しい組み合わせを創り出せば希少性を発揮できます。それが時代のトレンドにあっていれば、非常に貴重な存在となりえます。例えば、英語を話せるだけでは希少価値はないが、英語が話せる計理士や弁護士ならうんと希少性が増し、グローバル化の今日、持てはやされる可能性が高くなります。介護士で栄養士なら、今後の老齢化社会では引っ張りだこになるかも知れません。パソコンができる人はいくらでもいるが、ウェブサイト・デザイナーで、かつITインストラクターができれば希少性が増します。今日のような知的労働が中心の時代では、何らかの意味でコンサルタント的な仕事に就いている人が多いが、専門性を生かして、それを他人に伝え指導する技術があれば希少性が高まり、面白い仕事が舞い込む可能性が高まります。自分のエキスパート・パワーを理解するだけでなく、そうやって組み合わせの妙で希少性を創り出すことです。
2009.02.18
コメント(0)
-
嵯峨野も雪
朝起きたら屋根や小倉山の頂が真っ白。昼間も時々雪がちらついています。2月としては観測史上最高の気温と思ったら一挙に冬に逆戻り。昨日は大覚寺へ散歩で出かけたら昨年より1ヶ月近く早く梅の花が咲いていたのに。正に経済状況と同じで急降下ですね。ところで、労働環境が厳しくなる中で社会保険労務士は大忙しとか。というのも、高校卒業から丸50年が過ぎ、大学に入学したばかりの友が谷川岳でクレパスに転落して死亡したお参りもかねてクラス会をしようと故郷にいるクラスメートに幹事を依頼したら、件の事情で断られました。そこで、クラス会は諦め、気のあった連中だけを花見でも兼ねて集めようかなと思っていますが、桜の見頃を予想するのは難しいですね。今日の桜前線の予想では桜も早そうで、いつ頃にセッティングするかに悩みます。まあ、お節介な私でいつも幹事役をかっているが、時々「はた迷惑なのかな?」と思うこともあります。◆昨日の大覚寺
2009.02.17
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
やりたいことが分からない人は、14歳頃にやりたかったことを思い出して下さい。それが、人生で一番自分のやりたいことである場合が多いものです。宇宙飛行士を目指す角野直子さんは、中3の時にスペースシャトルの事故で女性教師が亡くなったのを見て「宇宙から授業をしたい」という夢を抱き、その夢を実現させるために東大で航空宇宙学を学び、宇宙開発事業団に就職した。宝塚歌劇団月組娘役トップの映美くららさんは、中学の修学旅行で初めて宝塚を訪れ、ロビーの赤い花柄の絨毯を踏みしめた途端に魔法に掛かったように「ここに絶対に入ろう」と決心し、2回目の受験で合格し夢をつかみました。悔しい思いをしたことを思い出してみるのもいいでしょう。悔しかったということは、自分の関心が深いことであり、好きなことにも通じます。やりたいことが明確にイメージできない人は、次のように考えてみて下さい。1.自分の好きなことを列挙してみる(体系化してみると広がりが出てくる)2.好きなことが生かせる職業を列挙してみる3.自分の得意なことと苦手なことを挙げてみる4.それらから総合的に判断して目指すべき職業候補を選んでみる
2009.02.17
コメント(0)
-
人の来るほど楽しいこともなく
70代の先輩から「見返りもないことに、よく一生懸命になれるね」とからかわれながら、若者たちと勉強会をしたりして遊んでいるが、「相手にはありがた迷惑ではないか」と思いつつも自分の生き甲斐のためにやっています。「あんなにやってあげたのに」とか見返りを求めたら続かないが、「来る者には安らぎを、去る者には幸せを」をモットーに、その時々の楽しみと充実感だけで十分という自己満足でやっているので続くのだろうと思っています。人に話すことは、楽しみや生き甲斐だけでなく、話す内容を整理することで惚け防止にもなり、自分の考えをまとめる上にも有効で、そのお陰で原稿がまとまることも多いものです。十分すぎる見返りを得ています。巣立っていった若者も多く、時折思い出して訪ねてくれる若者もいるが、それは余禄の楽しみです。バレンタインデーには、アメリカに渡って研究生活をしている女性博士からグリーティングカードも届きました。昨日も、東京で働いている若者が、リクルートのために卒業校に来るので夜に逢いたいと電話が掛かってきた。学生時代には、嵯峨野の我が隠れ家にも泊まっていったことのある若者で、初月給で酒器を贈ってくれたこともあります。彼の成長を見るのが嬉しくもあり、楽しみでもあります。今の時代にリクルートに熱心なことは良い会社の証拠とおだて、シンポジュームを心待ちにしています。この歳になると、何かをもらう喜びよりも、人が訪ねてくれるほど楽しいことはありません。人は人の中で生きている、そう思うこの頃です。
2009.02.16
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
人は生き甲斐を求めてどの世界でなら1等賞が取れるかを測り合いながら生きているとも言えるが、自分が好きなことが一番1等賞をとり易い世界です。「何でもいい、とにかく好きなことを見つけることだ。何かが好きであるということは、すなわちその人の才能なのだ。まず好きなことを見つけ、自分の特徴をつかむ。それが人生で自分を生かす道に繋がっていく」とサントリーの鳥井道夫さんも言われたが、心から好きでやりたいことならどんなに苦しくても頑張り通す力も湧いてくるし、それが運をも呼び込む原動力となります。知人の娘さんである矢井田瞳さんは、「小さい頃はスポーツばかりしていたが、家に帰れば両親の聴くレコードを繰り返し歌い、街を歩けば看板にメロディをつけて遊んでいた。想像したり物を作るのが好きだった。スポーツばかりしていたけど、いま思えば音楽が好きだった。19歳の時にギターを弾いている友達を見て、自分もできないだろうかと思い、ヤマハの1万円のギターを買った。自分なりにギターを触っていたら、1カ月ほどで有名な曲が何曲か弾けるようになり、気がつくと聴いたことのないメロディを歌っていた。そんな風に、誰かに聴かせるわけでもなく自然と歌を創るようになった」と言います。
2009.02.16
コメント(0)
-
街の気質
暇に任せて森毅さんの古い本を読み返していたら、一言で東京、大阪、京都を表すとしたら、東京は建前の町、大阪は本音の町、京都は趣味の町で、サロン的ネットワークを伝統としている街であると言う。京都はさしあたり軽いノリで趣味的なアイデアの始まりを提供する町で(ロックやノーパン喫茶も京都発祥)、大阪はその趣味的なものを商売にしてしまい、東京でスタンダード化されて各地に発信される。京都は暮らしにくいと言うが、それは京都人になろうとするからで、京都人の仲間になろうなどと考えると難しい街ではじき飛ばされてしまう。だが、社交性に富んでいるから「ちょっと軒先を貸してもらってます」と、よそ者として暮らすには住みやすい街である。あちらこちらに気楽な集まりがあり、サロン的に酒も飲みながらワイワイガヤガヤとやっている。狭い街だから、どこに顔を出しても知った人がいるが、気軽に集まりをハシゴすることもできる。また、東京人は見せる側だし、大阪人は見られる側とも言う。つまり、東京人は建前の世界が大切だからいかに自分を賢く見せるかに腐心し、自分がいかに気分良く体験を喋るかに重きを置いている。他方、大阪人はあほさ加減をうりにした吉本流の乗りで、聞いてくれる人がいかに楽しんでくれるかを考えるというわけだ。気楽に生きるには、始めにあほさ加減を見せる大阪流に限る。あほやと思っていたら案外賢いとこもあるやないのと評価が逆転したりするが、賢さが先だとちょっとドジっただけでもがっかりされてしまう。これはTVのクイズ番組を見ればよく分かる。
2009.02.15
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
3.発信能力 表現力ともいえるもので外へ発信する能力です思考したモノを、図形・記号・概念・行動で表現して発信する能力で、直接自らの身体を使って表現する場合もあれば、工芸品や文書、絵画、音楽などの産出物で表現する場合もあります。文章表現力、図形表現力、映像表現力、話術、リズム表現力、舞踊などの仕種による表現力、様々な物を創り出す手業、システムやゲームなどを創り出す構想力、スポーツなどの肉体的能力、教育や人を感化する指導力、管理監督や命令などの指揮力、販売やサービスなど親密な人間関係を作る力などです。少し難しい表現になったが、あなたにはこの三つの要素を組み合わせた意外な一面(例えば、一度見たり聞いたりしたことは忘れず、それらを独自の視点でまとめあげ、言葉や絵などで表現するのが得意な人もいるだろう)が隠されているはずです。そういう才能に目覚めさせ花開かせるのは、「自分には何かが秘められているはずだ」と求め続ける情熱です。できるだけ多くの感動体験をする中で、「私にもこんな能力があったのか」と気づいて欲しいものです。
2009.02.15
コメント(0)
-
お経は分からない
キリスト教などでは唯一絶対の神に救いを求めるが、釈迦は絶対の存在を認めなかったから、そこに信仰の対象というものがなく、すべてを任せれば救ってくれるという者はどこにもいない。釈迦自身は普通の人間であったが、常人よりも優れた智慧があって、超越者のいない世界で、生の苦しみに打ち勝つ道があることを独力で見つけ出し、それを私たちに教えてくれた。だから、私たちは釈迦という人物を信仰して「助けて下さい」と祈るのではなく、釈迦が説いた道を信頼して自分で歩んでいくのである。つまり、仏教の「信」とは信仰ではなく信頼なのだ、と花園大学の佐々木閑氏は言う。それには納得なのだが、お参りがあるたびに、あの意味の分からないお経を長々と聞かされるのにはウンザリする。意味が分からないから、皆、隣と久しぶりの再開に私語が弾む。お参りの意義は、普段会う機会が少なくなった親類縁者が久しぶりに集うことにあるだけと思いたくなる。日本には数千万人の仏教信者がいると思うが、どれだけの人が釈迦の素晴らしい生き方に対する教えを理解しているだろうか。仏教家の人たちは、もっと釈迦の教えを誰にでも分かる言葉で語って欲しいものだ。仏教の教えを簡単に言えば、中道・縁起・四聖諦・八正道の4つの真理にあると言われる。「中道」(ちゅうどう=何事も両極端はいけない。ほどほどがよい)「縁起」(えんぎ=親がいなければ子は生まれないように、物事には必ず原因があって結果が起こる。原因となるものに対して他の何かが色々な形で縁となって働きかけをし、その結果に変化が起きる。生まれたものもやがて死ぬ。若者もやがて老いる。愛し合う者たちにもいつか別れが来る。これは人間の多くの苦しみを生み出す原因である。このように物事はお互いに関係しあっている)「四聖諦」(ししょうたい)・「八正道」(はっしょうどう)は2月9日のブログ参照これらの修行を積むことによって煩悩をなくし、結果として苦を克服し、明るく楽しく生きることができると教えます。◆ひな祭りも近づいてきましたので京都国立博物館所蔵のお雛様を当分載せます
2009.02.14
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
能力をどう定義し分類するかとなると意外と難しいものだが、すべての行為行動は、何かをインプットして、中間で何らかの変換行動を行い、その結果として何かをアウトプットするプロセスそのものです。そこで、私たちの能力も受信能力と思考能力、発信能力の三つに分類してみました。1.受信能力 視覚・聴覚・味覚・触覚・嗅覚・感覚の六感の働きです例えば、物の真贋や美的なものを見極める、微妙な音を聞き分ける、微妙な味の違いがかる、触っただけで何ミクロンの差がわかる、臭いを嗅ぎ分ける、人情の機微が分かるなど様々な能力があります。それは、認知したモノと記憶しているモノとを評価(比較・選別・判断など)して判別する力の賜物です。2.思考能力 受け取った情報を分析し加工する能力です理解力、記憶力、体得力、認識力、処理力、洞察力、判断力、規則性を見抜く力、創造力、応用力などさまざまな思考能力があります。思考するときの特性、たとえば直観的か倫理的か、分析的か演繹的か、現実的か夢想的か、保守的か革新的か、目先的か長期的か、計画的か臨機応変か、逡巡型か即断即決型かなど性格的なものも、一つの能力と見なせないこともありません。
2009.02.14
コメント(0)
-
故郷の街も寂れて
故郷、四日市駅前の商店街を歩いてガックリ来た。休日なのに人がいないのです。各地で商店街の衰退が言われて久しいが、これほどとは思わなかった。NTTデータ研究所の調査によると、中心市街地が衰退している理由について「商店街などの個人経営の店舗に魅力がないため」(45%)や「郊外のショッピングセンターのように大規模な無料駐車場がないため」(42%)と商店街の魅力や大規模無料駐車場が不足していることに問題があると思っている人が多い。「この傾向は地方都市圏で住む人や高齢者ほど多く、とりわけ商店街の衰退は地方都市圏の高齢者にとっては深刻な問題とか。確かに、行ってみたいというコンセプトの店も少ないですね。自分ならどんな店に行ってみたいか、どんなときに楽しいか?そんなことを考えることもなく、漫然と店を構えているように思います。自分自身が楽しい、ワクワクする。そんな店なら、お客様も行ってみたくなるはず。まず、自分自身が楽しめることが大切ですね。その姿を見て、お客様も寄ってくるのだと思います。
2009.02.13
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
自分の心の奥底をじっくりと見つめて、自分の性格や能力上の長所短所に気づき、まずは良いところも悪いところもひっくるめた丸ごとの自分を好きになることです。それができた人は、世界一のお金持ちよりも心豊かなはずです。次は、その中で自分が勝負すべき物を見極めて徹底的に磨き上げることです。阪神のアリアス選手も、「僕は、ベースボールを始めた時からバッティングが大好きだった。人にはいろんな能力がある。スローイングに秀でた人もいれば、打つことに素晴らしい力を発揮する人、走るスピードが他の人より早いとかね。その能力を最大限に生かすことが大事だと思うんだ。プロに進みたいと思ったら、その能力に磨きをかけて、誰にも負けないまで伸ばすことが近道かな。誰にも何らかの能力があるんだから、一生懸命に努力して欲しい。僕も、今でももっと巧くなるように能力を伸ばしているよ」と言います。自らの天分を十二分に発揮できるところに、人間としての深い喜びと生き甲斐が生まれます。隣の目など気にせず、隣の人の役を演じたいなどと色目も使わず、自分にとってのはまり役を見つけて、その役が最も映えるように死ぬまで工夫し続けることです。
2009.02.13
コメント(0)
-

日本人は奇数(非対称性)を好む
親父の37回忌を切っ掛けにして、お参りは何故奇数が多いのか気になっていましたが、何気なく手に取った本箱の「宇宙の意思」という本を持って長距離バスに乗りページを繰っていたら手がかりがありました。西洋の二元論(物質と精神を別のものとみなす)の考えは対称性の概論を生み、対照的な数偶数をもってすべての本質を考えたが、東洋の一元論(物質と精神は不可分な存在ですべてに神が宿るなど)では非対称性を好み奇数を重視したそうです。俳句や和歌、七五三の祝、一本締めや三本締め、初七日、三回忌、七回忌・・・三七回忌を始め、庭園や建築、書画なども非対称性を好み重視したようです。円も直線の両端をつないで一つにしたもので矛盾はないとか。これも一つの見方かもしれませんね。それはそれとして、京都駅前に醍醐寺五大力さんで2月23日に行われる力比べの餅が飾られています。五大力菩薩とは、三宝と国土を守護する5人の大力のある菩薩様のことで、金剛吼(こんごうく)、竜王吼(りょうおうく)、無畏十力吼(むいじゅうりきく)、雷電吼(らいでんく)、無量力吼(むりょうりきく)の5菩薩をいいます。力比べでは、女性は90キロ(1俵半)、男性は150キロ(2俵半)の餅を持ち上げて持続する時間を競い、勝者には上の餅が与えられます。一度、ご覧になってはいかがですか?五大力から連想して五大という言葉が気になっていたのですが、件の本にそのことも書いてありました。よくお墓に行くとお塔婆が立ててあり「地水火風空」と書いてあるが、これが五大です。「大」というのは要素のことで、「地大」=肉体の要素、「水大」=肉体の中の水=水分、「火大」=肉体の中の火=熱、「風大」=肉体の中の風=呼吸、「空大」=以上の4つが集まって肉体の中の成長を促すことを表すようです。そして、地の要素で帰してやるのが土葬、水の要素で帰してやるのが水葬、火の要素で帰してやるのが火葬、風の要素で帰してやるのが風葬だそうです。日本では昔は土葬だったが現代では火葬ですよね。まあ、何となく変なことが気になるたちなのですが、多少スッキリとしました。
2009.02.12
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
魚に木登りを、猿に速く走ることを、馬に泳ぐことを期待するから上手くいかないのです。一人前になるとは、魚は魚なりに、猿は猿なりに、馬は馬なりに、自分に備わった個性を全うすることだと思います。大切なことは、ありのままの自分を受け入れ、変えることのできないものを冷静に受け入れる心と、変えることのできるものを変える勇気、そして、変えられないものと、変えられるものとを見極める知恵を持つことです。あなたは、変えることのできないものを変えようとしてイライラしていませんか?生まれてくる場所も、親兄弟も、境遇も、才能や性格も、自ら選ぶことはできません。そんな宿命を港とし、自らの命をそこに浮かぶ船とすれば、その後何処に出航するかは自らの意志次第です。つまり、自分の人生はいかようにも変えることはできます。自分が自分である証を見つけ、それを手放さなければ、人生は絶対に裏切らないはずです。そうやって、「自分は自分であればいい」「貴方は貴方であればいい」と悟ったとき、イライラや欲求不満は消え去り、心安らかに、明るく、楽しく、素直な人生が送れるはずです。
2009.02.12
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
だが、能力といっても、何を能力というかとなると難しい問題です。「私は東大でビリだったからノーベル賞をもらえた」とノーベル賞学者小柴昌俊さんが言われたが、テストで測れるのは記憶力などごく一部で、創造力は測れません。記憶は得意だが思考は苦手な人、記憶は苦手でも創造が得意な人、ゼロからの発想は苦手だが情報を編集し直して発展させるのが得意な人など、人間には様々なエキスパート・パワーがありそれぞれに違います。華やかなフィギュアスケートやシンクロナイズドスイミングを例にとってみよう。選手は新しい技の創造はできなくても技能表現が巧ければいい、コーチは自分自身では巧く技能表現ができなくても新しい技を創り出して指導できればいい、審判は自ら何もできなくても優劣を判断できる審美眼があればいいというように、役割によって必要な能力は違います。名選手が必ずしも名監督にはなれないように、自分の能力を見極め間違って別のパートを演じようとすると、幾ら努力しても報われないという悲劇が起きます。だから、自分の能力が何かをよく知ったうえで、それが最大限に生きる場を見つけることが大切なのです。
2009.02.11
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
「一人前の人間とは、各自がめいめい与えられた天賦の才能と力量をあらん限り尽くすことである。自分以外のところに求めるものではない」と新渡戸稲造は言ったが、自分をじっくりと見つめて、「自分にできることと、できないこと」をしっかりと見極め、まず自分の居場所をはっきりと意識することです。では、自分にしかできないこととは何だろうか? それがあなたの命です。◎自分とはいったい何者なのか ◎他の人とはどこが違うのか◎他の誰にも代用できない自分とは何か ◎これなら人に絶対に負けないものとは何かなどとじっくり考えて、どんなに小さなものでもいいから、誰にも負けない一番になれるものを探し出すことです。人から褒められることばかり気にせず、アトランタ・オリンピックで銅メダルをとった有森祐子さんが「自分を褒めたい」と言ったように、自分で自分を褒められるものを持つことが大切です。それは、真の意味での自立であり自分に誇りを持つことにも繋がります。
2009.02.10
コメント(0)
-
法要って何故奇数がおおいのかな?
11日は親父の37回忌があり、久しぶりに明日から田舎に帰ります。親父は、私が結婚した年に81才で亡くなりました。独り者の生活を謳歌していた私も、親父が危なくなり、結婚式くらい見せてあげようと思って結婚を急いだのですが、間に合わず3ヶ月の月命日ということもあり感慨深いものがあります。ところで、法要って何故奇数なんですかね?(50回忌まではみな奇数)そんなつまらないことを思いながら、明日は横浜にいる兄を誘湯の山温泉に泊まろうと思っています。(ですから12日のブログ書き込みは夜になると思います)私は、朝から出かけてついでに御在所に登る予定です。学生時代にはワンゲルをやっていたのでよく鈴鹿山脈に出かけたものです。もう何年も登っていないので楽しみです。ところで、お釈迦様の教えは膨大なうえになかなか難しいのですが、簡単に言ってしまえば心安らかに生きるための方法を次のように説かれているのではないかと思っています。1.苦しみはどのようなものであるかを問い(一切皆苦)苦しみの状態(苦諦)には四苦八苦(生まれること、老いること、病むこと、死ぬこと、憂い・悲しみ・苦痛・悩み・悶えること、憎い人に会うこと、愛する人と別れること、求めるモノを得られないこと)があり、これらすべてが苦である。2.その原因が何かを探り(諸行無常)苦しみが起こるのは集諦(享楽的欲望を求める妄執、個体の生存をむさぼる妄執、生存の滅無を望む妄執など)が原因で、その真因は諸行無常の事実を受け入れないことによる。3.苦しみの消滅とは何かを明らかにし(諸法無我)苦しみの消滅(滅諦)とは、前述の妄執から完全に離脱しえた状態になることであり、そのためには、捨て去り、放棄し、解脱し、こだわりを無くすることである。4.苦しみを消滅させる道(涅槃静寂)を実践することである。苦しみを消滅に導く道(道諦)は、八正道(正しい見解、正しい思惟、正しい言葉、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい気遣い、正しい精神統一)である。なかなか懇切丁寧にノウハウを伝授されているのですが、この当たり前のことを実行するとなると大変なことで、世の中のお坊様方もできていない人がほとんどだと思います。「明るく、楽しく、心安らかに生きる」道を体系的に説かれたお釈迦様も、唯一「死後のことは知らない」と言われているが、今最も人々が求めている「心の平安」を導くでもなく、現在の葬式仏教を目の当たりにすると心寂しいですね。
2009.02.09
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
幸せというものは、必ずしも高い地位や権力、お金などを得たり、その象徴としての大きな屋敷に住んだりすることではなく、顧みて悔いのない生活、確かな手触りをもった人生など、自分をよりよく発揮できたときに味わうものだと思います。だから、60億人の人がいれば、60億通りの幸せの形があるはずです。それを自分自身が納得して心から受け入れたとき、あなたは安らかで幸せな人生を送れるはずです。人間は意思の動物で、結局は「自分がなろうとした人間」にしかなりえないと思います。あなたも、筋書きのない、しかもやり直しのきかない人生のドラマを、ハッピー・エンドにするためのシナリオを作り、どう演じるかを真剣に考えてみてください。1.どういう人間になりたいのか2.どういう生活をしたいのか3.どういう仕事をしたいのかこの三点を自分なりに考え、後は「この道しかない」と自分自身が信じ、大きな自分なりの花を咲かせるまで執念深く続けられるか否かだけです。
2009.02.09
コメント(0)
-
命さえあれば
福岡で開かれた小中学生の弁論大会で「命を見つめて」という作文を読んだ猿渡瞳さんは、その2ヶ月半後、悪性リンパ腫で13才の命を閉じた。その全文を紹介します。みなさん、みなさんは本当の幸せってなんだと思いますか。実は、幸せが私たちの一番身近にあることを病気になったおかげで知ることができました。それは、地位でも、名誉でも、お金でもなく「今、生きていること」と言うことなんです。私は、小学校6年生の時に骨肉腫という骨のガンが発見され、約1年半に及ぶ闘病生活を送りました。この闘病生活の間に、一緒に病気と闘ってきた15人の大切な仲間が次々に亡くなっていきました。心も体もボロボロになりながら、私たちは生き続けるために必死に闘ってきました。しかし、あまりにも現実は厳しく、みんな一瞬にして亡くなって良かれ、生き続けることがこれほど困難で、これほど偉大なものかということを思い知らされました。みんないつの日にか、元気になっている自分を思い描きながら、どんなに苦しくても元気にがんばっていました。それなのに生き続けることができなくなって、どれほど悔しかったことでしょう。私がはっきり感じたのは、病気と闘っている人たちが誰よりも一番輝いていたということです。そして、健康な身体で学校に通ったり、家族や友達とあたり前のように毎日をすごせるということが、どれほど幸せなことかということです。たとえ、どんなに困難な壁にぶつかって悩んだり、苦しんだとしても、命さえあれば必ず前に進んでいけるんです。生きたくても生きられなかったたくさんの仲間が命をかけて教えてくれた大切なメッセージを、世界中の人々に伝えていくことが私の使命だと思っています。今の世の中、人と人が殺し合う戦争や、平気で人の命を奪う事件、そして、いじめを苦にした自殺など、悲しいニュースを見る都度に怒りの気持でいっぱいになります。私の大好きな詩人の言葉の中に「今の社会のほとんどの問題で悪に対して『自分には関係ない』と言う人が多くなっている。自分の見に降りかからない限り見て見ぬふりをする。それが実は、悪を応援することになる。私には関係ないというのは楽かもしれないが、一番人間をダメにさせていく。自分の人間らしさが削られてどんどん消えていってしまう」と書いてありました。本当にその通りだと思います。どんなに小さな悪に対しても、決して許してはいけないのです。そこから悪がエスカレートしていくのです。今の現実がそれです。命を軽く考えている人たちに、病気と闘っている人たちの姿を見てもらいたいです。みなさん、私たち人間は、いつどうなるかなんて誰にも分からないんです。だからこそ、1日1日がとても大切なんです。病気になったおかげで生きていく上で一番大切なことを知ることができました。今では心から病気に感謝しています。私は自分の使命を果たすため、亡くなったみんなの分まで精いっぱい生きていきます。みなさんも、今生きていることに感謝して、悔いのない人生を送って下さい。
2009.02.08
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
とくに、これからの差別化の時代には、自分にしかできない能力、自分が生まれてきた役割は何かを見極めて、それを磨いていくことが大切です。この世には、さまざまな花が咲き、草木が萌え、鳥や虫が舞うから豊かな自然がうまれます。人もまたさまざまだからこそ、豊かな働きを生み出していきます。豊かな進んだ社会とは、画一的な鋳型にはめ込まれたような人間がひしめいている社会ではないはずです。多様性を温かく包み込み、さまざまパーソナリティーが、それぞれの持ち味を生かして百花繚乱と咲き乱れることのできる社会であると思います。そして、それらがお互いを傷つけたりすることなしに共存でき、どのような人間にでも存在理由が認められ、自らの命をアカアカと燃やすことのできる社会です。とかく私たちは、「役に立つか、役に立たないか」(もっと端的に言えば「お金が有るか無いか」)という一律的な尺度で人の価値を測りがちだが、人はそれぞれに深い使命を持って生まれてきていると信じることです。それが、誰もが幸せになる唯一の道だと思います。
2009.02.08
コメント(0)
-
男が消える日?
京都に戦国武将のグッズを扱う店があり若い女性に人気とか。伊達政宗・真田幸村・石田三成が御三家で明智光秀も人気とか。その理由が、自分の生き方を貫いた男らしさにあるらしい。そういえば、草食系男子が増えているそうですね。(雄が消えるなんて放送もありましたね)あなたの周りに、こんな男性はいませんか?・居酒屋で皆がビールを飲む中、1人だけジュースを注文する。デザートも。・「ママとうまくやれる人でないと結婚は困る」と公言する・デートは割り勘。女性とラブホテルに行っても何もしないこともある。・海外旅行に興味がない。遊ぶなら地元で親しい友人とが好ましい。団塊ジュニア以下の年代では、おっとりと穏やか、家族と仲良し、スリムでお洒落、締まり屋さんで女性におごることはあまりない、がつがつと女性を追いかける肉食系ではなく、一緒にノンビリと草を食べる草食系タイプが増えているという。若い男性に車は売れず、嗜好面でも甘舌化と低カロリー化、酒もソフト化が進み(この頃、若者と飲むと梅酒が多いですね)、まったりと家で過ごす男性が増えているという。文学の世界でも、性愛の場面は敬遠され、ハリポタに代表されるファンタジー系が好まれる。そんな彼らは、概して環境意識やワークシェアへの関心が高く、新しい文化を創るはずで、これからの日本が幸せになるヒントがあると言う人もいるが?◆冬景色の桂川(渡月橋の下流)
2009.02.07
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
他人と比べてばかりいて、自分をよく見つめることもせず、「自分が嫌い」とか「自信が持てない」と言っていてもしょうがありません。他人との比較で劣等感を抱いたり優越感を抱いている限り、永遠に幸せにはなれません。生まれてきたままの自分と向き合い、自分を知ること無しには、やりたいことも分からないし、自分が好きにもなれないし、自信も生まれるはずがありません。長所も短所も、善心も悪心も併せ持つのが人間だから、自分の心の奥底をよく見つめて、自分の性格や能力の長所や短所に気づき、それらをひっくるめた自分を好きになること(自己肯定)です。そうすると、自分が愛おしくなるだけでなく、他人をも認める優しさが生まれてくるはずです。そのうえで、ありのままの自分が、どうしたら「明るく・楽しく・自分らしく」自信を持って生きていけるかを考えることです。つまり、自分のはまり役、自分の居場所を見つけることです。そうやってイキイキと生きていれば、自ずと自分も磨かれるし、他人も好きになってくれます。それが、自分の人生をキチンと生きると言うことであり、真の自立ではないでしょうか?
2009.02.07
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
英国人ファッションデザイナーのポール・スミスは日本に進出したとき、「日本の女性たちがみな同じブランドのバックを持っている姿は衝撃的だ。異常なことだ。他人と同じでないと不安だから? 購買力を示したいから? なぜ個性的であろうとしないのか。僕らの洋服を制服みたいに着て欲しくない」と言っていたが、日本人には外見だけでなく中身まで他人と一緒でありたい、他人によく見られたいという気風があるように思われてなりません。とくに若い人に共通するのは、自分自身に自信が無いのは致し方ないとしても、無視されたり浮くのを恐れて他人の目を気にしすぎることです。また周りも、仲間からぬきんでていたり、あるいは仲間からチョット外れていたりする人間を同じような鋳型にはめ込もうとしがちです。でも、そんなことをしていたら、自分というオリジナリティー(個性)がなくなって魅力が無くなってしまいます。人と同じなら貴方の存在意義はなく、誰とでも取り替えることのできるロボットと同じです。商品でも個性のないものは値段勝負しかないように、人間だって個性がなければユニクロ化の運命をたどりかねません。
2009.02.06
コメント(0)
-
若者たちと付き合って
昨日は繋がりネットワークを創りたいという若者たちと議論していたが、真面目すぎて内容が面白くないんですよね。この頃では定職にも就かず、NPO活動を志す若者たちも多いが、彼らにはお金を稼ぐということに対する抵抗感も強いように思います。NPOは営利ではできない部分を担うというのだが、自分たちが食えないでいて(未だに携帯代まで親がかり)、何が「幸せで豊かな社会創り」なのかと茶化しています。どんなに良い活動もまず自分たちが世間並みの生活ができるお金を儲けなければ続かないし、本当に人のためになる活動ならお金がついてこないのはおかしいと言うのだが、真面目すぎて机上の理想論に走りがちなのが気になります。また、お酒もあまり飲まず、バカ騒ぎをするでもなく、議論がクールで人間の機微をついたようなアイデアがでないのが欠点と言えます。でエビやイカ、タコなどの形をしたスナック菓子「おっとっと」のネーミングにまつわる裏話には創造性に対する一つの示唆があります。82年、健康ブームに乗って「健康」「自然」をイメージさせるものというコンセプトから、シーフード味が決定し、「それなら魚の形に」となり、商品名は味も形も魚なので最初はオーソドックスな「小さな水族館」でほぼ決まっていた。仕事後の酒の席でも議論が続き、製造ラインに流す1ヶ月前に急遽「なんかな~い」に変更が決まり、パッケージデザインも決まって後はラインに流すだけというだけだった。だが、酒の席で、魚の幼児語「おとと」に、酌をされて溢れそうになってつい口をついた「おっ、とっとっ・・・」をかけ、「酒の肴にもなるし」などとワイワイ言いながら再度「おっとっと」に変更されたとか。真面目に考えることも大切だが、このようにリラックスしたときに出るアイデアにこそ、人間の心をくすぐる生きたアイデアが出るように思います。これは、IT化社会になって何でもネットで済まそうとする現代社会への警鐘ともとれます。
2009.02.05
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
ジェームス三木さんは、ドラマの主人公には二つの条件があるといいます。一つは、ドラマはもめ事から成り立っているので、トラブルを解決する能力がない者は主人公にはなれません。それは、実社会でも同じです。私生活や仕事でも、うまくいっている間は能力や人間性はあまり問題にされないが、トラブルや失敗したときにどう対応し解決していくかで、その人の能力や人間性などの本性が試されます。そこで、生きる力を磨く必要があります。もう一つは、ドラマの主人公は、個性を生かしているからこそ魅力的に見えます。独自の人間観を持っていない者は、ドラマの主人公にはなれません。実社会でも全く同じで、その他の人と同じなら、あなたがそこに存在しなければならない必要性はなく、居場所を確保することは難しいと言えます。私たちには、持って生まれた個性や天分があります。残念ながら、それを変えることはできません。他人の役割を羨ましがり、自分にないものを欲しがって嘆いたり、無理にそれを得ようとして無益な努力を費やしたりするよりも、自分ならではの特徴を見つけ出し、自分ならではの役割に全力投球することが大切なのです。
2009.02.05
コメント(0)
-
もう梅が見頃ですね
朝からの若者たちとの勉強会を終えて、北野天満宮まで梅見がてらに散歩。もう結構花が咲いていて春近しを実感しました。中学生たちが沢山お参りをしていて、もう受験シーズン間近なんですね。菅原道真の御利益があることを願いつつ、ほほえましくなりました。神社の向かい側に粟餅のお店があります。戦後すぐの頃、田舎の我が家でも粟を作っていて懐かしく思いました。でも、食べた思い出はありません。素朴な味がいいが、この頃では結構高いんですよね。
2009.02.04
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
人生は、筋書きのないドラマだとよく言われます。そのドラマにおける主役は、どんな役であろうと自分自身です。その主役を、いかによりよく演じきるかということが、与えられた自分の人生をよりよく生きることにつながります。ドラマには、殿様の役もあれば草履取りの役もあります。人生のドラマにおいても、職業や地位などは実にさまざまだが、それは芝居の役割のようなものであって、重い役とか軽い役という区別はありません。人は顔も気性も違い、好みも違い、素質や能力も違います。人生の役割が違って当たり前です。 人生のドラマで役に軽重が生じるとすれば、その役を自分自身が納得して受け入れ、真剣に演じているか否かによるだけだと思います。大事なことは、自分にとってのはまり役を見つけ、その役の心をよくつかんで真剣に演じきることです。その時、その役者は人生のドラマにおける主人公となります。それにはまず、自分に備わっているもの、与えられているものを見いだして、それを最大限に発揮できる場を見つけることです。それが、あなたの居場所です。そうやって、自分にしかできない生き方を貫き通すことです。それが、SMAPではないが『世界に一つだけの花』を咲かせるということです。
2009.02.04
コメント(0)
-
節分のハシゴ
天龍寺~松尾神社~天山の湯(嵐山温泉)~車折神社と節分巡りの散歩。松尾神社では島根県増田の無形文化財神楽が奉納されていました。NHK朝の連続ドラマではないが島根と京都のコラボもいいですね。途中温泉に入って生ビールとお酒を飲んでいる間に小雨模様に。10キロくらいのいい散歩でした。鬼は外と貪欲と嫉妬、愚痴の3匹の鬼を心の中から追い出せたかな?この頃は淡白になってあまり関係ないが、この3匹を追い出すと心は平安ですね。体重も65キロ台でグー。
2009.02.03
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
どんな仕事に就くにしても、適齢期というものがあります。応用形態は様々だが、天職は35才までに身につけた経験の中にあると言います。サラリーマンにしても、30代前半までに創造性を発揮できない人は一生創造的な仕事は無理とも言われ、35歳頃までに社内で「こいつはできるな」と思われるような業績を上げないと良い仕事は任されず先が見えてきます。ですから、若い間はフリーターをして気ままに生き、自分の適正を見つければ良いという考えは通じません。35才が一般募集による年齢制限の上限でもあり、これという専門能力を持っていない限り転職も難しくなります。人付き合いにしても、人生のサポーターは35才迄の出会いの中にあります。つまり、君たちの一生も先は長いようだが大体35歳で決まると考えて良いと思います。結局、20代における貴方の方向付けと精進によって貴方の一生は決まるともいえます。だから、時間があるようであまり無いのが現実です。人生とは選択の連続で、その集積が人生です。ifは「もしあの時に、あれをしておけば」と、過去形に使っても意味がありません。「いま、もしこれを選べば」と未来に向かって何かを選びとり、それをやり続けることです。
2009.02.03
コメント(0)
-
浅間山噴火
浅間山を眺めながら暮らしている親友から、レベル3の噴火があったとメール。天明3年(1783)の大噴火でできた鬼押し出しは有名です。ライブカメラもあり http://www.town.karuizawa.nagano.jp/ctg/01804450/01804450.htmlところで日本には火山が幾つあるかご存じですか?日本には108もあり、富士山も過去2千年間に十数回の大噴火(1707年に最後の大噴火)があり、以来未だに火山らしいですね。自然の力と息の長さに比べたら、人間なんてちっぽけな存在ですね。それなのに、くだらないことでいがみ合っているのだからやるせないですね。
2009.02.02
コメント(0)
-
第1章 さまざまな花を咲かせよう
青春とは、来たるべき船出へ向けて準備を整える修行の時代だと思います。空海は、18歳の時に讃岐の国から京の都に出てきて大学に入ったが、24歳の時にドロップアウトして私度僧(自分勝手に頭を丸めた僧侶)となり、ボロをまとって各地を回る修行僧となった。やがて、31歳のとき無名の僧として遣唐使船に乗り込むまで、どこで何をしていたかは明らかでありません。だが、唐に滞在すること1年余、わずか2カ月前に密教の本山青竜寺に現れた日本の留学僧空海に密教の最高の地位にあった第七祖恵果大阿闍梨は、永い間修行している千人余の中国人門弟を差し置いて密教のすべてを伝授した。それによって、空海は当代随一の高僧となった。それは、青春の空白時代における修行の賜物だったと思います。「中途半端にやってもダメ。必死に全力疾走で勉強する。吸収できる年齢は35歳くらいまでと考えて自分を追い込んでいかないと本物の力にならない」と言う建築家の安藤忠雄さんは、19歳の1年間は朝9時から翌朝の4時まで机に向い、建築はもちろんインテリアデザイン、グラフィックデザインも含めて造形に関する総てに取り組んだそうです。
2009.02.02
コメント(0)
-
節分になぜ豆をまくの?
昨日は若い人とシンポジューム(お酒を飲みながらチョット真面目な話をする)を行いましたが、自分のキャリアを次の世代に伝えていくことは有意義でもあり楽しいものです。ところで、節分も近く昨日も手土産にお豆さんを戴きましたが、節分にはなぜ豆を蒔くのでしょうか? 平安時代には、節分の日に翌年の恵方にある家に宿を取るという風習があったが、室町時代頃にはこれが簡略化され、家の中の恵方にある部屋に移るというようになったそうです。この際、あらかじめ新しく移る部屋の厄払いの意味でその部屋に豆を撒いた(穀物には霊が宿っていて厄払い効果があると信じられていたようです)と言います。これが現在の豆まきの始まりだそうです。でも、この歳になると食べる豆の数が大変ですね。 淺田真央チャンが「歳は取っていくものですけど、見た目はそれより若く見えるのが目標です。いかに若々しく見られるか。でもまだ18才ですよ」と言っていたが、年よりも若く豆でも食べますかね。写真は送られてきた美山の冬景色です。
2009.02.01
コメント(0)
全51件 (51件中 1-50件目)