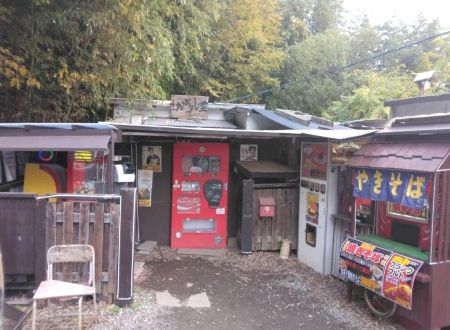2009年12月の記事
全47件 (47件中 1-47件目)
1
-
断食もあけました
断食3日目 塩を一つまみ入れた白湯を飲むと、ほんのりと甘さを感じます。少量の野菜サラダの朝食。舌の敏感さが戻り、自然の恵みの美味しさを味わいました。今朝の新聞には、世界の食糧危機の問題が取り上げられていました。それなのに、日本の農業の実情と私たちの食に対する姿勢は・・・今日で09年も終わりですね。この1年は貴方にとってどんな年でしたか?私にっては、今年も色んな出会いのあった楽しい年でした。昨日は、青蓮院塔頭の尼さんからお酒が届きました。春仁お出会いして、夜話の会をお勧めして続けてきました。お陰で、それをご縁にいま掲載中の釈迦の智慧を纏めることができました。兄弟や甥っ子たちにCDで渡したが、12月に入って88歳の姉が首の血管が詰まって倒れ、生老病死に対する処し方も現実のものとなり、不思議を感じています。高松のみかん園の息子さんからは、餅つきをしましたとのメールが入りました。懐かしいな。この青年は、12月に入ってから知人の紹介で訪れてくれました。市場には出せない小さなミカンが9トンもあって、畑で腐らせるのは勿体ないので青山国連大学前で売ったり利用方法を考えているという。そこで、知り合いたちにメールで年末チャリティ産直を訴えたら多くの方が協賛してくれました。27日にも青春18切符で東京からの帰省の折に立ち寄ってくれ、酒を酌み交わしながら話が弾み、高松には切符の有効期限24時ギリギリに着いたようです。長年、中学で支援学級の先生を務めている熊本の女先生からは便りが届きました。今年23歳になる教え子から「始めてボーナスをもらいました。だから、今日は私が払います」とお昼ご飯をご馳走になった便りが入っていました。私も経験があるが、先生にとって最高の喜びだと思います。そう言えば、福岡銀行の仕事で博多に行った折に、熊本まで足を延ばし、生徒たちに話しをしてから何年が経つのだろう。彼女とは、高崎の先生(「いい話しのおすそわけ」を読んでお手紙を戴き、その後お付き合い)の紹介で知り合ったが、来年はお母さんを連れて京都に来てくれるという。そういえば、4女相当の娘さんも、この高崎の先生の紹介で知り合ったのでした。学生時代に私の家をよく訪ねてくれた男性からも、来年結婚しますという電話が入りました。仙台出身の男性で、今は東京で勤めているが、友人の結婚式で両者の世話人を務めた二人が結婚するようです。お相手は青森の女性とか。式は故郷で挙げるみたいで、遠方だから来ていただくのも大変だから、機会を見つけて二人で京都に来てくれるとのこと。その後輩たちにも、11月、12月と志や就活の話しをしました。学生たちと付き合うようになって10年が経つが、初期に付き合っていた学生たちとの勉強会で知り合った若者の依頼で商店街で話しもしました。一つの縁が次の縁を呼び、そうやって広がっていく人との輪。それが、嵯峨野の夢前案内人を名乗っている私の今の喜びです。来年は「あと5年の命」と思って生きてきた2期目の最後の年です。「花の下にて春死なん」と願っている私ですが、取り敢えずは来春の桜が楽しみです。いや、その前に、忘年会が終わったと思ったら新年会の案内が幾つも届き、16日などは3つも重なっています。名古屋からは同期会の誘いもあるが、ヒョッとすれば初めての熊の肉が食べられるかもしれない狩猟が趣味の人(忘年会で知り合った)からの誘いに心が動きます。来年も楽しい出会いがありそうで、お迎えが来るその日まで「明るく、楽しく、自分らしく」心豊かな日々を送りたいと思っています。「太田さんは色んな知り合いがいて羨ましい」とよく言われるが、何も私が特別なわけではありません。誰にも出会いがあります。何かの縁で出会った方に、自分の時間をチョット割いて「どうしたら喜んでくれるだろうか」と相手の気持ちになってお付き合いするだけで良いのです。誰にも唯一平等な「1日は24時間」という時間をどう過ごすか、それは貴方の心の持ち方次第です。有意義にお使い下さい。この1年有難うございました。毎日、休まずに5本のブログやメルマガを書いてきたが、来年はブログも6年目に入ります。凡才だが、「続ける」ことが私の長所だと思っていますので、来年も宜しくお願いいたします。オーロラのライブ写真でこの1年を締めくくりたいと思います。良いお年を!
2009.12.31
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
釈迦は「人は時に我見・偏見に囚われて邪見に陥り、白いものを白と言わずして黒と言い、邪であるものを邪であると言わずして正しいと言い、道理ならざるものを非道理と言わずして道理であると言いがちだが、正しい見解・正しい見方をすることが大切(正見)とか、正しき見方をし、正しく考えるならば自ずと正しい言葉となるはずだが、人はとかく他人の悪口を言いたがり、二枚舌を使って要領よく振る舞ったり、あらぬことを真実のように語ったり、くだらぬことを付け加えたりする。正しい言葉(正語)を使え」と説いています。私たちは、外界のすべてをありのままに認識しているわけではなく、無意識に「情報を取捨選択」して取り入れ、自分なりに解釈して「自分の見たいように」見ています。例えば、一緒に同じ話を聞いたとしても、人によって心に響く言葉が違い、インパクトを受ける場面が違い、受け止め方が違う場合がよくあります。それは、聞く人の性格、経験知の差、興味や関心、価値観や信条、損得勘定や立場などによって、受け止め方が変わるからです。ときには、聞く人のその日のコンディションによっても受け止め方が変わる場合さえあります。
2009.12.31
コメント(0)
-
年末の断食も二日目
例年は年末年始にかけて行う3日断食も今日は二日目、何も食べない日です。ダイエットを目的にプチダイエットを行う人もいるが、私の場合は「食べなくても大丈夫」、止めようと思えば人間の根源的な欲求である食でもアルコールでも自分の意思で止められるという自信を持つためと言えば格好いいが、主として年3日の休肝日つくりが目的です。効果はてきめんで、毎朝鼻に水を通すのだが、酒を飲み過ぎると鼻の毛細血管が破れて鼻血混じりの鼻くそが出るのだが、断食にはいると鼻の通りが良くなり鼻くそも出なくなります。全く、爽快そのものです。それなら、毎週でも休肝日を作ればいいようなものの、身体に良いことをして長生きしたいとも思わないから厄介です。夏に足の痺れが出て、医者に「内臓には問題ないが、週1度は休肝日を作っては」と言われたが、「車はガソリンで走るが、私はアルコールで走ります」というほど、この50年間毎日酒を飲み続けてきました。まあ、お迎えが来るまで止める気もないが、今後は年に2回は断食をやろうと思っています。いずこの空の下に生まれても命の泉は清らかに流れ他の何物にも代え難く時とともにすぎ去りゆく今日一日は愛すべき身命である今日一日は尊ぶべき重宝である (南禅寺 日々是好日より)良い年末年始をお迎え下さい
2009.12.29
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
私たちはよく、「この目で見たから、この耳で聞いたから、間違いがない」と言いがちです。でも、本当にそうでしょうか?私たちは、目や耳で見たり聞いたりするのではなく、自分の心を通して物事を見たり聞いたりしています。目(耳も)は鏡のようなもので、それ自身はありのままの姿を映しているのだが、そこに意識が働くことによって見え方が変わってきます。その心が問題です。「惚れた目で見ればアバタもエクボ」に見えます。それが、アバタはアバタに見えたとき恋は冷めます。男は美人に弱いが、どんなに美しい女性でも、その身体を内側から見れば大小便の器にすぎません。つまり、自分の心が「どう見たいか」によって見え方が変わってきます。主義主張、イデオロギーや教義、自分の見解や損得や好き嫌いなどの煩悩に縛られていると本質が見えなくなってきます。自分の見解だけを無条件に「是」としていると、必ず自縄自縛に陥ってしまいます。その挙げ句、真実を見誤ってしまい失敗をすることになります。「自分が絶対に正しい」などと思い込まず、自分の意見にある程度の疑いを持って、人の意見に謙虚に耳を傾けることが道を誤らないためには大切です。
2009.12.29
コメント(0)
-
食と農業を考える
この間から、商店街で話したりミカン農家の息子が訪ねてきたりで、野菜や果物=農業について考える機会が増えました。このブログの読者にも熊本の農家の方が見えるが、農家はどこも若者が減って過疎化が進んでいます。それは、重労働の割には収入に魅力がないことが大きいと思います。人間にとって欠くことのできない食の生産者に魅力がなく衰退する一方では、輸入に頼った日本の食卓は危ないと思います。(食の自給率向上こそが安全保障の要と思うが)農業の一般的な構図は、大半の農家は栽培に取り組むだけです。農協は営農指導をしたり農業従事者に貸付をしたり、農産品を集荷し市場に出荷したりする部分を担う。市場は荷受が競りにより農産品を売りさばき、仲卸業者は市場で買いつけた農産品を小売業者や外食業者へ売り渡す。その結果、農家の手取りは通常で30%台、流通経費が60%台ということになる。そして、農業は気候に強く左右される産業だが、悪天候による不作や好天候による過剰生産荷余りなどのリスクの影響は農家がモロに被り、流通は一定の粗利益を確保することになる。だから、不作の時は値段が高騰する割には、豊作でも市場価格はそれほど下がらず、産地では空しく畑に捨てられ腐ることになる。地域の農協や農家、生産者団体は、歴史的な背景から地域に根ざした展開となりやすく、自分たちが生産した単品をいかに量をまとめて売っていくかというプロダクトアウト的な発想にとらわれやすい。生産地エリア、品目、販売先などを分散させ流通させることによって、リスクを回避をするという発想が少ないために、非常にリスキーでもある。また、商売においては特徴付けが当たり前であるが、農家においては右へならへ的発想で特徴がないため、どうしても価格勝負になってしまう。食の安全、安心への意識は高いが、有機や無農薬、省農薬、認証野菜などにしても、顧客価値は価格との関係で成り立つことの理解が弱く、価格が高すぎて、それほど消費が高まらないという問題を抱えています。【見にくいが図参照 右から こだわりはない(橙色)・同じ価格なら購入(黄色)・1割高までなら(水色)・2割高までなら(青色)・3割高までなら(グレー)・3割を超えても(濃い青)】この辺りのことについては、別のブログで「頑張れ商店街」の中で「人は何故モノを買うか」のテーマで書いていますのでご覧下さい。(ブックマークから入力可)ようは、消費者の求めるモノを、求める価格で、どう作るかという経営的発想が求められているといえます。それは補助金行政では解決できない問題で(補助金漬けの業界は最終的には競争力がなくなりさらに衰退する)、若い人たちが「三方=生産者・販売業者・消費者良し」の精神でスクラムを組んで自ら立ち向かい、(それは決して容易なことではないが)夢のある農業にするしかないように思います。
2009.12.29
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
お釈迦さまは、色眼鏡をかけず、とても晴れやかな世界を生きられた方です。それに対して私たちは、常に自己中心の心という色眼鏡をかけて(我見)世の中を見ており、真実の世界・悟りの世界を知らない危なっかしい存在です。ある高校生は、大学受験がすべてだという世界を生きていました。そういう人は、受験に失敗すると、「私の人生、終わりだ」と思ってしまいます。勝ち組・負け組ということが盛んに言われた時期があるが、勝ち負けがすべてだという世界に生きている人は、とてもしんどい人生だと思います。また、自らの欲望を満たすことがすべてだという世界に生きている人は、人の為に生きることの素晴らしさに気付けない、寂しい人生でしょう。このように、それぞれが自分勝手な世界を創り出して、それに自ら縛られ悩み苦しんでいるのが私たちの姿なのです。だからこそ自己中心の心を離れた、悟りの世界を聞かせてもらうことが大切なのです。悟りの世界は、すべてのものが光輝く世界であり、すべての人生が光輝く(すべての人生に尊い意味が与えられる)世界なのです。そんな晴れやかな景色を仰ぎながら、この迷い多き人生を生き抜いていきたいものです。
2009.12.29
コメント(0)
-
もうお休みの所が多いようですね
このところ忘年会が続き飲みすぎです。(ブログを読んでくれる人もガクンと少なくなり、年末年始の休みに入り、旅に出たり里帰りの人が多いことが推測されます。)昨日も甥っ子の帰るのと入れ違いに、高松のみかん園の息子が東京から高松へ青春18切符で帰る途中に立ち寄ってくれました。私手製のブリ大根で一杯やりながら、これからのみかん園経営について語り合い、高松に24時寸前に着く(日が変わると切符がダメに)普通列車で帰っていきました。若いって言うことは良いですね。そんな間にも嬉しい電話が入りました。同志社の学生時代には良く私の家で飲んだ若者(今は東京にいる)から、来年結婚することになりましたとの報告です。友達の結婚式で、新郎、新婦側それぞれの世話人だった二人がくっついたのだから、「縁は異なもの味なもの」です。仙台出身の男と青森出身の女、今から楽しみです。彼とミカン農家の息子を引き合わせる手配もし、また新しい出会いが起きるのも楽しみです。そうやって次代を担う人たちの縁の輪が広がっていくのが、70歳を目前に控えた年配者の楽しみでもあります。私は、今年は断食を年内に終わらせるため(息子が1日に来るというので)明日から断食に入り、今年1年の身体の掃除も終わりたいと考えています。お付き合い如何ですか?◆宇宙からの写真です
2009.12.28
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
二人の男が仲良く旅をしていて、森を抜けると遠くにきれいなお城が見えてきました。一人の男が、「きれいな赤いお城だね」と声をかけました。するともう一人の男が、「何を言っているんだい。あれは、きれいな青いお城だよ」と答えました。「赤いお城だ!」、「いや青いお城だ!」と、お互い一歩も譲りません。先ほどまで仲良く旅をしていた二人は、ついに喧嘩を始めてしまいました。そうこうしていると、向こうからお釈迦さまが歩いてこられました。そこで二人の男は、お釈迦さまに聞いてみることにし、「お釈迦さま、あそこに見えるお城は赤いお城ですよね」、「いえいえ、あれは青いお城ですよね」と二人は尋ねました。するとお釈迦さまは、「あれは赤い城でも青い城でもないよ。白い城だよ。お前たちは、それぞれ赤と青の色眼鏡をかけているから白い城が赤や青に見えるんだよ」と言われました。二人の男はあわてて色眼鏡をはずすと、きれいな白い城が輝いているのが見えました。その後二人は、また仲良く旅を続けました。この話は、私たちが常にものごとを、色眼鏡をかけて見てしまっていること(偏見・我見)に、気付かせてくれます。
2009.12.28
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
豊かになったはずの世の中で、いったい何を頼りにしたらよいのか、何がほんとうのことなのか、と混乱している人たちが急増しているように思います。そんな私たちに、お釈迦様が示してくださったのは、「いつでも」「どこでも」「だれにでも」通用する“ほんとうのこと”です。「いつでも」というのは、昔も今も変わらずに通用するということです。日本でもインドでも欧米など、どの国のどの町村でも、変わらずにあてはまるから「どこでも」です。人種も性別も年齢も関係なく、仏法にご縁のある人にもご縁のない人にも関係なく該当するから「だれにでも」ということです。だが、そんなお釈迦様の教えを、私たちは「いつか、どこかで、だれかが」というふうにしか聞いておらず、他人事になってしまっています。例えば、人間が老い、病み、死んでいくということは、どこでも、誰でも同じで、身近な人が老い、病み、亡くなっていかれるたびに嘆き悲しんでいます。何回老病死についての話を聞き、どれだけ老病死の知識を身につけても、自分自身の老いや病みや死については、その現実と向き合って正面から見つめることもなく、逃げ腰で日暮らししていることを思い知らされます。
2009.12.27
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
3.如意作意(聞いたことを理に従って考える)お釈迦様の弟子に周梨槃特という弟子がいたが、記憶力が悪く自分の姓名までも忘れてしまうほどでした。難しいことはダメだからと、「三業に悪を作らず(殺生・盗み・邪淫の三つの悪を犯さず)、正念に空を観ずれば(心を清らかにすれば)、無益の苦しみは免るべし(苦しみのない境地に至る)」とだけ教えたが、いくら努力しても覚えられません。そこでお釈迦様は一本の箒を与え、「これで朝夕、部屋を掃除するときに、“塵を払わん、垢を除かん”と言いなさい。それなら出来るだろう」と言われた。毎日、「塵を払わん、垢を除かん」と言いながら掃除をしているうちに、ある時「塵とは何か、垢とは何か。そうだ、こうして掃き集めている塵や垢のことではなく、心の塵や垢のことなのだ」と思い至り、教えを熱心に守って心を清め、遂に悟りを開いたそうです。お釈迦様は、「大切なのは、たとえ僅かなことでも、それに徹することだ」と諭されたのです。頭で聞いただけでは真理をつかむことはできません。理論と実践は両天秤のようなもので、行動の中でつかむことが大切です。だが、私たちは、多くのことを知るだけで満足し、自らは何も実行しようとしません。
2009.12.26
コメント(0)
-
暮れの嵯峨野で独り言
昨日はとても楽しい1日でした。一つは、ミカン農家の息子さんとは何度もメールのやりとりがありました。(迅速な対応を指導したばかりだが、大人たちよ、一時的には嫌われても良いから若者を身をもって指導して下さい。東京の知人の紹介で、たった2時間ばかり話した若者ですが、何か私を動かしたモノがあったのでしょうね? 実は、その知人自身も、よく考えてみると一度あっただけなんですよね。だから出会いは面白い)キメ細かで迅速な対応を若者に教えるためには、こちらが迅速な対応で手本を示す必要があります。そんなことを教えられたことのない若者も、こちらがそれを実践すれば自然と身についてきます。山本五十六の「やってみせ、やらせてみせる」という教訓がよく分かります。そして、「小さな親切、大きなお世話」的な私の思いに付き合ってくれる大人たちがいます。この世の中、まんざら捨てたものでもありません。一つは、23日に同志社で就活の話しをした学生たちからのメールです。何かを感じてくれた学生たちがいたようで、これも嬉しいことです。ここ10年余、学生たちの支援をしてきたが(恐らく社会人になれば忘れてしまうだろうが、「のに」を言わずこちらも忘れることです)、その時、何かを私の話に感じてくれればそれでいいのです。「来る者は拒まず、去る者は追わず。来る人に安らぎを、去る人に幸せを」これがモットーです。チョット格好が良いが、これは自分の精神衛生上のためでもあるのです。自己満足ですから、見返りを求めてはやっていられません。1人でも多くの大人が、そんな気持になってくれれば、この日本も捨てたものでもなくなるのでは?もう一つは、一昨年膵臓ガンで亡くなった友人の奥さんからの電話です。やっと、持ち前の機関銃のような言葉の玉が飛んできました。(半分は戸惑った私がいるが、半分は嬉しい気持で一杯)旦那の書籍や写真の整理をしていて、「これはどうしたら」と問われても返答に困るのだが、捨てがたい気持を誰かに話して背中を押して欲しい気持も分かります。(そう言えば、百人以上いたワンゲル部のリーダーとマネージャーで結婚式には私が司会をしたのだが、奥さんから「貴方たちは2個一ね(二人で一人)」と言われたことがあります)ご同輩型、とくにアルバムの整理は(捨てるのに一番困る)元気な内にしておくのが奥様孝行ですよ。私は、「私の生きた奇跡」という自家製の記録本を作り(1年毎の社会の動きを2ページで纏め、その次の2ページは自分の写真をスキャナで取り込み整理したモノ)、後の写真は捨てました。膨大なコンサルの資料も、この間若い人がもらってくれたモノを最後に整理(整理とは捨てるものなり)できました。後は自分の体自身の整理だが、今度こそ5年更新をせずに、来春辺り「花の下にて~」が現実になれば嬉しいのですが?(そうしたら75歳の先輩から90を覚悟しておけと、今朝もメールが入っていました)なかなか思うようにならないのがこの世。来年もピンピンとしているかもしれません。◆来年は「洞窟を抜けると春だった」を願いつつ
2009.12.24
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
2.正聞(教えを正しく聞く)正しく聞くということは大変難しいことです。我や欲があっては曲解してしまいます。すべてを無にして、その裏にある真理を捕まえなければならません。『正法眼蔵随聞記』には、「道を学ぶ人が教えを聞くときは、よくよく追求して聞き質し、その上にもわからないところは重ねて質問して、疑いのないようにしなくてはならない。質問すべきことを質問しない、言うべきことを言わないで過ごしてしまったら、自分の損害である。師は必ず弟子からの質問を待って、それについて詳しく答えを出されるものだ。自分で分かっていることでも、さらに何度も尋ねてはっきりさせるべきだ。師も“本当によくわかったか”と何度も尋ねて、“はい、よくわかりました”という答えを得て、初めて教えを説いたことになる」とあるが、徹底的に質問をする癖をつけたいものです。正しい教えを正しく聞く、という行為を繰り返すことによって、その行為が、深層心理に新たな種子を薫りたたせることを「正聞薫習」といいます。そして、この新たに薫じつけられた種子が、本来的にある本有種子を刺激し、芽生えさせて成熟せしめ、ついに真理を見抜く智慧を開花させるのです。
2009.12.24
コメント(0)
-
昨日は就活の話しをしました
昨日は同志社の3回生たちに就職の話しをしました。その最初に言ったことは、「企業から見ると、1人採用すると言うことは4億円の設備と同じだ」でした。大企業に勤めた場合の平均的な生涯賃金は3臆数千万円ですが、企業としては最低その1.3倍はかかります。「就活はセールス活動であり、初任給相当の薄型大画面のテレビを売り込むことさえ大変なのに、4億円の価値がある自分をどう売り込むかが面接で、4億円もの商品を売り込むとなれば並大抵のことではないよ」と話しを継ぎました。それには、敵を知り、己を知ることが第1です。細かい話しは省略するが、そこが甘いのではないでしょうか?
2009.12.24
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
1.善知識(良き師に出会う)良き師に出会うためには縁が必要だが、縁は何もしないでも突然に向こうからやってくるものではありません。自分に求める心が必要です。知る人は少ないと思うが、東海道五十三次の宿場の発想は、善財童子が師である文殊菩薩の指示に従って53人の善知識(師匠)を訪ね、道を求め修行して遂に仏の位に入るという「華厳経」の物語からきています。その53人のなかには、お坊さんから政治家、学者、商人、百姓から遊女まで含まれていて、「吾以外はすべて吾が師」と言った吉川英治さんではないが、すべての人を人生の師として学んでいけという教えです。終着駅京都の舞妓の修行も生半可ではありません。舞妓になる前の一年ほどは仕込みの期間で、置屋に住み込んで家の掃除からお母さん、芸妓、舞妓たちの用事や手伝いなどに走り回りながら言葉遣い、立ち居振る舞い、歩き方、正座の仕方、食事の作法などを徹底的に仕込まれながら舞の手ほどきを受け、この間に見込みがないものは帰されます。この世界で続く者は、辞めてどこへ行っても続くと呼ばれるほど厳しいが、それがプロ意識を生むのです。
2009.12.24
コメント(0)
-
嵯峨野は曇り空
昨夜はキムチ鍋を囲んで4時間ばかり楽しく会話が弾みました。若い頃を思い出しながら話すのが嬉しいのは歳を取った証拠ですかね。最後に残っていたコンサル資料も喜んで引き取ってもらい、これで資料の大部分が綺麗さっぱりとなくなりました。若者が帰った後も、持ち出したファイルに挟んであった2度にわたる退職挨拶や読者からの感謝の手紙を読み直したりと、つい時間の経つのを忘れていました。そして、そんなものについ嬉し涙を流している私。若者たちから若いと言われるが、やはり歳ですね。この間から学生たちに「サラリーマンこそ志を持て」「仕事は自分の生き様の表現であり、幸せを実現するための手段」と話しているが、私の根本の所は30代から変わっていないことを再認識しました。こう書いている最中に、「今日の勉強会宜しく」と学生からメールが入ったが、午後から就活が始まった3回生たちに就職の話しをします。昔の資料を読み返す気になったのも、何か因縁を感じます。人は「必要なときには、必要な人や情報に出会う」と話しているが実感ですね。この間、高松から寄ってくれたミカン農家の若者を応援しようと、チャリティー産直の案内をしたところ早速協力メールもあり嬉しい限りです。皆さんも宜しければご協力下さい。送料込み 5キロ2500円 10キロ3500円です少子化で家族数が少なく、5キロ(100~120個)もあると大変という反応が多いが、宅配便送料が1000円余かかるので、少量で取り扱いできないのがネックです。◆宇宙からの砂漠写真です
2009.12.23
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
「我以外皆我師」とは作家の故吉川英治さんが最も好んだ言葉の一つです。人生における師は、特定の2人や3人とは限りません。出会う人、接する人の全部が、ある意味では「我が師」となりうるものです。たとえ名もない人でも、年下の相手でも、一見下らないと思える人でも、人は全て皆、その人ならではの特徴や、自分の及ばない秀でた一面を宿しているものであり、こちに求める気持さえあれば、必ずや何らかを教えてくれる先生となりうるものです。だから、どんな相手であっても、軽く見下したり、バカにしてはいけません。倫理運動の創始者丸山敏雄さんに「万象は我が師」という言葉があるが、大宇宙の森羅万象ことごとくを、我を導いてくれる名師と受けとめられたのです。不幸にしてよき師を持たない人は、師を見つける能力(人を心から尊敬し、師と仰いで学ぶ姿勢)に欠けていたのではないかと反省してみることです。そんな人生では、幅も狭く、人間的成長も期待できません。まずは善き師についたうえで、その殻を破って自分流のものを工夫する(守破離)ことです。仏教では、正しい師について、正しい教えを正しく聞くことから道を歩み始めよと説きます。
2009.12.23
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
普段の生活をしていると、とにかく私達は求めることをします。お金を求める、名誉を求める、健康を求める、安全を求めるなど、このような求めることを全て含める形で、最終的には安らかさを求めようとします。しかし、安らかの語源や「休む」「止す」や「求心歇む処即ち無事」の語にもあるように、安らかさというのは、求めるものではありません。求める心が「休まる・止む」ときが、本当の安らかで生きるということです。求める根っこは自分の心にあるのだから、その心の根っこのところが解って、求めるということを一旦休んでしまう。安らかという言葉の語源が「休む」「止す」から来ているということは、実はそのヒントなのです。以上のような総ては、無明から起きます。そこで大切なのが、まず善い師(善知識)について、真理を正しく聞いたり見たりすることです。学問をするにもスポーツをするにも、あるいは自己を求めるにしても、自己流ではなかなか上達しません。ひとかどの人物、偉大な仕事を成し遂げた人は、必ず良師に恵まれていました。何事も、自分に合った先生を見つけて、じっくりと基礎を身につけることが大切です。
2009.12.22
コメント(0)
-
嵯峨野は風花が時折舞っています
今日の嵯峨野は晴れてはいるが雲もあり、時折り風花が舞う寒い日です。明日の夕方は若い人が相談事があって来るということで、寒いこともありキムチ鍋でもつつきながら語り合おうと、散歩がてら奥嵯峨に野菜を買いに行きました。でも、お目当ての良い大根がなく、小芋とネギだけを買ってきました。ところで、23日はまたこの間の学生たちの内3回生に呼ばれて、就活の話しをしなければならないので、この間から資料を整理しています。この頃はグループディスカッションが多いので、時間があれば例題をやってみたいと思いテーマをどうしようかと考えました。学生たちに「働く」ということを考えさせるためにも「仕事のできる人とは」にしようと思い、教育を兼ねて最後をどう締めくくるかを考えています。結論は「微差の積み重ねで大差を創り出せ」にしようと決めました。今日の新聞にも、この頃の若者は「なぜ」と突っ込んで考える人が少なくなったとあったが、ある程度の所まではできても、もう1歩が足りないことを私も痛切に感じています。例えば、私の所には若い人たちが勉強会の依頼や相談事で来たりするが、終わればそれまでです。(これは学生だけでなく社会人、起業希望者にも共通)帰り際にお礼を言うのは当たり前だが、その日の内にメールでもいいから1本送るか否かで印象が大きく違います。(スピードが感動を生む)私は、現役時代は何時もカバンの中に特製の葉書を入れていて、訪問先を出たところで簡単な文章をしたためて出すようにしていました。たったそれだけで、印象は大きく違うし、何とかしてやろうという気にもなります。考えるにしても、答えが出てから後5分、1日考えるか否かです。プレゼンの原稿を考えるにしても、毎日思いついたことを書き加えることで、1歩でも良いものにしようと努力を積み重ねることができるか否かです。勉強や情報収集にしても、1日30分、1件でもいいから積み重ねることができるか否かです。そうやって微差を積み重ね、いかに99.999点を目指すことができるか、それが当たり前にできる人が「仕事のできる」人だとお思います。大差を付けることを考えると大変だが、1日コンマ1のことでも100日続ければ10点、1年続ければ36点、10年続ければ誰もが追いつけないものになるはずです。
2009.12.21
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
「瞋憎」は「瞋恚」とも言われ、怒り憎む心です。これは我々が通常使っている「怒り」という意味とは異なり、驕り高ぶりから生じた「いかり」が「瞋恚」です。「驕り高ぶり」とは、過剰な自尊心です。これを傷つけられた時に、「瞋恚」が生じます。自尊心の拠り所が「アイデンティティー」(我)です。でも、諸法無我というように、「これが私だ」という確たるものなどありません。私たちは、何ごとも自分の思い通りになることを期待します。ときには、思い通りになるはずのないことまで、思い通りにしようとこだわります。そして、自分の思い通りにならないと、怒りや憎しみが起こります。怒りや憎しみは、他の人びとを傷つけると同時に、自分自身をも傷つけることになります。そして心の平静さを失わせ、ますます間違った方向に自分を追いやってしまいます。例えば、車を運転していて、無理な割り込み、追い越し運転をされると、「なんという奴だ」と、反射的に腹が立ってしまうことがあります。それで気持ちがすっとするかというと逆です。腹を立ててすっきりするかといえば、そんなことはなく、却って自分を苦しめます。腹を立てたことに悩み、腹を立てることで周りを暗くして、周りの人たちまで不愉快な気持ちにさせます。
2009.12.21
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
世間的な地位や名誉は今生のかざりにすぎません。「今生の飾り」である名聞名利に執着して、「俺が一番エライ」という錯覚に陥り、謙虚な心がなくなり、やがては自己中心的なものの考えが増長し、その結果、「○○が上手くいかないのは彼奴のせいだ」などと思うようになるのです。よいことは全部自分の力、悪いことは全て他人のせいにして、悪口を平気で言うような修羅の境界に堕ちるのです。名利=蔵の財や名聞=身の財は本当の財ではありません。人間の本当の幸福は、蔵や身の財によって決まるのではありません。心の豊かさ、強さによって決まります。どんな逆境にあろうが、常に心が希望と勇気に燃え、挑戦の気概が脈打っているならば、その生命には、歓喜と躍動と充実があります。そこに幸福の実像があるのです。そこで、「心の財」が大切になります。「心の財」は精神的な健康で、そこから生きようとする意欲が、希望と勇気が、張り合いが生まれます。それはまた、「蔵の財」「身の財」をもたらす源泉ともなります。人は、この「心の財」を積んでいく中で、生きることの尊さを知り、エゴに縛られた自分を脱し、人々の幸福という崇高な目的のために、生き生きと活動していくことができます。
2009.12.20
コメント(0)
-
ミカン農家も大変なようです
昨日は東京の知人に紹介されたと言って、松山のミカン農家の若者が立ち寄ってくれました。早稲田を出て勤めていたが不況で会社がダメになり、家業を手伝っている25歳の好青年です。今は東京で土日は朝市的な店を出し、販路開拓を目指しているようです。ご多分に漏れずミカン農家も高齢化が進み、この3日間ミカンの収穫を手伝い、朝4時台の列車に青春18切符で乗り、京都に途中下車して今日中に東京に着くとのことです。若いというのはいいものですね。夜行で旅をした学生の頃を思い出します。いろんなミカン談義をしたが、今はキンカンよりチョット大きいくらいの屑ミカンを何とか利用できないかと考えているようです。(アイデアがありましたら宜しく)ミカンは大きさや糖度で値段は変わるが、出荷価格が10キロ2千円程度で、その年の市場価格によっては赤字にもなりかねないそうです。すこし調べてみたら、お客様の購買値を100とした場合、農家出荷価格は37.5% 卸出荷価格50%(マージン12.5%)、仲買出荷価格75%(マージン25%)で小売マージンが25%程度という勘定です。この頃ではネットによる産直も盛んだが、品質にもよるが10キロ3~4千円程度が多いようです。また、果物の種類も増え、冬の定番だったミカンの消費量も落ちているようで、利用方法も模索しているようです。ネットで調べてみたら、こんな利用法もあります・極上竹チップ堆肥 屑ミカン+竹チップ 現代農業3月号・ミカン酒 ミカン皮+焼酎・ミカン風呂 ミカン皮をガーゼの袋に入れて・油よごれ落とし 柑橘類は洗剤代わりになります・ミカン葛湯 絞り汁を加える・ミカンジャムやミカンパンなどの他にも、いろんなレシピも出ていました。嵯峨野を案内しながら歩いていたら塩大福のお店が目について入ったら、彼の隣町の出身者ということで奇縁。熱心な学びの姿勢が好ましく、帰りに「人は何故モノを買うか」の原稿をCDにして持たせたが、なんとか成功して欲しいモノです。民主党は農家の所得保障云々と言っているが、一律保証というような戦略性のない保護ではなく、もっとやる気の出る農業に育てる手を打って欲しいモノです。
2009.12.19
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
無明の一つの実体は欲(煩悩)です。「貪愛」や「瞋憎」といわれる煩悩が、雲や霧のようにわき立ち、私どもの心に立ち込めて「真実信心」を覆い隠してしまいます。「貪愛」は「貪欲」とも言われ、しがみつく愛着・欲望です。私どもは、しがみつくべきでないものにしがみついてしまいます。それは無知によって起こる心の動きです。無知だから、しがみつけば必ず苦という結果をもたらすのに、それを知らずに、自分にとってこの上なく大切なものと錯覚して、愛着をいだくのです。その最たるものが名聞名利です。「名聞」とは、自分の名声が広く世に聞こえてほしいと願う心 、つまり自分の名誉を追い求める気持ちのことです。例えば、上位の階級についたことを誇らしく思い、偉くなったような気持ちで後輩を見下ろしたりするのが、これに当たります。逆に、役職についた人を見て、羨ましく思ったり、妬んだりする人もまた、名聞名利に執らわれているのです。「名利」とは、他より大きな利益を得ようと願う心をいいます。「名聞」も「名利」も、共に、”他に比べて自分の方が名声が高い”とか、”他と比べて自分の方が儲かっている”というように、自他を比べて、あくまでも自分のため、ということが中心となります。
2009.12.19
コメント(0)
-
嵐山は日曜日までライトアップ中
この頃は色んな所でライトアップをしているが嵐山も20日まで実施中です。野々宮から竹林にかけてはラッシュ並の人出です。昨日から明日にかけては全国的に雪らしいですが、嵐山は快晴です。日当たりの窓辺で来週学生たちに話す原稿を整理していると熱いくらいです。15日に同志社でキャリアプラン創りの話しをしたときに、大企業に勤めると生涯賃金は3億数千万円になるので、会社側としては諸経費を入れると1人採用すると言うことは4億円の設備投資をするのと同じだ。従って、4億円の価値がある自分という財産をいかに運用するかのプランがキャリアプランでもあるというような話しをしました。そしたら、早速3回生たちから23日の日曜日にもっと話しをして欲しいと言うことで、そのセミナー用のパワーポイントを作っています。まあ、若者たちと話しをするのは楽しく、生き甲斐にもなるので有り難いモノです。◆日本アルプスを宇宙から見た写真です
2009.12.18
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
「無明」は、私どもの心のなかでは「愚癡」というすがたをとってはたらきます。「愚癡」は、どうしようもない愚かさです。何が真実であるのか、まったくわかっていないのです。真実がわかっていないだけではなく、そのわかっていないことすら、わかっていないのです。逆に、自分にわかっていること、それが真実だと思い込んでいるのです。まことに愚かというほかはありません。(真にできる人は、真実が分かれば分かるほど、分からないことが増えてくる)物事の真理をわきまえない(=無明)故に、散乱心(色々な仕事や刺激に追われて心が散乱している状態)・昏沈心(散乱心の反対に何事にも懐疑的、否定的になり陰気になる状態)・不定心(心が落ち着かず動揺している状態)が起きます。つまり、真理を知らないから、小さな自我に拘る我執に捉われるようになります。すると、つまらないものが面白くて夢中になったり(欣 キン)、反対に大事なものや大切なものを嫌がる心が人間には起き、無闇に生に執着する(厭 エン)ようになってきます。それらが人間の業となり、始めも終わりもなく循環し(昨日の1から10)、永劫に迷える衆生となります。
2009.12.17
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
釈迦は、苦が生まれる因果関係を次のように言っています。1.老死を始めとしたすべての苦は生まれることによって生じる。2.生まれることによって欲望が生じることに苦の原因はある。3.欲望が生じるのは煩悩があるからである。4.煩悩は執着や渇愛、激しい欲望から生じる。5.執着や渇愛、激しい欲望は求める心の働きから起こる。6.求める心の働きは触れること(縁)によって生じる。7.触れたいという欲望は六処(肉体と精神)の器官を通して生じる。8.物質と精神は、眼で色や形を見て、耳で声を聞き、鼻で香りを嗅ぎ、舌で味を感じ、体で触れて、心で感じる事(識)によって生じる。9.眼で色や形を見て、耳で声を聞き、鼻で香りを嗅ぎ、舌で味を感じ、体で触れて、心で感じる事は、過去の悪い行為(の記憶)によって生じる。10.過去の悪い行為は根本的な無知(無明)から生じる。つまり、根本的な無知(無明=真実に暗く、真実を知見する智慧の明るさが欠けている状態)が私たちの迷いの根本となるのです。
2009.12.16
コメント(0)
-
何のために飯を食うのか?
昨夜は同志社の学生たちに話しをしました。自主ゼミで、「志を育む」というテーマを追究しているグループのメンバーが対象でした。私は、サラリーマンこそ「なぜその仕事につき、何を実現したいのか」という志を持って欲しいと何時も言っています。なぜなら、現在では一つの企業が世の中に及ぼす影響は計り知れず(薬害や各種の公害の垂れ流し、食品の偽装工作、自動車や原発などの不具合隠しなど、大企業が社会に与える影響は大きい)、高い志を持って仕事を志事にしていく必要性が高まっているからです。若い人たちが志と言うことを考えてくれるのは嬉しいのだが、足が地に着いた議論をして欲しいので「犬猫でも飯を食べるが、君は何のために飯を食うのか」という問いかけから始めました。そこから、「生きるとはなにか」「何のため生きるのか」「生きる力って何か」と思考を膨らませて欲しいからです。皆さんも考えてみませんか?そして、3,4回生もいたので次のような問いかけもしました。1.君のやりたい仕事は何?2.何故その仕事をしたいの?3.その仕事は人様のどんな役に立つの?4.その仕事をやり通す上で大切な志は何?5.それを通して何を実現したいの?6.その道で、千人に一人のプロになるのに必要なスキルは何?私はいつも、大上段に振りかぶって正論を述べるのではなく、ごく当たり前の単純なことから問いかけを始めます。経営の話しをするときには「人は何故モノを買うのか」(gooのブログで書いていますのでご参照下さい)と問い掛けるし、マネージメントの話しをするときは「人間の本性とは何か」「人は何によって動くのか」などと問い掛けます。その単純な中に真理があり、本質があるからです。でも、意外と単純なことだが答に誰もが詰まるモノです。その単純なことが分からずに、理論を振り回してもしようがないと私は思っています。ところで、話していて気になったのは、学生たちが本を読んでいないことです。白楽天も知らないし、小公女セイラも知らないし、三国志も知らないし、日本の諺も通じない・・・。共通認識のないうえで話しをするとなると、いちいち説明しなければならないので時間がかかるのが痛いですね。話は変わるが、食事と言うことでは、「個食化が共感力を失った時代を創り出す」という議論もあります。このところ、理由もなく人が殺されたり、小中高生による暴力事件が多発しています。長年サル類を観察してきた山極寿一京大教授は、「事件の背後に家族によって育まれる、他者に共感して生きる力を欠き、思うように自己実現できない若者たちの焦燥感がある」と言い、「人と人を結びつける社会を創り上げるうえで、会食が持つ意味は一般に思われている以上に大きい」とも言う。ファーストフードや電子レンジが発達して調理する時間が減り、コンビニが各地にできて、何時でも好きな時間に好きなモノが食べられるようになった反面、人が向かい合って交流する機会が激減しました。学生の間では便所飯というのも有るそうですね。教授は言う。会食は人間以外の霊長類には見られない。子供が初めて他者との葛藤を経験するのは、食事の席だと思う。年上の仲間と食事を囲み、皆と同じものを食べる。皆の気を損ねないように手を出す必要があるし、仲間と取る順番を決めたり、食物の交換をしたりする。食物を巡る葛藤を押さえて楽しく食卓を囲むことが共感力を育てる。昨今の食事は、互いに視線を合わせないようにして食べるサルに似てきたような気がする。これでは共感力は進まない。共感の欠如は自分への関心を煽り、人々は自分だけが満足できる世界に籠もろうとする。それは自分への過信を誘い、自分を評価しない社会への恨みとなって暴力を醸成する。それぞれの文化には決まった食事の作り方や作法があり、世代や地域によって変化する。それを体で感じ取りながら、自分の欲を制し仲間に合わせる楽しさを味わうことが、共感と信頼に満ちた社会を復活させ、暴力を押さえる近道だと思う・・・。また、コミュニケーション能力が落ちて、怒りを言葉で表現できないためにキレるという説もあります。◆宇宙から見た砂漠の写真です
2009.12.16
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
この世の総てのものは、絶えず移り変わり、実体のないものであるにもかかわらず、私たちは永遠に続くように錯覚し、執着するから煩悩が生じます。例えば、燦々と太陽が輝く昼間もやがて夜になり、永遠に続く夜もないように、良い状態が永遠に続くこともなく、悪い状態も永遠に続くものではありません。平家物語の冒頭には「祗園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらはす。おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、偏に風の前の塵に同じ」とあり、方丈記は「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。淀みに浮かぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし。世の中にある、人と栖と、またかくのごとし」と記しています。何事も永遠に続くように考えるから、驕り高ぶったり、執着したり、悩み苦しんだりします。自我にしても、実体がないものを真の自我と考え、それに固執するために多くの煩悩が起こり、それによって苦しむのです。そんな私たちがあらゆる煩悩から脱却して心静かな涅槃の境地に入り、「明るく、楽しく、心豊か」で幸せな日々をイキイキと過ごすための方法をお釈迦様は説きました。
2009.12.16
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
●実践のための徳目ーー無執着「世の中の種々さまざまな苦しみは、執着を縁として生ずる」「無知なまま、執着する人は、愚か者で、くりかえし苦しむ。苦しみの生起のもとを観察した智慧ある人は、執着してはならない」「(何かを)わがものであると執着して動揺している人々を見よ。世間における何ものをも、わがものであるとみなして固執してはならない。何であれ、“これはわがもの。これはひとのもの”と思わない人は、わがものという観念を知らない。このような人は、“自分にはない”といって悲しむことがない。無所有、無執着。それが(老いと死という激流に対して避難所となる)洲にほかならない。それを安らぎと呼ぶ。それは老いと死の消滅である」とあり、安らぎへいたる正しい生活を送るために、例えば名声・財産・食物・衣服・異性などに対する禁欲、あるいは嘘・怠惰・怒り・後悔など心を汚す行いを避けることなどであるが、これらを集約するものとして強調されるのが、「執着するな」ということです。 ●論争を避けること「世の中に多くの様々な永遠の真理があるわけではない。ただ想像して立てられているだけである。独断的な見解にもとづいて推論を立て、これが真理だ、間違いだと両極端の教えを説いているのである」 「ある人々が、真実だ、正しいということを、他の人々はうそだ、間違いだと争って議論する。なぜ修行者たちは同じことを説かないのか」と言い、自分の見解・信条についても執着しないことが求められ、自説にこだわり論争することは避けよと説いた。「自説にこだわり、これこそ真理だと論争する人々はみな、非難をうけるか、あるいは、時には賞賛をうることもある。くだらないことである。論争の報酬は(非難と賞賛の)二つだけである。これを見きわめ、論争を避けよ。論争では、安らぎを得るための智慧の追求が、論敵に勝つための理論の追求に変わる。日常経験の範囲を越えた形而上学的な問題が扱われ、それらは経験によって確かめられず、肯定・否定の両論が並び立ち決着はつかない。 論争は、論争のための論争に陥る。仏陀はこれを無用と考え、心の平安をめざすとは、論争しない境地に立つことで、あらゆる立場への無執着が強調された。
2009.12.15
コメント(0)
-
忠臣蔵の話題が聞こえてくると
12月になると忠臣蔵の放送がよくあるが、討ち入りの日が私の誕生日です。元禄を昭和に置き換えてくれると私の誕生日になります。ところで、内蔵助は開城を前に蓄えた金を分け与えるが(今で言う退職金、清算金ですね)、下ほど蓄財もないだろうと厚くしました。知行取りは500石以上は100石につき10両、それ以下は13両、15両、18両と下ほど厚くし、槍持ちの足軽では米2石でした。自分は辞退しています。こういっても、幾らくらいか分かりにくくて今ひとつピントきません。元々は米1石=2.5俵=1両が基本だった(10俵4両という記録あり)が、時代により変動しています。1石=2.5俵=150キロだが、精米したときの歩留まり率は現在では90~92%です。(江戸時代はもう少し玄米に近いものを食べていたと思われるので95%位に設定するほうがいいか)現在の米の小売値は500円程度/キロだから、精米率を95%とすれば1石71250円です。米は現在より高かったと言われているので1石=10万円程度の感覚と思われます。(時代により1両=10万円~20万円、1石=34万円という説もあります)千両箱というのは、1億から2億の金が詰まっていたと言えます。ところで、知行取りの武士で100石取りというのは、100石採れる知行(領地)をもらうと言うことだから、4公6民(ひどいときは6公4民もあったが)として手取りは4割ということになります。ですから、100石取りで手取り40石、年収400万円(~800万円)といえます。内蔵助は1500石取りだったから、実質年収は6000万円(~1億2000万円)程度です。原惣右衛門、片岡源五右衛門、堀部弥兵衛らの知行高は300石取りだから、年収1200万円(~2400万円)になります。現在の部長級でしょうね。それで家の子郎党も養っていたわけだったから、そんなに高給取りともいえません。下級武士は30俵2人扶持(1人扶持=5合/日=年4.5俵)などとよく時代劇に出てくるが、これは49俵相当だから200万円弱になります。現在の生活保護世帯より少ないワーキングプアで、下っ端はかなり生活が厳しかったでしょうね。◆オーロラのライブカメラです http://alive55.exblog.jp/i13/
2009.12.14
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
●縁起世界が無常であることを明らかにすることによって、この世の苦しみを説明する一方で、苦しみを滅するために、苦しみを生み出す原因が何であるかを追究することも行われた。いわゆる「縁起説」で、「苦しみは、なんらかの原因・条件(因縁)によって起こり、その原因・条件(因縁)がなくなれば、苦しみもなくなる」と説いた。後に整備されて12に纏められ(十二縁起)、「根源的な無知」が苦しみの根本的な原因とされ、「悟り」と対置された。●欲望と智慧(欲望を制するもの)「欲望をもち、欲求をおこして、欲望が果たせないと、人は矢に射られたかのように悩み苦しむ」「田畑・土地・黄金・牛・馬・召使・女性・親族など、 様々な欲望に人が執着するならば、(欲望は)力を用いることなく、 その人を征服し、災難がその人を踏みにじる。それから、 苦しみがその人につきまとう。難破船に水が入りこむように」とある。欲望が苦しみの原因であるという考え方は当時のインドの通念であり、苦行によってそれを払い落とそうとしていた。仏陀は欲望を制するものとして智慧を重視し、欲望を心の働きとみなし、苦行ではなく、真理を悟る智慧によって、欲望は制することができると説いた。 ●実践・努力--自力主義「その理法を知って、よく気をつけて行い、世間の執着を乗り越えよ」「熱心に努力せよ。思慮深く、思念をこらして、わたしの言葉を聞き、自分の安らぎを目指して訓練せよ」と、仏陀の基本姿勢は自力主義である。仏陀の教えは「真理を悟ること」による安らぎを究極の目的としていて、智慧が重視されるが、「世の中で善き人々は、見識、ヴェーダの学識、智慧があるからといって聖者であるとはいわない。(欲望を)制し、悩みなく、無欲となった人を、わたしは聖者という」とあり、それは真理を「理解すること」ではあっても、「分別によって概念的に理解すること」ではなく体験を重視した。 智慧は分別による知ではない。体験されるべきものである。教えにそった行いを通じて、安らぎという理想の体験に向かって努力することが求められた。明日に続く
2009.12.14
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
世の中には自分の思い通りにならないことが多く、苦しみに満ちている。釈迦は、この世の苦しみから脱することを望み、悟りを得て解脱した。この自らの体験をもとに、苦しみから安らぎへいたる道を人々に示すことを目指した。仏陀は理論よりも実践を重んじたが、その教えには一貫した思想傾向が認められる。 仏陀は、体系的な理論を説いたわけではなく、説く相手に応じて説き方を変えたといわれる。最古層の経典には、その特徴がよく現れている。なぜ、苦しみが生まれるのかを仏陀は理性的に追究し、「人々は、わがものであると執着したもののために苦しむ。所有しているものは常住ではないからである」、この世のものがすべて無常であるからであると悟った。そして、「ああ、この命の短いこと。百歳にならないうちに死ぬ。かりに、それより長生きしても、いずれは老衰のために死ぬ」「世の人が生存への渇望にとらわれ、ふるえているのを、わたしは見る。世俗の人々は、それぞれの生存への渇望から離れられず、死に直面して泣く」と思い至り、 どうせ死ぬのだから執着しなくてもいいではないか。また、この世の苦しみは死と強く結びついていると悟った。(諸行無常=総てのものは変化) ●安らぎ(涅槃、彼岸)「この世において、見たり聞いたり考えたり意識したりする形うるわしいものに対する欲望や貪りを除き去れば、不滅の安らぎの境地である」 この世の苦しみを脱して到達される安らぎが「涅槃」で、仏教の究極の目的です。涅槃はnibbaanaの音訳で、「消滅」を意味し、欲望を火に例えて、涅槃は火の吹き消された状態として表現されます。 また、欲望は激流に例えられ、涅槃はそれを越え渡ったところであるから、「彼岸」(paaram)ともいわれます(次ページ参照)。涅槃は、後には死と結びつけられるが、はじめは現世において得られるものとされていた。 ●神秘的なものの否定仏陀は、神あるいは神秘的なものを説き、それへの信仰あるいは呪いによって、問題を解決しようとしたわけではなかった。「呪術、夢占い、人相占い、星占い、鳥占い、懐妊術を行うな。わたしの教えにしたがうものは治療術にかかわるな」と、呪術、占いは禁止された。「根源的な無知が頭であると知れ。明知が信仰と思念と精神統一と意欲と努力に結びついて、頭を引き裂く」と言い、当初の仏陀の教えは、宗教的というよりも合理的で倫理的であったが、仏陀の教えに信頼を寄せ、帰依する人々の集団が形成されるにともなって、急速に宗教性が強まったものと考えられる。 ●合理的な思惟仏陀のものの見方はきわめて合理的で、苦しみが宿命や神の意志、あるいは偶然から起こるものであるとは考えなかった。苦しみが生ずるには、そこにかならず何らかの原因・条件がはたらくと考えた。(因果律) 根底となる考え方は合理的、理性的であるが、このことからただちに原始仏教のすべてを理性的であるとみなすことはできない。布教の過程では当時の俗信あるいは迷信を必ずしも排除しなかったからである。 仏陀の教えが合理的で理性的であるとは、根底となる考え方が合理的で理性的であるという意味である。(明日に続く)
2009.12.13
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
私たちは、お仏壇になぜご飯や果物などをお供えするのでしょうか?お釈迦様の16弟子の1人阿難が森の中で座禅をしていると、やせ衰えて、手足や首は針金のように細く、髪は乱れ、腹が大きく膨れ、醜い姿をした鬼神が現れて、「汝は3日後に命つきて、私のような常に飢えと渇きに苦しむ醜い姿に生まれ変わるであろう。そうなりたくなければ、飢えと渇きに苦しんでいる者たちに食べ物を施し、ありがたい教えを説いてくれれば、救われるであろう」と迫りました。阿難は驚いてお釈迦様のもとへ行き、「どうしたらいいでしょうか」と尋ねると、「陀羅尼を唱え、飲食を施しなさい。そうすれば、鬼神たちに寿命と福徳を与えることになるであろう」と示されました。飲食の供養によって、あらゆる苦悩をのぞき、人々の幸福を願うのがお供えの意味です。飽食の今日、私たちは食べ物を粗末にして残飯を山のように捨てています。もっと物の命の大切さ、有り難さ、万物に感謝する心を大切にして、今の自分の与えられた命を尊び、生かされていることに感謝したいものです。食べ物も総てが命をもっていて、その命を戴いて私たちは今を生きています。食事の時に「いただきます」と言うのは、「尊いあなたの命を戴きます」という意味です。
2009.12.12
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
お盆の行事は昔からの習慣だからと、ただなんとなく亡き人の精霊をお迎えしていることが多いものです。でも、それでは何の意味もありません。お釈迦様の10大弟子の1人、木連尊者が、教えに従って亡き母を苦界から救うことができ、喜びのあまりお釈迦様に「私ばかりでなく、世の人々が同じような供養をすれば、誰でも救われるのですか」と尋ねると、「慈悲心と孝順心を持って行えば、生者は安楽が得られ、亡者は浄土に生まれ変わるであろう」と仰いました。お盆は、一般的には亡者の冥福を願う(得度式で仏になっているのだから矛盾)行事だが、そのことを通して、現世に生きている私たちが仏の心に触れて慈悲心、孝順心を持つ機会にすることに真の意味があります。仏の心に触れるとは親(先祖)に触れることであり、親(先祖)を拝む心はそのまま仏を拝む心となり、それはそのまま我が身を拝む心です。こうした心の働きを孝順心といいます。(いまバトンを受け継いで生きている私に感謝)また、人間は自分一人では生きられるものではなく、多くの人々に支えられて生かされていることを思うとき、「ありがたい、尊いこと」と思わずにはいられません。この恩恵に報いるために、人々にかける愛の力を慈悲心といいます。
2009.12.10
コメント(0)
-
遺された時間を悔いなく生きる
昨日は88歳の姉が首筋の血管が詰まって倒れて入院したので見舞いに行ってきました。思ったより元気で一安心。その後は、高校生時代の知人(彼女も癌を患っている)と知り合いの喫茶で話しをしました。残された短い時間を好きなように生きる、すくなくとも悔いのないように生きることは、人生の後半を生きる者にとっては最大の課題です。私は死ぬまでは力一杯生きたく、ダラダラと惰性のままに生き長らえることだけは願い下げたいと常々思っています。でも、いつかは頭や肉体の衰えるときは必ずやってきます。だから生きたいだけ生きたら、あっさりとこの世に幕を引きたいと思っているが、そう上手くいくか?それには、自分がやりたいと仕事を持っていなければならないが、歳をとってから自分の満足のいくような仕事はそうあるはずもなく、自分で創り出さなければならない。その前提として、まず幕引きの時を決めなければならない。両親は81歳と82歳まで生き、兄弟も長生きの血統たが、私は70歳ぐらいでいいと常々思っている。そこで60歳からは「後5年の命」と自分で区切って生きてきたが、2回目の5年更新もあと1年である。5年間など、ダラダラと生きていればあっという間に過ぎてしまいます。だが、力一杯生きようと思うと、途中でへこたれないように心身ともに細心の注意が必要です。(そういえば、現役の時、3億円の仕事を前にドックに入ったことがありました)逆に、5年しか持たせる必要がないと思えば、エネルギーを最大限に燃焼させもできます。そこで、次代を担う若い人たちの生き甲斐と夢の実現の手助けに捧げることに思い定め精進しています。話すことで頭の整理もでき、本の原稿にもなるので一石二鳥です。先月は学生や若者たちと商店街の活性化を話したが、来週は同志社でキャリアプランに対する私なりの考え方を話します。◆嵐山 竹林のライトアップです(今年は11日より)
2009.12.10
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
この頃では、家でお参りすることも少なくなりましたが、参考までに。1.仏壇の前に進む前に正座し、ご本尊様にきちんと対面し手を合わせ一礼する。2.ローソクに火をつけます。使用済みマッチ入れのない場合は、湯飲み茶碗に水を入れ、マッチの燃え殻入れにされるといいでしょう。3.線香三本に火をつける。(宗派によって本数、立て方が異なる)三本の意味は仏法僧(ぶっぽうそう)といって、一本はみ仏様へ、もう一本はみ仏様の教えに、そして残りの一本はすべての仏さんに(亡くなられた方も戒名をつけていただいて仏さんの仲間入りをしている)供えるのです。三本のお線香はまとめてたてても良い。(一本一本、三角にたてることもあります)4.リンを二回、静かに打ちます。リン棒の持ち方は人差し指と、親指で軽くつまむようにもちます。(宗派によっては、リンの内側を鳴らす所もある)リンを鳴らすときには、リンリンと気ぜわしく鳴らさずに、り~ン、リ~ンと静かに打ち鳴らします。5.リン棒を置き、手を合わせ(合掌)、静かに祈ります。このときに般若心経などを唱えられる方は声を出して唱えます。(経は僧になるための教本で不要)
2009.12.10
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
経は仏教の聖典で、経(釈迦の教えを纏めたもの)・律(戒律)・論(経典に関する哲学的研究書)をあわせて「三蔵」と呼びます。「蔵」=「くら」の意味で、経を納めた経蔵、律を納めた律蔵、論蔵の三つから構成されている。釈尊の入滅された年に、五百人の弟子たちがインドはマガダ国の王舎城郊外の七葉窟に参集し、釈尊が生前に何を教えられたか、またいかなる戒律を定められたかを互いに確認しあい、経蔵と律蔵の基本的部分がここで編纂された。しかし、そこで編纂された聖典は、あくまでも人々の記憶にたよって保持され、口伝によって伝承されました。そのような時代が数百年間続いたと思われます。そして、紀元前1、2世紀の頃、このような伝承聖典が文字化されたと推定されています。したがって、お経の成立といえば、この文字化された聖典のことだと思ってよいでしょう。(以上は小乗仏教のお経)大乗仏教の経典は別物です。大乗仏教は小乗の出家主義を否定して、在家もまた救われると主張しました。そして、そのような主張をお経のなかに盛りこんだのです。だから、形式的にいうならば、大乗仏教の経典は釈尊が説かれたものではありません。後世の仏教徒たちの創作ということになります。
2009.12.09
コメント(0)
-

嵯峨野週末のご案内
今年も11日から嵐山花灯路が行われます。紅葉は終盤を迎えていますがお出かけ下さい。
2009.12.08
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
お墓参りは、心に思いが起こったときにいつでも、例え命日であろうとなかろうと、懐かしい思いが起こり、苦しい胸のうちが打明けたくなったり、うれしいことを報告したかったら、いつでもお参りすればいいのです。 年忌は亡くなった後の初七日、七七日=四十九日(満中陰)、百ヵ日はいうまでもなく、一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌というように順にくるから、その命日にお参りするのが普通です。また五十回忌ともなれぼ、早く親に別れた人は別として、大抵はやや遠い係累になってこようから、それらの方のためには春秋のお彼岸とかお盆にお参りすればいいと思います。 お彼岸は日本独自の先祖まつりの日であると共に、布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧の六つの修行法を中道を表わす中日の前後三日ずつに配した修養週間でもあるから、その意味をこめてお参りするのがよいでしょう。 お盆はご先祖が一年一度、里帰りをするときとされているから、家族中でお参りし、家族そろってご先祖を迎え送るのです。隣のお墓に誰もきていなくて、花も線香も水も上がっていなくて寂しそうだったら、ちょっと一本の花、一杯の水を分けてあげてはいかがでしょうか?
2009.12.08
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
我国で、お仏壇が個人の家に祀られるようになったのは、天武天皇が686年3月27日に、全国の、各家々に仏間、仏殿を造り、仏像や経典を置いて礼拝供養せよとの詔を下されたのが、一般にはお仏壇設置の初めとされています。 墓は遺骸や遺骨を葬った葬地であり、その霊魂を祀るための祭地でもあった。しかし庶民の間では古くは遺骸・遺骨を尊重する考えは薄く、むしろそれらを遠くに隔離しようとしました。それが墓地と祭地とが別のところになって両墓制を生むことになりました。死の忌み、死の穢れを怖れる気持の強い日本においては死骸の処置は厄介な問題でした。したがって忌み・穢れを厭わぬ宗派ができて墓を管理するようになったことは、墓制史上重大な問題でありました。 古くは墓は人の住居から離れたところに設けられたが、そこに二十五三昧講などの墓堂が建てられて寺院が次第にそれらの墓地を管掌するようになりました(830~850年頃)。庶民の墓地に石碑を建てるのは江戸時代からのようで、その歴史は新しい。古くは葬地に墓として設けても石をのせておくか、木を植える程度でした。そして霊魂を祀るたびごとに生木などを立てていたのが木の卒都婆となり、板碑となり、今日にみる石碑となりました。
2009.12.07
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
死後の霊を弔うという行法は、実に古くから存していました。忌服・服喪といい、遣族のものがある定められた期間「喪屋」とか「忌屋」と称する建物の中に入り、喪服を着て、いわゆる忌みごもりをしていたということが記録に残り、中国から儒教思想の移入によってもさらに強化されたようです。 人の死後、四十九日間をといい、この期間が過ぎた日をもってというのは、インドにおいてすでに行われてきたことで、人間が生前なした行為の結果(業)によって、次の生へと輪廻してゆくという考え方(輪廻転生)があり、人間が死滅して次の生に生まれ変わる間のことをといった。 は、またともいい、有とは存在という意味で、今現に生きつつある生存がで、それが終わって、次の生が始まるとのあいだの中間存在が、ここにいう中有です。しかし、本有のうち極善と極悪の業をなしたものには、中有はないとされ、死後ただちに次の生に移るとされるが、短いものは七日、もっとも長いときは四十九日間の中有があるとされていました。このような考え方から、七日ごとの仏事を営んで、亡霊を供養するという、ならわしが生まれ、今日の法事の原形であることはいうまでもありません。
2009.12.06
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
浄土真宗においては、亡くなった方に「冥福を祈る」こともありません。それは、亡くなった方を「諸仏」と見るからです。諸仏の方々は、「この世でのはたらきが終われば、阿弥陀如来さまのお浄土へお還りになる」のです。つまり、「亡くなった方は、この世でのはたらきを終えて、阿弥陀如来さまのお浄土へ還られた」と、浄土真宗の門徒は受け止めるのです。浄土真宗のお念仏は、「おかげさまと生かされ、ありがとうと生き抜く」と書いてあります。葬儀においても、弔辞や弔電でよく「ご冥福をお祈りいたします」という言葉が添えられます。でも、冥福を祈るとは、冥土の旅を無事終えて、良い世界に転生できるように祈ること、残された親族が一生懸命祈ることで、魂が浄化されるという説に基づくもので、不適切と言えます。(得度式で既に仏に)言葉の違いがハッキリ区分けされているのが「日本語」なのだから、あなたの「追悼の心」に添ったふさわしい「言葉」や「文章」で、目に見えない「こころ」を「形(言葉や文章)」にして伝えることが大切です。例:「謹んで(ご遺徳を偲び)哀悼の意を表します」「ご逝去を悼み、慎んでお悔やみ申し上げます」「ご生前のご苦労を偲び、謹んで敬弔の意を表します」
2009.12.05
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
戒名(浄土真宗では戒律がないので法名という)が何十万もすると問題になっているが、字によってご利益が違うものでなく、残された人のそれこそ見栄に過ぎません。仏の弟子になったときの名前が戒名であり、仏の弟子になる儀式である得度式において戒名をいただくことになります。たった一度のかけがえのない人生を我がまま、気ままな私の思いを先とせず、「天地の道理、仏戒に従って生きて参りましょう」という誓願を起こしたときに戴くのが戒名です。だから、本来は死んでからもらうのでは遅いわけで、天地の道理、生き方を聞く耳、読める目、それを行ずる身体のあるうちに一刻も早く戴くべきです。「泥多ければ仏大なり」というが、泥とは人生の悲しみや苦しみを象徴し、泥は仏を作る大切な材料であり、泥を嫌っていては仏は作れません。しかし、泥はあくまでも泥であって、泥を仏として昇華させるためには、その昇華の方法を学ばなければなりません。泥を肥料として仏を作り(つまり、挫折経験を生かす)、花を咲かせていけるように、此岸(煩悩に満ちたこの世)から彼岸(浄土)へと導くことを引導と言います。従って、生きているうちに戒名を戴いて引導を渡してもらうことが大切なのです。
2009.12.04
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
仏教における葬式の内容は得度式であり、「度」は渡ると同じ意味で、「得度」とは「彼岸に渡り得たり」と読んだらよく、仏の弟子になる儀式が得度式です。葬式は、死んでしまった人はもうこの世のことは全部おしまいになっているのだから、別れが身にしみて耐えている「遺された、生きている人たち」のためのものである。別れとは、実は相手を赦すことです。それまでの色々な行きがかりやしがらみ、愛憎悲喜万般をご破算にして、遺された人は総てをいきなり赦さなければならないし、赦さざるをえない。愛憎も生前に積もり積もった屈託も、そこで断ち切らなければならない。葬式でしなければならないのは、この断ちきりであり赦しである、と南直哉禅師は言う。本人が断ち切り難く赦しがたいものを、儀式の形を借りて強引に切らせ、けりをつけてしまう。「引導を渡す」というけれども、これは死者に渡すように見えて、実は遺された人に渡しているのだそうです。そして、私たちは死んだ相手を赦し、今度は「仏=ホトケ」(死者は仏になる)に対して、恐らくはあったに違いない自らの罪を仏から赦されなければなりません。拝むとは、仏の前で自分を省み、自分を変えていき、生き方を深めていくことを誓うことです。
2009.12.03
コメント(0)
-

今年は左京の方が紅葉が綺麗
今日は60まで住んでいた散歩道の紅葉を愛でに行く。真如堂~吉田山~法然院~南禅寺と4時間余歩く。嵯峨野の紅葉よりも赤が綺麗に発色していて目の保養。まだ今週末も楽しめそうですね。
2009.12.02
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
具体的には浄土教系統のものが念仏仏教に当たります。例えば「南無阿弥陀仏」という念仏は阿弥陀仏にすがる念仏です。自分で辛い修行をすることなく、この念仏を唱えることによって簡易に救済を得ようとするわけです。このような自分で修行することによらず救済を得ようとする立場を「他力」と言います。逆に、禅のように自分が修行することによって自ら苦しみから抜け出ようとする立場を「自力」と言います。 どの宗派にしろ仏教というものは全てこの世に存在するありとあらゆる苦しみから逃れ何ものにも惑わされないようになろうとするものであり、仏教の中の宗派の違いというのはその苦しみから逃れるための手段の違いにすぎないものであると考えられます。仏教は苦しんでいる人間の為の世界観なのです。 でも、お釈迦様は自分さえ偶像視することを諫められ、自力を説かれたように、念仏を唱えたりお経を聞くだけで救われるものではありません。日本人には、権威あるものを無自覚にありがたがる傾向があります。でも、自らが、もう一人の自己を求めて精進すること無しに、苦から脱して心安らかに生きることは不可能です。私としては、行動無くして成果無しと思います。
2009.12.02
コメント(0)
-
陽気に誘われて
時々サスペンスドラマの舞台になる落合へ行き岩の上で酒を飲む。最後の紅葉が綺麗。前の保津川を通る川下りの客が手を振るのに応じながら昼の一時を楽しむ。東海自然歩道を清滝に抜けて歩くが、高齢者の団体が多く(1.2キロの間断続的に続く)道を譲っていて普段の倍以上かかる。
2009.12.01
コメント(0)
-
第1章 釈迦と仏教の基礎知識
日本において末法思想というものがもてはやされた時代があった。末法思想とは釈迦の入滅後次第に釈迦の言葉(仏説)のみが残って仏説の実践やその実践の結果が失われていく時代に入っていくという考え方です。この考え方が広まると、個人がどんなに修行をしたところで決して救われることはないという考え方が流行し、自らの修行によらず既に悟りを開いている人物(仏)にすがることによって現世の苦しみから救ってもらおうとする考え方が出てきた。これが念仏仏教につながってくる。 念仏仏教の特徴は、特別の修業を行わなくとも誰でも苦しみから救済されることができるということにあり、このことは仏教の普及という意味では大きな貢献をした。実際に仏教の教義を学んだり理解したりすることの出来る人は圧倒的に少ないわけであるが、単に念仏を唱えるだけなら誰でも出来るからです。また仏教の複雑な教義を学んだり理解したりすることのできない生命(「人間」と書かなかったのは、輪廻転生によって全ての生命がつながっていると考えるからです)が仏になることが出来ないというのは、仏教根本の「全てのものを受け入れる」という命題に反するものであるといえよう。
2009.12.01
コメント(0)
全47件 (47件中 1-47件目)
1