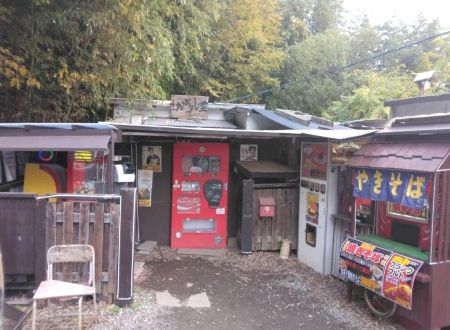2009年05月の記事
全58件 (58件中 1-50件目)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
心のお風呂マザー・テレサが来日したとき、「日本では飢えた人はあまり見かけないけれども、街を歩き人の話に耳を傾けてみると、インドの道端に横たわる人以上にたくさんの人が精神的に苦しんでいると感じました。インドではパンを与えれば微笑みを引き出すことができるが、日本では苦しんでいる人から微笑みを引き出すのは易しいことではありません。日本の皆さんの使命は、心の悩みをともに分かち合い、微笑みを取り戻すことではないでしょうか」と言った。心の悩みを解消してあげる良薬は、教えることでも導くことでもなく、ただ共感を持って聞いてくれる人がそばにいることである。聴いてくれる人がいるということが、どんなに人を苦しみから解放し、苦しみを乗り越えようとする力になるか計り知れない。子供であれ大人であれ、黙って共感して聞いてあげることが、相手を尊重するということである。不登校の子にしても、相手に問題を解決力する力があると信頼して共感を持って聞いてあげれば、その子は自分で考え解決していくようになるはずである。心に苦しみのある人の話を、ひたすら聞いてあげることが『心のお風呂』になる。
2009.05.31
コメント(0)
-
仕事の満足度≠収入の満足度
アニメーターの生活実態の大規模な調査がなされた。勤労理由の1位は「絵を描く仕事が好き」、3位「この仕事が楽しい」、4位「生き甲斐の一つ」とやる気は高い。だが、仕事に「十分に満足」「満足」が18.7%に対して、収入に「十分に満足」「満足」は10.5%で「大変不満」「多少不満」が69.6%もありました。年代別の収入は20代平均で110万円、30代でも213万円、40代以上でも400万円しかなく、概算の時給は動画298円、原画で689円にしかならない。給料の良し悪しと、生き甲斐や働き甲斐とは一致しないことが多い好例です。仕事とは何か? 何を基準に自分の仕事を選んだらいいのか?お金のためにとか、会社のためとか、世の中のためとか、人によって答えは様々でしょうが、私は何よりも自分のためにするのが仕事だと思う。お金も重要な要素には違いなく、自分の仕事の社会的な意義も大切でしょう。でも、それは一部分にしか過ぎません。突き詰めれば自分の人生のためです。その場合、何が大切かというと、仕事は目的ではなく、自分の人生の一つの手段に過ぎないということ。自分が納得いく人生を送れるかどうか、そのための一手段です。金持ちにならなくても幸福な人はいるし、金持ちになっても不幸な人はいっぱいいます。自分は「金持ちになりたいのか」、それとも「幸せになりたいのか」と心に聞いてみるとよい。幸せ計画で人生を考えてみると個性的になってくる。幸せ設計というのは、そもそも「自分にとっての幸せとは何か」を考えなければならないわけだから、自分の尺度を持って自分で考えなければならないそれは、自己実現にもつながる。自己実現とは、人間がそれぞれに持っている独自の可能性を発展成長させ、自分らしい個性を確立することである。そしてそれは、客観的には人間の生命力の表現であり、主観的には生の欲望の実現ということもできる。でも、業界として最低の生活は保障する仕組みがないと、よい成果の再生産は難しくなるとも思います。
2009.05.30
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
人のためにちょっと何かをするもの凄い財産があるのだが、好きなこともなく、自分を孤独で不幸の塊のように思いこんでいた未亡人が、ある心理療法の医者を訪ねた。そんな彼女にも、たった一つアフリカスミレを育てる趣味があった。そこで医者は彼女に、「アフリカスミレをできるだけたくさん育てて、日曜日に教会に持っていき、誕生日がきた人に一鉢ずつ贈りなさい」とアドバイスをした。未亡人がそれを実行すると、おもいがけない喜びの葉書やお礼の手紙が来るようになった。今までは誰も近づいてこなかったのに、自分の周りにだんだんと笑顔の人が近づいてくる。そして、未亡人はとても幸せな気分になった。「人間、生まれてきたからには、人のためにちょっと何かをすること」という意味のフランスの詩があったが、沢山しようと思うと大変だが、ちょっとしたボランティアなら誰にでもできるのではないだろうか。カミリー・ディキンソンは、「一羽の小鳥を癒しなば、我が人生に悔いあらじ」と言ったが、ニッコリ微笑むことだっていい。人の心を楽しませる努力をしたいものである。ボランティアというのは、決して無理してはダメ。遠くに出かけられなければ、隣の家の前の道を掃除してあげるだけでもいい。無理しなくてもいいのよ。ボランティアだと肩肘張らないで、自分のできる範囲で手伝いましょうよ、そうしないと長続きしない。ボランティア活動のために家族を犠牲にする必要はない、とマザー・テレサの仕事を手伝っている上流社会の婦人であるクマールさんは語る。目の不自由な人がそばにいれば、自分が読んでいる新聞を声を出して読んでやるだけでもいい。それも、自分が読みたい時間で充分である。年取った人のために窓を拭いてやったり洗濯してあげることだって立派な愛の表現である。いや、何をしなくても、苦しんでいる人がいるということを知っているだけでもいいのです、とマザー・テレサも言う。親切で慈しみ深くありなさい。あなたに出会った人が、誰でも前よりももっと気持ち良く明るくなって帰るようになさい。親切があなたの表情に、眼差しに、微笑みに、温かく声をかける言葉に現れるように・・・。何も特別のことをしなくても、普段の何気ない対応の中でボランティアはできる。
2009.05.30
コメント(0)
-
生と死の狭間で
「いつからが死なのか」という問題が論じられ、脳死を死と見なすか否かが国の審議会でも議論されています。それは、臓器移植という結論が先にあっての議論のように思えます。すなわち、我が国では臓器提供が少なくて海外で移植をするしかないケースが多く、海外から問題視され始め、臓器提供を増やす必要に迫られています。だが、そもそも「死とは何か」「生とは何か」という議論を横に置いておいて、人間の身体を部品のように扱うことに私自身は違和感を覚えます。病気の人としては、可能性があれば何をしてでも生き延びたい、生き延びさせたいという願いは分かるが、「生」と「死」というものをどう受け止めるかと言う議論をまずすべきではないのでしょうか?「生」と「死」というものは、医療の問題である前に、人間そのものの存在の問題だと思います。極論すれば、やがて医療が進んで脳の移植ができるようになるかもしれません。では、その時、誰が主体になるのか?ヒョッとすれば、移植された脳が他人の肉体を乗っ取ったという解釈もできるかもしれない。医療の進歩とは何なのか? ロボット化? 身体のパーツのリサイクル? そんなに生って軽いもの???そんな考えが、命の大切さが叫ばれるのとは裏腹に命の軽視が起きているように思えてきます。一四世ダライ・ラマは「この生ける肉体が存在する限り、人間として生を享けた以上、死は不可避的に訪れるであろう。しからば、その死を、それもまた人生の一部として享受するほかない」と言ったが、私達は生まれたときから死というゴールに向かって歩き始め、生老病死という苦にさいなまれます。生きたい人にとっては、100歳になっても生きたいと思うでしょう。それは、欲であり執着です。そこに苦が生まれます。でも、人生は長い短いに意味があるのではないと私は思っています。人生は「諸行無常(万物は常に変化し止まらない)・老少不定(死期に定まりは無い)・一寸先は闇」で、私たちには明日の運命すら知りようがありません。その時が来たら、黙っておさらばすればいいと言うのが私の考えだが、それは健康な人の考えることで、おしかりを受けることもよく知っています。精神科の女医キューブラー・ロスは、医師に臨終を宣言されて3分から5分後にまた息を吹き返した患者2500人に、「息を吹き返すまでにどんな体験をしたか」を聞いた結果、それらの患者に共通することが三つあったと京都の学会で発表しました。1.肉体と意識が分離し、自分の遺体を取り囲んでいる光景を高いところから見ていた。2.自分より先に死んだ肉親や愛した者が、そばに来て助けてくれようとした。3.愛と慈悲とに満ちた光に囲まれて、その光の源の方向に行きたいと思った。彼女は「今は、私はもう一つの世界が我々の死後にあることを信じます」と語ります。以来、ガンに冒された子供たちに「ぼくたち、どうなるの?」と聞かれると、「あなたは、サナギの殻をここに残して、あの世で蝶になるのよ」と言えるようになったと告白しています。医者から3カ月の命だと言われた9歳の少年から、「大好きなロス先生、あと一つだけ聞きたいことがあります。命ってなんですか。死ぬってどういうこと。どうして子供が死ななくちゃいけないの」という手紙をキューブラー・ロス博士は受け取った。それに答えて、簡単な言葉と絵で人生を描写した色鮮やかな小雑誌を作り上げ、「ほんの短いあいだだけ咲く花もあります……春がきたことを知らせ、希望があることを知らせる花だから、みんなから大切にされ、愛される花です。そして、その花は枯れます……でもその花は、やらなければならないことを、ちゃんとやり終えたのです」と言葉を添える。また、先生は「死はこわいものではない。じつのところ、死は人生で最も素晴らしい、方法もない経験になりうる。そうなるかどうかは、いま、自分の人生をどう生きているかにかかっている。そして、今というこの瞬間、大切なことはただ一つ、愛だけである」とも語る。死んだ後の世界が本当にあるかどうかは誰にも分からないが、あの世にも素晴らしい世界があり、蝶のように飛び回れると信じることができれば、死の恐怖から少しでも救われるのではないでしょうか。それも、ホスピスの一つかもしれないと思われてきます。こんなことを言った方もみえます。「死は嘆くべき出来事ではない。それは旅の終わりであり、目的地に着いたとき、持ち主が車(肉体)から降りるだけのことである。一つの完成であり、少なくともそうなるべき幸福な結末なのです」
2009.05.29
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
楽しいことを選び前向きに生きる人間には快中枢と不快中枢があって、不愉快なことがあれば不快中枢が働いて、できるだけ不快のない状況へと遠ざかるようにできている。例えば、天敵を回避する、不快な食べ物を吐き出す。空腹を満たすために獲物に接近する、商品の新機種が出ると飛びつく・・・など、快に接近することで不快を回避し、生き残りのチャンスを増大させてきた。どんなときも笑顔を絶やさない人気の若手女優広末涼子さんは、楽しい場所に自分を置いて、楽しいことを選び取るようにしていると、笑顔の秘けつを語る。自分がやりたくて選んだことなら、どんなに大変でも苦にならない。でも、仕事ばかりでは笑えないこともあるから、友達や家族と過ごす時間も大切である。どうしても笑えない時には、好きな音楽とか小物で遊んだりとか、周りに好きなものを集める。やっぱり、笑いには理由がいるんですよと語る。本当につらくて耐えられないことなんて、人生には何回もないと思うとも言い、受け身にならず、自分の選んだ道と納得していくのが広末流らしい。人間だから、落ち込むときもあるし、いらだつときもある。「生きるとはどういうことなのか」という壁に突き当たって、漠然とした不安に取りつかれたり、何か心がむなしくなるときもある。そんなとき、次の言葉をかみしめてみよう。・手塚治虫さんは、「人生に、いや、人間に終着駅はないと思いますよ」と笑顔で言った。・冒険家の植村直己さんは、「他人のやったことを羨ましがっても何にもなりません。自分のやることを考えるのが一番大切だと思います」と小さな声で言った。・画家の谷内六郎さんは、「体の中にたくさんの病気を持っています。いつのまにか、病気と仲良しになりました。病気と仲良しになることは、分厚い一冊の本を人生で持ったようなものでしょう」と照れながら言った。・画家の深沢七郎さんは露天ぶろに入りながら、「いつも人生を深く考えないで、鼻の穴から空気を吸っているでしょ。でもねぇ、時には、ああっ、今日の空気はうまいって感謝する日がなくてはいけないでしょ」と言った。毎日が人生。暗い顔して落ち込んでいてもしようがない。笑って生きようではないですか。戦争の後遺症で両足を切断し、右肩も動かない僧侶は、「よかったときや他人と比べるから苦しくなる。『いま、ある状態』をそのまま受け入れれば苦はなくなる。そうすると、なんのてらいもなくなり、素敵な笑顔でいられるようになる」と語る。全身全霊をかけて目の前のことに取り組んだとき、おのずと結果にこだわる心は消え、生きていることの本当の喜びを知ることができるはずです。
2009.05.29
コメント(0)
-
お茶しませんか
一昨日お茶屋さんにいただいた新茶を飲んでいます。色が良いですね。特に、お茶を入れた後の茶殻の緑色にはハッとさせられます。ところで、関東と関西ではお茶の好みが違い、関西の企業が東京に売り込みに行っても最初は上手くいかなかったとのことです。何故かと言えば、関西のお茶は香り高い透明感のある緑から黄色で色が薄いが、関東は茶色っぽい濃い色だからです。そこのところに、最初は気がつかなかったと言います。それには、歴史的な経緯があります。昨日、お茶壷道中の話を書いたが、あれは徳川家が山に貯蔵しておいたお茶を秋風が吹く頃に降ろしてきた行事です。その降ろしてきたお茶を殿様が飲んでから、はじめて庶民がその年の新茶を口にしたのです。今でも茶道で封切り茶という行事が秋にあるが、昔から 関東の新茶は秋でした。秋までに保管されたお茶は、後熟して味が変化していました。関東の人たちは、その変化した古茶を好んで飲んだのです。逆に関西は、お茶の産地が多いから新茶を好んで飲んだ。そういう歴史から嗜好の地域性は今でも残っています。冷蔵庫が普及してから、香り高い透明感のあるお茶がいつでも手に入るようになったのだが、それまで関東の人は後熟して赤味をおびた、甘味があって渋みは少ないお茶を好んでいたから不満の声が出た。そこで登場したのが深蒸し茶です。味の好みなんてこんなもので、ミッシェランの星に振り回せれるなんてバカらしいことです。また、煎茶の場合、同じ産地で100g500円から3000円位(1万円というのもあるが)の差があります。この差は摘み取り日の違いだそうです。 お茶の木は冬の間約半年位かけて養分を蓄え、春新に新しい芽が出ます。最初に摘まれるのは、幼い芽で大事に手摘みするので量も少ない。この新茶には旨味が凝縮されています。この頃が100g2000~3000円。だんだん日光を浴び育ってくると旨味が薄くなり渋味が育ってくるうえに、葉も伸びるので機械摘みになり量も増えます。こうなると価格も下がり、春の新茶は100g800~1000円で終了します。次に、約45日するとまた芽が伸びます。これが二番茶と呼ばれます。今度は暑い時期に1月半しか栄養が溜まっていないので旨味は少なくなり、この頃の品が100g500円以下になります。つまり、値段の差=旨味成分の差だそうです。煎茶を美味しく入れるには、3人分で一度湧かして70度程度に冷ましたお湯250ml(茶碗の容量は普通100mlで8分目位入れる)、茶葉1人分3~5gだそうです。1人当たり5g使うと3煎まで美味しく戴けます。1杯当たり5gで25円~150円(3杯飲めば8円~50円)になりますね。聞き茶を体験したことがあるが、私にはその差がほとんど分かりませんでした。ですから、凡人には無理に高いお茶を買う必要もないように思います。ペットボトルのお茶は、安い葉を使っている割には高いですね。たまには自分でお茶を入れて、心を落ち着けてみませんか?
2009.05.28
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せは小さな喜びを積み重ねていくことから石垣綾子さんは、「幸福というものは、連続していくものでなければならない。身の回りの小さな幸せを心に抱きとめて生きながら、遠くにある幸福への山道を登り続けて行くときに、小さな身辺の幸福が大きく広がっていく。自分の心で創り出したものではない小さな幸福、つまり手近な品物を持つことにやって味わう小さな幸福は、それきりの途切れた一時的なもので、大きな幸福へとつながるふくらみを与えてはくれない」と語る。私たちは、ものを持つことの幸せばかり追い求めてきました。財貨を得たことによる小さな喜びは、手に入ればそれで終わりです。それは更なる欲望に駆り立て、「もっと、もっと」と終わり無く飢餓感を引き起こします。ですから、いつまでも幸せになりません。幸福は、ある朝、突然に大きな足音をたてて近づいてくるものではありません。本当の幸せは、日常のささやかな生活の中に、小さな喜びを見つけることだと思います。ふだん何気なく見過ごしている小さな幸せを見逃さないで、それを自らの努力で大きく育てていくことです。そんな小さな喜びを積み重ねていくことが、豊かな心の幸せをもたらすのではないでしょうか?例えば、幸せ感覚は、いい言葉によっても養われます。外国人は、「おお、ビューティフル」「おお、ラブリー」「ウエルダン」「ベリーナイス」などと、自分自身もその言葉を楽しみ、人をほめ、励ます言葉をよく使います。美しいもの、素敵なもの、美味しいものに出合ったとき、自分に対しても、他人に対してもいい言葉をかける。たとえ小さなことでも、それは自分の心の中で幸せ感覚として広がり、確かなものになっていきます。いい言葉は、口にした人も、聞いた人も幸せにします。言葉は心に映えて、ますます思いを深めます。豊かな暮らしというものは、小さなことの中にも喜びをくみ取る感受性が根本的に必要なのではないでしょうか。ゆっくりと立ち止まり、見つめ、味わい、言葉に出して小さな喜びをかみしめていくことの繰り返しの中で、物事を深く味わい、喜び楽しむ心が幸せを育んでいくような気がします。そうやって人にあやされ、自分で自分をあやすことで幸せを大きくしていきたいものです。◆ニリンソウ
2009.05.28
コメント(0)
-
京都の老舗も大変
昨日は創業200年のお茶屋(販売)の7代目顧問と5時間ばかり嵐亭で話をしました。洋行帰りの人からリプトンのティーパックをもらい、日本茶のティーパックを始めて作った会社です。最初は水につけても溶けない紙を見つけることが大変で、四国で1社だけやっと見つけたそうです。それを、お母さんのシンガー・ミシンを使って縫ったそうだが、お茶でボビンがつまり怒られたとか。高島屋に持ち込んで販売をさせてもらったが、さっぱり売れなかったそうです。また、お茶壺道中を企画したが、第1回目の当日はジャジャ降りの雨で中止しようとしたら、当日岡崎公園で行われる別のイベントも中止になり、日経新聞からスペースが空けてあり紙面に穴が空くから出発だけでもと言われ、建仁寺を出たが、直ぐにずぶ濡れ。どうせ濡れたなら最期までとやけくそでやったら、各紙の紙面を飾ったよし。一度東京まで歩きたいと言うことになり、予算もないので遷都1200記念行事に持ち込んだら前年のイベントとして採用され、旧東海道を歩くことが実現した。7千万円余かかったが、日本橋についてバンザイしたのを今でも忘れられないという。よき時代の話です。京都には、創業何百年という企業が幾つもあるが、ご多分に漏れず古くからの伝統産業は市場縮小に苦労しています。お茶屋の業界も、ペットボトル全盛の時代になる一方(それも頭打ちだが)、急須のない家庭が45%という調査もあり、お茶葉を売る商売の方は大変なようです。そこで、お茶文化を復興させたいと70代の隠居は熱く語ります。文化事業としては素晴らしいのですが、なにせお金がかかることで、どうやってお金を掛けずにやるかが問題です。その辺りが私の役割だろうが、これから一緒に面白いことが始まりそうでワクワクしてきました。
2009.05.27
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
愚者と賢者の違い愚者というのは、常に不満を持っている人で、死ぬまで事足りる充足感がない。それぞれの時点で、相対的な豊かさじゃなく、自分の満足を早く見つけた人が賢者である。それで人生が終われば、非常に豊かなわけでしょう。他人との比較じゃない、とイラストレータ―の山藤章二さんは言う。充足感とか到達感というものは、自分の中だけで見つければいいものである。低い山に登って「ああ、楽しかった」という人もいれば、富士山に登らなければ気が済まない人もいるわけで、それぞれの満足するバーは違う。個人差があって、他人との比較ではない。他人から見たら、出世もしてお金もあって幸せそうに思えたとしても、当人がそう思わなければ生涯不満で終わってしまう。これは可哀相な人であり、バカな生き方である。ところが、今みたいに過度に情報が多いと、気がついたときには他人との比較になってしまいがちである。情報というのは、圧倒的に成功者の情報が多いから、そういう情報ばかりに接していると、自分が小さく見えてどんどん卑屈になってしまう。情報を吸収することも大切だが、過度な情報に流されないことはもっと大切だと思う。「幸福な家庭はそれぞれ似ているが、不幸な家庭は一つひとつ違っている」とトルストイは言いました。幸せな家庭では家族全員が今の状態に満ち足りてイキイキとしているが、不幸せの種は人さまざまで、家庭によって違うということでしょうか?幸せも不幸せも、突き詰めれば自分の心ひとつの置き所だと思います。生まれたばかりの赤ちゃんは、親のおっぱいさえ腹一杯飲んだあとは、もう何もいらないとばかりに幸せいっぱいの顔をしています。ところが、だんだんと年を重ねるに従って、あれも欲しい、これも欲しい、ああもしたい、こうもしたいと、欲望をいっぱい抱えて、それがなかなか叶えられないからといって「自分は何と不幸なんだろう」と不満でいっぱいなっていませんか?楽しみは 朝起きいでて 昨日まで 無かりし花の 咲ける見るとき (橘)こんな気持ちで身の回りの些細なことの中に楽しみの種を見つけていける人は、きっといつでも幸せいっぱいで生命エネルギーに満ち満ちていると思います。◆もうアザミの花が咲いています
2009.05.27
コメント(0)
-
滅びの笛の音が聞こえますか?
先日、新聞に雀やメダカを見かけなくなったという記事がありました。調べてみると、立教大学の三上修研究員の報告では、最近20年で80%、半世紀前とでは90%減り、現在の生息数は1800万羽とありました。たしかに、昔はどこでも雀を見たものだが、この頃では見るのは烏ばかりです。メダカにしても、何処の川にもいたのが見られなくなり、ペットショップで売っているようになりました。日本では、トキやコウノトリの絶滅が話題になり、再生がなされているが、地球上で様々な生物が絶滅の危機にあります。地球上には約4500~5000種の哺乳類がいるといわれています。そのうち、150種近くがすでに絶滅したといわれています。現在、絶滅する可能性の高いレッドリストに指定されているのは2000種ほどいます。レッドリストに指定されると取引が規制されるほか、積極的な保護活動が行われるようになるが、レッドリストに指定された時点で保護活動が開始されても間に合わない事も多くあります。カエルやサンショウウオ・カメといった両生類は、哺乳類よりさらに深刻な状況にあります。環境の変化に非常に敏感で、その地域にしか生息できない種も多いからです。生息地域の環境が温暖化によって変化すると、食べ物が無くなったり、体温を調節や皮膚呼吸などができなくなる事もあります。また、繁殖活動に藻大きな影響が出ており、温暖化の原因となっている公害物質や酸性雨の影響で、雌雄同体・オスの雌化が現れる固体が多くなっている事も絶滅が危惧されている原因の一つです。特にカエルは、日本国内に生息している種だけでも近い将来までにかなりの種が絶滅するといわれており、研究者たちが少しずつ種の存続のための保護活動を行っています。人間世界にも、豚インフルエンザや鳥インフルエンザ、エイズなどが蔓延するだけでなく、北朝鮮のような国も絶えず、環境問題も待ったなしで、滅びの笛の音が聞こえます。◆飼育されているメダカ
2009.05.26
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
心の掃除をするイライラやクヨクヨがたまるというのは、掃除もしていない部屋で過ごしているようなものである。そんな心の掃除には『感謝』でする」と斉藤茂太さんは語る。よい運命の主人公になりたかったら、心の中に感謝と歓喜の感情を持つことです。人の感情の中には、清いもの、美しいものと、そうでないもの(悪魔)を併せ持っています。卑劣な気持、弱い気持、憎み、妬み、悔やみの気持、怒り、悲しみ、恐れといった気持や言葉は、その人々の血液に毒素を生じ、生理的な不調和をもたらします。だから、いかなる時も、美しい純真な感情で、その心の思考を営むようにしなければなりません。そして、常に美しい言葉を使うとき、より一層よい結果となります。極端に言ったら、病気になっても、不運になっても、感謝することです。「冗談じゃない」と言うかもしれないが、大自然がもっと生かしてやろうとして、「そのままではだめになるよ。おまえの生き方を変えなさい」という啓示だと思うことです。心に感謝と歓喜の念が溢れ、積極的なよい言葉を吐き続ければ、運の方からすり寄ってきます。「お辞儀おばさん」と呼ばれていたご婦人は、「どんなものでもそこにはあるための立派な理由があるはずだし、何かの役に立っている。だから、自然と頭が下がってしまうんだよ」と言って、神社仏閣やお地蔵さんはもちろん、ご飯や橋、大樹にもお辞儀をする。そうやって90歳まで生き大往生した。どんなものにも存在する理由がある。路傍の小石や夜空にまたたく星にだって。我々がただその理由を知らないだけだが、知らないからといって疎かにしていいわけがない。自分が今こうして生きているというのは、もうそれだけで十分にありがたいことだ。そう思うところからスタートすると、大抵のものには感謝できるはずです。そんな感謝の気持ちが自分の心の中にわき起こってくると、大抵のものが自分に味方してくれるように見えてくるから不思議です。◆ビワ
2009.05.26
コメント(0)
-

笑顔は自他を救う
もう2年近くも逢っていない方(起業塾受講者)に「妙連夜話の集い」のご案内を差し上げたところ、「太田さんの笑顔を見たいから」と早速のご返事を戴きました。嬉しいですね。私が微笑みを意識するようになったのは何時の頃からだろうか?私は何度もどん底の体験があるが、苦しい中で「苦しいときほど笑顔を」という智慧が身につきました。つまらない顔をしていると、本当に自分の心までつまらなくなってしまうばかりか、周りの人まで不愉快になってきます。逆に、微笑は人の心を和ませてくれます。赤ちゃんの無心な笑顔を思い浮かべてください。そんな赤ちゃんを見つめていると、こちらも自然と優しい心になってくるはずです。微笑みは、他人に対する尊敬や感謝の気持ち、優しい心でものを見つめることから生まれます。そんな微笑みをいつも絶やさないためには、お化粧の前に不満を取り去ることだと元侍従長の浜尾実さんは仰いました。苦しいからこそ微笑みを絶やさないようにしていると、周りの人が明るくなり、それが自分に返ってきて、そのうちに本当に「明るく、楽しく」なってきます。そんな智慧をいつしか身につけました。今でいう社会福祉ボランティアの草分けであり、日本版マザーテレサみたいな一面を持った東京山谷のバタヤ部落で「アリの町のマリア」と慕われた北原怜子さんが、子供達に口癖のように話して聞かせた言葉があります。醜いものの中に美しさを 卑しいことの中に尊さを乏しい暮らしの中にも豊かさを まずいもののなかにも美味しさを苦しいことの中にも楽しさを ニッコリ笑って発見しよう和やかな顔や優しい微笑みは、お金や品物がなければできないものではありません。その気になれば、誰でも、いつでも、どこでもできることです。そのことが、とれだけ人の心を和らげ、周囲を明るくすることでしょう。そのことだけで、お世話になった社会の恩に報いる行為になります。特にお母さんは、子供たちが帰って来たときには笑顔で迎えてあげてください。◆35歳になる娘が幼稚園で描いた私と飲み屋で描いてくれた知人の私です
2009.05.25
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
現在感謝が煩いなく生きるコツ自分の生命は自分で守らなければならない。そのためにも、消極的に自分の命をスポイルするような表現をしないこと。同時に、それを実行に移す際には、不平不満を絶対に言うな。不平不満を言う奴に限って下を見ない。上ばかり見ている。世の中には俺より幸せな奴かいる。俺より悪いことをしやがって儲けている奴がいる、とかね。それで、自分が一番、何か恵まれていないように思うけれども、静かに下を見てごらん。喰うに困っている人間がどれだけいるか。病人で今死のうとしている人もいる。監獄でもって働いている人もいる。世界のどこかには、死刑の宣告を受けて、今首を絞められている人もいる。明けても暮れても、有り難い、嬉しい、でもっておくれるはずだけれども、あなた方の煩悶は大抵、自分が望むものが得られない時に起きているんだ。自分に甲斐性がなくて、それを自分のものにできないときに、それで煩悶する。一番いいことは、もし自分の望むものが自分のものにならなかったら、現在持っているものを価値高く感謝して、それを自分のものにしてゆきなさい。何に対しても現在感謝。こういう心掛けで自分の人生を生きてゆくと、心の中の煩いというものがなくなっちゃいます。と中村天風は言った。
2009.05.25
コメント(0)
-
人はなぜ騙されるのか
地域の交番から、「給付金の振り込みも近いので振り込め詐欺などにご用心」と電話がありました。近頃の交番も親切なものと感心したが、この電話番号(自宅と違う)をどうして知ったのだろうとチョット心配。ところで、犯罪統計によると、日本で1年間に約6万件の詐欺事件が報告されているが(振り込め詐欺だけで昨年8億円超)、実際にはこの何倍もあるに違いない。「おれ、おれ」詐欺をはじめとして、なぜあんなにいとも簡単に、何十万円、何百万円、何千万円、時には億のつく金をいとも簡単に騙し取られのかが不思議である。一つには、豊かになって、詐欺にかかっても別に生死にかかわるほどのこともない余分の金を持っている人が増えたことである。それが、人々の警戒心を解き鈍感にしている。一つには、地域社会でのつながりが薄くなって相談する人がいないことである。それに、核家族や老人社会になって寂しい人が増え、そんな心のスキに付け込まれる人もある。最大の原因は、もっと多くのものを手に入れたいという限りない人間の欲望である。自分の欲以上の損はしないというか、何を持った途端に騙される危険性が生まれる。ある人は、60歳を過ぎたら増やすことを考えないことと言ったが、それがまっとうな考えであろうと思う。ところで、詐欺師は、人に信用され、説得力があり、相手の立場に立ってものを考えたり感じたりすることができる人である。これは、人の上に立つ人や営業マンには欠かせない資質でもある。詐欺師を見習いたいものである。
2009.05.24
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
ツキを呼ぶ魔法の言葉イスラエルのお年寄りが、「ついている、ついていない、というツキというものはある。そのツキというものは簡単に手に入る。そのツキを呼び込む魔法の言葉がある。これを唱えていれば、誰でもツキっぱなしになる。一つは『ありがとう』、もう一つは『感謝します』で、どんなときでも自由に使っても良いが、ある状況の下で使い分けるとより効果的よ。『ありがとう』という言葉は、嫌なことがあったときに使ったらいい。イライラするときに「イライラさせてくれてありがとう」と言う。どうしてかというと、嫌なことが起きると嫌なことを考えるでしょう。そうするとね、また嫌なことが起きるのよ。そこで『ありがとう』と言うと、その不幸の鎖が断ち切れてしまうのよ。それだけでなく、逆に良いことが起きちゃうの。そして、何か良いことがあったら『感謝します』と言ってみたらどうかな。未来のことでも、未来のそうなって欲しいことをイメージして、『明日、○○させて頂き、ありがとうございます』と言い切ってしまうと、本当にそうなっちゃてしまうのよ。 逆に、汚い言葉、人の悪口を使うと、ツキが吹っ飛んじゃうのよ・・・」
2009.05.24
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
欲は捨てなくていいあれも欲しい、これも欲しいという欲は、人間の煩悩そのものである。煩悩におぼれて、欲しいものを借金して買えばやがて借金地獄が待っている。では、煩悩を捨てればいいのかとなると、私たちはそれほど意志も強くなく、煩悩を捨てようと思っても不可能なことである。だから、お釈迦様は「煩悩を捨てよ」とは言わずに、「離欲=欲から離れなさい」と説いている。たとえば、欲しい物が安く売っているのを見つけたとする。「ワァ安い。これ欲しい」では、煩悩におぼれてしまったことになる。そこで、ちょっと離れて冷静に考えてみる。とりあえず今日買うのをやめてみる。今日買うのを我慢できたら、もう一日我慢してみる。日が経つにつれて、やがて欲しいとも思わなくなってくるはずだ。これが離欲である。物が溢れている中で、私たちが忘れているのはこんな我慢の心である。我慢できずについ買ってしまった結果、狭い家の中は使わない物であふれている。とりあえず、家族がそろったときにテレビを見るのを少し我慢してみるのもよい。会話が弾んだり、ゲームをしたりして、家族の関係がしっくりしてきたという声がある。
2009.05.23
コメント(0)
-
心の時代への一つの試み
先月から、尼さんを囲んでの集いを始め、昨日は第2回目の打ち合わせをしました。始めた動機は、心の渇きを覚える人が多い今日、お釈迦様の説かれた「この世を心安らかに生きる」智慧を、一人でも多くの心の蔵に蓄えて欲しいという願いにあります。お釈迦様は「他に依存するものは動揺す」と言われ、80才で入滅されるとき「この世で自らを島とし自らを頼りとして、他人を頼りとせず、法(正しい教え=民族や信条の違いにかかわらず通用する天地の道理、真理)を島とし、法を拠り所として他のものをよりどころとせずにあれ」と遺言されました。人間は弱い存在で、何かに頼りたくなります。その心をお釈迦様は厳しく切り捨てられました。自らをも教主であることを否定され、どこまでも頼るべきものは、天地の道理であり、その道理に従って生き、生かされている自己であり、その法の前では自分さえ弟子達と同行に過ぎないという姿勢を示されたのです。頼るべきものは、財産でも、肩書きや権力でも、家族でもない。それらは無常という時の流れの中で、たちまち泡沫のように消えていってしまいます。それらは拠り所ではないばかりか、むしろ迷いの根源となります。もちろん、国家やお上でもなければ、神や仏でもなければ、仏像などの偶像でもありません。自分しかありません。誰にも、無性に腹が立つときもあれば、愚痴をこぼしたくなるときもあります。そういうとき、「そんなに腹を立ててもしょうがないがな」「愚痴をこぼしてみたってしょうがないがな」という、私の中のもう一人の醒めた私の声が聞こえてきます。この、もう一人の自己こそが拠り所で、この自己を育てることが大切だとお釈迦様は遺言されたのだと思います。沢木老師は、そのところを「自分が自分を自分で自分する」と仰り、「西方十万億土とは、自分から自分への距離のことだ」と仰ったが、「自分から自己への距離」と言い換えることができます。もう一人の私が育つほどに、その目が澄むほどに、どうしようもない私が見えてきます。「心の旅路」とは、そんなもう一人の自分を見つけ、磨くための長い、長い、永遠の旅路とも言えます。 そのとき、一人ではなかなかできないので、良き師、良き友とともに、良き教えに導かれて、もう一人の私へと通じる道を共に歩もうというのが、この夜話の集いです。それも、かしこまって拝聴するのではなく、車座になって、飲食もしながら、気楽にやろうというのが私の狙いです。そして、この試みがあちらこちらへと広がっていくことを願っています。
2009.05.22
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
森の賢者の声に耳を傾けようノンフィクション作家吉岡忍さんは、尾根やジャングルを歩いてたどり着いたミャンマーとの国境に近いタイ北部の山岳民族の小さな村の村長の家に何泊かした。毎朝、吉岡さんがコーヒーを進めるのだが、村長は最初の日にちょっと匂いをかいだだけで、決して口をつけようともしない。とうとう五日目の朝、なぜ口をつけないのかを聞いてみた。すると村長は穏やかな口調で、「もしそいつが一度飲んだら忘れられないくらいうまいものだとしたら、村は困ったことになる。村長のわしは若い者に言いつけて、何日もかかる遠い町まで買いに行かせるかもしれない。そんなことが続いたら、この貧しい村はめちゃくちゃになってしまうじゃないか」と答えた。振り返って、今の私たちはどうだろうか?今ここにある穏やかな生活に満足せず、何か新しいもの、美味しいものがないかと鵜の目鷹の目で探し回り、後先も考えずに飛びついて食い散らかし、あっと言う間に飽きてしまう。村長の言葉を、森の賢者の声、智慧者の声として耳を傾けたいものである。それが、この限りある地球と共生し、心豊かに暮らしていくためのコツであると思う。
2009.05.22
コメント(0)
-
水尾 米買い道を歩く
昨日は、真夏の陽気に誘われて散歩がてらのハイキング。いつもと違って鳥居本の鮎の宿を左に取り落合へ。隧道の向こうで映画撮影をしていたので(崖があるのでサスペンスものなど多い、この間から気になっていた水尾への「米買い道」を歩いてみました。落合から峠まで40分(迷いそうな所もある)、峠から水尾まで25分(割愛と歩きやすい道)。米の収穫が少なかった村人達は、山の中の細い杣道を通って、約片道2時間近くかけて町まで米を買いに来たようです。ナップサック一つでも厳しい道を、米を背負っての行き来は大変だったと思います。京都は、都会のように思われているが、洛中を出ればもう田舎です。私のいる嵯峨野も、大覚寺周辺は畑や田んぼが広がっています。左京区や右京区は一歩出れば山で、峠を越えた向こうは市内でも、もう限界部落に近いと思います。三方を山に囲まれた天然の要塞であると言うことは、京都は一歩出れば偉大な田舎といえます。水尾は、昔は山城と丹波の両国を結ぶ要所に当り、早くから開けていました。東の八瀬・大原に対して、西の清浄幽すい境として、大宮人にもよく知られていました。 また、水尾の地をこよなく愛し、後の世に「水尾天皇」とも呼ばれた「第56代清和天皇」(850年~880年)ゆかりの地としても知られています。 文徳天皇を父に持つ清和天皇は、清和源氏の祖とされるほか、出家後に修行のために、山城、大和、摂津などの寺院をまわり、帰路、水尾山寺に立ち寄った際にこの地の景観を気に入り、この水尾を終焉の地と定めたと言い伝えられています。新鮮な柚子を使った「柚子風呂」は,古くは清和天皇も好んだとされ、水尾の風物詩となっています。この柚子風呂と鳥すき又は鳥の水炊きを民家で楽しむことができます。柚子の季節になると、都会の雑踏から逃れてのんびり柚子風呂に入り、座敷で地鶏と自家栽培の野菜たっぷりの鳥すきを囲んでくつろぐお客さんで活気づきます。水尾からJR保津峡駅までは府道を4キロ下ります。保津川に降りて岩の上で本を読んでいると、川下りの船やカヌーが目の前を下っていきます。今日という日を楽しんでいる人を見るのは嬉しいものです。新型インフルエンザで京都もキャンセルが相次いでいるようだが、そんなに気にすることはないのではないでしょうか?どうせ人間は一度は死ぬのです。あまり思い煩わず、今日という日を楽しんで、お迎えが来るまで生きていこうと思います。◆水尾の里(こんなに田んぼが少ないところでも休耕田が)
2009.05.21
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
物事は八分目で押さえておく明治の文豪幸田露伴は『努力論』の中で、「幸福にあう人の多くは惜福の工夫のある人であって、悲運の人のほとんどはその工夫のない人である。福を惜しむというのは、倹約や吝嗇ではなく、すべてを享受し得べきところの福を取り尽くさず、使い尽くさず、これを天というか将来というか、いずれにしても冥々たり茫々たる運命に預けておき、積み置くことである」と言っている。花木を育てている人なら経験があると思うが、20輪の花の蕾があれば7,8輪は摘み取ってしまう。花を十分に咲かせ、実をならせば樹は疲れてしまい、翌年には花も実も少なくなる。適度に摘み取って7,8分にしてやると、花も実も大きく、なおかつ樹も疲れないので、翌年もしっかりと花も実もなる。何事をするにしても、八分目で押さえておくことが大切です。二分の余裕を持っていないと、世の中の動き、時の流れに対応できなくなります。「できるときには十分にやらないと損だ」と思いがちだか、十分までやるから損をするのです。後々のことを考えて、八分目にしておくのが一番いいようです。それを、この頃の日本人は、個人も企業でも、みな十分、いな一二分にやろうとします。これでは判断も狂ってくるし、世の中の流れが変わった時に対応できなくなります。たとえば、バブルの時を考えてみてください。「今、株や土地投機などをしない者はバカだ」とばかりに、多くの人が株や土地などに目一杯の投資をしました。最初はおっかなびっくりでやっていても、少し儲かると段々と大胆になり、借金をしてまで目一杯やった結果が、どうなったかはご存じの通りです。あのときに腹八分目で満足した人は、被害を被ることもなかったはずです。何事も腹八分目で、冷静に判断し、余裕を残しておくことが大切です。今の不況も同じですね。◆保津川下りを楽しむカヌー(JR保津峡駅の下)
2009.05.21
コメント(0)
-
善意の押し売り
酒を片手にウットリとしていたら、何の脈絡もなく青山春董という名前が浮かんできました。「確か、名古屋の尼さんで本箱に書籍があったはず」と思って探してみたら、「もう一人の私への旅」という10年前の本が出てきました。「よき師、よき友、よき教えに導かれて、もう一人の私へ通じる道」を説いた本だが、ペラペラと捲っていたら、太田久紀先生の「不害」という言葉の解説に出会った。「善の行為が刃となるということを忘れがちである。善が刃となるとは何か。善の押しつけである。善意のお節介である。それが善の行為であり、善意によるものであるだけに、当の本人は気づかぬことがある。善いことだから、少々押しつけても当然だと思うこともある」とある。確かに、「善いことには違いないが、チョット困ったな」とか、有り難迷惑に感じること、当惑すること、できたらお断りしたいという思いにかられることがあります。本人は、「善いことをしている」という自意識や、「相手のためにしてあげている」という思いが、相手の心の負担となりお荷物になっていることにはあまり気づかないものです。宗教の勧誘やボランティアの誘いにしても、「こんな善いことをあなたに勧めるのよ」という意識に辟易することも多いし、親の子供への愛の押しつけもその一つで、子供にしたら「うっとうしい」ということが多いものです。冷静に見れば、何のことはない、自分を犠牲にして人のためにやっているつもりでいるけれども、実はそれが自分の生き甲斐や喜びやら自己満足に過ぎないということがままあります。利他行に徹しているつもりの心の奧に、いつの間にか忍び込む利己の思いに気をつけなければなりません。インドの詩人タゴールは「あなたを愛させていただくことが、あなたのお荷物にならないように」と言ったが、そういえば、先日私も「私の思いが重荷になっていないでしょうか? 重荷と思ったら遠慮無く降ろして下さい」と言ったことがある。そんな潜在意識が働いて、この文章に出会ったのだろうか? 用心、用心!
2009.05.20
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
足るを知る京都龍安寺の庭に、「吾唯知足」を浮き彫りにした手水鉢がある。それは、お釈迦様がお亡くなりになる前の最後の説法を記した『遺教経』に由来しています。少欲(欲望を少なくする) 寂静(煩悩を離れ心を平静に保つ)精進(ひたすらに励む) 不忘念(物事の普遍的なあり方を忘れない)禅定(心を静めて対象に集中する) 修智慧(智慧を修める)認識(正しく考える)を修めることによって、知足(足を知る)を身につけよという教えです。昔から「足を知る者は、身貧しけれども心富む。得ることを貪る者は、身富めども心貧し」と言い、「満足している者は、最も求める者である」と教えます。この頃はストレス社会だと言われるが、それは「いま」に満足することなく、「もっと、もっと」と求めて得られない不満から起きます。人間は無一物で生まれてきて、無一物であの世に帰るのです。人間が生きていくためには、雨露の凌げる畳一枚の場所と椀に一杯の食べ物さえあれば十分です。そう悟ったとき、貴方は気楽に生きていけるはずです。東京農業大学を卒業したばかりの女性が、自給自足的な農村で無駄のない暮らしを体験してみたくてブラジルに農業実習に出かけた。飛行機を何度も乗り継いで、長距離バスとポンコツの車に揺られ、車の入らない道を馬揺られてブラジル北東部の村にたどり着いたが、「逃げだそうにも逃げ出せないところまで来てしまった」と後悔が先に立った。ちょうど米の収穫期で、彼女の生活は、小刀を使っての稲刈りと、棒でたたく脱穀作業に明け暮れた。手作業なので効率は良くない。でも楽しい。毎晩、人懐っこい子供たちと輪になって手をつなぎ、歌を歌った。テレビのない生活の何と新鮮なことか。ものはないが、必要ならナイフ一本で何でも作る。日本の生活が、いかに無駄なもので溢れているかを思い知らされた。素晴らしい大自然と心温かい人たちに囲まれた生活は、一生の思い出になったと言う。モノに溢れた私たちの生活が、本当に幸せなのかを考えさせられる話である。
2009.05.20
コメント(0)
-
「いま」を精一杯楽しむ
昨日の「ドキュメンタリー宣言」と裁判制度を描いた「家族」を見られましたか?36歳の時にガンを宣告された鯖江市の女性が、余命1年を宣告されて落語に打ち込み(大阪まで片道3時間かけて練習に通う)、昨年8月の余命リミットを過ぎた今も小学校や病院などで落語をしている話でした。彼女は、人に笑いを届けることで自分も生きる力をかき立て、「余命宣告があったからこそ楽しく生きられる」と語る。「家族」は認知症の人を殺害した裁判の話で、認知症患者の家族介護の大変さがからんでいました。この二つの話から、身近な人のことが頭から離れず、こんな文章を書く気になりました。人間は生まれた時にすでに死ぬ運命が決まっていて、死を免れようとしてどうあがいても無駄です。朝に生まれて夕に死す者もいれば、100歳まで元気に生きる者もいます。死にたくないという心から見れば、何百年生きても満足できないはずです。死を恐れて苦労するよりも、生きている間のことを考えるがいいと思いませんか?つまり、生きている間に、なすべきことを精一杯に成し遂げればそれでいいのです。死など恐れるよりも、生を恐れなければない。「なぜ私は生きているのか」ということを考えて、その生きていることを生きているらしくするには働くほかはない、と吉田松陰は弟子だった品川弥次郎に語る。自分は何のために生きるのかを明確に意識し、それに向かって精一杯生きることが生き切ることであり、そこにおのずと生き甲斐が生まれ、幸せな人生をおくれるはずです。ある人は、明日目覚めるとは限らない就寝の床を臨終の床と心得、周囲の人たちへの感謝をささげてから休むことを日課としているそうです。「明日には死ぬ」と本気で思ったとき、生きて暮らしている今日という一日がどれだけ輝いて見えることか。そんな大切な一日を、ぼんやり過ごしているわけにはいきません。なんとなく「いつ死ぬんだろうな」なんて考えていたのでは、毎日毎日がなんとなく過ぎていってしまいます。自分の死を真剣に考えることで、「今日一日を精一杯生きられる」というのが、死を深く見つめた古今の人が共通してたどりつく結論のようです。でも、死を見つめることは大切であっても、死後のことを思い詰めてくよくよする人が多いが、死を考えるとは実は生を考えることだということを忘れないで下さい。古代ギリシャ神話にこんな話があります。母親がヘラ女神の社に詣でる必要があったが、牛車の牛が畑に出ていて使えないので、二人の息子が牛の代わりに軛(くびき)につき、牛車を長い距離を牽いて行きました。用が済んだあと、母親は神に「あの孝行息子たちのために、この世における最高の幸せを授けてやってください」と祈りました。すると、神は、この祈りを聞き入れられた。その時、疲れて神殿で眠っていた二人の息子は、二度と目覚めることはなかった。死によってあらゆる苦から解放され「この世で最高の幸せとは死である」と、この話は物語っています。仏教でも、この世は苦であり、私たちはこの世に修行に来ているのであって、修行が終わった人からあの世に帰ると教えます。そう考えることが、安らかに生きるコツであると思います。
2009.05.19
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
放してみれば簡単に解決するマレーの原住民たちは、ヤシの実の殻に穴を開け、その中に米粒を少し入れて、そのヤシの実に縄をつけてヤシの木にぶら下げておく。すると、メガネザルがやってきて、片手をヤシの実の穴に突っ込み、中の米粒を握る。すると、拳が抜けなくなる。そうやってメガネザルは簡単に捕らまるという。しかしながら、私たちはこのメガネザルを笑えるでしょうか?一旦手に入れた財産や地位を手放す気になれずに、それに見苦しくしがみついている。はたから見ていると、何もあんなに汲々としなくてもと思うが、本人にすればそうは考えない。その財産や地位を守るために喧嘩をしたり、犯罪を犯したりまでする。快適な生活を手放せずに、夏になればクーラーをガンガンかけて冷房病の対策に長袖の服を着ている。クーラーを緩くしたり切ればいいのである。速いからと新幹線で目的地に行き、早く着き過ぎだからと喫茶店や映画館に入って時間をつぶしている。文明とは、そういう無駄を作り出すものである。人生は、放棄することによって、問題が簡単に解決したり気楽にもなれるのにと思う。キリスト教では、天国へ入るためには、狭い門から入らねばならぬと教えます。狭い門から入るためには、すべての持ち物を捨てなければなりません。身分という持ち物も、財産という持ち物も、傲慢という持ち物も、美形や学問という持ち物も、持っては入れない狭い門を潜らなければ天国には入れません。それらの荷は、天国では何の役にも立ちません。いや、そればかりか、かえって邪魔にさえなります。だが、私たちは、誰もが自分中心に生き、自愛と我欲を捨てられません。自分が、神様や仏様よりもずっと大事なのです。神仏のことを忘れても、自分のことを忘れることはありません。自分の好きなこと、嫌いなこと、嬉しいこと、悲しいことは決して忘れません。でも、神様の好きなこと、嫌いなこと、嬉しいこと、悲しいことは全然思い出しません。みんな自分中心です。そして、人と人との我がぶつかりあって、いつも争い心を苦しめています。
2009.05.19
コメント(0)
-
ハーメルンの笛の音が聞こえる
この頃、グローバル社会の怖さと、ハーメルンの笛のことをよく考えます。アメリカ発の世界同時不況、メキシコ発の豚インフルエンザ、アッという間に世界に蔓延です。この頃の環境変化や新インフルエンザ、親が子を子が親を殺し、植物化した若者・・・、異常発生した生物は限界を超えると滅びるとも言うが、いまハーメルンの笛の音が聞こえるような気もします。13世紀、ハーメルンに「鼠捕り」を名乗る色とりどりの衣装をまとった男がやって来て、報酬と引き換えに街を荒らしまわるネズミの駆除を持ち掛けた。ハーメルンの人々は男にネズミ退治の報酬を約束した。すると男は笛の音でネズミの群れを惹き付けると川におびき寄せ、ネズミを残さず溺れ死にさせた。ネズミ退治が成功したにも関わらず、ハーメルンの人々は約束を破り、笛吹き男への報酬を出し渋った。怒った笛吹き男はハーメルンの街を後にしたが、6月26日の朝再び戻って来た。住民が教会にいる間に、笛吹き男は再び笛を吹き鳴らし、ハーメルンの子供達を街から連れ去った。130人の少年少女が笛吹き男の後に続き、洞窟の中に誘い入れられた。そして、洞窟は内側から封印され、笛吹き男も洞窟に入った子供達も二度と戻って来なかった。さて、私達はなんの約束を守らなかったのか?
2009.05.18
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
生きる喜びを大切にガンと闘って13歳で亡くなった猿渡瞳さんは、病と闘いながら「生きる喜びを伝えたい」と次のような作文を書いた。みなさんは本当の幸せってなんだと思いますか。実は、私たちの一番身近にあることを病気になったおかげで知ることができました。それは、地位でも、お金でもなく、「今、生きていること」ということなんです。(中略)この闘病生活の間に一緒に病気と闘ってきた15人の大切な仲間が、次から次になくなっていきました。厳しい治療とあらゆる検査の連続で心も体もボロボロになりながら、私たちは生き続けるために必死に闘ってきました。しかし、あまりにも現実は厳しく、みんな一瞬にしてなくなっていかれ、生き続けることがこれほど困難で、これほど偉大なものかということを思い知らされました。(中略)私がハッキリ感じたのは、病気と闘っている人たちが誰よりも一番輝いていたということです。そして、健全な体で学校に通ったり、家族や友達と当たり前のように毎日を過ごせるということが、どれほど幸せなことかということです・・・。
2009.05.18
コメント(0)
-
心寂しきとき
仏様の最期の修行が微笑みの修行という。現代の宇宙飛行士にも笑顔の訓練があるという。私が40代前後のとき、挫折と絶望を味わったときに心に決めたのも「人前では微笑みを絶やさない」だった。そして、心寂しいときほど人前では微笑みを絶やさないようにしてきた。飲み屋の女将にも、その微笑みを「すてき」と言われたこともある。また、一生懸命に面倒を見てやったつもりでも、黙って離れていく人がほとんどである。すると、つい口から「のに」が出そうになる。そんなことを何度も経験して心寂しくなり、「来る人は拒まず、去る人は追わず」が信条にもなった。そして格好良く、「来る人には安らぎを、去る人には幸せを」などとうそぶいていた。人前でマイナス思考の言葉をはくことを避けてきたが、本心は「語らざれば 憂いなきに似たり」という詩そのものだ。憂い・・・が無いのではありません悲しみ・・が無いのでもありません語らない・・・だけなんです語れないほど 深い憂いだからです語れないほど 思い悲しみだからですまあ、そんな大層なことでなくても時には心寂しくなるときがある。この二日ばかりがそうだった。でも、「ゴッドハンド輝」を見ていて、輝の言葉にやっと心が晴れてきた。「人間というのは、結局、自分が差し出した時間や背負ったリスク以上のリターンを手にすることはできない」「欲っていうのは、一つの所に長く止まると出てくる。振り払うには行動するしかないんです」こんな言葉にも出会い、なにかホッとした。「そうだ 京都、行こう」ではないが、久しぶりに信州に行こうかな?友との最期の旅のつもりだった上高地以来、足が遠のいている。何故かガンも消えてしまった楽天的な友に逢いたくなった。
2009.05.17
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
ソフト化時代の幸せ日本の戦後は、衣食住などすべての面で「アメリカに追いつけ、追い越せ」をスローガンに、ひたすら物作りに励み、それを大量消費してきた。確かに、物があふれるようになった。では、それで幸せがつかめたかというと、決してそうではないはずである。昔に比べれば、生活は格段に豊かで便利になったにもかかわらず、「ありがたい」という気持ちも起こらず、心安らかな日々を送ることも少ない。結局、物に執着している限り幸せにはなれないということである。なぜ、私たちは、こんなにも物に執着するようになってしまったのだろうか?一つは、戦争による欠乏感の反動があると思う。その欠乏かを埋めるために、人を押しのけてでもとまっしぐらに突っ走っている間に、人間関係も希薄にやってしまった。そこで、ますます心の欠乏感を物や金で埋めようとしたのではないだろうか?今私たちに大切なことは、「心の欠乏感はものでは埋まらない」ということに気づくことである。物やお金に幸せを求める時代は、目標が明確なうえに、それを達成する方法も簡単である。戦後の高度成長のように、汗水垂らして一生懸命に働けばいい。だが買いたいものがないというほどに物が充足し、食うには困らない小金持ちになった後の幸せを何に求めるかは難しい。『日はまた沈む』の著者ビル・エモットは、「日本人は富の蓄積よりも、富を何に使うかの方が難しいいうことを知らない」と言っているか、まことに的を得た指摘であると思う。日本は80年代の前半に多くの人が夢みたアメリカンスタイルの生活を実現したところで、ポスト工業化社会に入るべきだったの、富の使い方を知らず、もっと儲けようの一点張りでバブル経済へと突っ走った。そして、一時的に世界一の金満国になったが、その富みを高齢化社会に備えることも、次時代への蓄えに回すこともなく大散財してしまった。今更いくらそのことを言っても始まらないが、大切なことは「しまった」と思ったら、そこで目覚めて今一度「幸せとは何か」を真剣に考え直すことであると思う。
2009.05.17
コメント(0)
-

カキツバタが綺麗ですね
いま菖蒲類が綺麗ですね。もう、水連も咲き始めています。昨日の葵祭にも関連すすr下賀茂神社から数分の太田神社のカキツバタもいいし、城陽の花菖蒲も好きです。菖蒲の仲間は200種類くらいあるそうですが、「いずれがアヤメかカキツバタ」と言われるように、いつもあやふやになってしまいます。簡単な見分け方は、花びらの基のところに、花菖蒲は黄色、カキツバタは白、アヤメは網目状の模様が、それぞれあることで区別できます。左からアヤメ・カキツバタ・菖蒲です
2009.05.16
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
その時その時の自分が幸せソントン・ワイルダーが書いた『わが町』という芝居がある。主人公のエミリーは、子供を産んだあと20歳代で死んでしまう。姑たちも先に死んでいて、舞台の右と左にこの世とあの世があるというシーンで、司会者が「自分が一番幸せだと思う日に、たった一度だけこの世に帰らせてあげる」と言う。エミリーは、12歳の誕生日を選ぶ。もちろんお父さんもお母さんも若く、エミリーは「パパとママが、こんなに若かったなんて知らなかった」と初めて気がつく。家の庭には懐かしくて素敵な物がいっぱいあるが、当時はどれも素敵だと分からなかった。そして、再び死んだ人の世界に帰ってきて、「本当の幸せが分かっていなかった。命が何万年もあるみたいに思いこんで、人間って、生きている時って何も見ていないですね。家族がちょっと顔を合わせたり、今という瞬間が幸せだということに気付いていなかった」と姑に語る。ちょっと立ち止まって、親や友達のこと、親切にしてくれた人のことを、少しでも思って見ることができれば、その時その時にもっと幸せを感じることができるはずである。
2009.05.16
コメント(0)
-
今日は葵祭
今日は葵祭だが、810年に嵯峨天皇の内親王が始めての斎王代を勤めてから1200年の節目とか。今年は裏千家家元の長女が選ばれたが、京都人といえども殆どの人がその方法を知らない。急にポッと公表されるのが当たり前になっていて、「へぇ、今年はこんな良家の娘さんが務めはるんやなぁ」と話題になる程度です。まあ、親子何代も選ばれることが多いが、これはちゃんとした理由があるそうです。斎王代を務めるには、かなりの資金を要するとされています。これは京都の大きなお祭りでは当たり前の事で、務める家が大部分の経費を準備しなければなりません。例えば、祇園祭の稚児さんの大役の場合でも同じです。その大役を引き受けた家がある程度の準備をしなければなりません。そのため斎王代さんは、それ相応の裕福で白足袋族に代表される良家の娘さんが選考されるわけです。
2009.05.15
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せってこんなもの小さな八百屋の「通用口」と書いたドアが開いて、黒いスーツ姿の女性が二人出てきた。「晩酌をして、お風呂に入って・・・」「なかなか出てこないんで、息子さんがのぞいたんですってね」二人の会話の断片から、店の主人が亡くなったらしい。初老の男が出てきて話に加わる。「復員してから死に物狂いで働いてさ。汗と涙の結晶がこれだけさ。店を閉めて、一杯やって風呂につかって。こんなものかね、人の一生なんて」「まあ、ぜいたく言ったらきりがないけど、時々イヤになるわねえ」「でも、ぜいたくいえばきりがない。同じようなものさ、誰だって。三度のご飯が食べられりゃ、それでいいんじゃないの。出世とか肩書なんて、肩に止まった枯れ葉みたいなもんだ。次の風がひと吹きすりゃ、どこかに飛んでいってしまう・・・」私の理想は、この八百屋の親爺さんのように逝くことだ。好きなことをして、こんな具合いに死んでいければ、それはある意味では王侯よりも幸せな人生ではないかと思う。 幸せは遠い山の彼方にあるのではなく、人が気づこうが気づくまいが、実は日々の暮らしの中に何気なく寄り添っているものではなかろうか?山のあなたの空遠く幸せ住むと人のいふ噫 われひとと尋ねゆきて涙さしぐみ かえりきぬ幸せ住むと人のいふカール・ブッセ 上田敏訳『山のあなた』
2009.05.15
コメント(0)
-
人肌の温もりを求めて
この間テレビで「はぐれ刑事」を見ていたら、便利屋に夕食を一緒にしてとか、話し相手になってとか、握手をしてとかいう依頼をする人の話がありました。そのなかで、年老いて都会の息子に引き取られた人が、人との触れ合いがなくなり、人肌の温もりが欲しくて握手を求める話があったが、「そんな?」とウソっぽく感じる人も多いと思うが、これは私も経験したことがあります。夫(私の友人)を亡くした名古屋在住の奥さんが、大阪に寄られたついでに京都の私を訪ねてくれたことがあります。そのとき、別れ際に「この数ヶ月人肌に触れたことがないので握手をして」と言われ、切なかったことを思い出しました。人は、人との繋がりの中で生きているということがよく分かります。「命」という小文を書きながら、フッと「はぐれ刑事」を思い出した次第だが、命を考える場合に3つの側面があることに思い至りました。一つは、気の遠くなるような祖先からの命のバトンを受け継いで「いま」を生きている「受け継がれる命」。一つは、「私は私」であって、他の誰とも取り替えのきかないたった「一つしかない命」。一つは、1人では生きられず互いに支え合って生きている「支え合う命」。「命」を考える場合、この三つの視点から考えることが大切だと思うが、それぞれにいろんな問題を抱えています。まあ、私のような歳になると、三番目の「支え合う命」が大切で、このところ飲み会が多いのもそのせいかなと思えてきます。かくいう私も、今週は3日も飲み会で潰れ、やや二日酔い気味です。そんなボンヤリとした気分を冷まそうと清滝まで散歩がてらのハイキングにでかければ、気分は若いつもりでも身体がついてこず、水際の岩の上で足が滑って強かに尾てい骨を打ち付け、腰の具合まで変になってしまいました。
2009.05.14
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
最高の幸せは安らぎ繁盛している店が手狭になったので、大きなビルの地下に新しい店を借りて商売を拡張した夫婦がいた。今までの店は信用できる社員に任せて、新しい店をご主人がやることにしたのだがなかなかうまくいかない。繁盛していた元の店も客足が遠のいてしまい、出て行くお金ばかりが増えて火の車である。人前ではニコニコしてはいるが、毎晩夫婦喧嘩も絶えない。借金がかさんで、とうとう両方の店とも手放す羽目になってしまった。今では小さなアパートに移り、ご主人は働きに出ている。はた目には「何もかも失って気の毒に」と思われがちだが、奥さんは「従業員の給料や仕入れの支払いをどうしよう、私のいない店で従業員が金を誤魔化しているのでは、と考えて心がささくれだっていた頃に比べれば、天国にいるようなものです」と穏やかに語る。このような話を聞くと、つくづくと心のやすらぎこそが一番の幸せなのだと思わずにはいられない。商売も家庭も、みんな心の安らぎを得るために必要なものである。これを忘れてしまうと、お金儲けだけの商売、見てくれだけの家庭になってしまい悲惨である。辞書を見ると、『幸せ』とは心が満ち足りていることとある。しかし、私たちの心はどれだけ満ち足りているだろうか?収入や資産、地位など目に見える豊かさと、精神や教養、関係、時間など目には見えない豊かさがある。心は、目に見えるものでは本当に満たされることはない。幸せ不幸せは、自分の心の中にある。毎日、今日という日に前向きに感謝して生きることである。
2009.05.14
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
ありのままに任せきって生きる精神薄弱児を持ったお母さんが頭の弱い子供のことで愚痴を言ったら、子供のないお母さんが「あなたは贅沢だ。私には愚痴を言いたい子供もいない」と言いました。これも道理で、たとえ頭の弱い子でも、我が子であるということは、子を持ったことのないお母さんから見れば尊い経験です。だが、無い子は泣かないが、有る子は泣くというように、出来の悪い子を持った人は「こんなことなら、いっそ子供がなかった方がよかった」と嘆く人のが人間です。これはすべてのことに通じます。金があればあったでなければなかったで、地位や名誉があればあったでなければなかったで、嘆くのが人間です。だから、いつまでも心安らかに過ごすことができません。心安らかに過ごそうと思ったら、他人と比べたり、ないものねだりをするのではなく、「今、ここ」に置かれた状況を素直に受け止め、冷静に対処していくことです。山岡鉄舟は「晴れてよし 曇りてよしふじの山 もとの姿は変わらざるなり」と詠んだが、いろいろのできごとは空に浮かんだ雲や霧のようなものと達観することです。つまり、置かれた環境のままに努力することです。若い時に交通事故に遭って失明し、失意と不安からアルコール依存症、自殺未遂などの数々の苦難を乗り越え、演歌歌手としてデビューした井上わこさんは語ります。目が見えないというハンディを抱えていても、このハンディがあることによって、正眼者に負けてなるものかというファイトが発生し、努力を積み重ねることによって人生の道が開けていくことがよくわかりました。障害者だからといって「やってもらって当たり前」という甘えた心は許されない。自分のできることに挑戦しながら、それでもできないことは素直に正眼者の方に手助けをして戴いて、その行為に対して「ありがとう」という感謝の気持ちがあればいいのではないでしょうか。そこに相手も「してやった」ではなく、「させてもらった」という気持ちなります。お互いに心が結ばれ、他人を思いやる心も生まれていくことでしょう。交通事故に遭遇したことが人生の転機となり、感動的な出会いによって閉ざされた心の窓も開いてまいりました。これは神様が私に与えてくれた天命だと思います。なくしたものをいつまでも悲しまず、前向きに明るく生きれば道は開けるものです。◆清滝と山藤の花
2009.05.13
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
豊かな心を取り戻すマザー・テレサは、ノーベル賞を受賞したときに次のように言った。世界中を見渡してみると、貧困は経済的に貧しい国々だけにあるのではありません。西洋にも癒やしがたい貧しさがあります。街頭で助けた人がもし空腹だったら、一皿のご飯やパンで空腹は治まります。しかし、社会から疎開され、不必要とされ、愛されることもなく、孤独でおののいている人の精神的貧しさは、根が深いものです。その貧しさを癒やすことは難しい。どんなに裕福な人、脚光を浴びている人、家族の愛に包まれている人でも、ふと独りぼっちの寂しさを感じ、誰からも必要とされていないと感じるときがある。そんな時、誰か黙って傍にいてくれるだけでよい、じっと話を聞いてくれる人がいたらと思うものです。また、お金を恵むだけで満足しないようにしましょう。お金がすべてではありません。貧しい人々の物質的な貧しさばかりでなく、その惨めさを理解し、精神的な傷口を手当てしてあげなければなりません。私たちが彼らと一つに結ばれ、その悲しみを分かち合うときにのみ、彼らは癒されるのです。日本は物質的には豊かだけれども、何かゆとりがなくて貧しく、心の豊かさを感じられないということをよく聞きます。その理由の一つは、忙しすぎて、今という時に立ち止まり、周りにあるものを深く見る機会を失って、自分に与えられたことをじっくり楽しむことができないところにあります。有名になるとか、お金を儲けるとか、成功するとかということが生きる目標になっているが、静かに落ち着いて生活していくこと、喜びを深めあっていくこと、互いに愛し合っていくこと、じっと見つめ合っていくこと、そういうことがなくては、せっかく人生を生きているのに、砂漠で生きているように味気ないつまらないものになってしまいます。素朴な人生、名もない人生、コツコツ地道に送っている続ける人生、町の平和な生活を伝えてくれる響きの中に人生を感じる、春夏秋冬が過ぎていく・・・、そういう当たり前のこと嬉しいこと、心を浮き立たせることとして心に感ずると、その時あなたは本当に心の豊かな人になります、と辻邦生さんは語る。
2009.05.12
コメント(0)
-
目先からの脱皮を
不況下でも、確実に増収増益をあげている企業があります。 1991年から93年のバブル不況のもとでも、28.3%の企業が増収増益を達成しています。もちろん減収減益であった企業が50.9%と約半数にのぼりたいへん厳しい状況にあったわけです。しかし増収増益をあげている企業は存在します。 同様に、97年、98年の不況期でも39.6%、2001、2002年のITバブル不況でも32.1%の企業が増収増益を達成しています。今回でも、ニンテンドーやユニクロなど過去最高の利益を上げている企業があります。不況時には、確実に減収減益に陥る企業も多いですが、ミクロで見ると必ずしもそうとも言えません。 結局、平均をめざしているわけではなくて、例外(つまり差別化)をめざしている。その例外をどうやって追求していくかが、経営陣の責任だと思います。 いかにして巧くマーケティングを展開してこの不況から脱して、消費者にとって豊かな社会を築いていけるかということが、大きな課題になってきます。ところが、日本人は個人であれ、個人の集団である組織であれ、遠き本質や戦略を追い求めるよりも、目先の目標や戦術的行動を追い求めます。そのために、どうしても同質化し単調になりがちです。個人の場合、「何のために生きるのか」ということを考えることもなく、良い学校に入学し、良い会社に入社し、ポストを一つでも上に昇進するといった目先の目標に邁進します。会社にしても、それ行けドンドンで目先の売上だけに拘りがちです。それでも市場が成長している間は良いが、ひとたび今日のように市場が縮小した途端に赤字へ転落です。トヨタにしても然りです。そして、目先の利益改善のために直ぐに人件費の削減に手を着けます。その結果は、長い目で見たとき技術の停滞と社員のやる気の喪失を招き、会社をジワジワと蝕んでいきます。もっと個人も組織も、本質的なことを大切にしたいモノです。
2009.05.11
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せを感じる人と感じない人財産や名誉がなければ不幸な人もいれば、そんなものがなくても幸せな人もいます。ある状態を不幸に感じるか、幸せに感じるかその人によって違います。状態そのものが人を幸、不幸にするわけではありません。その状態に劣等感を感じる人を不幸にします。財産や名誉がなければ不幸な人は、本人はそれらがないから不幸であると思い込んでいるが、それは錯覚にすぎない。そんな人は際限なく、得れば得たで不幸に思うはずです。世の中には、周りから幸せだと思ってもらうために努力する人がいます。自分がどのような人間であるかよりも、他人にどのように見られるかが重要になった人は不幸です。財産や名誉、地位、外見などにこだわる人は、完全な自己不在になっている証拠です。自己不在だからこそ自意識過剰になるのです。自意識過剰になると、見せびらかすための不要な品が溢れます。人に見せびらかすのは、自信のなさのご恩返しです。虚勢を張らずに、簡素な生活をしている人は自分に自信がある人です。今に感謝し、日々の生活の中に喜びを見いだせる人は幸せです。もう少し自分に自信があれば、どれほど多くの犠牲から解放され、人生を心豊かに楽しめるかわかりません。
2009.05.11
コメント(0)
-
心の時代?
昨日はお昼から電鉄会社主催の「心の時代」という講演会に出かけました。講師である比叡山延暦寺高僧は、関東の人に聞いた話では「葬儀にお坊さんを呼ばないのが9割」、関西でも病院から斎場に直行する直葬が増えているが、それもこれも日本人に宗教心がなくなってきた現れであり、本来はアフターサービスである葬儀に偏重してきた仏教界の結果でもあるとの話をされました。参加者も宣伝の割には、50人の定員に対して8割くらいの入り(それも企画者の知人が多く)で、高齢者が目立ちました。講演とセットになっていた竜安寺石庭も、人が多い上に改修中で侘び寂とはほど遠い環境でした。私主催の尼さんを囲む夜話の会は、10名の女性にメールを送っただけで数名も集まれば大成功と思っていたにもかかわらず、皆さんが友達を誘っておみえになり20代から60代までの人が20名近くも参加して下さり入りきれないほどの盛況でした。四角四面にかまえず、気楽にお酒も飲みながら夜話をしませんかというのが良かったようです。尼さんのお話も、多くの人の前で話すのが初めてにもかかわらず、お昼の高僧のお話よりもグーでした。私の目論みに一歩前進というところで嬉しい限りです。皆さん、仏教には関心はあるが、男のお坊さん方は堅苦しい話の上に近寄りがたいところがあり、敬して遠ざける傾向があるように思います。また、男性陣は仕事一方で仏教や生き方に対して興味を示さないが、本来の仏教の教えは仕事にも随分と参考になることが多いのをご存じないようです。飲み屋の繁盛する秘訣はまず女性をひきつけること、そうすれば男どももついてきて繁盛します。この催しも同じと信じて、まずは意識のある女性を中心に、小さな1歩を踏み出したいと思っています。
2009.05.10
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
便利さの中で失ったもの人間はさまざまな便利なものを創り出した。そうやって創り出した時間は、本来なら読書をするとか、考えるとか、人間として必要なゆとりの時間に当てられなければならないはずだ。ところが現実には、そうした文明が発達すればするほど、どうしたことか人間は物を考えなくなり、本も読まなくなってしまった。ゆとりどころか、いつしか自分自身さえ見失うほどの目まぐるしい社会を作り出してしまった。悲しいことに、人間の習性として、楽なもの、足りたものになれてしまうと、自分から努力して何かをしようとするタガが緩んでしまい、安易な受け身の姿勢にまわってしまう。どうも、世の中が便利になればばなるほど、それに比例して、人間が人間性を失っていくようだ。不便というものは、人間に工夫をさせる。人間は求めても不便を身近に置いておくべきだろう、と僧多聞さんは語る。全く同感である。時計を外し、車を止め、加工食品などをやめてみるとよい。心が時間から解き放たれて自然の移り変わりいるに心が躍り、公害の垂れ流しや不健康な生活から解き放たれ、手間暇かけることによって人間の心が育ってくるはずです。お金持ちになった。物持ちになった。美味しいものを食べられるようになった。でも、それで本当に幸せになったのだろうか?恵まれすぎていると、人の心の痛みがわからない。苦労して初めて、いろいろなありがたさが身にしみる。・今日も一生懸命に打ち込める仕事がある・今日も何事もなく家族全員が元気にそろった・今日も三度の食事にありつけた・今日も楽しく語りあえる友がいる当たり前のように思っているけれども、まことに「有り難し」である。自分が今、ここに生かされている不思議さを見つめ感謝しよう。また風が吹いている また雲が流れている明るい青い暑い空に 何の変わりもなかったように小鳥の歌が響いている 花の色がにおっている。
2009.05.10
コメント(0)
-
点の宗教心から線・面としての宗教心へ
◆日本人の宗教観の特徴は点(儀式・行事)としての宗教心にあるつまり、特定の宗派の信者というよりも、多種の宗教を特定の行事でのみ都合良く選択し、思想(哲学)性の欠如に特徴があると思います。例えば、初参り・七五三では神道、結婚式では神道かキリスト教、お祭りや正月の祝では神道、地鎮祭や建前などでは神道、葬式や先祖供養では仏教で執り行うように、普段の生活にプラス・オンして彩りを添えるものとして宗教を方便として使い、大多数は死ぬまでは神道が中心で死後は仏教と使い分けています。私を含めた日本人の多くは、自分を見つめることが欠如し、普段の生活では無宗教といってもよいのではないでしょうか?◆点としての宗教心から線・面の(生活の中の)宗教心へと転換し心安らかな日々を日本人の6,7割が鬱状態と言われる今日、いまほど「心」の救済を必要としている時代はないと思います。だが、依存の宗教は煩悩を冷まし、心の空虚さを埋める手助けに対して無気力で、その結果、占いや新興宗教、オカルトなどに走るのではないかと思えてきます。今、私たちは点からの宗教心から脱却して、普段の生活に於ける心のマイナス(八苦)をプラスに転換させる(幸せ)宗教心へと転換するべき時にきていると思います。その点、お釈迦様は「明るく、楽しく、心豊かに」幸せに生きるための智慧を説かれたのだから、今ほど仏教の出番が求められている時はないと思うのです。今日は、お昼からは竜安寺で比叡山の山田師のお話を聞き、夜は尼さんを囲んでお酒片手に満月を眺めながら夜話を行います。そんなこともあり、ここしばらく商況談義をしました。
2009.05.09
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せは自分の心の中にある「世の中の人を見ると、財産をたくさん持っている人は、怒りと辱めの二つの難が必ずやってくる。財産を持っていると、人がこれを奪おうとし、自分はそれを盗られまいとするとき、たちまち怒りが出てくる。あるいは口争いから訴訟になったり殴り合いになどになり、怒りも起きてくるし辱めも受けることになる。貧しくて欲張らなければ、まずその難を逃れて心は常に安らかで心配のない生活ができる。証拠は目の前に明らかで、仏教の教文を待つまでもない。それなのに道に暗い人は、財宝を蓄えて常に怒りを抱いている。これは最高の恥じである。貧しくても道を常に思うのが、先賢たちの尊び大いに喜びとするところだ」と『正法眼蔵随分記』は説きます。現在、私たちは大変に物の豊かな時代に生きているが、次から次へと欲望が高まってきて、安らぎからは一層遠ざかっていくような気がします。豊かさの中で失った、物の有り難さや命の尊さなどを感じる心を取り戻すことが、今ほど大切な時代はないと思われてなりません。社会が、成功したか否かを経済の側面からしか見ず、金さえあれば何でもできる社会だから、人々は一獲千金の夢を見て時には人道に反することすら行って金を得ようとする。この悪循環を断ち切るのは、地位的にも金銭的にも恵まれた立場にある人です。この人たちが奢るこることなく、人々の下に降りて奉仕すれば、世の中のすさみはなくなるのです。私が人々にトイレ掃除を勧めるのも、こうした下座の行為こそ、多くのことに気づかせてくれ、人間を謙虚にするからですとローヤルの鍵山秀三郎さんは語る。家庭には電化製品があふれ、街には自家用車があふれ、年間1千万人以上が海外に出掛ける豊かな国=日本になったにもかかわらず、豊かさを実感できず心に飢餓感を抱いている人が多いような気がします。それは、自己の欲望を際限なく膨らませて「足るを知らない」ことからおきます。それが、心のすさみの原因でもあります。この世には、「足るを知る人」と「足るを知らない人」がいると思います。結局、豊かさいうのは心の問題で、「足るを知る人」しか実感できません。ときには、気のおけない友とのんびりと酒を酌み交わしつつ、空を渡る風の音や小鳥の声に耳を傾けてみませんか。
2009.05.09
コメント(0)
-
あなたにとって仏教とは
昨日の仏教に対する議論ですが、恐らくは主婦の方のご意見が一般的なものだと思います。昔からの地元に住んでいる方はまだしも、地元をでた新家の人たちは、実家である法要を除けば仏教に接する機会もなく、60代になっても旦那寺もないというのが普通ではないでしょうか?子供の頃からお経に慣れ親しんだ地方の人にしても、「お経とはありがたいものだ」と無意識に思っているだけで、「何故ありがたいのか」「お経にどういう意味があるのか」を知っている方が果たしてどれほどいるでしょうか?多くの人(特に戦後都会に出た人)は、「宗教は何ですか」と問われれば「仏教」と答えるが、それは実家が仏教だっただけで、自ら求めて仏教徒になったわけでもないというのが実感だと思います。日本人の多くの実体は、死んだときの葬式を仏式でするだけで、精神的には無宗教と言った方がいいでしょう。その葬式さえ、葬祭センターでするようになって、一つの儀式としての仏教があるだけです。昔ながらのお墓も入らないとか、散骨してくれいう人も増えています。その点、キリスト教信者などの方は、自ら宗教を求めた方であり、毎週ミサもあって教えを聴く機会もあります。では、仏教では毎週説話をしているお寺がどれだけあるのでしょうか?京都にいても、真夏の暁天講座は別として、普段は接する機会もありません。私の意見に対して違和感を覚えられた方のように、自ら求め、勉強する方が果たしてどれだけいうのでしょうか?また、自分の生き方について真剣に考えている人が何人いるでしょうか?私はボランティア的に大学生に生きる意味を考えさせるために、今ブログで掲載している「君の咲かせたい花はどんな花」の話を何年もやっているが、今までそんなことを考えたこともない若者達ばかりです。かくいう70才近くなる私にしても、自分が悩んだことがあるから多少は意識があるだけで、そんなことを考えたこともない大人ばかりです。今回行う尼さんを囲む会にしても、男性は声を掛けても興味さえ示しません。だから参加者は女性ばかりです。それも、真っ正面から仏教の話と言ったら、まず参加者はないと思います。満月を眺めながら、お酒も飲み、夜話をするという色づけをして、始めて参加者があるというのが都会人の実体ではないでしょうか?不真面目だと怒られるかもしれないが、何であれ、生き方や仏教に興味を持ってもらうことが大切だと考えています。私は、大人達もそうですが、とくに修学旅行生や京都の大学で学ぶ若者達に命や生き方について考える機会を与える場に京都がなってほしいと願っています。そんな一歩を踏み出せればというのが私の真の願いなのです。
2009.05.08
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
未来に対する不安があっては幸せにはなれない日本の小学校五、六年生にアンケートを実施したところ、その八五%が程度の差こそあれ何らかの鬱状態で、その理由として次の3点が目立ちました。・将来やりたいことがない・別にやってみたい仕事も見つからない・大人になっても特に面白そうでもないあまり目立つこともせず、面倒なこともしない、とりあえず無難に、普通に、みんなと同じファッションで、みんなと同じような行動をしてよれば、誰からも何とも言われないし・・・。そんな覇気のない、ただ生きているだけという姿が見えてきます。一方、働き盛りの三〇代に対する調査では、老後に明るい見通しを持っていると答えたのは男性14.4%、女性15.8%しかいませんでした。子どもが目標を見出せない、大人が将来に希望が持てない日本。なんとなく活力が失われていくようで寂しい限りです。誰の人生でもない自分自身の一回きりの人生なのだから、もっと夢を持って命一杯に生きてほしいと思います。
2009.05.08
コメント(0)
-
仏教談義
お坊さんのブログ記事を読んで私がコメントしたことで面白い議論が展開されました◆ブログ本文(一部抜粋)4/5の日曜日の朝日新聞の朝刊を読んでいたら、"「おくりびと」に危機感"と題して、全日本仏教会長の松長有慶師(高野山真言宗管長)の記事があった。僧侶の立場から「おくりびと」をどう見ましたかという質問に対し、――葬儀はこれまで仏教の専売特許のような面が有ったのに、僧侶を含め宗教者は葬式にはいらないという雰囲気を感じた。と答えられている。確かに、「おくりびと」では僧侶はほとんど出てこなかったように思う。だが私はだからこそ、危機感というよりも、僧侶である自分自身のためによかったと思ったのだ。この映画を見ることによって、僧侶である自分が知らなかったことがわかってよかったのだ。だが、松長師は、――葬儀が形式化し、僧侶はお経を読むだけになってしまったという反省がある。多くの人が病院で亡くなる今、生命は医者の手に委ねられ、かつては僧侶が臨終に立ち会ったが、それが今では葬儀業者の担当である。僧侶が葬儀を通じて死の問題に介在することが難しくなっている。とも仰っている。確かにそれはその通りである。だが、ならばこそ我々僧侶は「生きる」ということについて、もっと目を向けなくてはいけないのではないだろうか。我々僧侶が、この現代でしなければいけないことは、そこにあるのではないように思う。実際には、葬儀の儀式が儀式としてのみ一人歩きし、そんなことに高額な費用を費やすことに意味を感じなくなっている現代人が多いのである。しかしそういう方々は「生きる」ということについてさえも、自分を見つめて考えたことがないのではないだろうか。「生きる」ということとしっかり向かい合うこと、これがいずれくる「死」と向かい合うことになるのだと思う。◆私のコメントこの苦に満ちた現世に生まれ落とされた人間が、「明るく、楽しく、自分らしく、心豊か」に生きるための知恵を授け、涅槃寂静に至るように導くのが仏教を含む宗教の役割ではないのか?檀家制度にあぐらをかいて、その本来の教えを布教することを忘れ、葬式や法事で普通の人には理解もできない無味乾燥なお経を唱えるだけの仏教が存在価値を失うのは当たり前のことです。リストラで職や家を失い、生きる力をうしなっている人たち、年間3万人を越える自殺者などに対して仏教は何をしたか?いまこそ、小さな力でも良いから、周りの人々に生き方について語りかけるときではないでしょうか?◆凡と名乗る人からの反論さて、上のコメントに少し違和感を覚えました。仏教が存在価値を失ったのは、僧侶だけの責任でもないと思います。信じようとしない、伝えない世代があった事も事実で、それは個々人、各家庭などの問題だと思います。理解が不可能であれ、僧侶による供養の読経はありがたいと私は思っています。「普通の人には理解もできない無味乾燥なお経を唱えるだけ」などと言ってもらっては気分が悪いですね。檀家は檀家で、意味を少しでも理解しようとし、「このような徳があるお経なのか、ありがたい…」と勉強し、理解や信心や感謝の心を深める事ができますから。なんとなく不愉快で、つらつらと述べてしまいました。失礼を致しました。◆ある主婦のコメント本日(4月21日)の読売新聞の朝刊12版「くらし」のページに『「直葬」都市部で広がり』という記事がありました。死後に通夜や告別式を行わず火葬するだけという形式のことだそうです。「おくりびと」がアカデミー賞を受賞できた一因は、特定の宗教性が薄かったから万人に受け入れやすかった、ということもあるのではないでしょうか。「千の風になって」という歌のヒットも、同様のことが感じられました。宗教にまったく関わりなく育ってしまったごく一般の人々が持っている宗教に対する近寄りがたさは、おそらく僧侶の方々の想像以上だと思います。実は私も檀家なのですが、マジメな信徒では決してないわけで、たまたま結婚した相手が長男で檀家で、好きで檀家になったわけじゃないしー、めんどくさいなーなどと反抗期の子供のような気持ちでおりまして、でもヨメの義務としてしかたがないか、とお墓掃除したり法事をしたりしてまいりました。そんなフマジメな私が、ある僧侶の方に、無知な質問をしたところ実に丁寧に明快にお答えくださって大変感激したのですね。それでやっと仏教に関心をもつようになりました。公立の学校では宗教は教えないし、一般人にはお葬式ぐらいしか仏教に触れる機会はないのです。ですから、その数少ない貴重な機会がこれからますます減少してしまうのは、やっぱりマズイのではないでしょうか?檀家はまさか「直葬」はするまいと、ご住職様方はお思いかもしれませんが、うちには「跡取り」がいませんので将来私の葬儀もどうなることやら。同様の親戚が2軒ありますし、うちのお寺はこれから確実に檀家が減少していくことでしょう。ここはやはり、僧侶の方々にはぜひとも「危機感」を覚えていただき、お葬式に限らず様々な機会に私たち一般人に親しく語りかけていただきたいと思います。どんなことがきっかけで私のような不良が改心するかもしれませんから。どうかよろしくお願い申し上げます。
2009.05.07
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せはみんなと共にどんな社会や生き方が幸せなのかを手軽に描いてみせることは難しいが、幸せは自分一人でなれるものではなく、周りの人も幸せで初めて自分も幸せになれるのだと思います。とすれば、周りから抜きんでた幸せなどではなく、周りの人々とも共有できるささやかな幸せこそ、幸せの原点だと考えなければならない。競争、競争と勇み立ち、人よりも一歩でも二歩でも先に行こうと自分を励まし、人をも叱咤激励する私たちの社会人は、やはりまだ幸せからはほど遠い社会だといわなければなりません。他人よりも優れているという意識や、衆に抜きん出ているという意識は、幸せにつながる意識というよりも、幸せを捕り逃しかねない意識です。幸せは、他人よりも優れること、衆に抜きん出ることも必要とはしません。日々の暮らしの中で育まれるべきものです。他人よりも優れよう、抜きん出ようという意識に侵されつつある社会の中で、多くの子供たちが晴れ晴れとしない日々を過ごしているというのが、私たちの目の前の風景ではないかと赤門塾の長谷川宏さんは語る。幸せを日々の何気ない生活の中に求め、今に感謝する気持ちを大切にしたいものです。トイレ掃除の実践で高名な鍵山秀三郎さんが、私の友人である内堀一夫さんが担任する高崎市立長野小学校の子供たちに送った手紙の一節が印象的です。みんなが幸せになりたいと思っていても、本当に幸せになることはとても難しいことです。今日は、皆さんが幸せになれる方法を私が教えましょう。自分が本当に幸せになろうとしたら、幸せな人の中にいつもいることですよ。そして、幸せな人ばかりの中にいたいと思ったら、自分が自分の周りの人たちを幸せにしてあげれば良いのです。人に対していつも思いやりの心をもって親切にしてあげれば、周りの人は全部幸せになり、自分も幸せな人の中にいられるのですよ。人間は、自分一人では幸せになれません。本当に幸せになるのは、幸せな人の中にいるときだけですよね・・・。私たちは、幸せをとかく人に求めがちです。そして、叶えられないと言って、親や連れ合い、周りの人たちに不満を抱きます。でも、幸せは決して人から分けてもらったり、与えられたりするものではなく、自分が生み出す努力をしなければならないものです。
2009.05.07
コメント(0)
-
人生も旅
この連休中、多くの人が旅をされたと思います。旅する意味は人により様々だろうが、未知の地にはどんな出会いがあるかというワクワク感と感動があり、知っている地には懐かしい人と出会う感動があります。それが、自分の心を若々しくしてくれます。かっての旅は道中が楽しかった。弥次さん喜多さんの東海道中も、水戸黄門さんの諸国漫遊も、目的地よりも道中そのものに意義があった。遠足や修学旅行にしても、車窓からの見知らぬ土地の風物の移りかわりに目を輝かせたものです。ところが、新幹線や飛行機、高速道の旅が中心になって、道中は退屈なものになってしまいました。人生もまた、ある意味では行く先の分からない(最期のゴールは死だが)旅だと思います。人生とは「自分は何者で、どうすれば幸せになれるのか、充足感をもてるのか」を見つけ出す終わりなき自己発見の旅ではないでしょうか?ところで、最も大切な人生の旅において、「いかに生き、いかに死すべきか」に心を傾けることもなくうかうかと老い、「自分の人生は何だったのだろう? もうやり無しもできない。生き甲斐を見つけることもできずに人生を終わるのか」と嘆く人は多いものです。「人生って、死ぬまでの時間をどう過ごすかってことなのね。そのために何かに夢中になる。何もしないでじっと死ぬのを待っているのって、ちょっと耐えられないよね。でも、何かをしていれば、その間に命が燃え尽きる。問題は何で燃え尽きるか。自分に適したものは何か。それが人の使命でしょ。その与えられた目的に夢中になっていれば、死ぬなんて恐くない」と、歌舞伎役者の坂東玉三郎さんも語ってみえました。理想的な人生とは、坂東さんではないが、死ぬまでの一瞬一瞬を夢中になって燃焼させられるものを持ち、毎日ワクワクドキドキしながら生きていくことだと思います。結局、一生夢中になれて自分の命を燃焼し尽くして悔いのないものとは何か、つまり「自分の人生には生きる価値がある」と自ら思える最大のものとは何かを突き止め、後は、蓮如が「幸せとは、実際に財産や名誉を獲得することではなく、実現を夢見ることにある」言ったように、自己実現を夢みて楽しく歩き続ければいいのではないでしょうか?人生の旅は、昔の旅のように道中が大切だと思います。幼稚園、小学校、中学校、高校は決して大学を目的地とした中間点ではなく、大学も良い会社に就職するための単なる中継地ではありません。平社員や課長も、より上のポストに行くための単なる中継地ではありません。それぞれ年代を大切に、その時代、時代をしっかりと生き、充実したものとして楽しむことが大切であると思う。あなたは、「ただ今」が充実し楽しいですか?楽しくないとしたら、どうしたらいいと思いますか?そんなことを、連休の最期に少しでも考えてみませんか?
2009.05.06
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せは偶然の産物漢字の「幸」、手を上下からはさんだ手枷を描いた象形文字です。つまり、「幸」というのは、刑罰の刑(これは枠の中に閉じ込められ懲らしめられる意味)と同系統の言葉です。刑にかかるのを危うく免れたのが「幸」であり、それから、思いもよらず運良く運んだという意味となり、後に広く幸福の意味となりました。「幸」の本来の意味は、僥倖の「倖」の字に残されています。思いがけない幸運の意味です。だから、幸福とは本質的に「棚からぼた餅」なのです。実はこれが大事です。私たちは幸福なとき、自分が努力したから幸福になった、自分は善人だから幸福なのだと思いがちです。そんな風に考えると、不幸な人は努力が足りないのだ、悪人なのと冷たい目で見るようになりがちです。そしてまた、いつか自分が不幸になったとき、自分自身のせいで不幸になったと思い込んで落ち込んでしまいがちです。幸福は「棚からぼた餅」であり偶然のものなんだと考えると、現在の幸福に感謝し、何時かやってくるかもしれない不幸に心の準備をしておくこともできるようになります。◆クリンソウはこれに似ているところから名付けられたという
2009.05.06
コメント(0)
-
生きるために死を考える
子供の日に「死」がテーマとは縁起でもないと思われるかもしれないが、「死」を考えるとは、実は今をどう「生きる」かを考えることだと思います。ガンを宣告された友もあり、私の心に残る言葉から幾つかをおすそわけ。◆死は生の対極としてではなく、生の一部として存在している。死というものは、生の一つの場面だと割り切り、自分なりに満足する生き方をしていれば安らかに逝ける。◆死に仕度と言っても、なにも暗く考える必要はない。どうせ死は避けられないものだからこそ、楽しく充実した一日一日を送ればいいのである。◆人間は、生まれたときから刻々に死につつあるのであって、死はなにも特別なものではない。刻々の死を意義あらしめるためには、刻々の生を最善を尽くして生きればいい。◆60才になったら、今ある財産を増やそうとか減らすまいと思わないことである。(増やそうとして詐欺に掛かる人が多いですね)◆生きる・・・その実体は瞬間にしかない。先のことは考えずに瞬間、瞬間に炸裂せよ。◆生も幻、死も幻。生のドラマの終幕が死である。長く生きればいいと言うものではなく、充実した舞台を演じた後、悔いの残らない終幕を迎えることこそ最高の幸せである。この歳になると、亡くなる人も出てきて、友人達から死の直前のメールも届く。◆大学のクラブで主将と主務の関係でタッグを組み、彼の結婚時には奥さんから「貴方たちは2人で一人前」と言われたほどの仲だった友人から膵臓ガンで亡くなる直前のメール。不思議に「死」に関して冷静でいられる。自分でも良くわからない。どうしても自分でしなければならぬということが見つかっていないからかも知れないが、これまで、「やることをしたら後はしょうがないでは無いか」と生きてきた一つの諦めのようなものがある。貴兄の信州の友人は治療を拒否してまで現在の生活を維持しているようだが、当方は出来る治療は受けるつもりでいても、その治療が体力的に追いついていけない部分があって往生している。医者に外科手術は出来ませんと言われ、当方からは点滴用のチュウブをつけて生活する気は無いですと宣言したので、これで治療の選択幅はぐっと狭まりました。後は体力勝負であり、病の進行具合次第なのです。「なるようにしかならないな」と思うしかないでしょう。◆上記で信州の友人と言われた彼は、結婚前のサラリーマン時代に新規事業を立ち上げたときにマーケティングを依頼して以来、互いに歳も同じで山好きでもあり毎年行き来をしているが、上記の友人と相前後して膵臓ガンを宣言されたときに上高地に招待したときに送ってきた五行詩。これが最後の 旅仕度か いにしえの旅人には 及びもないが 青葉うれし私は、西行の「願わくば 花の下にて 春死なん そのきさらぎの 望月のころ」を理想としているが、もう春も過ぎ来年しか望みが叶わないが、いざとなったら友人達のように達観できるか心配です。◆クリンソウ
2009.05.05
コメント(0)
-
第2章 幸せって何だろう 番外編
幸せって何?芹沢光治良著『人間の運命』の中で次郎は、「子供心に、財産とは何でやろうか、その財産を神に捧げた(親が天理教に入信)ということはどういうことか、貧乏になって不幸だと大人の言うのはどういう意味か、必死に考えた。自分は貧乏であると知っているが、そのために裸足で学校に行き、一片のサツマイモを弁当にしても、教室で学んだり、運動場で騒いだり、下校の途上に喧嘩をしたりして幸せである。貧乏のために、学校から帰っても、海辺へ打ち上げられる木片を拾いに行き、林や山へ落ち葉をかきに行かなければならないが、未開人のように自然の中に自由に生きていて幸せである。それなのに、大人はなぜ不幸であろうかと真剣に考えた」とある。いま私たちは、確かに物質的には豊かになりました。食べ物は世界中のものが季節に関係なく食べられます。寒さ暑さも、空調機のおかげで快適に凌げるようになりました。移動も、車や電車、飛行機で世界中を簡単にできます。でも豊かな自然は消え、人間関係はギスギスしています。それが本当の幸せでしょうか?例えば後進国に行く。すると、貧しい後進国の人を見て日本人は異口同音に言う。「まあ、可哀想に。見てよ、あの子裸足よ」「気の毒にね、あんなにやせ細って」・・・・そんな人たちに、「可愛そうにとか気の毒にといった言葉は禁句です。その言葉によって、どれだけ傷ついているか冷静に考えてみてください」とひろさちやさんは言うのが常であるそうだ。後進国の子供は裸足で遊んでいる。やせている。日本の子供は、なるほど裸足ではない。上等の靴を履いている。それは事実です。でも、裸足でのびのびと遊んでいる後進国の子と、学校でいじめに遭い、塾通いを強制されている日本の子と、どちらが幸せなのだろうか? やせている後進国の子と、肥満や糖尿高、高血圧などに悩むまでになった日本の子と、どちらが気の毒なのだろうか?ルカ伝には、「幸いなるかな、貧しき者よ」とあるように、貧しいから、裸足だから幸せでないというのは日本人の奢りであり高慢でしかないと思う。
2009.05.05
コメント(0)
全58件 (58件中 1-50件目)