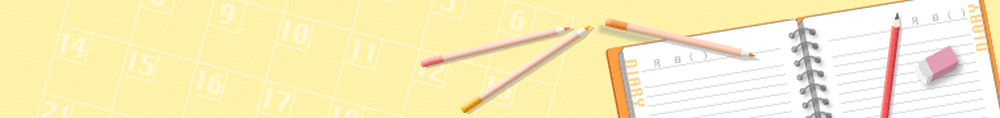2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年03月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
4月から長女が我が社に入社する・・・
時代によって富についての考え方も変わる。蓄積された物が富と考えられていた江戸時代は、『蔵』の数が富の基準であった。が、経済の進歩した昭和では、その物を生産し得る能力、生産力こそが真の富だとも考えられた。それでは生産力だけを増やせばいいかというと決してそうではない。生産は必ず消費が前提でなければならない。いくら生産しても、それが消費されなければ何の値打ちも持たない。消費する力があっての生産でなければならない。消費を創出する力も富だと言える・・・それが現在であり繁栄の道もそこから生まれてくると言える。話は変わるが・・・、来月から長女が我が社に入社する。身震いがするほどやる気を感じる。もちろん、今現在、社員は2人いるが、2人の頑張りにも感動する。自分を信じて集まってくる仲間に感謝、感謝・・・・、感謝しかない。やることが楽しくてしょうがない。
2005年03月30日
コメント(3)
-
《本来》とか《あるべき姿》にとらわれてはいけない
《本来》とか《あるべき姿》を実現できるのであればいいのだが・・・。本来と言う《手順》やあるべき姿と言う《状態》をアナタが知っていればの話だが・・・。判らなければ聞けばいいのだが、《本来》とか《あるべき姿》はなかなか聞けないものだ。その集団では、当たり前のことだから・・・。しかし、《自分に適した本来》や《自分に見合ったあるべき姿》を見つけださない限り、それは言葉の一人歩きに過ぎない。やはり、自分と他人は違う。もちろん、理論も知らず、技術もないのではどうしょうもないが・・・。
2005年03月28日
コメント(0)
-
ごめんなさい。。。
上下関係は、常に『意見の対立と信頼関係』、そして『役割分担と協働』という姿が理想だ。企業の目的を共有し、企業文化を前提に、お互いの経験と信念に基づいて言うべきは言い、主張すべきは主張するというような関係が望ましい。そのように議論しつつも、経験と信念に従い、受け入れるべきは受け入れる。開発を前提として、《課題》を議論し検証することによって、新たなモノをつくり上げる。そういう関係からは必ず、進化が生まれてくる。《問題》に関しては議論ではなく、行動によって解決するしかない。・・・・・・・・創業して、はや3ヶ月になろうとしている。お陰さまで、仕事はある。社員も増やさなければならない、2008年に向けて・・・。・・・・・・・・書き込みしていただいていますが、返事をする環境にありません。ごめんなさい。。。大阪では楽しい企画があったが・・・・次回こそ・・・。
2005年03月22日
コメント(3)
-
たまらなく貴女が好きだ!!
貴女の全てが欲しい!!貴女を強く強く抱きしめたい!!いつもいつも、貴女と同じ時間を過ごしたい!!・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・人を好きになるってことは、大人への階段を昇る五合目くらいかも知れない。『我慢』を『耐える』ことを知る人生の五合目くらいなのかもしれない。人生を左右する可能性のある責任を、初めて自らの決断で取る時期なのかもしれない。そんな昔のことを考えながら書いています。そんな好きな人を想う気持ちを持って仕事に取り組むなら、《成功しない人はいないだろう》と、ふっとそう想った。そうすれば、アナタの最善を尽くした結果が正しく実を結ぶだろう。なのに、何故、毎日毎日お酒を飲んで愚痴ばかりこぼしているの?何故、苦しいそうなの?何故、仕事が楽しくないの?好きになればいいのに・・・。仕事を好きになればいいのに・・・。仕事に《恋焦がれる気持ち》を持てばいいのに・・・。
2005年03月19日
コメント(4)
-
老兵になってはならない
『こんなものだ』と過去を基準に今を判断する。自分を正当化する。そのことが、成功事例であれば、社会に貢献しているのであればまだしも、そうでないにもかかわらず、過去の栄光にすがる。そして100店~200店の出店を考えると『こんなもんだ』と周りを納得させる。《5店~10店》の出店と《100店~200店》の出店に違いがあるかと言うと、そんなモノはない。数で許されるものはない。現場はいつも、お客様が主役。従業員の楽しい職場づくりが基本。ましてや、新規オープンだからと言って許されるものは何もない。そんな考えだから・・・。だからダメなんだとしか言いようがない。老兵になってはならない。静かに消え去る老兵になってはならない。基本に立ち返らなければ・・・。自分にまとわりついてる自分都合の垢は、しっかり落とさなければ・・・。過去を反省し、教訓にしなければ、自分で自分の幕引きをするしかない。
2005年03月18日
コメント(0)
-
金は後からついてくる。
仕事を任せる場合、適任者かどうかということがきわめて重要だが、実際には、なかなか判らない。しかし、何とか行けそうだと思ったら任命する。任せてしまう。高いレベルの人を求めるということも不可能ではないが、しかしそれは非常に手間と時間と金がかかる。だから、これなら『行ける』と思ったら任せてしまう。うまく行く場合もある。もちろん逆もある。それは多分、自分自身の判断基準が問われているのかもしれない・・・。ただ言えることは、最初から完全はないと言うことだ。小が大になる時は、どれだけでも高いレベルの判断基準がトップに求められる。何故ならば、企業は人なりなのだから・・・。やはり、企業はトップと言う人次第だ。人材でもない、ビジネスモデルでも商品でもない。もちろん、金でもない。
2005年03月16日
コメント(2)
-
商道徳はどんな商売にもある
商道徳とは何かというと、それは商売人としての『技の熟練と心の成熟』であると思う。それは、それぞれのビジネスに係わる者としての使命を自覚し実践、ひたすらこれを果たしていくということで醸成されるものだ。それは今も昔も同じであり、永遠に変わらないものと考えている。以前、私が勤務していた洋食のファミリーレストランは、徹底的にムリ・ムラ・ムダを省くことに努めてきた。徹底的に利益を追求し、さらに安く売ることに徹してきた。我々も、そのことで社会の役に立つものだと信じて一生懸命やった。振り返ると、直営チェーンとしては経常利益率業界NO1にもなった。ビジネスとしては正しかったと思うが、食堂業としては正しくはなかったと思う。例えば、日本では、食は本来、《医食同源》といわれてきた。当たり前と言えば当たり前のことだが、食堂業は『健康・安全・安心』の実現がテーマ。・・・・・・本来、人が24時間いつでも食事をすることはなかった。夜中にハンバーグやステーキを食べることが正しいかと言われればそれは、正しくないことだと思う。忘れてしまったことの償いをしなければならない。
2005年03月10日
コメント(0)
-
難しいことはない
コミュニケーションとは何かということについては、いろいろ理屈もあるかもしれないが、何も難しいことはない。普通に考えれば、言葉のやり取りだ。そこからがスタートであり、それは昔も今も同じ。家族の会話では、『おはよう』『顔洗った?』『ちゃんとご飯食べないとね』『いただきます』『おかわり』『ご馳走さま』『行ってきます』『行ってらっしゃい』『車に気をつけてね』などなど。従業員同士の会話では、『おはようございます』『お願いします』『はい了解』『ありがとう』『お先に失礼します』『お疲れ様です』などなど。お客様との会話では、『いらっしゃいませ』『少々お待ちくださいませ』『お待たせいたしました』『またお越しくださいませ』『ありがとうございます』などなど。その場に合った受け答えを、ひたすら果たしていくということ。そうして、言葉のやり取りが出来るようになれば、心が通うようになる。心が通えば行動になる。『心と言葉と行動』の三位一体、それが人間のコミュニケーションというもので、それはどのような『集団』、どんな『場』においても言えるのではないかと思う。
2005年03月04日
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-
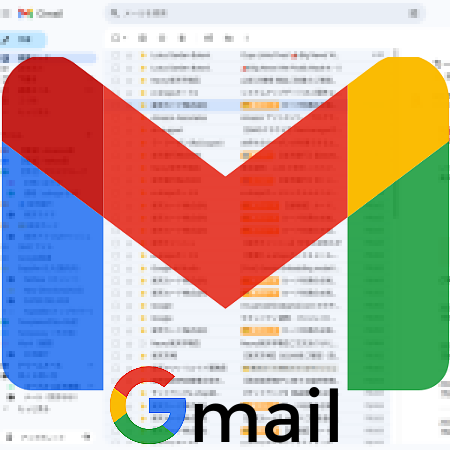
- ニュース
- 2026年1月 Gmail仕様変更! 他ドメイ…
- (2025-11-17 21:04:31)
-
-
-

- 政治について
- 高市「台湾発言」は中国の暴走に対す…
- (2025-11-17 20:23:12)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- 【ETF】売却方針でもおすすめ!?日…
- (2025-11-17 18:00:06)
-