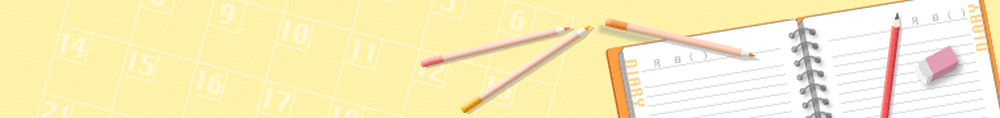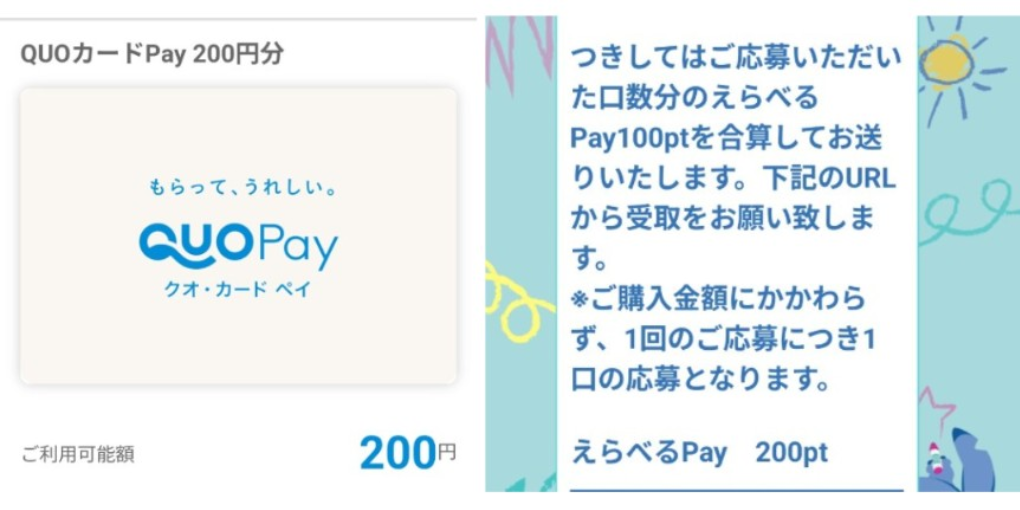2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2005年08月の記事
全9件 (9件中 1-9件目)
1
-
24時間テレビを見ながら・・・
荘園時代の一所懸命。一族郎党が生きるための糧を得る場所を命がけで守る。そして、江戸時代の一生懸命。生きるために必要な収入を得る地位を命がけで守る。そして今、一緒懸命。生きることが精一杯だった時代から人間にだけ与えられた《前頭前野》を活かし切る時代になった。みんなで一緒に懸命に生きる。共に生きる環境を守るために、そして環境づくりに命をかける。やっぱり人間は一人ではない。人間としての本来の生き方に気付く時代になったのかも知れない。
2005年08月27日
コメント(0)
-
エレベーター人生
『矢面に立つ』ということは、大変に勇気のいること。スリルがあるとか、貴重な経験だという人も中にはいるかもしれないが、本音を言えばあまり楽しいことではないと思う。しかし、敢然としてその矢面に立つことは、将来への投資となる貴重な経験となる。だから、経験しなければならないことを経験せずに、作業者から、管理者、さらには経営者として階層の階段を上がることは出来ない。必要な項目を修得することなく卒業なんてありえない。間違って卒業すれば、いつかはもう一度戻る運命にある。上がったり下がったりのエレベーター人生。《一喜一憂》《七転び八起き》の人生を送る。
2005年08月21日
コメント(1)
-
結果として技術の伝承が途絶え・・・
部下を叱れる人が少なくなってきた。ご機嫌をとることはしても、従業員を叱ることが出来ない。でも、怒鳴る人、声を荒げる人はたくさんいる。けなす人もたくさんいる。感情をコントロールする術を知らず、感情をそのまんまに出してしまう人たちが増えてきた。だから、部下は機嫌がいいかどうかを判断し対処する。年齢に関係なく要領よく振舞う。《しつけ、訓練、教育》を置き忘れ、上司と部下は情の世界に入り込み、お互いが甘え、頼るようになる。結果として技術の伝承が途絶えてきた。せめて、企業のトップは従業員に対し《会社に求めるのではなく、会社のために何をなすべきか》を考えるきっかけを与えなければならない。《会社に何かを期待して待っているアナタに会社は何もしてあげることは出来ない。せいぜい、40才になってリストラすることぐらいしか出来ない。そうしないと会社はよくならない。》とはっきりと言うべきだと思う。
2005年08月20日
コメント(2)
-
大きな大きな欲を描く
《欲の深い人》というと、普通はよくない人の代名詞として使われる。いわゆる欲に目がくらんで、『人を殺したり』『金を盗んだり』『人を騙したり』する事件があまりにも多いから・・・・。また、欲に眼がくらみ進むべき道を間違う人が余りにも多いからだろう。しかし、人間の欲望というものは、決して悪の根源ではなく、人間の生命力の現われでもある。例えて言えば、船を動かす蒸気力のようなもの。これを悪としてその絶滅をはかろうとすると、船を止めてしまうのと同じく、人間の生命をも断ってしまうことにもなる。欲望それ自体は善でも悪でもなく、生そのものであり、力だといってよい。その欲望をいかに善に用いるかということこそ大事だと思う。そのためには、ちっぽけな欲は持たないことだ。ちっぽけな欲は自分のことしか考えられなくなり、相手が見えなくなる。目先のことしか見えなくなる。だから犯罪に結びついていく。欲を正しい力に変えていくには、大きな大きな欲を描くことだ。それは社会との係わり・・・つまり社会貢献。実現するか?しないか?なんて考えなくていい。実現に向けて努力しさえすればいいだけなのだから・・・。余分なことも考えなくなるだろう。私は、大きな大きな欲は、別名《夢》と言えるのではないかと考えている。
2005年08月15日
コメント(0)
-
『料理が下手』な奥さんに感謝
料理をすることを習慣づけると、前頭部の血流が良くなり、判断したり計画を立てたりする脳機能が向上することを、東北大と大阪ガスの共同研究チームが実証した。調理中の能の動きを光トポグラフィという装置を使って観測したところ、○献立を考える○野菜を切る○いためる○盛り付ける―のいずれの時も、判断力や計画力をつかさどる前頭前野が活発に動いたということだ。この『前頭前野』は大脳の一部で、おでこのすぐ内側にある。思考や感情をコントロールしたりという、《人間ならではの知的活動の中枢》で、『能の中の能』と呼ばれている。慢性疲労などでこの部分の機能が落ちると、『善悪の判断がつかない』『計算ができない』『何処に行くつもりだったのか分からない』などの認知力の障害が起きる。人間の知的活動の中心であり、この機能を保つことが認知症(痴呆症)予防に重要とされる。老若男女を問わず、日常的に調理を楽しむことが、能を鍛えることになり痴呆症の予防にもなる。能と体の健康のために調理をすることは善いということだ。ある意味、『料理が下手だ』と奥さんに不平不満を抱いていたご主人は、結果として奥さんに感謝しなければならない。調理が好きになったきっかけは奥さんなんだから・・・。
2005年08月13日
コメント(4)
-
正しい意欲
新しいお店は、新しモノ好きな消費者の要望(ウォンツ)と開発者とによるお値打ちのやり取りが利便性、価格、雰囲気、サービス、そして商品等々という形となって繰り返され、よいお店になっていく。つまり、多くの生活者に贔屓(ひいき)にしていただき、支えていただけるようなお店に仕上がる。それは、現場で《お客様の声を集めて上司に報告する人》《使い勝手や作業手順の改善を提案した作業者》、そんなひとり一人の開発者がお客様の声を反映する努力をしたから、多くの人に指示されることになった。お店の従業員ひとり一人の正しい意欲の結果がお店の繁栄につながる。そんな仕事への取り組み方が出来る人って素晴らしいですよね。もちろん、そんな人は常に問題を自分に置き換えて考える人でもあり、当事者としてモノゴトに取り組む人だ。そんな前向きな考えの人々のお陰で、新しいお店は世の中に受け容れられるようになっていく。やはり、それは商品でもサービスでも同じことが言える。そんなひとり一人が集まる会社にしなければならない。
2005年08月12日
コメント(0)
-
『あの手この手』の指示命令
ある企業で、お盆休み期間、働く人の確保が出来ないから『店長がオープンからクローズまでの通しをやれ』『アルバイトには、12時間勤務をさせろ』という指示が出た。説得の口上は、『上司の私もやるから店長であるアナタがやるのは当然だ』『○○店長と△△店長もやるんだから、アナタにもやってもらわなくては困る』『人がいないんで、皆で協力してもらわなくては困る』もちろん労働基準法違反あり、労働契約違反ありのオンパレード。『あの手この手』の指示命令。『モグラたたき』的な対処療法。でも・・・・・・・・・、気合と根性でやる集団ではそんな指示があっても許せるかもしれない。たぶん、親分・子分の世界では、間違いなくその見返りがあるはずだから。そのような《人間関係も出来ていない》のに、《伝えるべき技術もない》のに、平気で労基法を違反する企業文化には、人は魅力を感じない。だから、募集しても人は集まってこない。人が集まらない原因を考えると原因は何処にあるか明白だ。しかし、当たり前のように、《従業員の幸せ》を標榜する企業で平然とそんなことが行なわれている。だから、外食産業に人が来ないんだ。だから、産業として育っていかないんだ。やるしかない。自分でやるしかない。
2005年08月11日
コメント(1)
-
楽しんで仕事に取り組む
いかなる産業でも、産業になる途上では、楽しくてむちゃくちゃ働いた人々がいたことは事実だ。それは自動車、家電そしてコンピュータなど、どの産業でもそうなのだと思う。私は今、世の中の《食を楽しく豊かに》していきたいという考えのもとに、楽しんで仕事に取り組んでいる。だから、楽しくてむちゃくちゃ働く集団を形成しなければならない。これが産業化につながる唯一の方法だろう。。。もちろん、産業化以前だから意味もなく《楽しんでやれ》と言うつもりはない。内容的には非常につらい作業の多いフードサービス業の中で、《自分たちだけのやりがい》を見出すためには、全部のフードサービス業がやっていることを否定していかなければならないのではないかと思う。うちは違うぞと言う差別化を打ち出さないと、働いている人は楽しくならないだろう。それは、《健康・安全・安心》をテーマに《医食同源》《地産地消》《食育》と言うことだ。《私はそれをやっている》という自信が持てる企業にしょうと決意をしている。
2005年08月07日
コメント(2)
-
墓参りに・・・
明日の朝、久しぶりに大分に帰る。畑が待っている。雑草が待っている。サトイモが待っている。墓参りにも行かなければ・・・。
2005年08月03日
コメント(0)
全9件 (9件中 1-9件目)
1