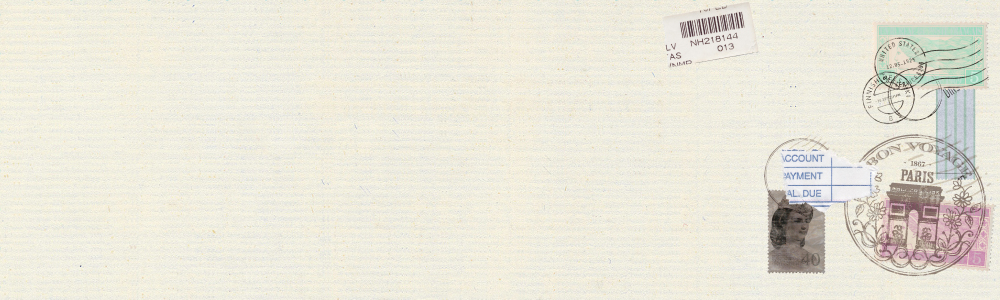2008年01月の記事
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
JAZZのお勉強
風邪か?頭痛気味。今日の練習は、Ad_lib書き。テーマをvoicingして覚えながら、ぱらぱらアドリブをしてみる。その場でぱらぱらとは弾けるけれど、楽譜に書き出すと考え込んでしまう。あまり止まって考え始めると、今度弾く時に弾き難かったりして。。定型句を入れたいとフレーズ集を参考に。フレーズの全調移調の練習も必要だと感じる。3コーラスくらいまで目標に。今日は頭痛いのでここまで。。
2008.01.31
コメント(0)
-
JAZZのお勉強
モード系とbopでは左のvoicingが異なる。モード系から入ったので、3rd or 7thからの積むvoicingばかりでは対応できない。ピアノ・ソロとしてメロディーと同時にvoicingする方法はあるところで少々やったが、bopってトリオでbassがある時とソロと同じvoicingでいけるってことなんだろうか???それなら、bopができればソロも怖くないってこと?!ということで、voicingのテキスト第1~3章、bassを押さえる2音、オブリを入れた3音、4音も練習のプログラムに組むことにした。今日はbop系のplayerのコンボシリーズの採譜を入手したので全体的にvoicingのみチェック。やはりローインターバル・リミッテド以低より3度重ねることはしていない。10度でうまく処理されている。soundとして違和感はない。。。bopでもvoicingの見解に間違いはなさそうだ。YouTubeでこのplayerの映像をダウンロード。flvからQuick Timeに変換できれば音源だけとか、映像みながら打ち込んでfinalに変換すればすぐ楽譜になるんだけれど、対応ソフトがOSのバージョンに対応してなくて残念。。いくつかやってみたい曲をMDに落として、1曲耳コピー始める。Interviewがかぶさっていて、Introはじめから鮮明には聞き取れないけど、途中からはOK。バラードなのでIntroとテーマのみだけど、ad_libもやってみるつもり。と同時にCD取り寄せ予定。ad_libもしっかり書いて作品として完成させたい。standardは採譜がいろいろでているけど、bop系の採譜って少ないなぁ。。自分で耳コピーするしかない。。There will never be another youLamentOne and only Loveしばらくこの3曲で。テンポの速い曲もやりたいなぁ。。CDとbop系の本の取り寄せを計画中。円高のうちに、アメリカから取り寄せ。現在レートは約107円。
2008.01.30
コメント(0)
-
これほし~い!
昨年から気になっていた。今日、講座で直接さわらせてもらって、気に入ってしまった!手にすっぽりおさまるくらいの大きさで、おもちゃみたいでloopは2小節程度だけれど、DAWに取り込んで使えそう。昔、Phat BoyというMIDIコントローラーを購入したけれど、使い切れなかった。2つ以上のコントローラーを楽器のように体で操作するには今イチ使いづらかった。でもこれはピッチ、フィルター、gateなど同時に感覚的に操作できる。それに音源付き。DAWのエフェクトは精巧なものが組み込まれているが、かける順番等によって効果も異なるので迷う。DAWという機械で音楽を扱うにしても、数字じゃないよなぁ、微妙な感覚は数字の打ち込みでは置き換えられないものだ。楽器を体の一部のように操れるように扱えなければ、心に響くものはできないだろう。身体感覚を数字に置き換えることはできても、その逆は難しいものだ。ところで、講座の終わりに先生とコルグの話になり、たしか何年か前にヤ0ハの関連会社になったはずだという話をした。コルグもヤ0ハに似たシンセを出したはず?、と先生はあまりご存知なかったみたいだったけど。改めて調べてみてびっくり。私はもとヨーロッパかどっか海外の会社だとばっかり思い込んでいたが、なんと日本の会社だった!創業者KさんとOさんとの頭文字をとり、そのお二人が作ったorgu(仏でオルガンの意)でコルグとなったらしい。知らなかった。
2008.01.29
コメント(0)
-
Jazz教室発表会の見学。
あるJazz教室の発表会の見学へ行ってきた。bopを教えてくれる教室を捜していて、普段のレッスン見学は出来ないが発表会は見学できるということで尋ねてみた。ライブハウスが教室となっていて、駅からも近く雰囲気もいい環境だ。発表会はレベルに応じて4部にわかれ、はじめの部は課題曲が決まっている。全員誰でも発表会に参加できるわけではなく、その課題曲を先生のお墨付きがでないと演奏できないらしい。参加できるのは1部であろうとある程度のレベルがなければだめなシステムらしい。上の部にいくほど曲数も2~3曲へと増え、4部はライブ経験者たちの演奏で、ミニライブといった感じでの演奏だった。発表会といえども、先生が一番前の演奏者のすぐ後ろに腰掛け、演奏を逐一チェックをしていた。演奏後、先生の講評が行なわれ、カウントの仕方に始まり、DRやBassへの合図やサウンドのコントロール、イントロ、テーマ、アドリブなどれぞれに出来不出来を逐一指摘。椅子のきしみから腰の安定度までチェック。(それにしても生徒さん、椅子の高さの調整をしている人は2人ぐらいしかいなかったなぁ。高めで弾いている人が多かった)まるで、公開レッスンとまではいかないけれど、試験の講評ような雰囲気だった。生徒さんはトリオでの演奏をする経験はあまりないであろうから、客観的にトリオやアンサンブルをする際のマナーや気配り、心配りのポイントを実地で指導することも兼ねているとしたら、たいへんきめ細やかな指導をされる先生ということになる。発表会というより、これもレッスンの一部という印象。カウントは足でとり、DRとBassに聞こえるように送っていた。また演奏中、足でカウントをとることを先生はチェックしていたようだ。演奏者各自、譜面台には大きな手描きの楽譜が置かれていて、アドリブを全部書いて、それを見ての演奏。アドリブを細かくチェックしてくれるとしたら、これはいい勉強になることだろう。あまり楽譜におこしたものをレッスンで見てくれる先生って今までいなかった。サウンドや音色にも細かくこだわって指導されているようだった。bopってもっとがんがん演奏するものだという印象を持っていたが、エレガントな音、、、というより、なんだかこわごわ演奏しているような印象だった。生徒さんがまだあまりトリオ演奏に慣れていないからなのか、ピアノ経験が浅いからなのか(でも中にはピアノの指導者が2名いた)、、と思いながら後半の部の演奏者の音が気になったが、ラストのお二人は割合明確な音色だった。音の出し方にも好みがあり、その方向性が異なるとやっかいなことになるだろうなぁと思いはじめた。ラストの人は男性だったこともあってか音色もよかったし、上手で好きな演奏だった。こんな演奏をする生徒さんがいるなら、いいかなぁ、、と思ったが、「音が雑だった」、、また、「自分がリズムにのるために刻むようなbackingならレッド・ガーランドようになってしまい、~のようにはならない」、、と講評されたので、少々がっかりしてしまった。先生の信望する~のようなプレイーヤーでなければならないようだ。とても丁寧に指導されていてレベルも高い生徒さんばかりで、アドリブも確実に上手になるような指導をしてもらえそうだとは思ったが、2点どうも気になった。ひとつは、左のvoicing。今までの先生はどちらかというど、モード系だったのでrootlessで3rd或は7thから積むやり方だったが、どうもbopはrootを必ず押さえよというものらしい。root-7thなら別に問題はないのだが、low-interval-limittedで3度を押さえる音がどうも気になってしかたがなかった。事前にこの先生のCDを購入して聞いた時に、はじめに気になった点がやはり生徒さんの演奏にも同じことを感じた。bopがすべてこういうサウンドになるのか、あまり聞き込んでいないので判断ができない。この先生の特徴なのか、bopそのものの特徴なのか、今の私には勉強不足で判断できない。慣れていないからか、とにかく、あまり生理的に好きでない。気持ち悪い。。もう一つはピアノのタッチ、音色だ。もちろんclassicとJazzでは発音は異なるが、どうもエレガントすぎて、ピアノという楽器の表現力の広さを利用しきっていないようで、心に入ってこない感じだ。生徒さんなので仕方ないのか、それにしても、皆同じような音の出し方だったので、少し疑問に感じた。たぶん、私の音色には合わないだろうし、これを一から変えるとなると、人生終わってしまいそ~。アドリブに慣れてなくてまだ下手でも、もっと個々の生徒さんの個性が現れる音色や演奏であってもいいのではと、私は思う。アドリブのレベルは高いが、同じような印象の演奏ばかりだったと、後になって思う。私自身、型にはまることを求められるレッスンにはおそらくついていけなくなるだろう。。生徒さんの演奏にも、こじんまりきれいにまとまるよりも、自分が表現できるような演奏をしてほしいと思っているから。先生の好みはこっちだろうな~なんて顔色うかがいながらレッスンを受け、演奏するのはあまり性に合わない。最後の演奏者の間まで、悩みに悩んで、講評を聞いて「あぁぁ~」と肩の力が抜けてしまった。この先生に習う覚悟が、今日の時点ではつかなかった。DRもBassも若手ながらいいプレーヤーで、ライブハウスをやっている所なので、トリオでの演奏の機会を持てるチャンスも高いであろうことは、大変魅力的だ。知らない曲の多いBopを丁寧に教えてもらえ、またアドリブも書いたものを指導してもらえるだろうことも捨てがたい。でもでも、、でも、、気になる点が。音は正直なのものだ。発するほうでも、受け取るほうでも。まだ先生探しは続きそう。。
2008.01.27
コメント(2)
-
今日のレッスン・メモ
ジャズ・セミナーの生徒さん、いい感じのswing!ぐいぐいドライブした演奏になってきた。"On Green Dolphin Street"の生徒さん、子供会の役員のお仕事で忙しいと言われていたがどんどん弾いてこられる。クラシックとは違うものをやってみたかったという理由でジャズをはじめたが、自らCDを集めてたくさん聞いているようで、弾くにしたがって自分のグルーブがどんどんでてくる。グレードの勉強でクラシック曲やポピュラーも何曲かやったけれど、この人には一番ジャズがあっているのかもしれないと思うほど主張がある演奏になってきた。早くデータつくらなければ、、。コード押さえながら一緒に楽譜おっかけていたら、細かいニュアンスが聞けない。次回からアドリブにとりかかる。前回スケールの話をかいつまんでした。ほんとうに必要なところだけなので、今整理中のスケール一覧表を完成させて、次回は体系的にスケールのお話をしたい。テーマにしたがって左のbackingしながら各スケールを弾けるように宿題にした。エバンスの「枯葉」の生徒さんも、データをパソコンで聞ける環境を整えてもらっているが、今日ある人から「伴奏君」を譲ってもらえるようになったと報告。これで練習環境はばっちり!カ0イ系の講師さんで自宅レッスンをされているので、子供さんのレッスン用のデータの情報もお話した。ヤ0ハ系のデータが多いんだけれど、、いいんだろうか?!ロー0ンド系のデータならいいっか!自分のレッスンだけでなく、お仕事にも使えるならば一石二鳥。クラシックで一人で弾くことに長年慣れてしまっているので、アンサンブルという感覚が少し薄い。自分が弾くことに夢中になってしまうのでドラム、ベースが耳に入ってこない。ベースのパートだけ集中して聞いてもらった。いろいろ発見があったようだ。テンポ・キープするのがやはり苦手。「伴奏君」が入手できたなら、飛躍的に改善されるだろう。次回からこちらもアドリブに入る。「花」を練習中の生徒さんも、練習用のデータのおかげで一定のテンポで演奏が流れるようになってきた。前回からの宿題で、コードの復習。大人Pのコースなので、本来はポピュラー・ピアノ科でやるコードの説明やコードを使うことはやらないのだけど、音楽をやるには最低限必要な知識だと私は個人的に思うので皆さんにコードの構成音くらいとはさっとわかるようなトレーニングをプログラムに組んでいる。3和音の作り方、さらに7thの積み方、sus4コード、復習でだいぶ思い出されたようだ。次回から間奏部、コード進行は決めているのでそれにしたがってメロディーを作る作業にはいる。コードから音を選択して、まずは弾くことから宿題に。「難しそ~!」と言われたけれど、「お洋服の組み合わせ、トップとボトム、それにアクセサリー、バック、靴など好きに組み合わせるのと同じですよ。」とアドバイス。正解なんて無いし、間違いもない。好きか嫌いか、自分のセンスに合うか合わないか、そんなところから音を選んでもらうことで創作につなげていってみたい。人の作ったものでなく、自分だけのもの、自分で創作できることの楽しみを知ってほしい。さてどうなることやら。。「愛の讃歌」を発表会で演奏される生徒さん、いつもは電子ピアノでレッスンしているが、今回ベーゼンで演奏できるからと、生ピアノでレッスンをしている。左の分散の箇所の弾き方をすくいあげるようにとアドバイス。最後の親指が下向きに重力がかかってしまうので、肘をサポートして動きの感覚を覚えてもらう。どうも力が入るとなぁと思っていたら、脇が閉まってしまう。脇が閉まるということは、力が入っているということ、自覚された。脇があくということは肘が自由に動くことになる。肘の動作で音色の違いにも敏感に反応した。やはり生ピアノだ。ペダルだけでなく、ちょっとした音色の違いがつぶさに音に影響すること、実感されたようだ。この生徒さん、実は生ピアノをお持ちなのだが、練習用にとわざわざクラビを購入。確かにデータを使えるので楽しみながら練習でき、歌うのが好きな方なので時々、カラオケ代わりにも使われているようだけれど、ピアノをきれいに弾くためには生ピアノの方がず~っといいんだとわかってもられたようだ。このパターンは幸い、8小節だけなので、左の動きの練習を集中的にしてもらう宿題をだした。ジャズ・セミナーの生徒さん対象にダウンロードしたMIDIデータでII-V7-Iのトレーニングはとてもいい!一様押さえられたら合格にしていたけれど、一定のテンポにのって全調種々の並びで押さえられるというモデルパターンがあるので、満足感も違う。頭で理解していても、一定のテンポにのって音楽的な流れで弾けなければ、練習の意味がない。各自でダウンロードしてもらえるので教材としてはありがたい。
2008.01.25
コメント(0)
-
今日のレッスン・メモ
テクニックと音楽の内容とは切り離しては考えられないものだとよく言われているが、レッスンでそれを感じることが多い。ちょっとしたフレーズだけれど、弾きにくそうに、或はよくつまづき弾き、弾き直しが多い箇所を見直してみると、必要のないところに力が入りすぎていることを発見する。弾いている本人は楽譜通り指を鍵盤に置くのに精一杯で手の中は力が入ったまま。指で弾くだけが打鍵ではない。腕の重みで適切な音量が無理無く出る。ブラームスのラプソディーの中でもそういう箇所があった。右手の2声、さらにその1声がオクターブになる所。オクターブを指で弾くため押さえこんでしまい、細かく動く内声が力んでしまって動かなくて弾き難そうになってしまっている。オクターブは腕の重みで弾き、その他の内声の動きはその反動で脱力して押さえつけないで軽めに弾くのがこつ。片手の2~3声や和音の難しいところだ。ブラームスのバラードも、トップのメロディーをしっかり響かせたいのだがなかなか音色が変わらない。メロディーと共に内声の和音も押さえなければならないので、和音に力んでしまう。その内声の和音を少し早めにあげてしまい、メロディーに重心を持っていくようにすると、埋もれてい待った音が整理されてトップが鮮明に聞こえてくるようになった。ハンマーが弦に当たるのは一瞬で力はその一瞬だけなのに、ダンパーが弦に戻らないようにキープするために必要以上の力を込めて鍵盤を押さえ込んでしまっていることが、初心者はともかく上級者でも多いのだ。頭では理解していてもどのフレーズでそうなってしまうかを個々に見分け判断する観察が必要だ。だいがい弾き難そうにしているフレーズは指使いをはじめ、こういった問題が関連していることが多い。特に弾いている生徒さんが自覚するのが難しいので、横で見極めてディスカスして意識してもらうことが必要なのかもしれない。初心~中級者も、指で弾くことに意識がいってしまって、腕でポジションを移動するということが連動してこない場合がある。それと鍵盤に触れてから打鍵するという2つの要素が同時にできてはじめてフレーズが流れる。「誰も寝てはならぬ」を練習中の生徒さんの場合、基礎練習でも肘が動かず固定してしまっていることがある。肘の動きを意識しもらうと力が抜けるが、固定していると手のポジションの移動が腕でやり難いようだ。曲の中で弾き難い、つまずく箇所を観察していくと、基礎練で言っていることに戻ってくる。反対に曲中での難箇所をを観察することで、ほんとに必要な基礎的なテクニックが何かが明らかになってくる。決して特殊なテクニックではなく、楽に、体にとって自然に弾ける方法を自分の体とコミュニケーションしながら捜していくこと。自然であるということが何より重要なのかもしれない。
2008.01.24
コメント(0)
-
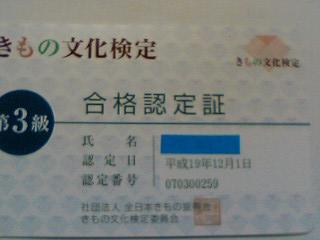
きもの文化検定3級~合格認定証届く!
昨年受けた「きもの文化検定」の3級。答え合わせする気もうせてしまったほどのできだったので、どうにでも~、、と思ってたけれど、どうにかなっていたようで、合格認定証が届いていた。今回は切り取り式でなくて、書類からペリッとはがすカード形式。うす~いですが。。合格率は約40%。時間が出来たら、またゆっくり問題を見直してチェックしてみよう。。送付されてきた「試験解答と解説」の冊子には、簡単な解説と、各問題が公式教本の何ページに記載されているかも書かれている。資料としては親切だ。純粋に断片的な着物の知識が少し整理され豊かになるきっかけになったのはこの検定のおかげかなぁ。とりあえずは、ホッ。
2008.01.23
コメント(6)
-

今日の朝食
昨日のカイザーゼンメルでサンドイッチ。こないなりました。ツナサンドと卵。卵の方は粗挽きマスタードを軽くぬって、ちょっと大人の味。ごちそ~さまでした!
2008.01.23
コメント(0)
-

今日のお料理教室
今日から全3回のパンコースに参加。メニューは、1、カイザーゼンメル2、レンコンのピッツア3、ホワイトソーセージのポトフ4、コーヒーはじめに手コネでこちらを仕込んでおいて、待ち時間の間に軽食を作り、こちらを昼食にいただく。パンの教室にはあまり参加した経験が無い。家ではHBが勝手にこねて焼いてくれる。せいぜい、コネ&発酵した生地を成形してオーブンで焼くぐらい。今日は一から手コネ。た~~いへんでした!手にはべたべたいつまでも引っつくは、叩いても叩いても手から離れてくれな~い!!この寒い時期に少々額に汗しながらの作業。に加えて、苦手な計量。。。55.4gづつ均等に分割。。最後には細切れになってしまい、やむなく先生が大きいものを分割してうまくまとめてくださった。ほんとは細切れにしてしまっては生地が傷むのでいけないのはわかっているのに、もうど~しよ~もないくらい収拾がつかなくて。。同じテーブルは皆さんベテランで、サッサと作業をそつなくこなしていかれる。私一人あたふたしながら、教えてもらっての作業。。親切で気持ちのいい方ばかりでよかった!同じ分量で作っても微妙に焼き上がりの大きさが異なる。後から聞いたら60gで分割した方も?!どうも私のは手についた分、テーブルについた分、ちょっとづつ目減りしてたようだ。。下手なあいだは、手やテーブルに生地を食べられちゃうようです。。パン生地の3~5gの違いはとっても大きな違いになるとは。同じ品質をキープするパン屋さんってたいへんな作業なのね。。。カイザーゼンメルは皇帝の王冠を形どったドイツパン。今日のは蒸したジャガイモ入り。カイザーゼンメルの型は何種類かあるけど、定番の5本線以外は身近で入手はやや難しいらしい。こちらは明日、サンドイッチにでもして朝食でいただく予定。ピザ生地はパリッとクリスピーにするため、強力粉だけでなく薄力粉が40%近く配分。より薄めでパリッとさせたければ、薄力粉の配分を多くするといい。今日はトッピングにレンコンの薄切りしたもので、チップのようではじめての食感。家ではいつもピッツア用のチーズだけれど、モッツアレラチーズでリッチに。トマトソースもホールトマト、オレガノ、塩・胡椒を混ぜ合わせただけで簡単。アンチョビを刻んで、しめじをのぜ、焼き上がりにサラダ水菜をドレッシングで和えたものをのせていただく。いつも丸い形で1枚づつしか焼けなかったけど、細長く2枚四角にのばせば、効率的に焼けるんだ。。。ちなみに、ホールトマトをつぶすのにビニール手袋が用意されていた。「手でぐちゅぐちゅしてください」と先生。なんて用意のいい?!そう言えばアメリカのお料理番組でホールトマトを使う際に、缶詰にちょくせつ調理用はさみをつっこみ、ぐちょぐちょと切り刻んでいた。。。(韓国の焼き肉カルビをはさみでちょきちょき切っていたのを思い出した。。)使えるものは何でも使えって。。ポトフもお野菜しっかりいただけて温まる一品。このコース、後2回も手コネのパンが必ず1種類ある。少々不安。。家でコネる練習は、、ちとむずかし。。でも何事も経験、経験、、頑張ろ~。。。ごちそ~さまでした!
2008.01.22
コメント(2)
-

今日のおやつ
打ち込み作業の合間に、おやつ作り。残っていた生クリームを使ってしまいたくて、作ったのはロールケーキ。相変わらず根性無しのロールケーキ。どよ~っと横に広がり気味。。。巻くのへた~!でも今日の生地はふんわりやわらかくてgood!卵 3こ薄力粉 35g砂糖 50gココア 15gお粉はもちろん、天ぷら粉を使用!これを使うと市販のスポンジのようにふわふわ。天ぷら粉には卵が含まれているためらしい。ロールケーキはお菓子の中では生地を焼くだけなので簡単だけれど、どうも何回やっても生クリームを巻くのがへたっぴ~。。今日もへばったように横ひろ、根性無しロールちゃんでした。お味はvery good!だったので、ゆるしてあげよ~。。ごちそ~さまでした!
2008.01.21
コメント(2)
-
Jazzのお勉強~Scale2
Scaleの表を楽譜に起こす作業は一様終了。対応したBasic Chordを記入できる欄も作る。指導用の資料と自分用の資料と。。どうもスケールの呼び方の異なるものがいろいろある。手持ちの本で、このあたりを整理する作業が必要だ。記述の仕方もいろいろ。♯9と♯2、♯4と♯11、♭6と♭13と♯5?Diminishedと名のつくものもDimihished (8 tone scale)Diminished (being with H step)Diminished Whole ToneDiminished (being with W step)DiminishedってMajorでもDominant 7thでも、MinorでもDiminished Chordでも使える。しっかり練習しなければ。。HmP5↓はSpanish or Jewish scaleという名前がついている?!Alt.オルタードとこれさえ知っておけばJazzなんてへへへぇ~、なんてそんな印象だったけど、いったいこの表でAlt.って何よ?!って思ってしまう。もっと勉強しなければ。。。このSyllabusをたたき台にして、まず整理して発展させていこう。
2008.01.20
コメント(0)
-
先週のレッスン・メモ
アレンジの楽譜作成や練習用のデータ、発表会用のデータ編集、体験レッスンなどばたばたと忙しいレッスン日が続いた。初心者のはじめての発表会参加者には早めに準備をしなければと、難解な宿題をだしてくれた「新世界」第二楽章の第2テーマを弾きたいと言っていた楽譜を、渡す際にデモ演奏。「お~っ!」といって手をたたいて喜んでくれた。第2テーマのフレーズはちゃんとご希望どおりになっていたようだ。でも私でなくてあなたが演奏するのよ。。メインテーマの譜読み、片手づつの練習は1回ですんなり進んだ。あとは両手の練習をしっかりやってもらって、問題は第2テーマ。易しくはしたつもりだけど、テキストの進度の要素だけではアレンジできないので、他の要素を教えつつ曲として仕上げに導いていかなければならない。若いから大丈夫よね!?ショスタコの青年君。オケ・スコアをコピーしてもらう。メインのデータを改変ひっつけるためこちらも打ち込み作業。。YOSHIKIの「アメジスト」や喜納さん「花」の練習用データもレッスンの合間に作る。メトロノームや声に出してカウントさせると、出来てるのか出来ていないのか、こちらも本人もわかりづらい。でもデータがあるとどこが不安か、或は等速感という音楽の流れが把握されやすいので、まずデータに合わせて弾けることを練習の目標にすることで、レッスンは進めやすい。リズム、等速感、音楽の流れは大変重要だ。つっかえつっかえ弾いていたり、弾けるとこは早く、弾けないところでゆっくりになったり、勝手に弾いていることが、音楽として良くないということ、また自分の演奏状態が自分一人ではなかなかわからないもの。練習用のデータはできたけれど、それに合わせる以前にリズムが正確に弾けない、、というかリズムは正確に理解はしているけれど、鍵盤をそのリズムどおりに弾くことに難儀している生徒さんが約2名。1曲は「瞳をとじて」16分の種々のリズムパターンがオンパレード、かつ、タイで連結されているためより難しい。ボーカル科で歌ったことのある曲らしいけど、歌うのと弾くのはちがうの?!と言いたくなるほど遅々。目の前の楽譜に視覚的にとらわれてしまって、耳に音が入ってこないようで、耳と連動して指の動きとしてリズムをとらえることが難しいようだ。視覚にとらわれるとこういうことがおきやすい。楽譜を音に置き換え、音を耳で覚え、指の動きにつながる。が、楽譜を指の動きに置き換える作業になってしまうと耳で覚えるということに繋がりにくい。楽譜なしで覚えてしまうほど感がいいほうではない。いろいろやってみるが、要は拍の頭を自分で刻めないことに原因がありそうだ。練習を繰り返して、どうも間違える箇所をしぼっていき、2拍の裏から3拍目の頭へのタイが、拍頭が刻めないので、さらに8分の長さがキープできず、そこでリズムが崩れる、というところまで詰めてレッスンは終了。もう1曲"Let It Be"も。よく知っている曲なだけに、16分をいい加減に弾いてくれる。右手だけなら多少ボーカルのように好きに弾いてくれてもいいけど、左と合わせるとなると、両手になった時にまた混乱する原因となる。知っている曲ほど「簡単!」と思うのはやはり素人さんの考えることだ。時々これにはまってしまう生徒さんがいる。好きな曲=よく知っている=簡単に弾けそう、、なんてとんでもな~い!この生徒さんはギター科にいて以前にこの曲はギターではやっているとの話。でもコードだけなので、ピアノのようにメロディーもコードどちらも弾かなければならないのとは、根本的に大変さは異なる。コードだけなら10分くらいでクリアできたが、まず右の16分、それから両手でという作業。。道のりが遠く感じられる。。頑張ってね。。ショパンのワルツを練習中の生徒さん。固い弾き方をするし、CDの演奏者の音楽的な違いがわからない、と言う反面、分析などには興味があり解釈を納得してはくれる。どうしたものかと思っていたが、CDを聞いてもらうとガラッと演奏が一度に変わった。音楽的な感性が無いわけではない。テクニックが無いのか?と思って左右別々に弾いてもらうと、解釈したとおりにフレーズや丁寧には弾ける。だけど、両手になるといきなりその出来ていたことが全く無視された演奏になってしまう。音楽的なものはどこに行ったの?!状態にこちらはとまどってしまう。そこでコミュニケーションを取ってみると、両手になると音を押さえることに意識がいってしまい耳で聞けなくなっているようだ。とにかく両手の練習とその練習方法に問題ありと発見。すこし安心。とにかく理論派、フレーズの切れ目を意識して、呼吸を感じて、というとゆっくりするということですね、とくる。確かに打ち込みのデータではテンポ120から100ぐらいに落とすことになるだろう。わかった!こういう生徒さんの場合には、MIDIデータの数値感覚でお話したほうがいいのだろう!抽象的でなく数値として具体的なレッスンというものがあってもいいかもしれない、と思いついた。講座で「このfは500gで」といった先生もおられた。特に男性にはこのほうが親切なのかもしれない。「新世界」のAudioデータのテンポ合わせをしたのを思いだした。「奏」のデータも編集しなければ。。後半転調でフラット5つでてくる。まだ1年目の初心者でどうしようかと思ったが、本人は頑張って譜読みしてきているので。練習用のMIDIデータを生徒さんに渡しているが、家でクラビや伴奏君、FDが使用できるキーボードを持っている場合はいいけれど、パソコンを使って聞いたり、練習に使ったりする生徒さんも増えてきた。ヤ0ハの市販のものはコピーが出来ないように、パソコンで読み込みできないものがあったりするが、私が作ったものはいくらでもコピーし放題なので、パソコンの内蔵音源で鳴ってくれる。あるおじさまはiTunesに入れてiPodに移し、それをポッケに入れてそれを聞きながらピアノで練習されている。新しい生徒さんにもMIDIを活用してほしいのでそのことを伝えることにしている。でもなんでだか、iPodに移せないデータもある、とのこと。どうしてなんだろ?調べなきゃ。。
2008.01.20
コメント(2)
-
Jazzのお勉強~Scale
スケールを教えるための資料作り。モードはさっと説明だけすでに済ませていたけれど、その後どう説明していけばいいか、スケール表を眺めて悩む。コードからどのスケールを選ぶか、Jamey A.のscale syllabusで、まず"Five Basic Categories"から確認することにした。C;Major盧場合、Major(=Ionian)C7;Dominant 7thの場合、MixolydianCm;Minorの場合、DorianCm7♭5;Half Diminishedの場合、LocrianCdim;Diminishedの場合、8tone scale(WHWHWHWH)ここから発展してどこまで説明しておけばいいか、リストをみて悩む。Major 7thコードなら、IonianかLydianで説明していたけれど、リストによると、10種ある。Major(=Ionian)Major Pentatonic (5音)Lydian ♯4 (=♯11)Bebop ♯5 (=♭13)ただし8音Harmonic Major ♭6 (=♭13)Lydian Augmented ♯4、♯5 (=♯11、=♭13)Augmented ♯2、♭6 (=♯9、♭13)6th Mode of Hamonic Minor ♯2、♯4、♭7 (=♭7、♯9、♯11)Diminished ♭2、♯2、♯4、♭7 (=♭7、♭9、♯9、♯11)Blues Scale ♭3、♯4、♭7 (=♭7、♯9、♯11)さらに、Dominant 7th系にはAltとだけかたづけられないほどで、こちらも10種。呼び方もいろいろあり混乱してしまう。表から譜面におこすことにした。これを全調?!う~~っ!
2008.01.18
コメント(0)
-

今日のおやつ
お正月で増えた体重にびっくり!これからまめに体重計にのることにした。間食はおあずけにしていたけれど、すこ~し減ったので、おやつ作り!「焼くだけのお菓子」vol.2から、レシピではカラメルバナナケーキなんだけれど、リンゴを使ってしまいたかったので変更して。。カラメルアップルケーキパウンドケーキの型を使うといつもうまく焼けない。真ん中の方がなかなか焼けなくて、ふくれてしまう。今日のケーキはカラメルソースを流し込んでリンゴを敷き詰めるため、出来上がりは逆さまになる。底がまっすぐになってくれない。それで少々傾いている。家で食べる分にはいいんだけれど。。丸型でも同じ。これはオーブンのせい?でも美味!なので、いっか!夕方見たら、あと一切れくらいになっていた。好評のようです。「焼くだけのお菓子」vol.2よりごちそ~さまでした!
2008.01.17
コメント(0)
-
英検1級のお勉強
英検は過去問2006年度1~2回のvoc.のノート作り終わり、2005年度へ。今回は毎回やったところまで、プリント・アウトして復習するサイクルができてきたので、印象に残りやすいようだ。英和と英英で例文を必ず記載するようにしている。1日5問20語4ページ、一回分25問100語20ページ、07年度版7回分で700語。昔の過去問は30問だったので120語で6回分、720語。。。今年の課題は覚えること、になりそう。この年齢で錆び付いた頭で、どこまで新しいことinputできるやら。。忘れていくことの方が多いのだから、忘れてあたりまえ、と思ってとりあえず、浴びるほど触れること。脳トレ、脳トレ、、。
2008.01.16
コメント(0)
-
今日の練習
寒い!練習していると足が冷える。エアコンの温度を上げても上の方だけ暖かくて、下の方は風ばかり。。今日はJazzの採譜されたソロを分析しながら弾く練習から。といっても生徒さんのウィントン・ケリーの"On Green~”、とエバンスの"Autumn Leaves"。音の使い方がよくわかる。Jerry Cokerの"How To Practice Jazz"の本を読み直しながら、あらためてJazzの練習の内容を見直す。どっと課題が。。もう一度しっかり計画を立てなければ。Classicは、スカルラッティを3/4ほど暗譜、ハイドンは1/3。最後の練習から1週間くらい空いてる?でもやったところは覚えていた。毎日練習できればもっとさっさと進むだろうに。やっては忘れ、思い出して少し進んでは忘れ。。でも全く弾かないより練習したところは暗譜覚えているものとわかり、諦めずに積み重ねていく努力は忘れないように。。今日はハチャトリアンも2ページ、ピアソラは4ページ(暗譜は危うい、、)、グラナドス5ページ。仕上げはショパンのエチュード。コード進行はほぼ頭に入った、けどミスタッチところどころ。まだ音符を追っかけてる状態。Classicも新しい曲の譜読みをやりたいけど、まずは暗譜を優先。
2008.01.16
コメント(0)
-
お仕事、お仕事。。
"On Green Dolphin Street"の打ち込みの続きと"Take The A Train"の打ち込みをはじめる。QuantizeでSwingがどうもうまくいかないので、Groove Quantizeを使ってみる。それからドボルザークの「新世界」第二楽章の第2テーマ超~~初心者用にアレンジの作業。まだはじめたばっかりで、メインテーマはテキストのレパートリーにあるけれど、それに合わせて第2テーマを弾けるようにアレンジしなければならない。音源聞きながら、どこをカットしてどうつなぎ合わせるか、さらにまだ始めた2か月の生徒さんが弾けるようにアレンジ、どうしたものか悩むところ。元調はD♭メジャーからC♯マイナー、再びD♭メジャーへ。データどうしたものか!?!?!持ってこられたスコア、コピーいいわ!といったけれど、こんどコピーしてもらおう。オケ譜の打ち込みは音数多くてたいへんなのよね。また仕事が増えた。。希望してくれるのはいいけど、、どんだけたいへんなことを要求しているのか、それがわかるようになるまで、いつかいつかその日が来るまでピアノ続けて上手になってくれよな~~。どんな先生でも引き受けてくれるとは思わんとってくれ~~!例のショスタコの青年です。。
2008.01.15
コメント(2)
-
突発性難聴
最近ある歌手の告白で話題になっている、突発性難聴。仕事柄他人事ではない。同業者や生徒さんにも何名か患った話を聞いたことがある。生ピアノだけのレッスンならまだしも、防音された密室での電子ピアノの音を長時間聞かなければならない環境や、DTMやDAWでのアレンジ・音楽製作の仕事の場合にも長時間ヘッドホーンで電子音を聞かなければならない。耳を酷使しているのを感じる。電子ピアノも改良されてきてはいるけれど、仕事始めた頃の機種は酷かった。レッスンが苦痛で拷問のような印象を持ったことがある。教室へ意見を言えるようになってきた頃に、生ピアノを部屋に入れることを要望して導入に成功。同じ苦痛を感じていた講師も多かったようだ。労働環境の改善は自ら要求しなければ、待っていても何も変わらない。教室の電子ピアノは高価なものが入っていて、実際に購入した生徒さんに機能の使い方を指導することや、買い換えや新規に購入する場合のデモの役目もある。でも大人のレッスンでは生ピアノ志向の方も多いし、販売目的だけにレッスンが利用されていてはたまったもんじゃない!商売道具のひとつである大切な耳。自分で守らなければ。以前のDTMの先生がある時から突然、データ再生の音量を落としだした。音量を押さえた方が種々の周波数を聞き分けやすい、との理由だったけど、今思うと共通するものがあったのではないかと推測する。あるドラムの先生がレッスン中耳栓してるって聞いて、「へぇ~?!」と思う反面、それはいい案かも、とも思った。高校の頃、あるロックバンドのチケットをもらい、席は前の方なので喜んでコンサートに出かけていったけれど、巨大アンプの前で、終わってからしばらく耳が縮んでしまったように人の声が聞こえなくてさんざんだった思い出がある。あんな音で毎日コンサートやってたらたまったもんじゃない。耳がおかしくなるか、或は耳栓してやるか。。。普段どんなに雑音の中にいるか、なかなか気がつかないものだ。レッスンで倍音を聞くことをしたことがある。私は5度、8度、7度までしか聞き分けられないけれど、じっと耳を澄ましていると、空調の音の大きさ、外を通る自転車の音、2階の人の気配、風の音、いろんな音の中にいるのに気づかされる。たまには音を消して、或は自然の中に身をおいて耳を休めてやりたい。耳を大切に!
2008.01.14
コメント(2)
-
アレンジ・製作のお仕事
昼近くからずっとパソコンの前。音源を取り込んでつなぎ合わせ、MIDIでの音足し、MixとMasterの作業。元CDのオケの音と途中でMIDIで付け加えた部分を違和感無くつなげるのに手間どる。時間合わせでAudioファイル引き延ばした部分に微妙に雑音。MIDIのデータでかぶせつつ、ティンパニーなどで盛り上げ隠す。。Reverbをどの程度入れていいものか。大きな会場でがんがんに鳴らすとエコーの入れ過ぎは音がぼやけてしまう。でもあった方が気持ちいいし。。ヘッドホーンで楽しむのと大きな会場でパリっと役目を果たしてくれる音と違うので、どうしたものか迷う。シュミレーションできればいいのになぁ。YouTubeで参考例を捜してみる。。まだまだMixとMasterの勉強をしなければ。もっといろんな技磨きたい!昨年の今頃、MIDI検定の2級実技の対策でMIDIにしがみついて頃に比べて進歩、、というか考え方の転換を経たのは大きかった。音楽、というか一つの作品を仕上げるのにはもっと違った側面があるという視点を知ったというのは私にとって大きなことだった。いつか、選手の遠征に海外についていって会場で自作データと体操の演技を見てみたい!1分30秒の夢~~!いくつになってもまだまだ夢は見れるもの?!頑張ろ~!
2008.01.13
コメント(0)
-
アレンジ・製作のお仕事
昨日の依頼の仕事、元MDが届きパソコンに取り込み、Audio編集でなんとか対処できそう。MIDIでもう少し音を増やして、コンプかけリバーブを加え、、とやっているうちに、アメリカ遠征ならもっとJapaneseっぽくしたいとも思い始める。でももう振り付けもできていて、イメージも決まっていることだろうし。。こういう時、画像を送ってもらって同期させてアレンジをふくらませることもできるだろう。iMovieで取り込めばDPで読み込みできるので、やってみたいけど、体操の先生の方に機材・環境があるかどうか。次回以降の提案としてみよう。サイズは決まっているので、アメリカ遠征ヴァージョンも考えてみよう。もう一曲は勇敢な曲なのに、中学1年生なのでかわいらしくアレンジしてほしいとのこと。むずかし!こちらもAudio編集でいこうと思ってCDレンタルしたら、パソコンで読み込めないものになっていた。はて?前回はたしかパソコンで読み込めたのに???違うバーションがでているかしら?DAWの勉強も次回からはMixとMasteringに入る。このあたりを実践でもっと生かせるようにしっかり勉強したいと思う。
2008.01.11
コメント(0)
-
アレンジ・製作のお仕事
器械体操の先生からtel。昨年のデータを後5秒伸ばしてほしい、との依頼。もう一曲の録音と。。選手がアメリカの大会に遠征に行くので急ぎでと言われたけど、、データは例のごとくメンテの際にことごとく消去してしまって、跡形もない。。デモで渡していたMDからAudioでうまく編集して伸ばせるか。。もう一曲はvocalが無いものなので、2曲をうまくつなぎ合わせることで今回はMIDIの打ち込み無しで製作してみることに。これで2曲めだ。アレンジ・製作した曲が海外に出て行くのは。1曲めはシドニー。こんどはアメリカのどこにいくんだろ~?どこかの大きな体育館で、大きな音で鳴らしてもらってこいよ~!昨年勉強をはじめたAudio編集でどこまでまかなえるか?!今年はじめの試練だ。。。
2008.01.10
コメント(0)
-
今日の練習
今日はあまり時間がなかったので、Jazzのメジャー系II-V7-Iのリストの1~12番をMIDIに合わせてトレーニング。BPMは120。次の課題はマイナー系のvoicingをMIDIに合わせてできるように。また、左でコードを取り、それにアドリブをのせるなどの練習もやってみよう。クラシックはスカルラッティ、昨日の4~5小節目を集中的に。頭の8小節、、なんとか手に入ってきた。(明日はわからないけど。。)1時間という時間のなんて短いこと。15分くらいの感じ。15分が2~3分くらいに感じる。子供の頃、1~2時間の練習って長く感じたけれど、最近は3~4時間なんてあっという間。どおりで年取るのも早いんだ。。。だんだん加速していくのを感じる。。じっくり本も読みたい。。時間を忘れてピアノに向かっていたい。年末に見たグレン・グールドの映画のある場面を思い出す。一日別荘で練習しているシーン。
2008.01.09
コメント(0)
-
今日のDAWのお勉強
年明けはじめてのレッスン。次回からMix and Masterへ。新たに3冊輸入。REMIXER'S BIBKE by Francis PreveMASHUP Construction Kit by Jordan "DJ Earworm" RosemanBURNING DOWN THE HOUSE一冊目はソフトの図から少し古め?!2冊目はAcidベース。Glossaryが役立ちそう。3冊目はwinの図ばっかり。winベースのソフトばかりで少々不安!ざ~っと眺めた限りの印象。英文卒の先生に翻訳出版などしてみません?と勧める。英語だけできてもDAWの知識がないと翻訳はできない。。日本訳があればそっちで済ますもの。でもJazzの理論書のように$30くらいの本が翻訳本が7980円くらいになっていたら、やっぱり原書の方を買うかな。。Jazzの理論書などの翻訳は最近増えてきたが、まだまだ知られていない良書はたくさんある。けど残念ながら翻訳されていない。ラテン系も事情はさらに厳しい。いい本を探してきて紹介したり、翻訳したりといったことができればいいなぁと昔から思っている。宝くじが当たって何か事業ができるなら財団でも作って音楽の知られていない良書の翻訳や、世界から講師を招いて公開講座やJameyのworkshopのようなことをやってみたい。夢のまた夢~。。次回は作品を持っていかなければ。。
2008.01.09
コメント(0)
-

今日のお着物
DAWのお勉強へ。今日は暖かくて着物日和。おはしょり、長め。帯揚げの処理がきれいじゃない。。。久しぶりの手結びのお太鼓。京友禅染めの道行。¥500でした。。
2008.01.09
コメント(0)
-
今日の練習。
午前中、英検のお勉強。午後からは少し打ち込み、その他ずっとピアノの前で過ごす。Jazzのコード・トレーニングにbopスケールのフレーズ全調warm-up。クラシックのレパの暗譜。作曲少々。あっという間に時間が過ぎてしまう。レパも数曲並行して暗譜し始めるが、なかなか覚えられない。スカルラッティははじめの4~5小節目が覚えられない!ハイドンはソナタなのにヴァリエーション形式なのでコード進行は同じだけれど異なるフレーズの出だしを間違えるととんでもないことに。ピアソラはイントロの4小節でさえ覚えられない。コードが単純でないことはわかっているけど、、イントロだけでこんなに手こずるとは。楽譜見たら弾けるのに。。並行してメインのメロディーのところは左のカウンターラインがまだ耳になじまないので覚えられない!仕上げはショパンのエチュード。コード進行は分析してあるので流れが滞るパート2つを集中して覚える。指を鍵盤になじませて確実にその音に指をのせる。分散の下降の左が音をミスる。へっと気がつくと2~3時間あっという間に過ぎている。あわてて次の課題を手をつける。自分の練習だけで、、ふぅ~。仕事の発表会用のアレンジ、あと2曲。打ち込み1曲。データの編集3曲。。。Jazzの採譜を弾く練習、3曲。。。。本も読みたいし、取り寄せた本も内容をチェックしたいし、、一日48時間くらいほし~!
2008.01.08
コメント(1)
-

今日のおやつ
今日はおぜんさい。おもちがまだ残ってます。ほっこりあったまりましょ!ごちそ~さまでした!
2008.01.07
コメント(2)
-
今日のJazzのお勉強
今日のvoicing'Round MidnightYou're Driving Me CrazyWhat Is This Thing Called Love?Cherokee
2008.01.06
コメント(0)
-

今日のおやつ
お正月用の残りの食材、クリームチーズとリンゴを使って、ダブルチーズケーキ。あんずの替わりにりんごを煮詰めて。 「焼くだけのお菓子」vol.2よりごちそ~さまでした!
2008.01.06
コメント(2)
-
今日のJazzのお勉強
今日のVoicing。Salt PeanutsGood BaitDear old StockholmWalkin'
2008.01.05
コメント(0)
-
今年の目標 その1
明確な目標が無いと進歩も感じられないし、達成感も満足感も得られない。ピアノが上手になりたい、とかレパートリーを増やしたいとか、漠然とした、抽象的なものでなく、はっきりとした形となる目標設定が必要だ。音楽、特にクラシックのジャンルでは自分のプログラムを作って演奏できるようになること、を目標にしたい。グレード2級を受けてみたいけれど、、まだすぐ受験には力不足なので、それに向けての1歩。自作曲、3級の時に作ったものでもいけるかなぁ。。作曲、即興も勉強したい!とりあえず期別に弾きたい曲をピック・アップ<バロック>1、ソナタ c♯minor/スカルラッティ2、トッカータ e minor/バッハ3、半音階的幻想曲とフーガ d minor/バッハ4、パルティータ/バッハ<古典>1、ソナタ C major/ハイドン2、ソナタ E♭ major /ハイドン<ロマン>1、ソナタ f minor/ブラームス2、バラード、ポロネーズ/ショパン3、ラフマニノフ4、タランテラ/リスト<近・現代>1、トッカータ /ハチャトゥーリャン2、ロンド/カバレフスキー3、アレグロ・コンチェルト c♯ major/グラナドス4、タンゴ・ラプソディ a minor/ピアソラ5、ソナタ/プロコフィエフ6、カプースティン<自由曲>近現代から残り1曲なんか短調が多い。。目玉の大曲がない。。弾きたいのはバロックと近・現代。とりあえず練習、暗譜。。
2008.01.05
コメント(0)
-

初詣、詣、もうで~
毎年訪れる石清水八幡宮へ両親と初詣。本殿もきれいに化粧直しされて、お天気もよく。。一度戻り昼食後、再び京都へ、都七福神の六波羅蜜寺へ。なんといっても、芸事の神様、弁財天にお参りしたくて。それと3日まで、初穂をいただけると聞き、五条へ。弁財天は都七福神で唯一女神、水を神格化したもので、言語や音楽の神として尊信。また、金運、財運の神として福徳自在のご利益とされている。芸事に秀でて、尚かつ、金・財運に恵まれればこれ以上望むことなし!今年もピアノ、音楽の勉強、練習に励むことを誓ってお参り。参拝し、住職さんが初穂を手渡してくれる。その後、金の文字から3回手前にまわし、お願い事を。都七福神の朱印色紙に朱印をもらう。朱印色紙といただいた初穂に芸事上達の絵馬と金運の俵を結んでもらう。さらに銭洗弁天様でお金を洗って、お守りに。六波羅蜜寺を後にしてえびす神社へ行く途中、建仁寺へ。お庭で一息。念願だった「風神雷神」もしっかり観て、お部屋や日本庭園、法堂の双龍図を観て、都七福神2つめのえびす神社へ。えびす様、その1。えびす様、その2。ユーモラス。朱印をもらい帰りしな鳥居に向かってお賽銭を投げる若い女性。鳥居中央のえびすさんの下に受け網があり一発でみごと投入。回りから拍手が!私も思わず、いいことあるわよ~!と言ってしまった。えびす神は、商売繁盛、旅行安全、豊漁等の守護神で庶民救済の神。知恵を働かせ体に汗して労働に従事していれば必ずこのえびす神が財福を授けてくれるそうだ。額に汗して今年もしっかり働きましょう!全国津々浦々七福神はあるけれど、日本最古のは都七福神で、今日の2つと松ヶ崎大黒天(大黒天)、東寺(毘沙門天)、赤山禅院(福禄寿神)、革堂(寿老神)、万福寺(布袋尊)。あと5つの寺社、頑張ってまわろ~!神様、仏様1つじゃねぇ~、なかなかお願い事聞いてくれそうにないので、たくさんあちこちお願いして回ることに。京都を訪れる楽しみがこれでまた一つ増えた!
2008.01.04
コメント(0)
-

初詣のお着物
昨日の初詣のお着物。母からもらったもの。お正月向け?!帯はポリの半幅。羽織を着て、その上にえんじの道行とショール、ベロアの足袋にユニクロのヒートテックのアンダー・ウエアと防寒対策も上手になったものだ。天気もよく暖かかったので寒くて困ることはなかった。帯つきで歩いている人をみかけたけど、さすがに寒そうだった。振袖だったから?振袖の場合どうするのでしょ?振袖用の羽織や道行ってあるのでしょうか?今年はポリの新しい柄やデザインのものを増やすのではなく、古くてもいいものをちゃんと手入れをして大事に楽しみたい。着物のクリーニングにチャレンジすること、桐のタンスがもう一つほしい。年末から着物雪崩がもう2回も。。
2008.01.04
コメント(2)
-
ウィーン・フィル・ニュー・イヤー・コンサート
毎年恒例のウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ニューイヤー・コンサート 2008を観る。ウィーン学友協会で弟は演奏を、両親は2回訪れている。1度は弟のコンサートで、2度目はベルリンで第九を歌いに行った際にウィーンへ足を伸ばして。。1度目はこの辺りの席で、、、2度目はこの前のいい席で~~でも椅子は竹のような固くて座りにくくて~、なんて両親で話している。私はウィーンに2度行ったことはあるけど、ここは一度も行ったことが無い!観客席にはお着物の姿の日本人がちらほら。いいなぁ~!台所で洗い物にまみれて、てんてこ舞いする年末年始でなくて、お着物で優雅にニュー・イヤー・コンサートをゆったり聞けるようなご身分になりた~~い!夢・夢・ゆめ~!シュトラウスってすごい作曲家。運動会でおなじみのオッフェンバックの「天国と地獄」のRemixをあの時代にやっていたなんて。。著作権はどうなってたんでしょうか?奥さんのために書かれた「かわいい曲」やトリッチ・トラッチ・ポルカ、定番のラデツキー行進曲、シュトラウスの作曲数は多い。ニュー・イヤーには明るくて軽快でしゃれていて優雅で新年らしい曲ばかり。35回目だそうだけれど、ず~っとシュトラウスの曲の演奏ばかりでどこまで続くのか興味深い。紹介されていたウィーン菓子もおいしそ!パティシエ野澤孝彦シェフのウィーン菓子専門店 Konditorei Neues あのお菓子の名前は何ていうのかしら?聞き逃してしまった。。
2008.01.02
コメント(0)
-

2008年度おせち料理
今年初の大仕事。おせち料理は妹との大作、、でもあっという間ですね。食べる時は。手をつける前に撮影会に時間をたっぷりかけて。メニューは、祝肴7種 1、黒豆 リンゴ和え 2、ピスタチオごまめ 3、数の子 ごま風味 4、紅白なます 生春巻き仕立て 5、しいたけのチーズ焼き 6、たたきごぼうの味噌漬け 7、紅白かまぼこ 祝盛3種 8、生麩 田楽 9、つくね団子の照り焼き 10、ほたてのたらマヨ焼き 11、千枚漬けとスモークサーモンの祝寿司 12、モンブランきんとん 13、お雑煮 14、豚の角煮祝肴7種+祝盛3種祝肴7種祝盛3種祝寿司サーモンと千枚漬けでさっぱり。お雑煮母の味。豚の角煮すっかり正月の定番メニューになってしまった。脂肪分は60~90分煮るので落ち、コラーゲンたっぷり。画像には無いけれど、「モンブランきんとん」(はなまるで紹介していた)は簡単美味!<材料>マロンクリーム 250g生クリーム 100cc栗の甘露煮 220g<作り方>1、ボールにマロンクリームとホイップした生クリームを半量 入れて混ぜ、さらに残りの生クリームを入れて混ぜる2、1に栗の甘露煮を入れて混ぜる
2008.01.01
コメント(4)
-

2007年最後の京都。
あらら、という間に年が明けてしまった。帰省してきた弟一家で総勢8名の食事の用意や後片付けでてんてこ舞いの毎日。12月30日に恒例の妹と姪(長女のみ)をつれての2007年度最後の京都。まずはお土産物の下見でちりめん細工館へ。町家でイタリアン、i Latiniへ。食べるのに専念してしまって画像をしっかり忘れていた。。さあ、これから目的地銀閣寺までしっかり歩くわよ!と地下鉄で「蹴上」まで行き、南禅寺へ。ほんとは湯豆腐でほっこりなんて思っていたけれど、小学生にはイタリアンの方がいいらしい。でも年末なので湯豆腐のお店も閉まっている所が多く、この頃の京都は予定を立てるのが難しい。年中無休、大晦日開いている、大晦日のみ閉まっている、30日から閉まっている所、、、など。南禅寺は拝観できず。琵琶湖疎水を上あがってのぞいてみた。姪には南禅寺とこの疎水が印象によく残っているようだった。妹のリクエストで哲学の道を北上。姪は鼻唄うたいなが、、「あんた哲学しながら歩き~や!それじゃ鼻歌の道やん!」「哲学って何?」「人生とはなんぞや?とか、なんで生まれてきたのか?とか、どう生きるのか?、とか考えたり、、、」説明しているだけで終わりそうなので、途中で止めました。2008年は子年なので、狛鼠のいる大豊神社へ寄る。普段は、ひっそりうっそうとした感じの神社が、想定通りこの日はテレビの取材や観光客も多かった。玉をかかえている狛鼠の左側が女性ということで、パチリ。立ち上がっている左側が男性らしい。取材の人に神主さんが話していたのを聞く。そろそろ疲れてきた姪の希望で、温まるため途中、よーじカフェ 銀閣寺店で休憩。二階の日当たりのいいお部屋でしばし、ほっこり。お庭もきれいでした。さらに一路銀閣寺へ。年末とはいえ、こちらはひっきりなしに観光客が。。銀砂灘がいつも印象的。最後に姪の和カフェに行きたいというリクエストで銀閣寺きみや、甘み処喜み家へ。地図をプリント・アウトしていたので、姪にお店を探させる。食べることなら俄然頑張る姪。父親(弟)似だ。。。お店も見つかり、姪は名物の「豆かん」を大人は温かいおぜんざいをいただく。姪に写真を撮ってもらう。黒くて美味しくなさそうに写ってるけど、おいしかったそうだ。日も暮れかけ、ラストのお買い物をするため三条へ戻り、鳩居堂、高島屋、ちりめん細工館へ。迷いに迷ってお土産を選び、長時間買い物をしてました。京の食材やお菓子関連はデパ地下がお勧め。だいたいのものはそろう。10時間遊びまくった一日。。おいてきた下二人の妹たちとお父さんは「とんかつ+回転駄菓子のお楽しみ」地元コースで一日を過ごしたようです。もうちょっと大きくなったら京都つれてってあげるからね~!
2008.01.01
コメント(0)
全35件 (35件中 1-35件目)
1
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- オーディオ機器について
- 12A6という真空管
- (2025-11-15 20:03:34)
-
-
-

- 防弾少年団(BTS)のパラダイス
- BTS - TinyTan Mini Speaker
- (2025-11-14 00:00:16)
-