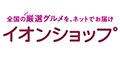PR
Calendar
Keyword Search
Comments
來應寺から常滑街道を右へ200m先に進むと、59番札所 萬年山 玉泉寺の参道口に至ります。今回はこの参道口に鎮座する「行者神變大菩薩」を掲載します。
 常滑街道から玉泉寺山門方向の参道の眺め。
常滑街道から玉泉寺山門方向の参道の眺め。
 長い参道の右側に写真の「行者神變大菩薩」は鎮座します。
長い参道の右側に写真の「行者神變大菩薩」は鎮座します。
石段右に役行者の諡号「行者神變大菩薩」と刻まれた石標が立てられ、石標側面に「創立70年記念」とあります。残念ながら石標や鳥居の寄進年を見ておらず、創建時期の想定ができません。
 「行者神變大菩薩」の全景。
「行者神變大菩薩」の全景。
高い石垣の神域に鳥居と常夜灯を構え、その奥に祠が建てられています。
日本の精神文化において、山岳信仰と仏教の融合は深い意味を持ち、その中心に位置するのが奈良時代の宗教的指導者であり、修験道の開祖とされる役行者(神變大菩薩)です。
彼は自然との調和を重視し、山々を聖域として崇める教えを通じて、人々の心身を癒す道を切り開きました。
この教えは、現代においても多くの人々に受け継がれています。
山岳宗教の時代には、既に古来の神道と大陸から伝来した仏教が習合していたと思われます。
山に宿る神々への畏敬の念と、仏教の山林修行の思想が結びつくことで、独自の信仰形態が形成されていったのではないでしょうか。
こうした宗教的融合の中で、修験道は誕生し、山を舞台にした厳しい修行を通じて、霊的な力を得る道として発展していきました。
文武天皇3年(699)、役行者は「人々を言葉で惑わしている」との讒言により伊豆大島へ流罪となります。
流刑先の伊豆大島では、大宝元年(701)に恩赦が許されまで、毎晩空を飛翔して富士山や伊豆の山々に向かい修行していたとも言われ、役行者の霊的な力と修行への執念を象徴する伝承として語り継がれています。
この出来事は、彼の生涯における試練の一つであり、信仰と修行の道がいかに困難であったかを物語っています。
寛政11年(1799)には、彼の没後1100年を迎え、生前の行いを尊び、光格天皇から「神変大菩薩」という諡号を贈られました。
前鬼・後鬼を従え、修行によって培われた強靭な身体と精神そのものが、彼の教えであり、御利益なのかもしれません。
 神から菩薩になった役行者、祠の前の鳥居に神仏習合の趣が漂う。
神から菩薩になった役行者、祠の前の鳥居に神仏習合の趣が漂う。
 祠全景。
祠全景。
大きな岩で組み上げた祠の上部には「村中安全」と刻まれ、その上には宝珠が乗せられています。
常夜灯の部材を流用して作られたものだろうか。
安置される像は当然ながら役行者像。
寺や神社の境内、山中などでよく見かけられますが、一般的には僧衣に袈裟をまとい、長いひげをたくわえ、手に錫杖を持ち、高下駄を履いて腰かけ、前鬼・後鬼を従えた姿で描かれます。
役行者が会得した計り知れない鎮魂と呪術の力が、大谷に近寄る災いから護っているのだろう。
後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 行者神變大菩薩
宗派 / -----
創建 / 不明
開基 / -----
開山 / -----
本尊 / 行者神變大菩薩
札所 / -----
所在地 / 常滑市大谷浜條118
來應(来応)寺から行者神變大菩薩 / 來應寺から常滑街道を右へ200m先、 徒歩3分
ほど。
参拝日 / 2025/10/21
関連記事
・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 八幡社
・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札所 金鈴山 曹源寺
・後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札 所金光山 來應寺
-
後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 58番札… 2025.11.14
-
後開催 第八回歩いて巡拝 知多四国 番外札… 2025.11.13
-
後開催第八回歩いて巡拝 知多四国 村社 … 2025.11.12