2006年06月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
地球の中心と繋がる確かな感覚
野口体操教室のスタッフは、日曜・火曜の本教室の他に夫々活動の場を持っています。直接、野口体操の伝え手としては勿論のこと、演劇・人形劇・精神医療などに野口体操は生かされています。そんな多忙な中、金曜日に教室を持っているスタッフの一人は、今日、5週目の金曜教室はお休みです。「梅雨の晴れ間のひととき、ちょうどお休みなのでチャンスとばかり、鬱蒼と生い茂る我が家の庭の植物たちの手入れをしました。ゆっくりと庭の草木たちとはなしあったのはひさしぶりです。庭には、ドクダミが群生していました。どくは「毒」、だみは「矯める・止める」という字を当てて、体内の毒を取り去る薬草として民間薬の役割をしています。子供の頃からなにかとこのドクダミの世話になってきました。名前のせいか、その臭いのせいか、ドクダミが咲かせる可憐な花のことを忘れて雑草として毟り取られてしまうのが気になります。このまま咲かせておきましょう。この土地に植えられた一番の古株は二十八年目になります。柿・梅・金木犀たちです。二十八年前、この土地に家を持った時に植え、じっとわたし達を見守ってきてくれました。その下で、アイビーや、蔓かの植物は身近な樹にからみついて、したたかに自分の生きる道をさがしています。中でも圧巻は竹です。門をはさんで右側から左側へ地下茎を張って、しばらく見ぬ間に一本だった竹が十本位にも増えていました。しかも地上に育つ節は、真っ直ぐに天を目指して伸びています。地球に根を張り、太陽と雨水と風を栄養にして・・・。ふつふつとからだが満たされてきました。我慢できなくなって、どうしても途中手を休めて「脳天一点逆立ち」をしました。地球の中心と繋がる確かな感覚が欲しくなったのでした。「したたか(下確か・下手然)とは、地球と一体化することによって生まれる『強さ・安らかさ』のことをいう」(野口三千三)
Jun 30, 2006
コメント(0)
-
意識でからだを支配することを止めた時
「手三拍子、足二拍子」という動きがあります。拍子の違う手と足の開閉で、手足の動きがすこしづつズレていくことを楽しみます。難解な、と言えば難解な動きなのですが、むしろその難解さを楽しむと言ったところでしょうか。楽しめばいいのですが、楽しめない人ほど思ったようにからだが付いてきません。足と手のリズムが違うからです。恐る恐る、出来ないで苦労している人に聞いてみました。「あなたのからだの中で何が起こっていますか?」ほとんどの人は答えられません。そんなことが分かるぐらいなら、とっくに出来ている、と言われるのがせいぜいです。何も分からないままに、混乱状態に突入します。そしてイライラします。自罰的にもなります。だんだん腹も立ってきます。気を取り直して、さてと、もう一度頭で組み立て直します。それがさらなる窮地に追い込みます。からだの動きは、意識の支配だけでは動けないのです。意識で支配すればするほど、からだは緊張してきます。任せているところが多ければ多いほど、からだの動きは自由になります。このことが本当に分かって、意識でからだを支配することを止めた時、からだは呪縛から開放されて、自由を取り戻しはじめます。「私は、できるだけ広い範囲のことについて、なるべく反射的に行動することでき、反射的に行動することのできないことは、ほんのわずかなことだけで、そのわずかなことについてだけ、意識的に判断する、それもやがて反射的に行動できるようになり、意識的判断という働きは、つぎの事柄のために、いつも休んで待機している、といった在り方がよいのだと思っている」(野口三千三)
Jun 29, 2006
コメント(0)
-
思っていたのとぜんぜん異いました
二回目の「野口体操入門ワークショップ」を行いました。参加していただいた方たちに対する感覚が、一回目の時とすっかり変わっていました。自分のからだが変わっているのを実感したのです。一回目は五月の初めに行いました。その時、パソコンの公募に応じてこれだけの人が集まってくる、というのは不思議な感覚でした。私の中に勝手な感想が巣食っていたのです。パソコンのネットに対する薄暗い印象です。彼らは家族がいても「引きこもり部屋」を持っていて、そうでなくても戸を閉め切った部屋で、夜中になるとゴソゴソ起きてきて、アルバイターをしながら好きな時だけ働いている、隠微な情熱を秘めてパソコンとだけ向き合っていて、人間関係はまるっきり下手で・・・、マスコミで流布されている印象をそのままインプットしたものです。何より不思議だったのは、「体操」は生身のからだを持って来なければ成立しないものなのに、どうやって「体操」のワークなど成立させるのだろうか・・・、ということでした。天性の人懐っこさと、「野口体操」で仕込んだ変化に対応する能力はそれなりに高いので、学びました。職場の帰りに疲れたからだで、それでも何かを求めて小走りに駆け込んでくる姿が印象的でした。みんな、人を求めている。人との関係の中で変化したいと願っている。何と言っても、見ず知らずの初めての人たちがこれだけ集まって、自分をさらけ出すワークに乗り込んでゆくエネルギーには、同じエネルギーで応えたいと思ったのでした。参加したみなさんもおっしゃいました。「本は読んでいたのです。でも、思っていたのとぜんぜん異いました。」「感覚とはもともと自分で体験し味わう他には判りようのないものなのであり、動物実験や他人の平均値ではどうにもならないもの、どうしても自分自身の生体実験による他はないものである」(野口三千三)
Jun 28, 2006
コメント(0)
-
そんな時、最高に力になるのが
伝え手と受け取る側が双方にそれぞれの思いを出し合って、さらなる新しいものを創りだしてゆけたら・・・。そう願わない伝え手はいません。伝え手の思いは思いの通りには伝わりません。それは自分を受け取る側に置き換えてみればすぐに分かることです。伝え手と受け取る側とのすれ違いは当然のことと言わなくてはなりません。大げさではなく、そこに百人いれば百人の受け取り方があります。だから面白いのです。それでも、伝え手は受け取る側に任せっきりにはなれません。思いを受け取ってもらいたいと必死になります。伝えたいことを受ける側のからだに落とすには、からだを空けて用意されていなくては落とし処がありません。まだ空けて用意されていないからだを攻め立てても、閉じたからだがますます頑なになって行きます。そんな時、最高に力になるのが、その人を、「そっと、そこに、おく」(野口三千三)ことです。又、からだの不自由な段階で、それでも気が急いて待っていられない人が陥るのが、からだの実感から分離された知的な解釈です。「頭では分かるんです。でも、できません。」分からなくてもいいんですよ。と言って、あえて足を引っ張っても、勿論気に入ってはもらえません。一応のケリをつけて、「よし分かった」にしなくては落ち着かないようです。そんな時、やっぱり役に立つのが、その人の今の状態を、「そっと、そこに、おく」(野口三千三)ことです。そんな状態に陥っている人たちは、意識でからだに命令を下しその命令に添って、ただ忙しく立ち働いているだけだからです。そっと、そこに、おいて上げれば、やがて疲れて力が抜ける時が来ることでしょう。そして、その人自ら、自分まるごとを「そっと、そこに、おく」ことを安心してできるようになることでしょう。 「からだの動きを探検してみると、動きとは、時間・空間・エネルギーの、位置や状態の相対的な変化の流れであるから、どこかが動くということはどこかが動かないということで、必ずからだのどこかは、地球に対し或はからだの他の部分に対しそっとそこにおかれていなければならない」(野口三千三)
Jun 27, 2006
コメント(0)
-
見渡せば花を愛でる人は沢山いて
毎週水曜日は舞台芸術学院に行くのですが、学生に会う楽しみの他に、少しの時間ですが、事務局のSさんと花の話をすることが足取りを軽くさせます。彼女は花が好きで、マンションのベランダから部屋の中まで花いっぱいにしています。買って来るだけでなく、挿し木をしたり、種を採取して種から植えたりして育てています。時々そのおすそ分けとして彼女の育てた花の鉢をいただきます。「元気にしているのよ」と花に言い聞かせてから手渡してくださいます。教室に参加している人からも「御所桜」と「ボケ」の花をいただきました。向かいの老夫婦から「千両」と「白山ぶき」が届きました。「上げようと思って、梅雨まで待っていたんだよ、朝晩水をおやりなさい」と言って。今日、月曜クラスの方から、日本種のアサガヲを三種いただきました。どの花も手を掛けて育てられ、お嫁に来ると言った感じでここまでやってきました。猫の額と言うにぴったりの狭い庭に、それでもみんな元気で、雨に新芽が鮮やかです。植木や花の教師は、隣近所にいます。どんなに梅雨の真っ最中でも、茂った草花には雨が当たりにくいこと、だから梅雨時でも朝夕の水やりは欠かせないこと、そして、水やりはそっと優しく、根元を傷めないようにやること、終わった花は摘んで、新しく咲く花に備えること、土と太陽と水が欠かせないこと、一番大切なことは、一つ一つの木や花の個性をそのまま大切にしてやること、見渡せば花を愛でる人は沢山いて、どの家の花も誇らしげに玄関に咲き誇っています。その花たちに挨拶をして歩くように散歩をします。梅雨の楽しみの一つです。野口三千三が「宇宙との交信の場」にした庭も、先生個人を超えて、街の人たちに感動を与えました。立ち止まって庭の草木とゆっくり話し合うことを楽しみにしていた人もいたと聞きました。こうして、庭にしゃがみ込んでいるとほとんど雑草のような草花にも気持を寄せることができます。地球に根を張り、地球から直接立ちあがっている植物たちに限りなく話しかけ、聴きたい。「地球上のすべての存在は地球の中心に集約される」(野口三千三)
Jun 26, 2006
コメント(0)
-
「ただ寄り添いなさい」
サッカー・ワールドカップ「ブラジル対日本戦」を四時に目覚ましを掛けて観戦しました。「オーストラリア対日本戦」、「クロアチア対日本戦」と観て来て、ああもうだめかもしれないと思いながらも、「僅かでも可能性のある限りわたし達は全力を尽くす」というジーコ監督のことばに、早朝だろうが寝不足だろうが、起きて観なければならない、と決心したのでした。見事に、惨敗というしかない負け方でしたが、観てよかったと感じたのは、選手たちの悔しい胸の内を垣間見ることができたことでした。何といっても胸打たれたのは力尽きてグランドに倒れこみ、涙して起き上がることの出来ない中田選手の脇で、最後まで跪いていた男性の姿でした。もちろん、何も聴こえては来ませんでしたし、カメラは中田選手の方を捉えていましたから、脇で跪いていた男性は後姿しか写っていなかったのですが、多分その男性は、一切の慰めのことばや、励ましのことばなど口にせず、ただ黙って、側に寄り添い続けているだけなのだろうと思われたのでした。チームにカウンセラーがいるのか否か、中田選手の担当なのか否かは知る由もありませんが、何とこの姿こそカウンセラーの姿勢だと感じさせました。野口体操を持って初めて精神医療に関わろうとした時、上野に診療所を開いておいでのH先生と出会いました。「一冊だけ本を薦めて頂けるとしたら、どの本をお薦め頂けるでしょうか」と教えを請いました。先生が迷わず薦めて下さったのは、セシュエー著、「分裂病の少女の手記]でした。そして、どうしても、もう一冊と、シュヴィング著「精神病者の魂への道」を薦めて下さいました。そこで読み取ったのは、彼らはどんな状態の時も、「その顔は虚ろで仮面のように死んでいた時」でさえも、自分に寄り添い続けてくれた人のことを感じ取り、忘れてはいないことでした。カウンセラーか、看護士か、その変わらぬ態度が彼のからだに安心感と安らぎを与えていくということでした。H先生は私に、私が当時関わっていた精神を病んでいる青年に「ただ寄り添いなさい」と教えてくださったのでした。その日から家族の沢山の要求、「しっかりして欲しい」「どんどん運動をしなさい」「強い精神を」・・・から彼を解放させるべく彼に寄り添ってきたのでした。野口体操とともに。「自分にとって強さとは何かを探検してみると、自分が新しく発見した強さというものが、今までの自分が強さだと思っていたことと全く異うものであったり、他の人それと全く異うことがあるということを、予め覚悟していることだ」(野口三先三)
Jun 25, 2006
コメント(0)
-
困っていると感じている人の方が
「どんな動きを、どのように大事にしているのか」は、その人の今と野口体操との関係をよく現しています。今日の授業では野口体操を続けている教室の人たちのそれぞれが、今、どんな動きを、どのように大事にしているのか、その動きが、自分にとってどんな意味を持つのか、そして、その動きを日常の生活の中でどんな時に、どんな思いでやられているのかを動きと共に話をしてもらいました。最近、右坐骨を痛めているRさん「『胎児の動き』と、『ぶら下げの動き』が好きです。『胎児の動き』の時も、『ぶら下げの動き』で降りていく時や立ってくる時も、右半身と左半身の違いがはっきりと分かるの。そしてそれが全身につたわって、つながっているということも・・・だから右坐骨神経痛でも安心して、痛くない道を選んで、ゆっくり丁寧に動いていけるの。」歌手のSさん「私は肩が凝ったり、頭痛があります。だから出番の前に楽屋でほんの少しの時間でも、しゃがんで腰を緩めたり、『ぶらさげの動き』をします。すると本番前の落ち着きを取り戻せるわ。」ミュージシャンのTさん「僕は『やすらぎの動き』は必ず毎日やるな。緩めることと張りがきもちいい。でも、まだすこし股関節から脚へ流れがないんだ。」聞けば、それぞれ自分のからだの不調を手がかりにしています。その方が、元気で何の障害もなくからだの動きが流れているときには気がつかなかった微妙な感覚がむしろ新鮮に分かってくるようですその方が、より自然に貞(き)きながら大事に丁寧に動いていくのでしよう。もっと、もっととからだを鍛えて行きたいと望む人より、困っていると感じている人の方が自分のからだを見直します。それは同時に自分を見直すことにほかなりません。「自分の日常生活から出発し、自分の日常生活に帰着する」ということの大切さを忘れてはならない。(野口三千三)
Jun 23, 2006
コメント(0)
-
まっすぐ基本的で本質的であれば
「本当のことを言ってもらうために来ました。」「その場面において、こんなに正確なことばで伝えてもらったことはありません。」木曜日クラスの、伝え手に対する期待と要求と理解しています。参加者の期待と要求の高さによって、伝え手は成長してゆきます。そんなクラスに来ると逆に元気を貰うことができます。「そのやり方を支持します」と言ってもらっていることが実感できます。基本を大事にしたい、本質的でいたい、だから、常にそこだけを見てきました。いつまでも若くいたいために、腰痛、肩こり、膝、を治すために、痩せるために、という望みや願いもわからないわけではありません。調子の悪い人にとっては痛切だからです。こんなことに効きますよ、といえば簡単なのです。しかし、体操は効能のためにやっているのではありません。「この運動にどんな意味があり価値があるのであろうか。それはそれをやってみた人が、それをやることの中で、それぞれ感じ取るものなのであろう。やる前からの固定された打算的・近視眼的な目的意識を持つことは、一見合理的で明快ではあるけれども、多くの場合、害はあってもけっしてよいことはない」(野口三千三)参加して下さっている人たちのからだの動きを見るときも基本に忠実に、その動きの本質を大切にしてきました。器用に出来たり、形だけだったり、物まねだったりするその人が感じられないからだの動きには妥協はしてきませんでした。「褒めてください。優しくしてください。」と言われなくとも、「厳しくしてください。ちゃんと見てください。」と言われなくとも、まっすぐ基本的で本質的であれば、そこで感じたことをあたりまえに伝えていけばいいのです。それを支え続けてくれたのが、このクラスです。「自然の力に任せきることできるような状態になり得る能力が力と呼ばれるものであることを、動きの実感によって納得する営みを体操という」(野口三千三)
Jun 22, 2006
コメント(0)
-
その学生の希望するところを援助するために力を注ぎます
他のみんなと同じ足取りではついて行けない、まだまだ同じスタート台に立つことが出来ない、このままには放っておけない、教育現場ではよくこんな子供の名前が挙げられます。ここ舞台芸術学院でもそんな学生が増えてきました。殊に、からだの動きが苦手なのです。ジーコ・ジャパンのサッカーで若者は盛り上がっています。野球の国際大会で日本中が熱くなったのもつい最近です。テレビにも新聞にもスポーツ欄があり、スポーツが市民権をもって人々の生活の中に浸透していることはたしかです。その頂点としてオリンピックが光り輝いています。一方で、からだの動きの不自由な若者たちが増えてきています。しかし、ここ舞台芸術学院は、バッサリ言い切れば、義務教育の場ではありません。ここは、才能に磨きを掛ける場です。今はまだ分からなくとも、自らの才能を見つけ出したい、その才能を伸ばしたい、と希望する学生にきっかけや機会を与え、教師はその学生の希望するところを援助するために力を注ぎます。しかし、それどころではない学生がいることも確かです。彼に伝えました。「希望するなら補講をやってもいいですよ。あなたが補講係になって何人か集めて。」一週間たっても返事がかえってきません。他者に働きかけたり、人を組織できないのかもしれません。どんな少年期を過ごしてきたのだろうか?自分のからだをどんなイメージで捉えているのだろうか?このままではいられない、不自由すぎる、という危機感がないのかもしれません。そこまで立ち入って、しばらくの間ゆっくり丁寧に、彼の内側から世界を見ることが、何か力になれるかもしれないのです。そんな補講をやります。[今自分自身の中にもっていながら、自分をふくめて誰も気づいていない無限の変化発展の可能性を、自分自身のからだの動きを手がかりとして、それを発見して育て、また、それがどんなものであるかさえ認識の網ですくうことのできないものまでも、そのままで発達させることができると考えるのである。](野口三千三)
Jun 21, 2006
コメント(0)
-
野口体操と私のくらし ― 冨美子さんの場合 ―
野口体操教室に参加されている人は沢山いらっしゃいます。その人たちにとって野口体操が教室から外に出た時、どんな力になっているのか・・・、その人のくらしの中でどう生かされているのか・・・、伝える側には大変気になる問題です。表現の場を持っている人はその作品で、専門の仕事をされている人はその仕事をとうして、どうか生かして欲しいと願っています。ご自分のホームページや、ブログをお持ちの方はそこで野口体操の経験を発表されています。直接わたくし達のもとに、素晴らしい経験のことばを寄せてくださる方たちがいらっしゃいます。許可を得てそのことばをブログで紹介させていただくことにしました。どうぞ経験のことばをお寄せ下さい。題して「野口体操と私のくらし」としました。「 ― 実感ということ―火曜日はお世話様でした。動きとともに、自分の中が変わってゆくことを少しづつ、わかってゆくことは、大変ですが楽しみでもあります。時々、美術展に出かけますが、私は何を見、何を感じてよいのか、わからなくなることがあります。さしたる感動を覚えることなく話題の絵を見て、満足しているだけなのかもしれません。最近「美術館で愛を語る」という本を読んだ中に、「美術館は他者の価値観に寛容になる訓練をつむ場所としての機能を持つ」とありました。美術だけでなく、あらゆる芸術に対してもいえることなのかもしれません。権威に委ねられた評価に目を曇らされて感動を強要されている私と、それを目の前にして実感をもてないでいる私は芸術を理解しているとは言いがたい。芸術に触れたとき、自分の中に何がおきているのかを、実感できることが大事なことなのだと思いました。それをキャッチできる体になるには、体操で訓練をつんでゆくことに、つながるのかなと思っています。 」「からだの動きの本質は中身の変化である。中身の変化の実感によって、生きることのすべてのものやコトを、繰り返し新しく捉え直す営みを体操という」(野口三千三)
Jun 20, 2006
コメント(0)
-
月曜日クラスの新しい出発です。
月曜日のクラスでも、野口三千三の著書を系統だって読みながら、それをからだの動きで確かめていくことになりました。処女作「原初生命体としての人間」からひもときます。全員集まった時だけ、と決めました。伝え手は何を目指しているのか、どんなクラスにしたらいいのか、どこに向かって行ったらいいのか、それらを、伝える側と受け取る側が共有することが困難でした。その距離を何とか埋めたいと、真ん中に野口三千三の著作を置くことにしました。月曜日クラスの新しい出発です。からだって、面白い、自分の可能性の全ては、自分のからだが持っている、当たり前のようにそう思える時が、必ず来ます。それはからだの動きの実感と共にやって来るのです。どの動きの時か・・・、どれぐらい時間が掛かるか・・・、楽しみながらやっていきましょう。「からだの動きの実感を手がかりとして、自然とは何か、人間とは何か、自分とは何かを探検する営みを体操という」(野口三千三)
Jun 19, 2006
コメント(0)
-
野口三千三の授業は
レインスティックといわれている細長い管がありまあす。ノルマタ(サボテン)に、その棘を外側から打ち込んであり、サボテンの棘をかいくぐって小石がすべり落ちる音が、雨の音に似ています。元はといえば、雨乞いのために使われた神具です。日照り続きをなんとかしたい、このレインスティックを手に唄い踊って神に祈りを捧げる、チリのダイアギア・インデアンたちの声が踊りが聴こえて来ます・・・。からだの重さは感じることはできても、音として聞こえてはきません。けれども、野口先生が授業の中で初めてレインスティックの音を聴かせて下さった時、「これを聴いてください」とおっしゃって、みんなが静まり返るのを待って、ゆっくりとその音を聞かせてくださったのでした。鳴り終わってもその場の空気は静まり返ったままでした。先生の中には、この音そのものと、この音が先生自身に与えた感動と、からだの動きと、そして、音を聴いた者に託す部分と・・・、伝え手としてのイメージが祈りのようにあったのでした。先生には「重さのつたはり・ながれ」が音になって聴こえていたのです。その夜、その細やかな音のあつまりが残ってなかなか寝付くことができませんでした。野口三千三の授業は、積み重ねられた準備と、熱い願いが込められてそこにいる者を根底から揺さぶったのでした。今日は、無数とも聴こえるサボテンの棘をかいくぐって小石がすべり落ちる音を、からだの中の「重さのつたはり・ながれ」と見立てて動きました。「やすらぎの動き」「しゃがむ・立つ動き」「ぶら下げの動き」「逆立ち」を、「レインスティック」からイメージを貰って動きました。どんな動きもからだの条件をくぐり抜けなければなりません。だからこそイメージをからだの動きに変えることが大切なのです。「私の言うイメージは観念的なものではなく具体的な働きである。この意味でのイメージはそのまま『力』と呼んでも差支えない」(野口三千三)
Jun 18, 2006
コメント(0)
-
いつの間にか痛みも忘れて
本格的な梅雨の季節です。自然は恵みの雨をもたらしてくれます。反面、大雨による土砂崩れなど、自然は容赦なく、厳しいものです。人間はほどほどに恩恵を受けられれば幸せ、などと勝手なことを言っている人がいます。自然の摂理を狂わしてしまっているのは、人間です。森林の無計画な伐採、車、コンクリート、道路舗装、エアコン・・・、少し前まで、穏やかな四季の移り変わりがありました。日本人はこの四季によって育てられ、自然を愛でるからだ感覚が優れてゆきました。梅雨もまたしっとりとした気持のいい四季の一つでした。そんな時代には、梅雨の間は梅雨の暮らし方がありました。しかし今は、からだもこの季節に順応できなくなってきています。Rさんは来日して二十年、からだも日本に馴染んできていました。野口体操も始めてから十年になります。このところ飛躍的にからだの中身がほぐれて、調子もよかったのです。家で「安らぎの動き」も気持ちよく出来るまでになりました。いろいろと分かってきていたのに・・・、です。「安らぎの動き」をしている最中です。「ポキツ!と音がして雷に打たれたように電気が走ってしばらく動けなかったの。」最近、坐骨神経痛に見舞われて難儀していた矢先でした。先週動くことができなかった彼女を「野口マッサージ」で迎えました。Rさんは安心して相手に身を任せて、いつの間にか痛みも忘れているようでした。マッサージは、からだを自然の分身に返してくれたのでした。「マッサージは、一般に筋肉や神経を対象として考えることが多い。しかし、骨を直接の対象とし、骨に真正面から向かってやることが大切である。骨の表面をなでさするだけではなく、骨の中身にまで直接語りかけるという思いで・・・」(野口三千三)
Jun 16, 2006
コメント(0)
-
自分自身が加わっていません
「出来る」を目標にした、その受け止め方に問題があったのです。いくら出来ても、その受け止め方では意味がありません。ザーザー振りの雨でも、この若い二人はやって来ます。二人とも、仕事を終えて、職場から二時間近くも掛けてやってくるのです。帰路は自宅まで三時間以上掛かります。伝える側も襟を正して迎え入れます。きっと、何か、よほど困っているのに違いありません。何も聞いたわけではありません。二人は全く違った現れ方だけれど、からだの動きに現れているのです。時間を掛けて一つ一つ丁寧に・・・クラスの先輩たちも協力を惜しみません。けれども、どんな助言もからだに入っていきません。一つ一つ丁寧に・・・が、かえって仇になっているのです。Rさん。肩をやれば肩だけ、腕に移れば腕だけ、肩はどうしたの?「ア、すっかり忘れていました。意識が行っていませんでした。」意識が行くって?「記憶してるんです、一つ一つ。」からだの動きは「まるごと全体」で変化しているのに・・・。いつも突然できるようになるのです。「いろいろやって、消去法です。良いと言われたのを一つ一つ憶えるんです。」だから、次に生かすことができなかったんだ・・・。I さん。いつも静かに黙って聴いています。Rさんとのやり取りも、他の人への助言も真面目に聴いて、立派にやり遂げようとします。「自分から働きかけるのが怖いんです。」「対話の動き」でなくても、一人の動きも自分から働きかけなくてはならないのに・・・。静・動、現れは違うけれど、二人とも自分自身が加わっていません。自分自身が参加して初めてその人の動きになるのです思いが伝わってこないのです。地球に「重さ」を働きかける、それは「思い」を働きかけることです。「思い」は、あなたの中、自分自身にあるのです。「からだの動きという角度から人間をみたとき、その主動力は筋肉の収縮緊張力ではなく、自分自身のからだの「重さと思ひ」である」(野口三千三)
Jun 15, 2006
コメント(0)
-
礼儀作法を言っているのではありません
舞台芸術学院では、なかなか馴染めない人、個別にもう少しサポートすればいいと思われる人に補講をしています。興味深いことに、補講を受ける大半の学生が箸を正しく持つことが出来ません。それは別に見てもやはり、箸を正しく持つことの出来ない学生が増えました。正しくとは、箸の機能を生かし切ることができるように、手と箸が繋がっているということです。礼儀作法を言っているのではありません。箸なんて、所詮二本の棒にすぎない、どうやって飯を食おうが、こっちの勝手だ、と言われてしまえばそれまでですが、しかし箸を使うことはそうともいえない重要な意味を持っていると考えます。箸は、さまざまな要素・機能から成り立っています。人差し指と中指の間に一本、中指と薬指の間に一本挟まれた都合二本の箸は、相手の指を変えながら機能しています。親指の働きが加わるからです。よく観察すれば、小指だってなかなかの働きをしてなくてはならない存在です。二本の箸を開いたり狭めたりして、大小のモノを挟み取ります。しっかり挟む、そっと摘む、その加減も力だけでやっているのではありません。モノと箸、箸に繋がる指との関係、さらには腕から胴体、そして足の下まで繋がっています。だから、からだの感覚がつかめない人は、箸を正しく持てないというのも納得がいきます。そして、一番考えさせられるのは、現在箸を持てないことではありません。現在持てないのはほとんどの場合、その人を育てた周囲の大人たちに責任があるといえましょう。箸を使うことは、幼児にとって最初の、からだへの複雑な働きかけなのかもしれません。それを認識した上での辛抱強い教え方、伝え方が悪かったのが、ほとんどの理由です。問題は、今からでも直すことが出来ない人です。そして、そういう人たちのほとんどは、新しいことを受け入れることが出来ない、特に、からだの実感を変えていく感覚が育っていないことです。この話を率直にして、授業が終わった後、廊下や階段で待っている学生がいました。「先生。箸持てないんです。今からでもやってみたいです。」「箸持てなくて、気持ち悪かったんです。」「わかった。やってみよう、一緒に」夏休みは補講で取られそうです。「生きることの基本的なことについて、それが自然の原理によって行われたとき、神はそのことに特有の快感(気持ちよさ)を感ずる能力を与えている」(野口三千三)
Jun 14, 2006
コメント(0)
-
手が、立ってしまった人間にとって・・・
う~ん、サッカー・ワールドカップ日本初戦、負けました。勝ち負けのあるところ、どちらかが負けるしかないわけですが・・・、しかも、相手国オーストラリアが三十五年ぶりの出場と聞けば・・・、いい顔しすぎでしょうか?けれどもそういったドラマを抜きにして、ただ勝ち負けだけは存在しません。昨日のご夫婦はどうだったのか気になっていたところ、報告がありました。「んも~、アッタマへきました。勝っている内は良かったんですけど、形勢が不利になると、勝った一点にまでケチ付けて、あれはファールだって。終いにはオーストラリアに点が入ると拍手するんです!」分からない気がしないわけではありませんが、彼女のアッタマへきた感じもよく伝わってきます。野口体操を続けていけるのかどうかは、聞いていません。今日の教室は、「指差し確認の動き」を、さまざまなバリエイションで動きました。久しぶりでした、この動きで動いたのは。そして、教室を広く使って汗を流したのも、久しぶりでした。「手」については「足」とともに、野口三千三の三冊の著書、「原初生命体としての人間」「野口体操・からだに貞く」「野口体操・おもさに貞く」で、野口三千三の考察するところを詳しく述べています。「和語の『て(手』は、《固形タの転》で、人体の一部の呼び名だけでなく、人間の行為行動のあらゆることに関するコトバとして、(母音交替してタ行の各音となり)これほど多種多様に使われるコトバなないであろう」(野口三千三)として様々な考察を展開しています。手が、立ってしまった人間にとって特別なものであることは言うまでもありません。からだの動きは常にそうなのですが、この野口体操の「指差し確認の動き」も又、さまざまな要素から成り立っています。一つ一つ解きほぐしながら、からだの中身と自然の原理を一致させていきました。野口三千三がなぜ「指差し確認の動き」を晩年まで大切にしていたのか、その核心にさらに近づけた気がします。
Jun 13, 2006
コメント(0)
-
今度はいつもと少し違うから・・・
「いつもと違って、少しいいんですが・・・」オリンピックの時も、彼女のこの訴えは聞きました。スポーツ好きのおつれ合いを持った女性からの訴えです。「夫はいつもと違って少しいいんです。ワールドカップに出場するだけで大したもんなんだよ、と初めて言いました。私は耳を疑るほどの驚きで、しばらく夫の顔を見つめてしまいました。」いつもは、優勝しなくては気のすまないおつれ合いは、テレビに映る選手に向かって罵詈雑言を浴びせるのだそうです。バカヤロー、なーんだ、がっかりさせるなよ。何しに出てきたんだ・・・。挙句の果ては、人格まで罵り出すのだそうです。彼女はそれがイヤでイヤで、試合そのものも楽しくなくなるのだそうです。「どうして試合そのものを楽しめないの? と聞けば、そんな、宗教家みたいな詰まんないこと言うなよ。と言われます。いつもは優しい夫なんですけど。」そして、「野口体操をやる前はそんな詰まらないことは言わなかったよ、少なくとも、俺と一緒に怒鳴りまくって応援していたぞ、って言われました。確かにそうでした。オーストラリヤ戦に負けたら・・・。いろいろ考えて、私、野口体操止めようかと・・・。でも、今度はいつもと少し違うから・・・、実際試合が始まってみなければ分かりませんが・・・。」彼女が野口体操を続けられますように、今日の日本の初戦、オーストラリヤ戦に勝利の女神が微笑みますように・・・。「私は、閉鎖的・逃避的・隠遁的・独善孤高的な生き方を好まない。満員電車の中も、衆人監視の中も、都会の雑踏も、俗悪な世間も、好きでもなく嫌いでもない。そのままが私の生きる場であるから大切なのである」ー私は「俗悪を楽しむ聖者である」 よりー(野口三千三)
Jun 12, 2006
コメント(0)
-
信頼関係の上に立って
「こんなこと、考えたこともありません。」初めての感覚、初めての考え方、初めての思想、初めての哲学、初めてのからだの動き、それはまさに野口体操に出逢ったとき、Mさんはいつもこう言って笑います。その笑いの中に、新しいものに対する好奇心と、期待を感じ取れます。「わかりません」これもMさんがよく口にすることばです。しかしそこには固くなさも、拒絶の気持ちも感じられません。分かったふり、知ったかぶりはしないだけ、正直に答えているだけ、伝わってくるのは自分自身に対する誠実さです。けれども、からだの動きに精一杯、今生きている自分自身を託したい、その気持ちは、動きの隅々から現れ出ています。やりたいことが出来たときのMさんも素直で、満面の笑みは嬉しさを隠せません。その信頼関係の上に立って、わたし達スタッフはMさんを、伝える側の基準にしています。Mさんの疑問は今分かっている限り答え、残った疑問はわたし達の疑問とします。Mさんの理解は全体の理解と考え、彼の理解の及ばない時はもう一度持ち帰ります。Mさんの困惑は、外の人の戸惑いでもあると考えて・・・。彼は今では日曜クラスの掛け替えのない存在の一人になっています。今日のMさんの「脳点一点逆立ち」は見事なものでした。「脳点一点逆立ち宣言」以来、脚を上げないで、「頭から腰までの逆立たち」に止めてきました。それは言わば、「途中までの逆立ち」です。脚を上げたいのをがまんするのは大変でした。でも、それこそこちらの狙いです。Mさんは、なぜ脚を上げない「途中までの逆立ち」をしているのかを、分かっていました。「丹田・子宮から新しい脚が生まれる」を経過して初めて脚を上げました。「ももの付け根」が明るく開かれて、そこから新鮮に、新しい脚が生まれ出てきたのです。「ももの付け根、この一点が開放され、明るいものになることによって、人間全体の在り方が、性格や雰囲気をふくめて大きく変えられていくことがあり得ると思っているのである」(野口三千三)繋がりました。胴体と脚が、そして、脳点と地球の中心が。さらに繋がることでしょう。「この一点が開放」されることが、「人間全体の在り方」へと・・・。
Jun 11, 2006
コメント(0)
-
背面に多数の眼(穴)を
三葉虫の化石を手にいれました。今年の第19回東京国際ミネラルフエアで、買い求めたものです。三葉虫は6億年から2億3000万年前に絶滅した海生節足動物です。興味深いことは、硬い骨格のある最初の動物だということです。また、初めて視覚システムを持った動物だということも、いっそう興味を持たせます。なんといっても、頭部や背面に複眼があることが魅せられます。海底を這うだけでなく、海中を泳ぎ回る種の中には、頭部や背面にも複眼があるものがいるそうです。わたし達人間は、老化と共に視力や聴力が衰えます。背面(背中)は特に硬くなりふさがれてしまいがちです。背中を丸め、暗~い背中で座り込んでいたり、四角い背中で、一枚岩のまま頑張って運動をしている人をよく見かけます。背中は自分で見ることができないため、注意されなければ気が付かないことです。野口体操の「つたはり・つながり・とほり・ながれ」の動きは、胴体にこそ「つたはり・つながり・とほり・ながれ」を求められます。暗い背中では動くことはできないのです。そこで今日は、三葉虫の化石からイメージをもらいました。「からだ中に複眼を」がテーマです。特に背面に多数の眼(穴)を、背中に明るさを、背中に「つたはり・つながり・とほり・ながれ」を、です。床で、掌で、背中で、触れ合いながら確かめました。Sさんは「頭が痛い!」と眉をしかめて参加されました。不調でもこうやって出かけておいでになるのは、ここに来れば何とかなる・・・という野口体操と仲間への信頼からでしょう。Sさんは体操を始めて5~6年になります。最初の頃は猫背で、胸が押さえられているようで、見ている者も苦しい気持ちにさせました。「こんなに続いている習い事ははじめてよ。しかも、やめようと思ったこともないわ」これも、からだの気持ちよさが、後押ししてくれているのです。今は背中も明るくなり、自分の中でも、客観的にも、背中の中身の変化と、姿の変化がはっきりと見えてきました。今日も床で、掌で、背中で、触れ合いながら確かめていくうちに、Sさんの表情は明るく変わりました。「うわあ!背中が温かくなって、頭もスッキリしてきたわ。」「『からだ』という言葉は躯立(からだち)の略だという。躯は『むくろ』で、身胴(むから)の転であるという。・・・・頭や手足を除いた『胴体』だけを意味した、ということもうなずけることである」(野口三千三)ーここで使用されている「躯」の字は、パソコン上の条件がありこの字をつかっていますー
Jun 9, 2006
コメント(0)
-
動きの変化ではじめてわかることがあります
「先生、同じことを二度やるっていいですね。」教室が終わった後、声をかけられました。いつも毎回、同じことをやっているのです。同じことをやっているけれど違うのです。だから、同じことを二度やったことはないのです。例えば、「ぶら下げの動き」は、具体的に毎回やっています。何回やっても新しい発見がある。何度やっても確かめることがある。その都度感じ方が違う。例えば、今日の、長いシルクの布を持って動いたことも、前回と同じことをやっているのではありません。そして例えば、「ぶら下げの動き」と「長いシルクの布を持った動き」は同じなのです。からだの中身の変化を問題にしているのです。モノはからだの外にあって眼でみえるから、形があるように惑わされてしまうのです。からだの外にあるからなおさら、からだの中身が変わらなければ動きが生まれないのです。からだの中身のように眼に見えないものを掴み取るというのは、困難なことです。「動き」でしか分からないことがあります。動きの変化ではじめてわかることがあります。感じるのです。「動き」で感じるのです。じっと眼を閉じて「内観」する、あるいは座禅を組むのと全く矛盾することなく、動いて、感じます。「視覚や聴覚のような遠隔受容器からくる感覚を捨て去ることによって、接触受容器(ここでは触・圧・痛など)や内界受容器(筋・健・関節・迷路・内臓など)による、からだの内側の全感覚で直接捉えることを、積極的に試みる必要性を強く感ずるのである」(野口三千三)
Jun 8, 2006
コメント(0)
-
「教える」なんて、とんでもないことでした
長い間野口体操教をやってこられたIさんから申し出がありました。「お忙しそうなので何でもお手伝い致します。」そのことばを素直にありがたく受けて止めて、ホームページ、ワークショップなどのパソコン上の手助けをしてもらうことにしました。しかし彼女は現在、パソコンを開いてメールを読むだけ、発信はしていません。それでは、先ずは、メールを送信できるように、その為には、文章が書けるように、大胆無謀にもそこまで、教えることになりました。案の定、やって見て情けないぐらいイヤになりました。「教える」なんて、とんでもないことでした。解決されないままに放置してあったことが何だったのか、はっきりしました。質問に何一つ答えられないのです。失敗ばかりして、それなのに解決しないまま放置されていたこと、出来たり出来なかったり、ほとんど偶然に任せて曖昧なことは何一つ教えられない。だから、応用問題ができない。しかし、いいこともありました。「あまりよく分かっていない人の方が何でも聞きやすい」というのです。それは、「よく分かっていないので、分からない人の気持ちが理解でき、待っていられる」のです。人にもよりますが、「よく出来る人は、結局自分でマウスを持ってどんどんやってしまうので、何も分からないまま」これはよく聞く訴えで、立場が変わって出来るようになると同じ態度で接する人はよく見かけます。共に学んだ一日でした。夜、Iさんからこんな素敵なメールが届いて驚き、感動しまた。「今日はお世話になりました。目標まで届かずに、時間になってしまい残念でしたが、楽しく、充実していました。習うより慣れろと言いますので、少しずつ、ヴァリエイションを増やせるように、パソコンにさわるようにします。何を書いて送ればよいのか迷いそうなので、「今日知った新しいこと」をテーマに送りたいと思います。夕方のテレビで、ダウン症で、盲、聾の六歳の男の子の生活が紹介されました。自傷行為がはげしいので目が離せないと困っていました。その行為は、盲、聾の人の特徴でもあるのですが、楽しむことが極端に制限されるので、自分の体をぶつけたり、殴ることで、体の中に起こる振動を楽しんでしまうと、説明されていました。 人間にとっての根源的な快とは、中が動くことなのかと感じました。物を見ることや、音を聞くことだけでも、細胞は動いているのでしょうか?」「漢字の『信』に対応する和語は何か、を探検し続けて半年以上たった。今のところ、それは『負けて、参って、任せて、待つ』の四つのコトバである」(野口三千三)
Jun 7, 2006
コメント(1)
-
「実感」が伴わなくてはならない
ニューヨークで治療の仕事をされている男性Nさんが、一回体験で参加されました。「野口先生のご本を読んで感動しました。それをからだで実感しに来ました。」一回だけ、というのは伝える側にも伝えられる側にも大変困難です。先ずはお試しに一回だけ、という一回体験の方がほとんどですが、Nさんのように遠方からおいでの一回体験の方には、一回だけ、に現実味があって、何を切り口に伝えていこうかと悩みます。今日の伝え手は自分の重さを地球に働きかけるために「乗る」こと。「乗る」という働きかけを、「実感する」ということ。を切り口に伝えていこうと試みました。乗ったつもり、乗った気がする、乗るふりではなくて、ほんとうに「乗る」には、「実感」が伴わなくてはなりません。「実感」という漢字を調べて驚きました。「実(み)」と「身(み)」は同根だというのです。そして、「感」の中には「口」という字が使われていますが、「口」という字は本来は「口(さい)」という字です。「口(さい)」とは、祈りの言葉を書いて入れておく神器です。又、「口(さい)」の上にーが書かれていますが、それは聖器である鉞(まさかり)をあらわしています。従って、祈りの言葉を入れた「口(さい)」の上に聖器である鉞を乗せて、「口(さい)」を守り、祈りの効果を中にとじ込め守る意味です。そのようにしておくと、神は夜中にひそかに訪れ、祈りに応えてくれる。神の「心がうごく」ことを「感」といい、転じて、心に感じること、「おもう」ことを「感」というのだと分かりました。そうか、そうだったんだ。自然の神のこころが動くように、祈りに応えてもらえるように、大切に重さを乗せていきたい。漢字を創った人たちの思いが伝わってきました。このコトバの思いをを、「寝た動き」、「やすらぎの動き」、「まの動き」、「ぶら下げの動き」など、からだの動きでたしかめました。今日のテーマー、ほんとうに「乗る」には、「実感」が伴わなくてはならない、は、ニューヨークからおいでになったNさんに「実感」していただけたでしょうか・・・。「楽しかったです。脚から腰に掛けて通りました」と言っていただきました。「コトバの問題が体操の問題と全く一致していることに気がついたんです。二つが全く同じ問題として重なり合っていることを、この頃はますます痛切に感じています」(野口三千三)
Jun 6, 2006
コメント(1)
-
野口体操は、「自然直伝」の体操です
ミネラルフェアーが開催されています。「体操とは大自然の神の『あやつり』に任せ切る世界のことである」(野口三千三)とする野口体操は、「自然直伝」の体操です。野口三千三は「私の先祖」と呼んで岩石・好物・化石と交信していました。岩石・鉱物・化石は、わたし達の生命の起源まで遡り、さらにそれ以前からこの地球に存在していたものです。それが今、具体的に存在し、触れることの出来るモノとしてここにあります。「わたし達のからだには、生命の起源からの記憶が残っている」と知った時、大きな驚きとともに勇気をもらったと感じました。「妊娠から出産への十ヶ月の過程で、生命の起源からの記憶をもう一度記憶し直す」と知った時、感動のあまり自分のからだを尊敬したくなったのでした。「わたし達の生命は岩石・鉱物・化石から生まれた」という野口三千三の仮説は俄かには信じられないと思ったほどの大胆さで迫ってきました。からだの認識が変わり、からだの動きの認識が変わるためには、岩石・鉱物・化石に対する実感こそ必要でした。お金持ちの悪趣味なコレクションの印象を免れなかった「石」から、「わたしの祖先」と実感するまでの距離は、からだの動きが埋めてくれました。自然の原理に適った動きでなければ本当の自由な動きは出来ないし、従って、本当に気持ち良くないことが、はっきり分かったのです。それから、からだの認識が変わり、からだの動きの認識が変わっていったのです
Jun 5, 2006
コメント(0)
-
伝え手の実感がレッスンを支えています
鞭のようなからだになることができたら、どんなにいいだろうか・・・。しなやかで、つたわりがよく、スピードがあって、エネルギッシュ・・・。自然のからだの動きは実のところ鞭そのもの。自然のからだを取り戻せば、からだは鞭になる。「鞭の構造と機能―下等動物から人間までの基本構造」と、野口三千三は伝え続けました。そして、野口先生は、自ら工夫し手作りした鞭を「免許皆伝」と言って手渡してくれました。勿論、自分たちでも鞭を沢山作りました。いろいろの長さの鞭を作ってからだの動きとの関係を確かめてきました。そうだ、そうに違いないと、信じてやってきました。「漢字の『信』は和語の『負けて、参って、任せて、待つこと』である」(野口三千三)まんざら夢のまた夢ではない、からだの実感で納得したとき、からだが変わっていました。このところ又からだの動きがラクになった、本当に自然のからだの動きは鞭そのもの、しかも、もっともっとラクになる予感がする・・・。伝え手の実感がレッスンを支えています。今日は「鞭とからだの動き」です。やっぱり、手にもって実際にやることが、大きな力になります。鞭にばかり関心が行きます。だから腕に力が入り、鞭を力ずくで振り回すだけです。地球に働きかけ、そこから貰うエネルギーが、からだの中を通り抜け鞭までつたわっていく、それはからだが鞭そのものになることです。からだが鞭そのものになったとき、何一つ作為はいらなくなるのです。
Jun 4, 2006
コメント(0)
-
今日は休刊日です
毎週土曜日は休刊日です。
Jun 3, 2006
コメント(0)
-
どんな国、どんな場所でも、地球の中心で繋がる
日本でも、様々な国の人たちとごく自然に行き交うことが出来るようになりました。ここ金曜日の教室も参加者のほとんどが海外の人です。彼らは日本国籍の人も含めて、母国と日本を行来しています。又、彼らはやりたいことを体験するために、うらやましい程軽やかに世界中を旅します。そんな彼・彼女たちのために、この教室も門を大きく開いています。「どんなに短い滞在でも、来日の際は必ず顔を出して体操をしたい」という彼らの希望からです。今日もスウエーデンから来客がありました。Pさんです。彼女は5年ほど前、在日中に半年ほど教室に参加していました。父上は合気道の師範で、Pさんもやっています。今度の来日は合気道の修行が主たる目的です。彼女は、自国での毎日の暮しが、野口体操でやられていると話してくれました。「何をやるのでも、ゆっくり、ちゃんと、野口体操でやればいいのよ、子どもを育てるのも・・・」嬉しそうに娘の写真も見せてくれました。彼女のために、「生卵立て」をしました。どの卵も、重さの軸は鉛直方向に繋がって見事にすっくと立っています。卵の形により多少傾いて立っているのが、重さの方向がはっきり分かって感動的です。外力を与えない限り、何時までも安心して立っているでしょう。「正座、しゃがむ、立つ、脳天逆立ち、・・・」の動きでも、足の裏、中身の状態を確かめながら、重さの方向を探りました。どんな姿勢でも、安心してからだの重さを預ける足の裏と、その方向を確かに感覚しようと・・・。そして、Pさんは勿論のこと、今は日本に居ない教室の参加者と、どんな国、どんな場所でも、地球の中心で繋がるという実感が持てたらと願っています。「重さは脚や腰・腕や肩で支えるのではなく、地球との接点を通じて地球の中心が受けてくれるのだ。」(野口三千三)
Jun 2, 2006
コメント(0)
-
からだと同じですよ
植木屋さんが来ました。いろいろ聴いて見ました。日当たりのこと、水やりのこと、剪定のこと、肥料のこと・・・・。結局、最後に言われたのは、「からだと同じですよ。」でした。「自分が暑い日は木も暑いんですよ、自分が水を飲みたいなあ、と思ったら木も水が欲しいんですよ。」そして、「イメージをもって剪定していったらいいと思います。」でした。「一回鋏を入れるたんびに、木の姿は見違えるように変わります。それを見ながら自分の描いたイメージに少しづつ向かっていけばいいんですよ。」さらに、「下手でいいんですよ。」でした。「自分らしくやればいいんですよ、楽しみながら、ね。植木の職人がやると、そりゃあ巧いけけど、一般的だし一日でやってしまいます。毎日少しづづおやりになったらいいと思いますよ。」もう一度、極意を伝えるように言われました。「何にも決まりは無いんですよ。木と話しをしながらやればいいんですよ。」と。「そうですね。はい。分かりました。」と何度も答えてうなづきました。木や草花と話し会ったり、教えてもらったりしたいと胸が膨らみました。小さなベランダで大事に大事に花を育てて、会えば必ず一輪持ってきてくれるともだちや、日当りの良い裏庭で育てて、玄関でお披露目させる苦労を厭わないともだち、花を植え替えたと言えば、喜んで見に来てくれるともだち、「狭いけれど、二百種類の木と花が育っているのよ、梅雨になったら株分けするよ。」と言ってくれるお向かいのおばあちゃん。それぞれの愛で方で木や花と付き合っている沢山の人の顔が思い出されました。そして、野口三千三と庭との深い関係です。「ここまで書いて、庭を見ると、春の花を咲かせた草や木が私を呼んでいる。足の裏に新しく重さを乗せると自然に立ち上がっていた。左足の裏に新しく重さを乗せると右足が自然に浮いて振り出されて第一歩を踏み出していた」(野口三千三)
Jun 1, 2006
コメント(0)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-
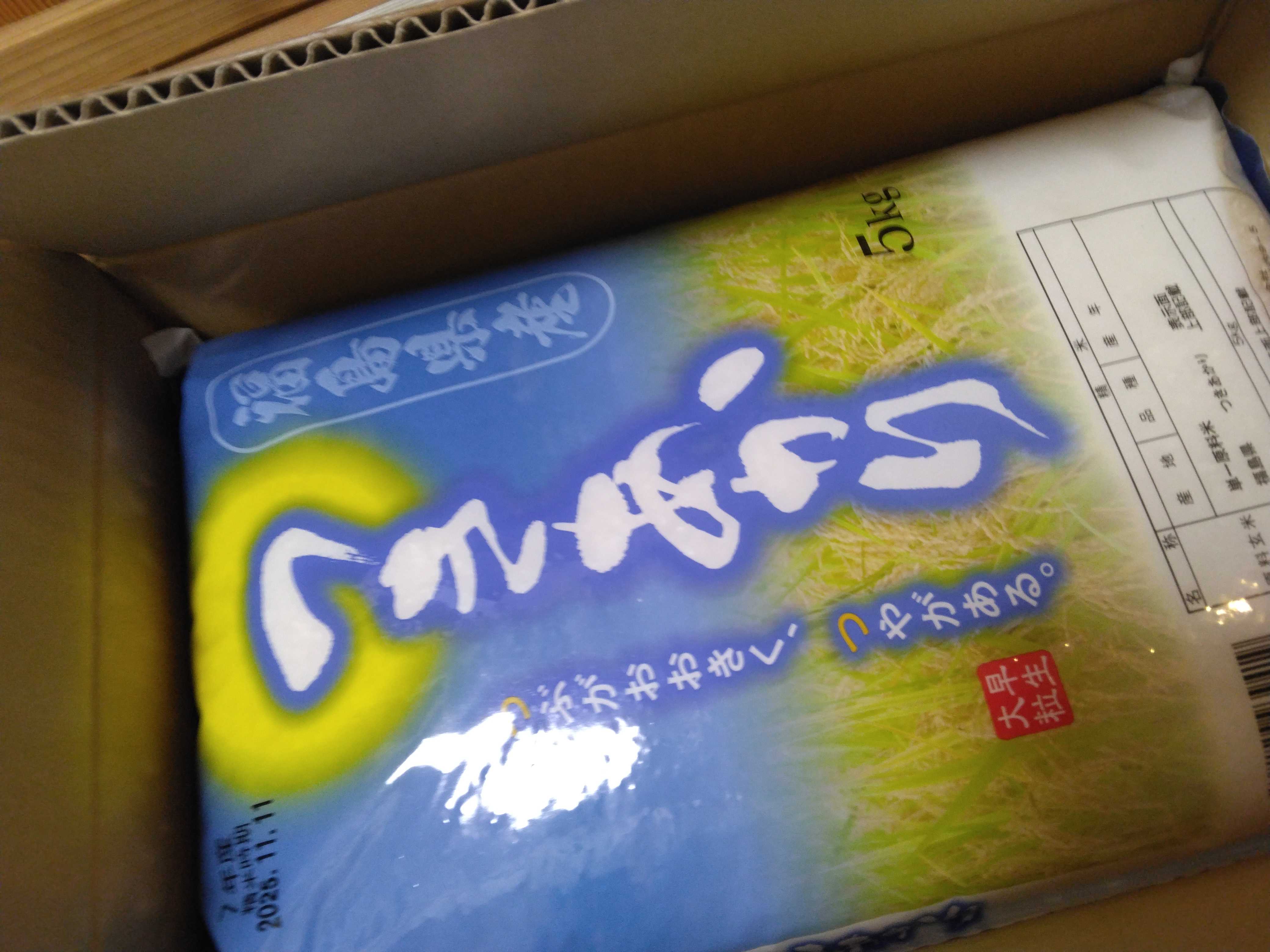
- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 米届いた 福島つきあかり8980円
- (2025-11-27 14:17:51)
-
-
-
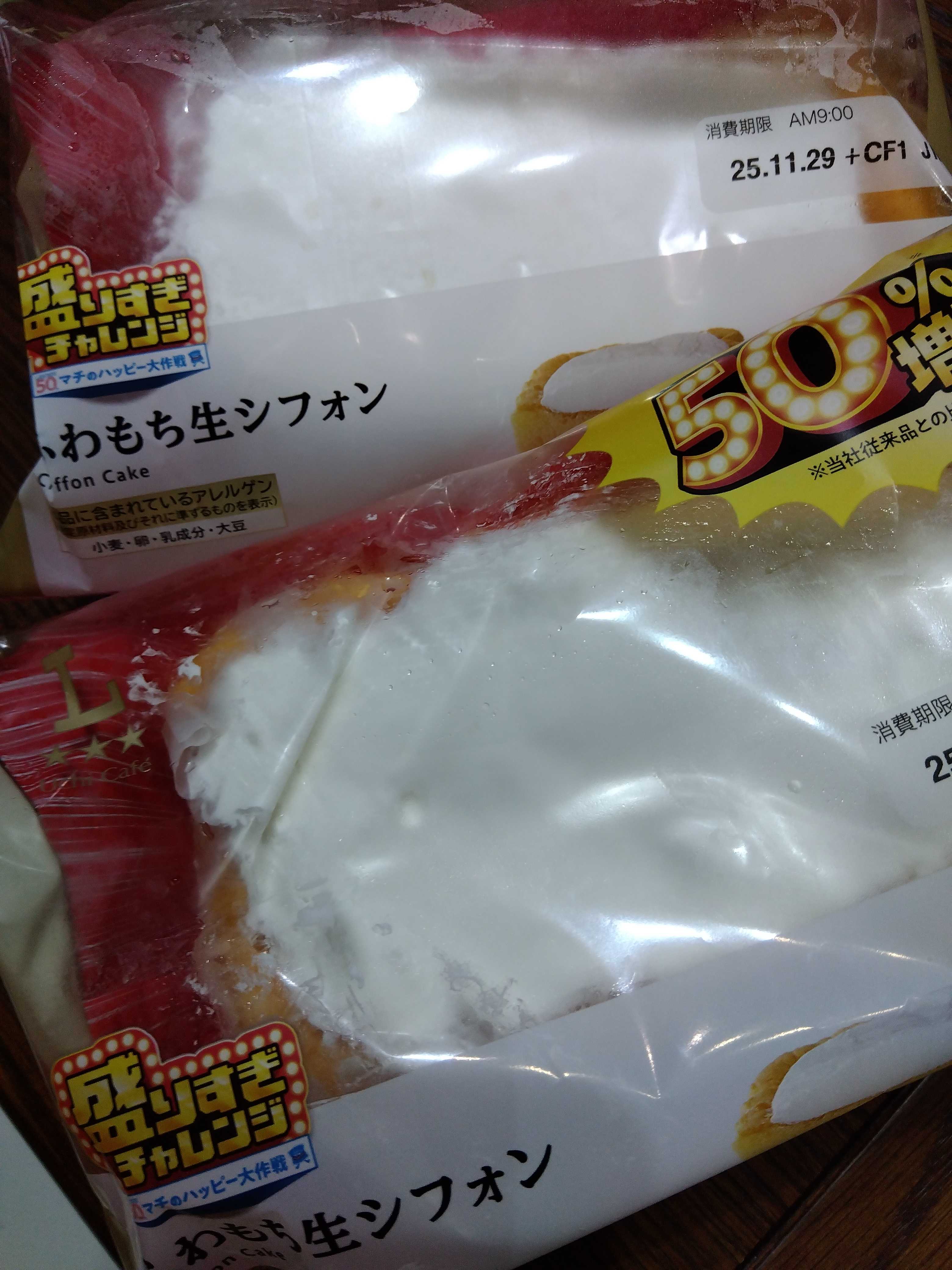
- 株主優待コレクション
- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…
- (2025-11-27 00:00:05)
-








